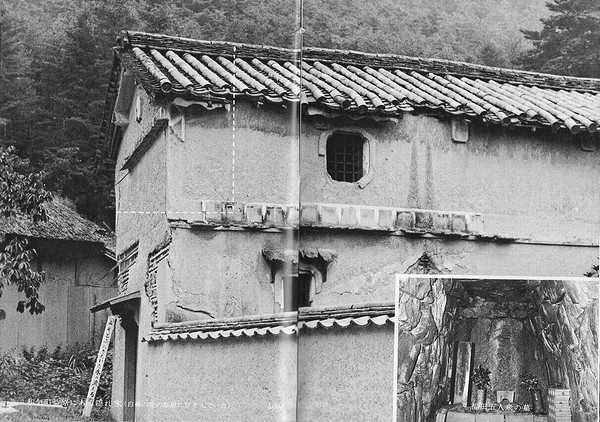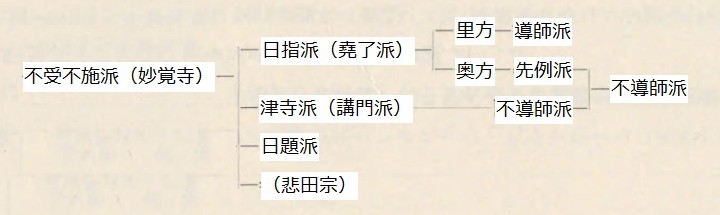|
亂姲暥丒尦榎埲屻偺庡偨傞朄擄亃
2018/12/23捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俇姫丂嬤悽侾乿1984丂傛傝
仦晄庴晄巤怣搆偺愴偄
姲暥俈擭摉帪偺椞柉偺怣嬄忬嫷偼師偺傛偆偵婰榐乮抮揷壠暥屔乽殸夢傝忋傞傔傗偡乿乯偝傟傞丅
丂椞柉偼椞庡偺嫮梫偡傞庲朄傪峴偭偰偄傞傛偆偵尒偣偐偗偰偄傞偑丄幚嵺偼樑嵳傪峴偭偰偄偨丅
攑帥偺敿悢埲忋偼晄庴晄巤攈帥堾偱偁偭偨幚懺偐傜丄埲忋偼晄庴晄巤攈怣搆偺幚懱偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅
弌帥偟偨晄庴晄巤攈憁椀偼偙偺傛偆側怣搆偺妀偲側傝丄枾偐偵嵼壠傪庁傝暓抎傪峔偊偰晍嫵偟偨丅師戞偵斵傜偺傕偲偵怣搆偼廤傑傝丄挬曢嶲寃偡傞傕偺傕偱偰丄帥堾偺傛偆偵側偭偨偲偄偆丅
仦旛慜栴揷晹朄擄丗栴揷晹榋恖廜
丂丂仺丂惓擵巵僒僀僩乮愘僒僀僩偵慻擖乯俵姲暥偺朄擄偲栴揷晹榋恖廜
丂丂仺丂旛慜栴揷晹榋恖廜丒擇廫敧恖廜曟強丂傪嶲徠
2018/11/15捛壛丗
仜乽壀嶳巗巎丂廆嫵嫵堢曇乿壀嶳巗巎曇廤埾堳夛丄徍榓係俁擭丂傛傝
丂嵅攲杮懞偵偁偭偨戝墹嶳杮媣帥偺乮柇妎堾乯擔娬乮擔椆偐乯偑曔傜偊傜傟傞偲丄偙傟偵婣埶偡傞壨杮丄壴朳側偳榋柤偼恎柦傪搳偘幪偰偰擵偵悘偄丄壀嶳偵弌偰朄偵弣偢傞丅
丂仸嵅攲杮媣帥偼乽旛慜偵偍偗傞姲暥俇擭偺擔楡廆攑帥堦棗乿偺尨斣258乣262.6傪嶲徠丅
擔娬埲壓偑孻偣傜傟偨偺偼姲暥俉擭乮1668乯俇寧侾俉擔乮侾俋擔偐乯偱丄懠偺侾柤偼峕屗偵岇憲偝傟偨偲偄偆丅
傑偨摨寧俀俉擔斵傜偺嵢巕俀俉恖偑崙奜偵捛曻偝傟傞丅
榋恖廜偺曟乮捛搲旇乯偼栴揷晹忈巕娾偲偄偆強偵偁傞丅乮乽愒斨孲帍乿乯
乽抮揷壠巎椶嶽乿偱偼榋恖廜偲偦偺嵢巕偼師偺傛偆偵婰榐偝傟傞丅
丂斨棞孲栴揷晹懞擵柉屲暫塹暲偵摨恖巕恟暫塹丄椆殺丂丄摨懞婌塃塹栧丄摨孲壛晹懞幍懢晇丄屲榊塃塹栧丄庱儝旐檰丄
丂栴揷晹懞嶰廫榊丄挿巕挿彆丄尮榋丄摨懞幍塃塹栧丄摨巕埨塃塹栧丄塃屲暫塹巕巗塃塹栧丄屲暫塹墮媣塃塹栧丄
丂摨懞榐塃塹栧巕屲榊暫塹丄惔憼丄摨婌敧榊捛曻丄
丂摨懞嶰榊嵍塹栧丄摨巕恟嵍塹栧丄恗嶰榊丄敧暫塹丄彆懢晇丄摨懞榋塃塹栧丄摨巕媑暫塹丄旐幫巪榁拞丄孲曭峴妬愳梌師暫塹傊旐怽搉
丂堄庯僴塃擵幰嫟晄庴晄巤廆栧寴怽崌媑棙巟扥擵敾宍巇娫晘乮傑偠偔乯桼怽僯晅丄
丂摢暘僲幰嶰榊嵍塹栧丄巗塃塹栧丄埨塃塹栧儝嫀擭弔儓儕饽幧旐嬄晅抲晄撏擵帠怽僯晅戝墶栚塱栰嶌塃塹栧丄戙姱摢惣懞尮屲榊僯
丂慂鑧旐嬄晅嬶僯嬦枴埾嵶払屼暦擛巣丄塃擵昳墬峕屗屼榁拞僿旐嬄払庯
榋恖廜奺恖偺抐嵾棟桼偼乽旐嬄弌妎乿偵偁傞偑丄師偺傛偆偱偁傞丅
丂丂丂屲丂暫丂塹
丂丒丒丒椆殺儝棤壆僯擖抲丒丒丒乮屼嬛惂偺乯堊晄庴晄巤堦懓壠巕枠堦柦堦摍僯怽崌丒丒丒埶廳嵾椷惉攕幰栫
丂丂丂椆丂丂丂殺
丂丒丒丒屲暫塹棤壆僯擡嫃栴揷晹懞擵幰僩儌悢恖堦枴椷摨怱丒丒丒乮屼嬛惂偺乯堊晄庴晄巤堦懓壠巕枠堦柦堦摍僯怽崌丒丒丒埶廳嵾椷惉攕幰栫
丂丂丂婌塃塹栧丄恗暫塹
丂丒丒丒栴揷晹懞擵幰僩儌悢恖堦枴椷椆殺儝嵼壠偵擖抲椆殺儝嵼壠僯擖抲擛帥挬曢嶲寃丒丒丒
丂乮屼嬛惂偺乯堊晄庴晄巤堦懓壠巕枠堦柦堦摍僯怽崌丒丒丒屲榊塃塹栧敀忬僯岓埶廳嵾椷惉攕幰栫
丂丂丂壛晹懞幍懢晇丄摨屲榊塃塹栧
丂丒丒丒栴揷晹懞擵幰嫟僩堦枴椷摨怱椆殺曽僿擛帥抳嶲寃丒丒丒廳嵾椷惉攕幰栫
丂丂丂幍塃塹栧丄巗塃塹栧丄埨塃塹栧丄挿彆丄屲榊暫塹丄惔憼丄媣塃塹栧丄婌敧榊丄尮榋榊丄嶰廫榊
丂丒丒丒栴揷晹懞擵幰嫟悢恖堦枴椷摨怱椆殺儝嵼壠僯擖抲擛帥挬曢嶲寃
丂丒丒丒乮屼嬛惂偺乯堊晄庴晄巤堦懓壠巕枠堦柦堦摍僯怽崌搆搣擵巇宍埶擵殸拞椷捛曻栫
丂丂丂恟塃塹栧丄敧暫塹丄恗嶰榊丄彆懢晇
丂嶰榊嵍塹栧悽樹僩儌丒丒丒
丂崱搙橜媍擵帪暘岶怱儝埲憗懍堦枴擵撪儝棧恊擵嵾儝扱岓忢乆岶怱擵桼嶰榊嵍塹栧瀚堊搆搣擵拞巕嫟擵岶峴儝姶柶尛僗幰栫
丂丂丂媑丂暫丂塹
丂崱搙橜媍擵帪暘岶怱儝埲憗懍堦枴擵撪儝棧擵嵾儝扱丒丒丒媑暫塹僇岶峴儝姶柶尛僗幰栫
晄庴晄巤攈偺憁椀偼峕屗憲傝偲偟丄廧怑傪枊晎偺帥幮曭峴偵堷偒搉偟丄帥幮曭峴椉恖偑庢挷傋丄張抐偡傞丅
丂姲暥俋擭乮1669乯俋寧侾係擔丄晄庴晄巤憁張暘丄彂暔儝抳僒僓儖晄庴晄巤朧庡嵍僲擛僔
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捗崅孲崱曐懞丂廆慞帥
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捗崅孲巻岺懞丂惣壀帥
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捗崅孲巻岺懞丂戝摽帥
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捗崅孲憪惗懞丂忢岝堾
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂捗崅孲憪惗懞丂嬍殺朧
丂塃屲恖俉寧俁擔旛慜傪敪偟擓嬨擔峕屗僯帄儖丄俋寧侾侽擔帥幮曭峴彫妢尨嶳忛庣僲揁僿嶲岦丄
丂嶳忛庣丄壛乆捾峛斻庣摨嵗僯僥徹暥偵敾宍壜抳巪払僙儔儗僔僇僶敾宍抳娫晘巪怽棫僯儓儕朄僲擛僋堖儝攳僊捛曻僙儔儖
側偍丄
丂仸捛曻偝傟偨帥堾偵偮偄偰偼乽旛慜偵偍偗傞姲暥俇擭偺擔楡廆攑帥堦棗乿偺尨斣67乣70乮廆慞帥乯丄159丒160乮巻岺乯丄188丒189乮憪惗乯傪嶲徠丅
2018/12/23捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俇姫丂嬤悽侾乿1984
杮挊偵栴揷晹榋恖廜偺婰弎偑偁傞偑丄妱垽丅
2019/08/08捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝
栴揷晹榋恖廜乮嵅攲榋恖廜乯丗
丂姲暥俉擭俇寧侾俋擔栴揷晹榋恖廜乮嵅攲榋恖廜乯偑旛慜暯堜偺桍尨孻応偱巃庱偺孻偵張偣傜傟傞丅
丂丂仺桍尨孻応偼旛慜忋摴孲栐昹懞丒柀懞丒暯堜懞拞偵偁傝
栴揷晹榋恖廜乮嵅攲榋恖廜乯偼埲壓偺嵅攲弌帥憁擔娬媦傃偦偺恊懓丒怣搆偺師偺榋恖偱偁傞丅
丂仺丂惓擵巵僒僀僩乮愘僒僀僩偵慻擖乯俵姲暥偺朄擄偲栴揷晹榋恖廜丂傛傝丂栴揷晹榋恖廜丂傪敳悎
丂丂1丄柇妎堾擔娬 嵅攲杮媣帥弌帥憁丅丂丂姲暥敧擭榋寧廫嬨擔庘丅
擇廫敧嵨丅
丂丂2丄壨杮恗暫塹 楡捠堾擔払
姲暥敧擭榋寧廫嬨擔庘丅擔娬孼丂嶰廫堦嵨偲傕丅
丂丂3丄壨杮屲暫塹
楡岝堾擔挿 姲暥敧擭榋寧廫嬨擔庘丅擔娬晝丂榋廫屲嵨丅
丂丂4丄壨杮婌塃塹栧 捠墌堾擔嫵
姲暥敧擭榋寧廫嬨擔庘丅丂丂丂丂 嶰廫嬨嵨丅
丂丂5丄徏揷屲榊塹栧 惔妎堾擔桳
姲暥敧擭榋寧廫嬨擔庘丅丂丂丂丂 擇廫幍嵨丅
丂丂6丄壴朳幍懢晇
朄塤堾擔桽 姲暥敧擭榋寧廫嬨擔庘丅丂丂丂丂 嶰廫堦嵨丅
偦偟偰丄偦偺懠恊椶墢幰抝彈巕嫙偵帄傞傑偱俀俉恖偑崙奜捛曻偺張暘傪庴偗傞丅
丂捛曻偝傟偨俀俉柤偺峴曽偼枹偩抦傟偢偲偄偆丅
偨偩堦偮丄偦傟偑恀幚偵嬤偄偐傕抦傟偸偲巚傢傟傞榖傪懡屆偺搰惓妎帥偺廆墘巵偐傜巉偭偨偺偱丄婰偡偙偲偲偡傞丅
丂壓憤崄庢孲孖尮挰偺娾晹偵偼抮忋擔庽傜慜榋惞恖楢彁偺杮懜偑偁傞偲慜弎亙亂恎抮懳榑丒姲塱朄擄亃亜2019/07/28仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿拞偵偁傝丅亜偟偨偑丄偙偺娾晹偺暿偺壠偵偪傚偭偲曄傢偭偨埵攙偑偁傞丅
偦偺埵攙偺棤柺偵偼乽屲戙栚傛傝巒傑傞丅偦傟傛傝愭晄徻乿偲彂偄偰偁傞丅
屲戙栚傛傝巒傑傝丄慜係戙偑晄徻偲偼丄堄枴怺挿側暥尵偱偼側偐傠偆偐丅
丂乮仸晄徻偱偼側偔丄壗摍偐偺帠忣偑偁傝丄慜係戙偼柧傜偐偵偱偒側偄偑丄朰傟偰偼側傜側偄弌棃帠偑偁偭偨偙偲傪帵嵈偡傞偺偱偼側偄偐丅乯
丂偙偺壠偺惄偼乽嵅攲乮偝偼偔乯乿偱偁傝丄壗帪偺崰偐傜偐娾晹偵偼乽嵅攲乿惄偑懡偔側偭偰偒偨偲偄偆丅
偦偟偰丄偙偺壠偑俀俉恖廜偺偆偪偺屻遽偩偲偄偆榖偼埲慜偐傜塢傢傟偰偄傞偦偆偱偁傞丅
傑偨旛慜偺嵅攲偼乽偝偊偒乿偱偁傞偑丄娾晹偺乽嵅攲乿偼偡傋偰乽偝偼偔乿偲屇偽傟傞偲偄偆丅
丂旛慜偺朄壺怣搆偵偲偭偰丄壓憤偼偝傎偳墦偄抧偱偼側偄丄旛慜偼椉憤抧嬫傊懡偔偺憁椀傪憲傝懕偗偰偒偨偺偩丅椺偊偽丄旛拞偱偁傞偑擔庽傗旛慜偺擔椞丒擔恑偱偁傞丅壓憤娾晹偲旛慜偺椉抂偵乽偝偼偔乿偲乽偝偊偒乿傪抲偄偰峫偊傞偺傕丄偁側偑偪柍杁偱偼側偄偩傠偆丅
丂栴揷晹榋恖廜偺張孻偼晄庴晄巤攈怣搆偵懳偟偰岞慠偲峴傢傟偨嵟弶偺惗柦孻偱偁傞丅偙偺巰偼師偺壨杮恗暫塹偺堚尵偲偲傕偵枾偐偵岅傝宲偑傟偰偒偨偲偄偆丅
丂師偼壨杮恗暫塹偺堚尵偱偁傞丅
丂乽懘屻幰丄晄摼婱堄岓丄屼暔墦偵曭嵼岓乮偍傕偺偳偍偵偧傫偠偨偰傑偮傝偦偆傠偆乯丅
丂愭乆丄偼偼偝傑屼壥旐惉岓桼丄彸怽岓傊嫟丄懘帪暘昦拞偵偰嫃怽岓屘丄屼偔傗傒偵晄嶲丄滿乆巆擮偵曭懚岓丅
丂嵍條偵屼嵗岓傊偽丄崱搙堦栧拞側傢偐偐傝丄擇廫恖饽幰巇嫃怽岓丅屲嶰擔拞偵屼朄搙偵旐嬄晅岓條偵屼嵗岓丅
丂傕偼傗惀枠偵偰屼嵗岓丅偁偲偵偰屼傦偐偆偨偺傒怽忋岓丅傕偼傗柧曢屼偩偄傕偔偵偰丄儈側儈側偄乮嫃乯怽岓丅
丂丂丂撿柍柇朄楡壺宱丂丂丂丂壨杮恗暫塹
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂楡捠堾擔摴乮壴墴乯
丂丂丂丂丂丂丂屲寧丂擔
丂丂丂丂丂楡廆條
丂丂丂丂丂悪嶳暯塃塹栧條乿
--- 乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
2019/09/19捛壛丗
仜乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿憡梩怢丄戝錟弌斉丄徍榓俆侾擭乮1976乯丂傛傝
乻栴揷晹俀俉恖廜乼乮俹丏94乣乯
丂栴揷晹俀俉恖廜偺柤慜偼師偺捠傝偱偁傞丅
壨杮梎塃塹栧嵢丄壨杮幍塃塹栧丄壨杮巗榊塃塹栧丄摨嵢丄摨壓彈丄壨杮埨塃塹栧丄摨嵢丄摨柡偍弔丄壨杮尮榋丄摨枀偍弔丄壨杮恗暫塹曣丄壀嶈慞暫塹丄壨杮婌塃塹栧巓丄摨梴彈偍徏丄壨杮恗暫塹嵢丄摨巕巗嶰榊乮俀嵨乯丄壴朳幍懢晇嵢丄摨柡偍漭丄摨巕彑師榊乮侾嵨乯丄壨杮巐榊塃塹栧
側偍丄壀嶈慞暫塹偼慶嶳柇妎帥俁俉悽媦傃係侽悽庍擔妛乮愰惓堾擔妛乯偺慶愭偱偁傞丅
丂仸埲忋俀侽柤偺柤慜偑偁傞偑丄屻偺俀柤偼椙偔暘偐傜側偄丅
丂仸慜弌偺丂乽壀嶳巗巎丂廆嫵嫵堢曇乿偵偁傞乽抮揷壠巎椶嶽乿偱偼
丂栴揷晹懞嶰廫榊丄挿巕挿彆丄尮榋丄摨懞幍塃塹栧丄摨巕埨塃塹栧丄塃屲暫塹巕巗塃塹栧丄屲暫塹墮媣塃塹栧丄摨懞榐塃塹栧巕屲榊暫塹丄惔憼丄摨婌敧榊捛曻丄
丂偲偁傞偺偱丄偙偺侾侽柤偼捛曻偝傟
丂摨懞嶰榊嵍塹栧丄摨巕恟嵍塹栧丄恗嶰榊丄敧暫塹丄彆懢晇丄摨懞榋塃塹栧丄摨巕媑暫塹丄旐幫巪榁拞丄偲偁傞偺偱丄幫柶偝傟偨偺偱偁傠偆丅
俀俉恖廜偼殸捛曻偲側傞偑丄嵟屻偵偼壓憤崄庢孲孖尮挰偵堏廧偟偨偲揱偊傜傟傞丅偦偺撪俆尙偼攑愨偟丄崱偼柍墢曟偑巆傞偲偄偆丅
偦偟偰尰嵼丄孖尮挰娾晹偵偼偦偺屻遽傜偟偒壠柤偑侾俇尙偁傞丅
偦傟偼丄慜弌偺丂乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿偺乽栴揷晹榋恖廜乿偺崁偵偁傞捠傝偱偁傞丅
侾俇尙偺撪丄
嵅攲尮彑巵偺壠偵偼慜榋惞恖偺堦恖擔峅乮暯夑椆怱堾擔峅乯偺欀涠梾傪強憼丅
嵅攲嬥梇巵偺壠偵偼曮塱嶰暩滫乮1706乯偺擔擡乮仸乯偺欀涠梾丄媦傃慜弎偺乽敔埵攙乿傪強憼丅
丂丂仸擔擡丗旛拞徏嶳乮崅椑乯偺恖偱丄晄庴晄巤偺屘偵悈楽偵擖傟傜傟傞偲偄偆丅
丂丂丂丂扐偟丄旛拞徏嶳偺擔擡偲偼暿恖偱偁傞壜擻惈偑崅偄丅
丂丂丂丂丂丂丂仺旛拞崅椑擔擡條
丂丂仸乽敔埵攙乿偺徻嵶偺婰嵹偁傝丅
偝傜偵丄娾晹抧嬫偺愇嫶婎朳巵偺壠偵偼慜榋惞恖偺擔尗丒擔峅丒擔恑偺嶰恖楢柤偺欀涠梾乮偙傟偼俁恖偺楢彁偱偼側偔丄侾枃偺巻偵俁偮偺撈棫偟偨欀涠梾傪偐偄偨傕偺乯偲擔椞媦傃擔廩偺欀涠梾偑強憼偝傟傞丅
丂丂丂丂丂仺慜榋惞恖楢彁偺戝欀涠梾
丂丂丂丂丂丂丂乮拲乯偙偺乽戝欀涠梾乿偵偮偄偰偼忋弍偺
丂丂丂丂丂丂丂丂仜乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿崅栰悷丒壀揷柧旻丄崙彂姧峴夛丄徍榓俆俀擭丂傛傝
丂丂丂丂丂丂丂丂丂楢彁偺欀涠梾乮俹丏81乣乯偵宖嵹偟偰偄傞乽戝欀涠梾乿偲摨堦偺傕偺偱偁傞丅
傑偨偙偺愇嫶壠偵偼戝崟擔墱乮栘憿丒擔墱傪戝崟偵婾憰偟偨傕偺乯憸偑旈憼偝傟偰偄傞丅
丂丂丂丂丂仺愇嫶壠強憼戝崟擔墱
乮戝崟擔墱偵偮偄偰偼慶嶳柇妎帥偲扥攇彫愹岲寴帥偺杮憸偺俁懱偺傒傪悢偊傞丅乯
壛偊偰丄擔庽強帩偲偄偆庫悢丄擔椞偺娦嬇彂丄擔煰偺憭憲暥丄婽嬀側偳傪強憼偡傞丅
偙傟傜偼丄偙偺抧嬫偺恖乆偲晄庴晄巤攈偼怺偄宷偑傝偑偁偭偨傕偺偲悇應偝傟傞偺偱偁傞丅
---乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿廔---
丂
仦旤嶌暉揷屲恖廜
丂仺丂屲恖廜曟強偵偮偄偰偼丂旤嶌暉揷丒暉揷屲恖廜曟強丂傪嶲徠
2018/12/23捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俇姫丂嬤悽侾乿1984丂傛傝
姲暥俋擭乮1669乯俁寧旤嶌暉揷懞嶳榌偺捤乮屻偵斾媢擈捤丒墶寠幃愇幒傪帩偮墌暛乯偱丄堦恖偺憁椀偲係恖偺斾媢擈偑抐怘擖掕偡傞丅
嵅攲杮媣帥弌帥憁寴廧堾擔惃偲柇堄乮俁係嵨乯丒柇掕乮俀侾嵨乯丒柇尰乮俀俀嵨乯丒柇惃乮係俀嵨乯偺係恖偺斾媢擈偱偁傞丅斵傜偼乽暉揷屲恖廜乿偲屇偽傟傞丅
擔惃偼寶晹懞偵惗傑傟丄俉嵨偺帪杮媣帥偱弌壠偟偨晄庴晄巤憁偱姲暥俇擭庤宍採弌傪嫅斲偟弌帥偡傞丅
丂偦偺屻曻楺惗妶傪憲偭偰偄偨偑丄抏埑偼傑偡傑偡寖偟偔丄乽擛愢廋峴偺峴幰丄屲広偵懌傜偞傞恎傪堦偮抲偔張側偟乿偲塢偭偨愗敆偟偨忬懺偲側傞丅擔惃偼丄摨嫿偺柇堄丒柇掕丒柇尰乮偲傕偵戝揷偺揷暎壠弌恎偲偄傢傟傞丅乯偲嵅攲懞弌恎偺柇惃傜偲偲傕偵抐怘傪寛堄偡傞丅係柤偺斾媢擈偼慜擭傛傝抐怘傪寛堄丄擔娬偵椪廔傪棅傫偱偄偨偺偱偁傞丅斵傜俆柤偼暉揷懞偺恖壠棤偵捤偑偁傞偺傪尒偮偗丄偙偙偱俀寧嶑擔傛傝抐怘偵擖傞丅擔惃偼戣栚傪彞偊偮偮丄捤偺愇暻偵戣栚傪崗傓丅俁寧屲恖偲傕恖抦傟偢壥偰傞偲偄偆丅
丂暉揷屲恖廜偺懠偵丄慡崙揑偵堊惌幰偵懳偡傞峈媍偺幪恎傪偟偨恖偼懡偄偲偄偆丅
丂乮旛慜偵偍偗傞帠椺偼師崁乽旛慜偵墬偗傞幪恎偺峈媍乿傪嶲徠乯
2019/07/28捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝
暉揷屲恖廜偺抐怘擖掕丗
丂嵅攲杮媣帥傪捛傢傟偨擔惃偼捗嶳偺奨偵愽傫偱偄偨傜偟偄丅偟偐偟捗嶳斔偺敆奞傕尩偟偔丄捗嶳巗奨偵愽傫偱偄偨擔廏偲偄偆憁偼帺奞丄傕偆堦恖偺擔媥偼壛栁愳偺寭揷愳尨偱張孻偝傟偨偲偄偆婰榐偲尵偄揱偊偑巆傞丅
丂擔惃傜暉揷屲恖廜偺徻嵶偵偮偄偰偼丄惓擵巵僒僀僩乮愘僒僀僩偵慻擖乯乽俵姲暥偺朄擄丒暉揷屲恖廜偺堚愓乿丂傪嶲徠婅偄偨偄丅
暉揷屲恖廜偺梫栺傪忋婰偺儁乕僕偐傜揮嵹偡傟偽
丂乮掑嫕嶰擭(1686)妎棽堾擔捠昅偺夁嫀挔(柇妎帥強憼)偵埶傞乯
丂媽楋嶰寧廫嶰擔 寴廧堾擔惃 丂丂丂丂巐廫嶰嵨丂丂悈擖傝栫
丂媽楋嶰寧廫敧擔 尯捠堾擔墌柇堄丂丂嶰廫巐嵨丂丂晄怘巐廫敧擔
丂媽楋嶰寧擇廫堦擔 怺擖堾擔尒柇掕丂丂擇廫堦嵨丂丂晄怘屲廫堦擔
丂媽楋嶰寧擇廫巐擔 棿岝堾擔庫柇尰丂丂擇廫擇嵨丂丂晄怘屲廫巐擔
丂媽楋嶰寧擇廫榋擔 執堾擔怣柇惃丂丂巐廫擇嵨丂丂晄怘屲廫榋擔
偱偁傞丅
丂抐怘擖掕偺寛堄偲巐恖偺彈惈怣搆偲偲傕偵愇幒偵饽傞偙偲偲側偭偨宱堒偼擔惃偺乽幪恎擵峴幰幪彂乿偲偄偆堚彂偑巆偝傟丄偦傟偑徻偟偄丅
偨偩偟丄偙偺堚彂偼擔惃帺昅偺傕偺偱偼側偔丄枛旜偵乽姲暥戞嬨撗楋枹偺崗偵幨偟廔傢傞丅丒丒屼強朷偵埶偭偰擵傪幨偡傕偺側傝丅彨棃屻尒偺恖乆丄擔屽偲堦曉偺夞岦棅傒曭傝岓側傝丅昅幰丂抦墌乿偲偟偰偁傞丅崱巆偭偰偄傞偺偼埨塱俉擭乮1779乯偺幨杮偱偁傞丅
丂側偍丄乽幪彂乿拞偺屲恖廜偺傎偐丄柇忩丒柇娬偺擇恖丄傑偨擔娬丒擔挿丒擔払丒擔嫵丒擔桽丒擔桳偺榋恖偺乽堦枴摨怱乿偺柤偑偱偰偔傞偺偱丄偙傟傪婰偡傞丅
丂丂仸擔娬埲壓榋恖偼栴揷晹榋恖廜偱偁傞丅
--- 乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
乑乽壀嶳導偺抧柤丂擔杮楌巎抧柤懱宯34乿暯杴幮丂傛傝
仦旤嶌媣暷撿忦孲暉揷懞乮媣暷孲丒尰捗嶳巗乯
丂斾媢擈捤偑偁傝丄偙偺捤偼屆暛偱偁傝丄朄壺捤偲傕屇傇丅
斨棞孲嵅攲懞偺晄庴晄巤攈杮媣帥弌帥憁擔惃偲愒嶁孲懢揷懞乮尰寶晹挰乯偺巐恖偺彈惈怣幰偑丄旛慜斔抮揷岝惌偺晄庴晄巤攈抏埑偵傛傝旤嶌偵摝傟丄偙偺抧偺屆暛偵愽擖偟丄抐怘偺枛偵屲恖偲傕棊柦偟偨強偲揱偊傞丅
乑乽姲暥偺朄擄偺暉揷屲恖廜偺堚愓偵偮偄偰乿乮暅尦丗惓擵巵僒僀僩乯丂傛傝
丂仸旛慜柇慞帥怣搆偱偁傞乽惓擵乿巵偑偐偮偰宖嵹偟偰偄偨儁乕僕偱偁傞
丂杮儁乕僕偼暵嵔偝傟丄尰嵼丄尒傞偙偲偼弌棃側偄偑丄徚幐偼惿偟傑傟傞偺偱丄娗棟恖乮s_minaga乯偑暅尦偟偨傕偺偱偁傞丅
姲暥俆擭偺暯夑杮搚帥惈抦堾擔弎丒忋憤墱捗柇妎帥媊櫈堾擔嬆丒嶨巌偑扟朄柧帥抭徠堾擔椆丒捗嶳尠惈帥柧惷堾擔煰傜偺棳嵾丄偺偪偵峕屗惵嶳帺鏆帥挿墦堾擔掚丒栰楥柇嫽帥埨崙堾擔島傜偺棳嵾〖屻榋惞恖〗偺偙偲丄
姲暥俇擭偺恀擛堾柇熌擔擻擈偺抐怘擖掕丒姲暥俉擭偺栴揷晹榋恖廜偺張孻丒捛曻丄摨擭崰偺慞嫽堾擔殺惞恖偺搚拞擖掕側偳偺偙偲丄
亀幪恎峴幰幪彂亁乯寴廧堾擔惃偺堚彂偲偝傟傞乯偵婎偯偔丄暉揷屲恖廜偺峴忬偺偙偲丄
側偳傊偺尵媦偑偁傞丅
乑乽惞乿p.141丂傛傝
丂暉揷屲恖廜偺婰榐傪巆偟偨偺偼抭殺擔屽偲偄偆憁偱偁傞丅偍偦傜偔擔屽偼擔惃偲摨巙偱偁傝丄抐怘擖掕傪嵟屻傑偱尒撏偗傞條偵埶棅偝傟偨偺偱偁傠偆偐丅
丂暉揷斾媢擈捤侾侽丗斾媢擈捤愇幒撪戣栚愖
乑僒僀僩丗乽捗嶳姠斉丂斾媢擈捤乮捗嶳巗暉揷乯乿丂傛傝
丂乮戝堄乯
寱屗屆暛孮偲搶捤丒惣捤
丂偙偺堦懷乮暉揷乯偵偼丄榋悽婭偐傜幍悽婭偵偐偗偰偮偔傜傟偨懡悢偺屆暛偑偁傝丄嵅椙嶳屆暛偺拞偺寱屗屆暛孮偲傛偽傟偰偄傞丅
偦偺巟孮偵偼丄娵嶳屆暛孮乮徚柵乯丄拞媨屆暛孮乮嬨婎乯丄崅栰嶳崻屆暛孮乮嶰婎乯丄寱屗屆暛孮乮廫擇婎乯側偳偑偁傞丅
慜曽屻墌暛偺崅栰嶳崻堦丒擇崋暛埲奜偺傎偲傫偳偼墌暛偱丄墶寠幃愇幒傪傕偪丄拞偵摡娀傪擺傔傞椺偑懡偄偺偑摿挜偱偁傞丅
丂斾媢擈捤偼偙偺屆暛孮拞偵偁傝丄寱屗搶捤乮廫巐崋暛乯偲屇偽傟偰偄傞丅
丂偙偺寱屗搶捤乮廫巐崋暛乯傕墌暛偱丄墶寠幃愇幒傪傕偮屆暛偺堦偮偱偁傞丅暛媢偼丄捈宎栺侾俋倣丄崅偝栺係倣丄愇幒偺婯柾偼丄墱峴俋丏俆倣丄暆栺侾丏俉倣偱丄崅偝偼栺俀倣偱偁傞丅
丂姲暥嬨擭乮1669乯擔楡廆晄庴晄巤攈偺惵擭憁擔惃偲偆傜庒偄巐恖偺彈惈怣幰偼旛慜斔偺廆嫵抏埑偵掞峈偟丄偙偺愇幒撪偱丄戣栚堦搑偵悢廫擔偺抐怘惗妶傪憲傝丄柦傪愨偮丅偙偺偙偲偐傜丄朄壺捤偁傞偄偼斾媢擈捤偲傕傛偽傟偰偄傞丅
偙偺屆暛惣懁偵偼丄傎傏摨宍摨戝偺墶寠幃愇幒暛偑偁傝丄寱屗惣捤乮廫嶰崋暛乯偱偁傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暯惉侾俆擭俉寧丂捗嶳巗嫵堢埾堳夛乮暥丗埬撪斅傛傝乯
暉揷屲恖廜
丂旛慜偱偺姲暥偺朄擄偼丄斔庡抮揷岝惌偵傛偭偰晄庴晄巤攈傊偺揙掙揑側抏埑偑壛偊傜傞丅
旛慜嵅攲杮媣帥廧憁偺扜廧堾擔惃惞恖偼擄傪撡傟偰嶌廈偵愽擖屻丄姲暥俋擭乮1669乯俀寧偵崯偺捤傪抐怘廔鄟偺抧偲掕傔偰擖楿偣傜傟偨丅墱暻偵岦偐偄撉宱彞戣偟偮偮尯戣傪崗傒丄廬偆係恖偺斾媢擈偲嫟偵擖掕偝傟傞丅
擔惃惞恖丂俁寧侾俁擔庘丂丂丂丂丂係侾嵨
柇堄擈丂丂俁寧侾俉擔庘丂丂丂丂丂俁係嵨
柇掕擈丂丂俁寧俀侾擔庘丂丂丂丂丂俀侾嵨
柇尰擈丂丂俁寧俀係擔庘丂丂丂丂丂俀俀嵨
柇惃擈丂丂俁寧俀俇擔庘丂丂丂丂丂係俀嵨丂丂
丂丂丂丂丂暯惉俀侾擭丂崅慶夛徜丂擔楡廆晄庴晄巤攈丂棫惓岇朄夛寶棫丂乮埬撪斅傛傝乯
捗嶳姠斉宖嵹幨恀
丂暉揷斾媢擈捤侾侾丂丂丂丂丂暉揷斾媢擈捤侾俀
乑乽暉揷乿亜斾媢擈捤侾丄俀丂暉揷偺屆暛孮丂傛傝
亅暉揷偺屆暛丒屆暛孮乮係乯亅
丂乮戝堄乯
亙斾媢擈捤亜嘆
丂俰俼捗嶳慄嵅椙嶳墂嬤偔偺媢椝偵偼丄俇悽婭屻敿偵憿傜傟偨彫婯柾偺屆暛偑偑懡偔偁傞丅
寱屗捤乮寱屗侾係崋暛乯偼寱屗屆暛孮偺偁傞媢椝傪搶偵墇偟偰嵶偄扟傪壓傝偰偄偔偲丄媢椝悶偺悈揷偵柺偟偨偲偙傠偵傎傏摨婯柾偺墌暛寱屗侾俁崋暛偲暲傫偱偁傞丅偲傕偵墶寠幃愇幒暛偁傞丅
侾係崋暛偼捈宎栺侾俋倣丄崅偝栺係倣偱丄愇幒婯柾偼墱峴偒俋.俆倣丄暆栺侾.俉倣崅偝偼栺係倣丅偄偯傟傕枹挷嵏偱偁傞丅
抧尦偱偼偙偺侾係崋暛傪寱屗捤傑偨偼斾媢擈捤偲屇傃丄捤擖岥偵偼戝惓俆擭偵晄庴晄巤攈偺怣幰偨偪偵傛偭偰曭擺偝傟偨愇摂饽偑棫偮丅
墶寠幃愇幒偺墱惓柺偵偼戣栚乽撿柍柇朄楡壺宱乿偲崗傑傟丄慄崄偑棫偰傜傟丄嫙壴偑偁傞丅
丂偙偺屆暛偺拞偱丄旛慜偐傜摝傟偰偒偨擔楡廆晄庴晄巤攈偺侾恖偺憁偲係恖偺斾媢擈偺俆恖偑丄柦傪愨偮丅
擔惃偼嵅攲乮尰榓婥挰乯杮媣帥偺憁偱丄姲暥偺朄擄偱捗嶳偵愽暁偟偰偄偨偑丄擔惃偼巰傪妎屽偟丄恖棦棧傟偨偙偺屆暛傪廔鄟偺抧偵寛傔傞丅
擔惃偵婣埶偟偰偄偨旛慜偺係恖偺擈憁傕抐怘擖掕傪寛堄偟屻傪捛偭偰棃傞丅
俆恖偑寛堄偟偨偺偼丄嬛嫵偝傟偨偙偲傊偺峈媍偲丄嬛惂偺晄庴憁偱偁傞偙偲偑傢偐傞偲帺暘偨偪偺張孻偩偗偵巭傑傜偢丄懡偔偺媇惖幰偑偱傞偙偲
傪嫲傟偨偐傜偱偁偭偨丅
俆恖偼姲暥俋擭乮1669乯偺俀寧偐傜俁寧偵偐偗偰抐怘擖掕偵帄傞丅
擔惃偼係俁擔偺抐怘偺屻係侾嵥偱擖掕丄擈憁偺柇惃擔怣偼係俀嵥丄柇堄擔墌偼俁係嵥丄柇尰擔庫偼俀俀嵥丄柇掕擔尰偼俀侾嵥丅
偙偺條巕偼擔惃偺巆偟偨堚彂乮幪彂乯偵婰偝傟傞丅
乑乽2021-12-13嵅椙嶳屆暛孮乿丂傛傝
丂乮戝堄乯
丂姲暥榋擭乮1666乯偵壀嶳斔偺晄庴晄巤攈傊偺抏埑偑巒傑傞丅
旛慜崙嵅攲偺晄庴晄巤攈帥堾丄杮媣帥偺擔惃惞恖偼丄旤嶌偵愽擖偟偨偑丄姲暥嬨擭乮1669乯偵係恖偺擈憁偲嫟偵偙偺搶捤傪抐怘廔鄟偺抧偲掕傔丄捤偺墶寠幃愇幒偵擖饽偟偰峈媍偺抐怘傪巒傔傞丅
搶捤偺墶寠幃愇幒
丂俆恖偼丄愇幒嵟墱偺愇偵乽撿柍柇朄楡壺宱乿偺戣栚傪崗傒丄抐怘傪偟側偑傜撉宱偲彞戣傪懕偗傞丅
戣栚偺崗傑傟偨愇
丂嬤偔偺愢柧斅傪撉傓偲丄俆恖偼摨擔偵朣偔側偭偨偺偱偼側偔丄姲暥嬨擭嶰寧廫嶰擔偐傜嶰寧擇廫榋擔偵偐偗偰堦恖枖堦恖偲朣偔側偭偰偄偭偨條憡偑抦傜傟偰偄傞丅嵟弶偵朣偔側偭偨偺偼丄擔惃惞恖偱偁偭偨丅
丂仸戣栚愇偺幨恀傪揮嵹偡傞丅
丂暉揷斾媢擈捤侾俁丂丂丂丂丂暉揷斾媢擈捤侾係
乑乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿丂傛傝
丂徍榓係俁擭暉揷屲恖廜300墦婖朄梫傪尩廋偡傞丅
偙偺帪丄搶捤偲惣捤偺娫偵丄嫙梴搩偲嬪旇偑寶偰傜傟傞丅
嬪旇偼攐恖憡梩桳棳偺嬪乽恎傪婑偣崌偆偸偔傕傝偺傒傪偄偺偪偲偡乿偑乽弣嫵暉揷屲恖廜嶰昐擭墦婖乿偺慜彂偒偲偲傕偵崗偝傟傞丅
丂擔惃偼寶晹偺嶻偱丄俉嵨偱嵅攲偺杮媣帥偵擖帥丄侾俇嵨傑偱廋峴丄姲塱俀侾擭傛傝巘愓傪宲偓丄杮媣帥廧偲側傞偲偄偆丅
係恖偺彈惈偺偆偪丄柇惃擔恵偼嵅攲懞弌恎丄柇堄丒柇尰丒柇掕偼寶晹懢揷偺揷暎壠偺弌傪巚傢傟傞丅
係擈偵偮偄偰偼寶晹懢揷偺揷暎挬惔巵壠偺曟抧偵斾媢擈捤偲屇傇捤偑偁傝丄偙傟偑係擈偺曟抧偲揱偊傞丅揷暎壠偺夁嫀挔偵傕係柤偺婰嵹偑偁傞丅
側偍丄嬥愳柇妎帥憼偺墑曮俆擭擔屽昅偺夁嫀挔媦傃掑嫕俁擭乮1686乯鍿棽堾擔捠昅偺夁嫀挔偵傕婰嵹偑偁傞丅
丂擔惃偺堚彂偺枛旜偵偼丄姲暥俋擭偺擭婭偲偲傕偵乽抦殺乿偺彁柤偑偁傝丄擔惃傜偺嵟屻傪尒撏偗偨怣幰偑偄偨傛偆偱偁傞丅偝傜偵暥堄偐傜乽抦殺乿偲擔屽偑摨堦恖暔偱偁傞偙偲偑樅傔偐偝傟偰偄傞丅
乑悇掕乽旛慜戝埨帥乮島栧攈乯宖嵹榑峫乿亜戞堦復丂擔楡廆晄庴晄巤攈偺楌巎丂暉揷屲恖廜丂傛傝
丂仸偍偦傜偔丄旛慜戝埨帥乮島栧攈乯偺娭學偡傞乽晄庴晄巤攈乿娭楢偺暥彂偱偁傞偲巚傢傟傞偑丄娞怱偺儖乕僩偵扝傝偮偗側偄偺偱丄偼偭偒傝偟側偄丅
丂乮戝堄乯
戞堦復丂擔楡廆晄庴晄巤攈偺楌巎
乽幪恎偺峴幰幪彂乿暉揷屲恖廜
丂暉揷屲恖廜偲偄傢傟傞偺偼丄嵅攲榋恖廜偲摨偠偔丄姲暥朄擄偺堦偮偱偁傞丅
丂杮媣帥弌帥憁丄擔惃偑丄奺抧偵偺偑傟側偑傜晍嫵妶摦傪峴偭偰偄偨偑丄枊晎偺扵嶕偺庤偼偒傃偟偔丄恎傪抲偔強傕側偄忬懺偲側偭偨丅偙偺偨傔姲暥嬨擭丄尰丄捗嶳巗暉揷偺嵅椙嶳屆暛偺拞偱丄晄庴晄巤媊偺偨傔傒偢偐傜抐怘偟偰丄擖掕偝傟偨傕偺偱偁傞丅
丂偙偺偲偒丄巐柤偺斾媢擈偑峴傪偲傕偵偟偨傕偺偱偁傞丅
丂崱乽幪恎偺峴幰幪彂乿偲尵偆擔惃忋恖偺彂抲偵傛偭偰丄偦偺堄偲偡傞偙偲傪丄幟傇偙偲偲偡傞丅
仦乽幪恎偺峴幰幪彂丂戞堦乿偺暥堄
丂朄壺宱丄朄巘昳偵偼丒丒丒乮拞棯乯丒丒丒
丂屷乆偼怣椡嫮偔宱暥庍彂傪巘偲嬄偄偱廋峴偟偰偒傑偟偨偑丄嫀擭傛傝涍棃丄庬乆偺埆岥偑偁傝丄嫲傠偟偄帠偱偁傝傑偡丅
丂宱暥偵偼丄怣椡寴屌偺幰偑丄彅暓偺掜巕偱偁傞偲偁傝丄慶巘偼乽怣椡偩傕庛偔偽丄偄偐偵擔楡偑丄掜巕丒抙撨偲柤忔傜偣媼偆偲傕丄傛傕屼梡偄偼岓偼偠丄怱偵擇偮傑偟傑偟偰丄怣怱偩偵庛偔岓偼偽丄曯偺愇偺扟傊偙傠傃丄嬻偺塉偺戝抧傊棊偮傞偲巚彚偣丄戝垻旲抧崠媈偄偁傞傋偐傜偢丄懘帪丄擔楡傪崷傒偝偣媼偆側丄曉偡曉偡傕奺偺怣怱偵埶傞傋偔岓乿偲偄傑偟傔媼偆偰偄傑偡丅
丂廧傓搚抧傕側偄恎偱偁傝傑偡偺偱丄弌帥偺杮婅偵晪偔傛傝懠帠側偔丄偦傟屘偵朄媊傪棫偰丄恀懎抝彈丄堎懱摨怱偺怣椡偵擟偟偰丄柇惃丒柇堄丒柇尰丒柇掕丒擔惃偺夞岦傪偍婅偄偄偨偟傑偡丅暲偵柇忩丒柇娬偺擇恖丄傑偨擔娬丒擔挿丒擔払丒擔嫵丒擔桽丒擔桳埲忋廫嶰恖偼丄奆堦枴摨怱偺峴幰偱偁偭偰丄摨偠偔丄巰偵晪偒傑偡丅奺埵傕憵業偺屼恎偱偁傝傑偡偐傜丄嵟屻丄椪廔偺徜丄彅暓偑寎偊偺慏幵偵忔偟偰寎偊偵嶲傝傑偡丅塢乆丅
丂晝堜偺柇忩丄柇娬偺擖掕偟偰壥偰偨斾媢擈媦丄栴揷晹偺榋恖廜偺柤傪偁偘偰丄堦枴摨怱偺幰偱偁傞偐傜夞岦傪棅傓偲彂偐傟偰偄傞丅
仦乽幪恎幪彂戞擇乿偺暥堄
乻暥復偑寚棊乼亙儅儅亜
偟偨丅亙儅儅亜
丂惤偵帠偺怱傪埬偠偰尒傟偽丄庒偟抦恖偑偁傟偽丄嵼強偺幰偑弌偰棃偰丄強傪捛弌偟丄偦傟偺傒側傜偢丄忛庡偵傑偱怽偟忋偘偰丄杮崙偼忛庡堘攚偺戝埆恖偲偟偰丄椬崙傊憲傝幪偰朄幰傪擸傑偡偙偲偼昁掕偱偁傞偲丄惀傪抦傝側偑傜堦恖偲偰傕丄嵼壠傪怽偟傑偟偨側傜偽丄堦恖偼廫恖偲側傝丄廫恖偼昐恖偲側傝丄埥偼寶晹偺朄幰丄懢揷偺恊椶摍丄峴幰偺柪榝傪偐偊傝傒偢偟偰丄嵾壢偵栤偼傞傞偙偲傪丄傛偔彸抦偟偰偄傑偡丅
丂帺嶿偺條偵暦偊傑偟傚偆偑丄嫲傜偔巐恖偺峴幰偼丄擛愢廋峴偺朄幰偱偁偭偰丄婼巕曣恄丄廫梾檵彈偑晄徰偺朸偵廻傝媼偆偰丄暓慜偺屼惥偺擛偔斵摍偺嵟屻丄椪廔傪屼庣岇壓偝傞偱偟傚偆丅
丂帺暘偼偦傟掱傑偱偲偼巚偄傑偣偸偑丄宱暥偺嫊偟偐傜偞傞偙偲傪抦傞偙偲偑弌棃傑偡丅
丂慠偟側偑傜丄摉帪偼埆悽偱偁偭偰丄崱搙丄宱暥偵憡姁傑偡偙偲丄懡悢偺恖偑埆偟偲巚偭偰丄尵偄傑偡偑丄彅暓強扸偺墄傃偑偁傝傑偡丅
丂偟偐偟側偑傜丄彅恖偼偙偺偙偲傪埆岥偄偨偟傑偡丅
丂惀偼夓婼偑悈傪傒偰丄墛偲尒傞條偵丄峴幰傪尒傞栚傕丄奺偺帺傜偺峴偄偑丄廋峴偑懌傜側偄偺偱丄棪捈偵暔偺巔傪尒傞偙偲偑丄弌棃側偄偐傜偱偁傝傑偡丅埆斾媢擈偲偄偼傟偰偄傞屲恖偼乽変傟恎柦傪垽偣偢丄偨偩柍忋摴傪惿傓乿偺嬥暥傪帺暘偺娽偺擛偔丄怱摼偰丄堦擔傪棅傝偲偣偢丄堦帪堦帪偺巙乽彫梸抦懌幪埆帩慞乿偺峴幰偱偁偭偰丄乽棃悽偵墬偰丄昁偢嶌暓傪摼傞偙偲乿偑擮婅偱偁傝傑偡丅
丒丒丒乮拞棯乯丒丒丒
丂扅丄屻悽傪婅偆恖偺嫲傞傋偒偙偲偼鎺朄嵾偱偁傝傑偡丅昁偢嫲傞傋偒傕偺偱偁傝傑偡丅
丂柇惃丒柇堄丒柇掕丒柇尰丄偺巐柤偺幰偑丄帪愡摓棃偟偨偺偱抐怘傪偟偨偄偲怽偟弌偰偄偨偑偙偺偙偲偵偮偄偰偼偟偽偟偍偟偲偳傔偰偄偨偑崱擭偵側偭偰斾媢擈偺廋峴偼摉抧偺朄嵾偱偁傞偲帥傗杮壠偵屼嵐懣偑偁偭偨偺偱偙偺暘偱偼杮婅偵晪偒偨偄偲偨偭偰婅偄弌偰棃偨偺偱愘憁傕彸抦偄偨偟傑偟偨丅乽変傟恎柦傪垽偣偢丄偨偩柍忋摴傪惿偟傓乿偲怱摼偊偰棃悽偵墬偰昁偢嶌暓傪摼傞偙偲偑擮婅偱偁傞偲彂偐傟偰偄傞丅
仦乽幪恎廍彂丂戞嶰乿偺暥堄
丂斾媢丄斾媢擈屲恖偺嵟屻椪廔偺帠傪丄怽暦偐偣偨偄偲偙傠傕丄戲嶳偁傝傑偡偑丄崯帠傪怽偟傑偟偨側傜偽丄忋堄傪埲偰丄杮崙偵憲傝曉偡條偵偝傟傞忈偑偁傝傑偡偙偲偼屼懚抦偺捠傝偱偁傝傑偡丅偦傟屘丄庬乆偲暘暿偟偰丄彅恖偺婥椡傪寁傝丄帪崗傪姩偊丄廧強傪恞偹偰丄偦偺寢壥丄姲暥戞嬨屓撗擭擇寧嶑擔偺憗挬偺屵慜榋帪偵丄惀傛傝撿堦棦敿掱偺偲偙傠丄暉揷懞偺壠偺墱偺嶳楬偺曈傝偵丄捤偑偁傝丄偙偺捤傪楈嶳戝抧偲墄擖傝偰丄欀涠梾傪偐偗丄壴崄摂柧偺嶰嫙梴傪旛偊丄屲恖堦摨偑庤傪崌偣丄娽傪暵偠丄撿柍柇朄楡壺宱偲戝惡偵偰彞偊曭傞桳條丄庩彑偲傕丄怽偡偵椶偄傑傟側偙偲偲峫偊傑偡丅崯帪偼嶰曮彅揤傕丄棃椪偝傟丄擺庴偝傟傞偙偲偱偁傝傑偡丅
丒丒丒乮拞棯乯丒丒丒
丂斾媢丒斾媢擈屲恖偺椪廔偺偙偲傪抦傜偣偨偄偲偙傠傕偁傝傑偡偑丄偦偆偡傟偽忋堄偵傛傝丄杮崙偵憲傝娨偝傟傞偙偲昁掕偵懚偠傑偡偺偱偙偺暉揷懞偺屆偄捤偺拞偱丄偙偙傪楈嶳戝抧偲峫偊偰擖柵偡傞愊傝偱偁傝傑偡偐傜怱偁傜傫恖偼丄枅擭擇寧偵偼偙偺抧傊屼嶲寃壓偝偄偲婰偝傟偰偄傞丅
仦乽幪恎幪彂丂戞巐乿偺暥堄
丂晄惿恎柦偺峴幰偺強婅傓側偟偐傜偢丄撗擇寧嶑擔丄塊偺崗偵丄斵偺捤偵恞偹擖傝丄屲恖堦摨楢嵗偟偰丄乽桳憡丒柍憡丒旕桳憡丒旕柍憡偺堄傪摼偰乿偙偺條側廜惗偺悢偵嵼傜傫幰偵丄恖偁傝偰暉傪媮傓偙偲丄変傕恖傕娞梫偱偁傞偙偲傪怽偟暦偐偣偰丄拞摴幚憡偺丄撿柍柇朄楡壺宱傪彂偒曭偭偨夞悢偼丄
丂丂曭彂屼戣栚丂擇昐嬨廫曉丂柇惃
丂丂丂丂摨丂丂丂擇昐巐廫敧曉丂柇堄
丂丂丂丂摨丂丂丂擇昐屲廫榋曉丂柇尰
丂丂丂丂摨丂丂丂擇昐嬨廫曉丂柇掕
丂丂丂丂摨丂丂丂嶰昐曉丂擔惃
丂偙偺條偵屲恖偵丄奺挔柺偑偁傝傑偡丅
丒丒丒乮拞棯乯丒丒丒
仦乽幪恎幪彂丂戞屲乿偺暥堄
丂偙偺偨傃丄斾媢丒斾媢擈廜偺嵟廔椪廔傪尒憲傝偄偨偟傑偡丅偟偐偟柪幏偵偲傜傢傟偨斾媢丒斾媢擈偱偁傞偲丄庢傝嵐懣偝傟傞偙偲偼丄撪乆懚偠偰偄傑偡丅娽慜偵尒偊偰丄惔忩側廋峴偵偮偄偰傕丄桺埆岥偣傜傟傑偡丅
丂嫷傫傗丄嶳扟偵偐偔傟丄彅恖偵塀枾偵偡傞帠偵偮偄偰丄媈擮傪帩偨傞傞帠偼栟偺偙偲偲懚偠傑偡丅愘憁丄崯偺棟桼傪怽偟忋偘偰傕丄偦偺媈偼惏傜偟偑偨偄偺偱丄崱暓慜偵墬偰丄帺愢惥尵偺嫵偊偱偁傝傑偡偺偱丄愘憁傕傑偨丄彅恖傊偺偁偐偟偺偨傔丄堦巻惥忬傪巆偟傑偡丅愘憁丄晄徻偺恎偱偁傝傑偡偑丄旛慜崙捗崅孲寶晹偺惗傑傟偱丄擇媨怴暫塹偺懛偱偁傝傑偡丅惗擭敧嵨偺帪丄摨崙斨棞孲嵅攲丄杮媣帥丄廳慞朧偵偰弌壠偟偰丄惗擭廫榋嵨嬨儢寧娫丄暓嫵傪妛傃丄姲塱擇廫堦擭峛怽惓寧廫嬨擔傛傝丄巘偺愓傪偮偓丄奜偵偼朄柦憡懕偺偐偨偪偲偟偰丄怳晳偄丄撪偵偼柤暦柤棙丄変枬曃幏偺幐偁傝丄偙偺條側幐攕傪惗擭擇廫屲嵨廫儢寧娫傕偦偺幐傪峫偊偢偵偍傝傑偟偨丅
丂擇廫屲嵨偺屲寧擇廫擔偵戝擔椫偵岦偐偄曭偭偰丄愘憁丄嬸抯埮柣偵偟偰丄暓摴偺怺媊傪抦傜偢丄慠偟側偑傜丄廻廗怺岤偺嬈偱偁傝傑偡偺偱丄枛戙摉帪偺埆悽偵惗傪庴偗丄堦惗擖柇妎偺戝嬌朄傪峴傢偢丄弌壠偺恎偲側偭偰丄柤棙丒柤暦丄変枬丒曃幏偺嫲傠偟偄偙偲偼丄彸抦偄偨偟傑偟偨偺偱丄廔偵丄変傟恎柦傪垽偣偢丄扐柍忋摴傪惿傓峴幰偲側傝傑偟偨丅
丒丒丒乮拞棯乯丒丒丒
丂愘憁偑嵟屻偺摫巘傪偄偨偟傑偡偑丄柪幰偺峴幰偱偁傞偲巚偆恖偺偨傔偵怽偟忋偘傑偡丅
幏拝偺曽傪埲偰丄摫巘傪偄偨偟傑偡側傜偽丄屲恖嫟偵柍娫抧崠偵懧偪傞偱偁傝傑偟傚偆丅崯摍丄屲恖偼乽嵟枛屻偺恎偵墬偄偰弌壠偟偰丄暓摴傪惉偤傫乿偺嬥尵偵傛偭偰丄夁嫀惗乆偺廳嵾丄尰嵼偺枱乆偺嬈丄斚擸丄廜嵾丄憵業偺擛偔宐擔傛偔徚彍偣傫偲丄弌壠偟偰丄怱側偔傕丄扅丄撿柍柇朄楡壺宱偲彞偊偰偄傑偡丅
丂偙偺屘偵媈側偔丄扅丄撿柍柇朄楡壺宱偲彞偊媼偆傋偟丅
丂柍擇偺怣怱偵廧偟偰丄扅丄撿柍柇朄楡壺宱偲戣栚傪彞偊媼偊偽丄乽婅傢偔偽丄崯偺岟摽傪埲偰晛偔堦愗偵媦傏偟偰変摍偲廜惗偲奆嫟偵暓摴傪惉偤傫乿偺嬥暥偺擛偔丄奆嫟偵丄暓偺巊偲側傝丄帺恎偺怣椡偼庛偔偟偰丄懠恖偺廋峴傪攋幐偡傞偺偼丄柍娫偺嬈場偲偄偆傋偒偱偁傝傑偟傚偆丅撿柍柇朄楡壺宱丅
仦乽幪恎幪彂丂戞榋乿
丂姲暥戞嬨撗楋枹偺崗偵幨嶩傞丅
丂埆昅側傝偲瀚傕丄屼強朷偵埶偭偰擵傪幨偡幰栫丅彨枓屻尒偺恖乆丄擔屽偲堦曉偺夞岦棅傒曭岓栫
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昅幰丂抦墌
丂丂埨塱敧擭屓堝嬨寧丂丂擔丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂塃傪枓摨晄抦
丂乽幪恎幪彂丂戞榋乿偼擔惃忋恖偺彂抲偱偼側偔抦墌偲尵偆恖偑壛昅偟偨傕偺偱偁傞丅
丂偙偺乽抦墌擔屽乿偲偼偳傫側恖暔偱偁偭偨偺偐丄傑偨丄擔惃忋恖偲偳傫側娭學偺偁偭偨恖暔側偺偐偵偮偄偰敀旹晲摽愭惗偼亀暉揷屲恖廜戞嶰昐墦婖亁偵偁偨傝姧峴偝傟偨乽帒椏乿偺拞偱師偺傛偆偵弎傋傜傟偰偄傞丅
丂姲暥偐傜嫕曐偵帄傞栺榋廫梋擭娫偵乽擔屽乿偲摨柤偺恖乆偼彅婰榐偐傜敳彂偟偰傒傞偲丄幍柤偺恖偑偁傞丅偟偐偟偙偺拞偐傜乽抦墌擔屽乿偱偁傞偲偡傞妋徹偼側偄偑柇妎帥偵揱傢傞乽擔屽帠乿偲徧偡傞屆偄丄夁嫀挔傛傝師偺傛偆側婰柤偺偁傞偙偲傪尒弌偟偨丅
丂丂瀚堊埆昅埶強朷柍惀旕廆幰栫
丂丂丂丂姳帪墑曮戞屲挌枻榋寧擓巐擔丂丂丂丂丂丂仜仜仜仜
仜丂仜
仜仜偺張偼杗廯傪傕偭偰枙徚偝傟偰偄傞偑
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昅幰丂?丂殺
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擔丂屽丂壴墴
偲敾撉偝傟傞偺偱偙偺恖暔偑幪恎幪彂丂戞榋偺昅幰乽抦墌擔屽乿偲摨堦恖偱偁傞偲棫徹偡傞偙偲偑弌棃傞丅塢乆丅
乽桺丄擔惃忋恖偲偺娭學偵偮偄偰偼屻擔偺尋媶偵傑偨偹偽側傜偸偑丄擔惃忋恖傛傝幪彂偺幨昅傪埶棅偝傟偨偲夝偡傟偽丄摨栧傑偨偼梋掱恊岎偺偁偭偨恖暔偲憐憸偝傟傞丅乿塢乆丅
彯昅幰晄抦偲偁傞偺偼挊柤側傜偞傞幰屘偵尓懟偟偰晄抦偲婰偟偨傕偺偱偁傞丅
場偵埨塱敧擭偼姲暥嬨擭傛傝昐廫擭屻偱偁傞丅
丂偙偺乽幪恎幪彂乿偵偼抐怘偟偰擖掕偣偞傞傪摼側偐偭偨摉帪偺忬嫷傗丄偦偺怱忣偑惗偒惗偒偲昤幨偝傟偰偄偰丄崱傕撉傓恖偺嬢傪惓偝偟傔傞傕偺偑偁傞丅
乻埲壓暥復晄柧乼亙儅儅亜
丂丂丂-end-
丂
仦旛慜偵墬偗傞幪恎偺峈媍
2018/12/23捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俇姫丂嬤悽侾乿1984丂傛傝
堊惌幰偵懳偡傞幪偰恎偺峈媍偼慡崙揑偵懡偔敪惗偡傞丅
旛慜偵偍偄偰偼師偺傛偆側幪恎偺峈媍偑抦傜傟傞丅
椆塣堾柇娬擔宐丄斨棞孲曢揷懞椆杮帥尦慶擔惓丄壜弴堾擔惓傜偼帺奞丄
慞嫽堾擔殺乮杒挿悾懞乯丄斾媢擈柇惷乮晝乆堜懞丄柇忩丄恀柇堾柇忩擔擻擈乯丄朄楡堾擔嫵乮擔鉙乯乮戝岦堜懞乯傜偑抐怘擖掕丄摿偵擔殺偼惗偒側偑傜壉偵擖偭偰搚拞偵杽傑傝彞戣偟偰壥偰傞偲偄偆丅
丂仺斾媢擈柇惷乮晝乆堜懞丄柇忩丄恀柇堾柇忩擔擻擈乯偵偮偄偰偼丄忋弎乽榓婥孲晝堜偺柇忩條乿傪嶲徠丅
丂仺擔殺忋恖偼師崁傪嶲徠
2019/05/29捛壛丗
慞嫽堾擔殺忋恖丗
仜擔殺忋恖曟旇乮壀嶳愰柇帥偵偁傝乯柫丂傛傝
擔殺惞恖偼擔慏惞恖僲崅掜僯僔僥丄惵峕柇挿帥偺廧怑僞儕
姲暥榋擭廫擇寧堸悈峴楬僯崙庡乮埲壓偼枹妋擣乯丂偲偁傞丅
丂仸惵峕柇挿帥偼楡徆帥枛丄惓廧嶳偲崋偡傞丅姲暥俇擭攑帥偲側傞丅
丂丂丂仺旛慜偵墬偗傞姲暥俇擭偺晄庴晄巤攈攑帥堦棗偺噦俉傪嶲徠丅
丂丂丂仺旛慜惵峕揤栰敧敠媨撿捁嫃戣栚/惵峕懞擔楡廆柇愹帥敧敠戝曥嶧憸
丂仸壀嶳愰柇帥偼旛慜戝嫙懞丒撪揷懞丒壀懞丒搶屆徏懞丒惣屆徏懞拞
仜乽壀嶳暥屔俆侾丂壀嶳偺廆嫵乿挿岝摽榓丄擔杮暥嫵弌斉丄徍榓係俉擭
丂擔殺忋恖偺娀壉
仜乽壀嶳導巎丂戞俇姫丂嬤悽侾乿1984丂傛傝
丂擔殺忋恖偺娀奧丗捗搰柇慞帥憼
仜乽嬛惂晄庴晄巤攈偺尋媶乿媨嶈塸廋丄暯妝帥彂揦丄1959乮徍榓俁係擭乯丂傛傝亙p.155亜
壀嶳導杒挿悾丄嵅摗弔氭巵偺悈揷偺懁偺捤偼屆偔偐傜晄庴晄巤愭巘偺曟偲偟偰崄壺偑嫙偊傜傟偰偄偨偑丄侾侽擭傎偳慜偵敪孈偝傟丄堚崪偼捗搰柇慞帥傊夵憭偝傟傞丅徍榓俁侾擭俋寧侾擔撧椙杮扖栫乮棫柦娰戝妛嫵庼乯丄摗堜弜乮壀嶳懢妛嫵庼乯丄悈栰嫳堦榊乮壀嶳戝妛彆嫵庼乯偲偲傕偵嵅摗巵戭傊庍擔泏忋恖偵埬撪偝傟攓尒偟偨偑丄偙偙偵偼戝彫俀屄偺娀壉偑弌偰戝偼俁広偽偐傝丄彫偼偦傟傛傝彮偟彫偝偄丅俀広係丆俆悺偺強丄廃埻偵俁屄偺彫寠偑偁偗傜傟丄宱婘偲巚偟偒傕偺偑嫟偵杽傔傜傟偰偄偨丅忋奧偵偼乽怺擖慣掕尒廫曽樑乿偲偄偆暥帤偑旝偐偵撉傑傟丄彫偝偄曽偺娀偵偼晈恖偺孂偲栘榦摍偑偁偭偨丅栘榦偼戝娀偺曽偵傕偁偭偨丅
偍偦傜偔偼偙偺摉帪偺抐怘擖掕偺愭巘偱丄晈恖偑偦偺偍嫙傪偟偨偺偱偼側偄偐丅偦偺擖掕幰偑壗恖偱偁傞偐偼婰榐傕岥旇傕慡偔揱傢偭偰偄側偄丅
仜乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿憡梩怢丄戝錟弌斉丄徍榓俆侾擭丂傛傝亙p.103-104亜
慞嫽堾擔殺偼擔慏掜巕丄楡徆帥枛偺廧帩偱偁偭偨丅壀嶳巗戝栰捯乮捯懞丒屻杒挿悾懞乯偱帺傜娀傪嶌傝丄偦偺拞偵擖傝丄廫悢擔堸傑偢怘傢偢偺屻壥偰傞丅愭擭揷曓偺拞偐傜丄偦偺帪偺娀偑僶儔僶儔偵側偭偰孈傝弌偝傟偨拞偵忋晹偲墶偺晹偵嶰屄偺岴偺偁傞斅偑偁偭偨丅屇媧偺偨傔偺岴偱偁傠偆丅
丂側偍乽怺擖慣掕尒廫曽樑乿偺敧帤擇峴偺杗彂傕偁偭偨丅偦傟偵榦侾屄丅
偝傜偵丄嬤偔偱堦屄暘偺婔暘彫偝偄娀偑僶儔僶儔偺斅愗傟偲側偭偰弌搚偡傞丅拞偵孂偲榦偑擖偭偰偄偨偙偲偐傜丄撃怣偺晈恖偑峴傪嫟偵偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅
丂偙偺俀屄偺娀偺斅偼捗搰柇慞帥偵曐娗丄曟偼壀嶳巗惣屆徏愰柇帥偵偁傞丅
2019/08/19捛壛丗
仜乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿崅栰悷丒壀揷柧旻丄崙彂姧峴夛丄徍榓俆俀擭丂傛傝
捗嶳巗椦揷丂忩怣堾擔媣曟丗
擔媣偼擔煰偺偁偲傪宲偄偱杮峴帥偺廧怑偵側偭偨偍傝丄姲暥朄擄偵偁偄捗嶳寭揷愳尨偺孻応偱巃庱偝傟偨丅
丂仸忋婰偵傛傟偽丄旤嶌偱傕媇惖偑弌傞丅椦揷偵擔媣偺曟偑偁傞丅乮幨恀宖嵹乯
丂丂丂丂嶌椦揷擔媣曟
丂仸擔煰偲偼嬍憿抙椦俆悽丄捗嶳尠惈帥楌戙偱偁傞丅忋婰偵偼杮峴帥偲偁傞偑尠惈帥偱偁傠偆丅
丂仸旤嶌捗嶳棼惈帥偲偼晄徻偱偁傞偑丄偍偦傜偔姲暥偺朄擄偱攑帥偲側偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅
2024/09/25捛壛丗
旤嶌偱偺朄擄乮旛朰乯丂丂丒丒丒旤嶌偺擔楡廆彅帥拞丒丒丒丂傛傝丗
丂忩怣堾擔媣丄寭揷釦偱孻巰乮擭寧晄徻乯丄擔媣偼擔煰偺朄掜丅擔媣嫙梴搩偑捗嶳巗屆椦揷嶳崻偺媢忋偵寶偰傜傟傞偑丄偦偺惣侾俆娫掱偺強傕忋恖捤偲屇偽傟傞応強偑偁傞丅偙偙偵孻巰屻偺擔媣偺庱媺傪枾憭偟偨偲棦徧偝傟偰偄傞丅乮屆椦揷嶳崻偲偼晄柧偱偁傞偑丄椦揷嶳崻岞柉娰偑偁傞晅嬤偱偁傠偆偐丅乯
丂側偍丄暉揷屲恖廜巎愓乮斾媢擈捤乯偵忩怣堾擔媣偺嫙梴搩偑偁傞丅
丂
2019/09/19捛壛丗
仜乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿憡梩怢丄戝錟弌斉丄徍榓俆侾擭乮1976乯丂傛傝
丂仦旤嶌捗嶳杮峴帥丗丂仺捗嶳惣帥挰杮峴帥亙旤嶌偺彅帥拞亜
墑庻嶳偲崋偡丅嫗搒柇妎帥枛丅庴晄巤攈偵愙庢偝傟丄攋媝偝傟傞丅
丂仦杮庻堾擔慏忋恖
擔慏乮壀嶳楡徆帥俀俁悽丄捗搰柇慞帥俋悽乯偼旤嶌媣暷撿孲愳岥懞柇愹埩傪嫆揰偲偟偰峅嫵拞拃傢傟丄暉搉懞嶳崻偺峕揷巵偺搚憼偵愽峴拞偵庘偡丅
扽壩偵偰涠旟偵晅偡偲偄偆丅
丂仸柧楋巐曡滫乮1658乯庘丅丂仺杮庻堾擔慏忋恖
丂仦擛朄堾楢媥
恄栚偵偰抐怘
丂仸徻嵶晄柧丄恄栚偼尰嵼偼媣暷孲媣暷撿挰恄栚拞偐
丂仦朄棫堾擔廏
姲暥俋擭乮1669乯俈寧俈擔捗嶳擇奒挰偵偰帺奞
丂仸徻嵶晄柧丄擇奒挰偼捗嶳忛壓
丂仦忩怣堾擔媣
寭揷愳尨偱孻巰丄孻巰偺擭寧偼晄徻丄嫙梴旇偼捗嶳巗屆椦揷帤嶳崻偺媢忋偵偁傞丅偦偺惣撿侾俆娫傎偳偺強偵忋恖捤偑偁傞丅擔媣偺庱媺傪枾憭偟偨偲樭徧偡傞丅
丂丂仺擔媣偼偡偖忋偵宖嵹偁傝丅
丂仦掑嫕俀擭乮1685乯係寧俀俋擔旤嶌媣暷撿孲媩嶍懞洀愹帥抙壠偱戝彲壆壨尨慞塃塹栧傜侾侽恖偺狩孻
丂仸徻嵶晄徻丄壨尨慞塃塹栧偵偮偄偰晄庴晄巤偲偺娭學偺妋擣偑庢傟側偄丄媩嶍懞洀愹帥偼晄徻丅
忔愬朧屲椫搩丗
丂榓婥孲摗栰杒懞乮榓婥孲榓婥挰摗栰348乯泬惉帥偺搶偵偁傞丅
姲暥俇擭乮1666乯抮揷岝惌偺晄庴晄巤抏埑偵斶暜偟偨摨抧偺朄災嶳暉徆帥廧怑忔愬朧乮惓慞朧乯偼帺傜恉傪愊傒廜恖娐帇偺拞偱壩掕偟偨愓偲偄偆丅
杮惈堾擔泏丗
丂擭戙偵偼尵媦偑側偄偑丄榓婥偵愽峴偟偰偄偨杮惈堾擔泏偼夆偐偵曔棛偺摜傒崬傑傟丄峇偰偨怣幰偑擔泏傪彫壆偺扽昒偺拞偵塀偡丅
曔棛偼愊傒忋偘偨扽昒偵偐偨偭傁偟偐傜憚傪巋偡丅偦偺堦巋偑傂偦傫偱偄偨擔泏偺榚暊傪漃傞傕丄偮偄偵氵堦偮棫偰偢偵擄傪摝傟傞丅
偟偐偟丄彎偼壔擽偟丄捝傒傕寖偟偔丄壛偊偰扵嶕傕尩偟偔側偭偨偺偱丄擔泏偼娕岇偺怣幰偺娽傪偐偡傔偰晬嬤偺忋丄拞丄壓偺嶰偮偺抮偺撪偺拞倐偺抮偵摍恎偟偰帺嶦偡傞丅偦偺偨傔丄擔泏傪偐偔傑偭偨媑朳壠偼抐愨傪柶傟丄崱擔偵帄傞丅
---乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿廔---
仦弶婜撪怣朄擄
2018/12/23捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俇姫丂嬤悽侾乿1984丂傛傝
丂仦愒嶁孲壨尨栄懞彲壆抐嵾朄擄
丂墑曮俁擭乮1675乯愒嶁孲壨尨栄懞彲壆憏暫塹媦傃偦偺掜巗榊塃塹栧偼擭峷枹恑偲晄庴晄巤憁妎忔堾偺塀暳偵傛傝丄抐嵾偲側傞丅
妎忔堾偼姲暥俋擭乮1669乯廆巪懼偊傪廰傝丄摨孲惣拞懞偵懞梐偗偲側傞傕丄偦偺梻擔峴曽傪偔傜傑偡丅偦偺偨傔惣拞懞彲壆偼擖楽俀侽擔偺屻丄栶傪彚偟忋偘傜傟傞丅
偦偺屻妎忔堾偼壨尨栄懞偺憏暫塹傜偵摻傢傟傞丅憏暫塹媦傃偦偺掜巗榊塃塹栧偼揤堜偵暓抎傪塀偟丄妎忔堾偺巰屻乮姲暥侾俁擭庘乯曟傪寶偰傞傎偳偺怣幰偱偁偭偨丅
斵傜偼栶恖偺娽傪偛傑偐偡偨傔丄壀嶳斔偑恄摴惪偺嫮惂傪掆巭偟偨偺偪傕丄昞柺偼恄摴惪偱捠偟偰偄偨丅偙傟偼偁偔傑偱怣嬄傪旈枾棥偵庣傝捠偦偆偲偡傞巔惃偱偁傠偆丅
丂擭峷枹恑偵偮偄偰傕嵞惗嶻傪晄壜擻偵偡傞傎偳偺夁崜側擭峷挜廂偵懳偟偰嫅斲偺巔惃傪娧偙偆偲偡傞傕偺偱偁偭偨丅
棟晄恠側晄庴晄巤抏埑偵懳偟偰偁偔傑偱嫅傕偆偲偡傞巔惃偲捠偢傞傕偺偱偁偭偨丅
丂仦斨棞孲戝堜懞晄庴晄巤朄擄
丂墑曮俇擭乮1678乯戝堜懞偱偼摨懞偺朄楡偺憭媀傪晄庴晄巤憁楡廧朧偑庢傝峴偭偨偙偲偑業尠偡傞丅
楡廧朧偍傛傃朄楡偺樹5恖偑楽幧丄彲壆敧塃塹栧偑捛崬偲側傞丅
偙偺帪丄庢挷傋偵偮偄偰偼丄擭婑拞偐傜丄乽憑嶕偑尩廳偵幚巤偝傟傞偲丄懡悢偺専嫇幰偱弌偰廂廍偑偮偐側偔側傞偺偱揔摉偵憑嶕偣傛乿偲偺柦偑弌傞丅
偙偺柦偺堄枴偡傞偲偙傠偼丄峀斖埻偵偐偮埑搢揑懡悢偺晄庴晄巤撪怣幰偑懚嵼偟偰偄偨偲偄偆偙偲偺偁傞庬偺乽嫲傟乿偑懚嵼偟偨偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅
丂仦旛拞壛梲孲塅嶳懞撪怣朄擄
丂掑嫕尦擭乮1684乯旛拞徏嶳斔椞偱偁傞壛梲孲塅嶳懞偱丄彲壆敧榊塃塹栧偺樹揱塃塹栧偑帥惪傪嫅斲偟偨偙偲偐傜丄晄庴晄巤撪怣偑敪妎偡傞丅
斵偵怣嬄傪姪傔偨壀嶳斔偺妎堄偲懌庣椞偺忩楡偺憑嶕傪傔偖傝丄嶰斔偺楢実憑嶕偑揥奐偡傞丅
妎堄偼忋摴孲拞旜懞偱曔敍偝傟擖楽偲側傞丅忩楡偼嵟屻傑偱峴曽偑暘偐傜側偐偭偨偲偄偆丅
偙偺帠審偼晄庴晄巤憁偺峴摦偑懠椞偵傑偱媦傃峀斖埻偵傢偨偭偰偄傞偙偲傪帵偟丄奺抧偱撪怣幰偺慻怐嶌傝偑峴傢傟偰偄偨偲悇應偝傟傞丅
丂仦斶揷晄庴晄巤攈壀嶳忛壓柇椦帥朄擄
丂揤榓俁擭乮1683乯忛壓柇椦帥偺摨廻憁俋柤偑忛壓偺挰壆偵嫃廧偟偰偄傞偙偲偑敪妎丄柇椦帥廧怑媦傃摨廻憁俋柤偑捛曻丄摨廻偺廻庡俉柤偑楽幧丄偦偺屲恖慻丒栚戙丒擭婑傜偼挰梐偗丒捛崬摍偺張暘傪庴偗傞丅
婛偵丄枊晎偼姲暥俆擭乮1665乯憁椀偺嵼壠偱偺晍嫵傪嬛偠偰偍傝丄壀嶳斔傕墑曮俁擭乮1675乯摨條偺嬛巭傪偡傞丅
丂偱偼側偤丄偦偺傛偆側偙偲偑壜擻偱偁偭偨偺偐丅摉帪柇椦帥偼斶揷晄庴晄巤攈偵懏偟丄摨攈偼岞媀堘攚偺晄庴晄巤偱偼側偄偲偺怗傟崬傒偑壜擻偱偁傝丄偦偺偙偲偑摨廻憁偺嵼壠崿嵼傪梕堈偵偟偨壜擻惈偑峫偊傜傟傞丅傑偨懞栶恖傕娷傔偨峀斖埻側晄庴晄巤撪怣幰偵傛傞帥惪偺婾憰偱偁傞丅偙偺応崌丄挰偺廆栧夵挔偵偼憁柤傪懎柤偵婾偭偰婰嵹傪偟偰偄傞丅
丂埲忋偺崻掙偵偼丄乽摨廻憁傜偼愭廧偺俁戙埲慜傛傝弌擖偡傞朧庡乿偱偁傝丄乽柇椦帥偑庤嫹偵側偭偨偨傔挰壆偵廧傑傢偣傞乿傛偵側偭偨偲偺柇椦帥偺曎柧偐傜丄摨廻憁偼晄庴晄巤嬛惂埲慜偐傜偺憁椀偱丄晄庴晄巤嬛惂偵傛偭偰柇椦帥偼斶揷攈偵揮岦偟偨偨傔丄摨廻憁偼帥傪弌偰丄挰壆偱晄庴晄巤憁偲偟偰偺妶摦傪峴偭偰偄偨偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅
丂仦斶揷晄庴晄巤攈旛慜暉壀柇嫽帥朄擄
丂掑嫕尦擭乮1684乯暉壀柇嫽帥偺摨廻憁俈柤偲偦偺壓恖俈柤偑柍愋偱斨棞丒榓婥孲偺懞乆偵嫃廧偟偰偄偨偙偲偑業掓丄柇嫽帥廧怑偼塀嫃傪柦偠傜傟傞丅
憁椀偺嵼壠偱偺晍嫵偑嬛偠傜傟偰偄偨偺偼忋偲摨偠偱偁傞丅
丂偱偼側偤丄偦偺傛偆側偙偲偑壜擻偱偁偭偨偺偐丅柇嫽帥傕摉帪偼斶揷晄庴晄巤攈偵懏偟丄惓摑晄庴晄巤攈偵偲偭偰夾偵棙梡偟傗偡偄帠忣偑偁偭偨偺偱偁傠偆丅傑偨懞栶恖傕娷傔偨峀斖埻側晄庴晄巤撪怣幰偵傛傞帥惪偺婾憰偑峴傢傟偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅
丂柇嫽帥偺応崌偺帥惪偺婾憿偺庤岥偼丄嫃懞偺懞栶恖偼柇嫽帥偱帥惪嵪偲偄偄丄堦曽柇嫽帥偱偼嫃懞偱帥惪嵪偱偁傞偲偟偰丄憃曽偑廆栧夵傔偺庤懕偒傪婾傝丄寢嬊丄摨廻憁偼柍愋偺傑傑嵼懞偟偰偄偨偙偲偵側傞丅
丂梫偡傞偵丄柇椦帥傕柇嫽帥傕埶偭偰棫偮婎斦偼晄庴晄巤攈怣搆偱偁偭偨偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅摉帪偼斵傜側偟偵偼帥堾偺懚懕偑婋偆偐偭偨偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅
丂尦榎係擭乮1691乯寢嬊丄枊晎尃椡偲偺懨嫤偺忋偵惉傝棫偮斶揷攈偼嬛惂偲側傞丅
仦掚悾嶰憁朄擄
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
丂掑嫕尦擭乮1684乯乮掑嫕俀擭偲傕塢偆乯旛拞掚悾偵墬偄偰懍惉堾擔墄側偳偑曔敍偝傟丄峕屗偵憲傜傟丄崠巰偡傞丅
2019/08/19捛壛丗
仜乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿崅栰悷丒壀揷柧旻丄崙彂姧峴夛丄徍榓俆俀擭丂傛傝
嵵摗怴敧榊嶰戭搰棳嵾
丂掑嫕係擭乮1687乯俀寧枊恇嵵摗怴敧榊丄嶰戭搰偵棳嵾偲側傞丅乽晄庴晄巤偲偄偊傞幾廆偵孹偒丄偦偺廆巪傪夵傓傋偐傜偢偲岯尰偡傞傪傕偰丄嶰戭搰偵墦搰偣傜傞丅傛偰晝孼掜傕墦搰偵張偣傜傞丅乿乮乽摽愳幚婰乿乯偲偄偆丅
怴敧榊偺晄庴晄巤怣嬄偑業尠偟偨偺偼丄彨孯壠峧媑偐傜枊恇偵壓帓偝傟傞嬀栞傪帿戅偟偨帠審偱偁傞丅
丂怴敧榊偼丄晝偲偲傕偵枊晎偍書偊偺擻栶幰偐傜枊恇偵庢傝棫偰傜傟偨幰偲偄偆丅
---
乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿廔---
2019/08/05捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝
掑嫕朄擄
丂掑嫕係擭乮1687乯愽暁偟偰偄偨帺鏆帥擔掚偼嵅搉偵棳偝傟傞丅
偦偺嵅搉偺擔掚偺傕偲偵丄旛慜偺朄棫摗揷懛榋偲峕屗偺朄棫峕揷尮幍偑朘傟傞丅尮幍偼懠偺擔掚掜巕偵棅傑傟丄懛榋偼帺暘偺巘傪尒晳偆偨傔偱偁偭偨丅
丂偲偙傠偑丄偙偺峴堊偑欓傔傜傟傞丅尮幍偵旘媟傪埶棅偟偨殺滀堾擔娗乮墌廃乯丒杮庣堾擔弌乮宐嶰乯偺擇憁傕曔傜偊傜傟丄係恖偲傕偳傕峕屗偵擖楽偝偣傜傟傞丅
偙偺帠審偼晄庴晄巤偺棳憁偵夛偄偵峴偔偙偲偑張敱偵抣偡傞傛偆偵側偭偨偙偲偲帥幮曭峴偺揮廆偺姪崘傪庴偗擖傟傟偽曐庍偡傞偲偄偆懺搙偑傑偩曐偨傟偰偄傞偙偲傪帵偡帠審偱偁偭偨丅偦偺屻偼晄庴晄巤偺憁傗朄棫偱偁傞偲抦傟傟偽丄擖楽丒棳嵾偺張敱偑偨偩偪偵寛掕偝傟傞傛偆偵側傞丅
揮廆姪崘傪嫅斲偟偨係恖偼嶧杸偵棳嵾偲側傞傕丄傂偲傝峕揷尮幍偩偗偼擖楽拞偵昦巰偟偨丅偙偺擖楽拞偺惱嫀偑旕忢偵懡偄偺傕晄庴晄巤攈怣搆偺庴擄偺摿怓偱偁傞丅
憐憸傪愨偡傞偁傞偄偼昅愩偵昞偟偑偨偄崏栤偑峴傢傟丄偦偺忋丄楽幧偺塹惗忬懺偼恖娫偺懴偊傜傟傞傕偺偱偼側偐偭偨偙偲偑峫偊傜傟傞丅
椺偊偽丄柧帯俁擭桞巼埩偺桳椡怣幰偩偭偨嶁杮恀妝乮榓暯乯偼乽傕偼傗懅傕懕偒怽偝偢丄岥偼暵偠丄婛偵椪廔偺怱傪寛偟乿偨傎偳偺崏栤偵懴偊丄掃搰偵棳偝傟偨偲偄偆丅
丂偙偺帪丄摗揷懛榋偺曣偼懚柦偱偁偭偨丅擔掚偺偙偺曣傊偺徚懅偑巆傞丅偍搰條偐傜徚懅乽搰屼忬乿偺嵟傕憗偄椺偱偁傞丅
--- 乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
2019/08/05捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝
斶揷嬛巭乮尦榎朄擄乯
丂斶揷晄庴晄巤攈偼棤愗傝幰偲攍傜傟嶶乆偺桳條偱偁偭偨偑丄偨偩棤愗傝幰偲偄偆偩偗偱偼嵪傑偝傟側偄傕偺偑偁傞丅
帥椞丗抧巕偺庴椞偼乽斶揷嫙梴乿偲偄偆嬯偟偄愗傝敳偗偱偁偭偨偑丄偙傟傕晄庴晄巤偺棫応傪庣傠偆偲偟偨偙偲偵懠側傜側偄丅
偦偟偰晄庴晄巤偵偨偄偟偰帥堾偲怣搆偺帥惪偗嬛巭偲偄偆峴惌張抲偵峈偟偰丄側偍傕帥堾偵傛傞晍嫵傪壜擻偵偡傞曽嶔偱偁偭偨偙偲傕帠幚偱偁傠偆丅
丂偟偐偟丄偄偮傑偱傕乽斶揷攈乿偲偄偆奜旐偑撪怣偺晄庴晄巤憁傪庣傞偙偲偼弌棃側偐偭偨丅
尦榎係擭乮1691乯係寧俀俉擔悑偵抐偼壓偝傟傞丅
帥幮曭峴偺怽偟搉偟偼師偺捠傝偱偁傞丅
丂乽彫柀抋惗帥丒旇暥扟朄壺帥丒扟拞姶滀帥塃嶰儢帥偙偲丄愭擭徹暥巇傝岓偲偙傠偵丄偄傑偵晄庴晄巤偺幾媊傪憡棫偰斶揷廆偲崋偟丄偙傟傪傂傠傔岓抜丄晄撏偒偵岓丅
岦屻丄斶揷晄庴晄巤傪夵傔岓偄偰庴晄巤偵傑偐傝側傝岓偐丄枖偼懠廆偵傑偐傝側傝岓偲傕丄偦偺抜偼強懚偵擟偣傋偔岓丄
丂帺崱埲屻丄斶揷屌偔掆巭偵嬄偣偮偗傜傟岓娫丄媫搙憡夵傔怽偡傋偔岓乿
枊晎偑弶傔偰丄晄庴晄巤傪乽幾媊乿偲抐偠偨偺偱偁傞丅彅戝柤偵傕摨條偺嬛椷偑揱払偝傟傞丅
斶揷嬛巭偼丄摿偵峕屗偲娭搶偵嫮偄徴寕傪梌偊丄壓憤偺懡偔偺埩偼偙偺帪偐傜巒傑傞偲偄偆丅
弌帥丒捛曻偝傟偨憁偼尦榎擭拞偩偗偱栺俈侽恖偲偄偆丅
榋寧偵偼峕屗偺晄庴晄巤憁搆偑帥幮曭峴偵楢峴偝傟傞丅棳孻抧偼慡偰埳摛幍搰偱偁偭偨丅偦偺憁椀偺憤悢偼偄傑偩妋掕偟擄偔丄嵟彮偼俇俉恖丄懡偄偺偼俉侾恖傑偱悢偊偰偄傞丅
棳憁偺側偐偵偼挿墦堾擔婲丒惔怱堾擔払偺傛偆偵峈媍偺娦嬇傪姼峴偟偨傕偺傕彮側偔側偄丅
---
乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
2019/08/19捛壛丗
仜乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿崅栰悷丒壀揷柧旻丄崙彂姧峴夛丄徍榓俆俀擭丂傛傝
丂斶揷攈嬛惂偵傛傝慺憗偔恎傪抧壓偵塀偟偨憁傕偁偭偨偑丄懡偔偺憁偑擖楽偝偣傜傟傞丅
塿慞堾擔憦偼埳摛怴搰偵棳嵾偱偁偭偨偑丄楽巰偡傞丅
宐岝堾擔姶偼峕屗偱帺慽乮崙庡娦嬇乯偡傞丅娦嬇憁偼妋幚偵棳嵾偱偁傞偑丄偦偺慜偵壗偐寧偐偺梘傝壆擖傝偑偁傞丅擔姶偼梘傝壆偱抐怘偟偰壥偰傞丅
---
忋憤懡屆挰愼堜丂擔憹壆晘愓
擔憹偼尦榎朄擄偺偍傝俇侽擔娫偺抐怘傪偟擖掕偟偨丅
丂仸擔憹壆晘愓偺幨恀宖嵹
--- 乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿廔---
仦嫕曐朄擄乮峴愳朄擄乯
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
丂忋憤峴愳懞偱偼敋敪揑側撪怣偺崅梘偑偁傝丄斵傜偼帥栶偺嫅斲丄扷撨帥偺戣栚島偵嶲壛偣偢丄択媊偵弌惾傪嫅傒丄捔庣偺恄幮偵傕嶲攓傪偟側偐偭偨丅峴愳柇愰帥丒杮庘帥偼怣嬄揑偵傕嵿惌揑偵傕捛偄媗傔傜傟傞丅
乑乽擔楡嫵抍巎奣愢乿丗
丂嫕曐俁擭乮1718乯忋憤峴愳柇愰帥丒杮庘帥偼抧摢傊偺慽偊偺嫇偵弌丄抧摢猕敿巐榊偼怣幰侾係恖傪曔敍丄侾係恖偼峕屗偵憲傜傟丄崏栤偵傛傝丄擔嬤忋恖偺嫃強偑抦傜傟丄擔嬤偼墢幰偺抧庡栁塃塹栧偲偲傕偵晄庴晄巤偺惓媊傪鎩濟丄擖楽偡傞丅
乮朄擄偼峕屗丄戝嶁偵旘壩偟丄怣搆偲慻怐杊塹偺偨傔乯彋愰堾擔梈丒椆塣堾擔梛摍傕帺慽偡傞丅偦偺懠懡偔偺憁傜乮墄怱丄桭慞丄懱塣丄尯桭丄擔梫丄楡媣丄慯慡傜乯偑帺慽偡傞丅
寢壥丄楽巰侾侽恖丄棳嵾俆恖丄搳崠俀恖丄捛曻俆恖偺媇惖傪弌偡丅
2019/08/05捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝
峴愳朄擄乮擔尮偲擔嬤乯
丂乽嫕曐嶰擭峴愳婰乿幠嶈榋擵忓丒昅丂偲偄偆朄擄婰榐偑偁傞丅
傑偨丄傕偆堦偮偺婰榐乽屼朄擄婰乿妎嫵堾擔壄丂傕偁傞丅
丂曮塱俀擭乮1705乯墦惉堾擔尮乮帺鏆埩奐婎挿墦堾擔掚掜巕丒旛慜戝庽埩俈悽杮惈堾擔泏巘乯偑忋憤埼嬿孲崙媑懞丒峴愳懞偵棃偰丄枾偐偵晄庴晄巤偺晍嫵傪巒傔傞丅
丂仺峕屗帺鏆埩乮峕屗帺鏆帥拞乯丂丂丂丂丂仺旛慜戝庽埩亙旛慜塿尨朄愹帥丒戝庽埩拞亜
偙偙偼埲慜偐傜晄庴晄巤偺崻嫆抧偱偁偭偨丅
擔尮偼峴愳懞嬨嵍塹栧偺懅巕傪愢偄偰朄棫偺楍偵壛偊丄摨偠偔嬨嵍塹栧偲柤忔傜偣傞丅偙偺慻怐偼侾侽恖傎偳偺撪怣傪暅妶偝偣傞丅
偦偺屻丄傂偦傗偐偵怣嬄偼懕偗傜傟偨傛偆偱偁傞丅
丂擔尮偺杤屻侾侽擭丄嫕曐尦擭乮1716乯偦偺掜巕偺惔弴堾擔嬤偑埼嬿孲惓棫帥懞偵傗偭偰偔傞丅擔嬤偼峴愳懞偺撪怣偺巜摫偵偁偨傞丅擔尮偺朄掜偱偁傞懱塣擔場傕峴愳懞偵棃朘偟偰偄偨丅嫕曐俀擭偵偼撪怣幰俀侽侽梋恖偑擔嬤偺傕偲偵廤傑傞丅
丂偲偙傠偑丄俀侽侽梋恖偺椡傪夁怣偟偨偺偐丄峴愳杮鐟帥丒峴愳柇愹帥丒戝栰岝暉帥偲偄偆庴攈偺怣搆偲偟偰偺柋傔傪慳偐偵偡傞傛偆偵側傞丅
抙撨帥偱偺島偵嶲壛傪嫅傒丄嶲寃偡傜嫅傓傛偆偵側傞丅偮偄偵偼撍弌偟偨侾係柤偑抙撨帥傊棧抙忬傪偨偨偒偮偗傞帠懺偵帄傞丅
丂椞庡偺婙杮猕敿巐榊偺専嫇偑巒傑偭偨丅
撪怣侾係柤乮嬨嵍塹栧側偳乯偑曔敍偝傟傞丅
擔嬤偼峕屗彫愇愳娭岥偺埩傪堷偒暐偄丄愒嶁偵堏傞丅偙偙偱丄擔嬤偼娦嬇忬傪彂偒偁偘傞丅
懱塣擔場偲墄怱擔慠偼擔嬤偺巜帵偱戝嶃傊摝傟傞丅
丂嫕曐俀擭俇寧侾侽擔丄擔嬤偼娦嬇忬傪実偊丄帥幮曭峴埨摗塃嫗夘栶戭傊弌摢偡傞丅
抧庡偺栁塃塹栧丒壠庣師榊塃塹栧丒慻柤庡丒擭婑側偳偑摨摴偡傞丅
曭峴偺庢挷傋偑廔傢偭偨帪丄撍慠丄壠庣師榊塃塹栧偑乽堦愗乿傪帺傜傇偪傑偗傞丅擔嬤偺埩偼峕屗彫愇愳娭岥偱偁傞偙偲丄墄怱偲懱塣偼忋曽傊摝傟丄墄怱偺埩偼壓扟嶳嶈偵偁傝丄彋愰堾擔梈傕堦枴偱偁傝偦偺埩偼敧挌杧偵偁傝丄斵傜偺掜巕偼壗恖偄傞側偳丒丒偱偁傞丅
丂朄擄偼奼戝偡傞丅
擔嬤偼擖楽偟丄嬐偐俀侽擔梋偱楽巰偡傞丅
抧庡栁塃塹栧偼帺暘偺摨嵾傪庡挘偟偰擖楽丄彋愰堾擔梈偲椆塣堾擔梛偼慻怐杊塹偺偨傔帺慽丅
戝嶃偵摝傟偨懱塣擔場偲墄怱擔慠丄偦傟偵慞峴堾擔惔乮桭慞乯偲掜巕偺尯桭擔梫丄朄棫偺戝抭堾擔忩偺屲恖偼峕屗偵傕偳傞丅
丂偙偙偱帥庡栁塃塹栧偼悑偵揮岦傪愰惥丄戝嶁偺棫墌堾擔怣偺嵼壠傑偱敀忬偡傞丅
懱塣擔場偲墄怱擔慠偑帺慽丄偙偺慜偵椆塣堾擔梛偑楽巰丅
丂偲偙傠偱丄擔尮丒擔嬤偼帺鏆埩擔掚偵偮側偑傞朄柆偱偁傞丅
丂丂仺峕屗帺鏆埩乮峕屗帺鏆帥拞乯丂丂丂丂丂仺旛慜戝庽埩亙旛慜塿尨朄愹帥丒戝庽埩拞亜
慞峴堾擔惔乮戝庽埩俉悽乯丒戝庽埩乮宱峴堾乯尯桭擔梫丒妎嫵堾擔壄傕懕偗偰帺慽偡傞寛堄傪屌傔偨偑丄偦偆側傟偽帺鏆埩偺朄柆偼愨偊偰偟傑偆丅
偙偙偱朄棫偺戝抭堾擔忩偑乽変偑恎偼榁偄偨丄偙偙偱巹偑廆媊偺偨傔偵変偑恎傪曺傛偆丅妎嫵堾偼庒偔戝婅傪壥偨偡傋偒乿偲偄偄丄帺傜偑帺慽偡傞丅
丂偙偺峴愳朄擄偼朄拞偲朄棫俋恖偑張敱偝傟丄楽巰係恖乮擔嬤丒擔梛丒擔梈丒擔忩乯丄埳摛戝搰棳嵾俀恖乮懱塣擔場丒墄怱擔慠乯丄嶰戭搰棳嵾俀恖乮慞峴堾擔惔丒宱峴堾尯桭擔梫乯丄戝嶁偱曔敍偝傟偨棫墌堾擔怣乮戝庽埩俋悽丒桞巼埩俁悽乯偼塀婒偵棳嵾偲側傞丅峴愳懞偺侾係恖偺撪怣幰偼俈柤偑搑拞偱棊柦丄巆傞俈栚偼揤戜廆傪嫮惂偝傟丄傗偭偲偺偙偲偱庍曻偝傟傞丅
丂偙偆偟偰丄峴愳懞偺晄庴晄巤撪怣慻怐偼夡柵偡傞丅
2019/08/19捛壛丗
仜乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿崅栰悷丒壀揷柧旻丄崙彂姧峴夛丄徍榓俆俀擭丂傛傝
丂棫殺堾擔怣乮戝庽埩俋悽丒桞巼埩俁悽乯偼丄峴愳朄擄偺帪戝嶁偵偄偨偑丄帺慽偡傞丅
丂丂仸棫殺堾擔怣亙嫕曐侾俇擭乮1731乯壔乛柇慞帥侾俀悽亜丂丂仺旛慜戝庽埩亙旛慜塿尨朄愹帥丒戝庽埩拞亜
嫕曐係擭係寧塀婒搰偵棳偝傟傞丅嫕曐侾俇擭乮1731乯擔怣庘丅
塀婒偱擔怣偺恎暱傪梐偐偭偨偺偼彲壆斅壆墶抧榋榊暫塹偱偁傞偑丄斵傪巒傔擔怣偵婣埶偟偨幰偑彮側偐傜偢偁偭偨傛偆偱丄擔怣偺曟偼斵傜偵傛偭偰乽慶恄條乿偲偟偰釰傜傟偰偒偨偲偄偆丅偙偺乽慶恄條乿偼嬤擭擔怣偺曟偲敾柧偡傞丅側偍丄偙偺曟旇偺偁傞偲偙傠傛傝彮偟崅偄強偵乽桞巼埩乿傪寢傫偩偲偄偆嬻抧偑偁傞丅
側偍丄丂擔怣曟偼塀婒搰惣嫿挰暯偵偁傞丅
--- 乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿廔---
丂丂2019/08/19捛壛丗
丂丂仜乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿崅栰悷丒壀揷柧旻丄崙彂姧峴夛丄徍榓俆俀擭丂傛傝
丂丂丂姲暥擭拞丄忋憤峴愳柇愹帥偼晄庴晄巤偺拞怱偺帥偱偁偭偨丅
丂丂偙偙偼婙杮丒猕敿巐榊偺抦峴抧偱丄姲暥朄擄偺帪柇愹帥擔梫偑峕屗偵屇傃弌偝傟偨偑丄擔梫偵懼偭偰椆娽堾擔弚偲偄偆憁偑弌摢偡傞丅
丂丂偙偺擔弚偼傛傎偳曎愩偑偝傢傗偐偱偁偭偨傛偆偱丄曭峴偺恞栤偵岻傒偵摎偊丄
丂丂乽堦惗晄庴晄巤屼柶乿偲偄偆寢壥偵側偭偰嶥怷懞乮峴愳偺嬤椬乯偵婣偭偰偔傞偲偄偆丅
丂丂姲暥擭拞偼丄屻擭偺抏埑偐傜斾傋傞偲丄傑偩娚傗偐側帪戙偱偁偭偨偲偄偆偙偲側偺偱偁傠偆丅
丂丂埼嬿挰嶥怷偵椆娽堾擔弚曟旇偑尰懚偡傞丅
丂丂丂---
乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿廔---
娦嬇偲棳嵾
丂擔墱偺懳攏棳嵾偐傜嫕曐俁擭乮1716乯偺峴愳朄擄傑偱栺侾侽侽恖傎偳偺晄庴晄巤憁偑屒搰偵憲傜傟傞丅
擔墱偲偼栧棳偑暿偱偁傞忢妝堾擔宱栧棳乮撪徹戣栚島乯傗廦栧棳柇枮帥擔塸側偳傪壛偊傟偽憤悢偼侾侽侽傪挻偊傞丅
丂挿岝摽榓乽弣嫵幰柤曤乿偵傛傟偽丄朄擄偺奼戝傪梷偊傞偨傔偵峴偆帺慽傪彍偒丄廃摓側弨旛偲寁夋偺傕偲偵側偝傟偨娦嬇偼侾俀恖傪悢偊傞丅
峴愳朄擄偺慞峴堾擔惔偲尯桭擔梫丄姲惌俆擭乮1793乯偵娦嬇偟偨杮柇堾擔庫偺傛偆偵丄壗傟傕棳孻抧嶰戭搰偐傜丄嵞搙偺娦嬇傪峴偭偨椺傕偁傞丅偙傟偵帺慽傪壛偊傟偽娦嬇偺悢偼偍傃偨偩偟偄悢偵偺傏傞丅
丂擔庫偼旛慜杮柇埩傪庡嵣偟偰偄偨丅擔庫偼娦嬇寛峴慜丄俀侽擔娫偺抐怘傪偟偰旛偊傞丅楽撪偼楎埆偱擔庫偵廬偭偰偄偨楡惉堾擔摽偼懱椡悐偊丄擔庫偺撉宱傪偒偒側偑傜楽撪偱懅傪堷偒庢傞丅
丂丂丂丂仺杮柇堾擔庫棯楌乮旛慜栴尨懞拞偵偁傝乯
丂曮楋俁擭乮1753乯旛慜戝庽埩媣墦堾擔慠偲戝嫵埩滀抭堾擔墢偲偑峕屗偱娦嬇傪峴偆丅
丂暥壔侾俀擭乮1815乯杮妎堾擔恑娦嬇傪峴偆丅偙偺娦嬇忬偺幨偟偑慶嶳柇妎帥偵偁傞丅擔恑偺巘偼桬峴堾擔挿偱偁傞偑丄擔挿偼慜擭偺暥壔侾侾擭乽惓朄曬崙榑乿傪寶敀偟偰楽巰偡傞丅嬦枴拞偺埖偄偑傂偳偔丄棳嵾傑偱柦傪曐偰側偐偭偨偺偩丅
棳孻抧偐傜偺撪怣巜摫
丂棳憁偼柦傪宷偖偩偗偱側偔丄杮搚偺撪怣傪巜摫偟丄朄柆傪惓偟偔宷偑側偗傟偽側傜側偐偭偨丅棳憁偺惗妶傪巟偊偨偺偼杮搚偺撪怣慻怐偐傜偺暔帒傗夞岦椏偱偁傝丄偦傟傜偲彂娙偺墲暅偼撪徹曋亅桝憲岎怣偺旈枾儖乕僩偵埾偹傜傟偨丅
丂杮柇堾擔庫偼嶰戭搰埳儢扟懞偵拝慏偟偨丅摉帪嶰戭搰偵偼晄庴晄巤偺棳憁偼堦恖傕偄側偐偭偨偑丄寎偊偰偔傟偨偺偼丄曮楋俁擭娦嬇偟偰屼憼搰偵棳偝傟偨滀抭堾擔墢偺廃摓側攝椂偱偁偭偨丅帠慜偵擔庫偺嶰戭搰攝棳傪偟偭偰偄偨擔墢偼屼憼搰偐傜丄怣棅偺偍偗傞慏摢偺巗塃塹栧偲慏庡偺栱暯偲傪嶰戭搰偵攈尛偟丄擔庫偺悽榖傪偝偣偨偺偱偁傞丅斵傜偼偍偦傜偔撪徹曋偺扴偄庤偱偁偭偨偺偱偁傠偆偐丅
丂擔庫偺撪怣巜摫偼丄俀侽侽梋恖偺晄庴晄巤棳憁偺拞偱丄摿昅偡傋偒摥偒傪巆偡丅
偦傟偼丄擔庫偺巜摫偼帺暘偺庡嵜偡傞杮柇埩偩偗偱側偔丄晄庴晄巤嫵抍偺摑堦偲偄偆娤揰偐傜峴傢傟偨偐傜偱偁傞丅擔庫偺巜摫偵傛偭偰宍惉偝傟巒傔偨摑堦嫵抍偺崪奿偼揤曐朄擄偱懝側傢傟傞傕丄嫵抍摑堦傪巙岦偡傞峫偊偼愰柇堾擔惓偵堷偒宲偑傟丄柧帯俋擭偺晄庴晄巤攈岞嫋偵偮側偑偭偰備偔丅
丂丂仺丂杮柇堾擔庫棯楌乮旛慜栴尨懞拞乯
擔庫偺忦栚
丂擔庫偼嫵抍偺摑堦偵偼偦偺婎慴偲側傞柧妋側忦婯偑昁梫偲峫偊丄嶰庬偺忦婯傪嶌惉偡傞丅
姲惌侾俀擭乮1800乯偺乽惔幰幃栚乿丄嫕榓尦擭乮1801乯偺乽朄拞幃栚乿丄暥壔係擭乮1807乯偺乽屼忦栚乿偱偁傞丅
--- 乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
仦曮楋朄擄
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
丂曮楋俁擭乮1753乯壀嶳偺怣搆偼暯堜嶳偵擔墱偺戝愇搩傪寶棫偟偰岞慠偲奐娽嫙梴傪偡傞丅擵偵懳偟庴攈偺帥堾偐傜偺慽偊偵傛傝旛慜丒旤嶌偱俀枩恖偺怣搆偑曔偊傜傟丄惔憁俋恖偑媇惖偲側傞丅
2019/09/19捛壛丗
仜乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿憡梩怢丄戝錟弌斉丄徍榓俆侾擭乮1976乯丂傛傝
丂曮楋俁擭乮1753乯捗嶳忛壓偺撪怣憁帨慞堾擔惀乮捗嶳弌恎乯偑曔敍丄擖楽偲側傝丄曮楋俈擭俁寧俋擔楽巰偡傞丅
壓嵁壆挰撪怣戝掚嬨塃塹栧嵢巕嫙俀俆恖丒屗愳挰嶰椫壆埳彆晝巕俀柤偼旤嶌捛曻丒壠嵿鑽強丄偦偺懠娭學幰偼庤嵔丄嬛懌丄挰撪梐偗丄怑柋墦椂丄嬣怲丄慻崌梐偗丄擭婑梐偗偲側傞丅
仦揤柧朄擄丗揤柧乮1781-1789乯
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
丂晄徻
2025/01/09捛壛丗
仜乽擔楡廆晄庴晄巤攈妞巎擭昞乿
丂揤柧尦擭乮1781乯
丂丂7.9丗惓峴堾擔梀乮廏娤乯丒怣峴堾擔绔乮夣墦乯丄鎩嬇彂乽晄庴崃惓婰乿傪傕偪峕屗帥幮曭峴強偵弌摢丅
丂丂8.24丗惓峴堾擔梀乮廏娤乯峕屗偱楽巰丄俆俉嵨丅旛慜戝庽埩侾係悽丅
丂丂揤柧俀擭
丂丂侾寧丗怣峴堾擔绔乮夣墦乯嶰戭搰傊攝棳乮乽夁嫀挔乿乯
丂丂3.20丗怣峴堾擔绔乮夣墦乯庘丄俀侾嵨丅
丂丂丂丂丂仜乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿丗揤柧朄擄丄帺鏆埩庡乮俇悽乯丄嶰戭搰攝棳偲寛偟丄揤柧俀擭峕屗偵偰楽巰丅乮乽慞彑埩夁嫀挔乿乯
埲忋偺婰榐偐傜敾抐偡傟偽丄
揤柧尦擭丄旛慜戝庽埩侾係悽惓峴堾擔梀乮廏娤乯丒峕屗帺鏆埩俇悽怣峴堾擔绔乮夣墦乯峕屗偵偰鎩嬇丄偄偢傟傕峕屗偵偰楽巰偡傞丅
扐偟丄乿怣峴堾擔绔偼嶰戭搰攝棳偲寛偡丅
丂仺峕屗帺鏆埩乮峕屗帺鏆帥拞乯丂丂丂丂丂仺旛慜戝庽埩亙旛慜塿尨朄愹帥丒戝庽埩拞亜
仦姲惌懡屆朄擄姲惌朄擄乮懡屆朄擄乯
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
丂姲惌俇擭乮1794乯拞懞抙椦塸懚偺慽偊偑偁傝丄朄拞侾係恖丒朄棫係恖偑曔敍偝傟丄俀侽柤偑崏栤巰丄巆傞侾柤乮杮惈堾擔惥乯偑嶰戭搰偵攝棳偝傟傞丅
偙偺朄擄偱壓憤偺撪怣偼傎傏夡柵忬懺偲側傞丅
丂仸杮惈乮惓乯堾擔惥偼斞捤埩庡丄暥惌侾俀擭乮1829乯庘丅
2019/08/13捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝丂p.203
丂嶰戭搰偺埳摛偵俋婎偺曟旇偑偁傞丅埳摛枽偵摃戜偑偁傝丄枽偵壓傝傞彫宎偑偁傝丄慮棦愳傪墶愗傞檤偵嫟摨曟抧偑偁傝丄彮偟棧傟偰晄庴晄巤棳憁偺曟偑偁傞丅
偦偺婎偵偼丄杮惓堾擔惥偺柤偲偦偺壴墴偑崗傑傟傞丅偦偺嵍塃偵偼尦榎偺朄擄偱嶰戭搰偵棳偝傟偨壓憤偺侾俇恖偺憁偺柤偑撉傔傞丅
丂擔惥偼姲惌懡屆偺朄擄偱偨偩堦恖偙偺嶰戭搰偵棳偝傟傞丅嵍塃偺愇搩偼丄婛偵尦榎朄擄偱棳偝傟偨憁偼慡偰巰杤偟偰偄偨偑丄擔惥偑偦偺巘傪挗偭偰寶偰偨嫙梴搩側偺偱偁傞丅丂俋婎偺曟偺拞偵偼忢妝堾擔宱栧棳偺惓摽堾擔彯偺曟傕偁傞丅
側偍晬嬤偵偼擔庫偺彫壆偺愇愊偑巆傞偲傕偄偆丅
丂偝偰丄懡屆朄擄偱偁傞丅
姲惌俇擭乮1794乯俋寧丄擔塸偲偄偆憁偑撪捠偟偨偙偲偵巒傑傞丅偨偩偪偵峕屗偐傜偺曔棛偑懡屆廃曈傪廝偄丄崄庢孲堦懷偑戝憑嶕偝傟傞丅
偙偺抧曽偺朄拞侾係恖偑崻偙偦偓曔敍偝傟丄杮惓堾擔惥埲奜偺朄拞偼曔敍屻侾儢寧偁傑傝偺撪偵楽巰偡傞丅偳傫側偵寖偟偄崏栤偑壛偊傜傟偨偐丄憐憸傕媦偽側偄丅偙傟偵偼丄慜擭偙偺抧曽偺朄摃偲巚傢傟傞杮帠堾擔姶偑惱嫀偟偰偄傞丅惱嫀慜丄娦嬇忬偺梡堄傪偟偰偍偔傛偆偵朄拞偵巜帵偟丄慡朄拞偑娦嬇忬傪梡堄偟偰偄偨偲偄偆丅曔敍偝傟娦嬇忬傪撍偒晅偗偨偙偲偑崏栤偺崜偝偵攺幵傪偐偗偨偺偐傕偟傟側偄丅
丂朄拞偩偗偱側偔丄俈柤偺朄棫傕楽巰偡傞丅
偝傜偵彅懞偺柤庡丒慻摢丒暯昐惄俆侾偑偙傟偵楢嵗偟丄夁椏丒捛曻丒栶媀庢傝忋偘側偳偺張暘傪庴偗傞偲偄偆寢枛偱偁偭偨丅
丂偱偼偙偺抧曽偺晄庴晄巤偼夡柵偟偨偺偐丄妋偐偵朄拞偼慡偰幐傢傟傞丄偟偐偟丄撪怣慻怐偼惗偒巆偭偰偄偨傕偺偲悇應偝傟傞丅
懞曽偵俆侾恖偺媇惖傪弌偡傕丄朄拞侾係恖傪巟偊傞偵偼彮側偡偓傞丅彮側偔偲傕丄悢昐恖偺撪怣偑偄偨偲峫偊側偗傟偽捯咫偑偁傢側偄丅俆侾柤偺媇惖傪偩偡傕丄懡偔偺撪怣偼惗偒巆偭偰偄偨偲悇應偝傟傞丅
丂傕偆堦偮偼懞曽偵懳偡傞敾寛彂偵丄婏柇側暥尵偑慡偰偺敾寛彂偵擖偭偰偄傞丅乮堦椺傪彍偔乯
偦傟偼乽晄庴晄巤攈憡帩偪岓媊偼偙傟柍偔岓偊偳傕乿偲偄偆暥尵偱丄偦傟傪慜採偵椺偊偽乽乑乑偼晄毥偵晅丄夁椏乮捛曻丒丒乯嬄偣偮偗傜傟岓乿偲偁傞丅
偮傑傝丄懞曽偺晄庴晄巤怣嬄偼張暘棟桼偱偼側偔丄曔敍偝傟偨朄拞偵晄庴晄巤偲偼抦傜偢抧柺傪戄偟丄恖暿挔偵擖傟側偐偭偨偙偲丄偁傞偄偼丄偡偱偵惱嫀偟偰偄傞晄庴晄巤憁偺曟旇傪曻抲偟偰偄偨側偳偺扨弮側庤棊偪傗懹枬偑張暘棟桼偲側偭偰偄傞偺偱偁傞丅
丂偳偆偄偆偙偲偐丅庤擖傟傪庴偗偨嬍憿丒搰丒搶戜丒斞捤丒戲丒拞嵅栰丒椦丒愼堜媦傃偦偺廃曈偺懞乆偱偼晄庴晄巤撪怣偑埑搢揑偵懡偐偭偨偺偱偁傞丅撪怣慡偰傪曔敍偟傛偆偲偡傟偽丄堦懞慡屗傪懳徾偵偟側偗傟偽側傜側偐偭偨懞傕偁偭偨偺偩丅椞庡偲偡傟偽偦傫側偙偲偼弌棃傞栿傕側偐偭偨丅偦傫側偙偲傪偡傟偽丄椞庡偼愑擟傪栤傢傟丄埆偔偡傟偽丄椞抧杤廂傕偁傝摼偨偱偁傠偆丅朄拞偲朄棫偼張暘偡傞丄怣搆偼庡偩偭偨幰偩偗傪張暘偡傞丅偦傟偱丄怣搆偲憁傪暘抐偟丄怣搆偼嫼偟偰偍偔偟偐側偄偲偄偆曽恓偑偳偙偐偱寛掕偝傟偨偺偱偁傠偆偲偟偐峫偊傛偆偑側偄丅
丂嬤悽偺帥抙惂搙偵傛傝丄帥偼塰偊丄憁偼埨廧偟丄抙壠偲偺娫偵偼宍幃揑側宷偑傝偑偁傞偩偗偲偄偆暓嫵偺桷攑偼丄栶恖偵媦傃丄撪怣揈敪偺昁梫惈傪姶偠偝偣側偐偭偨偲偄偆傋偒偱偁傠偆丅
丂偝偰丄郪懞偵擔煰丒擔島丒擔擮偺嶰婎偺旇偑偁傞丅擔島偺旇丒嫄戝側旇偼扏偒妱傜傟搚拞偺杽傔傜傟偰偄偨偺杧傝廤傔丄僶儔僶儔偵側傜側偄傛偆偵恓嬥偱寢傢偊偰傞丅擔島偺旇傪偨偨偒妱偭偨偺偼墴偟婑偣偨曔傝庤偺強嬈偲偄偆丅
--- 乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
2023/08/30捛壛丗
仜嬍憿亜乽杮柇堾揳乿旇丂傛傝
楡惈堾擔夝丗椦偺朄椦帥楌戙丅姲惌朄擄偵傛傝姲惌俇擭(1794)廫堦寧楽巰丅
丂仸楡惈堾擔夝偼椦偺朄椦帥楌戙偵偦偺柤偑側偄丄晄庴晄巤憁偱偁偭偨屘偲悇掕偝傟傞丅
仜嬍憿慜栰曟抧丂傛傝
丂懡屆傪拞怱偵丄姲惌俇擭(1794)偺廐丄晄庴攈偺戝抏埑偑峴傢傟傞丅
偙偺応強偵師偺屲恖偺朄擄幰偺曟偑敪尒偝傟偰偄傞丅
乽楈榟堾擔嫕姲惌榋擭廫堦寧擇廫屲擔丂惀岲堾擔棟戝摽摨擭摨寧擇廫榋擔丂摼墌堾朄廳擔恎摨擭摨寧廫巐擔丂怣峴堾忢朄擔庬摨擭廫擇寧幍擔丂堦憡堾朄払摨擭廫堦寧廫幍擔乿偄偢傟傕楽巰偲偝傟偰偄傞偑丄崏栤丄傑偨偼抐怘巰偵傛傞傕偺偲偄傢傟傞丅
丂塃偺偆偪擔嫕丒擔棟偼嬍憿偺埩庡偱丄擔恎丒擔庬丒堦憡堾偼偦傟偧傟梌塃塹栧丒梌嵍塹栧丒揱暫塹傪懎柤偲偟偨嬍憿懞擾壠偺弌恎幰偱偁傞丅
2023/10/13捛壛丗
仜乽懡屆挰巎丂壓姫乿丄乽擔楡廆晄庴晄巤攈撉巎擭昞乿丂傛傝
丂仸壓憤椦朄椦帥楌戙偱偁傞楡惈堾擔夝偼姲惌俇擭乮1794乯姲惌懡屆朄擄偵傛傝廫堦寧楽巰偡傞丅
丂丂仺楡惈堾擔夝偼嬍憿亜乽杮柇堾揳乿旇丂傪嶲徠
丂仸楡惈堾擔夝偼椦偺朄椦帥楌戙偵偦偺柤偑側偄偺偼丄忋婰偺夝愢偺捠傝偱偁傞丄晄庴晄巤憁偱偁偭偨屘偲悇掕偝傟傞丅
丂丂侾俋悽偐傜俀侾悽偼寚丄俀俀悽偼擔嶳偱庘擭寚丄俀俁悽寚偱偁傞丅
丂仸乽擔楡廆晄庴晄巤攈撉巎擭昞乿挿岝摽榓丒嵢幁弤巕丄奐柧彂堾丄徍榓俆俁擭丂p.169偵擔夝偺婰帠婰嵹丅
丂丂丂丂乽椦埩嫃廧丄晄尒攈乿丂偲偁傞丅丂仺晄尒攈偼晄庴晄巤攈偺暘攈拞偵偁傝丅
丂仸摨忋乽擔楡廆晄庴晄巤攈撉巎擭昞乿p.169偵乽姲惌俇擭侾侾寧侾俀擔丂怱尒堾擔恦楽巰偡傞丅壓憤椦懞朄椦帥塀嫃丂晄尒攈乿偲偁傞丅
仦旛拞憏捾朄擄
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
丂旛拞憏捾丒斅憅偼旛慜崙嫬偺廻応挰偱偐偮揤椞偱偁傝斔偺夘擖偺偟擄偄抧嬫偱偁傝丄庢掲傝偺尩偟偄旛慜偺朄拞偼偙偙傪嫆揰偵敿偽岞慠偲晍嫵妶摦傪峴偭偰偄偨丅
丂嫓榓俀擭乮1802乯嫼埿傪姶偠偨掚悾攞忛帥乮攞忛帥偲偼晄柧丄怣忛帥偐乯偲壓埳暉柇椦帥偺慽偊偑偁傝丄憅晘戙姱庤戙偑弌挘偟丄埩俇儢強傪曪埻偟丄憁侾俁恖朄棫俁恖偑曔敍偝傟傞丅斵傜偼峕屗偵憲傜傟丄楽巰幰侾侾柤丄棳嵾俀柤丄揮岦幰係柤傪弌偡丅
丂仺捗搰柇慞帥拞偺庻検堾擔弰偺崁傪嶲徠丅
2019/08/13捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝
憏捾朄擄偲擔弰偺敧忎棳孻
丂嫕榓俀擭乮1802乯旛拞憏捾朄擄偑婲傞丅
憏捾懞偼憅晘戙姱強乮枊晎乯巟攝偱丄偦偺憅晘戙姱捬怉枖嵍塹栧偺偲偙傠偵枾崘偑偁偭偨丅枾崘偺撪梕偼乽憏捾懞偵愗巟扥偑偄傞乿偲偄偆傕偺偱丄晄庴晄巤攈偺惃椡奼戝偵嫼埿傪姶偠偨庴攈偺擔楡廆帥堾偐傜枾崘偑側偝傟偨傛偆偱偁傞丅
丂側偤乽憏捾懞偵愗巟扥偑偄傞乿偲偄偆傛偆側庤偺崬傫偩枾崘偐偲塢偊偽丄憏捾懞偱偼晄庴晄巤攈偺榋埩偑塩傑傟偰偍傝丄晄庴晄巤怣嬄偼傑傞偱嫋偝傟偰偄傞偐偺傛偆側敿偽岞慠偨傞傕偺偩偭偨偲偄偄丄乽晄庴晄巤攈偑偄傞乿偲偺枾崘偼乽偦傫側偼偢偼側偄丅尰偵偍慜偳傕偺帥偱偼懞柉偺慡偰偑帥惪偗偟偰偄傞偱側偄偐丄偦傟偲傕偁偺帥惪徹暥偼嫊婾側偺偐乿偲側傝丄晄搒崌側偺偱偁傞丅
丂係寧俀係擔憗挬丄榋埩傪堦惸偵廝偄丄憁侾俁恖丄朄棫俁恖傪曔敍偡傞丅峕屗偵憲傜傟丄嬦枴拞偵椆崅堾擔惤乮俀俀嵨偲偄偆乯偲朄棫彆師榊偑棊柦丄偮偄偱係柤偺憁偑夵攈傪惥栺偡傞丅
夵攈偟偨係恖偼恖懌婑偣応傊廂梡偝傟傞丅偮傑傝晄庴晄巤憁偺棫応傪曻婞偟偨幰偼柍廻曻楺幰偺埖偄偟偐庴偗傜傟側偐偭偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅
丂偦偟偰丄偦偺屻丄俉恖偑嬦枴拞楽巰丄巆傞庻検堾擔弰偲宐挬堾擔払偺俀柤偑墦搰偲側傞丅偦偺懠憏捾懞乆柉侾俀柤偑夁椏側偳偺敱傪庴偗傞丅
丂嫕榓俁擭惓寧丄擔払偼棳嵾傪懸偨偢楽巰丄擔弰堦恖偑弔偺棳恖慏偱峕屗傪棧傟傞丅弌斂偺帪丄杮柇堾擔庫偑屻宲偲峫偊傞椆抭堾擔媉偑戝抇偵傕慏拞傑偱壣岊偄偵偄偭偨偲偄偆丅
丂嶰戭搰偱擔弰傪寎偊偨偺偼杮柇堾擔庫偱偁偭偨丅擔庫偵傛偭偰擔弰偼敿擭娫丄柺搢傪尒偰傕傜偆丅乮敧忎搰棳恖偼慡偰嶰戭搰偱敿擭娫夁偛偟丄偦傟偐傜敧忎搰傊堏偝傟傞丅乯擔弰偼敧忎搰拞僲嫿妦棫偵妱傝摉偰傜傟傞丅崱偼敧忎搰偱曟偺抦傟偰偄傞偺偼擔弰埲壓榋憁偱偁傞偑丄偙傟偼俀屄強偵暘偐傟丄嫙偵妦棫偵偁傞丅
丂敧忎搰偵拝偄偨擔弰偼憪埩傪擖庤偡傞丅偦傟偼搰栶恖偺彫壆晘傪嬥巕俀俆椉偱丄偟偐傕峕屗暐偄偲偄偆徹暥傪敪峴偟丄擖庤偡傞丅偮傑傝丄棳恖偲偼偄偊丄楌戙偺晄庴晄巤憁偼恀柺栚側惗妶懺搙偱偁傝丄偟偐傕妋幚偵暔帒偑憲傜傟偰偒偰丄偙傟偵偼怺偄懜宧偲怣梡偑攟傢傟偰偄偨偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅
丂暥壔侾俀擭乮1815乯杮妎堾擔恑偑垻晹旛拞庣偵弌慽偟丄敧忎棳嵾偲側傞丅擔恑偼拞僲嫿偺擔弰偺憪埩偵摨嫃偡傞偙偲偲側傞丅
丂暥壔侾係擭乮1817乯嶰戭搰偺擔庫偑庘偡傞丅夁嫀挔偦偺懠偑堚尵偵傛偭偰敧忎搰偺擔弰偵撏偗傜傟丄擔弰偼偦傟傪旛慜偵憲晅偟偨偲巚傢傟傞丅
丂偍偦傜偔摨擭偵杮妎堾擔恑庘丄俁侾嵨偱偁偭偨丅
丂暥惌侾俀擭乮1829乯俁寧丄杮庫堾擔嬤乮旛慜嵅攲柇愹埩乯偼棼柇堾擔廆偲偲傕偵忋棇偟丄娭敀戦巌壠偲愛惌嬨忦壠偵弌慽偡傞丅擔嬤偼乽朄壺廆擔墱拕棳旛慜旛拞梀楌偺嵐栧乿偲偟偰娦嬇忬傪採弌丄偦偺寢壥丄乽擔墱拕棳乿偲偟偰棇撪偱偺晍嫵傪嫋偝傟傞偙偲偲側傞丅偙傟偼庒姳偺柧傞偄挍偟偱丄堦偮偺帪戙偑廔鄟傪寎偊偮偮偁傞堦偮偺挍岓偱偁偭偨偺偐傕抦傟側偄丅擔嬤偺偙偲偼擔弰偵傕偨傜偝傟乽嫗搒偺庱旜丄帄嬌屼條巕傛傠偟偔屼嵗岓桼丄埾嵶彸抦抳偟岓丄塢乆乿偲偺旛慜偺慡偰偺憁丒怣幰偵埗偰偨彂娙偑巆傞丅
丂偝偰丄擔弰偼敧忎搰偱擇恖偺惵擭偵栚傪偮偗丄憁偲偟偰堢惉偟丄旛慜偵攈尛偡傞丅棫殺堾擔梫偲杮峴堾擔鎩偱偁傞丅偟偐偟丄偙偺擇恖偼揤曐偺戝朄擄偵偰棊柦偡傞丅
擔梫偼拞僲嫿妦棫懞嵅摗旻擵彆偺師抝偱偁傝丄挿抝偼旻懢榊偱丄摉帪晝偺柤戙偲偟偰懞栶尒廗偄偱偁偭偨丅師抝乮旻懢榊偺掜乯偼婌懢榊偲偄偄丄暥惌係擭乮1821乯偺惗傑傟偲巚傢傟傞丅偍偦傜偔揤曐俇擭乮1835乯偵敧忎傪弌丄峕屗偺怣幰偺悽榖傪庴偗偰偐傜旛慜偵岦偐偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅擔鎩偼椙偔暘偐傜側偄偑丄擔梫偲堦弿偵奀傪搉偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅
--- 乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
仦暥壔侾侾擭乮1814乯
2018/11/15捛壛丗
仜乽壀嶳巗巎丂廆嫵嫵堢曇乿壀嶳巗巎曇廤埾堳夛丄徍榓係俁擭丂傛傝
暥壔侾侾擭丄旛慜斔丄壀嶳栧揷偱柍検堾擔帄傪曔敍丄崠偵搳偢傞丅
仦暥惌俀擭乮1819乯旛慜塿尨朄擄
2019/02/09捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俉姫丂嬤悽俁乿1987丂傛傝
丂塿尨懞栘榓揷榓夘戭偵晄庴晄巤憁擔泏偑愽暁偟偰偄傞偙偲傪嶡抦偟偨孲曭峴偼攝壓偺栶恖偵戇曔傪柦偢傞丅栶恖偼悢恖偺庤壓傪堷偒楢傟丄栘榓揷戭傪庢傝埻傒丄擔泏傪曔傜偊丄敧敠媨恄姱偱偁傞枩戙壠偺強偵堷偒棫偰偰偄偔丅
偙偺嬞媫帠懺偵懞柉偨偪偼孡傗朹傪帩偪丄栶恖偨偪傪庢傝埻傒丄擔泏傪庢傝曉偦偆偲偡傞丅懡惃偵柍惃偦偟偰婥敆偵懞柉偑栶恖傪忋夞傝丄懞柉偼栶恖偵廝偄妡偐傝丄栶恖偺搧傪扗偄丄枩戙壠偺愇奯偵撍偭崬傒丄傊偟愜偭偰偟傑偆丅
丂偙偺憶摦偱擔泏偼媬弌偝傟丄摝憱丅
偟偐偟丄崱搙偼孲曭峴帺傜偑悢廫恖偺庤壓傪楢傟丄懞偺屗庡俉侽悢恖傪彚偟庢傝丄壀嶳傊楢峴丅
偦偺偨傔丄擔泏偼懞柉偺媬弌偲撪怣慻怐偺慡柵傪杊偖偨傔弌慽偡傞丅
偙偺朄擄偼帺傜偺怣嬄偺偨傔柦傪挘傞擾柉偺巔偑晜偒挙傝偲側傞偲摨帠偵婛惉偺恎暘惂搙偑曵夡偟偮偮偁傞偙偲傪帵偟偨傕偺偱偁傠偆丅
仦暥惌係擭乮1821乯旛慜栴尨朄擄
2018/11/15捛壛丗
仜乽壀嶳巗巎丂廆嫵嫵堢曇乿壀嶳巗巎曇廤埾堳夛丄徍榓係俁擭丂傛傝
暥惌係擭丄旛慜斔丄愒嶁孲柧椆堾擔憡丄捠払堾擔媊傎偐係柤偺撪怣幰傪専嫇丄搳崠丅
乑乽壀嶳導偺抧柤乿丂傛傝
丂愒嶁孲栴尨懞丗
丂暥惌係擭乮1821乯朄棫擔憡丒擔媊偑巬懞尨偺樈彆戭偱曔傜偊傜傟丄楽巰偡傞丅偙偺帪壠庡丒慻摢係柤傕搳崠偝傟傞丅
仦揤曐俀擭乮1831乯旛拞嶳揷懞偺朄擄
嶲峫暥專丗
仜乽傢偨偔偟偨偪偺暉揷乿妢愇棽廏丄1983/01丂亜丂俀.傓偐偟懞偱婲偒偨弌棃帠丂亜丂晄庴晄巤怣幰抏埑偝傟傞乮嶳揷屲恖廤帠審乯丂傛傝
丂揤曐尦擭懡悢偺撪怣幰偑曔敍偝傟憅晘戙姱強偵楢峴偝傟傞丅晄庴晄巤怣嬄傪抐偮偙偲傪惥栺偟偨傕偺偼幎愑偺忋丄曻柶偝傟傞丅
偟偐偟彲壆壀帯屲榊丒慻摢壀椙彆丒妢愇娾媑丒壀岾廫榊丒壀師榊敧偺俆柤偼婞嫵偣偢峕屗憲傝偲側傞丅
丂摉帪丄嶳揷懞偱偼晄庴晄巤攈怣嬄偺妶摦偑塡偝傟傞傕丄摉帪偺嶳揷懞偼揤椞偱偁偭偨偺偱丄岞慠偲旛慜丒旛拞偺斔栶恖偑怣幰偺掋嶡憑嶕偡傞偙偲偼崲擄偱偁偭偨丅憅晘戙姱強偱偼嫊柍憁巔側偳偵曄憰偟偰晄庴晄巤攈傪俁擭偵傢偨傝撪掋偟専嫇偵帄傞偲偄偆丅
丂乮暥惌俈擭乮1824乯嶳揷懞偼斅憅斔偐傜椞抧懼偟偰枊晎捈妽椞乮憅晘戙姱強巟攝乯偲側傞丅乯
慻摢壀椙彆偼峕屗岇憲搑拞偺揤曐擇擭幍寧擇廫敧擔惱嫀丄彲壆帯屲榊偼揤曐擇擭敧寧敧擔峕屗偺楽拞偱惱嫀丄娾媑傎偐俁恖偼婞嫵傪惥栺偟幫柶偝傟偰嶳揷懞傊偺婣崙傪嫋偝傟傞偲偄偆丅偟偐偟偙偺婞嫵偼昞柺偩偗偱偁偭偨偲偄偆丅
丂側偍丄嶳揷忩愹帥偼晄庴晄巤傪栙擣偟丄敪妎屻傕懞柉偐傜婣埶徹暥傪庢傜側偐偭偨偨傔俁侽擔偺昇嵡傪怽偟搉偝傟傞丅
丂丂仺旛拞嶳揷偺偍捤
仦揤曐朄擄
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
丂揤曐俉擭乮1837乯戝墫偺棎偺帪丄戝嶁島拞偐傜懡偔偺嶲壛幰傪弌偟偨偙偲偐傜丄棎屻偺抏埑傪彽偔偲塢偆丅
朄擄偼慡崙偵搉傝丄惣偼埨寍丒旛屻丄旛慜旛拞旤嶌丄巐崙偼嶿婒丄嫗搒丒戝嶁丒壨撪丒榓愹偺婨撪丄杒偼壛夑丒嵅搉丄娭搶偼峕屗丒忋憤丒壓憤媦傃旜挘偺怣幰傪幓偔曔敍丄夁崜側嬦枴傪峴偆丅
偙偺抏埑偼撪怣晄庴晄巤傪夡柵偝偣傞戝朄擄偱偁偭偨丅
2019/02/09捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俉姫丂嬤悽俁乿1987丂傛傝
丂揤曐朄擄偼揤曐俋擭乮1838乯俈寧傛傝巒傑偭偨枊晎偵傛傞慡崙揑婯柾偺晄庴晄巤抏埑帠審偱偁傞丅
尰嵼慡杄偼柧傜偐偱側偄偑丄偦偺憑嵏偼乽晲憡椉憤偺巐廈丄旜挘丄壛夑丄嫗搒丄戝嶁丄椉旛丄嶌廈媦巐崙摍乿偵搉傝乽崱擔桺揤曐俋擭偺朄擄偲塢傊偽屆榁摍偼嶰暁愴溕傪姶偢乿乮戝惓侾侽擭乽擔楡庡媊朄擄廤-撆屰弣嫵崋暿杮乿乯偲偄傢傟傞傎偳偱偁傞丅
巎椏揑偵柧傜偐偵偝傟偰偄傞傕偺偩偗偱傕丄楽巰俁侾恖丄摝朣拞昦巰侾柤丄棳嵾侾柤偵偺傏傞丅乽憏柵偺朄擄乿偲偄傢傟傞傎偳偺戝抏埑偱偁偭偨丅偙偺朄擄偵傛傝嫮屌側撪怣慻怐傕夡柵偲側傞丅
丂敀愳擔戣攈偼揤曐偺朄擄偱丄憁椀丒慻怐偑慡偰幐傢傟丄朄棫傪拞怱偵尰嵼傕撪怣傪懕偗偰偄傞丅
丂丂丂仺丂敀愳擔戣攈
丂媣暷塃塹栧攈傕揤曐偺朄擄偱丄憁椀丒慻怐偑慡偰幐傢傟丄摨怣偺怣幰偱丄崱傕撪怣傪懕偗偰偄傞丅
媣暷塃塹栧攈偺巒傑傝偼乽揤曐朄擄乿偺嵺偵島栧攈偺杮嫆抧偱偁傞戝嶁搶崅捗廜柇埩偑揈敪偝傟丄彫憁媣暷塃塹栧偑怷枛偺屼埩偵偨偳傝拝偒丄徚偊偐偐偭偨朄摂傪揱偊偨偙偲偵傛傞丅
丂偦偺屻柧帯弶擭偺島栧攈嵞嫽偺嵺偵側傫傜偐偺棟桼偱媣暷塃塹栧攈偲偟偰暘棧偡傞丅
丂丂丂仺丂媣暷塃塹栧攈
偲偙傠偱丄偙偺朄擄偼崱傑偱偺朄擄偲偼僷僞乕儞偑堘偆抏埑偱偁偭偨丅
戞侾偼丄崱傑偱偺朄擄偼巟攝椞庡偑嵎攝偡傞傕偺偱偁偭偨偑丄揤曐朄擄偱偼枊晎栶恖偑捈愙奺抧偵弌挘偟嵎攝偟偨偺偑摿挜偱偁傞丅
戞俀偼丄崱傑偱偼撪怣幰偺怣嬄偺崅梘偵嫼埿傪姶偠偨抙撨帥偺弌慽傗揈敪偐傜敪惗偟偨偑丄揤曐朄擄偱偼枊晎偵傛傞慡崙婯柾偺寁夋揑抏埑偱偁偭偨偺偑偦偺摿挜偱傕偁偭偨丅
暥壔丒暥惌婜傛傝憹壛偟偨懞曽憶摦丄揤曐婜偵昿搙偑崅傑偭偨昐惄堦潉傗懪偪毷偟偵枊晎偼婋婡姶傪偄偩偒丄廆嫵堎抂偲寢傃偮偔偙偲傪寵偭偰丄偙偺揤曐偺朄擄傪枊晎偑庡摫偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅
2019/08/13捛壛丗
仜乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿撧椙杮扖栫丒崅栰悷丄彫妛娰丄徍榓係俈擭丂傛傝
揤曐戝朄擄乮揤曐朄擄乛撪怣亅巤庡偺崻愨乯
丂揤曐俉擭乮1837乯戝墫暯敧榊偺棎偑婲傞丅偦偺慜擭偼戝婹閇偱偁偭偨丅
偙偲偺捈愙偺敪抂偼楡壺堾擔宲乮旛慜嵅攲柇愹埩庡巤墹堾擔柇偺掜巕偲偄偆乯偺帺敀偱偁傞丅擔宲偼戝嶁偱晍嫵偟偰偄偰俁侽恖傎偳偺怣幰傪摼傞丅
島拞偱晄庴晄巤岞嫋偺弌慽傪偡傋偒偲偄偆偙偲偵側傝丄擔宲偼峕屗偵弌偰弌慽偡傞傕丄帥崋嶳崋偑側偄偲偺棟桼偱媝壓偝傟丄婣嶃偡傞丅偦傟側傜丄廜柇埩偺柤傪巊偊偽椙偄偲偺偙偲偵側傞丅
丂擔宲偼搶崅捗懞偵堷偒堏傝丄廜柇埩偺傕偺偲恊偟偔側傞丅廜柇埩偑嫗搒愇搩帥枛偺岝挿帥塀嫃強偱偁傞偙偲傪暦偒弌偡丅偮傑傝廜柇埩偼撪怣偺埩偱偁偭偨偺偩丅
丂擔宲偼嵞傃峕屗偵弌偰丄崱搙偼乽愇搩帥枛岝挿帥塀嫃強廜柇埩乿偺尐彂偱弌慽偟偨偐傜丄庢傝忋偘偵側傝丄嬦枴偑偼偠傑偭偨強偱擔宲偼楽巰偡傞丅
曭峴偺恞栤偵偁偭偨擔宲偼撪怣慻怐偺幚忣傪怽偟棫偰偰偟傑偄丄偦偺堊廜柇埩傪偼偠傔偲偡傞撪怣慻怐偑堦惸偵専嫇偝傟傞朄擄偑敪惗偡傞丅
埲忋偼埨惌俆擭乮1858乯怣摼堾擔弫偑挊傢偟偨乽廜柇埩朄擄婰乿偵弌偰偔傞丅偙傟偼捗帥攈乮島栧攈乯婑傝偺暥彂偱偁傝丄偙偺暥彂偺榑揰偵偼懡彮偺僶僀傾僗偑偐偐偭偰偄傞偲傒傞傋偒偱偁傠偆丅
丂廜柇埩偼捗帥攈偺嫆揰偱偁傝丄壓憤偺晄庴晄巤傕廜柇埩偺宯摑偱偁傞丅
擔宲偑偄偔傜懠攈偺幰偲偼偄偊丄弶傔偺偆偪偼擔宲偑廜柇埩偺偙偲傪抦傜側偐偭偨偲偄偆偺偼晄壜夝偱偁傞丅傑偨擔宲偑巤墹堾擔柇偺掜巕偲偄偆偺傕媈栤偑偁傝丄擔巜攈偱偼娦嬇偺揱摑偑懕偄偰偍傝丄偄偐偵曭峴偺恞栤偑岻傒偲偟偰傕丄傗偡傗偡偲撪怣慻怐偺慡杄傪敀忬偡傞偲偄偆偺傕偍偐偟偄偺偱偁傞丅
丂寢嬊丄擔宲偺慺惈偼晄柧偲偡傞偟偐側偄偑丄朄擄偑慡崙偺撪怣慻怐偵媦傫偱偄偭偨宱夁偼柧傜偐偵偝傟偰偄側偄丅
寢壥偼旤嶌丒旛慜丒旛拞丒嶿婒丒嫗搒丒戝嶃丒壨撪丒榓愹丒壛夑丒嵅搉丒峕屗丒忋憤丒壓憤丒旜挘偺峀偄斖埻偱撪怣偑曔敍偝傟傞丅専嫇偼揤曐侾侾擭乮1840乯傑偱懕偔丅
丂楽巰偟偨朄拞偼宐廏堾擔姲乮拲乯丒戜嶳堾擔徠乮拲乯丒抭尯堾擔搶乮拲乯丒宐嶡堾擔挿乮拲乯丒楡壺堾擔宲丒擔彋偱偁傝丄敧忎弌恎偺擔梫丒擔鎩傕楽巰偟偨傛偆偱偁傞丅巤墹堾擔宲偼嶰戭搰偵墦搰偲側傞丅
丂乮拲乯偺巐巘偼捈壓偵拲婰偡傞丅
偙偺帪丄戜嶳堾擔徠偺掜巕偱屻偺愰柇堾擔惓傕廜柇埩偵偄偨偑丄嬱偗晅偗偨怣幰偺婡揮偱婋抧傪扙偟偰偄傞丅朄棫偲怣幰偱楽巰偟偨傕偺偼俀俈恖傑偱暘偐偭偰偄傞偑丄偦傟埲奜偵傕媇惖幰偼偄傞傛偆偱偁傞丅俀俈恖偺拞偵偼彈惈偺朄棫柇婌偑偄傞丅
丂捗帥攈乮島栧攈乯偺慡偰偺朄拞偼楽巰偟朄柆偑愨偊傞丄戝嶁傗壓憤偺撪怣慻怐偼夡柵偡傞丅擔巜攈偱傕斾塨嶳偵偄偨徠岝堾擔宐丒嶰戭棳憁偺擔柇丒敧忎棳憁偺擔弰偵傛偭偰嵶乆偲朄柆傪宷偖偙偲偵側傞丅
丂摉帪丄敧忎弌恎偺擔梫丒擔鎩偍傛傃旛慜偺朄棫戜嶳堾擔徠偼堦嫶椞偱偁傞旛拞搶媑愳懞丒惣媑愳懞偵愽暁偟偰偄偨丅擔梫偼旤嶌捗嶳忛壓丄旛慜偺朄棫忢暫塹偲擔鎩偼攲闼嶰挬偱曔敍偝傟傞丅擔梫丒擔鎩偼楽巰偲偄傢傟傞偑偙傟偼椙偔暘偐傜側偄丅
丂敧忎搰拞僲嫿妦棫偺媢偵偁傞俆婎偺晄庴晄巤憁偺曟旇偺撪擔梫偺曟旇偩偗彫宆偱偁傞丅戝宆係婎偼娫堘偄側偔杮搚偐傜憲偭偰偔傞愇嵽偱寶偰傜傟偨傕偺偱偁傞偑丄擔梫偺旇偑杮搚偺嵽偱偁傞偐偳偆偐偼晄柧偱偁傞丅擔梫旇偵偼乽擔楡惓廆擔梫戝摼埵/揤曐侾侾擭俉寧俀俋擔乿偲崗傒丄擖楽偟偨偐傜俁擭屻偺惱嫀偲側傞傢偗偱丄楽巰偼媈栤偲傕偄偊傞丅偄偢傟偵偣傛丄擔梫偺曟偼惗傑傟偨敧忎偺媢偺忋偵寶偰傜傟偰偄傞丅
丂仸宐廏堾擔姲丒戜嶳堾擔徠丒抭尯堾擔搶偼戝嶁崅捗廜柇埩偱曔敍偝傟傞偲偄偆丅
丂丂忋婰偼儁乕僕丗惓媊偺嫨傃侾俆/戝嶃崅捗偺廜柇埩傪嶲徠
--- 乽朰傟傜傟偨弣嫵幰乿廔---
2024/09/27捛壛丗
丂乮拲乯
仧宐廏堾擔姲丒宐嶡堾擔挿丒戜嶳堾擔徠丒抭尦堾擔搶
丂丂仺巐巘偺曟搩乮嫙梴搩乯偼旛慜搇桳柇楡帥乮旛慜愒嶁孲搇桳懞拞乯偵偁傝丅
丂丂仺旛慜幁悾杮妎帥拞偺島栧攈楌戙丒戝嶃崅捗廜柇埬宯晥側偳傪嶲徠丅
乑乽擔楡廆晄庴晄巤攈妞巎擭昞乿丂傛傝
丂丂揤曐俋擭乮1838乯7.16丗戝嶃廜柇埩扵嶕偝傟傞丅
丂宐廏堾擔姲丗
丂丂乮廜柇埬俋悽乯
丂丂揤曐俋擭7.20丗壨撪杒忦懞岝挿帥偱擔姲丒擔搶曔敍偝傟傞丅
丂丂揤曐侾侾擭12.18丗揤曐朄擄偺敾寛怽偟搉偟丅
丂丂揤曐侾俀擭11.20丗擔姲丄屗峕屗偵偰楽巰偡傞丅
丂丂丂仸庘擭偵偮偄偰偼丄
丂丂丂丂杮壔擔廆杮嶳擔島帥乮墶堜忋乯偺嫙梴搩媦傃廜柇埬楌戙偱偼揤曐俋擭俈寧侾俋擔庘偲偡傞丅
丂宐嶡堾擔挿丗
丂丂揤曐俋擭7.29丗擔挿丄榓愹傛傝婭埳傊摝朣拞丄庘偡傞丅
丂戜嶳堾擔徠丗
丂丂乮廜柇埩侾侽悽丒媽愭椺攈柇愹埩庡丒旛慜幁悾峕揷巵偺惗傑傟乯
丂丂揤曐俋擭7.21丗戝嶃崅捗挰拞擵挰挰堛幰戭偱擔徠曔敍偝傟傞丅
丂丂揤曐侾侽擭7.20丗擔徠丄峕屗偵偰楽巰偡傞丅
丂抭尦堾擔搶丗
丂丂揤曐俋擭7.20丗壨撪杒忦懞岝挿帥偱擔姲丒擔搶曔敍偝傟傞丅
丂丂丂仸揤曐俋擭俈寧侾俋擔庘丅搶帠堾丒抭尯堾偲傕丅
2018/11/15捛壛丗
仜乽壀嶳巗巎丂廆嫵嫵堢曇乿壀嶳巗巎曇廤埾堳夛丄徍榓係俁擭丂傛傝
丂揤曐俋擭乮1838乯戝嶁曭峴強偐傜栶恖偑壀嶳偵弌挘丄惣拞搰偺惣壆偵懾嵼丄壀嶳晬嬤傪扵嶕丄忋摴孲暯堜懞偺晉揷捈暫塹晇晈傪撪怣幰偲偟偰曔敍偡傞丅偙傟傪抦偭偨嬥愳偺朄棫丒屼摗媑屲榊偑斔挕偵帺慽丄乽梋偼晄庴晄巤偺朄棫側傝丄丒丒丒懞撪幓偔晄庴晄巤傪怣偢丄偙傟梋偑姪桿偡傞強偵偰丄姱偦傟梋傪敱偟偰丄斵傜傪幫偣丒丒丒乿偲捈暫塹晇晈偺堊曎岇偟偨偺偱丄悑偵尃椡懁偼晇晈傪曻柶丄媑屲榊傪搳崠偡傞丅
揤曐侾侽擭係寧俁侽擔朄棫丒屼摗媑屲榊偼桍尨孻応偱抐嵾偵張偣傜傟傞丅
2019/02/09捛壛丗
仜乽壀嶳導巎丂戞俉姫丂嬤悽俁乿1987丂傛傝
仦旛拞忋朳孲媑愳懞揤曐朄擄
丂揤曐俋擭乮1838乯侾侽寧俀俁擔丄戝嶁挰挰曭峴強栶恖偑庤壓侾俀恖傪楢傟偰丄旛拞忋朳孲媑愳懞偵弌挘偟丄搶媑愳懞惌暫塹丒斏敧媦傃惣媑愳懞栱暯偺俁柤偺曔敍偵棃傞丅梕媈偼俁柤偺晄庴晄巤怣嬄偺寵媈偱偁傞丅
摨懞彲壆徖杮峀塃塹栧偼丄摉帪摨抧偼堦嫶壠偺椞抧偱偁傞偺偱巟攝偺椞庡偵巉偄傪棫偰偰梸偟偄偲愢偒丄栶恖偵偼堷庢傪婅偆丅
梻擔丄婣懞偟偨俁柤偼抦峴強偱偁傞峕尨栶強偵楢峴偝傟傞丅
俀俇擔俁柤偼旛拞斅憅廻偵弌摢偝偣傜傟丄偝傜偵偦偺屻丄旛慜壀嶳偵楢峴偝傟擖楽偲側傞丅
惌暫塹丒斏敧偺庢挷傋傛傝媑愳懞撶擵忓丒慞嵍塹栧晝巕偑晄庴晄巤怣幰偱偁傞偙偲偑敾柧偡傞丅
傑偨媑愳懞偺暦偒崬傒傛傝丄旛慜嬥愳懞嶻偺忢暫塹偲憁椀杮峴堾擔鎩丒婌懢榊乮屻掍敮偟憁擔梫偲側傞乯傜偑丄旤嶌曈偵摝朣偟偨偙偲偑暘偐傝丄栶恖傜偼旤嶌偲嶿婒曽柺偺俀庤偵暘偐傟憑嶕偵岦偐偆丅
丂擔鎩丒忢暫塹丒枩屲榊傜偼旤嶌嫽捗偐傜嶳墇偊偟偰攲闼嶰挬傑偱摝偘偺傃偰偄偨偑丄曔敍偝傟傞丅
婌懢榊傕捗嶳偺庲壠壀嶈桾巐榊乮捗嶳斔壠榁嵅媣娫挿栧偺壠恇乯戭偵偐偔傑傢傟偰偄偨偑曔傜偊傜傟丄擔鎩傜偲偲傕偵壀嶳傊楢峴偝傟傞丅
婰榐偱偼壀嶳偵楢峴偝傟偨偺偼乽忢暫塹丒婌懢榊丒杮峴乮擔鎩乯丒抧摢憏帯丒奜偵堦恖乿乮乽戝嶁梌椡摨怱廜擖崬彚曔擵巒枛妎乿乯偲偁傞偑丄奜偵堦恖偲偼枩屲榊偱偁傠偆偑丄抧摢憏帯偲偼屻偺婰榐偵傕側偔晄柧偱偁傞丅
丂侾侾寧侾俇擔偵偼撶擵忓傕撽晅偒偱壀嶳偵楢峴偝傟傞丅埲忋偱媑愳懞偺専嫇偼廔椆偡傞丅
張暘偵偮偄偰偼戝嶁挰曭峴強偑壓偡丅
憁擔鎩丒擔梫乮婌懢榊乯偼戝嶁偵楢峴偝傟丄偱楽巰偡傞丅
忢暫塹偼擔鎩傜偲偲傕偵戝嶁偵楢峴偝傟偨偲巚傢傟傞傕婰榐偑側偔丄晄柧丅
惌暫塹丒斏敧丒撶擵忓偼乽懞梐偗乿丄栱暯偼乽娭學側偟乿偱曻柶丄侾侾寧俀俆擔偵斵傜偼婣懞偡傞丅
枩屲榊偼乽峔偄側偟乿偱侾侾擔婣懞偡傞丅
捗嶳斔壠榁嵅媣娫挿栧偼壠恇偺娔撀晄峴撏偱丄侾擔偺嵎峊偊丄壠恇壀嶈桾巐榊偼乽塱乆壣乿傪怽偟搉偝傟傞丅
---乽壀嶳導巎丂戞俉姫丂嬤悽俁乿廔---
2019/02/09捛壛丗
仜乽擄攇堦懓乿
仦旛拞忋朳孲媑愳懞揤曐朄擄
丂乽擄攇堦懓乿偲偄偆僽儘僌偑偁傝丄媑愳朄擄偵偮偄偰偺婰帠偑偁傞偺偱丄梫栺丒揮嵹偡傞丅
側偍丄揤曐偺媑愳懞朄擄偱丄曔敍偝傟偨斏敧偼擄攇巵偱丄擄攇斏敧偺屻遽偑僽儘僌乽擄攇堦懓乿傪娗棟偟偰偄傞傕偺偲巚傢傟傞丅
傑偨丄嶲徠暥專偲偟偰丄忋婰偺乽壀嶳導巎丂戞俉姫丂嬤悽俁乿偑嫇偘傜傟偰偄傞偺偱丄朄擄偺奣梫偼乽壀嶳導巎丂戞俉姫丂嬤悽俁乿偲摨條偺傕偺偲側偭偰偄傞偑丄怴偟偄帠幚傕懡偔岅傜傟傞丅
丂丂仺忋婰偺乽擄攇堦懓乿偺婰帠偺傎傏慡梕傪乽旛拞忋朳孲媑愳懞乿偵揮嵹偟偰偄傞偺偱丄嶲徠傪惪偆丅
傑偨丄旛拞媑愳懞偵偼旛慜嬥愳柇殸帥俉悽擔忛忋恖偑弰庎偡傞偲偄偆丅
憗偔偐傜擔楡廆偑峅捠偟偰偄偨搚抧暱偱偁傠偆偟丄嬛惂屻傕撪怣偑懡偔懚嵼偟偰偄偨懞偱偁傞丅
2019/09/19捛壛丗
仜乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿憡梩怢丄戝錟弌斉丄徍榓俆侾擭乮1976乯丂傛傝
壓憤朄擄
丂揤曐擭娫偺壓憤崄庢孲搰懞偺擾柉傜偵娭偡傞帒椏乽揤曐侾侾擭巕擭廆栧堦審屼嵸嫋涹偵峳憹巒枛偺婰乿偑偁傞丅
丂丂伀乽揤曐侾侾擭巕擭廆栧堦審屼嵸嫋涹偵峳憹巒枛偺婰乿偼壓宖伀乽懡屆挰巎丂忋姫乿拞偵偁傝丅
偙傟偼忋憤丒壓憤偱傕嫮楏側掞峈偲愽峴偑偁偭偨偙偲偺堦偮偺椺徹偱偁傞丅枊晎偵傛傞惁嶴側張孻偑孞傝曉偝傟傞拞偱丄朄柆偼側偍銅乆偲偟偰恠偒傞偙偲偼柍偐偭偨偺偱偁傞丅搰懞偼崱偱傕慡屗偑晄庴晄巤攈偱偁傞丅
丂揤曐俋擭乮1838乯俉寧崄庢孲搰懞偺昐惄赓塃塹栧丄嶰榊嵍塹栧傜俈恖偑曔敍偝傟丄偆偪俆恖偼峕屗偱嬦枴偝傟傞丅
嶰榊嵍塹栧偼俋寧偵楽巰丄赓塃塹栧偼弌楽偡傞傕侾侾寧偵昦巰丄拤暫塹偼梻擭俈寧偵婣懞傪嫋偝傟傞傕偦偺梻擭俁寧偵昦巰偡傞側偳壵崜偼庢挷傋偵憳偆丅
嶰榊嵍塹栧偺堚懓偺嬦枴偱樹慞錟偺嫙弎偑偁傞偑丄偦偺拞偵愛捗搶崅捗懞朄摢宐廏堾擔姲偺柤慜偑偱偰偔傞偑丄忋憤丒壓憤偺晄庴晄巤怣嬄偼愛捗崅捗廜柇埩偺宐廏堾擔姲偺塭嬁偱偁傞偙偲偑抦傜傟傞丅偮傑傝斵傜擾柉偼揤曐俋擭俈寧戝乆揑偵庤擖傟傪庴偗偨廜柇埩偺娭學幰偲偟偰嬦枴媻柧傪庴偗偨偺偱偁傞丅
2023/09/24捛壛丗
仜乽懡屆挰巎丂忋姫乿徍榓俇侽擭丂傛傝
仧壓憤懡屆挰堟偵墬偗傞晄庴晄巤攈偺朄擄丂丂忋姫335乣
丂壓憤懡屆挰堟偵墬偗傞晄庴晄巤攈偺朄擄
丂丂晄庴晄巤攈奣愢丄姲暥偺朄擄乮懡屆挰堟乯媦傃揤曐朄擄丒巒枛彂乮懡屆挰堟乯偺婰榐偱偁傞丅
丂丂丂忋弎偺乽壓憤朄擄乿拞偺乽揤曐侾侾擭巕擭廆栧堦審屼嵸嫋涹偵峳憹巒枛偺婰乿偺婰嵹傕偁傞丅
2023/09/24捛壛丗
仜乽懡屆挰巎丂壓姫乿徍榓俇侽擭丂傛傝
仧壓憤拞嵅栰偵墬偗傞晄庴晄巤攈偵懳偡傞抏埑丂丂壓姫641乣
丂晄庴晄巤攈偵懳偡傞抏埑亂拞嵅栰乯亃
丂丂姲惌朄擄乮壓憤拞嵅栰乯媦傃揤曐朄擄乮壓憤拞嵅栰乯偺婰榐偱偁傞丅
2019/11/28捛壛丗
仜乽傆傞偝偲暯堜乿暯惉俇擭丂傛傝
朄棫屻摗媑屲榊
丂揤曐俋擭乮1838乯丄揤曐偺朄擄偺帪丄慡崙偱晄庴晄巤攈偺扵嶕丒曔敍偑峴傢傟傞偑丄戝嶃偐傜弌挘拞偺栶恖偲斔栶恖偑惣拞搰偺廻壆偱偁傞惣壆偵廻攽拞偺暯堜懞晉揷捈暫塹晇嵢偑晄庴晄巤怣幰偱偁傞偙偲傪暦偒崬傒丄崠偵搳偠傞帠審偑婲傞丅
偙傟傪暦偄偨捗崅孲嬥愳偺朄棫丒屻摗媑屲榊偑斔偵捈慽偡傞丅
丂巹偑晄庴晄巤偺朄棫偱偁傞丅斔偼晇晈偩偗傪嵾恖偵偟偰偄傞偑丄怣幰偼偙偺擇恖偩偗偱偼側偔丄懞撪慡偰偱偁傞丅捈暫塹傪姪桿偟偨偺偼巹偱偁傞丅捈暫塹偼曻柶偟丄巹傪敱偡傞傋偒偱偁傞丂偲丅
斔偼捈暫塹晇晈傪幫偟丄媑屲榊傪搳崠偟丄梻侾侽擭乮曟旇偵偼揤曐俋擭偲偁傞偲偄偆乯桍尨孻応偱抐嵾偲側傞丅
丂仺桍尨孻応偼旛慜忋摴孲栐昹懞丒柀懞丒暯堜懞拞偵偁傝
2025/01/30捛壛丗
仧榓愹榓婥朄擄
丂揤曐俋擭俉寧丄戝嶁挰曭峴強梌椡偑弌挘偟丄榓愹榓婥懞丒堜僲岥懞偵偰抏埑偡傞丅
徾挜揑側帠審偑垻壘懢嶳偵擔憡曟搩傪攋夡偟丄宱愇傗曟愇傪晅嬤曻婞偟偨偙偲偱偁傞丅
丂仺乽榓愹怴嵼壠偺埩乮柍柤乯乿/乽榓愹垻栱懮埩乿亙擔憡忋恖帠愌丒榓婥朄擄傪娷傓亜
仦嶁杮榓暯乮恀妝乯擖楽丒棳孻
2013/07/04捛壛丗
仜乽壀嶳導嬞媫屆暥彂挷嵏曬崘彂丂晄庴晄巤攈巎椏栚榐乮俀乯乿丂傛傝
柧帯俁擭俉寧俁擔丄枊枛丒堐怴偺寖摦婜丄晄庴晄巤嵞嫽傪擮偠偦偺幚峴塣摦偵実傢偭偨偲偄偆棟桼偱丄曔敍丄侾侽寧偵幁媣嫃搰乮仸幁媣嫃搰彅搰偱偁傞愗巟扥棳孻抧偺掃搰乯偵棳孻偲側傞丅
晄庴晄巤傊偺嬛惂偼柧帯堐怴傕懕偄偰偄傞偲偄偆偙偲傪帵偡帠審偱偼偁傞偑丄偟偐偟丄晄庴晄巤偺嬛埑偼偙偺帠審偑杦偳嵟屻偱丄慟師娚榓偺弻岝偑尒偊丄侾擭偺孻婜傪宱偰丄梻係擭侾侽寧偵幫柶偲側傞丅
柧帯俁擭偺乽孻朄嬊怽搉乿偼師偺傛偆偵塢偆丅
丂屼栰孲懳攏捗搰懞擵撪惣嶁
丂丂丂憹帯丂杮柤丂嶁杮榓暯
丂懘曽媀屼惂嬛擵幾廆栧庢峴岓僯晅丒丒丒丄晄庴晄巤廆栧怣嬄抳僔忚僿幾憁儝榓婥孲塿尨懞僿桿堷僔摨強僯墬僥儌枾僯朄択僯媦岓忦
丂恟埲怱摼堘晄毥擵帄僯岓墬幁媣嫃搰搆孻怽晅岓栫
丂丂丂扐欀懮梾懘奜晄庴晄巤廆庢梡僸岓彂椶晄巆暐忋壜怽帠
2019/08/19捛壛丗
仜乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿崅栰悷丒壀揷柧旻丄崙彂姧峴夛丄徍榓俆俀擭丂傛傝
棳嵾抧丗埳摛彅搰偺奣梫
埳摛彅搰偵偼懡偔偺晄庴晄巤攈憁丒朄棫側偳偑棳偝傟傞丅
埳摛彅搰偼峕屗偐傜尒偰丄戝搰丄怴搰丄崅捗搰丄嶰戭搰丄屼憼搰丄敧忎搰偺弴偵撿偵暲傇丅
仠戝搰
仦奀拞帥丗
丂奀拞帥偵晄庴晄巤棳嵾憁俉柤偺曟旇偑尰懚丅
岦偐偭偰嵍抂偼擔廦栧棳搶慟堾擔鐥偺曟偱乽僪僂僥僀朧乿偲屇偽傟偰偄傞丅偙傟偼彈斊憁偲嬫暿偟偰偺懜徧偱偁傠偆丅
丂丂丂仺搶慟堾擔鐥丗忢妝堾擔宱拞
丂仸戝搰偵偼懡偔偺憁懎偑棳偝傟乮乽晄庴晄巤弣嫵偺楌巎乿偱偼俀俀柤偺憁懎偺柤偑偁傞丄擔廦栧棳擔鐥偺柤慜偼側偄乯憁偺柤慜傪摿掕偱偒側偄丅
丂仸搶慟堾擔鐥丗擔宱偺崅掜惓慞堾擔氭偺掜巕丄傕偟偔偼擔忛偺掜巕偲偄偆丅枩帯俁擭乮1660乯埳摛戝搰棳嵾偲側傞丅尦榎俆擭乮
1692乯庘丅
仦嫟摨曟抧撪丗
晄愼堾擔慠曟旇丂擔慠偼嫕曐俁擭峴愳朄擄偱棳嵾偲側傞丅
抭尛堾擔媊曟旇丂擔媊偼尦榎朄擄偱棳嵾偲側傞丅
偑尰懚丅
仠怴搰
尦榎朄擄偱棳嵾偵側偭偨嵟彑堾擔梴曟旇丂尰懚丅
仠恄捗搰
尦榎朄擄棳嵾偺俈婎偺晄庴晄巤憁偺曟偑巆傞丅
偝傜偵嶰戭搰傛傝搰懼偊偝傟偨棽尗堾擔徠偺曟旇乮屲椫搩乯偑巆傞丄
擔徠偼晉巑栧棳偺憁偱偁傝丄揤柧俁擭乮1783乯嶰戭搰偐傜娦嬇彂傪採弌偟偨嵾偵傛偭偰恄捗搰偵搰懼偊偲側傞丅尦榎朄擄晄庴晄巤俈憁偲偲傕偵柊傞丅
仠屼憼搰
曮楋俁擭乮1753乯媣墦堾擔慠偲偦偺掜巕滀抭堾擔墢偼峕屗帥幮曭峴偵弌慽娦嬇偡傞丅擔墢偼屼憼搰偵棳嵾偲側傞丅擔慠偼棳嵾慜偵崠巰偡傞丅擔墢曟旇偼屼憼搰偵尰懚丅
仠嶰戭搰
仦惓摑堾擔彯丗忢妝堾擔宱偺栧棳乮擔廦栧棳乯
丂擔彯偼嫗搒偺恖偱丄峕屗偵怴柇朄帥傪寶棫偟偰偄偨偑丄惛恑堾擔塸偲偺廆榑偵攕傟丄枩帯尦擭乮1660乯棳嵾偲側傞丅姲暥埲慜偺棳嵾偱偁傝丄嶰戭搰晄庴晄巤棳憁偺嵟弶偺棳憁偱偁偭偨丅搰偺尵偄揱偊偱偼丄娤壒壓嫶偵埩偺愓偑偁傝丄擔彯偼偙偙偵廧偟偰偄偨偲偄偆丅
丂丂丂仺惓摑堾擔彯丗忢妝堾擔宱拞
仦埳摛懞慮棦愳晄庴晄巤攈曟旇丗
丂搰撪堦廃摴楬偐傜埳摛枽偵壓傝偰偄偔偲搑拞偱慮棦愳傪墶愗傞丅偙偙偵俋婎偺曟偑偁傞丅
堦斣戝宆偺曟偑擔彯偺曟旇偱偁傞丅
堦偮偩偗暿偵側偭偰偄傞偺偼丄杮惓堾擔惥偺曟旇偱丄嵍塃偵侾俇憁偺柤偑偁傞丅
丂擔惥偼姲惌俇擭乮1794乯壓憤偺懡屆朄擄偱棳嵾偲側傞丅尦榎埲棃丄壓憤偐傜棳偝傟偰偒偨憁偼慡偰庘偟偰偄偨丅擔惥偼斵傜偺嫙梴偺偨傔偵侾婎偺搩傪寶棫偟偨偺偱偁傞丅
奜偺曟旇偼忩尮堾擔恑偑惓摑堾擔彯傗偦偺懠偺憁偺偨傔偵寶偰偨傕偺偱偁傞丅忩尮堾擔恑偼擔宱栧棳偱偁傝丄尦暥係擭乮1739乯棳嵾偲偁傞丅側偍丄埳摛懞偐傜奀娸偵弌傞婋尟側娫摴偵擔恑偑寶棫偟偨岎捠埨慡婩婅旇偑尰懚偡傞丅
仦惣扟抙椦擔弲偺曟丗
丂恎墑係俇悽乮屻偵彍楌乯柇忔堾擔彞偼擔弲偑晄庴晄巤憁偱偁傞偲帥幮曭峴偵採慽丄懳榑偲側傝丄偦偺寢壥擔弲偼嶰戭搰傊棳嵾偲偝傟丄擔彞偼擖楽屻楽巰偡傞丅
丂丂仸暥堄偼尨挊偺儅儅偱偁傞偑丄帠幚偺妋擣偑嵦傟側偄偟丄採慽偟偨擔彞偑擖楽偟楽巰偟偨偲偄偆堄枴偑晄柧丅
丂丂仸尨挊偵偼乽惣扟抙椦擔弲偺曟乿偺幨恀宖嵹偑偁傞偑丄曟旇偺敾撉偑傎傏晄擻丅
丂丂仸恎墑係俇悽乮屻偵彍楌乯柇忔堾擔彞偲偼晄徻丄擔弲偺堾崋側偳傕晄柧偱椙偔暘偐傜側偄丅
丂丂仸2023/09/02捛壛丗偙偺審偵偮偄偰偼丄
丂丂丂恎墑嶳亜恎墑係俇悽柇忔堾擔彞暅楋帠審丂偺崁偱徻嵶傪宖嵹偡傞丅
仦嶰戭搰埳儢扟偺曟抧丗
丂俆婎偺晄庴晄巤憁偺曟偑偁傞丅
宱峴堾擔梫乮忋憤峴愳朄擄偱棳嵾乯丄杮柇堾擔庫丄慞峴堾擔惔乮峴愳朄擄丒擔梫偺巘丒戝庽埩俉悽乯丄柧惷堾擔閌丄怱惀堾擔椛偱偁傞丅
仦嶰戭搰忢彑埩
尰嵼偼庴攈偺慞梴帥偺傕偺偱偁傞丅
丂仸慞梴帥偼慞梲帥偲傕彂偔丄挿婌嶳偲崋偡傞丅墳塱俀擭乮1395乯昐惄慞幍偺敪婅偵傛傝丄擔梴榓彯偑棃搰偟寶棫偟偨丅忢彑埩偺懚斲偼妋擣偑偱偒側偄丅傑偨斣恄摪偑偁傞丅
仠敧忎搰
仦敧忎搰拞擵嫿妦棫偺曟旇丗
丂俀屄強崌傢偣偰俈婎偺晄庴晄巤棳憁偺曟偑偁傞丅
崅戜偵弌偰嵍懁偵俆婎偑側傜傇丅嵍偐傜帨壎堾擔壇乮壜慡乯丒帨擮堾擔彆乮壜恀乯丒庻検堾擔弰丒杮妎堾擔恑丒棫殺堾擔梫偺俆婎偱偁傞丅偐側傝戝宆偱擔梫傪彍偔係恖偼旛慜偺弌恎偱偁傞丅戝宆偺愇偼敧忎偱偼嵦傟偢丄旛慜偐傜塣偽傟偨傕偺偱偁傠偆丅
擔弰偼嫕榓俁擭乮1803乯旛拞憏捾偺朄擄偱棳嵾偲側傞丅
嶰戭搰擔庫偼杮妎堾擔恑偲桬峴堾擔挿偵崙庡娦嬇偺怱摼傪彂娙偱帵偡偑丄偦偺屻丄擔挿偼峕屗偱娦嬇偟偰楽巰丄擔恑偼敧忎棳嵾偲側傞丅暥壔侾俀擭乮1815乯侾侾寧偺拝慏偱偁傞丅
擔梫偼敧忎弌恎偱丄擔弰偺掜巕偱偁傞丅妦棫偺俆婎偺曟旇偺偆偪丄堦斣塃偵偁傞偺偑擔梫偺曟旇偱偁傞丅偙傟偼彫宆偱偁傞偑丄惓柺偵乽擔楡惓廆擔梫戝摽埵丂揤曐侾侾擭俉寧俀俋擔乿偲崗柫偑偁傞丅扤偑寶棫偟偨偺偐丄乽棳恖挔乿偵偼擔梫偺柤偼嵹偭偰偄側偄丅傗偼傝擔梫偲擔鎩偼揤曐朄擄偵憳偄丄峕屗偱楽巰偟偨偲傒傞偺偑惓偟偄傛偆偱偁傞丅崗柫偺乽揤曐侾侾擭俉寧俀俋擔乿偼擔梫偺柦擔偱偼側偔丄偍偦傜偔曟旇傪寶棫偟偨擔偱偁傠偆丅彮擭掜巕擔梫偺巰傪擔弰偼抦偭偨丅擔梫偺惉挿偵嫻傪朿傜傑偣偰偟偨擔弰偺嵟屻偺婓朷偑抐偨傟偨宍偱偁傞丅偄偐偵嫮怣偺擔弰偱傕徴寕側偟偵偼嵪傑側偐偭偨偱偁傠偆丅偦偺傛偆側擔弰偑擔梫偺曟旇寶棫傪峫偊偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
仦擔尠偲擔惉
丂拞擵嫿妦棫偵偼嫟摨曟抧偑偁傝丄嵅摗慞懢榊巵偺曟抧偵忢氭堾擔尠偲忔擛堾擔惉偺曟偑偁傞丅
尦榎偺斶揷朄擄偱敧忎憲傝偵側偭偨俀俇恖偺撪偺俀恖偱偁傞丅惔懚偲壜慞傕敧忎憲傝偵偁傞偑丄斵傜係恖偼峕屗偱摨偠挿壆偵廧傫偱偄偨偲偄偆丅擔尠偲擔惉偺椉憁偼俆侽擭埲忋傕嵼搰偡傞丅
晄愼堾擔梇曟旇丗僕儑僂儀儞條丗
丂敧忎搰枛媑偲偄偆偲偙傠偵搚抧偺恖偑僕儑僂儀儞條偲悞傔偰偄偨憁偺埩偑偁偭偨丅僕儑僂儀儞條偼椆楩偲偄偆棳憁偱偁偭偨丅
椆楩偼朄崋傪晄愼堾擔梇偲偄偄丄壓憤拞懞抙椦偺憁偱偁偭偨偑丄晄庴晄巤憁偲偟偰敧忎棳嵾偲側傞丅
乮擔梇偼拞懞抙椦偺妛憁偱晄庴晄巤偼惓媊偱偁傞偲彞偊棳嵾偲側傞丅乯
乽棳恖柧嵶挔乿偱偼曮楋尦擭乮1751乯偵棳嵾偲偁傞偑乽晄庴晄巤攈朄擄帒椏廤乿偱偼姲墑尦擭乮1748乯偵棳偝傟丄曮楋俁擭乮1753乯偵惱嫀偲側偭偰偄傞丅偝傜偵乽嶰戭搰棳恖挔乿偵偼乽姲墑係擭係寧侾俉擔敧忎搰傊棳嵾乿偲偁傞偲偄偄丄偙傟偼嶰戭偐傜敧忎傊搉偭偨擔偱偁傝丄姲墑尦擭偐傜係擭乮曮楋尦擭乯傑偱嶰戭偵偄偨偲夝偡傋偒偐傕抦傟側偄丅
丂壛愳帯椙巵偵傛傟偽丄椆楩偼拞懞抙椦偱偼側偔斞崅抙椦偺妛摢偱偁偭偨偲偄偄丄摉帪偼庴攈乮恎墑攈乯偺抙椦偱偁偭偨斞崅偺拞偱椆楩堦恖偼晄庴晄巤偺惓媊偨傞偙偲傪庡挘偟丄帺傜乽擔墱栧棳乿傪徧偟偰偄偨偲偄偆丅偲偄偆偙偲偱偁傟偽丄斵偼晄庴晄巤憁偲偄偆傛傝庴晄巤攈偺拞偺斀棎幰偲偟偨曽偑揑妋偱偁傠偆丅
丂丂丂晄愼堾擔梇偵偮偄偰偼丄拞懞抙椦亜晄愼堾擔梇偺鎩嬇丂偵傕婰弎偁傝丅
仦敧忎棳嵾彅巘楢彁欀涠梾
丂敧忎棳嵾彅巘楢彁欀涠梾乮慶嶳柇妎帥憼乯
丂仸楢彁偺彅巘偼慡偰尦榎係擭乮1691乯棳嵾偱偁傞丅尦榎朄擄偱棳嵾偵側偭偨捈屻偵彁柤偝傟偨傕偺偲悇掕偝傟傞丅
丂楢彁偟偨憁埲奜偵傕尦榎係擭棳嵾偺憁傕懚柦偱偁偭偨偲巚傢傟傞傕丄偦傟傜偺憁偺楢彁偑側偄棟桼偼暘偐傜側偄丅
丂乑乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿憡梩怢丂傛傝
丂丂棫愥堾擔忩丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄擔掚偺帒丄旛慜栰乆岥偺恖丄嫕曐俁擭乮1718乯庘丄俈俆嵨
丂丂惓抭堾擔寬丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄擔掚偺帒丄晲廈偺恖丄曮塱俁擭乮1706乯庘丄俇侾嵨
丂丂惀恀堾擔庣丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄廧慞帥弌帥憁丄尦榎俇擭乮1693乯庘丄俈係嵨
丂丂椞廆堾擔廆丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄尦榎俇擭乮1693乯庘丄俈俀嵨
丂丂殺廧堾擔妎丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄壓扟摽戝帥庱丄旛慜偺恖丄曮塱尦擭乮1704乯庘丄俈俁嵨
丂丂棫尗堾丂棫尗丂擔梀丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄隉椆偺帒乮隉椆偺懎墮乯丄旛慜偺恖丄嫕曐係擭乮1719乯庘丄俈侾嵨
丂丂椙滀堾丂抭尮丂擔崉丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄擔掚偺帒丄峕屗偺恖丄墑嫕尦擭乮1744乯庘丄俈係嵨
丂丂忔擛堾丂椆尮丂擔惉丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄峕屗偺恖丄墑嫕係擭乮1747乯庘丄俈俀嵨
丂丂忢氭堾丂椆弐丂擔尠丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄峕屗偺恖丄姲曐尦擭乮1741乯庘丄俇俉嵨
丂丂杮抭堾丂壜慞丂擔椾丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄擔掚偺帒丄峕屗偺恖丄姲曐俀擭乮1742乯庘丄俈俁嵨
丂丂抭慞堾丂姤愖丂擔掑丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄埨寍偺恖丄嫕曐侾俀擭乮1727乯庘丄俉係嵨
丂丂尠棟堾丂惔懚丂擔梡丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄晲廈偺恖丄惓摽俁擭乮1713乯庘丄俆俀嵨
丂丂廆庴堾丂廆庴丂擔恀丗尦榎係乮1691乯棳嵾丄拞擵嫿拞擵塝偵擖悈丄嫕曐俁擭乮1718乯庘丄俈侾嵨
---
乽惞丂乗幨恀偱偮偯傞擔楡廆晄庴晄巤攈掞峈偺楌巎乗乿廔---
2019/09/19捛壛丗
仜乽晄庴晄巤攈弣嫵偺楌巎乿憡梩怢丄戝錟弌斉丄徍榓俆侾擭乮1976乯丂傛傝
尦榎係擭乮1691乯斶揷攈嬛惂偵傛偭偰曔敍偝傟丄埳摛幍搰偵棳偝傟偨憁懎偼俈係恖偵媦傇丅
偦偺屻丄枊枛崰傑偱偵棳偝傟偨憁懎偼侾侽俇恖偵払偡傞丅
乮乽晄庴晄巤攈朄擄巎椏廤乿壀嶳導抧曽巎帒椏憄彂俈丄挿岝摽榓丄1969丂
丂乽朄壺偺弣嫵幰偨偪乿媨嶈塸廋
丂乽晄庴晄巤偺朄擄暲偵棳憁惗妶偵偮偄偰乿塭嶳嬆梇亙乽擔楡廆晄庴晄巤攈偺尋媶乿強廂亜側偳偺挊嶌偑偁傞丅乯
崱丄忋婰側偳偺挊嶌偵傛偭偰丄婰榐揱彸偵柧傜偐側傞弣嫵棳孻幰傪嫇偘偰偍偔丅
丂仸杮彂偱偼師偺恖悢偺晄庴晄巤娭學偺憁懎偺柤慜偑婰嵹偝傟傞丅
丂丂埳摛戝搰丗俀俀柤
丂丂恄捗搰丂丗俈柤
丂丂嶰戭搰丂丗俁俆柤
丂嶰戭搰偱偼杮柇堾擔庫偑偲偔偵桳柤偱偁傞丅
丂丂丂丂仺杮柇堾擔庫棯楌乮旛慜栴尨懞拞偵偁傝乯
擔庫偺晝偼壀嶳斔抮揷巵偺帢堛偺堜忋棫埩偱係侽侽愇偳傝偱偁偭偨丅棫埩偼屻楽恖偟偰棽埨偲曄柤偟丄嬑峜偺巙巑偲岎傢傝丄斀枊晎偵孹偄偰偄偭偨丅
乮恊斔偱偁傞悈屗斔偑枊晎偺嬛惂傪斊偟偰晄庴憁擔梥傪彽惪偟偰偄偨偙偲傕巚偄婲偙偝偣傞丅乯
擔庫偺廧嫃愓偲偄傢傟偰偄傞強偼埳儢扟懞尨偺峀悾弶屲榊巵戭偺晘抧偺嵍曽偵椬愙偡傞嫹彫偺搚抧偱偁傞偑丄廧戭偼從幐偟晘抧偼奟曵傟偺偨傔曄杄偟偰偄傞偲偄偆丅
擔庫偼暥惌尦擭乮1818乯嵼搰俀俇擭俆俇嵨偱惗奤傪廔偊傞丅曟偼忢彑埩偺曟強偵偁傞丅
忢彑埩偼擔廦栧棳擔宱偺棳傟傪媯傓惓摑堾擔彯傗峴怣擔恑偺擛偒撪徹戣栚島偺娭學偑偁傞偲傒傜傟傞埩偱偁傞丅偙偙偺曟強偵偼慜弎偺擔庫偺傎偐擔崢乮梫乯丒擔惔丒擔嬇丒擔椛偺曟傕暲傫偱寶偮丅
側偍埳儢扟偵偼擔庫偑壎巘丒慶晝曣丒晝曣偺堊偵寶偰偨曬壎搩傕巆傞丅崅偝俀広俇悺俀暘丒暆俋悺偲偄偆傕偺偱偁傞偑丄暥壔侾係擭乮1817乯偺擭婭偲擔庫偺帺昅壴墴偑偁傞丅
埳儢扟懞偺傎偐埳摛懞偵偼俆婎偺嫙梴搩偑偁傞丅
堦偵偼宱峴堾擔崢乮梫乯寶棫偺擔楡係俆侽擭墦婖嫙梴乮嫕曐侾俇擭擭婭乯
擇偵偼峴怣擔恑寶棫偺惓摑堾擔彯偺嫙梴搩
嶰偵偼摨偠偔峴怣擔恑寶棫偺椉恊偺嫙梴搩
巐偵偼擔恑帺恎偺媡廋搩
屲偵偼杮惓堾擔惥寶棫偺愭巘廫榋恖暪婰偺嫙梴搩偱偁傞丅
丂埳摛懞偵偼晄庴晄巤憁偺曟偑俉婎偁傞丅枽傊偺彫宎傪壓偭偰偄偔偲侾杮偺彫愳偵弌夛偆丅慮棦愳偱偁傞偑丄偙偺晅嬤偵偁傞丅撪徹戣栚島偺擔彯偺曟傪壛偊傞偲俋婎偵側傞丅
2023/09/14捛壛丗
戝愹堾擔恵丗擔恵傕嶰戭搰棳憁偺堦恖偱偁傞丅
仜乽晄庴晄巤弣嫵偺楌巎乿偱偼
嶰戭搰晄庴攝棳憁
丂戝愹堾擔恵乮擔弴乯丂尦榎俋擭侾侾寧俉擔乮尦榎侾侾擭侾侾寧侾侽擔乯庘丄尦榎朄擄乮尦榎係擭俈寧俆擔攝棳乯壓憤杒拞懞柇暉帥弌帥憁丄懡屆偺惗丄扟偺恖丅
偲偁傞丅丂仺壓憤杒拞懞柇暉帥偼壓憤拞懞亜杒拞拞偺杒拞柇暉帥愓偲偟偰宖嵹丅
丂丂怴搰丂丗俇柤
丂丂屼憼搰丗侾柤
丂滀抭堾擔墢偱偁傞偑丄俀俉嵨傑偱旛慜捗崅孲壓揷偺戝嫵埩偵偄偨偑丄曮楋俁擭乮1753乯媣墦堾擔慠偲偲傕偵峕屗偵弌慽娦嬇丄偨偩偪偵曔敍偝傟擖楽丅
梻曮楋係擭擔慠偼俁俋嵨偱楽巰丄摨擭擔墢偼廐慏偱嶰戭搰偵憲傜傟偨偑丄摉帪偺姷廗偵廬偭偰偦偺搑拞丄嶰戭搰偱壓慏丄師偺弔曋偱屼憼搰偵堏憲偝傟傞丅偦偺帪擔墢偼俁侽嵨偱偁偭偨丅擔墢偑屼憼搰偵偰庘偟偨偺偼姲惌俉擭乮1796乯俈侾嵨偺崅楊偱偁偭偨丅
擔墢偵尷傜偢丄晄庴晄巤憁偺懡偔偼俈侽嵨慜屻偺崅楊傪曐偮丅偍偦傜偔偼擏怘傪攑偡傞嵷怘庡媊偑寬峃朄偵揔偭偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅
偦偟偰丄懡偔偺憁椀偼撪抧偐傜怣幰偨偪偵傛偭偰懡偔偺暔帒偑偁偮傑傝丄惗妶偼寛偟偰斶嶴側傕偺偱偼側偐偭偨傛偆偱偁傞丅
側偵傛傝丄撪抧偺撪怣傪巜摫偡傞巊柦姶丄偦偟偰偁傜備傞崏栤傗壵崜側崠拞傪愗傝敳偗偨嫮恱側擏懱偲怣嬄偺偨傔偵偼擛壗側傞恏嬯傕挼偹彍偗傞惛恄傪帩偭偰偄偨屘偱偁傠偆偲偄偆偟偐側偄丅
丂敧忎搰丗俁俇柤乮杮峴堾擔鎩偲棫殺堾擔梫偼曟旇偺傒偁傝丄棳憁偱偼側偄偨傔彍偔乯
嶰戭搰棳憁偺拞摴堾擔慞偼嶰戭搰嵼搰係俉擭偵偟偰俈侽嵨偱帵庘偡傞丅偙傟偼嵟傕嵼搰偺挿偄傕偺偱偁傞丅攝棳偺帪偼嬐偐俀俀嵨偺惵擭偱偁偭偨偙偲偵側傞丅
丂丂埲忋丂崌寁乮墑傋乯侾侽俈恖偺憁懎偑埳摛彅搰偵棳嵾偲側傝丄偦偺柤慜偑敾柧偟偰偄傞丅
|