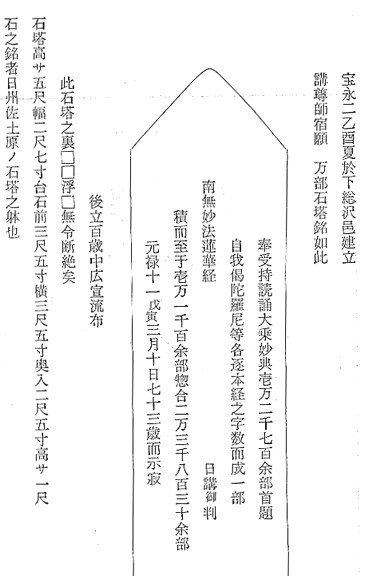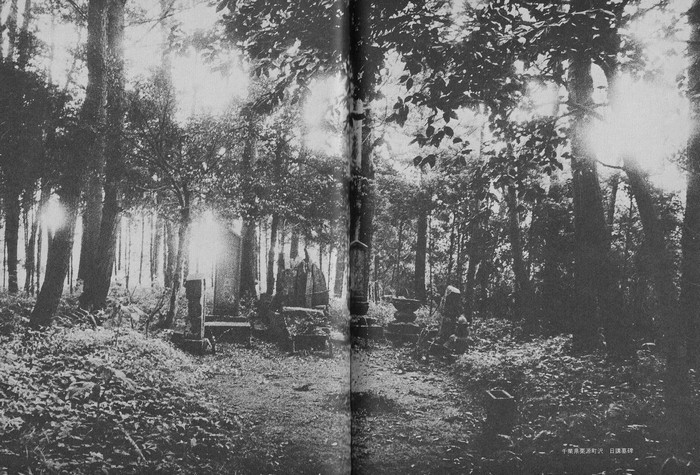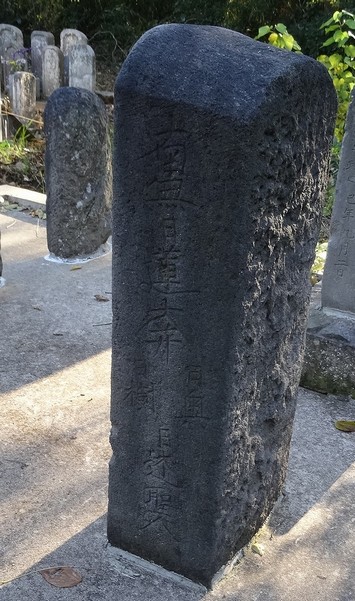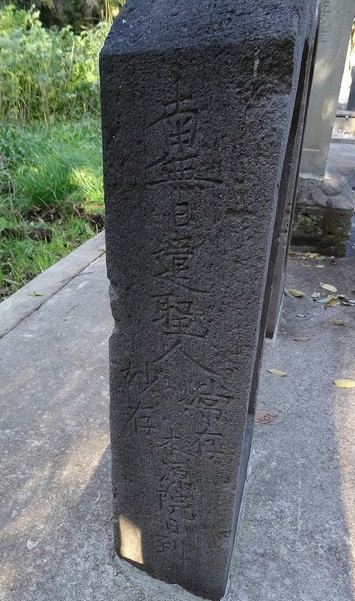���u�����Y�@Vol.189�@�����ꗑ���@����ɖ|�M���ꂽ�����v�i�L�Ƃ�@�ߘa4�N6�����j�@���
�@�����ꗑ���i���D���j�ƌĂԕ������A��n��̓��̉w������Ɠ����̏��������ɂ���B
�@�����ꗑ���́A���u���������y���Œ����Ԃɂ���ԑ傪����ȓnjo�𐬂��Ƃ������т𗯂߂邽�߂ɓ��u�̎���A��q�����Ă����̂ł���B���u�͋��s�̏o�g�A�э��h�тƒ����h�тŊw�сA��C�h�тł͍u�t���߂�B
�������A��C�h�тōu�t�����Ă���Ƃ��ɁA�����Ă����@�h�E�s��s�{�h�����{�ɋւ����A���u�͋��`��ς��Ȃ��������ߓ������֒Ǖ�����A���̒n�ŖS���Ȃ�B��q�͕�i�Q�N�i1705�j�ɂ��̗�������������B
�@���̌�A�����͋ւ���ꂽ�@�h�̂��̂ł��������߉ŏĂ���A�����Ė��߂���B
���݁A�����͋ߕӂ̐M�k�ɂ��@��N������A���ꂽ�ނ������̈͂��ő��˂��Ă�B
������s���U�w�K�ۂ̒k
�@�u�I���������������ژ^�v�I��������ψ���A��������A�����T�N�@�Ƃ�������������B��������
�{���ɂ́u��t�����E��錧��44�����c�����쎭���`���v�J�ʑO�́u��Ւn�}�v������A���̒n�}���画�f����ƁA�u�j�Ձ@�����ꗑ���v�̈ʒu�͌����S�S�����J�ʑO�Ɠ����ʒu�ɂ���Ǝv����̂ŁA�����S�S�����H���ňʒu�͓�������Ă��Ȃ������f�����B
�Ȃ��A�����Ɂu�O�А_�Ёv������A�����ɂ��u�j�Ձ@�����ꗑ���v�̕\��������B���̂��Ƃ́A�����ɂ��Γ����������\��������A����������������̐Δ肪����A���ݒn�ɑJ���ꂽ�\���͂���Ǝv����B�������E���m�F�Ő^�U�͕s����
�@�����u��l�ɂ��ẮA�����@���u�A�s��s�{�h�̕���Ɠ����@�Ȃǂ��Q�ƁB
�����u��l�����Γ��֘A�ʐ^
�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��P
�@�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��P�F���}�g��}�F�u���@�|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�@����A��
���a�T�Q�N���s�{�Ɍf�ڂ̎ʐ^�A���݂̌����⓹�̉w�̌����Ƃ͊u�₵���R�ђ��ɂ���A�B��Γ��ɑ��������Ȃ܂��ł���B
��L�́u����s���U�w�K�ۂ̒k�v�̂悤�ɁA�����J�ʂňʒu�����������Ƃ͂Ȃ��Ǝv����B
�������č�����A�����A�����A���u�A���E���E�q�A�����̐Γ������сA���̑��̕s�������u����Ă���̂́A���݂̒ʂ�ł���B
�@2023/12/27�lj��G
�@�������u���@�|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v����]��
�@�@�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��P-�P
���u�Y���ꂽ�}���ҁv�@����A��
�@�����S�S���J�ʑO���u�����Γ��Q
���a�S�V�N���s�{�ɋL�ڂ̎ʐ^�A��Ɠ��l�ɁA�R�ђ��ɂ���B
���݁i2023�N�j�ł͌��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u���u�@�䔻�i�����̂悤�Ɍ�����j�v�̒f�Ђ��ʂ�B
�@���u�������i�j�������j�F�^Web�T�C�g�@����A��
���݂͐j���Ɉ˂錋���ł͂Ȃ��A����̂Ȃ��l�p�̋������P�[�W�Ɏ��[�����B
����ł́A�O���猩���镶���͉��Ɍf�ڂ̂悤��
�@�얳���@�@�،o
�@�ώ��������ݐ���P��揔���@
�@�@��������N��E�E
�@�@�@���ݎO�甪�S������
�@�@�@���\�����\�O�Ύ���
�ł��邪�A���݂͌����Ȃ��A�u���u/�������v�i�������́u�䔻�v���H�j��u�����v��u������/�������v�Ȃǂ̕�����������ΕЂ�������B
���A�u�ώ��������ݐ���P��揔���v�́u�ώ��������ݐ���P��揔���v�ƁA�u��������N��E�E�v�́u���\�\��N��Ёv�Ɠǂ߂�B
�@���y�����u�����F�^Web�T�C�g�@����A��
���y���ɂ�����u�̗����ł��邪�A�ł��ӂ��ꂽ�����i�Γ��j�͂��̂悤�Ȍ`�ł������̂ł��낤���B
�@�i2023/12/20�lj��F�j
�@�����ł͖����Ǝv����B
��f�́u�吹�l��a���J���o�v�ł͓��u�̖����Γ���
�@�u�Γ��n���s���Z�@���O�����Ɖ@���l�����A���j���e�������A�؎R�m���Γ��`�������Y�A���j��ΔV铎��s�V�e���������t�^���́A���`�U�Y�A�M�҈��Z�@���O�V���͎ʃX�A���s�Ӄ���Θԃj�e�Δ胒�����������V�L�̃j�A���B��Γ�����m�ԃj�e�䌚���V�L�i���v
�@�@���؎R�i�z�R�j�̗��͓��̌`�炸�A��̐ɒ��ڕ�����̂ɁA���̌`�ɑU�킸�ɓ��O�͍���ɕ킢�A�܂����s������ł͖�̂܂ܐΔ�邱�Ƃ������́A�����̐Γ�����̂܂܂ɂČ�������B��
�Ƃ����A�]����
�����̐Γ����A��������悤�Ȗ��D���i�����j�̂悤�Ȍ`�ł͖����A��i���R�j�ɍ��Γ��ł������悤�ł���B
�ܘ_�A�̐Γ�����i���R�j�ł������͂��ŁA���ݔj�ӂ���Ďc��Γ��c�Ђ����R�ł��������Ƃ������Ă���Ǝv����B
2023/12/23�lj��F
���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
��i�Q�N�i1704�j���O�͓��u��l�̂��߂ɍ��y���̐i�I�R��͐M�҂̑�����ʼn^�ԁj�Ŗ������A�̓�����������B
2023/10/20�B�e�F
���u�����Γ��Ȃǐ�t���{���E���
�����u�����Γ��̒f�Ђɂ͎��̂悤�ɍ������B
�@�얳���@�@�،o
�@�@�@�ώ��������ݐ���P��揔���@�i��揔�͑��َ̈��́j
�@�@�@��������N��E�E�i�����\�\��N��ЂƐ��肳���B�j
�@�@�@�@�@���ݎO�甪�S������
�@�@�@�@�@���\�����\�O�Ύ���
�@�@�@�@�@�@�i������ɂ��Ă��A�����͏�L�Ɍf�ڂ�����B�j
�@���u�������P�@�@�@�@�@���u�������Q�@�@�@�@�@���u�������R�@�@�@�@�@���u�������S�@�@�@�@�@���u�������T
�������E�����E���q���{���F
�@�����E�����E���q���{���P�@�@�@�@�@�����E�����E���q���{���Q
�@���ʁu�얳���@�@�،o�v�A�u���i���h���܌��\��� �������l�v�u���i���M�ߎO���\��
�������l�v�u�����h�ы㌎�������@���q���l�v�ƍ����B
�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�@�@�ʁF180�~44����
�����Z�@���O�F���ۂP�V�N�U���Q�R����A���u���d�A�V�V�B
�@���O���l���P�@�@�@�@�@���O���l���Q
�����É@�����G
�@�������l���P�@�@�@�@�@�������l���Q
�@���ʁu������l���C��������v�A���ʁu��J��Ώ������l�ݕ��v�ƍ����B
�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�@�����l�������F�@�ʁF177�~43�����A�������l
�����N�@�����F���\�P�U�N�P���V����A��^�Q�R���A��t�k�тV���B
�@�������l���P�@�@�@�@�@�������l���Q�@�@�@�@�@�������l���R
�@���ʁF
�@�@�@�@�@�i��ǂł����j
�@�@�@�@�얳���@�@�،o�@�����@�i�ԉ��H�j�@�@�������͓����Ɠǂ߂Ȃ��͂Ȃ��B��
�@�@�@�@�@���\�\�Zᡖ��ꌎ�����H���E�E�@�@�@�ƍ����B
�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�@��莵�畔���A111�~37�����A�������l
���Γ��c���Ȃ�
�@�s����肻�̂P�@�@�@�@�@�s����肻�̂Q�@�@�@�@�@�s����肻�̂R�@�@�@�@�@�s����肻�̂S�E�T
���V�̂�������
���u���@�|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�@����]��
�@�������V�̂��������F�R�[���l�ڂɂ��Ȃ��Ƃ���ɕs��s�{�m�̕���W�߂Ă���B
���ꏊ�Ȃǂ̏�Ȃ��A�����B
�Ȃ��A������͒����ł��邪�A��Ɉ��i����j���������Ƃ͂��܂莑���ɂ͏���Ă��Ȃ����A�u���|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�ɂ͑���Ƃ����ʐ^���f�ڂ���Ă���̂ŁA�]�ڂ���B�i�ꏊ�Ȃǂ͑S���s���j
�@��������E���
�������V�̕�⸈�
���u���Y�@Vol-083�@��̕�⸈@�s���ő勉�̐Α����@�i�L�Ƃ�@����25�N4��15���j�v�@���
�i�v��j
�@���̉w������Ƃ̓�A���H�������������ɑ�n��̋�����n������A���̓��[�̈�p�ɕ�⸈����B
�@�����͖�3.4m�A����s���Ɏc��Α����̒��ł��ő勉�̋K�͂��ւ�B
�@��̕�⸈́A�������犰���V�N�i1667�j�ɑ��������B
��b���̐�3�ʂɁu�����ݕ��E�V���^�����^���A���^�Ԍ��V�E�����������E�l����{�����v�Ƃ��ꂼ�ꕶ�����ށB
2023/12/23�lj��F
���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@��d�Ɂu���ꖜ�����A���������Ԍ����v
�@��������
�@�����V�̕�⸈��FGoogkeMap�@����]��
��������^��
���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA�������s��A���a�T�Q�N�@���
�@�����̑y�őO��A�����ł͋ʑ������A��C���u�A����i��C�j���q�𒆐S�Ƃ��đ��Î��ӂɋ��͂ȋ����������A�V���^�i���N�@�����j�����̈�̗L�͂ȋN�_�ł������B
�@�V�^�̒n�Ɓi�}�}�j�͐��A�@�@�@�ؖV�@����V�@����V�@�{�S�V�@�w��V
�@�@�������́@���@�r�k����@���@���ё��������@�������@��a�c���@��ː��@���̍\���ł��邱�Ƃ͑O�ɏq�ׂ��ʂ�ł���B
�@�����̖@��ŕs��s�{�h�͋��ƂȂ邪�A���̊Ԑ^�͏}���҂���l���o���Ȃ������B���̂��Ƃ͎�h�ɕs��s�{�h��n�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���������Ɨ��ĂĂ����̂ł���B�{�R����͎�h�ɐڎ����ꂽ���A�����^�͊O�������́u���M���v�Ƃ��đ������Ă����̂ł���B
���N�@�����i�P�U���j�A���N�@�����i�Q�P���j�A�����@�����i�Q�Q���j�A�����@���O�i�Q�R���j�E�E�E�u�����@���j�i�P�P���j�q���u�̎��Џ���v�������̙|�a�C�ɂđ��`�Ȃ��쉻�v�Ɖߋ����ɂ���B
���������@���j�F�u�j�v�͎�+�t�̊����ŕ\�L����邪�u�j�v�ƕ\�L����B��
���������@���O�i�Q�R���j�F�{���ł́u�����v�Ƃ��邪�A�u��Ӂv�ł́u���O�v�Ƃ���̂ŁA����ɏ]���B��
�@�t�߂̓��M���͎��̂悤�ɔ������Ă���B
�@���Ď��@�������{���@����告���@�V�������@�V�m�@�V�^�����@�V�^�@���V���h���@�і������@�і������@�k���������@�����@���@�����鎛�@���薭�����@���˖@��@�D�z�嗧���@�D�z�������@���䖭�����@�ўl�������@���Ö������@�╔�������@�╔��掛�@�ʑ��@�؎��@���ю�����
�@���N�@�����͌��\�W�N�A���u�̗��Y�n���y���ɓn�C���A���̌㐼�ɐ^�B���Ƃ��āu������v��A�����Ɠ��s�����ǑI�i����@�j����͊Ћł���u�ɔ����ꂻ�̐����ɉ����A���ɋA��u�O�����v���J�݂���B�u�O�����v�͍u��h�ő�̈��Ƃ��ēV�ۂ̖@��܂Ŗ@�����p�����͎̂��m�̂��Ƃł���B
�@�^�ɂ͋����s��s�{����������͑����B�ꎞ���ɂ͊֓����̎x�z��@�����Z�@���O�i���u���d�j����˗�����Ă���^���̑����x������M�����O�����ƌ���ł����B
�@������ɂ��Ă͌��\�@��̌ォ�犰���̖@��܂ł̊Ԃ̖@���́A�����m�����Œ肵�����̂ł͖����������A�����m����B
���N�@�����i�V�^�P�U���j�A�{�A�@����A���o�@�����A���ω@�����A�����@���F�A����@�����A�����@�����A�q���@���c�A�����@���c�A�^���@�����A���P�@���q�A�p�P�@���ʁA���|���O���o���{�]�@��狁A��ω@���h�A�����@�����A�אÉ@����A�`�E�@�����A����������A����@�����A�u�N�@�����A����@���R�i�V�^�P�T���j�A���N�@�����i�V�^�Q�P���j�A�����@�����i�V�^�Q�Q���j�A�����@���O�i�V�^�Q�R���j
�@�����X�N�s��s�{�h�����A�����Q�P�N�����̒�q�����ٖ����V���̓��M�Ƌ��ɋ������Ă������A�^�R�R�����F���}�}�E�����������ƒU���i���U�k�E�d���j���s�a�ɂȂ�A�����͒U���ƍ��iू�������܂łɂȂ�B�U���̖w�ǂ͐^�𗣔����A�s��s�{�h�ɓ����鎖�ԂƂȂ�A���F���}�}�E�����������͂��ɑގ����邱�ƂɂȂ�B���ǂ͐^�U���̓��S�Q�����A�U�����݂̂ł������B�v�͌�����������������s��s�{�h�̎�h���@�ւ̐킢�ł������Ƃ������Ƃł���B
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
�@��R�ƍ����A����{�y�����B���t�@���B
�V���N���̑n���A�V���N���Ӑ^�̊J�n�A�J����@���ӁA�J��h�z���b���B
�i�����N����X�����ӂɂ���y�@�����@�B
�������N�̕s��s�{�����A���a�̘J�_���c�E�_�n���v�Ȃǂ̍ЉЂ��o�āA���a�Q�T�N�ȍ~�{���E�ɗ�����C�B
�@���������N�̕s��s�{�����Ƃ͏�q�́u�����X�N���M�h�k�i�U���j�̗��d�i���U�j�v�������Ɛ���B
�^���F
�J��@�@�����@���Ӂ@�����T�E�S�E�X�i1473�j53��
�@�Q���@�^��@���h�@�����R�E�V�E�S�i1494�j
�@�i�ȗ��j
�@�V���@�P�ˉ@�����@���a�R�E�P�E�R�i1617�j
�@�W���@�o���@�����@�c���X�E�X�E�P�U�i1604�j
�@�X���@�@���@��硁@���i�T�E�P�P�E�V�i1628�j
�P�O���@��z�@����@���i�P�S�E�P�O�i1637�j
�P�P���@�����@���j�@�����T�E�Q�E�S�i1665�j�����s��m��
�@����q�́u�[�����@��j�v�ł́u�����@���j�i�P�P���j�v�Ƃ���B
�@�ߋ����ɂ́u�����@���j�i�P�P���j�q���u�̎��Џ���v�������̙|�a�C�ɂđ��`�Ȃ��쉻�v�Ƃ���Ƃ����B
�@���u�[�����@��j�v�F�����@���j�A�����P�P�E�V�E�S�A�V�^�W���A�ўl�������R���B
�P�Q���@���@��ꟁ@�ݎ����E�P�Q�E�P�O�i1658�j
�P�R���@�r���@�����@���i���E�W�E�X�i1624�j
�P�S���@�b���@���q�@�勝���E�P�P�E�X�i1684�j
�P�T���@����@���R�@�勝�R�E�W�E�Q�R�i1686�j�����s��m�A�������
�P�U���@���N�@�����@���\�P�U�E�P�E�V�i1703�j�����s��m�A�������
�@����t�k�тV���B���\���N�������y���̓��u��K�ˁA�u��o���Չ����m��@�����v��B������J�c�B
�@�������͏�f�́u���u�����Γ��Ȃǐ�t���{���E���v���ɂ���B
�P�V���@���@���߁@�勝���E�R�E�S�i1684�j
�P�W���@��݉@�����@��i�Q�E�P�E�P�V�i1705�j
�P�X���@���@���Q�@���ۂT�E�R�E�P�i1684�j
�Q�X���@�@��@�����@�����S�E�P�O�E�Q�i1739�j
�Q�P���@���N�@�����i�V�^�Q�P���j�@���ۂP�R�E�R�E�P�O�i1728�j�����s��m�A�������
�Q�Q���@�����@�����i�V�^�Q�Q���j�@���ۂP�R�E�X�E�P�O�i1728�j�����s��m�A�������
�Q�R���@�����@���O�i�V�^�Q�R���j�@���ۂQ�O�E�P�O�E�Q�P�i1735�j�����s��m�A����������������́u���N�v������
�Q�S���@�����@�����@���a�Q�E�R�E�Q�Q�i1765�j
�Q�T���@�̖��@��迨�@�V���S�E�T�F�P�T�i1784�j
�Q�U���@�̐M�@�����@�V�����E�V�F�P�S�i1781�j
�@�i�ȗ��j
�R�R���@�^���@�����@�����R�W�E�P�E�P�@�����u�����X�N���M�h�k�i�U���j�̗��d�i���U�j�v�����̓����ҁ�
���V�^����
�@���@�R�~�����i�}�Ԏs��c�j
�@�����R���i����s�����C�j
�@����R���i���c�s��a�c���j
���u�����Y�@Vol-025�@��̐^�@���̎���{�]�����̕�i�L�Ƃ�@����20�N4��15���f�ځj�v�@���
�@�i�v��j
�{���F
�@�{���́A��`���A���������i�������j�A�Ԍ��O�ԁA���s�l�ԂŁA���ʂɈ�Ԃ̌��q��t���B����5�N�i1740�j�Ɛ���i�������̖n���j�B
�@�]�ˏ����A�������������̂S����̂��A��759�Η]�����̓��Ɋ܂܂�B
�x�z�F
�@�́A���̌���{�]�����m�s�n�ƂȂ�A����Ɋ���7�N�i1667�j�ɂ͓����]�����̑��m�s�n�ƂȂ����Ɛ���B�����ɂ͍]����595�Η]�A�]����164�A�㊯�x�z���i���{�́j140�Η]�A�p�����䏜�n9�Η]�A�v909�Η]�̑��ł������B
���{�]���e�͕��F
�@��n�ɂ́A�̎�A���{�]���e�́i9��ځj�̕悪���c��B�����͖�150�����A�Ɛΐ��ʂɂ́u�Г��@�a���m�X���勏�m�v�u�����N�N�����\�������v�̕�����2�̉Ɩ䂪���܂��B
�@�]�����́A��595�Η]�̑��A�╔���A�ԓc���A�������i�������s�j�A���ߊԑ��i���_�ސ쌧��a�s�j�ɍ��킹��1700�̒m�s�n�������{�ŁA9��ڐe�͂́A���[�˂�ۏ��[�ˁA�ڕt�Ȃǂ̖�E���߂�B
�@�]�����̑��n�͎s�J�P�c���i���V�h��j�ł���A�Ȃ��e�͂̕悾���^�ɂ���̂��͕s���B��̑��ʂɂ́A�����҂Ǝv����11�l�̖��O�����܂�邪�A�e�͂̎���A�����̐l�X�����̎���Â�Ō��������̂����m��Ȃ��B
2023/10/20�B�e�F
�@��^�����@�@�@�@�@������ڐ��F�����i22���E���ۂP�R�N��E�s��m�j��Ƃ���̂ŁA�]�˒����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ړ��ݕ����F228�~48����
�@��^�{���P�@�@�@�@�@��^�{���Q�F��f�u�����Y�@Vol-025�@��̐^�@���{�]�����̕�v�ɉ������B
�@��^�ɗ�
��^���F�P�R��̕�肪���ԁA���ǂł��Ȃ������łȂ��Ǝv����Γ������邪�A�P�S���b���@���q�A�P�T������@���R���s��m�E��������A�@��R�Q�V��/�����R�P�Q�R���e���@���T�A�Q�W�����`�@�����A�Q�X���E�S�@�����A�R�P�������@�����A���ԉ@���������ɂȂ������m�F�ł���A
�@��^�����P�@�@�@�@�@��^�����Q
�@�P�S���b���@���q����F���ʁu�b���@���q���l�v�@�@�@�@�@�P�T������@���R����F���ʁu�c�����\�ܐ�����@���R�v
�@���{�]���e�͕���F��f�́u�����Y�@Vol-025�@��̐^�@���̎���{�]�����̕�v�ɉ������B
�@��^�M�k�Õ��F�����̕��́u���i�\�l���N�l������v�̔N�I�������B
�@�g���R�c�Q�L�O���@�@�@�@�@���@�U�O�O������ړ��@�@�@�@�@���c���@�T�O�O������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���@���F�F170�~33�����A���i��N�����A�ܕS�N�����B
�@��^��ڐΓ��F���ʁu����ژZ�ݕ����������v�@�@�@�@�@�ɗ��V�z�L�O��ڔ��F�����X�N���c��
�lj����
GoogleMap�����Ă���ƁA�����ł���̂ŁA�m�����ǂ����͕s���ł��邪�A�����͂�����J������Ǝv����B
�����炭�{�������߂ɔ[�����i���ځj������A���̉��ɗ���肻�̂Q������Ǝv����B
�ʐ^�͉����GoogleMap����]�ځB
�@����肻�̂Q�E�P
�@����肻�̂Q�E�Q�F�����̑�^���̕\�ʁu�얳���@�@�،o�@���@���߁v�Ƃ���悤�Ɍ�����B���@���߂Ƃ���Ȃ�Ηɂ��P�V���ŁA�勝���E�R�E�S�i1684�j��ł���B���̑��̕��̖��͑S��������Ȃ��B
�@
�������s��s�{�h�
��ɕs��s�{�h�������B�����ɋ���R���肪�����A���̑�ӂ͎��̂Ƃ���ł���B
��������N
�@�̑�n��͑S�˂����@�@�s��s�{�h�ł��������A�]�˖��{�̏@���e�����A����h�Ƃ̑唼���]�@�����钆�A���݂̒h�Ƃ̐�c�͓��M�Ƃ��Ė����X�N�̌����܂ŐM����蔲���B
�@�����X�N�S���s��s�{�h������������A���n�ɋ��������ĐM�S���i�̓���Ƃ���B
�����������d�˓��ꂪ�V���������ׁA�h�ƂQ�O�˂̑��ӂ��Ȃ��ĐV�z�����ӁA�����P�Q�N����������c����B
�@�������]�ˊ��̋�����������A�M���̎��R����т̌����̈������̌����ł������Ǝv����B
2023/10/20�B�e�F
�@������P�@�@�@�@�@������Q�@�@�@�@�@������\�D
�Ȃ��A������ɑ�ٍ��V�Ƒ�ڔ肪����̂ŁA�t�L����B
�@������ٍ��V�P�@�@�@�@�@������ٍ��V�Q
�@��ٍ��V���ڐP�@�@�@�@�@��ٍ��V��ƖڐQ�F���ʉ摜���B�e���Ă��Ȃ������̂ŁAGoogleMap���]�ځB
2023/12/23�lj��F
���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
��������䶗�
�@���i�V�N�R���@��̍H�����F����
�@�@(���ʐ^�̌f�ڂ���B�j
�@
�������╔�������i������[��l�j
����s�╔1306�Ɍ�������B
���u���n�ē��v�ł͎��̂悤�ɉ]���B�i��Ӂj
�@�R�����u���������R�v�A�������u�����������v�Ə̂���B�u�����R�v�u�������v�ƒʏ̂���B
�����́A�哯�Q�N�i807�j�╔��n�ɑn�����ꂽ�u���@�E��~�@�v�Ɠ`����B
�剞���N�i1222�j��t���ꑰ�╔�ܘY���╔��z��ɂ�����A���ݒn�Ɉڐ݂��A���̂��u��t�R�v�u�ߑ��������v�Ƃ��đn������B
�����Q�N�i1330�j��~��苗����B�i����E�{�y����R���j�ɂ���ē��@�@�ɉ��@����A���̂����݂̂��̂ƂȂ�B
����`��A��t�Ƃ����i����B
��O��������A���R�����`���Ƃ̗L���̋b�������ĉ������D�̍ہA��\�̎��n���B
�����́u�����R�V�V�A�����V������i���A�h�Ɗ╔��~�ɋy�ԁv�Ƃ����B
���\���������G��A����ƌ�������\��Όܓl�̎����B
�����T�N�i1665�j�ȍ~�A�s��s�{�`���A��\�]�N�Ԗ��Z�ƂȂ�A��������B
�܂��A���̐�����������B�i��Ӂj
�u�I�����厚�╔������ɍ݂����S�T�O�ؓ��@�@�ɂ����ޔ@����{���Ƃ��B
���B�ɞH����䌳�N�V���J��Đ�t�R���Ď����i�������@���肵���A������N�O���V���Č������̏@�ɉ��ߑm���`�J�R����B
���`�͖{�y�����B�̒�q�Ȃ�A���ߊ��q���{���ɍ݂�V�Ɏt�����タ�{�����J���B
��t��ਂ߂Ɏ��n�������ē����Ȃ���̔V�𒆋��������`�������n����B
�̎��͌ËL�Û����ɂ߂đ����肵���A��i������Ȃ����U�����V�����Ď��ɁA�U���Ђɜ�肵���ȂĔV�����Ђ��ƓV�������������n��̂����Ƃ��������̂�v���c����N�\�ꌎ����ƌ��X�Ɏ��n�\��Όܓl�������B�v
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
�@����{�y�����A�����R�ƍ����A���t�@���B�J�R�͋�V�m���B�B
��䌳�N�i1222�j�u�J��h�z��t�ܘY���ߑ��������v��n���A��Ɍ����Q�N�i1330�j����R�����B�ɂ���ĉ��@�B
�Q�����`�̎��A����2750�A����37�V�A����7�����B�R�������̎��A�����`�������Q�O�������B
���̍��s��s�{�h�ƂȂ�A�ȍ~�P�O���N�Ԗ��Z�ƂȂ�B
��a�N���̑�ڔ�Q�����B
�@�����R�s���ł��邪�A���̋L�ڂ��Ȃ��B�]���Ċ�����[�̊m�F���̂�Ȃ��B
-----------
���Ɉ������P�O��������[��l�ɂ��Ă̎��т��f�ڂ���B
�@�A���A�P�O�����[�ɂ��ẮA��q�̌��n�����ɂ��u���@�@���@��Ӂv�ɂ�����Ȃ����A���́u���Ò��j�v�ɂ͌����B
�@�Ȃ��A������[�̕揊�͉��������ɂ��邪�A�����h�щ����@���[�Ƃ͑S���ʂ̑m���ł�����B
���u���Ò��j�i���a�U�O�N�j�v���n��j�ҁ����������쒆���@���^�_�ЁE���@����(�͂�����)���l(���[)�_���@���
�@�㐹�l�_�̈ʒu�ɂ��ẮA���̈ʒu�����ł��Ȃ����A�����悻�̌����͂��B
�@����
�@�������ÁE�����s����œ��{�����O���߂��A����������i������S�����E���݂̒��X�ǂ̓����j�̑O���E�܂��ē���i���n���j�̕��ʂɂP�T�O���قǓ쉺�A����ɉE�܂���_���ɉ����ĂP�O�O�������ɂ���A���͈͂�ʂ̔��ł���B�Ǘ�������Ԃ̕��͎���ꂪ�s���͂��Ă���A���킫�ɂ͑�����B
�@��͑b���܂߂č����͂P�D�Q���A���ʂɁA�u����[���l�@��_���@�c�����p��(1602)�����\�ܓ��v�A�E�ʂɂ́u�����R�{���u�|�����F(���{���S�X��)�@�쒆�������������j���v�A���ʂɂ́u�����\�\�l�h��(1701)������S�@�˔V�����\�ܓ��@�Ԍ��v�ƍ����B
�@�@������[���l���
�@�㐹�l���[�ɂ��Ă͎��������Ȃ��A���̑�����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�����ǕJ�́u�k�����j�v�̒��ŁA���[�ɂ��ĊȌ��Ɏ��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@�@�@���[
�m���[�A�ޕ��l�B�����j�[�N�ʃY�A�������j�����Čo���u�Y�B���ҁA�s�����X�B���A�������}�q�A�����j�ٓ��X�B��q�����X�A���L�H�N�A��A�t�������X�A�߁A�狁�X�B�B���A���݃����B���[�b�e���Y�B�\�o�j���K�X�A�Ӄj�t�A�����X�B�߁A�ƃe���ՁB�C�A�����V���T�q�B�����T��j蟣�l�������A���X�j�V�����X�A�߁A���P�o�V�����c�B��������}�K�B��`�E���c���I�E��j�E�G���{�j�����ꁄ�B
�@�@�@�Č͏�O刌`���i���͍��ɂ�����聁�c�A�܂�u��+�c�v�̊����ł���B�j
�@�@�@�����މA���f��
�@�@�@���j�Ɠ`�p
�@�@�@�m�t�i�p�o�S��
�������͐�����悷����A���[�͏�ɂ���憒�~(�����Ƃ�/�݂���E���킪��������)�������A�Ђ����ɓ���Ĕ����̈�Î��ɉB�ق���B�����ł͐����^�юĂ��E���A�ɂ��݂Ă͖@�ؑ�ڂ������Ė����̍K����O���鐶���ɖ�������B
�@���̒n�ɂ��邱�ƂR�N�A���܂��ܒ�q�̈�l���C�s�̂��ߓ�����K��A���[�����ĔߒQ���A���̂��߂ɂ����ɂ����łȂ̂��v�Ɩ₤���A���[�͏��ĕԓ������Ƃ����B
�@��ɁA���̒n����\�o(���\�o��J�������P�Q���Ƃ������疭�����ł��낤��)�Ɉڂ�A�ӔN�ɂȂ��Č̋��ɋA��B
�ՏI�̎��A��l�����Ɂu��M�͂Ɉ˂Ė����E����B�e���ɓw�͂���A�Ɋ��\���邱�ƂȂ���B���Ⴕ�M������͑����̎�������A��̝�(�͂�)�V�ɏ����A�����ȂČ�(������)�Ƃ���v�Ɛ����Ƃ����B
�@���[�͂��̐l�ƂȂ�͎��f�ŁA�����̐S�͖����ɋy�сA�ߕ��͌Â��Ȃ��Ă����ւ����A�C�����Ύ����Ő���Ċ����A���̓x���Ƃ��l���E���Ă͞�(������)�ō�����܂ɓ���Ă����A������ߕ��������܂������ɕ������Ƃ����B
����
�@���[�͍���S�I�����╔�i������s�╔)�ɐ��܂�A�╔�������̂P�O���ƂȂ��ču�����J���A��u����w�k�͊C�̂��Ƃ��ł������Ƃ����B
�������́A��ɍ��n�����[�P�S���E����k�эu��ł����������ʉ@�����P�W���ƂȂ邪�A���̌�Q�O�N�Ԗ��Z�ƂȂ�̗ʉ@����ɂ���čċ������B
���������\�S�N(1691)�̕s��s�{�e���̂��߁A���@������Ȃ��Ȃ����悤�ł���B�i���݂����@�@�ł��邩��A��h�ɓ]�����Ƃ����Ӗ��ł��낤�B�j
�@�������N�����猳�\�N���ɂ����Ă̕s��h�̒e���Ɛg���̑��E���{���͂Ƃ̖����ɂ��Ắu���O�@�̌n���v���u�����@���v�ȍ~�̓����@�Ȃǂ��Q�ƁB
�܂��A��Ɍf�ڂ́u������S�I���E�G�v�̍����Q�ƁB
2023/12/14�lj��F
���u�x���T�K��131�w�ԍ~���l�x�v�˒m����@���
�@������l�́u�ԍ~���l�v�ƌĂ��m������B����͓��[�ł���B
���[�͉������܂�ŁA����S�╔�̎��Ŋw�����J���w�������Ƃ����B�i�u���@�@�̐l�X�v�j
���[�͓V���V�N�i1579�j�����P�T���i���邢�͌c���V�N/1602�Ƃ��j���₷�B���[��l�̑����̎��A������ꗬ�̔�����ɏ������悤�Ɍ����A�ӂ�ɂ͖F�����[�����A���Ȃ�ԕق������~�肽�Ƃ����B
�Ȃ��A������l�́u�ԍ~���l�v�͔ђ˒k�сi�������j�J�c�̓�����l�ł���B
-----------
�����F�f�ГI�Ȏ�������W��
�����Q�N�i1330�j��~��苗����B�i����E�{�y����R���j�ɂ���ē��@�@�ɉ��@����A���̂����݂̂��̂ƂȂ�B
����`�i�J�R�H�j
��O������
�P�O��������[
���ю������P�W���@���̉@����F�╔�������Q�R���A�̗ʉ@�Ƃ������B
���ю������Q�T���@���É@�����F�╔��掛�P�U���A�╔�������Q�R���B�y���ۂP�X�N�S���T����A��t�k�тW���z
������
�@���������F�����R�������i����s���ѓc�j
2023/10/20�B�e�F
�@�╔�������R��O��ڐ��F���ʁu�����R�������v�@�@�@�@�@�������R��P�@�@�@�@�@�������R��Q
�@�������{���@�@�@�@�@�������ɗ��@�@�@�@�@����ϐ�����F
�@���������揊�P�@�@�@�@�@���������揊�Q�@�@�@�@�@���������揊�R�F�w�ǂ̕�̖����ǂݎ��Ȃ��B
�@�J�R���B��l����F�J�R/��V�m�E�嚢��苗����B��l
�@�@�Ȃ��u�I���������������ژ^�v�ł́A�u�����A158�~34�����v�Ƃ���B
�������╔��掛
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
���@�R�ƍ����A�����a�������B
�V�����N�i1532�j�n���A�J�R�J����O�Ó����P���V�����@����A�J��h�z�������Y�B���䂪�V�����N���n�������A�������Y����������A�^���@���]�@�A��F����������B
���F
�@�@�P���@���@�@����G���O�����P���V��
�@�@�Q���@���@���ԁ@�R���h�@�S���r�@�T����@���F�@�U����@����@�V�P�s�@���I�@�W���D�@�X���@���B
�@�P�O���@��暁@�@�@�P�P���@����@���G�@�@�@�@�P�Q���@�{�`�@����
�@�P�R���@�����m�s���b
�@�@�i����t�k�сE���ю��������ł�
�@�@�@�������Q�O���@�b��@�@���b�i�M��m�s�j�F���u�̓��L�u���ٓ��L�v�u�j���l�_�v�ɋL�ځB
�@�@�@�@�]�ːR�~�䎛���ŁA�~�䎛�j�p��A�k�тɗ����Ǝv����B�M��m�s�Ƃ��ĉ������ꂽ�̂ł��낤�B
�@�@�@�@�y���\�X�N�S���Q�V����A�╔��掛�P�R���A��t�k�ь�ɉ��@�z�Ƃ���B���u�[�����@��j�v��
�@�P�S���@铗ʉ@����
�@�P�T���@���P�@���^�F�y�P�P���P�O���A�╔��掛�P�T���i�u�[�����@��j�v�j�z
�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�@�@���P�@���^���l��F��i���\��������A173�~37�����A����n�i���ꏊ�s���j�Ƃ���B
�@�P�U���@����@����
�@�@�i����t�k�сE���ю��������ł�
�@�@�@�������Q�T���@���É@�����F�╔��掛�P�U���A�╔�������Q�R���B�y���ۂP�X�N�S���T����A��t�k�тW���z
�@�@�@�Ƃ���B���u�[�����@��j�v���@�������Ⴕ�Ă���B
�@�E�E�E�E
�@�Q�P���@���@���]�@�@�@�Q�Q���@�q���@���R�@�E�E�E
������
�������ѐ^�@���i���Ɍf�ځj�F�A�������@���̂��Ƃł��낤�B
�Ȃ��A��Ɍf�ڂ́u������S�I���E�G�v�̍����Q�ƁB
2023/10/20�B�e�F
�@�╔��掛�Q����ڐ��F�\�ʁu�얳���@�@�،o�@�@�E�v�A���ʁu�얳���@�@�،o���ݕ�/����ꌋ/�V�̒j���@���ۋ�b�C�J�i1742�j�O����\�����v�A�����ʁu�얳�@��俅������P���v�i�Ӗ�������Ȃ��j�A�E���ʖ������B
�@�@2023/12/23�lj��F���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�@�@��ړ��ݕ����F���ۑ��b�C�J�i1742�j�O����\�����A195�~44�����A����ꌋ�V��j���B
�@��掛�Q�����c�_���@�@�@�@�@��掛�Q�����W�F�܂�Ă��邪�A��������Ɓu��掛��������v��
�@��掛�R��O�ΊK
�@�R�卶��ڐ��F���ʁu�얳���@�@�،o�v���ʁu�얳���@���F�v�@�@�@�@�@�R��E��ڐ��F�����ʔ��ǂł����B
�@��掛�R��P�@�@�@�@�@��掛�R��Q�@�@�@�@�@��掛�R��R
�@��掛�{���P�@�@�@�@�@��掛�{���Q�@�@�@�@�@��掛���O�@�@�@�@�@��掛�����@�@�@�@�@��掛�ɗ�
�@��掛�����Q�F�������č�����S��ڂ������i�����Ɍf�ځj
�@��掛�����
�@��掛����萳���F�E���ʁu�c�R��\���ԁv�A�����ʂ͔��ǂł����B
�@�@�@���ʁu�c�R�J������l
�@�@�@�@�@�@�@���ԏ�l�@���r��l�@���h��l�@���F��l�@�����l
�@�@�@�@�@�@�@��暏�l�@���I��l�@�������^��l�@���t��l�@���B��l
�@�@�@�@�@�@�@���G��l�@������l�@���b��l�@�����l�@������l
�@�@�@�@�@�@�@���I��l�@������l�@������l�@���`��l�@���]��l�v�Ƒ�掛�J���Q�P���܂ŏZ�E�������ށB
�@�g���T�S�����R����F�q���@���R�͑�掛�Q�Q���A�э��Q�R�W���A������P�S�S���A�����P�S�N�i1817�j�V���Q����B
�@�q�v�@��᧐��l�F��掛�Q3���@�@�@�@�@�������^������F���R�i�����j���^���l/��Ɖ@�������l/���w�@���ׁi�H�j�哿
�@��掛��肻�̂Q�@�@�@�@�@���@��l���{����
�@�Η����]��l����F�R��E�ɖؑ���Η��̏��a�U�R�N�����̋�肪����B�u���Ȃ�欂ɐU���ւ�v
�����͉������N�i1744�j��掛�Q�P�����p���B���i�W�N�i1779�j�X���W���J���A�U�V�B
�@��掛��ڐΌQ�F�������č��̂Q��͐��ʖ��������ǂł��Ȃ����A��ړ��Ǝv����B
��������t�k��/���ю�����
�@�@���������ю������i��t�h�сj
���������ѐ^�@��
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@�ł�
�����R�ƍ����A�I����掛���i��Ɍf�ځj�B
�V���P�T�N�i1587�j�n���A�J�R�͐����V�����B
2023/12/23�lj��F
���u�I���������������ژ^�v�����T�N�@���
�@�ؑ������̔Ԑ_��������B�̂����ɏZ�g���_���J�������A���J�̏��ł��뜜�������l�����ӂƂ��āA���a�X�N�i1771�j���n�ɎO�\�Ԑ_���������A�O�\�ԕ�ӂ��n�߂�B
2023/10/20�B�e�F
�ߐ������͑�^���ł������悤�ł���B
�@�������ѐ^�@���@�@�@�@�@�^�@��������ڐ��F���Ǎ���B
�@���ѐ^�@���{���@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_�⓰�P�@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_�⓰�Q�@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_���@�@�@�@�@�^�@�����K�F���J���͕s��
�@�^�@������蓙�P�@�@�@�@�@�^�@������蓙�Q�@�@�@�@�@�J����V�������
�������ђ�--------------------
�@�@�@�����������ђˎj���}�������F���@�E���@�ՁE�ђˈ��E�B����E��ړ�
�������ђˑ�
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@�]�ˑO���͖��̂ł������Ǝv������A�s���B
���ۂP�O�N�i1725�j������{�R���̎x�z�ƂȂ�B
���P�Q�N�i1762�j�ɂ͑��̈ꕔ���������x�z�ƂȂ�A�x�z�������ېV�܂ő����B
�@�����́u���\�����v�E�u�V�ۋ����v�E�u�������́v�Ƃ��U�Q�U�Η]�B�@�������猩��A��W�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B
�O���Q�N�i1845�j�ɂ͐R���T�T�Q�Η]�E�Ɛ��͂P�S�V���A�������V�S�Η]�ŁE�Ɛ��R�R���ł������B
�@���̑��͒����ȗ��̌Ñ��Ō������i���j�E�������i���j�𒆐S�ɏW�����`�������B�܂�W���͌����Ƌ����Ƃɑ�ʂ����B
�j�����R�������A�]�˒������瑺�S�̂ŕ��������́A�_���w�̕s��s�{�h�̐M�ł��낤�B
���̑��ɂ͔ђˈ��i�����Ɍf�ځj������A���̒n���̕s��s�{�h�̋��_�ł������B
�@�ԍ~������i�v�s�@�����j
�ђˑ����܂�ŁA���ɗV�w���A�V�����N�i1573�j�̋��ɋA���������͌������ɖ@�ؒh�т��J���A���ꂪ�э����ɑJ����A��ɔэ��h�тƂ��ē��@�@�̍��{�h�тƂ��Ĕ��W����B
�@�@�@�@�@���╔���������́u�x���T�K��131�w�ԍ~���l�x�v�̍����Q�ƁB
�@���ЂƐM��
�@���@�͓��@�@�������i��������j�A���̖����������i���É��j�A�������i�����j�A�������i�p���E�������j�A�������i�p���E���É��j�A�������i�p���E����j�A������i�p���E������j�A�������i�p���E���ݒn�s���j�A���c���i�p���E���ݒn�s���j�ł������B
�@���Ȃ��A�������i�����j�̖����ђ˖��o���E�ђ˚��͏����s���ł���B
�@���p���������̂͑��������ł͕��S���ߏd�ł������Ƃ������Ƃł��낤�B�܂��Ă��h�̎��@�ł������������Ƃ��������̂����m��Ȃ��B
�����S�Ă����@�@�k�ł������B�M�����͏W�����ƂɁA�܂�A���E���E�V�c�ɕʂ�čs���Ă����B
�A���A�V�a�R�N�i1683�j�̑�ړ��́u���������ꓯ�v�Ƃ���A�����E��������v���đ����B
�܂��A�u�l�v�i�V�ۂU�N/1837�j�́u�����l���@�V�c���l���v�Ƃ���B
�@�@�@�@���u�l�v�͂������Ɍf�ځB�@�@�@
���@�ܕS�������͖������̒h�߂����i�W�N�i1779�j�ɁA�������̒h�߂����i�X�N�Ɂu�{�呺���v�ōs���Ă���B
���ۂR�N�i1743�j���̑�ړ��ɂ́u�\�O�u���v�Ƃ���A�u�������������Ƃ�������B
�܂��A��烖���̏��q�����U�N�i1756�j�����猩����B
�@�@�@�@�����Ɍf�ڂ̌������y�і��������Q��
�������i�p���E�������j�Ղɂ͓��@�l�S�\�����������ۂP�U�N�i1731�j�Ɍ�������Ă���B
�@�@�@�@���������i�p���j�����Ɍf��
�������ђ˕l
�@�ܓx�E�o�x�F35.735014460019066,
140.5620691513533�@�ɏ��݂���B
���u�x���T�K�@110�@�ђ˂�����@���܁v�˒m����A�������s��s�@���
�@�嗘���p���������ɉ��������H����A�u�˂̔ђˏW���ɒʂ��钚���H�ɍ����P���قǂ̕l�ƌĂ��Γ��i��ړ��j������B
����������ƁA�V�ۂU�N�i1837�j�ɔђˑ��́u�����l���v�Ɓu�V�c���l���v�ɂ�茚�Ă�ꂽ���Ƃ�������B
���l���Ƃ͎q�����E���Y�Ȃǂ��F�肷�鏗���̍u�i�W�܂�j�Łu�q���u�v�ȂǂƂ��Ă��B
�i�����ł͂قڌ����Ȃ����j�����ł͎��ʓV����S�q��_���q���Ƃ��ĐM�����B
���̐Γ��́u��Y�����v���肢�A�o�������A�u�{��S���{�v�ׂ̈Ɍ��������B���̍��͓V�ۂɋQ�[�̍��ŁA�э����ł��o�Y�ŖS���Ȃ����l���������̂����m��Ȃ��B
�@�ђˁu�l�v�P
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
���͎��̂Ƃ���B
�@�@�@���ʁF��N����聡�畔���A/����Y�{��S���{
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o
�@�@�@���ʁF�V�ۘZ���������������V/������@�����l���@�V�c���l��
�ȉ��AGoogleMap�@����]��
�@�ђˁu�l�v�Q�@�@�@�@�@�ђˁu�l�v�R
�������ђˌ�����
�ђˌ������O�j�G
�ђˌ������́u�O�j�v��э��h�т̃y�[�W���]�ڂ���B
013/06/26���M�E�C���F2024/02/04�u�����s��s�@�㊪�v�����M�E�C���F
�@�ђ˂ɗ����R�v�s�@������������B��i�P�T�N�i1408�j���p�̊J��Ɠ`����B
�����U���v�s�@���ׂ̒�q�ɗv�s�@�����Ƃ����w�m�������B�����͔�b�R�Ɋw�сA���ɕ����ŐS�@���b�E���o�@���q�Ɩ������Ɋw�ԁB
�V�����N�i1573�j�v�s�@�����͌̋��E�ђ˂ɋA��A���R�Y���̔삪����A�������Ɋw�����J���B
���ꂪ�ђ˒h�тŁA�J�u���A�����͂S�Q�C�R�ł������Ƃ����B
�@���v�s�@�����͔ђˑ��Ŗ@�،o�̍u�߂��s���A�����̗����҂��W�߂�B
�������b�R�V�w�̌�y�ɖ{���������̒�q�@���@�����A���{�����o�̒�q�o���@�����炪���āA���̓����E�����͓V���T�N�w�k�R�O�]����A��āA���s����ђ˂ɉ������A������̖@⥂ɉ����B
�@�������҂̐��͉v�X�������A����ɑΉ����邽�߁A���s��苳���@������Ăэu�߂̕⍲���Ȃ�����B
�@�@�ȍ~�A�⍲������̂̏Z�ތ����������@�Ə̂���悤�ɂȂ�B
�V���V�N�i1579�j�����͑J������B�����͔ђːV�c�̐����˂ɑ�����B
�����̑����̐܁A�V����Ԃ�䎁X�ƕ����~��Ă����̂ŁA�����́u�ԍ~������v�Ɖ]����B
�@�@�@���╔���������́u�x���T�K��131�w�ԍ~���l�x�v�̍����Q�ƁB
�����̌�͎㊥�Q�V�̓������u��ƂȂ邪�A�Ⴓ�̂̔������A��������͓��R���L���ɐg����B
�V���W�N�i1580�j�����͔э��������U�������ƕ��R�Y�������̏����ŁA�������i�@�֎��Ƃ��]���j�ɍu⥂��J���B
���̖������i�@�֎��j�w������ɔэ����ƂȂ�A�э��h�тɔ��W�����邱�ƂƂȂ�B
�@���������͖����Еʓ��ł���A�����͔э�������t�߂ɂ���A��ɖ����Еt�߂Ɉړ]�Ƃ����B
�Ȃ��A���̔N�����͋��s�ɋA��A������h�т��J���B
�@�@�@�����s������h��
---------------------�]�ڏI-----------------------
���u�����s��s�j�@�㊪�@�y�с@�����v�@���
�@�R���͗����R�A�@���͗v�s�@�ƍ����A���i�P�T�N�i1408�j���p�̊J��Ƃ���B�i�u����S���v�j
���Ƒ厛���ɑn�����ꂽ���A�����N���i1469~86�j���ݒn�ɑJ�����Ƃ����B�i�u���`�v�j
�]�ˊ��ɂ͒��R�@�،o�����A������10�����L�����B�i�̂ɖ{���ƒʏ̂����B�j
���@���ג��ł͖{���A�ɗ��A�c�t���A�ω����i���݂͑ޓ]�j�A�H������L���A�����S�S�O�A�h�k�W�U�l�Ƃ���B
����
�������ђˌ�����
�@�����������G
�@�@�ђ˖������i�����j
�@�@�@�����������F
�@�@�@�@�ђ˖��o���i�����s���j
�@�@�@�@�ђ˚��i�����s���j
�@�@�ђ˖������i���É��j
�@�@�ђ˖������i�p���E�������j
�@�@�ђˌ������i�p���E���É��j
�@�@�ђː�����i�p���E������j
�@�@�ђ˒������i�p���E������j
�@�@�ђ˖������i�p���E���ݒn�s���j
�@�@�ђ˒��c���i�p���E���ݒn�s���j
�@�@�֑��핟��
�����Α���
�����@�ܕS�������{���F����115����
�@�@�@���ʁF������@�@�����R������/��畔���A�@��\�l���@���ρi�ԉ��j
�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{��
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���c���@���F/�ܕS�����剶���
�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@���ʁF�ێ��@���i��M�q�ΐ����g���@�@�@�@��1780�N
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏʐ^����B
���ۂR�N��ړ��F���R�A����78����
�@�@�@�@�@�@�@���ێO��V�\���\�O���@�@�@�@�@�@��1743�N
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�H
�@�@�@�@�@�@�@�\�O�����@�E�E�E�H�H�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏʐ^����B
��ړ��F����83����
�@�@�@���ʁF���Z���q�Ώ\���\�O���@�������ђˑ�/�����R�������@�@�@��1756�N
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�@�@�E
�@�@�@���ʁF��烖�����{�@�{��@���c���Z�l�@�@���@�~�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�V�����N���q���F����65����
�@�@�@���ʁF�ܕS�����@��烖�����{�@�ӓ�
�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�V�����p�h�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1781�N
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���c���@���F
�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�@�@�@�@�@�\���\�O��
�@�@�@���ʁF��V�l�C�@�F�A���@�@��ܕS�Β��@�L�闬�z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ɏʐ^����B
���q���F����110����
�@�@�@���ʁF�����N��g�C�@�@�@�@�@�@��1805
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�E����/��V�l�C�@�F�A���@/�V���ו��@���y���J/���R��\�����@�����i�ԉ��j
�@�@�@���ʁF�A�O��P���@�{��@���R���A�L��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�M�q�ˁF���{���Y�E�q��@�@�@�@�@������
�萅�F�V�ۂP�S�N���@�@�@�@�@�@�@������
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@�ђˌ������R��
�@�ђˌ������{���P�@�@�@�@�@�ђˌ������{���Q�@�@�@�@�@�������{���G�z�F�@�ؒh�тƌf����B�@�@�@�@�@���������@��l����
�@�������c�t���@�@�@�@�@�������H�����F����A���������H�����Ƃ͕s���@�@�@�@�@�������ɗ�
�@���@�ܕS�������{���E�����@�@�@�@�@���@�ܕS�������{���E����
�@���ۂR�N��ړ��F�������A���Ƃ��̖���������A�����̂P/�R���������Ǝv����B
�@�V�����N���q��
�Ȃ��A�R�吳�ʂ͖����A�Q�������ɑ�^�̑�ړ��i�和���j�����邪�����B
�@�Q��������ړ��@�@�@�@�@�������R�吳���F�������GoogleMap����]��
�������ђ˖�����
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@���É��ɂ���A���@�R�ƍ����B�ђˌ��������B
��i�P�T�N�i1408�j���e�@���p�̊J��Ƃ����B�i�u���`�v�j
�P�T����Ꟃ͒����̑c�Ƃ����B
�S�q��_�͂Q���v�����@���e�̊J��Ƃ���A�p�������Ɉ��u����A�M���W�߂�B
�����R�N�̑�ŏ����Ď��A�����������B���F�͂��̌�̍Č��B
���F
�@�J�@�R�@���e�@���p
�@�Q�@���@�v�����@���e
�@�E�E�E
�@�P�T���@���
�@�E�E�E
�Α����Ƃ��āA����̕M�q�˂�����B�@������
�u�[�����@��j�v�ɂ��A�ђˈ��͖������n�Ƃ���A
���������ł���
�@���s�@����i�������P�X���j�A
�@�@����11.11.15��A�ђˑ��B���i�Q��15���j
�@�{���@��ꟁi�������Q�R���j�A
�@�@�ђˑ������a�̗��s�ō��f���Ă������A��a�҂������A������a�C�Ŏ₵���Ɠ`������B�u�@��j�v
�@�����@�����i�������Q�U���j�A
�@�@�ђˑ������a�̗��s�ō��f���Ă������A��a�҂������A������a�C�Ŏ₵���Ɠ`������B�u�i�s�j�v�j
�@�@�@�����ɂ��Ắu�ђˌ���B����v�ɉ����@�����擃������B�Q�Ƃ���B
�@��lj@�����i�������Q�V���j�A
�@�@���11.2.28��A�ђ˖������Q�V���B
���s��s�{�h�m���ŁA�ђˈ��ɊW����i���傩�j�B
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@�ђ˖������{���@�@�@�@�@������ב�P�_
�@���������揊
�@���n�����{���P�F���ʍ��c���@���F�A�J�R�����@���p�A�O�c���{�@����
�@���n�����{���Q�F��c�v�����@���e�A�{�����c�l���v�s�@���p
�@���n���擃�F�J�R�����@���p�A��c�v�����@���e
�@���������掏�E�O�F�P�Q�����O�A�P�R�������A�P�S�������A�P�T����ꟁA�P�U������
�@���������掏�E���F�S�Q�����v�A�S�R�����ցA�S�S������
���v�����@���e�F
�@���e�ɂ��ẮA���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�����ɂ����̐��h�̔O�����t���Ă������̂Ɛ��������B
���e�͏㑍�R���S���J�̐���ł���A��������S�ɋߐڂ��Ă��邱��
���R�@��@�̓��p�Ɏt�����A��̒��R�@�،o���ɑ����Ă�������
��t���ƊW�������A��t����{�R���R�̎G�M�����������e��������
���̎��́A���@�̌���@�̖{������O��Ă������ێ��`�����߁A�{���́u�s��s�{�v�̏@�`�ɗ����A�肻���Ď�����H���Ă���������
�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ��A���������������悤�Ƃ��������̓��@�@���y�ɍ��v�����̂ł͂Ȃ����Ɛ�������B
�������ђ˖�����
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@�����ɂ���A����R�ƍ����B�ђˌ��������B
�J�n�͖��e�@���p���邢�͜�i�P�W�N�i1411�j�Ö��@����̊J��Ɖ]���B�i�u���`�v�j
���F
�@���@�c�@���e�@���p
�@�J�@��@���@����
�@�E�E�E
�@�P�O���@�����@�����@�������N�\���\�Z����A�擃����B�������u�[�����@��j�v�ł͉@���͗��_�@�Ƃ���B
�@�@�@�ђˈ��E�s��s�{�m�ł���B
�@�P�P���@���Ɖ@���ԁ@�������u�[�����@��j�v�ł͉@���͚��P�@�Ƃ��邪�u�Ɓv�Ɓu�P�v�͓���ł��낤�B
�@�@�@�ђˈ��E�s��s�{�m�ł���B
�@�E�E�E
�Ȃ��A
���u�[�����@��j�v�ɂ��A�ђˈ��͖������n�Ƃ���邪�A��������������̂Q���̔ђˈ��ɊW����s��s�{�m�̖�����������B
���_�@�����i�������P�O���j
���u�@��j�v�ł́u�K�\���\�Z����A�ђˁv�Ƃ���B�擃������A�K�Ƃ͐������h�K�N�ł���B�A���u�s�j�v�ł͉@���𓌌��@�Ƃ���B
�~�P�@���ԁi�������P�P���j
�����Ɖ@�E���P�@�͓���ł��낤�B�u�@��j�v�ł́u���ی��N�W���Q�X����A�ʑ����v�Ƃ���B
�����Α���
���@�ܕS�������{���F140����
�@�@�@���ʁF�얳���@���F��ܕS������Ӗ������@�i�����e�̊��p��͏ȗ��j
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@�i�ԉ��j
�@�@�@�@�@���ʁF�@�@�@�����ꖜ��甪�S�l�\�O���@�i���u�s�j�v�ł͐��ʂɂ���Ƃ��邪�A���ʂɂ���j
�@�@�@�@���ʁF����u��断�T�ܕS�����A
�@�@�@�@�@���ʁF�@�@�@��������Z�S�O�\����
�@�@�@�@�@�@�i�����j�㎵�S�N�����m�E�E�E�i�������������j�E�E�E�L�闬�z��@�ێ����i���Ȉ�Z�����c�@�@��1777�N
�@�@�@�@�@�@�@�@����̒����̖��͖��m�F�ł��邪�A�����炭�w�ʂ̖��ł��낤�B
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@�ђ˖����������@�@�@�@�@�ђ˖������{��
�@���@�ܕS�������{���@�@�@�@�@���@�ܕS�������{������
�@���������擃�F���̂悤�ɂS����Ԃ��A
�����������
�@�@���[�擃�F���Ǖs�\�A���̉E�́h�\�������擃�h�F�ђˈ��W�ҁE�s��s�{�m�ƍ��������Ɍf�ځ�
�@�@����ɉE�́h�����O�E��N�̔N�I�A�E�E�E�E�哿�A�����Ȃǁh���ǂ߂�A�m���̕擃�ł��낤������ȊO�͔��Ǖs�\�B
�@�@�E�[�擃�F���͌�������
�@�̂S��ł���B
�@�������P�O���擃���F���@�@�c���\��������/�����������i�h�K�j��1711�N/�\���\�Z��
�������ђˈ���
�@���ݏꏊ�F�T�ˈܓx�E�o�x�F35.72955072134051, 140.55742630949754�@�t�߂ɂ���B
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@�ђˈ��̐Ղ͌��݂ł͂͂����肵�Ȃ��B
�����Ǝ��e�̕�n�Ɉ��Ղ炵�����̂�����B
���e�͓��@�@������i�p���j�����ɂ���A��n�ƂȂ��Ă��邪�A�R���ɂ���A�u�����@��v�ŕߔ����ꂽ�����������܂��Ă��������q�̉ƂƂ��߂����A�R������ƌ���E�������ɒʂ���B���̎������M���ł��������Ƃ���ʒu����l���Ă�����ɂ������\�����������f��͂ł��Ȃ��B
�@�����s��s���ł͔ђˈ��E�����V�c���𒆐S�ɕs��s�{�̐M���s���Ă����B
���o������āA�j���͖w�Ǔ`���Ȃ����A�����̃X��s�{�h�̉ߋ�������A�ђˑ��i250���j�A�g�c���i60���j�A�R��E���v�R�E�����̍��v�i90���j�قǂ̓��M�����݂������\�@��犰���@����}����܂łT�O���ɋ߂��@�������������Ƃ��m����B
���\�@��̖@��ҁF
���̈�l�Ƃ���
�@�����@���R����������B
�@�@���䓇�i�}�}�j���߁A�ђ˖������A�ђː��܂�A�U�Q��
�@�@�u�[�����@��j�v�ł�
�@�@�@�u���\14.10.21��A���\�@��A�O����߁A���q�������o���A�ђˑ��v�Ƃ���B
�@�@�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�ł�
�@�@�@�u�O����߁A���\14.10.21��A���q�������o���A�⑺�ɉB���A�@��̎��|����グ��A�ʑ����܂�A�ђː��܂�Ƃ������v
�@�@�u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�v�ł�
�@�@�@�u���\�S�N�V���T���@�����@���R��\�m����������S����i�ߋ����j�v�A
�@�@�@�u���\�P�S�N�P�O���Q�P���@�����@���R�v�A���q���c���������o���A�����ʑ����i�ђˑ��j�̐���A�O����m�v�Ƃ���B
���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA���a�T�Q�N�@���
�@���ђˈ��ɂ��āA���̂悤�ȋL�ڂ�����B
�ђˈ��F�����s���A�������n
�@���s�@����i�������P�X���j�F����11.11.15��A�ђˑ��B���i�Q��15���j�B
�@�M���@���\�F18����A�ђˁB
�@�P���@���ӁF���9.3.18��A�ђˉB���B
�@�ÐM�@��痁F���i3.11.27��A�ђˍr�k���B���B
�@��lj@�����i�������Q�V���j�F���11.2.28��A�ђ˖������Q�V���B
�@�~�P�@���ԁi�������P�P���j�F���ی��N�W���Q�X����A�ʑ����B�u�s�j�v�ł͉~�Ɖ@�B
�@�P�q�@�����F�S���P�Q����A�ђˁB
�@�{���@���F�F����4.10.11��A�]�ˉ��J�B
�@���s�@���E�i�������@���������͔ђˎ�����j�F9.9��A�ђ˒������B
�@�M�h�@���h�F���M�h�@�Ƃ͕s���A�M�É@���h�͖��a��.9.28��A�ђˑ��Ƃ���B
�@�{�@�@�����F����5.11.1��A�ђˉB���B
�@�����@�����F����2.10.1��A�ђˁB
�@�@���v�F12.1��A�ђ˓���B
�@�{���@�����F11.1��A�ђˏ����B
�@�{�s�@���s�F12.4��A�ђˑ��B
�@����@�����F��i3.1.3��A�ђˉ���B
�@���_�@�����i�������P�O���j�@�������N�\���\�Z����A�擃����B�������u�����s��s�j�v�ł͉@���͓����@�Ƃ���B
�@�~���@����F21��A�ђˁB
�@�K���@���ӁF���ʉ@�A���9.3.18��A���Ñ��B
�@�{���@��ꟁi�������Q�R���j�A�ђˑ������a�̗��s�ō��f���Ă������A��a�҂������A������a�C�Ŏ₵���Ɠ`������B���ɏ��Ȃ��B
�@�����@�����i�������Q�U���j�A�u�ђˌ���B����v�ɉ����@�����擃������B�Q�Ƃ���B
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@�����͌����������ւ��A����������ւ��A����E�����������₻�̋t�����ւ��A�������邱�Ƃ��\�ȗ��n�̂悤�Ɍ�����B���̈Ӗ��ň����\����ɑ��������ꏊ�Ǝv����B�u�����s��s�j�v�ł́u������ƌ���E�������ɒʂ���v�ƕ\�����Ă���B
�@�����ђˈ��ՂP�@�@�@�@�@�����ђˈ��ՂQ�@�@�@�@�@�����ђˈ��ՂR�@�@�@�@�@�����ђˈ��ՂS
�@�����ђˈ��ՂT�F���۔N���Ȃǂ̌Â��擃���_�݁E�U�݂��邪�A���l�̕擃�ł���A�m���̂��̂͂Ȃ��Ǝv����B
�������ђˎ����t�㋤����n
�@������n�ł��邪�A��n�����������̂ł��낤���A���X�r��Ă���B
�����A�u�s�j�v�ɋL�ڂ���Ă����^�̑�ړ��͛������Ă���B
�@���ݏꏊ�F�ܓx�E�o�x�F35.73346530069348,
140.55840588118016
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
[�ђˎ����t�㋤����n]
��ړ��F�}�t���A����169����
�@�@���ʁF���������ꓯ���V
�@�@�\�ʁF���@�@�����ꖜ�O�畔���A
�@�@���ʁF�V�a�O�Nᡈ�Z���\�O���@�@�@�@�@�@�@��1683�N
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�˒m�쎁�k�F�u�s��s�{�h�M�_���̕擃�����������A��n�����̂��߁A���̕擃�͕s���B
�@���̕擃�̉E���ʂɐn���ō�����悤�ȐՂ��������B�v
�@�������ꖜ�O�畔���A��ړ�
�@�������ꖜ�O�畔���A��ړ��\�ʖ��@�@�@�@�@�������ꖜ�O�畔���A��ړ��E�����F�V�a�O�N�̔N�I
�@���t���n�E�擃�ȂǂP�@�@�@�@�@���t���n�E�擃�ȂǂQ�F���́u�얳���@�@�،o�@�{���@��ꟊo�ʁv�ł��邪�A�{���@��Ꟃ͕s���B
�@���t���n�E�擃�ȂǂR�@�@�@�@�@���t���n�E�擃�ȂǂS
2024/02/24�lj��F
�@��L�̈˒m�쎁�k�G�u�s��s�{�h�M�_���̕擃�v�Ƃ́A���̂悤�ȕ擃�Ƃ̂�������B
�@�u�w�����s��s�j
�����x�i��204�E��i�j�Ɍf�ڂ̎ʐ^�́A�s��s�{�h�́w�ߋ����x�ɋL�ڂ��ꂽ�A�M�҂̖@�����́E���쎁�������A�����w�ߋ����x�̎c���Ă����������̂��̂Əƍ����āA�M�҂��m�肵�����̂ł���B���̕悪�ђˎ����t�㋤����n�ɂ���A���ŏ�����ꂽ�Ղ�����A������B�e���Čf�ڂ������̂ł���B
�Ƃ��낪�A���̕擃���������A��n�̉��C���Ŗ�����Ƃ��Ĉڂ���Ă��܂����̂͂Ȃ����Ǝv���B�v�@�ƁB
�@�܂�A
�@��ʁA�كy�[�W�̌f�ڂ������L�̋L���́A��L�E�˒m�쎁�̂������ɊY������擃�ł���Ɣ�������B
��ʌf�ڋL���G
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@�u���\�@��v�̍��ip.204)�Ɂu�s��s�{�h�m�̉B����v�Ƃ��āu�����@�����v�̕擃�̎ʐ^�f�ڂ�����B
�������A�ʐ^�̌f�ڂ݂̂ŁA���̑��̐����͂Ȃ��B
�@�����@�����ɂ��ẮA�u�[�����@��j�v�ł́u����5.12.11��A�ђˑ����������T�N�i1740�j���v�Ƃ�����A���̑��̏��͂Ȃ��B
���₵���N�I������A���\�@��ɊW�����m���Ǝv����B
�@�����@�����擃�F���ݏ��݂��s���́u�����t�㋤����n�v�ɂ������擃�ł���B
�������ђ˂̔p��
�@�F�������E�������E������E������
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
��������
������1318�Ԓn�ɕ�n������A���̕t�߂ɂ������Ǝv����B
�����R�ƍ����A�]�ˏ����̑n���Ɛ��肳���B�ђˌ��������B
�����V�N�i1824�j�ЏĎ��A�V�ۂS�N�i1833�j�Č��A�����P�O�N�������ɍ����B
���
�@�i�ȗ��j
�Α���
��ڕ�⸈F����282�����A�N�I�͂Ȃ��B
�@�u�쐳�@���z�t�C�v�ƍ�������B
���@�l�S�\�������F���R�A130����
�@�@�@�@����u������畔�@�@���ۏ\�Z�h��\���\�O���@�@�@�@��1731�N
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E��
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�c�@���@���F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E��
�@�@�@�@��j�l�S�\�����Җ�
��ړ��F���R�A130����
�@�@�@�@�@�@�@�����\���@�@�b���@����哿
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���ݕ����A
�@�@�@�@�@�@�@���ۓ�\���K�N�㌎��\����@�@�@�@�@��1735�N
��������
���É�1158�Ԓn�ɕ�n������A���̕t�߂ɂ������Ǝv����B
�����R�ƍ����A�ђˌ��������B�p���ɂȂ��������͕s���B
�����āA�����̋S�q��_���͋v�����@���e��l�̊J��Ɖ]���A�������ɂ��肵���A�������n���̐܁A�J���Ƃ����B
�����Q�N�̉Ђœ����ƂƂ��ɏĎ�����B�u�������ߋ����v
���
�@�J��@���@���P
�@�@�i�ȗ��j
�和���c��B
�@�V�ۏ\�l�N�i1843�j�̔N�I�A�����P�S�������i�ԉ��j�A�얳���@�@�،o�@�������A���h�a���@�ƍ����B
�������
������833�Ԓn���߂ɂ������Ɛ��肳���B
��{�R�ƍ����A�ђˌ��������B�ׂɑ�{�_�Ђ�����B�i��{�_�Ђ͌������Ƃ��]���B�u�˒m�쎁�v�j
���Ղ͔��ƕ�n�B
�@����n�͔ђˈ��Ր��肳���B�ђˈ��k�������ɑ�{�_�Ђ�����B
���������F�p���i�ђˌ���B����E�����@�����擃�j
������807�Ԓn�t�߂ɂ������Ǝv����B
�@�����ݏꏊ�F�T�ˈܓx�E�o�x�F35.7288481710778,
140.5585033017178�@�Ɛ��肷��B
�J�n�͕s���ł��邪�A�]�ˏ����̊J�n�Ǝv����B�ђˌ��������B
�p���ɂȂ��������͕s���B����͔��ƕ�n�B
[�������Ձ@��n]
�J�R���F���^�A65�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����܍b�\�V�@�@�@�@�@�@�@�@��1464�N
�@�@���ʁF�J�R�@���c�@���T���l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㌎�\����
���̑��R��̑�ړ�����B
���̓��A�Q��͕s��s�{�h�m���Ɋւ�����̂ł���B
2023/02/24�lj��F
���������s��s�˒m�쎁�@���玟�̂�������B
�@�u�����s��s�j�v�̒������Ղł����J�R���́A�����̐Γ��̉E���ɂ�����̂Ǝv����B
�@�܂��u�s�j�v�ł����u�Q��̕s��s�{�h�m���̕�v�́A���̓����Ƃ����P���Ǝv���B
�ȏォ��A
�p��������n�͉��ɋL�ڂ���u�ђˌ���B����v�������n�ł���A�����ɂ͏�f�́u�J�R���v�A���f�́u�B����i�����@�����j�v�A�y�э����݂͕s���m�ł͂��邪�u�s��s�{�h�m����P��v������ƕ�����B
�@���ђˌ���B����F�����@�����i�~���@�����j�擃�A�ݔp��������n
�����@�����i�~���@�����j�ɂ��ẮA�͂��Ɏ��̏����B
���u�[�����@��j�v��.290�@�ł�
�u�~���@�����@����2.1.21��A�ђˑ��A�ђ˖������v�Ƃ���B
�@���Ȃ��A�ђ˖������͔ђ˖������Ɠ���i�˒m�쎁�j
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@p.209�@�ł�
�u�ђˑ��ɂ́A���鎞�u�a���͂͂��_�����ꂵ��ł������A�s��s�{�m��������ڂ�������ƍ��������Ƃ����`�����c���Ă���B���������a�C�����̋F�����M�̊�Ղł������̂����m��Ȃ��B�v
2024/03/08�lj��F
���u�x���T�K��214�@�u�a�ގU�@�ђ˂�����v�˒m����A2024.03�@���
�@�x���s���ł͉u�a���s��`����ËL�^�͎c���Ă��Ȃ����A�B��u�u�a���瑺���~�����m���������v�̂Ƃ̌��`��ђ˂ŕ��������Ƃ�����B
���a�T�O�N��A�s���̊e���œ��얋�{�ɋ��Ƃ��ꂽ�u���@�@�s��s�{�h�v�̗��j���������Ƃ����邪�A���̎��ђˎ�����̕�n�i�p�������̕�n�j�ɂ����ړ������̑m���̊W�������̂ƕ����B
�@���̑m���̑�ړ��͍�����78�����ŁA���ʂɁu�얳���@�@�،o�@���������v�ƍ��ށB���ۂP�R�N�i1725�j�̌����ł���B
���̍��ђˑ��ʼnu�a�����s��������@�،o���u���ݎO��ܕS���v�����u�ގU�v���F�����̂ł��낤���B
�����́u�s��s�{�m�v�̖���ɂ��A�ђ˖������i�������j�Q�U���ŁA�ђˑ��𒆐S�ɕs��s�{�m�Ƃ��ĐM�����������m�ł���A�����Q�N�i1749�j�ɐ�������B�x���s���ł͔ђˈ�������V�c���𒆐S�ɖ}��200�N�ԁA�s��s�{�M����������400�l�߂��_����50�l�قǂ̕s��m�̊������m�F����Ă���B
�@��ې[���̂́A�����̑�ړ��ɂ͉ԂƁA���߂ł�2023�N�t�ފ݁u�e�A�^�X�c�v�A���N�H�ފ݁u����v�W���̐l�X�̑����k���������A���݂������ւ̓Ă��M���������Ă�����i�ł���B
�@�i�{�e�ł́A�����͖������Q�P���Ƃ��邪�A����͍Z���i�K�łQ�U���ւ̒����������Ȃ������Ƃ����悤�Ȏ���Ǝv����B�j
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
��q�̂悤�ɁA���̕�n�͔p�������̕�n�ł���B
�@�����@�����擃�̖�
�@�@�@�@�@�@�@����S�����ݎO��ܕS��
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�����E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�ێ����ۏ\�O��\���
�@�����@�����擃
�@�����擃���E�̕擃�P�F�����������擃�A�������ĉE���u�J�R���v�ł��낤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�R���͋͂��Ɂu���v�̂P�����̂ݓǂ߂邪�A��͑S�����ǂł��Ȃ��B
�@�����擃���E�̕擃�Q�F�������ĉE�[�������擃�@�@�@�@�@�����擃���E�̕擃�R�F�������č��[�������擃
�����������E�����V�c--------------------
��������
���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���i�T�v�j
�@�������𒆐S�Ƃ����W���Ƌ����V�c�̂Q�c�̏W������Ȃ�B�_�������́A��{�I�ɋߐ���ʂ��s��s�{�h�̐M��������т��B
�@�吳�P�O�N�́u����S�j�v�ł́A�u�F�ؔ��l�Ƃ����l�������āA�ނ͈��[�������̉Ɛb�ł��������A�c���P�R�N�i1608�j�����V�c���J���v�Ɠ`������Ƃ����B�c�����N�i1648�j�̕s��s�{�h���[�̙֑ɗ��{���Ɂu���l�����v�Ƃ���A���l�͎��݂��邱�Ƃ͕������Ă���B
�����F�؎��͑�X���s��s�{�@��̔M�S�ȐM�҂ł������B
�@���Ђ͓��@�@���厛�Ɩ��i�p���E�ʒu�s�ځj�A����͎O�А_�Ёi���c�͖��厛�j�ł���B
�����͑S�ē��@�@�ň��i�S�N�i1775�j�u�\�O���u���v�œ��@�ܕS�������{������������B
�����V�c�ł͏�������s��s�{�h�̐M������ŁA���̑��݂��m����B
���̐Ւn�ƌ����鏊�Ɋ����R�N�i1791�j�̓����S�T�O�������{���E���N����@���{���Ȃǂ�����B
2024/01/30�lj��F
���u�����s��s�j�@�㊪�v���a�T�V�N�@p.192�`�@���
���R�@�،o��
�@�����A���݂̑��Ò��E�����s��s�̔э��S��E�g�c�Ȃǂ͐�c���ƌĂ�A��{�I�ɐ�t���̐��͉��ɂ������B
�����āA��k�����ɂ͉�������t������ō����͎҂Ƃ��ČN�Ղ���B���̂悤�ȏ��ŁA���R�͈���Ƃ̌������т��ɂ���c�s�ɂ��̋������g�傷��B
�@���@�̑�h�z�ł������x�؏�E�i����j���J�R����������{�@�؎��ƌ���p�����������������R�ɊJ�R�����{�����̓��ꎛ�ƂȂ萬�������̂����R�@�،o���ł���B�����ē�k�����ɑ�������̗P�q��s�@���S�����R�O���ƂȂ�ɋy��œ��@���c�͍L�͂Ȕ��W������B
�@�����R�N�i1331�j�ȍ~�A����͐�c�s���̌�������ɓ��E���������v�R���E���R���O�J���Ȃǂ̓��E�E�Ɠc���𒆎R�Ɋ�i���Ă����B
�ȏ�̂悤�Ȕw�i�̒��ŁA�������͐�t���ꑰ�̋������ɂ���Ďx�z����Ă����B
�����@��
�@���i�W�N�i1271�j�́u�]�d�y��@��v�ɂ́A���@�̗L�͐M�k�Ƃ��đ��c�斾�E�]�J�����i���M�j�ƕ��ы����@���̂Ȃ��������Ă���B�@������c���������̏o�g�ƍl�����A�@���͑]�J���M�̒�A�������̑�{�̕��c�Ƃ����B
���Z�������i��É@�����o�ˁj
2023/10/24�lj��F
��ʑ��ɐڂ���ʒu�ɂ���B�i�˂̂���k���̓��������Ƌʑ��̋��ł���B�j
���u�������l�B�v���c�q�F�E�ԓc��d�A���a�R�U�N�ip.31�j�@���
�����͓����̎��ȐȂƂ��Đg�r�Θ_�Ő��_���킷�B���ۂP�V�N�i1732�j�P�Q���~���@���W�������̘Z�����o�o�˂̕\�����Ă�B�i�u�䏑栚g�����v�����j
2023/11/20�lj��F
�u�x���T�K�@���P�T�O�v�@���
�@�u�Z�����ˁv�͌Õ��Ƃ����B�����V�c�͕s��s�{�h�̐M���_�ł���A�����V�c���Ղ�����A���݂P�O�]��̕�����c�𗯂߂�
�]�ˌ���ɂ͑m���̕��y���ɉB���A�����ɂȂ�s��s�{�h���ċ����ꂽ��A����@��o���A���Ē������Ƃ����B
�Z�����̋I�v�������̎��J��ꂽ�Ƃ����B
�@�@�@���@�����V�c���Ղ͂������Ɍf�ڂ���B
2023/10/19�B�e�F
�@�����Z�����˂P�@�@�@�@�@�����Z�����˂Q�@�@�@�@�@�Z�����˕Q���@�@�@�@�@�Z��������
�@���@550�����E�Z������
�����������V�c���ՁE��n
���u�x���T�K���V�U�@�M�̑��Ձ@����������v�x���s�@���
�@�@�i���̒T�K�L�ɂ͏������Ȃ����A�����炭�������s��s�i���E�x���s�j�˒m�쎁�̒��Ǝv����B�j
�@���q�����A�����ɂ��|�����I�����鍠�ȍ~�ɁA�����E���v�R�E�Ўq�E��x�E�э��Ȃǂ̎��@�����R�̉e�����œ��@�@�ɓ]�@����B
���̂��������ƂȂ����̂́A���̒n�̌ꑰ�E�������ŁA�����@���͓��@�̒�q�ƂȂ�A�ꑰ���M�k�ƂȂ�B
�@�����V�c�͋������厛��O�ЎЂ�����{������k���ɂ���A�����Ɂu�F�ؐ��v������A�c���P�R�N�i1608�j�F�ؔ��l���W�����J�����Ƃ����`��������A���l�Ȃ�l���͌c�����N�i1648�j�̋L�^�Ŋm�F�ł���Ƃ����B
�@���̌�A���̒n�̓��@�@�͒�������ߐ��ɂ����ĘA�ȂƂ��̏��������������A���͐ڎ�I�X���ɌX���g��������R�̉���]�˖��{���͂̏@������ɍR���邱�ƂɂȂ�B���̐M�ԓx�͖��{���炷��u���V����˕s���ȏ@�h�v�Ƃ���A���ɂ͂��̒n�Ȃǂ̓��@�@�͕s��s�{�h�Ƃ��ċ��ƂȂ�A�n���ɐ��肻�̐M�𑱂��Ă������Ƃ�]�V�Ȃ������B����ɑ����{���͂��h�i�g���j�̎��@�͌������E�������e����������B
�@���̒n�ł́A���Ɋ����U�N�i1794�j��V�ۂX�N�i1838�j�ɂ͑����̑m������M�i�M�k�E�_���j���ߔ��E���S�E�撲�E����E�f�߂��A�r�������͍��⎀�E�쎀�Ȃǂ̋]���҂��o���A�m���̓��Ō�܂ŐM��]���Ȃ������҂͈ɓ������ɗ��߂ƂȂ�B���߂ƂȂ����҂́A���̐��͊m��͂��Ă��Ȃ����A�֓��i�]�ˁE�����E�㑍�Ȃǁj�łW�O�]�����z����Ɖ]���B
�@���Ƃ����@������Œn���ɐ��炴��Ȃ������s��s�{�h�͂��̋��_�Ƃ��ĎR���⋭�M�ғ@�ȂǂɁu���v��݂������𑱂��A�m���E�M�k�̕擃�͂Ǔy���ɉB������Ȃ������B
�@�����{�����猩�āA�����V�c�ɓ����O�̎R���ɁA���݂P�T��̕擃�����Ԉ�s������B�����擃�͖����i�����X�N�s��s�{�h���������j�ɂȂ�A�y������@��o�������̂Ƃ����B
�@�����̏܂����̈�s�̗��n�Ȃǂ���A�u�����V�c���v�͂��̕t�߂ɑ��݂������̂ƍl������B
�ł���Ȃ�A�܂��ɁA���̏ꏊ�́u�n��̐l�����́w�M�̑��Ձx��`������̂Ȃ̂ł���B
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@p.397�@���
�@�����V�c�ƌF�؎�
�u����S���v�吳�P�O�N�̐l�����ɌF�ؔ��l���ڂ�����B
����ɂ��A���[�������̉Ɛb�Ƃ��ČF�ؔ��l�̖����������A�c���P�R�N�i1608�j�ɋ����V�c���J�������Ƃ����`�������Ƃ����B
�c�����N�i1648�j�U���Q�R���̕s��s�{�h�m���[�̙�䶗��{���Ɂu���l�����v�Ƃ���A�F�ؔ��l�����݂��邱�Ƃ������B�F�؎��͍]�ˊ���ʂ��A�s��s�{�h�̔M�S�ȐM�҂ł������B
���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA���a�T�Q�N�@p.162�@���
�@���\�@��ȍ~�E���������܂ł̈��Ɩ@���̏��o��������A�����V�c���ɂ��Ă͎��̂悤�ł���B�B
�@�����̓��̋����V�c���̖@���͎��̂悤�ɏ����o�����B
�����V�c���F�~���@���W�A�{���@�����A�ÏƉ@�����A�����@���D
�@���~���@���W�F�O�V���蚢���@���W
�@���{���@�����F�O�T�{���@����
�@���ÏƉ@�����F
�@�@�u�[�����@��j�v�ł͕��3.8.18��A�����V�c
�@�������@���D�F�O�S�����@�����̉\�������邪�A�m��͂ł��Ȃ��B
�@�@�u�[�����@��j�v�ł́u��7.3��A���@�V�c�i�}�}�j�S���v�Ƃ���B
���u�x���T�K���P�Q�O�@���v�R������@�B����v�������s��s�E�˒m����@���
�@���v�R�̋�����n�̖؉��ƕ�n�Ɏ�暉@���_�i������120�����j�̋t�C��������B
�@�@���_�͓��̐��܂�ŁA���߂ƂȂ�O�N�ɋt�C�������āA�ߔ������Q�����O�ɉ������V�c���ł̊������m����B
2023/11/30�B�e�F
���������V�c����
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@�����V�c���Ոʒu�}�@�@�@�@�@�����V�c���Ռ����FGoogleMap����]�ځA�F�؉Ɠ@��߂��猩�グ
�@�ܓx�E�o�x�F35.75825352180285, 140.5094611199612
�@
�@���������V�c����
�@�����V�c���Օ擃�F��}�g��}�@�@�@�@�@�����V�c���Օ擃�Q�@�@�@�@�@�����V�c���Օ擃�R
�@�����V�c�F�؉��F�����V�c���Ղ��猩���낵���F�؉ƏZ��A�F�؉Ƃł͂W���܂ł̕��Ƃ����F�߂Ȃ������Ƃ����B�i�˒m�쎁�k�j
------------
�P�T��̕擃�̊T�v�F�����V�c���Օ擃�E���������F�O�P�`�P�T�̔ԍ��������B
�@�O�P�擃��i�c���j
�@�O�Q�푒�ҕs��
�@�O�R�M���@����/�S���@���P
�@�O�S�����@�����F�u�[�����@��j�v�ł����u�����V�c���@���E�����@���D�v�̉\������B
�@�O�T�{���@�����F�u�[�����@��j�v�ł́u�{���@�����F���i3.8.38��A�����V�c�v�u�����V�c�@���v�Ƃ���B
�@�O�U����@�����@�t
�@�O�V���蚢���@���W�F�擃�͚����@���W�Ɛ��肳���B���W�͓����Z�����������B
�@�O�W�����@������
�@�O�X�푒�ҕs��
�@�P�O�{���@����
�@�P�P����@��铁F�u�[�����@��j�v�ł͋���@���́F���i6�N9��9����A����E���쑺�Ƃ���B
�@�P�Q�����@���ƁF�⑺���̖@���ɓ��Ƃ���������B�u�[�����@��j�v
�@�P�R�푒�ҕs��
�@�P�S��遄���l���F�\�ʂ͎��̂Ƃ���B�@755�@756����
�@�P�T�푒�ҕs��
�@------------
�@�O�P�擃��i�c���j�F��͎����Ă���B
�@�O�Q�푒�ҕs���F�͂��Ɂu���@�v�̂ݓǂ߂邪�A��͑S���ǂ߂Ȃ��B
�@�O�R�M���@����/�S���@���P
�@�O�R�M���@����/�S���@���P�Q�F�i�\�ʁj�����͈ȉ��A�m���ł͂Ȃ��Ǝv����B
�@�@�@�@�@�����E�E�E�E�E�E
�@�@�@���@/�M���@����/�S���@���P
�@�@�@�@�@�����O�M���V�\���@�@�@�@�@�������O�N�́u�M�C�v1820�N
�@�O�S�����@�����F���͎��̂Ƃ���B
�@�@�@���@�@�����@����
�@�O�S�����@���������F�u�[�����@��j�v�ł́u�����V�c���@���Ƃ��đ����@���D�v����������B
�@�@����ɁA�u��7.3��A���@�V�c�i�}�}�j�S���v�Ƃ���B
�@�@���̕擃�̖�������ƁA�@���͑����@�ł��邪�A�����̓��ځi�����j�͑S�����ʂ����Ȃ��̂�����ł��낤�B
�@�@���Ɂu�[�����@��j�v�̂����u�����@�v���u�����@�v�̌�L���邢�́u�\�L�̗h��v�ł���Ƃ���ƁA
�@�@���̕擃�́u���i���j���@���D�v�ł���\�����������A�����́����������Ȃ�����A�푒�҂̊m��͓�����낤�B
�@�O�T�{���@�����F�{���@�����i�ԉ��j�Ƃ���B
�@�@���u�[�����@��j�v�ł́u�{���@�����F���i3.8.38��A�����V�c�v�Ƃ���A�����V�c�@���Ƃ���B
�@�O�U����@�����@�t�F�\�ʂ́u����@����@�����@�t�v�Ƃ���B
�@�O�V���蚢���@���W�F�����͎��̒ʂ�ŁA�擃�͚����@���W�Ɛ��肳���B
�@�O�V���蚢���@���W�F�����̉���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����\�Z�E�E�@�@�����ۏ\�Z�N�i�h��j1731�N
�@�@�@�얳���@�@�،o�@�����@�����@�@�@�����͐W�Ɍ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���Z���i�����j
�@�@����̒ʂ�ł���A�����Z�������ʂɂ́u�����@���W��]���V�v�Ƃ���A�����Z���������������m���ł���B
�@�@�@�������@���W�F���ۂP�U�N�R���U����A�����V�c�Z���������A�܂��V�c���@���Ƃ���B�i�u�[�����@��j�v�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�����Z������
�@�O�W�����@�������F�����́u�얳���@�@�،o�@�����i�ԉ��j�v
�@�O�W�����@�������Q
�@�@�������͓����A���ʂƂ��ǂ߂�A�u�[�����@��j�v�ł́u�����@�����A���\���N�T���Q�X���A�����V�c�v�Ƃ���B
�@�@�@����āA�����@�����擃�̉\���������B���ʂȂǖ����ŗv�m�F�B
�@�O�X�푒�ҕs���F�\�ʂ́u�얳���@�@�،o�v�Ƃ̂ݍ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʂȂǖ��m�F�A�m�F��v���B
�@�P�O�{���@�����F���ʂ͎��̒ʂ�B
�@�@�@�@�@�@�����l�E�E�E�E�@�������l�N�i�b�߁j1714�N
�@�@�@���@�@�{���@�����E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@���S�����E�E�E
�@�P�P����@��铑哿�F���ʂ͎��̒ʂ�B
�@�@�@�@�@�@�@���i�Z�����N�@�@�@�����i�Z�N�i���сj1777�N
�@�@�@���ʁ@����@��铑哿
�@�@�@�@�@�@�@�㌎�㟯����@�@�@�����F�ꂩ�����\�����ƂɎO�����������́B�u�㟯�E�����E�����v
�@�@�@�@�@�@�@�@���u�[�����@��j�v�ł͋���@���́F���i6�N9��9����A����E���쑺�Ƃ���B
�@�@�@�@�ˋ���@��铕擃�́u�������䖭���O��n���T�D�W�j�s��s�{�m����@��铁v�ɂ���B
�@�P�Q�����@���Ƒ哿�F�u���@�@�����@���Ƒ哿�v�ƍ�����B
�@�@�@�@�@�@�⑺���̖@���ɓ��Ƃ���������B�u�@��j�v
�@�P�R�푒�ҕs���F���͎��̒ʂ�
�@�@���ʁu�얳���@�@�،o�v
�@�@�E���ʁu�܁����N/����������/�E�E�i���t�j�E�E�E�E�v�@�@�@�����ܔN�i����j1755
�@�@�����ʁu�����E�E�E�E/�E�E�E�E�E�E�v
�@�P�S��遄���l���F�\�ʂ͎��̂Ƃ���B
�@�P�S��遄���l���E�����F�\�ʂ͎��̒ʂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����N�b�Ё@�@1674�N
�@�@���ʁ@�얳���@�@�،o�@��遄���l�i�j�`�Z���j��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㌎�\�ܓ�
�@�P�T�푒�ҕs���F���͎��̒ʂ�
�@�@���ʁF�u�얳���@�@�،o�@�����i�ԉ��j�v
�@�@�����ʁF�w�Ǔǂ߂Ȃ����A�����ѐF�̕ς�����R�s�̍���������B
�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�얳���@�@�،o���E�E�E�E
�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E���z���ׂ��v
�@�@���̑��̖ʂ͖��m�F�B
�����������@�E���ˑ�ړ�
2024/01/05�lj��F
�@���̑�ړ��͕ʖړI��GoogleMap���U�Ă���Ƃ��ɋ��R�����������̂ŁA���ƂȂ��Ă͂ǂ̂悤�ȑ���Ŕ��������̂��͕�����Ȃ��B�i����̍Č����ł��Ȃ��B�j
�@���Ɍf�ڂ���u�@�E���ˑ�ړ��v�̎ʐ^��GoogleMap�ɖ��ߍ��܂�āA���R�����ɂ͑�ړ������݂�����̂Ǝv����B
���ݏꏊ�i�ܓx�o�x�j�F35.74809755069098, 140.51141194286924
�@GoogleMap��ړ��@�@�@�@�@GoogleMap�q��ʐ^
�@�����̎ʐ^�P�������̏���Ȃ��A�ڍׂ͕s���B
2024/01/24�lj��F
���������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�@���A���̏����B
2024�N�O�P���Q�O���A�{��ړ�����������B
�@�����ʁF����Z���q�l���\�O���@�i1756�j
�@�E���ʁF�����R���厛��������@�����i�ԉ��j*
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���@���j
�Ƃ���B
���ʂ͎ʐ^�̒ʂ聃���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�E���ˁ��ƍ��ށB
�Ȃ��A���厛�Q�O���͍��܂ł̗��ł͒m���Ă��Ȃ��������ł���B
�܂��A���a50�N��ɋ����{������V�c�W���ɒʂ���ѓ����J�ʂ��A���̍H���̍ہA�ړ]��]�V�Ȃ�����A���̂��ߔ_���L�ꂪ�ł����ۂɂ����炭���ݒn�Ɉڂ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ̐������q�ׂ���B
�������������厛
���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���
�@�����R�ƍ����B�u��ρv�ɂ͓������N�i1306�j�̑n���A�J�R�����i���R�Q���j�Ƃ���B
���R�@�،o�����B
���݂͎Q�������̍��ɔ�A���O�A���ʂɖ{��������B
���@���ג��ɂ���{���E�ɗ��E�S�q��_���͖����̉ЂŏĎ��A���݂̖{���͖����R�U�N�Č��A���S�P�N���z���ꂽ���́B
�����ɂ͎��̐Γ�������B
�@���@�ܕS�������{���F�R��p���^�E����108�����B
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@��m�A���ʁF���i�S�N�i1775�j�̔N�I�A��ڈ�畔�@�ܕS�����@�\�O���u��
���Z�E�F�������Ȃǂ���
�@�J�R�@�@����
�@�P�P���@�{�o�@�����@����1.5.20
�@�P�W���@���q�@���Z�@����3.5.20
�@2024/01/24�lj��F
�@�@�����s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�����ɂ��A���܂Œm���Ă��Ȃ������Q�O���������i��q�̍��F�����@�E���ˑ�ړ��@���Q�Ɓj
�@�Q�O���@����@�����@����U�N�i1756�j�����̋����@�E���ˑ�ړ����ʂɋL�ڂ���B
�@�Q�R���@����
�@�R�T���@�C���@���P�@����4.2.10
2023/11/29�B�e�F
���݁A���厛�͌�������O��ǂ����ꏊ�Ɉʒu���邪�A�����J�ʑO�͉��Ɍf�ڂ̎O�Ћ{���疭�厛���o�āA�����˂̘e���āA�э��h�тɎ��郋�[�g���Ó��ł������Ƃ����B�i�������s��s�E�˒m�쎁�k�j
�@���厛������ڐ��F��ڂƋ����R���厛�@�ƍ����B
�@���@���F��ڐ��F��ڂƓ��@���F/�����R/���厛�@�ƍ����B
�@���@�U�T�O�����L�O���F�����c���@���F�Z�S�E�����L�O��@�ƍ����B
�@���厛��R���F�S����ǂł��Ȃ��B
�@2024/02/18�lj��F
�@���u�����s��s�j�@�㊪�v�ɖ��厛��ɂ��Ă̑}�G������̂œ]�ڂ���B
�@�@��L��R��̌������č��[�̔�
�@�@�@���厛�����^��ڔ�Q�P�@�@�@�@�@�����^��ڔ�Q�P�}�G
�@�@��L��R��̒����̔�
�@�@�@���厛�����^��ڔ�Q�Q�@�@�@�@�@�����^��ڔ�Q�Q�}�G
�@�@��L��R��̌������ĉE�[�̔�ɂ͖��̍��Ղ͔F�߂��Ȃ��̂Ŋ�������B
�@�������厛�{��
�@���厛���O���F��f�̂悤�Ɂu�Q�������̍��ɔ�A���O�A���ʂɖ{��������B�v�Ƃ�����A���݂͏��O���Ȃ��́A���O�Ղł��낤�B
�@���@�P����Q���@�@�@�@�@���@��m�T�O�O�������P�@�@�@�@�@���@��m�T�O�O�������Q�@�@�@�@�@�R�T���C���@���P���
�@�c�R��\�Z����������F���ʁF�r���@���������c�R��\�Z���A���ʁF�����Q�P�N�叜�X���T���̔N�I
�@�@�����R�Q�U���Ƃ��邪�A���厛�Q�U�����ǂ����͕s���B
��������������
���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���
�����O�̕�n�Ɂu����R�@���@�O�\�����[��@���v�Q�N�i1863�j�v�ƍ��܂ꂽ���{�肪����̂ŁA���̕t�߂ɑ��݂��B
�A���A�V���T�N�́u���@�{�����v�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��B
�@�������O�̏ꏊ���s���Ŗ����B
�����������O�А_��
���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���
�Ր_�̓A�}�e���X�E�����_�E�t�����_
�����A�萅�ɁA�Γ��āA�q�a�A�{�a������B�萅�͊����P�O�N�̖��A�Γ��U�͕����Q�N�̖��A���c�@�Q�Q�����P��@�ȂǂƂ���B
2023/11/29�B�e�F
�@�����O�А_�Дq�a�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�P�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�Q�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�R
�@�O�А_�Ж{�a�S�@�@�@�@�@�O�А_�Ж{�a�T�@�@�@�@�@�O�А_�Г��c�_�i����j�F���ۏ\���p�q�N�i1732�j�̔N�I������B
������������ړ��Q
���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���
���̂悤�ȐΓ��ނ�����B
C.�������q���{���F�R��p���^�E����144�����B
�@���ʁF�����c���q�A�@���ʁF���������сi1825�j�\����������
�@���i���ʁF���v�R�@�����@�P�O���̖��A�@���i���ʁF��絁@���c�@�⑺�@�쓇�@�{���@�l�����@�E�l
�@���i���ʁF��x�@�Ўq�@���R�V�c�@�э��@�P�P���̖�
D.���N���{���F�R��p���^�E����235�����B
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�얳���N��F/�����N�i1320�j�M�\/������\���
�@���ʁF�ێ��@�����Ȗ��i1859�j���~�Ō�ܕS�l�\�N/�E�E�E�E�E
�@���i���ʁF�э��`�����̂T�V�����̑������L���B�@�@���i���ʁF����`�@�̑������L���B
E,���@�Z�S�������{���F�R��p���^�E����238�����B
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@���F/�O���T�N�p��/�P�O���P�R��
�@���ʁF��N����ڎ���k�C�Z�S������/�E�E�E/��������K�N�i1855�j�O������/�E�E�E
�@���i���ʁF�э��`����̂P�T���̑������L���B
F.�������{���F�R��p���^�E����227�����B
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�얳������F/�N�i���N�p��/�\�ꌎ�\�O��
�@���ʁF�l�S�\�������A�����ݔN��O�h��V�H��/�ߑ��M�j���u��/��ڍu��
�@���i���ʁF���R�`���т̂T�O�����̑������L���B
���u�x���T�K�@�P�U�W�F����������@���N�̐Γ��v�x���s�A�˒m����@���
�@���N��l�͉������N�����̒n�ɐ��܂ꂽ�Ƃ����B
���N�͘Z�V�m�̈�l�Ƃ��Ċ��A��̓��N�嗬�̌��ƂȂ�B
���N�̖��͊֓��E���s�ɑ����̎��@���J���B�A����q�����͋��s�ɕz�����ʂ����A����ɂ��̒�q�����i��o��m���j�͐����ɑ����̎��@���J���B���̈Ӗ��ł͊�����O�̕s��s�{����{�I�ɂ͂��̓��N�嗬����h������B
�@���l�������̕_���ł����[�����i������䶔����E�l�������_���j�ɂ͎l�������Q���ł�����N���{��������B
�@�����O�y�є����쓌���ɂ͚삵����o��m���𒆐S�Ƃ����ړ������@�����E�c�t���E�H�T�ȂǂɌ�������Ă��邪�A
�@���N�����@�E���N�E�����E��o��m���i�����j�ƃZ�b�g�ł��邢�͒P�ƂŐ������J���Ă���B
�@�@�@���ȏ�̗l���ɂ��ẮA�R�z�����̓��@�@�����E�c�t��/��ڐΓ��̃y�[�W�̎Q�Ƃ���B
�@�@�@�@���̃y�[�W�Ō��������J���iCtrl�L�[�@+�@F�L�[�j�ŁA���N�̌�����Ō�������B
���̓��N�Ɋւ���Γ������x���s�ɂQ���i�����y�ѓ��R�V�c�j����B
�����ɂ͈����U�N�i1859�j���N���T�S�O�N�Ɍ�������A��ɂ͍���S�̂U�O���鑺�������܂��B�����ɂ��铯�����̑��̐Γ��ɂ������悤�ɑ����̑�����������B
����͊e���ɂ́u��ڍu���v������A���̗͂����W���Č������ꂽ���Ƃ������B
�߂��ɂ͒h�Ƃ������Ȃ���������A�����ő�ڍu���s���A�����ōs����э��h�т̔\���Ȃǂ̍u���ł̐��@�̕]�����L�܂�A�e������M�҂��Q�W�������̂Ɛ��������B
�@�Ȃ��A�����̑�ڐΌQ�ɂ͐̋ʊ_�����邪����͏��a�Q�V�N�Ɂu�э��g�ꕔ��ڍu�v�������������Ƃ��和�ɂ���B
�@���R�V�c�ɂ�����N���{���͎R�ђ��ɂ���A���ʂɁu���N��F�v�ƍ��݁A�������N�i1748�j�Ɂu���R�V�c���@�u���j���v�������L�Ƃ���B
�߂��Ɍc�����N�i1648�j�J�R�̌c����������A���Ɠ������h�Ƃ͂Ȃ��������э��h�т��猎�P��قǑm�������Đ��@�����ƋL�^����Ă���B
2023/11/29�B�e�F
�@��f�́u�����s��s�j�v�ŋ�����ꂽ��ړ��iC�AD�AE�AF�j�ȊO�ɂ����̑�ړ��iA�AB�AG�AH�AI�j������B
A.�L��������ړ�
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�L�������@�E/�얳����A��/�얳�ޔ@��/�E�E�E�E�E
�@���v��p���N�i1862�j�E�E�E�̔N�I���ǂݎ���B
B.�@�،o���ݕ���
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���ݕ���/���������㐶�P�|/�ȓ���ٗ����w�b
�@���ʂɂ͊�i�҂̖��O�▾�����ܔN�Z���̔N�I���ǂݎ���B
G.���@��ړ��i�s���j�F�얳���@�@�،o�@���c�������E�E�E�Ƃ��邪�A���Ǖs�\�B
H.�����J�@���S�N��
�@���ʁF�얳���@�@�،o�E�����E�����J�@���S�N�c�]�L�O���@�Ƃ��邪�ꕔ���Ǖs�\�B���@�@�����J�@���S�N�ł���Ȃ�A����͏��a�Q�V�N�ł���B
I.�@�،o���ݕ����i����j
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�ݕ����F�ݕ����͐���A�c�]�̖��͔��ǂł����B
������������ړ��Q
�@����������ړ��Q�P�F�������ĉE����A.�L��������ړ��i�E�[�Ŕ����̂ݎʂ�j�AB.�@�،o���ݕ����AC.�����c���q�AD.���N���{���AE.���@�Z�S�������{�������ԁB
�@����������ړ��Q�Q�F�������ĉE����D.���N���{���AE.���@�Z�S�������{���AF.�������{�������ԁB
�@����������ړ��Q�R�F�������ĉE����F.�������{���AG.���@��ړ��i�s���j�AH.�����J�@���S�N�������ԁB
�@����������ړ��Q�Q�|�P�F��O�Q�c�ڂ���AF.�������{���AE.���@�Z�S�������{���AD.���N���{�������ԁB
�@A.�L��������ړ��P�@�@�@�@�@A.�L��������ړ��Q
�@B.�@�،o���ݕ���
�@C.�����c���q���F�������q�͗l�X�ȐE�l�B�̐M�̑ΏۂɂȂ��Ă���B���̗��R�͕s���Ȃ���A���q�͎��@�����ɒ��͂������Ƃ�A�Ȏڂ��i���邢�͗A���j�������ƂȂǂ����̗R���ł͂Ȃ����Ɖ]����B
�����A�A���ʉ��A�w���t�A�ȕ��t�A�،^���A�A�����A�����A�������A����A��ˉ��A�[�A���A�b�艮�A�H�Ȃǂ��u���q�u�v������Ă��J�肷�邱�Ƃ��e�n�ɂ݂���B
�@D.���N���{���P�@�@�@�@�@�@D.���N���{���Q�@�@�@�@�@�@D.���N���{���R�@�@�@�@�@�@D.���N���{���S
�@E.���@�Z�S�������{���P�@�@�@�@�@E.���@�Z�S�������{���Q�@�@�@�@�@E.���@�Z�S�������{���R
�@F.�������{���P�@�@�@�@�@�@F.�������{���Q�@�@�@�@�@�@F.�������{���R
�@G.���@��ړ��i�s���j
�@H.�����J�@���S�N��
�@I.�@�،o���ݕ����i����j
���������v�R--------------------
���������v�R�O���V��ړ�
�ܓx�o�x�F35.7520638081645,
140.52274255258968�@�ɏ��݂���B
�э�������l�˂Ɠ��S�S�����@�˂̊Ԃ�ʂ錧���P�U���i���������s����j��k�サ�A������l�˂���}��350���قǂ̒n�_�œ��H���ɂ���B���̕t�߂͂P�U���������v�R�Ə����̋��E���ł��邪�A�����͈��v�R�ł���B
�@�Ȃ��A���̑�ړ��́A���x�ƂȂ����̕t�߂𑖍s���������܂ŋC�Â��Ȃ������Ƃ����������s��s�E�˒m�쎁�����R�u�����v�������̂ł���B
2023/11/30�B�e�F
���v�R�O���V��ړ��F
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@��O���V�@�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�u��O���V�q�v���邢�́u��O���V���v��������Ȃ����A�u�q�v�������́u���v�͐̃L�Y�̉\���������B
�@���ʁF�O���O���߁i1846�j�E�E�E�E�؉��@�Ɠǂ߂�B���̑��̕������������悤�ł��邪�A���Ղ��č��Ղ���Ȃ��B
��ʓI�ɂ́A�O���V�i�O���V�q�j�́A���V�i���z�j�E���V�i���j�E�����V�i���j�̎O���������B
�@�����͂��̑�ړ��P����ł��邪�A����1��画�f����A�����A���v�R���邢�͂��̎��͂̑��X�́u��ڍu���v���A�O���V�Ɍ܍��L�����F�肵�����̂ł��낤�Ɛ��������B
�@�Ȃ��A�O���V���Ƃ������Ƃł���A���������ŏ��ׁi�������j�y�т��̈ꕔ�̖����Ɂu���a�v�u�a�C�����v�̏��V�Ƃ����J���邪�A���̎O���V���Ƃ����\���͒Ⴍ�A��͂�O���V�i�O���V�q�j�Ƃ��ׂ��ł��낤�B
�@���v�R�O���V��ړ��@�@�@�@�@�O���V��ړ��E�\���@�@�@�@�@�O���V��ړ��E�����F�O���O���߁i1846�j�E�E�E�E�؉��@�Ɠǂ߂�B
���������v�R����
���u�����s��s�j�@�㊪�v���a�T�V�N�@���
�@���v�R���Î��ɂ͂Q�O��߂��肪�������A�j���I�ɂ����@�@�ւ̉��@�����t������B
�`���ł͚��Î��͂��Ƃ��ƈ��v�R���Ƃ����A�^���@���@�ł������Ƃ����B���鎞�A���R�R�����S�����̒n��K��A�����������A�Z�E�o�_�����S��q�ƂȂ�A���@�@�ɉ��߂��Ƃ����B
�@�����̔�Q�ɂ͓��@�@�ɉ��C���ꂽ��Ɍ������ꂽ��ڔ�ɍ������ĂV��̎�q�肪�c��B���̓��̂P��ɂ͍O�����N�i1278�j�̔N�I������A���̂��Ƃ͚��Î��͓��@�@���@�O�A�������@�ł��������Ƃ������B
�@�����R�N�i1331�j��t����ɂ���Ĉ��v�R���̓��E�E�Ɠc�T�i�����R�Ɋ�i���ꂽ���A����͕��c���߂������������̈ӌ��ɉ��������̂ł��낤�B�������̓��@�@�ւ̋A�˂ɂ��A���v�R���͑�ڔ�̌������ꂽ���S�N�i1341�j���ɂ͓��@�@���蒅�������̂ł��낤�B
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
���v�R�ƍ����B���R�@�،o�����B���v�R�������E�������Î����]���B
�Q�����ɔ�Q�A���ʂɔ��f���i�͂�����E�c�t���j�A�E�@�ɏ��O�A���ɖ{��������B
�P�X�����i�ɂ��A���ۍ��ɋq�a�E���O�E�ɗ����V���A�{�����C�������B
���
�J��@��s�@���S�i���R�O���j
�P�T���@��暉@���_�F���\9.11.28��A�V�U�A���\�@��_�Ó����߁A���v�R�ɉB���悠��B
�@�@�����v�R�̉B����ɂ��ẮA�����Ɍf�ځB
�@�����̑��̗��͊���
������
����畔���ّ�ړ��F����92�����F�얳���@�@�،o�@����畔����/�勝�R�N�i1686�j/���v�R���ꌋ�O
���@�ܕS�������{���F����108�����F�얳���@���F/���i�U�N�i1777�j
���@�ܕS�\�������{���F����149�����F�얳���@�@�،o�@�ܕS�\�䉓���@���@���F�@�@���/�����P�R�N�i1830�j
���v�R�@�E���ˑ�ړ��F������ړ��E����124����
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�E���ˁ@�E�E�E
�@���ʁF�������f�����N�����S��l����������@�E�E�E
�@���ʁF�E�E�E�@���P�O�N�i1760�j�E�E�E
��
�����s��s�w���͑S�ĉ����^��ł���B�܂��{���̔�͎�q��Ɠ얳���@�@�،o�����ޑ�ڔ�̂Q��ނɋ敪�����B
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@���Î��@�E���ˑ�ړ��F������ړ��F��d�ɂ́u�y�{�呺���v�Ƃ���B
���͑�ڔ�ł���B
���݂ɔ�Ƃ͒��������Ŏg��ꂽ���{���ł���A�S���ɕ��z���邪�A���̑����͊֓��n���ɕ��z����Ƃ����B
�����āA���̕��z�n��͊��q���m�̖{�ђn�ł��������Ƃ������A�����̕��m�̐M�Ɉˋ��������̂ƍl������Ƃ������B
�܂��A���̌��������͊��q�����玺�������ɏW�����A��k�����ȍ~�͎p�������B
�@��̎�ނł��邪�A���̕��z�̈�Ǝg�p����ނ̍ގ�����A�傫���͕����^�Ɖ����^�Ƃɕ�������B
�����^�͒����E���Ғn������Y�o�����ΐF�Њ�Ƃ����݂��������ށi�j�ő���ꂽ���̂������B
�����^�Ƃ͎�ɏ헤�}�g�R����Y�o����鍕�_��Њ�̔�������B
�Ȃ��A�u�����s��s�j�@�㊪�vp.894~�ɂ́A���v�R���Î��ɂ����́u�}�G�v�Ȃǂ̌f�ڂ�����̂ŁA�Q�Ƃ���B
���āA�~�Î������ɂ͈ȉ��̔肪����B
�@2024/02/18�lj��F�u�����s��s�j�@�㊪�v���}�G��]�ڂ���B
�@�����^��ڔ�(12)�F81�~80�~�W�A���a�T�N�i1356�j�̔N�I
�@�@�@�@���@��@�}�@�G
�@�����^��ڔ�(16)�F99�~49�~9�A�N�I�Ȃ�
�@�@�@�@���@��@�}�@�G
�@�����^��ڔ�(8)�F103�~70�~10�A���Q�N�i1339�j�̔N�I�A���E�ɓ얳���@�@�،o�E�E�E�ƍ����B
�@�@�@�@���@��@�}�@�G
�@�����^��ڔ�(11)�F94�~92�~11�A�N�i�Q�N�i1343�j�̔N�I�A���E�ɓ얳���@�@�،o�E�E�E�ƍ����B
�@�@�@�@���@��@�}�@�G
�@�����^��ڔ�(10)�F92�~79�~6�A���S�N�i1341�j�̔N�I
�@�@�@�@���@��@�}�@�G
�@�����^��ڔ�(13)�F76�~94�~12�A�N�����N�i1361�j�̔N�I
�@�@�@�@���@��@�}�@�G
�@�����^��ڔ�(18)�F85�~50�~10�i����́A���@�ʂ��炳��ɉ����P/4�����������Ǝv����j�A�N�I�s��
�@�@�@�@���@��@�}�@�G
�@��ڔ�ł́A�ȏ�̑��A�������u�����s��s�j�@�㊪�v�Ɏ��̂U��̑�ڔ�̑}�G��ʐ^���f�ڂ����B
�����^��ڔ�(9)�A(14)�㕔���A(15)�A(17)�㕔���A(19)�\�ʂقڔ����A(20)�E�㕔��1/4�̂ݎc���@�̂U�����B
���̂U��ɊY��������̂����ł���B
�@�c�]�̉����^��ڔ�P�@�@�@�@�@�c�]�̉����^��ڔ�Q
�@2024/02/18�lj��F�u�����s��s�j�@�㊪�v���c�]�̑}�G��]�ڂ���B
�@�@�A���A(20)�ɂ��Ă͓]�ڂ��ȗ�����B
�@�@�����^��ڔ�(�X)�}�G�@�@�@�@�@�����^��ڔ�(14)�}�G�@�@�@�@�@�����^��ڔ�(15)�}�G
�@�@�����^��ڔ�(17)�}�G�@�@�@�@�@�����^��ڔ�(19)�}�G
��q��ɂ��ẮA�u�����s��s�j�@�㊪�v�ɂ͉��̂Q����܂ލ��v�V��̎�q��̑}�G��ʐ^�̌f�ڂ�����B
�@�����^��q��
���Î��Γ���
�@���Î��Γ����F�ȉ��̂T��̐Γ��ނ�����B
�@�A���A�����Ɍf�ڂ̂R��́A�������ǂ���A���ʂȂǂ����m�F�Ȃǂ̗��R�ŁA
�@�Ǘ��l�is_minaga)�̌�F��������\�������邱�Ƃ����f�肵�Ēu���B
�@���@��l��ړ��F�\�ʂ́u�얳���@�@�،o�@�얳���@���F�v�Ǝv������s�m���B
�@���@�ܕS�\�������{���F�{�ʐ^�̐Γ������@�T�T�O�������{���ł���Ƃ͕s�m���ł���B
�@����畔���ّ�ړ��F�\�ʂɁu�얳���@�@�،o�@����畔���فv�ƍ�����Ǝv������s�m���ł���B
�@�c���J��@���S���l�F���ʂ̖����ɂ��Ắu�����s��s�@�㊪�vp.590�ɂ���B�{��͂P�X���E�҉@���i�B
�@�@�܂��A�����E���y�[�W�Ɂu���S���l�l�S�������{���v�i�݁E���v�R������n�j�̖@�ʁE���Ƌ��{���̎ʐ^�̌f�ڂ�����B
�@�@���v�R������n�͕s���A���{���͖����B
�@���@�ܕS�������{���F�قڊm��
�@�ȏ�Ƃ͕ʂɐV�����A���@�V�O�O�������F���a�T�W�N�����@������B
��������
�@���Î������@�@�@�@�@���f���E���O�@�@�@�@�@���Î����f���@�@�@�@�@���Î����O�@�@�@�@�@���Î��{���@�@�@�@�@���Î��ɗ�
���������v�R�B����F
�@�i��暉@���_�E���S�@���B�j
���u�x���T�K���P�Q�O�@���v�R������@�B����v�������s��s�E�˒m����@���
�@�B����Ƃ́A�]�ˎ��㖋�{���犈�����ւ���ꂽ���@�@�s��s�{�h�Ƃ����@�h������A���h�ł͒T���ꍡ�ɓ`���m����M�҂̕�������Ă�ł���B
�@�����Ò��S���אڂ��鋌�����s��s�э��n��E�g�c�n��E�ђ˒n��Ȃǂ⋌�I�����̑�E�╔�E���тȂǂ̑��X�ł�200�N�߂��ɓn��A���̐M���������Ă����B
���v�R�ɂ����̉B���悪����A����͋�����n�̉��܂����؉��Ƃ̕�n�ɂ���B
�P��͎�暉@���_�i������120�����j�̂��̂ł���A���_�͓��̐��܂�ŁA���߂ƂȂ�O�N�ɋt�C�������āA�ߔ������Q�����O�ɉ������V�c���ł̊������m����B
�����P��͐��S�@���B�i������60�����j�̂��̂ł���A���B�͈��v�R���܂�ŁA�O��֗��߂ƂȂ�A���\�S�N�i1691�j�U�O�ɂĎ₷��B����̒m�点���A�����ɕ擃�����Ă����̂Ǝv����B
���u�[�����@��j�v�@���
�@����暉@���_�F���\9.11.28��A���\�@��_�Ó����߁A���J���鎛�o���A���v�R�Z�A�����܂�B
�@�@�Ȃ��A���_�͈��v�R���Î��P�T���Ɖ]���B�i����̈��v�R���Î����Q�Ɓj
�@�@�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�F
�@�@�@�㑍���J���鎛�E���v�R�����ɋ��Z�A�@��Q�x�A�_�Ó��ł͐��S�@���ׂƓ������œ����B�����@�Ƃ��Ԃ�B
�@�@�@�Ȃ��A���S�@���ׂ͋g�c��˂��Q�ƁB
�@�����S�@���B�F���\4.11.9��A���\�@��O����߁A���v�R���܂�B
�@�@�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�F
�@�@�@���S�i�M�j�@�@��i��j�F�@���B�A���\�S�N���\�@��Ŕz���A�Z���s��A����֊Џ�����B
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@�u���\�@��v�̍��ip.204)�Ɂu��暉@���_�̖{���v�̌f�ڂ�����̂ŁA�]�ڂ���B
�@�@��暉@���_�̖{���F���\�S�N�i1691�j�Q���A�������F�؏��i���q�偡�����Â��j�E�E�E�i�j���͕s�m��
���t���画�f���āA���\�@��ŕߔ�����钼�O�Ɏ��^���ꂽ�֑ɗ��{���ł��낤�B
2024/02/23�lj��F
�@�����o���Γ����Ɏ�暉@���_�̋��{������B
�@�@���R�j��ʉ@���B�E��暉@���_�Γ�
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@���v�R�B����ʒu�}
�@�ܓx�E�o�x�G35.74753712177687, 140.51914786869898
�@���v�R�؉��ƕ揊�F�������ĉE���玩暉@���_�擃�A���S�@���B�擃�@�@�@�@�@��暉@���_�E���S�@���B�擃
�@��暉@���_�t�C���@�@�@�@�@��暉@���_�t�C���Q�F�w�ǖ����ǂݎ��Ȃ��B�����Ɋւ��鎑���͑S���Ȃ��B
�@�@�]���āA�{����_�Ƃ��鍪���͎������킹�Ă��Ȃ����A�@�{����暉@���_�Ƃ��鍪���́A
�@�@��q�u�u�x���T�K���P�Q�O�@���v�R������@�B����v�Ɏ�暉@���_�E���S�@���B�擃�̎ʐ^���f�ڂ���A
�@�@���̉�����Ŗ{����暉@���_�̕擃�Ɖ������Ă��邱�Ƃł���A���ꂪ�B��̍����ł���B
�@���S�@���B�擃�����F���@�@���S�@���B�o�ʁ@�@�@�@�@���S�@���B�擃�����F���\�l�h��
�@�؉��揊�ɂP���̑�ڔ肪����A�����́u�얳���@�@�،o�@���@���i�F�j�v�Ɠǂ߂邪�A���E�͑S����ǂł��Ȃ��B
�@�؉��ƕ揊���@�@�@�@�@�؉��ƕ揊��Q
���������v�R�̐Α����i���c�_�j
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@���c�_�͎��n�C���̘H�T�ɂ���B�i���n�C���͉~�Î��̂���J�n�̎��Ƃ����j
�}�t���K�A����55�����A���ʂ́u���c�_/���ۏ\��b�Џ\�ꌎ��/�{��@���E��v�ƍ��ށB
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@���v�R�n�C�����c�_�F���c�_�A���ۏ\��E�E�E�̕������ǂ߂�B
����������--------------------
����������������
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@����R�ƍ����A���R�@�،o�����B
���`�ł́A�Â��͎R�����ł��������A�i�\�N���i1558~70�j���W���J�R���A�������Ƃ����Ƃ����B
�u��ρv�ł͓V���R�N�i1578�j�̑n���Ƃ����B
�u���@���ג��v�ł͋����S�Q�O�A�h�k�Q�V�l�Ƃ���B
�R��O�ɖ和������A�R������Ɛ��ʂɖ{���A���Ɍɗ�������B
�����Α���
��@���F136����
�@�@���ʁF�@�@��ڎ��畔/��ܕS�������
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@��m�@����R
�@�@���ʁF�@�@���i���Ȉ�i1779�j�@���ȉ���
�@�@�@�@�@�@���Ɏʐ^����B
��ړ��F119����
�@�@���ʁF�@�@�畔�@���ێO�@���V�@�\�O�u���@�@��1743�N
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�얳���@��m
�@�@���ʁF�@�@���A�@�O���\�O���@�@������
�@�@�@�@�@�@�@����
�J�R���F93����
�@�@���ʁF�@�V���Z���ЎO������
�@�@���ʁF�c�R�J��@�{���@���P���l/����R�������m��������
�@�@���ʁF���������\�O���q�\�����{�@�y�����ޑ��V�@�@�@��1816�N
�@�@�@�@�@�@�@����
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@���@�T�O�O�������i�和�j�@�@�@�@�@�����������R���@�@�@�@�@�����������{���@�@�@�@�@�����������ɗ�
�@�������������擃�F���邢�͂����ɊJ�R���E��ړ�������̂����m��Ȃ��B
�@�P�Q�������@���M�F�c���\�@�����@���M/����/�S��/���ی��N�\���O��
�@�P�U�����R�@���d�F���ۂV�N��@�@�@�@�@�P�V�������@�����F���Q�N��@�@�@�@�@�Q�O�����O�@�����F���P�O�N��
�������э�--------------------
�������э����~��l�ˁi�����_���j
�@�������h�ъJ�u�E�J�c�d�_�@���~���ɂ���
�������э����S���l�S�����@��
��Ȃ��̂ŁA���Ɍf�ڂ́u���n�����v�ő�p����B
2024/02/18�lj��G
�u�����s��s�@�㊪�v���
���S��l�˂ɂ���
�u�V�ҁ@�э������y���v�F
�@�˃n�厚�ђ˂ɍ݃��A�����V�ԓ�k�U�ԁA�ˏ�j��A���A���R�ڂT�����P�ڂT���A���ۓєN�P�O���A�m�ʌ������c�g���Z���A���m�˃n���S��l�S�����@�L�O�˖�E�E�E�i�ȉ����j�E�E�E�E
�u����S�j�v�F
�@���������l�ˍk�ޒ��ɕ�擌���V�ԓ�k�U�ԏ�ɓ��������R�ڂT�����P�ڂT���\���S���l�S�����@�˂Ƒ肵���̗��Ӌy�щ����ɔэ�ᥕ��t�������J�R�]�X���̌����艝���叼�����肵���͞ǂ��苝�ۓєN�P�O���A�m�ʌ��Ȃ���́T����Ƃ���Ȃ�`�֞H�ӑm���ɕS���Ԃ̐��@���ׂ����@���O�߂��ƞH��
�@���uv�́u�A�v�E�u�d�v�َ̈��̂��邢�́u�A��v���Ӗ����銿���ł���Ƃ����B
2023/11/29�B�e�F
�@���S���@�ˌ��n�������@�@�@�@�@���S���l�S�����@���F�Õ��𐮌`�Ƃ���B
�@�S�����@�ːΔ��@�@�@�@�@�S�����@�ːΔ�E�㕔�@�@�@�@�@�S�����@�ːΔ�E����
�@�S�����@�ːΔ�E�����F���ۓсi1717�j�G�~���@�Ƃ���B
�@�S�����@�ːΔ�E�����F�{��B�m�ʌ���O���c�V�@�Ƃ���B
�@�@�{��͉B�҂̒ʌ��ŁA���̐Δ�̌����ŏO���i�l�X�Ȉ����j����Ƃ����ӂł��낤���B
�������э��h�сi�э����j
�@�������э��h�сi�э����j���э��h�я����˂����聄
�������э��@�؎�
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�u���`�v�ł͊J�R��Z�V�m�������邢�͓��E�Ƃ���B
�u���@���ג��v�ł͌c���N���ɓ����������J��Ƃ���B�{���͂T�ԂR�ځ~�S�ځA�����X�O�A�h�k�S�W�l�B
�u���@�{�����i���R�@�،o���h�����@���j�v�ł����R�@�،o�����Ƃ���B
���݂͏����i���������݂͑ޓ]�j�ƕ�n������̂݁B�L�^�ł͋q�a�����������A�������ЂŏĎ��B
���F
�@�����@��v�@�����@����R�N�����Q�Q����
�@�@�i�ȉ����j
�����Α���
�����@�T�T�O�������F����103����
�@�@�@�@�@�ܕS�\�������
�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�@�@�@���R�@�؎�
�@�@�i���ʁj�{��@�y�h���������㕸���G�\�l���@�ɑ��@�@�@�@�������X�N�i1826�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�J葉@����M���@�@�\�O�{��@�����i�ԉ��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����p���i�T�N�j�����\����@���R�d���q��
���i�㋟�{���F���R�A����130�����@�E�E�E�E�E��������
�@�@�@�@�@�@�@�����i�����������@�@�@�@���ۏ\�l�с@�@�@�@�@�@�����ۂP�S�N�i1729�j
�@�i���ʁj�얳���@�@�،o�@�@����@�@���@���z�i�ԉ��j
�@�@�@�@�@�@�@��X����������@�@�@�@����@���s
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@���@�T�T�O�������E�����@�@�@�@�@���@�T�T�O�������E�����A�����͏�Ɍf�ځB
����GoogleMap���]�ڎʐ^
�@�@�؎��Սq��ʐ^�F2024�N�Ƃ���B
�@�@�؎����菬���F�B�e����2017�N5���ƕ\������Ă���B�����炭���͑ޓ]���Ă��鏬���̎ʐ^�ł��낤�B
���ۉȐ����̕�F�ݖ@�؎�
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@�ł͎��̂悤�ɉ]���B
�@�����͓V���P�W�N�i1590�j���Âɓ]���������̑]�c���ɂ�����A���V���P�X�N�X���W���ɐ����B
�ۉȎ������Â�̂����̂͋͂��P�P�N�ŁA�c���V�N�i1602�j�M�B�����ɓ]����B
���������ÂɏZ�������A�`���̂悤�ɖ@�؎��ɉB�������̂��͕�����Ȃ��B
���̕�͌��\�R�N�i1690�j�э��h�тT�Q������Z��@�����ɂ���čČ�����Ă���B�����ƕۉȎ��Ƃ̊W�͕s���B
�@�@�@�@�������F�@�э��h�����́u�э��h�ї��擃�v�̍��ɋL������B
�@�@�@�@�������̕擃�ʐ^�F���t�@�ޑc�E����
�@�ۉȐ��������擃�P�@�@�@�@�@�ۉȐ��������擃�Q�F�������č����ˉ_�a�@�擃
�@�ۉȐ����擃�E�����F�ˉ_�a�@�@�@�@�@�@�ۉȐ����掺���E�����F�����@�a�@�E�E�E�E�E�����͂������Ɍf�ځB
���u�����蒠�i�P�j�ۉȐ����v�w�̕�v�����ǒ��ׁi�u�����s��̗��j�Ɩ����@��Q���v�����s��s�j�҂���ψ���A���a�T�Q�N�@�����j�@���
�@�@�؎�������n�̈���ɕۉȐ����v�w�̕�肪����B���ł��@�؎��h�Ƃ̐l�X�ɂ���ċ��{����Ă���B
�{�n��ɂ͕ۉȎ��̑��Èڕ��i�V���P�W�N�j�ɂ��A�������ꑰ�Ƌ��ɑ��ÂɈڂ�A�B�����Ƃ��ĉB�����Ƃ��Ė@�؎��ɏZ�݁A�����ŖS���Ȃ�A�����Œh�Ƃ̐l�X�͋��{���c�ݑ����Ă����Ƃ̓`��������B
�@�������A���̓`���𗠕t����j�����R�����A�܂����_������B
�����͎��̒ʂ�ł���B
�@�ډ_�@�a�����F�ۉȐ����@�@�@�@�@�����@�a�����F�ۉȐ�����
���̒ʂ�A���͌��\�R�N�i1690�j�̍Č��ł���B
�������ɂ́u��Č����\�O�M�ߔN�C����u�V�v���邪�A���̍Č������C���Ƃ́A�u�����N���v�i�э������������j�ł́u�t���������C�����Z��@�v�Ƃ���B
�����͔ђ˒h�тT�Q�㉻��A��̋��s������h�_�ɓ]���A�������N�J������B���t�@�ނ��N���B���q�������B
�����������Ƃ���A�э��ݏZ���A�������ĕ����Č������ƍl������Ƃ����B
���āA
�ۉȎ��̒��n�͎��̒ʂ�ł���B�u�����d�C���ƕ��v�Ȃǂɂ��B
���������������r�����������������������V�i�䓿�@�a���q�Őe�ˉ�Ï����ƂƂȂ�j�E�E�E�������e��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@���ۉȎ��͐M�Z����S�ۉȂɔ��˂���Ƃ����邪�A��������܂Ŗw�ǎj�����Ȃ��A�����E���r���m���邱�Ƃ͕s���Ɖ]����B
�Ȃ��A�u�����d�C���ƕ��v�ł͐����́u�e�����@�}���@�V���P�X�N�i1591�j�X���U�������@�@���h���v�Ƃ���A���r�́u�e�����@�}�O��@���\�Q�N�i1593�j�W���U�������@�@�����^�v�Ƃ����A����́u�}�O��v�͐��r�ɊY�����A�����́u�}���v���ꗂ�����B
�������u�����d�C���ƕ��v�ł͐����́u�V���P�W�N�i1590�j���ÂɂĈꖜ�������A�c���T�N�i1600�j���Â�]���A�M�Z�����̋��̓ܐ�������v�Ƃ���B
�@�������āA�u�M�Z�j���v�ɂ͉]�X�̋L�ڂ����邪�A�Ӗ��s���ɕt�A�L�ڂ��ȗ��B
�@�ȏ�ԉH���̔��\�_���ɂ��B�i���ԉH���_���Ƃ͕s���A�܂��ȏ�Ƃ͉����܂ł��w���̂����s���j
����ɂ���A�����Ŗ��ƂȂ�̂͐����y�ю������ÂɈꑰ�ƂƂ��ɈڏZ�������ǂ����Ƃ����_�ł��邪�A�i�ԉH���́j���ÈڏZ���m�肵�Ă���B�܂�A�ۉȎ��̑��Èڕ��͓V���P�W�N�H�ł���A�����̎��͓V���P�X�N�H�ł���A�悪�э��i�@�؎��j�ɂ��邱�Ƃ���A�����͍������瑽�ÂɈڏZ���A�Ԃ��Ȃ��������A�����đ��Âɂ�����B���������̖@�؎��ł������ł��낤�Ɛ������Ă���B�܂��������͕�����A�����ւ͋A�炸�A�@�؎��şf�����̂ł��낤�Əq�ׂĂ���B
�@����A�ԉH���͂��̘_���ŁA�����͕S�]�Ŗv�������ƂɂȂ�e�q�S��ő��ÈڏZ�͗L�蓾�Ȃ��Ƃ̔ے�_���q�ׂĂ���B
�@���ԉH���_���Ƃ����̂��s���ł���A�_�|���ǂ�������Ȃ��B
���������ς̖k���ʒj������́u�����E���r�ɂ��Ă͋^��_�������A���m�Ȃ��Ƃ͖w�Ǖ������Ă��Ȃ��A�����E�����̑��ÈڏZ�͎j���I�ɂ͗��t�����邪�A�����E���r�ɂ��Ă͕s���ł���v�Ƃ̘A������B
�@�������̎��͌c���V�N�ŁA�ۉȎ��̍������A�͂��̑O�N�ł���A�ʂ����Đ������͈�l���Â��邢�͖@�؎��Ɏc���Ă����̂ł��낤���B�����A�������@�؎��ɉB�����Ă������邢�͋F�菊�Ƃ��Ă������Ƃ͍l�����邪�A�j���͂Ȃ��B
�܂��A�������@�؎��ɑc�������̕�����ĕ������\�����l�����邪�z���̈���łȂ��B
�����͑��Â��獂���Ɉڂ��ĊԂ��Ȃ��c���U�N�������Ă���B
�@�ԉH���ɂ��ƁA
�u�����E���r�̕�̂��鍂���������i�ՍϏ@���S���h�A�����Ɍf�ځj�̕�n�ɓ������区�P�����������̕���Č������v�A���̕���ɂ́u���\�O�M�ߍ㌎�\�Z���@�@�ӎ���Č��V�v�Ƃ���A����͖@�؎��̐����y�ю��̕����u��Č����\�O�M�ߔN�C����u�V�v�ƈ�v����B
����͋��R�̈�v�ł͂Ȃ��A�����̉�Ï����ˎ�ۉȐ��M�i��ɐ��e�A���V�̑��A�R��ˎ�j�������̐����̕�Ɠ����ɔэ��̐����y�ю��̕���C���ɖ����čČ����������̂ł͂Ȃ����Ǝw�E���Ă���B
���R�@�؎��Ɋւ��āF
�@�͂��̕�n�Ǝ��@�ՂƂ��̈�p�ɂU�ԁ~�R�Ԕ����炢�̐V�������i�W����j�����邾���ł���B
�u�ߋ����v�ł͓��E�i������j���J�R�Ƃ��A���������J�R�����̒�q�ł���A���E�̌�A�����E���C�E���G�ƕ��������̗�������ނ��A�n�������q�����Ƃ���͔̂��ł͂Ȃ����B
�@�@�؎������Ɂu���N�������̂悤�ȕ����v������A�v��Ɓu�V���N���A�ۉȒe�����̕�ƂȂ�A�ۉȐ����̎������������V��@�؎��ɔ[�߁A�����哰�������������̐M���W�߂�B���������S���Ȃ�A����������_����������B�v�Ƃ���B������������`���̈���łȂ��B
�@���_�I�ɂ����A
�@�����y�ю��̕�͐������@�؎��ɉB�����S���Ȃ����ł͂Ȃ��A�����Ɖ��炩�̊W���o���A��ɕۉȎ��ɉ��̂���������������Ă����Ƃɂ��A������V�Ƃ��킹�ď����̐M�������A���{�����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƍl������̂łȂ����B
�NjL�F�V�����̔���
�@���ʖ@�؎����㕽�R���ɂ���āA�ۉȎ��Ɩ@�؎��Ɋւ��鎑�������������B
�@���[�͖@�؎��Z�m���A�ۉȎ����ɐ����y�ю��̕悪�y���̕�ɕ���Ă��邱�Ƃ�㉚��ȂǂŎ����A�悪���ɐ����y�ю��̂��̂������������Ƃł���A���̕ԏ������������B�i�A���ԏ��͉Éi�N���̂��̂Ǝv���A�����̕�̗R���ɔ������̂ł͂Ȃ��B�j
�@�ԏ��́w���Â͏����������Ă���A�ۉȂ̏��̂������Ες���Ă���A�����R�����@�͎�X������A������T����������̌��ߎ�͕�����Ȃ��̂�����ł���B
�������@�؎��͂���܂ő債���������Ȃ��A��͂����炭�ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B���n�͂Ԃ��ɒ��ׂ��������̕��������A���ߓ�B
�@�@�؎��ɂ͓x�X�����b�ɂȂ��Ă���̂ŁA�����ł͂��邪����T����@�؎��ɑ���̂ŁA����܂ł̎p�ō����u���Ăق����B�x�ƁB
�@�@�������́u�����s��̗��j�Ɩ����@��Q���v�ɋL�ڂ���Ă���̂ŁA�K�v����ΎQ�Ƃ���B
��Web�T�C�g�̏����
�����������F
�M�Z�����鉺�Ɍ�������B
�ۉȎ��̕�ł���A���������ɂ͕��c�����̕�A�ۉȐ����A�����̕�肪����B
�ۉȐ����̕�F�@���͌������a�V�֓��勏�m
�ۉȐ����̕�F�@���͑�a�M�����`�勏�m
���y�[�W�u���j�̊X�u�����v�T�K�@�`���c�ƂƕۉȉƂ����Ԍ������`�v�@���]�ځB
�ۉȐ���������i�������j
���̕�́A�u�������Ɛz�K�䗿�l�A�ۉȎ���l�@�v���V�d�e�A�o�ŔN���s���ɂ��A���\�R�M�N�X���i1690�j�ɉ�Ï��ۉȔ��琳�M�̖��ɂ���ē����ɍČ����ꂽ�Ƃ����B
�@�ۉȐ����E�����̕���F�������č��������̕擃
���M�B����
�@���M�B�����͕ۉȎ��̌̒n�ł���A�܂����Â���̈ڕ��n�ł����邪�A���̍����ɂ͐g���Ɏ���@�ؓ����ʂ��A������x�̓��@�@�̋���������ꂽ�y�n�ł���B
�������Ȃ���A�ۉȎ��̐����A�������A�����A�����̖@�������Ă݂�ƁA�v�X�A�u���_�@�a�֙Չh���勏�m�v�A�u�����@�a�~��������t�v�A�u�������a�V�֓��勏�m�v�A�u��a�M�����`�勏�m�v�ł���A���@�@�k�̂���ł͂Ȃ��B
�@���ɁA�O�q�̂悤�ɁA�����E�����̕擃�͗ՍϏ@���S���h�̌������ɂ���A���@�@���@�ł͂Ȃ��B
�����A�������@�@�@�؎��͕ۉȐ����A���V�̋A�˂����Ɠ`����B
�����������Ӗ��ŁA�э��̓��@�@�@�؎��ɐ����E�������̕擃������̂͊�قł����邵�A���ʂ���قǓ��قȂ��Ƃł��Ȃ������m��Ȃ��B
����������--------------------
����������@�E��
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�����R�ƍ����A���R�@�،o�����B
�J�n�͒厡�N���i1362-8�j�����Ƃ����i�u���`�v�j�A�����͏��u�@���c
�u���@���ג��v�ɂ͖{���߉ޔ@���A�{���V�ԁ~�T�ԁA����420�A�h�k�W���Ƃ���B
�{���̂ق������哰������B�{��������V�͔ŖȂǂɒ����M����Ă����B
���
�@�J��@���u�@���c
�@�Q���@��^�@���s
�@�U���@���É@�����@���U�N�V���W����
�@�W���@��y�@�����@�����R�N�P�O���P�Q��
�@�@�i�ȏ�@�̂݁j
���u�����s��s�j�@�㊪�v���a�T�V�N�@���
2��̉����^��q�肪����B
�P�D�����Q�N�����^��q��F��q�͖�ɁA�����Q�N�i1324�j
�@�����Q�N�����^��q���F2023/11/30�B�e
�@�����Q�N�����^��q��F�}���@�@�@�@�@�@�����Q�N�����^��q��F��e
�Q�D�����^��q��E��t
�@�����^��q��E��t2023/11/30�B�e
�@�����^��q��E��t�F�}���@�@�@�@�@�����^��q��E��t�F��e
2024/03/08�lj��F
���u�x���T�K��145�@�э�������@���c�̔�v�˒m����A�����R�O�N�U���@���
�@�э�������@�E���͔э��h�h�т̑n�݂Ɗւ�肪����B
�����ɂ��鞐���̍��܂ꂽ�Q��̔�̒��ŁA�����Q�N�i1324�j�̔N�I������́A���������ӂ����@�@�ɉ��@����ȑO�A�^�����V��̖������@�̑��݂�`������̂ł���B
���̌㋻���N���i1340�N��j�ɂȂ�ƁA���v�R�𒆐S�ɔэ��Ȃǎ��ӂɓ��@�@���L�܂�A�V���V�N�i1579�j�ɂ͔э��h�т��J�n�����B
�@�ȏ�̔�Ƃ͕ʂɋ�����n�ɑ�ڔ肪����B�i����A�}��110�~80�����A�얳���@�@�،o�ƍ����B�j
�\�ʂ̕����͊��ɖ��Ղ��ǂݎ���Ȃ��Ă��邪�A�S�O�N�قǑO�̒����̋L�^�ɂ��A���a�T�N�i1619�j���H�Ɍ������ꂽ���̂ł���B
�����Ɉ��������c�i����@�E���J��j�͌c���P�S�N�i1609�j�@�،o�ꖜ�����u�̔�������A���ꂪ���A�����̂ŋߗׂ̑m�ƐM�k�Ƃł��̔�����Ă��̂��R���Ɖ]����B
�@����@�E����ڔ��F�u�x���T�K��145�v���]��
���݂ɁA�@�،o�͑��u�ł���l�ň���Q���A�ꖜ���ł�5000���]��v����v�Z�ɂȂ�B
�@�{�����ɔ����哰������A���̔�����V�͓��c�̓njo���ɖ��Ɍ���A���̌ØV���������������Ƃ����A���̖k�����@��Əo���������Ɖ]���B�i�э��h�щ�������́u���N���v�j
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�����P��肪����B
�@�R��ڂ̉����^���F�������ɕt�����i�͕s��
�@�@2024/03/08�F��f�́u�x���T�K��145�v�ɉ��������A���a�T�N�i1619�j�̌����ŁA�J����Ấu�@�،o�ꖜ�����u�v���A��Ƃ����B
�@����@�E���{���@�@�@�@�@�@�E�������哰�F����i��f�́u�x���T�K��145�v�ɗR��������B�j
�@�Q����^�@���s�擃�F���������s�擃�i�}�͌������j�A���E�̕擃�͕s��
�������Ўq--------------------
�������Ўq����
�Ўq�R�ƍ����A���R�@�،o�����B
���u�����s��s�j�@�㊪�v���a�T�V�N�@���
�@��i�����i1410�j���n���A�J����S�A���c���~�A�����ɗ���Q�N�i1339�j���̔肠��B
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
���
�@�J��@�����@�����@���i�R�P�N�R���Q�U����A�J�R�肠��B
�@�Q���@�،��@���Ӂ@�T���P�X����A�����J��
�@�E�E�E
�@�V���@�퐥�@��ꟁ@���ۂV�N�P�Q���Q�T����A�O�����
�@�E�E�E
�@�����@���S�@���ׁ@
�@�@���u�����s��s�j�@�����vp.204�ł͐��S�@���ׂɂ��āA
�@�u���S�@���ׁ@�Ўq�o��(���ߋ����ɂ͂Ȃ��j�A���䓇���߁v�Ƃ���B
�@�@���������u�[�����@��j�v�ɂ́u�_�Ó��A���S�@���ׁF���������P�S���A����h�є����A�Ўq�o���A���ؐ����v
�@�Ƃ���̂ŁA�Ўq�o���Ƃ����͎̂����ł��낤�B
�@�@���������u�x���T�K��141�@�g�c������@��ˍu�v�A�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�A�u�[�����@��j�v�ł�
�@�@�u���ׂ́��_�Ó����߁��v�Ƃ���A���ߒn�̐H���Ⴂ������B
�@�������g�c��ˁi��É@�����E���S�@�����{���j�ɐ��S�@���ׂ̋��{��������B
�@�@�������g�c��ˁ������g�c����
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
����������
�u�㊪�v�@���
���̂Q��̉����^��ڔ�̉��������B
�P�D���Q�N��ڔ�F63�~4�P�~8�E����1/3���A�����E�g������A��ڂ͞���
�@���ߋ����ł́u���S��l������O�ʔV��A�A�ˎd�蓖�����J��B�N��̋`�͗��Q�N�i1339�j�W�����Ƃ����B�Γ��̂�菬���Ɉ��u�d��v�Ƃ���B�����ł������Q�N�̐Γ����A���̐Γ��ł���B
�@���̔�͓��n���̑�ڔ�ł͍ŌÂ̔N�I�������̂ł���B
�܂��A�ߋ����ł́u�����@�����J��@���͉����Ɖ]�@��i�R�P�N�b�C�R���Q�U���v�Ƃ���B�������A�j���I�ɂ͍]�ˏ����Ɏ���Ԃɂ͋ƂȂ��Ă���B
�@���䗪�Q�N�̔�́A���ꂪ���ɓ������珊������Ȃ�A��k�����ɓ��S�̊��������薭���J��ꂽ���Ƃ�������̂Ȃ̂ł��낤�B
�@���Q�N��ڔ�}���F�u�㊪�v���]�ځA�ʐ^�͎B�e�����B
�@���Q�N��ڔ�P�@�@�@�@�@���Q�N��ڔ�Q�F�����͋�X�ʎʐ^�Ɏʂ荞��ł������̂̐���ł���B
�Q�D�������^��ڔ�F85�~95�~10�A�㕔2/3���A��ڂ͕E���
�@�������^��ڔ�}���@�@�@�@�@�������^��ڔ�
���Ȃ��A�{�u�㊪�v�ɋL�ڂ���Ă��Ȃ���ڔ肪����̂ŁA���ɂ��̔�����グ�邱�ƂƂ���B
�������䎁��c��ڔ�
�@���䎁��c��ڔ�P�@�@�@�@�@���䎁��c��ڔ�Q
�@�����̔�̉\��������A�{��ǂ�����A���ʂ͍]�˒����̎��䎁�̔�Ɣ�������B
��Ɏ��䎁���c�̖�������A�Ȃ����S���̖@�������܂�A���̖@���͉�������̕Ўq���̗̎�ł��������{���䎁�̗��ƈ�v����B
���͈ꕔ���ǂ̌�肪����\���͂��邪�A���̂悤�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʑ��@�a�����E�E�E�����m/���\�l�\�O���\����@���P�S�N�i1764�j���Y
�@�@�@�@�i�Ɩ�j�@�@�A���@�a�����Á��������m/�����O�ߔ�����\�����@�����R�N�i1750�j���p
�@�@�얳�����@��
�@�얳���@�@�،o�@���䎁/���c
�@�@�얳�ޔ@��
�@�@�@�@�i�Ɩ�j�@�@�Ð��@�a���p�E�E�E�E�E�E/���\�O�r�O���E�E�E�E�@���P�R�N�i1763�j���u
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�a�E�E�E�E�E�勏�m/���i���r�����\�Z���@�@�@���i���r�N�i1775�j���[
��ɂ��镶�l�͉Ɩ�Ɛ��肷��B�A
�@�����䎁�̉Ɩ�͐V�c���ȗ��̕Ћ��ł���A�ꑰ��q���́A����ɑ������������u�ۂɕЋ�v��u�ۂɌ��Ћ�v�Ȃǂ̉Ɩ��p�����悤�ł���A�����ꂽ�Ɩ�́u�ۂɕЋ�v�̂悤�Ɍ�����B
�Ўq���̎x�z�F
���u�����v�̕Ўq���i�P�P�X�Η]�j�̎x�z�̍��ł͎��̂悤�ɉ]���B
�Ўq���͍]�ˑO�����璆���ɂ����Ă͊��{�x�m���A�����ȍ~�͊��{���䎁�̈ꋋ�x�z�ł������B
�@���{�x�m���͋��ۂQ�N�i1717�j���̌����s�ƂȂ邪�A�����������ɂ��A���ۂP�U�N�i1731�j���ՂƂȂ�B
���䎁�͒��u�̎��A�������N�i1736�j�x�͂̍ؒn�R�O�O�O���x�͕x�m�S�ȂǂS�S�Ɖ�������S�̌v�T�S���ɑJ�����B
�����炭�Ўq�������䎁�̒m�s�n�ƂȂ����͂��̎��̎��Ǝv����B
���u�����d�C���ƕ��v�]�˖��{�ҏS�A����9�N�i1812�j�A��������}���ّ��{�@���
�@�������d�C���ƕ��F���䎁�����}�A�A����\��ł���B
�@�������N�V���ɕЎq�̗̎�ƂȂ������{���䎁�ɂ��ĕW�L�̎j���͎��̂悤�Ɍ��B
�����d�C���ƕ��E���䎁�W�����F�����@�@14++
��L�̔�ɊW����͈͂ł����A���䎁�͒��p�|���u�i����S��̗L�j�|���Y�|���[�Ƒ�������B
�����āA���̂S���̐���������N�Ɩ@�����u�����d�C���ƕ��v���甲���o���Ǝ��̂悤�ł���B
���䒉�p�F�����R�N�W���Q�W�������A�@���Ú�
�@�i�A���@�a�����Á��������m/�����O�ߔ�����\�����@�̍����ƍ��v����B�j
���䒉�u�F���P�R�N�R���P�V�������A�@���E�p
�@�i�Ð��@�a���p�E�E�E�E�E�E/���\�O�r�O���E�E�E�E�@�̍����ƍ��v����B�j
���䒉�Y�F���a���N�R���P�X�������A�@���O��
�@�i�ʑ��@�a�����E�E�E�����m/���\�l�\�O���\����@�̍����ƍ��v����B�j�����P�S�N�͖��a���N�ɉ���
���䒉�[�F���i�S�N�V���P�U�������A�@���쐶
�@�i�����@�a�E�E�E�E�E�勏�m/���i���r�����\�Z���@�̍����ƍ��v����B�j
�@����āA��L�́u�����䎁��ڔ�v�͎��䎁�̐�c���{���Ɣ�������B
�@�ʁE�����Ȃǂ́u�����v���
�@�����Q
�@��ړ��F121����
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���S��@��畔���A
�@�@�@���ʁF�����U�N�i1666�j�̔N�I�A���@�Ўq�E��v�R�E�э����@�^�����]�l
�@�@�@�@�@������ɂ��ẮA�����ł����A�@���Ό���������B
�@�\�������A�E��ړ��F141����
�@�@�\�������A�E��ړ��F����
�@�@�\�������A�E��ړ��F���ʁF���ɋL�ڂ̒ʂ葽���̊W���������������B
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�\�������A
�@�@�@���ʁF�Ўq���@�R�葺�@�����s�ꑺ�@�k�����@���V�c�@�������@�_�葺�@�q���@�v�ۑ��@���葺
�@�@�@�@�@�@���v�R���@�������@�쒆���@�J���@�{�{���@��x���@�ؐϑ��@���ؑ��@�O�J���@�쓇��
�@�@�@�@�@�@�э����@�v�����@���Ñ��@�ؓ����@���c���@�㑍���ƔV�q���@����@�g�c���@���䑺�@�����@�������@�ђˑ�
�@�@�@�@�@�@�э����@�V�c�@���c�V�c�@�ʍ쑺�@�厛���@�厛���@�č����@���R���@�`�J�@���J���J�@���F���@�L�ؑ��@��������
�@�@�@���ʁF�����@�����B����S��c���@�Ўq��/�Ўq�R���@�\�ꐢ�@�����@����i�ԉ��j/�����s�����S�\�Z�l
�@�@�@�@�@�@���ۂV�N�i1722�j�̔N�I
�@���@�ܕS�������{���@16�F92����
�@�@���ʁF�얳�@���@���F
�@�@���ʁF����u���o��S��/����l�ݓ��ܕS��\���E�E�E
�@�@�@�@�@���i�\�N�i1781�j�̔N�I
�@�畔�E��ړ��@17�F82����
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�畔��
�@�@���ʁF�����Q�N�i1790�j�N�I
�@��畔���{��ړ��@18�F80����
�@�@���ʁF��Q�ǖ��@�@�،o�@��畔���{��
�@�@���ʁF�����P�R�N�i1816�j�N
�@��ړ��i�和�j
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@����
�@�@���ʁF�����S�N�i1792�j�N�I
�@�J�R���{���@20�F78����
�@�@���ʁF�J�R�@�����@���~���l/���i�Q�P�N�b���i1414�j/�R���Q�U��
�@�@���u�����s��s�j�v�ł́A�J�R�́u���~�v�Ƃ��邪�A�擃�ɂ́u�����v�ƍ�����B
�@�@���u���@�@���@��Ӂv�ɂ́w�u��ρv�ɂ͊J�R�����@�����Ƃ���x�Ƃ���B����āA�J�R�́u�����@�����v���������Ǝv����B
�@���擃�F���L�ȊO�ɂ��܂������̕擃������A���m�F�̕擃�������B
�@�P�P���@�����@�����@�@�@�@�@�P�Q���@�{���@�����@22�@930
�@�t�ɁA���ɖ��̂Ȃ��擋�����݂��A���̗��R�͕�����Ȃ��B���L�ȊO�ɂ����݂���B
�@��������Ñ哿�F���ɋL�ڂȂ��B
�@����@�����@�t���Q���l�F����@�����@�t/�����@���ܐ��l/�����@��晛���l�F���ɂȂ�
�@�����F
�@�������ΊK�F�ΊK�E�͖和�i��ړ��j�@�@�@�@�@�@���{���@�@�@�@�@���ɗ�
��������x--------------------
��x��
���@�@�������E���������y�ѐ��{�Ђ��J����B
��������x������
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
�@��ςɂ́u��a�R�N�i1347�j�S���̑n���A�J�R���S�B�J�����v�Ƃ���B
���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���
�@�����R�ƍ����A���R�@�،o�����B
��a���N�i1345�j����̊J�R�Ɖ]���B�i�u���`�v�j
�{���E�ɗ���L����B
�����F
�@��x��������
�@�э����@����
�������̐Α���
�E���@�ܕS�������{���F����94����
�@�@�얳�@���@���F/����ꖜ��/�ܕS�����@���i���Ȉ�N�X�����V
�E��ړ��F�和�����˂�A���R�A�����P�P�W����
�@�@�얳���@�@�،o�@�����@���h�i�ԉ��j/�얳���@���l�@�����R/���퐹�l�@�\�Z��
�E�单�V���F�R��p���^�A�����A����81�����B
�@�@���ʁF���@�单���V�@�����ꖜ���@(������)�@�������N�i1804�j
�@�@�@�����̐Γ��͖����A���m�F�E
�����������
�@�J��@�ʚ��@����
�@�Q���@���S�@���h
�@�R���@���S�@����
�@�S���@�ŏ��@���G
�@�T���@�^��@����
�@�U���@�q���@���s
�@�V���@�^�@�@����
�@�W���@�B�S�@����
�@�X���@����@���~
�P�O���@�����@����
�P�P���@���i�@���P
�P�Q���@�{���@��痁@���\8.6.23
�P�R���@��S�@�����@����3.10.2�@�����@�@�@�@�P�R����S�@�������
�P�S���@�q�P�@���B�@���\15.2.15�@�����@
�P�T���@�~�ω@���B�@��i2.7.����@
�P�U���@�{���@���h�@����2.8.26�@�����@�@�@�@�P�U���{���@���h���
�P�V���@��@�@���Ɓ@���i5.11.�A���@�����@�@�O�t�i���ƁE�����E�����j���
�P�W���A�P�X�A�Q�O�A�Q�P���@�ȗ�
�Q�Q���@�{�@�@�����@����5.10.17�@�����@�@�@�@�@���@��
�Q�R���@�V��@���I
�Q�S���@铒��@���[�@����8.10.10�@�����@�@�@�@�Q�S��铒��@���[���
�i�ȉ��@���j
2023/11/29�B�e�F
�@������������ڐ�
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@��d�F�����R�@�E���ʁF�吳�P�R�N�V���P�R�������@�����ʁF�c�R�R�P���@����@���R�i�ԉ��H�j�ƍ�����B
�@�������A��L�u�����s��s�j�@�����v�ł����u�和�����˂鎩�R�̑�ړ��v�Ƃ͌`����������قȂ�A���̊W�����ǂ�������Ȃ��B�܂����̎��R�̓����E��ړ��͋����ɂ͌�������Ȃ��B�s�v�c�ł͂���B
�@��x�������{���@�@�@�@�@��x�������ɗ�
�@���������F�P�@�@�@�@�@���������F�Q�@�@�@�@�@���������F�����F���l�̋{�a�����u�B
�@���̓��F�ɂ��ẮA�܂�������|���肪�Ȃ��A�s���ł���B���������Ǝv����u���L���Y���ׁv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��Ƃ����B
�@��������ɁA�����������ɂ͎��ʓ�������A���a�S�O�N��ɂ͖����������������ꂽ�Ƃ���A���̎����ʓ������͖{���ł��錫�����ɋ{�a�Ƌ��ɁA�ڂ��ꂽ�\��������̂ł͂Ƃ��v���邪�m�͂Ȃ��B
�@���������揊�P�F��������Ɠ��@�ܕS�������{��
�@���������揊�Q�F���������̕��Ǝv���邪�A�w�ǂ��ǂ߂Ȃ��B
�@���������揊�R�F���������̕��ł��邪�A�������ĉE�̂R��͖������̗���ł���B�i���������Q�Ɓj
�@���@�ܕS�������{���F�����͏�Ɍf��
�@���������F�w�lj�ǂł��Ȃ����A���S�@�����i�R���j�A�ŏ��@���G�i�S���j�Ȃǂ��ǂݎ���̂ŁA�����炭�����Ɛ��肳���B
���̑��̕��͏�f�́u���������v���Ɍf�ڂ���B
��������x�������p��
���u�����s��s�j�@�����v�����s��s�j�Ҏ[�ψ���A���a�U�Q�N�@���
�@��x�����V�����߂����̓��̕�n�����Ղł��낤�B
�@�@����x�������Ւn�}
���݁A�������͂Ȃ��A�����͎R�тƕ�n�ł���B���a�S�O�N��Ɍ������͎��ꂽ�Ƃ����B
�@�������S�����G�i���\�R�N/1459��j��������ɑn���i�u���`�v�j�Ƃ����B
����A��ςł͌��T���N�i1570�j�̑n���Ƃ���B
����ɁA������n�̗��Z�E���{���ɂ͊J�R���Z�@���Z�i���i�P�R�N/1632/�P�O���P�Q����j�Ƃ���B
�]�˒����A�����J�R�̂V�����ڂ������삩�玚���ɑJ���B
�������N�̋����G�}�ɂ͎Q��������Đ��ʂɖ{���i�q�a�j�A�E�ɕ�n�A���Ɍɗ��A�{���E����̍����Ɏ��ʓ�������B
���ʓ��͍]�˒��������̊J��Ɠ`�����A�P�X�������̎��Č������B
�Α����Ƃ��Ĉȉ�������B���u��㋟�{���v�ȊO�͖�����
�@�����和�F�Q�����������ɂ���A�����Q�N�i1819�j�̔N�I������B
�@���@�T�O�O�������F�q�a�Օt�߂ɂ���A���i�T�N�i1778�j�̔N�I�ł���B
�@��㋟�{���F���Ɍf�ځA���݂͖{���ł��錫������n�ɂ���B
�@�������ړ��F�n���̒n������ɋS��˂Ɖ]�����˂�����A���a�U�N�i1769�j�P�R������Ɍ������ꂽ��ړ����c��B
���������
�@�J�c�@���Z�@���Z
�@�Q���@����@����
�@�R���@���ځi�Z�j�@���G�@����3.9.26
�@�S���@��@�@����
�@�T���@�q���@���@�@���͌���������n�ɂ���
�@�U���@�ʌ��@����
�@�V���@�����@���ځ@����4.9.10
�@�W���@�����@���v
�@�X���@�����@�����i�q�̗����H�j�@���10.9.29
�P�O���@�v�i���j�s�@����@���6.�@.29
�P�P���@�[���@���F
�P�Q���@�����@���ā@����7.8.30�@���͌���������n�ɂ���
�P�R���@�C���@����
�P�S���@�{�L�@���F�@����14.7.17
�P�T���@����@�����@���͌���������n�ɂ���
�i�ȉ��@���j
2023/11/29�B�e�F
��������A��������n�ŎB�e�����ʐ^�ł���A���������A��������n���猫�����Ɉڂ��ꂽ���̂Ɛ��������B
�@�������J�R�`�P�S����㋟�{���F�P�Q���̖@�����ڂ����Ă��Ȃ����A���̗��R�͕s���ł���B
�@�@��f�́u�����s��s�j�v�ł����u������n�̗��Z�E���{���v�Ƃ͂��̐Γ��ł��낤�Ǝv����B
�@�T���q���@���@����@�@�@�@�@�@�P�T������@��������@�@�@�@�@�P�Q�������@���ĕ��
�@���N�@���G�哿����F�A�����G�Ƃ͗��ɂȂ��A�������W�̕�肩�ǂ����͕s���B
�������g�c--------------------
�������g�c��ˁi��É@�����E���S�@�����{���j
���u�x���T�K��141�@�g�c������@��ˍu�v�˒m����@���
�@�����̗т̒��ɋ�����n������A�����Ɂu��ˁi���Â��j�v�ƌĂ�鋟�{��������A�Q���Q�R���ɂ́u��ˍu�v���s���Ă���B
���{���͍�����80�����A���ʂɂ́u�������l�v�E�u���ב哿�v�ƍ��݁A���\�P�P�N�Q���Q�S���̔N�������܂��B
�@�����i��É@�j�͕s��s�{�m�ŁA���i�V�N�i1630�j�]�ˏ�ōs��ꂽ�u�g�r�Θ_�v�ŏ��f����B���]���{��ɗ��߁A���͓��琳�����a���ƂȂ�B���i�Q�P�N�W���Q�S������B
�@���ׁi���S�@�E���ؑ����܂�j���s��s�{�m�ł���A���������P�S���A���ђk�тP�U���Ȃǂ�𐢂���B
�Ƃ��낪���\�S�N�̌��\�@��ɂē��ׂ��ߔ�����A�_�Ó��ɗ��߁A���\�S�N�P�Q���P�U�����₷��B���̎��ɓ������ɗ��߂ƂȂ����m���͂W�O�l���܂�Ƃ����B
�g�c���ł̓��M�͖�U�O�l���m���A�V�ۖ@��i�V�ۂP�P�N�j�ł͑��l�P�R�l�E�������m�����撲�ׂ���Ƃ����B
�@���āA�˂̏�ɂ́u��˂̏��v�Ɖ]��ꂽ����S�O�O�N�̏��̑������A���̍����ɋ��{�����J���Ă����Ƃ����B
���a�R�Q�N��������̂��Y���̌�ˍu�ɂ���Đ�������A�����u���ɂ�鋟�{���������Ă���Ƃ����B
���u�s��s�{�h�}���̗��j�v�@���
�@���S�@���ׁ������@�E�����Ƃ��Ԃ遄�F���������o���m�A�Ջ��R�x�A�ЋłR�x�A���ؐ��܂�A���\�@��Ő_�Ó��z���ƂȂ�����暉@���_�Ɛ_�Ó��̓������œ�������B���ׂW�Q�Ŏ���B
���u�[�����@��j�v�@���
�@�_�Ó��A���S�@���ׁF���������P�S���A����h�є����A�Ўq�o���A���ؐ���
�Ȃ��A�⑫�Ȃ���A���o�����ˋ����̐Γ����ɓ�Q�j���@��m�Γ��̐��ʂɁu�����v�ƍ������Γ�������B�������A���̓��ׂ����S�@���ǂ����̊m�͂Ȃ��B
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@���ݏꏊ�F���ܓx�o�x��35.72862366351227, 140.50302362929565
�@�g�c�����ˈʒu�}�@�@�@�@
�������g�c������
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@�����R�ƍ����B���R�@�،o�����B�����J�R�͂P�S�����s�B
���`�ł́A���^���@�ŁA�߉ޓ������������A��a�R�N�i1347�j���_�@���䂪���@�@�Ƃ��ĊJ���Ƃ����B�i���̍s�u�㊪�v�j
�{���E�ɗ���i������A�V�ۂS�N�i1833�j�߉ޓ��ȂǑS�āB�V�ۂP�P�N�Č��B
�����ɔ����Ђ���B
���
���c�@���S
�J�R�@����
�@�i���ȉ��ȗ��A�擃�̎c������������A���m�F�j
�Α����ق��ȉ�������B
�P�D������ړ��i�和�j�F����230����
�@�@�@�@�@�@�@�@�s���F��@�߉ޖ����/��a���������l��@�@�c���F/���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Éi�O�N�M�����~�Ǔ����ڈ�/��C��M���{��ʁX�ʋL�ߋ�����/�O�\�ܐ��@�����i�ԉ��j
�@�i�\�ʁj�얳���@�@�،o�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�V�����S�@�܍��L��/���h���y/�ߑ��{���ʁX/����
�@�i���ʁj�@�V�ۂQ�N�h�K�O�����U/���R�O�\�O���@�����@���P�i�ԉ��j
�@�i��d�j�@�E�E�E�����E�����̎{��̖��O�����܂��E�E�E
�Q�D��ړ��F��⸈^�A����204����
�@�@�@�@�@�@�@��ڍu�ꌋ�@�]��/����������S�m�c�V���g�c���@�u��
�@�i�\�ʁj���ꖜ�����A
�@�@�@�@�@�@�@���\�\���ГV����
�R�D��ړ��F����75����
�@�@�@�@�@�@�@�@���v�Oᡈ�\����
�@�i�\�ʁj�얳���@�@�،o�@�@�E��
�@�@�@�@�@�@�@�@���R�O�\�Z���@�q�F��
�@�i��d�j�{���@�����̎{��̎����������B
�@�@���{��ړ��͎��������B
�S�D���@�ܕS�������{���F����208����
�@�@�@�@�@�@�@�@�{�R���R�O���@���S���l
�@�@�@�@�@�@�@�@�J�R�@��m�s�@���䐹�l
�@�i�\�ʁj�얳���@�@�،o�@���@�i�ԉ��j
�@�@�@�@�@�@�@�@���u/���ڈꖜ��/�_�͕i�ꖜ��/���A�@706
�@�@�@�@�@�@�@�@�����J蓒�a�O���僈�����i�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�S�O�\��N����
�@�i���ʁj�@�@���@�ܕS������
�@�@�@�@�@�@�@�@��������������ΎO�����c�@�{��@�y�h�����u�ʁX
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R��\�l���@�q�]�@�����i�ԉ��j
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@�g�c������������ړ��F�����͏�P�D�ɋL��
�@�g�c�������{���@�@�@�@�@�g�c�������{���G�z�@�@�@�@�@�g�c�������ɗ��@�@�@�@�@�������������F
�@��ړ��i��⸈^�j�F�����͏�Q�D�ɋL�ځB�A���A�������ǂ߂���Q�D�ɋL�ڂ̑�ړ��Ƃ͒f��ł����B
�@���@�ܕS�����E�����F�w�Ǔǂ߂Ȃ����A��q�S�D�̖����̂悤�Ɂu�얳���@�@�،o�@���@�i�ԉ��j�v�Ƃ���̂��낤�B
�@���@�ܕS�����E�������@�@�@�@�@���@�ܕS�����E�E�����F�������������͏�Ɍf�ڂ̒ʂ�B
�@�����ǖ������{���F�\�ʂ́u�얳���@�@�،o�@�����ǖ������{���v�ƍ����B
�@�@���E���ʂɖ����S�P�N�̔N�I�Ƒ�����̖��O���L��
�@��ڐE�s���F���ʂ͑S���ǂ߂Ȃ��A���ʂ��w�Ǔǂ߂�
�@���o���ݕ����{���F�\�ʂ́u�얳���@�@�،o�@���ݕ����{���v�ƍ����B
�@�@�����ʂɖ����R�R�N�̔N�I�A�E���ʂ͖��m�F�A��ɑ�ڍu���v�ƋL���B
�@��u���@���S�ꖜ�����A���F�\�ʂ́u����u���@���S�@�ꖜ�����A�v�ƍ����B
�@�@�E���ʂɐ����N���Ǝv����N�I������B�i�����ȊO�͓ǂݎ��Ȃ��j
�@�J�R���S�哿�擃�@�@�@�@�@�J����䐹�l�擃
�@���������擃�i����j�F�e�擃�ɂ��Ė��m�F
�������g�c���[��
���u�����s��s�j�@�����v���a�U�Q�N�@���
�@�V�_�R�ƍ����B�u��ρv�ɂ͉i�m�Q�N�i1294�j���V�m�����̊J�R�Ƃ���B�����������i�����J�R�j���B
�{���E�ɗ������肵���A�����Q�S�N�Ђŏ����Ď��B
���i�u�擃�v�ȂǂɈ˂�A�������̂݁j
�J�@��@����
���@���@���w�@�����@���\14.7.16��
�Q�S���@��M�@���s�@����13.8.20��
�@�@�@�E�������Ă���͈̂ȏ�
�@�@�@����N�@�����哿�A�����@�����哿�A���@����Ȃǂ̕擃������A�𐢂��B
�Γ��Ȃ�
�P�D������ړ��F����136����
�@�@�@���ꖜ�����A
�@�얳���@�@�،o�@�����@�@��F���ۏ\�ܜ��O���\���
�@�@�@��ڍu���@�j�����V
�Q�D��ړ��F����156�����A
�@�@�@�������N��C�H�ؔV���@����������i1748�j
�@�얳���@�@�،o�@�@�E
�@�@�@��i�O�����V�\�O���@�g�c�@�~�[���@���i�}�}�E�u�j��
�@�@�@�@�����̑�ړ��͖���
�R�D���@�ܕS�������{���F����104����
�@�얳�@�c���@���F�@�@�@�d����
�@�@�@���i��M�q�g���i1780�j
2023/11/30�B�e�F
�������s��s�i���x���s�j�˒m�쎁�̂��ē�����B
�@�g�c���[��������ړ��G��ɖ����Ȃǂ���
�@�g�c���[���{���@�@�@�@�@�g�c���[���{���Q�@�@�@�@�@�g�c���[���{���ɗ��@�@�@�@�@���[���}�Ԉ�ז��_
�@���[�����揊�@�@�@�@�@���@�ܕS�������{���G��ɖ����Ȃǂ���
�@�������{�@�����擃�@�@�@�@�@�Q�S����M�@���s
�@��N�@�����擃�F��N�@�����哿/�����Zᡖ�/�\�ꌎ�ܓ����i�����U�N��1823�N�j
�@�����E����擃�F���ʁF���@�@�����@�����哿��/�E���@����哿
����������S���Ò��̓��@�@--------------------
���u���Ò��j�v/�ʎj��/��O�́@����/���߁@�����O���\�\���q���㏉�����\�\�@�@�㊪95�`�@���
�����@�@�����̎��X�i���������Ò���j
�@����̖����̂悤�ɁA�ޗǕ��������h�̊����́A�Ñ�̋M�������̊k��j���ē����̔_���n���ɂ܂Ői�o���Ă���A�����ł͕��m�����߈�ʖ��O�ɉ���������܂łɕϖe�𐋂���B
����͊��q����̐V�������A�Ñ㖖������̓����̒��Ő������Y�̕ۏ����Ȃ��A���̖����ڂ̂�����ɂ��Ă����l�X�ɋ������_�I���ǂ����^���悤�Ƃ��������ł������̂ɑΉ����Č���ꂽ�����̕����ł������B���̔h�̑m�͖��O�ւ̎����ƂƂ��ɁA���P�~�ώ��Ƃ��s���Ă���B
�@�������ւ̔ᔻ�Ɣ��Ȃ̏�ɐ��܂ꂽ�V�����ɂ́A�@�R�̎n�߂���y�@�A���̐�C�O���E���͖{��̎v�z������ɐ����i�߂��e�a�̏�y�^�@(����@)�̂ق��A��Ղ̎��@�A�����̑����@�A�h���̗ՍϏ@�Ȃǂ�����B
�@�܂���y�M�ƕ���ŌÂ�����`�������@�ؐM�ł́A�������㖖���ȍ~�A��(�Ђ���)�ƌĂ��l�X����ʖ��O�̒��֓����ċ����ɓw�߂Ă������A���@(1222�`82)�͂��̋����W�����A�V���ɓ��@�@����������B
�@���[��������(����)�ɐ��܂ꂽ���@�͗c�����琴���R�ɓo���ĕ������w�Ԃ��A�߉ނ̋������Ȃ����܂��܂̌o�T�E�����E�@�h�ɕ������̂��ɋ^����������B
�����Ċ��q�E��b�E����ȂǂɗV�w�A�������邤���A��،o�̒��Łw�@�،o�x���ō��̐^���ł��邱�Ƃ��m�M����Ɏ���A�����ܔN(1253)�̋��ɋA���āw�@�،o�x�M���S�̈�h��n������B
�@���@�̐��́A�u�얳���@�@�،o�v�Ƒ�ڂ�������w�@�،o�x�̌����ɂ���ċ~����Ƃ����Ȗ��ȐM�`���ł���B
�ނ͔O�������߂Ƃ��鑼�@�h�����������A�w���������_�x�킵�Ė��{��ᔻ�����̂ŁA���яd�Ȃ锗�Q����B
���@�͂���ɂ��������z���𑱂��A�ӔN�͍b�㍑�̐g���R�ɂ������đ����̒��q���c���B
�@���@�̋����͊֓�����k�����ʂ̕��m�K��(�n���E��Ɛl�E����Ȃ�)�̎x�����A�����ł͕x�؏�E�A�]�J���M�A���c�斾�Ȃǂ̕��m���M�k�̒��j�ƂȂ��Ċ�������B
�����̏@�������ɂƂ��čݒn�̐������͂Ƃǂ̂悤�Ɍ��т��O��邩���A���̋��c�̏��������߂�d�厖�ł������B
����A���m�̑��ɂƂ��Ă��A���̈ꑰ��y�̐��̉��Ɍ��������鐸�_�I�Ȃ����ȂƂ��ď@�����K�v�ł���A�����͂������������̒��S�ł������B
���@�@�͐�t���̈ꑰ�A���Ƃɐ�c���̎�̐�c������Ƃ��̔튯�̊ԂɎ�����A���̗̈�ŐM�k�g�D���`������Ă������B
�@�x�؏�E�͊����S�������J�����̗̎�ł���A��t����̗L�͂Ȕ튯�ł������B
�ނ͒��ڋ����������@�̎���A��ɒ��R�@�،o���ƂȂ�@�؎����������A����Ɩ�����Ă��̏Z�E�ƂȂ�B
��N�ނ͐�c���̒����ɉB�����đ��������Ԃ��A����͌�������h��(���{��)�̂��ƂƂȂ�B(�⒍)
�@�k�⒍�l���R�@�،o���͓V���\�l�N(1545)�܂ł͖{�����E�@�؎��̓ň�吧���Ƃ��Ă���A�V���Ȍ�͖@�،o���Ə̂���B
�@�������E��c���E�P�䏯(��S)�͊��q�����ɂ͐�c����̗̒n�ŁA�����̓��@�@�͂���Ȍケ�̒n��Ő���ɐM�����̂ł��邪�A��c���ł͂��łɓ��@�ݐ����ɂ����̕z���͍s���Ă����悤�ł���B
���Ò���������������͎��`�ɂ��A���i�N��(1264�`74)�ɂ���܂ł̐^���@����@�@�ɉ��߂Ă���B
���m�~�ق͓��@�̋����ɂ���Ē�q�ƂȂ�A���قƉ��߂��Ƃ���A����Ȍ�A�ߖT�̑m���ł��̋����ɋA�˂�����̂����������Ƃ�����B
�@���̂悤�Ɋ����̎��@��ϋɓI�Ȑ��@�ɂ���ĉ��@�����邱�Ƃ��珉���̓��@�@�̊����͎n�܂�B
���Ò���ʑ����@�؎��́A���͊ω��@�Ƃ����^���@�̓���ł��������A�O�����N(1284)���@�̒���q����(�`1218)�̐��@�ɂ���ďZ�m���������@���ē����Ɩ������߁A�O���\�N�ɍ��̎����ɉ��̂����Ɠ`������B
���ʂ͓��@�剺�̂P�W���V�m�ɐ������A�x�̖͂{�o�����J�n����B
�@�ȏ�̂悤�ȉ��@�́A���̎��̏Z��������Ώۂɐ��@���邾���ł͂Ȃ��A���̒U�߂ł���̎�w���������ɋ���������ōs��ꂽ���Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A���@�����̒n�Ő��@�������Ƃ����������͎c�炸�B
�@���Ò��쒆�����̖������́A���`�ɂ��ΐ�����N(1300)���@�̒���q����(1239�`1311)���哈��(���Ò����̔���Ƃ��D�z�̊ێR�Ƃ�������)���ɓ������āA�����͐��~�R�����������A��ɂ��̎���ł���@��ł�������E���p���A��������ݒn�Ɉڂ��A�����R�Ɖ��߂��Ƃ�����B
�哈��͐�c����(1288�`1336)���z�������̂Ɠ`�����邩��A���̎��͓��R�A�����U�߂Ƃ������̂ƍl������B
�������́A��Ɉ��傪���ʓ��ł��������R�@�،o���̂����钆�R�嗬�ɑ����Ă���B
�@���ق͏��ߏx�͍��̐^���@��̊w���̈�l�ł��������A���@�̋����ɂ��g���R�Œ�q���肵�A��ɏ����(�x��)�E�h��(�킵�̂�)�h�R��(�㑍����)�E�������E���Ǝ�(�b��)�E�萬��(�헤)�Ȃǂ��J���B
���@�v�セ�̒���q�����́A�Z�V�m�𒆐S�Ɋe�n�ɋ������g�債�������A���ق͘Z�V�m�̌n����E���A���@�̒��n��C���ē��ٖ嗬�𗧂āA���̋��_�Ƃ��Ă����̎����J�����̂ł���B���ق̍���ɂ͑O�L���E�Ƙh�R�����p���������Ƃ�����B
�@���ق̒�q�ɘa���(�����݂̂���)(�a��苗�(�������))���@�Ƃ����m������B
��c���������Ñ��ɂ������a������ƌĂ�铰�̐Ղ��A��Ɉ���̎q���p���璆�R�Ɋ�i����A�@�،o���O�����S�̒�q�̓����E���傪�p�����Ă���̂ł��邪�A����ɂ͓��Ɠc�ܔ��A���ꔽ�A�݉ƈ�F���܂܂��B
���@�͓��@�ɐS�����Ă����炵���A���R�@�،o�������w���E�`����x�ɂ��Γ��@�����₵�Ēr���䶔��ɕt���ꂽ�Ƃ��u�ߒQ����̂��܂�v���̎ɗ����Β����瓐�ݏo���Ęh���ɔ[�߂��Ƃ����B�ɗ��͂��̌�A�������ɓ`�����A���E�̂Ƃ����R�֕����`������Ă���B
�����Ö������̐����ƈ�~�@���@�㊪134
�@���݁A���Ò����˂ɂ�����@�@����R�������́A�w����R���N�x�ɂ��Ώ�݉@�������O���N��(1278�`87)�ɊJ�n���A���ʂ̂Ƃ������l�N(1359)�\�ꌎ��\�����ɁA���R�@�،o���O�����S�𐿂��ċ��{���@���s���Ă���A�V���ܔN(1577)�ɑ��Ï�勍�����������䂩�猻�ݒn�ֈڂ��ċF�菊�Ƃ����Ƃ�����B
�����N�́A���{���O�\�l�������ɂ���Č��\�\��N(1698)�ɏ����ꂽ���̂ł���B
�@����A���a�l�N(1767)�ɑ��Ñ��̓c�����E�q��(�O��)�ɂ���Ē����ꂽ�w���ӗR���L�x�́A���\��N(1593)�̑��Ñ��̖��ɂ��A�c�����N(1602)�̏��꒠�ɂ����˖������͍ڂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�c�������A���a�N���Ɍ��ݒn�Ɉ����ڂ������̂炵���Ɛ��肵�Ă���B
�@�����͂܂����Ñ��ق��ߋ��̑��X�����@�@�ɉ��@��������ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@
�u�Â��ւ͐_�Е��t�ɂ����閘�F�^���@���助����B�R��̓������Ђ̕ʓ��ނ�������v�~(�����Ђ�����)�R�����ɂėL���V�A���㉞�i�N���A�����R�@��(��)�o���O�c���S��l�A����(�}�})���䑺���̖V�֑��A�|������@�A��S���V�ԁA�@�ԍO�ʂ̐��@�L��B���ɏ@�c�̍Ēa�Ɛ\�`�ւ���̑��m�Ȃ�A�����̗̎�A�˒v���A�ߋ��̒j�����Ƃ��Ƃ��݂ȉ��@����B(����)���߂��ʓ��쐳�@�Ƒ����߁A�����ߌ��B����A�V����@�x���ɖV���ɂĎ��������V�����������R��G������A�₩�ɓV�ƎR�@�����Ǝ��������ߌ�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�@�v�u�A�v�́u��_�v�u��_�v�̑�p�ł���B
�@�����ɉ��i�N��(1394�`1428)�Ƃ���͓̂��S�̍ݐ�����(1298�`1374)�Əd�Ȃ�Ȃ����A�����悤�ɓ��S�̕S�����@�őS�����@�����Ɠ`����w�ё��R���L�x�́A���̖V�̐��@�����N(1338)�Ƃ��Ă���B
�@���S�Ɋւ��ẮA�u��c����Ɛ�t�����v�̍��ň���Ƃ̊W���L�����A�����ł��̐��U������́w�{��(��)�ʓ�(��)���c���L�x(���ۈ��)�ɂ���Č���B
�@
�u���S�A�c�ɂ��Ē��R�����̎��ɓ����ďo�Ƃ��B���a���N�l�������̈▽���Ē��R�@�،o���Ɏ傽��B
��t����ɊO��̗͂�s���B�ꎞ�B�̍���S�ɏ������B�S�͊F�^���@�Ȃ�B�I���@��������ƕS���ɋy�ԁB
���v�R�~�Î��呴���ɋA�����Ď��������A��q�̗������B����[�ɗV�ԁB�^���@��������@�����߂Ď��������B
���q�Z�Y�ɉ����B���@�T��t�𐿂ЂĐ^���������߂ď�s����B�㕐�����v�NJ�S���c���Ɏ��苍���R���@����B
���O�Ɏ���B��t���n�����ď����B�����R�썑��������n���B���@������ɗ��v����B�V�c�V�����莛�Ƃ����܂ӁB
�t���R�Ɋ҂�B������N�܌��\�ܓ��₷�B�����\�v
�@�@���S�̐��v�N�ɂ��Ă͏����������Ē�܂�Ȃ����A�w���R�@�،o�����x�̗�㕈�͉i�m�Z�N(1298)�`�������N(1374)�Ƃ��Ă���B
���S��l��(�w���R�@�،o�����x�ɂ��)
�@���S���S�����@�������\�l���I������͉����̓��@�@�W�J�̑����Ƃ����ׂ������ł������B���S�́w������C�P���L�^�x(�w���ӗR���L�x�͂�����w�P���L�x�Ɨ��̂��Ă���)�̈ꍀ�u�䓰�{�������Ύd���v�ɂ́A���S�����U�ɋΎd�����J�����{�Ɩ{�����{�̋L�^������B
�����ɂ��A���S�͉�����N(1357)�l���O���̉������Ó��E��苗��䓰���{�A�����l�N�\�ꌎ��\�����̐�c�������䓰���{�A������N(1396)�̐�c�����Ó��E��Փ����{�Ȃǂɏ����t���߂����Ƃ��L����Ă���B
��Ԗڂ̌����䓰���w���ӗR���L�x�͖������Ɛ��肵�Ă���A���̓_�͏��߂ɏグ���w����R���N�x�Ɉ�v���Ă���B
�������Ɏ���Ƃ��ē`�����P�M�́w���@�ؓ����{�L�x�͓��S�̋��{�ɂ��ċL�������̂ł��邪�A�����ł͌����䓰�͌��@�ؓ��ƌĂ�Ă���A���ꂪ�������̑O�g�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B
�@�����ɏo�Ă������E�́A���������̉��숢苗����E�ł���B
���@�@�@���@���s�́w���@�@���T�x�ɂ��A���E�́u���قɉ����̖�����������ꂽ���Ƃɂ�蒆�R�̓��S�̂��Ƃɕ����A����Ɠ`���������s�Ȃ����Ƃ����A�w�V��[�ɏ��x�A�w�V��l�������x�Ȃǂ̏��ʖ{���`������B
�܂��������ɂ͓��@���l�̎ɗ����i�삳��Ă����炵���A���E�͂������S�ɕ��������Ƃ����B
�Ȃ��A���E�̖v�N�ɂ��āw�{���ʓ����c���L�x�ł͉������N(1311)�l���\����Ƃ��Ă��邪�A���S�Ɏɗ��^����|���L��������͗��N(1339)�ł���A�܂���̏��ʖ{�̉��t�͗��{�Ƃ��N�i���N(1341)�ł���A����ɉ�����N(1369)�ɐ�c�����Ó��E��֓����{���s���Ă��邩��A���E�̖v�N�͍N�i���N(1342)���牞����N(1396)�̊Ԃɐ��肳���v�ƋL����Ă���B
�@��c���傪���S�Ɋ�i�������̂̓��ɁA��������ɓ��E�c�n(���i����э݉ƈ�F)�����邪�A���̈���ɓ��Ƃ����̂́A���̓������Đ^���@���܂��͏�y�n�̑����ł���������̖��ł͂Ȃ����Ǝv����B�܂���傪���̂̓����瓰�E�c�n�̓�������S�ɉi����^���邱�Ƃɂ���ē��̌o�ς𒆎R�@�،o�����ɂ���A���S�������Ԃ����Ő��@���邱�Ƃɂ���āA���̒n��̈�~�@�������������ƂɂȂ�B
�@���̊�i�͌����O�N(1331)�ŁA���̎��͒������O�J(�݂�)���E�ғ��Ȃǂ̓��E�c�n���Ƃ��Ɋ�i����Ă��邪�A���̌����䓰�̊J�����{�܂łɓN���̎��Ԃ�����A���̏��߂���Ɂw�ё��R���L�x�ɂ��ΕS�����@�����������ƂɂȂ�B���̊Ԃɂ͊��q���{�̖ŖS���c������������A����͑傫���h�ꓮ���Ă����B
�@���Ñ��ł͓������떭�����̂ق��،˒J�̖������S�̐��@�ɂ���Đ^���@������@���Ă���B
�O�f�̉�����N�ɊJ�����{���c�܂ꂽ���E�̌䓰���₪�ē��@�@�̎��@�ɐ������Ă��������̂ƍl������B
�匴���̖@����(���̐����@)�́A���邢�͂��̓��̌�g�ł͂Ȃ����Ƃ��z�������̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�ߐ��̏��߂ɖ����������˂Ɉڂ�O�A���Ñ��ɂ͖��E�@�����E������(���̎����V)�̂ق��ɁA��іV���n�߂Ƃ��Ď��Ɉ��𐔂��鑽���̖V���������B
�@�@�@�����Ö��E�@�����E�������Ȃǂɂ��Ắu���Î��@�Ձv�����������ɂ��聄���Q�ƁB
��Ɉ��p�����w���ӗR���L�x�̒��̎R���������̈�ł���B
���S�̕S�����@�ʼn��@���ē쐳�@�Ɖ��߁A��ɖ@�����ƂȂ����Ƃ����̂ł��邪�A���͕��\�̖��ɂ͓�z�V�̖��ōڂ��Ă���B
���̌ア������쐳�@�ɉ��߂���A�@�����ƂȂ������̂ł��낤���B�@�����͌�ɖ������̖����ɂȂ��Ă���B
���̖V�͌�ɔp�₵���炵����іV�������A������������ɉ��߂��Ă��邪�A�����\��N�̑��Ñ��̎Ў����ג��ɍڂ�͖̂������E�@�����Ɩ��̎O���ɂ������A���͂��ׂĖ����������ېV�̂���ɂ͔p���ƂȂ��Ă���B
�����̏@�|�͈ꕔ�����@�@�Ƃ킩��ق��͖��炩�łȂ��B
�������w���ӗR���L�x�̏����ꂽ�����ɂ͂��Ƃ��Ƃ����@�@�ɉ��@���Ă������Ƃ͊ԈႢ����܂�(�����̖V������щ��̂��������ɂ��Ă͖{�������u�Ў��ꗗ�v�Q��)�B
�Ȃ��A�O���ŏq�ׂ��u���Ñ��a������v��u�������J�����v�Ȃǂ��A���̌ケ���̎��V�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�Ƃ���ő��Ñ��ߋ������Ƃ��Ƃ����@�@�ɉ��@���������̂��̂�����̗̎傪����ł��������͖��炩�łȂ����A�i�a��N(1376)�ɖ������ɓ��@��������i������U�߂́A���̑ٓ����ɂ��Ή~�鎛�}�����q��ь������Ƃ��̕ꕽ�����ł������B
�܂��A������N�K���̓��t�̂��閭�����̓��S�̙�䶗��{���ɂ́u���������^�V�v�Ƙe��������Ă���B
���̐l���́A��Ɂu������̐�c���Ɛ�c���̌n���v�ŐG�ꂽ�悤�ɁA��c����̑]���ł��̈�̂��p�����`���̔튯�ł���B
�����炭��c���̗L�͂Ȕ튯�Ƃ��Ďd����ƂƂ��ɁA���̒n��������I�Ɏx�z���A���̌o�ϓI���͂ɂ���Ė������̑�U�߂ƂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B
���������āA�i�a��N��\�ܓ��ɒ��R�@�،o���l�������������ē��@�����̊J�ዟ�{���C���ꂽ�ۂɂ��A�����͂��̖@����Ƃ肵���������̂Ǝv����B
�@���̎����ɑ��Â����Ƃ��Đ������Ă������Ƃ́A�O���ŐG�ꂽ�����Z�N(1361)�̓����̏���Ɂu���������Ñ��v�Ƃ��������ƂŖ��炩�ł���B
�����ē��@�����̑ٓ����ɂ́u���Ñ��������v�ƋL����Ă���A�����͖������Ɖ��߂Ă������ƂɂȂ�B���邢�͑��̊J�ዟ�{�����ɓ����ɂ���Ď������^�����A�����ɒ��R�̖����ƂȂ����Ƃ��l������B
�@�Ƃ���ł��̉~�鎛���͖{�������Ə̂��Ă���B��t�@�Ƃ̎l�ƘV�̉~�鎛���ƑS���ʂ̉ƌn�Ƃ��v���Ȃ����A�ƘV�̉~�鎛���͐�t���̎x���ł��邩�瓖�R�����ł���A�����̕���������ƋL����Ă���B
�ƘV�E�͐}����(���傤)�吭�Ɏn�܂邪�A���̐l�͐}���E�q������Ƃ��̂��A�������N(1334)�����A����̑㊯�����Ă������Ƃ���t�����̕���(���敶���[)�ɂ���Ēm����B
���̐l���X�͂̏���ɏo�Ă���}�����q��Ɠ���l���ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ͐�q�����B
���敶���ɂ͂��̂ق��ɂ��~�鎛���̐l���͑��������A�}�����q��ш����͂����Ɖ��炩�̊W��������̂ƍl������B
���Ï�̖k�ɃQ���W�x�Ƃ������̎c�钆���ِ̊Ղ�����B���ՂɌ��ѕt���邱�Ƃ͐T�܂˂Ȃ�ʂ��A���̖��͂��Ƃ��A�����̑������̒n�ň��������Ɍ����ł��������Ƃ���t����ꂽ�Ƃ����悤�ȉ��������Ă��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B
�@��ɐ�t������E���镃�q���u���E���×���𗎂Ƃ���Ď��n�����Ƃ��A���҂Ɖ^�������ɂ����~�鎛���ꑰ�����邪�A�������q�����̒n�ɗ����̂т����ċN��}�낤�Ƃ����̂��A���̒n���㐙���ł���~�鎛���̐��͌��ł��������߂ł͂Ȃ����Ƃ��z�������B
�@�����������͐�c�`���̔튯�ł���A�܂���t�@�Ƃ̉ƘV�ł���吭�̌n���ɂ͈����̖��͌����Ȃ��B
�����ň�C�ɂȂ�̂́A�w��t��n�}�x�Ɍ����鑽�È����̌Z�ɓ���������Ƃ����l���ł���B
����̑��ɂ������c�펟�Y�����̒��q�̈ʒu�ɂ���(�w�_��{�n�}�x�ł͈����̌Z���p�̎q�ƂȂ��Ă���)�A�ܑ��̎q������͂܂���c�����̂��Ă���(�u������̐�c���Ɛ�c���̌n���v�̌n�}�Q��)�B
�����Ƃ��̎q���l��ڂ܂ł���c���ł��������ǂ����͂킩��Ȃ��B
�܂��~�鎛�𖼏��Όn�}�͂��̂悤�ɋL���͂��ł��邩��A���̈������~�鎛�����ɔ�肷�邱�Ƃ͐T�܂˂Ȃ�Ȃ����A��c���Ƃ̊W�͕���q������c���̂��Ă��邱�Ƃ���\���l������B
�����n�}�ł͈���̎l���ł���A���S�Ɠ�����ł���\���͔����ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����Ƃ������W�̌n�}�ł͎O��悪�K�������]���ƌ��炸�A�Ҏ҂̎��R�ȊW�Â���������̂ŁA���܂�n�}��̊W��ʒu�ɂ������K�v�͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
�@�ނ���}�����q��ш����Ƃ��ẮA���T���ɂ��Ă̒X�͂̏���Ɍ�����}�����q��̕����ꑰ�Ƃ��Ẳ\�������肻���Ɏv����B
����������ɂ��ẮA���̂Ƃ��뉽�̎肪����������Ȃ��̂ŁA����̉ۑ�Ƃ��Ďc���Ă����B
�@���āA������q���i�a��N(1376)�ɖ@�،o���l������(1313�`99)�������ē��@�����̊J�ዟ�{���s�����A���̑O�N�̌܌���\�����̓��t�̂�������̖{�����������ɏ�������Ă���B
����ɂ́u���Ö؛����v�̘e����������B����͂����炭���Ñ������̈ӂł��낤�ƒ�����͂��̒��w���@�@�̐����ƓW�J�x(�g��O����)�̒��Ő��肳��Ă���B
�����Ă��ꂪ�{�������̏ꏊ��\�킷���̂ƍl����Ȃ�A���̎��_�ł͖������͂܂��������̂��Ă���A�܂������͑��Ñ��̓��ɂ��������ƂɂȂ�B(���̒n�͐��䌴�Ƃ��Ă��ɐ��䑺�ɓ��邽�߁A�������͐��䂩��ڂ����Ƃ������`�����Ă���)
�@�ȏ�̓_�𗥋C�ɍl����Ȃ�A�i�a���N(1375)�܌��ɂ͑��Ñ������ł���A�i�a��N�ɂ͑��Ñ��������ƂȂ��Ă����Ƃ������ƂɂȂ�A�������������Ɩ������߂�̂́A���̔��J���]�̊ԂƂ������ƂɂȂ�B
�܂�~�鎛��������U�߂ł����������ɓ��S�̌������{���s���A�������Ǝ��������߂āA�����炭���Ƃ��Ă̌`����������Ɏ������̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ낤�B
�������w�������̞x�x�ɂ��A�������Ɖ��̂����̂́A�i�a�l�N�\�ꌎ��\�����A���S�ɂ���ĊJ�����{���c���Ɠ`����Ă���B
�����Ƃ��A�w���R�@�،o�����x�̗�㕈�ɂ��A���S�̖v�N�͉������N(1374)���\���Ƃ��邩��A�����M����Ȃ�A���S�̊J�����{�͂����肳���̂ڂ�A���{������̂܂łɂ͎�̔N�����������Ƃ��l�����悤�B
�@�������A�w����R���N�x�ɂ��A�������͍O���N��(1278�`88)��݉@�������J��Ƃ��āA�n�����ꂽ�Ƃ����B�����炭����͌�������ɓ�������@�@�̓��Ƃ��ĊJ�n���ꂽ���Ƃ��̂��Ă���悤�Ɏv����B
�@�w���@�@���T�x�ɂ��A��݉@�����́u�������֓����j�Ƃ����A�㑍�������ɏZ���������]����̂����Ƃ����B���ߓ��@���l�̋����ɗ������̐M�҂ł��������A�̂��o�Ƃ����Ƃ����B����������(������)���Ђ炫�A�̂��������Âɂ����Ė������������A�܂��u��������(���A��A�}�})��n�����B
���̖v�N�ɂِ͈��������Ē肩�łȂ��B
�㑍�������`�ɂ��O����Z�N(1287)�O�������A�����������`�ɂ��O���Z�N(1283)�܌���ܓ��Ƃ���A����͂�������s���A�w�{���ʓ����c���L�x�͍O���Z�N�܌���O���Ƃ��Ă��邪�A���������s���ł���v�Ƃ��Ă���B
�@��A�̕����́A�u�u��(��)�������̓��F�����āA���|��������n�������v�Ƃ���̂��Ó��̂悤�ł���B
�@�@�@�@��������(���݂̐��o���̑O�g)�͉i�m�ܔN(���㎵)���R�@�،o�������ɂ���Đ^���@�����@�A��ɑ哈�a(��c���p�܂��͂��̌p����)����U�߂ƂȂ��ē��������F�����������Ƃ����A�܂��w���|�������L�x�͒厡�O�N(1364)�����ɂ���đn�����ꂽ�Ɠ`���Ă���B
�@�w���@�@���T�x�̓����̖v�N�ɑ��ẮA���Ö������J��̔N�͓K�����邪�A���E���|�̖������̏ꍇ�͓K�����Ȃ��B
�w���|�������L�x�͉����Z�N(1373)�܌���\�ܓ��v�Ƃ��A�O�Ɖ��̈ꎚ�Ⴂ�ł��邪�A���ꂪ�J�n�����̍��ɋy��ł���悤�ł���B
�Ȃ������J��̖��ɂ��ẮA������j(���˂�)���w���ӗR���L�����x(���a��)�ɂ��܂��܂̍ޗ�����čl�@���Ȃ���Ă��邱�Ƃ�t�L���Ă��������B
�܂��A�������J��Ƃ��鎛�ɂ́A�ȏ�̖������̂ق��ɁA���������(����)��������B
���̊J�n�͉����ܔN(1372)�Ɠ`�����Ă���B
�@���đ��Ñ����������������Ă���������ɓ��E�c�n�͖������Ɉ����p���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A���̌���@�،o�����ۗL���Ă������Ƃ͉��i�l�N(1397)�̊��q�������������ƁA���i��\���N(1420)�̐�t�����̎��̈��g��Ɂu���������X���Ɓv�ƋL����Ă��邱�Ƃɂ���Ēm����B�u���X�v�Ƃ���悤�ɁA����ɐ��𑝂₵�Ă����̂ł��낤�B
�����Ė����̖������Ƃ��Ă͉~�鎛���̂悤�ȑ�U�߂�V���Ɋl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�Ƃ������͉~�鎛���̂悤�ȑ�U�߂��ł������Ƃœ����玛�ɏ��i�����Ƃ����悤�B
���������̎�E����w�̎x���������̏@���{�݂ɂ͕s���ł���A���������h�z�̐M�͑m������đ����ɋ����e�������̂ł������B�ĐM�҂͊K�w���ƂɁA�܂��������Ƃɍu�����сA�����E�����̋~�ς�������F�����̂ł���B
�@�w���ӗR���L�x�ɂ���u�ߋ��̒j�����Ƃ��Ƃ��݂ȉ��@����v�Ƃ����悤�ȑ�����݂̐M�ł́A�����̉ʂ��������͂���߂đ傫���B
����͒P�ɐM�����̏�ł͂Ȃ������̂̂��܂��܂̊����̒��S�ł�����������A�̎�͂��̈ێ��̂��߂ɓc�n����i�����̂ł��낤�B
�M�������A�M��ʂ��ċ����̂�c�����邱�Ƃ͏��̓������~���ɂ����͂��ł���B
�@��c����̗P�q�ł�����S�́A����̖{���ł��钆�����ɂ����ẮA�쒆���Ɍ������N(1319)���{���̊�b��z�����ق��A�k�����k��́@�@�@��(���́A���s��)�A�������ł̓�������^���@������@�����Ă���B���̂ق��k�����v�ۂ̕������A��a�c�̕������Ȃǂ͓��S���J�R�Ƃ��đn������Ă���B
����Ȍケ���̎��͒��R�@�،o����{���Ƃ��Ă���Ƃ̊W��[�߂Ă������ƂɂȂ�B
�@��c����Ƃ��̌�p�҂炪���R�@�،o����^�ԍO�@���ȂǂɊ�i�������E�c�n�ɂ́A�O�q�̂悤�ɐ�c�����ł͑q������ɓ��A�����A���������v�R���Ȃǂ�����B
�����̓��݂͂Ȍ�������ɓ��̏ꍇ�Ɠ����悤�ɂ₪�Ė@�ؓ��ɉ��߂��A���ɂ͎��@�ɔ��W�������̂��������B���̑��A�����E�������̖�������E�Ƃ��̐_�c�Ȃǂ��������B(�⒍�Q��)�@
�k�⒍�l
�@�����Z�N(1361)�̓��S����ɂ́A�u���^���́v�̈�Ɂu��������E�@��_�c���E�����L���V�v�Ƃ���A��c����̔N�����ڏ���ɂ͂��̐_�c��i�̂��Ƃ��L����Ă���B
�܂��A��c�����Ɛ��肳������(�N������)�ɂ́u�������Ñ��V�J�m�_�c�ꔽ�A�����O�ʓ��m�c�ꔽ�A���v���܂܂�Ă���(�ȏ�A���R�@�،o������)�B
���̑��A������N(1445)�̓��Ւu���ɂ́u�����O�J�V�c�����Óc�v�̑����̂��Ƃ��L����Ă���(�s��s���R����@����)�B
�@
�@���������ɂ��ẮA�匴���̖�����(���A�@��������)���狏�˂̖������ɑJ������A��t���������Ɏw�肳��Ă��閭�������A���q����̗D��Ƃ����Ƃ��납��A���邢�͂���͈���ɂ���ĕ��J���ꂽ���̂ł���A���S�ɂ��̍���E�Ɛ_�c����i���ꂽ���̂ɓ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������肪���藧�̂ł���B
�@�������Đ�c���̓����E�암��т͂��̂قƂ�ǂ̎��Ƒ����S�̂����@���āA�������~�@�����������̂ł������B�������Ȃ�����嗬��c�����������㔼���琊�ނ������߁A���R�@�،o���Ƃ��̖嗬�͂��̉e�����A���̊���������Ă������B
�@��c���������̓��E�c�n�⓰�Ƃ���i�����n�悪��c�������E�암�Ɍ�����̂́A���̏��̂����S�̂ɋy��ł��Ȃ��������߂ƍl�����A���̂��ߖk���E�����ł͐^���@������@�@�ւ̉��@���s��ꂸ���݂Ɏ��������̂Ǝv����B
����Ɍ��钆���̐M��
�@�@���{���ɂ��ẮA���ʂ̊ԏȗ�����B
�����@�@�s��s�{�h�̖@���i���������Ò���j�@�@�㊪335�`
�@�@���s��s�{�h�T��
�@�@�������̖@��i���Ò���j
�@�@���V�ۖ@��E�n�����i���Ò���j�@�@
�@���i�\�N(1633)���{�͊C�O�n�q�E�f�Ղ̐����ƂƂ����L���V�^�����֎~����@�߂��o�������A����Ȍ�A�M�k�T���̂��߂ɏ@����߂��s���A�܂����@���ĕ����ɋA�˂����҂���͐����������B
���ꂪ��ʉ����Ď������x�ƂȂ�A�����͏������@��h�ߎ��Ƃ��A�����◷�s�Ȃǂ̍ۂɂ͎��̔��s����@�|��`���K�v�ƂȂ�B
���̂��߁A���@�͏����̎v�z�Ď@������ƂƂ��ɑ��̌ːЎ����������s���@�ւƂ��Ȃ��Ă��܂��B���������@�͌c����N(1597)�ȍ~�́u���@���@�@�x�v�A�����ܔN(1665)�́u�������@��|�v�Ȃǂɂ���Ă��т�����������A��ʂł͕ی�����̂ŁA�@���{���̏O���̋~�ς��͐����I�x�z�̖��[�̖�����S�킳��邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ȏ@�����x�̒��ŋN�������̂��A���@�@�s��s�{�h�̖@��ł���B
���Ò���ł͍]�ˏ������ɂ����E������E����E�匴�̊e�����قƂ�Ǒ�����ݓ��h�̐M�҂ł���A���ˁE�т����ʑ��E��Ȃǂ̑��X�ɂ��M�҂������B
�@�s��s�{�h�����̏@��Ƃ��ꂽ�̂́A�����ܔN(1665)�\���A���łɖ��{���琔�x�̒e��������ł������B
���̔h�͓��@����q�̘Z�V�m�̈�l�A���N�̗��ꂩ��h���������̂ŁA�@�c���@�́A���E�̎�͎߉ވ�l�ł���A���̈א��҂ł����Ă��߉ނ̓�������ׂ��l�Ԃł���Ƃ����v�z�������ɓ`�����i�Ƃ��āA���̏@�|��M���Ă���҂̋��{�����A�܂����̏@�|�̑m�ւ͋��{���{���Ȃ��Ƃ������`�����łɎ�葱�����@�|�ł���A���̏������͊����@�h�ɑ��Ă��V���𐁂����̂ł������B
�@���E�̎�͈�l�ł���A�̂ɑ��@�M�҂̋��{�͎��Ƃ����v�z���A���̈א��҂ɂƂ��āA���R�Ƃ��Ƃ��`�Ō���ꂽ�̂��A���\�l�N(1594)�ɏG�g���s������m���{�ւ̎��ނł������B
�@���̂Ƃ��A���s�n���ɂ�����s��s�{�z���̋��_�ł��������o���̏Z�E�����́A���`�ɔw�����Ƃ͂ł��Ȃ��ƎQ�������݁A���̏�ɁA掖@�Ƃ͖@���(����)�邾���łȂ��A�s�M�̋��{���邱�Ƃ�掖@�ɒʂ���A����Ȃ�����z�{����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ɓu�@�؊Џ�v���G�g�֒�o���āA�O�g����ɉB��Z�ށB
�@�����́A���s���O�E�҉Ƃ̐��܂�ł��������Ƃ���㉇�҂������A���̍s���ɂ���Ė{���̋��`�ɖڊo�߂��M�҂��A��m���{�ɏo�d�������X�����̂Ă����߁A���s���������ЂȂǂ��ْ[�א��Ƃ��ē�����r�����A�G�g�ɑi����B
�������ė��h�̘_���������A�₪�Čc���l�N(1599)�A���钆�ɂ����āA�����Ɠ��Ђ̑Θ_�ƂȂ�B
�u�@���|��v�����G�g�͂����s��ɂ������A���O�N�����Ɏ������A�����đi�������ƍN�́A���O�ɗ^�����g��̑傫���������Ƃ���A���Ђ̐��𐳂����Ƃ��A�������א���������҂Ƃ��đΔn�֗��Y�Ƃ���B
�Δn�̓������A�u���N�͔��т������A�c��������ƂȂ�v�ƁA�ꂵ�����Y�̓��X�̂��Ƃ��������������A���Ò����˂̍����ƂɎc����Ă���B
�@�c���\���N(1612)�͂���āA���s�ɋA���������́A���������������̂͂��炢�œ��Ђ�Ƃ��a�����Ȃ�A���a��N(1623)�ɂ́A���s���i��q���d����s��s�{�����̐����āA���̒�R�͏I�������B
�@���R���ɂ�����s��s�{�h�m�̎��́A�����ɋ��s�ɂ�������@�@�̓����ɂ����̂ŁA���{�ɋ��͂��Đ��͂̐L����}�鑤�ƁA���`�̏�����������ċ�����L�����Ƃ��鑤�̑����ł������B
�@���������āA�������]�˂Ɉڂ�ƁA�֓����g�����n�߁A�����̎�`����r��{�厛�̓����⒆�R�@�،o���̓�����́A���i�O�N(1626)�A�]�ˑ��㎛�ʼnc�܂ꂽ��㏫�R����G���v�l�̑��V�ɁA���@���u�o���s��ꂽ�ȂɎQ���͂��Ă����R�̕z�{�͎Ȃ������B�������A�g���R�v�����̓�����́A�����̎�`�Ɉًc���ƂȂ��A���̏��Ƃ��āA�z�{�����̂ł������B
�@���̓������������������Ƃ���A�r��{�厛�h�Ɛg���R�v�����h���Η����邱�ƂɂȂ�B
�����āA�Η��̐[�܂��J�����g���R��������ٌ��{�ɑi�������Ƃ���A���i���N(1630)�A�����y�����~�ɂ����āA������g�r�Θ_���s����B
�o�Ȃ����̂́A�s��s�{�h�����r��{�厛�����A���R�@�،o�������A����{�y�����O�A�����a�������́A�蕶�J�@�؎����i�A�����h�ѓ��[�A��h����͋v���������E�����E�����A�Ό������A�ʑ�����A�{����S���@�̗��h�e�X�Z���ŁA���{������͒������Ƃ��ēV�C�m���E���`���t�炪�o�Ȃ���B
�@���̌��ʁA�����̎�`����r��{�厛�h�́A�܂����s��Ďד��Ƃ���A�����͐M�B�ɓ߂ɗ�����A�����E���O�E���́E���[�E������͒Ǖ������B
�@����܂ł̑Η��͗��h�̒��S���@�̎哱�������Ƃ��Ă̐F�ʂ����������̂ŁA�������ʐM�҂ɋK�����y�Ԃ��Ƃ͂Ȃ������B
�x�d�Ȃ�e���ɂ���ċL�^�͉B����A�܂��͏��ł��ďڂ������Ƃ͂킩��Ȃ����A���̂Ƃ��r�㑤�Ƃ��ČĂяo���ꂽ���X�̖����݂Ă��A���Ò���̓��@�@���@�͂��̂��낷�łɁA���R�@�،o���̖����𒆐S�ɂ��̑啔�����s��s�{�h�ƂȂ��Ă����Ǝv����B
�@�u���i�@��v�ƌ�ɂ����邱�̎����ŁA�[���̕s��s�{�h���@�̂قƂ�ǂ͉��@�𐾂��Ď͂���邪�A��ʂ̐M�҂܂ł����@�����킯�ł͂Ȃ������B
���Ɍ��݂̑��Ò��E�I�����E�����s��s�n���ɂ�����M�҂̐M�����ɂ͑傫�ȕω��͂Ȃ������悤�ł���B
�@�܂��犰�i�\�l�N(1637)�������̗����N����A���m�ł͂Ȃ��A��̑̌��̂Ȃ��_�����A�M�̗͂Ɏx�����Ēc�������Ƃ��̒�R�̍�������ڂ̂�����ɂ������{�́A��ɐݒu�������Е�s�ɂ���āA�L���V�^���ƂƂ��Ɏ@�Ƃ�����@�h�̒e�����n�߂�B
�܂��u���@���@�@�x�v���e���@�Ɏ����āA��@�̖@�������A�V�`�𗧂ĂĊ���̖@������ȁA���{��������`���A�Ɩ�����B
����ɑ��āA���̖@�x�͏@�`�ɔ�����Ƃ��āA��������߂ď�i�����̂��A�s��s�{�h�̕���{�y�����q�A���Ö��o����ꟁA��C�h�ѓ��u�A�ʑ��h�ѓ�����ł������B
�@���{�͎@��������҂Ƃ��āA�����ܔN(1665)�\��������������߂ɂ���B
�u�����̑y�Łv�ƌĂ�邱�̎�������A�L���V�^���ɑ���Ɠ��l�̒e�����A��ʐM�҂ɂ܂ŋy��ł���悤�ɂȂ�B
�@�e���̉e�ɂ́A�@��̑���������ł����B
���鎛�̏Z�E���߂��Ď���ǂ���ƁA���Δh�̐g���n�����{�̎x�����ďZ�E�𑗂荞�݁A�����ŁA�������h�̏@����g�傷��Ƃ����������̂��Ă����B
���������\�̂���ɂȂ�ƐM�҂̐M�O���ł��Ȃ������߂��A��h�̑m�����ɓ���ƒh�Ƃ������悤�ɂȂ�A�o�c�ɍs���Â܂�悤�ɂȂ�B
�@��h����̐\������������āA���\�l�N(1691)�ɂ́A�㑍�A������тɒe�����s���A�Z��l�̑m���ɓ������֗����ꂽ�B
���̎��A���߂�ɐ悾���āA�S�Z���ɂ��Čl���ƂɎ@�̐M�҂ł��邩�ǂ��������X�ɒ�����o�����������ؕ�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@������V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�ߏO�@�d�E�q��@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�ȉ��\�ꖼ��)
�@��A�E�E��l�V�ҁA��X�^���@�ɂāA�ّm�U�߂ɕ����������A��(����)�������A���x���t���A�E�s��s�{�E�g���x�O�@��Ɛ\���Ҍ����́U�A����迠���ّm���o�A�}�x�\�������d��A�ד����ꎛ����ˎ��@�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S�厛���{��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������葺�@����@�@��
�@�@�@�@���\�l�N(1691)���m�܌��\���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������l��m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�����q�a
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���@�d�E�q��a
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@���E�q��a
�@
�@�e������ʐM�҂ɂ܂ŋy��ł���悤�ɂȂ�ƁA�s��s�{�h�̐M�҂́A�\�ʂ�������Ēn���ɐ��s�����B
��ʐM�҂͉��@���𖼎���o�Ē�o���Ď�h�̎��̒h�ƂƂȂ�A�z�{���o�����{����B
�����Ƃ��A�s��s�{�h���̂��鎛�͈�|����Ĉꎛ�Ƃ��đ��݂��Ȃ��������瓖�R�̂��Ƃł���B
��h�⑼�@�̎��͏������̂ق��A�s���̖��[�@�ւƂȂ��āA�h�k��Ƃ̏o���E���S�̋L�^�A�A�E�ɓ������Ă̐g���̏ؖ��A���s������Ƃ��̐g���̏ؖ��Ȃǂ����@�̎d���ƒ�߂��Ă����B
�@����ɑ��s��s�{�h�̐M�҂́A�e�����ƂɈ���݂��āA��ڍu�Ə̂��ďW�܂�A�Ђ����ɏ��Ă���s��s�{�h�m�̖@�b���A���{�����B
���̑m�����h�ł͖@��(�ق����イ)�Ƃ����B
�@���͎�h�̎��ŏC�Ƃ��A�m�Ђ����ƉB�����Ď�h�̎��𗣂�đg�D�ɓ���A�����݂ɒe���̖ڂ�A�e�n�̉B��Ƃ�����ړ����Ȃ���z�������B
�@�e���̑�ڍu�ɂ͖@��(�ق���イ)�Ƃ��������҂����āA�@���ړ��̈ē�����A�H���Ȃǐg�̎����̐��b�������B
�z�{�͖@��������āA�����K���i��@���ɓn�����@���Ƃ�ꂽ�B
���̎d�g�݂͌��݂ł�����Ă��āA�m���͓��H�ȑт������A�z�{�Ȃǂ̌����͎��������Ǘ����A�O�H�܂Ō������t�ł���B
�@���M(�\�ʏ�A��h�̎��̒h�ƂɂȂ��Ă����ʐM��)�\�@���\�@���̒n���g�D���ł�������A���Ò���ɂǂ̂��炢�̈�������������f�ГI�Ȏ������炽�ǂ��Ă݂�ƁA������E�⑺���E�D�z���E�ʑ����E�ʑ������E�����(�����낮��)���E������A�،ˈ�(��)�ƁA���݂��s��s�{�M�̑����Ă��鑺�X�ɑ����B
�@�e���͂���ɑ����āA���\�\��N(1698)�ɂ͈��[������������A�����ɓ���Ɖ����֒T���̎肪���тāA���Ô˗̂𒆐S�Ƃ��đ�e�����s��ꂽ�B
����͎j��u���Ö@���v�ƌĂ�Ă��邪�A����ɂ��Ắw�����쑺���L�x�ɋL����Ă���̂Œn��j�Ғ�����̏͂ɏ���B
���ɋN�����̂��u�V�ۖ@���v�ŁA�ȉ��Ɂw�����@��L�x(�ʖ��w�V�ۏ\��q�N�@��ꌏ��ً����r��(����܂�)�n�����V�L�x)������p����B�����͓V�ۋ�N(1838)�����͂��ߍ���S�𒆐S�ɂP�S�W���̎҂������߂��A�撲�ׂ��������̎n�����ł���B
�@
�@�@��ꌏ���L(��������)������܂��́A�V�ۋ�N���(���̂�����)������{�A�]�˕\(������)���������E�q���(���)�A�����@���L���V���A�����ɂāA���N�������������Ñ�����o���A�֓��������ˈ�Y�l��~�h�ɂāA��q�ɑ�����A���A�����@��Ҋ�R���F�E�q��A�����쑺�@�V(�}�})�A�����ɂĒ����q�A���V�厀���ɕt����(������)�厡�킒�q��(�����炦�ǂ�)�s���o�B��Ώ����Ñ��֔��A�����@�A����B���ƂĎs�Y���q����A�����@�A�����A���E�q��E�O�Y���q��A�s�����l���Ñ��ɂČ䒲�V��A�s�Y���q��E�Ώ����l�ґ��Ƃߎc��A�ܐl�ҍ]�˕\���o���ɑ�����A��|���Ќ��s�q����O��l�����A���o�@�A��(����)�֔킒���A��ᖡ���A�O�Y���q��ҋ㌎���{�ɕa���������A����l�l�ҏo�S�ɑ�����A���E�q��ҍ]�ˏh�`�ʉ@�O�r�c���ɂď\�ꌎ��{�a���������A�����q�җ��N�����~�O�A�����A�t�@�A�����N�q(��)�V�O�����{�ɓ��ɂĕa���v���A�E�q����O��l���ւɑ�����A�����ɉ��l�����������V��͌�B�������l�����{�ɑ�����A���X�֓��������R����Y�l���Ñ�����o���ɂāA�ߋ����X�����X���X�A���X���@���܂Ō�ďo���A���X���X����(������)����(��������)�V��V��(����)�X������A���V�ʂ荷���B
�@�@�@�@�@�k���l���͍ݘS���̏d�a�l�̎��e�{�݁B
�@�@�@�@�@�����_�͂��A��_�A��_���@�A�A�ő�p����B(�ȉ��������j
�@��A���X�����V�グ�ؕ��B
�@��A���@�������V�グ�ؕ��B
�@��A���l�����グ�ؕ��B
�@�@�@�E���ʎҗ����B
�@�@�@�@�@�k���l�グ�ؕ��́A�ً��ɕ����Ƃ������o���B���ؕ��Ƃ������B�����͌��㏑�B
�@�E�V��Q�ؕ��V��`�摵����A�{�탌����B���N�Z�����{�ɑ��X���X���@���܂ŏ����ɉ��l���䍷���ɂĔ��A�����@�A�]�ˏh�ҊO�_�c�䐬��(���Ƃ����Ȃ�݂�)�A������䒬�A��n�嗢���Ε��q�A�n�ɓ�O���A���ΐ�t�����单���A�E�h�X�ɔ�݂��ďo����҂��A�����\����ďo���ɂāA�ɉ��l���A�䔒�B�@���X���@���ꓯ�������A��Ǖ��@�A����䏑�����A�t�@�A�A���v����B���N�\�ꌎ���{�ɖ��X�䍷�����ȂĔ��A���o�@�A�E�h�Ɏ~���ɂāA�\�\�Z����ďo���ً����A�n�@��B
�k���l�����͕�s������̌ďo����B���������ď������邽�߂ɂ����B
�@�@�@�@�@�����ɕt�����A�����@�\�グ��
�@�������E�q��m�s���A����������S�������@�@���h���\�グ��B�َq�h�������E�q��Ɛ\���ҁA��@�x�V�s��s�{�@�傦�A�˂������A�������Ƃ��đK���l���A�O�E���A�������E�q����֍��o���A�E�V�i���ʌ����ɕt���������m�d����������B�����E�V�ҋV��Q�葴�O�d��(������)��V�ʂ�A���ւ�̋`���A����@��ɕt�����V�S�t���������V�A�႒��(�������Ȃ���)�h���ɉE�[(�Ă�)�V�җL���V��s������݂��i�A�䍷���Đ����͐\���l�����A����@�A�������B����h�����X���w�d��A�E�[�V�@�傦�g��s���\��l���d��ԁA����(�ȂɂƂ�)�i�ʔV���A�䎜���@�䊨�ٔV���l(�͂���)�ЁA��(�ЂƂ�)�Ɋ�グ��B
�@�E�����ɕt���\�グ��ʂ�A���������ᖳ�A����@��B
�@�@�@�V�ۏ\��q�܌��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E�q��m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S����
�@�@�֓�������o���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���h��
�@�@�@�@�@�@���R����Y�a
�@
�@�@�႒�������ɕt�����A�����@���A�\���@��
�@�������E�q��m�s���A����������S�����S���O�Y���q���P�����A�\���@��B���c���P�����@��`�A�s��s�{�@��`�@��������n���A��������A�E�@��y�A�V���@�����֕s���\�A���㑊���茓(����)��ɕt���A���������d����A�P�����A�\���@��B
�@���i�P�����A�\���@��A����Δ��l�����d��A�e�O�Y���q��`�͋�(����)�X���N�㌎���䏢�߂ɑ�����A�����c���@��A��A���Z��Ƃ��Ɠ����l�邵�A�_�Ɠn������B�R(����)�鏈�A�@��`���q(��)��\��ɔ됬��A���ʌ�ďo���䌩�����A���u�@��ʂ�A��V�O�V���d��A�������A�����@�A���������㑊����s���\�A�����V��(����)�X��(����)�Ƒ����茓��ԁA���������d������A�\���@��B���@�|�V�U�߂ɑ��ᖳ�A����@��B�E�@��Ɛ\�����ғ����P�N��(��)�O�A���l�ȕa���v���A��茚�Č�߁A�L�鎛���ꓯ�@��������(����)�Ќ�V�b(��)�A�E�s��s�{�@�傦�A�˂�������`�́A��N���N���Ɍ��(��)�A�����S���v���Ɛ\���җL���V�A���҂�芩�ߋA�˒v���A���l���\���P�N�ߑO�a���������A����ґ����S�����V��E���E�q��E�����O�Y���q��A�O�l�ɂďd���M�S�d���B�ۏB�����Ñ��@���b�G�@�����M�S�V�҂ǂ��{��(������)��W�ߌ�(����)����R�ɂāA�܁X�䓖�n���������������E�q����֍�������`�L���V�A�����@��`���M�ɂāA��ɘV�N�ɕt���A�������E�O�l�֔C���u����`�ɕt���A���l���O���ȂĔ@��(����)�l�V�V��l(�͂���)�Ќ��(��)�s�A�����@�@��(�ЂƂ�)�ɓ�L�@��ƐS���A���X�M�S�v����V�͑��ᖳ�A����@��B�`�@����Ɣ�(�₢��)��A���A�����@���A�]�l�V�\�����ߌ�V���]��(����)�����d���V���A����@��B�႒���A�䐧�֔V�@�傦�A�˂�������i�A��ᖡ���(�Ă�)���A�\���@�l�����A����@�@���A�����@��B�ȗ����@�ׂ��v�A�ܘ_�Ɠ��ꓯ�E�@�傦�g��\���ԕ~(�܂���)��ԁA����(�ȂɂƂ�)�i�ʔV���A�䎜���@�����(�т�)�V���l(�͂���)�ЁA��(�ЂƂ�)�ɕ��A����@��B
�@�E��������A�@��V���d�蕪�茓��ɕt���A���X�����d������ȂāA������ɂč��i���A����@��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E�q��m�s��
�@�@�@�V�ۏ\��q�N�܌��@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���@�P�����@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@�O�Y���q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�P��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y(��������)�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@���E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���@�V�E�q��
�@�@�֓�������o��
�@�@�@�@���R����Y�l
�@
�@�����n���ꂽ�ً��̓��e�́A�ۏB(�ےÍ��A���{)�{���@�����������ɂȂ�Ȃǂł������B
�ȉ��A���̐��ؕ����瑽�Ò��W�̎�Ȃ��̂������f�ڂ���B
�@
��A�F�E�q��O�S�l�E�O�l�A�s��s�{�@��䐧�ւ�႒����������i�s��(�ӂ炿)�Ɍ��A��ᖡ�V���S��������V�ɕt���A�ؕ����A�t�@���A�ꓯ��\(���܂�)���A����@��i���A�n�@��B
�@�k���l���̈�l�l�l�����Ò���̑����͋�O�l�ł���B
��A��R���O���X����g�����V�A���X�����V���̋��䐧�֔V�s��s�{�@��M���������s������݂��i�A�S�����s�s��(�ӂ䂫�Ƃǂ�)�s���ɕt���A����҉ߗ��K(����)�O�ѕ������A�t�@�A�g���ǂ��͋}�x(������)�䎶��킒�u��B
��A�����^�O�l�E���l�V�A�h�ƔV�ҋ��c���e�ߗ���(�Ђ���)�ɕs��s�{�@��M�v�����s������݂��i�A��ɏZ�E�������@�|����(��������)��F�����V�s���ɕt���A�ꓯ�N��(�Ђ�����)���A�t�@��B
��A�����������q�X(����)���E�q��V�A�s��s�{�@��ҏd���䐧�֔V�i�႒��(�킫�܂�)�A�N���E�@�ӑ�������B����A�������������V�厖�P�x�C���\�A�ۏB�����Ñ��O�������̖@�p�A���O�����ʓ������̖��O���ȂĎ挭(���J)�v���A��(���܂�)�ᖡ�ɑ�������A���@�ɂ͓���A��s�{�V���@�@�ɉ��h�������x(����)�|�V�\������A�E�n���s�͂ɕt���A�����Ɍ҉������A�t�@��B
�@�E�V�n�������A�t�@���A���X�a���������A�͏B(�͓���)�k������(�������J)���T�A���h�����q��A�����������O�Y���q��E���E�q��E�����q�Ҍ�ᖡ���a����������ԁA���|�����i���A�n�@��B(�ȉ��O���ȗ�)
�@�E���A�n�@�V��A�ꓯ���m��(������)��B��(����)�ߗ��K�O���V���ɓ����s�������A���[�@�|���A�n�@�A�������m�،�B��(����)���w(����)����́U�d�ȉ��A�t�@��B�ˎ�(�����)�䐿(����)�ؕ����グ�\�����@�����B
(�����ȗ�)
�@�@�@�@�V�ۏ\��N�q�\�\�Z��
�@�@���Ќ��s��
�@
�@���Ò���ł��̎����ɊW���Ĉȏ�̂悤�Ȑ��ؕ��������o�����̂́A���䑺�X���A�����쑺�P�O��(�������R���A�S������t�P��)�A�D�z���V���A�匴���R���A�k�����P�T��(�������Q��)�A�쒆���R���A�{�O�q���Q��(����)�A�ё��R���A���Ñ��X��(�������P��)�A�����R�Q��(�����S�P���A�S������t�P���A�����Q��)�A���v�X�R���B����S�ł͑E���E��x���E�{���E���͑��E�ђˑ��E�������E�r�k���E���쑺�E�������E���c���E�g�c���E�������E�╔���A�㑍���ł͕��ˌS�����E��R���ō��v�S�V���A���̑��łS���ł������B�܂������̑��X�̓��@�@�e�����ؕ����o���Ă���B
�@�@�@�@�@�k���l���ؕ��̏����̂��������쑺�̕���203�y�[�W�Ɍf�o���Ă���̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�T�C�g�ł́��s��s�{�h�ɑ���e���y������j�z�Ɍf�ڂ���B
�@�@�@�@�@����\���䐿���V��
��A���ʎ����V�s��s�{�@��ꌏ�ɕt�����A���o�@�A��ᖡ�V����A�n�@�A���ς�ɕt�A�A�����A�t�@��L�d�����ɕ���B�R(����)���ҁA�ǎ�(������)��������o��l�킒���A��z�@�A���l���ւ͉�S�ؕ����A�t�@����(�݂���)�A��`(���傤)���グ��l���A�n�@�،�B�ˎ��E���A�n�@�V����A��`���グ��l���d��B�˂��V�䐿�����グ�\���@�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E�q��m�s��
�@�@�@�V�ۏ\��N�q�\�\����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l�y��@�@�����q�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�V�E�q��@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���@�@�@�d�Y���q�@��
�@�@���Ќ��s���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@��u�q�@�@��
�@
�@����ɔނ�̎~�h��̍]�˂̗��ĉ����������o���Ă���B
�@
�@�@�@�@�@����\���䐿���V��
��A���ʕs��s�{�@��ꌏ�ɕt���A���@���v�X(���ꂼ��)�ɔ��A���o�@�A��ᖡ�V��N�ǔ��A�t�@�A�R�鏈�A�����A�n�@��ԁA�A���V����X���T�ݔ�݂��l�A�����~�h����������S���Ñ��A���@�@�����^�O�E���l�����A�\���@�i���A�n�@�،�B�˂��V�䐿�����グ�\�����@�����B
�@�@�@�V�ۏ\��N�q�\�\����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�单���Ε��q
�@�@���Ќ��s��
�@
�@���̂悤�ɂ��ꂼ�ꐿ���������o�����Ƃɂ���ē����҂͋A����������A���̂悤�Ɉꌏ�͗��������B
�@
�@�䎛�@���N��(�Ђ�����)�V�Ȕ��A�t�@��݂�@����p�N(�݂��̂�����)�������{�ɕs���c�䍷���ɂĔ��A���o�@�A�E�Ȍ�ƗL���V�A���{�ɂ͑��X���A���v���B
�@�����A�E�ؕ����A�t�@�X���X�A���N������{�Ɋ֓��������씼���l�A���J�������ق�~�h�ɂĔ��A�ďo�@�A���X��ؕ��V��`�킒��(����)���v�A���X�A���d����ς�B
(�w�����@��L�x)
�@�s��s�{�h�ɑ���u�V�ۖ@��v�̒e���́A����ŏI���̂ł��邪�A���̎撲�ׂɂ���āA�n���g�D�̓��e�A�A�����@�Ȃǂ̂��ׂĂ����{�ɒm���Ă��܂����B
�w���҂���������ɘA���Ԃ�f����A��S�ؕ����o���ĉ��@�𐾂������M�����͍Ăђn���g�D����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�e���̐Ղ��Ƃǂ߂铇�̕�n
�@���{�m�s�n�ł��������ߎ�������т����Ȃ��������ƂƁA�����̂悤�ɒT���҂�����ɂ����v�Q�̎��R���������������Ƃ������ē��n�̖@���͒�������Ă����Ƃ������Ƃ��ł��悤�B
�@�s��s�{�h�����Ƃ̉��쎡�ǎ��́A�w�[�����@��j�x�ɂ����āA�u�V�ۖ@��v�̔��[�́A���{�̒T���ɂ���Ĕ��o�������̂ł͂Ȃ��A�s��s�{�h�̌����ƁA���߂ɂ��ꂽ�@���͖̎Ƃ�����āA���˓���Ɛď����ɉ��đi�������Ƃɂ���Ƃ���Ă���B
�܂��A���������{�ɋւ���ꂽ�@���ł͂��邪�A���Ƃ��L���V�^���̂悤�ɁA���S�ɒn���ɐ���ŐM���Ă����@���Ƃ͈قȂ�A�u�V���|�Łv�Ƃ����g�����Ɋ�Â��Č��R�Ɩ��{�ɏ㏑�����������Ƃ��A���яd�Ȃ�e�����������ł���Ƃ�������Ă���B
�@�Ȃ��A�������o�������̓��A�����̓��@�@���J���́u���Z�ɕt�����сv�ƕt�L����Ă���B
���J���͎�h�̎��ŁA�����ɂ͑������鐔�ł��邪�A����͎�h���s��s�{�h�̋����y�n�����@�����邽�߂ɐ݂��������������̂ł��낤�B
���������̎����ɂ��ׂĖ��Z�ł������Ƃ��������́A�������̂ł��낤���B
�@�u�V�ۖ@��v�őg�D�̉�ł����s��s�{�h�́A�ϋɓI�ȉ^�����N�������Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�@���p�����͔̂�b�R�V�w���ł������ƌ��@���b������l�ł���A���̉^���͓��b�̒�q�A�閭�@�����ƁA�O�������ǂ��������̖�����N�̓�����҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@�������A������̍ċ����A�e�n�̓��M�������o�������@�͂ɑ��Ă͓��@�@����E��v��h�ǒ��̔�������A�܂��A�M�̎��R�͐��{���F�߂��@�h�ɂ̂��������̂ł���Ƃ��ċp�����ꂽ�̂ł������B
�@���Ò���ł͖����V�N�ɁA�����̒�q�`�����A�쒆���ēc���E�q��A�����ˑ����E�q��@���������Ƃ���A���@�^�����n�܂�A�����W�N�ɂ͐��ˑ��@��Z�E��Ƃ��āA���������q�E�ؗ^���q��E���R���Y���q�E���R�l�Y���q�E���R�P���q�E����v�E�q��E�V���q��炪�@�_���s���A���̌��ʕ��@���邱�ƂɂȂ����B
�@�����X�N�l���\���A�@��ċ��^���͌������A���@�@�s��s�{�h�Ƃ��Ĕh���ċ���������A�����̉�����݂����ƁA���R����Ò��̗��؎R���o����{�R�Ƃ��āA���N�l����\����ɓ���������A���\�l�N�\������ɂ͋ʑ�������ݗ�����A�Ȍ㌻�݂ɑ����Ă���B
���i������������j�s��s�{�h�ɑ���e���@�@����641�`
�@�@�������@��i����������j
�@�@���V�ۖ@��i����������j
�@��������אڂ̓���ƂƂ��ɑS�˕s��s�{�h�ł���B
���������ďW�����Ɏ��@�炵�������͂Ȃ��A����Ƌ��L�̋���ƌĂԌ����𗘗p���āA���ׂĂ̕����I�s�����s���Ă���B
���̋���ɂ��Ă̐ݒu�ϑJ�ɂ��Ă͌�ɏq�ׂ邪�A�S���т����E���o���̒h�ƂɂȂ��Ă���B
��n������n���ɋ����ň�J���ɂȂ��Ă��邪�A�����X�N�ɕs��s�{�h�������ƂȂ�܂ł́A�����R�ɓ�J���A����m��Ɉ�J���������Ƃ����B
�@�����ɁA�@�|����������Ă��玚���R�̓�J���𓌑�̎������O�Ɉڂ����Ƃ����͕̂\�����̂��ƂŁA��h�̓��@�@���Ă��Ȃ�������͕s��s�{�h�ł��������߁A�����ɓ������Ă͓��@�@�̑m���𗊂�Ŗ���������̂́A��ɂȂ��Ă����[���@��o���Ĕ邩�ɓ����n�ɉ������A�s��s�{�̉B��m���ɂ���ĕʂɉ�������Ƃ����B
�@��̌����Ă����n�͉���̂��̂ł���A�̂Ȃ����䖭���O�̕悱���c��ݑ�̂ق�Ƃ��̕�ł���Ƃ��Ă������炱���A�����ɂȂ��Č������ꂽ�Ƃ��ɂ͉��̒�R���Ȃ��������ɕ�n�̈ړ]���Ȃ��ꂽ�̂ł��낤�B
�@����ɕs��s�{�h�ɑ��ē��얋�{�������ɂ��т����e���������������w�N���s���x�͏ڂ����L���Ă���B
���̂��Ƃɂ��Ă͐����ɑウ�ē��L�������̂܂܌f���邱�Ƃɂ���B
�����쑺�����ɂ�銰���@��̈��
��A�����Z�N�\��(1794)���
�@����`�l��p�@�ߑ��s��s�{�V�m���폢�ߌ�@�A�V�䉺���퐬����l�l���O���V�ʂ�
�@�@�@�@���Ö{�h���吴���q�j��~�h
�@�@��ю����q��l��㌴�P�E�q��A���l���{�������A�֓��S��l���哈�F�O�Y�A�䏬�l�ڕ��r�䌹���q�A�䏬�l�ڕ��勴�P�l�Y�A�֓��S�㕍�䕁�����r�䕽�g�Y
�@�E�\������ʍ쑺�B���剮�폢�߁@����B���폢�߃j����Ɠ���
�@�l�������]������M�h�폢�ߌ�
�@�O�������E�ё�������s�c�폢�ߌ�
�@�㌎�A�����钆�ђˑ��]�����
�@�\���\�����ċ�c�A�V�o�Ɠl�]�ˌ䊨���s�ȟ��b���l�֎w�o�X
�@���\�Z�����ĘZ�c����w�o�j���A������l�ʍ쑺�^���q��
��A�\���\����ʍ쑺�䍷�o�V��Ɨ^�E�q��@�����q����S��t�A���E�q��荽�A������Ɛr�܍��q��@�������l���S�A���������������q��@�ɉE�q����S�A�g���s�Y���q�荽�A������ђˑ������q�@�r�E�q��荽�A�����Z���������E�q��@�����q��@��������E�q��@�ʑ����`���q�E�l�l���S��t��
�@������v���q�E�ʍ씼���q�����Z���q�O�l�ҏh��a���t��
��A�\�ꌎ�������o�ƕ���ً�����
�@�o���ʍ�@��h�@�@�ʍ���o��
�@�V�@�g�c�@�M�\�@�@�������o
�@�V�@���q�@���D�@�@�������o
�@�V�@�ʍ�@�����@�@�������o
�@�V�@�]�ˁ@�F�P�@�@������o
�@�V�@����@���~�@�@�{����o
�@�V�@���@�@�{���@�@�ђ˂��o
�@�V�@�z��@�����@�@�������o
�@�V�@�����@�h�{�@�@�������o��
�@�V�@�]�ˁ@���S�@�@�������o��
�@�V�@������M�h�@�@������o
�@�V�@���@�@�b���@�@������o
�@�V�@�]�ˁ@�@���@�@�ё����o
�@�V�@�n�����S���@�@�������o
�E�E�l�l�O�@�\�ꌎ������迠�E�l�S����������@�c�l�l�䑶���j����ً���n������t��
��A�����܃P�����S�l�V���A�ё����动���q�A���������q��A�ʑ��`���q�A�^�E�q��A�r�܍��q��A���䑺�����E�q��A�ʑ������h�^���q��E���l�o�S�V��a���d��
�@�@�@�@(����)
�@
�@�@�@����\��D�V��
��A���������X�S�����n�ʃj���s��s�{�@�h������o�Ƌ��@�ĉ���ᖡ�V�㍶�V�ʂ��t��
��A���S�@�����`�@�s��(�}�})�s�{�䐧�֕��ٓ��ݑ�����h�@����j�����@��@�h��ƗL�V��l��x�菑���o�V�@�荟�x���@�d���V�\����i�@�ӕs�̓j�t������t��
��A�����@�猺�@�{���@�r�ËV�@�s��s�{�@�h�ґc�t���@�V�{�ӂƐS����Ƃ��@�䐧�֔V�V��ٔ�ݖ��X�E�@�h������o�ƂƂ��既������d�|�\����n���@�ӕs�̓j�t������t��
��A�b���`�c�N���s��s�{�@�h������m�V��q�j�����o�Ǝd�@��迠�E�@�h�������M�S�d����@��ᖡ�V�㑼�@�j�҂�������(��)�����@���@�@�V���j�����h�d�|�\����i�@�E�\��n����p�@�䐧�֔V�V�s�ىE�@�h�����@���@�j�ґ����������|�\����n���@�ӕs�̓j�t������t��
��A�ʍ쑺���E�q��n�ʃj����h�@�`�@�s��s�{�n�c�t���@�V�{�ӂƐS����Ƃ��@�䐧�֔V�V�ٓ��݉E�@�h�������@(�p)����j�됬���@��j�����@�F�P�j���������������i�������\���@���X���@��d�|�\����n���@�ӕs�̓j�t�����j��n�R������t�@�a���d��
��A�������n�ʃj���F�P�`�@�s��s�{�䐧�֔V�`��ٔ�݉E�@�h������h�@���퐬���@��E�@�h��ƗL�V�l�d���V�|�\����i�s�̓j�t�@�����j��n�R������t���@�a���d��
��A�ʍ�`���q�n�ʃj��D�@�@�����ɉE�q����j���h�{�@�`�@�s���s�{�@�h�n�c�t���@�V�{�ӗ^(��)�S����Ƃ��@�䐧�֔V�`�ٓ��݉E�@�h������o�Ƃ�������������@����@�d���V�|�\�����@�ӕs�̓j�t������n�n�O�l��������t���@�a���d��
��A�{�r�܍��q����j��~�@�@�ђˑ��`���q��n�ʃj����@�@�ё��@�ю��@���S���@�@�������E�q���Ƃ��גn�ʃj���@���@�@���쑺�v���q���j���M�h�`�@�s��s�{�c�t���@�V�{�ӂƐS����Ƃ��@�䐧�֔V�V�ٓ��݉E�@�h�����@��j���@�d���V�|�\����i�s�̓j�t�@�����j��n�R�ܐl��������t���@�a���d��
�E��n���ꓯ���m��،�@�˔V�䐿�ؕ�����\��@�@��
�O���S���@���v��d�u�V�V�@�ّm�`����o��،�@�˔V������`����\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]�˒J��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�ю��@��
�@�@�@�����Z�Γ�(1794)�\�ꌎ������
�@
�@�@�@�V�ۏ\��N(1840)�܌�������
�@�@�@�@���B�������R���s�Y�l
���Ñ��]��o���j�t���X��ďo�V�V�V�n�@�s��s�{�@�����j�t�����ƕʖ��O�����@��l�ʑ��Õl�c���P���q���]�j������l���Y���j����������]��ďo���V��@���������X�@��V��n������迠�����i�@���j�T�u����
�@
�ደ�����j�t���t�ȕ�\���
�x���d�Y�m�s������������S�����쑺�S���V�E�q�受�[���ȁ@�������q�@�����q�@�^���q��@�ɕ��q�@����^�y���q�@�R�p��V���m�s�������S�������q�受�[����@������@���[�₷�@�ΒJ�F�V���m�s���S����E�q��@�����q��@���吭�E�q��@�����\�Y���q�m�s�����吴���q�@�g���K���q��@�_���R���m�s���S����t�~�p�@����I�Ɏ�g�^�͋��m�S���P���q�@����O�؉E�q��ꓯ��\���
�����`�䐧�֔V�s��s�{�V�`�@������ƔV�|����V��@���i�V�q�受�[���ȁ@�����q�受�[����@���E�q��@�����q�@�ɕ��q�@�~�p�@���q��@���������`�@��X���@�@�j�����ґ����������U�߃j���ᖳ�����@�R���������S�����O�Y���q��g�������m�n��ҁ@�N���s�o�@���l�\����ҁ@�ۏB�����Ñ��b�G�@�����Ɛ\�@�Ԍo�V�s�җL�V�@����l�o�͌����j�a�����X������(�}�})�������Ǝ��j��L��E���j�t�@��c���@��V�@�j���Ƃ��ā@�@��l�v�|���i�����ڗL�V����r�j���S���@�����єN��迠�ґK��E�l���@�O�E�d�R�E�O�Y���q��]��������(�K)�Ƃ��đ��锤�j��l��������ˎd���ҁ@�`�@�����n�]�l�]���i����`�n�����������
�@���ʌ�ᖡ��҉\���l�����������@�䗘�Q�V����d�@�Ȍ�}�x���~�������g�\�ԕ~��@�����䎜�ߔV�䍹���@�j�����
��A�O�؉E�q��@�����q�@�����q�@�K���q��@�P���q�@��E�q��@�^�y���q�@���E�q��`�@�O���@�����U�߃j������@�R�������V��迠�@��j�g��V������@�e����������˂�������`�j������L�Ɓ@�����j�����ăn�����ѓx�o�������
��A���E�q��@����@���q��@�����q�@���E�q��@���E�q��@�����q�@�ΉE�q��@�P���q��@�m���q�@�y���q�@�����@���E�q��@�Õ��q�@���V��@�s���q��@���ܕ��q�@�y���q��@�����q�@�g(�}�})�@�����q��@���E�q��@�앺�q�@�V�E�q��@�����q��@�����q�@�E���O�V���̑����j��l���������@�E�����j�t����V�V�s�\���@��玆�A�t�ȕ�\���@�ȏ�
�@�@�@�q�܌�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���\�Y�m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S�����쑺
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@�V�E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^���q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɕ��q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�^�y���q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�p��V���m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������S����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�������q�受�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ΒJ�F�V���m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������S����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@��E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@���q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@���E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����d�Y���q�m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�����q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���@�K���q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_���R���m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S����t�@�~�p
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����I�Ɏ�^�͋��m
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�O�؉E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@�P���q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@���E�q��
�@�@�@�@�֓������o��
�@�@�@�@�@�@���R����Y�l
�@
��A���V�ۏ\��(1840)�Z�����O�����c��
�@�䎛�Е�s�@�����ɉ��lゟ�����E�l�V���̍]��ďo���������Ղ������@�����y�㎧�x���\�Y�S�������q�@�ΒJ�F�V���S�����q��@�E����O���Y���吭�E�q��@�^�͋��O�؉E�q��@�����������o���j�������������������@����������s���l�]������������@���㎛�@�j�������y�㓯������������j���\���܃c�����ꓯ���X���@迠��o��V�@��B�����Ñ��]��o��V���䒲�V�ʂ����@�E��������A����t�@���X�ꓯ�����\����\�l��迠�s�c�A����
�@
�@�@�@�@���Ì�o���]����lゟ���o�����D�V�����T
�@�@�ደ�ȏ��t��\���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���\�Y�m�s�������쑺
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@�^���q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ΒJ�F�V���m�s������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@���q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�͋��m�S���@���E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�p��V���m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���@�����q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�₷
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_���R���m�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S����t�@�~�p
����V�s��s�{�@��j�A�˒v���@�������Ƃ��ď��X���������S�����O�Y�E�q��]���͌�i�@���ʌ����j�t�n�����m�d�������
�����ꓯ�@������s�s�͒i��@�����ҁ@�ꌾ�\���l�������@����@�P�������X���w�d�Ȍ�g�s�\�l�d��ԁ@�����i�ʔV�䎜�ߌ䊨�ٔV���l�j�����
�E�����j�t����V�V�s�\���
�@�@�@�@�@�q�܌�
�@�@�@�@�֓���o�������o��
�@�@�@�@�@�@�@���R����Y�l
�@
�@�ȏオ�A�s��s�{�h�̑m���ƐM�k�ɉ�����ꂽ�e���̎������A�����ɏZ�ޑ��тƎ��g���L�����L�^�̈ꕔ�ł���B
���̒e������ǂ̂悤�ɂ��ē���悤���ƍ���Â炵����S�̗l�q�������Ɍ����A�p�c�ȓ��L�����ɁA�ǂގ҂̐S�ɑi������̂�����B
�@�O�i�̊����Z�N����n�܂��A�̒e�����A�@��j�͑��Ö@��ƋK�肵�Ă���B
�����J�n�ɓ������đ��X�̖���ɐM�Җ��������o�����A�������|����ɂ��Ēe�����i�߂�ꂽ�Ƃ����Ă���B
��i�̓V�ۏ\��N����̒e���͑S���I�K�͂ōs���A���̂Ƃ������{�́A�������������鎑���ɂ���Ə̂��ĐM�ҁE�m�����������č��o�������B
�����M���č��o�������߂ɂ��̖���������Ƃ��ēO��I�ɒe���������i�߂�ꂽ�B
���̖������N�u���Ȓ��v�ƌĂ�Ŋ��ݎ�����Ƃ����B
��-----�����s��s�{�h�B����-----
��������Ց���������---------------------
�@�@�@�@�@��������Α��������ݐ}
����������h��/������
�@�@�@����������h�сi�@���R�������j
���������菼�t�������
�@�����莚���t�ɓ�����ׂ�����B�����͏���h�сi�������j�����ł���B
�u�����j�v�@���F
�@���Â���R�q�Ɍ��������ƁA���F����̒����������A�������Q�������ɂ��Ȃ��Ă��āA���̂��悻���S�n�Ƃ�����Ƃ���(�����t1910�Ԓn�t��)�ɁA��֑�����̓��H���W�����Ă��Ă��邪�A����ƕ��Ԃ悤�ɐΑ��̓�����ׂ�����B���̂悤�ɍ��ށB
�u���@�L�a�Ï鈮�������A�ʑ��H�R�N�g�@�Έ�K���Y�@�H�R���s�@��������@�H�R�t���Y�@����
�@�k�@�R�q���s�����쓹�A���H�R���d�@�����F�g�@���R�����Y�@�╔�ȕf�����A
�@���@�I���v�ꍲ���ݒn�A���ѐV��@�Έ�ΌܘY�@�э����@�������S�@�ѐr��@�����t�g�A
�@��@�������Ð��c�@�@�A��ʑ��Έ�R���Y�@���c�F���Y�@�x�V�����@�{�{�ѓc�v�@���c���R�g���@���R�����@���ό��L�O�@�吳�\�l�G�O���v
2023/10/19�B�e�F
�@���蓹����ׂP�@�@�@�@�@���蓹����ׂP
���������菟�h�R�\�����@�@�u���Ò��j�@�㊪�v898�`
�@���˂̓�1957�Ԓn�ɂ���A���̒��猵���ЂƂ͋������c���͂���ő�����B
�R���E���N
�@�w���@���ג��x�i���������j�ł�
�@�@�@�@��t���lj�����������S�����葺���˃m��
�@�@�@�@�@��t�������[�������S�������a������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�\����
��A�{���@�߉ޖ���
��A�R���@�����J�R���^���l�R�g�n���[�������S�������������؍��ߑ��v�ɌZ�A�������S�����a�����Z�E�������l�m�k��j�V�e���^�g�]�t�A�V���ܕ��\�N(1536)�l�����n���j���e���̖������g�]�t�L���V�j�t�A�V���ܕ��\�N���������ӎ��n���X�g�A���ØV�m���胒�L�ڃX���m�~�@�ȏ�
��A���F�Ԑ��@�{���c���Ԕ����܊Ԕ��A�ɗ��c��ԉ��܊ԁ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@��O�S�ܒ؎���\����
��A���������@���V�@�������O��c��ԉ���ԁ@�@�@�@�@��A���������@���V
��A���O���L�n�@�k�n�i�ʈ뒬�됤�l���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�ђi�ʎO���O��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�ȉ�����)
�@�ȏ�ł��邪�A����ɗR���ɂ��Ắw�ߋ����x�̈ꕔ�ɁA���̂悤�ɂ���B
�@�u�V���O�N(�����)�\�ꌎ���R�J��h�@���^���l�A�[�B���Γ��^���g���������ꎛ��@�^�g�n�[�B���ؑ�V���v��A���؍��ߑ��v�m�ɌZ��A��m�s����������a�̕����Γ��^���������L�e�R���J�L�V������A���R�ꎛ�m�ؕ����{�R�����t��{���j�L�V�A�����l���f�t�m��ؕ��ʃj�L�V�A���j�i���m�ؕ��L�V�j����(�����ꎛ�n�\��S��@���s���l�����N�\�ꐢ�v�P�@���~���l���\���������T��)�v
�@��L�̓��ł́A���̊J�n�ɂ��āu�V���ܔN�v�Ɓu�V���O�N�v�̗��N���L����Ă��邪�A�ØV�̌����`���Ɖߋ����L�ڂɖ�l�\�N�̍�������B
�@���w�ɂ͖{�����߉ޔ@���A����@���o�`�A�l��F�A�l�V���A�O���ɑc�t�����u����A�E���ɑc�t�����E�ŏ��ׁA�����ɐ~�q���q��S�q��_�E�e�m�\�����E�O�\�Ԑ_�E�n���ϐ����E�V�_���[�߂���B
�O��i���O��j�F
�@���w���͘Z�{�̉~���Ŏx�����A��ɓ�d��ؑ��́A�r�����͂邩�ɑ傫�ȏ��킪�悹����B
�V�ۋ�N(1838)�㌎��\�Z�������̎���Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�����͑����̋y�약���q�ł���Ɠ`�����A���Ƃ̕�ɁA���̂悤�ɍ��܂�Ă���B
�u���R���O��ҁ@�t����@�������l�V�Č����@�����ҕ��~��@������h��@�ˏC�����Éi�l�N�O�����q�E���[�V�v
�@���̘O��͏�w���ɞ�����݂艺���邱�Ƃɂ���ċύt��ۂƂ����A�����m�푈���ɞ��������[���ꂽ��ɂ́A���悻���d�ʂ̐��݂���Ă���B
���̏����͎��̂Ƃ���ł������Ƃ����B
�@�@�@���ŏ���폟�h�R�\�����ɏ�Z�^��T������،o�V�y�v��畔���A��
�@�@�@���ʒ�����햭�o�\�����ُ��@�^�E�������C�u�Ҏ����퓿�@�������s
�@�@�@�ߕꐴ���@��������[�ӓ��Җ�^�ȏ��^�@�@�������ѓ���؉E���
�@�@�@��c���@�E�L���������ꎧ�߁^������i��O�������W�Z���g�˓�
�@�@�@�@�@�@�{�剺��������S���c���Z�l�@���R���Y�E�q�喽�d�@�@���v���@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�������S�k���V�����葺���h�R�\�����@�\�l�������@�����h���@�]�ː_�c�Z����O����
�������̐Α����E�Δ�
�@�����ɂ͊���̐Α�������B
�R��킫�̑�ړ��F
�@�u�V���O�N��(1575)�\�ꌎ����v�u�V�a�l(1684)�v�u���ی�(1720)�v�̔N�������܂��B
�����Βi�̉���ړ��F
�@�u�얳���@�@�،o�����O�������A�@�����܉���(1715)�\�����@���h�R�\�����\�l�����[�\�ܐ����^�@�������葺��ڍu���@�{���@�~�����[�O�O�@����e���ʐ擏��X���썰�s���@�@�S����@�{�Ɖ@�������s���P�@�����@�����l�p�q(1792)�����d�g�����R��\�O����������쎏�L�@����쓇�W�ߐ{�P���q�v�ƍ����B
2023/10/19�B�e�F
���[��Α����^���Ɠ��R�ꎛ�ŁA��Α��ɓ��^�����J�������h�@���^����N�B�����Ƃ��āA����̒n�Ɍ��Ă��Ɠ`����B����W�N�i1680�j�ɓ��^������Ɨ����A�\�����ƂȂ�Ƃ����B
�@�ΊK����ڔ��F���ʂ́u�얳���@�@�،o�����O�������A�v���̑��͏�Ɍf�ځB
�@�\�����ΊK
�@�����ՕW���F��Ղ͔\�����𒆐S�Ƃ��āA����n�S�̂ɍL����B�A���A���͂ɂ͑傫�ȓy�ۂ�ȗցA�Ռ��Ǝv�����\���_�݂�����A���݂͔\������l�Ƃ������\���͕s���ł���B
�@�R��O�Q���F�P��͑�ڐŁA���ʁu�얳���@�@�،o�@����i�ԉ��j/�c�R��\�Z�k�@�v�ƍ��ނ��A�����P��͑S�����ǂł����s���B
�\�����R��F���O��ł���B�l����L�^����]�˖����̌����Ɛ��肳���B�܂����̖�̐v�}�u�G�v����������Ƃ����B
�@�\�����R��P�@�@�@�@�@�\�����R��Q�@�@�@�@�@�\�����R��R�@�@�@�@�@�\�����R��S�@�@�@�@�@�\�����R��T
�@�\���������@�@�@�@�@�@�\�����{���@�@�@�@�@�@�\�����ɗ��@�@�@�@�@�@�\������ז��_
�@���@500�������F���@500�����̐����͓V�����N�i1781�j�ł��邩�炻�̍��̌����ł��낤�B
�@�单�V�Γ��@�@�@�@�@�@����l�V��
�Ȃ��A�u���Ò��j�v�ʼn]�����R��킫�̑�ړ��F�u�V���O�N��(1575)�\�ꌎ����v�u�V�a�l(1684)�v�u���ی�(1720)�v�̔N�������܂��B���Ƃ͕s���ł���B
���H�T�̏��K�E�{�Ȃ�
�@�@�������ЁA�z�K���_�A�ω����A�n���ω��A���W�A�M�\���ȂǑ����̂��̂����邪�A���̂Q�_�����グ��B
�@�����苍���V���K�@�������̋����V����
�@�����薭���Ё@�@�@�@���������Ò��̖�������
������_��
���Â���̎Ђł���B
��������ߐ��͖k�����E�������Ȃǂ̑��h���A����ƍN����͂R�O�̎��̊�i����B
�����́u�Ⓦ��ז{�{�v�Ə̂�����A�����Q�N����_�ЂƉ������A�����U�N���ЂƂȂ�B
�@���ڍׂ͏ȗ���
�������_��
���̎Ђ͌����Ёi�͂��߂͔\���������ɂ���A���c�͔\�����ł������j�A�����q�Ёi�쓇�����q�Ё������̋����V�������j�A�V���Ёi�����Ђɂ������j�̎O�Ђ����J���ꂽ���̂ŁA������L�O���Č��Ă�ꂽ��̒����ɂ́u�吳�Z�N�܌����J�I�O�v�Ƃ���B
��������Ց�����ʑ�---------------------
�@�@�@�@�@�@����ʑ��Α��������ݐ}
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�{�}��Ɂu�������͂��̕t�߁H�v�ƕ��������邪�A���͋����V�c�ɂ������v���A�Q����������ł���B�j
�@�@�@�@�@�@���@�@�@��ʑ��d�ː}
�@�@�@�@�@�@��-----�����s��s�{�h�B����-----
����ʑ�
�����Ò��j/�n��j��/����֑�/��ʑ��@���
�����̋N���@�㊪1002
�@��ʑ����߂���R��ɂ́A���\�̌Õ������@�̂܂c��B
�Ȃ��A���݂܂œ�ʑ����ł́A�n���ɊW����Ǝv����i�ʑ��́j�H�[�ՂƖڂ������͔̂��@����Ă��Ȃ��B
�@���݁A�I�R��㗬�ɖʂ����u�˒n�тɂ́A�ʑ���n�𒆐S�Ƃ��ĂW�̌Õ��Q��������B���̒��Œ��ڂ��ׂ���\������Õ��Q�E�隬�͎��̗l�ł���B
�E��ʑ������Õ��@����(�o��)
�@�����@�̂��̘Z�J���B�Õ����ӂ��s��s�{�h�@��m�̕悪��������B
�@�@�@�����n�������̈ڍׂ͕s���B����(�o��)�ɂ͖@��҂̕悪���邪�A����Ƃ͕ʂ��B
�E��ʑ����ʁE�������A�Ï��ʌÕ�
�@���݂̏�֗c�t���~�n���炻�̓쐼��n�ɂ����Ă̖�����ɌÑ�Z���Ղ�����A�y��̏o�y�ƊL�k�w��������B
�@�㐢�u�B����@�̗��v�Ƃ����A�@��҂̕悪�����B
�@�@�@�����n�������̈ڍׂ͕s���B�������n����B
2023/10/19�B�e�F
�@�ʑ����ʂ��������n������B
��L�́u�@��҂̕悪�����v�Ƃ̏��Ɋ�Â��A������̕�n��T������B
�m�͂Ȃ����A������̕�n�Ŏ��̎ʐ^�̈�s���@��҂̕����W�߂����ł��낤�Ǝv����B
�@�@���ʖ@��ҕ擃�P�@�@�@�@�@�@���ʖ@��ҕ擃�Q
�����̕�肪���Ԃ��A���ǂł��Ȃ����̂������A��X���ǂł������̂����̂U��ł���B
�@�y�����@���ÁA���O�i����{�y�����S�@���O�̉\�������邪�A�s���j�A���\�@�����A
�@����@�����i�g���S�U�������㕜��j�A��É@�����E�g�P�@�����E���P�@�����i�R��l�A�L�j�A�b���@���s�z
���̒��ɂ́u��É@�����v�y�шӊO�Ȃ������́u�g���S�U������@�������v������B
2023/11/29�B�e�F
�@�ēx�A�������n��K�₷��B
�@���ʖ@��ҕ擃�R�@�@�@�@�@�@�@���ʖ@��ҕ擃�R�E��������
�����ɂ́A�P�V��̖@��҂̕擃���W�߂��Ă���B�i�g�r�s���̐Β���������ƂP�W��j
�@���f�ڎʐ^���ŁA�����2023/10/19�B�e�A�����2023/11/29�B�e�������B
�@���i�P�j�Ȃǂ̕\���͏�Ɍf�ڂ́u���ʖ@��ҕ擃�R�E��������v�\�������i�����j�ɑΉ�����B
����͍����ȑm���ł́u���@�E���N�E���푼���{���v�A�s��s�{�h��t�ł́u�����E���i���l���{���v��V���Ɋm�F�B
�i�P�j���i�g�r�s���j
�i�Q�j�����@���Õ擃
�@�����@���Ð��l�F���Âɂ��Ă͏��Ȃ�
�i�R�j���[�@�����i����j�擃
�@�����[�@�����萳���F���@�@���[�@�����E�E�E�E�E
�@�����[�@�����葤���F�V�ێ��\�N�����@��
�@�@�@�@�t���ʂ͔������A�s���A�w�ʂ͖��m�F�B
�i�S�j���O���D��
�@���O�����D���F�얳���@�@�،o�@���O�����@�ƍ��ށB
�@�@�A���A���̏������Ȃ��̂ŁA���S�@���O�i�c���Q�N�i1649�j�W���V����B����{�y��17���j���ǂ����͕�����Ȃ����A
�@�@���S�@�̉\���͍����Ǝv����B
�@�����O�����D���Q�F�얳���@�@�،o�@���O�����@�ƍ��ށB�E�E�E�E�E��́����͍����Ɣ���
�@�@�@�@�w�ʂȂǂ͖��m�F�B
�i�T�j�T�ԕ擃
�@���T�ԕ擃�E�����F�u�얳���@�@�،o�v�ƍ��ނƎv������A���͔��ʂł����B
�@�@�@���ʂɁu���������E�E�E�v�̔N�I������A�t���ʁE�w�ʂ͖��m�F�B
�i�U�j���\�@�����擃
�@���\�@��������F���u���@�@���\�@�����S�ʁ@�����Z�b�ГV�@�\�ꌎ�\�ꁡ�v
�@�@�����U�N����Ƃ���A���̔N�͑��Â̊����@��ő����̋]���҂��o�����N�ł���A
�@�@�����͕s�ڂł͂��邪�A���Ö@��̖@��҂̉\�������ɍ����Ǝv����B
�i�V�j�V�ԕ擃
�@�@���ʂ͑S���������ǂł��Ȃ��A���̑��̖ʂ͖��m�F�B
�i�W�j����@�����擃�F�g���S�U�������㕜��
�@����@�������l�F
�@�g���S�U�������̓����̕��i���{���j������Ƃ͈ӊO�ł���A�����ł���B
�@�@�������͈��i�U�N�T���Q�W����A�g���S�U���i�����㕜��j���J�������S���i�u�[�����@��j�v�j
�@�@�������ɂ��Ắu�g���S�U������@����������v���Q�ƁB
�@�Ȃ��A�����ɂ́��u�����v�y�сu�������J�v�����̊T�v���L���̂ŎQ�Ƃ���B
�@2024/03/21�lj��F
�@�@�������ˑl����n�ɖ���@�����i����@���s�j�̖��������擃�i�j������B
�@�@������ӊO�ł���B
�i�X�j��É@�����E�g�P�@�����E���P�@�������{��
 |
�����E�����E�����O�t�̋��{���Ɛ������邪�A���̌����̌o�܂͕s���B
�@��É@�����E�g�P�@�����E���P�@�������{��
�@�F���}�g��}
���ʖ����͎��̂悤�ɍ��ށB
�@�@�@���i����b�\�������l��
�@�@��É@�������l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e���t�@�@�@�@�@�@����Z��߁i1678�j
�@�얳���@�@�،o�@�@�@�@�@���P�@�����哿
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������l��
�@�@�@�@�g�P�@�������l
�@�@�@�@�@�����\��h��l������
�������͊��i�Q�P�N/1644�@�W���Q�S������
�������͊����P�P�N/1671�@�S���S������A�ʑ��h�тS���A���������P�W���A�u�[�����@��j�v
�������ɂ��Ă͏��Ȃ��A�����̌����u�e���t�v�Ƃ͕s���B |
�i�P�O�j�P�O�ԕ擃
�@���P�O�ԕ擃�E�����F�u�얳���@�@�،o�@�����i�ԉ��j�v�Ƃ���A�����ʂ͔��ǂł����B���̂Q�ʂ͖��m�F�B
�i�P�P�j�P�P�ԕ擃
�@���ʂ͑S���������ǂł��Ȃ��A���̑��̖ʂ͖��m�F�B
�i�P�Q�j���@�E���N�E���푼���{���@
�@�����@�E���N�E���푼���{���E�O���F�얳���@�@�،o�@�얳���@���F�v�Ɛh�����Ĕ��ǂł���B
�@�����@�E���N�E���푼���{���E�������F�얳���N��F�@�얳�������l/�얳���퐹�l�@�얳�������l
�@�����@�E���N�E���푼���{���E�E�����F�ǂݎ�����A���E�ɓ얳�E�E�E�E�̌`���Ŏl�t�i�S���l�j�̖���������Ǝv������A���ǂł����B
�i�P�R�j�P�R�ԕ擃
�@���P�R�ԕ擃�E�\�ʁ@219+�F���@�@�@�����̑��A���̍��E�ɂ����炭����N�������L���Ǝv������A���m�ɔ��ǂł����B
�i�P�S�j�P�S�ԕ擃
�@���P�S�ԕ擃�E�����F�@220�u�����@�����@�����v�ł��낤���A�قړǂ߂Ȃ��A���̑��̖ʂ͖��m�F�B
�i�P�T�j�P�T�ԕ擃
�@���P�T�ԕ擃�E�����F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@
�@�@�@�얳���@�@�،o�@������ʁ@�Ǝv���邪�A�w�Ǔǂ߂Ȃ��B
�i�P�U�j�P�U�ԕ擃�F�j��
�@���P�U�ԕ擃�E�����F�f�ГI�Ɂu�i�얳���@�j�@�v�A�u���`�i�H�j�v�A�u�����v�Ȃǂ��ǂ߂邪�A�S�e�͕s���B
�i�P�V�j�����E���i���l���{��
�@�������E���i���l���{��
 |
�@�������E���i���l���{���E�S�ʂP
�@�������E���i���l���{���E�S�ʂQ�F��������
�@�������E���i���l���{���E�S�ʂR�F���}�g��}
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�얳�������l
�@�@�@�얳���@�@�،o�@�@�@�O���\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�얳���i���l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l����\��
�@�������l�̍��E�Ɂu���i�����v�u�O���\���v�̎����������A���̓����͔h�c�Ő��@�����ƒm���B
�@�܂����i���l�̍��ɔN���͌�������Ȃ����A�u�l����\�v�̓��t������A����͏C�T�@���i�̎��������3�N�S���Q�Q���̌����ƈ�v����̂ŁA�M�B��c���߂̔蕶�J�P�R�����i�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B
�@���݂Ɂu�[�����@��j�v�ɂ��A���i�̓����̏�l�͑��ɂQ������A��l�͎����@���i�i���W���P����A�ʑ����j�A������l�͎��P�@���i�i�����R�N�R���Q�P����A����h�ђf�H���j���������Ă���B |
�i�P�W�j�b���@���s�擃
�@�b���@���s����F�����u���ʁF�얳���@�@�،o�@���ʁF���@�@�b���@���s�哿�v
���s�ɂ��Ă͏��Ȃ��A�s���B
�ʑ����ʕ�n�̂��ˁH
�@��n���ɂ��˗l�ȍ��܂肪����A�������J����Ă���`�Ղ�����A�����u�@��ҁv�̕�Ȃǂ����߂��Ă����Ƃ������ƂɊW����̂����m��Ȃ��B
�@���ʑ����ʂ��ˁH�@�@�@�@�@���ʑ����ʂ��˒����F�����ɂ͐Γ��ނ̎c���Ǝv���镔�ނ��u����Ă���B
���u�����v�y�сu�������J�v�����̊T�v
�@�@���͉����э���т̋߂��A�c�����э��h�тɂĊw�сA���a���N�i1764�j�э��h�т̂P�Q�W��̕���\���ƂȂ�B
���i�R�N�i1774�j�g���S�U���ɐW�R�A���i�T�N���J�h�сi�����j�Ɛg���R�����͓����������N�����B
�����͓�����s��s�{�m�Ƃ��Ď��Е�s�ɒ�i�A�t�ɐ��J�h�ё����������i�A����ɂ������y�ѐ��J�h�т͍]�˂ɏ�������A�ᖡ���s����B
���ʁA�����͋ᖡ���ɘS�����邪�A�����͖{�ӂɔ����s��s�{�ח��Ƃ��Ēf�߂���A�g���R����͏���Ƃ����B
����̓����͈�R�����E�k�}�̍߂ɂ��O��։����A���̑��̊W�҂����ꂼ��ɏ�������Ď����͗�������B
�o�܂ɂ��ẮA����Ȃ��������������A�܂��������s��s�{�m�ł������Ƃ͎v���Ȃ����A���{�̏��f���s��s�{�ח��Ƃ������R�ł��������ƁA����ɕt�߂̉����э��i�߂��j�o�g�ł��������Ƃ���A�s��s�{��t�Ƃ��ĕ��i�������͋��{���j�����̒n���Ɍ��Ă�ꂽ���̂Ǝv����B
2023/12/27�lj��F
���u�[�����@��j�v�@�ł͎��̂悤�ɉ]���B
�@����̕�n�ɐg���R��㖭��@�����̕�肪����B
�@�@������̕�n�ɏ��݂Ƃ��邪�A���݂͏�̎ʐ^�̂悤�ɋʑ����ʂ̕�n�ɂ���B����ɕʂ̓����̕�肪���邩�A���ʂƓ���Ƃ����Ⴆ�����̂ǂ��炩�ł��낤�B
�@���i�T�N�g���R���ʓ����S�Ă����̍Č��������āA���J�h�ѓ����Ɠ����Ƃ̑Ό��ƂȂ�A�����͘S���A�����͎O����߂ƂȂ�B�����͓�����s��s�{�h�Ƃ���B
�����͒J���P��������g���S�U���ɐW�R�������A�P�����͓��M���̈ꎛ�ł������B�����Ɏc����Ă���Éߋ����ɂ́u���J�P�����������l�j���]�X�A���ώt�ƌZ���q�i���i�����@�����̏��A�����͔��O�̖@���A����V���q�Əo�g�j�v�ƋL�ڂ���A���M���������ƑP�����͊W���������B
�@�����̌Éߋ����̍s�͈Ӗ���������Ȃ��B
���̐��J�����͐��s���Ă������M���A���ʎR�S�ĂƂ��������ŘI�悵�Ă��܂��������ł���B
�E��ʑ��O�쌴�A����Õ�
�@��ʑ��Ɩk���̋����ŁA��n��т��Õ��Q�ł���B�ڂ����͖{������ψ���ɂ��w����E���L�Õ��Q���@�����x(���a�T�R�N)�ɂ��邪�A�~�����R�V��A�O����~�����W��m�F����Ă���B�O�쌴��n�ɂ́A�����ȍ~���@��m���̕悪���߉B�����Ă����B
�@�@�@�����n�������̈ڍׂ͕s���B�O�쌴��n����B
�E��ʑ����F��Õ�
�@�Õ��Q���̑O����~���͌��`�����̂܂c������Õ��ŁA�S���X�R���A�~�����̒��a�͂S�S���A�S���I��̂��̂ł��낤�Ƃ����Ă���(�����@)
�@�@�@�����n�������̈ڍׂ͕s���B
�E�ʑ��隬(���A�u��n)
�@�V���P�U(1588)�N�܂ł̋ʑ��隬�Ƃ����A���x�E�O�x�̐Ղ��c��B���약��`�̕悪����A�s��s�{�M�k�̉B������������B
�@�@�@�����Ɍf�ڂ̓��鎛�Ձi�ʑ���Ձj�ł����u�����鎛���@�́A���̉B�����ł������v�Ƃ����L�q����������B
�@�@�@�����Ɍf�ڂ̗��؎��̍��F���鎛�B����ɂ͕����@�����M��䶗����鑠����Ă��������A���؎��{���͂��̙�䶗��ł���B
���ʑ��h��/�@�؎�
�@�@���ʑ��h��/�@�؎�
��������Ց�����ʑ��i�ʕ�R�j���؎�
�@�@/�ʑ���/�{�������@�����M��䶗�
���u���Ò��j�v/�n��j��/�����(�Ƃ���)��/��ʑ�(�݂Ȃ݂��܂���)/�@���^�_�ЁE���@�@�㊪1042�`���
�@���J(����)1447�Ԓn�ɂ���B
�{���́A�����@�����M�̙�䶗��ŁA���鎛�B����ɔ鑠����Ă����s��h�т̏����ƂƂ��Ɉڂ��ꂽ���̂ł���B
�@�@�����鎛�B����͉��Ɍf�ڂ́u�����鎛��(�ʑ��隬)�v�y�я�Ɍf�ڂ́u�����̋N�����ʑ��隬�v�̍����Q�ƁB
�@�s��s�{�h�̋֗߂������ꂽ�����X�N�l������A����܂Ő���ł����@���M�k�炪�N��������A�����h�т̕��̖V�����肤���Ė����P�Q�N�ɏH�R�ܘY�E�q��Ƃ̓y�n�Ɍ��Ă����̂ŁA���O������̗��؋���o����{�R�Ƃ����ʑ���������̑O�g�ł���B
�����ď��a�Q�V�N�Ɉ�R�Ƃ��ēƗ����A�ʕ�R���؎��Ə̂����B
�����͓��M�Q�O���˂ł��������A���݂͂W�O�˂𐔂��Ă���B
2023/10/19�B�e�G
�@�ʑ����؎������@�@�@�@�@�ʑ����؎��{���@�@�@�@�@�����@���s�E�O�Z���l��
�@�O�Z���l���G�O�Z���l��͎ʐ^�̂��̂Ɛ������邪�A�m�F��ӂ�A�ʂɑ��݂��邩���m��Ȃ��B
�@�����@���s���G���s�͕s�ڂł��邪�A���ɏq�ׂ�悤�ɁA�ʑ������Ƃ������ƂƎv����B�����Q�P�N�����B
�@�@�����������o���Ɂu�����@���s�擃�v������B
�@�@�@�@�@���W�j�����@���s�擃
�@�@�@�@�@�@�����@���s�擃�@�@�@�@�@�����@���s�擃�Q
�@�@�@�@�@�@�\�ʁF�얳���@�@�،o�@�����@���s���l
�@�@�@�@�@�@�������@���s�擃�R
�@�@�@�@�@�@�@���ʁF������O�����d��/�S�\�N���\�l�@���u�S�\�N�v�Ƃ͕s���A���邢�͌�ǂ�������Ȃ��B
�����؎����ǂ̕��E�j�ւ͍L���_�݂���B
�������@���s�E�O�Z���l��@�Ȃ�
�����ɂ́A������ʂɂ���Ė����Q�P�N�P�Q���Ɍ��Ă�ꂽ���㋳���@���s�ƘZ���l(�@��)�̔肪����B
�����āA�����������ɏH�R��������A�x�V�`����A�x�V�j��(�ᓰ)�肪���сA�����ɂ͈�w�̍��{���V�g����Ȃǂ����B
�@�Z�����ˁ@�E�E�E�E�E���Ɍf�ځu����ʑ��H�T�̏��K�E�{�Ȃǁv�̓��c�_�̓��H�����쑤�i�����j�ɂ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̓������l�o�˂Ɠ������̂ł���B�j
�@�������l�o�ˁ@�E�E�E�E�E���Ɍf�ځu����ʑ��H�T�̏��K�E�{�Ȃǁv�̓��c�_�̓��H�����쑤�i�����j�ɂ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u��ʑ��Α��������ݐ}�v���́u��l�ˁv�������̒˂Ǝv����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����݂͋ʑ��Ƃ̋��E�ɐڂ��鍁��S�����ɂ���B�j
�@��l��(�����h�эu�c���~��)�@�@�@�������h�ъJ�u�E�J�c�d�_�@���~�ɂ���A�x���s�э��P�U�X�X�ɏ��݁B
�@�|���_(���߂�)�l(�ʑ��h�юn�c������)�@�E�E�E�E�E��ʑ������˕�n���ɂ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʑ��O���n�Ɉڐ݂���Ă���Ǝv����B
�@�O���n�@�E�E�E�E�E���Ɍf�ځu����Ց�����ʑ��O���n�v�ɂ���A�������Ö@��̌ܐl�̖@��҂̕�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����݂ł́u�����ˁv��u�����ˁv���瑽���̕��E���{���Ȃǂ��ڐ݂��ꂦ����Ǝv����B
�@���ʌ�ˁ@�E�E�E�E�E�s�ځA�A����ʑ������Е��߂����ʂł���A���̕t�߂̕�n�ɂ���̂����m��Ȃ��B
�@�@�@�@�Ȃ�
�@���ʑ����؎��FGoogleMap�@���
�@���Ő��@������l�F��̓����M��䶗��{���̌f�ڂ���B�i���؎��{���̙֑ɗ��̌f�ڂ͖����j
�@���ʑ����؎����c�R���o�����ł���B
�@���ʑ����F
�@�@��������S���ÁE�����E�ʑ��̈�s�ɂ͋ʍ���i�ʑ��j�E�ʍ쓌���i�ʑ��j�Ȃǂ̂V�������������Ƃ��A���a�R�O�N�ɔ�������B
�@�@�@�@�����O�@�̌n�����n���ɐ������s��s�{�h
�@���������Ö@��
�@�@�����̋ʑ��E���E����E�ђˁE��E������E�сE����y�т��̎��ӂ̑��X�͓��M�������A�����U�N�i1794�j�E�����s����B
�@�@���̖@��ł��̒n���̑g�D�͑Ō�����B���ɖ@���͉�ł��A��L�̈�������ꂽ���̂Ǝv����B
�@�@�@�@�����O�@�̌n�����������Ö@��
�Ȃ��A�J�i�����j�ɓ��c�_������B
�@�J���c�_�ܓx�o�x�F35.76550524936086,
140.50700536718804�i���؎���100���t�߂ɂ���B�j
�u���j�v�ł�
�@���J(����)(��ʑ�1462��)�ɂ�����̂́A���ʑ��隬�̓��鎛���̂̔��n�̈�p�ŁA�ʑ��{���ւ̓����ł������B
���̈�~�������u�����_(�ǂ��낭����)�v�ƌĂ�ł���B
�@���̕a��u�a�Ɍ䗘�v�����Ɠ`�����A���̐{�ɂ́u�����O���ГV(1746)�\�A���H�R���א��v�Ƃ���B�����̐Ή�͒j���Ɏ����ٌ`�̐������B
2023/10/19�B�e�G
�@�ʑ��J�i�����j���c�_
���ʑ����쓹�c�_�@���u���j�v��聄
�@������1096�Ԃ�1�ɂ͓���B
���F�ւ̒ʋŁA�Ö̓�̖̍����ɂ���A��^�̂��͍̂��ɕ������܂�č����͓ǂ߂��A�������͕��Ă���B
�����q�u��@���u���j�v��聄
�@������1109�Ԓn�ŁA�ʑ����甐�F�ɒʂ��铹�[�ɂ���A�����Ȓ˂̏�ɁA��O��A�Γ�������B����͑�H�E�A����E�Ȃǂ̏��E�l�̑g�����J�������̂ŁA���_�͐������q�ł���B���q�u�ƌĂ�A�������q�̐���������ĂĂ���B
�@���̂����̎�Ȕ�ɂ͎��̂悤�ɍ��܂�Ă���B�u�������q��Q�S�N�ՋL�O�@�吳�E�����ā@�ᓰ���@�H�Ƒg�������`��g�@���R�ċg�@�Έ��g�@�����K���Y�@�Έ�M���Y�@���{�ё��@��P�J�����Y�@��P�J���g�@�F��e���@�약��@�F�������@�����h�g�v�u�얳���@�@�،o�@�������q�ω����q�́@�\�~���ԁ@���Oᡓ�(1753)��\����@��ʑ������@���Z�@�����v�u�����c���q�@�����㕸��(1826)�O����\����v
�@�����āA������N(1826)�O�������̂��̂̑�ɂ͎��̖����L����Ă���B�u��܉q��@�y�g�@�蔪�@�^���@�L�g�@�y���@�V���@�����@�O���q��@���g�@�ѕ��@�呠�@�Õ��q�@�����@�ё��@�F���@��g�@�@�@���@�@�@���@�����@���g�@�����@�씪�@���ܕ��q�@�����@�叕�@�g���@�^�܉E�q��@�����@�����v
2023/10/19�B�e�F
�ʑ����쒹���Ɠ��c�_
�@���̒����Ɠ��c���͕s�ނ荇���Ȃ̂ŁA���̒����͑��q�u��̂��̂����m��Ȃ��B�Ƃ����̂́A���q�u��͕��߂Ɍ������炸�A���邢�͒����w��ɂ���˂̏�ɂ���̂����m��Ȃ��B�i�ˏ�͒T�������B�j�����Ɏʂ�͓̂��c�_�ł���B
�ʑ����쓹�c�_�F�P��̓��c�_�����邪�A��L�̐�������������A���c�_�P��͏����ړ����Ă��邩���m��Ȃ��B
�Ȃ��A���̒����Ɠ��c�_�̒n�_��k�シ��Δ��F�Ɏ���A���ɕ��A��������ɓ��������������ˁi��n�j�ł���B
�@�ʑ����쓹�c�_�P�@�@�@�@�@�ʑ����쓹�c�_�Q
���s��s�{�h�̎j�ց@�㊪1043�`
�@���؎��̏��ǂ���s��s�{�̈�Ղ�e���ɍR�����l�X�̕��Ȃǂɂ��ċL���B
���ʑ������B�����
�@�ʑ���~�ɂU�J�����������Ƃ�����B
�@�@���Q�l�F�@�����O�@�̌n�����n���ɐ������s��s�{�h
�P�j����B�����E�E�E����ʑ�2168�Ԓn�A�y�ʑ������z
�@������2168�Ԃ̐Έ�Ɖ��~���ł��邪�A���R�̉����獈���o�ĐX�̒��̈��ɒʂ��A���̏��a�͊O������`�����Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����B
�@�s��h�̑m���Ђ����ɉB��Z�݁A�܂��������ē��M�҂ƂƂ��ɖ@������葱�������̈��́A���h�����̌���吳�N�Ԃ܂Ŏc����Ă������A�Έ�Ƃ̉B�����d����X��܂Ŏg���Ă����Ƃ����B
�@���́u�B�����d�v�́A�s��h�Ǝ�h�̕��d��w�����킹�ɂ������̂ŁA�\���d�͐��ʍ��~�ɔh��ɏ����Ă��邪�A�s��h���M�҂́A���̗��ʂɂ����Ĕ[�˂ɉB���ꂽ���h�̕��d�ɏ��^�̙�䶗����|���A�\���d����ɋ����������Ĕq��ł����Ƃ����A���҂̗ՏI�o�ɓ����Ďg��ꂽ���u�J�����̔��v�ɂ́A�h�ёm�̈������ȂǕs��h�̔镨���B����Ă����Ƃ����B
2023/10/19�B�e�F
�@�ʑ�����B���ՂP�F�Έ�Ɖ��~
�@�ʑ�����B���ՂQ�F�Έ�Ɩ�A���̖�\�͐Έ�Ƃ����̒n�̍��_�E�x�_�̊K�w�ł��������Ƃ��������̂����m��Ȃ��B
�@�ʑ�����B���ՂR�F�Έ�Ɨ����@�@�@�@�@�ʑ�����B���ՂS�F�B���Ɏ��铹�ł����������m��Ȃ��B
�Q�j���鎛���@�E�E�E�����鎛���ɋL�ڂ���B
�@�����͕\�ʏ�͎�h�ŁA���l�ɑ����ʓI�Ȏ��������Ă������A���@�ɕs��h�̕������䶗����B���A�s��h�Ƃ��Ă̍s�@�͖�ɂȂ��čs�����Ƃ����B
�R�j�⒆�̗��R�E�E�E���ʒu������ł����B
�@�⒆�̗��R�ŁA����ܘY�E�q��̗��R�ł���B
�S�j���ʈ��E�E�E�������ʂ���̂ł��낤���A�����Ɉʒu�͓���ł����B
�@���ʈ��Ŏ����ʂɂ���B���̔鑠���Ă������ɓ��@�M�ɂȂ��䶗�(�@��)�ߋ���(�ʑ��@��҂̎����L������)�Ȃǂ���������B
�T�j�������E�E�E���ʒu������ł����B�y�V�c�����z
�@�ʑ���n������L���̎R�ђ��ŁA�Z�����ˁA�~���J(����߂�����)���߂��A�����V�c�F�؉Ƃ�����Ă����B�s��h�@��҂̉ߋ������������A�R���ɂ͕s��m�̕�����ߎc����Ă���Ƃ����B
�@�������͌��x���s�A�������s��s�A��ʑ��ɐڂ��A���̓���ł���B
�U�j�x�V�`����ՁE�E�E���S���ʒu������ł����B
�@���͎͂R�тŐl�Ƃ�����Ă���B�ꉮ���̊Ԃ̏��ւ��g�����Ƃ�����B
�@�@�@�����O�@�̌n�����������Ö@��
���ʑ�������(����)�@�@�㊪1044�`
�@�@�����É@������E���P�@������Ȃ�
�@������2178�Ԓn�ɂ���B�E�E�E�E�ʒu������ł��Ȃ����A��L�u����B�����v�̖k���ʂɕ�n�i�����n�j������A�����ł��낤�Ǝv����B
��撆���ɂ͌Õ���̍����S���قǂ̒˂�����A�l��̐Δ肪���Ă���B
�P�j���É@������
�@�ʑ��k���ܐ��\��(�@�؎�����)���É@�����̔�ł��邪�A��L���_�̌����ɂ����̂ŁA�u�얳���@�@�،o���É@�������l�@����S���C�N(1678)��������@�M�\�V���`�h�����t����@���������@���_�����v�ƍ��������B
�Q�j���P�@�����i��t�h���J�c�j
�@���P�@�����͊��ю������ɏ�t�h�т��J���A���q�������̓ł���B�u�얳���@�@�،o�@�������l�@���P�@�@���\�P�O���N�N(1697)�����\������v�Ƃ���B
�R�j���@��m�ܕS������
�@���̈��ɂ́u�얳���@�@�،o��Q�ǖ��o��畔�@���@��m�ܕS���������@��畔�@�@���@���\���蔪�S�����A�V�����h�N��(1791)�\���\�O��������(���ꂽ�Ղ���)�v�Ƃ���B
�S�j���������@���_��
�@���_�͋ʑ��̗�؉Əo�g�ŁA��t�h��(���сE������)�X���A���q�������R�����C�����w�m�ł���B
�蕶�͎��̂悤�ɍ��܂��B�u�얳���@�@�،o�@���������@���_���l�ʁ@�J������@�`�V�q����@���ۂU�N�h�N�N(1721)�\��������v
���_�́A���O�Ɏ����̐�t���M�����̕������B(�V�O��Ƃ��X�O��Ƃ�������)
���ʑ������u�{���@�a�v���@�@�㊪1045�`
�@�ˁi��L�̓����˂ł��낤�j�̍���ɂ���Ⴂ�˂ɎO��̐Γ������сA���̍��[�̐́u�{���@�a�v��ł���B
��͂Ɂu���@�@�{���@�a�@������Z��o�@�������b�q(1744)�l����\��������@�{��@�@���@�F�K�������@�|�B��疺��h(�����)�O�ʓa�����@�b�z�����Օ��ꑰ�썰�@���싏�����������d���v�ƍ����B
�@�u�{���@�a�v�Ƃ́A���|���L�����(�S�Q���Η])�����|��j���̘Z���ŁA���Ƃ͕̉h(�����)�����P�G�։ł����l�ł���B
���̂��Ƃɂ��čL���s�ɏƉ�邪�A���̂悤�ȉ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L
�@�P�A�{���@�a������Z��o�́A�L���˂S��ˎ叼��(���)�j���̏��[�P�A���ߎ�P�B���\�P�V�N(1704)������\�������B�������N(1744)�l����\��������B�͕h�P�G�̓����B�iWikipedia�ł́u���쒉�������A�̂��X���������A�̂��͕h�P�G���Ƃ���B�j
�@�Q�A�͕h���́A��X�_�y�������Ē���Ɏd�������Ƃ̉ƕ��ŁA�{���@�a���ł����̂͌����[���]��ʉ͕h�P�G�ł���A���T�N(1755)�Z���ܓ��ɂT�Q�Ő����Ƃ���B(�������T)
�@�R�A�Օ��ꑰ(���_�ɋA�˂��Ă������{)�Ƃ̊W�ɂ��āA�����d�C���ƕ����̌n�}�ɕs�ځB
�@�S�A���@�@�s��s�{�h��ی삵���l���ɁA�L���˂Q��ˎ�������̓����A�����@������B
�@�@�܂���h���ɂ��čL���s���}���ق́A���̂悤�ɋL���Ă���B
�@�@�J���o�^���B�͕h���B���ƁB�{���������B����[�����������̓�j�Q�c�����A��Ƃ�n���ĉ͕h�Ə̂��B
�@��X�_�y���ȂĒ���Ɏd���A�����Ɏ���ؑ��ɗq�݂�������ꂽ�B
�������\�����\�����\���v�\�����\�G���\���M�\�����\���v�\�����\�G�x�\���Ձ\��G�\���\�G���\���F�\�P�G(�{���@�̕v)�\���G�i�{���@���q�Ǝv����j�\�G���\���S�\���\�����\�����\���q�\�����\���ā\���p
�@
�@�L���ˎ��쎁�͕s��s�{�h�̊O��҂ł��邪�A������v�l�����@�́A���{�̏��˂ɑ���s��h�e���ɍR���ꂸ�A���\�S�N(1631)�V��@�ɉ��@���Ă���B�����A���ꂪ�\�ʂ����̂��Ƃł��������ۂ��́A���ɂ��Ă͕s���ł���B
�@�܂��A��t�h��(������)�͋����鎛�ƂƂ����L�����O���̖����ł���A���_�̊w���Ɗ���Ԃ肩�炵�Ă��A��쎁�̋����O�삪���������ƂƎv���A�����@�̌����������{���@�i�{���@���j�����_�����āA���ʂ̌��Ƃ̓����ł���Ȃ���s��h�̓��M�𑱂��Ă������Ƃ����Ȃ����悤�B
�@���̖{���@��́A���n�̕s��h�m(���邢�͓��_��)���L���̒n��K�ꂽ�Ƃ����Ƃ̉��`�������Ƃ���A���̈̕ӂ����߂āA�{���@�Ɠ��_�ɋA�˂������{�Օ����̋��{�̂��߁A���_�̓�\�O����ɓ���������(�@���@�j�B�т̖@�ю����B�������Ö@���ɂ�蓯�U�N(1794)�\�ꌎ�S��)�����Ă����̂ł���Ƃ����Ă���B
�@���@���@�������сE�@�ю����Q�ƁB
�@���@���@�����͗т̖@�ю����ɂ��̖����Ȃ��A�s��s�{�m�ł������̂Ɛ��肳���B
�@���@�ю����ł���@���@�����͊����U�N�i1794�j�������Ö@��ɂ��\�ꌎ�S������B
�@�@�u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�v�������a�E�Ȏ��~�q�A�J�����@�A���a�T�R�N�@�u�N�\�v169�ɋL��
�@���i2023/12/06�摜���ցj
�@�@����E�O�c�E���ƊW�}�F�敟�@�E��暉@�i�U�P�j�E���P�E�����@�i���P�j�E�{���@�i�[�P�j�n��
�@�����������@�y�т��̌����������{���@�Ƃ̉����s��s�{�m���Ƃ̌q��������ɓ`����̂́A�u�{���@�a��v�ł���A�܂������ʑ����鎛�����������t�h�сi���ђh�сj�i�������j���L�����O�����ł���Ƃ����{���W�Ȃ̂ł��낤�B
2023/10/19�B�e�F
�@�{���@�a�ق�����@�@�@�@�@�{���@�a����@�@�@�@�@�{���@�a���E����
�@����@����F����@�吳���S��/���ۋ�b�C�i1794�j�ƍ��ނ��A����@�吳���S�Ƃ͕s���B
����Ց�����ʑ������˕�n�@�㊪1046�`
�@�@�@�����@�������/���m�@���q���{��/�����E�����E�����E���O�E���́E���[���{��/������
�@��������2073�Ԓn�ɂ���A�u�o���ˁv�Ƃ������B
�@�@�@�������˕�n�i�������n�j�͍��͓�ʑ�������n�Ƃ������悤�ł���B
�@�@�@�@�f�����������l�����̍q��ʐ^�œ�ʑ�������n�z��ʒu�ł̕�n�炵���f�����m�F�B
�s��s�{�h�m�̕��A���{���������������ď����ȕ��˂�����N�����Ă���B
�@���̒��Łu�J�����C�����l�v�ƌĂ�Ă���̂́A�ʑ��h�ъJ����@�����̕��ł���B
�@�����͏�ɖ��{�̐���̌����|�߁A�������@�@���x�z���邱�Ƃ͋����Ȃ��Ƃ��āu�|���_(����߂����)�v���B
���̔蕶�́u�|���_��@�������l�O�S�\�����L�O��@���a�\�l�N���I�@��ʑ��M�k���v�ƍ����B
�@�@2023/12/27�lj��F
�@�@���u���|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�Ɂu�J�����l�v���̌f�ڂ�����̂œ]�ڂ���B
�@�@�@�J�����l����F�u�Ж��_�v�̕M�ҁE�����@�������ł���B�斘�̍���u�J�����C��v�Ə̂���Ƃ����B
�@����ɑ���Γ��������A�u��旹���a���N�b�\(1764)�����g���@�{�哹���v�Ƃ���B
�@���̒˂ɂ͎O��̐Γ�������B
���ꂼ��
�u���@�얳���@���F�@�얳���N��F�@�얳������F�v
�u���@���q���l�@�����N�h��(1681)�㌎����v�@�����m�@���q�ł���B
�u�����@�����������F�����}�[�N�i�\���s�\�����j�̕\����@���a��(1768)������\�Z���@���l�N�b��(1754)�\���\�O���@�ё�����������������@���@�����@���Ƌt�C�v
�ƍ����B
�@�܂��ʂ̒˂Ɏl���A
�u�얳�������l�@�������l�@�������l�@���O���l�@���̐��l�@���[���l�v
�u�ϖ��@���G�o�ʁ@�������V�V(1654)�Z�����{�����v
�u�����@�@�����v��@�����@�����t�C�@������(1661)�N�h�N�������{�ܓ��v
�u�����@����������F�����}�[�N�i�\���s�\�����j�̕\����@������p�ИZ������O�\�l�@���k���@�F�k����A玅��(���@)�����F�����}�[�N�i�\���s�\�����j�̕\����@�E���v�����@���O�ʗ����O�j�������j������͓����M�����q�@���^�@�a���O�勏�m�@�������Y�`�ƌܒj���ܘY�`�����H�r���`���V���@�^��@�a���Ƒ�o�v
�̂悤�ɓǂݎ���B
����Ց�����ʑ��O���n�@�㊪1047�`
�����O��揊�ɂ���
�@�O���n�̈���FGoogleMap�q��ʐ^�F2024/01/16���ցF
�@�@�@�O���n�ɂ����āA�s��s�{�h��t�̕揊�͎��̂R�����ɏW��Ă���Ǝv����B
�@�@�@�@�O���n�����@��ҕ揊��
�@�@�@�@�O���n�����@��ҕ揊��
�@�@�@�@�O���n���V�@��ҕ揊���F�ʑ������˂�ʑ������˕�n�Ȃǂ���ߔN�J���ꂽ�擃���W�߂��Ă�����Ɛ��肳���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���֘A�y�[�W�F��-----�����s��s�{�h�B����-----
�@���O��1611�Ԃ�2�����ݒn�ł���B
�@���Â𒆐S�ɁA�����U�N(1794)�̏H�A�s��h�̑�e�����s����B�@�@�@���������Ö@��
���̏ꏊ�Ɏ��̌ܐl�̖@��҂̕悪��������Ă���B
�@��h�@�����@�@�@�@�����Z�N�\�ꌎ��\�ܓ��@
�@���D�@�����哿�@���N������\�Z���@
�@���~�@�@�d���g�@���N�����\�l���@
�@�M�s�@��@����@���N�\�����@
�@�ꑊ�@�@�B�@�@�@�@���N�\�ꌎ�\����
�@�@��������S���Ƃ���Ă��邪�A����A�܂��͒f�H���ɂ����̂Ƃ�����B
�@�E�̂��������E�����͋ʑ��̈���ŁA���g�E����E�ꑊ�@�͂��ꂼ��^�E�q��E�^���q��E�`���q���Ƃ����ʑ����_�Ƃ̏o�g�҂ł���B
�@�@���Ȃ��A��L�̂T�l�̖@��҂̓��A�m�F�ł����擃�͌���i2023/11/26���݁j�u��h�@�����v�̂P��݂̂ł���B
���O���n�����@��ҕ揊���O���n�����@��ҕ揊��
2023/10/1�X�B�e�F
�@�O���n�͋ʑ����؎��̊Ǘ��Ƃ����B�i�u���j�v�j
�@��q�̂悤�ɁA�ʑ��O���n�ɏ�ɋL�ڂ̌ܐl�̖@��҂̕悪��������Ă���Ƃ����B
�������A���ʂ́A�T�����s�\���ŁA��L�̂T�l�̕��͔����ł����B
���O���n�����@��ҕ揊��
�@���@��ҕ揊�P�@�@�@�@�@���@��ҕ揊�Q�F������̕��������̔��ǂ����������B
�{��揊�ł͔��ǂ��������̂Q��ɂ��Čf�ڂ���B
���Ɖ@����
�@��Ɖ@��������F���\�l�H������/���@��Ɖ@��������/�l���\�Z���ƍ����B
��Ɖ@�����ɂ��Ắu�[�����@��j�i�ȉ��E�[���j�v�u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�i�ȉ��E�N�\�j�v�ɋL�ڂ��Ȃ��A�ڍׂ͕s���B
������@���~��
�@���\�T�N�N�I����F���ʂɌ��\�ܐp�\�V/�Z���\�ܓ��ƍ�����B
���ʂ̖��͖��m�F�����A��N���璲������u����@���~�v�ł���\���������Ɣ����B
����@���~�ɂ��ẮA
�@�u�[���vp.275�ł́u���\�T�N�U���P�T���E����@���~�f�H���E�ʑ��h�сE�U�P�ˁv�Ap.291�u�ʑ��������o���ʑ��k�ђf�H�v�Ƃ���B
�@�u�N�\�vp.107�ł́u���\�S�N�U���P�T���E����@���~�ʍ�Œf�H���肷��B�U�P�B���\�T�N�U���P�T���Ƃ��B�v�Ƃ���B
�@���@��ҕ揊�F���@��ҕ揊�̐����ɂ��s��s�{�h����҂̕擃���W�߂��Ă���B
�����̕������������ǂ���A�܂��T�����s�\���ő唼�̕��̏ڍׂ͕s���ł���B
����@���@
�@����@���@����F���ʂ́u����@���@���l�v�A�����ʂ́u���i��q�N�i1780�j�v�ƍ�����B
�@�u�[���vp.294�ł́u����@���@�@�T���P�R����v�Ƃ̂L�ڂ����
���b�h�@����
�@�b�h�@��������F�u�b�h�@�����v�ƍ��ށB
�b�h�@�����ɂ��Ă�
�@�u�[���vp.295�ł́u�����V�N�P�P���U����ʑ����v�Ƃ���B
�@�u�N�\�vp.180�ł́u�����V�N�P�P���U���v�A�����ʍ쑺�̏Z�v�Ƃ���B
2023/11/29�B�e�i����j�F
�@���ʂ͓ǂݎ�肪�\�܂��͈ꕔ�\�Ȉȉ��̕擃�ɂ��Čf�ڂ���B
���̒��ŁA�����ȕs��s�{�m�Ƃ��āA���u��l�̕擃�i���{���j�P��m�F�����B
�@�ǂݎ�肪����ȕ擃���������ŁA�\�ʂɁu�얳���@�@�v���������ޕ擃���U�������B
�����͑��ʂȂǂɖ@�������܂��\���������A����A���ʂȂǂ̊m�F���\���ł͂Ȃ��A����̊m�F��ւB
������@���B���l
�@��@���B���l�擃�F�͂�����Ƃ͓ǂ߂Ȃ����A�u��@���B���l�v�̂悤�ɓǂ߂�B
������@�������l
�@����@�������l�擃�F���@�@����@�������l�A�u�[�����@��j�v�i�ȉ��u�@��j�v�j�F�V��7.11.4��A�r�k��
�������@��������
�@�����@�����擃�F�얳���@�@�،o�@�����@�������ʁi�����S�ʂł��낤���j�A�����͔j��Ă���̂ł��낤���H
����h�@����
�@��h�@�����擃�F�u�@��j�v�F����6.11.26��A���Ö@����S���A�ʑ����܂�A�����
����Ɖ@�������
�@��Ɖ@�����擃�F���@�@��Ɖ@�������/���\�\�O�M�C�N/�l���\�Z��
���@���@�����哿/�ʐ��@�������l/���s�@�����哿
�@�O��t�擃�F�얳���@�@�،o�@�@���@�����哿/�ʐ��@�������l/���s�@�����哿
�����Ɛ��l
�@���Ɛ��l�擃�F�얳���@�@�،o�@���Ɛ��l/�����E�E/����������
�������@���C�哿
�@�����@���C�哿�擃�F�얳���@�@�،o/�����@���C�哿/�����E�E����
������@����
�@����@���ӕ擃�F�얳���@�@�،o�@����@����/���Z���q�N/������\����A�u�@��j�v�F���6.1.20��A�ʑ���
���Ŏ�@����/���{�@����
�@�Ŏ�@����/���{�@�����擃�F�얳���@�@�،o/�Ŏ�@����/���{�@����/�哿
�@�@���Ŏ�@�����̓����͔��ǂł��Ȃ����A�܂��u�Ŏ�@�����v�ł��낤�B
�@�@2024/08/02�lj��F
�@�@�u�[���vp.155�ɂ́F
�@�@�����i�����E���ہE�����j�E�E�E�n���@���ɐ���ł���@���͌�������Ȃ����A
�@�@��肪�������z���Ă���@���Ƃ����V���Ŏ�@����������B
�@�@�V�u�Ќ̖x�z�`�����̕ł́A�Ŏ�@�����͒ʏ̖��q��A�V���R�ӉƏo�g�ŁA
�@�@�u�L���E�g�E�ˁA�Ɖ]����܊�̕�����ی��N�����\�ܓ��A�V���A�Ŏ�@�����v�Ƃ�����肪����A
�@�@���ɗё��ɂ����𗧂āA��h�ߒŖ��Ƃɐ������̖{�������^���Ă���B
�@�@�@���u�L���E�g�E�ˁv�Ƃ͏�Ȃ��A�s���B
�@�@p.288�ł͘Ŏ�@�����@�����S�N�P���Q����@�����@�Ƃ���B
�@�@�@�{�T�C�g�Ŋm�F���Ă���̂́A���̕擃�Ɓu���䖭���O��n���T�D�T�j�s��s�{�m�Ŏ�@�����v�̂Q���ł���B
�@�@�@�@�@�Ŏ�@����/���{�@�����擃�Q
����v�@���s�哿
�@��v�@���s�哿�F�얳���@�@�،o�@��v�@���s�哿/���a�����E�E/�����\�ܓ��A�u�@��j�v���a3.3.15��A�R�q�B��
���O���n�E���@��ҕ揊�F
�@�O���n�E���@��ҕ揊
�����S�@����
�@���S�@�����擃�F���@/���S�@�����E�E�E/�i�E�̗�͋j�F�Ȃ͍̂��ꂽ�̂ł��낤���H
����ᧉ@����/�~�@�@����/�~�s�@����
�@��ᧉ@����/�~�@�@����/�~�s�@�����擃�F���@/��ᧉ@����/�~�@�@����/�~�s�@����
���ʐ��@�����i�H�j
�@�ʐ��@�����i�H�j�擃
�����u���l
�@���u��l���{���F

|
�@���u���l���{���F���}�g��}
�@���u���l�������F
�@���\�\�ꁡ����/���u���l/�O���\���ƍ����B
�i�Ȃ��A���\�P�P�N�̊��x�͕�ЁB�j
�@�ܘ_�A���\�P�P�N�R���P�O���͓��u��l�̎���N���ł���B
�@ |
���O���n���V�@��ҕ揊��
2023/10/19�B�e�i����j�A2023/11/29�B�e�i����j�F
�@�u���Ò��j�v�Ҏ[�̌�A���̑O���n�ɂ́A��q�́u�����ˁv�y�сu�ʑ��������n�v�Ȃǂ��瑽���̕s��s�{�h��t�̕��E���{���ނ��A�ڂ��ꂽ�Ɛ��肳��A�u�s��s�{�h��t�̕擃�E���{���ށv���ї������恃�V�@��ҕ揊��������B
�@���O���n�̈���FGoogleMap�q��ʐ^�F2024/01/16���ցF
�@�@�O���n�ɂ����āA�s��s�{�h��t�̕揊�͎��̂R�����ɏW��Ă���Ǝv����B
�@�@�@�O���n�����@��ҕ揊��
�@�@�@�O���n�����@��ҕ揊��
�@�@�@�O���n���V�@��ҕ揊���F�ʑ������˂�ʑ������˕�n�Ȃǂ���ߔN�J���ꂽ�擃���W�߂��Ă�����Ɛ��肳���B
�擃�E���{���ށF�O��i��ʁj�������č����
�@�O�O�P�E�@���@�擃�i���ܓ|����j
�@�O�O�Q�E�����H�@����
�@�O�O�R�E�O�O�R�擃�i�s���j
�@�O�O�S�E�@���@�@�S���s�ق��擃
�@�O�O�T�E�@�s�@����
�@�O�O�U�E�����@���P
�@�O�O�V�E�k���J��c����
�@�O�O�W�E���q���l�擃
�@�O�O�X�E���Z���l
�@�O�P�O�E�����@���`
�@�O�P�P�E���P�@����(��t�h�ъJ�c�j
�@�O�P�Q�E���W�@����
�擃�E���{���ށF������F�������č����
�@���O�P�E���O�P�擃
�@���O�Q�E�{��@����
�@���O�R�E�����@����
�@���O�S�E�i����j�s���ꖜ�����A
�@���O�T�E�����@���u
�@���O�U�E���@���N������
�@���O�V�E���P�Q�N���U
�@���O�W�E���@�ܕS������
�@���O�X�E���q�@����
�擃�E���{���ށF���i�k���j�������č����
�@��O�P�E����@����
�@��O�Q�E����/�����O�̐i�[
�@��O�R�E�����@����
�@��O�S�E���U�i�s�m�F�j
�@��O�T�E����s���ܐ畔���A��
�@��O�U�E�����O�S�\������
�@��O�V�E���U�i�s�m�F�j
�@��O�W�E���������@���_
�@��O�X�E���É@����
�@��P�O�E���P�Q�N���U
�ł���B
���O���n���V�@��ҕ揊��
�@���O���n���V�@��ҕ揊���@�@�@�@�@���O���n���V�@��ҕ揊���E��������
���O��i��ʁj
�O�O�V�E�������l�i�ʑ��k���j
 |
�O�O�W�E���q���l
 |
�O�P�P�E���P�@�������l(��t�h�ъJ�c�j
 |
���擃�E���{���ށF�O��i��ʁj�������č����
�O�O�P�E�@���@�擃�i���ܓ|��擃�j
�@�O�O�P��@���@���ܓ|��擃
�@���O�O�P�E�@���@�擃�i���ܓ|��擃�j �F�@���@�̖����c��B
�O�O�Q�E�����H�@����
�@�O�O�Q�E�����H�@����擃�F�����F���ۏ\�Z�h��/�����H�@����/�l���ち�������@�i���Ȃ��j
�O�O�R�E�O�O�R�擃
�@���O�O�R�E�O�O�R�擃�F�얳���@�@�����@�������l�@�Ɠǂݎ��邪�A�����Ȃǂ͔j��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�j���͌̈ӂȂ̂��A�s�R�͂Ȃ̂��͕s���j
�@���O�O�R�E�O�O�R�擃�E����
�O�O�S�E�@���@�@�S���s�ق��擃
�@���O�O�S�E�@���@�@�S���s�ق��擃�F�\�ʂ̖��͎��̂Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�M�s�@�@�^����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����O��ߔN�E�E�E�E�i����3�N/1738)
�@�@�@�@�@���@�@�@���@�@�S���s�@�E�E�E�E�@�͐�+���̎��ł���̂Łu�@�v�̑����ł��낤�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�ꖭ�^���@��
�@���O�O�S�E�@���@�@�S���s�ق��擃�E����
�O�O�T�E�@�s�@����
�@�O�O�T�E�@�s�@�����擃�F�����F����K/����@�s�@�����o��/�����l���@�i���Ȃ��j
�O�O�U�E�����@���P
�@�O�O�U�E�����@���P�擃�F���͕����s���@�@�@�@�i���Ȃ��j
�O�O�V�E�k���J��c����
�@�O�O�V�E�k���J��c�����F�����@�F��}�g��}
�@�@�����F���i���N�\�������Z������/�얳���@�@�،o�@�k���J��c�������l[�����H/����]/�@�ؕ���u�H���A�V����
�@�@�@�i�����R�N�i1654�j�P�O���R�O���J���j
�@�@�Ȃ��B���̕擃�́u�������n���ڐ݁v���ꂽ�擃�i��O�U�E�����O�S�\�������j�Ƃ͕ʂ̂��̂ł���A
�@�@�@��������ڐ݂��ꂽ���͕s���ł���B
�@2023/01/21�lj��F
�@���O07�E�k���J��c�����E�����}
�@�@�������Č�������B�i���̂悤�ɓǂ߂�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�����������Z����{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�얳���@�@�،o�@�k���J��c�������l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؕ���u���A�V�����V
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���h�E�E
�@�@�@���u���i�����������Z����{�v�ɂ��āA�N���͓ǂݎ��Ȃ����A
�@�@�@�u�����͊��i�P�O�N(1637)�O���ɋʑ��@�؎��Ɉڂ�A�̎����R���̂Ђ����ȊO������ċʑ��h�т�n�݂��A
�@�@�@���̊J��ƂȂ�v�Ɖ]����̂ŁA���i�P�O�N�̔N�I�ł������Ƃ��v���A���������ł���A���̔N�I�͊��i�P�O�N�ł��낤�B
�@�@�@�܂�A����͋ʑ��k�ёn�݂̔N�I���������̂ł��낤�Ƃ��v����B�i���݂Ɋ��i�\�N�̊��x��ᡓсj
�@�@�@�@�����
�@�@�@�u�����@���h�v�́u���^�@���h�v�Ƃ������邪�s�m���ł���B�@
�@�@�@�������A�����u���^�@���h�v���Ƃ���A�u���^�@���h�v�͋ʑ��k�тQ���ł���A���̋��{���́u���^�@���h�v��
�@�@�@�u���i�P�O�N�U����{�v�܂�u�@�ؕ���u���A�V���v�V�����������������͂�����L�O���Č��������Ɖ��߂ł���B
�@�@�@�@�Ȃ��A�u���^�@���h�v�擃���ʑ��@�؎��揊�ɂ���B���h�тQ�����^�@���h�����
�O�O�W�E���q���l�擃
�@�O�O�W�E���q���l����F���m�@�F��}�g��}
�@�@�y�������n���ڐ݂Ɛ���z
�@�@�����F�����h�сi1691�j/���@�@���q���l/�㌎���
�O�O�X�E���Z���l
�@�O�O�X�E���Z���l�擃�F���������@���_�̌����ł��낤���A�����̓������ǂ߂����l�̖��͕s���B
�@�@�����F���������@���_���l�ׁH�q����/���@�@��������ɗ����������l/�����O�����N�\�ꌎ�������������E�E�E���L�ɕύX
�@�O�O�X�E���Z���l�擃�E����
�@�@�����F���������@���_���l��q����/���@�@��������ɗ������Z���l/�����O�����N����������������
�@�@�ʐ��@���Z�F����3.3.14��A�ʑ����i�u�@��j�v�j�E�E�E����N�����v�������������v���Ȃ����A�ʐ��@�Ǝv����B
�O�P�O�E�����@���`
�@�O�P�O�E�����@���`�擃
�@�@�����F���\��p�N�N/���@�@�����@���`/�\�����ܓ�
�@�@�u�N�\�vp.155�F�u���12�N11��24�������@���`�v�i�P�P���Q�U���Ƃ��j�s���h�̑c�A�����ё��Z�v
�@�@�u�[���vp.282�F�u���12�N10��25����A�s���h���J���A85�v�@��p.295�F�u���12�N11��24����s���h�ё��v
�O�P�P�E���P�@����(��t�h�ъJ�c�j
�@�O�P�P�E���P�@���������F��}�g��}
�@�@�y�����˂��ڐ݂Ɛ���z
�@�@�����F���P�@/�얳���@�@�،o�@�������l
�O�P�Q�E���W�@����
�@�O�P�Q�E���W�@�����擃
�@�@�����F���l�b���V/���@�@���W�@����/�p�\�����@�@�i���Ȃ��j
��������
���O�T�E���u���l
 |
���O�X�E���q�@�������l
 |
���擃�E���{���ށF������F�������č����
���O�P�E���O�P�擃
�@�����O�P�E���O�P�擃�F�\�ʁF���@�@�̂ݓǂݎ���B����ȊO�́A�R��ɓn�蕶��������悤�Ɍ����邪�A���ǂł��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͖��ՂȂ̂��j��Ȃ̂��s���ł��邪�A�j�ꂽ�悤�ɂ��v����B
���O�Q�E�{��@����
�@���O�Q�E�{��@�����擃�F�����F�����l�h����/���v�H�{��@�����哿�H/���������ܓ��E�E�E���L�ɕύX
�@�@�u�[���vp.281�F�u����4�N1��15���{��@������A�����ʑ����@�؎��v
�@�����O�Q�E�{��@�����擃�E����
�@�@�����F�����l�h����/����{��@�����哿/���������ܓ��i���͔N�̈ӁA�����{�����T���͏{�̈Ӂj
���O�R�E�����@����
�@���O�R�E�����@�����擃�F�����F���������\����/���@�����@��P�H����/�s�N���\��ˁ@�@�i���Ȃ��j�E�E�E���L�ɕύX
�@�����O�R�E�����@�����擃�E�����F�����F���������\����/���@�����@��P����/�s�N���\���
���O�S�E�i����j�s���ꖜ�����A
�@���O�S�E�i����j�s���ꖜ�����A�F�����炭����ꖜ�����A�L�O��Ǝv����B
�@�@�����F�i�P�s�ڔ��Ǖs�\�j/�����@�����H��/��J��[��u��/������]�s���ꖜ�����A/��������
���O�T�E�����@���u
�@���O�T�E�����@���u�擃�F��}�g��}
�@�@�����F��s���g���A�ɖ��㓹/�얳���@�@�،o�@�����@���u���l/��������ܕS�\����ӓ�
�@�@���o�܂͕s���ł��邪�A�s��s�{�嗬�h�i���w�h�j��̂Ǝv����揊�ɍu��h�i�Î��h�j�W�̕�肪����B
���O�U�E���@���N������
�@���O�U�E���@���N�������{��
�@�@�y�������n���ڐ݂Ɛ���z
���O�V�E���P�Q�N���U
�@�O�V�E���P�Q�N���U
���O�W�E���@�ܕS������
�@���O�W�E���@�ܕS������
�@�@�y�����˂��ڐ݂Ɛ���z
�@�@�����F��Q椖��o�@�ܕS����/�얳���@�@�،o�@���@��m/��畔�@���
���O�X�E���q�@����
�@���O�X�E���q�@�����擃�F��}�g��}
�@�@�����F����p�\/�얳���@�@�،o�@���q�@�����i�ԉ��j/�㌎��\�l��
�@�@�u�[�����@��j�v�ł́u���q�@�����@���Q�N�X���Q�O����ʑ����v�Ƃ���B
�����i�k���j
��O�U�E�������l�i���_��j
 |
��O�X�E�������l
 |
���擃�E���{���ށF���i�k���j�������č����
��O�P�E����@����
�@��O�P�E����@�����擃
�@�@�����F�������N/���≄��@���x�����o��/�\�ꌎ�Z���Z�l�ˁ@�@�i���Ȃ��j
�@����O�P�E����@�����擃�E�����F���l�N�i�b���j�̔N�I�ƕ�����B
��O�Q�E����/�����������O���̓��i���[
�@��O�Q�E���������������O���̓��i���[��t��
�@�@�y�������n���ڐ݂Ɛ���z
�@�@�����F�얳�������l(�������l/�������l/���O���l/���̐��l/���i���l/���[���l)
��O�R�E�����@����
�@��O�R�E�����@����擃
�@�@�����F������Ȗ�/�얳���@�@�،o����/�\�\�O��
�@�@�u�[���vp.280�F�u�����Q�N(1749�j12��1�R���@�����@�����@�����ʑ����v�@��p.290�F�u�����@����A�����Q�N12��1�R����A�s���h�v
��O�S�E���U�i�s�m�F�j
�@��O�S�E���U�i�s�m�F�j
�@����O�S�E�Γ��U�F�ʐ^�̉E�[
��O�T�E����s���ܐ畔���A��
�@��O�T�E����s���ܐ畔���A��
�@�@�����F������l�S�]���@�W��@���x�哿/���e�H�@�s���ܐ畔���A/�J����Z�S���@��暉@�����哃
�@�@�i���x�E�����̏��Ȃ��j
��O�U�E�����O�S�\������
�@��O�U�E�����O�S�\�������F��}�g��}
�@�@�y�������n���ڐ݂Ɛ���z
�@�@�����F�Ж��_��/�������l�O�S�\�����L�O��/���a�\�l�N���~��ʑ��M�k��
�@�@�@2023/12/27�lj��F
�@�@�@��Ɍf�ڂ́u�������n�v�ɂ������ł��낤���́u�����O�S�\������v�̎ʐ^��
�@�@�@���u���|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v���J�����l����Ƃ��Čf�ڂ���Ă���B
�@�@�@��̌`�猩�āA���̉�����Ɠ���̂��̔��f���ėǂ��Ǝv����B
�@�@�@�܂��A���̎ʐ^�̑O�ɂ͐Γ��U���Q��ʂ邪�A���̂Q������̕�n�ɍ��킹�Ĉڐ݂��ꂽ�Ƃ���A
�@�@�@���̋��ɂ͂S��̐Γ��U�����邪�A���̓��̂Q��ł���\�������ɍ����Ɛ��������B
�@�@�@�i�ǂ̂Q��Ɗm�肷�邱�Ƃ͌���ł͍���ł���B�j
��O�V�E���U�i�s�m�F�j
�@�@�@�E�E�E�ʐ^�Ȃ��E�E�E
��O�W�E���������@���_
�@��O�W�E���������@���_�擃
�@�@�y�����˂��ڐ݂Ɛ���z
�@�@�����F���������@/�얳���@�@�،o�@���_���l��
�@�@�u�[���vp.297�A279�F�u���ۂU�N10��3����A���q�������R���A��t�h�тX���A�ʑ����܂�v
�@�@�u�N�\�vp.131�F�u���ۂU�N10��3�������@���_�v�i59�j�����A�������ђh�є\���A�����ʑ������B���v
��O�X�E���É@����
�@��O�X�E���É@�����擃�F��}�g��}
�@�y�����˂��ڐ݂Ɛ���z�E�E�E�����������_�̌����i���ʂɖ�������Ǝv����j
�@�@�����F���É@/�얳���@�@�،o�@�������l
��P�O�E���P�Q�N���U
�@��P�O�E���P�Q�N���U
�@�@�����F���\��p�ߔN�܌��g���i1762�j
--------------------------------------------------------------------------------------------------
����ʑ��H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�㊪1048�`
�ޘZ���������c�_�F
�@�@������邪���̂P������グ��B
�@�@�����L�Ƃ͕ʂɁA�ʑ����؎��̍��ɒJ�i�����j���c�_���f�ڂ���B��
�@���ԗ��l�Z�O�Ԃ̓�Ɉ���A�����͑��Ò��Ɣ����s��s���E�̓��H�[�ł���B
�ʏ́y�Z�������z�Ə̂��ꂽ���S���ŁA���݂͔��n�тɂȂ��Ă���A���@�@�O�k��(����E�����E�э�)�̔\���ł������y�����̘Z�����ˁz�i�����݂͋����j�������������Z�������i��É@�����o�ˁj���ɐڂ��Ă���B���X���̔э��E����E�ʍ�E�������̍����n�_�ł�����B
�@�{�ŁA�ٌ`�̐̋������\������A���̔w�ʂɎ��̍���������B�u���c�_�@���a���N��(1801)�㌎�g���v
�@���̌㕔�ɐΑ��̈ē����W������A����ɂ́u�l����������@�V�ƍc���_�Q�q�L�O�@�����э��@�x���@�����s�ꓹ�@��������R�q���Ѝ���@�������@�������Á@���c�@�ŎR���@�吳�\�O�N�㌎���V�@��ʑ��ߐ{�����Y�@�x�V�K���Y�@�Έ䏼���Y�@�약���O�Y�v�Ƃ���B���ݎ��͔͂��n�Ƃ��ĊJ���ꂽ���A���Ă�100Ha(1000���������j�]�̐X�ётł������B
�@������ԗ��̓��c�_�F�k������B�e�A�ʂ�u�{�v�����c�_�ł��낤���A�ٌ`�̐̋����Ƃ͕s���B
�@�w��ɏ������Δ�炵�����̂��ʂ邪���ꂪ�u�ē����W�v�ł��낤���B
�@���̐�������������A�������č��i���j�̖����Ɂy�����̘Z�����ˁz������Ǝv����B
�@�u��ʑ��Α��������ݐ}�v���́u��l�ˁv�������̒˂Ǝv����B
�@�Ȃ��A���́y�����̘Z�����ˁz�E�ԗ��̓��c�_�̓�����̒n���������i���x���s�E�������s��s�j�ł���A
�@�B�����i�������j�̂������ꏊ�ł��낤�Ǝv����B
2023/10/19�B�e�F
�@�ʑ��Z�������@�@�@�@�@�Z���������c�_�E���W�@�@�@�@�@�Z���������c�_
�@�Z���������W�F�����ɂ��ẮA��Ɍf�ځB
�ޓ����ړ�
�@������1714�Ԃ̂P�ɂ���B���݂͔��n�̒��ł��邪�A�Â��͌Õ��̏�ɂ���A���Ɉ��������s���đ����̎��҂��o�����Ƃ��A�����F��Ɍ��Ă�ꂽ�Ɠ`������B���̎�K���������q���Ȃǂ̓V�_�u�����悭�Q�q�������̂ł���Ƃ����B
�u��i�l����(1707)�V�c�@�얳���@�@�،o�@����O�畔���A�@����ꌋ�j���v�ƍ����B
�@�@���@�؎��Q�������t�߂ɂP��̑�ړ������邪�A����ł��낤���H���S���ʂ��̂ŁA����ɂ����ړ��i�����j�ł���B��
�ޑO���ړ��F�u��ʑ��Α��������ݐ}�v�ɋL�ڂ���邪�A�f�����������l�����ŒT�����s���B
�@���O��1670�Ԃ̂Q�ŁA�X���ɉ��������ƏH�R�܌��}�g�̉Α���ՂƂ����B�u�얳���@�@�،o�@�����܍M�\��(1740)�\�����������@�w�Y�@���������v�ƍ����B
�ދ��
�@�x�V�����V���̌���Œ}�O���c��Ɏd�����x�V�ΉÂ̒��j�ꍲ���|�e�����t�O�����p�������A���̋��ł���B
�@���͕��̎��R�ɑ����ō��܂�Ă��邪�A�������N�܂Ŏ��O��1611�Ԃ̂Q���M���ɖ��߂��Ă����B
���̑O���n��1600�N��ɑꂽ���̂ŁA�l�����痣�ꂽ�ϒK�̏Z�ގ₵�����ł������Ƃ����B
�@�s��s�{�e�������̒n���ɏW�����ꂽ�Ƃ��A���@�@���h�ьn�̕s��̑m�A��u�͒n���ɐ��s���A���̕��͂��Ƃ��Ƃ��y�̒��ɖ��߂�ꂽ�B�s��s�{�ċ��������ꂽ������N�ȍ~�A���\�̕���@��o���ꂽ�������n���ɖ����Ă�����̂�����Ƃ����B
���̋������̈�ŁA�x�V���̈ꑰ����͊����Z�N�ɎO�l�̖@��҂��o���Ă���B
�@���̋�́A�@
�@�@�@�@�@�₦�X��܂Ă��䂩�����C�s���ȁ@
�ł���B�@
�@�܂�������̋��ɂ́A�u�̂��Ƃɏ`���Ȃ܂��������ȁ@��(��)����(�m��)
�@�����吳���N�㌎���V�@�@�약���߁@�H�R���@�약��t�@�Έ�@��@�약�Û��@�����f���@�Έ�e�G�@�H�R�g���@���R���_�@���������@�F�䁡���@���R�m�Á@���{���_�@���쁡���@���~���@�Έ�V��@��J�~�u�@�x�V���R�@���������@�약�����@�����a���@���{�яH�@���c�Ő�@�x�V�`���@�l���~�X���ᓰ�@�M�v
�@���̋��̋߂��ɍ��̕��������āA��������t�߂̑�c�܂ő����A�����܂ł͋��n��ɂ��Ȃ����Ƃ����B���̋�͂��̍����r���̂ł��낤�B
2023/11/29�B�e�F
�@�|�e�����t�O������F�|�e�����t�O���̖{���͕y�V�ꍲ
�@�m�@�ԁ@��@���F���\3�N3��2���A�ɉ��앗�����ł̉Ԍ��̉̐�̔���Ƃ����B
�@�@�吳�V�N�����A�����H���Ō��ݒn�ɑJ�����B�Ȃ��ׂɂ����^�̐Δ�͒�����Ƃ����B
�@���c�]�̈╨�̍��͏ȗ�����B
����ʑ������@�@�㊪1027�`
�@���@�������Ò��̖������̍��ɂ���B
����ʑ��Έ��ב喾�_�@�@�㊪1030�`
�@��ʑ����{�c��1136�Ԓn�ŁA�{�c�̐��c��O�ɂ����u�̒��i���J���Ă���B
�@���͂͌Â��隬���Â���悤�Ȓn�`�ŁA���~�ՂƎv���镽�n���c�����B���̔��ɂ͌Õ��炵���˂���������B
�@���̎Ђ͎Q�������ɏZ�ސΈ�Ƃ̐�X�オ�A�슴�Ċ����������̂ł���Ƃ�����B
�����Ɏ��R�Ηl�̔肪����A���̍�����������B
�@�@(�\)�x�O���́@�@�@�V���ו�
�@�@�@�@�얳���@�@�،o�t�����Έ��ב喾�_
�@�@�@�@�����ʐ_�́@�@�@�܍����A
�@�@(��)������\��N�㌎�x���S�ؐϑ����R���E�q��@�N�Z�\�l�Ε�
�q�a�E��ɏ㉮�t�̔n���ϐ��������l���A�������͖����O�\��N�Ə��a�O�N�̂��̂ŁA���̓��͖����ł���B
�@��ז��_�������@�@�@�@�@�@��ז��_�n���ω����F�w��ɍ��L�̔肪�ʂ�B�i���ʐ^�͉�����f�����������l�������]�ځj
2023/10/19�B�e�F
�@���łɁA�Гa�͑ޓ]���Ă���A�����炭��ځE��ב喾�_�̔�͎Г`�ՂɈڐ݂��ꂽ���̂Ǝv����B
�܂��A��ב喾�_�̐M�͊�{�I�ɔ_�k�_�Ƃ��Ă̂��̂ł��낤���A���@�@�̗����Ȓn��ł́A��ׂɌ��炸�_�������@�@�ƌ��т��Ƒ�ڂƌ��������X����������B
����ɁA���̒n���ł́i������ʂɁj�n���ω����J���邱�Ƃ������Ǝv����B�����̔_�k�͋�����ł��邪�A�֓��ł͔_�k���n����ł���Ƃ������ƂȂ̂ł��낤���B
�@�ʑ��Έ��ז��_�@�@�@�@�@�Έ��Гa�ՂP�@�@�@�@�@�Έ��ב�ڔ��@�@�@�@�@�Έ��ב�ڔ����
�@�Έ��Гa�ՂQ�@�@�@�@�@�@�Έ��אΊK�@�@�@�@�@�@�@�@�����n���ω��S��P�@�@�@�@�@�����n���ω��S��Q
��������Ց�����ʑ����鎛��(�ʑ��隬)�@�㊪1035
�@�����1349�Ԃ�2�B�~���R�ƍ����B�L�����O�����B
����̒n�����͓��A�����͖x�Ղ���u��n�ɘA��A���k���͐��c�ɖʂ��Ă���B�[����x������A�v�Q�A�x��Ȃǂ̒n���������c��A�������ꂼ��̒����ɗN���r������B�ڂ��������͂Ȃ����A�����̍�(1368�`71)�ɂ͖약�ɉ��팾�A����(1472�`86)�̍��ɂ͖약�ɉ��퐴�������ɂ����Ƃ����Ă���B
�@�V���P�U�N(1588)�ɖ약�ɉ���`�͑m�Ђɓ����ĊJ��A�Ï��ʓI��̈��ɓ������B
���̐Ό䓰������@�ƍ��������鎛�̑O�g�ŁA����{�y�����ł������������ӂ��A���߂Ĉ������Ƃ���Ƃ����B
�@�@�؎��Ɉ����ӂ̙�䶗��ɂ́u�ʑ��V���@�I��V�䓰�{����@���m�Q�N��q(1468)�\������v�ƋL����Ă���B
���̌���i�̂Ƃ��ɌÏ��ʂ���ʍ�隬�Ɉڂ�A����@����~���R���鎛�Ɖ��߂��B
�@�����P�Q�N�O����\�O���Ђɑ����Ď������܂܁A�Q�T���^�͉@�������Ō�Ƃ��Ē��茧��Y��(������s��Y��)�Ɏ��Ђ��ڂ�A�ߋ�������ё��̏Y���ƒh�Ƃ̈ꕔ�͘@�؎��Ɉڂ����B
�@���̒h�Ƃ͕s��s�{�̓��M�������A������Ɂ����鎛���@�́A���̉B�����Ƃ��ĂЂ����ɓ��M�����𑱂��Ă����B
�@�@�����́�B�����ɂ͕����@�����M�̙�䶗����鑠����Ă��āA���݂���͋ʑ����؎��{���ƂȂ�B
�@���Ղɂ͗��Z�E�̂ق������̕�肪�c����Ă���A�隬��`���悤�Ƃ���f�肪����̂܂c��A���̖T��Ɉ��̔肪�����āA���̂悤�ɍ��܂�Ă���B
�@�u�얳���@�@�،o�@����@���i��l
�@�k������S��֑���ʑ��̓��鎛�ҁ@���a���N(1615)���i��l�V�J��{�R�|�B�L�����O���V������@�������P�Q�N�O����\�O�����F�Ęԁ@�허�`�������F�����}�[�N�i�\���s�\�����j�̕\�����Č��V���@���j���ړ]���@�����茧���ދn�S��Y�����V���������l�\��N������@�T�h�ƔV�ʁX�וӓ��N���Җ�@�����S�Q�N�P�Q���R���H�R�t�ޏ��@���ݎғ�ʑ�����d���Y�@�ɓ��ɔV���@�H�R���ܘY�@�������Y�@�H�R�e���@�Έ䐭�ܘY�@�ɓ��g�@�R�������@��؋T���Y�v
�@���Ղ����x���ւ��Ă������̑�n��ɔ����{���J���Ă���B���약�ɉ��̎��_�ł������Ɠ`�����Ă��邪�A���݂͖약�Ƃ̎��_�ƂȂ�B�ؑ��Ɛ̏��J�ł���B
�@���ʑ��̑��̋N���ł����u�ʑ��隬���s��s�{�M�k�̉B����v�Ƃ́u�����鎛���@�́A���̉B�����Ƃ��ĂЂ����ɓ��M�����𑱂��Ă����v�Ƃ����L�q����������Ǝv����B
�@���u����@���i��l�v�ƍ������͌�������B
�@�@�@�@���鎛������G�����̔肪���i��ł���B�i�f�����������l�����@���]�ځj
�@�������Y�Ɏ��Ђ��ڂ����~���R���鎛���L�����O�����ł��邪�A���̗R���͕s���B���O�����ɂ���B
��2023/10/19�B�e�F
���鎛�Ղ͋ʑ���Ղ̓�̈�s�ɂ������Ǝv���邪�A���F�ՂȂǂ̈�ւ͌�������Ȃ��B
�����A��̈�s�ɂ͎��̖������R�n�ƕ�Ηނ���������Ďc��B���̕����ɓ��鎛���������Ɛ����������ł���B
�@�ʑ����鎛�ՂP�F�������č����ʑ���̎�s�ŁA�E�ɓ��鎛��Ηނ��ʂ�B
�@�ʑ����鎛�ՂQ�@�@�@�@�@���鎛��ΗނP�@�@�@�@�@���鎛��ΗނQ�@�@�@�@�@���鎛��ΗނR
�@����@���i���{���@�@�@�@�@�ʑ����鎛�Ք�
�@���鎛��Ηޔz�u�}
�@�@���鎛��Ηނ͎��̂悤�ɔz�u�����B�i�ԍ��͎ʐ^��̕\������ԍ��ɑΉ��j
�@�@�i�P�j�����E�𖾂ł����B
�@�@�i�Q�j�얳���@�@�،o�@����������/�����ZᡉN�i1666�j/�l���\���
�@�@�i�R�j���@�@���M�@���d/���ۏ\��ᡉN�i1733�j/�\�����@�����̓�+���̊����œǂ߂Ȃ��B
�@�@�i�S�j�c���\�l���@���Ɖ@�����哿
�@�@�i�T�j���@�@�����/���M�\�i1680�j��/�����
�@�@�i�U�j���̉@�v�h���x/���v�@��������
�@�@�i�V�j�얳���@�@�،o�@������/���\���q�i���\�X�N�i1996�j�j
�@�@�i�W�j�얳���@�@�،o�@����@���i
�@�@�i�X�j�蔼��
�@�@�i�P�O�j���ǂł����s���B
�@�@�i�P�P�j���ʁF�얳���@�@�،o�@�����i�ԉ��j�A���ʂɍ��������邪�ʐ^���Ȃ��̂ŕs��
�@�@�i�P�Q�j�ʐ^�Ȃ�
�@�@�i�P�R�j���@�@����@���E���z灵��/����ڎ��畔������/���������i�����O��l�S��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i灵����A���̕����͕���Ȃ��������悩�H�j
�@�@�i�P�S�j�ʐ^�Ȃ��ŕs��
�@�@�i�P�T�j�ʐ^�Ȃ��ŕs��
�@�����ʑ���ՂP�@�@�@�@�@�����ʑ���ՂQ�@�@�@�@�@�����ʑ���ՂR�@�@�@�@�@�����ʑ���ՂS
�@�����ʑ���ՂT�@�@�@�@�@�����ʑ���ՂU
�@�ʑ���Ք����{�@�@�@�@�@�ʑ���Փ��c�_
��������Ց�����ʑ��i��c�R�j�������@�㊪1037
�@���u��n1336�Ԓn�ɂ���B��ʑ��隬�̖k���ɂ���A�ʏ́h�v�Q�̍�h����Q���������B
�@�����̎��@�䒠�̋L�^�ɂ��ƁA�@
�@�@�@��t���lj�����������S��֑���ʑ����u��n
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�@�،o�����@���@�@�@������
��A�{���@�߉ޖ���
��A�R���@�^���@�m�m�V���c��V�����N��(1368�`74)�{���@�،o���O��ڐ�t���S�O�ʃm�߁@���j�˃e�@�|�y�r��������
�@�@�@�@�@�n���A�c���R�K(1867)�O���������j�e�{���ɗ��Ď��A��������C�N�ċ�
��A�{���Ԑ��@�Ԍ��܊ԁ@���s�O�ԁ@�@�@��A�����ؐ��@�l�S���\��@�@�@��A�h�k�l���@�S�\���l(�ȉ���)
�@�Ђ̂��߁A�j����m�镶���͂Ȃ����A�ߋ����̈�߂Ɂu���R�J��Ìc���N(1387)�܌���S�@���c��l�v�Ƃ���A�{���́u������v�ɂ́u�L�؎R�������v�̍�����������B
�@���������̉E���ɂ���Γ��ɂ́u�얳���@�@�،o�@�����P�Q�剳�N(1815)�����˓��@��c�R�������v�ƍ��܂��B
����������Ɂu��֎��_��v�̋L�O�肪�����Ă���B���̎��_��͑匴�H�w�̐��w�v�z�����H�����W�܂�ŁA�L���̓Ĕ_�Ǝu�g�����q��̎w�����Z�p�w���݂̂Ȃ炸�A�i�]��A�����̔��Ƌ����w���ȂǁA�������珺�a�����Ɏ���܂Ŋ��������B�L�O��̌����͏��a���N�ł���B
�@�Q�������̍��̔�́A�n���u��n����Ѝu���_�����������J��u��Ëv�V(�单�V)�v�ł���B�u���،����@���ᎋ�O���@�얳���@�@�،o�@��Ëv�V�_�@���ڊC���ʐ��̉����X�@�C�@�ڑ�@�Éi�ܐp�q(�ꔪ�ܓ�)�܌��b�q�u���@�����V�v
�@���̍u���̐_���͓J���ۂ̚��q�œ��₩�ȍs���ł������Ƃ����B
2023/10/19�B�e
�@��i��Ëv�V)�F��Ëv�V�͑单�V�A�����������ɂ���B��ɗR���f�ځB
�@�ʑ��������Q���@�@�@�@�@�ʑ���������ڔ��@�@�@�@�@�������{���E�ɗ�
��������Ց�����ʑ��i���@�R�j���F���x���@�@�㊪1038
�@�����F3765�Ԓn�ɂ���B
���F�W���̑�n�����Ɉʒu���A���ĕ����V�c�Ƃ���ꂽ���W���̐��݂̐e�Ƃ������ׂ����ÔˉƘV�E�����^�܍��q��Ɛ[���������̂��鎛�ł���B
�@�����́w���@�䒠�L�^�x�ɂ��ƁA�@
�@�@�@��t���lj�����������S��֑���ʑ������F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@���R�@�،o�����@���@�@�@���x��
��A�{���@�߉ޖ���
��A�R���@�{���n���������S��x���������㐢�Z�E���~�A���i���N(1624)�����\�O�������w��F���n�@�S���Z�E�����㌳�\�P�R�N(1700)�\�����E���������w�ړ]
��A�{���Ԑ��@�Ԍ����ԁ@���s�܊ԁ@�@�@�@��A�����ؐ��@�Z�S�O�\�ܒ@�@�@�@��A�h�k�l���@�S�l�\�l
�@���̂悤�ɋL����A
����ɗR���ɂ��Ă͓V�۔N���ɍ��o�����w���x���R���x�ɂ��ƁA���̂悤�ł���B
�@�@�@�@�@�ደ��q�j����\���
��A��̕���ʑ������F�V�c���x���R��
�@���ʌ�q�j�t�ߋ������D�V�ʃ��Ȑ\���
�@���������V�ӎ�Ҍ�̎叼���L�O��l�Ȍ�̐��@���̓���x���j�L�V�@���R���x������ʑ����V�����F�V�c���@�˖��V
�@�������t���R�����R�@�Ԍo�������j������
�@���\�\�O�N�C�����������g�\�m���@�d��@嫑R�����R��j�e�L�V�́@��̎�Ȏ̌�Ќ���̍��V���l������
�@���V���s�L�䎁�����������蓖�n�]��o�A���Ì�㊯���약���q��a��ƘV�����^�܍��q��a����\����o���ߓc���R�ѓ����V�����Z�V�V�с@�����V�x�z�j�푊���
��A��̎�l����c�n�뒬�O���]�A�V�O�l�}�����ڃj�e�q�̎d��n���j�����
��A�����ŕݔ��ꗬ�@�@�����^�܍��q��a�@�@�@��A�Ŗ���@�@�@�@�@�L��蕺�q�a�@�@�@��A�O��@�@�@�@�@�@���약���q��a
��A�S�q��_���c��m�@��x����莝�Q
�@�����i��s���������O���Ȑϗ��������v�����l�@����������L�V��L�d���j�����@�E��ƘV��������a�䍲�ΔV�ߌ�q�j�t�\���
�@�@�@�V�ۂT��(1834)�܌��\���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U������g��
�@�@�@�@�@����\��D�V��
��A���x�����Z�j�t�����V�����Y���ҎU�ݖ��V�l�@�P���Ό���j�����y�[�O��������d��i��n��،�@�˔V���
�@�@�@��D�@��
�@�@�@�V�ۂP�Q�N�N(1841)�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U������@�����q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P���q
�@�@��G�����m��
�@
�@���݂̌����͌�N�ɉ��z���ꂽ���̂ŁA�R�傾���������̖ʉe��`����B
�@�����̉E���ɑ�ړ�������B
���ꂼ��u�얳���@�@�،o�@�����@�y�r�M�m�@�����R���ДN(1806)�܌�������A�Éi�Q�ȓєN(1849)�����\������R���O�����A��@���R�v�u�얳���@�@�،o�@���R�Q�P���@���������@�@���R�v�ƍ����B
�@�E��ɂ����ړ��͓��@�ܕS�����̂��̂ŁA���i�W�N(1779)�̌����ł���B�����č����́A�u�Ȉ�@�唭�f���S�q���V�@�{��h�z������P�@���x���s�y�@���G(�ԉ�)�@���뗼�y�h���@���S�D���u���@�����E�q�哯�����q�@���ҋ��E�q��@���S�D�����q�哯�@�@�@�@���@�@�s�E�q��@���S�D��@�q��@���g���q�@���y���q��@�����E�q��v�ƂȂ�B
�@���̑�ړ��ƕ���ŁA�����̑�h�z�ł����镞���^�܍��q��̋��{��������A�u�����@�ÐM���d���m�@���ۂU�h�N��(1721)�����\�����@���m���B��ʑ����V�c�J���V�{��哖��������h�z�����^�܍��q��V��@�ז{����l���F�V�c���E�������@�����S�ݐp�q(1792)�\���ߑ����V�Җ�@�@���R���x���\�ܐ��얭�@���`(�ԉ�)�j���u���v�Ƃ���B����ƕ��Ԃ������̑�ړ��́A�����P�O�N(1813)�ɏ\���������̂Ƃ��Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B
�@���̕�n�����ɂ́A���R�̗����L�����肪����A�u���@�J�R���~�哿�@�c���Q����(1597)�܌������@��c���s�@���O�o�ʁ@�����T����(1715)�����ܓ��@�������݉@����o�ʁ@�����Q�p�C(1712)�\�ꌎ���l���@�{��@�����O�������@��q�@���ۂX�b�C�V(1724)������\�l���v�ƍ����B
2023/10/19�B�e�F
���F���x��
�@�R�剡��ڐ��F��ɂ���ʂ�A�����́u�얳���@�@�،o�@�����@�y�r�M�m�@�����R���ДN(1806)�܌�������A�Éi�Q�ȓєN(1849)�����\������R���O�����A��@���R�v
�@���F���x���R��P�@�@�@�@�@���F���x���R��Q�@�@�@�@�@���F���x���R��R
�@���F���x�������P�@�@�@�@�@���F���x�������Q�@�@�@�@�@���F���x���{��
�@���F���x����ڐ��F���ʖ��F�u�얳���@�@�،o�@�r���V�S�W�����P�i�ԉ��j�v�i�{��@���P�͕���7�i1995�j.2.27��j�ߔN�̂��̂ł���B
�@��ڐE���{���R���@�@�@�@�@���@�ܕS�������F���i�W�N(1779)�̌���
�@�����^�܍��q�募�{���F���ʖ��F�u�����@�ÐM���d���m�v�A�����ɂ��Ă͏�ɉ������B
�@�����畔���A�����F���ʖ��F�u�얳���@�@�،o�@�����畔�@���A�V�����v�ł���A�����P�O�N(1813)�ɏ\���������̌����ł��낤�B
�@���x��������@�@�@�@�@���x�����掏�@�@�@�@�@���x����㋌���P�@�@�@�@�@���x����㋌���Q
�@���x���@���_�@�@�@�@�@���x���@���_���{��
�@�@��͑y�ܘY�Ƃ����`���ł���A��������S���Ñ��i���q�˗́j�̔_���i�x�_�j�Ƃ̋L�^���m�F����A���݂Ƃ����B
���q�˂̉Ր��ɑ��A���R�ƌ��i���邢�͉ƌp�j�ɒ��i�A�y�ܘY�v�Ȃ����Y�ƂȂ�A�j�q4�l�����߂Ƃ���Ɠ`�������B�i���i�̊m���Ȏj���͂Ȃ��Ƃ����B�j
����A���Q�N�i1752�j�y�ܘY�e�q�̕S����̔N�ł���Ƃ��āu�������Ջ��m�v�̖@����拂���A�����R�N�i1791�j�ɂ͖x�c�����ɂ�蓿���@�̉@����������B
�������ʑ��g���R�Q�q���W
�@�����P�U���i���������s����j�ƕ��c�E������ʂƂ̕���ɂ���B
���̓��W�̂���ꏊ�͋ʑ��E���v�R�E�����̂R�����ڂ���Ƃ���ŁA�������͕��c�ł���B���W���̂��̂͋ʑ��n���Ǝv����B
2023/11/29�B�e�F
�@�g���R�Q�q���W�P�F�g���R�Q�q���ƍ��ށB�w�ʂɂ́u���a�U�N�v�Ƃ���B
�@�g���R�Q�q���W�Q�F�����@����_�ЁE�E�E�ƍ��ށB
��������Ց����쓇�E���c�E��---------------------
�쓇���@�@�@�@�@���쓇�Α��������ݐ}
���쓇�R�������@�@�u���Ò��j�@�㊪�v826�`
�@����353�Ԓn�ɂ���B���Ă͓�ʑ��E����X���ɉ����Ă��������H���ύX����A���݂͌������ÁE�R�c���̖k���ƂȂ����B���@�@�ł���B
�@�����́A�����ȑO�͐_�������̂��߁A���{��_���������Ò��̖����������̕ʓ��Ƃ��ĉ^�c����A���������ɂ͏��w�Z���֑�����A�אڊe���̓o�L����ƂȂ�������������B
�@�����́w���@�䒠�x�ɂ��ƁA
�@�@��t���lj��@����������S��֑��쓇�@���V�^
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����h�сj���������@���@�@�@������
��A�{���@�\�E��䶗�
��A�R���A�J�R�n����g�]�t�A�����l�Nᡈ�(1463)�\�ꌎ�Z�����ȃe��X�A�N��l�S����N�i���A�R�����V�j�t�n���N�����s�ڈ��b�e�����ØV�m����j�R���o�A�����m�R�����쓇�R�g�H�t�����g���̃X�B�̃j�ÐՃg�X�����A���J�R�m�����N���m�~����B
��A�{���Ԑ��@�Ԍ����Ԕ��@���s�l�Ԕ��@�@�@�@�@��A���O���@����Ԕ��@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�S���E���
��A�h�k�ˈ��@�\���(�ȉ���)
�@�Ƃ����B
�@�Q�������ɂ����ړ�(�����W�T����)�ɂ́A�u�얳���@�@�،o�@���c�ܕS�\�����@�ӓ��@�����\��ȉN�N(1829)�\�����@�g���@���R���ꐢ����(�ԉ�)�v�ƍ��܂�A�@����n�ɂ͓��������ȍ~�̕������B
�@���O�ɒ݂�ꂽ�����́A�����m�푈�̍ۂɋ��o�������A����ɂ͎��̂悤�ȍ������������B�u�V���ו��@���ƈ����@����������S�쓇���������V�@�����\��Ȗ��N(1799)�O���g���@���ߐ{���Ł@���t�@�X�莵�@�����K���@��ؐꑠ�@���H���s�_�c�Z����s���@�������M��@�{��]�ˍu���v
2023/10/19�B�e�F
�@�쓇������������ڐ��@�@�@�@�@�쓇�������{���@�@�@�@�@�쓇�������{�������@�@�@�@�@�쓇�������ɗ�
�@�����������
���쓇���@�R�@�������@�@�u���Ò��j�@�㊪�v827�`
�@���J213�Ԓn�ɂ���B
�����w�Z�Ւn����{�{�Ɏ��鋌�ʊw�H�̍����ɕ�n������A���̖k���́A���ݎR�тɂȂ��Ă��镽�n���@�������ł���Ƃ����B
�@�э���啽�R�����މB���ē��������Ƃ����邪�A�N���A���ȂǕs���ȓ_�������B
�����ɎQ�l�Ƃ��āw����S���x���炻�̋L�q��]�ڂ���B
�@�@�������B��֑��쓇���J�ɍ݂荡�k�ނ���@���`�ɞH�Ӂ@�{���͑m����Ȃ���̔V���J��@�i�\���@�ؖV�����V�𒆋����@�������ƕ��R������(�Y��)�ƞH�Ӂ@�̂���m�ƂȂ�{���ɑމB����Ɓ@�������ܔN�㌎�啗�ׂ̈ߎ�����|������Ȃā@�V��{���������ɍ����B(�������ւ̍����F�́A�吳�O�N�ꌎ��\�Z���ł���)
�@���R����A���펞��B�����쓇���J���@��������ɍ݂�Ɓ@����O�͎�Ə̂�(��Ɏ���ɍ��)�э����Ȃ�@����Õ����ɔэ��ܘY�y�іk���������n���э��F���Y������@�W������̑c�Ȃ�ނ��@����i�\��N�\���O�����Ȃđ����@�q�펞�Y������Ə̂��V���\�Z�N�\�\�ܓ����Ȃđ����@�`�֞H�Ӂ@����͐�t������ɂ��ā@�c��ȗ��{����̂��@�V���̖��N�Ɏ���_�ɋA���@�q���������B
�@���̎����ɗאڂ��ĕ�n������A�\���b�A��\�l�������̕��ƁA���̂悤�ɍ��܂ꂽ�����U�O�����قǂ̑�ړ������B���ʂɁu�얳���@�@�،o�@�@�c���@��m�@�ܕS�����v���E�Ɂu���u�L��O�畔�@�v����O�犪�v�u���i��\�h�N�V(1781)�\���\�O���@��哖�W�u���@���l��������v
�@��GoogkeMap�Ō���ƁA�Ւn�ɍs�����͕s���m�ŁA�����炭�R�тɊ҂����\������B�쐼�̔n���ω��͊m�F�ł���A��Տ��w�Z�L�O��͓����������Ɉړ]���Ă���B��������̐i���H���B���ɂȂ��Ă���B
2023/10/19�B�e
�@�����쓇�n���ω��F�삩��@�������Ɏ���҂ɔn���ω����J����B��������@�������ւ͂����ł���B
�쓇�@������
�@�@������������F�������ĉE����A�Q�T������E�w��ɕs�ڕ��E���o�E�w��Ɏ��R�Ε�W�E�Q�P�������E�Q�S�������E�P�Q�����b�E�s�ڕ��E�Γ��U���c���ł���B
�@�Q�T������@�������F�c�����ܐ�����@���吹�l/�������M�߁i1810�j��/�������ܓ�
�@�鎦�@���o����F�鎦�@���o���l/�O��������i1845�j�N/�����\�܁i�H�j���B�Ȃ��w��E�̕�͖������A�w�㍶�Ɏ��R�����邪���Ǝv����B
�@���l���ρi�H�j���@��������F���l���ρi�H�j���@������/��N�͔��ǂł���
�@�Q�P���q���@��������F�c�����ꐢ�q���@�����哿/���a���M�Ёi1770�j�N/�㌎��\���
�@�\��S�@���b����F�\��S�@���b�哿/�������i1737�j�N/�\�ܓ�����
�@�����@��������F���@�@�����@����/�勝��N���H/�����\����
�@���U���c��
�@���@500�������P�@�@�@�@�@���@500�������Q�F���ʖ����͏�ɋL�ځA���Ɍf�ڂ̒J��n����ړ��ł���B
���J��n����ړ�
�Α��������ݐ}�Ɂu��ړ��v���L�ڂ���邪�A���y�Ȃ��i�s���j�B
2023/11/20�lj��F���́u��ړ��v�͘@�������ɂ���u���@500�������v���w���B
���c���@�@�@�@�@�����c�Α��������ݐ}
���������c�@�����@�@�u���Ò��j�@�㊪�v984�`
�@����117�Ԃɂ���A�����̂قڒ��S�n�ł���B
���@�@�ŁA�����̊ϒ������̎t�ł�����h����������̗�������݁A���Z�E���܂���m�ł���B
�@�����\��N�́w���@���ג��x�ł�
�@�@��t���lj�����������S���c��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�����葺�i����h�сj���������@�@���@�@�@�@����
��A�{���@�\�E��䶗�
��A�R���@�����J�c������g�H�t�A�ב��쓇�������g���c�����t�X�A�R�g嫃������ʃj���L�����U���n���`�����ڏZ�m��`�����Z�V�҃i�������A�}�����Ð^���@�m���Ճi���V�J�l�S�\�N�O���@�@�j���@�V���惒�ȃe�����m�J�R�g�i�X�A�R�����V�j�t�����ØV�m�������ȃe���L�v�V��
��A�{���@�c�Z�ԁ@���l�ԎO�ځ@�@�@�@�@��A�ɗ��@�c�܊ԁ@���O�ԎO�ځ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�l�S�l�E�O�@���L�n����
��A���������@��F�@�@�@�@�@�߉ޓ��@�c��ԁ@�����
��A�{���߉ޕ�
�@�R���@�Y���n�����m���S�j�ʒu�V�ېV�O���S���_�������Z�V�J�A����`���Ӄ��ȃe���_����n���Г��j�J���V�A���������ʃc�����s���Z�A�T�`�߉ރm��냒���u�V���j�߉ޓ��g���q�A�����C�U���G�ۑ��d��@�@�@�����@�@���V
��A���������@�@���V
��A���O���L�n�@�@�@�k�n���ʎ����������@���c���m���n������S�Z�E�~�E�l�K�Z�Ё@�@�@�R�є��ʁ@�@���V�@�@�@��n���ʁ@�@���V
��A�Z�E�@�@�����Z�E�����咡�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�S���\���l�@�@�@�@�@��A�����������@�E�O���\�Z��
�@�ȏ�
�@�@�@�@�E�V�ʎ撲���ᖳ�V���@�@�@�@�@�@�@�����\��N�\�ꌎ���l��
�@
�@���w�ɂ͎O���E�S�q��_��P�_�E���N��F�E�߉ޖ��E�߉�湼�ϑ��E�������̏��������u����A����Ƃ��āu�a�����ŕs�V�s���v�Ə����ꂽ���@��l�^�M�B���_�䏊�l�^�M�B�ћ햋�B�u�얳���@�@�،o�얳�O�\�Ԑ_�q��@�����~���҉���_�ʁ@�x�O���̌����ʐ_�́@�����\�l���N�N(1817)����v�ƋL���ꂽ�O�\�Ԑ_��䶗�������B�k���͒��a���R�O�����قǂŁA�u���v���(1862)���v�R�؉������q�v�̕�����������B
�@�ߋ����ɂ͊����l�N(1463)�ȗ��̗��Z�E�����L����Ă���ق��A������N(1812)�̉Ќ�A�{���E�ɗ��̍Č��ɓw�͂����h�ƈꓯ�̗l�q���A�����ɋL�^����Ă���B
�����̐Γ��E�Δ�
�@�R�卶��ɎO�\�Ԑ_�̏���������B
�@�،o����삷��O�\�̐_�X���J����̂ł��邪�A�����ɂ͐~�q�ɓ������ꑸ�����u����Ă���B
�@���̑O�ɓ��̔肪����A�u�얳�������F�@�q�k�_���P��@������\��N���\�܌��\�ܓ����V�@���F�䒉���q�v�A
�u��\�O��匎�V�����u�v����l�������A�@���u�v����\�������A�@�r���q��@�a�g�@�^���q�@�����q�@�V�ۋ�N���(�ꔪ�O��)�l�����с@������\�Z�Nᡖ��܌��Č��V�@�����q�@�����q��@�����q��v�A�����đ�Ɂu�F��v���q�@�ɓ����g�@���厡�Y�@���R�O���q��@�F��@�O�Y�@�z����Y�@���R�����@���R�����q���������@�������q�偡�������@���V�E�q��@�F�䍑���Y�@���R�����@���R�s���Y�@�z��d���q�@�����O�Y�v�Ƃ��ꂼ�ꍏ�܂��B
�@�R��O����ɂ͕����\��N(1829)�����̑�ړ�������A���̍����ɂ����⸈͊������N(1667)�̂��̂ł���B
�@�R������������E��ɂ́A�����\��N�Ɍ��Ă�ꂽ��t�@���̔肪����B
�@�����ɕ���ŗ��Z�E�̕�����邪�A�ꂫ��傫���Γ��Ɂu�吳��N�O����\����v�@���@�@�a���h��@��@�c�S�\�N�䉓���L�O�g�V�e���t�V�艄���R��l�\��k�@�q�ϒ�������V�@�ێ����a�ܔN�\�����C��V��@�����z��d���q������w���肪���╧�̓��ɖ@���̌����₯���i���P���x(��������)�v�ƍ��܂�Ă���B����͓��R�l�\�ꐢ�a�J�ϒ�t�̋��{�̂��߂Ɍ��Ă����̂ł���B
�@�ϒ��́A������\�N�ɑ����̉z��d���q�Ƃɐ��܂�āu���v�Ɩ��t�����A�̂��k���a�J�D���Y�ɉł������A���I�푈�ɏo�������v���펀�������Ƃ���A���̕������߂ɔ��𗎂��āA���@�@�̖�Վ��ŋ��s�s���_�̒n�ɂ�����(���݂͎��ꌧ�ߍ]�����s)�������ɓ���A�@�啚���{�判�e���̉������h��̂��ƂŏC�Ƃ��d�ˁA���ɂ͐��n�̖@�����Z�E�ƂȂ����l�ł���B
��n�F
�@��n�͖@���������500���قǗ��ꂽ���A���N229�Ԓn�̂P�ɂ���B�쓇�Ɍ������ŁA��������{�{�E�R�q�֒ʂ���ߓ����������B
�@���̕ӂ͋ߗׂɖ�������ŁA���ł������̒��̖��邢�쉀�ł��邪�A�Â��͎R�тɈ͂܂ꒋ�Ȃ��Â���n�ł������B
�@�鑐��������ق̈Â�����ʂ蔲����ƁA�c�̒��Ԃ𗬂���ɉ˂���ꂽ��{�̊ۖ؋��̂Ƃ���ɏo��B���܂��ܖ铹�ɂȂ����l�B���A�̊ԉA��Ɍ����B�ꂷ��V��̔����������ƌ��Ⴆ�A����}�����܂�ɁA�x�X��ɗ������Ƃ����B
�@���������b���������̉��k�ƂȂ��āA����P���̖؋��ɉ˂��ւ���ꂽ�吳����܂ő������Ƃ������Ƃł���B
�@�������ԐΓ��ɂ́A���\����(1688�`)����̂��̂����������A���ƏĂ���̈���ɂ��铯���J�R���搹�l�̋��{���ɂ́A�u�얳���@�@�،o���@��m�@�����]���@�����R�J����搹�l�@�����l�N��(1463)�\�ꌎ�Z���@�V�����h�N(1781)�\���\�O�������@�y�{��ߐ{�V���q��@�z��d���q�@�����u���v�ƍ��܂��B
�@�܂������ɂ́A���c�̏W���ɂƂ��ĖY��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A������N(1812)������\�����̑�Ђɂ���Ď���l�̗c���̕悪����A�u���@����d���v�u���@���݉d���v�Ƃ��ꂼ��ɍ��܂��B
�@���̑�Ђɂ��āA���p�����ØV�̒k�b���̘^����ƁA�u���̒��������肩��o���́A�܂���̊����ɐ����A�~�̊��������������Ɏ��X�ƔR���Ђ낪��A���̐l�B�������������́A�ƂĂ���ɕ����Ȃ��ΐ��ɂȂ��Ă����B�҈Ђ��ӂ邤�̒��ɓ��g���ĂԐ��A�~�������߂鐺�A����͂܂��ɒn���G���̂��̂ł���B
�@���̎������܂ǂ������̐l�B�̍����̒��ŁA���܂��o�������l�̏������������B�Ƃ��ׂ蓯�m�ŁA�ӂ���V�ђ��Ԃł�������l�́A�݂��Ɏ���Ƃ肠���đ��̂����̒�ɓ��������A�����ɂ������܂��̎肪�����ė����̂ŁA�̕��������Ė{���̉��̉��ɐg���B�����B���������̉��͓�l��������܂܂̉����ɔR������A���ɖ{�������ꗎ���Ă��܂����B
�@�n���̂悤�ȂЂƖ邪�����A���̏ĐՂ����l�̖��c�ȏĎ��̂��T���o���ꂽ�B�g�������������Ȃ����肳�܂ł��������A��l�̕�e�B�́A�Ă������ꂽ��[�ɂ킸���Ɏc���������̎Ȃ��A�����ŐD���Ďq���ɒ������ȕ��ł���ƌ������A�܂Ȃ���Ɉ�����Ă������v�Ƃ������Ƃł���B
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a56�N�@���
�@�����R�ƍ����B���茰�������B
�J�R�͖��@�@����B��ςł͊J�R���@�@����Ƃ���B
2023/11/29�B�e�F
�@��O��ڐΐ����F�얳���@�@�،o�@���h���@�Ƃ���B�@�@�@�@�@�R��O��ڐΔN�I�F�����\��N(1829)�Ƃ���B
�@�R��O��⸈P�@�@�@�@�@�R��O��⸈Q�F��ڈꖜ�����A/�������N(1667)/���c���^����
�@���c�@�����R���@�@�@�@�@���c�@�����{���@�@�@�@�@���c�@�����ɗ�
�@�@�����O�\�Ԑ_���@�@�@�@�@��\�O��匎�V���Δ�P�F���ʁ@�@�@�@�@��\�O��匎�V���Δ�Q�F����
�@�������F�Δ��F�w�Ǔǂ߂Ȃ����������F�Δ�ł��낤�B
�@�@���������P�@�@�@�@�@�@���������Q�F�����Ǝv������A�����ǂ߂��͂����肵�Ȃ��B
�@���@�@�a���h���P�@�@�@�@�@���@�@�a���h���Q�F���h��@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����h��͔��O���n�������i���앟�n�����j�Ȃǂɏ�������B
�@�@�������E�Γ����F��ړ��╶���N���̕��Ȃǂ�����B
�@��t�@������Γ��F���ʁF�얳���@�@�،o�@��t�@������A�����P�X�N�����Ƃ����B
�@��ڐ��̂P�F�����F���ʂ͓얳���@�@�،o�@�@�E�A��ɉ����R/�@�����@�ƍ��ނ̂ŁA�Â�������ł��낤���B�N�I�͖��m�F�B
�@��ڐ��̂Q�F�����F�얳���@�@�،o�@�O�E����/�����R/�@�����@�Ƃ���̂ł�����Â�������ł��낤���B�N�I�͖��m�F�B
�Ȃ��A��n�͖@���������500���قǗ��ꂽ���A���N229�Ԓn�̂P�ɂ���A�u�J�R���搹�l�̋��{���v��Õ������Ƃ̂��Ƃł��邪�A�����B
�����c�H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�@�u���Ò��j�@�㊪�v988�`
�@��ړ�
�@���{��465�Ԓn��2�̌Õ��̏�ɓ����Ă��āA�����̐l�B�́u�o�ˁv�ƌĂԁB
�@�@�����́A���Đ^���@�ł��������オ����A�܂��s��s�{�h�ɑ������Ƃ��������āA���̒˂̎��ӂɓ��h�̐Γ��ꂪ�������Ƃ����Ă���B�����ꂩ�̏@�h�̌o����[�߂Ē˂�z�������Ƃ���o�˂ƌĂԂ̂ł��낤�B
�@�����̎���͑����L�n�ł��������A�̂������������āA���݂͎��L�n�ɂȂ�B
�@�Δ�ɂ͑�ڂƁu�\�O���u���@���c�����F�䎁�z�쎁���R���@����Ѝ�(1758)�����\�O���@�������ɓ����v�ƍ��܂�A�������ɂ͑�ڂƁu�얳�{�t�v���߉ށ@�얳�{����s���@�@������N���q�ߗ��ݏ��X�펀�썰�@�����\��N�\���v����O���ܐ犪���A��啽�R�@�@�@���R�����q��@���R�����q�@�F�䏯���q�@�z��s�Y���q�@���R�����@���R�O���q��v�Ƃ���B
�@�i���ȉ��ȗ��j
���Q��̑�ړ��͔����ł����i2023/11/29�j�A�����̂܂܁B
�⑺�@�@�@�@�@�@����Α��������ݐ}
���u�[�����@��j�vp.163�@���
�⑺���F�⑺�ɂ͍⑺�����������Ƃ����A�@���͈ȉ����m����B
�@�ʖ��@���́i�J��j�A�{�A�@��ꟁA���u�@���B�A�{���@�����A�q���@���^�A��暉@�����A�~���@����
�Ȃ��A�⑺���̈ʒu�ɂ��ẮA��F���ł���B
�������▭�����@�@�u���Ò��j�@�㊪�v948�`
�@���J373�Ԓn�̈�ɂ�����@�@�̎��@�ŁA�h�Ƃ͂Q�V���]�ł���B
�����P�Q�N�́w�Ў����ג��x�ł́A
�@�@�@����������S�⑺���T�N
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�����葺�i����h�сj���������@���@�@�@������
��A�{���@�\�E��䶗�
��A�R���@�������̐^���@�m���Ճi���V�J�@�������N(1476)�m�����@�@�j���@�V�@�������ȃe�����m�J�c�g�X�@�����\�O�N�h�N(1481)�܌��ܓ����ȃe��X�@�V�ۏ\�N(1839)�m���j�����@�Y���Ѓj�냊�̃j�Ï��Y�퓙�Ď��V�R���g�̃X�x�L���m�i�V�@�˃e�{���m�L�^�����V�L�X���m�~�@�n���N�����s��
��A�{���@�Ԍ��Z�ԁ@���s�l�Ԕ�
��A���������@��F�@�@�����@�@�����
�@�q�����@�{���@�g�˓V���@�R���@�V���n����j�����S�q��\�������i�����q����m��샒�i�X���_�m�@�N�g�̃V��X�j���l�m�A�˃X�����i���@�����ȃe�×������q�����g���q�����݃����j�������ۑ��v�V������
��A���������@���V
��A���O���L�n�@���ʈ딽�㐤�E�l���⑺�y���@�@�R�є��ʁ@���V�@��n���ʁ@���V
��A�Z�E�@�E�����Z�j�t�������S�����葺�������Z�E���쏇�v�@�@�@�@�@��A�h�k�l����E��l
��A�����������E�O���\�l���l�\�Ԍ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�V�ʎ撲���ᖳ�V���@�@�@�����\��N�\�ꌎ���l��
�@�Ƃ��邪�A�����ŌÂ̎��@�Ƃ̌��`������B
�@�܂��A�w��֑����y���x�́u���Ãn�^���@�i���V�g�]�t�A�����k���j�����A���A�m�����m�J��j�V�e�R�������m�ʓ��E�^���A�㐢���`�l���߉ޑ������u�X�A�^�c�m��i���g�C�t�v���̂悤�ɋL���Ă���B
�@�㐢���`�̂Ƃ��A�ꎞ�͕s��s�{�h�ɂ����������A�x�d�Ȃ�e���Ɋ������ꂸ�]�������B
�����Ɏ���܂Œ�����}��_�̕ʓ��ł��������Ƃ́A��L�̂Ƃ���ł���B
�Ȃ��A����Ƃ��Ĉ��u����Ă����Ƃ����Ă���^�c��̎߉ޑ��́A���݂͌�����Ȃ��B
�@�{�����ɂ���╏��Ɂu����������S���⑺�R���������l���k�@�F�G��@���y�h����������P�@�����Z�Ȗ���(1809)�\�g�C�v�Ƃ���A���������̉E���ɂ����ڔ�ɂ́u�����O�E�F����L�����O��������q�@�ܕS�����וӓ��@��\�����@���i��M�q��(1780)���@�y���u����c���{������v�ƍ��܂�Ă���B
�@�܂��A�����ɂ����̈ꖇ�ɁA���a�O�N(1354)�̔N���������邱�Ƃ͑O�L�i���ȗ��j�̂Ƃ���ł��邪�A����ɂ���Ă��A�����R���̈�[�����������m���Ƃ����悤�B
������
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a56�N�@���
�����R�ƍ����A���茰�������B
��ςɂ͊J�R�����R�����Ƃ���B
�@�����j�E������
2023/11/29�B�e�F
�@���݁A���F��F�A��A����̌Õ���c���݂̂ŁA���鐊������B
�Ȃ��A�����E�ɂ����ڔ�͌����Ƃ��Ă��邩���m��Ȃ��B
�@�▭�������F���ǂł����A��q�́u���a�O�N(1354)�̔N����������v�肩�ǂ����͕s���B
�@�▭�����{��
�@�▭�����Õ�P�@�@�@�@�@�▭�����Õ�Q�F���͖w�Ǔǂ߂Ȃ����A�����炭�M�k�̕��Ǝv����B
�������▭�s���@�@�u���Ò��j�@�㊪�v950�`
�@���������Z�Z�Z�Ԓn�̈�ɂ���B���@�@�̎��@�ŁA�h�Ƃ͓��]�ł���B
�������A�w�Ў����ג��x�ɂ́A
�@�@�@�@����������S�⑺��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�����葺�i����h�сj���������@���@�@�@���s��
��A�{���@�\�E��䶗�
��A�R���@�����J�R���������G�g�H�t�����\�Z�N�b�C(��l���l)���ȃe��X���m���m�������o���V�e�Éi�ܔN(�ꔪ�ܓ�)�j�����Ѓj�냊���F�Ď��V�̃j�R�����V�@�˃e�{���m�L�^���q�k���j�@�V����(1532�`54)�M�ғ����m���D���j���a��N(1623)�g���D�A���g�L�ڃA���m�~
��A�{���@�Ԍ��O�ԎO�ځ@���s�܊ԎO�ځ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�ܕS�Z�E�l��
��A���������@��F�@�@�@�@�߉ޓ��@�Ԍ���ԁ@���s��ԎO�ځ@�@�@�@�{���@�߉ޕ�
�@�@�R���@�}�����m���n�J���ȗ��m�����L�V�҃i�������@�����m�V�y�g嫃����R���m���҃i�V�@���߉ޓ��g���t���m�~�@��X�m�Z�m�h�k�m�]�̓����q�C�U�����w���j�ۑ��X�g嫃��@�ߔN�j���������m�@�|�j�����V�@���j�p���m�G�胒���V�V�J�j�ʃj��N�����@���Z�����@�R���g嫃������m�Z�E�^���ҊY���ی�m�C��痃t�Z�X���n�A���w�J���X�@�M���m���n�����Ѓm�ۃj�����e����ƃ��i�N�R�����V�j�t�����m���`�j�]�e���L�v�V��
��A�����������V�@
��A���O���L�n�@�@�k�n���ʁ@�딽�됤����@�⑺�m���@�@�@�R�є��ʁ@���V�@�@�@��n���ʁ@���V
��A�h�k�l���@���\�Z�l�@�@�@�@��A�����������E�O���E�l���l�E�Ԍځ@�ȏ�
�@�ƋL����A�w��֑����y���x�ɂ�
�u�����\�Z�N(1484)�����m�n���j�V�e�A�m���G�J��X�A���Ð^���@�i���v�ƋL�^����Ă���B
�@�R���̕����ɂ�����悤�ɁA�Ђ̂��ߏ��L�^�͎����A���̏ڍׂ�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A��؎l�Y���q�Ƃɓ`����������̙�䶗��Ɂu�V�ۏ\�N(1839)�{���ċ��v�ƋL�����B
�@�{�����ɂ͖��a���N(1771)�N���̓���Ə��R���ォ��O��܂ł̈ʔv������A�����̐Γ��Ăɂ́u���Ĉ��@�ӓ����{�@�@�������@���c���F�ܕS�����@������h�{�@����N���@�ێ��V�����h�N(�ꎵ����)�㌎�v�ƍ��܂�A��ڔ�ɂ́u���@���F���@�ܕS������@�{�喭���R�h���������@���i�\�h�N��(1781)�\���\�O�������v�Ƃ���B
�@���̖��s���ł́A���ď@���s���̈�Ƃ��āA�q�������ɂ�鎟�̂悤�ȏK�킵���������Ƃ����B����́A���N����l�������̟�ɍs��ꂽ���̂ŁA�����̌܍���\�O���炢�܂ł̓������A�e���ƌĂԔN���̒j�q���w���҂ɂ��āA�O���̎����Ɏ��̂悤�Ț��q���t�����тȂ���e�ƁX�����A�Ăⓤ�̊�̂���B
�@�@�����Ⴉ�̕Ď�Ă���A���Â�����A���ɂ���A�A�g����`���b�|���݂�����B
�@�W�߂��Ă⏬������K�����Ɏ����A��ƁA��e�B���Ԕт�Ò������A�ʂɉƁX���玝��������藿�������킹�āA��q���ꂵ��ɏZ�E�̖@�b���Ȃ�������߂����̂ł���B
�@�����ē����́A�����̎Q�w�l�ɂ͍���W�߂����ō��������������o����A�q���B�́A�߉ޑ����悹���`�����H�ŏ���t�����Ƃ����Ē��H�����ނƁA�Z�E��擪�ɗ`�������ōs���g�݁A�����獻�q���ւƐi�ށB�����ŗ`�̎��͂����������H�ɉ��t�����A���ɕ�܂ꂽ�`�����������܂��ƁA�̕t����������͎��X�ƐU�����Ƃ���Ă����B�����čŌ�ɁA���ɂ���ď�߂�ꂽ�߉ޑ������̑��������킵�A�₪�Ă��̑������ɋA���Ă��̍s���͏I���B
�@�����ŁA���W���̕����ɂ��Ăӂ�Ԃ��Ă݂�ƁA�����̐V�������`�̂��̂������āA���̂قƂ�ǂ����@�@�ł���B
�@�c���@���O���ܔN(1282)�r��{�厛�ɓ���̌�A�����E���N�E�����E�����E�����E�����̘Z�l�̍��킪�g���R�ɋv���������āA�V���̖@��̑��̋������z���čL���z�����ꂽ���@�@�́A���̊ԁA�{瑈�v�h�A�{瑏���h�ɕ�����A��ɏ@�h���̕��������������A������N�ɖ{瑈�v�h�͓��@�@�Ƒ��̂��邱�ƂɂȂ�A���{�R��g���R�v�����Ƃ��A�l��{�R��r��{�厛�E���s�������E�{�����E���R�@�،o���ƒ�߂��B
�@���̂��Ƃ���A���s���͖{瑈�v�h����o�������̋�����钆�R�@�،o���̖嗬�ł���A�������́A�����{瑈�v�h����o�����ւ̋��`��M��r��{�厛�̕����Ƃ�����B
�@�܂��A���ɂQ�Q���قǂ̕s��s�{�h������B��������@���n�c�Ƃ�����@�@�̈�h�ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A���Î��ӂɂ͑����̐M�҂�����A���s�E�����̗���������ɓ���������������������A�������e�����ē]�������Ƃ����B
�@���ݓ��W���ɂ��̔h�̎��@�͂Ȃ��A�Q�Q���̒h�k�����́A��ʑ��i�ʕ�R�j���؎������̕�Ƃ��Ă���B
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a56�N�@���
�����R�ƍ����B���茰�������B
��ςɂ͊J�R�����@���G�Ƃ���B
�@�����j�E���s��
2023/11/29�B�e�F
�@���s���̈ȑO�̎p�͕�����Ȃ����A�ߔN�A������E�{���E�ɗ��Ȃǂ��V������A���揊���������ꂽ�悤�ł���B
�@�▭�s���������@�@�@�@�@�▭�s���{��
�@�▭�s���ɗ��F�ɗ��͏�L�̒��j�E���s���ƍ������A����̌����Ǝv����B�ł���Ȃ�Όɗ��͉����ł��낤�B
�@�▭�s�����揊�@�@�@�@�@�▭�s�����G��l����F�J����@���G��l�Ƃ���B
��������E�H�T�̏��K�E�{�Ȃ�
�����c�_
�@������P�J511�Ԓn�ɂ���B����Ђ̑O�̓��H��k�w100���قǍs���ƁA���̍����ɐΑ��̏��{�����悻��Z�`�O�Z�قǁA�܂�d�Ȃ�悤�ɕ���ł���B�u���i�{�@�⑺�R�莁��啐�E��@���ۏ\�Ȗ��N(1725)�\�ꌎ�\�ܓ��v�Ƃ�����̂̂ق��A�V�ہE�Éi�Ȃǂ̔N�����킸���ɒf�ЂɌ����邾���ł���B
2023/11/29�B�e�G
�@������P�J�̓��c�_�P�@�@�@�@�@������P�J�̓��c�_�Q
�Ȃ��A���̓��c�_�̐��k�̒J�Ɂu�K�P�����g�E��n�v������B
�@�i���݁A�u�K�P�����g�E��n�v�͓P������A���Ɍf�ڂ́u�����n�v�Ɉړ]�����B�j
���̓��c�_���琼�k�����ɒJ�����铹������A10��m�~�����Ƃ���Ɂu���j�v�ʼn]���u�K�P�����g�E��n�v������͂��ł���B
�������A��n�ɉ��铹�͍r��A�b���T�����A��n�炵�����̂͑S����������Ȃ��B
�@�^�悭�A���߂ō�ƒ��̐l�������̂ŕ��������B
�u���c�_�̂���ꏊ���琼�����ɒJ���������Ƃ���ɕ�n������͂������E�E�E�v�Ƃ̖⍇���ɁA�u�ȑO�ɂ͕�n�����������A���͂����Ȃ��B�ړ]��͒m��Ȃ��E�E�A�����̓��͔p���ƂȂ�A�r��A�댯������s���Ȃ������ǂ��E�E�E�v�Ƃ̕ԓ��ł������B
�@���̌�A������^�悭�A�s��s�{�̐M�k�̕��ɏo��A���̕��̌��ł́A
�w�u�K�P�����g�E��n�v�͍�����S�A�T�N�O�i�m�M�͂Ȃ��l�q�j�Ɂu�����n�v�Ɉړ]�����A���n�ɂ͕�͈�Ȃ��A��n�ɏ���Βi�����������A���͖��������E�E�E�A�ړ]��́u�����n�v�ł́A����30�����قǂ̃R���N���[�g���̊�d�����A���̏�ɕ��𐮑R�ƕ��ׂĂ����悪���邪�A���ꂪ�u�K�P�����g�E��n�v�ɂ��������ł���B�E�E�E�x
�Ƃ̂�����������A�u�K�P�����g�E�v���������邱�Ƃ��ł����B
���n���ω��E���W
�@���c�_���炳��ɖk�w100���قǂ̏��ŁA���o�ˌO�l�Ԓn�̖T�ł���B�X���Ǖ��n�_�ɂȂ��Ă���B�u�n���ϐ����v�ƍ��܂ꂽ���{�𒆐S�Ɉ�Z�قǂ̒f�Ђ������Ă��邪�A��[�̎������̓ǂݎ�����̂͂Ȃ������B
�@�������班�����ꂽ�Ƃ���ɐ̓��W�������āA����ɂ́u�����ܔN��(1822)�\�ꌎ�@�����C���E���q�����@����R�q���捲�����@�m�ǐ_�����������쓹�@�э����R��蔪���s�ꓹ�v�ƍ��܂�Ă���B
�@�@�i���ȉ��̘H�T�̏��K�E�{�Ȃǂ͏ȗ��j
2023/11/29�B�e�F
���̕���͍����ł����̖����A���Ȃ𔖈Â��]�ˊ��̕��͋C���c���ꏊ�ł���B
�@��n���ω��E���W�F�������ĉE���n���ω��Ǝv���邪�m�͂Ȃ��B�@�@�@�@�@��E�n���ω��F�����S���ǂ߂��m�͂Ȃ��B
�@���W�E����R�q���捲�����@�@�@�@�@���W�E�m�ǐ_�����������쓹
��������̕�n�@�u���Ò��j�@�㊪�v953�`
�@��n�́A������499�A��501�Ԓn�A���K�P�����g�E468�Ԓn�̂Q�A��469�Ԓn�̂Q�A���@�����̌v�܃J���ɂ���B
�@�Â��N���̍��܂ꂽ��������A���̏W���ł͌��\(1988�`)�ȑO�̕�͒������Ƃ����邪�A�����ɂ͌��a��N(1623)�A���i�l�N(1627)�ȂǁA����������B
�@���K�P�����g�E�F�������̏��ЂŁu���������v�Ƃ̕\�L�ɐڂ����ƋL�����邪�A���n�ł̗��n���l������Ɓu�R�����v�̈ӂł���Ƃ��v����B
����K�P�����g�E��n�F
�@���̖�������Ζʒ����ɂ����āA�܂���ɖ���������t�ɓ����Ă��邳�܂́A��߂�ꂽ���n�̊������������[������B
�����Ɍ����̔�ɁA�s��s�{�h�ɐ[���Ȃ���̂���Z�l�̑m�������L����Ă��邪�A���̈�l��l�ɂ��Ă̊T�v�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�~���@���Ƒ哿�@���̋L�^�ɂ́u�����v�ƁB����l�ł���A��ʑ��ɕs��s�{�h�̈����J�����l�B���ێl�N�\�ꌎ�ܓ���B
�@�@���~���@���Ƃ͍⑺���@���Ƃ��ċ�������B�i�u�[�����@��j�v�j
�@�����@���^�哿�@�т̖@�����\�ܐ��B�V�����N�\����\�l����B��ʑ��ɕ悠��B
�@玆�{�@����哿�@����B���ƌĂ�A�����̈��ɏZ�݊��ێO�N�ܓ���B
�@���^�@�����哿�@���ɏZ�ށB������N��\������B
�@�h�{�@����哿�@�����̎Y�œ�����ɏZ�ށB�����Z�N�\�ꌎ�\�O���S���B
�@�^�h�@�����o�ʁ@�o���E�Z���Ƃ��ɕs���B�w�����@��L�^�x�Ɂu�\�ꌎ�\�ܓ������S���v�Ƃ���A����l���B
����E�����n�F
�@�K�P�����g�E��n�Ƃ͑ΏۓI�ɁA�u�ː�[�Ɉʒu�������邢�Ƃ���ŁA���������炱�̒n�ֈڂ������̂Ƃ����Ă���B
�@�召�̌Õ���̒˂������ɂ����āA�s��s�{�h���e�����ꂽ�Ƃ��A���h�̕�߂Ēˏ�ɐ���y�������̂ł���Ƃ������A�܂��A�ߔN�ɂȂ��Ē˂�z�������̂�����B���̒˂̈�Ɏ��R�`�̐Β������Ă��Ă��āA�u��l�ˁ@���a��\��N�\���@��؍K�l�Y���V�v�ƍ��܂�Ă���B
�@�����̒˂̏�ɂ́A�Γ������Ă��Ă��邪�A���̂����̌��\�\�Z�N(1703)�̑�ڔ�͂قڊ��S�Ȍ`�Ŏc��A�u����ڈ�畔���ف@���\�\�Zᡖ��\���\�O���@���@�E�����@���s�\�]�l�@�������⑺�@�y��V�E�q��@�ז쏯��Y�@�z�쒷���q�@��؎u���q�@���R���ܘY�@�ē��앺�q�@�y�씼���@�x�R�^���Y�@���������q�@���V�r�V���@��ؐr�ܘY�@���R�O�\�Y�@�R�葷���Y�@�R��@��@�����Ér�v�ƍ��܂�Ă���A�f�Ђ̂��̂Ɂu��ڎ��ꖜ���@�����O�N(1738)�v�u�����܍M�\�V(1740)�v�ȂǂƓǂݎ�����̂��������B
�@���̕�n�̐����ɂ��铹�H��������Ƃ̋��E�ƂȂ��Ă��邪�A�������ɂ���˂́A�����̍��A���R���Ƃ̋��E�����ɏ��i�����⑺�ɑ��āA�|����Ȃ���������̑��l�B���A���ɂ��Ē˂�z�������̂ł���Ƃ����B
�@�Ȃ��A���n�ߕӂ̔�����y��Ђ��o�y���邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃł���B
2023/11/29�B�e�F
�����n�F�˂������ɂ���Ƃ������A���n�Œ����Ɏ��F�ł���˂͐�l�˂��܂߂S��ł���B�A���A�O�O�ɒT���A�����Ƃ���̂����m��Ȃ��B
�@�╽���n�E���F�Q��ʂ邪�A�������ĉE�̒˂���l�˂ł���B
��l�ˁF��l�˂̐ΕW����B
�@�╽���n�E��l�˂P�@�@�@�@�@�╽���n�E��l�˂Q�@�@�@�@�@�╽���n�E��l�˂R�@�@�@�@�@�╽���n�E��l�˂S
�˂P�F��ړ�����B
�@�╽���n�E�˂P�[�P�@�@�@�@�@�╽���n�E�˂P�[�Q
�@�╽���n�E�˂P�[�R�F���\�\�Z�N��ړ��A�����͏�ɋL�ڂ���B�@�@�@�@�@�╽���n�E�˂P�[�S�F��������l���������B
�˂Q�F��ړ�����B
�@�╽���n�E�˂Q�[�P�@�@�@�@�@�╽���n�E�˂Q�[�Q�@�@�@�@�@�╽���n�E�˂Q�[�R�F
�@�@��ړ��F���ʁF�얳���@�@�،o/���ꖜ������/������E�E�\�ꌎ�g���A�����ʂɂ͑����̕�������l���������B
�˂R
�@�╽���n�E�˂R
2023/11/29�B�e�F
����E�����n���^���K�P�����g�E�揊
�����n�Ɉړ]�����K�P�����h�E��n�̌���ł���B�S���łP�V��𐔂���B
�@���K�P�����g�E�揊�P�F���}�g��}�@�@�@�@�@���K�P�����g�E�揊�Q�F���}�ɕ������ꂵ������
�@���K�P�����g�E�揊�R�@�@�@�@�@���K�P�����g�E�揊�S
�i�P�j�M�k��P
�@�@�O�ʁF���@�@�،o�@�e灵/���\�Oᡖ��i1763�j�Z�����/��v�@�����@�P����/
�@�@�@�@�@�v�s�@���i�H�j���@/���ۏ\�ꕸ�߁i1726�j��������/�@������/���Z���q�i1756�j�\�ꌎ�\����
�@�@�@�ʐ^�͉��ɂ���B
�i�Q�j�M�k��Q
�@�@�O�ʁF���@/���ۏ\���i1727�j�l���\�ܓ�/���@�@��������/����@����������/���۔�ᡉK�i1723�j�\�������
�@�i�P�j�i�Q�j�M�k��P�E�Q�F���ꂼ��O�ʂ̖��͏�L�̂Ƃ���ł���B
�i�R�j�����s��s�{�Z��t���{��
�U���̕s��s�{��t�̖@�����L�����B�������A�����̎�����o�܂͑S��������Ȃ��B
�U���̐�t�̗����́A��Ɍf�ځu�K�P�����g�E��n�v�Ɍf�ڂ̒ʂ�ł��邪�A���߂āA�u�[�����@��j�v����̋L�������킹�Čf�ڂ���B
�@�@�i�u�[�����@��j�v����̋L���͎Α̂ŕ\�L����B�j
�@�~���@���Ƒ哿�@���̋L�^�ɂ́u�����v�ƁB����l�ł���A��ʑ��ɕs��s�{�h�̈����J�����l�B���ێl�N�\�ꌎ�ܓ���B
�@�@�@�~���@�����F���ۂS�N�i1719�j�P�P���T����A�ʑ����J��B
�@�@�@�A���A���~���@���Ƃ͍⑺���@���Ƃ��ċ�������B�i�u�[�����@��j�v�j
�@�����@���^�哿�@�т̖@�����\�ܐ��B�V�����N�\����\�l����B��ʑ��ɕ悠��B
�@�@�i��ʑ��̕�͌��݂̂Ƃ���m�F���ł��Ȃ��B�j
�@�@�@�V�����N�i1781�j�P�O���Q�S����A�ё��@�����\�ܐ��i���i�X�N/1779/�R���Q�W���j
�@玆�{�@����哿�@����B���ƌĂ�A�����̈��ɏZ�݊��ێO�N�ܓ���B
�@�@�@���ۂR�N�i1743�j�Q���T����A����B��
�@���^�@�����哿�@���ɏZ�ށB������N��\������B
�@�@�@�����Q�N�i1745�j�Q���Q�V����A����
�@�h�{�@����哿�@�����̎Y�œ�����ɏZ�ށB�����Z�N�\�ꌎ�\�O���S���B
�@�@�@�����U�N�i1794�j�P�P���P�R���A���Ö@����S���A������A�������܂�
�@�@�@�܂��A����͓V�����N�i1781�j���́i�S�j���@�E���N�E�����O��F���{���������悤�ł���B
�@�^�h�@�����o�ʁ@�o���E�Z���Ƃ��ɕs���B�w�����@��L�^�x�Ɂu�\�ꌎ�\�ܓ������S���v�Ƃ���A����l���B
�@�@�@�L���Ȃ�
�i�S�j���@�E���N�E�����O��F���{��
���@�E���N�E�����̎O��F����������`���͎̕l�������n���邢�͐����i���O�E�����j�ł悭��������`���Ǝv����B
���邢�͋��@���������O�Ɖ����Ƃ̊W���l����ƁA���O�E�����n�̕`�����ړ����ꂽ�̂����m��Ȃ��B
�@�i�S�j���@�E���N�E�����O��F���{���E�O���F
�@�@�@�O�ʁF�얳���@�@�،o/�얳�����@��/�얳�߉ޖ����/���@���F
�@�i�S�j���@�E���N�E�����O��F���{���E�����F
�@�@�@���ʁF�얳���Սs��F/�얳��s��F/���N��F
�@�i�S�j���@�E���N�E�����O��F���{���E�����F
�@�@�@���ʁF�얳��s��F/�얳�����s��F/������F
�@�i�S�j���@�E���N�E�����O��F���{���E�w���F���}�g��}
�@�@�@�w�ʁF��Ώ��������P���@�V�����h�N�N�i1781�j�㌎�N���@�h�{�@����/
�@�@�@�@�@�@�@��ܕS�Β��A�闬�z/��腕��ߒf��/��J�Ꮵ����ݐ畔
 |
�w�ʂ̖������A
�V�����N�ɘh�{�@����i1781�j����������P���A�J�Ꮵ����ݐ畔���A�Ƃ��Č����i�N���j�������̂ł��邱�Ƃ�������B
�h�{�@����哿�ɂ��ẮA��Ɍf�ڂ�
�i�R�j�����s��s�{�Z��t���{���ɋL�ڂ�����̂ŁA�Q�Ƃ���B
�܂��A�i�R�j�����s��s�{�Z��t���{���̍����ɂ��A�����l���u�Z��t���{���v�������ƍ�����B
�@�����̎Y�œ�����ɏZ�ށB�����Z�N�i1794�j�\�ꌎ�\�O���S���B����L�́i�R�j�����s��s�{�Z��t���{�����ɂ��̖����������B
�@�@�@�@����F�����U�N�i1794�j�P�P���P�R���A���Ö@����S���A������A�������܂� |
�i�T�j�M�k��R
�@�T�j�M�k��R�F�O�ʁF���@/�勝���b�q�l���\���/�@���@����灵��/�^�@�@����灵��/�������Z���\���
�i�U�j���@�E�����E�����E���q�E�������{��
�@�i�U�j���@�E�����E�����E�����E�������{���F�O��
�@�@�@�O�ʁF�얳���@�@�،o/�얳�����/�얳�߉ޘ�/�����܉���/�������@����
�����ܔN�i1715�j�ɖ{���@�����ɂ���đ������ꂽ�Ǝv���邪�A�����ŁA�����E�����E���q�E�����̋��{������������Ă����悤�ł���B
�\�ʂ͑�ڂ��������݁A�����ʂɁu�����E�����E���q�v�A�E���ʂɁu�����v�ƍ��ތ`���ŁA���炩�ɉB���Ӑ}���������Ǝv����B
�Ȃ��A�������l�Ƃ͚�ʉ@�����������Q�N�i1653�j�⁄�Ɛ�������邪�A�����ł���Ȃ�A�����͖{�y�[�W�⏼��h�т̃y�[�W�ŏq�ׂĂ���悤�ɁA���n�����[
�����n�@�؏@���R�������o������k���\���i���茰�����P�S���j�A�╔�������P�W����ŁA�g�r�Θ_�ɂ��������Ă���s��s�{�m�ł���B
�܂��A�{���@�����ɂ��Ắu�[�����@��j�v�ɂ́u���W���P�Q����A�⑺�v�Ƃ���A�܂��⑺���̖@���ip.163�j�Ƃ���Ă���B
�i�V�j�M�k��S
�@�i�V�j�M�k��S�F�O�ʁF���@/�H�����m�M�m/�^���@���q/��r���m�����M���A���ʁF�H�@�����\��ȉN�N���i�H�j�������/�^�@�����l�����N��������A���ʁF��@�Éi�ܐp�q�\�ꌎ����
�i�W�j�M�k��T
�@�O�ʁF���@/����@�����M�m/���@�����M���A���ʁF�Éi���b�ДN�����\�Z��
�@�ʐ^�͉��ɂ���B
�i�X�j�M�k��U
�@�O�ʁF���@/���@��h���K/����@���ϓ���/���x�A���ʁF�V���Z���ߎ����\�Z��/�V���Z���ߐ������
�@�i�W�j�i�X�j�M�k��T�E�U�F���ꂼ����̖��͏�L�̂Ƃ���ł���B
�i�P�O�j�M�k��V
�@�O�ʁF���@/�C��@�@�Y���m/�@�؉@���S�M���A���ʁF�����Z�Ȗ��\�ꌎ�\�O����
�@�ʐ^�͉��ɂ���B
�i�P�P�j�M�k��W
�@�O�ʁF���@/���y���@�]/�Ŏ��i�H�j�@���]�A���ʁF�����O�K�\���\����
�@�i�P�O�j�i�P�P�j�M�k��V�E�W�F���ꂼ����̖��͏�L�̂Ƃ���ł���B
�i�P�Q�j�M�k��X
�@�O�ʁF���@/�b���@�@�ƐM�m/�X��@�����M���A���ʁF�����O�\��N�\���\����/�y�썲�\�Y/����
�@�ʐ^�͉��ɂ���B
�i�P�R�j�M�k��P�O
�@�O�ʁF���@/�����@�}�x����/�X�i�@�������x
�@�i�P�Q�j�i�P�R�j�M�k��X�E�P�O�F���ꂼ����̖��͏�L�̂Ƃ���ł���B
�i�P�S�j�M�k��P�P
�@�i�P�S�j�M�k��P�P�E�O���F���@�����V�_
�@�i�P�S�j�M�k��P�P�E�����F�R糎����`/�Z�ˎ�
�@�@�c��̑��ʂ͖��m�F�B
�i�P�T�j�M�k��P�Q
�@�i�P�T�j�M�k��P�Q�F�O�ʁF���@/�S暉@����/�����@���������A���ʁF�������ȓэΌ܌����/����
�i�P�U�j�M�k��P�R
�@�i�P�U�j�M�k��P�R�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�M�@�@�@�@�@�@�@�@������N
�@�@�@�@�O�ʁF���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�@�����i�H�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���~�@�@�@�@�@�@�@�@�\�ꌎ������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ۓ�јZ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���A���A���X���Ղ��A���m�ɓǂ߂Ȃ�����������̂ŁA���m���͕ۏł��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɁA�����N�N�i1745�j�A������Ȗ��N�i1749�j�A���ۓєN�i1717�j�̊��x�Ɛ���ł���B
�i�P�V�j�M�k��P�S
�@�i�P�V�j�M�k��P�S�F�O�ʁF���@�@����灵��/���ێl�Ȉ�N/�\�ꌎ��\���
��������E�R�����������}��_(�����)���@�@�u���Ò��j�@�㊪�v943�`
�@���{�c463�Ԓn�����̒����n�ł���B�W���̂قڒ����ŁA��{�̘V�������������B
�R���E���N
�@�����\��N�́w�_�Ж��ג��x�ɂ́A
�@�@�@����������S�⑺���{��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i���}��_
�@��A�Ր_�@��R�
�@��A�R���@�i�\��Ȗ��N(1559)�����m�R�ØV�m����j���X
�@��A�{�Ё@�l�ڎl�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@��A�q�a�@�Ԍ��O�ԉ��s���
�@��A�����ؐ��@�S���\�O�@�@�@�@�@�@��A�M�k�l���@�\�O�l
�@���̂悤�ɋL����Ă��邪�A�Ȃ��R���ɂ��āw������}��_�_���R���L�x�̈ꕔ�����ĎQ�l�ɋ��������B
�@�@�@�@�@������}��_�N���L
�@�}�X����������S�k��������V���j�������J�V���t��_�m�N�����X���j�A�Ր_��R�L���n�ɜQ�����ɜQ�f���m��q�j���V�}�V�e�@�R�������Z���t���L��_�j�V�e�V�Ó��k�m�O�c�m���j�����Z���t�_�i���c�c(����)
�@���Ѓn�Γ���Y���m��_�g�V�e�@���e���V�c�m��F�������`�P�m���{�����i�\��N��(��܌܋�)�E�댎�n���V�@��R�L�������J�V�@�R���匠�����n�䖼���q��R���匠���g���Ã������q�A�R�������m�ʓ��^���V�����N�i���V�K�A�����ېV�g���j�Ѝ��������������}��_�g���X�B
�@�R���j���A�n��m�@�N�J�I���j�Q���m�׃J�@�Гa�����V�^�����ȃe�c����N(�ꔪ�Z�Z)���z���c�Z�����B���j�䑺���l�E�܌˃��Z�X�B�����Q�E��N�Гa�����i���V���A���m�撷�j���e���q�m���g�Q�d�{�����n���ʃm��V�ؔ��̃m�S�z���ȃc�e�����j���փq�����j�����B
�@���j��Ճn�N�X������E�l�������j�����s�c�Q�W�@����j���ăL��҃m���m�����g�P�n���X�A�����`�������m�Y�a�j�����`�������_�m���m�����g�Q�^���×�i��(�ȉ���)
�@�@�@���a�Z�N���㌎�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��؋��l�Y��
�@
�@���̎Ђ̖{�{�͎��ꌧ��Îs��{�ɒ���������g��ЂŁA���Ƃ͎R��Ƌߍ]�̍������ނ�����}�R�ɍ����Ă������Ƃ�����}�_�ЂƂ������A��b�R������J����Ă���͓V��@�̎��_�ƂȂ��ĎR���M�����܂�A�e�n�Ɋ������ꂽ�Ƃ����B
�@�R���L�Ɍ������Ղ̓��́u�炩�����̓��v�Ƃ����A�ǂ��̉Ƃł����H�͍�炸�ɁA���B�܂ł��������ċ����ɏW�܂�̂ł���B�����ɂ͑傫�ȕ����R��������A�邪������ƍ��}�̑��ۂ������āA��������ԎQ���ɂ͏o�X���o��B�_�O�ɎQ�q�̂̂��A�S�������Ԃ̉ƂŐH�������ɂ��A���̌�͈�������Ԃɐ���邱�ƂȂ����y�������ׂ���킯�ł���B
�@���̔�p�́A���ׂĐ_�c�̎��n�ɂ���Ęd���Ă������A�_�n���v�ɂ���Đ_�c���x���Ȃ��Ȃ�A����ƂƂ��ɂ��̍Վ������ł����B
�_��̏��ЁE�Γ�
�@�����ɂ͎��̂悤�ȏ��ЁE�Γ��Ȃǂ�������B
������
�@�Βi��o��������ɂ���ؑ��̏��F�ŁA�_���͋L����Ă��Ȃ����A�Ր_�͗_�c�ʑ��ł���B
�单�V��
�@�������ĐΑ��̏��{������A�u�얳�单�V���v����ܖ������A�@�����\��N��q(�ꔪ��)�㌎�g���b�q�u���@�@���v�ƍ��܂�Ă���B�����_�̈�_�ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ�
�O��u���i�����͐Ε�+���̊����A���̓y���ΕɂȂ��������j
�@�单�V�̂��ɂ����āu��\�O�錎�V���@�V���ו��܍����A�@�V�ۏ\�ܔN�b�C(�ꔪ�l�l)�\�ꌎ�@�@�ӎ����絒��@�{�����������q���b�l�R�蕽��@�y�씼���q�@��ؐd���v�ƍ��܂�Ă���B
�@�{�a�����̑��̉��ɂ́A�_���̕������j���������{���O����āA���̂悤�ɔ��ǂł����B�u�O���l������(1847)�㌎��g�����������E�q��v�u���i�ܐ\(1446)�㌎�g���y��܍��q��v�u���i�O��(1774)�\��\�ܓ��@�R���v
�@���̑��ɕ����\��N(1829)�ƓV�ۘZ�N(1835)�ɕ�[���ꂽ�Γ��Ă����邪�A���̓����q�A�Α���Ȃǂ͂�����������E�吳�ȍ~�̂��̂ł���B
�@�Α������́A�����O�\��N�ɓ��I����̊M���L�O�Ƃ��Č��Ă����̂ŁA�b�ɁA�o���R�l��Z�l�A���N�l��ܐl�A�^���l�O�ܐl�A���q�y��O�l�̖����A�L����Ă���B
�@�{�a���̓������ɁA��̘V�Ɍ����悤�ɁA�����m�푈��v�҂̒����肪���邪�A����͏��a��\���N�\�ꌎ�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B
�@������ƕ���ł���̂��t��(�ז쌛�i)�̔�ŁA���a�Q�X�N�X���Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B
�@�@�i���㗪�j
2023/11/29�B�e�F
�@������E�R�������@�@�@�@�@�@��R�������q�a�@�@�@�@�@��R�������{�a
�@������\�O��Γ��F��ɋL�q����B���̐��K���单�V��
�@�����单�V���F��ɋL�q����B
�@�����������F��ɋL�q����B�ؑ��̏��F�͐Α��̏��F�ɑ��ւ���Ă���Ɛ��肳���B
�@�@�������c�_�P�@�@�@�@�@�������c�_�Q
�@�{�a���w��ɓ��c�_�Ǝv������K���������邪�A�u���j�v�ɂ͐G����Ă��Ȃ��̂ŁA�����炭�u������P�J511�Ԓn�ɁA�܂�d�Ȃ�悤�ɕ���ł��铹�c�_�v�̊�����J���ꂽ���̂Ƒz������B���l�I�Ȍ����ł���B��
�@���u������P�J511�Ԓn�ɁA�܂�d�Ȃ�悤�ɕ���ł��铹�c�_�v�Ƃ́A��f�́u��������E�H�T�̏��K�E�{�Ȃǁv�ɂ���B
�������������k��------------------
�@�@�@�@�@�@�@���k���Α��������ݐ}
�@�@�@�@�@�@�@���@�����k���d�ː}
���u���Ò��j�v���n��j�ҁ����������k���@���
�����̂������@�@����145�`
�@���݂̑��Ò��́A�I�R�삨��щ��݂̐��c�ɂ���ē����ɓ���Ă���B
���̓�����n�̔����ɋ߂��ʐς��߂Ă���̂����k�����ŁA�����͂���ɘZ�̏W���ɕ������B
�v��(����)�E�k��(������)�E�_�s(���傤)�E�J��(���)�E�{(�݂�)�E���(�����Ȃ�)�ł���B
�@���̂����A�k���̓�ʑ��ɐڂ����W��������ł��邪�A�����͂��̐��������قŁA���a�Q�X�N�̒��������܂ł͏W�����������Ə�֑��ɕ�����A��������ʍl������悤�ɁA��v���H�E�͐�Ȃǂɂ���ċ敪���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���̎���Ɉ�A��˂��Ƃɏ����̑����قɂ��Ă����B
�@����́A�勝�R�N(1686)�ɂ͂��߂ďW���ƂȂ����Ƃ��A�X�̉Ƃ����ꂼ��o�g�n�̐e���A���������Ƃ���A���̂悤�ɂȂ����Ƃ����邪�A���ł��k���Ɠ�ʑ��ɂقڔ��������������Ă���B���Ȃ݂ɁA�V�ːЂ��Ґ�����钼�O(�����S�N)�ɁA�k�����ɑ����Ă����̂́A�˒J���A�{���E���E�\���E��؎������ꂼ��ꌬ���ł������B
���������k���≪�隬/�팰�����@�@����176�`
���u���Ò��j�v���n��j�ҁ����������k���@���
���≪�隬
�@�k���E�{����p�T�T�R�Ԓn�ŏW���̓����˒[�ɂ���A��i�ƍ���ɂȂ�B
�O���𐅓c�Ɉ͂܂꒭�]�Ɍb�܂ꂽ�ꏊ�ŁA�����̑�n�ɖʂ��������͖x��̓��H�ɂ���Ċu�₳��Ă���A�k���̎R�ѓ��͎Ζʂ���i�̊R�n�ƂȂ��Ă��āA�ꌩ���ėv�Q�̒n�ł���ƒm���B
�@�@�≪�隬�i�q��ʐ^����j
�@�����́A���������ɑ��@����c�Ƃ��鎵�����̒��G�͑����S���R�قɋ��ĕ��R�𐩂Ƃ������A�����肳��Ɍܑ���o���G�M���A���́E�����ƂƂ��ɉ������������̂��ċ���Ƃ����Ƃ���ł���B
���R�G�M�����R�R�����S�Ɏt�����ē��i�Ə̂��A�k��������Ă����ƂŒm����B
�@���̌�a���G���̂Ƃ��k�����ɏ]���ď��c���ɐ�������A���j���`�͎R����ɓ������A�k�����̖ŖS�ƂƂ��ɓ�j�G�M����Ē����ɋA��A��A�|��̓����̂Ă��Ƃ����B
���팰����
�@��啽�R�G���������킢�ɉ�����ĕs�݂̊ԁA�≪�̗��������Ă����̂���ؐm���q���ׂƂ����A�p��̌�m���ƂȂ��đ��������āA����ɎU�����l�X�̕�F�����Ƃ�����B
���̑�������̏�p�R�팰���ł���B
���̏팰���ɂ��Ă̋L�^�͂قƂ�nj������炸�A�ܐl�g�����Ȃǂɂ��̖�����������x�ł��邪�A�p���Ղ̈���ɗ��Z�E�̎��̂悤�ȋ��{�肪�c������B
�@�@�J�R�@����@����
�@�@�@���p�@����
�@�@�O���@�����@����
�@�@�l���@�����@���
�@�@�ܐ��@�@�s�@���h
�@�@�Z���@�i���@����
�@�@�����@�{���@�����哿�@�@���ۓ�N(1717)�l���\�ܓ�
�@�@�㐢�@�ʖ{�@�����哿�@�@������N(1749)
�@�����Ĉ��̔肪����A�����ɂ́u�O�畔�@������(1740)�@�@�ځ@��p�R�@�얳���@�@�،o�@�\�O���u���@�팰���j���@�����㐢�ʖ{�@�v�ƋL���B
�@���݂́A��Ղ̂قƂ�ǂ͑�؉Ƃ����L���A���Z�E�̈ʔv�����Ƃ��J����B
��喖��̕��R�ƂƑ�؉ƂƂ͑O�L�̂悤�ȊW�����邱�Ƃ���A���R���܌��̓��傽���͐V�N�̑����ɑ�؉Ƃ֏W�܂��Đ�c�̗���q���A�R���ɔN�n�̏��s�����Ƃ�s���̂��Ƃ��Ă������A���̂��Ƃ́A�ߔN�܂łȂ���Ă����Ƃ������Ƃł���B
�@�Ō�ɁA�w����S���x�̋��֎��̍��ɏ�����Ă��邱�Ƃ������ɓ]�ڂ��ĎQ�l�ɋ����B
�@�u�����厚�k�����{�Ɉ�Ԛ�����B�����n�ƈׂ�B�ĂŚ≪��ƞH�ӁB���R�G���̑��邽�肵���A���c������G������q�Ƌ��ɌR�ɏ]�ЁA�Ɛb�V�𗯎炵�A���㐋�ɔp���ƈׂ�B�v
2023/10/18�B�e�F
�@�����������≪�隬�Ƃ����A�쑤���Ƃɓ���ʘH���甪���Ђɓo�铹������B�����А��ɏ팰���Z�E��肪����B
�@�팰�������Q�F�������ĉE������@���{���A�J�R����Z�����{���A�������A�㐢���A�핷���@��E���s�@������A�M�k��肪�Q��A���v�@����哿��肪���ԁB
�@�팰���Z�E����G�������ĉE������@���{���A�J�R����Z�����{���A�������A�㐢���B
�@���@���F���{���F�N�I�Ȃǖ��m�F
�@�J�R����Z�����{���@�@�@�@�@�J�R�`�Z�����{�������F�����́u�J�R�@����@�����A�@���p�@����A�O���@�����@����A�l���@�����@��狁A�ܐ��@�@�s�@���h�A�Z���@�i���@�����@�����v�ƍ��݁A���Ɂu�t�͚����������i�H�j���v�A�E�Ɂu�����{���@�����t�C�v�Ƃ���B
�@�����{���@�����哿����F���ۓ�N(1717)�l���\�ܓ�
�@�㐢�ʖ{�@�����哿����F������N(1749)
�@�핷���@��E���s�@�������F�M�k��A�u�R�v�̒����̍��E�Ɂu��v�����A灬�i������E��ُ͉̈��́j�́u灵�v�Ɖ������B灵�̓ǂ݂́u���C�v�ł���A�{���́u�ˁv�����́u��v�Ǝv����B
�@���v�@����哿����F�u�������q�N�i�H�j/�X���X���v�ƍ����邪�A�ߐ��̔N���ōŏ������ł���N���͌��a�A���\�A�����A�����ł��邪�A���̌��N���q�N�ɊY������N���͏�������������ł͂Ȃ��B�]���āA�N���͕s���Ƃ��邵���Ȃ��B
��L�̌�������Z���̕��̓��A7���������Ă���̂ŁA�V�����Ƃ��v���邪�A��N�����s���ł���̂ŁA���ꂪ�V���Ƃ͒f��ł��Ȃ��B
�@�܂��A��L�́u�팰�������Q�v�̌������č��ɂS��̋��{�������ԁB
���̒��Ɂu�{���@�����哿���v�����B���̂R��͐M�k�̕��ł���B
�@�{���@�����哿����F���T��畔�{���@�����哿/���ۏ\���i1725�j���������@�Ƃ���B�����͏�Ɍf�ڂ́u�J�R����Z�����{���v�Ɂu�����{���@�����t�C�v�Ƃ����܂�Ă���B
�u�J�R����Z�����{���v�������̋t�C���Ƃ���A�V���������ł���\�����������A�W�����������ۓ�N(1717)�̎�ŁA�����̎�N�����ۏ\���i1725�j�Ƃ���A7�����W���������₵�����������ƂɂȂ�A�V�����B�����ĂW���ɏZ�E���������Ƃ������ƂłȂ���A���낪����Ȃ��B�]���āA�������V���ƒf����ł��Ȃ��B
���팰�����ɐڂ��锪����
�@�{�����В����E�⓰�@�@�@�@�@�{�����Ж{�a�P�@�@�@�@�@�{�����Ж{�a�Q
���k���������Ё@�@����194�`
�@�@���������Ò��̖�������
�������@���[���l�揊�i�������k���@�@�@�����[���l
���u���Ò��j�v���n��j�ҁ����������k���@���
�������@���[���l�揊�@�@�@�����[��l
�@�����R�P�W�U�Ԃ̂S�ɂ���B
�쒆�i�������炭���X�ǂ̕���j���猧�����ÁE�R�c����k�i���Đ_�s�W���̓����Ɏ���ƁA���̌������ւ��Ă��ʒu�ɑ����Ă���B�J�Òn���ł���B
�@������[��l�揊�F��GoogleMap�ňʒu�𐄒肵�A�摜����������̂ł���B
�@�@������n�̈ܓx�E�o�x�F35.748309680289445,140.49466304400343�@�t�߁B
�@�@���掿�������A���̖��⍂�D��̔Ȃǂ̕������ǂݎ��Ȃ��̂ŁA�����܂Ő���ł���B
�@�@�A���A���L�Ɏ����悤�ɁA��̑O�Ɂu���D��̔v�����邱�ƁA�u�ؑ������̒��Ɉ��u�v����Ă��邱�ƁA
�@�@��O�̕������u��؉Ɓv�Ɣ��f�ł��邱�ƂȂǂ���A���[�揊�Ɣ��f�������̂ł���B
�@�@�ł��邩��A�u����v�Ƃ����Ē����B
�������@���[/�����h�тW��
�@���[�̌n���ɂ��ẮA�������ɑ��ʼn����ɏ��̂�L���A�{�̚≪���ł��������R�����̌n���ɂ��ƁA���c������ƂƂ��ɚ≪�A��A��ɉƍN�̏��ق��f����ċA�_�����G�M�̒�ɔ��Y�E�q��ы`��������A���̓�q�����㐢�̓��w�ƒ�̓��[�ł���B
�@�@���u���@�@���@��Ӂv�ł͏��X���͓��w�i�@���͋j�A���i���N�i1624�j�V���Q�X���A�P�Q���͓��[�Ƃ���B
�@�@�A���A���[�̉@���A��N�͋̂܂܂ł���B���[�͓��w�̎���B
���̂��Ƃ����ē��Ƌ��ߋ����Ɂu���[���l�@�c���O�M��(1650)�Z���\����@�Z�\���Ή��@�����R�����@�@���R�\�@�Z����@��鍶�J��F�����v�Ƃ���B
�@���[�͉����@�ƍ����A�O�L�̂悤���k����̏\���o�āA�h�тƂȂ������{���̔����\���ƂȂ������A���i���N(1630�j�̐g�r�Θ_�ɕs��s�{���̑�\�Ƃ��āA�r��{�厛�̒����@����(���ƒ����h�јZ��)�ƂƂ��ɁA�g���R�v�����̓�����ɑΘ_�������ʁA�@���ł͂Ȃ������l(�ƍN)�̐�K�ɂ���ĕs��s�{�͔�Ȃ���̂ƍْ肳��A�����h�є\�����珜���ƂȂ�A���B���֗��߂̏�������B
�@�����āA���B�֗����ꂽ���[�́A���ˎ�����ѓ������̂��Ƃɂ��a���̐g�ƂȂ�B
�@�@�������h���A���O�@�̌n�����g�r�Θ_�E���i�@���A������l�B
�����������Ɠy���Y�v
�@�������A���ꍑ��X�s�ňꖜ��̂��Ă����y���͓���Y�v(���Ђ�)�́A�c����N(1604)�ɉƍN���瑽�Â���т��̕t�߂̒n�Ōܐ�̉������Ďx�z�ɋy��ł������A���̎q���d�����a���N(1622)�ɍĂьܐ���������ꂽ�Ƃ��A���Â̌ܐ�{�ɕԏサ�āA�V�����̒n�ꖜ�����ɂ����Ă��̏��̂Ƃ����B�����Ĕ˒����X�s����E�c(���킫�s)�Ɉڂ��A�E�c�˓�(��X�s�ꖜ�A�E�c�ꖜ��)���������B���̗Y�v�͓��������̖����ł���B
�@�u�����́A�E�c�Ɏ����~(�ɉꉮ�~�Ƃ�)��^���ċ��Z�������v(�w���@�@�w�S���x�E��Q�P��)�Ƃ��邩��A�����͗a���������[�̐g���A���Â̒n�ɊW���[���܂��`��ɂ�������Ƃ��납��y���Y�d�ɑ��������̂ł͂Ȃ��낤���B�����ē��[�́A���̗��Y�m�Ƃ͈قȂ鑊���̔�����悤�Ɏv����B
�@�@����镽�E�c�̎��n�����i���[�̈��j
�����[��l���
�@�O�q�̂悤�ɁA�c���O�N�Z���\����A���ߒn�ɂ����ĘZ�\���̐��U���I���A���̈�̂��^��Ŗ��������̂����̒n�ł���Ƃ����B
�@��n�ɓ���ƁA���̕��O�Ɂ@
�@�@�@�@�@����
�@�@[�����@�@�O�Z���l]���[���l�V��
�@�@�����J�×�؉ƎY�����h�\��
�@�@�z�����B��镽�E�c
�@�@�c���O�N�ИZ���\����@�Z�\���Ύ�
�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�s��s�{�h
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������@��V
�@�Ɩn�����ꂽ���D��̔�����B
���̓��͍�����Q���قǂŁA�ؑ������̒��Ɉ��u����Ă���B
���ʂɁu���@�@�،o�@���[���l�v�A�E���ʂƍ����ʂɂ͂��ꂼ��u�c���O�M�ИZ���\����v�A�u�����k�������N��(����)�v�ƍ��܂�Ă���B
�@���̔�́A�������@��ł������s��s�{�̐l�����́A���������悤�ȕ�����Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�����ɂȂ��Ă��̋ւ������ꂽ��ɁA�M��҂����̎�ɂ���Č������ꂽ���̂ł��낤�B
�@���݂��̕�n�͓��W���̗�؉Ƃ��Ǘ����Ă��邪�A�O�L�n�����̂悤�ɓ��ƂƂƂ����������A���i�\�l�N���N(1637)�㌎��\����ɓ��[�����M�ŏ�������䶗��ƈߗނ̈ꕔ�A��̂��^��ŗ������̖ؕЂō��ꂽ�ʔv������Ƃ̂��Ƃł���B
���������킫�s�����߃P��̗�؏d�Y���ɂ��╨���c����Ă���Ƃ����B
�����R�܌��}��n���̓��[��l���
�@�Ȃ��A���[�̕���������邱�Ƃ�t�L����B
���̏ꏊ�͓��{�����e�̒ʏ̕��R�܌��}��n�Ƃ����Ă���Ƃ���ŁA�����͂P���قǂ���A���ɖʂ��Č��Ă��Ă���B
�@���ʂɁu�얳���@�@�،o�@���[(�ԉ�)�v�ƍ�������Ă���݂̂ŁA�h�є\���őS���ɂ��̖���m��ꂽ���m�̂��̂Ƃ��Ă͎��f�ł���B�������C�i�̈�ꂽ��ł���B
�@����́A���[�����O�Ɏ����Ō��Ă����̂ł���Ƃ����Ă���B���邢�͗��ߒn�ł��̐��U���I��邱�Ƃ�\�����Ă̂��Ƃł��邩������Ȃ��B
�@���u���R�܌��}��n�v�̈ʒu�͊T�ˌ����������A�{��n���́u���[��l���v�͑S��������A�s���ł���B
�@���u���R�܌��}�v�͉��Ɍf�ځB
2023/10/18�B�e�F
�@���̕��͏�L�́u���Ò��j�v�ɂ���悤�ɁA�ܘ_�^��ł͂Ȃ��A�s��s�{�h�������ƂȂ��������ɂȂ��Č��Ă�ꂽ���{���ł��낤�B
����ɂ���A�̋������Ɍ������ꂽ���Ƃ͂��̌������i���M�S�̂Ȃ���P�Ƃł��낤�Ɗ�����B
�������[��l�揊
�_������⸈��F���ւ̌`�Ԃ����قł��邪�A��⸈ł��낤�A�A���A�N�̕��Ȃ̂��́A���[���ɗׂɌ������������ǂł����s���B
�_���O���Q���F�_���ɕ���Ō����A�N�̕��Ȃ̂��́A���������ǂł����s���B
���[��l�揊�ē����F���[���l�V��
�@���A�����@�@�����h�є\���A�����������R���E�q��m�q�A���i�V�N�g�r�Θ_�A��ӈ�w�g�̃V���m���A�����ѓ��a���g�i���E�c�@�j�w�k���{���X�B�c���O�N�Z���\������z���j��X�B���j�Z�\����
2023/10/20�B�e�F
�@�������[��l�揊�R�@�@�@�@�@���[��l���E��⸈�
�@���[��l���S�@�@�@�@�@���[��l���T�@�@�@�@�@���[��l���U�F���[���l
�@���[��l���V�F���ʁ@�@�@�@�@���[��l���W�F����
�@�揊����⸈��@�@�@�@�@��⸈����F���ǂł���
���k�����Z����_�^�ʓ���É@�@�@����180�`
�@�k�����������l�Ԓn�ɂ���A�������ÁE�R�c���ɉ������Ƃ���ŁA��t��ʃo�X��u�Z���v�ʼn��Ԃ���ƁA��O�ɉԛ��③��̑咹��(���a�P�O�N�ꌎ����)������A��������{�a�Ɏ���ΎQ���̗��킫�ɂ́A����S�N�𐔂��鋐�����ނ������Ă���B���̋����̍L���͎O�畽�����ɂ��y�ڂ��Ƃ��Ă���B
�Ր_�͈ɜQ�����E�ɜQ�����E�V�ƍc��_�E�fᵚj���E���ǖ��E�g�q���̘Z�_�ŁA�{�a�E���ɖ��ЉF��_�ЁE�ێЗY���_�Ђ��ʂɌ��Ă��Ă���B
�Ȃ�������_�́A�����S�R�N�Ɏ��������獇�J�������̂ŁA�Ր_�͗_�c�ʖ��ł���B
�@�@���_�Ђ̗R���͏ȗ�����B��
���̕ʓ���É@�́A�_�������̊��K�ɂ���Đ_�Ћ����ɂ���A���i�����Ɍf�ځj�̖����ł������B
���̂��Ƃ�����͎̂��̕����ł���B
�@�@��`�V��
��A����É@�@�V�`�ҏ]���N�ׁ@�M���V������@�ʎ������Ȍ�@�e�j���]�d�������w�}��
��A���`�V�d�v�W�������Ė{���@��w�V�l�������݂��́@�������@�މ@����D�@��
�@�@�@���\�P�S�h���N(1701)���l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��É@�@��
�@�@�@�@���l
�@�_�������߂͖������N�l���ɕz�B���ꂽ���A�����ɂ��ẮA���̂悤�ɋL�^�����B
�@�@�@�������N���ʓ���É@���В�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S�k�����@�@�������S��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؓ��@�@�@��É@
��A�ܐ��E���@�@�@�����������n
�@�@�@�Z�����V�@�������@�@�@�@�A�V�j�E�Z�V����
�@�E�V�ʑ��ᖳ�����@�ȏ�
�@�@�@�������N�C�\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S�k����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�s�E�q��@�@����@�����q��
�@�@�@�@�䌧�m���@�@�@�����
2023/10/19�B�e�F
���c��É@��ŋ��I�ȍ��Ղ͑�ڔ�������i����͋ߑ�̂��̂ł��낤�j�A�O���I�ɂ͂܂��������Ղ͌����Ȃ��B
�@�k�����Z����_��P
�@�k�����Z����_��Q�F���̒n���Ɠ��̂��̂ŁA�L�I�̐_�X����ڂ̊�Ɋ��������B
�@�k�����Z����_�q�a�P�@�@�@�@�@�k�����Z����_�q�a�Q�@�@�@�@�@�k�����Z����_�{�a�P�@�@�@�@�@�k�����Z����_�{�a�Q
�@�k�����Z����_�Ж����@�@�@�@�@�k�����Z����_�萅��
���������k���k����
��Wikipedia�@���
�@�R���͖@���R�A�{���͎߉ޔ@���B���{�R�́A��{�R�@�،o���B�e�t�@���B
�V���N�ԁi757–765�j�ɊӐ^�ɂ���ĊJ�n����A���s���Ə̂����@�ł������Ɠ`���B
���̌�̎����E���i�̗��̌�A�����̂����c���͐�t���̋��_���̂ƂȂ�A�i�m�N�ԁi1293–1298�j�������Z���̎��ɓ����͐^���@�ƂȂ�Ƃ����B
��a�Q�N�i1346�j���R�@�،o�����S�ɂ���Ăɓ��@�@�ɉ��@�A�����̏��Ɖ��߂�ꒆ�R�嗬�ƂȂ�B
�V���T�N�i1577�j���Ï�勍�������̐��炪����A�V���P�X�N�i1591�j����ƍN�A���n12����i�B
�����F
�@�����R���ώ��i��t������S���Ò��k���j�@�������Ɍf��
�@����É@�i�p���j�F�Z����_���c�Ŗ����̐_�������Ŕp���i��̘Z����_�̍��ɋL�ځj
���u���@�@���@��Ӂv
���R�@�،o�����A�@���R�ƍ����A�e�t�@���B
�V����F�N���i747-765�j�̊J�n�B���s���ƍ����A���@���B
�J��͏�s�@���S�B��a�N���A���R�R�����S���@�����@�A���s���������B
���i�Q�O�N�啗�œ|��A�@�����茻�ݒn�ֈړ]�B
���Ɂu�@12���@���[�v�i�@���̋L�ڂȂ��j�Ƃ���B
���u���Ò��j�v/ ��j��/������/�k��(�����Ȃ�)/�@���^�_�ЁE���@�@���
���@���R��
�R���E���N
�@�w�������@���ג��x�ɂ��ƁA
�@�@�@�@��t���lj�����������S�����k�����k��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�؏@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@��
�@��A�{���@�@�@�߉ޖ���
�@��A�R���@�@�@�V���N��(�����`���Z�l)���m�Ӑ^�n���j�V�e�A���掛�������s���g�̃V�A���@��`���k�g�i�������V�c�m�䒺�莛�g�]�B��a��N(��O�l�Z)�L�̓��@�@�j���@�A���������g�����B�V���\���N�����{����ƃ����A�n���s�����n�E��Δ��l����(�����l�N��n�g�i��)�B�E���Ãm�R�����ȃe���ۃm�x�A��ӎ��m�{�l�����@���R�m����M�z�ʎ����B
�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ���ԁ@���s�Z�ԎO�ځ@�@�@�@�@��A�ɗ��Ԑ��@�Ԍ��܊ԎO�ځ@���s�E��
�@��A�����ؐ��@��S�E���@�@�@�@�@��A�h�k�l���@��S�O�E�ܐl
�吳���N�����O�\����W���������Z�����@�@�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@���W�����́u�{�y�[�W���k���{���Ձv�ɋL�ڂ���B
�@�i�m�N��(1292-98)�ɓ�����@���͓��Q����G���Ƌ��ɁA����܂ł̗��@����^���@�ւƉ��߁A
��a�Q�N(1346)�������R�@�،o���O���ł��������S�����v�R��(�����s��s�э�)�s�������ɂ����Đ��@���������Ă����Ƃ��A�����͖@�_���A���S�̔�}���Ɍh�����A�A�����ē��@�@�ɉ��@�����B�����Ďt��̋`�����і�������Ɖ��߁A���������Ƃ����̂ł���B
�@�����́A���ݒn�k���̍���u�@����v�Ɍ��Ă��Ă������A�啗�̂��ߓ|���̂ŘZ�����s�̂Ƃ����i��\�N(1413)�㌎�Ɍ��݂̏ꏊ�ֈړ]���āA�{�����Č����A���̎��������ɂ���ē����@�����Ă�ꂽ�B
�@���̌�A���ӏ��ƂȂ��������\�o������́A����̋F�菊�Ƃ��ēV���ܔN(1577)�ɐ��D�E������Ă��邪�A����͑O�L���S�����n����~�̎x�z�Ґ�c����̎q�ł���A�������܂����̎q���ł��邱�ƂȂǂɂ����̂ł��낤�B
����ƍN����Ȃǂ̕������c������B�i�������͏ȗ��j
���ۂP�V�N(1732)��Q�P�������͉i�㐹�Ղ�\������B
�@�����́A�����h���X�Q���E���P��h���U�U���E���k�퓿���P�S���E�a�̎R�������P�T���Ȃǂ��C���A���W�N(1758)�\����ɘZ�\�O�Ŏ���A�ߋ����ɂ́u���ϘN����_(�}�})�@�@��̓����@���R�i���c�@�����R����@�I�B��������c�v�ƋL���B
�@�����|�퓿���P�S���́u��d�@�����@���W�N�P�Q���P����v�ƋL���B
�@���I�Ɋ��䎛�P�T���́u��d�@�����@���W�N�P�Q���P����v�ƋL���B
������̐Γ��E���{�@�@����220�`
�@��������t�߂̓��H�킫�ɑ�ړ�������B
�u�얳���@�@�،o�@[�@���R��]�v�Ƃ���A�����ʂɂ�
�@�u�@�c�掵�S������s���v
�@�u��V�l�C�F�d���@�@���a�\�ܔN�\�g���@�@���R��l�\�����{Ꟊ@���m�@����@���ꌴ���j�@�����ؓ��V���@�@���@�@�y���H���Y�@���@���v�ԁ@���@���@�@�����@���@�@���@�O�}�@���i�v�ƍ�����B���Z�E�̑�l�\�����{Ꟊ@���m�̕M�ɂȂ�B
�@�m���嗼���ɓ��̑�ړ�������B
���̉E���ɂ́A�u�얳���@�@�،o�@������@���@�@���R�����\�k�@�@�����@����(�ԉ�)�@���a��V�Ύ��M��(1770)���t�Ǔ��v�Ƃ���A���ʂɂ�
�u���c���F�ܕS������ӓ��@�]���a�ДN�\��N�V�ԗa���C�P�Ɓ@����������ݕ������O���S�ݕՁ@���u���o��畔�\�틟�{�@�v���s�@�V�����N�h�N�\�������O���@�\�������j��畔���A�ב剶��Ӂ@�ȍ�������c�ݑ�V�O��œ����i�@�r�c���c��O�����B����������N�@�{�o�@�a�������_�勏�m�ӓ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�k�@��\�ܐ�����(�ԉ�)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ݓ쒆�������R�F�E�q��h���v�@�ƍ����B
�@���̎x���҂ł��镽�R�F�E�q��Ƃ́A�O�L�n�}�ɂ���G��(���E�q��E���d�Y)�̎O�j��P�̂��Ƃł���B���Ƃ��ĉF�E�q��Ƃ̑c�ƂȂ������A���R�Ƃ̌n���������A���i�Z�N(1777)�ɂ͓��ꑰ�̉ߋ����ɕM���Ƃ��Ă���B�������N(1796)�ɂW�P�Ŗv���B
�@�����̂��̂ɂ́A�u�얳���@�@�،o�@�@�c�Z�S�������O�\�㐢���s�@�s�ω@�@�^���@���m(�����E�d�j)�@�����@����������o(�d�j�Ȃ킳)�@�����\��N��ЎO���{���@���R�ܘY���q�h�����v�B
�@����ɂ́A�u��[�@�]�ˍ䒬���������@�l�ډ����M�@���a���M��(1770)�����g�˓��@��\�ܐ������@�����v�Ƃ���B
�@�m�����������E���̉��ɂ͗��Z�E�̕�����сA��h�z���R���̕�n������B
�����̔��ǂł�����̂ŌÂ����̂ɂ́u���i�P�P�b��(1634)�l����\�O�����R�ɕ��q�@�����`���o�O�\�O�N��v�Ƃ��邪�A���G�M(�@���@�@�@�a���`����)�̎O�\�O����ɓ������Ē��q�ɕ��q(�G��)�������������̂ł��낤�B
�@��͔���قǂ��_�݂���A������������E��k�����玺�������̂��̂ŁA��������ڔ�Ƃ�����B
�@���@�u�얳���@�@�،o�@�얳�߉ޖ���Ł@�i�a��[���C](1367)�@�����v
�@���
�@�@�u�厝���V���@�@�@�@�@�@�@��A�ړV��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�m
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���恡��
�@�@�@�@�@��s�ٕӍs��(��F)�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�얳����@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����恡��
�@�@�@�얳���@�@�،o(�@��)�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�얳�߉ޔ@���@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������
�@�@�@�@�@��s�����s��(��F)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@���i�\��N(��l�Z��)�\���\��
�@�@�@��@��V���@�@�@�@�@�@�呝���V���v
�@�@���̔�́w�����������l�x(���{�G����)���\��(���E�|���E���y�L�c��)�ɂƂ肠�����Ă�����̂ł���B
�@
�@��O
�@�@�u�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�הߕꖭ����u��
�@�@�@�@�@�얳����@���@�\�O�N���瘹�l��
�@�@�@�얳���@�@�،o�@�@�����@�E�������v
�@�@�@�@�@�얳�ډޖ���Ł@�@�@���@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���\��N(��l�O��)�\�ꌎ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�q�h���v
�@
�@���̂ق��ɁA������N(1490)�A�������N(1498)�A�V�����N(1532)�A�V�����N(1573)�̂��̂ƁA���Ղ̂��ߔ��Ǖs�\�̈�����B
�@�������䕗�ɂ���ē|�A���i��\�N(1416)�Ɍ��ݒn�ɍČ����ꂽ���Ƃ͊��q�̂Ƃ���ł��邪�A�@����ɂ��鎛�Ղɂ͉��i�O�\�N(1423)�̔N��������䶗��肪���Ă��Ă��āA�������ÂԂ悷���Ƃ��Ă���B�Ȃ����̐Γ����w�����������l�x�Z�E���\��ɋL�ڂ���Ă�����̂ł���B
�@�{�����w�͑������̂��̂ŁA�{���\�E������䶗����������J����A�E���̕ʓ��ɂ͓y���o���Ƃ����������V(�����V)�̑��A�e���������u�����B
�@�����̐�ב����ǕJ�������w�k�����j�x�̒��œ����Ɋ��ꕶ������A�����ɍČf���ď��̍����I�肽���B
�@�@����
�@���R���A��a�����@��ਓ�@�ؓ����B���k�O���L�O�n����@�����B�����Ж�B
�ЗL��ꍏ��֑ɗ���B�����A���i�\�O�N�\���B�W�[����@�S��\�ܔN�Ǖ���ҁB
���L�H�A���m�Ӑ^�n��{���y�g���������A�y�����Q����B���Q�����������B�R�A�Ӑ^�����`�A�����ߏ��s���Փ���B�̌ƎɃ��V�B
�@�@�J����J�H���
�@�@�L���Јϓ��䗉��
�@�@�ˑR�ۓ�I�Õ�����
�@�@�W�����N�@����
�����ƕ��R�ꑰ
�@�����ɁA�����������������F�菊�Ƃ������Ƃ��q�ׂ����A����ȑO�̗L�͂Ȏx���҂��≪���i����Ɍf�ځj�啽�R���̂������Ƃ��L���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�����ɑ�����@���̌��Ⴊ�A���R���𖼏���ċ{�̚≪��ɂ������A�\�O���̋G�M�ɂ��ĕ��R�ƌn�}�́A�u���q��с@���i�����@�����≪��j���e�@�k�����j���X���c���j���@�H�W�\�Z�ѓ�S��\�����@���B�����S�@���B�����S���R���@���������v�A�u���S�@�����@���R�O�ӏ��j�@�������������R�ߕӁ@��m����ӏ��v�ƋL���A�܂����Ɖߋ����Ɂu���R�G�d����@���q��ыG�M���@�k�����@���R���J��S�t�V��@�@���R���n�V�N�@�����T�N(1372)�����\���v�@���i��l�v
�@�Ƃ���A���ߋ����ɂ́u���R���n��U�߁@�����ܔN�����\���@���i���l�@���R���q��с@�S�t��q�v�Ə�����Ă��邱�ƂȂǂ�����ƁA���S�̐��@�ɋA���������������@���āA���������Ɖ��߂�����ɁA���̋G�M����U�߂Ƃ��Ă��̑n���������������̂Ǝv����B�����܂ł��Ȃ����ݒn�Ɉڂ�ȑO�́A�@����̒n�ɂ����Ăł���B
���d�_�@���~���@�@��������l
�c���R�N(1598)�э��h�эu��̓������g���R�ɓ]���A���̌�C�Ƃ��ē��~(�d�_�@)�������ꂽ�̂ł��邪�A���~�͂��̔C�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��̐g�������A�Ђ����ɏ��ɓ���B���������~��炤�O�k�����͓����ɏW�܂�A����ɂ��̐��������Ȃ����̂ŁA���N���{���Ɉڂ��ču���J�����B���ꂪ�����h�т̂͂��܂�Ƃ����B
�@���~�͓����̗��ł͂Ȃ����A���̋����͑�X�p����Ă������Ƃ����B
�@�G�M���炳��ɏ\�����o���≪�Ō�̏��G�M�̂Ƃ��A�A�_���ċ��m�ƂȂ邪�A�G�M�̒픪�Y�E�q��ы`���̓�q�����ꂼ�ꓯ���㐢�E���\�̓��w�E���[�Z��ł���A����̒��q�G�Ƃ͓����̍r�p�����l�q�����Đ[���p���A���̍��𓊂��ĕ����ɓw�߁A���܂Ő₦�Ă������̂������A�p��Ă������̂𑱂���悤�ɂ����Ƃ����B
�@�㐢�͓��w�ł���B���w�͌�ɎR���h�{�{�����̊J�R�ƂȂ邪�A�s��s�{�m�ł������B
�@�\���[�ł���B
�@���R���́A�G�M�̒��j�G�Ƃ�����p���A�����i�����j���߂ē����̕����ɗ͂𒍂����B
���̎q�������������Ă��ꂼ��u�܌��}�v���̂���悤�ɂȂ邪�A�ܒj�͏o�Ƃ��ė����@�����Ƃ����A�����̏\�l���ƂȂ����B
�����ĉߋ����Ɂu���R�G�ƌܒj�@���R�\�l���Z�@�����@���c�@�������@�@����Z�N(1678)�\�ꌎ�Z���@�\��Ή��v�Ƃ���悤�ɁA�����̏��c�ƂȂ�B
�@�����̒�(�G�Ƃ̔��j)������@���R�ŁA�������ߋ����Ɂu���R�ɕ��q�G�Ɣ��j�@��@���R�^�\�l���@�勝�O�N(1686)������\�O���@�\��Ή��v�Ƃ��邪�A�^�͕���{�y�������ŁA�s��s�{�@���Ƃ��ē��n���ɂ����钆�S�I�Ȏ��@�ł������B
2023/10/18�B�e�F
�@�k����̗��G�i�����@�j���[��l�͏����Ƃ����B
�u���@�@���@��Ӂv�ł͏��X���͓��w�i�@���͋j�A���i���N�i1624�j�V���Q�X���A�P�Q���͓��[�Ƃ���B�A���A���[�̉@���A��N�͋̂܂܂ł���B���[�͓��w�̎���B
�@�k�����������@�@�@�@�@����ڐ��F��L�̏��a�T�T�N�̑�ړ��Ǝv����B
�@������ٍ��V�F�u�Α��������ݐ}�v�k���ł͏��R���ɕٍ��V�Ƃ���B
�@�@�u���Ò��j�@�����vp.237�ɂ͏������̓쑤����ɁE�E�E����B�ؑ��̏��{�Łu�\���V�v�ƌĂ�ł���B
�@�@���ۂ��J�����ł͂Ȃ��A�ʏ�̙��V�Ƃ͎���قɂ���B�����@�ɂ��Ă͒m��l�����Ȃ��B
�@�@�Ƃ���A���̙��V�̂��ƂƎv����B
�@�R��O�E��ڐP�F�����͏�f�ځ@�@�@�@�@�R��O�E��ڐQ�F�@�c�Z�S�������O�\�㐢���s
�@�R��O����ڐ��F�����͏�f��
�@���R���@�@�@�@�@���R��P�@�@�@�@�@���R��Q�@�@�@�@�@���R��G�z
�@���m�����P�@�@�@�@�@���m�����Q
�@���{���P�@�@�@�@�@���{���Q�@�@�@�@�@���ɗ�
�@���ݗ싟�{���F�����̔肪���Ċ|������B��ʼn]���u��͔���قǂ��_�݂���v���̂��W�߂�ꂽ�̂ł��낤���B
�@����Q�P�@�@�@�@�@����Q�Q
�@���V������@�@�@�@�@�������P
�@�J�c�E��c�E�O�c�Δ��F�J�c���S�E��c�i�k��苗��j�����F�O�c�i������苗��j����
�@�������Q�@�@�@�@�@�������R�@�@�@�@�@�������S
���k������@�s�R�{�����@�@����224�`
�@�����1391�Ԓn�̂P�ɂ���B���V�c�ƌĂꂽ����W���ɂ����邽����̎��ł���B���J�R�{�y���̖����B
�w�������@���ג��x�ɂ͎��̂悤�ɋL���B
�@�@�@�@�@�@��t���lj��X��������S�����k���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�y����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�{����
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ��@�@�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��܊ԁ@���s�O�ԎO�ځ@�����l�\��N�l����\����Ď�
�@�@��A�����@�@�@�Ԍ��O�ԁ@���s��ԁ@�@�@�@�@���O
�@�@��A�����ؐ��@�ܕS���@�@�@�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�S�E�l
�@���ݓ����͖��Z�B
�����ɂ���召���̑�ړ��ɂ́A���a�Q�N�Ɠ��X�N�ɋ˒J�ÉE�q��ɂ���Č��Ă�ꂽ�|�����܂��B
�@�{�������̕�n�����ɂ�����̐Δ�́A���F�E����V�c�J��̑c�Ƃ����鑽�ÔˉƘV�����^�܍��q��̕��ŁA����ɂ́u�����@�ÐM���d��ʁ@���ۘZ�h�N��(1721)�����\�����@�����^�܍��q��ѕ�����@�������v�ƍ��܂��B
�@��n�̉��ɗ��Z�E�̕�肪����A���̒��̈��ɓ����̗R���E���̗��j�̈�[���L�������̂�����B
����ɂ��ƁA����̎n�܂�͒勝�R�N(1686)����ł���B��i�Q�N(1705)�ɉ������炩���������ڂ����ƂɂȂ��āA����i�R�N�Ɍ�����������B�Z�V�m�̈�l�E���N�̊J��ɂȂ�u����̖{�y���v�ƌĂ�钷�J�R�{�y���̖����Ƃ��āA�����Q�Q���̉~���@���F���Ɍ}���ĊJ��Ƃ����B
���̂��Ƃ��L�O���ċ��ۂW�N(1723)�ɔ�����������Ƃ����B�����͎��̂Ƃ���ł���B
�@�@�u��i�O����(1706)������\���
�@�@�@�ċ��{��@��؎����q�@�@�щ@���
�@�@�@���\�ܐp�\(1692)�\�ꌎ�O��
�@�@�@����얳���@�偬(��F)�@���J�R��\���F
�@�@�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�@�@�@�����@���N�@��l�ꊱ�P�����A�����{���@���i
�@�@�@����{�y������������V�c�@�s�R�{�������^�v
�@�����ʂɁu�����J���@�勝��刁(��)(1686)�㌎���������v
�@�E���ʂɁu���۔�ᡉK�\�ꌎ�\�O�������@��i��(1705)�㌎�l���@��������v
����V�c�̊J���Ƌ��ɓ��A�����l�����̕�Ƃ��Č������ꂽ���̂Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B
�@�Ȃ��A���a�\�Z�N�����́w���@�@���@��Ӂx�ł́A�����̉��v�Ƃ��āu��ςɂ́A������(1473)�N���̑n���B�J�R�{�y���㐢�����@���ӂƂ���v�Ƃ���B
2023/10/18�B�e�F
�@����{����������ڐ��F�召�Q���B�@�@�@�@�@������ڐi���j
�@����{�����{���P�@�@�@�@�@����{�����{���Q
���������k���J�����ώ�
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
�@���Ök����i��Ɍf�ځj���A�����R�ƍ����A����S���Ò��J��
��ςɂ��ݎ����N�i1658�j�n���A�J�R�����@���`�Ƃ���B
�@�@���ȏ�݂̂ő��̏��͂Ȃ��B
���u�����j�v����226�`2
�����R���ώ��F
�@���J�ÂP�P�Q�T�Ԃ̂Q�ɂ���B���̏W���͂��̎����������悤�ɁA�����ɂ܂������n�̒������X������k�ɑ���A���̗��킫�ɖ��Ƃ����邪�A���̓�����n�ւƒʂ���⓹��o�����Ƃ���ɓ���������B�����B���́u�{�y�[�W���k���v���Ɍf�ځB
�w�������@���ג��x�ɂ�
�@�@�@�@�@��t���lj��X��������S�����k�����J
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���@�@�@���ώ�
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ��@�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ���ԁ@���s���ԁ@�@��A�����ؐ��@�O�S��E�@�@�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�S�E��l
�Ƃ���A�R���͕s�ڂƂȂ��Ă��邪�A�����Ɏc��ߋ����ɂ́u���R�J������@���`���l�@������q�N�����@���\��v(���A���̔N���E���x�ɋ^�₠��B�u�����v�Ƃ����1175�`1177�N�ł���A�u��q�v���̂��1168�N��1228�N�A�܂��͂���ɂU�O�N�������������ꂩ�̔N�ɂȂ�)�B
�u�����n�����Q�N(1659)�m�n���i���A���j�h���n�O�˃A���V�m�~�v�Ƒ��n�L���Ă���A�w���@�@���@��Ӂx�Ɂu��ςɂ͖������N(1658)�����̑n���B�J�R�����@���`�Ƃ���v�Ƃ��邱�ƂƁA�����ނˈ�v����B
�@�܂��A���ߋ����`���ɂ���u�֓��@�؎��w�Z���W�v�Ƒ肷�鍀�ɂ͊e�h�т̔\���̖����L����A��ʓI�ɂ͉B����Ă���s��s�{�h�̐��l���܂Ŗ��炩�ɂ��Ă���B
���̒h�і��́A�э������_�R�@�֎�(�э��h��)�A�㑍�����������R���@��(�����h��)�A���������������R���{��(�����h��)�A��������@��R���u��(����h��)�A�����ʑ����@�R�@�؎�(�ʑ��h��)�A������C�����R������(��C�h��)�Ȃǂł���B
�@����ɗ��O�ɂ́A��i�Q�N(1705)�\����鐼�J�ʼnЂ�����A�h�сE�������E�������E����������ѓ��B�����E�������H�_�ƂȂǂV�O�]�����Ď������Ƃ��̖͗l�⌴���ȂǂƂƂ��ɁA�V�����N(1787)�ɒh�т��ēx�̉Ђɑ����������L����Ă���B
������̐Γ����E���{�@�@����228�`
�@�{�����w�E��ɂ́A�S�q��_�̐~�q������A���݂��W�����̎�w�������琒�h�����B
�@�Γ����Ƃ��āA��O�ɑ�ړ�������A�u�얳���@�@�،o�@���ώ��@�����P�S�N���N(1817)�����@���N�喭����y�h���v�ƍ��ށB
�@�{���E��ɏ���������A�Α��Ɗp�����[�߂���B
�Α��ɂ́A�u�얳�߉ޘŎO���P�����A�@�����S�劽��@�V����p刁(�ꎵ����)�l���g���@�{���@�c�V�v�Ƃ���B
�p���ɂ́A���Ɏ����悤�ɑ����̐��l�������܂����A���̑啔����������Ă���B����͌�N�ɕs��s�{�M�����ƂȂ�A���̏؋���铽����Ӑ}����Ȃ��ꂽ���̂ł��낤�B
�@�@�@�@�@�@�@���@���ώ���ڊp��
�@
�@�@�u�얳�����[���Ӎs𦬠�@��s𦬠]�@���N��F
�@�@�얳���@�@�،o�@�얳���@���F
�@�@�얳�߉�[��s𦬠�@�����s𦬠]�@������F
�@�@�������l�@�������l�@�����哿
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�፹��
�@�@[�������l�@�������l�@�������l�@�������l�@�������l�@�������l]�@����(�ԉ�)
�@�@�Z�V�m�@���e���l�@�������l�@���̐��l
�@�@��V�m�@�������l�@�������l�@���O���l
�@�@���V�m�@�@�@�@�@�@�������l�@���i���l
�@
�@�@���������[�ȉ�@�T���@�E�������v
�@�@���c����ܕS���������@���~���@���M����
�@�@�V�s�Y�������ӗ�c�ҁ@���{���@�P�v����
�@�@�M���U���V�M�R祔���_��@�����@���M����
�@�@�@�@�@���a���M��(1770)�g�˓�
�@�Ȃ��A�E�̐��l���̌����ɂ��ẮA�킸���Ɏ��̂悤�ɔ��ǂł�����̂�����B
���Ȃ킿���q�E���u�E�����E���ׁE���_�E���`�E���ƂȂǂŁA��������@��ɂ����錆�m�ł���B
�@�܂������ɂ́A���q����ꎮ�A�����q�E�Y���q�̓��A��������g������A���ł����N�����̓y�p�����Ə̂�����h���̎������ɁA���h�c�����������q�������𒅂��A�������̋ȂƋ��ɏW�����̊e�˂����A�S���s�����s���Ă���B���̂����E�N���ɂ��Ă͒m��l���Ȃ��B
2023/10/18�B�e�F
���@��l���n��t��ڊp��
 |
���n��t��ڊp�������F���}�g��}
���n��t��ڊp�������F
�@�얳�����[���Ӎs𦬠�@��s𦬠]�@���N��F
�@�얳���@�@�،o�@�얳���@���F
�@�얳�߉ށ@[��s𦬠�@�����s𦬠]�@������F
�@�@�ƍ��ށB
���n��t��ڊp���E�ʂP�F
�@��i�͘Z�V�m/��V�m/���V�m
�@���i�͓��e���l/�������l�@�ƍ��ށB
�@�@����Ă���������l�͓������l�Ɠǂ߂�B |
�@���n��t��ڊp���E�ʂQ�F��i�́������l/�������l/�������l�A���i�͓��̐��l/���O���l/���i���l�@�ƍ��ށB
�@�@��i�̓����͍���Ă��邪�A�����A�����A���[�Ɣ��lj\�ł���B
�@�S�̂ł�
�@�@�Z�V�m�@�@�@�@�@�@�������l�i�����j�@���̐��l
�@�@�@�@�@�@���e���l
�@�@��V�m�@�@�@�@�@�@�������l�i�����j�@���O���l
�@�@�@�@�@�@�������l�i�����j
�@�@���V�m�@�@�@�@�@�@�������l�i���[�j�@���i���l�@�@�ƍ�����B
�@���n��t��ڊp�����ʂP�F�ŏ�i����
�@�ʐ^���������ǂł��Ȃ����A�����炭�������č�������q�E���u�E�����ł͂Ȃ����낤���B
�@���n��t��ڊp�����ʂQ�F�ォ��Q�i�ڕ���
�@����Ă�������́A�������č�������ׁE���_�E���Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@���n��t��ڊp�����ʂR�F�ォ��R�i�ڂƍʼn��i����
�@�ォ��R�i�ڂ̍���Ă�������́A���ǂł��Ȃ��B
�@�ʼn��i�́A��L�̒��j�ɂ���悤�ɁA�J�፹��/����(�ԉ�)�@�ł��낤�B
�@�S�̂ł�
�@�@�������l�i�����H�j�@�������l�i���ƁH�j�@�����哿
�@�@�������l�i���u�H�j�@�������l�i���_�H�j�@�������l�@�@�J�፹��/����(�ԉ�)
�@�@�������l�i���q�H�j�@�������l�i���ׁH�j�@�������l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƍ�������B
�@�w�ʂ͖��m�F�Ȃ���A��L�̒��j�ɂ���悤�ɁA
�@�@���������[�ȉ�@�T���@�E�������v
�@�@���c����ܕS���������@���~���@���M����
�@�@�V�s�Y�������ӗ�c�ҁ@���{���@�P�v����
�@�@�M���U���V�M�R祔���_��@�����i���j�@���M����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̊����́u�C+�b+�L�v�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a���M��(1770)�g�˓��@�ł��낤�B
���a�V�N(1770)�A���@��l�ܕS���������ׁ̈A�ɋ[�������ɁA�Y��ĂȂ�Ȃ���c�����ݑ��_�ƂȂ�E�E�Ƃ�����ӂł��낤�B
���͖{���@�����A�~���@����A�����E�@�����ł���B
���a�V�N(1770)�Ɖ]���A�s��s�{�h�̒e�����{�i�����������N������}��100�N�̌�ł���A�s��s�{�h�����S�ɋ����̍��ł���B�悭������t�̖������Γ����������ꂽ���̂Ǝv�����A���̖����㐢�ɍ����ꂽ�Ƃ����ǂ��A����ɓ`������Ƃ͊��S�[�����̂�����B
�@�J�Ö��ώ������@�@�@�@�@���ώ�������ڐ��@�@�@�@�@�J�Ö��ώ��{���F�����T�N���z
�@���ώ�������P�F�������č�����A�Q�S���O���@���ʑ哿�A���i�H�j�����x���l�A�J�������@���琹�l�̕��
�@���ώ�������Q�F�������č�����A�ל�i�H�j�@�����哿�A�Q�X���d�ʉ@�����哿�E�i���Ǖs�\�̂P���j�A�i���Ǖs�\�̂Q���j�A�R�W����m�@�������l�A�����͕�ژZ�畔�i���فj�A���@����/�����\��N�E�E�E�A�P�S�������@����/���Q�N�E�E�E�A�X������@����/��i�T�N�E�E�E�A�i���ǂł����j�A�����@���s���l�@�ł���B
���J�Â̓��c�_(��)�@
�u���Ò��j�@�����vp.235�`6�@�Ɏ��̂悤�ɂ���B
�@�Γ��̈��ɂ́u��Q�w�O��P���@���ی����\(1716)�\����\�����@�������k�����@���x�@�����v�Ƃ���B
���̐Γ��̖k���ɐ{���R��A���K���T��قǂ���B���̒n��̖ؓ����ꑰ�����J���Ă���Ƃ����B
�Ȃ��A�ؓ����̉��c�ɂ͎R���i�C���j�ɂ܂��l�������Ƃ����B
�������琼�����Ɂu���R�̏Z�g�Ёv������B���Z�g�Ђ́u���Ò��j�@�����vp.194���Q�Ɓ�
�@�Z�g�Јܓx�o�x�F35.74733126377235,
140.49521013187447�A�Γ��ܓx�o�x�F35.74710405118565, 140.49558765278027
2023/10/18�lj��F
�@��Q�w�O��P�����@�@�@�@�@���R�Z�g���_
�@��Q�w�O��P���Γ��t���F�f��������eMap���A�ʐ^�������u�Γ��v�A���߂ɓ��c�_�E�Z�g�Ђ�����B
���k���̎��@�Ձ@�@����230�`
�@���ɁA���͔p���ƂȂ������@�Ղ�K�ˁA���肵���̂����������Ă݂悤�B�܂��k���̓��[�E�{�̏W���֓����Ă݂�B
���k���{���Ձi�{�̏W���ɍ݁j
�@�t���_�Ђɗאڂ���A�Δ肪����u�����@�얳���@�@�،o�@�ז{�R�������L�O�@�h�ƌ����@�吳���N�����O�\���v�ƍ����B
�w�������@���ג��x�́A���̂悤�ɋL���Ă���B
�����B���k�����ɂ́u�吳���N�����O�\����W���������Z�����v�i�w�������@���ג��x�j�@�Ƃ���B
�@
�@�@�@�@�@��t���lj��X��������S�k�������{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@����
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ��@�@�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ����ԁ@���s�l�ԁ@�@�@��A�����ؐ��@�O�S�E��@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�O�E�ܐl
�@
�@�J�R�ɂ��āA�{���ł�����̉ߋ����ɂ́u�O��������苗����~�@�����R�N(1386)�l������@����y�@�@�����{���J�R��v�ƋL���B
���i�Q�P�N(1414)�����߂Ƃ��鎟�̌܊�̔肪����B
�@���i�Q�P�N(1414)�A�i���S�N(1432)�A�i���P�Q�N(1440)�A�����R�N(1446)�A���\�S�N(1430)
�@�@��������������E�����̂��̂ł���B
�@�܂��A���ɂ��Ă̌Õ�������ʏ��ɕۑ�����Ă��邪�A�s��s�{�̋ᖡ�Ǝ����ɂ��ĎQ�l�ƂȂ�̂ŁA���ɍڂ���B
�@�@�@�ȏ����ύ׃j�\���
��A��@�x�V�s��s�{���X�ᖡ�d�A�ʎ����N���h���ꓝ�ᖡ�𐋁A�}�x�����A�����B�������V�l���j�M�V�Җ������B�U�ߎ��֎�u��Ӟ��������B
�@�@�����A�Γ��E���k���ʏ��j������ҁA���͖����l�\�@�|�A���l�ʏ��V��ғ���ؖ������B
�@�@�֑ɗ��V�`�͑O���L���A���V�ٕʂ��Ȃ������d����҂������̑����A���~���n�َ��]���A�ĕ��\��B
�@�@�h���ꓝ�A���u��B
�@�@�E�V�ʂ�j���ᖳ�����B�ȏ�
�@�@�@�@�@�Џ\�����O���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������(�}�})�@��
2023/10/18�B�e�F
�@�{���Ք�P�@�@�@�@�@�{���Ք�Q�@�@�@�@�@�{���Ք�R�F�����͏�ɂ���@�@�@�@�@�{�t�����_
���k�����{�팰����
�{�ɂ͌�����(�����苌����h��)�̖����Ƃ��ď�p�R�������i�팰�������j�����������A�u�≪�隬�v�̍��i��Ɍf�ځj�ɋL�ڂ�����B
���k���E�i�v�ہj����R��������
�@���v��3020�Ԓn�ɂ���B
�v�ۏW���̒��S�n�œ��H�̏\���Ɍ���鏊�ɏW�������A����Ɠ��H���͂����E�̏ꏊ�ł���B���݂͕�n�ƂȂ�B
�@�����́A���{���̖����ł��������A�쒆���V�J(�܂��͒���Ƃ�)�ɂ��������������A�Ύ��ɑ������̂����ݒn�̐��J�Ɉڂ�A�ċ�����ɓ������ē������Z�ł������������̌������g�p���A�����Ɏ��Ђ��������ꂽ���Ƃɂ���Ĕp���ƂȂ����悤�ł���B���{�����B
�@�@�w�������@���ג��x�@
�@�@�@�@�@��t���lj��X��������S�����k�����v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@������
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ��@�@�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��܊ԎO�ځ@���s�O�ԎO��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�ɗ�
�@�@��A�����ؐ��@���E��@�@�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�O�E��l
�@�@�@�@�@�@�A���A�����l�\�ܔN�Z������������쒆�������������������g���̃X�i�����ӂ��ׂ��j
�@���݂ł́A��ړ��Ɣ肪���c��̂݁B
���̑�ړ���Ɂu�������얳���@�@�،o�@���ۂQ�O���K�N(1735)�O���l���@�P���@�����哿�@�V�ۂP�P�q�N(1840)�\�ꌎ�ǒC�@���������@���Ɓ@�y�h�������v�Ƃ���B
��́u���i�R�S�N(1427)�v�̕������ǂݎ���݂̂ł���B
�@�Ȃ��A�������s��s�{���M���Ƃ��Ēm���A���\�P�P�N(1698)�\�ꌎ�\���ɎO��Ŏ��S�������@���{�́A�u�����k�����������o���A���Ð����v�ŁA�s��s�{�M�E�z���̉Ȃɂ��O��֗��߂ƂȂ�A���̒n�Ŗv��(�w�[�����@��j�x)�B
�@�����@���{�F
�@�@���u�s��s�{�}���̗��j�v�ł�
�@�@�@�O��s��z���m
�@�@�@�@���@���{�i�����j�@���\�X�N�P�P���W���i���\�P�P�N�P�P���P�O���j��A
�@�@�@�@���\�@��i���\�S�N�V���T���z���j�����k�����������o���m�A���Â̐��A�J�̐l�B�@�Ƃ���B
�@�@���u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�v116�y�[�W�@�ł�
�@�@�@���\�P�P�N(1698)�\�ꌎ�\���A�O����@�����A�h�_�A�����k�����������o���A�������Ñ����A�O����m�@�Ƃ���B
�@������ȑO�A���\���N(1688)�ɓ��{���R�R�������̋L���������̈�߂Ɂu�v�ۖ������@���؏�R�����v�ۂֈ���B�@���̖{���V�`����X�B���\�l�N�����{���A������`���L�v�Ƃ���A�@����٘_���������������́A���{���Ƃ̉������₵�A���\�S�N�ɍĂы���ɕ������Ƃ���B
2023/10/18�B�e�F
�@�E���������F���݂͕�n�ƂȂ邪�A�������E�Ɋ���̔p���̂��̂Ǝv����Γ��ނ��c��B
�@�E�����������@�@�@�@�@�E�������Γ��ނP�@�@�@�@�@�E�������Γ��ނQ�F�R��قǎc���Ǝv����B
�@������������ڐP
�@������������ڐQ�F��ɖ������ƍ��ށB���E�O��͖��m�F�Ȃ���A���j�ʼn]���u�������얳���@�@�،o�@���ۂQ�O���K�N(1735)�O���l���@�P���@�����哿�@�V�ۂP�P�q�N(1840)�\�ꌎ�ǒC�@���������@���Ɓ@�y�h�������v�ł���Ǝv����B
�@���@���{���P�F���w�ʂ͖��m�F
�@���@���{���Q�F�w�ʂ́u�V�����N�����\���\�O��/����������v�A�E���ʂ͎ʐ^�������A���ǂł����B
�@�E�T�i�H�j�@���^���F���^���l�Ƃ��邩��A�����������^�̕��ł��낤���B�w�ʂȂǖ��m�F�B
���k���E�i�v�ہj��������
2023/10/18�B�e�F
�@�E�������̓��ɂ͖������Ƃ������@�����������̂Ɛ��肳���B
�u���Ò��j�v�͖�������z�V��Ȃǂɂ��Ĉ�ؐG��Ȃ����A���̎������疭�����̑��݂������т�����B
�A���A�u���Ò��j�@�����vp.44�ł́A�u��c���ɂ�����i��t���E��c���j����̋��ق͌E(���Ò��k�����v��)�ɂ������Ɠ��{���̌ËL�͓`���Ă���B�v�Ƃ���B
�@����ɁA�u���@�@���ĎR�Ō������N�v�i�p���t���b�g�j�Ɂu�L�ڂ̗��}�v�ɂ���
�n�����u�E�v�Ƃ���A�Ō����̐����v�ۏW��A�k���������Ւn�E�������Ւn�A�k���ɉz�V��i��t���勏�ِՁj�Ƃ���B�����炭���������t�����قɊւ��鉽�����̎�������肪���������̂Ɛ��������B
�܂��A���̒n�Ɏc��i���Ɍf�ځj�B��@���L���l��̍��ʂɂ́u�z�V��썡�h�w/���������v�̍���������A�z�V��y�і����������݂������Ƃ��m���B
�z�V��ɂ��Ă��A���Ò��j�͉������Ȃ����A�Ō����k���Ɂu�v�ۏ�Ձv������AGoogleMap�ɂ͕����̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B
�z�V��Ƃ͂��̋v�ۏ�Ɛ��肳���B
�@GoogleMap�Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^�̈ꖇ�u�v�ۏ�Ɛ�t����ɂ����v�i�����j�ɂ��A����̋L�q�͊T�ˁu���Ò��j�v�̋L�q�ɉ����B
����͐�c���ɑ����̓��@�@���@�����������Ƃ������A���̐�t�����삵�����@�Q�ɂ��̋v�ہi�E�j�̘Ō����E�������E�����������������̂Ɛ��肳���B
��L�@�����́u�z�V��썡�h�w�v�Ƃ͉z�V��́u��v�́u���v�i�V�����j�u�h�w�v�Ɖ�����A�������̂������ꏊ�͌E�i�v�ہj�̒��S�n�ł���A�z�V�鉺�ł���A���̐V�����h�w�Ƃ��ċ@�\���Ă��������̂Ɖ��߂����B
1023/10/18�B�e�F
�@�E�������ՐΓ����F����
�@���L���x���l���@�@�@�@�@���L���x���l�荶�ʂP
�@���L���x���l�荶�ʂQ�F���L���l�荶�ʂ́u�z�V��썡�h�w/���������v�ƍ��ށB
�@�B��@���L���l���F�����Z�Ȗ��i1809�j�E�E�E/�B��@���L���l/�����E�E�E�E�E�E�ƍ����B�E�ʁE�w�ʂ͖��m�F�B
�@�@��@���x���l���F�����@��@���x���l�A�E�ʁE�w�ʂ͖��m�F�B
�@�����s���Γ��F�ӂ����݁A�ʐ^���������Ǐo�����A�u�얳���@�@�،o�@�������B�i�H�j�E�E�E�E�v�ƍ�����B
�@�T���@���������l���F�����炭���������Ǝv������m�͂Ȃ��B
���k���E�i�v�ہj���h�R�Ō�����
�@�����ݕ������͕����P�W�N�i2006�j���A���F��F���Č�����A��������������A�ċ�����Ă���B
�@���v��3013�Ԃ̒n�ŁA�O�L�������ՂƂ͓����ɑ��铹�H�����Ăđ����Ă���B��i�ƍ���Ō��݂͕�n�ƂȂ�B
�쒆���������B�����������������쒆�ɂ���B
�w�������@���ג��x
�@�@�@�@��t���lj�����������S�����k�����v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�Ō���
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ��@�@�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��܊ԁ@���s�l�ԁ@�@�@��A�����ؐ��@�S���E�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�O�E���l
�w���@�@���@��Ӂx�ł́u��ςɂ͒厡�N��(1362�`67)�̑n���B�J�R���R�@�،o���O����s�@���S�Ƃ���v�Ƃ��A���S����t����̔���A���n������@���đ����̎��@�����@������������A���̑n�߂Ƃ���悤�ł���B
����́A�����Ղɂ��闑���ɂ���Ă������B���Ȃ킿�����ɂ́u�J�c�@�얳���S���l�@�����V�N����(1374)�܌��\����v�ƍ������B
��GoogleMap�@���
GoogleMap�Ŋm�F����ƁA�Ō����Ղ͐�������A�V������F�i���㌚�z�Ǝv����j����������A�u���@�@���h�R�Ō����v�̐V�����������u���h�R�Ō������N�v�Δ�����Ă��A�Â���ڐ��c��悤�ł���B
����āA�ʐ^���f�ڂ���B
�@�ċ��k���Ō����P�F�����@�@�@�@�ċ��k���Ō����Q�F���F�@�@�@�@�@�ċ��k���Ō����R�F������
�@�ċ��k���Ō����S�F�u���S���l�Ɩ��h�R�Ō������N�v�Δ�
2023/10/18�B�e�F
���u���@�@���ĎR�Ō������N�v�i�p���t���b�g�j�@���
�@���S��l�^�M��䶗�
�@���S���l�Ɩ��ĎR�Ō������N�E�{���F���́u���S���l�Ɩ��ĎR�Ō������N�E�Δ�v�ɋL�����̂ł���B
2023/10/18�B�e�F
�@�Ō�������
�@������ڐ��F�\�ʂ͑�ځA�����ʂ́u�@��@�����哿�v�u�@�E�ݗ씲��`�y�v�Ƃ���A��ʂ͖��m�F�ŔN�I�Ȃǂ͕s���B
�@���S���l�Ɩ��ĎR�Ō������N�E�Δ��@�@�@�@�@�ċ��Ō������F
�@�Ō������_���F�U��̕�ƂP��̔肪����B
�@�J�c���S���l���F��L�́u���S���l�Ɩ��ĎR�Ō������N�E�{���v�ł͓��S�͉����V�N�i1374�j�₵�A�����Ō����ɑ�����Ƃ����B
�@���@�@�������F�����ʂɂ́u�k���������|�Y�V�ۏ\�N/�Ȉ吳���\�O�������掵�\�l�v�ƋL���悤�ɓǂ߂�A�E���ʁE�w�ʂ͖��m�F�B
�@�������͕s���ł��邪�]�ˌ���̏Z���ł������Ǝv����B
�@�Q�V���{���@��������F�吳�P�S�N�����@�@�@�@�@�R�Q���E�lj@����E�Q�S���ڐ��@���z���
�@�Ō������F�P��邪�A�܂��������ǂł����B�u���S���l�Ɩ��ĎR�Ō������N�E�{���v�ɂ́u�P����v�Ƃ�������������Ƃ����A���̈Ӗ��̉��������B
2023/11/02�lj��F
�@�֑��F
�u���@�@���ĎR�Ō������N�v�i�p���t���b�g�j�ł́A�A����Ƃ��āu��229-0105�@���͌��s���͌Β����5-15�v���L�ڂ���A�Ō����������Ƃ���A�Z�E�����L�ڂ����B
�@���������A�Z���u��229-0105�@���͌��s���͌Β����5-15�v�́u��252-0175�@�͌��s�����T�v�Ƃ��Č��������̂ŁA���݂͍��L�ɏZ���\�����ύX����Ă���̂ł��낤�B�f�����������l�����Ȃǂł́A�����ɂ́A�u���@�@���،��Ёv�����݂���B
�@��GoogleMap�Ŏʐ^������ƁA�Z�V�炵����F�Ƃ��ׂ̗Ɂu�����z�[���Ō����v�̊Ŕ��f�������z�i���V�z�[�����j������A�ꉞ�@���{�݂ł͂���l�q�ł���B
�@�����،��ЁF�u���@�@���@��Ӂv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A���Ԃ��s���ł���B
�@�������A�u���@�@�|�[�^���T�C�g�v��u���@�@�_�ސ쌧��ꕔ�@�����v�̊Ǔ����@�ꗗ�ɂ́u���،��Ёv�́u��252-0244�@���͌��s������c��6105�|3�v�ƏЉ���B
�@���̏Z������������ƁA��{�I�ɂ͎��@���̍\���ł͂Ȃ��A�Z��̂悤�Ɍ�����B�����A�@���Ǝv������ɐԒ������K�������A���邢�͂��������،��Ђł��邩���邢�͌��Ђł������̂����m��Ȃ��B
�@�������z�[���Ō����F���V��Ƃ��đ����̍L����Љ�Ȃ���Ă���̂ŁA���V��Ƃ��Ă̎��̂͂���Ǝv����B
�@���̒��ɂ́u�Ō����Ƃ́F�Ō����͓��S���l���B�����Ƃ��āA�]�����߂����ꂽ�����ł��B�v�Ƃ̏Љ������̂ŁA���������E�Ō�����������J���Ƃ��A�E�Ō��������،��ЂɎ�荞�܂ꂽ�E�E�E�Ȃǂ̐������ł��悤���A������ɂ���A�v��������ł͎��Ԃ͕s���ł���B
���H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�@����234�`
���c�_�i�Ύ��j�������J����B
�v�ہE�k��E�_�s�E����E�J�Ái�Q�����j�E�{�i�Q�����j�Ȃǂɂ���B
�k��ɂ͎R���E�ٓV�i�Q�����j�E�����E�O�\�Ԑ_�̌Ђ�����B
�@�����̑��͊���
�@�Ȃ��A���R����k�֓�ʑ��֔����鑽�ÎR�c���̓r���Ɂu�����V���v�i�u�Α��������ݐ}�v�j�ɂ��邪�A�܂������s���A�ʒu���s�ځB
�������������쒆------------------
�@�@�@�@���쒆�Α��������ݐ}
�@�@�@�@���@�����쒆�d�ː}
���������R�܌��}
�@�����R�ꑰ�ƕs��s�{�m�i���R�E���[�E�����E�b���E�����j
�@�@���R�i����@�E������@���A��^�P�S���A�勝�O�N(1686)������\�O����j
�@�@���[�i�����@�j
�@�@�����i�����@�E�k���������P�P���A�ђ˖@���j
�@�@�b���i���ۘZ�N(1721)���䓇���߁E�����O�N(1738)�䑠���֓��ցA���ی��N�h��(1741)���������j
�@�@�����i���ۘZ�N(1721)���䓇���߁E�����O�N(1738)�䑠���֓��ցA���܉���(1755)�܌���\�O��(���ܓ�)��j
�@�@�@�b���E�����͋����̏o�����ł���́A�@���͍���A�@���͕s���ł���B
�@�@���̑��A�m��ꂴ��s��s�{�m�����������Ɛ�������Ă���B
���u���Ò��j�v/�n��j��/������/�쒆(�݂Ȃ݂Ȃ�)�����̎x�z�ҁ@���
�����R�܌��}
�@���{�������ƕ�n�̊Ԃɂ��鋌�X����k�ɐi�ނƁA��≺����̓����ɖk�ʂ��ē��c�_���J���Ă���B
���̎БO�𓌂֓������Ƃ��낪��n�ɂȂ��Ă��āA���̒����Ɏ��f�Ȃ��畗�i�̂��������Ă��Ă���B���ꂪ�Ō�̚≪��i���k���̍��Ɍf�ځj��ŁA��̌܌��}�̑c�Ƃ����镽�R�Z�Y�E�q��ыG�M�̕�ł���B
�@�@����̎ʐ^�f�ځF�s�N���ɕt���s�]�ځB
�@�@�����̕��R�Z�Y�E�q��ыG�M�̕��̏ꏊ������ł��Ȃ��A�k�����ɕ��R�ƕ揊�����邪�A���̊W���s���B
�@�u�@�@�@�a���`�����@�@�r�@�a���@����@���R�Z�Y�E�q��ѕ_�@�c�����p��(1602)�l����\�O���v���̂悤�ɍ��܂��B�u�@�r�@�v�͋G�M�̕v�l(�ʑ����약�ɉ��̓ŁA�v�ɐ旧�����\�l�N(1595)�ꌎ�\����v)�̂��Ƃł���B
�@�G�M�̒��j�G�Ƃ́A���ƂƂ��ɖ{�c�����ʂ��ĉƍN��菵���ꂽ���A�u�����C�s����Ƃ���v�Ƃ������Ƃł���ɉ������A�э��@�S�̖����ȂƂ��A����(����)�ƂȂ�c���O�N(1650)�����\���A�Z�\��Ŗv�����B�@���@���@�����B
�@���̋G�Ƃɋ�l�̎q��������A���̓��̎l�l�����Ƃ��A�{�Ƃ��܂߂Č܌��ƂȂ����B���ꂪ�u���R�܌��}�v�̏��߂ł���B
����
���j�G���A��j�L�m(����݂�)�A�O�j�F���A�l�j�L���A���j�g�d���u���R�܌��}�v�𐬂��B
��Ƃ𐬂��Ȃ�����
�ܒj�͏o�Ƃ��āi���k���j���\�l�������@�����哿�ƂȂ�A����Z�N(1678)�\�ꌎ�Z���Ɍ\��Ŗv�����B
�Z�j����(����Y)�͓L�ؕ��R�������q�����̗{�q�ƂȂ�A���|�������i�����Ɍf�ځj�̖������������B�����\��N(1672)�Z���\�����Ɏl�\��Ŗv�B
���j�͏o�Ƃ��đ�(�I�����E���݂͍���s��)�@���R�^�\�l��(�܂��\�A�\�ܐ��Ƃ�)����@���R�哿�ƂȂ�B
�@�^�͕���{�y���̖������s��s�{�h���M���ł���B
�勝�O�N(1686)������\�O���Ɍ\��Ŗv���Ă��邪�A�s��h�m�Ƃ��Ēe�������L�^�͌����Ȃ��B
�����R���ƕs��s�{�h�i���䓇���l/�b���E�����j
�@�����Ŕ��j���R�̂��ƂɊ֘A���āA���R���ƕs��s�{�h�Ƃ̂��Ƃɂ��ĐG��Ă����B
�܂��s��s�{�m�ł��邱�Ƃ��͂����肵�Ă���҂Ƃ��āA������@���ł������������R������A�G���̎q���Y�E�q���(�`��)�Ƃ��������@���[�͗��߂ɂȂ��Ă���B
�L�m�̑��L��(�b��)�E�s���q(����)�Z��ɂ��Ă͌�q���邪�A�F���n�ł͑��̐����q(�����@����)������A��N���Ì�Ɏd�������E�q��G�F�́A�~�P�@����(�i���k���j�������\�ꐢ�E�ђ˖@���E�ʑ���)�ɂ��āu�\�J�J�t�i���v�Ƃ��Ă���B
�ߋ����̒��ɂ��s��s�{�m�̖��������L����Ă���A�����̏��炵�āA�����~�߂邱�Ƃ͂��Ȃ��ɂ���A�������̐M��҂��������Ƃ͗e�Ղɍl�����邱�Ƃł���B
�@�����Ɉ�ʂ̌Õ���������B
�@�@�@���䓇���l
��A�����呠����l��̕��@����������S�쒆���@�S�������q�y�́@�b��
��A����̕��������S�����@�S�������q�O�j�@����
�@�E���m�́A�����l�P�E�q���s��s�{�j������ȃj���A���O(��)�����֓��ֈt�A�������l���n�A�O��ɍ]�˕֑D�j���������\��B���֏ؕ��g������V�����j���u�\��B���א\��@�z�����@�ȏ�
�@�@�@�����l�N(1739)�㌎�\�l��
�@�@�@�@�ē���Z�Y�l������@�䑠��
�@�@�@�@�@������q��l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_��@���l
�@�@�@�@�@�x���K���l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㌩�@�����q��
�@�@�@�@�@���؋��ܘY�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@�r�E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�䑠��������Õ����ʁA�I�R�y�g��)
�@����͌b���E�����̗��m�����ۘZ�N(1721)�\�ꌎ�ɔ��䓇�֗�����A���߂̐g�Ȃ��痬�l�̑P�E�q��ɕs��s�{�����߂���(�Ƃ�)�ɂ���āA�����O�N(1738)�����ɁA�䑠���֓��ւ��ɂȂ����Ƃ��̋L�^�ł���B���䓇�ɏ\���N�A�䑠���ֈڂ���Ă��炻�ꂼ��O�N�Ə\���N�̌�Ɏ��S�A���͓����Ɍ������Ă���B
�@�@���莝�������i�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�ł͔��䓇���m�A�䑠�����m���Ɍb���E�����̗��m�̖��������Ȃ��B
�@���̌b���E�������m�͌܌��}�̈�L�m�n����o���s��s�{�m�ł���B
�L�m�̎q�L�P�͔��u�q(��ɊۉE�q��)�Ƃ����A���̒��j�L�����b���A���j�s���q�������Ȃ̂ł���B
�n������щߋ����ɂ��ƌb���́A�c���O�V���Ō�ɋg���q�Ƃ����A�O�\��̂Ƃ��m�ƂȂ��Ă���B
�u�b���@�t�@���R�L�P���q�g���q�L�����@���ی��N�h��(1741)��������@�Z�\��Ζv�v�B
�����͗c���T�V���A��Ɏs���q(�s��)�ƂȂ�A��\���̂Ƃ��o�Ƃ��Ē����h�тɊw��ł���B
�ߋ����ɂ́u�����@�t�@���R�����q�L�P���j�s���q�@��\���Ύ��@�t�g��@���܉���(1755)�܌���\�O��(���ܓ�)�Z�\��Ζv�v�Ƃ���B
�o�ƂƂقړ����ɔ��䓇�֗����ꂽ���ƂɂȂ�B
�@�s��s�{�h�ɊW�����؋��̂��ׂĂ�j���A�B����������̂��̂Ƃ��Ďc���ꂽ�M�d�Ȏj���ł��邪�A���R�Ƃɓ`���ߋ����̒��ł��̌b���E�����ɂ��Ă͂��ꂼ�ꖼ�O�̈ꎚ�����A�b���E�����Ƃ��̖��������ւ����Ă��邱�Ƃ�t�L���Ă����B
���������쒆�E�����h�сi���{���j
�@�����������h�сi���{���j
���������~��l��
�@�������h�ъJ�u�E�J�c�d�_�@���~���ɂ���B
���������쒆����R�������i���̖������j�@����76�`
�@���������ł͎��̕s��s�{�m���m����B
�@�@�P�V�����^�i���薭�����w�������E�����a�����\�㐢�j
�@�@�Q�O�����q(��C�E����k�щ���A����\�㐢�A�c�R���o�����l��)
�@�@�Q�P������(�ʑ��@�؎��l��)
�@�@�R�X������(�h�ѕS��\��)
�@�쒆�����h�R�S�S�Ԃ̂Q�ɏ��݁B�Z���́u��(�݂�)�̎��v�ƌĂԁB
����R�ƍ�����B�ߐ��ɂ́u�֓��̐G���v�ł������B�i���֓��Ƃ͂ǂ��܂ł͈̔͂ł������̂��͕s���j
���R���E���N
�@���\�W�N(1695)���ˌ����������i�T�j�ł�
�@�@���ɂQ�W�����������ˌ����̗v���Œ�o���������ł���B
�@�@�@����R�������R�����I�i���̊����͕s���j
�@�k������S��絍�����䖭�����ҁA���@��F�V��l�A�刢苗��z��V���ُ�l�J��V�����B�t�������c���ЊہA�����[���M�����ꊯ���{����(�}�})�B�c������o�b�ԁA�w����s�V�x�m�S������V�ʓ��A�Z�z��[���̉z�㈢苗����B�����@��F���ԑޑ��V��A����t�����_�@�`�@��܁A�I���@�t�V��k�B��玆�����ߕ����ߏ��ē����s�q�A�h���L�H�A����������ߓ����s�q�@�ʓ��z��[���s�큡�����@���ɗ\�V�g�L���g�]�]�B�����������s�q���V�i���q�ǁB�َt�t�V�U�z���L�ҁA���t���쑍�h������F��擹��A�����R�h�R������B�t�����x�m�R������瑖�ړ����`�A�ち���V������������l��ᥖ{瑈�v�V���`��������ɒ��������R�㗈�k���哈��n�ꎛ�A�H���~�R�������B�������@��F�O����N�l�������^�َt���䶗��A�����_���e�A�@�t�⍜�A�����ߑ����`�H���H�^�c��A�@�c�ё��َt��A�쎝�V�����`�ݘ����B�����l�S�N��玆��B������V�{�����^�h�������ꎛ�H�B�R���ȍ��������R���h�ҁA�]�������R�ғ����������A�������h���@��������B�̑y�����������w���R�V���ʘ����R�B���ڕ����@�����@�����I�^���R�����V����A嫑R�ȓ��@�c���̒��R�����������������@���R�����m���ؐցB���̍��������A�ߗ��@�`�V���A�A�r�p��݉ߔ��U���A���L���S��B���̔\���ڑ������W�U�z���L�֘^���[�T����
�@�@�@���\���N����(1695)�Z��
�@�����@��z���˒��[�����������V���W�^�]
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����R�����������L
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���s�ؔV
�@�@��A���O�E�@�@�@�@�@�@�]�����n�@�@�@�@�@��A�����@�@�@�@�@�@�@�@�}�O���
�@�@��A�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꌬ�@�@�@�@�@�@�@�@�@��A�����@�@�@�@�@�@�@�@��P��
�@�@��A�x�z���@�@�@�@�@�@�@�����P���@�@�@�@�@�@����V���@�@�@(�ȉ���L)
�@�܂��A
�w�������@���ג��x�ł͎��̂悤�ɂ���A�R���ɂ��Ă͂��̓��e�������ł���B
�@�@�@��t���lj��X��������S�����쒆�����h
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�،o����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@������
��A�{���@�@�@�߉ޖ���
��A�R���@�@�@�����Q�N(1300)���@��l�m�����يJ��i���B���كn�����m�M�����m���i���B���V��@�m�m�j�V�e�A�x�m�S�����m��m�ʓ��^���V���A���@��l�n�@�|�����m�ۃj�e�A���X�@�`�����_�V�I�j���@��l�j�A���Z���B�˔V�����m�ߎ�E���m���ߏ��ē����s�q�{���e�A���ك�����j�i�w�����X�B���j�h�k���L�g�]�t�҃A���A���ك����P�e�㑍���h�m���j�����A��F�������Z�V���`�����R�h�R�����i���B�R�V�e��A�������哈��j�����ꎛ���n���V�A���~�R�������g���N�B������كm������E�i�����m�����������j�ڃV�A�R���������e�����R�������g���N�B�����Z�S�N�j�����g�X�B�̃j�O���Q�N(1279)�l�����@�������كj���P�����^�����䶗��A�������j���@��l�m���M�i�������j�����j���݃Z��
�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ����ԁ@���s���ԁ@�@�@�@�@��A�ɗ��Ԑ��@�Ԍ��Z�ԁ@���s�E��
�@��A�q�a�Ԑ��@�Ԍ���ԁ@���s���ԁ@�@�@�@�@��A���O���@�@�Ԍ���ԁ@���s���
�@��A�y��@�@�@�Ԍ��O�ԁ@���s��ԁ@�@�@�@�@��A�R��@�@�@�Ԍ��Z�ԁ@���s�l��
�@��A�o���@�@�@�Ԍ���ԎO�ځ@���s��ԎO��
�@��A�����ؐ��@�O��S�l�@���L�n��l��
�@��A���������@��F�@�������A�{���@�������F�A�R���@���N(1751�`63)�m�n���@�����@�Ԍ��Z�ځ@���s�Z��
�@��A���O���L�n�@(�ʋL)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�@�ܕS�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�ȉ���)
�@�R�����N�ɂ��Ă̏d�v�ȕt�L�E�ؕ��Ȃǂ͂���������̎ʂ��ۑ�����Ă���A�Q�l�Ƃ��Ă��̈ꕔ�����Ɏ��^����B
��A���@�ё��ɂ���
�@��A�c�����`
�@�َt��F�S�[�N�V�e��������|���V�e�c���ꐿ�q��_�გ�ꋋ�t���j�@�c�_��V���C�_��V�e�m��(�^�})�n�N�A�a�m�F�S�\���X�����[�V�A�̃j�]�j�C�Z�_��V�e���@�J��鮃���������B��X�O�@�m�u����V�A�闬�z���F���ʃw�g�B�j�V�e�䎝�Q�m���A�����n���A���n�����m���i���g�����m�������u�V�e�����T�n�A���@�J��鮍����j�~���A�@�m�s�҃����V�e�m���胒���Z�V���w�V�@�]�]
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����L
��A���@��^���ɂ���
�@�@�@��`���吹�l��ɗ���
�@�@�@�@�@�ߒm���@�،o������(��F)���s���U��
�@�E��ɗ��ҁA�����B�r��䶔��V��a������@[���~����[���ٔV��q]�A�ߒV����V�]↉��Β�����V������R[�㑍���h���@�ؓ���]�L�}���^�V�k����A↔[���ɗ����ܒ��R�O�@����E�����t�䍜���Β�ৎ��́A��t���وȗ���㑊�`�V�Ԉ��u�N�v�����h���V�A嫑R�C���萬�A�V�|���ߕ����ɗ����O���A���������R�@�ԓ���B����y�V�^���גv���d�V���ڐ���V��^�V�Ҕ@��
�@�@�@���N���ΌȉK(��O�O��)�\�ꌎ���Z��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�t���E�@�ݔ�
�@�˓��R���g������ɗ��V���O���@���R�ʓ���[�V���H�L������V�B���E�ݔ�
�O�A���������_���e�ɂ���
�@�@�@�������V����
�@�E���{�ҁA�䍂�c���_����V���m��ĕ��j�e�}�V�}�V��R�\�V�`�w��B�R�ԁA�䍂�c�O�\������V���m��M�^���w�N��b�B���m���������s�\��e�����m�N���A�䔻������A���w�N��j�A�����\�V��B�����Ȍ�B�䍂�c�����َt�w��t���j��B�َt�����E�t�w��t���j�e�A�E�t����������X���`�\�A�����������Ր\����
�@�@�@�O���O�N��1557)�����O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�@�@����(����)
�l�A�R���ɂ��Ă̕t�L�E�ِ�
�@�C�@���H�A�h�R���m���N�j�n�A������l�P�m�@���m�����l�g���j�s�e���_�V����I�����V�e�����s�q�����@�Z�V�����g�X�B
�@�@�s�q�{�e�l�l���ӁA���l�n���j�^���jX�A��l�n�s�����A���������G�A���كi���B
�@�@���G�s�q�m�{�����e�{�@�jX�A�َt�s���I�j�o�s�X�g�]�]
�@���@���E�����j���Z�V��
�@�@��{�]�A���\��n�x�͍��x�m������n���ُd��m���̖�B
�@�@�@�Ԍo�m�̃j��v���A�V����������ĕ������\���j�e�L�X�A���������A���A�A�V���m�O���n�ʕM�g���w�^���A
�@�@�R���j���M�����n�䎩�M(���@��)��
�@�@�@�@������l�N�h��(��O�l��)�\����
�@�@�@�@�@����������c�m���哈�m��A�ז���L�V�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�@�ݔ�
�@�n�@�哈�m��g�ҁA�D�z�{�m�ԃj�e�����g�]���A���A���n�D�z�m����B�����j�~�R�g�]�R�A���A
�@�@���R�哈�m��j�݃����n���~�R�g�]�q�A���m��j�ڃ��e����R�g�����g�]�t���L�m�����ȃe�l���n�A
�@�@���m���~�R�����m�����ȃe�R���g�X���b�B
�@�@�ᛕ�n�E�t��N���ŏ��J蓃m���n���n�����m�����~�R�m���i���w�V�B
�@�@���g�哈�i���g����j�a�e�����g�����b�B����q��w�n�哈�g�n�������m���i���g�]�w���B�ᛕ�n���n�������i���w�L�b
�@�@�@�@���]�A�O�i�j�n�����w�ڃ������n�c�ӏ�g�]���]�B�ᛕ�n��g�]�n���m�c�Ӄm��m�n���j�V�e�A
�@�@�@�@��m�������g���w�V�̍����n�j���e�����g�]����R�g�]�J�A�A�V���N���m�n�����g�]�J�B�s�R
�����ՂƕϑJ
�@���āA���n���̓����͐��a�Q�N(1313)�Ɍ��݂̒n�Ɍ��Ă��A�ȗ��U�V�O�N�ɋy�ԗ��j����ށB
���̒��œ��ɋL���ׂ��������A��㕈�̏��ɏ]���A�q�ׂ�B
�@�J����ق́A���@�ɋA�˂��V��@�����@���A���@�@�̕z���ɓw�߂��̂ɁA�����̒n���E�����ߏ��Ăɒǂ���B
����͓����̊��q���{(���R���@)�����@�@�̐^�����܂��[�������ł����A���@�h�m���̈��������������Ƃ���A�@�Ƃ��Ēe��������Ƃ������Ƃ�w�i�Ƃ��Ă���B���̂Ƃ��A���ق̒Ǖ��ƂƂ��ɑ����̉��@�҂������������A����Ɋւ����A�̎������u�M���@���v�ƌĂԁB
�@�\�ꐢ����i���ȗ��j
�@�\�ܐ�����A���R�@�،o���Ƃ̊Ԃɖ{���������߂����Ă̑��_�����������A�����̗R���𗧏��邱�Ƃɂ��q���ƂȂ�A������ؖƏ��ƂȂ�B���R�Z�������̑i��ɂ��ƁA���i�P�X�N(1642)�l���̂��Ƃł���B
�@�\�������^�i���薭�����w�������E�����a�����\�㐢�j�͕s��s�{�M��҂ł��������B���̑�ɖ{���������B
�@�������q(��C�E����k�щ���A����\�㐢�A�c�R���o�����l��)�A��\�ꐢ����(�ʑ��@�؎��l��)���A�Ƃ��ɕs��s�{�m�ł���B
���q�͒����h�ь��\���߂Ă��邪�A�����T�N(1665)�\�ɁA�ɗ\�F�a���֗��߂ƂȂ�B
���̔N�́A���{���s��s�{�����@��ƒ�߁A���Ɨ����ꎛ�Ƃ���ꂽ�㑍�h�R�����Z�A�B�����o�H�V��ɗ��߂ƂȂ�ȂǁA���n���́u�����̑y�Łv�Ƃ���ꂽ�@��̗��������r���B
�@�����ɂ�����s��s�{�m�́A���ʂɉB�ꂽ���̂͒m��悵���Ȃ����A�O����������Ė��a�X�N(1772)�ɖv�����O�\�㐢���������h�M��҂ł������Ƃ��납��݂Ă��A���������Ԃɂ킽���Ă��̖����������Ă������̂Ǝv����B���̈�ʂ̌Õ����������̎����@���ɕ����B
�@
�@�@�@�s��s�{�ᗐ�V���V����
��A�������������܃g�m���\�T�Y�@���F�n�s��s�{�m�@���i�s���ϔV�N�����疖�j���������N�h�N(1661)�����g�C�@���R�ꌋ�V�O�h�@�h��
�@�@�ʐ��@�@�~�N�@�~�s�V�@�_�萳���@�@��b�^�V�@�����ƌ��V�@�э����V�i�����̕����͕s���j�@�v�쒪�����@���O�n�@�����@���R�@�����@�ؓ��@��x�@�{�@�g�c�@�R��@�_��@�ؐρ@�ёq�@���{�@��@�с@���Ӂ@�����@�Ўq�@�{����@����@���@�ʍ�@�э��@��z�n�@���@�ۓc����
�@
�@�x�d�Ȃ錵�����e���ɑ����A���̂��ׂĂ�铽���A��ʂ̖��O�܂ō�����Ė��v��������ɁA�悭�����̕�����ۊǂ������ƁA���Q������̂ł���B
�@��\�ܐ����G��ɖ{���E�������������A��\�������@�̂Ƃ��勝��N(��Z����)�ɏ����ƞ����A���\�\�N(��Z�㎵)�ɋq�a�����������B
���̞����͑��풆���o���ꂽ���A���̖������܂�Ă����Ƃ����B
�@�i�������͊����ɕt���A�ȗ��j
�@��\���������̂Ƃ��ɂ́A�������ŏo�J��������B
�@�O�\�������ȍ~�A���ƒ����h�щ���̌𗬂��p�ɂɑ����B�i����̗�͏ȗ��j
�@�O�\�㐢����(�h�ѕS��\��)�́A�s��s�{�m�ł���A�O�匚���̎��ւ��c���i��q�j���A���̐Γ��ƕ����̋��{��ɂ́A���̂悤�ɍ��܂��B
�@
�@�O�匚���@��V�����@���h�O��@���\�M�C��(1760)�O����
�@���R�晿�㐢�����@����������t�O��@�������O���O��@���y�@�~���@�@������@�o�n�@�s�P�@�ȐM���C�@���R����c��X�@�{���@���Z�������吹�l����
�@�@�@���a��p�C�N(17772)�\����\�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���b�l�@�����@�d���q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R����@�����R����@�����@�������l
�@�i���ȉ��̗��͏ȗ��j
���������@�{�����w
�@���w�ɂ͎��̑������J����B
��Ȃ��̂͌�{���E�듃�����E�l�m��m�l���E�@�c�����͏\�l��A�����Q�N(1300)�J��̑c�t���@���A���ٍ�̓��@��F���A�@�c����_��̓��@����@���A���@��^�����~�q�E�S�q��_�E�ٍ��V�E������m�E�V���V�_�E���فE���e�E������[�E��Ëv�V�Ȃǂł���B
�@�����ŁA���q�̂��̂Əd������_�����邪�A�����Õ����w�R�������u�x����u����V���v�̈ꕔ��]�L���Ă݂�B
�@�@�i���ȗ�����j
�@����F�Βi��o��߂��Ƃ���ɂ���B
�@�E��̑�ڔ�F�u�얳���@�@�،o�@�����@�����R�@�{���M�j��������P�@�ċ�ᢊ�哌�J��Ғ��@�����P�R�ݕ��q(1816)�������U�l�\�ܐ����m��v�Ƃ���B
�@�R��F�d�w�A10.8�~7.2���B��K�����̐��ʂɁA���Ôˎ叼�����̉Ɩ�ł���~���䂪�t�����B�����͏����Ƃ̕�Ƃ��āA�\�㏟���Ȍ�̕�肪���Ă���B
�@�R�卶���n�F���̉��Ɂu�J�R���ِ��l�@�������h��N(1311)�Z����\�Z���v�Ƃ������͂��߁A���Z�E�̕�肪���R�ƕ��ԁB
���̗���ɑ����Ĉ�Q�̔������B���̒��ōŌÂ̐Δ�ɂ͎��̂悤�ɍ�����B�u�J�R����m�s���p���l�@���i�R�OᡙǍ�(2423)�����\������@���iᡁ@��(1773)�O�S�\�����V�䌚���@�`�@���E�v�B
�@���p���l�Ƃ́A�쒆������(������)�ɂ������ʏ��@�^�̊J�R�ŁA���E�͌�̏Z�E�ł���B
���̐^�͖���������(����)�ŁA�������́A�����E�x�z���@�R�U�J���Ɋւ��鎷�����s���A�h�Ƃɑ����ʓI�Ȏ����ɓ����ł���^���������Ă������A�����P�V�N�ɔp���ƂȂ�A�������ɍ��������B
�@���O���F�ĎO�C�z�̋L�^�͂��邪�A�勝�Q�N(1685)���������̎p�����ɓ`����B�����̖��͑O�q�̂Ƃ���ł���B
�@�{���E�ɗ��F���ǂɈ͂܂��B�{�������ɂł���B
�@�V���{�F��������������쑤�ɂ���B�����J�����̒��ɐ{������A�u�ێ��Éi�܍ݐp�q(1852)�[���ܓ��@�����V�v�ƁB�БO�̐Α���ɂ́u��[�@�M�q���@�c�����Ή��N(1865)�㌎�v�Ƃ���B�܂��Љ��̒��ɉi���U�N(1434)�̑�ڔ�A���Ɏ�q�肪����B���̑��~�������̌����̈ꕔ������A�{�����͖{�����w�Ɉ��u�����B���̎Ђ��A�^�ɂ������̂��ڂ������̂ł���B
�@�������F�V���{�ƕ��ԁB��������h��̏����ŁA��͂葸���͓��w�Ɉ��u�����B
�������͂����܂ł��Ȃ���t���̎��_�ł���B�����Ő�t���Ɠ����̂������������ʂ̌Õ����������Ƃǂ߂Ă��������B
���̖������́A���Ă͋��������̗ђ��ɂ��蓌�J�Z���̎��_�ƂȂ��Ă����̂��A�����Q�P�N�Ɉڂ������̂ł���B
�@�i�������͏ȗ��j
����ړ�
�@�V���{�ɕ���œ��̑�ړ������B
���̈�̔�l�̂��̂ɂ͎��̂悤�ɍ��܂��B�u�얳���@�@�،o�@���a�T��q(1768)�\�O���u���@��J�ጺ��ܐ畔���A�@���c�ܕS�����@����������ꖜ���@�V�����N�N(�P781)�\���\�O���@�l�\�O�����I�v�Ƃ���A���ʂɂ͊J�R���ق���l�\���`�܂ł̗�㖼���A�L�����B
�@������́A������R���]�̂��̂ɂ́A�@
�u�얳���@�@�،o�@���@���F�@���������@������@�F禱��c��X��ʁ@�ߍ]���^������������@�F禱��c��X�K�����q��ߍ]���������@�����@��������@��䎮���@���@�@�a���M�����@���h�@�a�������@�I�����~�M�@�@�����[�@�B�M�@�������@�@�[�J�a�d�Y�F�@�t�R��Ӂ@�[�S�@���E����@������l�Y�F禱�@�јQ�F���Y�F禱�@�ݎ��F禱�@���߉����l�Y�@���ʂ���P���q�@�u�@�@�������Y�@�n�ӎ��F禱�@�_������@�����@��c��X�@�{�@�@�Z�~�����{��{��@�i�Z�@��������@�z�K���d���@��c��X�@���鎁�F禱�@��c��X�@�{��@�{��l�@���B�L���S�]�ˉ��J�r�V�[�������������ȁ@�P�C�@���S�����@�P���@���O�����@�S���@�b�ρ@�b���@�����~�q�@�@���@�����ю��F禱�@��c��X�@�ꐫ�@�@�C�����@�t���@���Z�����@���Z�v
�@�ƍ��܂��B
������(�v��)�ƕ揊
�@��ړ��̉��ɁA��i�����_�Ɉ͂܂ꂽ���Q������B���ꂪ�����Ƃ䂩��̐[�����Ôˎ叼��(�v��)�Ə\�㏟��(�̂�)�A�\��㏟��(�Ȃ�)�A�\�O�㏟�e(����)����т��̉Ƒ��̕揊�ł���B
�@�i���ȉ����j
��������
�@�i�����̍��͏ȗ��j
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
���R�@�،o�����A�����W�B
�{���Ƃ��ē����P�A�����P�R�A�x�z�����@�Q�V��L�����B
�����F
�@�����g�c���[���F�����g�c��
�@�ؓ��R���@���F��������l�����@�ɂ���ĉ��@�B�i��j�������̖����ł���A�܂��������o���i�����₭�j�ł������B
22023/10/18�B�e�F
�@�R�卶��ɕ�n������A���̉��Ɂu�J�R���ِ��l�v��A���Z�E�̕�肪���R�ƕ��ԁB�܂������Ĉ�Q�̔������E�E�Ƃ̂��Ƃł��邪�A�����ɏI���B
�@�����������Q���ΊK�@�@�@�@�@����������O��ڐ��F��ɖ����f�ځA�����P�R�ΔN�I�B�@�@�@�@�@��������������
�@�R��͎O�ԎO�˂̔��r�O��A���ʋK�͂�7.89�~4.88���B���ꉮ���A�g�^�����B�����N���̌����Ɛ��肳���B
�@�����������R��P�@�@�@�@�@�����������R��Q�@�@�@�@�@�����������R��R�@�@�@�@�@�����������R��S
�@�����������R��T�@�@�@�@�@�����������R��U�@�@�@�@�@�������R���V���P�@�@�@�@�������R���V���Q
�@�����������R���@�@�@�@�@�������{���E�ɗ�
�@�������{�����@�@�@�@�@�������{���P�@�@�@�@�@�������{���Q
�@�������ɗ����@�@�@�@�@�������ɗ��P�@�@�@�@�@�������ɗ��Q�@�@�@�@�@�������������F�V���{
�@�������������P�@�@�@�@�@�������������Q�@�@�@�@�@�������������G�z
�@���������O�P�@�@�@�@�@���������O�Q�F���a�U�N�̌����ƋL�^�����B
�@��������ڐΌQ�F�������ĉE����u���a�ܕ�q��ڐv�u��ڐE���@���F�v�u�V���ڐv�u�얳���e���l�v��ł���B
�@���a�ܕ�q��ڐ��F���͏�Ɍf�ځ@�@�@�@�@��ڐE���@���F�@�@�@�@�@�V���ڐ��F�N�I�R���Ȃǖ��m�F
�@�얳���e���l���F�������\�N�i1488�j�Ƒ��ʂɍ��ށB
�@�v���i�����j�ƕ揊�F�R���͏�Ɍf��
�������쒆�|�юR�������i���|�j�@�@����97�`
�쒆�����|163�Ԓn�ɏ��݁B
���R���E���N
�@���L�ł́A�@
�厡�O�N(1364)�܌��n���j�V�e�A��m�s������l�m�J��i���B���m�n���S�����������A���Ñ��������y�q�����O�P���m�J�c�j�V�e�A�����Z�N(1373)�܌����ܓ����\�j�V�e���ŃZ���B�����R�@�،o������
�@�ƁA�����B
�@�����́A�㑍�Ό����ē����]�猓�j���A�̂��ɏo�Ƃ��ď�݉@�����Ɖ��߂�(�w���ÁE���������v�x�w���@�@���@��Ӂx�̖���R�������Ə�ݎR�������̍��B�w����S���x)�Ƃ��A�ē����j�̎q�ł���(���{���O�\�l����v�@�����L�́w����R���N�x)�Ƃ������A���̖v�N�ɂ��Ă��O���Z�N(1283)�܌���\�ܓ�(�w����R���N�x�w���@�@���@��Ӂx�̖���R�������̍�)�A�����ܔN(1372)�܌���\�ܓ�(�w����Ӂx����R�������̍�)�A�����Z�N(1373)�܌���\�ܓ�(�w����Ӂx�|�юR�������̍��B�w�|�юR�������L�x)�ƁA�O��������B
�@�Ό�������(���Ɩ������A�����Q�N�ɑ������Ɖ���)�L�ɂ��ƁA�����Z�N(1254)�ɗ̎�ē����]�炪����̑����ɏ@�c���@���}���A�ꑰ�������ċA�˂����̂����̑n�܂�ŁA������N(1276)�\�ꌎ�\����ɖ@�������Ă�B
�̂��Ɍ��j�͓��x���ē����ƂȂ�A������(��������)���q�ɑ����A�팓�p�ƂƂ��ɐ��䌴�i������S���䑺���j�ɖ@���c���āA�c�t����(��频c�t)�����u�A��c����т̒��S����ɂȂ����Ƃ����B
�@���̒n���ɗ����������̏ڍׂ͕s���ł��邪�A�@�|�O��ɔM�S�ŁA�����ɗ����̂������ړI�Ƃ��A�E�̎O��������n���������̂ł��낤�B
�@���̒n�́A���̎����i�����|�j�������悤�Ɏ��͈�т͒|�тł���A���Ô˂ł͂����̒|�������āi�����z�j�p�ނƂ����悤�ł���B
�@�@�i���ȉ����j
�������̌������E��
�@���݂̎R��͍��h���ؖ�ł��邪�A���Ƃ̎R��́A���������̏��a������ƍ����ɏ\���i�̐Βi������A�����o��߂��Ƃ���ɂ�����傪����ł���A
�@���̎R�剺�ɑ�ړ�������B
�u�얳���@�@�،o�@���H�P��䑎핧�ʑR�������V�̕s圯���X�@�����l�N�h��(1821)�����@���ܐ����ٓ���@�k�����̓��R�h�z�M�j�����@�������v�ƍ����B
�@�����͂S�O�Q�ŁA���ʂ̖{���͏\����(���q�@�E���ۓ�N(1742)�v)�̂Ƃ��Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ������A�ߔN���C�����B
�@�{������̕�n�����Ɉ�i�Ə������u������A�����ɖ�����������B
���`�ɂ��Ɗ��i��N(1632)�ɏZ�E���傪�����������̂ł���Ƃ����B���̒n�ɂ͐�t���ɑ����Ă�����x��̓ߐ{�����A�V���̗���Ɠ����ɉB�ނ��ēy���A�_�����Ƃ̌��`������A��t�ꑰ�̎��_�ł��閭�����ƂƂ��ɓ��|�ɓ���A��Ɉ�F�����ĂĂ�����J�������̂ł��낤�B
�@�{�������͕�n�ł���B���̉����ʂɓL�ؕ��R�Ƃ̎n�c�}���̕悪���E���̊}���k�ƂƂ��Ɍ��B
�@�}���͖�(��)���E�����Ƃ������A�O�L�≪���G�M�̒�ł���B
�@���̒��S�̘A��ɂ́u���@�@�،o�@���푸�@���c�ʁ@�c���l�h�K�\�\����@���@�@�،o�@�ߏ햾�@������@���i�O����(1626)�Z���\�ܓ��v�ƁA�}���v�w�����܂�A
�@�E�̊}���k�ɂ́u���@�@�،o�@���h�@�a�c�^����ʁ@������O�b��(��Z�l)�O����\�Z���@���M�@���]�������ʁv�B
�@���������ɂ́u���@�@�،o�@���P�@����㚑�ʁ@�������ᡖ�(��Z�O)�l����@�����@�����@�������ʁ@���R�����q����v�Ƃ���B
�@���̓L�ؕ��R���������ɉ����Ɗ�i�����������̌Õ���������B
�@�@�@�i�������j
��Ɖ@�X���������Ë��m�@�������b�q(1744)������\���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�v��@���\���(���āB�����q�A�}���E�v�ᓙ�m�̃A���B�ƃ��햞���j�����A�㐼�@��c�j�d�w���ё��V�A���q�s�r��j�C��R���������n���A�c���������\�Z������i�X�w�L�ؕ��R���n���x)
�@�@�@�i�������j
�@�Ƃ���ŁA���|�̖������Ƃ����Δ�Œm���A���̔N��̌Â��␔�̑������Ƃł͒����L���ł���B
����������
�@�����̔�͑�̂P���O��̂��̂ł���B
�@�U�O�O�N����Ό����o�Ă��邽�߁A���ɖ��Ղ̂��ߓǂݎ��Ȃ��������������A�Ⴆ�Ζ�O�ɂ�����ɂ́A�������̒n�ɌN�Ղ�����t���̈ꑰ����ȉ��̖������܂�Ă���A���ɗ�����Ȃ��M�d�ȕ������Ƃ�����B
�@���܂����ɁA�����A�Y������镶�����̍s�������Ă��Ȃ���A���̑S�������^���Ă������ƂƂ���B
�@�@�@�i���P�P��ɂ��Ė��̋L�ڂ����邪�A���̋L�ڂ͑�ʂł���ȗ�����A�K�v�ȏꍇ�́u���Ò��j�v�̎Q�Ƃ��肤�B
�@�@�@�@�قځu�얳���@�@�،o�v�̑�ڂ𒆐S�Ƃ����ڔ�̂悤�ł���B�j
�������F
�k�����h�R�Ō����Ձ@�������������k����
2023/10/30�lj��F
���u�����j�v�@���
�@�|�юR�������R��E�ΊK
���̎ʐ^�ɂ��A�m���ɁA�R��O���\�i�̐ΊK�ł���A�R�剺�ɑ�ڔ肪����B�R�剜�ɂ͖{���炵���������ʂ�B
�������A����͎R��O�͐ΊK�ł͂Ȃ��A���́u�ʐ^�v��u���Ò��j�v�́u���݂̎R��́A�����ɖʂ����ނ���܁Z�Z�N�͒�����Ǝv���鐙�̎}���ɂ��鍕�h���ؖ�ł��邪�A���Ƃ̎R��́A���������̏��a������ƍ����ɏ\���i�̐Βi������A�����o��߂��Ƃ���ɂ�����傪����ł���v�Ƃ����L�q�Ƃ͈قȂ��Ă���B
�@���ēx�A������v����B
�@��2023/11/30��L�̎�����|�ю��Ɋm�F�B
�@�@���|�������k�F�R��O�͊m���ɐΊK�ł������B
�@���@�̐��������Ɍ����V�S�����J�ʁA����ɂ���J�̎��A�V�S��������R�剺�ɑ�ʂ̉J�������ꍞ�ݎR��O�ΊK������B
�@������_�@�ɎR��O�ɓy�������A�t���b�g�ɂ���Ɠ����ɁA�k���ɏo������݂��A���݂̎p�ƂȂ�B
�@�m���ɁA�ȑO�A�R��O�͐ΊK������A�ΊK������ē��R�����悤�ł���B
2023/11/01�lj��F
���u���@�@���ĎR�Ō������N�v�i�p���t���b�g�j�@���
�@���̃p���t���ɍڂ�����ȗ��Ȉē��}�ɂ��A���Í��{�����������w�Z���瓂�|�����������֖k�シ�邪�A���̒������̓����V�J�ł���B���̓��H�̓����ŁA�V�J���瓂�|�������Ɏ���ԂɁu���퐹�l�B�����v�A���̖k�Ɂu�������Ւn�v�Ƃ̕\��������B�����k�͓��|�������ł���B
�����炭���݂͉��̈╨���c��Ȃ��Ǝv���邪�A��L�Q�̎��@�����������Ƃ��z�肳��Ă���B
�ȏ�A���Y�Ƃ��Ēlj�����B
2023/10/18�B�e�F
�@���|�������ɂ͂P�S��̉����^�肪���݂���Ƃ����B����͉����S�N�i1371�j�`�i���P�O�N�i1438�j�ɑ������ꂽ���̂ŁA���̊Ԃ̗��j��Y�قɌ����̂ł���Ƃ����B
�@���|���������ؖ��@�@�@�@�@�@���ؖ剡��ڐ��F����͐V�������̂��H�A�v�����B
�@���|�������R���@�@�@�@�@�R��O��ڐ��F���ꂪ�u���Ò��j�v�ɋL�ڂ̎R�剺�̑�ړ��ł��낤���H�A�v�����B
�@���|�������{���@�@�@�@�@���|�������ɗ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���|�������������P�@�@�@�@�@�@���|�������������Q
�@���@���F��ڔ肻�̂P�F�{��ڔ�̒�����v����B
�@���@���F��ڔ肻�̂Q�F���̂P�Ƒ������Ă��邪�ʂł���A�{��ڔ��������v����B
�@�������E��㕈
�@������l����F����ZᡉN/������m�s�������l/�܌����ܓ��i�܌����ܓ��͈ꕔ����j�@�@�@�@�@���|��������㕈
�@���|�����������
�@�L�ؕ��R�Ǝn�c�}���ꑰ���@�@�@�@�@�}���ꑰ�����
�@��L�̋L�q�ł́u�L�ؕ��R�Ƃ̎n�c�}���̕悪���E���̊}���k�ƂƂ��Ɍ��B
�@�}���͖�(��)���E�����Ƃ������A�O�L�≪���G�M�̒�ł���B
�@���̒��S�̘A��ɂ́u���@�@�،o�@���푸�@���c�ʁ@�c���l�h�K�\�\����@���@�@�،o�@�ߏ햾�@������@���i�O����(1626)�Z���\�ܓ��v�ƁA�}���v�w�����܂�A
�@�E�̊}���k�ɂ́u���@�@�،o�@���h�@�a�c�^����ʁ@������O�b��(��Z�l)�O����\�Z���@���M�@���]�������ʁv�B
�@���������ɂ́u���@�@�،o�@���P�@����㚑�ʁ@�������ᡖ�(��Z�O)�l����@�����@�����@�������ʁ@���R�����q����v�Ƃ���B�v
�@���|���������F�����ɂ͂P3��u�����B
�@�肻�̂O�P�@�@�@�@�@�肻�̂O�Q�@�@�@�@�@�肻�̂O�R�@�@�@�@�@�肻�̂O�S�F���i�\�ܔN�܌��\����̔N�I
�@�肻�̂O�T�@�@�@�@�@�肻�̂O�U�@�@�@�@�@�肻�̂O�V�@�@�@�@�@�肻�̂O�W�@�@�@�@�@�@�肻�̂O�X
�@�肻�̂P�O�@�@�@�@�@�肻�̂P�P�@�@�@�@�@�肻�̂P�Q�@�@�@�@�@�肻�̂P�R
�������쒆���h�R�������@�@����113�`
�@�쒆����1711�Ԓn�ɏ��݁B�����R�@�،o������
���R���E���N
�@���݂͓��@�@�ł��邪�A���Ƃ͐^���@�A���S�����̒n��z���̂Ƃ��A�k����Ɠ�����̒�a��N(1346)�ɉ��@�����Ƃ������邪�A���`�ɂ��ƁA��c���̎��t����͋����ѓy���ɍ\���A���̒���_�ł��鍂�c�̖����Ђ̕ʓ���S�V������Ɍ��ĂċF�菊�Ƃ���(�܂��A�����А����̎��R�ɋF�菊�����Ăĕʓ����Ƃ����Ƃ�)���A���ꂪ��̓������ł���Ƃ����B
�@���������c�����Ё��������Ò��̖��������Q�ƁF�����Е��c����ɓ������ƂȂ�Ƃ����B
�@���u����E���S�E��t����E�œ������E�����E���S�R�������E�����v�̍����Q��
�����āA���@�ƁA�������ɂȂ������������w���{���Õ����x�͎��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@�@��A�������ËL�����l�ӂ�ɁA����(���{��)�͐����E�×�(1324�`29)�̍��A���R�O����s�@���S���l�O����䇈��Ȃ�B
�@�@�H(����)���t�������𑍂̈��v�R�ɔ���B���E(�v��)�����߂��B��t�������c����̂��B�l��c�a(���E�a)�ƌĂԁB
�@�@���������ɏ�f��z���B��X�S�t�����ď��ɕ���ɓ���B�t�̍u����J���ɁA�����ɖ��@�̎������ȂĂ��B
�@�@��t��玆�ɉ��Ďn�߂ėS�t�ɋA���A�����яo(�}�})��^������@�ؐ��ɂƉ��ށA���œ��������Ȃ�B
�@�@����q�𓊂��ē㔯�����ށB�t������Ɉ���̓��ȂāA���������ƞH�ӁA������ƞH�ӁB(�ȉ���)
�@�܂��A�������R���ɂ́A
�@�@�����n�������N(1368)�l�����R�@�،o����O�����S��l�m�J��i���B
�@�@���^���@�j�e�쒆���ѓy�����t��������m�F�菊�i���B
�@�@���N���S��l�@�|���O�����g�~�V���n�j�����A�K�X�ѓy��m�Ӄj�e����j���q�|�v�������X���n�A
�@�@�ڃj�A���V��q�����S�j���V�o�ƃZ�V���A�Z�������g�C�q�탒����g�C�t�B
�@�@�˔V���m�Z�E���C�@�A���V�������S�j�����A���@�V�e���C�����g�����������S�m�k��g�i���j�˃��e���S�m�J��g�X�B
�@�@������n�t�m�ヒ���L�@�O�M����i�����ȃe���@�m�^�M���ꕝ�����P�����A�������j�`���Z���B
�Ƃ���A���̔N��ɂ��Ă͈٘_������悤�ł��邪�A�J��E���@�͓��S�ɂ���ĂȂ��ꂽ�Ƃ���_�ɂ��ẮA�ߗב����@�̏ꍇ�Ɠ����ł���B
�������̌������E�Δ�
�@�����̒ؐ��͂T�Q�T�Ƃ����A���F�̈�ɖ����Ђ��J����B
��t���ꑰ�̎��_�ł��邱�Ƃ͂Ƃɒm���Ă��邪�A��h�z��t���傪���̕��^���F�O�������̂ł��낤�B���ɂ͓������̉Ɩ�ł����s�����t�����B
�@�����БO�E�R��E��ɔq�a����̎��ʓ�������B�{���͎��ʓV���ŁA�g���R�v�����̒���Ƃ��ē��@�̍�����N�����ʎR���J���Ĉȗ��A���@�̎��_�Ƃ���Ă���B���O�̘k���͓V�����N(1787)�ɑ��l����i�������̂ŁA����ۑ�����Ă���B
�@�����̍����ɂ��鏬�K�́A�Г�����̐_�Œm����Õ��_�Ђ̕��ЂŁA���q�͖��N�O���̑�Q�l�ɂ���ČÕ��{��(�Ȗ،�)�̂��D����Ȃ�킵�ɂȂ��Ă���Ƃ����B
�@�R��O�̐Γ��ɂ́A���̂悤�ɍ��܂�Ă���B
�@�u�얳���@���F�@�ܕS�������ĎR��\�Z���X���@�����㑢���@��ܕS�Β��@�A�闬�z�@�y�h���@���i��������(�ꎵ����)�����@�{��l�@�@���@���J�Z���q�@�@�r�E�q��@�W�l�ȁ@�@�J�ÉE�q��@���J���E�q��@���J�ɏ��@�{�����q�@���씪�@�œ`���Y�@���@�@�@�@�����q�@�W�l�Y���q�@���r���q��@���J�����q�@�œ����q�v�@
�@����́A���@�̖v��܁Z�Z�N�ɂȂ낤�Ƃ���Ƃ��A���̉���̂��߂Ɍ��Ă���ڔ�ł���B
�@�{�����w�ɂ͖{���̎߉ޖ����͂��߁A�꓃�����l��F���́E���@���l���E�S�q��_���E�����V�����E���������Ȃǂ����u����A���@��������䶗�������B
�@�����ɂ͗��Z�E�ق��̕�n������A����(1652�`54)�A����(1658�`60)�N��̐Γ������������钆�ŁA���̎O��̔�(��������������̂���)�͎��̂悤�ɍ��܂��B
�@�@���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E��������O�N��
�@�@�@�@�@�@�@�얳����@��
�@�@(�V�W)�얳���@�@�،o�@(�@��)
�@�@�@�@�@�@�@������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i��N(1402)���@(��)����
�@���
�@�@�@�@�@�얳��s���Ӎs��F�@�E�u�҈הߕ�
�@�@�@�@�얳����@���@�@�@�@�@�@�^��u��\�O
�@�@�@�얳���@�@�،o�@�@�@�@�@�N������
�@�@�@�@�얳�ډޖ���Ł@�@�@�@���T���@�E
�@�@�@�@�@�얳��s�����s��F�@�@�������v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�\�l�V(1407)������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�q��(���͓�)�h��
�@��O
�@�@�@�@�@���\�ܔN�h��(1461)�����\����@�������@
�@�@�@�@�厝���V��(�s����q)�@�@��A�ړV��
�@�@�@�@�@�@�@�@��ٓ��@�偡�@�@�@����
�@�@�@�@�@��ُ�s�ٕӍs��F�@�@�����@�@�@���~
�@�@�@�@��ّ���@���@�S�q��_�@���h�@���@
�@�@�@�얳���@�@�،o�@�����@(�ԉ�)�@�����@����
�@�@�@�@��ف��ޖ���Ł@�\�������@�����@����
�@�@�@�@�@��ُ�s�����@�@�@�@�@�@���~�@�S��
�@�@�@�@�������V��(������q)�呝���V���@�����@���P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���S�@
�@���̔�̔N���u���\�v�͂S�N�̏\��\����܂łŁA�u���\�T�N�v�Ƃ͉��������u�����Q�N�v�̂��Ƃł���B���Ε���Õ����ɂ́A��������ȑO�̔N�����g����͂悭������B
�@�Ȃ����̔�́A���Ɠ��J�������ɂ��������̂ł���Ƃ����B
2023/10/18�B�e�F
�@��ɂ��Ă͒��ӗ͎U���Ō��������Ă���B
�@�������R��O��ڐ��F�����͏�Ɍf�ځA���i�V�N���@�ܕS�����B
�@�������R���@�@�@�@�@�������{���E�ɗ��@�@�@�@�@�������{���@�@�@�@�@�������V�ɗ��@�@�@�@�@�������웏�a
�@���������ʑ喾�_�@�@�@�@�@�@���ʑ喾�_�{�a�@�@�@�@�@�������Õ���
�@���������揊�F���̌Õ�S��i�s���@���P�A�����@����A�����@���r�A�R�T���ח�@�����j�̕�肪������A��㕈���Ȃ��������͕s���B
�������쒆�퍂�S�R�������@�@����117�`
�@�쒆�����J1850�Ԃ̂Q�ɏ��݁B�����Ó��{������
���R���E���N
�@���@�@�ŁA�h�Ƃ͂T�T���قǂł���B
�R�����N�ɂ��ẮA�Ђɂ��Õ����ނ̏Ď��̂��߁A���̏ڍׂ͕s���ł���B
���{���R�R�������ɂ��w�k�єN�v���x�ɒf�ГI�ɋL�^����Ă��邪�A�����̗��j�͏�ɓ��{���ƕ\����̂ł���A���e�I�ɂ��d������Ƃ��낪�����B
�@�@�����킹�āA�������{���i�����h�сj���Q�Ƃ��ׂ��B
�@��c���̎��t���傪�����E�×�̂���(1324�`29)�A���R�@�،o���O�����S�ɋA�˂��ėP�q�Ƃ��A����ɑ��̓�q(������P�q�Ƃ�)������E����Ǝ����̖����^���ē��S�̒�q�Ƃ���B
�����Đ��J�Ɏ������Ăē��S���J��A�������Z���Ƃ��āu���S�R�������v�Ɩ��Â��A����������đn�n�Ƃ���Ƃ����B
�@�@���@������E���S�E��t����E�œ������E�����E���S�R�������E����
�@�V���P�T�N(1587)�ɓ��S�̎q���E���R�P�O��̓�俒�͋��s�������ю���b�Ƃ��a瀂ɂ��A�������I�ɉB�������߂��A���̎q���T���ē������Ɉڂ邱�ƂɂȂ�B
�@�@�����R�P�O��̓�俒�@�����R�@�،o���E���R��俒�E���b
�@�@���䖭�����E�����������b�ɂ��Ắ@���䖭���������b�����@�@�����������@���Q��
�@�@�����R�֔Ԃɂ��Ắ@�������h���������R�@�،o���E���R��俒�E���b�@�̍����Q��
���̂Ƃ����R�̏Y��ߑ����Ȃǂ��Ƃ��Ɉڂ����̂ŁA��ɓ��T�͗���̂䂦�������ĒǕ�����邱�ƂɂȂ�̂ł��邪�A�������Ɉڂ��Ă���ێR��k�������������A�V���������J���Ă�����u�����R���{���v�Ɩ��Â��A�����ƂȂ����������̓����o���V��[�J(�ڂ�����)(���݂̗c�t���ɕt��)�Ɉڂ��A�u��v�̎��������āu�퍂�S�R�������v�Ƃ����B�܂��A���̓��T�̂Ƃ����{���́u�������v�Ɖ��߂Ă���B
�@���̌�A�э��h�эu���肩��g�������������~���́A���߂ɉ����Đ��������Ăѓ��{���ɉ��߁A�����h�тƂ��ĊJ�u����̂ł���B
�@�@�������@�������h�ъJ�u�E�J�c�d�_�@���~
���~�͌ܔN�̌�ɍĂєэ��h�юl���u��ƂȂ邪�A����p������q�����́u��N���F��V�J�Ɉڂ��ē������Ɩ��Â��ȂĖ��@�ƂȂ��B���Ղɑ�u�����c���A�z���Đ����R���{���ƞH�ӁB
���ی��N�b�\�̍�(1644)�Ɏ���đ攪�c�ʐS���t���̒n�Ɉڂ��A����@�����J���A���O�������K����n�����āA�ȂĈ�剾���ƂȂ��B�������R��A�ڂɗ֚�v(�d�_�~��`)�A�Ƃ�������ł������B
�@�����͖������E�q���t�߂ɂ��������A�E�̂悤�ȕϑJ���o�Č��݂̂Ƃ���ɒ�߂�ꂽ�悤�ł��B
�����Ɍ��J�R��E�R����̕��͎��̂悤�ł���B
�J�R��
�@�u�����J��R�O�c��s�@���S���l�@���R�����J���俒���l�c���O����N(1596)�܌���\����@���V���B�������с@�@���N�Ȗ�(1679)�Z���l���@�V�k�`�ꌋ�V�O�k�ގ��V�v
�R����
�@�u�퍂�S�R���������V�J�j�݃��A�����l�\�ܔN�ꌎ�\�����ЁB���F�Ď��A�{�R�m���j�˃�����������(�k�����v�ێO�Z��Z�Ԓn�E�����n)�g�����A���h�ё哪���Օ~�n�딽�Q�����l�����{�R�������^�Z�����A�吳�Z�N�܌��\�ܓ����J�j�]�W�������g���X�B��玆�@�c�Z�S�\�����L�O�m�׃����n�j��J�Җ�B���a�Z�N�t�ފ݉���A�����������������n�c�A�{�C�@�q�s���E�v
�@�@���ɁA�w�������@���ג��x��蓌�����E�������̕�����]�ڂ���B
�@�@�@��t���lj��X��������S�쒆�����V�J
�@�@�����l�\�ܔN�Z������������k���������֍���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@������
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ��@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�厡���N(��O�Z��)�n���@���S��l�J��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��Z�ԎO�ځ@���s�܊ԁ@�@�l�\�ܔN�ꌎ�\�����Ď��m�|�͗�
�@�@��A�����ؐ��@��S��E�l�@���L�n��l��@�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�S�O�E��l
�@�@�@�@�@�@(�ȉ���)
�@
�@�@��t���lj��X��������S������(��)�����v�ہ@[�吳�Z�N�㌎�\�O���@�ځ����������恡����
�@�@�����l�\�ܔN�Z��������@�����쒆���������{���w�������Y���^�������������g���̃m������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@��(��)�����i���͖����^�ŏ����A���ƒlj��j
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ���
�@�@��A�R���@�@�@�s�ځ@[�����l�\�ܔN�Z��������@�����쒆�������������������g���̃X]
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��܊ԎO�ځ@���s�O�ԎO��
�@�@�@�@�@�@�吳�Z�N�㌎�\�O�����z���@�{���@��E��،܍��@�@�ɗ��@�E���؎�����
�@�@�@�@�@�@�吳���N�l���������@�{���E�ɗ����z�H���v�H��
�@�@��A�����ؐ��@���E��@���L�n��l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��n�딽�Q����E�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�E�̈�s�ɂ��Ă̊W�����A���Ŏ鏑������Ă��邪�����s��)
�@�@��A�h�k�l���@�O�E��l
�@�@�@�@�@(�ȉ���)
�����̌������E�Δ�
�@�{�����w�ɂ́A�꓃�����l�m�E������c�t���E���@�������u����A�E���̋S�q��_�Ȃǂ�����B
�@�����ɂ͗��Z�E�̕�ƂƂ��ɁA�N���⍏���l���̂��Ƃɂ��ċM�d�Ȕ肪����A���ɂ�����L���Č�w�Ɏ����B
�@��O�̑�ړ�
�@�@�u�얳���@�@�،o�@�������@�c���S���@�~�t�T��@�O�؊u�@���Ñp�K�@�x��h���@�V���q��@�[�͖���@���ޕ���J�h�z�p����������P�@�����O�N�M�C(1820)�O���@���R�O�\���������v
�@���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�u�҈ׁ@�ߕ�@�@�h��
�@�@�@�@�@�@�@�얳����@��
�@�@(�V�W)�얳���@�@�،o�@�@(�@��)
�@�@�@�@�@�@�@�얳�߉ޖ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�厡��N关�K(��O�Z�O)�\���@��
�@���(�f��)
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�ׁ�����
�@�@�@�@�@�얳����@��
�@�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�@�@�@�얳�߉ޖ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�厡������
�@��O
�@�@�@�厝���V���@�@��A�ړV��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�������ڏ\�O�N����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������瘹���i�ʼnʖ�i���́u��+�b�v�̕����j
�@�@�@�@�@�@�@�@��ٕٝӍs��F�@�얳�����t��(��)�i���́u�z�v�̕����j
�@�@�@�@�@�@�@�얳��s��F�@�@�얳�@��吹�l
�@�@�@�@�@�@�얳����@���@�@�@�S�q��_�@�{��
�@�@(�V�W)�얳���@�@�،o�@(�@��)
�@�@�@�@�@�@�얳�߉ޖ��@�@�\������
�@�@�@�@�@�@�@��ُ�s��F�@�얳��X��t��l��(��)�i���́u�z�v�̕����j
�@�@�@�@�@�@�@�@��و����s��F�@������ߗ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���h��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ëg��N(1442)�K���\�ܓ�
�@�@�@�������V���@�呝���V��
�@��l
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�������o��ߕꖭ����
�@�@�@�@�@�얳��s�ٕӍs��F�@�O�\�O����T���@�E�O��
�@�@�@�@�얳����@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�q��_
�@�@�@�얳���@�@�،o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\������
�@�@�@�@�얳�ډޖ����
�@�@�@�@�@�얳��s�����s��F�@�������v��
�@�@�@�@�@�@������N���N(1455)�������O��
�@���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ܔN�b�\(1464)�㌎������
�@�@�@�厝���V��(�s��������q)�@��A�ړV��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�얳���Ӎs��F�@��ړV���@�얳�@��吹�l�@�垐�V��
�@�@�@�@�@�@�@�얳��s��F�@�얳�ɗ����@�V�Ƒ�_
�@�@�@�@�@�@�얳����@���@�얳����t����F�@�S�q��_
�@�@(�V�W)�얳���@�@�،o�@���@(�ԉ�)
�@�@�@�@�@�@�얳�߉ޖ���Ł@�얳������F�@�\������
�@�@�@�@�@�@�@�얳��s��F�@�얳���ށ����@�ߒړV���@�������F
�@�@�@�@�@�@�@�@�얳�����s��F�@�匎�V���@�얳������l
�@�@�@�������V��(����������q)�@�呝���V��
�@�@�����āA�ʼn���Ɏ��̍�����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�א�F�����@(�@��)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�\�O�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����t�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������S
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�@�t�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H�t�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
2023/10/18�B�e�F
��ɋL�ڂ́u�R����v�͖����A���݂��m�F�����B
�@������������ڐ��F�����͏�Ɍf�ځA�����O�N�N�I�B�@�@�@�@�@���������������Β�
�@�����������{���E�ɗ��@�@�@�@�@�������������炩
�@�������R����ڐ��F�q���S�q��_/�얳���@�@�،o/���S�R/�������@�ƍ����B
�@�����E����F�����͓��@���F�Δ�i�N�I�ȂǕs�ځj�A���̌������č��͊J����S�Δ�A��ނ��������ʂ�A�w��̌����͏Z�E�̏Z���ł���B
�@�J����S�Δ��F��Ɍf�ڂ́u�J�R��v�ł���A�c���J��R�O�c�m�s�@���S���l�ƍ����B�w��͔�ށB
�@�Α��Z�p���F�����Ƃ��v������A�m�͂Ȃ��B
�@�������肻�̂P�F�قڍ������ǂ߂��B�@�@�@�@�@�������肻�̂Q�F���ǂ�����A��ɋL�ڂ́u���v�ł��낤�B
�@�������肻�̂R�F�w�Ǎ������ǂ߂��B�@�@�@�@�@�������肻�̂S�F�Q��̔肪�ʂ���A�قڍ������ǂ߂��B
���쒆���V�c��n
�@���{�����ɂ���L��ȕ�n�ł���A�����̔�E�Γ��ނ��U�݂���B
2023/10/19�B�e�F
�@�����̔�E�Γ��ނ̈������グ��B
�@�쒆�V�c��n�Γ����F�S�ďڍׂ͕s�ځi�����s�\���j
�@�쒆�V�c��n��⸈��@�@�@�@�@�쒆�V�c��n���@�@�@�@�@�쒆�V�c��n��ڐ�
�������쒆���c�����Ё@�@�u���Ò��j�@�����v38�`
�@���@�������Ò��̖������̍��ɂ���B
�������쒆�h�����V���i�h����_�Ёj�@�u���Ò��j�@�����v44�`
�@���@�����̋����V���̍��ɂ���B
���쒆�E�V�c�̓��c�_
�@���{�������O����A�k�ɋȂ��鋌�X�������ƁA���ɐ��тɕ���ꂽ���{�������������A�E�͒ł̌Ö��ї������n�ƂȂ�B
�@���̓��́E�E�E���X���ŁA���̏؍��Ƃ������ׂ��Δ肪���H�̕�n���ɕ��ԁB
���̈�Ɂu���@�����Z���_�БO�j���������l���Z�ԁ@�吳�@�N�O���@�H��ꔪ�Z�Z�~�@���H���C�ҏa�J�@�@�@�吳���N�O���@�������V�v�Ƃ���B
�@���ꂩ��\��A�O�����ꂽ�Ƃ���ɋ��n�̎��_�Ƃ��Ēm����n���ϐ�����(�����R�W����)������A����ɂ́u�n���ϐ����@���a�O�N�O���@�n�����v�Ƃ���B
�@�����ɐΑ����W�������āA�u�얳���@�@�،o�@��������@�����@��ǁ@��܂R�@�����s��@��\���@�Ă������@�k���������@�܂����@��܂���(�R�q)�݂��@�V�ۘZ��(�ꔪ�O��)�\�ꌎ�g���@�쒆����卲���q����܂��v�ƍ��܂�Ă���A�Q�w�ɖK��闷�l�����̕ւɋ��������̂ł��낤�B
�@�≪��啽�R�G�M��n�ւ̓����ő�Ⓦ���̂Ƃ���ɁA�ʊ_�Ɉ͂܂�A�ؑ������̌��k�����̓��c�_������B���̎Ђ͓��ɂ��̌䗘�v����ŁA�葫��a�ސl�͎БO�ɐς܂�Ă��鏬����āA���̒ɂނƂ����������ƁA�����܂���������Ƃ����B�����āA�������l�͏��̐���{�ɂ��ĕ�[����K�킵�ł���B
�@���݂��\���\�����̏H�Ղ�ɂ́A�V�Ăō�����Î���|�̏����ɓ���ċ�����B���f�̋����E���|�Ȃǂ��A���ɂ͌����Ȃ��قǍs���͂��Ă݂���B�����̏��݂͎��V�c�ꔪ�Z��Ԃł���B
2023/10/18�B�e�F
�@�쒆�E�V�c�̓��c�_�P
�@�쒆�E�V�c�̓��c�_�Q�F�͂�����u���c�_�v�Ǝʂ��Ă�����̂͂R��A�u���v�A�u�c�_�v�Ǝʂ�A���c�_�Ɣ��ʂł�����̂͂U��قǂ���B���̑��������́u��`�v��u�ʔv�`�v�̐Α������W�ς��Ă��邪���������c�_�Ǝv����B
�u���Ò��j�v�ʼn]���u�������l�i�������v�������������l�j�͏��̐���{�ɂ��ĕ�[����K�킵�v�œ��c�_���[�������̂ł��낤���B
�@�Ȃ��A���]�X�̐Δ�A�n���ϐ������A������̐Α����W�͖��m�F�ł���B
���������쒆�E������[��l�揊
������[��l�͏�q���╔�������P�O���ł���B
�@��������[�̕揊�͉��������ɂ��邪�A�����h�щ����@���[�Ƃ͑S���ʂ̑m���ł���B
��������a�c�E��ؓ��E������@--------------------
��a�c
����a�c�a�c�R�������@�@�u�����j�@�����v272�`
�@����101�Ԓn�ŁA�������ÁE���{���̓쑤�ɂ����āA��t��ʃo�X��u�{���v�����̓�����Ƃ��Ȃ�B
�����̓��[����W���̏Z���E���c�̂��ׂĂ����n���钭�]�ł���B
�R���E���N
�@���̎��́A��a�c���ɂ���Ȃ��瑺���̒h�Ƃ͓�˂݂̂ł���B�������܂��A��������їאڂ����n�Ɍ���͑��S�˂ɂ킽��B
�w�������@���ג��x�͎��̂悤�ɋL���B
�@�@�@�@�@��t���lj�����������S��a�c�����a�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�،o�����@�@���@�@�@������
�@�@��A�{���@�@�@�@�߉ޖ��@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�@�Ԍ����Ԕ��@���s�O�Ԕ��@�@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�@�O�S�l�\��
�@�@��A���O���L�n�@��(���M)�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�@�l�\��l�@�@�@�@�ȏ�
�@
�@�܂��A�����P�X�N�l�������A���y����؎O�V��E����l��q��g�̏���������w����������S��a�c�����v���j�x�ɂ́u�������n�k������j�A�����@�@��B�a�c�R�g���X�B�������������S���R���@�،o��������B�n���N�����厡��N(1363)�����v�Ƃ���A����ɁA���\���N(1688)���������ɓ��{���O�\�O������(�B�{�@�ʉ�)���L�����w�k�єN�v���x�̖����ɂ́u�a�c��������(�}�})�A���k�єV������v�Ƃ���B�����`���ł͒厡��N�ɓ��{���O�c���S(��s�@)�̊J��ɂ����̂ł���Ƃ������Ă���B
���{�E�Α���
�@�����ɂ����[���͂���������k���̍������̂ł���B
��ړ��F
�����E��ɂ���u�a�c�R�������@�����@����@�����@���`�@�����@���̕��Z�N(1756)�������@�M���@���L�v�ƍ����B
��铃�F
�O�i�b�̑傫�Ȃ��̂ŁA�u��铕�@���v��p���N(1862)�l���@�a�c�R�������b�`��@���O�S�D�{���ؓ��D�\�Y(�������̖��O�Ƌ��z)�v�Ƃ���A�u�����Q�S�N��b�ďC���v�̎���������B
��^�Α����F
�@�{���O�ɂ���A�㉮�t���ŁB����ɂ́A�\�Ɂu���r�@�Éi�ZᡉN��(1853)���ėǒC�@�a�c�R���������狏��`��@���b�l�J�Ðm���q��@��������q��@�O�J(�݂�)���E�q��@���F���q��@���d�Ǖ��q�@�����O�V��@���M�z�W���@�쒆�W�R���v�B���ʂɂ͋ߋ����X�̖��O���T�O�l�قǂƁA���ꂼ��̋��z�B�����čŌ�Ɂu�{�a�c��Ғ��@�����S�D�v�ƍ��������B
�Γ��āF
�@���̍���ɂ��菬�^�ł��邪�A�u���O�@�Éi�ZᡉN�N(1853)�㌎�g���b�`��@�{��ʑ��W�약���E�q��@���W���؎O�V��v�Ƃ���B
�{�����w�F
���ʓ��w�ɂ́A�c�t���𒆐S�ɂ��ď��������u����邪�A�����Ɉ�i�Ƒ����ȉƌ^�~�q������A�����ɂ͖�t�@�����J���A���ɑO�L�̎q���ϐ�����F�A�E�ɖ�t�@�����ő��\��_��������B
�����̔@���͓��Ɋ�a�ɑ��Ă��̗쌱���������A�ߋ��ߍ݂��瑽���̐M�҂��W�܂����Ƃ�����B
�@�O�L�̐Γ��āE���Ȃǂ̂قƂ�ǂ��Éi�N��(1848�`�T�R)�̂��̂ŁA���w�O�̒����Ɍ���G�z��A����ɕ��ԊG�n���A������̂��̂��疾���ɂ����Ă̂��̂������B�����̂��̂����Ă��A���̓��������ɐM�S�҂������Q�w���������z���ł���B
�@���̕����́A�����̂��Ƃ𖾂炩�ɕ�����Ă�����̂Ƃ����悤�B
�@�@�@�@������D�V��
��A�䓙�g�������Y��Ƃ����A�@���Z�\��j������B���ʊ�a���ρA�䓖�@��t�l�S��j�t�A�����O�����V���ċ��M�S�d�x�`�����B������V�ʂ�j�䐢�b�킒�������x���A����@��B�R����ҁA�Ē����l�g���㉽�l�V�o����Ƃ���������A���X��(��)����f���|�\�ԕ~��B�ׂ��O����\��������D�@�ˎ��@����
�@�@�@�����l��(1857)�܌�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s��o�H�h�@�g���y��@�����@��
�@�@�@�@��t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ɯ��@�@�@�@��ʓ��l�@�@�@�@�@���n���s�@�����Y
�@�@�@������D�V��
��A�䓙�g�������Y��Ƃ����A�Z�\��Α�����B���ʊ�a���ρA�䓖�@��t�l�O�����V���S�葊�|�ċ��A�䗘�v�L���V�����S�������j�t�A�����ċ��M�S�v�x�A�A�葦�����������ԁA�����䐢�b�킒�������u���A����@��B�ܘ_�ޕ�g���j�t�@���l�V�`�o����Ƃ���������A��M�@�j���X�Ό���f���|�\�ԕ~��B���A����@��������D�@�ˎ��@��
�@�@�@�����l���܌���\�Z��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s��o�H�h�@�@
�@�@�@�@��t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���y��@�����@��@�@�@�@�@�@�@��Ɯ��@�@�@�@�@���n���s�@�����Y
�@�@�@�@�@�@��ʓ��l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�M�S�Q�Ă̂��ߊ�a���悭�Ȃ�A�ēx�Ă肽���̂ł�낵�����肢����Ƃ����킯�ŁA�����̕��K�̈�[������������B
�@�����ւ̎Q�w�͕a�C�������F�肷�邾���łȂ��A��ʓI�Ȋό����s�Ƃ��Ă̂��̂��������̂ł��낤���A���̍L�����o�O�S�O�Ǎ⒬�̐l��������K�ꂽ�܁A���邢�͖Y�ꂽ�̂�������Ȃ����̂悤�Ȓʍs��`���c����Ă����B
�@�@�@��`��D�V��
��A�|�B�̔��㍑�O殌S�O�Ǎ⑺�e���Y�A���ҋV�@�|��X�@�ԏ@��j���A�ّm�U�߃j���������B�R�������ʐS��j�t�A�b�B�g���R���j�����Q�w�j��o���A�������A�䎜�b���@��ՔV�������^���킒����B�s�邒�d��n�R�A���V���ĔV���j���A����@��B�ᖔ�a�����d�ߎҁA�����V���A�䍹(��)�@���@���u���킒����B�ލK�����n�R����j��m�点���킒����B����ˎ���D�@��
�@�@�@�����l���N������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������S
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P����
�@�@�@�@�����w���@�䎛�@
�@�@�@�@�@�@�@���m�O��
�@�@�@�@�������X
�@�@�@�@�@�@�@���l�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���A�E�@�͓�_�E��_�A���͕Ԃ�_�̑�p�j
�@�ߋ��̂��ƁA���l�̂��ƂȂ���ʍs��`��u���čs�����e���Y�́A�A������܂łǂ�Ȃɂ����������Ƃł��낤�B
�@�Ȃ��A���܂ŋL�q���������������E�{���Ȃǂ̖͗l�́A���a�T�U�N���܂ł̂��Ƃł���B�{���͗��N�A���đւ��H���̂��߉�̂��A���ɐV�z���c�����B
�@�����𒆐S�Ƃ��čs����s���̈�ɑ�ڍu�����邪�A�{�W���ƍ����Ŗ~�Ət�H�̔ފ݂̎O��A��Ƃ��ĘV�l�����������ɏW�܂�A��c�̖������F���đ�ڂ�������B
�@���̂ق��A�������s���Ă�����̂ɁA�S�q��_�u�E�\�O���u�����邪�A����͕w�l��������Ƃ������̂ŁA���Ԃ����̐݉c�ɓ�����A�njo��ɂ͂��y�����p�ӂ����B
�@�Ȃ��A���W���̎q���u�ɂ��Ă͑O�q�̂Ƃ���i���ȗ��j�ł���B
2023/10/18�B�e�F
��^�Α����y�ѐΓ��U�͎��������B�i���݂����H�j
�@�a�c�����������@�@�@�@�@�@������ڔ��F��ɖ�������A���Z�N(1756)�N�I�A��O�ɓ��c�_���u�����B
�@������铕�F��̖�������A���v��p���N(1862�j�N�I
�@��ڐQ���F�P��͌����܍M�\�i1740�j�\���̔N�I�A�u���@�����܍M�\�\���@�a�c�R/�얳���@�@�؋�����/�n�@�c�����������@�������v�ƒ���B�@�����P��͓��@���F�E��ڔ�ł���B�N�I�ȂǏڍׂ͖������E�s���B
�@�a�c����������
�@�m�����Q���F�t�͓����@���v�i�勝�R�N��1686��/�����Q�T����j�A��@�M���@�Y�������i���ۂW�N��1723��/�V���P����j�B�������Z���Ǝv�������オ�s���Ŋm�F�ł��Ȃ��B
�@�������X����������F���R�X���F�P�@�����i���ی��h�э�1741��/�T�������U����j�ƋL���B
��ؓ�
����ؓ����c�Y��Ёi�������Ёj
�@�@���������Ò��̖�������
���ؓ��R���@���@�u���Ò��j�@�����v292�`
�@��ؓ����ӓc471�Ԓn�ŁA�W���̂قڒ����Ɉʒu����B
�R���E���N
�@�w�������@���ג��x�ł́A
�@�@�@�@�@��t���lj�����������S������ؓ����ӓc
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��j���������@�@���@�@�@���@��
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޖ���
�@�@��A�R���@�@�@������N�����쒆����������l�����@��l�m�����j�e�^���@���@�X�@�J��n������l�i��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��܊ԁ@���s�l�ԁ@�@�@�@�@��A�ɗ��Ԑ��@�Ԍ��O�ԎO�ځ@���s�Z�ԁ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�ܕS�l��
�@�@��A�h�k�l���@��E��l
�Ƃ���B
���̖������l�����@��l�Ƃ́A���[����苗����̂��A���E����������Ό��̘h���֓]�Z�ƂȂ�A�O�N(1451)�����\�O���ɖv�����l�ł���B
�w���@�@���@��Ӂx�ɂ͓����̉��v�ɂ��āu��ςɂ͉������N(1489)�N���̑n���B�J�R�����Ƃ���v�ƋL���A�J�R�͓����������ƂȂ��Ă���B
�@���ɁA���������́w�ؓ��R���@�������N�x�������������ɏ������߂čڂ���B
�@�����������R�̏��߂͐^���C���̗��ɂ��ĎR���̓�����B�R���������V�@��Ɛ\���́A�O���̉��V���ɂ߁A���͐��ގ����n�̔@���A�ɓ��鎖�̔@���A���݂̓��s���ʖ�B
�����ɐl�c��\��������V�c�̌�F�����l�N(1359)�A���c�̌�ė����R�m�O���s�@���S��l�A�֓���O�ʂ̎n�߁A�悸���R�̋ߋ��ߗ��ɗ��点�����Č���@��C�s�̐�(��)���(��)���A�q���n���������ɂ��ċߗ������̋M�ˍ����̎Q�w�̌Q�W�𐬂�����A���S��l�A�l�X�Ɏ�������₢�����B(�ȉ��]��)
�@�@���̂��Ƃɂ���āA�����͐^���@�ł��������ƂƁA�����l�N(1359)�ɒ��R�O�����S�����n����z���ɕ������Ƃ��A���̐��@�������ƂȂǂ��m����B
�@�܂��A�Éߋ����̉����Ɂ@
���^(�}�})���g�]�n�����m����@�k�����j���g�]��L�ɏ��X���������@�R���j����玅�^���������X�@�N�����^�������Y�@�吹�l�m�����n�@�������(1493)�l���������������g�L���@�{�蔪�ljE�q��g�L�]�X
�]���뗎����Ԏ���]�����㖜���g�]���w�ڃV�@�������؎��ljE�q�哹�@��߃���[���Ԏ���]�S�l�L�e����m��M�҃j�e�@�l�\�Z�x�m�t�C���퐬�@���x�惒�c�L����������P�퐬��ԁ@���n���V�y���i���n�@�䓰�{�萬�e�����V�������V���@�����n���
�q�����؈ꓝ���������V�h�߃j�t�@�����j�����퐬��@�������@[���Ԏ�������]�J�R�j�퐬�A�Z��O���h�߃g�V�]���ɏ��]�X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���]���i�O�\�l��������Ύ��������\�N
[���z�@�{�@��]�J�R�v�����@���e�吹�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����\��Ζ}�Z�\��N�s�ɐg��
�E�ғ������u�V���e��l��ʔv�V�ʖ�@�w�Փ��E�M
�ێ������Oᡖ������\�l���]�˃��������@���������[�B�B�m�������Q�\�ܓ����R�]��[�u�Җ�@���n�V�Y����b�Ɠ��\(���R�ܐ�)��
�������؋v���Y�@�O�x���V��@�{�哖���M�S�h�z�l�ܐl
�@
�����R���c���E���l
�S�S���~䖝�@��F�吹�l������\���N�߃e�J���X�@�i�a�܌Ȗ�(1379)�Z���J���@����(���������J��)�����Z�\���N�ږ��N��(1338�`41)�m��吹�l��^�M�m��u���كj���^�V�喝�(�}�})�����䎝�Q�j�e�@���A�e��������c�V���哈���@�j�����������X�@������j�ڃ��@�哈�g�]�@�q�q
�E�Éߋ����j�L�V�L��
�@�ؓ��R���@���h���J
�@�h�����؎��ljE�q��@�m���q�@�������q��@���V���@�����q�@�d�E�q��@���Y�E�q��@�����q�@�܍��q��@�s�Y���q�@�����q��@(����)�@�^�����@�s�O�Y�@�D�E�q��@�ܕ��q�@�d���q�@�F���q�@�����@�����q�@�����q�@�����q�@�d���@���h�Œ����q�@���E�q��@���ɕ��q�@�ܕ��q�@���c�ܘY�E�q��@�앺�q�@���������q��@���Y�E�q��@�a�c�O�V��@�v�E�q��@���J�K��
�@���̂悤�ɋL����Ă��邪�A�ߋ����̔N�オ�s���̏セ�̏��݂��͂������A�����Č��������������߁A���e�̔c��������ł���B
�@�����̗R����q�˂��ŁA�m�Ƃ��������ɂ����̂Ƃ��Ă͎��̈ꎲ������B
�@�@�{���E���������l�\�̓��`�����i���N(1778)�ɏ������؏��ł���B
�@�@�@����ɂ�
�@�ؓ��R���@���ҁ@���̖k�������j�L�V���V�^���@�������@�@���V�V�Ɖ]
���R��l�c���@���l�V�ˋ����v���@�@������苗������Ɖ]���𖭘@���Ɖ��@������M���N�ԋ��V�����䓰�j�ځ@���㖾����ᡉN�N�쒆���F�쓰�ֈڂ�
���\����q�N���V�ؓ��ֈځ@���ؓ��R���@��
���R�����V�o(����)�����ÔV�L�^�ᖡ�V�㖳����Җ�
�ᖖ���@�_�L�V���ҁ@�������ȉv�؋��@�������َ��^�V�{�����Y�@���^�V�Җ�
�@�@�@���i������N��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����R�l�\���`�@(�ԉ�)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؓ��R���@���\�����[���p
�@���̂悤�ɁA������顚���L���A�o��(���O�̌���a�����)�ł��邱�Ƃ��ԈႢ�Ȃ��Ƃ��Ă���B
�Ȃ��A�����o���ł��邱�Ƃ͕������������Ɏ��̂悤�ɋL����Ă���B
�@�@��A�ؓ����@���n�����j���@���R�V�����o��a���
�@�@�@���R�o�d�V�߁@�����V�����j��������@�����n�N�؉����
�@�@��A���@�������o���@���R����ڌ���m�s���t(����)�V���M�ރm���j�ݔV��
�@�����̂��Ƃ��瓖���̊T�v��m�邱�Ƃ����A�������ɂ��Ă̐V�E���z���C�A���̑���オ�s�����ł��낤�����Ƃɂ��ẮA���D���̑��̕����ނ��킸�������Ȃ��A�ڍׂ͂킩��Ȃ��B�����A�ߋ�������ɋL����Ă����㎁���̗��ɁA�������ŗ��L����Ă��邭�炢�ł���B
�������܂Ƃ߂Ď��ɏq�ׂĂ݂�B
�@�܂��㐢�����͓��E���M�̖�������(�N�i��N(1343)�܌���)�ꎲ�����߂Ă���B����́u�������F�@���\�\��N�ȉK(1699)�����\�����@���{������M���@�������V�v�̓��D�ɂ���Ă킩��B
�@�����āA���̌�ɏ��������̂ł��낤���A������̗��ʂ�
���\��{��[�Г땪���O���ܕ�]�@������E���t�V��^�M�����L�^���@�ؓ��R���@����Z�V����@���ΗL�h�M�ו���M�ꖭ���쑝�i���V�C���\���@�]�N�i��N�����\�h���O�S�\��N��@�˖��@���㐢�M������]���|����
�@�@�@���\�\�l�N�h��(1701)������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@(�ԉ�)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�咆�����@�œc�ɕ��q
�Ɩ�������\��������(�w�S�@)�����������Ă���B
�@����
�\�O�����S�@���M�̗��ɂ́u������v�ƋL����Ă��邪�A���̑�(�v�N����݂Ė��a�̂���(1764�`72)�Ǝv����)�ɞ��������̎��Ƃ𐬂������̂ł��낤�B
�\�����̗��[���p�̂Ƃ��́A�@�c�ܕS�����ɓ������Ă̋��{�������������悤�ł���B
�{���Ɍ������č���ɁA�|�_�Ɉ͂܂�A�����ɖʂ���1.3���̐Δ�Łu�얳���@���F�����ݕ����A�@���i��M�q(1480)�\���\�O���@���@�h�����@��ڍ\���v���ʂɁu�ܕS�����V�����@�ؓ��R�\�������[���p�v�̂悤�ɍ��܂�Ă���B
�\�����h���@���p(��ɓ���)�ƂȂ邪�A�����ɂ́u�䏊�ƍ��ց@�q�a�C���v�Ə�����Ă���B
�Ȍ㕶���N��(1818�`30)�ɂȂ��Ă̓�\�l�����S�@�����̗��ɂ��A�������u�䏊�ƍ����C�������@�v�ƁA��C�̂��Ƃ��L���Ă���B
��\�ܐ����w�����́A�����E���ɂ����1.3���̑�ړ��������������A����ɂ́u�얳���@�@�،o�@��ڈ�畔[��������]���h���@�V�ۓ�N�h�K(1831)�@�������ܐ��@���w�����@(�ԉ�)�v�̍�����������B
�\���������@�����̂Ƃ�����A�h�k�ēc�����v���A���̊Ԃ͖��N����Z�Z�C������i���邱�ƂɂȂ����B���̏��͎��̂Ƃ���ł���B
�@�@�ēc�����v���V�ԔN�X�Ζ�����S�C��[�����@�E��j�n�א�c��X�Z�e�ő��������ꏔ����
�@�@��j�n���ݍЏ�����M�������������i�F禱�@��������u���@�@�،o�S�����s�L�Ӗ��Җ�
�@�@�@�@�@�Éi�q�N(1852)�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������������@�����@�ދL
�@���̎ēc�����v�Ƃ́A���݂̑��Ò��ɂ����Č\���ƂƋ��Ɏc�邽���̊�������(���J�����ꊇ���Ďx�z�B����Ƒ㊯�E�̎�Ƃ̒��Ԃɂ����ĔN�v�E�����̊����ĂȂǂ��s���A�g���͎m���ɏ�����)���߂Ă���B
�@�����Ė����ƂȂ�A
�O�\�������@����̂Ƃ��Ɂu�q�a�䏊�V�K�����v�B
�O�\�l�������@���^(�吳���N�ɎR��̋��@���l�\�ƂȂ�A�{���E�ɗ������Č����Ē����ƂȂ���)�́u���c�������j�A���v�Ƃ���B���̌���Z���_�@���G�������Č܁Z�N�߂��Z�����A���݂͒��J�쑶�Y�t�����R�O�\�Z���ł���B
�@�ȏ�́A���Z�E�̂����ŋL�^�Ɏc���ꂽ���e���L�������̂ł��邪�A�Ⴆ�ΎO�\�ꐢ���r��ɂ�����u�����ߑցv�̂��ƂɊւ��镶���́A���̑O�オ�s���ł������肵�Ĕ��ǂ��r������ł������B
�@�܂��A�����h�ѓ��{���̖�m�ł������Z�E�́A�������瓯�h�тֈڂ����̂��܂߂Ď��̋�l�𐔂��A���̌𗬂̐[������Ă���B
�@�@�\�ꐢ���\�@�@�������u�@�@�\�������p�@�@���E�@�@�@�@�\�������p�@�@���E�@�@�@�@��\�l�������@�����O��
�@�@��\�Z�����Z�@�������u�@�@��\���������@�������ȁ@�@��\�������^�@���E�@�@�@�@��\�㐢���ʁ@������
�@�@�O�\������@�@��������
�@���̒��ŁA�\�ꐢ���\(�b�Ɖ@)�̂��Ƃ���A�������@��ł������s��s�{�h�ɂ��Ăӂ�Ă݂����B
�@���ꂼ�����{���E���������̍��ɋL���Ă���悤�ɁA�����Ƃ��s��s�{�h���@�Ƃ��ďd�v�Ȉʒu���߂Ă����Ɠ������A���q�̏��������܂��������e���������Ƃ��Ă��̖���m���Ă��邪�A���̏��������������Ȃ킿���̓��\�ł���B���n�̐l�ŁA���ۓ�\�N(1735)�ɖv���Ă��邱�Ƃ����킩��Ȃ����A���̍����܂ō�����ĕs��s�{�h�ł��邱�Ƃ��B���������Ƃ��ẮA���R�ł��낤�B
�@�@���u���@�@���@��Ӂv�ł͌b�Ɖ@���\�͑�V���A���ۂQ�O�N�T���Q�S����Ƃ���B
�@�{�R�ł���������������u����v�ɂ́u���F�n�s��s�{�m�@���i�s���ϔV�N������v�Ƃ���A���̒��Ɏؓ��̑�����������Ă��邱�Ƃ����Ă��A��������ѓ������s��s�{�h�̖@�����e��Ă������̂Ƃ����悤�B���{���\�������\���@���̖@���͂��ꂪ���ׂĂ̎����Ɛl���ł͂Ȃ��ɂ���A�\�Ɍ����邱�ƂȂ��p����Ă��������̂Ǝv����B
�@����͉����ēV�ۋ�N(1838)�̂�����u�V�ۖ@���v�̂Ƃ��A���M�ؕ����o���āu���\���Ȃ��v�Ƃ��ꂽ���M�҂́A��ؓ��ɗאڂ��鑺�Ƃ��Ă͑�x���O�l�A�k������ܐl�A�쒆���O�l�A�g�c���P�P�l�ł��������A���̂悤�ȏ�Ԃ̒��œ�ؓ��͂����̉e�����ǂ��Ă������̂ł��낤���B�����ł������Ƃ͎v���Ȃ����A�j�����Ȃ��A�܂��͕s��s�{�h�W�̂��͉̂B�ł��A����ɂ͉�₂����Ǝv����_�������邱�Ƃ���A�������N�Ƌ��ɂ�����������̌����ɑ҂B
���@�؎����{�E�Α���
�����̐����ɂ͋}�Ζʂ������Ă��邪�A���̒����Ɂu���j���喾�_�v�Ɓu������P�_�v���J����B������N(�ꔪ��Z)����Ɍ������ꂽ���̂Ƃ����A�i�������j���a�\���N���ɍČ������B
����F
���@�^�M�Ƃ�����O����N(1279)�㌎��\������^�̙�䶗�������A�g���R�l�\���~�ʉ@���ւɂ����O�N(1753)�̗�����������B
���ˏ��B�m�{�Z�@���i�̙�䶗�������A����͕��l�N(1754)�̂��̂ł���B
�O�L���E�M�̖������F���ꕝ�ɉ����āA��ב喾�_���E�������������ꂼ��ꕝ���ۑ������B
�Α����ށF
�����E�V�ۂ̑O�L���{���E��B���Z�E�̕�Ȃǂ̂ق��A���̂悤�Ȃ��̂�����B
�@��(��)�@����76�����A����57�����̂��̂ŁA�N�����͓ǂݎ��Ȃ��B
�@��(��)�@�N���Ƃ��Ă킸���Ɂu�@�Z���l�������v���ǂ߂�B
�@����@���̐Α���ɂ́u�V���Z�N(1786)�l���g���v�̕��������܂��B
2023/10/18�B�e�F
�@���@�������E��ڐ��F��ڐ̑��ʂ̕��������ǂłȂ����A��L�ł́u�얳���@�@�،o�@��ڈ�畔[��������]���h���@�V�ۓ�N�h�K(1831)�@�������ܐ��@���w�����@(�ԉ�)�v�Ƃ���B
�@�ؓ����@���{���@�@�@�@�@�ؓ����@���ɗ��@�@�@�@�@���j���喾�_�E������P�_�P�@�@�@�@�@���j���喾�_�E������P�_�Q
�@���@���Γ����@�@�@�@�@���@����R���F��L�̒ʂ�B�@�@�@�@�@���@����⸈��F�ڍׂ͕s�ځB
�@���@�����@���F��L�Ɂu�{���Ɍ������č���ɁA�|�_�Ɉ͂܂�A�����ɖʂ���1.3���̐Δ�Łu�얳���@���F�����ݕ����A�@���i��M�q(1480)�\���\�O���@���@�h�����@��ڍ\���v���ʂɁu�ܕS�����V�����@�ؓ��R�\�������[���p�v�̂悤�ɍ��܂�Ă���B�v�Ƃ���̂�����ł��낤�Ǝv����B
���ؓ�����ꖜ�����A�Γ�
�ؓ����V�g��n�ɏ��݂���B��n�͖����Ђ̖k�����ʁi��250���j�̍���ɂ���B
�R���Ȃǂ͕s���ł���B
�@����ꖜ�����A�Γ��F�����ꖜ�����A���i�h+�N�j/���\�\���b�\�N�i1704�j/���@�Ƃ���B
�����
���t���_�Ё@�R���E���N
�@�@�@�i���ȗ��j
�����؏�ƎR�������@�@�u���Ò��j�@�����v328�`
�@�t���_�Ђ̐����A���H�����Ă�����ɂ��菊�ݒn�͎����330�Ԓn�ł���B
�w�������@���ג��x�ł́A
�@�@�@�@��t���lj��X��������S��������؏��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�،o�����@���@�@�@������
�@��A�{���@�߉ޖ���
�@��A�R���@�����n�����@�j�V�e����m�����m�J��j�V�e����Q�N�����@�c�����N(��Z�l��)��������V�e�Č��V�������g�̃X
�@��A�{���Ԑ��@�Ԍ����ԁ@���s�܊Ԕ��@�@�@�@�@�@��A�ɗ��Ԑ��@�Ԍ��Z�Ԕ��@���s�l�Ԕ�
�@��A�����ؐ��@�O�S���E�Z�@�@��S���E��@���L�n�@�@�@�@�@�S�ܒ@�@�@�@���L�n
�@��A�h�k�l���@��S�l�E���l
�Ƃ���A
�w���@�@���@��Ӂx�͂��̉��v���u�c�����N(1648)�̑n���B�J�R�����B�J������B(��ςɂ͊J�R�����A�J������Ƃ���)�v�ƋL���B
���n�̎���L���鎑���E���N�Ȃǂ͉E�̊O�Ɍ�������Ȃ��B
�@�{�a���w�̉E�ɂ͓��@���l�ؑ��A�����w�ɂ͑单�V�����J����A���֓���ʎ��ɂ͐~�q�ɓ������S�q��_�E�������E�V�_�������u�����B
����̏��{�E�Δ�
�@�{�a�O�ɂ͎��̂悤�Ȃ��̂�������B
����
�@����64�����A���a37�����̂��̂Łu�{���ʁX���y�@�h�������薞���@���u������@���i�Z���єN(1777)�����g�C�Ē��얳���@�@�،o�@�\�Z��������@��������S���ؑ���ƎR�������@��Y�v�̍���������B���Ȃ킿�A�\�Z�������̂Ƃ��ɍĒ��������̂ł���B
�ł��炵(�ʏ̂��邪��)
�@�u�Éi�ܐp�q(1852)�\�ꌎ�������V���T�R�ŏ�@(�����s��s���R��)�Y���@��i���R�t�C�U�ߒ��@���Z������v�̋L������A���a��31�����̂��̂ł���B
���ʓ�
�@���������̉E���ɁA���ʓV����{���Ƃ���B�ؑ����������ŊԌ��E���s�Ƃ�3.6���̌����ł���B
�����ɐΓ�������A�u���ʑ喾�_�@�V�����h�N�N(1781)�\�ꌎ�@�D�����s�E�q��v�Ə����B�����đ����̂��铏�D�ɂ́A�u�������ȓщ[(1789)�Z���g�C�����@����ѓc���Y�q��@��H�ѓc���E�q��v���̂悤�ɓǂ߂�B�܂��{���̔[�߂�ꂽ�~�q�ɂ́A���̓������ʂɖn��������A�u�����ʑ喾�_�@�V�ۑ攪(1837)���ɋ�����噩�]���v�B
����ɁA�����ɂ��铏�D�̗��ʂ�
�@�����ʓ��n��i���N(1704)�j�����V�������N(1789)�ċ��X�@���������ċ�迠���\��N�@�ċ������{�N迠�S�l�\��N�o�߃Z���@����������S��\��N�m�Ñ����i���o�@�������O�a�m��j���i�J���Y�@�˃e�h���]�c���׃V�@���j���c�ꌈ��C�U�����Z��
�v�X�F�M�͑��i���h�a��
�@�@�@�@�@���a�l�N�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������O���������W��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���h�����@���撷�@�@�ѓc���Y
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���b�l�@�ѓc�P�Y�@�W�����Y�@�W�H���Y
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��H�@�@�@�ѓc�`��
�����l(���Ƒ�P�_)
�@�����������E�{���O���vጂ̐_�Ƃ����閭�Ƒ�P�_���J����B���a�O�N(1766)�̑n���ŁA���n���vጂ����s�������Ƃ��猚�Ă�ꂽ�Ƃ����B
�ؑ����������ŊԌ���ԁA���s���ڂ̌����ł���B
�@�u�瑁�ӂ�@�K�������͋g����@���݂������́@���s������v�̘a�̂��f�z�����B
�Βi�̏㉺�ɂ��ꂼ������Β�
�@�㕔�̂��̂ɂ́u�얳���@�@�،o�@����(�ԉ�)�@��ܕS�Ή������������\����(1815)�\�ꌎ�@�ӓ��@��ƎR�����C�@�@��哖���y��Ғ��@���b�l�O�я����q��@�ѓc�r�O�Y�@�ѓc�����v�B��Ɂu�������v�Ƃ���B
�@�Βi���ɂ�����̂ɂ́A���ʂɁu�������v�Ƃ���ق��A���̂悤�ɍ��܂��B
�@�@�v�H�@���a�l�\�l�N�����@�@�i���ȉ����j
���Z�E���
�@�ŌÂ̂��̂ɂ́u�c���O�N(1650)����������v�̋I�N������B����͒����̑c�Ƃ�������@(��)�̂��̂ł��낤�B
�Ȃ������ɕۊǂ̏Y��E�����Ƃ��āA���e�E���S�����l�̐e�M�Ƃ������䶗����ꕝ���ƁA�߉ޔ@���̗ՏI��`�����|���ꕝ������B
�@�����V�c�̐l�B�́A���Ă͐�c�̎��̒h�k�ł��������A�ڏZ���A�����͓����o��(��������)�̒h�ƂƂȂ��Ă����悤�ł���B
���݂͓��������ɑ����Ă��邪�A���̈ڒh�͖����O�\�N����Ǝv����B���̂��Ƃɂ���ď@���I���s���͓���Ƌ��ɂƂ�s����悤�ɂȂ����B
2023/12/29�B�e�F
�@�������ΊK�E�ΊK���������@�@�@�@�@�ΊK���ڐ��F�������͏�L�̖{���ɂ���B
�@���،������{���P�@�@�@�@�@���،������{���Q�@�@�@�@�@���،������ɗ�
�@���������Ƒ�P�_���@�@�@�@�@���Ƒ�P�_�������@�@�@�@�@���������ʎR�@�@�@�@�@���������ʓ��@�@�@�@�@���ʓ�����
�H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�u���Ò��j�@�����v333�`
�E���ؑ����c�_
�@���������o�āA�쒆���ʂ֒ʂ��钬�����s���ƁA���̍��܂���n�_�ɓ��c�_�����ʂ����J���Ă���B����O1010�Ԃ̏ꏊ�ł���B�����Ă��̈��50�����̂��̂Łu�����܍M�\�N(1740)�\�g�Ǔ��v�̔N�����ǂ߂�B���̈�͂�������Ⴂ�������L���A���a�O�\��N�Z���ɓ���؋�Ƃ��ĕ��J�������̂ł���B�����n���Ɍ��\����Ƃ���A�肽���n�ŁA�������炻�̐�{�ɂ��ĕԂ��Ƃ������K�́A���̗�ɂ������邱�Ƃł���B���̂��߂��A���̎��ӂɂ͋ʐ������ɂ���B�����ɂ͒ŁE�~�̌Ö̉��ɒ���������A�������u����Ă���B���̈�Ɂu��[�@�����Z��(1859)�������@�ѓc�����q��v�Ƃ��邪�A���̏��^�̂��͖̂����ł���B
�E���ؑ��m�ԋ��
�@���c�_�킫�ɂ���̂��m�Ԃ̋��ł���B����90�����A��76�����̔��̂��̂ŁA�u�_����^�_�l���x�錎���Ɓ@�͂��z(�m��)�v�ƍ��܂�Ă���B�����ė��ʂɂ́A
�@�@�@��[�@�F�O���~���@�H�z�������@�特
�@�@�@�@�@�Ԓ��@�_���@�X���@��凮�@�k��
�@�@�@�@�@�R���@�I�_�@���t�@�߁X�@�@�@
�@�@�@�@�@�ǐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ۏ\��h�N(1841)�Џt
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�@�V��
�ƕ�[�Ҕo�l�����̉덆������B
2023/11/29�B�e�F
�@���ؓ��c�_�P�@�@�@�@�@���ؓ��c�_�Q�@�@�@�@�@���ؓ��c�_�R�@�@�@�@�@���ؓ��c�_�S�@�@�@�@�@���ؓ��c�_�T
�@���ؔm�ԋ��
�����ؑ��̕���
�@�������̑c��́A�Ƃ����Ă������ɂ���������̐헐���牓�̂��A�V���̍��������͂���œ��쎁�̎����ɂȂ��Ă���̂��Ƃł���ɂ���A���݂��������j���͂قƂ�ǎc����Ă��Ȃ��B
�@���i��@���{�̐���̂܂܂Ɂu���������E�����v�A�Ս��ȔN�v�旧�Ăɂ���Ĕ_���̈�Ɨ��U���������낤���A���i�̎�i�ɏo����������B
�����Ɏ������̋ߍ݂ɂ����Ĉ�l�̊��{�m�s����l�̂��߁A���ɗނ̂Ȃ��ꂵ�݂����P�P�J���̔_���������A�Ȕ����Ȃ�����V�֑i��������������B
�@�����͗��M�̏㌇���������A�Ӗ��s���̂Ƃ��낪�����āA���ǂ��邱�Ƃ��ɂ߂č���ł��������A�ł��邾�����Ղȕ��ɂȂ����Ď��ɍڂ��邱�ƂƂ����B
�Ȃ��u�i��ĕ��v�Ƃ́A���c���E�փP��������̐w�ɐ�������āA���i��N(1625)�ɑ��͍����q�E�����A�����������E��ׁE���n�A�㑍���R�ӂȂǘZ�S�̂����ɂQ�T�R�O�Η]��m�s���ׂ�������A�����O�N�]�܈ʉ��ɏ�����Ċĕ��Ə̂��A���ܔN�ɏ㑍�����ˁA�������x�����S�̂����ɂP�O�O�O�̉������A���ׂĂR�T�R�O�Η]��m�s���ď����O�N(1654)���\�O�Ŏ��������u��E�q��E����(��������)�v��c�Ƃ��A��ɂ���E�����n���ɏ��̂�L���邪�A�]���̔��O(�����Ђ�)(�`��Y�E�ĕ�)�̂Ƃ����\�\�l�N(1701)�ɉ�������S�̍ђn�������āA��������S�Ɏn�߂Ēm�s���ׂ��y�n���ڂ���Ă���B���ꂪ�����V�c�����o���ꂽ�O�L�i��ɂ������l���Ǝv����B
�@���̕��́u�ĕ��v�͔N��I�ɂ݂Ĕ��O�̑����O(��������)�̂��Ƃł��낤���A���O�N(1753)�������̈╕���p���B
�l���I�ɂ��̉��l������悤�Ȃ��Ƃ��ĎO����A�o�d�E�q�y��~������ɋy��ł���(�w�����d�C���ƕ��x)�B
�@���́A�u�i��ĕ��l��m�s���@�㑍�����\��P���S�����\���v�̏����o���Ɏn�܂��Ă���B
�@
�����̌�n���l�ɂ́A�ǂȂ��̐��b�ŏ�������ꂽ�̂ł��傤���A�ߍ��c�ɂ̏��S���ł���҂��ߔN�_����`�u�����D�]�v�Ɩ��̂��Đ_�E�܂����̕�������A��ɂ������������D�ݑ�R�t�ł���܂��B���̎ҁA�ǂ������킯�ŕ��m�ɂȂ����̂��A���̉ĂɌ�n�����l���������q��Ɖ������A�d��l�ɏ��������܂����B
�@�����āA�㌎���{���u��m�s�������v�Ƃ������ƂŁA�P�䐴��Ƃ����Q�l�̂̎҂Ƒ��y���A��A��������g���ĉ������ė���ꂽ�̂ł����A��̊O���Ђ̍����l�ŁA���X�ɒ����Ă���A
�u�䓙�͂��̓x�A���߂Ēm�s��������ė����B���X�͊n�ꍂ�ɑ����̏j�V�E���q�����o���ׂ��B���̂悤�ɂȂ�����҂́A������p�ɂ��Ċi�ʂ̔z����������̂ł���v
�Ȃǂ̕s�@�Ȃ��Ƃ�\����A�ǂ̑��X�ł����勤�܂Ŗ����ɋ��n���ꂽ�̂ŁA���X�ł͓����āA���ǂ��͍��܂Ō�n���l���l���ɑ��蕨�E���K�ȂǍ����o�������Ƃ͂Ȃ��|��\���q�ׁA���K���̑�����������(�d��)�Ƃ��Ĉ���ɍ����o���Ȃ������Ƃ���A�傢�ɗ��������X�ɂĂ���A�����Ȃ��Ƃ�\�����̂ł��B����
�u���̂��сA���߂Ẳ�X�ɑ��Ė���@�Ȏd���ł���̂ŁA���܂Łu�����v���s�킸�ɓ��N�̖L���ɊW�Ȃ����N�̕��ς��ȂĔN�v��[�߂Ă����u��Ɓv�̑��X�ł��낤�Ƃ��A���N���͑��d�Ƃ��A�Ȃ����̏�ꑺ�����n�����������߁A��ƔN�G������Ă���Ƃ���͖��N���n�����Ēi�X���Ƃ��|���A���X�̕S�������ׂ��v
�@���̂悤�ȓ�̂����A�S���������肽�Ԃ炩���A�V���ɉ��Ă������炦�A���l�Ƃ��Z����(�낭�܂�����)(�u�Z�����v�̂��ƁB�O�_�E��_�̑��A���̐l���������ĘZ�l�ł������邱��)�Ƃ��đ��y��n�ɏ悹����Ȃǂ̑��A�u��Ɓv�̑��X�ɑ��ł��|������A���n�̓���������Ď��ۂɌ��n��������������܂��B
�@���́A�ȑO��薼��̋��ĂƂ��ĉ�����Ă������̂����炵�A�܂��E�ɍ����グ����p�����\�N���ɂ���Ƃ̌������ł����A����ɂ͋��傽�������_�����A�����̏ꏊ�ɑi���o�邩�̗l�q�ł����B���������̂ł͓a�l�̌䖼�O���o�邱�ƂɂȂ�A�ꂻ�������Ă��鑺�X�S�������͓�a�v���܂��B
�@���N�́A�����̐l�͒m��Ȃ����낤���A���N�ɘj�銱鯂ł���A���̏㔪���\������̑啗�J�̂��ߕS���Z�Ƃ������݂ɔ�Q���đ�j���A�܂����̏o���������A���N�ł��B�����̌�n���l���������̌�p�̈�(�s��̂Ƃ��A�N�v�����������Ĕ[�߂�����)�������ꂽ�Ƃ���ɁA�E�ɐ\���グ��悤�ɁA���������q�傪���S�������č��������Ƃ��茾���Ă͕S���𗩂߂ċ���A���X�̕S���͐��藧���čs���܂���B�����ɂ�ނ����k���A�V�ዤ�ɋ����Ă��肢��\���グ�鎟��ł��B�����Ƃ��A�ꑺ���ɕʂ̏���ɐ\���グ�邱�ƂƁA��������͂���܂���B
�@��e�ޒ��l���ɂ��������������āA���̏��Ȃ�тɑ��X����̏������ᖡ�̏�A���������q��̎x�z���珜����A�S���������čs�����悤�ɋ���������A�吨�̕S���A�ǂ�Ȃɂ��L��K���ɑ����܂��B
�@�Ȃ��܂��A�ύׂ̋V�͂��q�˂̐߁A�S����X����ɂĐ\���グ�܂��B�ȏ�
�@�@�@���\�ꖤ�̋㌎��(1761)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��m�s���\��P��
�@�@�@�@�i��я��l
�@
�@�u�����q�ƒn���ɂ͏��Ăʁv�ł͂Ȃ����A��E�̌��͂������ĕS�����Ј����A�������������~�ɑ���n���@�ւ̉������m�ɋ������ꂽ�_���̎p�������ɂ������B
�����āA����n�߂����{�̓����͂𗝉����邱�Ƃ��ł���B
���̈��������q��̏��Ƃɋꂵ�߂�ꂽ�_���̑i���͂Ȃ������A�Ō�ɂ́A�u�m�s�����ǂ�ȑ����ɂȂ��Ă��A�܂�͔ނ̈��S����o�����Ƃł�����\�\�v�Ƃ��������Ă���B
�@�O�㌎�̑i��Əd������Ƃ��������A�_���̔ߒɂȐ���������ʂ̌Õ����ɂ���ĕ����Ă݂����B
�@
�@(�����q���)�������A����ǂ����ĂъĈȗ��A���͂������ɗ��s�s�����A���̏ア�낢��̏ؕ��������Ă͖����ɉ���������A�m�s�������Ƃ��ċ�A�\�������̂Ƃ��A�����Ŗʐϕs���̂Ƃ���ɂ́u�S�����v�ƌ����A�Ɛ�(���n��)�ȂǏ����ł��o���ɂȂ�ΐV���ɔN�v��\�����A�܂���Ƃ̑��X�ɑ��d���|����̂ɁA�����q��͕M�悾���Ŋ��������o���Ă��܂��A���͌����؊�������Ă��@�O�E�ߓ��̔N�v�������A���͏]�O���̕���(��)�E����(��)�E�i�r(��)�Ȃ�тɉ���̔N�v���������̂��Ƃ▼��̋��ĂȂǁA��������q�ׂ������Đ���艺���u���ꂽ���̂������Ɏ��グ�A�����ɂ��ď����ł��\���J�����܂������Ƃ�����A����Ȃǂ������ė��܂��B
�@�E�̂��ƂȂǂɂ��Ă��ؕ������A���͓I�Ɉ�`��������藧�Ă�ꂽ����ł��B�[�����s���Ȃ��܁T�v�����Ȃ���`�������o�����̂ł��B
�@�������A���X�̑y�S���͓��S�Ȃ炸�A���肢��\���グ�邱�ƂɂȂ�܂����B�ύׂ͏���̒ʂ菭��������͂���܂���B��͎̋������������Ƃł���܂��B�����ɂ�����������ĕS���菑�̒ʂ��ᖡ�̏�A�����q��̔Ȑ\���t�������~�߁A���̏㐴���q��ɂ��āA���̎x�z��������悤�ɂ��ĉ�����A���X�吨�̕S���A�������ėL������܂��B
�@���̂悤�Ȏ���ł����A��n���l�̂��Ƃɂ��Ă����k�Ȃ�����ɑ����ċ���܂��B�E�̂��ƂŒm�s���������ƂȂ��Ă��A�܂�͐����q�傪���S�������Ė@�O�ȓ�������������ɂق��Ȃ�܂���B
�@�����ɂ��Č�e�ޗl���܂Ō��J�𑊊|���A�Ȃ��܂����X�͎����č����ł���A�킯�Ă����N�͋��N�œ�V�����Ă���ɂ�������炸�A�]�ˋl�̔�p�����T��A���Ƃ���V���ɂł���܂��B
�@�������܂������̎|����e�͂̏�A��d���̌�����������āA���X�S�����������čs����܂��悤�ɂ��肢�\���グ�܂��B
�@�����͂��̕S���肢�̂��Ƃɂ��āA�挎��\�����萴���q������̏h�ւ̂��a�����������A�������V�v���ċ���܂��B����ɂ��Ă������߂�������A���a���ƂȂ鎖�͒v�����Ȃ��Ƒ����܂����A��������B�Ă��肢�����]�ˏh�ɋ����܂��悤�ɁA��낵�����肢�\���グ�܂��B
�@�Ȃ��ύׂɂ��ẮA���q�˂̐ߌ����Ő\���グ�邱�Ƃƒv���܂��B
�@�@�@���\�ꖤ(�N)�\�ꌎ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㑍�����\��P��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g��
�@�@�@�@�i��ɐD�l
�@
�@��O���킵���m�s����l�̏��Ƃɉ����A����������Ŕ_�������͔�J���Ă����B�������Ȃ����傽���͂��a���̐g�ƂȂ�Ȃ���A�Ђ����炨�肢�̋V�ɋy�̂ł���B
�@�c�O�Ȃ���A���̂��Ƃɂ��Ăǂ̂悤�Ȍ��ʂɂȂ������͕s���ł���B�������A���̂悤�Ȃ��Ƃ������Ɏ������̎��͂ŋN����A�c�悽���͕M��ɐs�����ʂقǂ̔E�]���������ė������Ƃ��A�܂�ō���̂��Ƃ̂悤�ɕ����яo����ė���̂ł���B
�_���̐���
�@����܂ŁA�m�s����l�̔��Ƃ���ɑ���_���̎p���Ƃ�グ�����A���ɕʂ̕������炻�̗l�q�����Ă݂悤�B
�@�N�v��[�ɍ��l�܂����_�����q�������ɍ��o���A���̐g���(����)�������ċ��[�������������������B�u����ɍ��o�����ȏ�A��ƕ��ʂ�ɋ߁A�����N�G���ɕs�s�����������ꍇ���̈�̂��Ƃ͐g�������l�ɉ����ď������A�a�C���O���������Ē��ς��ƂȂ����Ƃ��͈�����邱�Ɓv�Ȃǂ���e�Ƃ����ؕ��ɂ���Č��������̐g�����S�����ꂽ�B���̋����Ƃ��Ă͈�J�N�œ���O���O�オ�����A���Ɂu��Έꗼ�v�Ƃ����ĉ��Ŋ��Z���Ă݂Ă��A���݂ł͈�Z���~�O��̋��z�ł���B���Ƃ��߁E�H�E�Z�̍Œ�ۏ�͂���Ă��悤�Ƃ��A���̘J����������݂Ă����ɒ�����ł��邩���킩��B
�@���ɕ����I�Ȗʂ��琶���̈�[�����邱�Ƃɂ���B
�@
�@�@�@���Q���c����D�V��
��A���ʋM�a�̐����ȁA�����q�a�����Ƃ��䓙���[�ɖ���j���A���q�����c���ܔ����ʎ����ʒ��ʔ�Y��A�҃j�a��u�����Ȃ�B����s���V�V�j���e���j�A�߂́A�E�Y�����q�c�����ʒ��Ƃ��A�M�a�j���Ԃ��\��B�ד����ꎝ�Q����D�e�ޏؕ��A����ȍ��o�����\���@��
�@�@�@�V�۔��єN�g�˓��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�ށ@�����q�@�@�y��@���g�@�@�ؐl�@�����Y
�@�@�@�}�l�@�����q�a
�@
�@����́A����ɓ����莝�Q���Ƃ��ē�Z���ƌܔ����̓c����a���������A����s���ƂȂ����Ƃ��ɂ͂��Ԃ�����Ƃ����ؕ��ł���B
�@���̂́A�{���Ƃ��Ẳ��g�����������Ƃ��̏ؕ��ł���B
�@
�@�@�@��\�{�q����D�V��
��A�䓙�����掖�A���l�S���a�̐����ȂāA�����{���j�i���\�����ᖳ�����B�ד�M��ƈ���q�l�E���������B������q�E���͍���̐ؑ��n�����\�A�����q�E���͎q�ǂ��v��o����Y���V��葊�n�����\�A�c�������͏��V�ߋ�j���n�����\��B
�E���q����A�{���j�i�����́A�����既�ᗐ�W�\�V�͏����������B��(�}�})�ꗢ��V��ƕ��w����V�A���͉䖙���d��C�j���s�\�V�L���V��n�R�A���Ƃ��䏟�莟��j�䎷�l(�Ƃ�͂��炢)���탌����B�ד������ֈ�D�����@��
�@�@�@�N�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���q��@�@�ؐl�@�`���q��@�@�}�l�@�S��
�@�@�@�@�{���@���E�q��a
�@
�@�����ł́A����̂Ƃ��Ɉ�Z���A�q���o�Y�̂Ƃ��Ɉ�Z���A���̎q���̏��ߋ�Ɏc����Z�����A�������ēn���悤�ɂȂ��Ă��邪�A���̂悤�Ȃ��Ƃ����K�Ƃ��Ă������悤�ł���B
���O�E���Y�E���E�䏊���@�@--------------------
�\�]�O(�Ƃ��)
�@������
�{�O�q(���Ƃ݂���)
������
692�`694/1069�y�[�W
�@���ʑ��Ԓn�ɂ���B�����R�����@�������Ə̂��A�V�`�^���@�������h�����݂���)
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
�J�O�q���ʎ�
721�`721/1069�y�[�W
�@�s������˘Z���Z�Ԓn�ɂ���A�����R�@�ω@���ʎ��Ə̂���H���R�n�̏C�s��
�i���ȉ��ȗ��j
�o��(���łʂ�)
�F��R�������@�V�`�^���@
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
�O��(�Ђ̂�)
�O�ؐ��{��_
�O�ؐ��{��_
�@�@��������������Ò��̖���������
�����R������
644�`646/1069�y�[�W
�@�����m�n��ɂ���A�{���ɑ���@���ŁA�����R�ƍ����Ă���B�V�`�^���@�L�R�h�ɑ����q�쑺(���ƍ������A�������s)�ϕ����̖����ł���B
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
���Y
�@���Ď��Y���Ə̂������̏W���́A�����Ò����ꂩ�瓌�k���֖�Z�L���B���͌I�R������ɍ���A���͑��E�o���A��͐��Ó��A�k�͏��O�q�̊e�W���ɐڂ���u�˒n�тɁA�P�O�O�˂��܂�̐��тɂS�V�O�]�l�̐l����L���A�����ɂ����Ă͋��w�̑�W���ɑ�����B
���a�Q�X�N�̒��������O�́A���v�ꑺ�̒��S�n�Ƃ��āA�v�ꑺ�̎�v�Ȍ��I�@�ւ̂قƂ�ǂ͂��̏W���ɒu���ꂽ�B
���R��n(���J1835)�ɂ���u�i�m�O�N(1295)�\���\�l���v�A�܂��u������N(1320)�v�ƍ��܂ꂽ�̔肪����B
���Y����R�i�䎛
�@������ܔ��ܔԒn�ɂ���A�ꔽ�O�����܂�̋����͘V���Ɉ͂܂�A������ɑ���ꂽ�{���̑剮�����Â��Ȃ������܂��������Ă���B�u����R����@�i�䎛�v�Ə̂��A�V�`�^���@�q�R�h�ɑ�����
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
���Y�����Ё��������Ò��̖���������
���
����R���A�@
611�`611/1069�y�[�W
�@��厚����435�Ԃɂ���A��R���A�@�Ə̂��A����(������)�L�ώ��̖����ł���B�^���@�q�R�h
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
�����@�ؓ��@�u���Ò��j�@�����v615�`
�@���Ԍ���385�̓��H����Βi��o�����Ƃ���ɂ���A�^��(�I������)���Ƃ�����@�@�M�k�̕�n���Ɍ��Ă��Ă���B
25�������قǂ̓����ŁA���@�h�ɑ����鑺�l�B�̏@���I�s�����A�����ōs����B
���Ì�(�����͂�)
���Ì��F��R���@�ω����@�^���@�V�`�h
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
����
���Ó��Α��匠��
438�`439/1069�y�[�W
�@�u�Α��匠���A��V��A���V��A�c����(1866)�O���g�˓��@���Ó��W�u���v�Ƃ���B
�@�{�Ђ͐_�ސ쌧��R���ɂ���A�Ր_�͑�R�_���ł���B���̋��ΐM�̈�ՂƂ������A�J��̐_�Ƃ��Ė������B���͈��v���_�ЂƂ����B
���������R�n���@�E�E�E�E�^���@�q�R�h
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
�䏊��
�䏊��V�䒆�喽�_�Ё��������Ò��̖���������
���䏊��@�ؓ��@�u���Ò��j�@�����v466�`
�@�����c�_177�Ԓn�ɂ���A�����\�l�N�v�ꑺ�˒�����́w�_�Ў��@���ג��x�ɁA�u��A�{������@���A��A�R�����ځA���Ö������A��A�����ؐ��l���A��A�M�k��\�l�v�ƋL����Ă�����@�@�̌䓰�ŁA�������������ɐΓ��Q�Ɉ͂܂�Ă���B
�@���w�ɂ͐~�q���Z�قǕ���ł��邪�A���S�I�Ȃ��̂͑c�t���@��l���ŁA���̔��Ɂu���B���Z�l�{�藧���������b�q��(�ꔪ�Z�l)�����g�C���v�Ɩn������Ă���B
�@���W���̑��ː��R�W�˂̂����Q�O�˂����@�@�ł��邪�A���̔��ɋL����Ă��閭����Ƃ́A�������̓��ɕ�d���Ă�����m�̂��Ƃł����낤���B
�@���ŁA����@���Ǝv����~�q���O�����āA��̔��ɂ́u�������b�q(1864)��O���ċ����������\���v�ƋL����Ă���B
�@�q��������������A�S�q��_��������B���������d�����Ƃ����A�q���u�̖{�n���ł���B
�@���Ƃ̈ꑸ�͕��l���ŁA�~�q�̔��ɂ́u�k������S�v�ꑺ�V���䏊�䍂���V���q��Z�\���S��j�t�@�����\��N�Β��H��������m�V��`�����[�@���Ηz�����O���u���䓰�j�ڃX�Җ�@�h�H�l���×W�ѓc�v�g�@�J������[�ԉ�]���Ö������l�\�ꐢ�v�Ə�����Ă���B
�@�������̖{�Ђ͌F�{�s�V�x���ɒ�����������_�ЂŁA���a�����ɗ쌱�������A�M�҂͑S���ɑ����B
����(�Ă炳��)
����y���R���T���@�V�`�^���@�������h
�@�@�@�i���ȉ��ȗ��j
��ˎR
��ˎR��t���@�u���Ò��j�@�����v541�`
�@�ߋ��ɂ͐��J���̎��@���������悤�ł��邪�A���݂͈ꎛ���Ȃ��A���̂قƂ�ǂ͎��쓌�T���̒h�ƂŁA�@���I�ȏ��s���͑�t���ōs���Ă���B
�����������@--------------------
�@�@�@�@�@�����ÐΑ��������ݐ}
�����Ẩ��v�Ǝx�z�ҁ@�@����353�`
�@�@�i�O���j
�@����(1183�`1573)�ɂ͐�t���̏��̂ƂȂ�B
��k����(1336�`92)��t����̌�������͑��Õt�߂�̂��đ��Î��𖼏��A�O�q������������A���t�ȉ���c�����̂��Ďq�������ɓ`����(���f�ٖ{��t�n�})�B
���������ɂ́A��t���̎x���������������×̎�ƂȂ�l�ׂ�̂���(�w���×R���L�x)�B
�@�V���P�W�N(1590)��������c���T�N(1600)�\�ꌎ�܂ŕۉȐ����B���X�N(1604)���猳�a�W�N(1622)�ɂ����Ă͓y���Y�v(���Ђ�)�E�Y�d(������)���q�B
���̌�A�c���P�T�N(1610)�t���獲�q�ˎ�ƂȂ��Ă����y�䗘�����A���i�P�O�N(1633)�ɌÉ͂ֈڂ�܂ŏ��̂Ƃ���(�w�����d�C���ƕ��x)�B
�ꎞ���{�����̂ƂȂ��������i�P�Q�N(1635)�������`�̗̒n�ƂȂ�A�����Ɏ���܂Ŏ�������B
�@�@�i�㗪�j
�����������i����R�������j�@�@����373�`
�@�R���E���N�@�@�@�@�@�������������A������������
�@������2550�Ԓn�ɂ���B���@�@�Ŏ߉ޑ���l��F��{���Ƃ���B
�w����S���x�ɁA�u���`�ɍO����(1278�`87)��݉@�����̑n���Ƃ���B
�����͖{�����������j�Ə̂��A�㑍�������̐l�ŁA��ɓ��@�ɋA�˂����̒�q�ƂȂ�B
�@�@�����䖭��R���������Q�Ɓ@�@�@�@�@���������Ό��������̊J�R�ł���B
�c�t���̓��@�����͓����̎������������̂ŁA��؎O�̂̑c���Ə̂��A���@�͂��̑��Ɏ�����陂�t���āA�u颂̑c�t�v�Ɩ��Â��B
���ߐ��䑺�����ɂ���������ɍ��̒n�Ɉڂ��B
�@�@���匴�E����E������E������E����������E�@���^�_�ЁE���@���Q��
���\�l�N(1691)��������������{���Ɍw��F���𖽂����A���l�N(1754)�O�����͂�t�����Ƃ������ꂽ�v�Ƃ���B
�@���䂩�瑽�ÂɈڂ����N��͖��炩�łȂ����A�w���×R���L�x�ɂ́u���\�E�V���̖��ɂ��c�����N(1602)�̏��꒠�ɂ��V�����\�Z�J���A���Ƃ��\���J���ŁA�������͍ڂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�c���̖��N�����a��(1615�`23)�Ɉ����ڂ����Ƃ݂���B
�Ï��Ɂu���i�l�N(1627)�]�˒J���@�����̌Ó����ڂ��A���̓��͋��ۏ\�l�N(1729)�Z���̌����v�Ƃ���B
�@�����́w�Ў����ג��x�ɂ́@
�@�@�@�@�@��t���lj�����������S����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�،o���������R�@�،o������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@������
�@�@��A�{���@�@�@���@���߉ޑ���l��F�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s�ځ@�@�@�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ���ԁ@���s�Z�ԎO��
�@�@��A�����ؐ��@���E��@�@���L�n��l��
�@�@��A���������@��F�@�c�t���@�{���F���@��l�@�R���F�s�ځ@�����F�Ԍ����ԎO�ځ@���s����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����x�V���@�{���F�����x�V�@�R���F�s�ځ@�����F�Ԍ��l�ԁ@���s�O��
�@�@��A�Z�E�@�@�@�b��{�s�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�玵�E�l�l�@�@�ȏ�
�@�Ƃ���B
�@���\�\��N(1698)���{���O�\�l����v�@�����ɂ���ď����ꂽ�w����R���N�x�������ɂ���A���͂��̔����ł���B
�@�@�@�@�@����R���N
�@���������ӑ�����R�������ҁ@��݉@�������l�V���J蓖�@�����Ό����]�猓�j���`�@�c�V�w�V�O���@��(������)�������p(����)�����s�N�听�@�X�^�O�@�V�u���������@���t�m�@�֚��s���@�{���e�m���ȋ����@��ȍO���Z�Nᡖ��܌����ܓ����R����@���@�(��)�n�ғ��@�c�V�ݐ��I��(�����炩)�����V�����V�V��嫖����V�@�Ȏ����V�����������@����ʋ��������R�V�O�����S���l�@�]��@�o�c���{�V�K���������l�N�\�ꌎ��������@�����������]�@�֔V��n��@(����)�����n������@�V���ܔN�L�������\�o������@抓����@��玆�����ȍ����F�菊�@�ȘH���r�j�����L��ڒu�z�n�@���O�V��R���ތÏ�V��c��@�c�����|�k�����\��(������)�V�V���ܔN����t��������冺���P����(�㗪)
�@�@�@���\�\�ꗴ�ɕ�ЍΌ܌���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����R���{�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��v�@�����L
�@�{���N���́A���ۓ�N(1717)�ɖ�������\�l���q�_�@���M�����ʂ������̂ł���B
����̏����E�������E����
�@�E�����c�t�����u���@����
�@�������̓��@�����͑��Ɂu�Ђ��̑c�t�v�ƌĂ�A���g��Ŋ�A�ʊ�A���`�B���̗e�p�ɂ͍����ȓ������m�̖ʉe���Â�����̂�����B���݂͈߂𒅂��āA�t�H�̈ߑւ�����d�����B�������̍�B(���a�l�\�l�N�܌����@���l�W�L�^)
�@�h�Ə����̑c�t���ؔŊ|���ɂ́u�}��R�V�c�t�����ҁ@�g���@�r���{(�}�})�O�́@���V���@���l���V�`���@���c��𦬠��E��ڎ���J��V�쑜��e��@���Ñ����䖭��R���������ܐ����ρv�Ƃ���B
�@���̖@�ʂ́A������ڎ����A�G����ڎO�������A������ڌܐ��A�I����ڋ㐡�����A������ڌܐ��A������ڎO���A�ʕ��ܐ��ܕ��A���������ܕ��ŁA�ޗ��͗ǎ��̕O�ނŒ���ڎ����A����ڎO���A�����㐡�O���̕���O��Ɋ����Ď啔�Ƃ��A���㎈���͂��t���A�g�����͒���ڎO�������A�����������A�����l���������Ă���B���Ɠ��̎O�p�`�̌������₢�㎈���I�ŊĂ���B�����͂���Ɋ�ʂ����O�Ŋ���Ă���B���͋ʊ�ׂ̈ł���B�����������̒���o���̕����͊Ă���B�啔�̑O��̊���͓����ł͊��͕��ς��Ă��邪�A�����ɗ��č�����E�ւƌX������ŎΖʂ��Ȃ��Ă���B���啔�̑O��̓�����Ɉ�t�̖n��������(���痈ꎁ�̕w�[���̋��y�j�x)�B
�@�ٓ���(�n��)�͏ȗ����邪�A���͉i�a��N(1376)��\�ܓ��A��h�ߕ������}���̕�Ɖ~�鎛�}�����q��ь������̑����Ƃ���B
�@�~�鎛���͐�t���̈ꑰ�ł���A�����͑��Â�̂��������̎q�ɓ�����悤�ł���(���R�@�،o�������A�����ܔN(1372)���������g��)�B��t���͌��������ł�����������𖼏�������R�͕s�ڂł���B
�@�E�k��(����)
���Ï�勍���\�o������̊�i�A�u���i�������Ӗ���R��������U�ߋ����E�ߑ�v�����h���@�V���ܔN���N�nj��Z���@�������Z�m����@���@���e�v�̍���������B���A�a�O�Z���`�ŁA���������̕a�����F��̂��ߓ��̓��ĂƂƂ��Ɋ�i�����Ƃ�����(�w���×R���L�x)���A���Ă͕s���ł���B
�@�E����̉�������ڔ�
�@���ŁA�j�����邪�A���̈��͉����ܔN(1372)�\�ꌎ�̌����ł���B
�@�E���铕
�@�R������E�ɉÉi��N(1849)���������B��卂��O�V�E�q��E���Α������q��E���ˑ����E�q��̍���������B���224���̔[���z����ю��������܂��B
�@�E���ړ�
�@�����ɂ͕���N(1759)�����B���ɂ́u��؎O�[�c�t���F���u�v�Ƃ���A�u�{�����^�s�@��_�O���q��@��_�����q�@�������E�q��@����^���q�@�g���u���v�ƍ����B
�@�E���̑��̐Γ���
�@�������ɉ���l�N(1676)�O���A�����j��������������⸈�
�@���i���N(1778)�\�������̌ܕS����
�@�����\�l�N�\�������̘Z�S������ړ�������B
�@�܂��Βi��ɕ��R�����q��i�̏�铕��ΉÉi�ܔN(1852)�A�������N(1790)�A�������Éi���N(1854)�A��s��F�Α�������A��ɑO�ɖ����x�V�A���q�肪����B
�@�E���O
�@���ċ��������̒��i�ɂ������B�����ɂ́u���\�Oᡖ��N(1763)���H�@��\�㐢�q���@���ƒ��H�]�ː_�c�Z���������������s��@�{��l�D�z�܍��q�唭�N���y�h���v�ƍ����A�������ɂċ��o�B���݂̏��O����ў����͏��a�T�S�N�̌��������B
�@�E���L�����䶗��{��������B
�@�@���S�@�����@��N(1357)�K���A�����@�i�a�@���N(1375)�܌��A�����@���i�\�Z�N(1409)�����i�����̕����͕s���j
�@�@���e�@�����\�Z�N(1484)�����A��俒�@���T�@�O�N(1572)�����A��俒�@�V���@�ܔN(1577)�܌�
�@�@��俒�@�V���@��N(1581)�㌎�A���b�@���\�@�O�N(1594)�\�ꌎ�A���ʁ@�c���@�Z�N(1601)�㌎
�@�i�㗪�j
2023/10/19�B�e�F
�@������������F�F�u���j�v�O���r�A����]�ځA���a�R�S�N�匴���̖���������J�����B�����͖�V�R�����B���q����̍�Ɛ��肳��A��t�����̑��ł���\���������B
�@���Ö��������铕�F�Éi��N(1849)�����@�@�@�@�@���Ö��������ڐ��F����N(1759)����
�@�������R��P�@�@�@�@�@�������R��Q�@�@�@�@�@�������Q���@�@�@�@�@�������������F��
�@�������{���P�@�@�@�@�@�������{���Q�@�@�@�@�@�������c�t���@�@�@�@�@�������ɗ��@�@�@�@�@���������O�@�@�@�@�@��������
�@��������ڕ�
�@���������E���Ôp��������@�@�@�@�@����������
�@���������E���Ôp�����掏���̂P�F
�@����O���A����O�@�����A����O�������A����O���@���A�V�����i���j�����A�x���{�@���A�{���������A�����^�O�����ƍ��ށB
�@���������E���Ôp�����掏���̂Q�F
�@�匴���@�����A�匴���������A���˖{�����A���˚��\���A�L�����A�L�����v���A�L���@���ƍ��ށB
�@�ȏ�̔p���͑S�ĉ��́����Î��Ձ��ɋL�ڂ���B
�@��������⸈��F����l�N(1676)�̂��̂��i���m�F�j
�����Î��@�Ձ@�@����378�`
�@�]�ˎ���ɂ́A�����Ɏ��@���\���J��������(�c���V�N���꒠)�Ƃ������A���݂͖������݂̂��@�������A�����͔p�����B
�p���ɂȂ������@�͎��̒ʂ�ł���B
�@�����Ñ匴���@����
�匴���ɂ������B
�r�̏��т��Ï��R�@������ł��������A�����R�P�N���䏬�c�ӁE�ˍ��ʉ߂��錧���̕~�݂ɂ���ċ��������f�����B
�����̋����͂T�Q�P�A���@�@���R�@�،o���̖����ŊJ��͕s�ځB���Ɛ����@�Ə̂��A���{�̕ӂɂ������Ƃ����A����ɓV�����N(1573)�匴���Ɉڂ����Ƃ���B
�����͂͂��ߓ쑤�̎R���ɂ����������A�Ȃ̂œV��(1830�`40)�̂���k���Ɉڂ��B�������������悭�Ȃ莛�\�����悩�����Ƃ�����B
�@�吳�Ɏ���S�P���Óc���ǂ̂Ƃ��i�����Áj���˖������ƍ����������A���a�R�N�ɔp���ƂȂ����B
�@�u�}�f�C�h�v�̕�n�ɗ���肪����B
�@�@���u�}�f�C�h�v�̕�n�Ƃ͈ʒu�s���ł��邪�A�{����n�̂��Ƃł���Ȃ�A�����ɖ@���i�����j���������̕�肪����A
�@�@���̕�肪�Y������̂����m��Ȃ��B
�܂��V�����h�ɂ̔����͋��a���N(1801)�̒����ŁA�@�����̖������܂��B
�@�����썂��ɖ�����������A���N�Z���\�ܓ��ɍ炪�s��ꂽ���A���a�R�T�N�p���ƂȂ�A�������͖������Ɉڂ����B
�@�w�Ў����ג��x�ł�
�@�@��t���lj�����������S���Ò����Î��匴��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�،o����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�O�N�p��
�@��A�{���@�@�@�߉ޕ�
�@��A�R���@�@�@�s��[�����l�\��N�����\�O���������e�W��������O�j�A���V���i�������ɂ���j���{���j�����X]
�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��܊ԎO�ځ@���s�܊ԁ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�ܕS��E��@�@�@�@�@��A�Z�E�@�@�@�Óc���
�@��A�h�k�l���@(�L�ڂȂ�)
�@�@�吳�P�O�N����������t��ρW�����啪�����S�O�d���G�ړ]���j�����������������W�������������G�ړ]�m�㓪���m�y�n�������G��t�X�@�吳�\��N�ꌎ��������t���m���܌�����Y������X�L�ڃX
�@���Ȃ��A���Ɍf�ڂ̒��h�R�������͖@�����̉����Ƃ����B
2023/11/20�B�e�F
�������Ö@������
�@���Â̓��@�@�̍O���̉ߒ��ŁA���S�͉�����N(1357)�l���O���ɉ������Ó��E��苗��䓰���{�A�����l�N�i1359�j�\�ꌎ��\�����̐�c�������䓰���{�A������N(1396)�̐�c�����Ó��E��Փ����{�Ȃǂɏ����t���߂����Ƃ��L�^����Ă���B
��L�̉�����N�ɊJ�����{���c�܂ꂽ���E�i���������j�̌䓰���₪�ē��@�@�̎��@�ɐ������Ă��������̂ƍl������B
�匴���̖@����(���̐����@)�́A���邢�͂��̓��̌�g�ł͂Ȃ����Ƃ��z�������̂ł���B�i�u���Ò��j�v�j
�@���Ö@�����ՂP�F�r�i���V�r�H�j�̌����Ɍ���������A�����������Ɖ]���B�r��O�ɂ͑�Γ��U���c��A�ٍ��V�Ђ�����B�ٍ��V�Ђ̌������č����H���u�Ă��Ƃ��낪�������̂������ꏊ�Ɛ��肳���B
�@���Ö@�����ՂQ
�@�@������Γ��U�P�@�@�@�@�@�@������Γ��U�Q�F�ӏ��R�͖@�����̎R��
�@�@������Γ��U�R�F�u�ӏ��R��\�l�����R�v�ƍ����B
�@�@�����̑�Γ��U�̖��ɂ��Ắu���Ñ匴�������v���������Ò��̖����������ɂ���B
�@�@�����ٍ��V���F���̎Ђ͑�������V�Ёi���ɋL���f�ځj�ł���A�@�����Ƃ͖��W�����m��Ȃ��B
�@�Ȃ��A�匴�������̍��Ɂu���āi�匴���������j�����ɂ��������i���N(1778)�]�ˑ�ŋ������A�������s�����ŋ����A��呺�c�����q��[�̐Γ��ẮA���a�T�Q�N�r�[�ٍ��V�O�Ɉڌ�����B�v�Ƃ���̂ŁA���m�F�ł͂��邪�A���V�БO�ɂ���Γ��U������ł��邩���m��Ȃ��B
�@����@�����������ՂP�F����匴���������Օt�߂ɏ��K���c��A���������Â��K�Ƃ��v������s���B
�@������������ՂQ�F�Α��w���̎c�����c�邪�������̂��̂��ǂ����͕s���B
����ɁA�u�Α��������ݐ}�v�ɂ��A��L�́u��Γ��U�v�O�Ɂu�������F��v�̕\�������邪�A�s���ł���B
��Γ��U�̉��ɏ������Α������i�̂悤�Ɍ�����j�����邪����ł��납�H�B���������N�̔N�I�������B
�@�����Ö،˒J�i����O�j���i���ʒu����ł����j
����R���͖،˒J�̒r�̏�ɂ������B
�����͑��ÍŌÂ̎��@�ŁA�`���ɂ��Α哯�N��(806�`9)�O�@��t�̊J��ŁA���̒n���u�V����v�Ə̂��A�O�̒n���u����O�v�Ɩ��t�����Ƃ����B
���͂��Ɛ^���@�Ŗ�t�@�������u�������A��������̂͂��ߓ��S�̕z���ɂ����@�@�ɉ��@�����Ɠ`������B
�����ߋ����Ɂu�ȑO�͕ӓc�O�Ȃ�A���������딨�̏��Ȃ�A���̎����͎R��m�E�q��̉��~�Ȃ�v�܂��u���̎��A���������ɂďĂ���A�N���͊����ܖ��N(1665)�\�ܓ��Ȃ�A�ߔN�͊����N(1749)�l���\�����鎩�ɂĎc�炸�āA�ߋ����܂ł��Ă���v�Ɓw���i�L�^�x�ɂ���B
���N��(1751�`63)��������������B
�V�۔N���ɂ͌��V�Ɋ�ς̏�A�\�J�N�ɂ킽���ďt�H�Ƃ��ŋ���������(�����L�^)�Ƃ̂��Ƃ����A�����Ɏ����Ď��^�������A���Q�U�N���Í������w�Z�A���S�O�N���Ô_�w�Z�̉��Z�ɂƂȂ�B
�吳���N���ɔp���ƂȂ�匴���@�����ɍ����A�@�������܂��������ɍ�����B
�吳�W�N�{���p���ēc���Ɉڒz����A�����̈ꕔ���ޗF��(����)�Ƃ����B
���n�͑��Ñ�J���ɂ���ď��ł����B
�@�����Í����^�O���i�����݁A���Ղ͐e�Б�_(�����l)�ƂȂ�j
�@�����ɂ����āA�����R�Ə̂���B
�w���\����x�ɐ���V�Ƃ���B�܂������@��V�Ƃ������A�w�^�O���ߋ����x�Ɂu�J�R���v���l�V����\�O�ДN(1554)��\�����J���v�Ƃ���(���i�L�^)�B
�����͒��R�@�鎛�̖����ŁA���̗a�莛�ł�����(���E���ۋL�^)�B
�������h�ɂ̔����͂��Ɛ^�O���̂��̂ŁA�����O�Ύ�����(1806)�~�\���̒����ɂȂ�u���̐��b�l�����d���q�@�������q�@��_�����q�@�F�ꑺ���Y���q�@��،��E�q��@�{���\�����ܕ��q�@�{�������q��@�{�����s�@�@���M�m�@�H���q��M�m�@�����M���@�����t�������@������Ǔ����M�`�v�̖�������B
�@�����Ö{��������
�����R�Ə̂��Ė{���ɂ������B
�u�Ï��ɂ͎����V�Ƃ���A�����V���̍��J�����v�Ƃ���(���i�L�^)�B
���Ă̓����̗��R�̕ӂ�ɕ��Z�N(1756)�����̈�א{�A���i�l�N(1775)�̎O�鋟�{�肪����B
�܂������m�̕�肪�{����n�ɂ���B
2023/10/20�B�e�F
�@���Ö{���������P�U������F��ʂ́u������/�\�Z���@�����@����v�ƍ����B�w��ɂS��قǕ�肪���邪�u�哿�v�Ȃǂ̕����������A��������������̕��ł��邩���m��Ȃ��B
�@�����Öx���{�@��
�x�̐K�ɂ������B�u�Ï��ɂ͘@�ؖV�Ƃ���A���@�؎R�ƍ����v(���i�L�^)�Ƃ���A���������̖����ł������B
�����̑�ڔ肪�A���܍����̎d�u���n�ɂ���B
�����͒厡��N(1363)���E���ʂ̒�q�����̊J��ł���B���̎��͒��₵�������T��N(1571)�@���V�ɂ���čċ������(���E���ۋL�^)�B
�@�����ÐV��������
�@�V���R�ۂɂ���A���h�R�Ə̂����B�u�Ï��ɂ͊w��V�ƗL��v�Ƃ���(���i�L�^)�B�܂����~���Ə����ꂽ���̂�����B�Ï��R�@�����̉����ł������B
�@�����Ñ匴��������
�@�匴���ɂ������B�u�Ï��ɂ͑呠�V�ƗL��A���̎�����ˍ���z������Ɖ]���B���̎������̖������ɂďĎ��A�ޏĂȂ��v�Ƃ���(���i�E�����L�^)�B
�@�����Ö،˒J�i����O�j���@��
�@�،˒J�ɂ������B�u�Ï��ɂ͌c�z�V�Ƃ���v�Ƃ���(���i�L�^)�B
�@�����Ö،˒J�i����O�j������
�@�R���͖��F�R�ŁA�،˒J�ɂ������B�u�Ï��ɂ͓�~�V�ƗL�B���̓������͌Ðl�̘b���Ɏł̓������͑O���J�������Ȃ�B�����������Q�Ȃ�Ɖ]�ւ�B�q�a���ɍ����ֈ�������A���Ղ֍��̓����������Ȃ�A�{�͍��c�̎���������v�Ƃ���(���i�L�^)�B
�@�����Ö،˒J�i����O�j�@����
�@�،˒J�ɂ������B�u�Ï��ɓ�z�V�Ƃ���A�������̖�����B��{��_�̕ʓ����ށv�Ƃ���(���i�L�^)�B�V�ƎR�Ə̂����B
�@�Ȃ��A���������c�ł�������{��L�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�@������{��_�G
�@�@�u���j�v�ł́�������O�ɂ���A�Ր_�̓A�}�e���X�A�R���͕s�ځA���c�͖،˒J�ɂ������V�ƎR�@�����ł������B���Ƃ���B
�@�@�u���n�ē��v�ł́��哯�Q�N�ɐ�����A�}�e���X���������A����Ƃ������Ƃ������Ɖ]���B
�@�@�u���̌�V����@�x�Ɏ��������͗�����R��G�ꑊ����₩�ɓV�ƎR�@�����Ə������߂�B
�@�@�n���͒����ȑO�Ǝv����B�v�i�����Ӗ��s���j�Ƃ���B
�@�@�������N�_�������ɂ��A�Ր_�A�}�e���X�͎��@��蕪�����A�ʏ͓̂V�ƎR�Ж���{��_�ƂȂ�B���Ɛ����B
�@�@�܂��A
�@�@�{�a�O�̐Γ��ẮA�����O�N(1746)�\���Ôˎm�g�c�S�E�q�喞��A�K�����E�q��[�t(��)�̊�i�������̂ł���B
�@�@���������ɓV���O�N(1783)�����A���q�u�������̐����c���q�ƁA
�@�@�V�ۋ�N(1838)�\�R�@���A���x�̐K�����q�����̎R�_���J��Γ�������B
�@�@�������ɉÉi���N(1848)�����A������i�̑傫�Ȏ������B
�@�@�l�ʂɑ��Ôˎm�A��������A���Ñ�����A�g���A�S������͂��ߊ�i�ҘZ�ܖ��̎��������܂�Ă���B
�@�@�����̒����͕����\��N(1815)�l���̌����Łu�ʓ��@�����\�ܐ����@���ϑ�v�Ƃ���B�@�Ƃ����B
�@�@2023/10/19�B�e�F
�@�@���̒n���ł͑�_�̓_�C�V���Ɣ�����B
�@�@�ȑO�͓V�ƎR�@�����Ə̂����悤�ł��邪�A���݂͍��Ɛ_���R�Ƃ��ċC���������B
�@�@��{��_�����@�@�@�@�@�@��{��_�����@�@�@�@�@��{��_�{�a
�@�����Î˖{����
�@�����R�Ə̂��ċ��˂ɂ������B�u�Ï��ɂ͖{�z�V�Ƃ���v�Ƃ���(���i�L�^)�B
�@�����Îˉ~�\��
�@���˂ɂ������B�u�Ï��ɂ͉~�z�V�Ƃ���v�Ƃ���(���i�L�^)�B
�@�����ÍL����
�@�L���ɂ������B�u�Ï��ɂ͖{��V�ƌ�������A���̎��͐��ˑ��̊C�V�J����������Ɖ]����v�Ƃ���(���i�L�^)�B
�@�N�i���N(1342)�����A���E�����̒�q�����̊J��ł���(���E���ۋL�^)�B
�@�Ȃ��A���Ɍf�ڂ́u�L�����c�_�v�̍����Q�ƁB
�@�����ÍL�����v��
�@�L���ɂ������B�u�Ï��ɂ͘@��V�Ɖ]�ӁA���̖V���ƌ��ւ���B�̂�����̎u�w���Ɖ]�ӂȂ�B����̍���肩���ֈ����ɂ�������v�Ƃ���(���i�E�����L�^)�B
�@�����ÍL���R�@��
�@�L���ɂ���L���R���̂����B�u�Ï��ɂ͈��V�ƗL��A�����₽��B����y���q��旧�A�@�Ɖ]���v�Ƃ���(���i�L�^)�B�����̂���p���ɂȂ����B
�@�����ÍL��������
�@�����ێ��N�̋L�^�Ɏ������o�Ă��邪�A���̐Ղ͕s���ł���B
�����ÁE�H�T�̏��K�E���{�E��Ȃǁ@�@����382�`
���Ñ匴������
����������
���ÌÏ閭��
����������
�@�ȏ���������Ò��̖��������Ɍf��
�ٍ��V�̏��K��
�@���Ñ匴���ٓV�{
�@���Ë��˕ٓV�{
�@���ÐؒʕٓV�@�Ƃ���B
2023/10/20�B�e�F
��L�̓��A
���匴���ٓV�{��
�@���匴��3865�Ԓn�̒r�̒[�ɂ���B�w���×R���L�x�Ɂu���\��(1688�`1703)�ٍ��V���_����蓖���ֈڂ��A�i�F��낵���p���r�֊����̗R�A���̐ߖL�O�珟�ȗl���^�䐾��̗R�]�X�v�Ƃ���B���Ȃٍ͕��V������̐����O�N(1713)�O��Ή�������喼�ɗ��B
�@���Г��u�ٍ˓V�v�̝G�z�Ɂu���������ӗ̎匹���S�@���i�O�N(1774)���~���{��i�V�v�Ƃ���B
�@�܂������̋L�^�Ɂu�����N��(1818�`29)�̎傪(��)�Ɛ\�����̂��n�߁A���q���W�ߕٍ��V�̉J�Ƃ�A��t�Ă��o�����̎�����ӂ��n�ߌ�v�Ƃ���B�i�u���Ò��j�v�j
�@���ʐ^�ɂ��Ă��匴���@�����ɂ���B
�S�q��_�F���Âɂ͂���������B
�@���Í����S�q��_�F�e�Ќ����̋����ɂ���B�����Q�Q�N�������l���ɂ�����J��ꂽ�B
�@���Ö{���S�q��_�F����_�Ћ����ɂ���B
�@�@�����т���̓��Ԑ\������̌�e�|���Ɂu���ۏ\�O�N(1728)�{�����l���v�Ƃ���A��e�͏�@�M�Ƃ���B
�@���Í���O�S�q��_�G��{��_�����ɂ���B
�@�@�{�͉������N(1744)�܌��g���̌����ł���B���_�̏����т���͑匴���E�V���E�x�̐K�E�����̏��l�����ɂ���čs����B
�@���ÐؒʋS�q��_�F�V�_�Ђ̋����ɂ���B
�@���ÍL���S�q��_�F�����Ñ�2284�m1�Ԓn�ŁA�ʏ̌Ï��ɂ���B
�@�@���D�Ɂu�����ܔN(1822)������g�������B����S���ӑ����v�Ƃ���B
�@�@�@�@�@���ʐ^�͒����Ɍf�ځB
�@�@�@�i�������т���F��t���������ق̃T�C�g�ɂ͎��̂悤�ȉ��������B
�@�@�@�@�����̔_�Ɓ|����S���Ò����Â̎���
�@�@�@�@����S���Ò����ӂł̓I�r�V����j���ʁX�ɍs���Ă���A���I�r�V���͎q���ɉh������ď��������ōs����B
�@�@�@�@��_�̂ł���S�q��_�̊|�����⋟��������A���H�Ƌ��ɂ߂ł����̂��̂��ē��Ԃ̈��p���s���B)
2023/10/19�B�e�F
�����ÍL���S�q��_
�@�L���Łu���Â��������v�̏ꏊ��T�����ɁA���̒n��̋撷�ł�����i��L�S�q��_���D�ɂ�����̈ꑰ�Ǝv����j�Əo��A�����ƍ��킹�Ĉē����B
�L�����������E�S�q��_�͑��̎��_�ŁA�����������J����Ƃ����B
�L���̋S�q��_�E���ʎR�E���������E���c�_�̈ʒu�ɂ��Ắu���ÍL���ē��}�v�Ɏ����B
�@�L���S�q��_�P�F�������č��ɂR��̐��K���ʂ邪�A�L�����ʎR�ł���B
�@�L���S�q��_�Q�@�@�@�@�@�L���S�q��_�R�@�@�@�@�@���Ï�e�`�Ռ��F�S�q��_�w��͑��Ï�ՂŞe�`�Ռ����c��B
2023/10/19�B�e�F
���L�����ʎR
�u���Ò��j�@�����v�ł�
�@�L�����ʎR�@�����Ñ�2284�m�P�Ԓn�i���L���S�q��_�Ɠ���̔Ԓn�ł���j�ɂ���A�ʏ̌Ï�Ƃ�����Ƃ���ł���B
������\���N�㌎�����̐{�������āA�߂��ɂ͓V�یܔN(1834)�̎O�\�Ԑ_�{�A���a�l�N�̌Õ��_�Ђ̐{������B
�@�L�����ʎR�F�������č�����A�Õ��_�ЁE�O�\�Ԑ_�E�����Q�V�N�{�ł���B
�@�Õ��_�А{�@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_�E�����Q�V�N�{
���c�_�F���Âɂ͂���������B
�@�i�����c�_�E�n���ω��E�{�E��ڔ�E�ω��E���ʑ喾�_�ȂǑ������邪�A�L���͏ȗ��j
�@����L�̒��̍L�����ʎЂɂ��ẮA������̍L���S�q��_�̍��Ɍf�ځB
�@�����̒��̍L�����c�_�͒ʂ肪����Ŗڂɂ����̂ŁA���^����B
2023/10/19�B�e�F
���L�����c�_
�@���L��2375�m1�Ԓn�̋������猧���ւ̏o���̂Ƃ���ɂ���B
���i��N(1780)�̐{���J���̒��ɂ���B���a�\��N�ɎЉ������C�����B
�@�Ȃ��A����ɂ͖{���Ə̂���ؔ��ɔ[�߂�ꂽ�{�����邪�A����͎l������w�����Ă������̂Ƃ����Ă���B
�@�����āA�����ɂ͂��ĎO�{�̑叼������A����ɂ܂�鎟�̂悤�ȑ��Ôˎ�̑��̓`��������B
�@���̂����̈�{�̏��́A�l�̒ʍs�ɂ͎x�Ⴊ�Ȃ��������A���ɂ��Ԃ���悤�Ɋ����Ȃ��Ă����B����Ƃ����Â̓a�l��������ʂ邱�ƂɂȂ������A�s��̐擪���s�����̕�悪���̏��ɐG��邨���ꂪ����̂ŁA���l�����͂���邱�Ƃɂ����B
�@�����A����������ďW�܂����Ƃ���A�H��ɋȂ��Ă����������̂����ɐL�тāA���������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����B����͂ЂƂ��ɓ��c�_�̐_�Ђɂ����̂ł���Ƃ��āA�܂��܂����̐M��[�߁A���̘b�������瑺�ւƓ`����ėL���ɂȂ����A�Ƃ������Ƃł���B
�@�܂����̔肪���邪�A����͋߂��̏�(�W�)�Ղɂ��������̂ŁA���łɖ��ł��Ă���B�������̎�q�Ƒ�ڔ�ł���B
2023/10/19�B�e�F
�@�L�����c�_
�@�L�����c�_�J���G���i�X�N�̐Ή������̒��Ɉ��u����Ă���̂ł��낤���B�Ȃ��A�ؔ��ɔ[�߂�ꂽ�{�Ƃ͕s���B
�@��Q��E�Δ��F��́u���j�v�ɋL�ڂ̂��̂ł��낤�A�Δ�̐��i�͖������ǂł����܂��`����ǂ�������Ȃ��s���A����S�����ǂł����B
�@�u�܂����̔肪���邪�A����͋߂��̏�(�W�)�Ղɂ��������́v�Ƃ����A�W��Ƃ����͕̂s���ł��邪�A�����߂��Ɂu�L���c�_�Z���^�v������A�����炭�������W��ŏ��ՂƐ��肷�邪�A�m�͂Ȃ��B
�L���ɂ́��������v�����L���R�@���������Ƃ����B�i��Ɍf�ڂ������Î��@�Ղ̍����Q�Ɗ肤�B�j
2023/12/01�B�e�F
�@�L����Q���F�L�����i���E�����̒�q�����̊J��Ƃ����j�R���Ƃ����A����́A���̍��Ղ܂Ŗ��Ղ����悤�ŁA�܂��������ǂł��Ȃ��B
�@�L���}���k�F���܂�ޗ�����Ȃ����A�}�i���͌����j�t�̕擃�Ǝv����A�����L�����R���̐Γ��Ȃ�A�m���̕擃�ł��낤���A���͑S�����Ղ��A�܂������s���ł���B
�ёq���i���J��n�E�L����n�ɂ���Ǝv������m�Ȃ��j
�@�����J2021�Ԓn�̍L����n�ɂ��鉺����ŁA��88�E��49�����B�i���O�N(1384)�����̌����ł���B
�@�V�W�E��ځE�@��������A�����Ɂu����@���@�߉ޔ@���@��s���Սs���i��𦬠�ł��낤�j�@��s�����s���i��𦬠�ł��낤�j�@�F�q�h���@�E�u�҈וꖭ���\�O����v�̖���������B
�@�@�������ɂ͉��f�̓����E�����E���q�̉����肪����B
������⸈i�������߂ł��낤���A�ʒu�s���j
�@������2797�Ԓn�ŁA�����̎d�u���n�ɂ���B�������ĉE�ɖ�S���A���ɖ�Q���̓��̕�⸈�����A
�@��͏�����N(1653)�l���A��ڏ\�������A���L�O���Č������ꂽ�B�u�J�ጚ�V�ȑ��t�C�v�̍������ǂ߂�B
�@���́A�u��ڌܐ畔�����@������(1674)�K���@���������ӑ��{���@�{��l�����@�~�\�������@�����������v�̍��������ǂł��邪���ł��r�������B
�{����ڔ�i�{����n���߂��j
�@���{��3008�Ԓn�Ŗ{���Α�������ɂ���B���a�ܔN(1768)�̌����ł���B
���@�ܕS������i�ʒu�s�ځj
�@�������J�Α���ɂ���B���i��N(1780)�̌����ł���B
�匴�����C���{��i�匴�����߂ł���̂��낤���A�܂ł��Ǖ�n�Ƃ͕s���j
�@�܂ł��Ǖ�n�ɂ���B�����\��N(1814)�Ɛ����ܔN(1715)�����̓�����A��ڏ��C���{��ł���B
�ёq�䉓����y�����E�����E���q�z�i���J��n�E�L����n�ɂ���Ǝv������m�Ȃ��j
�@�����J2021�Ԓn�̕�n���ɂ���B����N(1752)�̌����ŁA�����E�����̕S�\�����A���q�S�������ł���B
�@�������ɂ͏�f�̔ёq��������B
�@�������E�����P�T�O�����E���q�P�O�O�����ł���Έ��i�X�N�i1781�j�O�オ�Ó��Ǝv����B
�{����n
�m���Ǝv�����肪���݂��邪�A�ڍׂ͕s���B
2023/10/20�B�e�F
�@�{����n�����K�F���c�_���@�@�@�@�@����m���̕���@�@�@�@�@�{���@���W�哿���
�@�@�{���@���W�哿���͎��̂悤�ɍ����B
�@�@�@�@�@�@�@�聡������������
�@�@�@�@���@�@�{���@���W�哿
�@�@�@�@�@�@�@�i�@�S���ǂ߂Ȃ��@�@�j
�؉���n�i�匴����n�j���u���W�E���c�_�E�n���ω��v
�@�؉���n�i�匴����n�j�̉��ɂ��铹�W�E���c�_�E�n���ω��ł��邪�A�u���Ò��j�v�ɂ͊m�����Ȃ��B
�����́A���݂͎��Ă��邪�A���C���̋����̕����ꂾ�����Ɛ��肳���B
���W�́A���Â��܂������������ɋ߂��A��ǂł��Ȃ��B���c�_�E�n���ω��Ɛ��肳��鏬�K���Q���A������肩�ł͂Ȃ����A�u�Α��������ݐ}�v��GoogleMap�ł͂������肠��B
2023/10/20�B�e�G
�@���W�E���c�_�E�n���ω��P�@�@�@�@�@���W�E���c�_�E�n���ω��Q�@�@�@�@�@���W�E���c�_�E�n���ω��R
2024/02/05�lj��F
�@��q�̓��W�ɂ��āA�u���Ò��j�v�ɋL�q������̂����������̂ŁA�]�ڂ���B
���u���Ò��j�v�́u�y�t�z�u���Ò������}�v�ɂ��āvp.328�`�@���
�@�@�i�O���j
�@�]�˓����u�܂ł��ǁv�̍��o���Đ���֏o�A�ʏ́u�ꗢ�ˁv�̓��c�_�̏��ʼnE�܂�A���싴�̂Ƃ���Ō��݂̍����Ǝ߂Ɍ������A�쑽�ł́u��C(��������)���v�Ƃ��������̂�����o��A�O�А_�Ђ̑O�֏o�āA���̌�͍����Ƃقړ����R�[�X���s���悤�ł���(�u�����}�v�Q��)�B�u�܂ł��ǁv�̍�̕���_�ɗ����W�͖�����\�N�̂��̂ł��邪�A�u�����ÁA�����s��A�Ă���(���q)�A�k�\�]�O�A������c�A���n��A���O���ˁA������A�����v�ƋL����Ă���B
�@���u�}�f�C�h�v�Ƃ͈Ӗ��s���ł��邪�A�u���Ò��j�v�̒f�ГI�ȋL�q����A�؉���n���߂��邢�͖@�����Օt�߂��u�}�f�C�h�v���w���Ɛ��肳���B
�@�����W�͖����Q�O�N�̂��̂ŁA���E�k�E���̒n���͏�L�̓]�ڂ̒ʂ�ł���B
�؉���n�i�匴����n�j��ڐ�
�P��̑�ڐ�����A���ʂ́u�얳���@�@�،o�v�A�����ʂɂ́u�����\��i1814�j�E�E�ȉ���ǂł����j�v�ƍ�����B
�u���Ò��j�v�ɂ͊m�����Ȃ��B�܂ł��Ǖ�n�ɂ��镶���\��N(1814)�̑匴�����C���{�肪�Y������\���͂��邪�A�܂ł��Ǖ�n�Ƃ͕s���ł���B
�@���݂ɁA�܂ł��Ǖ�n�ɂ���u�����\��N�N�I�̑�ڐv�͎��̎ʐ^�ł���B
2023/10/20�B�e�G
�@���Ö؉���n��ڐP�@�@�@�@�@���Ö؉���n��ڐQ
�����ÁE�e�Б�_(�����l)�E�E�E�^�O���Ձ@�@����368�`
�@������2787�Ԓn���^�O���Ղɂ���B
�Ñ��Ï�勍���\�o������̗���J��A�c���\��N(1614)�̌����Ɠ`������B
�w���×R���L�x�Ɂu�c�c����\�o��S������R���S��ɓ��肵�����^�O���ɖ@�Ԋ����A�e�Б匠���ɍՂ���A�������ē�����Ӎ炱�ꂠ��A��_�̂�q����ɑ��т͍��̑�����ƂȂ�B������ȗ��������h����v�Ƃ���B
���݂̍�͖��N�ꌎ�����A�㌎�����̗����s���Ă���B�Е�̓��͈��������O�g�p�������̂Ƃ����A�ӔN��������Ɠ`�����铇�̌S�i���E�q�傪��i�����B�k������сu��[�v�̑K�z�́A��R����o�y�������K�Œ����������̂ł���B
�@�����́u���ӌÏ�啽���b�����\�o���������n�v�̖��A�܁Z�i�̐Βi�A�����q�A���Ȃǂ�����������������q���̊�i�ł���B�����Ɉ����N�x�̐{������B
�@���{��͈�����255�N�ɓ�����c����N����(1866)�O�������A���������u���ɂ���Č��������B
�{��l�͎����q��E�l�Y�E�q��E�ɉE�q��E�d���q��E�Í��q��E�����q�E�y�E�q��E�����q��E���E�q��E���E�q��ł������B
�@��̕\�Ɂu�얳���@�@�،o�@�e�Б匠���u�O�����\�݊����A�@�����u���v�B���ʂɁu�c�����h���ӌÏ�勍���\�o�畽���b������@�@抐�俒�@�a���^������T���@�c���\���N�p�q�O���������@����������S�\�ܔN�Փ��ד�e�Ј��i��匠����@��������V�����ꎩ��@�y�V�v�d���s�@���V���@���������V�œ������Y����ЉДV�_�ꎨ�@�c���N���Џt�O�������@��A���d����u�ДV����ށ@�������㐢���E�����v�ƍ��܂��B
�@�i�㗪�A���{��ɂ́u��ځv�����܂�邱�Ƃɗ��ӁB�j
2023/10/20�B�e�F
�@���Ðe�Б�_�@�@�@�@�@���Ðe�Б�_�Гa�P�@�@�@�@�@���Ðe�Б�_�Гa�Q�@�@�@�@�@���Ðe�Б�_�Гa�R
�@���Ðe�Б�_���{��P�@�@�@�@�@���Ðe�Б�_���{��Q�F���{��ڍׂ͏�Ɍf�ڂ���
�@���Ðe�Б�_���K�F���c�_��
�����Ô���_�Ё@�@���@�����̋����V����
�@�����Í���O�V�_�ЁA���Í���O��ЂȂǎc�]�́u�Ёv�͏ȗ��B
�����Á����@--------------------
�@�@�@�@�@�������Α��������ݐ}
�@�@�@�@�@���@���@���@㉁@���@�@�@�@�F�������E�������E�告���E���������`�����B���{�͖�����F�B
�@�@2023/10/19�B�e�F���Â����������瓇��]�ނP
�@�@2023/12/01�B�e�F���Â����������瓇��]�ނQ�F���n�ɕ����ԓ��l�̉e�������W���ł���B
�����������o���i�s��s�{�h�j
�@���W���̎��@���L�q����ɂ������āA�O�����ĐG��Ă����������Ƃ�����B
����́A���͈ꑺ�������ē��@�@�s��s�{�h�ł��邱�Ƃł���B
���̔h�́A�����ɂ����Ă͓������ł͂Ȃ��A������E����E�匴�̊e�������قƂ�Ǒ�����݂œ��h�ł���A�ꑺ�̒��ňꕔ�����h�ł��鑺�X�́A���ˁE�т���A��ʑ��E��ɋy�ԁB
�@���ɂ́A�����ł�����J���A�s��s�{�h�ŏZ�E�̍ݏZ���鐳�o��������A���h�e������̎�����`�����\���c�����B�܂��A���h�̏@��Ƃ�������Õ����ނ��A���o���ɂɔ[�߂��A�����̌����҂��K��邱�ƂȂǂ���A�s��s�{�h�̑�\�I�ȂƂ���ɂȂ����悤�ł���B
�����o���@�@����443�`
�@���b���2320�Ԓn�ɂ���B
���c�̒��ɕ����ԋu�˒n�̒��S�Ɉʒu����B���@�@�s��s�{�h�̎��@�ŁA�����R���o���Ƃ����B
�����R���o��
�@��������ɏ����ꂽ�w�Ў��䒠�x�ɂ́A���̂悤�ɋL����Ă���݂̂ł���B
�@�@�@�@��t������S���Ò������Q�S��E�Ԓn
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�h�@���@�؏@�@���o��
�@�@�{���@�@�c���@����\�E��Z�m������䶗�
�@���H����1.2���قǍ����Ȃ����Ƃ���ɎR�傪���Ă��A���ʂ̊z�ɂ́u�����R�v�ƍ�������Ă���B
�O��̒��S�ɋ�ǂ̘V�������т��A�{���ƌɗ�������ł���B�����2.7���l�ʂ̊����������������āA���a�U�O�����قǂ̞����ɂ́A�@
�@����؏��L�V�@
�䍟�y�����@�@����؎��ݐ_��
�����쐥�O�@�@����ؔ�v�V��
���@�����ߍL��i���o�@�얳���@�@�،o�n�@���N�m�O�@�����}�f�������x�V�@���{���m��؏O���m�Ӗڃ��@�q���P�������A��
�@����ؐr�[�V��
��t������S�������@���@�@�s��s�{�h�����R���o���@���@���F���S�����{��@��^�s�]�c�M�q�@�~�h���@�L�q�@�L���s�������O
�@�@�Ƃ���A�����E�����Ƃ��ɏ��a�T�T�N�Z���Ɍ��݂��ꂽ���̂ł���B
�@�����ɂ͍���2.5���قǂ̐Γ��Ĉ���A�{���O�ɂ���A�u�@���h�_�����O�ē��c��l�S�\�N���@��i�Γ��ē��@�Ȉԑc���ݕ������T�I�lj��V������@���a�Z�N�O���\���F��鑾�Y�@�y�V����@�y�V�����v�A�u�y�V����@�������o�@�O���q��@����]��E�{���Ȏ�n�����N���Q���������I�����M�����@���ΐ������݉ƐE�@����笑吳�Z�N��E�{���ȑ�V���@�y�V����@�y�V�����v�ƍ��ށB
�@�ɂ͖{���O�����ɂ����āA�Â��͕����ܔN(1447)���납��̌Õ����E��䶗��Ȃǂ����\�_�A���̎���ƂƂ��ɔ[�߂���B
�@�{�������ɂ���P���قǂ̐Γ��͑��q�u���ŁA�u�����c���q�V����p�ДN(1782)�����g�����V�@�\���v�ƍ��܂�Ă���B
�@�{�������ɂ��鍂���P���قǂ̐Γ��ɂ́u�s�މ@�@�������@�V�ۏ\��N�M�q(1840)�H���������v�ƍ��܂�A��ɂ́u�M�q���@��絁@���ˁ@�ΐ��@�����@���Á@�����@�Ó��@�ђˁ@���@�{�@�D�z�@�J�V�c�@��R�@���@���X��@�]�ˁv�Ƃ��邱�Ƃ���A���q���̎t���̂��̂Ǝv����B
�@�{������Ɍ������Ă��锼���͒��a30�������܂�̂��̂ŁA�u���o���ċ��m�t�@�����@���s���l���i�����̕����͕s���j��ߋ�������������������_������₍X�s�ڑc�t���ᔜ�ϑ��@���l��\������j��c��X���m�ׁ@�c�R�Q�w�L�O�j���o���֍��m������[�X�@���a�l�\���N�l����\�ܓ��@�{�咇���Z��ڌS�i�����q�@�Ȏu�Îq�@�������ڌS�i���f�@�Ȏ��q�v�̍���������B
���O�\�Ԑ_�F
�@��h�̎�����J��ꂽ�̂ł��낤���A���݂͋����̖k���Ɋ_���Ŋu�Ă��Ă��邪�A������������A���i����Βi��o��ƁA�ؑ�����������1.5���ɂP���قǂ̎O�\�Ԑ_�̖{�a������B�Βi�ɂ́A�u��[��؍K�O�Y���a�\��N�@���v�Ƃ���A�R���N���[�g����ɂ́u��[����둠�@��ؓДV���@��؍K�O�Y�@�F�䐴��@���a�\��N�㌎�g���v�Ƃ���B
2023/11/30�B�e�F����A2023/12/01�B�e�F����
�@�������W�����H�P�@�@�@�@�@�������W�����H�Q
�@���������o����O�@�@�@�@�@���o���R���@�@�@�@�@�����o���R��P
�@���o���{���P�@�@�@�@�@���o���{���Q�@�@�@�@�@�����o���{���R�@�@�@�@�@���o���ɗ��@�@�@�@�@���o�����O
�@���o�����@�@�@�@�@���@�E�҉@�F�����`�M�m�F���̕��ɂ��Ă͕s���B
�@�����c���q���F��ɋL�ڂ���
�@�c�R�E���n�Ȃǒc�Q�L�O���F�c�R���o���A��c���Z�l�O�A���c�ܐl�O�A���n�i���@�E����j�Ȃǒc�Q
�@�O�\�Ԑ_���P�@�@�@�@�@�O�\�Ԑ_���Q�F��ɋL�ڂ���
���o������
�@�Γ��́u�R�v�̎��`�ɕ��ׂ��A�����Γ���i���ʁj�A�쑤�Γ���i�k�ʁj�A�����Γ���i���ʁj�Ɛ��������B
�@�@�@�@�@���摜�N���b�N�ʼn摜�͊g��\��
�@
�쑤�Γ����F
�쑤�Γ���͎�Ƃ��āA�����������W�܂�s��s�{�h�ɐ�s�����Γ��A��̓I�ɂ͒��R�n�̐�t�Γ����z�u�����B
��P�j���u���o���݈�畔�ق����A���@�@��Q�j�֑ɗ��{���Γ��@�@��R�j��݉@�������{���@�@��S�j������@���{��
��T�j������@�֑ɗ��{���Γ��@�@��U�j����֑ɗ��{���Γ��@�@��V�j���e��䶗��{���Γ�
�@�쑤�Γ���P�@�@�@�@�@�@�@�@�쑤�Γ���Q
�@�쑤�Γ���P�E��������
��P�j���u���o���݈�畔�ق����A��
�@���u���o���݈�畔�ق����A��
�@�@�@�@�@�@����u��断�o���݈�畔
�@�@�\�ʁF�얳���@�@�،o�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�����������O��ܕS��
��Q�j�֑ɗ��{���Γ�
�@�֑ɗ��{���Γ��P�@�@�@�@�@�֑ɗ��{���Γ��Q�@�@�@�@�@�֑ɗ��{���Γ��R�F���i�E���i
�@�\�ʏ㕔�͙�䶗��{���ŁA�u�얳���@�@�،o�v���E�ɑ����A��s��F�A�ޖ��A��s��F�Ȃǂ�������B
�@�\�ʒ��i�́@��o��m��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���N��F
�@�@�@�@�@�@�@�@���@���F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S���l�@�ƍ�����B
�@�\�ʉ��i�́@��X�����l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��X���哿�@�ƍ�����B�i�ꕔ���ǂł��Ȃ����������邪�A���L�̂悤�ɐ�������B�j
��R�j��݉@�������{��
�@��݉@�������{���F��݉@�����͓����������E���Ñ��������y�ђ������|�������R�P���̊J�c�ł���B
�@�Ȃ��A���g�͐V�����l�q�ł���A�����Ǝv����B
�@�����ʁF�O���Zᡖ��N�܌��ܓ��@�@�@��1283�N���@�����ʂ̓��t�͓����̎�����ł��낤���A�����̎�N�͈�肵�Ȃ��Ƃ����B
�@��݉@�����͉����Ό��������i���E�������j�̊J��h�zꎓ����]�猓�j�̖@���ł���A�Ό��������͌����Q�N�i1276�j�̊J�n�Ɖ]���B
�@�u���Ò��j�v�ł́A��݉@�����́u�������֓����j�Ƃ����A�㑍�������ɏZ���������]����̂����Ƃ����B
�@���ߓ��@���l�̋����ɗ������̐M�҂ł��������A�̂��o�Ƃ����Ƃ����B����������(������)���Ђ炫�A
�@�̂��������Âɂ����Ė������������A�u��(��)�������̓��F�����āA���|��������n�������B
�@���̖v�N�ɂِ͈��������Ē肩�łȂ��B
�@�㑍�������`�ɂ��O����Z�N(1287)�O�������A�����������`�ɂ��O���Z�N(1283)�܌���ܓ��Ƃ���A
�@����͂�������s���A�w�{���ʓ����c���L�x�͍O���Z�N�܌���O���Ƃ��Ă��邪�A���������s���ł���v�Ƃ��Ă���B
��S�j������@���{��
�@������@���{��
�@���ʁF�얳���@�@�،o�@����[�ԉ�]�i�������ǂ߂Ȃ����u���@�v�Ɛ�������j
�@�@���@�Ɛ��肷�闝�R�͂��̐Γ�����^�ł���A�Γ����̐��ʂɂ���A���������̐��ʂ̒����Ɉʒu���A
�@���N�����Ȃǂ��]����ʒu�ɂ��邩��ł���B��������A�t�ɓ��@�ł��邱�Ƃ̍������������̂����̂��A������B
��T�j������@�֑ɗ��{���Γ�
�@������@��䶗��{���Γ��P�@�@�@�@�@������@��䶗��{���Γ��Q
�@�֑ɗ��{���Γ��A���@�Ɛ������闝�R�͏�L�Ɠ���ł���B
��U�j����֑ɗ��{���Γ�
�@����֑ɗ��{���Γ�
�@�@�@�@�@�얳�����@��
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�@����[�ԉ�]
�@�@�@�@�@�얳�߉ޖ����
��V�j���e��䶗��{���Γ�
�@���e��䶗��{���Γ�
�@�@�@�@�@�얳�����@���@�@�얳�@��吹�l/�얳�������l
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�@�@���e[�ԉ�]
�@�@�@�@�@�얳�߉ޖ���Ł@�얳�������l/�얳���S���l
��������
���P�j���E������l���{���@�@���Q�j���s���Γ��@�@���R�j��ʉ@���B�E��暉@���_�Γ��@�@���S�j��u���o���ݕ����A��
���T�j��ړ�[�s��]�E���[�E�E]���@�@���U�j��ړ�[���@]�@�@�@�@���V�j��ړ�[�s��]���̂P�@�@���W�j�����@���s�擃
���X�j��ړ�[��������]�@�@��10�j�C���ʌ����O�\�l�ݕՐ��A��
�@��������P�@�@�@�@�@�@�@��������Q
�@��������P�E��������
���P�j���E������l���{��
�@���E������l���{���P�F�얳���@�@�،o�@�����吹�l
�@���E������l���{���Q�F���i���M���O���\��
�@���E������l���{���R�F�[��S�\�䉓���ӓ�/�����M�k��
�@���̋��{���͓����ɂ��萼�ʂ���B�����ɂ������Γ�����B
���Q�j���s����
�@���s����
�@�@�S�����ǂł��Ȃ��A�����͓얳���@�@�،o�Ǝv����B
���R�j��ʉ@���B�E��暉@���_�Γ�
�@��ʉ@���B�E��暉@���_�Γ�
�@�@�@�@�@�@�@��ʉ@���B�哿��
�@�@���ʁF���@
�@�@�@�@�@�@�@��暉@���_�哿��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�̉E�̍����͏��������ǂł��Ȃ��B
�@�����B�F����8.12.23��i1668�j�A�����������P�Q��
�@�����_�F���\9.11.28��i1696�j�A���\�@��_�Ó����߁A���J���鎛�o���A���v�R�Z�A��������A���v�R�ɋ��{���i�B���j����B
���S�j��u���o���ݕ����A��
�@��u���o���ݕ����A���E�����F�얳���@�@�،o
�@��u���o���ݕ����A���E�����F���\�l�h��/�ꌎ�����H/�����E�E�E�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����\�S�N�Ǝv���邪�A�u���v�Ɓu�l�v�ȊO�͕s�m���ł���B�m�F��v����B
�@��u���o���ݕ����A���E�����F����u���o���ݕ����A/���@�쎝���i�����j����
���T�j��ړ�[�s��]�E���[�E�E]��
�@��ړ�[�s��]�E���[�E�E]��
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o
�@�@���ʁF���[�ȉ����ǂł���]
�@�@���ʁF[���ǂł���]��/[���ǂł���]���@�@�@���u���v�̕��������Q�����lj\
���U�j��ړ�[���@]
�@��ړ�[���@]�P�@�@�@�@�@��ړ�[���@]�Q�E����
�@�@�\�ʁF�얳���@�@�،o�@����
�@�����@��ړ��F����
�@�@����Ō���Ƃ܂��u���@[�ԉ�]�Ɣ��f�ł���B
�@�@�Ȃ��A�����ʂ͖����ł��邱�Ƃ͊m�F�ρB
���V�j��ړ�[�s��]���̂P
�@��ړ�[�s��]���̂P
�@�@�㕔�́u�얳���@�@�،o�v�ȊO�͔��ǂł��Ȃ��B
���W�j�����@���s�擃
�@�����@���s�擃�@�@�@�@�@�����@���s�擃�Q
�@�@�\�ʁF�얳���@�@�،o�@�����@���s���l
�@�������@���s�擃�R
�@�@���ʁF������O�����d��/�S�\�N���\�l�@���u�S�\�N�v�Ƃ͕s���A���邢�͌�ǂ�������Ȃ��B
�@�������@���s�F
�@�u���Ò��j�v���ʑ����؎��̍��ňȉ��̂悤�ɂ����B
�@�@�@�؎������ɂ́A������ʂɂ���Ė����Q�P�N�P�Q���Ɍ��Ă�ꂽ���㋳���@���s�ƘZ���l(�@��)�̔肪����B
�@�������u���Ò��j�v�������o���̍��ł́A��f�̂悤��
�@�@�{������Ɍ������Ă��锼���͒��a30�������܂�̂��̂ŁA�u���o���ċ��m�t�@�����@���s���l���i�����̕����͕s���j��ߋ�������������������_������₍X�s�ڑc�t���ᔜ�ϑ��@���l��\������j��c��X���m�ׁ@�c�R�Q�w�L�O�j���o���֍��m������[�X�@���a�l�\���N�l����\�ܓ��@�{�咇���Z��ڌS�i�����q�@�Ȏu�Îq�@�������ڌS�i���f�@�Ȏ��q�v�̍���������B
�@�@���ʑ����؎��ɋ����@���s��������B
���X�j��ړ�[��������]
�@����ړ�[��������]�E�S���@�@�@�@�@����ړ�[��������]�E�����F�얳���@�@�،o�@�����@��������
��10�j�C���ʌ����O�\�l�ݕՐ��A��
�@���C���ʌ����O�\�l�ݕՐ��A��
�@�@�@�\�ʁF�얳���@�@�،o
�@�@�@�@���ʁF��������ܕS�ΜA�闬�z
�@�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ċ��Đ�����
�@�@�@�@�@�@�@�F��C���ʌ����O�\�l�ݕՐ��A�ꌋ�O��
�@�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ׁ�������
�@�@�@�@�@�@�@�F�����������������a�\�N�ꌎ�g���@�@�ƍ����B
��������
���P�j���E������l���{���@�@���Q�j�O�Z���l���{���@�@���R�j��ړ�[�s��]���̂Q�@�@���S�j��ړ�[�s��]���̂R
���T�j��ړ�[�s��]���̂S�@�@���U�j��ړ�[�s��]���̂T�@�@�@���V�j��ړ�[�s��]���̂U�@�@���W�j�����@���v�擃(���_�@���擃)
�@��������P�@�@�@�@�@�@�@��������Q
�@��������P�E��������
���P�j���E������l���{��
�@�����E������l���{���P�@�@�@�@�@���E������l���{���Q
�@���̋��{���͐Γ��������ɂ��蓌�ʂ���B�����ɂ������Γ�����B
�@�@�@���ʁF��[�H]����[�ȉ��s��]
�@�@�@�@�@�@���������N�����l���\�O������[�ȉ��s��]
�@�@�@�@�@�������͖����Q�W�N�ł���̂ŁA�����Q�W�N�܂�s��s�{�h�ċ��̌�̑����ƒm���B
���Q�j�O�Z���l���{��
�@�O�Z���l���{���P�@�@�@�@�@�O�Z���l���{���Q
�@�@�������l�@�@���i���l
�@�@�������l�@�@���O���l�@�@�@�������͐h�����Ă��̂悤�ɓǂ߂�B
�@�@���̐��l�@�@���[���l�@�@�@�����̂͂قړǂ߂Ȃ����A�O�Z���l���{���ł���A���̂Ɛ���ł���B
���R�j��ړ�[�s��]���̂Q
�@��ړ�[�s��]���̂Q
�@�@���ʒ����͓얳���@�@�،o�A�ʼn��i�ɁE�E���l�A�E�E���l�A�E�E���l�ƕ��ԈȊO�͔��ǂł��Ȉ�B
���S�j��ړ�[�s��]���̂R
�@��ړ�[�s��]���̂R
�@�@�㕔�̖��@�ȊO�A�قƂ�ǔ��ǂł����B
���T�j��ړ�[�s��]���̂S
�@��ړ�[�s��]���̂S
�@�@�@[�얳���@�@�،o��]�����@�������l�@�ȊO�͑S�����ǂł����B
���U�j��ړ�[�s��]���̂T
�@��ړ�[�s��]���̂T
�@�@�@�����́u�얳���@�@�،o�v�ȊO�A���ǂł����B
���V�j��ړ�[�s��]���̂U
�@��ړ�[�s��]���̂U
�@�@�@�����́u�얳���@�@�،o�v�ȊO�A���ǂł����B
���W�j�����@���v�擃
�@�����@���v�擃�F���_�@���擃
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o
�@�@���ʁF�����@���v����
�@�@���ʁF���a�Z�\��N�O�����迁��/���_�@���s�N���\�l��
�@�@���ʁF���a�Z�\��N���؎�/���o��/�������M�k�ꓯ����
���������������i�{�o�R�������j
���f�̂悤�ɁA����Ɉړ]����Ƃ������A����i���ދn�S�㒷�葺���싽�j�ł̑��݂��m�F�ł��Ȃ��B
��2024/02/23�lj��F
���̂悤�Ɍ��E����s�ꎵ�ʎR���������Y������B
�����ʎR������
���茧����s��3����420�ɏ��݂���B
�{����HP�@���
�u�������ɂ��āv��v��ƁA
�@���\9�N�i1696�j�R����o�̑�Ɏ��ʑ喾�_�����݁A�g�����ʎR�Ɍw�ŖƋ��ē����ɂ��̑������J�����̂����̑��n�ł���B
���T�N�i1755�j�Гa�������A�v�{�@���@�����R�@�،o������S�q��_�̑����ƋF���{����䶗��̎��^��B
�Ȍ�O�g�\����薭�����F�������A�܂����a3�N�i1803�j���{�������琴�����呸�_����������B
����40�N�i1907�N�j8��1�����ʎR�����̑c�A��{�����͖{�R�y�т��̋̋��āA���ʎЂɐ�t������S���̖��������ړ]���A�O�_�i���ʓV���E�������F�E�������j�̊O�ɏ\�E�{�������u���ĐV���ɓ��@�@���ʎR��������n�����J�R�ƂȂ�B
�Ƃ���B
�@�����������̈ړ]�͂������R�X�N�ł��邩��A�����S�O�N�ɓ����������ړ]�Ƃ������Ƃƒ���͍����B
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�@�ɂ��A�قڈꌾ���ς��Ȃ��u���v�v���L�ڂ����B
�@���ʎR�ƍ����A���R�@�،o�����B
�������F�S�q��_�A�����A���ʓV���A�������̑��߉ށA����A�\�������A�单�V�A�����A��߁A�\��ʊω��A�������A����ׂ̏������J���A�G�M�̈��������@�@�̓T�^�̗l����悷��B
�����������������@����445�`
�@�O���̐��o���́A���Ɩ{�o�R�������Ƃ�����h�̎��ŁA�����X�N�ɕs��s�{�h���ċ������ƁA���l���������ĕ��@�������߁A��h���@�Ƃ��Ă͂��̑��S���뜜������ԂɂȂ�B
�@�����\�O�N�́w���@�����x�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�@�@�@�@���@����
�@�@��t���lj��X��������S�������b���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����������S���R�����@�@��v�h�@�Ԍo����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�R�@������
�@�@��A�{���@�O���@�@�@�@�@��A�R���@�n���N���s�ڃg嫁@���Éi���N�x���F�Ď��@���x�������h�k����ȍČ�
�@�@��A�����@��S���E��@���L�n����@�@�@�@�@��A���F�@�{������(�Ԍ���ԁ@���s�܊�)�ɗ���(�Ԍ��l�Ԕ��@���s�Z�Ԕ�)
�@�@��A�Z�E�@���V�@�@�@�@�@��A���O���L�n�@���V�@�@�@�@�@��A�h�k�@�ܐl�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�ȉ��ȗ�)
�@�@�@�@�@�����\�O�N�����Z��
�@�@�����Ɍ�����悤�ɁA�h�Ƃ͂킸���ܐl�ł���B
�����Č�ɂ́A���̕����������悤�ɁA���茧�ւƈړ]���čs���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���
�@�@���l���l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����S������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�@�@�@�����O�\��N�����\�ܓ��t�蒷�茧���g�n�S�㒷�葺���싽�ֈړ]�m�����̓N
�@�@�@�@�@�����l�\��N�������
�@�@�@�@�@�@��t���m���@�L�g����
�@�@�O���V�ʊY���ړ]��������ԍ��@�y��͌��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�����������S�C�@�@�@�@�@�@��u�t�@���{�י��@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ތ��g���y��嗧���Z�E�@�@���u�t�@�����N�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���h�Ƒy��@�@�@�@�@�@�@�@���썲�s�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���g�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�V�O�E�q��@��
�@�@�@�@�@�@�^�i��m�s�@�X�c�����a
�@
�@�������Ē���ֈړ]�����������̓y�n�⌚���́A���̕����Ɍ�����悤�ɁA���֔��p����A���݂̐��o�������݂���ꏊ�Ɩ{���́A���̂Ƃ��̂��̂ł���B
�@�@�@�@�@�y�n�������n��
�@�@�@����S�������@�@�@���b������Q�S��E��
�@�@��A�S����n�Q���E����@�@�@�@�W��W�ԁW��n������
�@�@��A�ؑ��������Ɩ{���듏�@�@�@�@�@�����؎l�E�ܒ�
�@�@��A�ؑ��������ƌɗ��듏�@�@�@�@�@�����ؓ�E��؈덇��
�@�@�@�@�����n�����S��E�܉~��
�@�@�@�E���n������j�̎����
�@�@�@�@�@�����l�\��N�����O�\���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����S���Ò������O�S��\�ԁ@�@�@�@�@�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����S�L�a���ђ˔��S�\��Ԓn�@�@�@�@�@�@�������Z�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�����������S�C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�י��@��
�@�@�@�@����S������
�@�@�@�@�@�@�F��F��Y�a�@�F��s�Y���q��a�@�F��F�g�a�@�F��鑾�Y�a�@�S�i�����q�a�@�S�i�v���a
�@
�@�������̉��N�ɂ��āA�O�L�́w���@�����x�ɂ́u�n���N���s�ڃg�����ǂ��\�\�v�Ƃ��邪�A�쒆�̒|�юR�������X�L�Ɂu�厡�O�N(1364)�܌��n���ŁA�J��͓�����l�ł���B���m�͓����������E���Ñ��������y�ѓ�(�쒆������)�O�P���̊J�c�ł���v�Ƃ̈ꕶ������A���E��������\�������Ȃ����\��N(1761)�ɏ������߂��w����ژ^�x�̖`���ɂ́A�u�i�m�ܒ���(1297)�����{�R��c���V������l���ŏ��ܕ���O�ʔV�����^���@�@�@��V�v���ɎҖ�@���哈�a�˓�e������O��A��U�߁@�@���q�������l�[�������c�c�v�Ƃ���B�܂��������̈�߂Ɂu��A���R�J�c�����l��{���ꕝ�A�i�m�ܒ��ѓ��R�J蓔V������^��v�Ƃ��L���Ă���B�E�̖{�R��c���V������l�Ƃ́A���R�@�،o�������̂��Ƃł��낤���A���̐ܕ��O�ʂ̂Ƃ��ɐ^���@������@���A���哈�����U�߂ƂȂ��āA�����̎���ɓ������Ă��Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B
�@���@�@�����������A����������
����ژ^
�@�����āA�����ܔN(��l�l��)�Z�E�Ǝv������h���A���̂��߂ɏ����₵���u�������v�Ƒ肷��ꕶ�����邪�A���ꂪ������Ă��玵�N��ɁA���E�n�����̍U���œ���͗��邵�Ă���B
�@����ɗ��闂�N�̍N����N(1456)�܌���\�ܓ��ɁA���R�@�،o���J�c�x�؏�E(��C�@����)���l�̌�ɗ��A�䒼�M�{�������^����Ƃ����|�̈ꕶ������A�O���O�N(1557��܌�)������\����ɂ́A����U���R�̈ꑰ�ł��錴���傩��A�O��Ɉ��������ĕی삷��Ƃ̈��g�t�^����Ă���B
���������������F
�������Ø@�؎R�{�@���@��������������
�������告���i�p���j�@�������ɋL��
���������告���i�p���j�@�@����449�`
�@������1981�Ԓn�ɂ����āA���ʂ̋�L���������̍s�����B
�w�������x(�N���s��)�ɂ́A�@
�@�@�@�R���s�ځ@�n���N�����s���@�J�R�s��
�@�@��A�{�����@��m�ؑ����@�䋖�̎����@�ړ]�X�@�@�@�@�@��A�ߋ�������M�k�O���@�䋖�m��g�����։��M�ғ��X
�@�@��A�{���@���܊Ԕ����l�Ԕ��@�@�@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�ܕS���\��@�@�@(�ȉ��ȗ�)
�Ƃ���A�����R�U�N�ɂ͎��̏��ނ���o����Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�p����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t������S������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�o�R���������@���@�@�@�告��
����S���Ò������S���E��ԁ@������
��A�������ʁ@�딽�Z���E�܃g(��)�@�L�d�n�@�������S���E��ԁ@������
��A��n���ʁ@�Q���g�@�@����告���@�L�d�n
��A���F�듏�@�Ԍ��ފԎQ�ځ@���s�l�ԎQ�ځ@�A��Ԏl�ډ��s�Q�ԎQ�ڃm���֕t�L�i��
�@�@�E�告���V�V�n�A���断�����V�����j�V�e�A�����n�̗������Œn�j�V�e�A�n�d���œ��h�ƃj�e���[�������A���������E�l�N�����A���F���������N���q�포�w�Z�Ƀj�ݎؖ��σm��g�p��A�W�E�ܔN�j�����A���Z���h�V�s�K�j�׃��^�����A������c�V�㏔�œ��n�A���ȃe�N�X���[���A�ˑR�g�V�e�A�w�Z�j���p�v����B
�@�@�R���j���ʏ��w�Z�߉����j�����A���@�m���̃��p�V�A�w�Z�j�ύX�Z�V�����m�s���~�`�j�t�A���۔p���V�`��o��ԁA�����O��[�N����@�V��䕷�͔퐬���x�A�ʎ��}�ʋy�ݎؖ�菑�E���{���Y�֍��@������
�@�@�@�����Q�E�Z�N�Q���\����@�@�@�@�@�@�@�@�Ў��y��l�@�F��s�Y���q�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W�@�@�@�ˑ��ɑ��@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W�撷�@�F��F��Y�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[�W�S�W����c���@�@�A�鎛�Z�E]�@�I������@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[�@�ރm�`������j�Q�P���L�V�]�e�F�p���j�����ڍ��X�j���V��]
�@�@��t���m���Ό����O�a
�@
�@���̔p���肢�ɂ���ĐՒn�ƌ����͖����ŕ����������A���ۂ͑��Ðq�포�w�Z�̕�����ł����������w�Z���A�]���ǂ���g�p���邱�ƂƂȂ�B
�@�������A���R�V�N�ɂ��̕����ꂪ�p�~���ꂽ���Ƃ������āA�{���Ƌ������A�V�����݂̎����ɏ[�Ă邽�ߑg���ł��閭�Z�E�֔��p���A�Ȗ،��������ֈړ]�����B���ꂪ�����S�P�N�H�̂��Ƃł���B
�@�@���������i���݂͓����s�j�ւ̈ړ]��͕̏s���ł���B
���������������i�p���j�@�@����451�`
�@���݂��̏��݂�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���o���̕����ɁA�R���̈�[��`���鎟�̈ꕶ���c�����B
�@��t����̎q�������n�����A���̖v��A�쒆�������ƍ������邪�A���~�̎���ɍĂѕ�����ēV���O�N(1534)�Ɉ�R�Ƃ��ēƗ������悤�ł���B
�����͎��̂Ƃ���ł���B
�@���������R���V���B�R�����Ɛ\�Ґ�c�a�V���ޛ�(��)�āA�،����j����A�R����c�a�˗L���@���������@�A�O��(����)����U�߃j�ݓ��j�����A���Ƃ��]���R���S���l�O��{����\�A�ɏ��L�����A���V���j�A��c�a�䁡�S�V��A�������|�уj�������Ҍ���A�R�j��c�a�j����\���������ށA�����������ؗp��j��ݎ���B
�@�R�������N�V��������j�������V�����퐬�䎀���A��Ֆ������B�ޖ������������ꎛ�j�������A��q�U�ߎ��������֏A�\��B�R�����~������j��ԁA�S�t�V��{��������\�A��Ղ𗧐\�x�R�\�j�A����{���䕪�������������R��ԁA�s�y�͌j�A���~�w��V�����A�}�䏬����V�����a�֗V�R�j��z��ܐ߁A�l�j�\���j�A�S�t�V��{�����\�R������ԁA�s�v�V�j���A���~�q�~�\��֎ҁA�⏊�V��{�����Č����ԁA���V�V��������n�h�����A�ܕS���j�����`����靚��l�j�@���O��{���\���A���o�R�������Ɛ\���폑�����퉺�j�A��q�����l����Ď��o���������@�����c�Ď��\��B������靚�t�V��{���n���\��B�R�S�t�V��{���n��c��ԁA���Z��俒���l�V��{����\�����s�V�����j�t���\�����B
�@���~��c�n�@�@�������V�U�ߐ����j��w���A��l���t�s�\��ҁA�}�V�V���앪�V�U�ߓ��~������o�����A�����������d��B�@���L�×������B��X�L�u�\���t����@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����t���~
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�V�������V
�@�@�@�V���O�N�b��(��O�l)�O��
�@
�@���̑��A�@�����E�������E�L�鎛�E���h���̎l�J���ɂ��ẮA�����݂̂��c��A�����̑��G�}�ɂ����悻���݂����������ŁA�ڍׂ͕s���ł���B
���H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�@����452�`
��������n
�@����V��2413�ɂ���B
�����͌Ï�Ղ̈���ŁA�ł̌Ö̉A�ɁA�s��s�{�h�M�҂ł��������Ƃ��B�����߂ɉ��������ꂽ�Γ���A����ڂ��āA���ʂ̉������ǂݎ��Ȃ��悤�ɂ����Γ�������A�܂��A���a�Q�R�N�ɁA�Ï�Ղ̈�p����̓y��Ƃ̂Ƃ��ɏo���l�������Γ��ɂ́A�u��t�ƗE�m�V��v�ƍ��܂�Ă���B
�@���{���ɂ��鋤����n�́u���������ꂽ�Γ��v�Ɋւ��Ă�
��q������������S���Ò��������@�@�s��s�{�h�̖@��i���������Ò���j�@�@�㊪335�`
�Ɍf�ڂ̎ʐ^
�@�e���̐Ղ��Ƃǂ߂铇�̕�n
���Y������Ǝv����B
2023/12/27�lj��G
���u���|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�Ɂu���揊�v�̎ʐ^������̂œ]�ڂ���B
�@�����������F��葤�ʂɑm�̖@�������݁A������݉Ƃ̕�Ɩ��������āA�@�����B�����Ƃ���B
�C�P�@���ӊo�ʁi���Ղ͕s���j�Ƃ���B
2023/11/30�B�e�F
��q�̂悤�ɁA�@��̍��Ղ��c���Γ���B����͎����ł����B
�����A���̎ʐ^�̂悤�ɌÂ��擃���������ꂽ��悪����A����炪�Y������̂����m��Ȃ����A�������Ă��Ȃ��̂ŕs���ł���B
�@��m���n�擃�P�@�@�@�@�@��m���n�擃�Q
����������
�@���������Ò��̖��������ɂ���B
���ܔ��c�E�сE���ˁE�ΐ��E��c�E�D�z�E�����@�@--------------------
�ܔ��c
�W�����Ɏ��@�͂Ȃ��A�������N�̌ːЕ�ɂ��ƂP�O�˂̂����X�˂��џC��(�ŎR��)�^���@�@�����A�P�˂��э������@�n�����̒h�Ƃł���B
���ܔ��c�O�\�Ԑ_�@�@�u���Ò��j�@�����v583�`
�Z���͏��ėё�����ڏZ�����Ƃ����A���̎��O�\�Ԑ_�����Ƃ����J�����Ƃ����B
�@�厚�ю��O���(����₾��)1351�Ԓn�ɂ���B���w�ɎO�Z�̐_�����J���Ă���B
�����ɋS�q��_�K������A�K���Ɂu���a�\�l�N�r�h�R�����J��v�̓��D������B�܂��Α��̎�́A�����P�Q�N�A�����R�q���Y�̊�i�ł���B
�сi�͂₵�j
�����Á��і@�ю��i�r�h�R�j�@����55
�`
���u���Ò��j�v/�n��j��/�����Ò�/��/�@���^�_�ЁE���@�@���
�r�h�R�@�ю�
�@���r�[388�Ԃ̂P�ɂ���B�����ɂȂ�܂ł͂��̏W�����Ɏ����O�P���������Ƃ����邪�A�����̂��Ƃɂ��ĕ��R���́u���҉��~�V���A�������@���E�@�ю��E�@�����̎��v�Ƒ肷�鏬���̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ�B
�@
�@���̐̏������h�K�N(931)�l�c�Z�\���鐝�V�c�V��F�A���������q�ɉ��ĕ��e������d�����Ĕe��L���A�Z�l�F������Ȃď����ɉz������ƂȂ�B�Q���c�肵�S���������Ȃ�B
�@���̌�����ДN(1338)�A�����������R�̍��A���R�O�����S��l��@�O�ʂׁ̈A���䏬���������ɉ��Č��������A���������������B
���̎���������ĉ��@���肯��B����ɓ������߂Ė@�̓���ƂȂ��A���юR���@���ƍ����B
�Z���������S��l�̒�q�ƂȂ�āA���B�Ɖ������A�J�R�Ɛ\���`�ӂ�Ȃ�B�s�w���݂đ��l���w�����邱�Ɠ�\�]�N�A�����܍M�q�N(1360)�\����\�������Ȃ�B
�@�������S�l�\�]�N���o�Čc����C�N(1604)�A�ɐ����E��̏��y���|�����l�A�c�q���ɑ��̋ߋ��ɂČܐ��q�̂Ȃ����B
���N�P�O�N�����t(1605)���s���{�����q�l�Ɛ\���l��o��������A��V���։��艮�����ėё��̓c���䌟�n�̏�A�����߉����u�����߁A���員���q�傱�̒n�ֈ����Ɋ肢�A���Ɏ�����㏜�n�ɗV����A�䏳�����t������B���̖��@������Ȃ�B
������e�̍��Ə̂��A��̔��n�����̑�Ɖ]�Ђ���B
�@���@�������A�V���T�Ȗ��N(1379)�l����\�ܓ��I�����B�O�������A���i�R�P�b�C�N(1424)�O����\����I�����B
��q��l����A�������t�̌���k���B
�������͈��Y���̋S�q��_�����������āA�����r�̒[�Ɉꎛ��n�����A�r�h�R�@�ю��ƍ����B
�����Q�M�ДN(1470)�܌���\����I�����B
��q���~�k���A�ӔN�B�����Đ��h�R�@������n�����B�����X���єN(1477)�\������I�����B
�O�P�������P�ɉh���Ė@�����炩�ɋP���A���@���N�̈ł��Ƃ��B���ɗL����Ȃ肯��B
���S��l�͉����V�b�ДN(1374)�܌��\����J�����B
�@���i�P�R�����N(1406)���@���O�������A�h�M�k�Ƌ��ɐ��i�w�͂��ēy��A��˂�z���O�\�O����̋��{���c�݂���B�����̒˂���l�˂Ə̂���Ȃ�B
�@�@(��)�@���݂�����l��836�ԂɁA�召���̒˂�����B
�@�@����l�˂ɂ���
�@�u���Ò��j�v�����́u�ё��E�d�ː}�v�ɂ��A�@�ю������̎R�ђ��Ɂu��l�ˈ�Ձv�Ƃ̕\��������A��������L�̓��S�́u��l�ˁv�Ǝv����B�Ȃ��A��l�˂̂����k�ɂ́u��l�ˌÕ��Q�v�Ƃ̕\��������B
�u��l�ˁv�̌���ɂ��ẮA��Ȃ����AGoogle�}�b�v�ȂǂŒ��ׂ�����ł́A�u��l�ˁv�́A�����炭�A�R�ђ��Ɏc�����Ă���̂ł��낤���A�ē��Ȃ��ɂ́A���̒˂ɍs�������Ƃ��ł��Ȃ��悤�Ȋ����ł͂���B
�Ȃ��A�u��l�ˁv�͌����ݒ��̍������ƍ������d���Ƃ��N���X��������ɂ���Ǝv���A���������݂ɓ������āA�u��l�ˁv���j���Ƃ������Ƃ͖Ƃꂽ�Ǝv����B
�@
�@�E�̎O�J���ɂ��Ė����S�N�́w�Ў��n���؎撲���x�́A���̂悤�ɓ����̗l�q��`����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S�ё�
�@�@��A�������n�O�S���E�@�@���@�@��v�h
�@�@�@�@�@���ؖ������@�@�@�@�@�@���@��
�@�@��A������S�O�E�l�@�@�@���@���h
�@�@�@�@�@��N�v�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ю��@�@(�ڒʎO�ځ`���ڂ̐��E�Ŕ��{�A���ȗ�)
�@�@��A�����됤�O���@�@�@�@���@�@��v�h
�@�@�@�@�@��N�v�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@���ؖ������
�@
�@����ɁA�����ɍ��ꂽ�w�Ў����ג��x�ɂ́A�@�ю����������̂悤�ɋL�����B
�@
�@�@�@�@�@��t���lj�����������S���Ò��ю��ܒ[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@��v�h�@�a�������@�@�ю�
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޔ@��
�@�@��A�R���@�@�@���a�����K�N(1615)�����m�R�ØV�m����j�`�t
�@�@��A�����ؐ��@�Q�S�l�@�@�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@��E��l
�@
�@�܂����ݖ@�ю��Ɏc����Ă���w�@�ю��R���x�͎��̂悤�ɓ`����B
�@�@���L������ɁA�l�c��\�Z�����V�c�̌�F�����R��ДN(1338)���R�O�����S���l�V������A���ё��������@����̈ꎛ��{���̓���ƈׂ����юR���@���ƍ����B��������S���̒�q�ƂȂ�A���щ@���B�Ə̂��A��@��`�ɋށB�����P�T�M�q�N(1360)�\����\���₷�B
�@�������o�ĎO�������Ɏ���A��q��l����B
��������Ə̂��A�t�̌���k���B��������Ə̂��A�������r�̒[�Ɉꎛ�����āA�r�h�R�@�ю��ƍ����B���@���́A���㑊�`���B
�@��\�㐢�Ɏ���A�����ېV�̍ەs��s�{�h�ċ��ׂ̈߂ɒh�ƌ������A���ɖ@�ю��ɕ������B���@���������āA�ȂČ����Ɏ���B�@����`�ӂ邱�Ǝ��ɓ�\�L�Z���B
�@�@�@�吳�\�N�\�����C
�@�@�@�@�����R(�����h��)�O�S����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@����
�����́w�@�ю��R���x�͂��̂܂܁A�^�V�����傫�Ȕ�ɍ�����A�����Ɍ��Ă��Ă���B
�@
���ȏ�̗v���ȉ��ł���B
�@�ȏ�̕������猩��ƁA����N(1338)���S�̕z���̂Ƃ����@���Ė��@���ƂȂ�A�c���P�O�N(1605)����V���ֈ����A�ڒz�����B
�@�����O���Z�E�̓����ɓ����E�����Ɠ�l�̒�q���������A�������t�̂��Ƃ��p���œ����l���ƂȂ�A�����͕ʂɖ@�ю���n�����ĊJ�R�ƂȂ����B�̂��A�����͂��̒�q���~�ɖ@�ю��Z�E�̍�������A����ɖ@������n�������B
�@�����X�N�ɕs��s�{�h��������������ƁA���@���h�Ƃ̑����͕s��s�{�h�ɉ��h�����B
���̂��߂ɓ����ł͒h�Ƃ���������Ƃ���ƂȂ�A�o�c��̗��R�������Ė@�ю��ɕ������ꂽ�B
���̌�A����ɖ@���������Ė@�ю��������c�����̂ł���B
���݂������̒h�Ƃ͂Q�T�������ŁA��������ƁX�͕s��s�{�h���̑��ł���B
�@�R���ɂ́A���@���Ղ���ڂ����Ƃ����鍂��64�����̔��������āu�J�R���щ@���B�哿�@�����T�M�q�N(�k���N���E1360)�\����\���v�Ɩ��@���J�R���`�̉@���Ɩv�N�����܂�A
�@�ю��J�R�̐Γ�(77����)�ɂ́A�u�J�R������l���V����N�@�����O�\���N�ꌎ�����㌚�V�v�Ƃ���B
�@�����ɂ���120�����قǂ̐Γ��́u���@��t�Z�S�����v�Ƃ��Ă���A�����R�V�N�ꌎ�ɉE�Ɠ��������������������̂ł���B
�@���@�E�@�ѓ�J�������̗��R���A�R�����ł͕s��s�{�h�ւ̉��h�ł���Ƃ����Ă��邪�A���h�͖����ɂȂ��Ă͂��߂čL�܂������̂ł͂Ȃ��B
�@�ю��@�n���Ɂu�J�R�����@���@���O��������q�@�@�щ@�g���X�@�����Q�M�ДN(1470)�܌���\����v�Ɩ��m�ɋL����Ă��Ȃ���A�\�㐢�����\�O���܂łܑ̌�ɂ��ẮA��\���R�̖����L���݂̂ŁA���͖@�������Ȃ��ɂȂ��Ă���B
�܂����@����㏑�ɂ��A��\�l�����r�Ɠ�\�ܐ������̖v�N�L�^���L����Ă��Ȃ��B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�e���@�Ƃ��Z�E���s��s�{�h�ł������ꍇ�ɑ����������ŁA�m�͓����Ȃ��ɂ��Ă��A����(1711)����Ȍ�̂��Ƃł�����A���h�e���̎���Ƃقڍ��v���邱�Ƃ���݂Ă��A���̂��납�炷�łɕs��s�{�h�M�҂����������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@���@�ю����ł����@���@�����͊����U�N�i1794�j�������Ö@���ɂ��\�ꌎ�S������B
�@�@�u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�v�������a�E�Ȏ��~�q�A�J�����@�A���a�T�R�N�@p.169�@�ł�
�@�@�@�@�ш����Z�A�s���h�@�Ƃ���B
�@�@���@���@�����͋ʑ����u�{���@�a�v���@���Q��
�@���@���@�����͗т̖@�ю����ɂ��̖����Ȃ��̂́A��L�̉���̒ʂ�ł���A�s��s�{�m�ł������̂Ɛ��肳���B
�@�@�P�X������Q�P���͌��A�Q�Q���͓��R�Ŏ�N���A�Q�R�����ł���B
�@���S���@���v�i�@�ю��B���j�����ɂ��̖����Ȃ��B
�@�@����u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�vp.169�Ɂu�����U�N�P�P���P�Q���@�S���@���v�S������B�����ё��@�ю��B���@�s���h�v�Ƃ���B
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
�@�r�ĎR�ƍ����A�����a�������A���t�@���B
���a���N�i1615�j�̑n���A�J�R�@�щ@�����B�V���N���ɖ��@�������́B
�u��ρv�ɂ͖����Q�P�N�ё����������@��[�J�R���щ@���B�A����N�n��]�y�ѐ��@�R�@�����̂Q�����������Ƃ���B
�@�@�P���@�@�щ@�����@����2.5.29(1470�j
�@�@�Q���@����@�����@����9
�@�@�i�����j
�@�P�S���@�B�S�@���ǁ@�V��2�i1782�j�F�@�s��m�ł���A���ˑl����n�ɓ��ǁi���j�̕擃����B
�@�@�i�����j
�@�P�X������Q�P���͌�
�@�Q�Q���@���R�i��N���j
�@�Q�R����
�@�@�i�����j
�@�Q�W���@�@�@�@�����@�吳�P�S�N�F�@�擃����i���Ɍf�ځj�A��x�@�E�吳14.2.15��
�@�i�㗪�j
�@�@���@���@�����͏���
�@�@���S���@���v�͉B���i����菜�����j
�@�@�������@���W�͜�ꂭ������
2023/12/01�B�e�F
�@�і@�ю����ł͏�q�̂悤�ɁA�@���@�����y�ѐS���@���v���m���邪�A�s��m�Ƃ��Ă͟����@���W���m����B
�����@���W�ɂ��Ă͂��̕擃�����䖭���O��n�ɂ���B
�@�@���䖭���O��n���T�D�S�j�s��s�{�m�����@���W�F�u�@��j�v�F���6.4.26��A�ё��@�ю��P�R���A���˖@��A�ѐ���@�ł���B
�@�і@�ю���ړ��F��f�̂悤�ɁA������120�����A�u���@��t�Z�S�����v�ƍ����A�����R�V�N�����i�����ł͗𐢂ɂȂ��j�������B
�@�@�ю��𐢕�n
�@�p���@�����F��f�́u���@���Ղ���ڂ����Ƃ����鍂��64�����̔�v�Ɛ��肳��邪�A���͖��Ղ��ǂ߂Ȃ��B
�@��f�ɂ́u�J�R���щ@���B�哿�@�����T�M�q�N(�k���N���E1360)�\����\���v�Ɓu���@���J�R���`�̉@���Ɩv�N�����܂�v�Ƃ���̂ŁA���̂悤�Ȗ������܂�Ă���Ɨ������邵���Ȃ��B
�@�@�ю��J�R�E���擃�F������ǂݎ�����A��f�ɂ���u�@�ю��J�R�̐Γ�(77����)�ɂ́A�w�J�R������l���V����N�@�����O�\���N�ꌎ�����㌚�V�x�v�Ƃ���̂ŁA���̗l�ɂ͓ǂݎ���B
�@�Q�W����x�@�����擃�F���ʂ́u��x�@������l/�吳�\�l�N/�\�ܓ��v�ƍ����B
�@�m�����s���擃�F���ʂɂ́u����/����/�����@�����@�t�v�Ɠǂ߂邪�A�m�����͔��ǂł����B
�@�і@�ю����F
���сE�H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�u���Ò��j�@�����v559�`
�@���������̊e���ɂ́A�ЂƂ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��ɂ���A����̐Γ���{������B
�@�@�i���ȉ���]�ځA�c�]�͏ȗ�����B�j
�n���ϐ����F��J���ɂ���B
�@���I���J(����͂�����)823�Ԃɂ́A�����P���]�̐Γ�������A�u�얳���@�@�،o�@�n���ϐ����@���v��p���N(1862)�\���g�����V�@����ؕ����q�v�ƍ��܂�A
�������́A������(�Ȃ���)645�Ԃɂ���U�T�����̂��̂ŁA�u�n���ϐ�����F���a��p��(1802)�\�g���@�ё��v�ƍ��܂��B
��F
�@����������(���傤��݂���)657�Ԃ̕�n���ɁA�悱�U�O�����A���ĂV�T�����قǂŁA���Ă̎x�z�Ґ�t���ꑰ�̋��{��ł���Ɠ`������邪�A�����̎����{��̖��O�͕s���ł���B
���̔�ɍ��܂ꂽ�����́A�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t���d
�@�@�@�@�@�@�팓�q�Z�l�@�㑍���@
�@�@�@�@���t���i���@�P��@���
�@�@�@�@�얳���@�@�،o�@�x���@��A
�@�@�@�@�@��t��팓���@�Ŗ��@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C��@�^��@�@�ȏ�̂悤�ɖ��Ăɔ��ǂł���B
���ˁE�ΐ��@�@�u���Ò��j�@�����v473�`
�@���Ƃ́A���ꂼ�ꂪ���ˑ��A�ΐ������̂��ēƗ����A�����Ƃɒ�����J��A�����ێ����ė������A�����ɁA�������ォ��Ȃɂ��ɂ��ċ����̐����Ƃ��Ă����B
���̗��R���A�u�n�������Ă��邤���ɁA�Ƒł�����Ĕ��ʂ��������v�Əq�ׂĂ���(�u�����o�菑�v)�B
����ɉ����āA�ΐ��ɂ��Ă̎����ɂ��R�����̂ŁA�����ł͕X��ꑺ�Ƃ��ċL�q���Ă������Ƃɂ���B
�@���Ök������암�̐��c�n��֔�����ɒ���o������n���A�r���ł���ɓ����ɓ���A���̐����������͂���ŁA���Ë���ƍ��J�삪����Ă���B�����āA�˒[���̐�𐅓c���я�ɍL�����Ă��邪�A�k���̏W�������˂ŁA���̓��[�̏W�����ΐ��ł���B
���ΐ����_�R�ΐ����@�u���Ò��j�@�����v495�`
�@���ΐ�1053�Ԃɂ���B�^�������^���@�ł���B�i�ȉ��ȗ��j
�����ˏ�ƎR�@��@�u���Ò��j�@�����v496�`
�@���J�m��1019�Ԓn�ɂ���B
�����́w�Ў����ג��x�ł́A
�@�@�@�@�@��t���lj�����������S���Ò����ˎ��J�m��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����j�a�������@���@�@��v�h�@�@�
�@�@��A�{���@�@�@�O���@�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��O�ԎO�ځ@���s�O�ԎO�ځ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@��S���E���@���L�n��l��
�@�@��A���O���L�n�@(�ȗ�)�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�Z�E���l
��L�ł́u�s�ځv�Ƃ��Ă��邪�A����ȑO�̓V�ۏ\�l�N(1843)�ɁA�{�R�֒�o���������ɂ��ƁA
�@�@�@�@�@�@�V�ۏ\�l�N�K����
�@�@�@�@�@�@��q�j�t���㒠
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S���ˑ��@�@�@�
�@�@��i�O�����N(1706)�����\�ܓ�
�@�@��A�J�R�@�q���@�����哿
�@�@����
�@�@��A�c���@�������
�@�@��A�n�@���Z��l����
�@�@�@�@�@�@������Όܓl�㏡�Z���@�@�����r���O�l���@�@���Z�Όܓl���Z���c�n
�@�@�@�@�@�@�@�@����������l�l�㏡�@�@�@�@�ۓc�ꎵ�l�Z��
�@�@��A���n�@�������@�@�@�@�@��A�����@�㐤�\�Z�����n�@�@�@�@�@��A���Y�n�ʁ@�������
�@�@��A�h���@�l�E�������댬�x�@�@�l���Y��S���O�l�@[���j�S�\�ܐl�@�����S���l]
�@�@�@�E�V�ʑ������ᖳ�����@�ȏ�
�@�@�@�@�@�V�ۏ\�l�N�K������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������S��c�����ˑ��@�@�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[�}�㍑�@�v���ĎY]�@�O�\�ꐢ�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���y��@�����q�@�@����l�@���Y���q
�@�@�@�@�@�@��{�R���m��
�@���Ȃ킿�A��i�O�N(1706)�q���@����ɂ���ĊJ���ꂽ�Ƃ����B
�@����ɁA���݂̉ߋ���(�����S�R�N���R�̎O�\��������@���ËL)�ɂ́A�u����(�}�})�E�������x�̉Ђɂ��A���̈���Ď��������Ƃ���A�J��E���E�n���N��Ȃǂ͕s���ł��������A�ЉЂ̍r�p���C���̂��ߍ�Ƃ����Ă����Ƃ��A�w������N�Ȝ�(�}�})(1369�j�܌��Z���x�ƍ��܂ꂽ��ڔ���@��o�����B���̕����͕s���ł���v�Ƃ̓��e���L����Ă���B
�@�����āA�����ɂ��镶���\��N(1815)�����̔�Ɂu�J�R�V�Ɖ@�����哿�v�Ƃ��邱�Ƃ��l�������āA�@��ɂ��āw���@�@���@���(���a�T�U�N�r��{�厛����)�x�̋L���Ă��邱�Ƃ����Ă݂悤�B
�@�@�@�u�k�c���l���@���@�@�@�k�����l�O�@�S�q��_�@������m�@�����x�V
�@�@�@�k���v�l������(1369)�N�̑n���B�J�R�ϏƉ@�����B���t�@���B(��ςɂ͊J�R����Ƃ���)�v
�@���̂悤�ɁA�����̊J�R�͓����ŁA������N�ɑn�����ꂽ�Ƃ��Ă���B
�@�����ɂ́u�c���J�c�q��@����哿�@�{��h�ߒ��@�c���O�\�q�b(�ԉ�)�v�ƍ��܂ꂽ�O���ܔN(1845)���������̑�ړ�������A������J�R�E�J�c�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͑O�L�̓V�ۏ\�l�N�����Ɠ��l�ł��邪�A�n���N���Ƃ����i�O�N(1706)�ȑO�́A�����\��N(1672)�O���Ɍ��Ă�ꂽ�������n�ɂ��邱�ƂȂǂ���A�����̊J�n�͏��Ȃ��Ƃ���i�O�N�ȑO�ł����āA���̔N�ɓ�����J�R�Ƃ���V�ۏ\�l�N�����́A���r�̐��ނ��Ăї����Ȃ炵�߂��A�����̑c�Ƃ��Ă̓���̂��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ȃ��A�����̉Ђɂ��āA����D�V��̋L�^�ɂ��ƁA�u����(�}�})�\�N(1827)�\�ꌎ��\�ܓ��@��Ď��A�V�ۓ�N(1831)�Z�����r��蔃���A�����Č��B�����l�N�Z���ďĎ��A�Z���������v�ƁA���̂悤�ɂȂ��Ă���B
�@���Ă͊Ԍ����\���(�Q�P����)�������Ƃ����{��(�ߋ���)�́A�����l�N�̏Ď���A���{���Ƃ��Č��Ă�ꂽ���̂ŁA���l�\�O�N�ɑ�C�U���������A���݂̖{���͏��a��N�ɍČ����ꂽ���̂ł���B���̌�����Ɍ�����ꂽ���ɂ́A�u�v���Ґ�ߖ@���V�펧�ØŎn�ᐥ�̉���ᢑ��ÛY�i�N�ґ��D�R�Ȑ��M�ܚM��ꤖ@���ە�����������������ݐ̋�ꑷ�V�Ώ��L�쓂��N�V�������v�V�R���e���R�c�R�E���@�Q�v�V�������M���r�R�o�ʼn��h�ȁ�������熓��ҏ��v�����ɜ��i�_ᢐM��~���t�i�Ȗ��Ɂ@�ە����\�O�N���q(�ꔪ��Z)�Z���Z��������h�z�u���@�얳���@�@�،o�@���V�`�B����S���ˑ���ƎR�@��v�ƍ��܂�Ă���B
����̏��K�E�Γ�
�@�����ɂ͑�ړ�������B
���̈��ɂ́u�얳���@�@�،o�@��ܕS�Β��A�闬�z�@�ܕS�\�������@��njo�v�����畔�@�������b�\(1824)�\���\�O���@��ƎR���㐢������@�@��u���v�Ƃ���B
���̈��́A�O�o�́A�O���ܔN�Ɍ��Ă�ꂽ�u�c���J�c�q��@����哿�v�Ƃ�����̂ł���B
�@�܂��A�M�q�����V�̕肪����A���ꂼ�ꎟ�̂悤�ɍ��܂�Ă���B
�u���@�@���@��v����M�m�@�����\�O�M��(1830)�������ܓ��@�ܖؓc�D�V��v�A�u���@�����@�@������M�m�@�����ܕ��(1858)��������@�ܖؓc�D�V��v�B
�@����́A�����l�N(1821)���납��q��̋���ɓ������Ă����D�V�啃�q�̂��̂ŁA�M�q�����̂̕�����ł��낤�B
2023/12/01�B�e�F
�s��s�{�h�����ł��������A���M���̈�ł������Ƃ����B�������A���͂�����Â�����̂͂Ȃ��Ǝv����B
�@�@�������
�@���@�ܕS�\�������E�����F�u�얳���@�@�،o�@��ܕS�Β��A�闬�z�@�ܕS�\�������v�A��L�ɋL�ڂ���A�����V�N�i1824�j�̔N�I�B
�@���@��m��ړ��E�����F�u�얳���@�@�،o�@���@��m�@�@�E�v�A��ɉ���̌f�ڂ���B
�@���@��m��ړ��E�����F�u�O���ܐ\�N�i1848�j����/�{��h�ߒ�/�c���O�\��/�q�b(�ԉ�)�v
�@��������̑��ʂ͖��m�F�ł��邪�A��f�̉���̂悤�Ɂu�c���J�c�q��@����哿�v�Ƃ���Ǝv����B
�@�@������@�@�@�@�@�@��{���@�@�@�@�@�@��{���E�ɗ�
�@�@����_���F����ɓ��������邪�A�O�А_�ЂɎ���ΊK�ł���B
�@�J�R�����擃�F�u�c�R�J�R�V�Ɖ@�����哿�v�A��ɉ������B�����P�Q�N(1815�j�����B
�@�q��@�����擃�F�u���@�@����@�q��@�����S��/��i�O����(1706)��/�������{�ʏ܁v
�����ˎO�Б�_�@
�@���˂̒���ŁA���J�m��1297�Ԃɂ���B���̎Ђɂ��Ė����́w�Ў����ג��x�́A���̂悤�ɋL���Ă���B
�@�@�@�@�@�@��t���lj�����������S���Ò����ˎ��J�m��
�@�@���i�Ё@�O�Б�_
�@��A�Ր_�@�V�ƍc��_�@�_�c�ʖ��@�o�Î喽
�@��A�R���@���i���b���N(��O��l)���������m�R�ØV�m����j���X
�@��A�Гa�@�{�a�@�@�@�@�@�@��A�����@���E��@�@�@�@�@�@��A���q�@�Z�E��
�@�@�W���k���̑�n��ɂ���A���͂͒ł̌Öɕ����Ă���B�{�a�͈��������ŁA��E�����[�g���l���قǂ̟O����ł���B�{�a�Ɍ������ĉE��̉J���̓��ɖؑ����{�������u����Ă��āA�_���͋L����Ă͂��Ȃ����A�ƋƔɐ��̐_�咹�l�ƁA�w��̐_�V���{�ł���Ƃ����Ă���B
�@���Ƃ��ẮA�����P����̐Γ��Ă������A�u��_���@�Éi���N�\(2848)�㌎�g���@��卂�������q�v�ƍ��E���������܂�Ă���B�Éi���N(1854)��[�̎�ɂ́A���b�l�^���q�@�����q�@�m���q��@�̖���������B
2023/12/01�B�e�F
�@�{�_�Ђ͖@����R�ɂ���A�@��ł͎O�\�Ԑ_�����邩��ƏЉ�ꂽ�B����āA�O�\�Ԑ_�̂���ŖK�₵�����A���ׂ�ƎO�А_�ЂƂ��Ē������Ă����B
�@�Ȃ��A�A�}�e���X�E�z���_�T�P�E�t�c�k�V���J��Ђ��O�\�Ԑ_�ƔF�����Ă���͕̂s���ł���B
�O�А_�Ў��̂������ېV�O�܂ł͎O�\�Ԑ_�ł������̂��A���邢�̓A�}�e���X�E�����_�E�t�����_���O�\�Ԑ_���\�������Ր_�ł���̂ŁA�����ē��@�@���@�ł͎O�\�Ԑ_�Ə̂���̂ł��낤���B�ł��A����͖@������̂��ƂŁA���̎��@�ł͂������������͂��Ȃ��̂ł��邩�B
�@����Ƃ��A���ɂ��Ďv���A���{�I�Ɋ��Ⴂ�����Ă��邾���A�܂�O�А_�Ђ͎O�\�Ԑ_�ł͂Ȃ��A�O�\�Ԑ_�͕ʂɍ��J����Ă���̂ł͂Ȃ����B�O�А_�Ђւ̐ΊK�r���ɏ��K�i���Ɍf�ځj�����������A���������̍Ր_�͊m�F�ł��Ȃ��������A���̏��K���O�\�Ԑ_�ł������̂����m��Ȃ��B
2023/12/01�B�e�F
�@���ˎO�Б�_�P�P�@�@�@�@�@���ˎO�Б�_�P�Q�@�@�@�@�@���ˎO�Б�_�P�R�@�@�@�@�@���ˎO�Б�_�P�S�@�@�@�@�@���ˎO�Б�_�P�T
�@���ˎO�Б�_�P�U�@�@�@�@�@���ˎO�Б�_�P�V�@�@�@�@�@���ˎO�Б�_�P�W�@�@�@�@�@���ˎO�Б�_�P�X
�@���ˎO�Б�_�����F��f�̂悤�ɑ咹�喾�_�A�V�_�ł��낤�A�����͐V�K�̖��Ђł��낤�A
�@�O�Б�_�Q���̏��K�F���̏��K�͕s���ł��邪�A�O�\�Ԑ_�����m��Ȃ��B
�����o�����ˏo����(���s��s�{�h���)�@�u���Ò��j�@�����v500�`
�@�@�i���o�����ˋ����j
�@���C�V�J725�Ԃɂ���B
�������N�����ɐ��{���M�̎��R��F�߂�V�@�����z���A�₪�ĕs��s�{�h�������ƂȂ邪�A�����N�\���\����A�@��Z�E�g������F�Ƒ��l�������@�_�̌��ʁA�@��h�Ƃ𗣂��B
���̂Ƃ��̐M�҂̐l�����ɂ���Đ݂���ꂽ���̂ł���B
���������̉�(��)�@���h�́A����ɑ����̖����������悤�ŁA���Ɍf����ꕶ(������)���A�����̎����`������̂ł���B
�@�@�@�@�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��\�ܑ��돬��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����S���ˑ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؒ��E�q��
�@�E��\���A�����Ɠ��@�@�s��s�{�h�M�j�t�A�{�N�댎�����ȑ��z�B�j�Ə��V�A�{����@��Z�E�g������F�ցA���F���n����l���x�\������A�ސ����������A�c���V���V���a�A�{���s�����{���l���ߌ㎀���d�A�����M���ԁA�����V�V���K�X�E�s��s�{�h���擯�S����E���Ԓn�R���g�����������E���⏬�������j�˗��v����l���⌾�L�V�A�����j����@�E�g������F�֑g���V�҃��ȏ��F�����n������l���ڐ\���������s�d�A���]�V�g���e�ʔV���̗����V�㉼���d�u��ԁA���@��͕�\���@�ȏ�
�@�@�@�@�@������N�\�ܓ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���@�@�@�@�ؒ��E�q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�ޑy��@�@���R���Y���q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���y��@�@�����ɍ��q��
�@�@�@�@�߈�
�@���w�ɂ́A���a��p�C(1772)���������E��铉ԉ��̋S�q��_�摜�����邪�A����͕s��s�{�h�M�҂����ōs���q���u�̖{���ł���Ƃ����B
�@�@������A���̏o�������ǂ��Ȃ��Ă���̂��́A�s���ł���B�iGoogleMap�ł��l�q�͕�����Ȃ��B�j
2023/12/01�B�e�F
����u���o�����ˋ���v�ƝG�z���f�����F�Ɠ��@�`�����`�s��m�̐�t�̐Γ����W�߂��Ă���B
�@���o�����ˋ����@�@�@�@�@���o�����ˋ���G�z�F�T��Ɂu���ˋ���@���c�L�O��v������A�����ɂ́u�M�k�Q�W���̂S�N�̐ϗ������ɗ��c�ɉ^�тȂ������ƁA���͕����Q�S�N�i2012�j�ł������v���ƂȂǂ��L�����B
�@�c�R���S���Q�q�L�O���@�@�@�@�@�c�R���S���Q�q�L�O���F�u���O�{�R�Q�q�L�O��v�A�\�ʂɂ͔N�I�Ȃǂ͂Ȃ��B
�@���ˋ����ړ�����F�ȉ��̂U��̐Γ�������B
�@���ˋ����ړ����E��������
�@�@��P�j�������{��
�@�@��Q�j���@��m��(���\�S�N����)
�@�@��R�j���@�E�����E�����E���q���{���F���@500�����A����150�����A����150�����A���q100�������{��
�@�@��S�j���@��l���n��t���{���F���@��l���n�Ƃ��āA�\�ʂɂ͓��@�E���N�E�����A���ʂɂ͓��e�E�����E���u�E���q�E�����A
�@�@�@�@�@����ɋt���ʂɂ͓����E�����E���i�E���́E���O�E���[�A���ʂɂ͔��Ǖs�\�ȑm���U���̊e��t��������B
�@�@��T�j���u���{��
�@�@��U�j���Ǖs�\�Γ�
�@���ˋ����ړ������F�ȉ��̂Q��̐Γ�������B
�@�@���P�j�s��m��q�@���P�擃
�@�@���Q�j���Ǖs�\�Γ�
�@���ˋ����ړ������F�ȉ��̂S��̐Γ��ƂQ��̐Γ��c��������B
�@���ˋ����ړ�����E��������
�@�@���P�j���Ǖs�\�Γ�
�@�@���Q�j������l���{��
�@�@���R�j����E���u���o�s���A��(����)
�@�@���S�j���Ǖs�\�Γ�
�@�@���T�j��ړ��c��
�@�@���U�j�����ړ��c��
��P�j�������{��
�@�������{���E�����@�@�@�@�@�������{���E���ʕ����F�얳���@�@�،o�@����(�ԉ�)
�@�������{���E�����F�אM�j�M�����y
�@�������{���E�����F���i���M��(1630)�O������
�@�����̎����͕s���B
��Q�j���@��m��
�@���\�S�N�̓��ׂ̏����������Γ��Ǝv���邪�A�����N�͕���Ȃ��B
�@���@��m���E����
�@���@��m�Γ��E���ʕ����F���̂悤�ɍ�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�얳�����@���@�@�@�@�@���\�l�N(1691)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���畔��ӓ�
�@�@�@���ʁF���@�@�،o�@�얳���@��m
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�얳�߉ޖ���Ł@�@�@�@�h���������
�@���ʂ͖����Ǝv����A�w�ʂ͖��m�F�B
�@��������u���\�l�N(1691)�v�̓������������Γ��Ǝv����B���ׂƂ͕s���ł��邪�A���S�@���ׁi���\�S�N�P�Q���P�U����A�������\�@��_�Ó����߁A���������P�S���A���ђh�тP�U���j�ł���\���͋����Ǝv����B
�@��L�̓��ׂ����S�@���ׂł���Ƃ��āA
�@���S�@���ׂɂ��ẮA�����Ўq����(�����Ўq��)�����A�����g�c��ˁi�����g�c���j�Ɏ�É@�����E���S�@�����{��������B
�@�@
��R�j���@�E�����E�����E���q���{��
�@���i�X�N�����A���@500�����A����150�����A����150�����A���q100�������{���ł���B
�@���@�E�����E�����E���q���{���E�����F�얳���@�@�،o�@���@���F
�@���@�E�����E�����E���q���{���E����
�@�@�F�[�@��ܕS�䉓恑剶�~�ӔV�ꕪ/�V���n�v/�܍��L��/���i���M�q�N�i1780�j/����������������/���V
�@���@�E�����E�����E���q���{���E�����F��ܕS�Β�/�A�闬�z/�����(�H)������ݕ����A/�c���M�j��/�y�O�쒆�ꌋ�@�h��
�@���@�E�����E�����E���q���{���E�w���F�������l�@��S�\����/�������l�@��S�\����/���q���l�@��S����
�@���i�X�N(1780)���@500�����E����150�����E����150�����E���q100�����E����50000�����A�œ����i���ˑ����j�u���ɂ���Č������ꂽ���̂ł��낤�B
��S�j���@��l���n��t���{��
�@���@��l���n�Ƃ��āA�\�ʂɂ͓��@�E���N�E�����A���ʓ�͓��e�E�����E���u�E���q�E�����A����ɋt���ʂɂ͓����E�����E���i�E���́E���O�E���[�A���ʂɂ͔��Ǖs�\�ȑm���U���̊e��t��������B
�@���@��l���n��t���{���E�����F�얳���@�@�،o�@�얳���@���F/�얳���N��F/�얳������F
�@���@��l���n��t���{���E�����F���e���l/�������l/�Ő��@�����吹�l/�����@���u���l/���m�@���q���l/���É@�������l
�@�@�����Ó�ꟁA�G�i���J�����A��暎�����������i�r������j�̂́@���ˑl����n�ɂ���
�@�@�u�P�j���@�\�E�֑ɗ��E���@���n��t���{���v�Ō�����u�r���v�Ɠ����\�}�ł��낤���B
�@�@�u�@�������@�̊Ōo�ɓ��t�߂Ă������Ɓv�̐���Ɋւ���_���ŁA���u�́u��v�Ƃ��A�u���v�Ƃ���ꟁE����
�@�@������x����������Ƃ̑Η�������A���ꂪ���݂ɑ�����ł��邪�A�����̍���S�ł͓��u�𐳓��Ƃ���v�z�ɗ��̂ł��낤���B
�@���@��l���n��t���{���E�����F�����@�������l/��É@�������l/�C�P�@���i���l/�猺�@���̐��l/���S�@���O���l/����@���[���l
�@���@��l���n��t���{���E�w���F���͖w�ǔ��ǂł��Ȃ��B���L�̒ʂ�ŁA�͂��ɉ@�A���A�哿�Ȃǂ������ł��邾���ł���B
�@�@�@�@�@�@�@���������������@�����@��������
�@�@�@�����������������������@��������������
�@�@�@�@�@�@�@�����@�����偡�@�����������哿
�@���ǂł��Ȃ��̂́A���Ղ�ۂ̔ɖȂǂ̗��R�ł͂Ȃ��A�����◝�R�͕s���ł��邪�A�����炭�̈ӂɖ������ꂽ�悤�Ɏv����B
�@�͂��ɔ��ǂł��镶�����琄������ɁA�U���̑m���̖@���������Ă������̂Ǝv����B
�@�܂��A����͈͂ɂ͔N�I�͂Ȃ��A�����̎���̑������͕s���B
��T�j���u���{��
�@���u���{���E�����F�얳���@�@�،o
�@���u���{���E�w���F��s���g��/�A�ɖ��㓹/���u(�ԉ�)
�@�@���u��s���g��/�A�ɖ��㓹�v�́w�@�،o�x�́u�����i��\�O�v�ɐ������i�����߉ނ̌��t�j�Ƃ����B
�@�������ʂɂ͖��͂Ȃ��B
��U�j���Ǖs�\�Γ��E��U
�@���Ǖs�\�Γ��E�����F�R�s�̖������邪�A���̓��̒����́u�얳���@�@�،o�@(���Ǖs�\)�v�ł���Ǝv���邪�A���E�͑S�����ǂł��Ȃ��B
�@�Ȃ��A�����ʁE�w�ʂ͖��m�F
���P�j�s��m��q�@���P�擃
�@��q�@���P�擃�E�����F�얳���@�@�،o�@����������
�@��q�@���P�擃�E���ʕ����F���\�O���\���\�����@�@(1763�N)
�@����͎���N�Ɣ��f�ł��邪�A�u���@�@�s��s�{�h椎j�N�\�v�̔N�\������Ɓu���P�Rᡖ��N�P�O���P�V���F��q�@���P�v��10.16�Ƃ����@�������ˑ��B���v�Ƃ���B
�@�u�[�����@��j�v�ł́u��q�@���P�@���13.10.17��A���ˑ��v�Ƃ���B
�@��q�@���P�擃�E���ʕ����F���ʂ̖�����u��q�@���P�v�Ɣ������A���̖@����O���ɔ��ǂ���A�u��q�@���P�v�Ɩ��炩�ɔ��lj\�ł���B
�@�Ȃ��A�t���ʁE���ʂ͖��m�F�ł���B
���Q�j���Ǖs�\�Γ��E���Q
�@���Ǖs�\�Γ��E���Q�E�����F�u�얳���@�@�،o�@(�@���Ǝ����������Ɛ���)�v
�@���Ǖs�\�Γ��E���Q�E���ʕ����F�@���͑S���ǂ߂Ȃ��A������́u���v�̕������������A�Ⴆ�u���a�v�ȂǂɎ��₵���Ǝv����B
�@�Ȃ��A�����ʂƂ��u�@�v(�H)�̕����ł���A���͂Ȃ��B���̗����ʂ̌`���͍]�˒����Ɍ�����`���Ǝv����B
�@�܂��A�w�ʂ͖��m�F�B
���P�j���Ǖs�\�Γ��E���P
�@���Ǖs�\�Γ��E���P�E�\���@�@�@�@�@���Ǖs�\�Γ��E���P�E�\�ʕ����F�u���@�@���S�@�����S�ʁv�̂悤�ɓǂ߂Ȃ��͂Ȃ����A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̐S�̓����i�u���r�v�Ɠǂ߂Ȃ��͂Ȃ��j�����ǂł��Ȃ����߁A�m�����͊m��ł��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�莝�������ł́u���S�@�v���Y���҂͂Ȃ��B
���Q�j������l���{��
�@������l���{���E�����F�u�얳���@�@�،o�@�ċ��@������吹�l�v�@�@�@�@�@������l���{���E���ʕ���
�@���ʁ@�F�����l�\��N�Z�����O���J���@���/����[����]�@����(�ԉ�)�@�@�����/����[����]�@�����@�Ƃ͕s��
�@���ʁ@�F�w�Ǔǂݎ��Ȃ����A�M�k���̕���������A�����̗R���Ȃǂ���������Ă���Ɛ��������B
�@�@�c�R���o���A���P���A�ᏼ�����烊���N
���R�j����E���u���o�s���A��(����)
�@����E���u���o�s���A�Γ�(����)�E�����F�����́u�얳���@�@�،o�v�Ɛ���A���̍��E�Ɂu����v�u���v�ȂǂƂ���̂ŁA
�@�����炭�u���u���o�s���A�v�Γ��ł��낤�B���邢�͑m���̕擃�ł��邩������Ȃ��B
���S�j���Ǖs�\�Γ��E���S
�@���Ǖs�\�Γ��E���S�E���ʁF���Ǖs�\
���T�j��ړ��c���E���T
�@��ړ��c���E���T�E�����F�u�얳���@�@�،o�v�ƍ��ޑ�ړ��ł��������Ƃ�������Ȃ��B
���U�j�����ړ��c���E���U
�@�����ړ��c���E���U�E�����F�������܂�邪�A���ǂł��镶�����Ȃ��A�܂������̕s���B
�����˓��c�_
�����V�X���i���ʼn������j���班���������ɓ��������ɐ��ˋ�����邪�A���̌����_�i�����H�j�p�ɐ��˓��c�_������B
���̈ʒu�ɂ��ẮA�����Ɍf�ڂ́u�������ˏd�ː}�v�ɂ���B
2023/12/01�B�e�F
�@���˓��c�_
���������ˑl����n
2023/12/01�B�e�F
�@���˖@������c�Ɍ������V���̓r���ɂ���B
�ܓx�E�o�x�F35.72094582397097,140.45291566735347�@�t�߂ɏ��݁B
�@�������ˏd�ː}�F�l����n�Ƃ��āA�R�����L�ڂ���邪�A���グ��Γ��͈�Ԑ����̑l����n�ł���B
���̕�n�́A�@������c�Ɍ������r���ɂ��̑��݂�m��A��X������������̂ł���B
�u���Ò��j�v�{���ɂ���،��y���Ȃ��A���̕�n�̐��i�͕�����Ȃ��B
����ȂɌÂ���n�ł͖����l�q�ł���A���K�͂ł��邪�A���̂S��̐Α��͕s��s�{�h�ɊW������̂Ɣ��f�����B
�@���ˑl����n��ڕ��i��������j
�����ɂ́A���̎l��̕s��s�{�h�W�Ǝv����Γ�������B�@
�@�����������
�P�j�u���@�\�E�֑ɗ�/���@���n��t���{���v�A
�Q�j�u���S�@����E����@���s�E�@���@���W�E�B�S�@�����ق��擃�v�A
�R�j�u�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂P�v�A
�S�j�u�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂Q�v�ł���B
�@�Ō�̕擃�i�u�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂Q�v�F�ʼnE�[�j�͍������Ⴍ�A���ɖ�����Ďʐ^�ɂ͖w�ǎʂ��Ă��Ȃ��B
�P�j���@�\�E�֑ɗ��E���@���n��t���{��
�@�\�E��䶗�/��t���{���E�����F
�@�\�E��䶗�/��t���{���E���ʕ����F
���ʂ͐Β����@�\�E�֑ɗ����Β������B�E�E�E�|�����͏ȗ�
�@�i���@�\�E��䶗��ɂ��ẮA���f�́u�����@�\�E��䶗��v���Q�ƁB�j
���̐Β���䶗��̉E�[�ɂ́u�O���O�N�M�C(1280)���������@���ʁv�Ƃ���A���@(�ԉ�)�̍����ɂ́u�@�Z/�c�V�v�Ƃ���B
�O���R�N�̓��@�\�E��䶗����ʂ��i���ʁj���A�@�Z�Ȃ���̂����̕������Ƃ������Ƃł��낤���B
�@�\�E��䶗�/��t���{���E�����F
�@�@�Z�V�m�@���e���l�@�������l�@���̐��l
�@�@��V�m�@�������l�@�������l�@���O���l
�@�@���V�m�@�������l�@���[���l�@���i���l�@�ƍ����B
�@�@�@�Z�V�m�A���V�m�A��V�m�@�i���Z�V�m�A�����V�m�A����V�m�͉��Ɍf�ځB�j
�@�@�@���e�͒��R�嗬�A�����͋ߐ��s��s�{�h�c�A�r������E���R�����E���R���[�E�������́E������O�E�蕶�J���i�͑O�Z���l�B
�@�@�@�����͒����@�E�ʑ��h�_�J�c�B
�@�\�E��䶗�/��t���{���E�����F
�@�@�������l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E����
�@�@���K���l�@�������l�@���吹�l
�@�@���u���l�@���^���l�@���`���l�@���x���l
�@�@���q���l�@���~���l�@���_���l�@���Ɛ��l�@�ƍ����B
�@�@�@��C���u�E�ʑ������E������q�͌�Z���l
�@�@�@�@�i��Z���l�ŋ��Ó�ꟁE�G�i���J�����E��暎����낪�����Ă���̂͗��m��ꟁE�����Ɗ֓��̓���͓��w�����ʂ��x�����A
�@�@�@�@�Î����������x���������u�ƑΗ������̂Ȃ̂ł��낤���Ɛ������邪�A�����̈���o�Ȃ��B
�@�@�@�@���Ó�ꟁA�G�i���J�����A��暎�����������i�r������j�̂́@������Ɍf�ڂ́u���o�����ˋ���v�ɂ���
�@�@�@�@�u��S�j���@��l���n��t���{���v�Ŕr������̂Ɠ����\�}�ł���B�j
�@�@�@���^�E���~�E����E���`�E���_�E���x�E���Ƃ͉@���������߁A����ł����B
�@�@�@���K�E�����͕s���B
�@�\�E��䶗�/��t���{���E�w���F
�@�@�@�@�@���@�@�S���@�퐴���r�@��@����@�ܐ畔���A
�@�@�@�@�@���w�@�@�s�@���^���p�@����@���������@���@�@�Z�����@�����@灋�Z����
�@�@�@���c�ܕS�����@�@�@�@�@���s�@���x���M�@�@��@����@�@�@��灋��@������s
�@�@�@�@�@���x�@���@�@���������@�@�M�@�������s�@�@���@����
�@�@�@�@�@���`�@���B�@�@�����M�@���@�@�@�Z���ʁ@��G�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�ܕ��\�N�\���\�O���@�@�ƋL���B
�@���i�ܔN(1776)�ɓ��@500�����E���o5000�����A�ő������ꂽ�̂ł��낤���B
�@�����̉����������邪�A��ԏ�i�̓��@�E���w�E���x�E���`�͑m���ł���\�����������A����ȊO�͂����炭�݉ƐM�҂̂��̂Ǝv����B
�@�Ȃ��A���̓��́u���@�@�Z�����v�Ɓu�@��@����v�͉��Ɍf�ڂ́u�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂P�v�̕擃���ɂ���u���@灋�Z�����v�y�сu灋��@������s�v�Ɠ���l���ł��낤�B
----------------
�����@�\�E��䶗��F
�@��ڏ\�E�֑ɗ��͓��@��l�̍l�ĂŁA�����ŋL�����֑ɗ��ł���B
���̌`���͙�䶗��̒��S�Ɂu��ځv�i�얳���@�@�،o�j��������A����ɒ������i�ɂ͓��@�̏����Ɖԉ����L����A���̗��e�ɂ͖@�،o��������߉ގ߉ޖ��E�@�،o�̐��������ؖ����������@���̓A�{���E瑉��̏���F�A�ȉ��A�\�E���������ꂽ���̂ł���B
�@�\�E�Ƃ͌��Ɩ����̎��_����P�O��̐��E�i�l���Z���j�����������̂ŁA��E�͕��E�E��F �E�E���o �E�E�����E�̎l���A���E�͓V��E�E�l�ԊE�E�C���E�E�{���E�E��S�E�E�n���E�̘Z���������B
�{���E瑉��̏���F�͖@�،o��P�T�i�u�]�n�N�o�i�v�ő�n���N�o�����@�،o���O�ʂ����s��F�E���Ӎs��F�E��s��F�E�����s��F�������B
�\�E�ɂ͎��̏������\�����B
�l���ɂ͎l�V���i�����V�E�L�ړV�E�����V�E������V�j��z���B
���̑��A��F�Ƃ��ĕ����F�E������F�E���ӕ�F�E��F�A����ɏ\�E�̕\�ۂƂ��ĕs�������A���������A�q�d���̎ɗ������ҁA���ɑ��̉ޗt���ҁA��ߓV�A���V�A���V�A���V�A�����V�A�S�q��_�A�\�������A��Z�V�A���C���A��k�B���A�]�����A�嗴���A��苐��A�V���t�A�B����t�A�ʂĂ͓��{�̐_�X�ł���V�ƁA�������F�Ȃǂ�z���B
�@���������@�\�E��䶗��̗Ꭶ
�����@�̘Z�V�m
�@�F�����A���N�A�����A�����A�����A����
�����N�̋�V�m
�@�F��㈢苗������A��戢苗������i���[�����j�A�勳��苗����ցi�������j�A��@��苗����P�A
�@�@��~��苗����T�i���`�j�A��O��苗����́A���d��[����A������苗����s�i�����[���s�j�A�z����苗��N�c
�����@�̒��V�m�F��ʓI�ɂ͎��̓��@����q�������B
�@����i��戢苗��A����厛<�F����>�J��j
�@���فi�z��[�E�z�㈢苗��E�Ό��h�R���J��j
�@���E�i������E���숢苗��j
�@���@�i�a��[�E�a��苗��B�А��������A���{�������A�����x���R�������B�r��{�厛�E���J���{�����@���Ȃǂ��j
�@�V�ځi��@�[�E���Z��苗��B�̂���@�[�����B�����͔��R���B���q�{�����A�i��V�������A���썲�얭�����A�����{�厛�ȂNJJ��j
�@�����i�q�C�A���V��@�m�B��{�����������@�B�蕶�J�@�؎��A�J���������A�G�i���J�@�����J��B���ؖ��B���j
�@���B�i��O�[�A�������@���̊J��B���^���m�̑P�q�j
�@���ʁi���������㈢苗��A������암���A�c��͖��ʓ��T��B�x�͒r�c�{�o���A�����C�㎛<�C����>�J��j
�@�����i�W�H���A�@�Z�������J��Ƃ��Ė@�����J�R�j
�@���G�i������B�����͍������B�㑍�������Z���B
�@���Ɓi����[�B�����͍��v�Ԏ��B�����a�����J��B���Ö��o���O���j
�@���ہi�����B�����͍��v�Ԏ��B���Ö��o���A�a�����O���j
�@�����i�}�O���A�����͍H�����B��C�������Z���j
�@�����i�A�n���B�����C���J��j
�@�����i�����[�B�����͉����א��A�Ȃ͐����B���n���鎛�J��j
�@�����i�����B���͑�c�斾�B���R�@�،o���j
�@�����i���n��苗��A�@��[�A�F�����B�����[�̑\���A���n���鎛�A���n�������Z���j
�@���i�i�O�ʌ��A��i��苗��A���S�A���^�B���P�A����͌Z��B�g���O���j
----------------
�Q�j���S�@����E����@���s�E�@���@���W�E�B�S�@�����ق��擃
���S�@����E����@���s�E�@���@���W�E�B�S�@�����ق��擃�E�����F
�@�@�@�@���S�@���萹�l�@�����N(1757)��������
�@�@�@�@����@���s���l�@���i�Z����(1777)�܌������
�@�@�얳���@�@�،o�@�@�@�@�@���@���W���l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������K�V(1795)/�������l��
�@�@�@�@�B�S�@�����哿�@�V����p��(1782)�������
�@�@�@�@�@�@�ƍ����B
���ʂɋL���ꂽ�m���ɂ��Ă͎��̏����B
�@----------------------
�@���S�@���萹�l�F�s��m
�@�@�u椎j�N�\�v�F���V�N�V���Q�O����A�������P�W��
�@�@�u�@��j�v�F���7.7.20��A�]�˖������P�W��
�@����@���s���l�F������E�@�����画�f����A�g���S�U���i��ɏ����E�����j����@�����ł��낤�B
�@�@�@�������A�����Ɠ��s�́h��炬�h���Ȃ��������Ă���̂��͕�����Ȃ��B
�@�@�@�@�������擋���ʑ��������n�ɂ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ����䖭���O��n�ɕ擃������Ƃ̏������邪�m�F�ł��Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@���g���S�U������@����������@���Q��
�@�@�u椎j�N�\�v�F���i�U�N�T���Q�X����A��������A�]�˂ŘS���A�g���S�U���A�ђ˒h�щ���A���J�P�������P��q�A�э�������B
�@�@�u�@��j�v�F����@�����A���i6.5.29��A�g���S�U���i�����j
�@�@���@���W���l�F��Ȃ��A�s��m���ǂ����͕s���ł��邪�A���̂Q�����s��m�ł���A
�@�@���s���s��m�ƋL�^����Ă��邱�Ƃ����킹��A�s��m�ł���\���͍����Ǝv����B
�@�B�S�@�����哿�F�s��m
�@�@�u椎j�N�\�v�F�����i���ǁj�������ё�
�@�@�u�@��j�v�F�B�S�@���ǁA�V��2.8.9��A���ю������R�P���A�і@�ю��P�S���i�����j
�@----------------------
�@���S�@����E����@���s�E�@���@���W�E�B�S�@�����ق��擃�E����
�@�@�@�@�@�����M���@���\�M�C(1760)�l���E�E
�@�@�َ��@���g�����@���\�M�C(1760)�E�E�E�E�E�@�ƍ����B
�@�@�@�����炭�A�݉Ɓi���ʂɕs��m�̉��������܂��̂ɓ��M�j�̕���ł��낤�B
�@���S�@����E����@���s�E�@���@���W�E�B�S�@�����ق��擃�E����
�@�@���S�@�@�������@���a�Z�ȉN(1769)�\���\��
�@�@���ʼn@���h�����@���i�l����(1775)�\���@�ƍ����B
�@�@�@��f�̑��ʂƓ������A�݉Ɓi���M�j�̕���ł��낤�B
�@�w�ʂ͖��m�F�B
�R�j�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂P
�@�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂P�E����
�@�@�@�@�@�V�����N(1781)�l�������
�@�@�@�@���@灋(��)�Z����
�@�@���@�@�@�@�@�����@��������(�ȁH)/������(1796)�C�N/�Z���\�O��
�@�@�@�@灋(��)��@������s
�@�@�@�@�@�����\���(1804)���������@�@�@�ƍ����B
�@�@(��)�u灋�v�́u�@�v�̌Î��A�u灋�v����u氵�i�����j�v�Ɓu���v�̕��������o���đg�ݍ��킹���������A���ݎg���Ă���u�@�v�ł���Ƃ����B
�@�@�@�܂��A�����u���@灋�Z�����v�Ɓu灋��@������s�v�́A��Ɍf�ڂ́u�\�E��䶗�/��t���{���E�w�ʁv���ɂ�������u���@�@�Z�����v�Ɓu�@��@����v�Ɠ���l���Ǝv����B
�@�ł��邱�Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ��ł��낤���A�Ȃ��Q�c�̕擃�ɉ��������܂�Ă���̂��͕�����Ȃ��B
�S�j�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂Q
�@�݉Ɓi�M�k�j�擃���̂Q�E����
�@�@�@���@�@�v���@���l�E�E/�V�䖭�S�M�E�@�@�ƍ����B
�@���ʂ́u�����\��q(1828)�㌎�E�E�v�ƍ����B�v�N���邢�͌����N���L�����̂ł��낤�B
�@�t���ʁE�w�ʂ͖��m�F�B
��c(����)
�@�@�@�@�@��������c�d�ː}
����c�A�鎛�Ձ@�u���Ò��j�@�����v528�`
�@���W���ɂ͌��݁A���@�͂Ȃ��A�Z���̂قƂ�ǂ͐��˂̖@����Ƃ��Ă��邪�A�Â��͗ߖ@�R�A�鎛�Ə̂��������������B
�@���Ă��̏W���́A�����n��(���É��~����)�Ɏ��𒆐S�ɂ��Ă����Ă������A�㐢�ɂȂ��āA��n�̐��c����Ɏ��@�ƂƂ��ɈڏZ�����ƌ��`�����Ă���B
�@�ڏZ�̎����m���|��̈�Ƃ��āA�ڏZ��̎��@�ՂɌ����A���݂ł���ڍu�Ȃǂ��s���Ă��铰�i�����{���j�̓��ɁA�A�鎛�̓��D���ߔN�܂ł���A����ɂ́u�����O�N(1251)���V�v�Ɠǂ݂Ƃꂽ�Ƃ����B
�@���̂���͊��q���{�ܑ㏫�R���k�̎���ŁA���@�������R�ŏ��߂āu�얳���@�@�،o�v�̑�ڂ������ĐV�����@����@�@���J�����Q�N�O�̔N�ł���B
���̂��Ƃ���l����ƁA�E�̓��D�͑�n�����n�ֈڂ����Ƃ��̂��̂ł͂Ȃ��A��n�̎��É��~�i���A�鎛�Ձj�Ɍ��Ă��Ă����V��@�������͐^���@�ł������Ƃ��̂��̂Ƃ����悤�B
�@�ڒz���ꂽ�Ƃ�����Ƃ���͒�n�т̎���m�e70�Ԓn�i�����{���̐���77�n�ԁA����67�Ԓn������j������ŁA��E�����������̋������番����ē����������i�������j�����ł��邪�A��c����ŎR���ʼnz�֒ʂ���V��������̋u�̏�ɑ���ꂽ���߁A�_�����玛�@�Ւn�֓���悤�Ȋ����ł���B�����ɗ���ړ��i�����ݐ}�ɂ����ړ��ł��낤�j���Ȃ������Ƃ͂킩��Ȃ��قǒ|���������Ă���B
�@�u�̓�ʂ͕��n�ł��邪��i�ɂȂ��Ă��āA�O�i�̐����ɂ͒r�Ղ�����A��(����)���ɂ��c���̐��i�����{���̉�����̘e��n�j�����̒r�ɂ������ł����̂ł����낤���B
��i�̕��n�͋u�̒����ŁA���̍���ɕ�n�i����̘e��n�j������A�E��ɂ��铰�̏ꏊ�́A���{���ՂƂ������Ƃł���B
�@��������̓����ɑ�ړ�(��P��)�������āA�u�얳���@�@�،o�@�A�鎛�@��ܕS�Β��A�闬�z�@�����O���ГV(1806)�����g�˓��@�c���\�����뉤�����@�{���@���K���l�@�����@�������l�@���s�@�������l�v�Ƃ���A��n�̒��ɂ���قړ����傫���̑�ړ��ɂ́u�얳���@�@�،o�@���c��t�ܕS�\�����@�J�R���S�@�����@�O�������@�l�������@������ꟁ@�����@�O�������@�ܐ������@�Z�����C�@���������@��������@�㐢���i�@�\�������@�\�ꐢ��徧�@�\�����@�\�O�������@�\�l�������@�\�ܐ����Ł@�\�Z�����Y�@�\�������ρ@�{���\�Z�����Y�@�H�t�����q��@�������q��h�����@�V�ۓ�N�h�K(1831)�\���\�������ϑ�v�ƁA���̖������܂��B
�@���̑�ړ��ɁA�J�R�Ƃ��ē��S�̖��������邪�A�\�l���I���߂ɉ�����т�z�����A�����̎��@����@�@�ɉ��@���������R�@�،o���O����s�@���S�Ɠ���l�����Ƃ���ƁA�ȑO�͑��@�ł������������A���̂Ƃ�������@�@���@�ƂȂ������Ƃɂ���āu�J�R���S�v�Ƃ������̂Ǝv����B����͉��@���̑������J�R����S�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�������Ȃ����悤�B
�@�����āA���̗�Ɍ�����̂Ɠ����悤�ɁA�s��s�{�h�e���ɂ�������Đ��ނ������^���Ăї����Ȃ炵�߂��̂��u������ꟁv�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����̕�̈�Ɂu���R���ꐢ�בP�@�������l�@���������N���㌎�\����@�h�ƒ��v�Ƃ��邱�Ƃ���A���̂���܂Ŏ��͂������悤�ł���B
�@�@�@�����n�͊J�����i�݁A�������x�ϖe���Ă���l�q�ł���B
�@�܂��A�ڂ����N���͕s���ł��邪�A�����̂��鎞���Ɏ��Ђ茧�썂���S��L�n���Y�c��ܘZ�Ԃֈڂ��A�L�n�R�A�鎛�ƂȂ��Č��݂ɑ����Ă���Ƃ������Ƃł���B
�@�@���L�n�R�A�鎛����O�̓��@�@�������ɂ��聄�͓쓇���s��L�n���Q�V�W�Ɍ�������B
�@�Ȃ��A������ɏ����ꂽ�w�Ў����ג��x�ɓ����͍ڂ����Ă��Ȃ��B
�@�����̗l����m����̂͂قƂ�ǎc����Ă��Ȃ����A�̌��Ɍ�����ꂽ���a��R�O�����]�̔���������A����ɂ́A�u���`����c���ߖ@�R�A�鎛�Y��@���Ê�M���@�c�Z�q��@���b�l�T�J�C�K���q��B���@�`�_�����q��@�T�J�C�����q��B���@�`�_���E�q��@�{����X�����@�P�F�@�O���O�N��(1846)�܌��g���@(�ȉ����Ǖs�\)�v�̎����ǂ݂Ƃ��B
2023/12/01�B�e�F
�@������c�ɂ��ẮA�قڑ��������ŏ�Ԃ̎S���悷��B
���X�A���W�ł���A�n��I�ɂ͋����ł�������ɁA�����̓S���t��Ƃ��ĐZ�H����A�k���͎Y�p�u����ƂȂ�A������암�������H�Ɨp�n�Ƃ��čX�n�Ɖ����A�����ďW���������k�ɍ��������c�т���\��ō���H�����i�s����l���ł���B
���̂��߁A�l�Ƃ͒������ɐ��˓_�݂��邾���̂悤�ł���B
���݂��W���Ƃ��Ă͏��ł��������R�ł��邪�A�߂������A�ߐ��ȗ��̋����̂Ƃ��Ắu��c�v�͊ԈႢ�Ȃ����ł�����̂Ǝv����B
�@���݁A�͂��ɋ����̂Ƃ��Ă̐�c�̖ʉe�́A�p���ƂȂ��������̐�ɂ����ړ��A��ړ�����̜A�鎛�ւ̒Z���r��ʂĂ��Q���A���̐�ɂ��鑐�̔ɖ��鋫���ƈ�F�̍r�p�������A�y�т��̐��ɂ���N������������`�Ղ������Ȃ���n�i��̘e��n�j�����ł���B
�@����ƁA�����ł͂��邪�A��ӂɂ͐z�K�_�ЁA���W�E���_�l�i��ړ��Ɠ��W�����˂�j�E���c�_�Ȃǂ��c���Ă���悤�ł���B
���̜A�鎛�Ղ��c�隬�Ȃǂ͂�������X�n�Ɖ����Ă���悤�ł���B
�@���q����E���~���{��`�Ɏx�z�������{����ł��鏫����\�������镗�i�ł��낤�B
�Ȃ��A��c�A�鎛�͏��a�T�U�N�́u���@�@���@��Ӂv�ɋL�ڂ��Ȃ��B
�@�A�鎛�����E��ړ��E�Q��
�@�A�鎛��ړ��F������P���Ƃ���B�@�@�@�@�@�A�鎛��ړ���d�F�u�A�鎛�v�Ƃ���B
�@�A�鎛��ړ������F�u�����O���ГV(1806)/�����g�˓��@�c���\�����뉤/�����v
�@�A�鎛��ړ������F�u��ܕS�Β��A�闬�z�v
�@�A�鎛��ړ��w�ʂP�F�@�@�@�@�@�A�鎛��ړ��w�ʂQ�F���ǂ����炢���u�{���@���K/�t���@����/���s�@�����v�Ƃ���B
�@�A�鎛�������グ�@�@�@�@�@�A�鎛�����������@�@�@�@�@�A�鎛���{���@�@�@�@�@�A�鎛���{���Q
�@�A�鎛��n�F�V�C�W��̕擃������B
�@�A�鎛�𐢕擃�����F�u���c��t�ܕS�\�����@�얳���@�@�،o�v
�@�A�鎛�𐢕擃�����F�u�J�R���S�@�����@�O�������@�l�������@������ꟁ@�����@�O�������@�ܐ������@�Z�����C�@���������@��������@�㐢���i�@�\�������@�\�ꐢ��徧�@�\�����@�\�O�������@�\�l�������@�\�ܐ����Ł@�\�Z�����Y�@�\�������ρv
�@�A�鎛�𐢕擃�����F�u�{���\�Z�����Y�@�H�t�����q��@�������q��h�����@�V�ۓ�N�h�K(1831)�\���\�������ϑ�v
�@�A�鎛�R�P�������擃�F�u�c�R�O�\�ꐢ�@�בP�@�������l�v�A���ʂɂ́u���������N���㌎�\����v�ƍ����B
����c�E�H�T�̏��K�E�{�E�Γ��Ȃǁ@�u���Ò��j�@�����v530�`
�@�����_�l�̂ݓ]�ڂ���B
���_�l
�@���{�m�O209�Ԃ�2�����̏��ݒn�ŁA����z�K�_�ЎQ�������ł���B
�O���H�̒��S������i�����Ȃ��Ă���Ƃ���ɗ���70c���قǂ̐{�ŁA���̂悤�ɍ��܂��B
�u�얳���@�@�،o�@���_���@�����Z���N(1823)�Z���\�ܓ��@�����@���c�@�ޖƐ�(����)�@���X��@���q�@�]�˓��@�k��(��)�Á@����Ƃ�(����)�@�����@�����@����@�����쓹�@��R���@�ŎR�@���J�@����ƃ~(��x)�@�����I(����)���@�ߋ����b�l���������D�E�q��v�B
�D�z
�_�Ђɂ��ẮA�F��E���g�Ёi�Q�Ёj�E���c��ЁE�����V�������邪�A����Ёi�����V���j�������̋����V�������̂ݓ]�ڂ���B
���D�z�@���R�嗧���@�u���Ò��j�@�����v963�`
�@������2022�Ԃɂ���B
�W���̂قڒ��S�n�ŁA���Â��牡�ł�������������Ɍ�����Βi��o�����Ƃ���ł���B
���Ă͖�������O�����肩�炻�̎Q�������������A�����H���ɂ���Ĉړ������Ƃ����B
�R���E���N
�w�Ў����ג��x�ł�
�@�@�@�@�@�@�@��t���lj�����������S�������D�z������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�����a�������@�嗧��
�@�@��A�{���@�@�@�O��c�t�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�V�����O�b�ДN(��܌l)�n��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ����ԎO�ځ@���s�܊ԎO�ځ@�@�@�@�@��A�����Ԑ��@�Ԍ��l�ԁ@���s�Z��
�@�@��A�����ؐ��@�O�S��@�@�@�@�@��A���O���L�n�@(�ȗ�)�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�l�S�E�l�l
�@���̗R���ɂ��ẮA���ɂ킸���ɓ`�����镶���̈�߂ɁA��N�ɂȂ��Ă��珑���ꂽ�Ǝv����u�NjL�v������A
�n���ҁ@�̎��t���������O�j�@���[�g�]�t�A�n���^���@�i���A�u�����������J�c�������l�g�����m�Z��́A�@���_�W�e�A���X�A�������Ӄg�����A��F�������V�@���R�g���V�A�n���n�̎僈�����V�A��i�l����(1707)�㌎�{�R�a�����𐢑咆�@���F���l�㖖���g����
�@
�Ƃ��邪�A���̈������џC���R�����ɔs��Ď��Q�����Ƃ��������ɂ��āA�w�R�����`�L�x�ɂ͍O�����N(1555)�A�w���ӗR���L�x�ɂ͓V���\�O�N(1585)�Ƃ��A�����̐e�Ќ����ɂ���蕶�͂��̖v�N���c���\���N(1612)�ƋL���B
�@�܂������ɂ��ẮA�O���N��(1278�`88)���Ö��������J��čO���Z�N(1283)�ɖv�������Ƃ��������N�ɂ���A���|(�쒆)�������͂��̎��L�ɒ厡�O�N(1364)�����ɂ���Č������ꂽ���ƂƁA���̖v�N�������Z�N(1373)�ƋL��(�����ɂ��Ă͒ʎj�Ғ����u���Ö������̐����ƈ�~�@���v�̍��Q��)�B
�@������ɂ���A�����̎O�j�@���V(��̓���)���A�����Ɓu�����m�Z��́A�@���_�W�e�A���X�v�Ƃ���E�̒NjL�́A�����Ɠ������ҊԂ̍ł��߂��v�N���Ƃ��Ă݂��Ƃ��A�����Ɉꔪ��N���̂Ђ炫�����邱�Ƃ��炵�Ă��A�\���ɒ��ӂ��Č���K�v������B
�@�@�����̕����E�Y��ނ́A���a���N�O���O�\�����ޏĂɂ��Ђ̂��߉����ƂƂ��ɏĎ����A���[���𖾂���˂Ȃ�Ȃ����e���������̗R�����N�A����ю��ӂ̎����T�邤���ŁA�傫�ȏ�Q���c�����B
�@���̌�h�Ƃ̓w�͂ɂ���ē���N�ꌎ�O�����瓰�F�̍Č��ɒ��肵�A���N�O����\�����ɗ����J�����{���s����B
������̐Γ��E�Δ�
�i�P�j��ړ��F
�@�O�i�̑b�̏��1.3���]�̐Γ��������A�u�얳���@�@�،o�@���v�Oᡈ�N(1863)�\�������V��������c��X�Ɠ����S�h�����{���V�ʁX������P�@�C�P�@�@�B���s�M�m�@�P�B�@���C����M�����@���c���F�Z�S���������������A���v
�i�Q�j��ړ��F
�@������P������A�u�얳���@�@�،o�@���@���F�@����ڈꖜ����[�ܕS�����@�V�����h�N�N(1781)�\���\�O���@�c���ꌋ�i�}�}�j�@�@���R�\�����@�v
�@�@���u�c���ꌋ�v�Ƃ���̂́u�d���ꌋ�v�̌�A�ł��낤�B
�i�R�j�S�q��_���F
�@������90�����A�u�S�`�S�q�ꑸ�_���O�@�얳���@�@�،o�@����u�v�����畔���A�@�O���l�N����(�ꔪ�l��)�㌎�@���{��u���ꌋ�ޗ��V�v
�i�S�j�单���F
�@����63�����قǂŁA�u���u�v����ꖜ�����A���@�얳���@�@�،o�@�얳�单���V�_�@�������������ʕ�@���R�\�l��������@�b�q�u�����@���a�l�N�b�q(1804)�l���v
�i�T�j�S�q��_���F
�@����72�����A�u��Y���ғ��j�����@�얳���@�@�،o�@�S�q�ꑸ�_�@����u�v������ܕS���@���v���h�єN(1861)�㌎���@���J�u���v�Ƃ��ꂼ�ꍏ�ށB
�i�U�j����F
�@�����͖�90�����ŁA�u�����J����ӏ�l�@�����@�O�������@�l�������@�ܐ����^�@�Z�������@�������v�@���������@�㐢���H�@�\�����ǁ@�\�ꐢ����@�\���ׁ@�\�O�����[�v�Ƃ��邪�A���̌���͓����E���r�E�����E����E���c�E�����E���ʁE����E�����E���F�E���ƁE���ʁE���p�E�����E�����E���Y�E�����Ƒ����A���a��\��N�܌��ȍ~�́A���Z�E�̎O�\�ꐢ���S�@���L(�F�⌺�F)�t�ɂ���Ă��̖@�������p�����B
�@�i���c�]�̔�͏ȗ��B�j
2024/021/�Q�P�lj��F
���u�[�����@��j�v�Ȃǂł͑D�z�嗧���A�D�z�������͓��M���Ɖ]����B�i�A���A�������͏��F���ŁA�s���ł���B�j
����ɁA���\�̖@��ȍ~�A�D�z���������������Ƃ��m����B�i�D�z�������F���B�j
�܂��V�ۖ@��ł͑D�z���ł��������撲�ׂ��s���A���M�̕ߔ��҂��o�������Ƃ��m����B
�����a�������ł��邱�Ƃ��A���\���O��̋��̕��݂����������Ƃ���������̂����m��Ȃ��B
�v�͑D�z���s��s�{�h�̍����n�̈�ł������B
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
�@�@���R�ƍ����A�����a�������A���t�@���B
�V���Q�Q�N�i1554�j�n���A�J�R�͖@���@���ӁB
2023/11/30�B�e�F
�嗧���͕s��s�{�h�����ł��������A���M���̈�ł������Ƃ������A���݂ł͓��Ɍ����Ȃ���͂Ȃ��Ǝv����B
�@�D�z�嗧��������P�@�@�@�@�@�D�z�嗧��������Q�F��L�i�P�j��ړ��E���@�U�O�O�������ł���B
�@�D�z�嗧�����i���@�@�@�@�@�嗧�����{���P�@�@�@�@�@�嗧�����{���Q�@�@�@�@�@�嗧�����ɗ�
�@�嗧����ړ��F�O��ɂU��A���ɂR��A���v�X��̑�ړ������ԁB
�O��͌������ĉE����A�B�v�@�힊����M�m�擃�A���@�[�ܕS�������A�单���V�_���A��ڐ��S�����A���A�O���l�N�S�q��_���A���v���N�S�q��_���ł���A���͓������A��椖��o���ݎ��畔���A���A��ړ��i���i�s���j�A��椖��o�s�����ݔ���]�����A�̂R��ł���B
�O��U��F
�@�B�v�@�힊����M�m�擃
���ʁF�B�v�@�힊����M�m�A��d�ɕM�����F�����炭�݉Ƃ̕擃�ł��낤�A�M�����Ƃ͕s���B
�@���@�[�ܕS�������F�i�Q�j��ړ��ɊY������B
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@���@���F
�@�@�@���ʁF�V�����h�N�N�\���\�O���@�h���ꌋ�@�@���R�\�����@�@�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@���R�\�����@�͓��ׁF����6.1.4��
�@�单���V�_���F�i�S�j�单���ɊY������B
�@��ڐ��S�����A���F
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@��ڐ��S��/�y�h��/�M�j�M��
�@�@�@���ʁF���a�l�b�q�i1804�j�̔N�I��������B�B
�@�O���l�N�S�q��_���F�i�R�j�S�q��_���ɊY������B
�@���v���N�S�q��_���F�i�T�j�S�q��_���ɊY������B
���R��F
�@��椖��o���ݎ��畔���A���F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t�����@����������偡
�@ �@�@���ʁF���@�@��椖��o���ݎ��畔�@���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ӓ��ΔV�@�{��퓿�@����@�h���@�ƍ�����B
�@��ړ��i���i�s���j�F
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�����i�ԉ��j�@�@�@�@�������̊��������f�ł��Ȃ��B
�@��椖��o�s�����ݔ���]�����A�F
�@�@�@�@�@�@��椖��o�s�����ݔ���]��
�@�@���ʁF�얳���@�@�،o
�@�@�@�@�@�@���ۏ\���p�q�i1732�j�\�����
���D�z���~�R�������@�u�����j�@�����v960�`
�@������2031�Ԃɂ���B
�������ʂ�蓇�W���ɒʂ��鋌������A�ێR�̕��Ɍ����������������p�ŁA���Ă͖ڔ����ʂ�ł��������A���݂͐����ɑ��ÁE���ŊԂ̌������ł������߁A�X������O��Ă���B
�R���E���N
�@�w�Ў����ג��x�ł�
�@�@�@�@�@�@�@�@��t���lj�����������S�������D�z������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@���������@������
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޔ@���@�@�@�@�@��A�R���@�@�@���\��N(1689)�n���m�R�ØV�m����j���X
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ���ԁ@���s��ԁ@�@�@�@��A�����Ԑ��@�Ԍ��Z�ԁ@���s�l�ԁ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�S�l�E�O��
�@�@��A���O���L�n�@(�ȗ�)�@�@�@�@�@�@��A�h�k�l���@�S��E�l�l
�@�Ƃ����B
�@�w���@�@���@��Ӂx�ł́A�u�����\��(1480)�N�̑n���B�J�R���~�@�����B�Z�E�͒��t�@���B
(��ςɂ͉i�m�ܔN�q1297�r�ꌎ�\�ܓ��̑n���A�J�R�����Ƃ���)�v�Ƃ��āA���{�������R�@�،o���Ƃ���B
�@���̎������Z�̎��オ�����������߂��A���`�ɂ��Ă͎������U�����ĕs���ł���A�`���������c��B
����ɂ��ƁA���E���ˁE�D�z�O�J���̑������t�߂̓y������{���̎߉ޑ����o�y�������Ƃ��炻�̒n���߉ޑ�Ƃ����悤�ɂȂ����Ƃ����B
�@�܂��A���݂̓��n����̎��߉ޑ�ɖ������߉ޓ������Ă��Ă������A����Ƃ����Ɉ��a�����s�������Ƃ����̓����M��ł���Ƃ��Ď�肱�킵�A�����D�z�Ɉڂ��čČ������Ƃ������B
�@�Ƃ��ɖ������疾���ɂ����Ắu�q��ߑ��v�Ƃ��đ����̎Q�w�҂��W�߁A�����Ɍf�����Ă���G�n�ɂ͓������ʂ���̕�[�Җ�������A�߉ޓ��V��ɕ`���ꂽ�G�ɂ͔ɉh����̖��c�肪������B
�@���̎q��ߑ��̗쌱�͌��݂ɂ������p����A�c���̖鋃���E�������̂��߂Ƃ��āA���D���ɗ���l�����������B
�@���̌�ɖ��Z�̎�����o�Č����Z�E�F�⌺�F�t���}�����������́A�������r�ꂽ���ߋߔN�������肱�킵�A�N�ق����Ă���B
�@�߉ޓ��������c����Ă��邪�A���̉�L�̋[���ɂ́u����������S�M�z�����~�R�������q�|��@���O�@�������������q��@�����g�ܘY�@�������E�q��@�����������q�@�Éi�O�M���N(1850)�\�ꌎ���@��咆�����c�����E�q��@�����R粋g���q��@�牮�d���@�����r�܉E�q��v�ƍ��ށB
������̐Γ��E��
�Γ��āF
�u��[���O�吳�Z�N�\���@�@���F��呠�v�A�Α���Ɂu���O�����\��N���ꌎ�g���@�e結M�k�@�q���@���~�R�O�\�ꐢ���C��ċ��V�@�����M�k��������l�R粕����q��@�F�䗘�����@�Ŗ����Y���q��@��؋����q��@���Ð���K�g�b�v�B
��ړ��F
�u�얳���@�@�،o�@���c��m�Z�S��������u�v����ܖ����@�L��O��ܕS���@�얳�q��ߑ����u�@�������N�b�q(1864)�\�����V�@���~�R��\�㐢���F��v
�k���F
���a�R�U�����قǁA�u�{��卲�����V�����j��̎{���ʁX�����@�P�@��[�����\�O�C�\�ܓ����~�R�O�\��������@�q��ߑ����O�v�Ƃ���B
�߉ޓ��̉E��ɐΓ��ꂪ���邪�A���̂Ȃ��̐Γ��F
1.3���قǂŁA�\�Ɂu�V笉@���R�剥���m�@�F�䍲�x�剥��@�����\�l���N(1817)�\�ꌎ��\�O���@��������Ղ͂�l�@�����E��ꕧ��ɂ���������̂�(���s��)�M�풆�@�����\�O���q�l���������V�v�Ƃ���A���M�z���̂ق����݂̔����s��E������s�ƁA��h�E���E�I���E�ŎR�E���Œ�����@�����ɂ����Ďl��J���̖������܂�Ă���B
�@�i���ȉ��ȗ��j
2023/11/30�B�e�F
��ړ��F
�@��������ړ��P�F�얳���@�@�،o�@�@�@�@�@��������ړ��Q�F�얳�q��ߑ����u
�@��������ړ��R�F���c��m�Z�S�������/���u�v����ܖ���/�L��O��ܕS��
�@�Ȃ��A�w�ʁF�������N�b�q(1864)�\�����V�@���~�R��\�㐢���F��
�@�������߉ޓ��P�@�@�@�@�@�������߉ޓ��Q�@�@�@�@�@�������߉ޓ��R�@�@�@�@�@�������߉ޓ��S�@�@�@�@�@�@�������߉ޓ��T
�@�����������N��
�@�V笉@���R�剥�擃�@�@�@�@�@铓��@��痕擃�F���~�R�O�\�l��
�@����������P�@�@�@�@�@����������Q�@�@�@�@�@����������R�@�@�@�@�@����������S
�@����������T�@�@�@�@�@����������U�@�@�@�@�@����������V
���D�z�����R�����@�@�u�����j�@�����v958�`
�@������2041�Ԓn�ŁA��n�������֖���ɂ��o�Ă��镔���ɂ��鏬���W���̒������Ɉʒu����B
�R���E���N
�@�����́w�Ў����ג��x�ł�
�@�@�@�@�@�@�@��t���lj�����������S�������D�z������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V��@�@�ω������@�����@
�@�@�@�@�@�@�@�i�����ݓV��@�̌́A�ȉ��ȗ��j
�����͗אڂ���ŎR�����V���R�ω������̖����ł���B
�@�ω������͓V�����N(781)�̑n���Ɠ`�����A�u�ŎR�̐m���l�v�Ƃ��Đe���܂�Ă��鎛�ŁA���q����ɂ͂W�O�]��̖��@���������Ƃ����B
�@�����@�͖����́w�Ў����ג��x�ɋL���ꂽ��A�N���͕s���ł��邪�A�Ђɂ���ĂقƂ�ǂ̎��������������߁A���̏ڍׂ�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���D�z�E�H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�u���Ò��j�@�����v968�`
�����{�F
���ˏ�1741�Ԃɂ���B��O���w�Z���̋u��ŁA���̎Q���͋}��ƂȂ�B50�����قǂ̐{�ŁA�u�������F�@���a��\�ܔN�������@�Ŗ������V���v�B
�i����ЁA�����ЁA��ԎЁA�ٓV�ЁA�ٍ��V�{�Ȃǂ̏����K�A�M�\���A���c�_�i��������j�Ȃǂ͏ȗ��j
����(�����̂�)
�����ˍ�R���@�������@�u���Ò��j�@�����v1000�`
�@���ˍ�343�Ԃɂ���B������Ղɋ߂��A��O��ʂ��đ��Ò����牡�Œ������������͂�������قǂȂ��ŎR���֓���B
�@�����ɂ͂��āA�����̂ق��ɐ��C���A�������A���J���A�������A�����A��{�@�Ȃǂ̎��@���������Ƃ͑��l�̌��ł��邪�A���܂ł͂��̐Ղ������炩�Ȃ��̂����Ȃ��A�c���Ă���͖̂�������J�������ł���B
�R���E���N
�����́w�Ў����ג��x�ł�
�@�@�@�@��t���lj�����������S�������������ˍ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^���@�@�^�������@������
�@�@�@�@�@�@�i���^���@�ɂāA�ȉ��ȗ��j
���匴�E����E������E������E�����@--------------------
�匴
���匴�V�䒆��_�Ё@�u���Ò��j�@�����v711�`
�@�@���������Ò��̖���������
���匴�ω�����(���A�@��)�@�u���Ò��j�@�����v713�`
�@���đ匴���́A�s��s�{�@�k�̂������ł͒����ȑ��݂ł������B
���h�̊W�Õ����ɂ͂������̖��������A���Ò������┪���s��s���k���A�������k�����̕s��s�{�@�k�̉ƂɁA��ƏĈ�̂��镧������邱�Ƃ�����B
���̑��͑匴���̑�Ƃ���J���̑�Ƃ�������B
�@��J���́A�s��s�{�h�j���Ƃ��ďd�v�������́w�|�Ő_���L�x�₻�̏���(��L)�Ȃǂ��������Ă��邱�Ƃ���݂Ă��A���n�ɂ����钆�S�����Ƃł��������Ƃ͎����ł��낤�B
�@���쎞��ɂ͕\�ʂ͂Ƃ������A�S���т��s��s�{�h����M���Ă������A���݂ł͕s��s�{�@�h�̐��ы�ˁA���@�@�l�ˁA�^���@��O�˂ł���B
�����Ă��ꂼ��E�э��E���E����E���Â̎��̒h�Ƃɂ킩��A�W�����Ɏ��@�͂Ȃ��B
�@������N(1712)�̐����ɂ́A���r�_�̑O�s�Ɂu���l�ԁA���O�ԁA���E��A���Ďl���v�Ƃ��āA���A�@�����̎��n���̑��݂��L����Ă���B
����ɖ������N�̌ːЕ�ɂ́u�쑽����E��Ԓn���@���L�n�^���@���A���v�̖��������A���@�̋��ՂƂ����Ă����n�Ɨאڂ���ω����Օt�߂ɁA���̐��A�@�����������Ƃ����Ă���B
�@������̕s��s�{�h�e���ɓ������āA���̑��ɂ͐[���@��̏��Ղ��c���Ă��Ȃ����c����Ă������������Ȃ��A������d�v�����Ƃ��āA�����҂̎�ɓn�����܂܍s���s���ɂȂ��Ă����i�������j���Ƃ���A���̊Ԃ̎���ɂ��Ă̏ڍׂ����������m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���`�ɁA���@�ƕ���Ŋω����������Ă����Ƃ̂��ƂŁA��N���Ղ̔��n������F�̊ω������o�y�������Ƃ�����B
���̊ω����ՂƂ����Ă������ɂ́A���A�@�Z�E�̕��ł��낤���Ȃ�����������������A�u����m�s�@��茫�@����Z���(1678)�@���\�O���v�ƍ��܂�Ă���B
�@���@�ՂƂ����鎚�k�̓�435��2�Ԃ͕�n�ɂȂ��Ă��āA�����č����ɁA����ő���ꂽ���`�ƌ^�Ő��ʂɒ����̕t���ꂽ����܊���ׂČ��Ă��Ă���B
���̂����̓��ɂ͕��������܂�Ă��āA���ɂ́u���i�l�N���K(1627)���������@�t�C�P�������S���v�Ɠǂ݂Ƃ�A���̈��ɂ́u�V�a��p��(1682)�㌎�l���v�Ƃ������܂�Ă���B
�@�����ɁA�s��s�{�h�̒��S�ƂȂ��Ă�����J�Ƃ̉��c�ɁA���h�@�c���������������Ȃ̈ꕔ������A���ɎQ�l�Ƃ��čڂ���B
���̈����́u�����v�́A��J�y�E�q��Ǝl��ڂ̓���̕s��s�{�@���ŁA���Ȗ����̓��t�O����\�����́u�c���l�N(1651)�O����\�����v�ł���A�s��s�{�h�̑���@���A�����̉����ɑ���ӗ�̏��Ȃł���A�Ɠ`�����Ă���B
�@�@(�O��)
�@��X�䖙�͑�����R�m�i�@�߁�����@�M�V������F����x���Ɍ�@���\�o��~���l�@�E�{���m�����P�ܘY�����^�H(�����)�@���ꁡ�N�@�M�V�V����͔V�i��V��J�j���C���ԁ������Ƀj��@����䉹�M�ĉ����n�\�x���@��q�O��@���P�ܘY���ܖ旼�R��ւƂ��@�����]�������җߑ��x���i�����@�P�O�F�X�����m�R�ڏo�x��@{���@�ɏ��\��ԉ�S�Ռ�@����������ҁ@�ߋA�H���X�\�q����㉹��@���X�ތ�
�@�@�@�O���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����(�ԉ�)
�@�@�@�@�����V�]
�@�����ɂ����オ�Â��A���Ǎ���̉ӏ�������A���̏㏑�������u�U�炵�����v�ɂ������߂��Ă���̂ŁA���������Ӗ������ɂ����B����͏��Ȃ̌㔼���炵���A�悫�̔����̍s���͕s���ł���B
�@�i�����F�d�v�ȕs��s�{�h���������A������s���s���Ƃ��Ă��錤���҂Ƃ͉��R��w�̌����҂Ƙ�������B�j
2023/12/01�B�e�F
���A�@�Ղɂ��ẮA�������Ⴂ�����Ă��āA�ʂ̏ꏊ���B�e�A��Ō��������Ƃ���A�匴�����̖k���̏W��ƕ�n�̂���ꏊ�ł��낤�Ɣ��f��ύX����Ɏ���B
2024/02/28�lj��F
�@����匴���A�@�ՂP�@�@�@�@�@����匴���A�@�ՂQ�F������f�����������l��������]��
����
�����̋N����@�u���Ò��j�@�����v670�`
�@�@�i���O���j
�@���̂������т���c�������ƌĂ�Ă������Ƃ́A�����̎j���ɋL����Ă���Ƃ���ł���B
�����ɁA���̎����𗠕t���锽�ʁA����̓�𓊂������Ă���ꖇ�̔肪�������Ă���B
���̔�͂��Ēr�Ȃ̓��Ƃ���Ă������̂��A�j���A�U���J�������y�j�ƒB�ɂ���āA���ݒn�̐��V�{�_�Ћ����Ɉڂ��ꂽ���̂Ƃ����Ă��邪�A�ŏ��ɔ�������A�u����Ă������ꏊ�͂ǂ����m��悵���Ȃ��A�܂��ØV���m��Ȃ��B
�����
�@���̔�ɂ͎��̂悤�ȕ��������܂�Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@���숢
�@�@�E�ӎ�҈�
�@�@�ꌋ�S�\�l
�@�@�t�C�@��@
�@�@�����l��(���)��
�@�@�i�a���N[���K]�@�@�@�@���i�a���N�i1375�j
�@�@�l�����ܓ��h��
�@��ɂ́A�u���a�O�\�Z�N��\�Z���Č��@���Ò����y���ҏW�ψ���@�H��h�i�v�Ƃ���B
�܂����̕��ʂ��ǂ���ɍl�@���Ă݂�ƁA�i�a���N(1375)�l����\�ܓ��ɕ��숢�Ƃ����l�����A���u��܁Z�l�̐��O���{�ƁA���łɖS���Ȃ��Ă���l�̐l�X�̕������߂Ɍ��Ă����̂Ɖ��߂����B
�@�@�@�����̉i�a���N�̔�͓��䖭���Ђ̋����ɑJ����Č�������B
�@�@�@�@�@�i���䐯�V�{�_�ЁF���������Ò��̖����������j
�@�����҂ł��낤�Ǝv���镽�숢�Ƃ͂����Ȃ�l���ł��邩��m�邽�߂ɁA�i�a�̂��낱�̒n���̓����҂ł�������t�����w���f�ٖ{��t�n�}�x�ɂ���Ē��ׂ�ƁA�\�ܑ��t�����̍��Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����B
�@�i���ȉ��ȗ��j
�@��t��A���O�O�N(1333)�܌��\�Z���n�e�`��(�V�c)�j���A�������V�囒�g���B�ߌ��j��L���A������N(1335)�\�ꌎ����������(����)�A�����l�N(1337)���\���k�����~�`��m��w�g�i���A�ܕS�R�j�e�ŃP���K��j�������q�A�����j�n�i���G�w�w���q�o�A�����獂�S�C���L���j�g���c�J�n�X�����j���S�j���X�g�A�Q�l�����L�j�o�A�ω���N(��O�܈�)�����N�Z�\��A�@���숢��ɕ������B
�@���̈ꕶ�ɂ��A���숢�Ȃ�l���\�ܑ��t�����ł��邱�ƂɂȂ�B����͐�t�����{�Ƃ̓��̂Ő�t��̏��ł���B
�@���̒���̊�������͌����̒������s��ꂽ����ŁA������ɖ������āA���R�Ƃ��Ĉ�g�̔ɉh���͂��邩�A�Ƃ��̏��R���ɂ��Ĉ��ׂ邩�A���̐����̎��������ɕ������Ƃ��钩����ƁA���͂ɂ���Ă����D�����Ƃ��镐�ƕ��Ƃ̊Ԃɗ��n�����m�́A�g�̋��A�ɐS��Y�܂�������ł��������B
�@��t���݂̂łȂ��A�֓��̍����́A�Ƃ��ɁA���q�A�Z�푊����Đ�����̂ł���B���Ò���ł͌����O�N(1336)������\�����ɐ�t������R���A��c���R���U�߂��y����̐킪����A����͍��ɓ`�����Ă���B
�@���������Љ��ł��������߂ɋt�C�A���Ȃ킿���琶���Ă��邤���ɌȂ̕����悤�Ȃ��Ƃ��s��ꂽ�̂ł͂���܂����B
�@���̂ق��ɂ����̔�ɂ͋^�₪����B�܂������̎���ł���B�蕶�ɍ��܂ꂽ�i�a���N(1375)�ɂ́A�@���숢�Ƃ���������͐����Z�N(1351)���łɖv���đ������̎���ɂȂ��Ă���B����ɐ�c�����U�߂�����̋��{�肪�Ȃɂ䂦�ɐ�c�����Ɍ��Ă�ꂽ�̂��B�����́w���f�ٖ{��t�n�}�x�ł͒���̖@�����숢��ɕ��ƂȂ��Ă��邪�A�w��t��n�}�x�ł͑P���퓿�@����ɕ��ƂȂ��Ă���B�܂��t�C�ɂ��Ă̍l���������`�ł��邩������Ȃ��B���ɂ킩�ɂ����ɂ��Ă𗧏��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���j�ɂ����鍡��̉ۑ�Ƃ��ďd�v�Ȃ��Ƃł��낤�B
�@�����ɂ���ẮA�j��ɖ����Ƃǂ߂镐���̋��{�������Ă��A�����̎���ɔމ�U�h�̓I�ƂȂ��Ă������Ƃ́A���̒n���헪�̋��_�ł���A���ꂾ���J��╶���̐i�y�n�ł��������Ƃ�@���ɕ������̂Ƃ����悤�B
������{�Ҏ��Ձ@�u���Ò��j�@�����v675�`
�@�������s��s�{�h�M�̑��ł���B���l�͓��쎞��̒����e���̊��ԁA�Ђ����ɕs��s�{�̋�����M���Ȃ���ς������A���Ȃ��������Ă��̏@�h�ł���B
���ꂾ���ɑc�搒�q�̏��s���͐̂̂Ƃ���ł�����Ă��āA��n�Ȃǂ���������A�\�ܓ��ɂ͕K�����|����A���Ȃ�������̂悤�ɐ���ȏꏊ�ł���B
�@�����e���̍Ό��̒��Ő������i�Ƃ��āA�\�ʏ�͎�h�ł����ʓI�ȓ��@�@�k�Ƃ��Ď��@�����c�������A���������ꂽ������N�ȍ~�͎�h�̎��𗣂�Ė{���̕s��s�{�h��W�Ԃ��āA�������O997�Ԓn��1�ɕs��s�{�h�����A�i�N�ɂ킽��ߊ���ʂ������B
�@�₪�Ă��̋���ׂ͗̒�����ֈڂ���āA�������̖��߂𑱂��Ă���B�U�ߎ��͓��̐��o���ł���B
�@�@�@������͕s��s�{�h������쑽����Ƃ��Č�������B���f�́u������쑽����̐ݗ��v�̍����Q�ƁB
�@�U��h�M�҂�h�ƂƂ��āA���M�҂�Nj��̎肩���葱�������@�̐Ղ������˂�ƁA���̈�͎�����978�Ԓn��1�ɂ����āA�W���̒����Ɉʒu���A���݂͏W������Ă��Ă���B
�@�����́w���@�䒠�x�ł�
�@�@�@�@�@��t���lj�����������S���Ò��쑽����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�������@�{�Ҏ�
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޔ@���@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��Z�ԁ@���s�l�ԁ@�@�@�@�@��A�����ؐ��@�S��E��@�@�@�@�@��A�Z�E�@�@�@����B�Y
�@�@��A�d�k�l���@��E�O�l
�@�܂��A��L�����̒��ɓ����̔��������܂ꂽ�Ƃ��̂��Ƃ��L�������̈ꕶ������B
�@�@�@����͏�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t������������S�쑽��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�W��g���@�ؓ������q��
�@�E��\���B������66�Ԓn���@�@����R�{�Ҏ��A�{�������֔�����ӊ|�u�A�{��������ߑO�\�����A�E���ƃi�����쎵�Y���q�A�s������p�W���迠�͐\�o��j�t�A�U���m�Ҏ������j����S���葊�q�������s�\�A�����m�i���j
��A�����@�@���
�@�@�A�@���n�V��ڌܐ��ʁ@�@�@�@�ڕ��E�܊іڈʁ@�@�@������E��~�ʁ@�@�@�@�@���E�����Z�N(1666)�܌���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��c���匴�����䑺
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�@�����ܘY���q�i���ȉ��V���ȗ��j
�@
�@�E�i�ߖT���X���q���A�X�j�s�q�s�����A�S�N�����V���ƃg����B���i��͐\���@�@�ȏ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�h���y��@�g���@�ؓ������q��@��
�@�@�@�����\��N�\�����
�@�@�@�@�@��t���߁@�Č��@�a�a
�@�@�����Ă��̎��Ղ���ŋ߈ڂ��ꂽ�Ƃ����Γ��O���������O��n�̈���ɂ����āA���ꂼ�ꎟ�̂悤�ɍ��܂�Ă���B
�@�@(����)�u�얳���@�@�،o���@��t�@�����\��ȉN�N(1829)�@�����ܕS�\���v
�@�@(����)�u������畔���ُ��@���\�\�N���N(1697)�@����ꌋ�j���v
�@�@(�E��)�u������畔�ܕS�����ӓ��@�V�����N�p(�h)�N�N(1781)�\���\�O���@����R�{�Ҏ��y�h���v
�@�@(����)�u���@�@�����l(�E��)�V�ۘZ����(1835)�\�����v
�@�@(����)�u�S���@�������l�@�V�ۏ\�܍b�C�N(1844)�㌎��\�l�����v
�@
�@�������ĐΔ��Õ������������A�{�Ҏ��͌��\�\�N(1687)���疾���\��N�܂ł́A��h���@�Ƃ��đ��݂��Ă����悤�ł���B
�吳���ɂȂ��Ă���͎��@�䒠�ɂ��̎������Ƃǂ߂�݂̂ŁA���@�̌����͑��̏W��̂悤�Ȗ������ʂ����݂̂ł������B
�����āA���̂��납��{�Ҏ��̎��Ђ͏H�c���̖^���Ɉڂ��ꂽ�Ƃ����Ă��邪�A���m�ɂ͂킩��Ȃ��B
�@�@�@���H�c���Ɏ��Ђ��ڂ����{�Ҏ��͒���������s���B
�@�@�@���{�Ҏ��Ղɂ��āA
�@�@�@��X�t�߂ɋ����킹���N�z�̕��ɐq�˂���u���̎���̘b���v�Ɖ]���u�S��������Ȃ��v�Ƃ������Ƃł������B
�@�@�@����n�͌�������S���̖��Ƃ��W�������Ȃ����A��F�̌��������邾���ŁA���@�Ղ��Â�����̂́A
�@�@�@�������Ⴂ�łȂ���A�܂����������悤�ł���B
�@�@�@�B��̋~���͌�q����u�����O��n�ɑJ���ꂽ�R��̕擃�v�݂̂Ȃ̂ł��낤�B
�@����ɂ�����J���������Ƃ������Ƃł��邪�A���̍ݏ��������ł���̂��A�ØV�������m��Ȃ��B�����A���̕����ɂ���đ��݂̎��������͏��邱�Ƃ��ł���B
�@�@�@�@�@���n���\��D�V��
�@�@�ꌚ�ƈ듏�@�A���\�Ԍ��@�@�l�ԁ@�@���s�@�@�@��ԁ@�@�O�j��ڑ��(��)����
�@�@�@�@����E�~��
�@�@�@�E�҉䓙�掝�V���ƈ듏�@���x�M�a���֔��n���@������j���\���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��S�\�ԁ@�n�呑��
�@�@�@�@�@�����ܐp�\�N�\�ꌎ
�@�@�@�@�@�@�����@���o�@�a
������E�H�T�̏��K�A�{�Ȃǁ@�u���Ò��j�@�����v679�`
�@�s��s�{�h�Ƃ��ċ����c�����ێ������������߂��A���̐_���ɑ���S�͋ɂ߂Ĕ����B
���������āA�M�̑Ώە��ƂȂ鏬�K�A�������A�Ε��Ȃǂ͂قƂ�ǂȂ��B
�@�@�i�������E��ړ��̂ݓ]�ڂ���B�j
�����䐯�V�{�_�ЁF���������Ò��̖���������
�����䖭���O��n
���u���Ò��j�v�����@�@�s��s�{�h�̖@��i���������Ò���j�@�@�㊪335�`�@�ꕔ����
�@���i�\�N(1633)���{�͊C�O�n�q�E�f�Ղ̐����ƂƂ��ɃL���V�^�����֎~����@�߂��o�����A����Ȍ�A�M�k�T���̂��߂ɏ@����߂��s���A�܂����@���ĕ����ɋA�˂����҂���͐����������B
���ꂪ��ʉ����Ď������x�ƂȂ�A�����͏������@��h�ߎ��Ƃ��A�����◷�s�Ȃǂ̍ۂɂ͎��̔��s����@�|��`���K�v�ƂȂ�B
���̂��߁A���@�͏����̎v�z�Ď@������ƂƂ��ɑ��̌ːЎ����������s���@�ւƂ��Ȃ��Ă��܂��B���������@�͌c����N(1597)�ȍ~�́u���@���@�@�x�v�A�����ܔN(1665)�́u�������@��|�v�Ȃǂɂ���Ă��т�����������A��ʂł͕ی�����̂ŁA�@���{���̏O���̋~�ς��͐����I�x�z�̖��[�̖�����S�킳��邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�ȏ@�����x�̒��ŋN�������̂��A���@�@�s��s�{�h�̖@��ł���B
���Ò���ł͍]�ˏ������ɂ͓��E������E����E�匴�̊e�����قƂ�Ǒ�����ݓ��h�̐M�҂ł���A���ˁE�т����ʑ��E��Ȃǂ̑��X�ɂ��M�҂������B
���u���Ò��j�v���i������������j�s��s�{�h�ɑ���e���@�@����641�`�@�ꕔ����
�@��������אڂ̓���ƂƂ��ɑS�˕s��s�{�h�ł���B
���������ďW�����Ɏ��@�炵�������͂Ȃ��A����Ƌ��L�̋���ƌĂԌ����𗘗p���āA���ׂĂ̕����I�s�����s���Ă���B
���̋���ɂ��Ă̐ݒu�ϑJ�ɂ��Ă͌�ɏq�ׂ邪�A�S���т����E���o���̒h�ƂɂȂ��Ă���B
��n������n���ɋ����ň�J���ɂȂ��Ă��邪�A�����X�N�ɕs��s�{�h�������ƂȂ�܂ł́A�����R�ɓ�J���A����m��Ɉ�J���������Ƃ����B
�@�����ɁA�@�|����������Ă��玚���R�̓�J���𓌑�̎������O�Ɉڂ����Ƃ����͕̂\�����̂��ƂŁA��h�̓��@�@���Ă��Ȃ�������͕s��s�{�h�ł��������߁A�����ɓ������Ă͓��@�@�̑m���𗊂�Ŗ���������̂́A��ɂȂ��Ă����[���@��o���Ĕ邩�ɓ����n�ɉ������A�s��s�{�̉B��m���ɂ���ĕʂɉ�������Ƃ����B
�@��̌����Ă����n�͉���̂��̂ł���A�̂Ȃ����䖭���O�̕悱���c��ݑ�̂ق�Ƃ��̕�ł���Ƃ��Ă������炱���A�����ɂȂ��Č������ꂽ�Ƃ��ɂ͉��̒�R���Ȃ��������ɕ�n�̈ړ]���Ȃ��ꂽ�̂ł��낤�B
�����O��n�ɓ��䖭���i���䐯�V�{�_�Ёj������A�����Ђ͎������O999�Ԓn�ɂ���A�{�a�͖ؑ��i���݂̓R���N���[�g���j�ł��̋����ɑO�L�̉i�a���N[���K]�ƍ��܂ꂽ�肪���Ă���B�@�@�@���i�a���N��1375�N�ł���B
���̔�͏�ɋL�ڂ̒ʂ�ł���A���݂ł͖����Ћ����Ɉڐ݂���A�����ɏ��݂���B���������Ò��̖���������
2023/12/01�B�e�F
�@���䖭���ЂP�@�@�@�@�@���䖭���ЂQ�F�������č��̍g�t�������̌�Ɂu�i�a���N����v�������Ɏʂ�B
�i�a���N���̔�̊m�F�͂����A����ĎB�e�͂����B�]���ĉ��̌f�ڎʐ^�iGoogkeMap����]�ځj�͐���ł���B
�@����i�a���N����P�@�@�@�@�@����i�a���N����Q
�@�@�@�@�@�@�@�����䖭���O��n�ʒu�}
���䖭���O��n�i�������n�j
�u���Ò��j�v�ł͈ȉ��̂悤�ɉ]���B
�@�܂��A���̕�n�̈���ɂ́A�{�Ҏ�����ŋ߁i���u�ŋ߁v�Ƃ��邪�A���݂���ł́A�����I�قǑO�ɂȂ�B�j�ڂ��ꂽ�Ƃ����Γ��O������āA���ꂼ�ꎟ�̂悤�ɍ��܂�Ă���B
�@�@�����@��
�@�@�@(����)�u�얳���@�@�،o���@��t�@�����\��ȉN�N(1829)�@�����ܕS�\���v�@�@�����@��t�͓��@��m�̌�A
�@�@�@(����)�u������畔���ُ��@���\�\�N���N(1697)�@����ꌋ�j���v
�@�@�@(�E��)�u������畔�ܕS�����ӓ��@�V�����N�p(�h)�N�N(1781)�\���\�O���@����R�{�Ҏ��y�h���v
�@�@�����@�����擃
�@�@�@(����)�u���@�������l(�E��)�V�ۘZ����(1835)�\�����v
�@�@���S���@�����擃
�@�@�@(����)�u�S���@�������l�@�V�ۏ\�܍b�C�N(1844)/�㌎��\�l�����v
������������A
��L�́u���Ò��j�v�ł����擃�ȊO�ɁA���̂悤�Ȓ��ڂ��ׂ��Γ��������̐Γ��i�擃�j������B
�@�Q�D��������A
�@�S�D�����O��n��P�擃��ɂ́A������s��s�{�m�ł���
�@�@���s�@���^�A�����@���d�A�����@�����A�����@���W�A�Ŏ�@�����A���@�@���ʁA����@��铁A����@���G�Ȃǂ̕擃������B
�@�U�D�����O��n��Q�擃��ɂ́A�s��s�{�m�����@���p�E���m�{���@�����̕擃������B
�P�D�{�Ҏ�����ڂ��ꂽ�Ƃ����Γ��O��
�@�{�Ҏ�����ڐݕ擃�R���F�������č�����u�{�Ҏ����@���v�A�u���@�����擃�v�A�u�S���@�����擃�v�ł���B
�@�P�D�P�j�{�Ҏ����@��
�@�{�Ҏ����@���E�����F�u�얳���@�@�،o�@���@��m�@�E�E�E�v
�@�{�Ҏ����@���E���ʏڍ��F���@��m�̍��E�̖��͔��ǂ�����A��L���u�����\��ȉN�N(1829)/�����ܕS�\���v�ƕ�����B
�@�{�Ҏ����@���E���ʂP�F�u������畔�E�E�E/�V�����E�E�E/���i�R�{���v
�@�@���ӂŌ����Ȃ���������L�ŕ₤�ƁA
�@�@�u������畔�ܕS�����ӓ��@�V�����N�p(�h)�N�N(1781)�\���\�O���@����R�{�Ҏ��y�h���v�ƂȂ�A
�@�@�V�����N���i�R�̑y�h�������@�T�O�O������������畔���A���ׂ��Ɠǂ߂�B
�@�{�Ҏ����@���E���ʂQ�F�u�������E�E�E/���\�E�E�E�E�v
�@�@���������A�ӂŌ����Ȃ���������L�ŕ₤�ƁA�u������畔���ُ��@���\�\�N���N(1697)�@����ꌋ�j���v�ƂȂ�A
�@�@���\�P�O�N����ꌋ�j������������畔���A���ׂ��Ɠǂ߂�B
�@�ȏォ��A���̐Γ��͖{�Ҏ��h�M�k�̌����Ŗ{�Ҏ��ɂ��������̂Ɛ��肳��A
�����P�Q�N�i1829�j���@�T�T�O�����Ɍ�������A�����Ɍ��\�P�O�N(1697)�̏�������畔���A�A�V�����N(1781)�̓��@�T�O�O�����y�я�������畔���A���L�O����Γ��ƕ���B�ܘ_�A�V�����N�͓��@�ܕS�����̐����ł���B
�@�P�D�Q�j���@�����擃
�@���@�����擃�F�����̎��Օs��
�@�@(����)�u���@�������l(�E��)�V�ۘZ����(1835)�\�����v
�@�P�D�R�j�S���@�����擃
�@�S���@�����擃�F�����̎��Օs��
�@�@(����)�u�S���@�������l�@�V�ۏ\�܍b�C�N(1844)/�㌎��\�l�����v
�Q�D���������
�@���������
�@��������E�������F�����̓��͓ǂݎ��Ȃ����A���͓ǂݎ���̂ŁA�u�����v�̋��{���Ɛ���A
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@����(�ԉ�)�@�@�������͐���
�@�@�@���E�����ʁF�����ł���B�@�@�@�@�@���ʁF�m�F�����Ă��Ȃ��B
�@��L�ŁA�u���v���́u���v�͓ǂݎ��Ȃ��Ƃ������A���X�A�u���v�͒���ꂸ�A�u���v�̂ݒ����Ă����\�������邾�낤�B
���̎���A�����āA�u�����v�Ƃ͂����u���v�Ƃ�������A�����ւ̐��h�͕\���邪�A���̈Ӑ}���B�����ߊ����Ă������������������\��������̂ł͂Ȃ����B
�@�Ƃ���ŁA���̐�������̎���͉����Ȃ̂ł��낤���B
���g�͔��ɐV���������A������ɑk��Â����̂ł͂Ȃ��悤�Ɍ�����B
�������A�u�đ��v�̏ꍇ���̎|�̖�������ꍇ������A���ꂪ�m�F�ł��Ă��Ȃ��̂ŁA�V�������̂Ƃ��f��͂ł��Ȃ��B
�A���A�w�ʂ����m�F�ł���̂ŁA�����Ɂu�đ��v�̎|�̖�������A��������̂ł��邪�A���ǂ͕�����Ȃ��B
�����A���g�͈ٗl�Ȓ��ɐV���������A���ꂪ�Â����g���������Ƃɂ����̂ł���\�����̂Ă���Ȃ��B
�R�D�����E���K�i�H�j�擃
�@�G�P�@�����擃�F�����̎��Ղ͕s��
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�G�P�@�����@�t
�@�@�@���ʁF���������N�O���\�l������@�@�@�@�@�@�@�c��R�ʂ͖��m�F
�@�����@���K[�H]�擃�F���K�̎��Ղ͕s��
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o�@�����@���K���ʁF���K�͌�ǂ̉\������B
�@�@�@���ʁF�����\��N�Z���\��������@�@�@�@�@�@�@�c��R�ʂ͖��m�F
�S�D������@�֘A�Γ��R��
�@���@�֘A�Γ��R���F���@��𦬠�Γ��i�������č��j�A������@���{���i�����j�A���@�Β��֑ɗ��{���i�E�j�̂R����ԁB
�@�@�����͑�^�̐Γ��ł���B
�@�S�D�P�j���@��𦬠�Γ��@
�@���@��𦬠�Γ��E����
�@�@���ʁF�@�Ŗڏ�Ɩ@�ؐr�[���`
�@�@�@�@�@�얳���@�@�،o�@���@��𦬠
�@�@�@�@�@�@�b�ډv�P�@�Ҕ�v�u�ِ�
�@���@��𦬠�Γ��E���ʂP�F�u�����������E�E�E�@�@/���ۏ\�O��\�N�����E�E�v�@�@�����ۂP�R�N�i1728�j
�@���@��𦬠�Γ��E���ʂQ�F�u�x�m�������E�E�E�@�@/�E�E�E�E�E�@�@�v
�@�S�D�Q�j������@���{��
�@������@���{���E�����F�u�얳���@�@�،o�@����(�ԉ�)�v�@�@�������͓��@�Ǝv���邪�A��ǂ̉\������
�@������@���{���E��������
�@������@���{���E���ʂP�F
�@�@�@�@�u�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ۓ�p���E�E�@�v�@�@�@�����ۓ�N�i�p���j1742�N
�@�@�@�@�u��ܕS�Β��A�闬�z/��腕��ߒf��@�@�@�E���ˁv
�@�@�@�@�u�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�����E�E�E�@�v
�@������@���{���E���ʂQ
�@�@�@�@�u��椑�断�T���ݕ�/���u�v�������E�E�E�E�v
�@�S�D�R�j���@�Β��֑ɗ��{��
�@���@�Β��֑ɗ��{���E���ʂP
�@���@�Β��֑ɗ��{���E���ʂQ�F�u�Β��֑ɗ��{���@���@(�ԉ�)�v
�@���@�Β��֑ɗ��{���E�����F�@�u���ʁF�@���閧�{�n��E�E�E�E�E�E�E/�ፂ�c�������\�E�{���v
�T�D�����O��n��P�擃��
�@�s��s�{�m�ł������s�@���^�A�����@���d�A�����@�����A�����@���W�A�Ŏ�@�����A���@�@���ʁA����@��铁A����@���G�Ȃǂ̕擃���U�������B
�@�����O��n��P�擃���F�S�e
�@�T�D�P�j�s��s�{�m���s�@���^�F�u�[�����@��j�i�ȉ��u�@��j�v�j�F����5.11.25��A�������i��������j
�@���s�@���^�擃�E�����F�u�얳���@�@�،o�v
�@���s�@���^�擃�E���ʂP�F�u��k���Ǖs�\�l�v
�@���s�@���^�擃�E���ʂQ�@�@�@�@�@���s�@���^�擃�E���ʂQ�����F�u���s�@���^�哿/���ہ����E�E/�\�ꌎ���ܓ��v
�@�T�D�Q�j�s��s�{�m�����@���d�F�u�@��j�v�F���i9.10.18��A�ʑ��J
�@���d�E�������m�擃
�@�����@���d�擃�E�����F�u���@�@�����@���d���l�v
�@�����@���d�擃�E���ʕ����F�u���i�ち�����\���\�����v
�@�@�c��̑��ʁF[���Ǖs�\]
�@�T�D�R�j�s��s�{�m�����@�����F�u�@��j�v�F����6.1.11��A�⑺
�@�����@�����E�����F�u���@�@�����@�����哿�v
�@�@�����ʂƂ�[�ǂݎ�荢��]
�@�T�D�S�j�s��s�{�m�����@���W�F�u�@��j�v�F���6.4.26��A�ё��@�ю��P�R���A���˖@��A�ѐ���
�@�����@���W�擃�E�����F�u���@�@�����@���W�哿�v
�@�����@���W�擃�E�����F�u�E�E�E�\�O��/���E�E�E�E/�l����E�E�E�E�v
�@�T�D�T�j�s��s�{�m�Ŏ�@�����F�u�@��j�v�F����4.1.2��A������
�@�Ŏ�@�����擃�E�����F�u�E�E�@�Ŏ�@�������l/�����l�E�E�E/��������v�@�@�@�������S�N�i�h���j�@1751�N
�@�@2024/08/02�lj��F
�@�@�u�[���vp.155�ɂ́F
�@�@�����i�����E���ہE�����j�E�E�E�n���@���ɐ���ł���@���͌�������Ȃ����A
�@�@��肪�������z���Ă���@���Ƃ����V���Ŏ�@����������B
�@�@�V�u�Ќ̖x�z�`�����̕ł́A�Ŏ�@�����͒ʏ̖��q��A�V���R�ӉƏo�g�ŁA
�@�@�u�L���E�g�E�ˁA�Ɖ]����܊�̕�����ی��N�����\�ܓ��A�V���A�Ŏ�@�����v�Ƃ�����肪����A
�@�@���ɗё��ɂ����𗧂āA��h�ߒŖ��Ƃɐ������̖{�������^���Ă���B
�@�@�@���u�L���E�g�E�ˁv�Ƃ͏�Ȃ��A�s���B
�@�@p.288�ł͘Ŏ�@�����@�����S�N�P���Q����@�����@�Ƃ���B
�@�@�@�{�T�C�g�Ŋm�F���Ă���̂́A���̕擃���ʑ���n���O���n�����@��ҕ揊���Ŏ�@����/���{�@�����擃�̂Q���ł���B
�@�T�D�U�j�s��s�{�m���@�@���ʁF�u�@��j�v�F���a8.10.23��A�ѐ���
�@���@�@���ʕ擃�E�����F�u�얳���@�@�،o�@���@�@���ʑ哿�v
�@���@�@���ʕ擃�E���ʕ���
�@�@�@���ʁE���ʂR�ʂƂ����m�F
�@�T�D�V�j���S�@�����E�@�����擃
�@���S�@�����E�@�����擃
�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@���S�@�����E�E
�@�@�@���ʁF���@
�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�����E�E�@�@�@����͕s�m��
�@���S�@�����E�@�����Ƃ��o��s���A
�@���S�@�̍��͓��B��l�i���v�R�B����j�����݂��邪�A�u�����v�́u���B�v�Ƃ͓ǂ߂��A�܂������̏����F���ł���
�@�u���S�@�����v���u���B�v�Ɨސ������|������Ȃ��B
�@�T�D�W�j�s��s�{�m����@��铁F�u�@��j�v�F�����V�c���@�����i6.9.9��A����E���쑺�@�y�ьd���@���{
�@�@������@��铕擃�͋����V�c���Ձ����������E�����V�c���F�P�P����@��铑哿���ɂ�����B
�@�d���@���{�E����@��铕擃
�@�@�@�@�@�@�F�@�@�d���@���{���l�@�@�@���o��s��
�@�@�@���ʁF���@
�@�@�@�@�@�@�F�@�@����@��铐��l�@�@�@���u�@��j�v�F�����V�c���@�����i6.9.9��A����E���쑺
�@�T�D�X�j�s��s�{�m����@���G�F�u�@��j�v�F�勝1.11.3��
�@����@���G�擃�E�����F�E���ʂɁu�\�ꌎ��{�O���v������A���G�̎��⌎���Əd�Ȃ�B
�@����@���G�擃�E���ʕ����F[���@�@����@���G���l]�@�����ǂ�����A�����炭���L�̂悤�Ɍ�����B
�@�T�D10�j����M�k�̕擃
�@����M�k�̕擃
�@�@�@�@�@�@�F�@�@���ۏ\���p�q������i�H�j���@�@�@�@��1732�N
�@�@�@�@�@�@�F�@�����@������
�@�@�@���ʁF�얳���@�@�،o
�@�@�@�@�@�@�F�@�{�ۉ@���_���
�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@���a�l�N��\�ꌎ�����@�@�@�@�@�@��1767�N
�@�@�@�@�@�����炭�A�M�k�̕擃�Ǝv����B
�U�D�����O��n��Q�擃��
�@�u�R�̎��v�ɔz�u�����B
�@�����O��n��Q�擃��P
�@�@���ʌ������ĉE����A�M�k�̕擃�A�s��s�{�m�����@���p�擃�A�����@�a�擃�A���N�T�O�O�������{���̂S����ԁB
�@�����O��n��Q�擃��Q
�@�@�W��قǂ̕擃�����Ԃ��A�ڍׂ������B�����͐M�҂̕擃�Ǝv���邪�A����ɂ���Ē������K�v�ł���B
�@�����O��n��Q�擃��R
�@�@�T����Ԃ��A���̓��̂P��͕s��s�{�m�{���@�����̕擃�ł���B���̑��͐M�҂̕擃�ł��낤�B
�@�U�D�P�j�s��s�{�m�����@���p�F�u�@��j�v�F���\11.2.22��A���q�������S���@�@[���\�\��N�i��Ёj1698�N]
�@�����@���p�擃�E�����F�����F���ʁF�u�t�́@�����@���p�哿�v
�@�����@���p�擃�E�w���F�u���\(�\��)�������В��t������v�@�@�@�����t�F�A��Q���̂���
�@�U�D�Q�j�����@�a��������擃
�@�����@�a���擃�E�����F�\�ʁF���@�@�����@�a���������o��
�@�A���A�u�����@�a���������o�v�Ƃ͑S���s���A����͊��{���������̎�ł������Ƃ�������A���邢�͈������̈ꑰ�Ƃ��l������邪�A�S���̑z���ł���B���ʂɂ́u���ۏ\�O��\�V�v�ƍ��ނ̂ŁA���ۂP�R�N�i1728�j���v�N�ł��낤�B
�@�U�D�R�j���N500������
�@���N�T�O�O�������{���E�����F�u�얳���@�@�،o�@�얳���N��F�v
�@���N�T�O�O�������{���E���ʂP�F
�@�@�@�u�@������ȉK���������v�@�@�@�������Q�N��1819�N�@�����N�F�����Q�N�i1320�j�P���Q�P����
�@�@�@�u�������ґ�ܕS�����v
�@�@�@�u�@�����R��o���E�E�E�E�E�v
�@���N�T�O�O�������{���E���ʂQ�F�u���@�@�b�N�@�������l/�����\ᡓэ�/�O���\�ܓ��v�@�@�������P�O�N��1813�N
�@�@�@�@�@�������̏��͂Ȃ�
�@�����Q�N�i1819�j�����N�T�O�O�����������ɂ��̕����������ꂽ�̂ł��낤���A���ʂɂ͌b�N�@�����̉����Ǝ���N�������P�O�N�i1813�j�������ނ̂ŁA�����̕擃�������˂����̂Ȃ̂ł��낤���B
�@�U�D�S�j�s��s�{�m�{���@�����F�u�@��j�v�F9.19��A���q��
�@�{���@�����擃�F�����̕擃�́u���@�@�{���@�����哿�v�Ƃ���B
�@�@�u���v�̕������ǂݎ���̂ŁA���a�i�������͋��ہj�̎���ł��낤�Ǝv����B
���̑��A
�@�����O��n�E�Õ擃�F�ڍׂȒ����͂����A������v���邾�낤�B
�������ړ��F�@�@�u���Ò��j�@�����v
�@�H����524�Ԃ�5�ɂ���B�L�����̒����ɂ�������Ă��Ă���B
���ʂɂ́u�얳���@�@�،o�ϐ����v�A�E���Ɂu���a���h��(1801)�\�ꌎ�g���v�A�����Ɂu�����쑺�@���䑺�����v�ƍ��܂�Ă��āA���̐Γ��k���ɝ˔n�̏�(���܂��Ă�)���������Ƃ����邪�A���邢�͔p�n�����߂Ɍ��Ă��n���ϐ������̂悤�Ȃ��̂ł�������������Ȃ��B
2024/03/07�lj��F
�@���n�͖��K��AGoogleStreetview�Ő���������A�����ł����B�͂����āA���n�Ɍ������邩�ǂ����͕s���B
������
���������쁄�s��s�{�h�ɑ���e���@�@�u���Ò��j�@�����v641�`
�@�@�����@�@�s��s�{�h�̖@���ɓ]��
�������얭�����Ձ@�@�u���Ò��j�@�����v650�`
�@�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA���M�҂Ƃ��Čł��s��s�{��M���Ȃ�����A�\�ʓI�ɂ͎�h�łȂ���Ό������e���������邱�Ƃ͕s�\�ł��������Ƃ���A�l�X�͎��J�̓�����Ԓn�ɂ����������������̕�Ƃ����B�����ɂ��Ė����́w���@�䒠�x�ɂ͎��̂悤�ɍڂ����Ă���B
�@�@�@��t���lj�����������S���Ò��쑽���J
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�����@������
�@��A�{���@�@�@�߉ޔ@���@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��Z�ԁ@���s�l�Ԕ��@�@�@�@�@��A�����ؐ��@��S�@�@���L�n����@�@�@�@�@��A�Z�E�@�@�@���c�q�s
�@��A�d�k�l���@�E�l�@�@�@�@�@�ȏ�
�@���̂悤�ɗR���s�ڂƂȂ��Ă��邪�w�N���s���x�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�@��A���\�\��N�K(��Z���)�Z���\�l���ӌ܃c�����j�����������ďo(�}�})�X�@���N�������A
�@�@��A�����Z�N�Ȗ�(�ꔪ�Z��)�\���\��A�����q�a�C�������J�ዟ�{
�@�@��A���|�Y(�����L���Ȃ�)�@�@�@�@�@�@��A��i�Y���E���]�@�@�@�@�@�@��A���ā@���āY��U��
�@�@��A�łȂ炵�@��c�@�@�@�@�@�@�]�ːM�Ҏl�J���@�@�@�@�@�@��A���ׁ̍@�@�O��
�@�E�ҁ@�Z����@�b���t�V��
�@
�Q�w�����V�C�����@������ؗ������V�ԁ@�ɗ���i�O�m�E�]�l�@�@���C�s�����d�т既�@�䓖���@�֑��C���t�����ǖ@���m���[�@�c���F��ߑ֑���O����
�O��l�������C������O����
��~�q���V�������m���
�E�ҍ������啧�t����
��(��)�V�Z�m�b���t�V���W�V�o(�ȉ���)
�@
�@���̂悤�ɂ��ĕ����Z�N�q�a�̏C���Ə����̊J�ዟ�{���s���A�Â��ēV�ۋ�N(1838)��O�̐Βi�������A�V�ۏ\�O�N(1842)�ɂ͖���������ꂽ�B
�@�����ĉÉi���N(1854)�l������͎����̑ݕt�����n�߂�ꂽ�B
���̐��x�͕ʖ��u�������v�Ƃ��Ă�A���@�ێ��������^�p���Ĉ��̌����l�B�ɔN���ꊄ���炢�őݕt���A���̗��q�������Ď��̈ێ���ɏ[�Ă���@�ŁA�e���@�ōL���s��ꂽ�B
���߂͓����̌�����ړI�Ƃ��čs��ꂽ���߂Ɂu�������v�Ɩ��t����ꂽ�炵�����A����^�c�ێ������ƂȂ�A���������ɂ���Ă͖{���������肷�邱�Ƃ��������炵���B
�������ł́A�����̘Z���͐V�܉E�q��c�ꂪ��i���A�ݕt���͑�����Z���ɕ��ϊ��ő݂����悤�ł���B
�@���ݓ����Ղɂ́A�̓����Â�����̂Ƃ��Ă͒��̉̌��Ɋ|�����Ă��锼��������邾���ŁA���̍����͎��̂Ƃ���ł���B
���u�v����ꖜ���@�E�V�u�ӎ�ҁ@���������{���V�ʁX�u���V�����앧�ʕ����e�����F禱
�@�@���V���B����S��c�������̑�
�@�@�@�������V(�ꎵ�O��)�\���\�O��
�@�@�@�@�@�����R�������@�\���[
�@�א�c���e�������{��@�����d�Y���q
�@�א�c���e���{��@���v�ԋg���q
�@�ו��o���@�������{��@��ؐV���Y
�@�@�@�@�@�@�@�@�y�U�ߒ�
�@�ז@���@�@�����@�{��
�@�@�@�@�@�@���䑺�@����(�g)���@�Ε����@�s�Y���q�@���Y���q��@�����q�@���I�R���q�@��Ύ��@�����@�����݂��@�����Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�Γc�����O�Y�@�ԋ{��
�@�@�@�@�@�@�]�ː_�c�Z�����a����
�얳����@���@�얳���@�@�،o�@�얳�߉ޕ����@�S�q��_�@�@�؎��O�\�Ԑ_�@�\���E��
2023/12/01�B�e�F
�@���݁A���Ղɂ́u���Ò��������p�{�݁v�������A���̖T��Ɏ�̐Γ����c��݂̂ł���B
���얭������
�@���얭�����ՂP�@�@�@�@�@�@���얭�����ՂQ�F�����́u���Ò��������p�{�݁v
�@�������ՐΓ��ނP�@�@�@�@�@�������ՐΓ��ނQ�@�@�@�@�@�������ՐΓ��ނR
�@�������Ց�ړ��E�����F�얳���@�@�،o
�@�@���ʁF�V���ו����y���J/�܍��L���ݖ����y
�@�@���ʁF��V�l�C�F�A���@/���@�ݔN�A�闬�z�@�ƍ��ށB
�@�������Ց�ړ��E�����F�@�V�ۏ\�O�i1842�j�p�ЎO��/�����R�\�㐢�@����(�ԉ�)/�{���@���v�ԏ@�O�@�y��������
�@���ƕ擃�E�d���F�������猩�đ��Ƃ̕擃�Q��ƕ�⸈c�����d�˂����̂�
�@�����@���@�����擃�F�����͓������A�����ʂ��ǂݎ��Ȃ�
�@�m���s���擃�P�F�E�E�E��灵��A�����炭���Ƃł��낤�@�@�@�@�@�m���s���擃�Q�F���@����灵��A�����炭���Ƃł��낤
�@�m���s���擃�R
��������쑽����̐ݗ��@�@�u���Ò��j�@�����v652�`
�@���̂悤�ɁA��F�ꓰ�����c���ꂽ���������A������N�ɕs��s�{�h�̋����������ƁA�}������Ă��������������Ă��h�k�͈�Ăɕs��s�{�h�֑���A���͌���݂邤���ɂ��т�Ă������B
����͉��@�Ƃ����������ɔ�߂��Ă������̂������I�ɔ��U�����ƌ���ׂ��ł��낤�B
�@�s��s�{�h�̗����ɂ�Ēh�Ƃ��������������̂��т���͂Ђǂ��A�吳�P�O�N�Ɋǒ���m���͍����C���ɒ�o�����e�\�����ɂ́A�u�{���\�A�ɗ���A�����A�꓃�A�����l��F�A�@�c��t�v�Ƃ��āA���@�̖ʖڂ͕ۂ��Ă͂�����̂́A�Z�E�͓����茰�����Z�E���c�q�s�̌����ƂȂ�A�h�Ƃ́A��t���v�ԏ@���A�_����c�Ɏ��Y�A�����{�����Y�̎O���шꔪ���݂̂ƂȂ����B
�Ԃ��Ȃ����̒h�Ƃ�����āA�o�L��ɖ����Ƃǂ߂邾���̎��ƂȂ�A���a�R�R�N�ɂ͌�������蕥���ĐV���������ق����Ă�ꂽ�B
�@����A�{���̕s��s�{�h�ɗ��A�薭�������痣�ꂽ�l�X�́A�M�̋���ǂ���Ƃ��Ă̏�������߂ɁA�ߋ��̐l�B�ɌĂъ|���āA������Q�T�ˁA����P�X�ˁA�匴�T�ˁA�тU�ˁA��R�Q�ˁA�D���P�ˁA�����Q�ˌv�U�O�˂��쑽����Ɩ��t�����ړ��𓌑䎚�����O997�Ԓn�������邱�ƂƂ��A�����P�W�N�l���\�����ɓ�����l�����ق��ď㓏�����s�����B
���Q�O�N�\���ɕA���Q�S�N�\�ɐH�������Ă��A�{���̑c�t�����͓����̐M�k������A���Q�U�N�ɓ��w�{��d�����������B
�@�����������W�N�ȗ������Ȃǂ̍ċ��o�肩��A���X�N�l���\���������ċ���������A�e�n�ŐM�k�̐����������ɂӂ����ł����Ȃ��ŁA���R�O�N���߂������납��A���Ŕj�̌��J�҂ł���@������ƕ⍲�������̊ԂɁA�@���ɂ��Ă̌����̑��Ⴊ�ڗ��悤�ɂȂ����B
�����́A�×��s��s�{�M�k�͓��@�̎҈ȊO�Ƃ͌���炸�A�܂��ɐ��_�{�Ȃǂ̂��P���𐿂��鎖���������肷�邪�A���̂悤�Ȃ��Ƃ����߁A�����Ƒ��Ƃ̌𗬂����R�ɂ��ׂ��ł���Ə������B
����ɑ��ē����́A�Ö@�쎝�����s��s�{�h�̖ʖڂł���Ƃ��Č݂��ɏ��炸�A�Η���[�߂Ă������̂ł���B
�����āA���ɂ͓������g��ނ��Ƃ������ԂƂȂ�A���̔g��͊쑽����̐M�ҊԂɂ��y�B
�@��������������E�����̗��t���a�����āu�O�������v�̖{���ɗ��҂�ׂ����Ƃ���a�Z�g�ƁA����ސg���Č��ʓI�ɂ͕s��s�{�h���痣�ꂽ�������x������M�k������ɏo���肳���鎖��掖@�ł���Ƃ���g�Ƃ̊Ԃœ������N�������B
�����ē��R�S�N�\���\����ɘa�Z�g�̑匴�T�ˁA����T�ˁA������V�ˁA�тQ�˂̂P�X�˂͊쑽����𗣂�ē����o���̒����h�ƂƂȂ�B
�ȗ����N�ԐM�̑����ɑË��͂Ȃ��������A�吳�R�N�Ɏ����ė��҂ɘa�����������A�a�������ɂ����ē���Ɍ��Ă��Ă����쑽�����́A���j�I�g�����ʂ������Ƃ��Ď���邱�ƂɂȂ������A�����̈ꕔ�͌��ݒn�̎��_�̏�949�Ԓn�ֈڒz����ė��h�ɑ������Ă���B
�@�@�@�����O�@�̌n�����s��s�{�h�̕��h�������ȍ~�̕��h�������h�@�Q��
�@���̂Ƃ��̘a����������e�͂��悻���̂Ƃ���ł���B
�@�@�@�a������
�@����S���Ò��쑽���䎚�������S��E���Ԓn�m��n�O��M�y���Ԓn�j�݃���ړ��듏���@�����O�\���N�㌎�����o���s�a�m�׃����L�ێ��V���z�X�����\�n�U���V���@����o�����c�m�㕪�z���@������V�a���X�������m�@�V
�@��A��n�O�M����J�����Y�O��\�O���j���`�ύX�X����
�@��A��ړ��듏��������E�~��@������E�~�����p��g�V�e�c���E�~������c�Ɏ��Y�O�O�\�㖼�j�n�X��
�@��A���E�~���n���ۗ��l��J�����Y�a�j�ԃX��
�@�@�@�A�V�o���������܉~���c�o�X��
�@��A�ȑO�����o���j�e�a�����n�ۊǓ��i�V�݃����i�n�����j�e�ًc���V��
�@��A�����O�\�ܔN�㌎��\�Z���o�����c�m����ړ������v�V�@���ߎ�ב֒u�L��_��n�@���������^���x�L��
�@�E�a��������ʃ��쐬�V�@�o����ʈ������V�ًc�i�N������
�@�@�@�@�吳�O�N�����\�Z��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a���ψ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��J�����Y�@��@�@�@�@�����@���g�@��@�@�@�������E�q��@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���@�����@��@�@�@�@�@���{�@�Ǐ��@��@�@�@���{�⑾�Y�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؓ��h�O�Y�@��@�@�@�@�����@���s�@��@�@�@����c�Ɏ��Y�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��؊�O�Y�@��@�@�@�@��J����i�@��
2023/12/01�B�e�F
��������쑽���
�@����쑽����P�@�@�@�@�@����쑽����Q�F�s��s�{�h���싳��Ƃ̊Ŕ��f����B
�@����쑽������]�P�F�ʐ^������ԏ�̊��̉Ɖ�������@�@�@�@�@����쑽������]�Q
��������E�H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�@�u���Ò��j�@�����v655�`
�@���@�Ƃ̌����������Ƃ������A���@�����т����r������قnj��������`�����s��s�{�h�M�̏W�������ɁA���Ɣ�ׂĖ앧��{�̐��͂������ď��Ȃ��B
�@�@�����c�_�A�n���ω��A��ׁA�V�_�ЂȂǂ��邪�A�쑽����̌����̈ꕔ���ڌ����ꂽ���ɂ͙��V�Ђ�����B
�ٓV�ЁF
�@���J�m����l���Ԃɂ���A���̎Ђ��炢�����̗����𖾂炩�ɂ��Ă�����̂͏��Ȃ��B�w�N���s���x�̈�߂Ɏ��̂悤�ɋL����Ă���B
�u�y�ЕٓV�{�V�����V�V�n�A��(����)�\�Z�N��(1731)�Z������`(�e)�㌎�\��(��)���H�Ȃ����Ɍ�(�\��)�\�ܓ��j�������A�X�B
���ߍΔԖ�^�y���q�@���ܘY�A��H�n���Ñ��V�V�E�q��(�j)�V�e���䕽���Y�A�ؔғ��������q�A�ύ׃n���D�j�L�X�B
�ʃj�^��o���\�����u��J��d��D��[�Җ�B
�E�Вn�n���ܘY�@�P���q�@�^�y���q���R�Вn�j��i�V�A�Вn�̕������A�X�v�Ƃ���A�����E�[���̋���ɂ́u����������S�����쑺����ٍ˓V����@���ۏ\�Z�h��N�����g���@�쏬�������v�ƍ��܂�Ă��āA�����Ȃǂɂ��č��ق͂�����̂̑n�n�N�͕������Ă���B
�����Ă��̂���ٍ͕˓V�����̒���ł������悤�ł���B
�܂��A���̎���Ɍ��Ă��Ďc���Ă�����̂͑O�L�̋[��삾���ŁA�ؑ������͏��a�l�\�Z�N�̎R����ɂ���Ēׂ���A���݂̓R���N���[�g����̂��̂ɂȂ��Ă���B
2023/12/01�B�e�F
�@���V�Ђ͍���쑽����ɗאڂ��Ă���B
�@�@���왞�V�ЂP�@�@�@�@�@���왞�V�ЂQ
������(�Ƃ�����)
�������얞�����Ձ@�@�u���Ò��j�@�����v614�`
�@���ݓ��W���Ɏ��@�͂Ȃ��B
�ƁX�̏@�|�ɂ͓��@�@�Ɛ^���@�Ƃ������āA������䖭�����A���Ö������A�џC(�ŎR��)�@�����ɕ�����Ă���B
�@�����Z�N(1666)�̖��ɂ́A�u�ՏƉ@���ݎO������v�ƋL����Ă��āA�����l�N�{�J�����ւ̓͏��ɂ��A�u�V�`�^���@�ՏƉ@�@������N�v�n�Z�E�l�v�Ƃ���B����ɂ��̌�̎Ў��䒠�ɂ́A���Ɍ�����悤�Ɂu�������v�̖����ڂ����Ă���B
�@���������͐^���@�A�@������k�ł���B
����
������̈�ՁE����
�E������Q
�@���a�R�R�N�A���Í��Z�Љ�ȃN���u�̒����ɂ��A�n���ɑO����~���Q�A�����R�A�~���Q�U�A�v�R�P��̌Õ����Q���Ȃ��A�Q��̑O����~���͂��ꂼ�꒷��40���A����3.2���B����20���A����2���ł���B�~���Q�U��A���łɔ��Ƃ��ĊJ������Ă��邽�ߌv������̂��̂��X��A���͕����Ƃ��ɒ��a20���ȉ��A�����͂����ނ˂Q���ȉ��ŁA�قƂ�ǂ͌��`���Ƃǂ߂Ă��Ȃ��B
�@�i�����̋��Ղ�]�ڂ��A�c�]�͏ȗ��j
�E���䖭������
�@�������킫��o�����Ƃ���ɖ������Ղ�����B�����������E�a�����̖����ŁA�ʏ́u��̎��v�ƌĂ�Ă����B
�����R�O�N�A�{�R�������閭�����ƍ��������B
2023/12/01�B�e�F
�@���䖭�������F�������č���̊R�オ���Ձi���݂͖��Ɓj�Ǝv������A���̍��ՂɂȂ��Ǝv����B
�E���䐳���@��
�@�������@�ɂ���B�����ɂ��Đ����@�Ƃ������@�����������Ƃ��玚���ƂȂ����B
�u�����@�ˁv�ƌĂꂽ����30���̑傫�Ȓ˂��������B���a�R�R�N���뒲�����A��ɔ��ɑ������Ēn�斯�ɕ��������B
�E��������f�H��
�@���`�ɁA�W���n����ɓ��@�@�s��s�{�h�m�������A���h�ɑ��開�{�̒e���ɍR���A����f�H�������Ƃ����f�H�Ղ�����Ƃ����邪�A�m�F�ł��Ȃ������B�Ȃ��A������N(1669)�n粎����q��Ɏ��^������ڙ�䶗�������B
2023/12/27�lj��F��������f�H��
���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA�������s��A���a�T�Q�N�@���
���\�̖@��ł͑����̑m�������߂ƂȂ�B
�����s��s�{�h�ł��������A���V�y�ѐg������̒e���ɑς�����Ȃ����������̎��@���A��R�����A�s��s�{�h���ߓc�h����h�ƌ�ނ�������B
������������h�͎��X�ƋA����`�𔗂肭��B
�������Ɏ���A�s��s�{�h�͍Ō�̔����Ƃ��Ď�h�ɓ]���邱�Ƃ����ۂ���B���͂͂����̑m�������X�Ɠ��ɗ��߂Ƃ���B
�����ł́A�����̒e���ɑ��A�����̍R�c�f�H���������B
���̒��̑m���Ƃ��āA�b���@�����E�{�{�i�v�j�@���{������B
�ނ�͎��̂悤�ɓ`������B
�@�b���@�����F���䖭���������ɂĂT���P�����f�H�V���R���f�H���A���\�S�N�V���R����
�@�{�v�@���{�F���䖭���������ɂĂT���P�����f�H�V���S���f�H���A���\�S�N�V���S����
�@�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�̈ɓ��哇�s��z���m�̈ꗗ��
�@�����@�����G���\11.10(7).3��A��������h�A�]�ˏO�A�����ܑ��v�g���������q�n���ɋ��Z�@�Ƃ���B
�@�u�[�����@��j�v�ł�
�@�����@�����G���\11.7.23��A���\�@��A�哇���߁A���䑺�@�Ƃ���B
����ɂ���A���i���j���@�����͐���o�g�œ����Ɍq����s��m�ł������̂ł��낤�B
�@����A��q�̂悤�Ɂu���Ò��j�v�ł́u����f�H�������Ƃ����f�H�Ղ�����Ƃ����邪�A�m�F�ł��Ȃ������B�v�Ɖ]�����A
�u���|�ʐ^�łÂ���@�@�s��s�{�h��R�̗��j�|�v�ɂ́u�������~�Ձv�Ƃ��ĕ��̎ʐ^���f�ڂ����B
�@����������~���F�ʐ^�������������͊m�F�ł��Ȃ��B
2024/02/26�lj��F
���u�[�����@��j�v�@���
�@���䑺�ɂ́A�����͕̂s���Ȃ���s��s�{�h�̈����m����B
���䑺�̈��i�����s���A���䖭�����n�H�j
�@���F
�@�^�P�@���Z�F����13.5.17��A���䑺
�@�s�w�@���x�F��i7.11.4��A�����������i�s���j
������E�@���^�_�ЁE���@�@�@�u���Ò��j�@�����v763�`
�@�����܂ő����ɖ������E������������A����������@�@���@�ŁA�Z���͂��Ƃ��Ƃ����@�̐M�҂ł���B
���Ö������͂��Ɛ��䌴����˂̂�����ɂ������Ƃ����B
�@���ďZ���͐^���@��M���Ă������A�����l�N(1359)���R�@�،o���̎O�����S�����@�ؓ����{�ɂ��āA�@�؍O���̕S�����@�����A�ߋ��̒j�������Ƃ��Ƃ����@�����Ƃ̐�������(����R���N)�B
�@�@�@�����S�S�����@�ˁE�E�E���~��l�˂̒������ɂ���B
�@�܂������ɎR������(�O�֑�_)���������ĎY�y�_�Ƃ��A�Â�����̖��ԐM�Ƃ��ē��c�_�E�M�\�E�n���ω��Ȃǂ��J��A���҂��A���҂��A���@�y�Ȃǂ�����B
�����䖭��R�������i�݂傤���j�@�@�u���Ò��j�@�����v765�`
�@�����J358�Ԓn�ɂ���A�꓃�����l�m���{�������u������@�@�̎��@�ł���B
���`�ɍO����(1278�`87)��݉@�����̊J��Ƃ���B
�@�{���̎��͂ɁA�߉ނ̓�e�m�Ƃ����鎂�q�ɏ��������A���ۂɂ܂����镁������F�ƁA�s���E���������B�����E�L�ځE�����E�����̎l�V����z���A�܂��{�����d�ɐ������A�E�d�ɋS�q��_�Ə\���������J���Ă���B
�@�܂���̂̑c�t�������邪�A�ʒd�̑��ɂ́u�J�c�������@����e�t���g���@����č��c���F�v�̖�������B�c�t���̂킫�ɊJ�c�����A������e�̑�������B����͕����\�l�N(1817)�c�t���[�����C�̍ۂɍ����̂ł���B
�@�Ȃ��A�����̎R���u����R�v�����Ö������Ɠ����ł���A����ȊW������悤�Ɏv����B
���Ö������������̊J�R�ł���A�������B�����Ƃ��đn�������Ƃ��납��A����R�����̂����Ƃ̐�������B
�@��O�ɓV�����N(1781)�㌎�����̏@�c�ܕS������A������n�ɖ��a��N(1772)�܌������̊J�R�����̎l�S�����肪����B
�����k����ɋS�q��_�K������B
�@�����́w�Ў����ג��x�ł́@
�@�@�@�@��t���lj�����������S���Ò����䎚���J
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@������
�@�@��A�{���@�@�@�߉ޕ��@�@�@�@�@�@�@��A�R���@�@�@�s��
�@�@��A���F�Ԑ��@�Ԍ��Z�ԎO�ځ@���s�܊ԁ@�@�@�@��A�����ؐ��@��S�Q�E�l�@���L�n����
�@�@��A�Z�E�@�@�@���������@�@�@�@�@��A�h�k�l���@��S��E���l
�@�Ƃ���B
���u���@�@�s��s�{�h�ǎj�N�\�v�@�ɂ͎��̋L������B
�~��@���G�i���j�@�@p.112
�@�O��Œf�H����B痁i��E��j���B�������{���o���܂��͐��䖭�����o���Ƃ������B�|���悷��B�������Ð��܂�A�O����m�B
2023/12/01�B�e�F
�@�������@�c�ܕS������P�G���ʁ@�@�@�@�@�������@�c�ܕS������Q�F���ʁA���͏�ɋL��
�@�������R���@�@�@�@�@�������{���@�@�@�@�@�������ɗ�
�@���������揊�@�@�@�@�@�������J�R������
�@�������c�Q�L�O��P�@�@�@�@�@�������c�Q�L�O��Q�F�g���E���ʎR�E�����Ȃǂ̒c�Q�����{����Ă���B
�@�������S�q��_�@�@�@�@�@�������S�q��_����
�@���āE����擃�F�S�q��_�����ɂ���B
�@����@���đ哿�i���������K�N�\�\����j�A���q�@����哿�i���E�E�E�E���O�\���j�Ƃ��邪�A���哿�͖��������ł͂Ȃ��A�s���ł���B�A���u����v�́u��v�͈���������̉\������B
������E�H�T�̏��K�E�{�Ȃǁ@�@�u���Ò��j�@�����v767�`
��ڔ�
�@�����������ɓ��̉������肪���邪�A���ł��Ė��͓ǂ߂Ȃ��B
�܂������k��̋�����n�ɓ��̉�������ڔ肪����B
���͍���66�����A��59�����Łu�ו���O�\�O�N����@�������N(1374)�������Z���v�B
�������͍���78�����A��37c���Łu�E�ז������������S����@�i��(��)�Z�N�b��(1434)�������v�Ƃ���A�Ƃ��ɁA�u��t���j���E���Ε��сv�ɍڂ����Ă���B
�@�i���c�]�̂��̂͏ȗ��j
----------------------------------------------------------------------------------------------------
���������q������
2019/09/19�lj��F
���u���@�@���@��Ӂv�r��{�厛�A���a�T�U�N�@���
�@�ؗюR�ƍ����A���s�퓿�����A���t�@���B
�J�R���t�{�@����A�J��͐����@�����A�J��h�z�͍��q��叼���a����v�B
�������J��������������̈ꎛ�Ƃ����B
�V���S�N�i1576�j���肪��������卑����V���������A���̕�Ƃ��đ�葺�ɍČ��A�ؗюR�������Ə̂���B
�����N���ɓ��������q��叼���a���Ƃ��̎������@�a�ɂ��A���q�{���̌��ݒn�ֈړ]�E�ċ����A�������ɉ��߂�B
�P���������O�Y�喾���P�W���֓]�o�B
�@�������͕s��s�{�m�A�����@��̍��A�喾���Z�E�ł������Ǝv������A�����Ƃ����B
�����o�Ŋ����ؗюR���ɁB�i�ؗюR���ɂ̑n���������邢�͂ǂ̑�Ȃ̂����̌��y�͂Ȃ��A�s���j
�@�����q�������ؗюR���ɂ̑����㉚��F�Z��{�����̎����ɏo�Ă���B
2019/09/19�lj��F
���u�s��s�{�h�}���̗��j�v���t�L�A���U�o�ŁA���a�T�P�N�i1976�j�@���
�����̂���A���q�̏������i�����������j�ɂ͉،��@���q�i���O���얭�����P�O���j�������B
�@���،��@���q�����O���얭�����P�O���A��ɑ��͈ߊ}�喾���P�V���i�����j�Ƃ����B
�@�ߊ}�喾�����珜���͓��q�E�����Ȃǂ��s��s�{�m�̌̂ł��낤�B
�@�Ȃ��A�u�s��s�{�h�}���̗��j�v�ł́u�������ɓ��q�������v�Ƃ��邪�A�u���@�@���@��Ӂv�Ɍf�ڂ̏��������Z�E���ɁA
�@���q�̖��O�͂Ȃ��B�i�ꎞ�g�������A�������ꂽ���ł��낤�B�j
2023/08/29�lj��F
�@���P�@�����͂Q���A���������@���_�͂R���i���_���������ɂ���j
2023/10/07�lj��F
�����R���@���̃y�[�W�@���
�@�����������͎ؓ������@���P�P���b�Ɖ@���\�i���n�̐l�ŁA���ۓ�\�N/1735�@��j�ł���B
�A���A�u���@�@���@��Ӂv�ł͌b�Ɖ@���\�͑�V���A���ۂQ�O�N�T���Q�S����Ƃ���B
2023/12/10�lj��F
���u�[�����@��j�v���쎡�ǁA�������s��A���a�T�Q�N�@���
�@�V���S�N�i1576�j��^���t�{�@���肪����S����卑����V�����������Ė��^����n������B
����T�N�i1677�j���q�ˎ叼���a����v�̓����E�����@��ߓ��t���A���^�������q�Ɉڂ��A�������Ɖ��̂��A�ċ�����B
�J��͐����@�����ŁA�����͎O�Y�喾���P�W���ł���B
�����̖@��O��A�����E���u�E���q�̂R�t�͏������i�����@��ߓ��t���j�ə�䶗��{�������^���Ă���B�����͊����U�N�K���Q�W���A���u�������U�N�Љāi���āj�A���q�͊����V�N�P�P���V���ł���B
�����̑y�Ō�A�����̕s��s�{�h�͑傫�ȑŌ����邪�A���������̑y�ł͎��́E�n�q�̍Č�t�ł���������A���́E�n�q�̎��������Ȃ������͂��̒e���̑Ō��ڎ邱�Ƃ͂Ȃ������B
�������͔ˎ叼����v�̊O��ɂ��A�h�Ƃ������������̋`�����Ə�����Ă����B����́A�������͕s��s�{�̒��S�Ƃ��đ䓪���邱�ƂɂȂ�B
�����@�����͋ʑ��k�т�j�p����A�����V�N�T���Q�V���������Ŏ₷�B�y�����V�N�T���Q�V����A�ʑ��k�є��A���~�R�A59�z
�Q���͎��P�@�����i��t�k�ъJ�c�j���p���B
----------------------------------------------------------------------------------------------------
����������{�y��
�@������{�y��
���������R�@�،o��
�@�����R�@�،o��
���������؎R���s��
���݂͒P���Ǝv������A�ߐ������R�@�،o�����B
�Z�p��d����L����B
�@���@�������؎R���s��
�������^�ԍO�@��
�@���^�ԍO�@��
���������@�@���F�s��s��쒬
�@�J�R�͓��@��l�̑�h�z�]�J���M�B��ɑ]�J���M�͏o�Ƃ��A���@��l���@�@���X�̖@������������B
�Ȃ��A���M�̎q�����͖�C�������̊J��h�z�ł���B
�����R�N�i1277�j�A�������̒n�i���s��s�j�Ɉꎛ���J���A���g�̏o���Ɩ@������]�J�R�@�@���ƍ�����B
�Ȃ������̖@��ŁA�ɗ\�g�c�ɒǕ��ƂȂ��������͖@�@���P�W���B
�@�����@�@�������͕s��s�{�h�i�����̖@��j��Z��l����O�����B���̎���́��]�ːR��暎��������Q�ƁB
�@�������ɂ��Ắu���O�@�̌n���v���ɂ���A�u�����v�̃��[�h�Ō�����ctl
+ F������B
����{�y�����B
���݁A�[�s�@�A���s�@�̎���������B
���㑍�̏���
���㑍�Ό�������
�@���Ό�������
���㑍�h���h�R��
�@���h���h�R��
�����Y������
�����F������{�^��
�����[�̏���
�����[�����a����
�@�������a����/���e�t���@��
�����[�{�s��
�O�ԓ�w����L����B
2016/04/06�쐬�F2024/05/01�X�V�F�z�[���y�[�W�A���{�̓��k�A���@��l�̐��n8
|