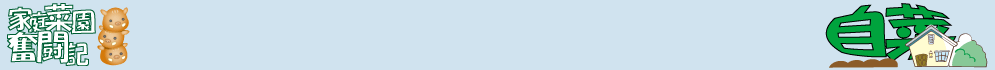
![]()
![]()
![]()

育苗箱で、種からの栽培に挑戦。狭いけれど4株を栽培します。
この胡瓜は地面を這って栽培するのですが、支柱を立てて栽培してみました。
品種:地這胡瓜(アタリア) 生産地:***(記録忘れ)

育苗箱で種まき。全部で23粒蒔く。
用意する物:
腐葉土、育苗箱、炭、草木灰、ふるい、新聞紙、上呂
バーク堆肥入り培養土を種の層に使いました。
この腐葉土は細かい土状がないので、培養土を兼用しました。
芽が出るまで育苗箱の上を新聞紙で覆って乾燥を防いでおき、水は与えません。

1つ、小さな芽が出てきました。
他はまだ出ないので新聞紙を覆ったままにしておきます。

やっとポットに移植できました。
今年は、春の陽気がまともではありませんでした。寒暖の差が4月末まで続きました。しかもその差が激しい!そのせいか、苗が成長しません。
種を植えてから1ヶ月も経ってしまいました。

苦土石灰150gを散布し、よくすき込む。
この時もまだ苗は育っていません。半月ほど遅れそうかな?


バーク堆肥:1kg
鶏ふん :300g
を、キュウリは根が浅いので全面によくすき込む。
こんな感じで苗のポットを並べてみました。35cmはちょっと間隔が狭いかな?
(40cmは欲しかった。)

左のように、有機栽培で育てた苗は、根が良く張っています。
びっしりとポット全体を覆っています。
おそらく中も根で一杯でしょう。でも定植するときは土をくずさず根を傷めないように埋めてくださいね。

拡大してみました。![]()
細かな綿毛のような根毛がたくさん出ています。
根毛は微生物が出した栄養分を吸い上げる働きがあるので、苗が元気な証拠です。
配置は少し変更して「ひし形」にしました。
四角だと縦が35cmなので40cmにするための苦肉の策です。

![]()
空梅雨や、晴れ続きだと様子を見て水やりします。
苗の周りに、バーク堆肥(2kg)を敷き詰め、その上に腐葉土を蒔き、培養土でうっすらと表面を覆っておきました。
支柱を苗の外側に4本、補強のため左右に2本と渡しを1本で組みました。


![]()
矢印の苗の拡大と蕾の番号
![]() 下から5番目にあった蕾で、雌花になるのでしょうか。
下から5番目にあった蕾で、雌花になるのでしょうか。


![]()
横から見た様子

![]()
ツルも出ています。
![]()
下から3番目にあった蕾で、雄花でしょう。
観察してみましょう。


ほっとくと、葉が無くなってしまいそうです。
ウリハムシは、昼間は敏感ですが、夕方には鈍感になるので出来る限り駆除します。

![]()
ウリハムシ
![]()
半日で右のような無惨な姿になってしまいました。


この日、1番花が咲きました。
喜んでいると、
夕方、ゾッとするような事件がおこりました。

そう、もっと怖いと思ったのは、ダンゴムシが根本をかじっているのを目撃しました。
根幹を齧られると対処のしようがありません。
ダンゴムシはそこら中にわんさかいます。
直ぐ、周りの腐葉土をどかし、日当たりよくし、土を固めてダンゴムシが潜り込めないようにしておきました。
応急対策です。
予想外でしたね!

1番花が大きくならず、変色してきました。
原因がわからないので、切り取ってしまいました。
また、ウリハムシとダンゴムシが花をかじってしまい、防ぎきれません。
翌日、葉の裏に隠れて立派に育っていましたが、もう1個は、蚊取り線香みたいに丸まっています。

![]()
左のキュウリは
この日で長さ約10cm
![]()
右の「蚊取り線香」は
直径?6cmでした。

有名なうどんこ病で、下の葉から上に向かって移っていきます。
取っても取ってもなくなりません。

一般的にチッ素分が多く、カリ成分が少ないと発生しやすいというので、草木灰を散布しておきました。
プランターのパセリにも発生!

![]() 草木灰
草木灰
初めてのキュウリの栽培で、タネから育てたので愛着があります。
タネ蒔きから、ちょうど3ヶ月です。長かったなあ。
左のキュウリは長さ、ちょうど20cmでした。丸くなっているのは、ちょっと大きくなりすぎた感じです。

関係ないですが、切り取った所から滴がポタポタと出てきたので記念に撮影しました。
周りの景色がきれいに写ってます。![]()


アブラムシは何所にでも現れるやっかいな害虫です。
葉の裏で見つけた大群です。
一枚だけだったので切り取って捨てました。他の葉には無いようです。

約2mの高さになったので4株のキュウリの先端をすべて切り取ります。


4株分のキュウリ畑で、高さは1m60cmです。
うどんこ病になった葉を次から次へと取っていった為、下の葉は殆どなくなり風通しが良くなっています。
尚、下から30cmまでの葉は取った方が良いそうです。
でも、なかなかうどんこ病が治まりません。ひどくはないのですが、ポツポツ発生しています。
根気よくニンニク木酢液を散布していますが、梅雨の真っ最中で散布しても雨に流されてしまいます。降らない時間を見計らって散布するしかありません。
4株分ですが、かなりの収穫がありました。次から次へとなり、食べきれないほどでした。うどんこ病は草木灰の殺虫剤でなんとか治まっているようです。

完全ではありませんが、うどんこ病には草木灰を水に溶かした液を直接葉に散布すると効き目があります。
パセリもこれで直りました。
作り方はこちら。
7月の終わり頃から、みずみずしさが無くなってきました。
この頃にやけにウリハムシが増えてきたように思えます。

ひとつ試しにキュウリをそのままにしておき、種を観察するため左のように30cm位になったら切り取っておいてみましょう。

切って中を見てみましたが、あまり良いできではありませんでした。
うーん、最初はこんなもんかな?

今年のキュウリ栽培記録はこれでおしまいです。
問題:種は「地這」というところがそもそも問題かな。
ウリハムシやウドンコ病などは多少ありましたがそれほどの被害はありませんでした。ただ、4株では少し多すぎたので2株ぐらいのほうがちょうどいいかもしれません。
![]()
![]() 家庭菜園奮闘記・栽培記録
家庭菜園奮闘記・栽培記録
