THE SEVENTH EMIGRANT |
|||
| 沖縄を考える 沖縄で考える |
| Toppage | Critic | 図書室 | リンク | Emigrant |
THE SEVENTH EMIGRANT |
|||
| 沖縄を考える 沖縄で考える |
| 「沖縄処分」に反対する「独立琉球」という想像力 | ||
| 仲里 効 | ||
| ソウル大学でのプロジェクト 私は今、この原稿を韓国のソウルで書いている。正確にいえばソウル大学で11月17日から20日までの4日間行われている「継続する東アジアの戦争と戦後-沖縄戦、済州道4・3事件、朝鮮戦争」のプロジェクトの一報告者として、また他の報告の聞き手として居合わせたことで、そこでの沖縄と韓国・済州島との応答の熱気に触発されながら、言葉に向っている、ということになる。 こう書き出さざるを得なかったのは、このプロジェクトが10月29日に日米政府間で合意された「在日米軍再編」が東アジアに及ぼすであろう軍事・政治的な影響と逆向きにではあれ交差していると思えるからである。いや、それどころか米軍の戦略的な布置に一体化する形で自衛隊の拡大・強化を目指した「再編」なるものがアジア太平洋の緊張と敵対を仮想し、それをテコにして東アジアの政治・軍事地図を根本から変えるほどの規模と内容に注目するとき、あるいは「日米同盟・未来のための変革と再編」という名の「再編」が描く「未来」がいかなる倒錯的なものなのかを考え合わせるとき、その倒錯へのある意味では国家を介在させない「抵抗の想像力」を模索し、創り上げるささやかだが貴重な試みのひとつでもあると思えたからである。たとえそれがいくつもの迂回の道をたどらなければならないにしてもである。 ソウル大学の鄭根埴は「問題設定」のなかで、このプロジェクトは東アジアの総合的な討論というよりは、「新たな問題の枠組みを形成していくためのひとつの出発点あるいは飛び石としての意味合いが大きい」といっていた。たしかにこれは「出発点」にすぎない。だが「飛び石」という言葉が付与されるとき、学術上のはじまりの表徴という意味を超えて、近・現代の東アジアの人々が植民地主義と冷戦体制によって引き裂かれた歴史的経験がにわかに浮上している。そしてそれは「東アジアでの帝国/植民地体制から冷戦/分断体制への移行に横たわっている戦争の経験を、周辺あるいはマイノリティの立場からあらためて省察しなおすとき、より明白な意味を表すだろう」としたことでいっそう核心を顕すことになる。戦争の記憶と経験を、周縁の立場から省察する、そのことによって召還される存在のカタチ、それはまぎれもない「飛び石」としかいいようがないのである。「飛び石」とはいわば、「帝国/植民地体制」と「冷戦/分断体制」によって引き裂かれた歴史的身体の空間化された名なのだ、といえよう。 こうした「飛び石」状の歴史的身体はしかし、他なるものの発見と相互交渉がないかぎり、それ自体の存在においては孤立の別名に甘んじるしかないだろう。それゆえに出会いと交渉、接触と分有がいっそう切実になってくる。「長期間にわたって持続した冷戦体制では、各国家と地域が孤立、細分化(断片化)されながら、自己中心的な視角にとどまっていた。1990年代後半からこのような細分化(断片化)した様相はある程度解消しはじめたが、だからといって過去の遺産が克服されたわけではない。そのひとつの例として、米軍基地問題を媒介として沖縄と韓国では1997年から下からの連帯が形成されはじめたが、沖縄・台湾・済州道を媒介として東アジア全体を今一度考えなおす」というとき、接触と分有の思想は歴史からの要請として了解されるはずである。だが私はここに書き入れられているひとつの文字にとても敏感になっている自分に気づかされた。 ひとつの文字とは何か。それは済州<道>のことである。普段は済州<島>と呼称されるそこが<道>と表記される背後に、韓国内部で起こった最近の変化を思わずにはいられなかった。そのとき<道>は行政的単位を越えて二重の意味を帯びてくる。<島>が<道>となること、そこには国家のカタチをリライトせざるを得ないほどの政治的要請があったのだろうか。ソウルにいる間、その問いの納得いく解答を得る機会を失してしまったが、たえずそのことは私の頭を去来していた。 というのは、済州島が「自治政府」になることを韓国政府が認めたという報道を、つい3週間ほど前、沖縄の地元2紙(沖縄タイムスと琉球新報)で小さくないスペースを割いて紹介していた記事を強い関心をもって読んでいたからである。そのこともあって、出席したプロジェクトの「問題設定」の冒頭で、冷戦体制のもとでの分断と細片化された東アジア全体を見直すコンテクストのなかで「沖縄・台湾・済州道」という連なりとして定位されていることに、少なからぬ驚きを覚えずにはいられなかった。植民地主義と冷戦によって分断され、細片化された「飛び石」のひとつの<島>で起こった変化に、私はその連なりのあとひとつの「飛び石」でもある沖縄について、とりわけ沖縄の未来を窒息させかねない「米軍再編」への抵抗の想像力について考えないわけにはいかなかった。 東アジアにおける冷戦のもとでの熱戦の起点となった1945年の沖縄戦、1947年の台湾2・28事件、1948年の済州島4・3事件、1950年の朝鮮戦争。沖縄・台湾・済州島(道)・韓国、これら東アジアの群島と半島は、長い間冷戦の負の遺産を生かされてきた。日本の戦後体制・憲法の外部で戦争と占領の継続としてのアメリカの軍事的植民地状態に放置され、72年の「日本復帰」後も変わらぬ現実におかれてきた沖縄。国連的秩序のもとで「国家なき国家」の状況を強いられてきた台湾、そして韓国の周縁として疎外の変数を刻んだ済州島。東アジアの周縁の「飛び石」たちはまた、幾つもの帝国が折り重なった<境界>でもあった。 沖縄とは温度差が20度以上もある晩秋のソウルの市街に入った夕刻、立ち並ぶビルディングの方形をかすめて赤く満ちた生まれたての満月が架かっていた。肌を刺す夜の乾いた冷気に身をおくと、火照っていく小さな律動が私の内部にも満ちていくのを感じた。そして「飛び石」という言葉がイメージさせる孤立の位相が、東アジアの群島と半島に散種された分有と連帯の可能性として開かれていく予兆を、在米沖縄人大学教授コージ・タイラの名とともに思い起こしていた。 コージ・タイラの「雑音」 コージ・タイラは、これまで沖縄が東アジアに向かって開かれていく道を、沖縄の日本からの分離と「独立」にその可能性を描きこんできた。1997年に沖縄の若者を意識して行われたレクチャー「琉球独立の新視点」(『EDGE』第5号所収)は、これまで展開してきた自らの言語的実践を反復しつつも、歴史的変化の予兆を孕んだ東アジア情勢への独自な視点を介在させた再提示でもあった。そのメッセージは、95年の米兵による少女レイプ事件をきっかけにして立ち上げられた沖縄の動きのなかに受け継がれ、貯蔵されてきた経験と応答しつつ、それを政治的想像力において掬い取り、沖縄の持つ可能性のギリギリの所まで引き延ばし、組み替えていく試みでもあった。95年以降の沖縄へのポレミークな介入としても読めるが、それ以上に私たちに想像力のタタカイへと促す、そのような性格を持っていた。 このレクチャーの冒頭、コージ・タイラは自らの提言を「雑音」に擬していた。「私も沖縄の地位や進路について、大衆運動を支援したころがあります。これをきっかけに、その後5、6年または10年毎に、沖縄の地位が何らかの変化が生じる度に、何かと雑音をたててまいりました。今日もその伝で雑音をたてて見ることにしました」といっていたが、ここから伝わってくるのは、沖縄の変わり目に大衆運動を支援してきたにもかかわらず、その度にその支援が反古にされてきた苦い述懐として聴くこともできる。今度も「ほんとうは沖縄の人たちには届かないのかもしれない」というある種の自嘲のようなものと、それでもなお沖縄に、とりわけ沖縄の若い世代に対して発せざるを得ない老学者のなかに流れ込んでいる、この島の<未来への郷愁>として呼びかけていくような両義的な声の響きとしてである。しかもその声は冷静な世界認識に裏打ちされているため、独特な諧調と陰影を織り込んでもいた。コージ・タイラがいう「雑音」とは、そのような複数の声として理解されなければならない。決して謙遜や衒いとしていわれたのではない。沖縄の未来へのやみがたい、だが反語的にしか託しようがない郷愁と見まがう希望のようなもの。あるいはそこに冷たい熱気を読みとるべきなのだろうか。 コージ・タイラは、東アジアの政治的現況がアメリカのヘゲモニーによって占有され、東アジア諸国はそれぞれアメリカと二国間で結んだ条約や協定で拘束されている事実を挙げていた。「日本とアメリカ、中国とアメリカ、韓国とアメリカ、台湾とアメリカ、という具合に、アジア諸国はみなアメリカ合衆国の遠距離操作網の中に入っているわけです。ということは、アジア諸国はまだアメリカ合衆国の世界政策から解放されていない」として、そうした二国間関係でワシントンに集中されている、アメリカとアジアの支配・従属関係を打開するひとつとしてEATO(East Asian Treaty Organization)のようなものを構想する。そのためにはアジア諸国が関係を濃密にし、アジアの平和と安定を連帯責任で実現することの必要性を説く。沖縄の米軍基地の要・不要を決定するのは、他でもない、東アジアが独自性を発揮した関係を作り出せるかどうかにかかっているというのである。 それだけなら取り立てていうべきほどのことでもない。が、目を凝らしたいところは「主権」という概念の罠に陥る危険を注意深く避けている次のような言葉である。「『主権』にこだわり過ぎる国民国家の時代には、国家間の疑心暗鬼が国際関係の日常茶飯事になっています。東アジア諸国間の相互不信を利用して、アメリカの軍事基地が沖縄に在るわけであります。とすれば、沖縄にできる国際貢献というものは、国家間の疑惑や紛争の平和裡の解消へ向けて、『お手伝い』をすることではなかろうかと考えられます」と。 ここで2つのことに注目したい。ひとつは、「国家」と対になった「主権」概念の排外性を見誤らないこと、あとのひとつは「お手伝い」という控えめな言い方に、国家間の疑惑や紛争のもととなっている「主権」の排外性を越えたところに「独立琉球」を視野に入れていることである。国家を介在させないさまざまなレベルでのアジア諸域との関係と交流を仲介するアリーナの実績をつむこと、とりわけ国連的秩序のもとで「国家」として認められていない台湾と中国との和解にむけたプロセスに「独立琉球」を書き込んでいるところにコージ・タイラの政治的想像力の際だった特徴がある。 だから「独立琉球」は、自らの軍隊はもちろんのことアメリカや日本の軍隊の進駐を許さない<完全非武装・非武装無力>でなければならない。ここに最初に引用した鄭根埴の「沖縄・台湾・済州道を媒介として東アジア全体を今一度考えなおす」問題意識との深い共鳴をみてもいい。主権に閉ざされた国家としてではなく、半島と群島の「飛び石」として徹底して<あいだ>を生きる、国家なき国家、主体なき主体においてこそ獲得される。<明かしえぬ共同体>のリアルなのだ。 東アジアの和解の空間を創出する「独立琉球」を荒唐無稽な政治的空想とみるものは、そのことによって想像力の貧困さを撃たれるだろう。「米軍再編」がコージ・タイラが8年前に危惧した「日米安保体制下で、日本がアメリカのアジア政策に完全服従ないし同調して、中国を仮想敵視した戦略で、東アジアの協調・連帯に背く立場を取っている」としたことに強く傾いていくことをみるならば、「独立琉球」の構想力の射程と生々しさに改めて気づかされるはずだ。 日米両政府による「沖縄処分」 「日米同盟・未来のための変革と再編」という名の「米軍再編」は、沖縄の民意を完璧に無視したものである。そもそも「沖縄の負担軽減と抑止力の維持」というときの、「抑止力」と「負担軽減」は等価に扱える性格のものではなく、軍事戦略からするそれである以上、「抑止力」に重心がおかれることはいうまでもない。いや、ここでいわれる「抑止力」という軍事的表象さえ、誰によってどのようになされようとしているかを考えるならば、擬制にしかすぎない。沖縄の現実に即してみれば、米軍と自衛隊が一体化した軍事機能の効率的な再配置という以上に、沖縄社会の北と南の分断であり、北部地域の<軍事的なゲットー化>を招くものである。ここに見えてくる日米の軍事的ヘゲモニーの移動と再配置は、沖縄の未来を大きく歪めることは明らかである。 これはもはや「再編」ではなく、日米の共同謀議よる「沖縄処分」にほかならない。そしてその背後にあるのは、再編協議の米側責任者であるローレンス国防副次官が「(普天間飛行場移設案について)日本政府が実現できると自信があるというので提案を受け入れた。われわれはそれを信じる。必要なのはナショナル・ウイル(国家意志)だ」(沖縄タイムス11月10日)と発言した、「ナショナル・ウイル(国家意志)」の存在である。この「ナショナル・ウイル」こそ「主権」の名による「国防」や「外交」として発動される暴力の避難所にして砦なのだ。「米軍再編」に沖縄の人々が「処分」をみたのは、「名護市民投票」や「県民投票」などによって示された沖縄の民意を無視したからではない。「ナショナル・ウイル」の発動を敏感に感じ取ったからである。 戦争と占領の経験を通した沖縄と韓国・済州島(道)の言語と映像の対話において、私はしばしば沖縄の南北を引き裂き、北部を軍事的ゲットー化するイメージを振り払うことは出来なかった。そしてこれから沖縄が向きあわざるを得ない「ナショナル・ウイル」について考えるとき、そこでいわれた<方法としての沖縄>と<方法としての済州島>の交差するところに、コージ・タイラが東アジアの時空に書き込んだ「独立琉球」を差し向けてみたい強い思いに駆られた。分断と細片化を余儀なくされ、いくつもの帝国が重なって「飛び石」として存在させられた群島と半島の経験を開き、繋いでいくことを痛感させられた。 コージ・タイラの「遠い声」を間近に聴き取った鵜飼哲が、「それは任意の一地域の独立ではなく、既成の独立概念の単なる適用でもありえない。独立そのものを発明すること、あるいは発明し直すことが求められる。そのような出来事を、コージ・タイラが、『沖縄独立』ではなく、あえて『琉球独立』と呼んだこと、そのことの意味を、さらに考え続けていきたいと思う」とした場所で、私もまた考えていきたい誘惑をおさえることはできない。「独立そのものを発明すること、あるいは発明し直すこと」――まさにそこにおいてこそ、大きな曲がり角を曲がろうとする沖縄の抵抗の想像力が試されているはずだ。 8年前のコージ・タイラが波立てた「雑音」を、沖縄から遠く離れた晩秋のソウルでより身近に感じつつ、自らの生の自然時間と「独立琉球」の道程の歴史時間を測り、たとえ期待とは逆行していたとしてもその時は自分は生きているはずはないのだから「白骨に痛痒を感じることはまずありません」という幾分アイロニーを込めた言葉で歴史を逆なでするように沖縄の<今>に投げかけた黙示のような審級の前で立ち止まってみる。 「従来の独立論争は、独立すべきかどうかという当為論争であったのですが、この2、3年の間に当為は当然化して、実践の論議に発展してきたように思われます。大袈裟な言い方をすれば、沖縄は独立過程に入ったとすることもできましょう。」 この「雑音」を聴き取るためには、ある特別な耳が必要だろうか? いや、こういうべきなのかもしれない。この審級においてこそ「沖縄処分」として発動される「ナショナル・ウイル」とよく相対化できるはずだ。今、沖縄では戦後抵抗の記憶を呼び起こし、それを発見し直していくさまざまな試みが世代や階層を横断し胎動しつつあるが、問題は国家の避難所にして砦でもある「ナショナル・ウイル」の発動を律し、それを越える文体を創出できるかどうかにかかっている。そうでない限り、沖縄のトラッジ・コメディは繰り返されるであろう。 (『世界』岩波2006・1) |
| 安易な移住続々、行き詰まり…人口急増の石垣島困惑 沖縄県石垣島。台湾の目と鼻の先にあるこの亜熱帯の島では、ここ数年、本土からの移住者が急増している。 青い空と海、温暖な気候にあこがれて、首都圏などから島にやってくる人々がほとんどだが、突然、大挙して移住者が押しかけてきたことで、困惑も広がっている。単なる“楽園願望”だけで島に飛び込んでくる若者たちもいるからだ。石垣市では、移住の影響について、本格的な情報収集に乗り出した。 石垣市によると、住民票の異動だけを見ても、一昨年から島の転入人口は約3000人も増加している。これに、住民票を異動しないで生活をしている人も含めると、その数は5000人に達するという。「具体的な分析をしていないので、はっきりしたことは言えないが、おそらく、ほとんどが本土からの移住者だろう」と、同市企画調整室の長嶺康茂副主幹は推測する。 沖縄県全体では、同じ2年間で約5万1500人が本土から移り住んでいるが、転勤などで沖縄本島にやってきた人も多く含まれているとみられる。 石垣市の現在の人口は約4万5000人。これまではおおむね微増で推移してきたが、一昨年を境に急増を始めた。 異常とも言えるこのブームの背景には、いくつかの理由が指摘されている。そのひとつは、航空・旅行会社のPRや、雑誌の特集などで楽園イメージが広まったこと。また、周辺の八重山の島を舞台にしたテレビドラマも、人気を後押しした。都市化が進んだ沖縄本島より、手つかずの自然が多いうえ、沖縄らしさを色濃く残していることも魅力らしい。 移住してくる人たちの年齢層は幅広い。夫の定年を機にやってくる夫婦や、働き盛りの30~40代の男性のほか、本土での就職をあきらめて、島に希望を求めてきた若者もいる。 製薬会社を退職し、昨年2月に一戸建てを購入し、大阪から移住してきた小川利一さん(57)は、「真冬でも半袖でいられるし、都会のようなストレスはまったくない。人生とは何てすばらしいんだろう、とここにきて実感しています」と話す。 一方で、「先の見えない不況に絶望した人々がやってくるケースも多い」。そう話すのは、市内にある不動産会社の男性社員だ。この社員は、移住者向けに賃貸住宅を仲介してきたが、「都会でバリバリ競争して、血道をあげるだけが人生ではない、と悟った人たちが目立つ」と指摘する。 だが、国内でも有効求人倍率が最低水準にとどまっている沖縄県の中でも、観光や農業が基幹産業である石垣市の雇用情勢は、非常に厳しく、下見もせずに安易に移住しても、就職難に見舞われるケースは少なくない。「島に渡ってくる若者の中には、仕事先もなく、苦労している人たちも多い」のだという。 思ったような仕事に就けず、「理想と違った」と不満を口にするものの、本土に戻る気力もなくし、島で放浪生活を送る若い男性もいるという。 石垣市では最近、移住が島に対してどのような影響を与えるか、調査に本腰を入れ始めた。もともと暮らしていた住民との摩擦も考えられる一方、都会のIT業界、サービス業界などに従事していた移住者たちが持っているノウハウが、「島おこし」に活用できる可能性もあるからだ。 「喜んでいいのか、それとも問題として考えなければならないのか。正直言って、どう評価していいか、はかりかねている」 長嶺副主幹は、戸惑いながら、打ち明けた。 |
| 午後9時32分。沖縄から望む夜の太平洋は、どこか紺色に見えた。 奇妙に大きく映える月が、水平線上に無数の光の粒を散らしている。暗視装置には強すぎる光だった。手前にはそれよりもずっと暗い辺野古の町の灯があり、国道を挟んで隣接する米軍基地から養分を吸い取り、辛うじて瞬いているネオンの寂れた光彩が、沖縄の現状を端的に伝えているようだった。 琉球王国の栄華を伝える首里城や、「ありったけの地獄をかき集めた」沖縄戦の傷痕を留める戦跡公園。無数のガマ--鍾乳洞を内包する、隆起珊瑚礁から形成された島の神秘的な景観と、どこまでも透明な海。青と赤の原色に彩られた、観光地としての沖縄の顔が集中する南部に較べ、島の大部分を占める中部から北部にかけての一帯を覆う色は、湿り気を帯びた緑と乾いた茶の中間色だ。延々と連なる砂糖キビ畑と、射爆演習に焦がされ、抉られた大地の色。この辺野古にも濃く現れているそれらの色は、薩摩侵攻から始まった侵略と貧困の歴史を、地続きに引き受けているこの島の素の色なのかもしれなかった。 本土防衛の不沈空母として位置づけられながら、実際に米軍の上陸が始まれば、大本営の戦略的判断によって当然のごとく見殺しにされた島。15万人に及ぶ住民を悶死させた罪は、国政レベルではついに一度も総括されることなく、反共の防波堤として仮初の主権を与えられたこの国が、契約の証として勝者に差し出した島。トゥエルブは、それを指しておまえと同じだと言っていた。平和国家の帳尻を合わせるために作られた装置として、一般社会とは切り離され、時々の都合によって発動される「超法規的措置」に従い、後ろ暗い仕事をこなしてきたおまえは、この珊瑚の島-ウルマそのものだ、と。よくわからない話しだったが、トゥエルブがそう言うのならそうなのだろう。いずれ任務とは関係のないことだと思い、理沙は暗視装置の目を目標に向け直した。 国道329号線を縁取る道路灯の向こうに、無数のガラスの目を穿った建物の連なりがある。無個性なコンクリートの箱が並び建つ光景は団地のそれを連想させるが、大きくゆとりを持たされた配置は、日本とは感覚を異にするものだ。その先には消防署から銀行、劇場、放送局まで備えた街の灯りがあり、本島中東部から三角の頭を突き出している辺野古崎の上に、キャンプ・シュワブと呼ばれる在沖海兵隊の総合演習基地を形作っている。岬の両側は戦車揚陸艦の揚陸用ランプと上陸演習地の斜面に囲まれ、国道に沿ってうねる数キロのフェンスの川に遮断されている一帯は、2000人の海兵隊員が家族とともに暮らす一大居留地であり、国道の手前、この久志岳を含む内陸側に広大な用地を確保している射爆場ともども、日本の中の「外国」を現出しているのだった。 (……) 間を走る辺野古美謝川に阻まれ、隣接するキャンプ・シュワブとは別々のコミュニティを形成している基地。司令部ビルを中心とした人員駐屯地区と、39個の半地下覆土式弾薬庫が点在する高台は、辺野古弾薬基地と呼ばれる在沖海兵隊唯一最大の火薬庫だった。 大浦湾に面する起伏の多い敷地は、海側を断崖に囲まれており、厳重に警備された内陸側ゲート以外には、いっさいアクセスする術がない。弾薬庫区域は基地の中でさらに二重のフェンスに囲われ、警備と夜間作業のためにひときわ明るい照明が完備されてもいる。以前からNBC(核・生物・科学)兵器貯蔵の疑惑が絶えなかった天然の要塞を見つめて、横に立ったトゥエルブが「よくもそろえたものだ」と苦笑していた。 |
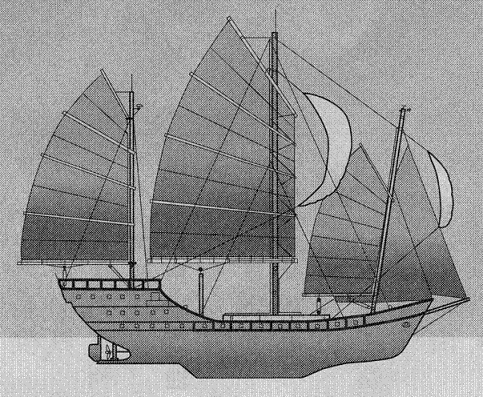
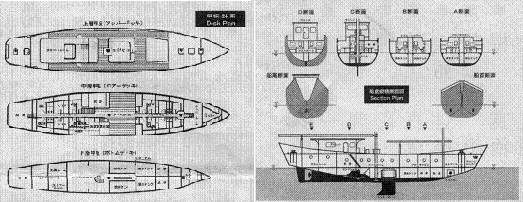 アメリカズ・カップで有名な故ピーター・ブレーク卿、ハワイ出身の海洋冒険家ナイノア・トンプソンさんらも参加し、世界的な話題にもなった。
アメリカズ・カップで有名な故ピーター・ブレーク卿、ハワイ出身の海洋冒険家ナイノア・トンプソンさんらも参加し、世界的な話題にもなった。↑この素材の作成者のホームページもどうぞ(フリー素材満載です。)