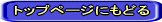�ѐ�
�w�u�Ӌ����A�W�A�v�̃A�C�f���e�B�e�B�E�|���e�B�N�X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\����E��p�E���`�x�i���Ώ��X2005.2�j
�@�{�N�����ɏ㈲����b����Ă���ł���B����Ɋ֘A���镔���ɂ̂��y�������A�ȉ��ɖڎ����������B
���́@�{���̎��p
��P���u�A���ύX�v�̈�Y�Ƃ��Ẳ���i�V���i���Y��
�@��P�́u�����R�������^���v�̐��i
�@��Q�� ��㏉�����ꏔ���}�̓Ɨ��_�\�\���s���������̐��̎���
�@��R�́u�c�����A�v�Ɓu�����A�v�\�\����A�C�f���e�B�e�B�̏\���H
��Q���u�A���ύX�v�̈�Y�Ƃ��Ă̑�p�G�X�m�|���e�B�N�X
�@��S�́u�ȐЖ����v�Əӌo�ύ��́u�w�{�y���x����v
�@��T�́u�V���������v����u�V��p�����v�ւ̓]�Q�̐����I����
��R���u�A���ύX�v�̈�Y�Ƃ��Ă̍��`�A�C�f���e�B�e�B
�@��U�́u���`�����́v�̊m���Ɓu���`�l�v�̑z���E�n��
�@��V�́u�ꍑ�vVS�u�x�v�̗͊w�ƍ��`�Z���̃A�C�f���e�B�e�B
�I�́u�Ӌ����A�W�A�v�A�C�f���e�B�e�B�E�|���e�B�N�X�̃_�C�i�~�Y��
�@�u���́@�{���̎��p�v�ŁA�g�{���́A����E��p�E���`�����āu�Ӌ����A�W�A�v�Ƃ����V�����n��T�O���N���A���̂����Ƃ��d�v�ȓ����ł���u�A���ύX�v�ɂ���Ă����炳�ꂽ���̎O�̒n��̃_�C�i�~�b�N�ȃA�C�f���e�B�e�B�E�|���e�B�N�X���r������̂ł���B�^�c�c�����́u���A�W�A�v�Ƃ������n��T�O�ł͓��n��̏����ۂ͂���ɓ�����A�s�\���ŏ���������Ȃ��Ƃ��낪���邩��ł���B�^�����āA�u�Ӌ����A�W�A�v�Ƃ����V���Ȓn��T�O�̒�N�́A�ߔN�̍��ۊW��n�撁���̕ω������ӎ��������̂ł���B�h
�@�����āA���Ɂg��p�E���`�E���������u�Ӌ����A�W�A�v�̂����Ƃ���{�I�����́A���̎O�̒n�悪�O�ߑ�Ȃ����ߑ�ɂ����ē��A�W�A�́u���S�v�ł��钆���E���{�ɂ������āA�u�Ӌ��v�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă������Ƃł���B�^�c�c�u���ؐ��E�V�X�e���v�i�u�؈Β����v�j�̃Z���^�[�Ɉʒu���钆�����w���B�������A�Ƃ�킯�ߑ�́u���S���A�W�A�v���l����ꍇ�A�����̂ق��ɁA���̌㔼����u���ؐ��E�V�X�e���v���痣�E����Ɠ����ɁA����u�����v���`�����A�����ċߑ�ɓ���Ɠ��A�W�A�́u���S�v�ł��钆���ɂ��������ړI�Ȓ�����s�Ȃ��Ă������{��������ɓ���邱�Ƃ͑Ó��ł��낤�B�h
�@���Ɂg�u�Ӌ����A�W�A�v�̂����Ƃ��d�v�ȃL�[���[�h�́A�u�A���ύX�v�ƌ����Ă悢�B�ߑ�ȗ��A�u�Ӌ����A�W�A�v�n��́A��x�Ȃ����O�x�ɂ킽�肻�̎匠�������͐����I�A�����ύX���ꂽ��A�u�ٖ����v�̐A���n�I�x�z�����肵���o���������Ă���B�c�c�^�u�Ӌ����A�W�A�v�́u�A���ύX�v�̌`�Ԃɂ́A��̃p�^�[�����܂܂�Ă���B�ЂƂ́A�����╹���ɂ���Ă����炳�ꂽ������u�O���v�u�ٖ����v�x�z�ł���A�����ЂƂ́A������u�c�����A�v�Ƃ����A�����Ƃ��Ă͐����Ȃ��̂ł���B�h
�@��O�Ɂg�\���I���Ƃ��Ắu�A���ύX�v���A�u�c���v�ɕ��A�����u�Ӌ����A�W�A�v�ɂ����炵���V���Ȗ��Ƃ́A�u�c���v�Ƃ̍����������ɒ�������u�Ӌ����A�W�A�v�Z���̃A�C�f���e�B�e�B���̌��݉��ł���B�����āA���̌��ۂ́u�Ӌ����A�W�A�v�̈��́u�E�Ӌ����v�̓����Ƃ��đ������悤�B�h
�����������p�܂��āA������߂���_���ɂ��Ă̂ݐG���B
�@�u��P�́v�ɂ����āA�g����Z���́u�A�C�f���e�B�e�B���v�͂������Đ��̃A�����J������1972�N�̓��{���A�Ɏn�܂����̂ł͂Ȃ��A����́u�ߑ�̖��J���v�Ƃ����1879�N�̗��������i�u���������v�j�ɂ܂ők�邱�Ƃ��ł���B�h�Ǝw�E���A�g�������A�ߌ���j�̗��������A���{�ւ̓����E��������сu���{�l�A�C�f���e�B�e�B�v�̊m���E�w�͎͂嗬�I���݂ł���A�u����l�v�A�C�f���e�B�e�B�������������I�����܂Ōې����铮���͖T���ɂ����Ȃ��Ƃ�������B�h
�i�P�j�����Ƃ��M�҂́g���j�͏��҂ɂ���ď������B�h�Ƃ��A�g�����́u�����v�ɐ��������������{�̘_���ɕ������������`�j�ς́A�����ԁA�嗬�I�_���Ƃ��āA�u���{�����̓���v��u�������ƌ`���̌������Ȃ���Ɓv�A�����āu����Љ�ߑ㉻�̌_�@�v�Ƃ����������Ŗ\�͓I���i���������{���̗��������𐳓������Ă����B�܂��A���̂悤�Ȏj�ς̉������ŁA�������Ȃ������ʐ��ɖ����������u�����v���ł��閾�����{���g�p�����p��́A���ʂ��������ɕ��R�Ƃ��̂܂ܗp�����Ă����B�u�������d��ȉ߂���Ƃ������߂̒����v�̈Ӗ����܂u���������v�Ƃ������t��A�������̉��߂����^�����u�E���^���v�A�^�������Ƃ��u�E���l�v�Ə̂����p��̂���܂ł̎g�����́A���̍D��ł��낤�B�h
�i�Q�j�u���������v�ȍ~�́u���������ւ̔��Ή^���̑������v�̏]���̒���ɑ��āA�g�M�҂͂��̉^�����u�����R�������^���v�ƋK�肷��i�ѐ�2003�j�B���`�I�ɂ͗������̉��߂�������^�����w���A�L�`�I�ɂ́A���{�́u���������v�ɂ��������܂��܂Ȍ`�ԂœW�J���ꂽ���O�̗����G���[�g�E���O�ɂ�锽�Β�R�^�����w���B�������A������̕����e�F�ł��̐��i���������ƈقȂ����Ǝv����u������^���v���A���{�̒��ڎx�z�ɔ�����_������̒�R�^���ł���Ƒ������邽�߁A�L�`�Ƃ��Ắu�����R�������^���v�̔��e�ɓ���Ă��悢�B�ȏ�̒�`����A���̊֘A�p��Ɋւ��ẮA�u���������v���u���������v�Ƃ��A�܂��u�E���l�v��u�E���h�v����̓I�l�E�Q���`�Ԃ��l�����u��V��ҁv�u�����^�������Ɓv�u�����^���w���ҁv�u�����S���ҁv�u������R�h�v�u�嗬��R�h�v�ȂǂƂ��Ďg�p����B�h
�i�R�j���Ă��������u�����^���v�����A�M�҂͎��̎O�_�����̓����Ƃ��ċ����Ă���B�u�P��K�͂ȉ^���ƌ`�Ԃ̑��l���E���ې��E��\�͐��^�Q�G���[�g�w�哱�̉^���^�R�^���Q���ɂ�����_�����̊��I����v
�@���Ɂg�O�ߑ�Љ�̗������������ɂ�����܂ŁA�����E���ƈӎ����r�I��������̂́A��͂�m�����������̂Ƃ��问���G���[�g�w�ł���B�ߑ�Љ�ɂ����Ă����������ʉ��w�s���̖����ӎ��̊��A�����̗����_���w�Ɍ����ɑ��݂������Ƃ́A����Ύ��R�Ȃ��Ƃł��낤�B���������āA�O�ߑ�Љ�ɂ����āA�G���[�g�w�̗L���ȓ������Ȃ�������A�܂������̌����͐����ɂ�����鎀���̖��łȂ�������A��ʉ��w�_���ɂ�鎩���I��K�͂ȑ�O�^�������肦�Ȃ��ƌ����悤�B�h
�@�g���ɁA���������G���[�g�w�������ł��鎑���͐���Ă����B�c�c���{�̐V�����x�z�͕��͂�w�i�ɐ��s���Ă��邤���ɁA���������̍s���@�ւ͂��łɓ��{�̐V�����s���V�X�e���ɍX�R���ꂽ���߁A�������p�����邩����u�V���v�ɂ������钷���I�{�C�R�b�g�͕s�\�ł���B��ʔ_���̔�\�͓I�s���]�^���ւ̎Q���͉^���̍ŏ�������E���ɖ��������I�Ή��ɂ����Ȃ�Ȃ������̂ł��낤�B�h
�@��O�ɁA�g��ʔ_���̍��݂̑Ώۂ͎��{�E�m���݂̂Ȃ炸�A�F���E��a�ł��������͂��ł��邽�߁A����ɉ��{�E�m���ɍ��݂������A����ɐe���݂̂Ȃ��u�F���E��a�l�v�̎x�z�����}����\�}�͘_���I�ɂ����������Ȃ����낤�B�܂��A��������Ă��������_���ւ́u����v�[�u�́A���ہA���{�́u�V���v���ŋ������Ă��Ȃ��������߁A�u�x�z�v�͔_���̕��ՓI������ꂽ�Ƃ��l���������B�������A�_�������̏d�����Ă��鐶���̖ʂōl����A���{�̐V�����x�z�V�X�e���͋����̎��{�ɂ�铝���̐��Ƒ傫�ȕω��͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��A��ʔ_���̕����ɂ������钷���I��R�ӎ������ʓI�ɗ}���铭����L�����ƌ�����B�����Ȃ�A�����E���ƃ��x���̐��_�I�M�O����������D�悷�问���̔_�������ɂƂ��ẮA�����������Ɉ������Ȃ�������A�����҂��N�ł��邩��傰���ɖ₤���Ƃ����Ȃ������̂ł��낤�B����́A�_�������������I�ɍR�������^���ɎQ������ӗ~���ł���������Ƃ��čl�����悤�B�h
�ȉ��A�{���̉���Ɋւ�镔���݂̂̔��������B
��P�́@�u�����R�������^���v�̐��i
��S�߁@�����^���̔�������
��T�߁@�u�����A�C�f���e�B�e�B�v�̋ÏW
�c�c
�@�u�����A�C�f���e�B�e�B�v�́A�������ė��������̂��ƂŌ����n�߂��̂ł͂Ȃ��B���������̑O�ɂ��łɂ��̗����א��ҁE�G���[�g��̂������ɑ��݂��Ă����B���Ⴗ��A1872�N�̗������g�߂̈ɍ]���q�i�����A���g�j�E�X��p�e�����ہi���L�P�A���g�j�E�쉮���e�_��i���ېV�A�Q�c���j��͓��{�̕����O�����Ƃ̉�ɂ����āA�哇�����́u�ł��䗮���ꑮ�Ȃ肵�ɁA�̂��c���N�ԁA�F�l�ׂ̈ɉ��̂���v�ꂽ�̂Łu��ɕԖ߁v���Ă��炢�����Ɩ����V���{�ɗv�������i��ɏ꒩���w���������^�x1977�j����́A267�N�O��1609�N�ɎF���̗����N�U�Ƃ���ȗ��̍���ւ̕s�����ԐړI�Ɏ����Ă���Ɠ����ɁA���������F�����Ă��鎩��̍��y�͈̔͂́A�����F���̒D��ɂ���Ď��������������܂ŃJ�o�[���Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B�����[�����ƂɁA��ʂɌ�����ߑ�i�V���i���Y���̍\���v�f�Ɍ������Ȃ����y�ւ̈����́A�����̗����G���[�g�����������Ă����u�����A�C�f���e�B�e�B�v�ɂ͂��łɓ����Ă����̂ł���B�����āA���̂悤�ɁA�����א��҂�G���[�g�����̂������ɑ��݂����u�����A�C�f���e�B�e�B�v�̈ێ��ƕ\�o�́A�F���E���{�ɂ������鉅�l�ɂ���ė��Â����Ă������Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�c�c
�@�����A���̂悤�ɗ��������Ƃ��������̂Ȃ��Łu�����A�C�f���e�B�e�B�v���ÏW���ꋭ�����ꂽ���ۂ́A�������Ďɂ��鋌�����w�����E�G���[�g�����̂������̋����͈݂͂̂ɂƂǂ܂炸�A����{���ȊO�̐擇�n��ɂ��A������x�g�債�Ă������B�����̊W�ł��̕ӂɂ��Ă̏ڏq���ȗ����邪�A�����������ɋN�����{�Ấu�T���V�[�����v�́A�����������^���̔g�y�E�g��Ȃǂ�ʂ��ĉ���{���ŋN�����������E���{�x�z�ւ̃{�C�R�b�g�^�����A���Ӓn��܂ōL�����Ă������Ƃ��������Ɠ����ɁA�������̖ŖS�Ƃ��������̂Ȃ��ŁA�擇���u�����v�Ƃ����^�������̂̈�����ӎ��������ƌ����悤�B
���тɁ@�u�����R�������^���v�̗��j�I�ʒu�Â�
�@�������͓��A�W�A�̈ꏬ���Ƃ��āA�Ƃ�킯17���I�����̎F���̐N�U����܂Ŗf�Ղ�ʂ��đO�ߑ㓌�A�W�A�����̈ꗃ��S���Ă������A�ߑ�ɓ��낤�Ƃ��������ɁA���ɖS���̉^��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�܂��A�������̕������߂����S�����I�Â����g�p����́u�����R�������^���v���A���ǁA�ڕW�͂܂������ʂ�����Ȃ��܂܁A���Ɏ��s�ɏI������B
�@�u�����R�������^���v�̔s�����l����ɂ́A�^���̕���Ȃǂ��܂��܂Ȏ��_����l�@���邱�Ƃ��\�ł��邪�A��������=�����S���ƂƂ��Ɂu�����R�������^���v����芪�����ԂƋ�Ԃ��猟�����邱�Ƃ��ł���B���̌����������ԂƋ�Ԃ̎˒��ɓ���̂́A������u�`���Ƌߑ�v�u���S�ƕӋ��v�u���ƃV�X�e���ƍ��ۃV�X�e���v�Ƃ����O�̎����ƌ�����B
�@�܂��A�����̍��ƃV�X�e���Ɨ�������芪�����ۃV�X�e�������Ă݂悤�B���{�ɂ�镹���܂ł̗����́A���ꂵ���ꉤ���̑̍ق������Ă����B���̂��߁A�������̍��ƃV�X�e���́A�����_�Ƃ���O�ߑ�̉������Ƃ̗ތ^�ɑ�����ƌ��Ă悢�B�܂���������芪�����ۃV�X�e���ɖڂ�]����A�����͐����i�������j�̍����̐����Ő����ɕ��f���A�����̒��N�E����i�x�g�i���j�A�ə��i�r���}�j�Ȃǂƕ��ѐ��̈ꑮ���ƂȂ����A17���I�ȍ~�F���ɂ��A�����o�ϓI�x�z�Ɛ����I������悤�ɂȂ�A������u�����v�Ƃ�����Ԃɒu����Ă����B�O�ߑ㓌�A�W�A�̍��ے����ł���u���ؐ��E�V�X�e���v�i�u�؈Β����v�j�́A�����ɋN������ߑ�̎匠���Ƃ̌����ɂ͑��e����Ȃ����߁A�l�ގЉ�W�̒i�K�_���猾���A���A�W�A�̂��̑O�ߑ㍑�ۃV�X�e����������u�ߑ��@�v�ɒ��ʂ���������Ȃ��Ȃ�B�������A�����E���v�V�X�e���̏@�卑�ł��鐴�����̑���������̋ߑ�̔g�ɂ��������q���ɔ������邱�Ƃ��ł����A���ǁA���������ɓۂ܂�Ă��܂��Ƃ������|��̌����ƂȂ����B����܂ň��ׂ��������A�W�A���E�������̏Ռ��́A�O�ߑ�́u���ؐ��E�V�X�e���v�Ƃ��̋ߑ�ɂ�����ϗe���Ȃ킿�u���ؐ��E�V�X�e���v�́u�ϑԁv�Ƃ̑����̌��ʂł���ƍl���Ă悢�B��̓I�Ɍ����A���{�≢�Ă̗���̊O���ɂ���āA���͑��������X�Ƒr�����Ă��������肩�A����͔��A���n��ԂɊׂ����B�����A���̑������ɕ��ۂ���A�Ɨ��̑I������^�����Ȃ������̂ł���B���̈Ӗ��ŁA�O�ߑ�̈ꉤ���Ƃ��Ă̗������̖ŖS���A�u�狌�v����E�o�ł��Ȃ������u�����R�������^���v�̎��s���A���́u�`���Ƌߑ�v�������́u�O�ߑ�v�Ɓu�ߑ�v�̑����̋A�����ƌ�����B�������ɁA�N����������̃A�W�A�N�o�ɂ͂������Đ�����������Ƃ͌����Ȃ����A������̓��{�������ېV�ŋߑ㍑�Ƃɐ��܂�ς�낤�Ƃ��Ă��������ɏƂ点�A��@���ɖ��������������̎����ɂ����Ă������G���[�g�����̌����Ɍ����鎩�ȉ��v�̈ӎv����ыߑ㉻���o�̌��@�͂�茰���ł���B
�@�����A�������͋ߑ㍑�ƂɂȂ�O�Ƀ^�C�~���O�悭�u�����v���ꂽ���߁A�����S����˒��ɓ����A�u�������v�u���������v��ΏۂƂ���i�V���i���E�A�C�f���e�B�e�B���{�i�I�Ɋm������@����������B�܂��A���̓_�ɂ��֘A���Ă��邪�A�u�����R�������^���v�͋ߑ�I�i�V���i���Y���̐��i���\���ɑттĂ��Ȃ����߁A�ߌ���̉���i�V���i���Y���̔��W�⍂�g�������炷�����͂Ƃ��Ă͕s�\�����ƌ�����B
�@�������A�O�q�����悤�ɁA�u�����R�������^���v�͂��ꂪ�i�s���Ă����l�����I�ɂ����āA�����G���[�g�w�̂������Ɂu�����A�C�f���e�B�e�B�v�������̒��x�A�ÏW���ꂽ�ƌ�����B����́A���{���\�͓I�E����I�ɗ�������łڂ����ߒ��ɂ��Ƃ��낪�傫���B���̍��ƈӎ������ттĂ���u�����A�C�f���e�B�e�B�v�́A�^���̒��S�ł���̎m�������ɂƂǂ܂炸�A�𒆐S�ɓ��S�~��ɉ���{���S�̂⏔���ӑ����̒n���G���[�g�����̂������ɂ��L�����Ă����B�����A��ʖ��O���ɂƂ��ẮA���{�̗��������͖����Ƃ��Ɂu��a���v�̓������Ӗ����鑤�ʂ������ƌ����邾�낤�B�܂��A����ɂ���āu�x�z�ҁv�̓��{�l�Ƃ̐ڐG�@��̑����������炳�ꂽ�B�Ƃ��ɂ��̌�̓����ߒ���ڐG�ߒ��ɐ����������ʂ���A���ꖯ�O�́u����l�v�Ƃ������Ȉӎ��Ɓu��a�l�v�Ƃ������҈ӎ����蒅���Ă����B
�@�u�����R�������^���v�́A������j��̍ő傩������Ȑ����Љ�^���ł���ɂƂǂ܂�Ȃ��B�������ɁA�^���̎�v�`�Ԃ͐����ɂ�����~�����芈���ł��炴������Ȃ����Ƃ���A�ȏ�́u���ؐ��E�V�X�e���v�������͓`���I�u���S�|�Ӌ��v�v�z�\���z���Ă��Ȃ����ʂ͔ے�ł��Ȃ��B�������A�u�����R�������^���v�́A�����G���[�g����������I�ӎv�ʼn^����W�J���Ă���_����A��������Z���ɂ����Ă���B���̎���I�s���l���́A�����I�ȃC���[�W�̋��������j�̂Ȃ��Ŋi�ʂ̈Ӗ���L���Ă���B�u�����R�������^���v�́A������������ڕW��B���ł����Ɏ��s�Ŗ�������B�������A���̉^���Ō��ꂽ�����G���[�g�����̍��ƈӎ��ƁA��ʖ��O�ɂ܂ōL����������u�����A�C�f���e�B�e�B�v�́A���̌�A�����Ό��������āu���{�l�v�̈���ɂȂ낤�Ƃ����u���{�A�C�f���e�B�e�B�v�̍\�z�𑽂��ꏭ�Ȃ���}������G�l���M�[�ƂȂ�Â��Ă����B
�@�������i�s���Ă��镡���I�u������v�̊j�S�́A������Ƃ��ĉ���̃A�C�f���e�B�e�B�ɐ[����������Ă���B����Z���̂��̃A�C�f���e�B�e�B�̊����̒������j�I���J���́A�܂��ɗ����Z���̈ӎv������1879�N���{�̗��������ɂ���Ă����炳�ꂽ�̂ł���B�܂��A���́u����A�C�f���e�B�e�B�v�̂��������̐��������ۂ́A����ȍ~�����̗��j�I�ߖڂ̂���ɕ��o��������̓Ɨ��_�E�Ɨ��^���ŕ\������Ă����B���̐����I��̐��̊m��������ߌ���u����i�V���i���Y���v�̋N�_�́A�܂��ɖ{�͂ŋc�_���Ă����u�����R�������^���v�ɋ��߂�ׂ��ł��낤�B
�c�c
��Q�� �@��㏉�����ꏔ���}�̓Ɨ��_�\�\ ���s���������̐��̎���
��P�߁@��O����A�C�f���e�B�e�B�̊���
�P�@�u������v�̓��{�ւ̓����^���̌��E
�c�c
�@�����Â����{�ɒ�R���邩�A����Ƃ����{�̈���ɂȂ邩�A����͓��������̉���m���l�ɔ���ꂽ��Y�̑I���ł������B����͌�҂������B�u������^���v�ɂ��ϋɓI�ɎQ���������c���~�i1865��1938�j�́A�^���I����Ɉ�]���ē��{�ւ̓����^���ɐg�𓊂����B���c�́u������݂̎d���܂œ��{���v�Ƃ����́A�u������v�̓��{�ւ̓����̓w�͂��ے�������̂ł������B������肩�A���c���~�̂悤�Ȑl�����A����̓Ǝ������쎝���闧�ꂩ�牫��̓O��I�ȓ��{����i���闧��ւƕϐ߂��邱�Ǝ��́A�܂��ɋߑ�ȍ~����Z���̃A�C�f���e�B�e�B�����j�����̃V���{���b�N�ȏo�����ł���B
�@������ɂ���A���c���~���n�߂Ƃ��鉫��̐V����G���[�g����ш�ʑ�O���߂��������{�ւ̓����̕����́A�����m�푈�I���܂łÂ����B���悻�����I�ɋy�Ԃ��̉���Љ�̎���I���{���u���́A���{���{�̓O��I��������ɍ��v���邩�����ŁA�����̐��ʂ����߂����A����Z���S�̂����S�ȁu���{�l�v�Ƃ��Ď��o����܂łɂ�����Ȃ������B���c���~���\��ΎႩ���������ЂƂ�̃G���[�g�A�u����w�̕��v�Ə̂��ꑽ���̕���ʼn��ꌤ���ɑ���ȍv���𐋂����ɔg���Q�i1876�\ 1947�j�̃A�C�f���e�B�e�B���߂��銋���͂��̍D��ł��낤�B
�@�����������u���̓z�����v��搉̂��A�����I�ɂ킽���Ċw��I�ɉ���̎�̐����⏬�����u�������c�_�v���ؖ����悤�Ƃ��Ă����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ɔg���Q�́A�I�풼��Ɏc�����Ō�̘_���ɂ����āA����܂ł̐����I�w�͂ɖ������������[�����t���q�ׂĂ���B�u�c�c�n����Œ鍑��`���I���������鎞�A����l�́w�ɂ����x����������āA�w���ܐ��x���y���ݏ\���ɂ��̌������Đ��E�̕����ɍv�����邱�Ƃ��ł���v�i�ɔg���Q�w������j����x����1998�j�ƁA���Ắu�z�����v�̎�������lj������Ă��Ȃ��u�ɂ����v�Ƃ��A����̎j�ς��݂̂Ȃ炸�A�{���ɉ������闈��ׂ��u���ܐ��v�ɂ����ẮA���ꕶ���̍v�����ׂ��Ώۂ͓��{�������E�ł���ƈ���w�҂̔ӔN�̐S�����I���Ă���B���̂悤�Ȉɔg���Q�́u����l�v�Ɓu���{�l�v�Ƃ̂������̜p�j�́A�܂��Ɂu���{�l�v�ɂȂ낤�Ɠw�͂������A���ǁu���{�l�ɐ����Ȃ��v�i�����ꌧ�m������������j��O�̑����̉���G���[�g�Ƒ�O�̃A�C�f���e�B�e�B�����̏k�}�ƌ����悤�B
�Q�@��㏉���́u����Ɨ��_�v���߂����s�����Ɖۑ�
�@�u���{�l�ɐ����Ȃ��v�S�̈ꕔ�́A�I��ɂƂ��Ȃ��āu���{����v�u����Ɨ��v�Ƃ������������ʼn���Љ�ɂ����Č���ꂽ�B���̌��ۂ́A��O�̔����I�ɋy�ԁu���{�����v��{���ւ̔����Ƒ������邪�A������������т��̔����Ƃ��Ă̕����^���ȍ~�u���Łv�����͂��̉���i�V���i���Y���́u�Đ��v�́A�ߌ��㉫��Љ�Ɏ����I�ɑ��݂��Ă����A�C�f���e�B�e�B����������ƂɂƂ��ẮA�����Ȃ�Ӌ`��L���Ă���̂ł��낤���B
�c�c
��Q�߁@����̓Ǝ����}�̐����Ɖ^�c
��R�߁@�������}�̐��i�ƓƗ��_
��S�߁@�Ɨ��_�̎���
��T�߁@�Ɨ������̌`���Ə��ł̔w�i
�@��㏉���ɂ����鉫��Ɨ��_�����̔w�i�ɂ��āA�܂����Ɏw�E�ł���̂́A�����m�푈�ɂ�������{�̔s�k�ƃA�����J�R�̉���㗤�A�����x�z�ł���B����͓��{�̈ꕔ����藣����A�s���I�ɂ͓��{�ƕʌɒu���ꂽ�B���̌����́A�Ɨ������̌`���ɐ�D�̊�������̂ł���B
�@���ɁA���̎����A����̖@�I�n�ʂ̕s���Đ��͓Ɨ��_�̗L���ȗ��_�I�����ƂȂ����B�܂��A1943�N�̃J�C���錾�ɂ͉���̒n�ʂɂ��Ė�������Ă��Ȃ����A�u���{���͂܂��\�͋y���×|�ɂ����{�������悵���鑼�̂��������̒n����쒀�����ׂ��v�Ə�����Ă���A����ł́A���{�����D�����n��̂����ɉ�����܂܂��Ƃ��錩�����������B�܂��A�|�c�_���錾�̑�8���ɂ́u�J�C���錾�̏����͗��s�����ׂ��A�܂����{���̎匠�͖{�B�A�k�C���A��B�y�юl���Ȃ�тɉ䓙�̌��肷�鏔�����ɋnj�������ׂ��v�ƁA���{�̍��͈̔͂��͂�����Ɓu�匠�v�Ƃ������t�Ŏ����Ă���A���{�̂��ꂪ����ɋy�Ȃ��Ƃ����߂���Ă���B�܂��A�u����̍ŏI�I�A���͐폟���ɂ��u�a��c�ɂ���Č��肳���v�Ƃ����I�グ�̕��j�́A�u����n�ʖ���_�v�ƂȂ���A�Ɨ��_�҂ɂ͗L���ł������B
�@��O�ɁA��㏉���ɂ����āA���ڂ̎x�z�҂ł���A�����J�̉���n�ʂ̏����ɂ������鐭��͑N���ł͂Ȃ������B����D�v�ƐV�萷�w�E���Ă���悤�ɁA�A�����J�́u�w����l�͓��{�l�ł͂Ȃ��x�Ȃǂƌ����Ȃ�����A�����Ɨ������悤�Ƃ����悤�Ȑ�����Ƃ��Ȃ������v�i����D�v�E�V�萷��w�������\�N�x1965�j�B���̂悤�ȃA�����J�̑Ή���R����{���j�̕s���m���ɂ���āA�Ɨ��_�̓W�J���\�ƂȂ����B
�@��l�ɁA�{�y���}�̉��ꕜ�A�ւ̏��ɓI�ȑԓx�ł���B�Ȃ��ł��A���̓��{���Y�}���L�����c����̒�ĂŁi���c���w�����Љ�^���j�x1979�j�A1946�N2��24���ɑ�5��}���Łu�����v�v�ʼn�������l�A���ɑ������u���ꖯ���̓Ɨ����j�����b�Z�[�W�v�͂悭�m���Ă���B���{���Y�}�̂��̏����̍l���́A����l���}�≂�����Y�}�̓Ɨ��u���ɑ傫�ȉe����^�����ł��낤�B�܂��A���{�Љ�}�������ɂ͉��ꕜ�A�����ł��o�����i����D�v�E�V�萷���O�f1965�j�A�����}���u���A�����_�v�ɌX���Ă����B
�@��܂ɁA���ۊW�ɂ������̕ω��ł���B����E���̏I���ɂ���āA����ɗאڂ��铌�A�W�A�A����A�W�A���܂ރA�W�A�n��A�A�t���J�n��̋��A���n�͎��X�ƐA���n����������Ɨ����Ă���B��������{�u�鍑��`�v�́u�A���n�I�x�z�v�����Ƃ����������Ƃ�A����ɂ������ƈʒu�Â��邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ɨ��_�͂��������E�A���n��`�̗���ɑ����ꏭ�Ȃ���e������Ă����B
�@�ȏ�̎����ɏ悶������Ɨ��C�^�̍��܂�̍��{�I������T�邽�߂ɁA�Ɨ��_�҂̘_�����ɂ��āA���̎O�̗��j�̍\���I�v��������Ɏw�E�������B
�@�܂��A�����ĉ��ꂪ�u�Ɨ����v�i���̓_�Ɋւ���ю��g�̒��g1609�N�F���̗����N�U�܂ł́u�����͓Ɨ����������v�Ƃ��������́A���{�Ƃ̊W���ӎ����A���ē��{����Ɨ����Ă������Ƃ��Ӗ����ׂ������A�����\���v��ʂ��āu���ؐ��E�V�X�e���v�ɕ�ۂ��ꂽ�����͒�������Ɨ������킯�ł͂Ȃ��A�@�卑�����̑����������̂ŁA�����͏I�n�u���Ɨ����v�ƋK�肷�ׂ��ł��낤�B�������A�F���̐N�U�ȍ~�́A�����́u�Ɨ����v�͂��������ቺ�����ƌ�����B�h�j�ł������Ƃ������j�ւ̋��D�ł���B����́A1429�N�Ɂu�O�R����v�ɕʂ���������������a�����Ĉȍ~�A1609�N�̎F���N�U�܂œ��{�Ƃ̐����I�W�͔�����������A�����𒆐S�Ƃ����u���ؐ��E�V�X�e���v�֑g�ݍ��܂�邱�Ƃœ��A�W�A�A����A�W�A�ƐϋɓI�Ȗf�ՁE�����𗬂�ʂ��Ĕɉh�̎����z�����B�F���ɕ�����������A�����͈ꍑ�̑̍ق��ێ����A1879�N�������{�ɋ����I�ɕ��������܂ő��������B
�c�c
�@���ɁA���{�ւ̑������ł���B�u�Ɨ����������v�͓��{�ɂ���Ėłڂ��ꂽ�݂̂Ȃ炸�A�F����270�N�ɂ���Ԍo�ϓI��您��ѐ����I���A�Ƃ�킯�����I�������܂ޖ������{�ɂ�鈳���A���ʐ��琶�܂ꂽ���{�ւ̉��l�́A���������ȗ��̉���i�V���i���Y�����x����傫�Ȗ������ʂ������B
�c�c
�@��㉫��Ɨ��w���̗��j�̍\���I�v��������ɍl����ɂ́A����Ɠ��{�̂������ɑ��݂��閯�������̂悭�w�E����Ă����u����v����������B���{�Ƃ̈قȂ������݂���A����͒����Ȃǂ̕����̉e�����Ȃ���Ǝ��̉��ꕶ�����`�����Ă����B
�c�c
�@�ȏ�̎���w�i����j�I�v������㏉���̓������x�����ƍl������B�Ƃ��낪�A�Ȃ����̎��������Ɍ���ꂽ����Љ�̓Ɨ��u���́A1950�N��ɓ���ƂƂ��Ɏ���ɑޒ������A�^���ɑ�ւ���Ă������̂��낤���B
�@�܂����ɁA������߂��鍑�ې����̕ω��ł���B���̋��ڂ́A1949�N�㔼����1950�N�ɂ����āA�u�a��c���T�����A�����J�͉������n�Ƃ��Ĉ����Â��������ɓ�������Ƃ������j�����肳�ꂽ�Ɖ���ɂ��`�����n�߂�����ł���B�܂��A���̂���A�����嗤�ɂ����Ă͋��Y�}�������a�����A�u�y�n�ڎ��v��i�߂�A�����J��������P�v�I�ɌR����n�����悤�Ƃ������Ƃɂ������A����ł͈�ʓI�Ɍx���S�������A�������͂�������̊v�V�w�c���q���ɔ��������B����A���{�{�y�ł́A�R����`�v�z�͈�|����A�����͕��a���@�Ɩ����`������悤�ɂȂ����B�����A����̖��剻�͐i�܂Ȃ����肩�A�A�����J�R���{�̌��_�ւ̒e���͂܂��܂����܂����B���̌��ʁA�A�����J�ւ̕s�M�������܂�A�A�����J�̂��Ƃŕ��a�ȓƗ�����n��Ƃ̉\���͌��z�ƈӎ������悤�ɂȂ�A���a�I�u�c���v���{�ւ̌X�����܂����̂ł���B
�@���ɁA�����Ȗ����A�C�f���e�B�e�B�̌`���̎��s�ł���B���������ȗ��A�������{�̓����������炵���̂́A������܂މ��ꕶ���̓O��I�����ł���A����̐l�X�ւ́u���{�l�ӎ��v�̐A�����ł������B�܂��A�ɔg���Q�Ȃǂ́u�������c�_�v�̌��ʂŁA���{���A�u�c���v�Ƃ���F���͂�����Ƃ��č������c���Ă����B���@�����a�̂悤�ȁu��łȓƗ����_�Ɓv����A���{�l�Ɖ���l�́u�e�q�W�v�ł���Ƃ̍l����ے肵�Ȃ�����A�u�����̑c������Z��̊ԕ��Ƃ������ׂ��W�v���Əq�ׂĂ���i���@�����a�u����Ɨ��_�v�w�����o�ρx1951�j�B�u���ꖯ���v�̈ӎ����l�X�ɍ��Â������Ă��Ȃ��������Ƃ́A��㏉���̂�����Ɨ��_�̔s�k�̒v���I�����ł��낤�B��O�ɁA��O�^���̌��@������B���������}�̓Ɨ��_�́A1950�N��̕��A�^���̂悤�ɁA��K�͂ȏ����������s�Ȃ�����A�g�D�I�ȑ�O�^���̔��W�����肷��ɂ͂�����Ȃ������B�����̉���ł́A��������u�����{�̓ƍفv�Ȃǂ̕�����̓I�Ȑ������Ƃ��Ēf�R�d�v�ł������B�������Đ��}���n�߂Ƃ���G���[�g�����������鏉���̓Ɨ��I�v���́A�u�Ɨ��^���v�ł͂Ȃ��Ɨ��_�ɂƂǂ܂����̂ł���B
���тɁu���^�i�V���i���Y���v�̏h���H
�c�c
�@�������A�P���I�ȏ�ɂ킽�鉫��i�V���i���Y���̂��̘A�����́A���ǁu�����I�����v���A����������鉫��̎�̐��̉�������Ȃ������B����́A�u���ꖯ���v�ӎ����ł���A���������ӎ��Ɏx�����Ă��Ȃ������Ɨ��^���͐����I�e���������ł��Ȃ�����ł��낤�B�i�V���i���Y���͋ߑ㍑�Ƃ̒a���ƂƂ��ɏo�������Ƃ����c�_���炷��A���́u���ꖯ���ӎ��v�̐Ǝ㐫�́A�ߑ㍑�ƂɂȂ�O�Ƀ^�C�~���O�悭�u�����v���ꂽ�����E���ꂪ�A���̖����ӎ��̐����̋@���D��ꂽ���ƂɗR������ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����A���含�̂��閯���ӎ��̊��́A���j�I�Ɍ���A���ꂪ����Ă��鑼���I�u�卑�ˑ���`�v�������炵�����̂ƌ����邾�낤�B�����ɕt�f������A�F���ɋA�������肷�鏬�������́u���Ȑ������v�́A�ߑ�ȗ��̉���Ɨ��_�E�Ɨ��^���ɂ����e����Ă���B���̌������ƕK�R���͔ے�ł��Ȃ����A�������n�߉��ď����ɋ~���Q�芈����W�J���Ă����u�����R�������^���v��A�A�����J�̖����`�����ƌo�ϗ͂Ɉˑ����Ȃ���Ɨ����Ă������Ƃ����㏉���ɂ����鏔���}�̓Ɨ��w���A���邢�͂��̌�̗������a�}�A���������}�̓Ɨ��_�̂�������������x���̐��i��ттĂ����B���łȎ��含���������Ă��邱�̉���i�V���i���Y�����u���^�i�V���i���Y���v�ƕ\�����Ă悢���낤�B�Ȃ��Ȃ�A���̐��i�́A���̎���I���Ăł͂Ȃ��A�l�̑���ɗ���Ȃ��玞�̕������ɂ��������Ĕ�ԑ��̎p�Ɏ��Ă��邩��ł���B
�@�������ɁA�u�ߑ�v�͗����N��x�g�i���̂悤�ȓ������A�W�A�̂��Ắu�Ӌ��v�̂悤�ɋߑ㍑�Ƃɐ�������@���^���Ȃ������B�������A����Љ�ɓ��{�l�A�C�f���e�B�e�B����{�i�V���i���Y������ł͂Ȃ��A�����㉫��Љ�̈�̉��͑O�ߑ�ɂ͕��Չ����Ȃ������u����l�v�ӎ��≫��i�V���i���Y���̐������������Ă����B���̓_�́A�{�_�̗p���鉼���̂ЂƂł���A�G�X�j�V�e�B�́u�ߑ㉻�̋t���v�����̑Ó��������߂Ďx���Ă���ƌ����悤�B
�@�Ƃ���ŁA����́u�卑�ˑ��v�Ƃ����u���^�i�V���i���Y���v�̐��i�́A���Ɂu�O�ߑ�v�́u�Ӌ��I�h���v�̉e��Z���ɏh���Ă���B����������A�����̉�����A������Ƃ��āu�O�ߑ�v�Ɓu�ߑ�v�A�����āu�����v�Ɓu���Ɓv�ɖ|�M���ꂽ���j�I��Ԃɒu����Â��Ă���̂ł���B
�c�c
��R�� �u�c�����A�v�Ɓu�����A�v�\�\����A�C�f���e�B�e�B�̏\���H
��P�߁@����A�C�f���e�B�e�B�̎j�I������
�c�c
�@�u���������v�̘_���ɂ����{���{�́u��������v���u���{������v�̋����I���s�ɂ���āA�ߑ�ȗ��A����̒m���l�▯�O�͎���̃A�C�f���e�B�e�B���߂����ċ�Y������A�܂����Â��Ă����B���̊�������A�C�f���e�B�e�B�̊�{�I�\�}�́A�u���{�l�v���u����l�v���A�Ƃ������̂ł���B�O�҂́A�u�������c�_�v�ʼn���Ɠ��{�̃G�X�j�b�N�N���̋��ʐ����ې�������A�ߑ�I���{�Љ�ւ̍����ɂ�錻���I���v����������B����́A�G�X�j�V�e�B���_���猩��A�{���I�J���咣���錴����`�Ɨ��v���������铹���`�̍����̂ł���B����A��҂́A����Љ�̗��j�I�n�������ł���12���I�ȍ~�Ƃ�킯����������̓��{�Ƃ̈قȂ����j�I���݂�Ǝ������d������Ɠ����ɁA�F���̌o�ϓI���Ƃ����u�Í��̎���v��A�ߑ�ȗ����{�Љ�ɑg�ݍ��܂ꂽ�ߒ��ɂ�����u��a�l�v�Ƃ̐ڐG�ɂ���Ď����ʂ̌o���A�����āu�����v�Ŏ���œI��ɂ��������Ă���B�܂��A��҂́A���{����̗��E�����̗��j�̏I�����Ӗ����邱�Ƃ��咣���Ă���B������܂��A���͑O�҂Ɠ��l�A�{���_�Ɨ��v�_�̍��̂ł���B��������A���̃A�C�f���e�B�e�B���D��ɂ������̗���ɋ��ʂ��Ă���̂́A����������j�I�L���Ɨ��v�̑I���ł���B�ł́A���@�⒅��_����v���Ă���ɂ�������炸�A�Ȃ��A���ӎ��ɂ����đΗ��I�\�}�������Ă����̂��B����́A����̏W�c�́u�ߋ��v�Ɋւ���L���̑I����@�A�܂����_�I����������I�����b�g���܂߂����v�̑I����@�̑���ɗR������̂ł��낤�B
�c�c
��Q�߁@�C�f�I���M�[�Ƃ��Ắu�c�����A�^���v
�c�c
�Q�u�w�v�V�x�I���ΐ���O�^���v�Ƃ��Ắu���A�^���v
�@�ȏ�̂悤�ɁA�u���A�^���v�͂قڎl�����I�Ƃ��������Ό��Ői�s�����A���l�ȓ��e���܂���^���ł���B���������āA���̐��i�̌����͂������ėe�Ղȍ�Ƃł͂Ȃ��B�Ƃ͂����A�^���Ɍ���ꂽ�����Ƃ��N���ȓ����́A��ʂ̏Z�����^���Ɋ������܂��Ƃ����u��O���v�ł���B�����ɁA���̐��ȓ����͂�����ʂ̏Z���ɒ����Ό��ɂ킽�肻�̃G�l���M�[���^���ɓ��������������Əd�v�Ȍ����͂́A�C�f�I���M�[�I�ȗv���ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��ł��낤�B�ł���Ȃ�A�u���A�^���v�����ő�̌����͂Ƃ��ẴC�f�I���M�[�Ƃ͂Ȃ낤���B�����Ƃ��Č��_���ɏq�ׂ�A����́A�u�Љ��`�I�w�v�V�x�v�z�v�Ɓu���{�i�V���i���Y���^���v�Ƃ�����̊�́A����u���A�^���v�̐��i��\�����̂Ƃ��Ă����Ƃ��I�m�Ȃ��̂ƍl������Ƃ������Ƃł���B
�@�܂��A�u���A�^���v�̂ЂƂڂ̊�ł���u�w�v�V�x�I���̐���O�^���v�Ƃ͂����Ȃ���̂ł��낤���B�������A�A�����ɂ����āA�u���{���A��]��ł����v����̏Z���́A���Ȃ炸����������u�v�V�v�h�ɑ����Ă����Ƃ͌���Ȃ��B�������A��O�^���Ƃ��Ắu���A�^���v�̎�̂́A�u�v�V�v�̐��i��N���ɑттĂ��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B���ɁA���������^�����ǂ̂悤�Ȑ��}��g�D�ɂ���ă��[�h����W�J���ꂽ���A�^�����e�����ɕ�����ۑ��A��O������ɓ������Čf���Ă����X���[�K���͂����Ȃ鐭���I�C�f�I���M�[�����܂�ł������A�ȉ����炻�́u�v�V���v���l�@���Ă݂�B
�@�܂��A�u���A�^���v�̎w���Ҋi�ɓ�����g�D���T�ς��Ă݂悤�B�O�q�����悤�ɁA�����i�K�́u���A�^���v���e�ɓ�������̂́A1951�N�̏����^���ł������B���̏����^�����n���������̂́A�قڂ��̒��O�ɑg�D���ꂽ�u���{���A���i������v�Ɓu���{���A���i�N���u��v�ł���B�O�҂́A���X���O�̎Љ��O�}�i�ȉ��A�u�Б�}�v�Ə̂��j��O�q�}�ł��鉫��l���}�i�ȉ��A�u�l���}�v�Ə̂��j�𒆐S�ɔ����������̂ŁA��҂͉���N�A����𒆐S�Ƃ������̂ł���B�v����ɁA�u���A�^���v�͍ŏ����炷�łɁu�v�V�F�v��L���Ă���̂ł���B
�@���̌�A�u���A�^���v�̑��i�K�ɓ�����1953�N�ɁA����N�A����≫��w�l�A����ȂǂT�c�̂̋��͂Łu���ꏔ���c�����A������v�i������j����������A�u���A�^���v�̐��i��S���悤�ɂȂ����B���̑g�D�̕M���i�́A���̑O�N�ɐݗ����ꂽ�u�v�V�F�v�Z���ȉ��ꋳ�E����ł���B���̎����̊�����́u���A�^���v�𐄐i���Ȃ�����A�u�ČR��n�ɔ����闧��ɂ͂Ȃ��v�ƕٖ����i����D�v�w��㎑���E����x1969�j�A�Ė����{���̑g�D�Ƃ��ẴC���[�W�蒅���ɗ͔����悤�Ƃ��Ă����B�Ƃ͂����A�Ė����{����́A��͂�u���Y��`�I�Ȃ��́v��u�����{���v�̒c�̂ƌ����Ă����悤�ł���i����j�B���ہA���̎����̊�����S�����u�ꊇ�����v���́u�y�n�����v��u���A�^���v�e���ւ̔��������Ȃǂ���݂�A������́u���̐��F�v�Ɓu�v�V�F�v�͂ނ���܂��܂��Z���ɂȂ����ƌ�����B
�@1960�N��ɓ����Ċ�����́A���̌v17�c�̂̋��͂Ŕ��������ő�̕��A���i�g�D�ł���u���ꌧ�c�����A���c��v�i���A���j�ƍ��������B���̕��A���ɎQ���������̎�Ȓc�̂́A�}�Ƃ��Ē��ڂɉ��������}�̎Б�}�A�l���}�A����Љ�}�i�ȉ��A�u�Љ�}�v�Ə̂��j�A�����ĉ��ꊯ���J���g���Ȃǂł���B�����A���A���͗^�}�̎����}�ɎQ�����Ăт��������A�����}�́u�]���A�c�����A�^���Ȃ���̂́A�ꕔ�̔��Ď�`�҂ɗ��p���ꂽ����݂�����v�Ƃ��Ă�����{�C�R�b�g������j���̂����B�����āA�����}����ё��̕ێ�n���͂́A������Ƃ���1956�N�Ɏ����}������ʈψ���̌ۓ��Ō������ꂽ�u������E�����v�Ȃǂ̂��ƂŊ�����W�J���邱�ƂɌŎ������i���ꋦ��w�쉇17�N�̕��݁x1973�j�B�������A���̑g�D�́A�����u�������v���J���A�f���s�i���s�Ȃ��Ă������A���ƈقȂ�A��O�^���̃C���[�W���m���ł����A�u���A�^���v�̖T���I���݂ɂ����Ȃ������B������ɂ���A�ێ�n�����̕��A�������o�[�̊�U��́A�����I�u�v�V��F�v���蒅���Ă����B
�@�ނ��A�u�v�V�v�e�h�̋����́A�u���A�^���v�̐��i�݂̂Ɍ��炸�A���̐����I���͂�����������B���Ƃ��A�u���A�^���v�̂ЂƂ̐��ʂł����Ȍ��I���F�߂��A1968�N11���̗��@�@�c���ƂƂ��ɏ��̎�Ȍ��I���s����ɓ�����A���E����Ɩ�}�e�}�̂��ƂɁu�v�V������c�v���g�D����A����j�̂��̑����ꂽ�B�u�v�V�v�w�c�̂��̂悤�ȑ��p�I�������͂́A�u���A�^���v���u�v�V�����v�Ƃ����C���[�W�ɍ��o��^���Ă��܂����̂ł���B
�@������ɂ���A���̂悤�ɂ��āA���X�������������i��ł������A���̂��ƂŁA1960�N�ɓ����Ă���́u���A�^���v�́u�v�V���v�u���̐����v�u��O���v�������Ƃ��ɑN���Ɍ���Ă������B���̂悤�Ȑ��i����A�u���A�^���v�͈��́u�w�v�V�x�I���̐���O�^���v�ƋK�肷�邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�@�������Ȃ���A�u���A�^���v�̎Љ��`�I�u�v�V���v����V�I���E��L���Ă����B�Ƃ����̂́u�c�����A�v��O��Ƃ��Ă��̉^���́A�̂��ɏڏq���邪�A�ŏ�����i�V���i���Y���Ƃ��������ЂƂ̃C�f�I���M�[��������Ă�������ł���B�u�J���҂͑c���������Ȃ��v�ƃ��[�j�����w�E���Ă���悤�ɁA�Љ��`���̐��^���́A���Ƃ�����K�����ɒ��Ⴕ�����ۓI����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āA�u�����E���Ɓv�̗��v��ΏۂƂ���i�V���i���Y���Ƃ͍��{�I�ɑ��e��Ȃ��͂��ł���B�������ɁA��㑽���̐A���n�ɂ�����Љ��`�v�����A������`�Ƃ�����œW�J���ꖵ�������v�f���܂�ł���B�������A������`����i�Ƃ��������̐A���n�ōs�Ȃ���Љ��`�v�����A����Ƌt�Ɂu�c�����A�v�Ƃ����i�V���i���Y������o�����Љ��`�̃C�f�I���M�[����i�Ƃ��鉫��ɂ�����u�w�v�V�x�I���̐���O�^���v�̕�܂��閵���͖{���I������Ȃ��̂ł���B���������u���A�^���v���L���Ă���̎��́A���̖{���I�����������ł��Ȃ����̂ł���ƌ����Ă悢�B
�@���̂悤�ȑ̎��̂��ƂŎ�i�Ƃ��ė��p�����u���A�^���v�̎Љ��`�I�C�f�I���M�[�́A�u�I��I�C�f�I���M�[�v�ƈʒu�Â����悤
�R�@�u���{�i�V���i���Y���^���v�Ƃ��Ắu���A�^���v
�@������ɂ���A�u���A�^���v�͂��̒S����̐����I�����₻�̌f����C�f�I���M�[�v�z����݂�A�u�w�v�V�x�I���̐���O�^���v�̐��i��L���Ă��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�������A���̐����I�ۑ��C�f�I���M�[�G�ɗ��߂��u���A�^���v��i�߂��嗬�h�ƈ���āA��嗬�Ƃ��Ĕ�r�I�P���ɉ���̓��{���A��������l��g�D�����݂��Ă����B���������āA�B��A�u���A�^���v�̎嗬�h�Ɣ�嗬�h�Ƃ̂������ŋ��L�ł�����̂́A�{���̊�{���O�ł���u����͑c�����{�A��ׂ����v�Ƃ����u���{�i�V���i���Y���v�̐��i�݂̂ł���B
�c�c
�@���ہA�u���{���A�v�����قƂ�ǂ̎҂̗��r�_�́A��͂�u����l�����{�l�v��u����͓��{�̈ꕔ�ł���v�Ƃ��������ɂ���B����̓��{���A�����������I�풼���1945�N�W���S���ɉ���̕ČR�i�ߊ����̕��A�Q�菑�ɂ����Ď��������g�nj��́A���A�̗��R���܂��u����l�͓��{�l�ł�����v�i���g�nj��w����c�����A�^���L�x1964�j�Əq�ׂĂ���B�܂��A1951�N�Ɏ��̎Б�}���L���̌���������u����l�͑�a�����ł���v�ƁA����������̉H�n���G�i���ی�1617�\1675�j�́u�������c�_�v�����߂��A���������āu���{���A�͐l��̎��R�v�Ǝ咣���Ă���i��������u���{���A�͐l��̎��R�v�w�����o�ρE10�x1951�j�B�v����ɁA�u����l�E���{�l��̉��v�̖����Ƃ��Ȃ�́A�u���A�v�҂���щ^���҂��Ƃ��ɂ߂�������{�I���O�Ȃ̂ł���B�c�c
�S�u���A�^���v�̃C�f�I���M�[��
�@����A���ڂ��ׂ����ƂɁA�u����̓��{���A�v�͖{������̋A�����Ɋւ���ЂƂ̑I�����Ő��}�̂ЂƂ̐����I�咣�ɂ����Ȃ������͂��ł��邪�A�u���A�^���v�̒S����Ƃ��Ă̏��v�V���}�́A����𑼂̋�̓I��������Ɠ���ɂ͂����i�ʂȒn�ʂƂ��Ĉ����Ă����B�u���ꌧ���Ƃ��Ă͌����̐����̑P���ɂ�����炸�c���ɕ��A���邱�Ƃ����������̎{��̎w�����ׂ������ڕW�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ���1964�N���_�ɂ�����u���A���}�v�ł���Б�}�̎咣�������ڗđR�ł��낤�B��������A�ЂƂ̐����I�ڕW�ł���͂��́u�c�����A�v�́A����ɐ��}�̂ق��̐����I�ۑ�ɗD�悳��������ɐi�B�ۂ���ɂƂǂ܂炸�A���ׂĂ̍s���𗥂���ЂƂ̃C�f�I���M�[�܂ŏ��i��������悤�ɂȂ����̂ł���B
�@���́A���v�V���}�̊�{�I�����I�����ł���u�Љ��`�I�w�v�V�x�v�z�v�ƑN���ȃi�V���i���E�A�C�f���e�B�e�B�Ƃ��Ắu���{�i�V���i���Y���v�Ƃ�����̃C�f�I���M�[�̔����ȑg�ݍ��킹�̂����Ő��������C�f�I���M�[�́A���̉^���̂����Ƃ���{�I���@�ł���u��O�̓����v�ɂ���āA1960�N��ɓ���A�Ƃ���60�N��̔����납����ȃp���[�����悤�ɂȂ����B�����āA���́u���A�^���v�̃C�f�I���M�[���́A����̋A�����߂����āu���{���A�v�ȊO�̈قȂ����v�z�Ǝw�������ނ悤�ɂȂ����B����������A�u���{���A�_�v�ɔ�����A���_�͒����Ԉ��̃^�u�[�ƂȂ�A����ɂ��̑��݂ł����Ԃ��啝�ɏk������Ă����̂ł���B
�@�������A����n�ʂ̏������߂����āA�u���A�_�v�ƑΒu����u�A�_�v���邢�́u�����A�_�v�͒ꗬ������Ă����Ƃ͂����A�������Ċ��S�ɏ����Ă����킯�ł͂Ȃ��B1960�N�㔼�Έȍ~�A�Ƃ��ɓ��č��ӂɂ���n���������肳��A���N�́u��n�����v�͔s�F���Z���ɂȂ���1968�N���납��A�u���A�^���v�͓��h�������n�߁A�����钧��������Ȃ��s�N�ȃC�f�I���M�[���ւƔ��W���Ă����u���A�v�z�v���A�悤�₭���߂Ĕ��Ȃ̒i�K�ɓ������B���̂悤�ȏ�ω��̂Ȃ��ŁA�ꗬ�ł������u�A�_�v���邢�́u�����A�_�v���}���ɕ��サ�A���̏����̋�Ԃ��^���\�Ȕ͈͂܂ň�C�Ɋg��ł���悤�ɂȂ����̂ł���B���������ȗ��O�x�ڂ́u����i�V���i���Y���v�̏o���ł���B
��R�߁u�����A�^���vI�|�u���A���Ș_�v�̎v�z�\��
�P�u�����A�_�v�̒�`
�@�]���A1960�N�㖖���猻�ꂽ�A�u���A�^���v�ɑΏ����u���A�v�ɔ����铮���́A�u�����A�_�v�Ƃ���A��㉫��̂ЂƂ̎v�z�I�����Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă����B�ނ��A�u�����A�v�̓����́A�قډ���S���Ȋ�����u���A�^���v�̑�O�^���Ƃ��Ẵp���[�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��B�������A�u�����A�v�̓����́A�������ď����Ȏv�z�I�u���Ș_�v�Ƃ����v�����x���݂̂ɑ��݂������̂ł͂Ȃ��B�u���A�v�ɔ�����g�D�̌�����X����`�A���������A�����č����I�����ۂ̌Ăт����Ƃ��̌ĉ��܂ŁA�^���̃��x���͊g�債���̂ł���B���������āA���̓������u�����A�_�v�����u�����A�^���v�ƌď̂����������K�ł͂Ȃ��낤���B
�@���āA���̐����I�^���ƘA�����C�f�I���M�[�I�ɂ����G�������u���A�^���v�قǂł͂Ȃ����A�u�����A�^���v�̒�`���������ĊȒP�ȍ�Ƃł͂Ȃ��B������܂��A���`�ƍL�`�̗������猟�����邱�Ƃ��ł���B�܂��A���`�Ƃ��Ắu�����A�^���v�́u���A�^���v�ɒ��ڂ��A�u���한�A�v�̔s�k�ň�C�ɕ��サ���A�����ʂ�u���A�_�v��u���A�^���v�ւ̔��ȂƂ��Ă̓����ł���B�������A���̒�`�́A�u���A�^���v�̎���ł���u�v�V�v�w�c�����݂̂ɒ��ڂ��A����ƘA������o�ϊE��ێ琨�͂́u���A�����_�v�A�����āu���A�^���v�̍��g�Œꗬ����]�V�Ȃ����ꂽ�]���̓Ɨ��E�����u���́u����i�V���i���Y���v�̓����������Ƃ��Ă���B���������āA�L�`�Ƃ��Ắu�����A�^���v�́A�@�u���A�v�^���҂Ȃ����u���A�^���v�Q���҂̎��Ȕ��Ȃ���́u���A���Ș_�v�A�A�����������瑶�݂��o�ϓI���v�̎����o�������ێ�h�́u���A�����_�v�A�����ćB�ĕ��o�����]���́u�����E����Ɨ��_�v�A�Ƃ����O�̗���́A�u����A�C�f���e�B�e�B�v�̋����Ƃ������ʂ̎�i��ʂ��Ĉ��̒��x���ݓI�Ɍĉ����������A����܂ł́u���A�^���v�Ƒ������闣���w���̓����ł���A�ЂƂ́u�����I�w����i�V���i���Y���x�v�̔g�ł���B
�Q�u���A���Ș_�v�̓���
�c�c
�@���́u�����A�v�̘_�w����Ă����̂́A��������̗B��̑������ł���w�V���ꕶ�w�x�ł���B�����̑�18���i1970�N12���j��19���i1971�N�R���j�͘A�����āu�����A�_�v�̓��W��g��Łu�����A�_�v��W�J���Ă����B���������u�����A�v�Ƃ������t�̏��o�́A���̓��W�ɂ���i�V�얾2000�j�B
�@���̓��W�̂ق��A�u�����A�_�v�̕M���i�Ɩڂ��ꓖ���́w�V���ꕶ�w�x�̕ҏW���ł���A���l�E�W���[�i���X�g�E�v�z�Ƃł��������V�얾��1970�N�P���P������w����^�C���X�x�̘A�ڊ��ł���u�����70�N��v�ō��v21�M���s�Ȃ��Ă����B���̎��M��ʂ��ĐV��́u�����A�v�z�v���������Ă����A���̏W�听�ƌ����ׂ��_�W���w�����Ƃ̋���x�i1972�j�Ɏ��߂�ꂽ�B�u���ꎩ���̌o�T�v�Ƃ��̂����ނ̂��̉���I�Ȓ���́A�ގ��g�̌��t�ɂ��A�u�c�c�i���A�^�����j���������̒��ŁA�w���A�x�v�z�����{���ւ̓����u�������݂�����v�z�̕a�������Ȃ�ɍl���߂Ȃ���A�a���̐؏����u���v�����̂ł������B�����́A�u���A�v�z�v�a���̍����ł���u���Ɛ�Ύ�`�v�Ƃ��̎Y���ł��鉫��l�́u���Ȕډ��E�����`�v���S�O�Ȃ��̔ᔻ���s�Ȃ��������ŁA�u����A�C�f���e�B�e�B�v�̉Ɣ����͓I�������_��L��������̊m������Ă���B
�@����A�������l����o�������얞�M���1969�N�Ɂu�]�����ɗ����ꓬ���\�\���A�̃X���[�K�����̂Ă�I�v�i�w��x�W���j�A�����āu����\�\�������̎v�z�v�i�w�f���]�x�V�����A1971�N�j�Ƃ������_���\���A�u�c�����A�v��u�����v�v�z�ւ̒ɗ�Ȕᔻ��ʂ��āu���ꎩ�����_�v�̊m����i���Ă���B���̎v�z�I���݂́A�̂��ɏo�ł����w����E�����Ƌ����̎v�z�\�\�u�����̓ꕶ�v�ւ̉˂��鋴�x�i1987�j�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�����A�V�얾��얞�M������Ⴂ����ɑ����邪�A�u�����A�_�v�ɂ����Ă͐�s�Ș_�q�Ƃ��Ēm���Ă���̂́A���@���E�ł���B�u���ꏭ���h�v�����̂��鎁�́A�u����̈⏑�v�i1972�j�ȂǂŁA�u�w�c�����A�^���x���A���ՂȖ��O�ӎ��𗧋r�_�ɁA���Ƙ_�����������������ɖ��O�̖{�y���{�ւ̋��܂������O�𖢐����̂܂܊|������ł����v�i���@���E1972�j�Ƃ܂��u���A�^���v�̘c�݂ɂ������A�S�O�Ȃ��ᔻ��W�J���Ă����B���̌�A���@���E�ق��́u���A���Ȕh�v�Ɠ��l�A�u���A�v�z�v�ւ̔ᔻ�ɂƂǂ܂炸�A�u���}�g�v�ƑΉ�����u���܂�ւ问���l�v�̒Ɍ��т��Ă����B����ł���w���ꏭ���h�x�i1981�j�͒��@���E��60�N��ȗ��̎v�z���W�Ă���B
�@�u���A���Ș_�v�́A���̎v�z�I���H�Ƃ��āA1970�N11��5���ɍs�Ȃ�ꂽ�����Q���I���{�C�R�b�g��i���Ĕ��Ή^����W�J���A�������n�̏��g�D���ĉ����Ĕ������Ă�ł������A�u����Ԋҁv�͂��łɌ��肳�ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA���u�v�V�v�g�D�����̒�R������A�����Ă�������������Ƃ��āu�o�����Ă��Ȃ��v��O���������݂��Ă������߁A��K�͂ȁu�����A��O�^���v���ł��Ȃ��܂܁A�u�Ԋҁv���}���邱�ƂɂȂ����B
�R�u���A���Ș_�v�̎v�z�\��
�@�������A�V�얾���n�߁A�얞�M��A���@���E�Ȃǁu���A���Ș_�v�̑�\�҂������S�O�Ȃ��u�����A�v�z�v�́A�u�����A�^���v�Ɉˋ������闝�_��������ƂŁA�����ȉe�����y�ڂ����݂̂Ȃ炸�A1972�N�̕��A������݂ɂ�����܂ʼne���͂����Â��Ă���ƌ����悤�B�u���A���Ȕh�v�ɑ�����ׂ��V�얾��̊�{�I�v�z��Ղ́A��Ɏl�̒����琬�藧���Ă���B���Ȃ킿�@�����̍��������ƁE�����E���́E�鍑��`�ɋ��߂�ׂ��A�A�u���A�^���v�̒��ڂ̕a�ł́A�@�̔��e�ɓ��鑼���I�Ƃ������������I�u������`�v�ł���B�B���{�l�ɂ�������u�َ����E���ӎ��v�����Ȕډ��⎖���`���������A���{���̍��ƌ��͂𑊑Ή�����v���X�̃p���[�����L���Ă���A�C����A�C�f���e�B�e�B���݂̐������́A���ꎩ�̂̎�̐��Ɏg�p��������A���ƁE�����E���́E�鍑��`�ɔ����镐��Ƃ��Ă̈Ӌ`���傫���A�Ƃ������Ƃł��낤�B
�@���̂S�̒����������������悤�ɁA�u���A���Ș_�v�̑��́u���A���Δh�v�ɂȂ���ȓ����́A�܂�������Ƃ��āu�鍑��`�v�ɔ�����u�v�V���v����������B���ɁA�u���A�^���v�𗯕ۂȂ��ɒɗ�ɔᔻ���Ă��邪�A�u����̐����I�Ɨ��v�Ɋւ��閾���Ȓ�������Ă���B��������A�u���A���Ș_�v�́u���A�^���v�ւ̔��ȁE���Ƃ���ɑ�������w�j����Ă��邪�A��̓I��������̒܂ŕK�������s�����A��{�I�Ɏv�z�̃��x���ɂƂǂ܂����̂ł���B����́A�u���Ɓv�Ƃ����ŋ��̐����I���u�܂łɔ�����ȏ�A����̐����I��̐��m���̍ŏI�I�w�W�ł���u�������a���v�Ƃ����V���ȁu���Ɓv�̌��݂ɖ����������邩��ł���B�u�Љ��`�I�w�v�V�x�v�z�v�Ɓu���{�i�V���i���Y���v�Ƃ̖����Łu�\�������v�u���A�^���v���狳�P���u���A���Ș_�v���A�u�������a���v�ł͂Ȃ��A�B���Ŕ��I�ȁu�������a�Љ�v�����������Ȃ��������Ȃł���B����́u���A���Ș_�v�̐i�����ł���A���E�ł��������B
�@�������u���A���Ș_�v�҂́u���ƁE�����E���́E�鍑��`�v�Ƃ����u�v�V�v�z�v����u���{���v�Ƃ����u���Ɓv�ɖҔ������Ă���ɂƂǂ܂炸�A�u���}�g�i�l�j�v�Ƃ̑Ό��p�����͂����肵�Ă���B��҂��x���Ă���̂́u���{�i�V���i���Y���v�Ƒ�������u����A�C�f���e�B�e�B�v�ł���B���������āA�u���A���Ș_�v�̋���Ȕ��u���}�g�i�l�j�v���_����l����A���ꂪ�_���I�ɓƗ��_�ւȂ����Ă��������ĕs���R�ł͂Ȃ��B�����āA�u���A���Ș_�v�i�u�����A�_�v�j�ƓƗ��_�Ƃ̊W�ɂ��āA�V�얾�͋ߒ��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�w�����A�x�_�́A���Ԃł����Ό����Ă���悤�Ɂw�Ɨ��x�_�̓��`��ł͂Ȃ����A���҂����ڂɏd�Ȃ荇�����������L���Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B������w�Ɨ��x�_�́A�w�����A�x�_���咣������{���𑊑Ή����鎋�_����荞��ŁA���̉^���_�̑���ɂ��邾�낤���A�w�����A�x�_���咣����l�́A�����̐����I�I���ɂ����āw�Ɨ��x�_�ɋ�����W���������邩��ł���v�Ɓi�V�얾�w����E�����Ɣ��t�x2000�j�B
�@�������ɁA�u���A���Ș_�v���v�z�I�ɓƗ��_��⋭����������ʂ����Ă������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�������A����̓Ɨ��_�́A1960�N�㖖�Ɂu���A���Ș_�v���o�ꂷ��܂ł̋ߌ���̒������j�̑�͂ɂ��łɑ��݂��A60�N�㖖�ɍL�`�́u�����A�^���v�̂ЂƂ̗���Ƃ��čĕ��o�����̂ł���B����ԊґO�́u���A���Ș_�v�ƓƗ��_�Ƃ̊W�́A�v�z�I�r�W�������������ʂƐ����I�ڕW�̋����i���鑤�ʂƂ̏_��ȕ⊮�W�ɂ���ƌ����ׂ��ł��낤�B
��S�߁@�u�����A�^���v�U�|�u���A�����_�v�ƓƗ��_�̕���
�P�u���A�����_�v�o���̕���
�@1960�N��̖��Ɍ��ꂽ�u�����A�^���v�̎O�̗���̂Ȃ��ŁA��r�I�嗬�ł���̂́A�u���A�^���v�̃p���[�̈ꕔ���z�����u���A���Ș_�v�ł���ƌ�����B�������Ɂu���A���Ș_�v�i�u�����A�_�v�j�́A���Ƃւ̍��ꉻ���Ƃ��ē��{���A���ۂ��咣����_�ŁA���́u���A���Θ_�v�Ƌ��ʂ��Ă��邪�A���̐��i�͑����݂̌��ɑ��ق������ʂ�L���Ă���B
�@�u���A���Ș_�v�Ƒ��̕��A���Ή^���̗��h�Ƃ̂����Ƃ��d�v�ȑ��ٓ_�́A�O�҂��u�v�V�v�w�c����ďo���������̂ł��邪�A�u�v�V�v�z�v��������Ƃ��ĔZ���ɑттĂ��邱�Ƃł���B���̈Ӗ��ł́A���́u�����A�v�̗���́A���̊�{�I�����C�f�I���M�[�̐��i����l����u��v�V�n�v�Ȃ����u�ێ�n�v�ɕ��ނ���邱�ƂɂȂ�B
�@���āA���́u��v�V�n�v�́u�����A�v�̓����́A���̖{�����炳��ɕ�����A�Q�̎x���ɂȂ�B�ЂƂ́A�Ԋ҂����܂��Ă���A�}���サ���o�ϊE��ꕔ�̕ێ�n�����Ƃɂ��u���A�����_�v�ł���B�����ЂƂ́A���i�I�ɁA�m�ł���u����A�C�f���e�B�e�B�v����o��������㏉���̓Ɨ��_�Ǝ��n�I�����ȂȂ����L����1950�N��ȗ��̏��Ɨ��̓����ł���B
�c�c
�Q�@1950�\60�N��Ɨ��_�̐���
�@�u��v�V�n�v�Łu�����A�^���v�̂�����p���߂��̂́A����i�V���i���Y���̎˒��ɓ��鐭���I�ڕW�Ƃ��Ă̓Ɨ��_�ōČ��ł���B
�c�c
���тɁ@�u�c���v���߂���u���A�v�E�u�����A�v�̋L���E�z���\���Ɖ���A�C�f���e�B�e�B�̓���
�P�@����ɂ�����L���̑n��
�@�G�X�e�j�V�e�B�_�̌�����`�A�v���[�`���咣����A���Ȃ킿�G�X�j�b�N�E�A�C�f���e�B�e�B�́A�̂╶���̓����A�����W�Ƃ������u�q�ϓI�v�u���j�����v�ɂ���Č`�����ꂽ�Ƃ��������A�������^���������͋��\���ꂽ�G�X�j�b�N�N���E���j�⌻�݂̎Љ�I�̌��Ȃǂɂ���č\�����ꂽ�u�W���I�L���v�ɍ��E�������̂ł���A�Ƃ����u�L���_�v����㔪�Z�N��ȗ����ڂ������B����͖{�����ێ�����G�X�j�b�N�E�A�C�f���e�B�e�B�����̗v���Ɋւ��闧��ł�����B���́u�W���I�L���v�͂������Đ��܂���ŕs�ςȂ��̂ł͂Ȃ�����Ȃ����n���\�Ȃ��̂ł���B�Ƃ�킯����ɂ����Č���ꂽ�`�ԑ���ȃA�C�f���e�B�e�B�́A���́u�L���v�̑I���A����A�n���ɂ��Ƃ��낪�����ƌ�����B�ł́A�Ȃ��A�C�f���e�B�e�B��n������͂�L���Ă���u�W���I�L���v�ɂ����āA�K�������^���ł͂Ȃ��u�G�X�j�b�N�N���v��u�G�X�j�b�N�W�c�̗��j�v���d�v�ƂȂ�̂ł��낤���B����́A�l�Ԃ̂������ɑ��݂�������Ƃ����ł��J�́A�����Ō��ꂽ�l�ԊW�ł��邽�߁A�u���ʂ̃G�X�j�b�N�N���v��u���j�I�o���v���������邱�ƂŁA���̋[���I�u���E���v��z���������Ԃ�^���邱�Ƃ��ł��邩��ł���B
�@���āA����̏ɖڂ�]���Ă݂悤�B�u���A�^���v�Q���҂̂��u���{�l�A�C�f���e�B�e�B�v�̑O��́A�u����l�͓��{�l�ł���A����͓��{�̈ꕔ�ł���v�Ƃ������Ƃł���B����́A�u���{���v���a������O�̐�j����ɂ����āA�u����l�͓��{�l�̈ꕪ�Ŏx�ł���v���ƁA���ꂩ��H�n���G�i���ی��j�́u�������c�_�v�I�L�q��A�ɔg���Q�炪���U�������āu�ؖ������v�u������͂��߉��ꕶ���͓��{���������^�Ƃ��Ă���v���Ƃ����̂܂ܐM���Ă��邩��ƌ�����B����A�u�����A�_�v�҂�Ɨ��_�҂́A�t�Ɂu���{�l�v�Ɓu����l�v�̈Ⴂ���������A�����Ɨ������Ƃł�����y���R���i�g�Ȃǂ́A�u�����l�͓��{�l�ł͂Ȃ��v��u���{�͑c���ɔv�������Ă���B���̍����́A�u����͗��j���n�܂��Ă��璷���ԓƎ��̎Љ���ĉ�����L���Ă����v���ƁA�����Ă���������{�ƈقȂ����Ǝ��̕��������悤�ɂȂ������ƂȂǂɋ��߂��Ă���B
�@���҂��������Ă���A�܂�������������u���j�I�����v�́A���̂悤�ɈقȂ����A�C�f���e�B�e�B�����o���̒҂ɂ���đI������A����̃G�X�j�b�N�N���̐��������咣���Ă����̂ł���B����́A�G�X�j�b�N�̋N�����A�l�ԏW�c�̃A�C�f���e�B�e�B�ɂƂ��Ă����ɏd�v�ł��邩�Ƃ������Ƃ���Ă���Ɠ����ɁA�l�ԏW�c�́u���j�v�́A�����Ɏ���̂��ړI�ɂ���đ��삵�n�����ꂽ���Ƃ������Ƃ������Ă���B���ہA�Ƃ�킯�ߌ���̉���ɂ�����u���{�l�v�A�C�f���e�B�e�B�̌`���Ɍ������Ȃ��u����l�v�Ɓu���{�l�v�́u���ʂ����l�ԏW�c�v�ł���Ƃ������Ƃ������O�Ɂu�L���v�����邽�߂ɁA���{�ꋳ�炨��эc�����ɂ��A�G�X�j�b�N�}�[�N�ł���u�����F�v�̏�����Ƃ��A���������ȗ��s�Ȃ��Ă����B����ɂ����邱�̃G�X�j�V�e�B�̏�����Ɓi�u�E�������v�j�ƐV���ȃA�C�f���e�B�e�B�̐A������Ɓi���{�l�ӎ��̌`���j�̓����́A���ƌ��͂�w�i�Ƃ����ォ��̋����ɂƂǂ܂炸�A����G���[�g�ɂ��ƏZ���̋��͂Ƃ���������̓w�͂��������A�Ƃ������Ƃł���B
�@���̂悤�ȋ��͂Ȉ�̉���Ƃ̌��ʁA����Љ�ɂ����āu���{�l�v�A�C�f���e�B�e�B�����łȊ�Ղ������Ē蒅���Ă����B���́u���A�^���v�Ƃ������ꖯ�Ԃɂ�������{�i�V���i���Y���w���̎Љ�ۂ̏o���Ɛ��ȑ�O�����̗͂́A��O�́u���{�l�v�Ƃ����u�W���I�L���v�A�����̐�������Ă���B����A�u�����A�_�v�҂�Ɨ��_�҂̋�������u����A�C�f���e�B�e�B�v�͍Đ��Y�ł����Ԃ͗^�����Ȃ��������߁A����̐��������Ӗ����鉫��i�V���i���Y���̕��Չ���Ƃ͐����ł��Ȃ��܂܍����ɂ��Ă���A�Ƃ������Ƃ������悤�B
�Q�@�u���A�v�Ɓu�����A�v���猩���A�C�f���e�B�e�B�̏�����
�i�P�j���v�̑I��
�@�ނ��A�u���A�v�Ȃ����u�����A�v�̗����ꂪ�A���ꂼ��̗��O���咣���邳���ɁA�������ɗp����ꂽ�̂́A�u���j�I�W�c�L���v�ł��邪�A�����I���v�Nj��w���͌����Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�u���A�^���v�ɂ�����y�n�����A�l�������A�����������A�����ē��{�����@�����Ƃ����������̓��e����A�u���{�ɕ��A������A�����̖��͂��ׂĉ����ł���v�Ƃ����M�O���������l���������ɑ��������B�����A�u�����A�_�v��Ɨ��_���咣����҂́A���Ƃ��A�����}�}��ł����X���������u���{���A�͔ߌ��̍Č��v�Ƃ����c�_����A���̗��v�Nj��̎p��������B�܂��A�o�ϊE�E�ێ�n���S�́u����l�̉��������v�́u���A�����_�v���A��Ɍo�c�҂����̗��v���Ŏ炷�闧�ꂩ����̂ł���B���̈Ӗ��ŁA�G�X�j�V�e�B���_�̂����ЂƂ̗��h�ł���A�A�C�f���e�B�e�B�͗��v�̂��߂ɋÏW���ꂽ�Ǝ咣���铹���`�̃A�v���[�`�̑Ó������u���A�v�Ɓu�����A�v���ۂ��猟�ł���ƌ�����̂ł���B
�i�Q�j�G�X�j�b�N���E�̖���
�@�u�c�����A�v�咣�҂̂����ЂƂ̘_���́A���{�l���������Ƃ���Ɠ����ɁA�A�����J�l���ٖ���������Ƃ������Ƃł���B����A�u�����A�_�v��Ɨ��_�҂ɂƂ��āA���{�l���A�����J�l�����������Ƃ͓��������ł͂Ȃ��Ǝ咣���Ă���B���ꂼ��̎咣�̑Ó����͂Ƃ������A�u�����v�́u�فv���u���v���Ƃ������Ƃ���ʂ���G�X�j�b�N���E�̓A�C�f���e�B�e�B�̌`���ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ́A����̃P�[�X����������ł���B
�i�R�j�A�C�f���e�B�e�B�̗�����
�@����ɂ�����A�C�f���e�B�e�B�̌`���̂����Ƃ��d�v�ȓ����̂ЂƂ́A��͂肻�́u�������v�ł���B��㏉���ɓƗ��_���咣�������Ƃ����邪�A���̌��]���āu���A�^���v�̎���ɂȂ�A�u���A���}�v�Ə̂����Б�}�����̏��L���̃|�X�g�ɂ��A�������������A�t�ɁA���āu���A�^���v�̐擪�ɗ����Ă������A1997�N�ɂȂ��āw����Ɨ��錾�x�����M�����{����̗��E�����A������s���̑�R����Ȃǂ́A�܂��ɃA�C�f���e�B�e�B�ϗe�̍D��ł��낤�B�����āA�Ƃ��ɖ{�͂ɂ����ċc�_���Ă��鉫��ɂ�����A�C�f���e�B�e�B�̔������ۂ��A�܂��ɂ��́u�������v���݂��Ƃɕ\�����Ă���ƌ����悤�B
�@�ނ��A���̃A�C�f���e�B�e�B�́u�������v�́A���x�̍��͂��邪�A����Ɍ��炸�A�{���̑�2�A3���ɂ����Ď��グ�Ă���ق��́u�Ӌ����A�W�A�v�n��ł����p�⍁�`�̃P�[�X�����������B��������A�G�X�j�b�N���E�́u�������v�́A�u�Ӌ��v�n��̃A�C�f���e�B�e�B�`���ɂ����Č����Ɍ���������ł���B
�I�́@�u�Ӌ����A�W�A�v�A�C�f���e�B�e�B�E�|���e�B�N�X�̃_�C�i�~�Y��
��P�� �u�Ӌ����A�W�A�v�A�C�f���e�B�e�B�E�|���e�B�N�X�̗v���čl
�P�u�E�Ӌ����v���ۂ́u�O�ߑ�v�Ɓu�ߑ�v�̏Փ˂̎Y��
�@���͂Œ��Ă����ꃌ�x���̉����́A�����ɂ����Ă��N���Ă���u�Ӌ����A�W�A�v�A�C�f���e�B�e�B�̐������E���݉�������u�E�Ӌ����v���ۂ��A�u�O�ߑ�v�Ɓu�ߑ�v�̏Փ˂ɂ���ĎY�o���ꂽ���̂ł���A�Ƃ������Ƃł���B
�c�c
�@�܂��A�u���S�v���̕ω�������A�]���́u���S�v���Ƃ��ߑ㉻�A���Ȃ킿�u�O�ߑ㍑�Ɓv����u�ߑ㍑�Ɓv�֒E�炷������Ɍ������ɂ́A�����̉��Ǝs���Љ�̏o���ɂƂ��Ȃ��A�c��吧�̓����ƍ��������̑n�o���s���ł������B���̓�̃v���Z�X���i�ނƁA�u���S�v���O�ߑ�ɂ�����ŏd�v�ȑ������ł���R���͂��x�[�X�Ƃ��鐳�����������悤�ɂȂ�B���A�W�A�̋ߑ㉻�́A��������r�I�ɒx��Ă���A�O�ߑ�ɂ����Ă�蕁�ՓI�������u���S�v�́u�Ӌ��v�ɂ������镐�͎�`�́A������p�ɂ������钆���̐����������悤�ɁA���̉e��������Ƃ��Ĉꕔ�c���Ă���ƌ����悤�B����������A���A�W�A�n��ɂ�����ߑ㉻������ɐi�߂A�u�Ӌ��v�ւ̕��͎�`�ɂ��u���S�v�̈ێ��͂܂��܂�����ɂȂ邾�낤�B�ߑ㉻�̐��n�Ɍ������Ă������̓��{�́A�O�ߑ�i1609�N�F���̗����N�U�j�������͋ߑ㏉���i1879�N���{�̗��������j�ɂ����ė����E����ɂ������čs�Ȃ����悤�ȕ��͍s�g���قƂ�Ǖs�\�ɂȂ������肩�A��O�܂ł̈�{���������������̈�̉�������O���C��������������A���ꕶ���d��������ɐi��ł����B����́A���{������́u���S�v�ւ̎�����������铮���Ƃ��đ�������B�܂��A�ߑ㍑�ƌ��݂̍Œ��ł��鍡���̒����́A���{�قǁu�Ӌ��v�d���悤�Ƃ��Ă���Ƃ͌����Ȃ����̂́A1980�N��ɓ���A���Ɠ�����ւ̎p���ɂ����ď]���́u���͉���v����u���a����v�ւ̓]���ƁA���̂��߂́u�ꍑ�x�v�̍\�z����u�Ӌ��v�ɂ������鐭��̏_���������B�����āA�u�ߑ�v���i�ނƁA�u�Ӌ��v�ɂ�������u���S�v�̗D�z�Ȓn�ʂ�����ቺ���Ă����ƍl�����悤�B
�@����A�u�Ӌ��v������́A�ߑ�Љ�����炵���`���I�u���S�����Ӌ��v�̊W�ω��Ɓu�E�Ӌ����v���ۂ����͂�����M����B����́A���Ȃ��Ƃ��l�̊p�x����ώ@���邱�Ƃ��ł���B���ɁA�ߑ�ɂ�����u������{��`�v�Ƃ������ׂ��}�X�R�~�̔��B�́A�{���܂Ƃ܂�Ȃ������u�Ӌ��v�n��̈�̉��������炵���B���͂Œ��Ă���u�ߑ㉻�t���v�́A�{�_�̎��،����ɂ����đ����̎��ۂ���m�F�ł���B���Ƃ��A���Ƃ��ƕ��Ր���L���Ă��Ȃ������u����l�v�A�C�f���e�B�e�B�́A������̋ߑ㉻�ߒ��ɂ����Č`������A���Չ����ꂽ�̂ł���B�܂��A���ɂȂ��ċ}���ɕ��Չ������u��p�l�v�ӎ���A�u���`�l�v�ӎ������l�A�ߑ�Љ�i�ނȂ��Ŕ����������ۂł���B���̂悤�ȁu�Ӌ��v�̋ߑ㉻�ߒ��Ɍ�����u�Ӌ��v�n��̓y���A�C�f���e�B�e�B�̕��Չ����ۂ́A���u�Ӌ��v�G�X�j�b�N�E�O���[�v�̌����͂�����������ƂƂ��ɁA�u���S�v�ɂ������鎩��̗�������u�Ӌ��v�ӎ���ቺ�����A�K�������u���S�v�ɏ]�����Ȃ��u�E�Ӌ����v�ӎ��̖G��𑣐i�����̂ł���B
�@���ɁA�O�ߑ�ɂ����ĕ��ՓI�Ɍ����Ȃ������A�ߑ�̍������݂̂��߂ɁA�������Ƃ��Ȃ������������ʂ��āA������́u���S�v�̕������x�[�X�Ƃ���u���������v�̌��ʓI�������́A�u�Ӌ��v�n��Z���́u���E�o�v�̂��߁A����u�����v�ɋ��͂��鑤�ʂ����邪�A����A�u�Ӌ��v�n��Z���̔����������N���������ʂ�����B��2�͂ɂ��w�E���Ă���悤�ɁA��㏉���̉���Ɨ��_�\�o�̈���́A��������������̋����I�����ɂ���̂ł���B�܂���T�͂ōl�@���Ă����p�i�V���i���Y���̍��g�Ɩ��ڂɊW���Ă���̂́A��㍑���}�́u�c���������^���v�ւ̔����ɂ���B����ɑ�U�͂ŕ��͂��Ă���ԊҌ�́u���`�l�v�A�C�f���e�B�e�B�̌��݉����܂��u�������v�̎h���������ʂ����݂����̂ł���B
�@�����āA��O�ɁA�ߑ�Љ�̕��ՓI�C�f�I���M�[�ł��郊�x�����Y���́A�u�Ӌ����A�W�A�v�n��̃A�C�f���e�B�e�B�̐������ɐ�������^����ꂽ�̂ł���B�u�c�����A�v�̑O�����Ȃ����̉����A�Љ�̎��R������I���剻�����g����1990�N��ȍ~�̑�p�A�����ĕԊҖ�肪���シ��悤�ɂȂ���1980�N��ȍ~�̍��`�́u���S�v�ɂ������鎩��̑����E���v����삷�邽�߂̍R���ɂ����āA�l���⎩�R�̊m�ۂ́A�˂ɑO�ʂɌf�����Ă����X���[�K���ł������B�����������R��`�w���̋ߑ�̐��E�����ɕ֏悵���R����ʂ��āA�u�Ӌ��v�n��Z���̎咣�̐������͈��̒��x�m�ۂ��邱�Ƃ��ł�������ł���B�u�Ӌ����A�W�A�v�ɂ�����A�C�f���e�B�e�B�̐������́A�܂��ɂ��̂悤�ɉ������ꂽ�̂ł���B�u�Ӌ����A�W�A�v�ɂ����郊�x�����Y���ƃA�C�f���e�B�e�B�Ƃ̍��̌��ۂ́A�Ƃ��ɑ�V�͂̃|�X�g�Ԋ҂ɂ�����u���`�l�v�A�C�f���e�B�e�B�̍\�����͂ɂ����Ė��炩�ɂȂ��Ă���B
�@���̂悤�ɂ��āA����ɂ�����u�Ӌ����A�W�A�v�n��̃A�C�f���e�B�e�B�̐������E���݉����ۂ���u�E�Ӌ����v���ۂ́A�u�O�ߑ�v�Ɓu�ߑ�v�̏Փ˂ɂ���Đ��܂ꂽ�Y���Ȃ̂ł���B�c�c
�Q�@�u�A���ύX�v�Ɓu�Ӌ��A�C�f���e�B�e�B�v���Ƃ̈��ʊW
�@���āA�{���̎O�̒n��ɂ���������،����ɂ��A���炩�ɂȂ��������Ƃ��d�v�ȓ_�́A�u�A���ύX�v�Ɓu�Ӌ����A�W�A�v�n��̃A�C�f���e�B�e�B���Ƃ͂���߂Ė��ڂȊW�ɂ���Ƃ������Ƃł��낤�B�����āA���̖��ڂȊW�Ƃ́A�����ɂ��i�s���́u�Ӌ����A�W�A�v�n��̓y���A�C�f���e�B�e�B�̊������������炵���̂��A�u���S�v���m�̗͊W�̋A���Ƃ��Ă����́u�Ӌ��v�n���Ώۂɍs�Ȃ��Ă����u�A���ύX�v�ł���A�Ƃ������ʊW�Ȃ̂ł���B��������܂ł��Ȃ��A�u�A���ύX�v�͂���Ȃ�u���S�v�ɂ��u�Ӌ��v�̈ڏ��E������Ƃł͂Ȃ��A��������ЂƂ̍\���I���ł��邽�߁A���́u���ʊW���v�̑Ó����́A�{�����ŗ����ꂽ���̎l�_�Ɏx�����Ă���B
�i�P�j�u�Z���s�݁v�́u�c�����A�v�Ɓu�Ӌ����A�W�A�v�̃A�C�f���e�B�e�B���
�@���͂ɂ����Ă��w�E���Ă���悤�ɁA���u�Ӌ����A�W�A�v�ɂ�����O�́u�Ԋҁv�̐����ߒ��ɂ����āA�u�Ԋҁv����鑤�̏Z���̎Q���͕s�\���Ȃ������S�ɖ�������Ă������Ƃ����炩�ł���B
�c�c
�@�ȏ�̂悤�ȁu�Ԋҁv�ߒ��ɂ�����u�Z���s�݁v�̖��́A�����u�Ӌ����A�W�A�v�ɂ�����u���S�v�ɂ������鉓�S�͂̌��݉����A���Ȃ킿�u���������v���ɒ������Ă���̂ł���B
�i�Q�j�u�c�����A�v��̍��ʐ���Ɓu�Ӌ��v�A�C�f���e�B�e�B�̌��݉��E������
�@�u�c�����A�v��́u�Ӌ����A�W�A�v�Z���̃A�C�f���e�B�e�B���́A�u�Ԋҁv�̐����ߒ��ɂ�����u�Z���s�݁v�ɋN������Ƃ��낪�������A���̎��������ۂȂ������������̌��݉��E���������ۂ́A�u�Ԋҁv��̍��ʓI�ȃG�X�j�b�N����⋭���I�u��������v�ɂ����ڂɂ�������Ă���B
�@�܂��A����̃P�[�X�����Ă݂�ƁA��O�́u��������v�ɂ����āA�u�����D�v�ɏے�����鉫�ꕶ���ɂ�������}�����̂��Ă����B���ɂȂ�ƁA�A�����J�̎x�z���o�āA1972�N�́u�c�����A�v��A����ɂ������čs�Ȃ����u���ʐ���v�͂�����Ƃ��đ����̗̈�Ō�����B�u�ԊҌ�̎����͕ԊґO��30���ɏk�������v�ق��ɁA�����Ƃ��悭�w�E����Ă���̂͂�����u��n���v�ł���B���Ȃ킿�A�u���y��0.6���ɂ����Ȃ�����ɁA�Ȃ��ݓ��ČR��p�{�݂�75�����W�����Ă���̂��B�{�y���A���Ɣ�r���āA�{�y�ł͕ČR��n��60���������Ă���̂ɁA�Ȃ�����ł�15�����������Ă��Ȃ��̂��v�Ƃ������Ƃł������i��c���G1996�j�B���́u��n���ʐ���v�́A���A��̉���i�V���i���Y�����h������L�[���[�h�ƂȂ����B
�c�c
�i�R�j�A���n�x�z�E�����́u�A���ύX�v�o���Ɓu�Ӌ��v�A�C�f���e�B�e�B�̕s���艻
�@�u�Ӌ����A�W�A�v�́A�ߑ�Љ�ɂȂ�O�ɁA�������͂���Ɉڍs���n�߂悤�Ƃ���Ƃ��ɁA�p���[�E�|���e�B�N�X�E�Q�[���ɂ���āA�s�{�ӂɂ��u�A���ύX�v�������I�ɍs�Ȃ��A�u�ٖ����v�x�z�̌o��������������Ȃ��Ȃ����B�A�w���푈����1842�N���`�̒�������C�M���X�ւ̊����A1879�N���{�̈���I���������A1895�N�����푈�̏��҂ł�����{�̐험�i�Ƃ��đ�p�̊����A�Ƃ��������҂̐V���ȗ̓y�̊l���́A�u�Ӌ����v�ɂƂ��āu�ٖ����v�x�z�̎��オ�n�܂������Ƃ��Ӗ�����B
�c�c
�@�A�C�f���e�B�e�B���\������ɂ͕����̗v�f�͕s���ł���B�A���n���ɂƂ��Ȃ��ٕ������Z�����邱�Ƃɂ���āA�u�Ӌ��v�Z�����������Ɓu�c���v�̂���Ƃ̍��ق����������傫���Ȃ����Ɠ����ɁA���̃A�C�f���e�B�e�B�̌`���́u�]�v�ȁv������^����悤�ɂ��Ȃ����B���̂悤�ȁu�ٖ����v�x�z�̌o���́A�u�Ӌ��v�ɂƂ��āA�ԊҌ�́u�ꍑ�v�̃i�V���i���E�A�C�f���e�B�e�B�v���ɓK���ł����A�A�C�f���e�B�e�B�̖�肪�N���₷���d�v�Ȉ���ɂȂ����̂ł���B�������A�u�ٖ����v�̐A���n�x�z����u����v���ꂽ�u�Ӌ��v���A�Ɨ���I�ׂ��Ɂu�c���v�ɕ��A�������͕Ԋ҂��ꂽ���Ǝ��̂́A�ēx�́u�A���ύX�v���Ӗ�����B���̂��߁A�u�Ӌ��v�n��́A�����̍č\����������x�o�����Ȃ���Ȃ炸�A�܂����̃A�C�f���e�B�e�B�`���̕s����ȏ�Ԃ��ӂ����э������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�i�S�j�u�Ӌ����A�W�A�v�n��̑���_�Ɓu�c�����A�v��A�C�f���e�B�e�B���̏��ϐ�
�@�A�C�f���e�B�e�B���Ɓu�A���ύX�v�Ƃ̊W���߂����āA�u�Ӌ����A�W�A�v�n�悪���ʂ��Ă���_�́A�ȏ�̒ʂ�ł���B�������A�����܂ł��Ȃ��A�O�̒n��ɂ͑��Ⴕ�Ă���_���������ď��Ȃ��Ȃ��B
�@�������ɎO�ɏW�邱�Ƃ��ł��悤�B�܂����ɁA�u�c�����A�v�ɂ������āA��p�i1945�N�j�Ɖ���i1972�N�j�̏Z���͊��}�Ȃ����M�]���Ă������A���`�i1997�N�j�̕��́A�ނ���s��������Â��Ă����B���ɁA��p�ɂ����ĐV���ȏ@�卑�Ȃ����A�������҂ł��������{�ɂ�������A�C�f���e�B�e�B�́A�u�c�����A�v���Ă��甼���I�o�߂������������̒��x�c���Ă���B����A���`�Ɋւ��Č����Έꐢ�I���̐A���n�������s�Ȃ��Â����C�M���X�ɂ�������A���ӎ��͂قƂ�NjN����Ȃ������B����̃A�����J�ɂ�������A���ӎ��̌��@���ގ������P�[�X�ł���B����́A�Ȃ��ł��낤���B��O�ɁA�������̎O�̒n��̃A�C�f���e�B�e�B��肪�������������x�����Ȃ�قȂ��Ă��邪�A��������E����͉̂��ł��낤���B
�@�܂��A���̓_�ɂ��Đ����ł��邱�Ƃ́A�@�u�c�����A�v����������܂ŁA��p�͒������A����͓��{��c���Ƃ���ӎ��͔�r�I�ɋ����������A���`�̒����ɂ�������u�c���ӎ��v�͑��ΓI�Ɋ��������Ƃł���B����ɁA�A���́u���v���x��������Ƃ��d�v�ȗv���́A�c���Ƃ̌o�ϓI�i���ƎЉ�x�̑��قł���B�O�҂ɂ��ẮA�Ԋ҂̎��_�ɂ����āA��l������̍��������Y�̊i���͂��悻30�{�ɏ��A��҂ɂ��ẮA�Љ��`��}�ƍق̒����Ύ��R��`�@���Љ�̍��`�Ƃ����Η��\�}�������̍��`�Z���̓��̂Ȃ��ɌŒ艻�������߂ł���B���̓�̑��ʂɂ����ẮA����������`�́A�u�Ԋҁv�����u�ꍑ�v�̒������D�ʂɂ������B�v����ɁA�Z�����͐V���ȏ@�卑�E�����҂��u�c���v�Ƃ��Ĉ������ǂ����A�܂��A���́u�c���v�Ƃ̌o�ρE�Љ�I�i���ɂ����ẮA�ǂ̒��x�̃M���b�v�����݂��Ă���̂��A����́u�c���v���D�ʂɂ��邩�A����Ƃ���ʂɂ��邩�A��Âɔ��f���Ă����̂ł���B
�@���_�ɂ��ẮA���{�͉���Ƒ�p�ɂ������ċ����I����������s�Ȃ��Ă������A���`��155�N�ԓ��������C�M���X���A�������27�N�Ԏx�z�����A�����J���A���{�ɔ�ׂ�ƁA�_��ȕ���������̂��Ă������Ƃ́A���ڂ��ׂ��ł��낤�B�܂��A���`�Ɖ���ɂƂ��ẮA�C�M���X�ƃA�����J�́A�u���炩�Ɂv�u�ٖ����v�ł���A�u��������v�Ȃ����u�c���v�Ƃ��Ď���₷����������{�Ɣ�r����ƁA�����I�E���j�I�A�q�͕n��ł������B����A���������s���ꂽ���ǂ����A�x�z�҂��u�ٖ����v�ł��邩�ǂ����́A�u�Ӌ����A�W�A�v�n��̓�������鑤�̋A���ӎ��ɑ傫�ȉe����^����d�v�ȕϐ��ł���B
�@�������A�u�ٖ����v����u�c���v�ɂȂ邱�Ƃ́A��Εs�\�ł͂Ȃ��B����̃P�[�X�́A���̖���ɋ����[���o���������Ă��ꂽ�B1879�N�̗��������̂����A�����ɔ����问�����{����嗬�̃G���[�g�����͂ނ��̂��Ƃł��邪�i��1�́j�A��ʂ̗������O�̑命�����A�u���}�g�v��c���ɂ�����A����u���}�g�l�v�ɂȂ肽�������킯�ł͂Ȃ������B�������A��㏉���́u�����u���v���o�āA�}���ɂ���Ɏ���đ������̂́A�u�c�����A�^���v�ł������B���āA����̍���łڂ����u�G�v�ł������͂��̓��{�́A��]���āu�c���v�ɂȂ����̂ł���B����́A�������āu���A�^���v�̐헪�����ł͐����ł����A�����[���ۑ�Ƃ��Ďc����邪�A���{�̓�������̐����͏d�v�����ׂ��ł��낤�B�i��3�́j�B������ɂ���A�u�ٖ����v�́u�c���v�ɂȂ肤��̂ł���B
�@��O�_�A���Ȃ킿�u�Ӌ��v�Z���A�C�f���e�B�e�B�̐��������x�����E����ϐ��͂�葽���A���G�ł��낤�B�ȏ�̐��_�Ƃ���d�Ȃ��Ă��邾�낤���A��P�������R���̎��،�������A���̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B�@�u�Ӌ��v�n��́u�Ԋҁv�O�ɂ����鎩���x�A���Ȃ킿�u���S�v�i�u�ꍑ�v�j�ɂ�������o�ϓI�E�����I�ˑ��x�͍������A�Ⴂ���A�A�u�Ԋҁv�O�ɁA�����E�Љ�E�o�ρE�����̕���ɂ����āA�u�Ӌ��v�Ɓu���S�v�i�u�ꍑ�v�j�̍��͂ǂ�قǑ傫�����A�B�u�Ԋҁv�ɂ�������Z���̎^�ۈӎ��̋���A�C�u�Ԋҁv�ߒ��ɂ����āA�Z�����ǂ̒��x�u�s�݁v���������A�D�u�Ԋҁv��̍��ʐ���͂ǂ�قǐ��s����Ă������A�E�u�Ԋҁv��ɂ����āA�ǂ̒��x�̎������ۏ���Ă��邩�A�F���������A�u�c�����A�v�́A���ǁA�u�Ԋҁv���ꂽ�u�Ӌ��v�ɔ@���Ȃ�\���I���v�������炵���̂��A�Ȃǂł���B�c�c
��Q�� �A�C�f���e�B�e�B�̗��_�Ɓu�Ӌ����A�W�A�v
�P�@�����I�E�����I�A�C�f���e�B�e�B�����E�������̍čl
�Q�@�u�Ӌ����A�W�A�v�̃P�[�X�̓A�C�f���e�B�e�B���_�ɓ��Ă͂܂邩
�i�P�j�A�C�f���e�B�e�B�̐����E�������Ɓu�Ӌ����A�W�A�v
�@�`�@���j�̏��Y���A�ߑ�̎Y����
�@�܂��A��q�̉����Ɋւ���l�@�ł���G��Ă��邪�A�����̈ӎ��Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�́A���j�I�A������L������̂ł��邩�A�܂��͋ߑ�I�Y���ł��邩�A�Ƃ�������ɂ������āA�{�_����A��҂��Ó��ł���Ɣ��f�ł���B
�@�P�������Ɍ����A������u����l�v�u��p�l�v�u���`�l�v�Ƃ����Љ�I���Ր����������I�A�C�f���e�B�e�B�������͐����I�A�C�f���e�B�e�B�́A��������A�����̂��炷�łɑ��݂��Ă������̂ł͂Ȃ��A�ߑ�ɂȂ��Ă��珉�߂ďo�������Љ�ۂł���B���������������N����܂ŁA500�N�ɋy���j�����������ɂ����āA�𒆐S�Ƃ���u�����ӎ��v�́A�ꕔ�̎m���G���[�g�̂������ɂ͑��݂��Ă������A����������ɓ����u�����l�v�A�C�f���e�B�e�B�͕��ՓI�A���ӎ��Ƃ��đ��݂��Ă͂��Ȃ������̂ł���B�ނ���A�����̈�̉��ӎ��́A���������ɂ���Đ��܂ꂽ��@�����瑣�i���ꂽ�̂ł���B�����āA���̌�̋ߑ㉻�ւ̐i�݂���сu���}�g�x�z�v�E�u���{��������v�Ȃǂ̂Ȃ�����A�u����l�ӎ��v���悤�₭���Չ����Ă������̂ł���B�i��P�́j
�@�a�@�����I�J���A�ڐG�̎Y����
�@�A�C�f���e�B�e�B�̐����͌����I�J�ɂ����̂��A����Ƃ��u�����v�Ɓu�ނ�v�Ƃ̐ڐG�ߒ��Ő��܂ꂽ���̂��A�Ƃ����u�Η��v�̗��_�ɂ��āA�{�_����A���҂͕K�������������Ă��炸�A�������邱�Ƃ��\�ł���A�Ƃ������ʂ��o���B
�@�c�c
�@�A�C�f���e�B�e�B�͑Ώۂ̑�����ӎ�������A�ڐG�����肷�邱�Ƃɂ���ċ�������邪�A�Ȃ��u�����v���A�ЂƂ̃O���[�v�ɑ����邩�́A������Ƃ��đg�D�̌������K�v�ł���B�u�����I�J�v�͂��̃j�[�Y�ɉ�������̂ł���B�����A�u���Ƃ��Ɠ����l�ԁv�Ƃ����ӎ��ɏے������u�����I�J�v�͂��܂��܂ȗv�f���܂�ł��顁u����l�v���܂Ƃ߂��J�́A��ɋ��L���Ă��錌���A���j�����A���j�I���݂Ƃ��������ʓ_����\����������A�u��p�l�v�Ɓu���`�l�v�̋ÏW�͂́A������`�����������A�������j�I�o������т������琶�܂��W���I�L���ɂ����̂ł��낤�B
�@�b�@�Љ�ϓ��̎Y�����A���v�ی�̓��
�i�Q�j�A�C�f���e�B�e�B�̖{���Ɓu�Ӌ����A�W�A�v
�@�`�@�ς��A�s�ς�
�@����܂ł̃A�C�f���e�B�e�B�����ɂ�����A�����ЂƂ̘_���́A�A�C�f���e�B�e�B�Ƃ������̂��A�ςȂ��̂ł��邩�A����Ƃ��s�ςȂ��̂��A�Ƃ������Ƃł������B���̓_�ɂ��ẮA�{�_����u�ςł���v�Ɩ��m�ȓ������o�Ă���
�@1879�N�̗��������܂ň�ʂ̗����Z���ɂ͂قƂ�Ǒ��݂����Ȃ������u���{�l�v�Ƃ����A���ӎ��́A���̌�̓��{�ւ̓�������ɂ���ď��X�ɐ��܂�蒅���Ă������Ƃ�A�ߑ�ȍ~����ɑ��݂���u����l�v�ӎ��Ɓu���{�l�v�ӎ��Ƃ�����̃A�C�f���e�B�e�B�́A�Ƃ��ɂ͑O�҂������A�Ƃ��ɂ͌�҂������Ƃ������Ƃ�����A�A�C�f���e�B�e�B�̉ϐ����M���顁@
�@�c�c
�@�a�@���݂̂��̂��A�z���������̂�
�@�G�X�j�b�N�E�A�C�f���e�B�e�B�ƃi�V���i���E�A�C�f���e�B�e�B���܂ރA�C�f���e�B�e�B�Ƃ����A���ӎ��́A���݂��������̂̈ӎ��ł��邩�A����Ƃ��u�z���̋����́v�ӎ��ł��邩�́A�{�_����K�����������ȉ��o���Ă��Ȃ��B�������A���݂̂��̂ł��邩�ۂ��͕ʂƂ��āA�����̏ꍇ�A�A�C�f���e�B�e�B�͂������ɁA�z�������肷��ߒ����o�Đ�������A�������ꂽ���̂ł��邱�Ƃ́A�{�����̕��͍�Ƃ�����ؖ�����Ă���
�@�c�c
�@�b�@���R�̏��Y���A�n���������̂�
�@�{���̍l�@����A�ߑ�ɂ�����A�C�f���e�B�e�B�Ƃ����A���ӎ��́A���R�Ɍ`�����ꂽ���̂Ƃ��������A�l�דI�ɍ\�z���ꂽ���̂Ƃ������ʂ��Z���ł���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�c�c
�@�����Č����A�u�Ӌ����A�W�A�v�n��̓y���A�C�f���e�B�e�B�́A�I�v�ȗ��j�̂Ȃ��Ŏ��R�ɐ�������A����ɋ��ł�����̂ɂȂ����̂ł͂Ȃ��A�A���E�匠�ύX��u�c�����A�v�ɂƂ��Ȃ����ߑ�Љ�i�ނȂ��Ō`�����ꂽ���̂ł���B��������A���̒n��̃A�C�f���e�B�e�B�́A�Љ�̌����A���������ڐG�E�𗬁A���v�̑��D�A�Ƃ������ߑ㐫�Ɏh������Ċ��������ꂽ�̂ł���B�܂��A���̃A�C�f���e�B�e�B�̖{���́A�ς�肤����̂ł���A�n�����ꂽ��A�܂��n�����ꂽ�肵�����ʂ�Z���ɗL���Ă�����̂Ȃ̂ł���B
��R�� �u�Ӌ����A�W�A�v�����̉ۑ�ƓW�]
�c�c
�R�@�{���̖ړI�̍čl�ƓW�]�@
�c�c
�@�v����ɁA�u�{�[�_���X���v��u�O���[�o�����v���i��ł��A�u�ߑ㍑�Ɓv�����{�I�ɕϗe�����邱�Ƃ͂ł����A���Ƃ͂�����Ƃ��āu���v�����v�K�v��������ȏ�A�u�Ӌ��v�n��̗��v���]���ɂ��Ȃ��ۏ͂Ȃ������������A�O�q���Ă����A�����܂łÂ��Ă���u�Ӌ����A�W�A�v�n��ɂ�������u�匠���Ɓv�́u���ƗD��v���̗}���ƍ��ʂ́A���̂悤��21���I�̐��E�ɂ����Ă������Â����낤�B���������āA�����́u�ߑ�v�Ȃ����u�|�X�g�ߑ�v�ɂ����Ă�����Ƃ��ĐF�Z���c���Ă���O�ߑ㓌�A�W�A�̓`���I�u���S�����Ӌ��v�ϔO���A���̂悤�ȐV�������I�ɂ����Ă����S�ɂ͏��ł��Ȃ����낤�B
�@������ɂ���A�u���S�v�Ƃ��a瀂ɂ���āu�Ӌ��v����h���������������������菜���̐���݂��Ȃ���A�V�������I�̒n������E���A���肵�Ȃ��ł��낤�B���������A�O�ߑ���ߑ���u���S�v��u�卑�v�Ƃ����_���Ō`������Ă����u�ォ��v�̍��ۊW�␢�E�V�X�e����������Ȃ��̂ɂ��邽�߂ɂ́A�u�|�X�g�ߑ�v�ɓ��낤�Ƃ��Ă��錻�݂ɂ����ẮA�V���Ȕ��z���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���̈Ӗ��ŁA�{���̒��悤�Ƃ��Ă���A�u�Ӌ��v��n������Ȃ�n�撁�����x�[�X�ɂ����u������v�̍��ۊW�␢�E�V�X�e���̍\�z���O���A�����肢�������čl���鉿�l������̂ł͂Ȃ��낤���B
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɂ��ǂ�