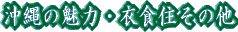
塩屋湾のウンガミ
グスク巡りの時に、多くの御嶽ウタキに出会いましたが、それらのすくなからずの場所で、お供え物やお線香を焚いての祈りに、遭遇しました。今もなお、それらの御嶽が地域の人々の中に生きており、日常の中に溶け込んでいるように感じられました。塩屋湾のウンガミも同じように、厳粛さや荘厳さを保ちながら、しかし、決して日常の営みとはかけ離れたものではないことに感激しました。祭りの途中で遅刻してきた神人が急いで衣装を纏ったり、祭りを準備する人たちから「一年に一回だから忘れちゃうのよね」というような会話がこぼれたり…。
翌日(8/19)の琉球新報・沖縄タイムスの朝刊にそれぞれ掲載されています。
いくつかのサイトを見つけましたのでご紹介します。文化庁・重要無形民俗文化財の「塩屋湾のウンガミ」・Wonder沖縄/沖縄デジタルアーカイブの「塩屋のウンガミ」
以下の文章は、当日いただいたパンフレットを採録したものです。
塩屋湾のウンガミ(塩屋港内・解説宮城竹秀・みなと会)
 はじめに
はじめに
「宵ん暁んなれし面影ぬ立たん日やねさみ塩屋ぬ煙」
私たちが誇りとする郷土塩屋の自然の美しさと人情の美しさをよく謡ったもので、いい知れない、詩情と郷愁がかきたてられる。この美しい自然の中に私たちの祖先は永い年月の間に、ある時は自然の美しさを賞し、ある時は風雨とたたかって生活の基盤を築き上げてきた。そこに美しい人情が培われ、素朴な風俗習慣、民話、伝説、行事等の民俗が伝えられてきた。その中で、最も古く大きく盛んに伝承されてきたのが海神祭である。
海神祭は古い時代に北部の村々で起こり、語り伝えられてきたが、時代が進むにつれてその影が薄らぎつつある時、塩屋では昔そのままの姿を残して盛大に行われている。それは、海と山に囲まれ、そこから生活の糧を得ていたことから、海の幸、山の幸を祈願する行事とその自然条件とあわわせて村人たち(門中一族郎党)の団結心の強さが、私たちの誇りとする海神祭が育ち伝えられてきたのではないかと考えられる。
素朴で古く美しいものをいつまでも大切にして残したい願いはみんな共通して感じていることだと思う・私たち郷里(四か字又は七か字)に生まれた者としてこれだけは知っていただき、また、はじめて海神祭をご覧になる方々の参考にと思って、田港アサギから始まって屋古、塩屋、兼久浜までに行はれる行事の一連の流れをまとめて海神祭の案内としたい。
海神祭
時、毎年旧盆明けの猪の日に行われるがどうして猪の日を選んだかは明らかでない。
行事の一連の流れの内容から豊作・豊漁(猟)祭であることがうかがえる。
所、田港、屋古、塩屋(シナバ)、兼久浜(ナガリ)
年代、いつごろ起こったかもはっきりしないが、塩屋の旧家の家系が18代と言われるので、それから推測して4〜5百年前、村の立ち始め頃だと推定される。
拝ンマールと踊いマール
ウガンマール(ハーブイマール)と踊いマール(ワラビミキマール又はチヌマキマールともいう)が隔年毎に行われるが、ウガンマールはヌルを始め神人たちの祈願の供物が多くなり、踊いマールは、神司は簡略され、翌日、塩屋では踊りがあり、田港、屋古ではサーサーが行われる。
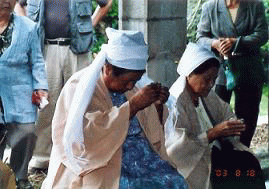
ウンケー
海神祭の前夜神人の出ている元屋に集まり神屋のあるところは神屋(お宮といっている)で、ないところは、その家のパシグチでニレーの神をお迎えする。
ヌルはサンナムと島方とメービーをしたがえて、ヌン殿地でお迎えする。明日の海神際を告げ衆人万人拝まれるようにと案内する。
田港アサギ
ヌルは田港のウフェ屋(村の総支配をするお起しの神)【何でもない日に訪れれば、きれいに整地された「駐車場」と見間違うでしょう。】を拝み次にヌン殿地でサンナムと島方とメービーが一緒になって今日の無事を祈願し、島方が小太鼓をポンポンと叩き先導してアサギに向かう。
その頃神人たちは各々の前ビー(世話役)に付添側を流れるタンナ川に行き、水撫りといって川を拝み、終わりに三回ずつ額に水を撫でる。そこに参加しなかった神人達は別の容器にいれてきた水を回して三回ずつ額に水を撫でる。【説明をしてくれた「門中の長老」?の方は「男性禁制の川です。見るのは結構ですが、触れないように。」といった後、「こうしたきまりも廃れていくでしょう。でも、今は、是非とも男性の方は川に入らないようにお願いします。」と淡々と語っていました。】(ミソギの名残と言われる)それが済むとウンケー酌が始まる。
ヌル【先ほどの長老の話によると、現在のヌルは13歳の時に指名されたそうですが、就任を嫌ったのか、「暴れた」そうです。それ以上に驚いたのは、当時の県知事による「任命書」です。ヌル=ノロが琉球王国の時代には立派な「宗務国家公務員」だったのは知っていましたが、「昭和初期」でも県知事に任命されていたのです。】はアサギの南側の山に向かいその他若ヌル、大勢頭、セーファ、根神、スリ神と一定のタムト(座席が決まっている)が定まっている。
ヌルが前のお酒を盃に注いで祭りの始まりを告げる。ご来臨のお礼と門中の人々の健康、豊作、ハーリーの乗組員の無事を祈願する。その間、他の神人をはじめ島方も一緒に手を合わせて祈願する。それが済むと神酒が配られ、【私たちにも振る舞われました。「ヨーグルト味の甘酒」という神酒でしたが、島方?の一人の人は、「今年のはジョートー」と言っていました。】門中の人々は各々の門中の神人を拝み餅をいただく、終戦直後は田港アサギに参加する神人は島方を合わせて30余名を数えたが老齢で不参加があったり、旅に出る者がいたりしてその数は15〜16人に減っている。【ここに参加していた神人は5人で、島方は5〜6人のようでした。】
芭蕉布の衣装を着ている神人は二アサギ(タアサギ)と言って屋古のアサギにも参加する。はじめから白衣装の人は一アサギ(チュアサギ)で田港だけに参加する。そこで行事が終わると、島方の鳴らす太鼓とヌザイを持った四人の島方の先導で屋古アサギに向かう。
屋古アサギ
 田港アサギから屋古アサギまでの2kmの行程を島方を先頭に約20分位で到着する。屋古アサギは、アサギの広場の中心に太い柱を立て、それを中心にクームー(藁で編んだ日よけ、クモの巣に似ている)が張られ、その周辺は芭蕉の葉の屋根でめぐらされ、下は芭蕉の葉をムシロ代りに敷き、いかにも素朴で神秘感がする。【照りつける陽差しの下で、ゆったりとした時間が流れていました。】
田港アサギから屋古アサギまでの2kmの行程を島方を先頭に約20分位で到着する。屋古アサギは、アサギの広場の中心に太い柱を立て、それを中心にクームー(藁で編んだ日よけ、クモの巣に似ている)が張られ、その周辺は芭蕉の葉の屋根でめぐらされ、下は芭蕉の葉をムシロ代りに敷き、いかにも素朴で神秘感がする。【照りつける陽差しの下で、ゆったりとした時間が流れていました。】
ヌルはアサギを背にして南向き(海に向く)若ヌル、セーファ、根神等、定まったタムト(一定の座席)に座り、島方は中央の太柱を囲んで車座になり、地家(屋古ナーカ)前田屋の長男がヌルに花米とお酒を供えてウトゥイケーをする。【この時のお酒は「泡盛−瑞泉?」で、お米は「コシヒカリ」でした。】
それが終るとヌルの前には長蛇の列ができてヌルを拝む。(ヌルは誰が拝んでもよい)各々の神人の前も門中の人々が拝み、盃を交わし餅を貰うと、この一年間の厄が払われ健康になるとのことで、先を競って拝む。
屋古アサギではアシビ神とハーリー神とスリ神に分けられるが、弓を持って「ヨンコイヨンコイ」【どうも、「ヨンコイ・オンコイ」と聞こえました。】と唱えながら支柱の太柱を回る。はじめ七周し、途中白衣装からイツ衣装(絹の模様の入った衣装)に着替える。回る回数は島方が小石で数える。その時ヌルも衣装を着替え、頭にチヌマキを乗せ、マガ玉ををかけカンザシをさす。二回目は五週して終る。
このヨイコイの神舞はユガフ【世果報】を願っているに違いないと思うが詳らかでない。ある人は船を漕ぐしぐさではないかと言っているが、弓を持ってのしぐさは猪を追い込んでいるように思われる。ここでのしめくくりは神ウスイで終る。
神ウスイ
神ウスイは若ヌル、大勢頭、スリ神の三人が山の方に向かって深く拝むようにうつ伏せになるとヌルがひとりひとりススキの束で背中を叩く。ヌルが「ウーシー」といって背中を叩くと、後方のヌルのメービーが「ワッサレー」と応える。それを三回繰り返す。それが済むと、ヌル、若ヌル、大シルは駕籠【この駕籠は田港からついてきましたが、ヌルたちは乗らずカラのままだったので、てっきりこれは神様を乗せているつもりなのだと思いました。後で聞くと、昔は10台以上も連ねて練り歩いたということです。】に乗り、ハーリー神はフルガンサに待機しているハーリーに向かう。島方を先導にヌルの一団は陸路シナバ(青年浜)に向かう。
ハーリー神がハーリーに乗り終るとヌルと駕籠はウフマチヤキで一旦駕籠を止めて、ハーリーの出発を見届けて、また、行列が動き出す。
御願バーリー
|
 |
|
 |
ハーリーは最初は、フギバン(20人乗りで若い青年たちが乗る)が出発し続いてウフバーリー(40余人乗り)の三艘【田港、屋古、塩屋】が出発する。各々のハーリーにはハーリー神が2・3人乗って漕ぎ手のエイサーエイサーの掛け声に合わせて前後にあおぐクバ扇に合わせてしぶきをあげて疾走する様は龍が水をかき分けて走るようで荘観である。対岸では各村々の婦人たちが藁鉢巻に藁帯姿【この藁衣装が何とも言えず印象的でした。】で腰まで海につかり手サジを打ち振り太鼓を叩いて迎える姿は他には見られない圧巻である。ハーリーが岸辺に着くと乗り組員も櫂を持って海に飛び込み、櫂と櫂を合わせ叩きながら勝利を誇り、海神祭も最高潮に達する。【屋古のフギバンがターンに失敗したのか、こちらに帰ってくる時に、あれよあれよ、という間に沈みはじめました。でも、ちょうど「水舟」状態(サバニの項参照)になり、青年たちは漕ぐ手を休めず、船体は海面下に没したまま突き進み、岸まで辿り着きました。】
その頃、陸路ヌルの行列が通る。すると今までにぎやかだった婦人たちやハーリーの乗組員たちも一斉に鉢巻を取り櫂を横にして敬虔な気持ちでヌルを拝む。沿道の 人々もひざまずいて拝む中を島方が太鼓を叩き「ヌールヌメーカラ、スニンマンニン、アンヅーク、チマズークウトイミソーリ、ウッサレリー」と唱えながら通る。その時は一瞬水を打ったように静まり返る。【私たちもハーリー見物に打ち興じていましたが、ヌルたちを乗せた駕籠を見るとやはり敬虔な気持ちにさせられました。もっとも跪いて拝む人は見かけませんでしたが。】
人々もひざまずいて拝む中を島方が太鼓を叩き「ヌールヌメーカラ、スニンマンニン、アンヅーク、チマズークウトイミソーリ、ウッサレリー」と唱えながら通る。その時は一瞬水を打ったように静まり返る。【私たちもハーリー見物に打ち興じていましたが、ヌルたちを乗せた駕籠を見るとやはり敬虔な気持ちにさせられました。もっとも跪いて拝む人は見かけませんでしたが。】
ナガリ
ヌルの行列は兼久浜に向かう。渚にヌルを中心に若ヌル、大シル、スリ神門中の付人達がひざまずいて西の海(ニレー)に向かって祈願する。
ヌルの祈願
「ニレー龍宮カラ、アマチャニシラチャニ、ワシヌトイガククリモーテ、ツーシジャー、クェーフーシーフー、ツクルムズクイ、マンサクヌウタシキミソーリ、ユイムンハップムンヌンウタシキミソーリ」と祈願が終ると島方が水ぎわで西の海に向かって又ザイで塩をかきあげイルカを捕るしぐさをする。
パーシ
ナガリの行事が済むとヌルの行列は同じ神道をシナバに戻る。ヒンメー酒(小休止)の後、小太鼓を吊るしてヌルの唱えるウムイに神人たちが唱和する。
パーシのウムイ
ヨハヨハ スクムイスクダキ ヌルクイシン トハシグチヌンジカキテ スクムイスクダキ ハニラムト ハニアサギ ヌンジカキテ シザララキシザラムイ ハニラムト ハニアサギ ヌンジカキテ ナガリマリ ウトイミソーチ クインヌル ウマンチュニウガマリテ ウマンチュヌウユイトラ ミルクユンフイミチラ アケザーバーニヌキタリテ ムカシヤ アンルスタル カンルスタル
シザララキシザラムイ ハニラムト ハニアサギ ヌンジカキテ ナガリマリ ウトイミソーチ クインヌル ウマンチュニウガマリテ ウマンチュヌウユイトラ ミルクユンフイミチラ アケザーバーニヌキタリテ ムカシヤ アンルスタル カンルスタル
ウムイが終ると奉納角力が始まるヌルは角力の途中で田港に帰る。【ノロ?車とフロントガラスに貼紙がなされた車で帰っていきました。以下の行事は翌日でしたので残念ながら体験できませんでした。】
ヤーサグイ
翌日、ウガンマールに行われる行事で田港、白浜(元はトノキヤ)はヌルを中心に田港、白浜の神人たちが屋古、塩屋では若ヌル根神をはじめ、神人たちがヌンドンチ、根神屋をはじめ、神人の元屋を回り、その家の不浄を払い一家の健康と繁栄を祈る行事である。
踊り
隔年毎に行われる。踊いマールに塩屋のアサギマーで女だけで、しかも三味線を用いず太鼓のはやしだけで露天で行われる。
それは生活と信仰から生まれた素朴な沖縄の生活芸能発達の形をとどめているようである。一説には塩焚きの夜伽とも言われている。
屋古、田港ではサーサーといって村中の人々が集まってウフェーヤ、アサギマーで神酒をふるまい踊ったりして賑やかで素朴な遊びが行われる。
THE SEVENTH EMIGRANT に戻る
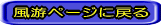


 はじめに
はじめに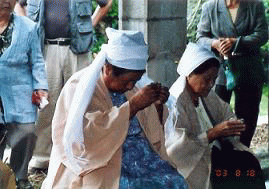
 田港アサギから屋古アサギまでの2kmの行程を島方を先頭に約20分位で到着する。屋古アサギは、アサギの広場の中心に太い柱を立て、それを中心にクームー(藁で編んだ日よけ、クモの巣に似ている)が張られ、その周辺は芭蕉の葉の屋根でめぐらされ、下は芭蕉の葉をムシロ代りに敷き、いかにも素朴で神秘感がする。【照りつける陽差しの下で、ゆったりとした時間が流れていました。】
田港アサギから屋古アサギまでの2kmの行程を島方を先頭に約20分位で到着する。屋古アサギは、アサギの広場の中心に太い柱を立て、それを中心にクームー(藁で編んだ日よけ、クモの巣に似ている)が張られ、その周辺は芭蕉の葉の屋根でめぐらされ、下は芭蕉の葉をムシロ代りに敷き、いかにも素朴で神秘感がする。【照りつける陽差しの下で、ゆったりとした時間が流れていました。】

 人々もひざまずいて拝む中を島方が太鼓を叩き「ヌールヌメーカラ、スニンマンニン、アンヅーク、チマズークウトイミソーリ、ウッサレリー」と唱えながら通る。その時は一瞬水を打ったように静まり返る。【私たちもハーリー見物に打ち興じていましたが、ヌルたちを乗せた駕籠を見るとやはり敬虔な気持ちにさせられました。もっとも跪いて拝む人は見かけませんでしたが。】
人々もひざまずいて拝む中を島方が太鼓を叩き「ヌールヌメーカラ、スニンマンニン、アンヅーク、チマズークウトイミソーリ、ウッサレリー」と唱えながら通る。その時は一瞬水を打ったように静まり返る。【私たちもハーリー見物に打ち興じていましたが、ヌルたちを乗せた駕籠を見るとやはり敬虔な気持ちにさせられました。もっとも跪いて拝む人は見かけませんでしたが。】