| 万延文久元治リンク | 東北 | 関八州・江戸 | 東海・北陸・甲信 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 洋上 | 前ページへ |
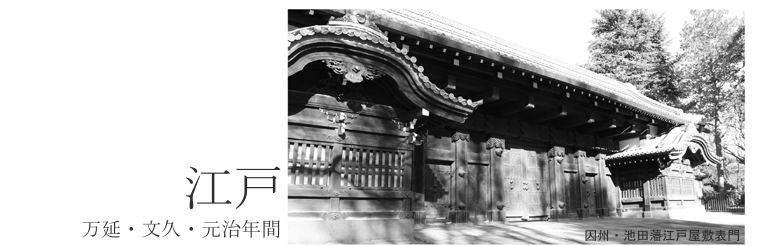
●文久元年(1861)
3月5日-浮世絵師歌川国芳(65)没。
3月23日-将軍家茂、仏、蘭、米、英、露5国に江戸、大坂の開市、兵庫、新潟の開港7年延期を要請する。
5月28日-水戸浪士、芝高輪のイギリス公使館(東禅寺)を襲う。
7月1日-講武所伝習生、軍艦乗込御用方に洋服着用が許される。
7月9日-英公使オールコック、老中安藤信正にロシア軍艦を退去させることを約束する。
11月15日-皇女和宮、江戸に到着。
12月22日-竹内保徳、福沢諭吉、箕作秋坪(みつくりゆうへい)、寺島宗則ら遺欧使節が出発。
幕府、江戸および関八州の宿屋・料理屋などに私娼を置くことを禁止した。
●文久2年(1862)
1月15日-水戸浪士平山平介ら老中安藤信正を襲う。信正負傷し、4月11日、老中を罷免される。(坂下門外の変)
2月11日-和宮、将軍家茂と婚儀。
3月1日-2代目河竹新七の「青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)」(白波五人男)、市村座で初演。
5月28日-東禅寺警備の松本藩士・伊藤軍兵衛が同寺へ侵入し水兵2名を斬殺。
6月10日-勅使大原重徳、江戸城に入り徳川慶喜、松平慶永の幕閣登用の勅旨を将軍家茂に伝える。
7月4日-幕府が諸藩に外国艦船購入に自由を与える。
7月6日-一橋慶喜が将軍後見職となる。
7月 9日-松平慶永、政事総裁職を命ぜられる。国益主法掛廃止。
閏8月1日-会津藩主松平容保、京都守護職を命ぜられる。
閏8月22日-参勤交代制改革(大名妻子の帰国を許す)。
10月-坂本竜馬、元氷川下の勝海舟を訪ね、その門下となる。これ以降、竜馬は勝屋敷や築地南
小田原町の軍艦操練所(総督・永井玄蕃頭尚志<げんばのかみなおむね>)へ通う。
→【竜馬の足跡⑯進む/戻る】
10月28日-三条実美、姉小路公知らが、将軍家茂に攘夷督促の勅旨を伝える。
12月 5日-将軍家茂、勅旨順奉の答書を勅使に渡す。
12月13日-幕府、諸大名以下に総出仕を命じ、攘夷の根本方針を布告。
12月-竜馬、幕府軍艦・順動丸で勝と共に品川を出港(航海の目的は老中小笠原長異行<ながみち>
による京摂の海防視察)、兵庫へ向かう。→
【竜馬の足跡⑰進む/戻る】
●文久3年(1863)
2月4日-清川八郎が講武所指南役・松平上総介に建議、閣老板周防守を説得、浪士組成る。小石川伝通院で会合。
2月8日-浪士組234名(取締付-芹沢鴨、池田徳太郎、斎藤熊三郎(清川八郎実弟)ほか23名。近藤勇は池田の手伝役)、
将軍家茂上京に伴い列外警衛として上洛する。
2月13日-将軍家茂、江戸を出発、上京の途につく。
2月22日-イギリス代理公使ニール、江戸湾頭に進航し、生麦事件の償金を要求。
3月14日-10万石以上の大名に京都守護兵提出の命。
3月28日-京から江戸へ帰って来た浪士組の一部を本所三笠町の旗本小笠原加賀守の空屋敷、西尾主水の屋敷(後に新徴組御役屋敷)
へ収容。
4月2日-竜馬、大久保忠寛(一翁)訪問、松平春嶽宛ての親書を託せられる。→
【竜馬の足跡⑳進む/戻る】
4月13日-清川八郎が麻布赤羽橋付近で、佐々木只三郎ら幕府側浪士隊員に暗殺される。
4月17日-幕府はこれまでの浪士組を庄内藩酒井繁之丞の付属とし、新たに「新徴組」とし、改めて江戸市中の
取締りを命じる。
5月9日-老中格小笠原長行(ながみち)が、生麦事件の賠償金44万ドルを独断で支払う。
5月10日-英・米・仏・晋・蘭5国の使者、幕府に国交拒絶を非難し、居留民の退去を強要すれば自衛行動に出ると通告。
5月18日-幕府は、イギリス・フランス両軍の横浜駐屯を認める。
8月-坂本竜馬、江戸着。9月、勝海舟と共に順動丸で大阪へ。→
【竜馬の足跡(28)進む/戻る】
9月14日-幕府、横浜鎖港について外国側と交渉開始。
10月-市中の武士・商人が理由なく浪士に殺される事件が多発する。
11月-竜馬、江戸着。桶町の千葉道場にわらじを脱ぐ。12月大晦日-竜馬、
神戸へ向けて観光丸で品川を出港。→【竜馬の足跡(30)進む/戻る】
12月20日-幕府が各国公使と輸入品税率引き下げについて協議し、調印する。
12月27日-将軍家茂、勝海舟とともに翔鶴丸で上洛すべく品川を出港。
12月29日-横浜鎖港使節一行出発。
12月29日-幕府がスイスと修好通商条約を結ぷ。
●元治元年(1864)
3月22日-フランスの日本駐在公使として、レオン・ロツシュが着任する。
6月-竜馬、江戸着。しばらく滞在した後、勝とともに下田へ。→
【竜馬の足跡(36)進む/戻る】
7月24日-幕府が英・仏・米・蘭に、パリ約定の破棄を宣告する。
7月24日-幕府が長州追討の勅命を受けて西国21藩に出兵を命じる(第1次長州征伐)。
8月 2日-幕府、長州藩征討令を下す。(第一次長州征伐)
9月22日-幕府が、英・米・仏・蘭4国との下関事件賠償に関する約定に調印する
(償金300万両支払いまたは下関か瀬戸内海1港の開港)。
10月11日-幕府が、将軍上洛の無事終了を祝い市中の13万3,541世帯に金6万3,000両を分配する。
11月10日-勝海舟、軍艦奉行免職。
12月18日-小栗忠順、軍艦奉行を命ぜられる。
12月28日-将軍家茂、勝海舟とともに翔鶴丸で上洛すべく品川を出港。