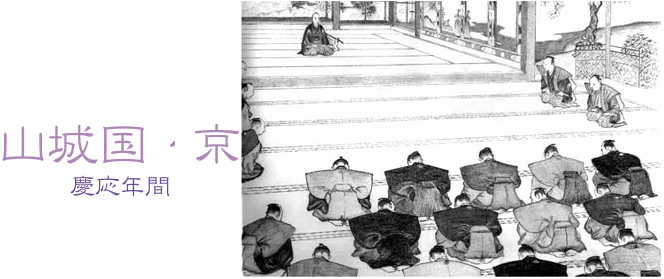
| 慶応年間リンク⇒ | 東北 | 関八州・江戸 | 東海・北陸・甲信 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 洋上 | 前ページへ |
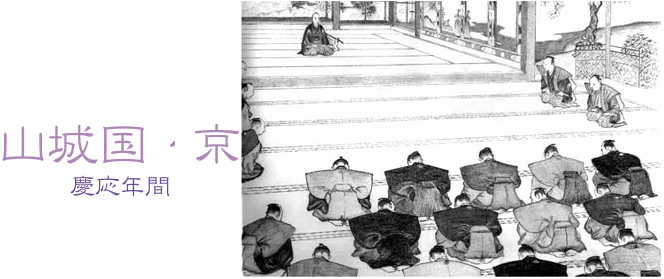
●慶応元年(1865)
●慶応2年(1866)
●慶応3年(1867)
●慶応4年(1868・明治元年)
3月−新撰組、屯所を壬生から西本願寺へ移す。
6月−坂本竜馬、中岡慎太郎、薩摩藩邸で西郷と面会。長州藩銃器購入の便宜供与の事後承諾を得る。→
【竜馬の足跡(46)進む/戻る】
9月21日−将軍家茂が参内し、長州征伐を奏上、勅許を得る。
10月1日−将軍家茂が4国との条約勅許と兵庫開港を朝廷に願い出る。翌2日、将軍職の辞表を提出する。
10月5日-条約勅許・兵庫先開港不許可の勅書下る。
10月−西郷隆盛が、長州征伐阻止のため兵を率いて上洛する。
11月−竜馬、京都所司代、新選組、見廻組などの警戒網を縫って潜伏。24日−大阪から長崎へ。→
【竜馬の足跡(51)進む/戻る】
1月19日−竜馬、伏見寺田屋へ入る。
1月20日−薩摩藩邸で、長州・桂小五郎、薩藩・西郷隆盛と面談。翌21日、桂が再度、西郷、小松帯刀、大久保一蔵
と会談。薩長連合の密約なる。
1月24日−竜馬と三吉慎蔵は寺田屋で伏見奉行所の捕吏に襲われて負傷。脱出して大山彦八に救出され伏見の薩摩藩邸
に匿われる。29日、小松、西郷の帰国に同行し京を立つ。龍、中岡慎太郎、三吉慎蔵同行。→
【竜馬の足跡(55)進む/戻る】
8月−海軍奉行・勝海舟、慶喜の意を受け長州と談判のため安芸へ。
8月20日−家茂の喪を発し、一橋慶喜が徳川家宗家を相続することを発表する。
8月21日-幕長交戦中止の朝命下る。
12月5日-慶喜将軍宣下。
12月25日-孝明天皇没(36歳)。喪が発せられたのは29日。
1月9日−睦仁親王(明治天皇)が即位。
3月5日−将軍慶喜が、兵庫の開港を奏請する。(3.19不許可)
3月−伊東甲子太郎、新撰組を別れ「高台寺党」を結成、高台寺・月真院に屯所を構える。
5月21日−土佐藩士板垣退助、中岡慎太郎らが、西郷隆盛と討幕挙兵を密約する。
5月24日−将軍慶喜が、兵庫開港の勅許を受ける。
6月15日−竜馬、京都着。河原町三条下ル車道酢屋・中川嘉兵衛宅を宿舎とする。中岡慎太郎に
「船中八策」を起草させる。この後、翌月にかけて京都で奔走し、「薩土盟約」、「薩土芸盟約」を成立させ、
岩倉具視などを訪問、武力討幕論を抑える。
6月22日−土佐藩士後藤象二郎・坂本竜馬・中岡慎太郎,薩摩藩士西郷隆盛・
大久保利通らが,大政奉還の盟約を結ぶ。
7月29日−長崎英国水兵殺害事件発生。松平春嶽から山内容堂宛ての親書を託され、土佐藩大監察・佐々木
三四郎に渡すため大坂へ向かう。→
【竜馬の足跡(66)進む/戻る】
8月5日−幕府、山城国を禁裏御料とするため領主に上地を命じる。
10月9日−竜馬、大阪経由京都着。酢屋に入る。10日、若年寄永井尚志に面会、大政奉還建白書の
採用を説く。この後、河原町蛸薬師下ル醤油商近江屋新助方に移る。このころ戸田、中島、岡内と諮り、
「新官制擬定書」を起草し、戸田から西郷に渡す。
10月13日−長州藩、薩摩藩に討幕の密勅が出る。
10月14日−将軍慶喜が大政奉還を上奏。
10月15日−朝廷、大政奉還を勅許。徳川慶勝、松平慶永、島津久光、伊達宗城、山内豊信、鍋島斉正および10万石以上の諸侯に上洛令を出す。
10月24日−徳川慶喜が、朝廷に征夷大将軍の辞職を請う。
10月24日−竜馬、岡本健三郎を伴い福井に向かう。→
【竜馬の足跡(72)進む/戻る】
11月5日−竜馬、帰京。福山、神山に松平春嶽の返書を渡す。この頃、「新政府綱領八策」を起草する。
11月15日−竜馬の投宿する近江屋に、夕方、中岡慎太郎来訪。岡本、菊屋峰吉も来訪。午後9時頃、岡本、
峰吉は所用のため外出。その直後、刺客に襲われ、坂本竜馬(33)、闘死。中岡慎太郎(30)、下僕藤吉は重傷。中岡は17日、絶命する。
11月−伊東甲子太郎ら「高台寺党」が新撰組に斬殺される。
12月9日−朝廷は、王政復古の大号令を出す。小御所会議で徳川慶喜の辞官・納地を決める。
1月3日−鳥羽・伏見で薩摩・長州藩兵と旧幕府軍が戦う(鳥羽・伏見の戦い。戊辰戦争の開始)。
1月7日-慶喜追討令下る。
1月10日−新政府が、徳川慶喜などの官位を奪い、旧幕府領を直轄とする。
1月29日−新政府が、京阪の豪商を招いて会計基立金として300万両の献金を命じる。
2月3日−新政府が、徳川慶喜親征の詔を発布する。
2月9日−有栖川宮熾人(たるひと)親王が東征大総督となり、東海・東山・北睦3道の軍を指揮することとなる。
2月11日-東征軍、京都出発。
2月23日−新政府の機関紙「太政官日誌」が創刊される。
2月30日−フランス公使、オランダ代理公使が参内謁見するが、イギリス公使パークスは参内途中を襲われ中止する。
3月14日−天皇が五箇条の誓文を誓う。
3月15日−新政府が旧幕府の高札を撤去し、徒党・強訴・逃散・キリスト教などを禁じた掲示を出す(五榜(ごぼう)の掲示)。
3月28日−新政府が神仏分離令を出す。以後、廃仏毀釈の運動がおこる。
閏4月 1日−英国公使パークス、天皇に信任状提出。
閏4月27日−新政府が政体書を出し、政治組織などを定める。
8月26日−天皇誕生日を天長節とする旨の布告が出る。
8月27日−明治天皇即位の礼が行われる。
9月8日−明治と改元され、一世一元の制が定められる。
9月20日−天皇が、東幸のため京都を出発する。