平成29年1月1日
The Cricket in Times Square (George Selden)☀☀☀
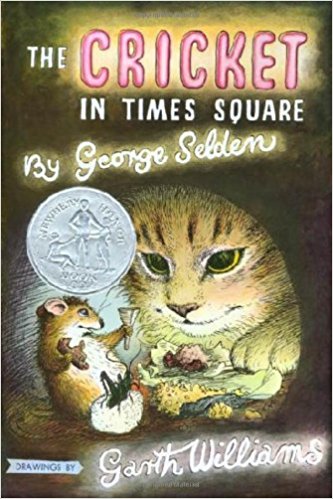
ニューヨーク駅のスタンドで新聞を売る家族のもとにあらわれたコオロギのChester。息子のMarioがマッチ箱に入れてペットとして飼い始める。そのChesterのもとに、夜、ネズミのTucker とネコのHarryが現れて、友達となる。意図せずに引き起こしてしまう騒動と、そのことの埋め合わせに起こすことになる奇跡。1960年ニューベリー名誉賞受賞作品で、楽しいお話しを年の初めの1日には読みたくて、手にした。そして期待以上だった。Marioという少年も家族も、Chester,
Tucker, Harryも、チャイナタウンの老人達も、車掌のPaulも、ランチカウンターのMickeyも、みんないいなあと思えて。皇帝とコオロギの話も。終わりもよくって、続編を読むことにした。休むことなく日々働き続けることでのみ成り立つ庶民の大変ともいえる暮らしの中でも、お互いへの思いやりを当たり前のことのように示せる人々。みんないいやつだから、個性の違いも楽しいハーモニーを織りなして、互いの関係を深めていくことになる3匹。大人になって、かくありたい姿が、そして関係が、ここにはすべてある。
“Delightful reading for the whole family.” (The horn Book magazine)
平成29年1月8日
Sill Alice (Lisa Genova)☀☀
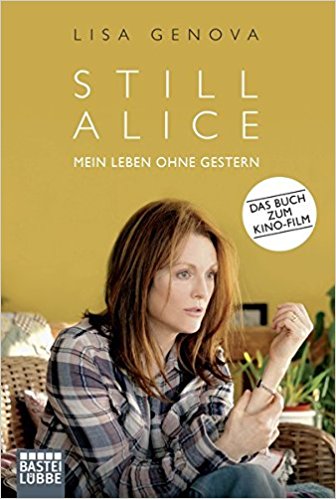
50歳、ハーバード大学言語学の教授アリスは、同じくハーバード大学教授の夫に、3人のそれぞれの道をしっかり歩んでいる優秀な子ども達(次女の進路だけには多少不満があるとしても)と、家庭も仕事も充実した日々を過ごしている。その幸せな日常に突然影を落とし始めるのが、記憶が突然途切れるという症状。急速に激しさを増し、ほどなく若年性アルツハイマーと診断をされることになる。自分の覚書のメモも理解できなくなる、慣れ親しんだはずの道でどこだかわからなくなる、紹介されたばかりなのに、思い出せないー症状はエスカレートする一方で、ついには、大学の職も去るしかなくなる。論文、学会、発表、講義、学生の指導―全てアリスの卓越した知性が当たり前のように享受してきたことが失われ、さらには読書する力や言語機能さえも退化していく。そうしたアリスの病の進行と葛藤が、一人称で語られる。夫も子供たちもアリスに理解を示しサポートをしてくれるが、アリスの苦しみが軽減するわけではない。自分ができてきたことを全て失っていき、自分が誰かも分からない日、されには自分が愛している人も認識できない日が来るーその確実にやってくる日にアリスはどう向き合うのか。物語はアリスの答えを見つける旅でもある。“What
if I wake up and don’t know who my husband is? What if I don’t know where
I am or recognize myself in the mirror? When will I no longer be me?” (p.291)
自分が自分でなくなる最悪の日には自ら死を選ぶことも考える。それでも、最終的には、タイトルの示す通り、結局、「アリスはアリスであり続ける」。アリスが彼女の知性で得てきた全てのことを失っていく混乱と葛藤の中でも示し得た冷静で論理的な思考と行動は、Alice
そのもの。何よりも、すべての能力を、病や事故で失ったとしても、「私を私にするもの」は残り続けるはず。それが人間のはず。2年間で大きな手術を2回もして、今の私も、前の私でないことだらけ、いくつも前には当たり前にできた能力を失って、まるで別の人間のようで無力感で途方に暮れるような時もある。でもこの私は、前と同じ私なのだ。人間の能力は、愛する人についての記憶を含めて、その人を形作るもの。でもその逆はない。持っている能力をすべて失っても、その人が誰であるかは絶対に奪えない。それが人間の尊厳のはず。Still
Alice―そうだよね。夫も子どもも、そうだとは認識できなくなっても、Still Alice。私に、同じ病をもってアリスほどの強さを示せるのかと問えば、ノー。自分の弱さともまた向き合っていくしなないーStill
Me.できる限りを丁寧に強く生きなければ。最後まで、Still Meであるために。この2年間、自分に言い聞かせている言葉を、また言い聞かせる。
“I couldn’t put it down.” (The Boston Globe)
分かります。