平成21年12月31日~1月3日
New Moon (Sephenie Meyer)☀☀☀

Bellaを愛するゆえに、離れていくEdward。その喪失を埋めるかのように、一人の魅力的な少年Jacobの急接近。Bellaの熱烈な求愛者がまた現れてというところが、物語の前半の読みどころ。そしてJacobもまたある秘密が・・・。
“Tees will relish this new adventure and hunger for more.”(Booklist)
そう、私もティーンです。
Eclipse (Sephenie Meyer)☀☀☀

EdwardとJacobという二人の求愛者の間でも、BellaのEdwardへの愛情は揺るがない。ただ、ヴァンパイアとの永遠の愛をかなえるためには、人間であるBellaが決断するべきこともまた多く・・・。
“Her story, recounted in hypnotic, dreamy prose, encapsulates perfectly
the teenage feeling of sexual tension and alienation” (The Times)
Breaking Dawnawn (Sephenie Meyer)☀☀☀

Bellaの決断後、Edwardと生きることは、何を二人にもたらすのか・・・。終わり—私は満足。
Bellaは本当に強い。精神的にも、そして肉体的にも。最終巻まで読んで、ともかくBellaが強いこと、愛することにひたむきなことは印象的だった。もちろんこのシリーズのファンの少女達は、EdwardとJacobという、まさに対極にして究極の魅力的な二人の男の子に恋されるストーリーに一番に胸をときめかすのだろうけれど、その彼女達だって、冷静に考えれば、このBellaのような選択、こんな二人の素晴らしい求愛者を前にしても、誰もしないのでは。少なくとも私は絶対だめ(17歳の自分に戻れたとしても・・・ホント。)自分に痛いことがあまりにも多すぎる。それを、ただただ愛のためにやっていくBellaは、まさに普通の女の子ではなく、愛される資格が十分ありの健気で強くて格好いいヒロインなのであろうーーと結論。
年末から3日までは、1年で我が家の人口密度が一番高くなる。冬休暇で帰広する息子、その上に彼の友達が訪ねてきて、かつ泊まっていくから。一方、彼も、友達のところにふらっと泊まりに行き、朝今度は一緒に帰って「ごはんは?」という感じ。親としては、いつでもおいしい食事をいつもより多人数で食べることのできる用意、すなわち冷蔵庫に様々なシナリオにそなえて材料を詰め込んでさえしていればいいということで、食事を要求される以外の時間は自由。いる時ぐらいは、食事を作ってやりたいと思えば、こちらとしても外出するのも嫌。というわけで、結局、家で多くの時間が空いている。それをいいことに、3巻読みきり。英語がとても簡単なのと、途中で、少しズルをする(だって、ハイライトの「戦い」は、ティーンエイジャーではない私には、さすがにそこまで「ハラハラする」というわけにはいかないので・・・。これが、ティーンとの決定的な違いかも。)ので、本の見事な厚さの割りに、あっという間。激しい頭痛が絶え間なく3日連続(これが、今一番の、人生のロマンスの要素から程遠いことである)という今年は悲しいスタートだったけれど、耐えやすくはしてくれたみたい。
口にしたら赤面するような素直な愛の言葉も、またいいよね。いくつになっても人生はロマンス一杯のはずという持論を肯定してくれるような話し。さすがに読み終えた直後でさえも、一流の文学作品と言うほどには盲目になってはいないけれど、女の子が夢中になって読む理由はちゃんと理解した。長い時を生きているがゆえ、そして自らがBellaに自分が課す犠牲に悩むがゆえに、情熱的でありながら、一方でストイックで古典的な愛の言葉を吐き続けるEdwardと、自分に勝機が少ないだけに、悲しさを秘めながら、ひたむきに、時には挑戦的に、ストレートに愛情を言葉で示し続けるJacob、その二人がBellaに言う全ての言葉が、おそらく恋に恋する少女のまさに夢だろうから。そして、そういう時代をはるかに過ぎても、十分二人のやり取りは楽しい。何箇所か読み直したのも、そうした二人の言葉。いくつになっても、甘いことばはおいしいよ。。。これが最終結論。息子に教えてやろうかな。ただそう思って使ってくるような男性は、また少女達の最悪の反理想なるものに違いない。彼には失礼ながら、他の諸々の条件も不十分だろうし。止めた。
人生はロマンスに満ちていると信じている仲間でもあった母の墓参りーー息子の帰郷に合わせて正月明けにも。あなたの娘は、今年はヴァンパイアロマンスからスタートしましたーーと報告。
ガザへの地上侵攻が始まった。世界の人々の、人生のロマンスを信じる想いがまた喪失するようなニュース。
平成21年1月18日
Into the Wild( (Jon Krakauer)☂

実話は、起こったこと自体は最初から知っているゆえに、どこまで出来事に関わった人に共感していくかで物語として読めるかどうかが決まる。詳細なインタビューで1人の若者の軌跡を丁寧にたどる作者の努力自体には感嘆したけれど、親を完全に拒絶し、それまでの人生からも、最後はいわゆる文明なるものからも離れて、冒険を求め、アラスカの荒野で餓死した若者を、最後まで読んで理解してみたい気持ちが失せた以上、私には読み続けることは無理だった。悲劇的な出来事とは思ったけれど、若いからねと素直に思えないのは、私がまさに同世代の若者を子どもに持つ親の方だからかもしれないし、今の不況の中で、住むところ、食べるものを確保しようと、多くの人々が苦闘しているニュースを毎日聞いているからかもしれない。日常をどこまで生き抜くかの努力こそ、挑むべき冒険なのに、と思えて。この書評の最後の部分は私にはおきなかった。丁度100ページと、物語の半分近くまで読んでいたけれど、である。
“Compelling and tragic. Hard to put down.”(San Francisco Chronicle)
平成21年1月23日~1月28日
Historian (Elizabeth Kostova)☂

アムステルダムに住む16歳の少女が、偶然書斎で見つけた父親の本の謎を解き明かすストーリー、らしい。というのは、816頁の小説の、丁度200頁で見切りをつけたから。引き込まれてしまうかも、と、夜寝る前に期待し、読むとすぐ眠くなるというパターンが続いた。旅をしては彼女に一部ずつ語っていく父親の回顧の話のペースがあまりにもゆっくりで、「また次の旅まで待つの?」という間延びした感じ。私だったら、父親に一日中全てを話させるけどな。あの程度の話なら。翌日の夜、素晴らしい書評を眺めては、もうちょっと努力して読み続けようかと思うのだけれど、そうなると、自分がただ楽しいからしている読書なのに意味がない。その眺めた書評が、本の最初の数頁を占めている書評の最初の
これーー“Part thriller, part history, part romance…. Lostova has a keen sense
of storytelling and she has a marvelous tale to tell.”(Victria A. Brownworth,
Baltimore sun) 3つの融合が最後にはおもしろくからむのだろうけれど、200頁の時点では、もう次のページをめくる気は失せていた。
平成21年1月30日~31日
Frost at Christmas (R.D. Wingfield)☀☀☀☀☀
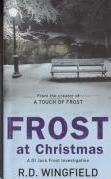
クリスマスまで10日、英国の田舎町デントンで、8歳の少女が日曜学校の帰宅途中で失踪する。事件を担当することになったFrost警部、この、自分の机さえ綺麗にできない、書類仕事は片付けられない警部は、事件に対しては、解決まで諦めない、まさにプロである。小説の最初のシーンが、どのように事件とからむのか、ほとんど最後までわからない構成で、しかも、様々な悲しい人間の性が示され、それに過去の事件までからまってきて、全く予想がつかない展開である。下品なコメントもする、いわゆるガサツな男、でも、彼のキャラクターは憎めない。135頁では、声を出して笑った。何よりも細かい様々なストーリーがたくみに絡み合う感じはすごい。彼の妻が亡くなっていること自体も、小説では早くから示されながら、彼との本当の関係は、サスペンスに満ちて、部分的に、そして段階的に示されるのである。223頁,243頁、そして、337頁。こうした展開にはまいった。探偵物の主人公が、人間としても魅力的で、正義感があって、物語が並の読み手には展開が想像できないサスペンスに満ちていたら、おもしろいはず。
裏表紙にある
“Affecting, frightening and, especially in Frost’s dialogue, extremely
amusing.” (Listener)
シリーズはまだ5冊あるようで、自分がまだ読んでないからラッキーと感じたことが、私のはまり方を物語っている。この本は、クリスマスのレストランのディナーの予約時間まで書店にいて、買った5冊のうちの一つ。時間が限られていて買うと、どうしても、表紙と、背表紙の書評が決め手になる。そして自分の勘(これがFrost警部と違って冴えないことが多い)。クリスマスの翌日に最初に読んだTwilight
ヴァンパイアーロマンスははまって、すぐ続編3冊をお正月にかけて注文して読んだ。つまり、大アタリ。でも、今年になって読んだInto the Wild もHistorian
も、途中で見切りをつけた。つまり、ハズレ。そして、残った2冊の一冊は、このクリスマスのついたタイトルに引かれて買ったけれど、正解。クリスマスに買って最後に残っている5冊のうちの最後はOmen だから、おそらく読まないままの気がする。全然読みたいと思えないもの。あの日は、書店で見て一度読んでみようかなと確かに思ったのに。幸せ気分のクリスマスには、いつもは読めない怖い話も、なんか強気になって読めるような気になるらしい。これも、Frost警部が物語の中で暴いてしまうような人間の悲しい性の一つかも。
平成21年2月1日
The History of Love (Nicole Krause)☀☀☀
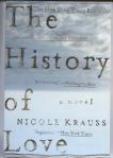
80歳の老人、Leo、その少年時代からの友達,Brunoの淡々とした、穏やかな、そして老いた者だけの持つ物悲しさも感じさせる一日から小説は始まる。そして、父親が母親に与えた本、The
History of Love の中のヒロインにちなんで名をつけられた14歳の生き生きとした少女Almaが登場。このThe History of
Loveをめぐるミステリーは、60年の月日にまたがり、異なる理由で立ち切られた様々な愛を描きだしながら、LeoとAlmaの接点へ近づいていく。ユーモラスなLeoの語りに微笑み、生きることの力に満ちたAlmaの語りに元気が出ていたら、涙がじわっと出る箇所に出会うし、なんだかミステリーは少しずつ分かった気がしているけれど、終わりまで、そのミステリーを生み出すしかなかった人間の性を見せつけられるし、といった小説だった。この話を読み終えないで置く事は難しい。そして最後の最後の頁で、わっと泣いた。沢山の絶賛の書評が載っていたけれど、一番自分の思いに近かった部分は
“Even in moments of startling peculiarity, Krauss touches the most common
elements of the heart. In the final pages, the fractured stories of The
History of Love fall together like a desperate embrace.” (Ron Charles,
Washington Post)
“Wonderful and haunting…deftly layered….Its mysteries are intricate and
absorbing and its characters unforgettable….Not quite a thriller, not exactly
a coming-of-age story, nor a Holocaust memoir, The History of Love manages
to be all three and also something more: a breathtaking mediation o loss
and love. It’s the sort of book that makes life bearable after all.” (Miami
Herald)
良い本を読むと家族にストーリーを言いたくなる。今回も夜説明しながら、涙で話せなくなった。粗筋だけを口にすると、悲しくなる。でも、これをそれだけにさせなかった作者はすごい。夜、眠れなくて、またストーリーを思った。たとえ、望む形の愛情を手に入れたと思った人生でさえ、愛する者の喪失を免れ得ない。だからこそ、また人生は愛おしいのだとわかる年にはなった。
そして、この小説が描いたように、愛そのものは永続できるということも。喪失後の想いさえ、無ではなくて、名をつけれる。小説にあったように、“Word
for everything” でも、自分にとって代替不可能な者たちの名は、そのまま代替不可能な「自分の人生」でもある。大事に、大事に、毎日を生きようっと。
平成21年2月9日~10日
Everything is Illuminated (Jonathan Safranforer)☂

92頁で一旦ストップ。素晴らしい書評が沢山ついていて迷いながら。変わり者の青年とこれまた一癖も二癖もある祖父と、ユダヤ系アメリカ人の人探しの旅。結構おもしろい箇所もあるし、英語での通訳の箇所や、犬との絡み合いなんか思わず吹き出した。謎解きの旅は始まったばかりだから、今からがいよいよなのだろう。でも、過去の出来事と現在と行ったり来たりする形式に、なじめないまま、ネットで注文していた本の方が届き始めて、そちらをどうしても読みたくなったので、自分の気持ちに素直に止めることに。これは、また戻って読むつもり。そうするべきだろうなと思わせる書評の一つ:
“Read it, and you’ll feel altered, chastened—seared in the fire of something
new.” (Washington Post Book World)
平成21年2月11日
The Curious Case of Benjamin Button (E.Scott Fitzgerald)☀☀

生まれたばかりの赤ちゃんが、もしすでに老人であったら、物語はその設定で始まる。さらに、全ての
人々が辿る老いへの道を、全く逆に進むとしたらーーまさに、そうした生を生きたBenjaminの人生を綴る短編である。感傷的な言葉を一切排除し、まるで、小さなメモ帳に綴られた一人の奇妙な人生の出来事を淡々と綴ったという感じ。読んでみて、しばらく考えてしまう。上映中の映画を見てから読んだので、映画(これは、原作とはかなり違います)の印象とどうしても一緒にして、考えてしまう。この奇妙な人生を生きるということは人間にとってどういう意味を持つのだろうと思った。出会う人々と同じような時を生きて、共有する記憶を重ねていくという仮定があってこそ、その出会いにも意味がある。親も、友達も、恋人も、子どもである。別れ自体は不可抗力で避けられない。でも、少なくとも、同じ方向を向いて生きて、その人生を分かち合ったことに、そして分かちあおうとすることに意味があるのかも。原作も映画も淡々と描いているけれど、結構考えてしまった。この小説の終わり、”He
did not remember. He did not remember clearly whether milk was warm or
cool at his last feeding…”(p.30)がある。全ての赤ちゃんの始まりの記憶が、喩えるなら「甘いミルク」の匂い、そのものなのなんだと思った。でも、Benjamine には逆だった。奇妙で、悲しい。
丁度、子どもから家へメール。何かの授業のレポートで、自分の周りの人々が自分を何に喩えるかを使わなければいけないので二人とも書いてくれない?とだけ。それでも、いつもよりは長いメール。早速張り切って、自分が先に書いて、家族にも、続いて書いてやって、と頼む。「生クリームの白いケーキ」と正直に書いて、しかも括弧して、(母さんは、本質的に、誰に対しても悪意を持つことがない、あなたの優しさをいつも高くかっています。)家族が後で続けて書いたのを見ると、私の書いたのも納得したけれど、一番に浮かんだのは「マラソンランナー」として、パターンを真似て(一旦始めたら、粘り強くやり遂げるところかな)とか書いてあった。返信として押しながら、一人でかなり感傷的になった。この小説の影響らしい。ケーキとマラソンランナーか、そうあなたを見ている私達も、いつかは必ずあなたより先に去るしかないけれど、少なくとも今は同じように記憶を共有して歩もうね、と思った。いつまでたっても「有難う、みたいなメール」が来ない。メールのタイトルを「無事着いた???」にして嫌味に催促したら、メールのタイトルを「Re:着いた」にして返信してきて、中身には触れず。このあたり、なんかねえ。一人だけ感傷的になって損した。自分の母親が結構執念深いことに、今だに気づいていないのが、またケーキぽい。「喩えれば(ミルク)そのものの時代から20年、今もさほど変わらず(生クリーム)です・・・」と書けば、反応があったかも。
平成21年2月15日
Slumdog Millionaire (Vikas Swarup)☀☀☀☀☀

インドのモンバイのスラムに住む18歳のウェイター、Ram Mohammad Thomasが警察に逮捕される。クイズ番組で全13問に正解し、10億ルピーという賞金を得た翌日である。不正を働いたのでなければ、彼のような者に正解など出来ないという疑いである。実際は、何が起きたのかーー物語は、そこから始まっていく。過去の出来事が、前後しながら、彼自身の口から語られて、それがクイズ番組での正解の謎と関わってくる。「わあ、おもしろい」というのが、読んでいる最中に何度も自分に向けた感想である。本当に、小説を読む楽しさを味わっているという感じ。まさに流れにのって、読んでいくだけ。彼の不思議な名前の理由も、彼の人生もだんだん理解する、これこそ、謎解きのようなおもしろさ。同時に、主人公やその周りの人々が生き生きとして伝わってきて、楽しいことも、傑作な出来事も、人生の悲劇も、不条理も、そして、幸運も、一緒に彼とともに感じているような気分。何よりも、主人公をきっと好きになる。幸せを願ってしまう。窓から、2月とは思えないような穏やかな春の陽射しを眺めながら読むのに、まさにふさわしい小説。読み終わって、ああ、楽しかった、と思った。映画が話題になっているので、先に原作を読んでみたけれど、こんな原作を基にしたら、映画もきっといいだろうな。
“Readers will consider themselves winners after spending time in the world
of this very rich tale.”
(The Washington Post Book World)
その通りだった。
平成21年2月20日
A Touch of Frost (R.D. Wingfiedl)☀☀☀☀☀

英国デントン市、フロスト警部のシリーズの一冊。おぞましい連続強姦事件、少女の失踪、強盗、ひき逃げ、様々な事件が起こる中で、フロスト警部が、飄々と、嫌味な上役の言葉をかわしながら、一緒について回る若い同僚の批判的な眼差しも物ともせず、あっという間に全ての真相にたどりつく。その間に、事件に関わる人々や警察の人間模様が、フロスト警部自身の過去の妻との思い出とも関わりながら、描かれる。よくもまあこんなに一作に盛り込めるよね、と読み終わると思ったのは、前に読んだFrost
at Christmasと同じ。だらしなくて、下品なコメントも往々にするフロスト警部だけど、彼の人間らしさは好きだなと思えるのも一緒。社会ではじかれてしまった存在に向ける眼差しだけは、優しいのよね。犯罪に対しては、鋭く、弱い者に優しい。これで十分。さらに、几帳面で、上品で、そして家庭にも恵まれていたら、あり得ない存在になる。今までの2作のレベルで、全6作を書いたとしたら、作者もすごい。まだ読んでないシリーズの4作が本棚に並んでいるのを見て、ニコニコしてしまう。楽しみ。最後に、いつも一緒に回った若い刑事の尊敬を勝ち得るのもいい。”Not
very long, sir”(p.425)――わっときた。いい箇所ね。
“What impresses most is the extraordinarily vivid interplay between the
police characters. Frost himself is splendidly drawn.”(The Times)
平成21年2月23日~2月26日
Night Frost (R.D. Wingfield)☀☀☀☀☀
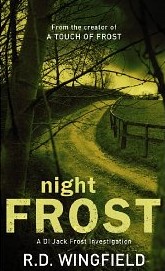
英国デントン市、フロスト警部は、インフルエンザで人手不足の署内で、一気に押し寄せる様々な事件に対処する。少女の自殺、老女を襲う凶悪犯罪、脅迫の手紙、不審火――いつものことながら(同じような構成なのに、飽きさせないのはすごいかも!)全ての事件がからみあって、短期間で謎が解き明かされていくのも一緒なら、フロスト警部の汚いオフィスも、書類仕事一切だめなのも、下品なジョークも一緒。俗物の署長も相変わらず。そこに毎回登場するらしい、新顔。今まで読んだ2作と一番違っているのはここで、フロストに最後は尊敬の念を持つ若い警官や刑事ではなくて、出世欲がいやらしいほど旺盛な刑事が登場する。こうした若者に対しても、フロスト警部の変わらない彼らしさや人間的なゆとりが発揮されることがわかって、今まで以上に楽しめた。ふっと笑う箇所が一杯ある。事件の性質はいつも以上におぞましいので、楽しんだ、楽しんだ、というのは気が引けるのだけど、こうしたジャンルの小説では、事件はいわば背景で、解決する過程の方を楽しむのだから、気にしないことにして、書くことにすれば、かなり楽しめた。フロスト警部と同僚達とのやり取りのいくつかは、つい家族にも無理やり披露してしまったけれど、このシリーズを読んでいなくても噴出したぐらい。
ちなみに、
取り調べの男について同僚との会話、完全なる俗物Mullett署長はジョークの一番のターゲット。
“you know what a slimy little sod he is,’ ‘Yes,’ ‘I sometimes think he’s
Mr. Mullett’s illegitimate son.’(p.231)
その俗物署長は、結果ばかり気にして犯人逮捕時にも法外な要求。だから、フロスト警部思わず、
Stupid Sod. How the hell do you get a knife-wielding mass-murderer down
from a 200-foot crane by the book? (p.348)
でも、フロスト警部は、筋が通らないことには、ちゃんと発言する。だから
手柄や出世にとらわれた、同じく俗物の若いGilmore刑事には
‘We’re supposed to be a team, son,’ said Frost, ‘not all fighting for Brownie
points,’ (p252)
権威をかざして、特別扱いを要求する輩には
‘Do you know who I am?’ ‘I know what you are’ (p.291)
という感じ。
最後の凶悪犯罪の解決の時は、何か、人間の性って悲しいよね、と思わず思い(354頁)、最後の頁では、にっこり笑った。良かったじゃない、フロスト、って感じで、彼の愛すべき仕草が浮かんだぐらい。あと読めるのが3作しか残っていないのが、すでに残念。
“Multiple Cases, multiple bodies and lashing of police in-fighting. Fast,
furious and funny.”(The Daily Telegraph, London)
この小説、今回一番受けたのは、ここかも。
‘He’s drunk’ hisses Gilmore.
‘He’s tired,’ said Frost. (p.27)
丁度、N大臣の国際会議での不可解な会見の模様が印象深い頃で、なんか一人で受けた。
N大臣も、フロスト警部のような人物がこう一言言ってくれたらよかったのにね。「疲れているんだろ」って。
平成21年2月27日~3月1日
Hard Frost (R.D.Wingfield)☀☀☀☀☀

英国、デントン市、フロスト警部の4作目。凶悪犯罪と様々な犯罪との見事な絡み合い、短期間に解決、というのも、俗物の署長も、新顔の登場も一緒。今までの3作と違っていたのは、子どもの失踪・誘拐殺人が最初から出てくる点で、犯罪自体がずっと生々しく感じること、新顔がいわゆる新しい人物だけではなくて、フロスト警部の元同僚で、自分の娘の交通事故死にからむ未解決の捜査について、フロスト警部を逆恨みしている刑事も登場という点である。それから、もう一つの違いーーフロスト警部の孤独をいつも以上に感じたこと。彼の私生活での孤独(256頁、今まで以上に感じます)、俗物の署長の嫌らしさ(今まで以上に感じる。‘I’m
on holidays so Mullett won’t suspect me.’ ‘If you were dead he’d still
suspect you,’ said Wells grimly. (p.13)、Mullett removed his glasses and
polished them sadly. ‘I can’t save you from the wolves this time, inspector.’
He oozed insincerity. When have you ever? Thought Frost. (p284) 実際、こんな人間が上役や同僚だと、私なら、疲れる、疲れる。。。愚痴りたくなる。そして、フロスト警部だって、全く疲れないわけではないみたい。ただ、フロスト警部は、ジョークで対処、人間の大きさの違いというところ)、そして、最後の最後の事件の解決の仕方、人ってそんなに変わらないよね、違いすぎる人間を理解しないんだよね・・・とちょっと悲しく思ったり。亡き妻も含めて、彼を理解する者が少ない孤独を今回は何回も感じてしまう。ただし、読者をかなりすっきりさせてくれる(!!!)同僚の爆弾発言の箇所があって、その埋め合わせはしてくれているのかも。まあ、のっけから、ジョークを繰り出すフロスト警部は、孤独を抱えながらも、飄々と生きれるのだとは信じている。そんなこと思いながら、読み終わった私――作者が、すでに私の中に、フロスト警部に対する愛情を育ててしまったということでしょう。まさに小説の力。孤独を抱えながら、”The
joy of working with Frost was that he never let the circumstances of the
case he was workng on get him down.(p.33)”と思わせるような、愛すべき主人公を生み出したというわけだから。
最後の最後の頁の行動――彼にとっての「真実の意味・正義の在る所」がわかって好き。こんな警察だといい。
“Inspector Jack Frost is deplorable yet funny, a comic monster on the side
of the angels” (Guardian)
4作目になったせいか、もしかしたら、ここが引っかかることになっていくのかも・・・という想像が働くようになって、少し当たったりも。ところが、ある意味で、最後にきて終わり方の予想は全く違っていた。本当に小説家って凄い。私になんかに、たやすく結末のオチを想像できるようにしてないから、シリーズの魅力があり得たのよね。続けて読んでいきそうな感じ。ただ、読みたいけれど、後2作しかもうフロスト警部を読めない、とためらう私もいる。
平成21年3月6日~9日
Winter Frost (R.D.Wingfield)☀☀☀☀☀

フロスト警部の5作目。謎めいて、意味深で、後になって全てわかってくるような短いオープニング、短期間の間に絡み合う、連続猟奇的事件を含めた、複数の事件、全く理解のない上司Mullette署長、新顔――全ていつものパターン。でも、今回の特徴は、Mullette署長が、ずっと気に障らないし、むしろ、一貫して、経費削減と騒ぎ続ける彼に同情さえ覚えること(フロスト思わず言ってしまう――’How
much is this going to cost?’ shrilled Mullett. ‘Cost?’ echoed Frost incredulously.
‘What the hell does the cost matter? A police officer’s life is at stake.’
p.467) 、新顔の若いMorgan刑事が肝心な時に大間抜けな行為(フロストさえ言ってしまう――’Go and get me a mug of
tea and a bacon sandwich and bring it to the murder incident room. If you
turn up with cocoa and a fairy cake, you’re sacked.’ p.75)をしては、何回もフロストを窮地に(時には、思いがけない副産物も!)という状況、である。そのせいか、フロストの置かれる状況自体は、今まで以上に深刻なのだけれど、同情も、心配もせず、ただただフロストらしさ(やる時は本当にやる!!)を楽しみながら、最後まで読んだ。寝る前に読んでいたけれど、最後は、朝起きるなり読み始め。もう読み終わるまで待つのは無理だった。事件自体は本当におぞましいし、フロストのジョークや発言には、女性としては抗議の一つもするべきだろうけれど、正直、何度も何度もくすっと笑って、あ、と事件の発展に驚き、という、この種の小説の楽しみを全て与えてもらって、もう文句なし。もう一つ、今回の違いは、最後の最後の頁が、まさに全ての「解決」になっていること。最後の最後、ホント巧いです。作者はすごい。読み終えた瞬間、「読んじゃった、残念」と思った。後一冊しか、残っていない。
“If you enjoy crime fiction at all, read this. If you’ve never read a crime
novel in your life, start with this one” (Morning Star)
“R.D. Wingfield has created possibly the most accurate picture of police
work in crime fiction today…Winter Frost is an absolute cracker.”(Sherlock
Holmes)
その夜、コンサートで、マーラーの「巨人」を聞いた。このフロストシリーズと同じ、まさに最初から終わりまでエンターテイメントと思った。これでもか、これでもか、って聞きどころを散りばめている。マーラーの良さを再認識。頑張るのは素晴らしいこと!
平成21年3月12日~14日
A Killing Frost (R.D.Wingfield)☀☀☀☀☀
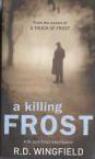
デントン署、フロスト警部のシリーズの最後。いつもながらの、ショッキングな始まり、連続凶悪犯罪と複数の犯罪の絡み合い、短期間での犯罪と解決の繰り返し、署内の人間模様、責任は取らずに手柄だけ取りたい完全俗物Millette署長。今回の新顔は、新人でも、野心家でもない、フロスト追い出しに画策する本物の悪意の持ち主、Skinner警部チーフ。それゆえ、フロストの災難は、全6作で最大のものとなる。犯罪もいつも以上に生々しい。それでも、相変わらず、おかしい。今回は特に、Skinner警部が、自分の都合のいいように勝手なことを言ってはヒステリックに命令する度に使う言葉が、“comprende?”で、フロストの応答には、毎回笑ってしまう。ちなみに最初は、“Comprende,
signora.”(75頁)。“comprende?”—しばらく家族に連発するマイブームに。悪意をもって自分を陥れる上役達に、淡々と応答、自分がするべきことだけはやり通すフロストだから、同僚だって、わかるんですよね。“So
who are you going to obey?” asked Frost. “A fat-bellied sober chief inspector
or a drunken sod like Me?”(258頁)ずぼらで、下品で、正義感があって、捜査にだけは頭が切れて、エネルギッシュシュ、そして、何ともいえない人間味。6作全部に出てくる亡き妻との日々の回想箇所、今回のクリスマスの思い出は鮮烈。今まで6作、読む度に二人の関係について私の印象は変わった。でも、最後が、これでよかった。「誰かをたまらなく愛し、その人にたまらないほど自分も愛されたことが幸福。たとえ、それが持続はできなかったとしても。だから、いいよね、フロスト。」思うことができたから。それに、最後、なんか「希望」も見える。もちろん、いつも通り、事件も彼の災難も、最後は、きっちり、すっきりで、思わず、Millette,Comprehende?
“More twists than a bucket of eels.”(STUART MACBRIDE)
“Indecently exciting. The pace is relentless…and Frost himself is, as
he might himself say, a flaming delight.”(Daily Telegraph)
もうこれからのフロスト警部には会えない。ただ、私の中では、フロストはデントン署内で今日も活躍中(凶悪事件の発生率はぐんと減っているといいね。デントン市の犯罪防止もしっかりやってくださいよ。)。私生活も、きっと“a
flaming good!” ああ、でも、会いたいよ。
平成21年18日~22日
Everything is Illuminated (Jonathan Safranforer)☀☀☀

(一度やめた本ですが、読んでみました。)
アメリカからウクライナまで、かつて戦時にナチスから自分の祖父を助けてくれた女性を探してやってきたユダヤ人のJonathanの通訳をして、ウクライナ人の若者Alexもまた自分の祖父と犬とともに旅をする。英語のわかるAlexが、全くお互いの言うことがわからない彼の祖父とJonathanの間を取り持つ、そのやり取りも、この犬(名前も絶妙!!)の行動も、笑い、笑いそのもの。でも、彼等の旅の終わり、戦争時に起きたことについての発見は、Jonathanだけでなく、Alexの人生にも及ぶ。ある程度予想したいたようで、全く予想していなかったような、そんな最後だった。誠実な人間にとっては、現在を生きることは、過去と切り離せない。だから、そうした人間は悲しくて、いとおしい。「悪い人間」でないほど、過去を抱えて、生きるしかないから。”I
am not a bad person,” he said. “I am a good person who has lived in a bad
time” “I know this,” I said.(Even if you were a bad person, I would still
know that you are a good person.)(’p.227) “Grandfather is not a bad person,
Jonathan. Everyone performs bad actions. I do. Father does. Even you do.
A bad person is someone who does not lament his bad actions.”(p.145) 本当だと思った。いくつもはっとするような言葉にあう。Jonathan自身が祖父までの家族の歴史を後でつづった小説、AlexのJonathanへの手紙、そして、旅での出来事、の3つが絡みあう複雑な構成で、実際、現在と過去を行ったり来たりというのに入りこめず、100頁までいかないで読むのを止めてしまっていたが、今回は、今まで小説では見たことがないような様々な実験的な言語の使い方も含めて、笑って、はっと胸をつかれて、最後に本を置きながら、最後まで読んでよかったと思った。この小説にもう一度戻ったのは、沢山の興味深い書評のためだから、感謝。
“Read, you can feel the life beating.” (Philadelphia Inquirer)
“A book that illuminates so much with such odd and original beauty.” (Daniel
Menderlsohn, New York magazine)
この小説で個人的にはっとした箇所。
What’s it about? She asked.
It’s about love.
She laughed. They’re all about love. (p.202)
私が本を読むのも、どんな本も愛について書いてあるからという気がする。身近な人の寂しさを埋めてあげることにおいてさえ、私は無力。そんな無力な想いを人生で感じなければいけないことについて、私は幼い時にも、若い時にも、考えてみれば数年前まで、本当には知らなかったように思う。でも、その頃知らないながら読んでいた小説の中の、そんな想いを持った人々が、今頃になって私を支えていることに気づく。無力だけれど、いつか愛した人々にまた会えた時、がんばったと言ってもらえるように、小説の中に生きていた人々のように、今自分にできることをがんばりたいと思えるのも、そうした小説のお陰。居なくなった人を恋しく思い、生きることを楽しく思えない人を前と同じように幸せにすることはできない。だから悲しい。でも、そんな誰にも代わることができない一人の人が人生に存在したから、それだからこそ、その人生は素晴らしいのだとわかるのも、小説のおかげである。多分にその人の子どもであるがゆえに似ている自分は、いつか、そんな同じような喪失の孤独に耐えて生きることができるのか、または、愛する人を孤独にさせるという憂いをかかえて逝かなければいけないのか、この数年、考えることが多くなった。どちらもとても悲しいから、ともかく今を大事に生きるだけ。
4月1日
Walk Two Moons (Sharon Creech)☀☀☀
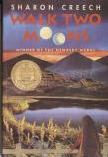
母親が父親と自分を残して家を出た後、13歳の少女Salは何を思い、何を求め、何を見つけるのかーーという少女の体験を描いたニューベリー賞受賞の児童文学。対象が青少年だからと軽く流すぐらいのつもりで読み始めたけれど、少女の母親への思い、その思いを見つめさせる父親、友達、彼等の家族、祖父母、といった人々のエピソード、そして人間の死と生についてまでが重層的に描かれていて、最後まで引き込まれて一気に読んだ。最後まで謎解きのような展開で、最終的には、Salを含めて描かれた全ての人々を優しく暖かく感じられる結末が、児童文学の賞にふさわしいと思えるような作品。小説って、自分の今の気持ちに忠実だから、一番印象に残ったのは、Salの祖父母だった。”That
bed has been around my whole entire life, and I’m going to die in that
bed, and then that bed will know everything there is to know about me.”(p.79)この”marriage
bed”の話し、とても好き。”I’ve been by her side for fifty-one years, except for three
days when she left me for the egg man. I’m holding on to her hand, see?
If you want me to let go, you’ll have to chop my hand off.”(p.256) 幸せな結婚の姿は、文化を超えてかわらない。そして、一人になる時が、誰にも訪れることも。どんなに大変でも、最後まで幸せでいる努力をするしかないことも。”This
ain’t your marriage bed.”(p.273)――Salのような言葉を、父に心の中でつぶやいた日が私にもあったことを思い出した。
“Packed with humor and affection…an odyssey of unexpected twists and surprising
conclusions.” (Newbery Award Selection Committee)
平成21年5月6日
The Miracle at Speedy Motors (Alexander McCall Smith)☀☀
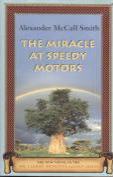
大好きなシリーズの9作目。Ramotswe、Makutsiにまた会えるだけで、嬉しいし、Matekoniも相変わらずいいし、このシリーズは、最初から読んで、主人公達の生き方を追ってきて、好きになって、ますます好きになることを少しも疑わずに読める、そんな物語だと、また確認。今回は、あっという間に読んでしまって、「あれもう終わったの??」的な不謹慎なことを一瞬感じたりもした。だって、一作目から、様々な事件の依頼を通して描かれる人間模様と、それらに答えを示していくRamotswe自身の人生の進展に、そして、Makutsiの登場と、穏やかなペースの中にも、十分ハラハラもしてきたのだろうし、結局、9作目になったら、2人の人生は、もう何があっても大丈夫と無意識に思ってしまうのかも。それでも、読み終えた瞬間の一瞬のあっけなさの後、幸せな満足感がこみ上げた。「悪意」に、「奇跡」に、Ramotsweが最後に出した答えは、確かに、彼女を知り尽くした気がする大ファンとしては、当たり前にも思えたけれど、やはりすごいこと。そして自分もそうありたいこと。ペーパーバックが出るのを待っていたけれど、もう待ちきれないで買って読むことにしたのは正解だった。ゴールデンウィークの終わりの夜は、優しい気持ちで締めくくり。
昨日は「子どもの日」。子どもの時、子どもであることはイコール幸福であることといつも信じさせくれていた父のところに顔を出し、また、「子どもの日」を楽しい「冒険の旅」(コレ実に一杯しました!!時には、カナリツカレタ・・・。)の思い出で一杯にしてくれた子どもにもメールしておいた。2人がそれぞれ元気でいてくれるだけでいいよねと思った。そうしたわずかな自分の行為だけで、いつもながら勝手な自己満足に浸っていたら、夜、家族から、「母の日」のワインが用意されていた。今年のその日は、大学の行事で家にいないからか。人生は、優しい人がいると、本当にいいものになる。もっと、自分も頑張らなくてはと自然に思えるもの。“It
is not at all foolish to hope for miracle,” she said. “No, it is not foolish,
Rra. Not foolish at all. There are many miracles.”(p.213) 優しさだけが、「奇跡」を一杯もたらすんだよね。
“Delightful…Millions of readers around the world seem to hunger for the
kindness, dignity, and humor McCall Smith celebrates in Mma Ramotswe.”
(The Oregonian)