平成20年1月28日~29日
Life of Pi (Yann Martel)☀☀☀
あっという間に読める本。今まで読んだ本のどれにも、このストーリーは重ならないと思う。全く先を想像することは出来ない展開である。一言でいえば、最初から生存だけは読者にわかっている、インドの少年と動物(しかも・・・虎)の漂流記ということになるのだろうが、人が生きることは、そして、その意味はと、読み終えてから考えてしまった。かなり好きな小説となった。虚構でしかあり得ないようなストーリーでありながら、それを一時も読んでいる間は思わせない。生きることは尊いことで、それゆえ、私達は極限までその生とあることを努力するのだと信じる。表紙のボートの絵を見るだけでも、読みたくなるかも。
“Life of Pi” is a real adventure: brutal, tender, expressive, dramatic,
and disarmingly funny…It’s difficult to stop reading when the pages run
out” (San Francisco Chronicle)
平成20年1月30日~31日
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (Mark Haddon)☀☀☀☀☀
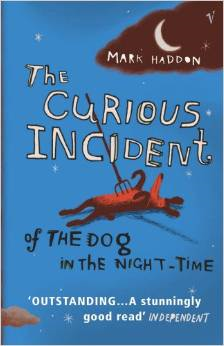
これも上に挙げた本と一緒で、表紙の絵だけ見ても読みたくなる。また、同じように、ストーリー展開が意外性に満ちている。近所の犬が殺されていたことから始まる、イギリスのごく普通の街に住むクリストファー少年の、その犬を殺害した者を捜索する旅は、まさに予想できないような展開となって少年の生活を変えていく。高機能自閉症である少年の優れた数学的思考に感服し、そのこだわりや導かれた結論の意外さに思わず微笑む時もありながら、結局は、家族とは、人が成長するとは、ということを考えてしまう。先の予想もつかないミステリーでもあり、何かおかしくもあり、そしてふいにジーンとくるという感じ。
“Christopher, do you understand that I love you?” という父への彼の返答に、私は最初の涙がわっと溢れた。109頁である。この少年が言ったような子どもへの愛を私も示してきたのだと信じたい。結末も好き。時々、どんなに途中までの展開が好きな話でも、結末に至って、ご都合主義的に全てをあるべき場所にあわてて収まらせた感じでがっかりすることがある。でも、これはそうではない。納得の結末。
“Wondrous…Brilliantly inventive, full of dazzling set pieces…unbearably
sad, yet also skillfully dodging any encounters with sentimentality…Not
simply the most original novel I’ve read in years…it’s also one of the
best.(The Times)
平成20年1月31日~2月1日
Kite Runner (Khaled Hosseini)☀☀☀☀
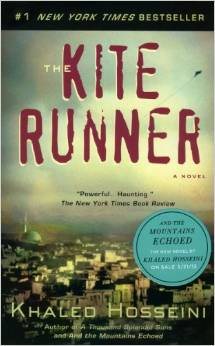
映画公開が迫っているので読んでみた。アフガニスタンの2人の少年を中心にした物話である。実際には語り手の少年が主人公といっていいのだろう。初めてアフガニスタンにも凧揚げがあること、そして
“Kite Runner” の意味を知った。そのまま一気に読み終えないで、この本を置くことは難しいと感じる。何が起こったのか、どうなったのか、気になって止められない。どうなったか気になるために飛ばしてみたくもなった。話を読み終わって、自分が声にしてみたい、訳したいと思う言葉があることがある。この話では、“For
you, a thousand times over” 。特に、その言葉が出てきた2回目。読み終えたら、そう思う人は多いだろう。この本を原作とする映画の批評には、後半は虚構性をどうしても感じてしまうと書いてあった。でも、一生後悔するほどの過ちを、善良な、そして自分を愛する者にしてしまうような愚かな人間にも、誰にも想像できないほどヒロイックにもなれる瞬間がある――そう信じたいロマンチストの私は、最後まで、この虚構の世界にただただ浸り続けた。
“An astonishing, powerful book.” (Diane Sawyer)
平成20年2月7日~2月10日☀☀☀☀
The Shadow of the Wind (Carlos Ruiz Zion)
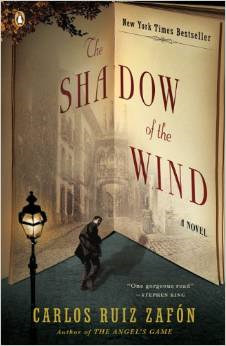
上記の本を読み終えて、「この本を買った人はこれも買っています。」といったネット書店での言葉を信用して、2冊購入した、その内の一冊。スペインのバルセロナを舞台にしたスペイン語の原作の英訳本。全ての用事を終えて夜寝る前に本を読むことが多いのだが、これは、まさに真夜中に読むのにふさわしいミステリーもの。1人の少年が一冊の本を手に入れたことで始まる探索は、全てが闇のイメージを与えるエピソードばかり。かなり分厚いので、もし読み終えておもしろくなかったらと20ページ位まではなかなか入り込めないままだった。でもそこからは、かなり引き込まれていく。最後は、どうなるのかを知りたくて、読む速度が速まってくるのを自分でも感じた。「あ、そうだったのか。そうくるのか。」と言いそうになる箇所が必ず一箇所あると思う。これは、みんな同じページでそう思うのでは。377頁である。数年前に日本ではやった韓国ドラマが一瞬浮かんだ。でも、これも(その韓国ドラマも!)作者に騙されたようには感じない。フェアーにそれまでもヒントは示されていたように思うから、やはりこの物語は上手く書かれている。四日目に本を開いた時には頭痛がずっとあるつらい一日だったが、それでも結局読み続けて終えてしまった。ちなみに、最後には、ミステリーで挙げられた場所が地図とともに示されている。ただ、こうしたタイプの物語の後では、行ってそれを見てみたいという気には、怖がりの私はなれない。どんな大都市にも、大きな都市であるがゆえの、多くの人が住んでいながら、誰も見ていない闇の空間は存在するのだろうけれど、自分の家がホント小さくてよかったーーと感じた。地下室なんて絶対いらないとも。
“The Shadow of the Wind will keep you up nights—and it’ll be time well
spent. Absolutely marvelous.” (Kirkus Reviews)
平成20年2月11日
The Time Traveler’s Wife (Audrey Niffenegger)☂
上記の本と一緒に購入した2冊のうちの一冊。書評どおりならバレンタインデーにかけて読むには最適な本に思えたが、どうしても入り込めないまま、読み続けるかどうかを考えながらの我慢くらべのようになってきた。80ページあたりでついに限界。主人公達の言葉や行動によって、作者が読者にどう思わせたいのかが、あまりにも見え見えだと感じた。作意を感じてしまったら、もうその物語に入るのは不可能だと、見切りをつけた。
“A soaring celebration of the victory of love over time.” (Chicago Tribune) これが表紙にある。こう感じて読み続けられたら、本当によかったのだけど、私には駄目だった。
平成20年2月12日~2月14日
The Long Goodbye (Raymond Chandler)☀☀☀
一度もこの有名な探偵マーロウのシリーズを読んだことがなかったので、一冊はと思い読んで見たが、実に格好いい探偵である。この本のタイトルの意味も読み終えてわかれば、これまた格好いいと思うことしきり。こんな人がバレンタインデーに一緒にいたら疲れるけれど、虚構の中でのクールな格好よさなら大歓迎。“To
say goodbye is to die a little” ――この言葉を心でつぶやいているのが様になる男性もそういないだろう。それゆえ、一番納得できた書評は、これである。このシリーズをもう一冊読んでみようかと思う。
“Chandler’s the perfect novelist for our times…He takes us into a different
world, a world that’s like ours, but isn’t.” (Carolyn See)
この本を読むと、コーヒーを飲みたくなる。いつもコーヒーが出てくるからだろう。物語から特定の食べ物をむしょうに食べてみたいという食欲を喚起されることの多い私だが、今年のバレンタインデーのメニューは、迷うことなくメインをパエリアにした。この間読んでいたバルセロナを舞台にした物語のせいなのだと思う。
3月になれば、私の大好きな “The No.1 Ladies’ Detective Agency” (Alexander MaCall Smith) のシリーズの最新刊が出る。今からとても楽しみ。このシリーズは、2年前のゴールデンウィーク中に始めて読み始めて、全部を読み終えた。季節はずれの風邪でダウンして外出も出来ない日々だったのだが、そのせいで、全シリーズを読みきれたので、このゴールデンウィークの印象は結局かなり良いものになった。アフリカを舞台にしたこのシリーズに一貫して流れる不思議なユーモアも好きだが、主人公自体が人間として素敵なのである。読むと、このように自分もおおらかに生きていけたらいいのにと思ってしまう。笑いと、気持ちのよい涙と、読後感の爽やかさは、この数年間で読んだ本の中でも群を抜いている。どんなに好きな話でも、実際に存在していると仮定してみて、主人公に会ってみたいという時と、主人公には会いたくない時がある。これは断然前者。しかも主要な登場人物みんなに会ってみたいと思わせる本でもある。一度も読んでいなくて、読みたいと思える物語は手元になくなった。今まで読んだ本を読み返したい時もあるが、今は新しい本を読んでみたくてたまらない時期のようである。結局、マーロウシリーズをどうしても読み続けたくなったので、買ってみることにした。
平成20年2月17日
The Tale of Despereaux (Kate DiCamillo)☀☀
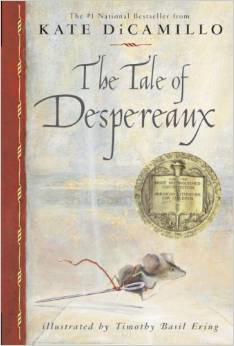
マーロウのシリーズ2冊を買う時に、おもしろいかもと思って一緒に3冊買った本のうちの一冊。マーロウにもすぐ会いたい気分だったが、いざ全然想像もつかない物語を前にすると、そちらから読みたくなった。となると、最初に手にしたのは、表紙のネズミがかわいいこの本ということになる。子ども向けの本のようで、1~2時間もあれば読める。お城の片隅に生まれたネズミを中心におとぎ話の形ですすむ。彼は小さくて、生まれた時から目があいていて、そして他のネズミとは違う。語り手が読者によびかけて、物語の中の言葉の意味を語るところなど、とてもユーモラス。65頁では、声を出して笑ってしまった。残念ながら、私は、この母ネズミっぽいかも。ここでのエピソードが、この話全体の特徴を物語っている。子どもの話ですが、描かれるのは、現実であり、それを、あくまでさらっと、極端にシニカルでもなく、完全に茶化すわけでもなく、淡々とユーモラスに描いているという感じ。もうすぐ映画化と表紙にはってあるが、本自体は2003年に出ているようなので、もう映画になっているのだろうか。映画にするのは難しそう。場面によっては、本当に怖い感じを与える。実際、表紙の絵のかわいさ以上に、中にはこわいと感じる挿絵が多かった。おとぎ話の形でありながら、現実以上に現実的に、残酷さ、後悔、憎しみ、恨み、愚かさ、持たざる者と持つ者、弱肉強食、無理解、そうしたことが全部物語に入っているのだから。これ以上書くとストーリーを示唆してしまいそうだが、ただ、それと同時に、希望や勇気や赦し、そして関係の再生が入っているから、いいのだろう。児童向けの話が、あまりに現実の残酷さを入れ込むのはどうなのかと思うことも多いのだが、これは独自の世界を展開していて、それはそれで納得できる。そして何よりも合間にくすっと笑えもする。そう感じた私としては、下の書評は全く納得。“light”
と “soup” については、そうよね、そうよね、というところ。読むとわかる。読み終えて、あらためて考えると、私は、母ネズミばかりか父ネズミにも似ている(特に209頁で感じてしまう)・・・というわけで、言い訳っぽく(そうしてしまうから、似ていると感じるのだろうけれど)、ネズミなみに小さな、でも普通の存在である自分を見つめたりもした。
“Forgiveness, light, love, and soup. These essential ingredients combine
into a tale that is as soul stirring as it is delicious.” (Booklist)
“
2月17日~18日
I am the Messenger(Markus Zusak)☀☀☀
表紙の絵もユニーク(一回見てください!)、始まりの事件も印象的、ミステリーの形で、ある一つの謎だけがずっととかれないで残っていく。ただ小説は、そうした謎解きの形をとりながら、その過程での主人公の成長と彼をとりまく人間との関係の変化を描いているのだとは思う。ヤングアダルト向けの本のようだが、素直に楽しめる。最後の謎の答えだけは「そういうわけ・・・」とは思ったけれど。19歳の青年が主人公。何かではありたいという隠した思いやフラストレーション、そして、取り巻く人々との大小の葛藤は、若いということは大変なことでもあるのだと思わせる。はるか昔にその時期を終えた自分としては、過去の自分に重ねるというより、今19歳真っ最中の自分の家族に思いが飛んでいった。“What
do you hate me so much?” (243頁)と母親に聞いた彼への、その母親の返事は印象的。自分自身の人生についての不幸な思いは、本来愛することを素直に示せるはずの人間との関係にも影を落とすのだろう。息子にとっては、暢気すぎて、彼の興味を持つことや、熱心にしている活動にも無関心で、往々にして無神経なコメントをする親でもある(ゴメンネ。。。)私だけれど、母親が少なくとも今ある場所にかなり幸せを感じながらいつも自分の人生を楽しんでいることだけは、彼にとってもきっと悪いことではないのだろうなと思った瞬間である。
“It’s funny, engrossing, and suspenseful, and it will appeal to a wide
audience.” (KLIATT)
2月19日~20日
The Book Thief (Markus Zusak)☀☀☀☀☀
話題作ということだけは知っていた本を手に取った。ここ数週間はノンストップ状態で読んでいるので、この本からはゆっくり読もうと思ったのだけど、この本こそ、途中で読むのをやめるは難しい。結局、夜読み始めて、昼間もつい読んで、また寝る前に読んでと、500ページの本を終えてしまった。最初から1939年ナチスの台頭するドイツのミュンヘンに生きる少女リーゼルの話、語り手は死神――となれば、戦争、死といった人間の悲劇そのものが書かれているのは明らか、それが上手に、極めて上手に書かれているのだと感じてしまう。理不尽な死を多く描いた小説に、その死者の数に比例して必ずしも心が動くわけではないことは、これまでの経験で誰でも知っている。ただただ現実の反映のような人間の愚行や醜さをこれでもかこれでもかと提示されるのであれば、もう小説として読む必要はない。自分を小説の場で主人公とともに同時に存在させながら、出来事を見つめる作者の視点にも共感し、心が強く動かされる、そうしたものが小説だろうから。そして、リーゼルと、リーゼルを取り巻く人々の運命が気になって(時には途中で運命が示唆されているがゆえに、かえって)どんどん読み続けたが、最後の運命がどんなに過酷なものでも、好きな本といえると思った。読み終わった後、涙は出ていたが、気になった頁をあらためて見ることが出来たのは、そんな本だったから。丁度、リーゼルが「言葉」に向ける相反する思いが小説に描かれるように、言葉は人を泣かせ、憎しみをあおる、捨て去りたいようなものであると同時に、人に他者を愛し自身を省みることを可能にする偉大なものなのである。
“It was the beginning of the greatest Christmas ever. Little food. No presents.
But there was a snowman in their basement.”(312頁) “There were stars,” he
said. “They burned my eyes.”(379頁) “You’ve done enough.”(398頁)。もう一度、そうした偉大な言葉に会いたくて戻っていった。これだけでは特別の意味もないような言葉。でも、この本を読めば、これらの言葉がどんな思いを読者にさせるのかがわかると思う。少なくとも私は、これらの言葉に最初にあった瞬間に胸がつまった。
多くの賞をとった本なので、絶賛の書評が本にもあふれていたが、個人的にまさに同感というのはこれである。途中でやめるのは実に難しい。
“Both gripping and touching, a work that kept me up late into the night
feverishly reading the last 300 pages. You can’t ask for much more than
that.” (The Plain Dealer)
3週間で9冊。ちょっと小説ばかり読みすぎているかも。1年の間に数回来る、どうしても本を読むのを止められない時期のようである。だって楽しいのですもの、としていいようがない。考えてみれば、自分が一人で楽しむための小説の時間はほとんどないという月日も本当はかなり長くあった。その時にしか出来ない自分の役割をともかく精一杯果たしたかった自分と、その時だけ一緒に出来ることを最大限一緒にして過ごした家族との日々がいとおしく思えるから、こうして一人で小説を読む時間が前より格段に取れる状態になって、素直にまた幸せを感じることができるということは確か。
ただ、今日から、小説は夜の眠りにつく前の一時にとどめたい。研究で読みたい本もたまっている。マーロウシリーズが今2冊手元にあるので、夜だけ読んでいくつもり。
平成20年2月22日~2月23日
The Big Sleep (Raymond Chandler)☀☀
マーロウ探偵登場の一作目。6作目の40代の彼に最初に会った私には、過去に戻って若い過去の彼に出会ったという感。まさに白黒ハリウッド映画が浮かびそうな豪華な屋敷とリッチでセクシーな女性達で始まるスタートで、6作目の見知らぬ男女が登場する始まりとマーロウがその男性に向ける友情のようなものが印象的だったせいもあって、いわゆる探偵物の紋切り型のストーリーだったら退屈かもと構えたりもしたが、途中から、やっぱりという形で引き込まれた。最後は、これもやっぱりという感じで、タイトルの意味がわかって、これまたうなずいた。ストーリーの組み立てが上手い。失踪者の消息を求める依頼から始まるハードボイルドの探偵物だから、仕方ないけれど、自分が使うこともない言葉ばかりが頭に入ってはくるのは確かである。“egg-headed”,
“cheese head”、とか、実際の会話には、気障すぎるか、危険すぎるかのどちらかになって使えない言葉が多いけれど。“I’m too tired
to talk, too tired to eat, too tired to think. But if you think I’m not
too tired to take orders from Eddie Mars—try getting your gat out before
I shoot your good ear off.” (126頁)という具合ですものね。
本の前書きについていたコメントから、納得する箇所を紹介。
“The Big Sleep, however, is such fun to read you probably won’t notice
how clever its author is being. Chandler remains the king of the one-liner.”(Ian
Rankin)
平成20年2月23日~24日
Farewell, My Loverly (Raymond Chandler)☀☀☀
手元にあると続けて読みたくなるみたいで、あっという間に読んでしまった。これは、最初に読んだ6作目と同じタイプの始まりで、「これから何が起こるの?」というわくわく感は大である。これでマーロウを読むのは3作目。ジャンルからいって、このシリーズでの魅力的な女性達のステレオタイプは仕方がないのだろうけれど、それ以外にも、今だとどうなのかなという言葉は沢山出てくる。40年に出版だから、これが、まさにその時のアメリカの現実の反映でもあるのだろう。“nigger”
”Indian” “sneering at it the way Jap gardeners do”というPCでない言葉が次々でてくる。同時に、使うことはないけれど、おもしろい気になる表現も多い。”Somebody
ought to sew buttons on his face.”(95頁)。マーロウは相変わらずクールで、007の映画の最新作に出ていた俳優(読んでいるとマーロウのイメージでどうしても浮かんでしまう)しか言えそうもない言葉を言い続け、それはそれでとても格好いい。“Do
you do much of this sort of thing?” “Practically none. I’m a Tibetan monk,
in my space.”(135頁) “You wouldn’t want to hire an assistant, would you?
Not if it only cost you a kind word now and then?” “No.”(95頁)なんて会話ばかりだから。
ちなみに、私がこの小説の世界にいたら、いつでも、“like a hen having hiccups.”(116頁)という感じになるかも。このジャンルの小説は、やはり自分の現実でないところに良さがある。彼のモラルが、あれだけ(!!!)もてながらも彼を結局1人にしている。そして同時に魅力的にしていると感じる。だから、本の前書きから;
“Marlowe is a hard-boiled, wisecracking detective with a big streak of
integrity down his spine and with a moral code of his own.”(Colin Dexter)
明日からは、前に読んだ本をもう一回読むか、マーロウシリーズの残りを買って読んでみようか、迷い中。
丁度この本を読み終わった今日、新聞に、1981年のロスでおきた殺人事件に関して、その時の日本人の容疑者であった人物がサイパンで逮捕と出ていた。殺人という犯罪に容疑者としても被害者としても関わってしまうのは嫌だが、今の私だったら、アメリカのロスでは怖い、ともかくロスの市警は信用できない、無罪の証明は私立探偵マーロウに頼まないといけない、なんて、思ってしまいそう。でもマーロウの厳しい女性を見る眼を知りながら直接依頼をしに行くのも、これまたかなりつらいなーーということにもなる。困った。
平成20年2月25日~27日
The Secret Garden (Franses Hodgson Burnett)☀☀

原書では一度も読んだことがないのを思い出して読んでみることに。子ども時代に読んだ時さほど好きな話ではなかったので、一度は原書で読んでおきたいなという軽い気持ちでスタート。物語は、父親とも母親とも暖かい思い出のない少女、”disagreeable-looking
child”として登場するメアリーを中心に進むのだが、孤独なメアリーが自分が好きといえる人々が増えていく過程は、今の方がずっと楽しめた。”Ive’
nothing to do,” said Mary. “Nothing belongs to me. I found it myself and
I got into it myself. I was only just like the robin and they wouldn’t
take it from the robin.” (p.121) ”You are as nice as Martha said you were.
I live you, and you make the fifth person. I never thought I should like
five people.”(p.131) 両親と10歳までは一緒に暮らしながら、ここまでの孤独な思いは、子どもの私には全く共感できなかったのかも。そういう子ども時代を持たせてもらったことに、今さらながら感謝する。他にも色々なことに気づいてはっとした感じで、読んでみてよかった。
書評ではないけれど、カバーの裏に書いてある作者の紹介を一部。
“Frances Hodgson Burnett was a born storyteller. Even as a young child,
her greatest pleasure was in making up stories and acting them out, using
her dolls as characters. She wrote over forty books, including the classic
A Little Princess.”
ちなみに、このA Little Princess.は、かなり前に読んだ。”I—tried not to be anything else,”
she answered in a low voice—“even when I was coldest and hungriest—I tried
not to be.” 子どもの頃何度も読んで(こちらはかなり好きだったみたいな)記憶していた邦訳とあわせてみたかった。そして満足。本て、どんな理由で読んでも何かしら楽しめるものだからいいですよね。
平成20年2月29日~3月3日
The Good Husband of Zebra Drive (Alexander McCall Smith)☀☀☀☀☀
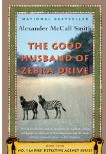
大好きなシリーズの最新刊8作目(正確には、ペーバーバックとしては。ハードカバーでは昨年にさらに9作目がでている)が届く。「わあ~い」という歓声を心の中でであげる。夜眠りにつく前だけの読書と決めたので、少し読んで次の夜、としたけれど、夜は眠い日が続いて、少しずつしか進まない。ついに3日に別の時間も読んで終了、というか、もう最後まで読まないで本を置くのは無理と判断。そういう気持ちにさせる本である。いつも同じような気分になって読み終える。なんか人生が良いことで満ちているような気分である。登場人物の人生には、少しずつ変化もおきているのだけれど、過去7巻の物語自体の進み方(事件と私的な出来事がからみあって、最後は(・・・書くべきではないですよネ)で終わり)は一緒である。だから、私は、いつも通り、くすっと声を出して笑い、何回もにっこりし、そうね、人生はそうよね、と共感する。158頁の結婚についての考えは「そう、そうよね、そういうものよね。」と叫びたいほどだった。
ちなみに、マーロウはコーヒーを飲みたくさせたけれど、このシリーズでは、“bush tea”――飲みたいけれど、日本で手に入るのかなといつも思ってしまう。
本の表紙の書評、私の読み終えた後の気持ちにぴったりなので。本を読み終わって、家族に思わず「読んじゃったのよね。」と愚痴ってしまった。もう読めないのが残念という気になる本。揃えているのはペーバーバックだけれど、ハードカバーの新刊も買おうか・・・。
“McCall Smith’s fans seem to hunger for the kindness, dignity and humor
he celebrates in Mma Ramotswe, and this book will not disappoint them.”
(The Oregonian)
同時に、寝る前だけと決めて4冊購入したのが到着する。話題のものもあるから学生にも推薦できるから読まないと、と自分に言い訳して他の時間も取っていかないようにしないと。
3月5日
Deal Breaker (Harlan Coben)☂
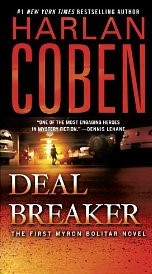
数十ページ近く読んでみた。犯罪小説で、かなり際どい(私的には)感じで、これはこれでおもしろくなるのだろうけれど、問題は、人物の関係や説明のところで、「今、自分は小説を読んでいるのだ。」と意識してしまうこと。2時間のサスペンススペシャルを見始めたような気分。事件の始まり自体を読んでしまったから、いつかまた戻って一応最後まで読むことにする。しかし、途中でおいてもさほど続きが気にならない犯罪小説では、自分とは相性が悪いのかも。。
今や、テキサス、オハイオ、ロードアイランド州大好き。ジャック・ニコルソンも急に好きということに。
CNNとABCをあけて、2画面で刻々変わる速報を追い(微妙に数値が違うので)、同時に、ネットのビデオで勝利スピーチ聞いて喜んでいる日本女性がいるって、ヒラリーが知ったら苦笑するかも。
「どこでも、年令層の高い女性だけにはもてるのねえ。。。」私にとっては、彼女の “likability” は問題なし。
3月7日~9日
The Memory Keeper’s Daughter (Kim Edwards)☀☀☀
1964年吹雪の夜、医師であるディビッドが、妻の出産直後にした一つの選択――妻に告げた双子のうちの一人の死――が、この4百頁にもなる25年間の物語の始まりである。人生には、やり直しがきかないように思われる選択があって、その選択自体はほとんど一瞬にされたのに、少なくとも希望と信じたもののためにされたのに、その選択に囚われた人生をそれからずっと歩むことがある。ディビッドにとっては、吹雪、出産、看護婦、自分の過去、妹、そうした全てが一緒になった夜、一瞬にした選択。2005年に出版されている。私が、仮にその年より前にこの本を読めたとして、今回のように感じたかはわからないとは思った。小説とは、所詮、読んでいる時点での自分自身を見つめることだから。だから最後は泣いた。同じ2005年に逝った母との間にあった自分の選択をやり直せたらと思って、自分の言葉を一つだけ過去に戻って変えることができたらと思って、泣きたくなることがある。悲しくて、その一瞬は世界にたった一人でいるような気がする。これからもずっと、私はその時を何度も何度も持つのだろう。私のような想いを持つ者にはつらいだろうけれど、それがない人々には読んだ方がいいのかも。私達の人生に、デイビッドのあの吹雪の夜はきっとあるのだろうから。
一日目の夜、80頁までは、丁寧すぎるともいえる詳細な状況や人物描写が気になって、下手な小説を読んでいる感じ、登場人物の誰にも感情移入が全く出来ない、二日目の夜、180頁あたりで、続きが気になり、三日目、残りはもう午前中に読みきるしかない運命に。何回か涙がでた。最後の2頁はかなり。最初に気になった丁寧な描写は、タイトルにもある「記憶」そのものを象徴していたから、そうあるべきだったのだ、そう納得した。
“Absolutely mesmerizing.” (Sue Monk Kidd)
平成20年3月10日~12日
Water for Elephant (Sara Gruen)☀☀
表紙がサーカステントに入る真紅の長い上着の男の後姿で、意味深な題名、下に載せてある書評も、殺人、愛、と言う言葉で彩られているので、暗めのドラマティックな話かと思って読み始めたが、あれっという感じで、最初から、90歳を超えた老人が登場する。その主人公ジョイコブの今と過去、大恐慌時代のサーカスを舞台にした出来事、が組み合わさって物語は続く。そもそも最初から、ジェイコブの回想の中で家族のことも出てくるので、誰でも、物語の途中でも、「あ、ジェイコブとこの人は・・・・なるんだろうな。」というある種の結末を推測は出来るだろう。それでも、サーカスの舞台裏におこる人間模様は興味深いし、引き込まれる。なぜジョイコブに語らせたのかが、最後まで行くとわかる気がする。最後がいいな。情熱にあふれた若い日々と老いた日々が全くつながらない形で存在する人生はつまらない。私も、両方を切り離せないような形で自分の人生を全うできたらいいな。だから、同感する書評は、これに決まり。
“Gruen performs a double trick in her novel: she gives an engrossing picture
of circus life as well as a taste of what it’s like to grow old.” (Minneapolis
Star Tribune)
平成20年3月17日~18日
Tsotsi (Athol Fugard)☀☀
南アフリカを舞台にしたTsotsiと呼ばれる1人の青年の過去と現在が交差する、それを引き起こすのが、彼が手にした「あるもの」。人生の選択肢が与えられていない中、ともかく生きることを余儀なくされる者の痛みの大きさは計り知れない。まさに“
Suddenly, very sharply, and with more pain than he had ever felt before
in his life, light stabbed his darkness and he remembered.”(p.57)。それでも、自分の生き方を変えるのは、ほんの一つの「出会い」からかもしれない。不条理が課す痛みなしに自分の過去を振り返ることが出来る、交わす言葉から痛みを思い出す怖れもなく現在を生きていける、そういう自分の幸せを思った。丁度、丸2日ほど病気でダウンして起きれなかった後に読んだので、特に感じてしまった。「何か作ってあげたいけれど、君が変わったものを最近よく作るから、冷蔵庫の材料ではちょっと僕には無理なんだよねえ。」と家族が私に言った、その言葉に、言い方に、苦しいとうなっていた寝床の中でも笑った。確かに、最近エスニック料理やら、まさに新しいレシピーへの熱狂の日々なるものにいる。今冷蔵庫にあるものを当惑して眺めている家族を想像して微笑んだ。そして、それなのに、その材料を使って「タイのレッドカレー」をどうにか作って持ってきてくれた時には、無理しても起きて少し食べた。こんな穏やかな一瞬一瞬が幸せな記憶になっていくのだと思った。Tsotsiには、その覚えておきたい過去がないのだ。彼だけでなく、不条理が当たり前になった場所では。そう感想を述べている自分が、まさにその外に出てずるいほど安穏としているんだと思って、胸が痛んだ。
最近DVDを家族で見て、原作を読んでみたもの。映画を見て原作を読むと、私はせっかちで、どうしても、どこが違うのだろうと気になって、スピードリーディングの練習状態。本来の本を読んだという時の読み方と違ってしまう。残念なことをした。これは映画を見る前に読んでみたかった。だから、あえて、以下を選ぶことに。映画の前に読んでみてください。ちなみに、映画も素晴らしいの一言。原作とかなり違う点もあり、どちらも納得はします。ただ私は、「あるもの」との出会い方は、原作の方がより納得したのに、結末は(「あるもの」との出会い方が異なるから、小説と映画では必然的に異なるしかないのに)、映画の方が好きという、矛盾したことを思った。希望は多いほどいい。
“A primary candidate for either the Nobel Prize in Literature or the Nobel
Peace Prize.” (New Yorker)
平成20年3月26日
The High Window (Raymond Chandler)☀☀
マーロウに出会った1ヶ月半前に比べると、かなりマーロウスタイルに慣れたせいか、最後のオチらしいものも、途中で初めて想像もついた。しかもあたっていた。この点が今まで読んだ3作よりは落ちるのかも。マーロウの友情や愛情という個人的な感情も今まで読んだ3作のようには出てこないので、人間関係での関わりも浅いということになり、今までのより淡々と読んでしまうのは確かである。でも、事件自体はアメリカの白黒ハードボイルド映画のイメージそのものの直球だし、マーロウの格好よさは、慣れてもやはりかなりのもの。物語への感情移入という点では強くなかったので、むしろ、「もうマーロウぽい」という一歩引いた感じで味わえた。“Don’t
ask me thing I don’t know. I can’t tell you the answers. And don’t ask
me thing I do know, because I won’t tell you the answers.”(p.27) “The earth
is full of people who don’t laugh much , Mr. Palermo.”(p.192) といった具合。
午後に思いがけないアクシデント、寝床で動けない状態で読んだ。数日動けないとわかり、昼間から読書の理由は出来たけれど、予定していて出来ないことを考えると情けない気持ち。そんな時に読んでいないで手元にあった数冊の一冊が、この本なのはラッキーと感じるような、そんなタイプの本である。しばし、自分の惨めさを忘れた。世界が全然違うもの。マーロウには、私におきたようなアクシデントは絶対ないだろうね。
今まで気がつかなかったけれど、本の最初に、マーロウの説明があった。その納得できる一箇所。ハードボイルドの探偵は、天涯孤独という設定がやはり似合ってしまうのは文化を超えて共通。
“I’m a native son, born in Santa Rosa, both parents dead, no brothers or
sisters.”
平成20年3月27日~28日
The Glass Castle (Jeannette Walls)☀☀☀
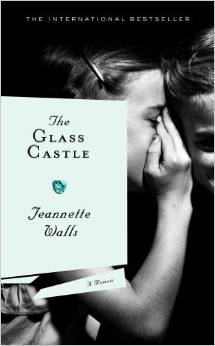
幼い時からの各地を転々とし貧しくて日々の食べ物にも事欠いた体験を語ったノンフィクション。この緻密な、そして詳細にわたる家族との日々の記録が、小説以上に信じがたいものなのだ。これがノンフィクションではなかったら、「そんな親いないでしょ」と言って読むのを止めていただろう。でも、そうではないのだから、当然、読みながら色々なことを思うし、読み終わって、また何かふーんと考えてしまう。いつか築く
”The Glass Castle” を熱く語ることは出来ても、現実はアルコール中毒で行動が伴わない父親、”artist”としての自己満足の世界を求める母親、両親が、子どもの最低限ともいえる生活条件を維持する意欲に欠けている時、子どもはどう感じ、どう生きたのか――読めば、この本に一つの例がある。そういう父親も母親も持たなかったし、そして自分がこんな親であることだけは絶対嫌だと感じる私は、読みながら、イライラもした。空腹な子どもを見ながら、自分だけチョコレートを隠れてかじった箇所など――“She’d
already eaten half of it. Mom started crying. “I can’t help it,” she sobbed.
“I’m a sugar addict, just like your father is an alcoholic.”(p/174) ところが読み終わって、そうした箇所を見直すと、何か不思議な感情に捉われる。
“Why spend the afternoon making a meal that will be gone in an hour,” “I
can do a painting that will last forever?” (p56) 私だって、この母親と紙一重、ただ違った自己満足のために、がんばって親をやっていただけなのかも。仕事をしていても食事だけは全部作る、とほとんど脅迫観念のように、朝早く出勤する日でも必ず味噌汁と和風の朝食を用意して出る、毎日弁当を作る、遅く帰ると思われる日はシチューやサラダをあらかじめ作っておく、テーブルには5品は並べる、ことができる「ちゃんとした母親」なる自己イメージのために頑張っていたのかも。さらには、元々自分が好きだった料理が、それに一番使いやすかったという自己本位の選択だったのかも。その結果、子どもはカップ麺の経験が一度もないままで、他の人が食べているのを見ても食べてみようという気にもならない青年に育った。今自炊しているけれど、食べ始めたのだろうか。全然食べないというのも何か生きづらそう。実際、カップ麺をたまに食べるとおいしいもの。実はそうして過ごした長い月日、きまって一年に数回、一人で家にいる昼間、私はどうしてもカップ麺が食べたくなって、一つだけ買って来て昼食にしていた。今でもそう。何たる矛盾。そう笑って、この本を読み終えられるのは、作者の子どもとして親を見る視線が、他者には悲惨と思える状況でも、ある種の暖かさを失うことないからだろう。つまり、人間は、親が完璧でいるから、さらには完璧でいようとしてくれるから愛するわけでもないのだという当たり前のことを気づかせてくれる。その視線を言葉であらためて説明するのではなく、悲惨とも言える状況を描いた文章で同時に描いてみせたのは、すごい書き手なのだと思う。
もっと誉めた書評はあったけれど、私はこれ。自分も同じように感情が揺れたから。
“The Glass Castle will at times exhaust you, occasionally fill you with
fury, and finally leave you in slack-jawed wonderment.” (National review
Online)
どうにか動くことだけは出来るので、29日からは、また料理に復帰。家族の「無理しないでも――」という非難の声にも関わらす台所に踏ん張って、もし万が一無理して悪くなった時のために、次の日の夕食のコロッケの下ごしらえまでしている、その矛盾した行動にちょっと笑えたのは、読み終えたばかりの本のせいだろう。家族の食事はちゃんと作る。どうも、この自己イメージは、すでにゆずれない自己のレベルになってしまったらしい。しょうがない。矛盾を内に抱えて、徹底的に、この自分をがんばろうっと。
平成20年4月10日~25日
A Star Called Henry (Roddy Doyle)☂
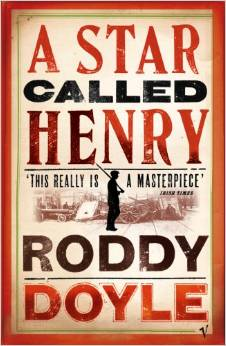
100頁でストップ。本に引き込まれることが出来ないまま、読み続ける気になれなくなった。セメスターの始まりで忙しく、寝る前にちょっとずつ読めるだけだったせいだとは思うけれど、そのちょっとずつ読むうちに、続きもさほど気にならなくなったのは、物語との相性も悪かったのであろう。何よりも、本当に続きが読みたければ、きっとどこかの時点で寝る時間も惜しんで読んだであろうから。主人公は、20世紀初頭にダブリンに生まれ、父は彼の成長を見ることもなく街から消え、母に育てられる。悲惨さの部分を読んで、これから彼の人生の大きな展開部分を読むのだろうけれど、それを読みたいと思えなくなった今、読み続けるのは無理になった。本の表紙には、以下の言葉も。ただし、読みきっていないので、検証不可能である。
“This really is a masterpiece.”(Irish Times)
平成20年4月27日
Daddy-Long-Legs (Jean Webster)☀☀☀
子ども時代に日本語では何十回も読んでいるのだが、原作は一度も読んでないことを思い出して読んでみた。ストーリーは書くまでもないだろう。だって『あしながおじさん』なのだから。大人になって読んだことがなかったせいか、とても新鮮に感じて、読んでよかったと感じた。子どもの時でも、主人公のポジティブな物事の受け止め方は素晴らしいと感じていたのだろうけれど、あらためて読むと、本当にそうよね、と思ってしまう。ひどい咳が止まらず休みをかねて横になって読んだのに、窓から見える春の空とぴったりの物語で、元気まで出てきた。“I’ve
discovered the true secret of happiness, Daddy, and that is to live in
the now. Not to be forever regretting the past, or anticipating the future;
but to get the most that you can out of this very instant…I’m going to
enjoy every second, and I’m going to know I’m enjoying it while I’m enjoying
it….”(p.154) 最後に、”Did you ever know such a philosopheress as I am developing
into?”とジュディーがおじさんに聞いている。少女時代には答えられなかった私も、今ならこれについてさえ、何ページも大学生のジュディにあてて解説できそう。年を取っただけの知識は身につけたということらしい。私も、ジュディのように幸福を生きるように努力だけはしてきたとは思うけれど、やっぱりそれでやっぱりよかったよね、と久しぶりに読んだ話にかなり勇気付けられた。積み重ねてきた“I
little happiness”を楽しんできてよかった。だから年を取ることを恐れることがないから。その時々で味わえる幸せを何も逃すことなかったから。読んだ後の幸福感は持続して、咳が出て眠れないと思えたその夜でさえも、合間に幸せな眠りをもらえたような気がした。
書評ではなく、あらためて、納得した箇所をもう一つ。
“You know, Daddy, I think that the most necessary quality for any person
to have is imagination. It makes people able to put themselves in other
people’s places. It makes them kind and sympathetic and understanding.”
(pp.94-95)
平成20年4月29日
Atonement (Ian McEwan)☁
戦争の足音がひたひたとせまる1935年の夏、一人の少女ブライオニーの言葉が人々を変えていく。映画が公開されていることで、読んでみた。本の裏表紙にも書いてあるし、映画公開にあたっても「一人の少女の想像と誤解からみちびかれる言葉、それによって引き裂かれる姉セシーリアと雇い人の息子ロビー、激変する運命」的な説明は何度も何度も目にしているせいか、まして、タイトルもこの言葉であるから、読み始める前から、半分物語を知っている感があるのはしょうがないかもと思う。この小説自体は、想像力すぐれたブライオニーの小説家としての語りで終わる。残念ながら、ストーリーは劇的、そして、私の感情移入は最小であった。何よりも、ブライオニーに私の同情も共感も、どんな理解したいような感情もわきあがらなかった。彼女の ’atonement’とは、語らないことにあるべき。本当にそうであるように意図するのなら。そして、彼女のしたことは、語ることを可能にさせないほど重いのだ、と感じてしまう。彼女の饒舌な語りの中に、むしろ嫌悪感を感じてしまう。私が、ロビーとセシーリアなら、ブライオニーの最後の語りの中のように、彼女の想像力の中で幸福に生かしてもらうことなど望みもしない。ただ、ブライオニーに関わりあわない人生をもう一度やり直すことを望むだろう。物語中で、ロビーが”I’ll
be quite honest with you. I’m torn between breaking your stupid neck here
and taking you outside and throwing you down the stairs.”(p459)に一番納得がいったもの。ただし、ロビー達にさえ、そんなには感情移入できなかったのだけど。
素晴らしい書評が沢山あるのだが、本自体を好きになれなかった私は、同じ気持ちに一番近いという意味で、これを選ぶことに。少なくとも、ある意味では、作者はそうなのだろうと思う。
“McEwan is technically at the height of his powers, and can do more or
less anything he likes with the novel form.” (The New York Review of Books)