平成24年7月24日~26日
A Christmas Memory (Truman Capote)☀☀☀☀
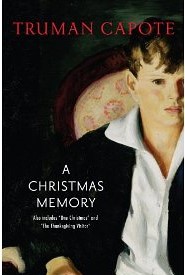
カポーティの3つの短編、A Christmas Memory, One Christmas, The thanksgiving Visitor――クリスマス、そして感謝祭の日々を扱った三篇。季節はずれともいえる内容なのに、その時だけは、真夏の夜、やさしい涼しい風がふいてきた、そんな感じ。両親と別れ親類と住む少年の2回のクリスマスとある感謝祭の想い出は、カポーティ自身の自伝的要素が強いという。としたら、子ども時代の彼は孤独でなかったはず。彼をバディと呼ぶスックがいたのだから。ただ、その子ども時代が極端に短かったことが彼の孤独となった、ということですよね。でもそうだとしても、思い出をこれだけの言葉で描ける文才を持った者に、本当の孤独なんてあるのだろうか。彼の伝記的な小説(今までで読んだ本の中で一番厚い本です!)をずっと前に読んだ時、彼の作品をいくつも読み返したことがある。あの時、読まなかったこれらの短編を読んで、また彼の作品を読み返したくなった。スックの言葉、“I’ll
wager at the very end a body realized the Lord has already shown Himself.
That things as they are” “just what they’ve always seen, was seeing Him.”(p.27)
に、父親にあてた手紙(p.53)、そして、“Buddy: there is only one unpardonable sin” (p.104) というスックの言葉と行為、三篇全てに、はっとする箇所が用意されているのです。
“deliberate cruelty”――しばらく考えてしまいました。その悪意や憎悪の源を理解したとしても、自分は何も得ないように最近は感じていること、自分に多少とも存在するinnocenceを大切にして、心を乱されることなく、優しい人々とだけ生きていきたい、そんな気持ちも行為ももう赦してもらえるのではないかと、特にこの2年間は思ってしますこと、をです。だって、生きてきた日々より、残された日々の方が少ないのですから。だけど、そう思ってはだめなのだと思えました。他者に向けた指は必ず自分をも指すのでしょうから。努力を続けます。
“Capote, in a bright, fluttering, wheeling way, makes all the tinsel and
confetti and embroidery that bind together such delicate emotions as nostalgia
and sentimentality come vigorously to life.” (The New Yorker)
平成24年7月27日~7月31日
Eminent Outlaws (Christopher Bram)☀☀
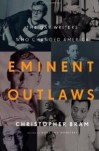
米国のゲイの小説家、劇作家、詩人達が、アウトローとして存在しながら、実は文化の主要なパイオニアであった第2次世界大戦後の50年間の米国の歴史を、彼等の業績、活躍だけでなく、「肉声」を繋ぎながら、丁寧に描きだしたノンフィクション。論文のために読み始めたのに、まさに小説を読んだ読後感で、興味深いといった次元を超えていたので、ここに記しておくことに。自らが選択できない特性のために少数派、凡人には選択できない才能を持つという点でも少数派であるゲイ作家達が、アメリカ文化の担い手となっていった模様は、感動的ですらある。Capote,
Vidal, Williams, Isherwoodは当然ながら出てくることを予期していたけれど、Cunninghamとかもそうだとわかって、あらためて、読み返したくなった。Navaも出ていて嬉しかった。
“With elegant authority and fraternal sympathy, he analyzes their problems
as writers but much more, with a thrilling delight, he applauds their best
writing. I gobbled it all up, reminded of writing I can never forget.”
(Ian Mckellen)
“A story of travails and triumphs’—of what gay men have told each other
and the world—Eminent Outlaw is also, above all, about love, storytelling,
and the abiding commitment to the written word.” (Brenda Wineapple)
著者自身が、ゲイの作家であることによるのでしょうね。記述に優しさがあります。彼の作者と物語の関係についての記述も納得。
丁度読み終えた翌日、Gore Vidalの死去のニュース。
時代も社会も連続性の中にある。
平成24年8月3日~4日
Tomcat in Love (Tom O’Brien)☀☀☀
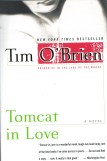
49歳、大学の言語学教員のThomas。子ども時代の友、Herbie, 彼の妹で、Thomasの愛情の対象、Lorna Sueの3人をめぐっておこる、奇妙でミステリアスなブラック・コメディー。Thomasの言語への執着(子ども時代のengineから、Lorna
Sueからの“Don’t be a 18-year-old.”にいたるまで、もう沢山でてきます。笑えます!!)は、さておいて、Lorna Sue
への執着心によって引きおこされる彼の行動をユーモラスに感じる一方で、Thomasの人生はどんどん悪くなっていくようで、しかもベトナム戦争時の思い出までそこにからんできては、まさかまさかと結末が不安になったぐらい。何かに執着するって、誰でもあるはず。一度でも客観的に自分自身を見ることができたら、地位、名誉や、評判、富、さらには、他人に勝る、ライバルを打ち破る、私達は妙な執着心に囚われて、傑作な一人コメディを演じているのが実は見える。時には、ブラックなコメディを演じて、対象となった者達を恐がらせてもいるのだろう。それを思うと、初恋の女性への愛情と言語――彼の執着心って、ずっとずっとまとも。だからこそ、読者としては、執着から逃れられず破滅的な道を進んでいるようにみる、弱点だらけのThomasを見捨てることが出来ず、彼なりの「ハッピーエンド」を祈ってしまうのでしょうね。結末、よかったです。これでいいよね、と思って本を置きました。言語への執着――最後まで生きています!!
だからでしょうか、沢山書評が掲載されていた中で、一番近いと感じたのは、↓。
“The real question is how does Tim O’Brien make us empathize with his anti-hero?
Try laugh-out-loud humor. Tray playing with language with the skill of
a consummate juggler. The result is a contemporary satire on human nature.”
(Book Report)
北島選手が最後にリレーでメダルを取れて嬉しい。
卓球の女子もメダルが確実ということで嬉しい。ボルトの金メダルも嬉しい。
嬉しそうな彼らを見ると、こちらまで嬉しくなる。
何べんもネットで視聴してしまいます。元気が出てきます。
8月6日、平和な世界を祈って、黙祷しました。
オリンピックの祭典が、言葉どおり世界中の平和のもとに開かれる日が来ますように。
平成24年8月7日~9日
War Dances (Sherman Alexie)☀☀
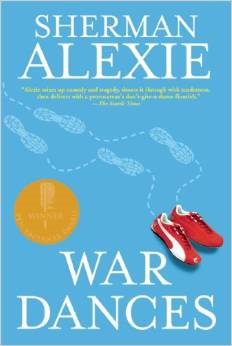
20篇以上の短編と詩からなる、アレクシーによる作品集。今年の3月、書棚に一気に増えた彼の作品の一つ。最初に読んだ小説ほど「大好き!!!」(ここ数年、新しい本を読んでいくだけ。時間もないし、読み返しはしない。それなのに、これだけは、もうすでに一回読み返し。ああ、また読みたくなってきた。きっと、この後、また読む。。)なのには出会わないけれど、彼の作品を読むと、その小説のジュニアが成長して、ひょこっと顔を出している、そんな感じを持ってしまう。北米先住民というキーワードがいつも物語の根底にある、それもまたいつも同じ。今回は、今まで読んだものより幅広い人間関係が描かれていると思うし、それらもまた上手に描かれていると思うけれど、それでも、この短編集のタイトルにもなっていて、作者を、そしてジュニアを、一番思わせるWar
Dancesが一番印象に残った。先住民達の毛布のやり取りでの会話にくすっと笑い(p.35)、そして、最後に、ジーンとします。そうですよね。永遠に会えない寂しさを、その人に言いたい言葉に出会う度に、思い出すのです。そんなもの。私もそう。最後の文を読んでから、しばらく本を抱えていました。自分がその人に言いたい言葉を思って胸がいっぱいになりました。アレクシ―は、本当に物語るのが上手い作家。
“”Sherman Alexie mixes up comedy and tragedy, shoots it through with tenderness,
then delivers with a provocateur’s don’t-give-a-damn flourish. He’s unique,
and his new book, War Dances, is another case in point.” (Mary Ann Gwinn,
Seattle Times)
オリンピックでのシーンを何度もネットで見て、ジーンとするのが日課に。
日本選手のメダルラッシュのせいもあって、今回のオリンピックはいつも以上に
それをしているような。嬉しそうな姿を見ると、こちらも幸せになるものね。
平成24年12月27日
Abraham Loncoln Vampire Hunter (Seth Grahame-Smith)☂

米国史上最も有名な大統領であるリンカーンが、まさにタイトル通り、「ヴァンパイア―・ハンター」だったことを、歴史の事実と虚構のミックスで語ったお話。映画化される小説ということで前に買っていたのを、時間が出来て読み始めたけれど、100頁を過ぎても、物語の中に引き込まれているような瞬間がなく、残り300頁を読んでもと本を置いた。決定的になったのは、Poeの登場。あ、ここで出てきた、どうなるの、と思わないわけだから、もう止め時と感じた。それでも最後まで読めば、上手く虚構と事実を併せているなって作者の努力に感心はしたのかもしれないけれど、物語としては最後まで楽しむことはなかったかも。私の好きな物語のタイプではないみたい。
ちなみに、本に出ていた書評は、
“An original vampire tale with humor, heart, and bit.. a rare find indeed.”
(Los Angeles Times)
確かにリンカーン大統領をヴァンパイアー・ハンターとするなど、かなり独創的ですものね。
平成24年12月29日
Bridge to Terabithia (Katherine Patherson)☀
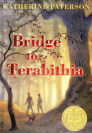
田舎町に住む11歳のJesseの日常――子どもに愛情がないわけではないけれど、貧しく、日々の生活で精いっぱいで、彼の隠された気持ちまで考える余裕がない親たち、小うるさい姉妹たちという状況で、自分らしさを隠し、他から認められることに無関心でもいられず、といったように、完全には自分の居場所を見いだせていない彼と、都会から引っ越してきた少女Leslieとの間で、友情が生まれる。人生の苦さも含めて、Jesseの心の成長を描く、きっと良いお話。というのは、最後の展開は、どうなんでしょうと感じたから。あまりにも唐突。それがなかったら、素直に良いお話と思えたのだけど。児童書なので、1時間もたたない内に読み終えて、そのまま優しい気持ちで、となるはずでしたが。。
“Eloquent and assured.” (Kirkus Reviews)
平成24年12月29日
Kira-Kira (Cynthia Kadohata)☀☀

1950年代、次女のKatieの視点から書かれた日系アメリカ人の家族の物語。アイオワ州からジョージア州へ引っ越し、鶏肉加工工場で、日夜必死で働き続ける両親と、その生活に影を落とし始める姉Lynnの病気、時代の移り変わりが物語に織り込まれていく。Kira-Kiraのタイトルの意味がすべて明瞭になるのは物語も最後。自分の過去の想いと重ねるような場面が何回かあり、涙を何回かこぼして、それでも暖かい気持ちで本を終えた。私もあの時、言葉を選んでいたら、そんな思いで眠れぬ夜が何回あっただろう。数えきれないほど。でも私だけではないのだ。Katieに向けられた言葉を自分にも言ってもらったように感じて、救われるような思いがした。私も、kira-kiraと精一杯生きることで、赦してもらえる、そう思った。“take
a simple, everyday object like a box of Kleenex and use it to prove how
amazing the world is.” (p.224)
“Will speak to readers who have lost someone they love or fear that they
could.” (Booklist, starred review)
これもニューベリー賞をとった児童書。Bridge to Terabithiaと続けて読んだら、どちらも偶然、主人公の喪失と成長というテーマを扱っていた。こちらの物語での喪失は、悲しいけれど、それでも誰の人生でも避けることのできない喪失として少なくとも受け止められた。喪失の対象への読者としての自分の思い入れが、Bridgeの方では、ほとんど存在しないで、むしろ物語の作為性、ご都合的展開が最後になって気になってしまったということなのか。もちろん児童書を大人の私が読んでいるからかも。子どもはそうではないのかなあ。どうなのでしょうね。でも、私自身は、子ども時代好きだった本は今でも好きだし、今読んで好きな本は、子ども時代にもし読んだとして、わからないことが多くても、きっと好きだったろうと思うのです。そう思うと、この本も、私のお気に入りになったのかは疑問です。私が子ども時代好きだった、そして今も好きな児童書で描かれた死は、少なくとも、それをメインにして作家が子どもの成長を書こうとはしていないと感じられたのです。だから、私は好きだったし、今もそうなのではないかと。