平成23年1月1日
A Short History of Tractors in Ukrainian (Marina Lewycka)☀☀☀☀

イギリスに住むウクライナ出身の84歳の父親が、妻を亡くして2年後、ウクライナの36歳の子連れのブロンドのグラマラスな女性Valentinaとの結婚を娘達に告げる。年の差に、そして、見え見えの女性の魂胆に、あわてたのは物語の語り手である妹娘であるNadezhada。今まで決して仲が良くてたまらないというわけではなかった姉のVeraとも共闘して、父親を救い出すべく悪戦苦闘。しかし、ウクライナ女性の方のしたたかさは二人の想像を上回るもので・・・と物語はすすむ。大学教員でもある妹は、途中で、ウクライナでの父親と母親の暮らしふり、特に、戦後生まれた自分が経験しなかった出来事を発見していき、次第に、自分達家族が、いかに歴史の中で生きてきたのかを知ることになる。Valentinaのすさまじい生き方に、強気でいても、結局負かされて、後手後手にまわるNadezhadaの対応に何度もくすっとし、探偵さながらの彼女の奮闘と、それを上回るValentinaの想像を絶する発言・行動に笑っているのに、だんだん、生きるとはどういうことか、家族とは何か、老いることは何か、姉妹の関係って何なのかを強く感じてしまう。コメディータッチなのに、ジーンとさせる、そんな本。評判通りで、1年の始まりを良い本で始められてよかった。最後の父親の言葉が傑作です。
"Delightful, funny, touching” (Spectater)
平成23年1月2日~3日
Six Suspects (Vikas Swarup)☀☀
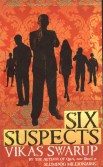
インドの悪徳実業家Vicky Raiが、自分の不正に得た無罪判決を祝う自宅のパーティで撃ち殺される。ピストルを持っていた6人が容疑者――元大臣、アメリカ人映画プロデューサー、有名女優、部族民、窃盗青年、そして、被害者自身の父親。それぞれの動機が何であり、なぜそこにピストルを持ってくることになったのかが、語られていき、最後に、真犯人が明かされていく。500ページを超える本は、それぞれの容疑者達のエピソードを章ごとに重ねていく形となっている。100頁あたりまでは、一つ一つのエピソードが長すぎて前作(「スラムドッグミリオネア」)のようなスピード感がないよね、と思っていたけれど、気づけば、どんどん読みすすんで、結局、読み終えてしまった。最後の真犯人のあたりは、もうひとひねりあってもと思うけれど、楽しく(時には、恐ろしく残酷な出来事も含めて)読めてしまうのは、エンターテイメント作品に徹しているからか。不正義、賄賂、汚職、陰謀、嘘、貧困、スラム、公害、差別、殺人、レイプ、といったことが、ポンポン投げ込まれているけれど、それでもそこに生きる人々のたくましさが伝わってくるし、そこにこそ、インド人の作家としての作者の愛情も置かれているのだろう。インド社会の暗部がここまで背景に書かれていて、それでいてエンターテイメント作品であり続けるのは、前作と同じで、作者が巧いのだろうな。それにしても、ガンジーが乗り移ったエピソードや、刑務所での元大学教授の男の応答など、誰もがははんとくる有名な言葉や小説やセリフをちりばめて、まさにエンターテイメントそのもの。
“What is your name?” “Mt name is Red.” “What are you in jail for?” “”Atonement.” ”And what do you think will be your punishment?” “One hundred years of solitude.” “Who is your best friend here?” “The boy in the striped pajamas.”(p.157)
“But how will I live without seeing you? “Love doesn’t end just because we don’t see each other,”(p.207)という具合なのですから。
“Unusual, witty, quirkily, cleverly plotted, intelligent… a rollicking good read.” (Marcel Berlins, The Times)
31日の夜から、年越しそば、お雑煮、お節料理、夜のご馳走、初詣、全部計画通りしても、それでも、その間は、のんびり本を読む時間がたっぷり。冷蔵庫に入りきらなくて、玄関脇のおいた箱に緊急に冷蔵した食材も、3日後には、きれいに片付く。計画・手順がよかったワタシ!!と自画自賛。食べて、読めて、両方の意味で美味しい3日間。マイナーな驚きとかなりのアクシデントはあったけれど(これがないと、私ではなくなるから仕方がない・・・しかし、痛かった、今も。。)、全てひっくるめて、平和なお正月が終わりました。
平成23年1月9日
God Save the Child (Robert B. Parker) ☀☀

私立探偵スペンサーシリーズの一冊。15歳の少年の失踪事件を依頼されたスペンサーが、少年の捜索をすすめて、事件の真相にたどり着く。身代金の要求、少年の連れて出たペット、母親との関係、そして、スペンサー自身の恋もからんでいく。今まで読んでいない探偵物を読んでみようとアメリカの有名探偵シリーズを数冊購入して置いたままになっていたのを読んでみた。人間観察は鋭く、無駄な言葉を言わず、行動し、かなり腕力もある、そして、恋にはなかなか素早い、そんなスペンサーがしっかりイメージできて、ハラハラするとはいえなかったけれど、それなりに展開に引き込まれた。最後に母親のリアクションがいい。“Just
‘whether’ ” I said. “ I beg your pardon?” he said. “ ‘Whether’ implies
‘or not,’ I said. (p.34)こんな感じです、スペンサーは。個性のある探偵物は、楽しめます。気になるのは、裏表紙の犬を連れた男。これがスペンサーってこと??それはないでしょ。彼はこうではないはず!
スペンサーシリーズに対して:
“Spenser probably had more to do with changing the private eye from a coffin-chaser
to a full-bodied human being than any other detective hero.” (The Chicago
Sun-Times)
あと2冊買っていたのも読むつもり。ただ探偵物(私立も警察も一緒にして)の本として、私の中でランクをつけるなら、ポワロ、フロスト、ブラウン神父、マーロウ、そして、ミス・ラモツエ(もうすぐ新刊であえる。ウレシイ)は別格。それらに比べたら、スペンサーは、楽しめる、といったレベル。
今、ある探偵ブームで、二人でDVDを一話ずつ見ていくのが日課。これが本当に素晴らしい。今年の前半の我が家の最大ヒットになりそう。
平成23年1月24日~29日
Maurice (E. M. Forster)☀☀

同性愛が「正しい愛」であると認められなかった時代、そして場所で、同性に向ける愛情を自分の中に認め人生を選択していく一人の青年モリスの物語。ケンブリッジ大学で出会った、モリスが愛し、愛されたクライブは、社会の中で「正しく」生きるために選択をし、モリスもまた苦しみ、揺らぎ、最後の選択をする。「正しい愛」を文化が決めるのなら、文化ほど理不尽で不合理なものはない。そして、それを知りつつ、私達は文化にとらわれて生きるしかない。それだからこそ、最後のモリスの決意が、心に染みた。
"I care for you in the real sense, and always shall. We were young
idiots, weren’t we? –But one can get something even out of idiocy. Development.
” (p.155)"What a comfort the man was! Science is better than sympathy,
if only it is science.” (p.188) ’development’‘science’の名をつけて、愛情を抑圧する。それが私達の作りだしている文化。残酷。でも、その残酷さの中でも、貫くことができる愛情を持てるのも、また私達人間。ずっと昔、若くて、自信一杯で、そのくせ、もしこれから本当の愛情を持てる人に巡り合わなかったらどうしよう、見え張りだから、文化のプレッシャーに耐えきれず、その振りをして生きることになったらどうしよう、なんて、誰にも言えない不安を抱えていた自分を思い出した。自分は見つけたのだから、幸運だったからいいなんて思いたくない。文化の与える「正しさの基準」の中で、揺らぎながら、迷いながら、他者との真実の愛を求めてしまう、そんな人間として、私達はみな同じ。フォースターの作品ということで読み始めたけれど、それだけはある。
本の裏表紙にある小説の中の言葉:
‘People were all around them, but with eyes that had gone intensely blue
he whispered. “ I love you.” ’
エジプトの騒乱は広がる一方です。エジプトは、私にとって最初に経験した外国で、今でも、外国という言葉で最初に頭に浮かぶ国です。あの時、私達がのった飛行機はパキスタンのカラチにとまり、エジプトへ。日本からとても遠い場、そして混沌として異文化そのもの、カイロの街は、それでも、その時の私には平和な場所でした。ニュース報道に出てくる混乱の街。本当の平和やデモクラシーを得るための過程だとしても、犠牲者の数が増える状況には心が痛みます。世界は狭くなりましたが、平和になったわけではないのです。
平成23年2月11日
The Time for the Traditionally Built (AlexanderMcCall Smith)☀☀

ボツワナの探偵Mma Ramotswe シリーズ10作目。依頼と本人と周りの人々の日常の出来事がからまって、最後は全てが解決に向かうというパターンは、これまでと一緒。大好きなシリーズの10作目を買いそびれていたのを、ついに読んだ。前回の9作目でもちょっと感じたことを、今回は強く感じた。つまり、物語の質は今いち。登場人物も、事件の展開も、結末の感じも全て今までと同じなのだけれど、やっぱり10作目ともなるとマンネリということかも。事件の答えが日常の中から浮かび上がるという展開のおもしろさも、今回は随分パワーダウンという感じである。初めて、アフリカやボツワナの精神についての結び付けの記述もしつこいとも思った。でも、でもである。彼女達が大好きだから、懐かしい人々と新作で再会できる喜びを優先して、不満は横において、読みました。最初の出会いで虜にして、新刊が出る度に私を幸せな気持ちにさせてくれたシリーズです。マンネリ、パワーダウン。確かに。でも、文句は言わず、次回(もうすぐ手に入る)も読むつもり。こんな読書もありです。
“Tea Time for the Traditinally Built is the tenth in the series, just as
enjoyable, heartwarming, amusing and elegantly written as the others.”
(Marcel Berlins, The Times)
この人、私以上にファンなのかなあ。だって、いくらなんでも、今回のが今までのレベルと一緒とはいえないから。ただ、”enjoyable, heartwarming,
amusing and elegantly written” まさに、このシリーズの魅力の根幹。それ自体は失われていないのは確かだもね。でも、やっぱり随分、・・・止めましょう。何作も書いて、同じレベルなんて、要求しすぎだもね。
平成23年2月12日
From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler (E.L.konigsburg)☀☀☀

12歳の少女Claudiaは弟のJamieを誘って、家出。メトロポリタン美術館に隠れて住むという大胆な計画を実行する。そこで、ミケランジェロ作といわれている天使像に心を惹かれ、その秘密を自ら解き明かそうとする。高い評価を受けている古典的児童書なのにまだ読んだことがない作品、ということで読み始めた。70頁位で、やっぱり子ども向きだもの、ハラハラもしないし、やめようかな、でもすぐ読めるからついでに、なんて思いながら読んでいたら、なんと、最後近くで、わっと涙が出てきた。自分が何者かでありたい、でもどのように証明するのかもわからない、だけど、あくまでも「自分の努力で得た結果」で証明したい、そんなクローディアに共感し、姉弟の「子どもらしい」(そして、これこそ「人間らしいもの」と信じたい)真っすぐさに、心が動いたのでしょう。最後まで読んでよかった。姉弟の車の中での二人で決めた秘密の計画、とてもいい。"I
want to go back different.”(p.119) みな思うよね。(それとも、"differently” でいくか。姉弟の文法さらには人生談義(?)も楽しい。読めば、この意味わかります。)
“The captivating story is fresh and crisply written with uncommonly real
and likable characters and genuine dialogue and humor.” (Booklist)
平成23年2月13日
How Town (Michael Nava)☀☀☀

ロサンジエスルスの弁護士Henry Riosミステリーシリーズの三作目。小児性愛癖を持つ資産家名士のポールが殺人罪に問われ、疎遠になっている姉から弁護を頼まれることから、物語は始まる。ポールは、かつてヘンリーが愛情を強く感じていた親友の兄であり、また姉の友達の夫でもある。長期間残していくことになるAIDS患者の恋人を案じながらも、弁護を引き受け、故郷に戻り、長い間会うこともなかった姉と親友と会う。それは、自分自身の過去の苦い記憶とも再会することを意味した。崩壊した家族、歪んだ性と屈折した愛情、欲望、憎悪、偏見、人間模様は読んでいて厭になるぐらい醜くさえあるのだけれど、それだからこそ、ヘンリーと恋人との間の素直な誠実な愛情表現が美しい。事件の真相に向けて、淡々と、でも自分の主義を曲げずに、弁護士として、ゲイとして、人間として、自分らしく行動する彼は魅力的である。リオス弁護士と(おそらく大多数の)他の弁護士達との違いは、彼がゲイ・ヒスパニックのマイノリティであること、そして、彼の「正義の貫き方」。
応答がいい。あんなどうしようもない男をなぜ弁護するのと聞かれたヘンリー。
“Well, the answer changes depending on the case,” I replied. “Sometimes
I defend someone because I think he deserves a break, or maybe just because
I like him. And sometimes I do it because, whatever the guy’s done, worse
has been done to him.” I grinned. “And sometimes I do it for money. And
sometimes I do it because no one else will. Like this case.” (p84) 弁護士はこうであってほしい。
“Nava’s Mysteries are faithful to the conventions of the genre, but they
are set apart by their insight, compassion, and sense of social justice.”
(Los Angeles Times)
読書以外の理由で、まず一冊だけ購入して読み始めたのだが、3作目から読んだことを後悔。すぐに他のを購入することに決めた。
平成23年2月20日
The Little Death (Michael Nava)☀☀☀☀

ロサンジエスルスの弁護士Henry Riosシリーズの一作目。ヘンリーが、薬物をとって現実の不安から逃れている青年ヒューに出会い、彼を愛したことから、過去の出来事にまでさかのぼる一連の殺人事件に入り込んでいくことに。ヘンリーは若いけれど、人間の幸せは、名声や富にあるのではなく、人間的な愛情の交換や正義の具現としての弁護士としての仕事にあるとすでに知っている。声高に愛情や正義を叫ぶのでなく、淡々と、しかし一貫して自分の道をすすむ。魅力的な主人公である。ロマンスや幸福を求める強い思い、社会の偏見や異なる人間を客観的に見つめる視線、揺るがない正義、他者への穏やかで冷静な応答――魅力的な主人公がいれば、物語は一気に読ませますよね。
"Every choice closes doors," I said, "and at some point you are left in the little room of yourself. I think most people who get to that room go crazy because they're surrounded with missed possibilitie4s and no principle to explain or justify why they made the choices they did. I don't invite unhappiness,
Aaron. Avoiding conflict may not be the noblest principle, but it works
for me.” (p.18)
哲学的コメントが多いです。
“Lawyer Henry Rios’s Loyalty to wealthy wastrel Hugh Paris strongly recalls
the male bonding in Raymond Chandler’s Classic ‘The Long Goodbye.’” (Publishers
Weekly)
確かにそうかも。ただ、マジョリティの「男性」を生きることが出来るマーロウと、マイノリティの「ゲイ男性」を生きるしかないリオスの違いは大きい。それだからこそ、彼等は「違う言語」を使う。それが文化。同時に、その中でも、同じ「正義」を語る。だからマーロウもリオスも好きです。
平成23年3月1日
The Double Comfort Safari Club (Alexander McCall Smith)☀☀
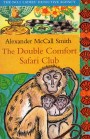
ボツワナの探偵Mma Ramotswe シリーズ11作目。複数の探偵依頼と、ラモツエを取り巻く人々の私的な事件がからまって、最後はすべてがきちんと解決というのは、今までと一緒。違ったのは、前作に引き続き、私が入り込めないこと。人間味溢れる解決までのストーリーは同じなのだけれど、前は癒されると感じていた、繰り返されるボツワナへの愛、アフリカへの想いの記述にさえ、またかという感じを持った。さらには、「事故」は、なんか物語のためとはいえ、このシリーズとしてはやり過ぎよねと違和感さえ持った。そして、同時に、大好きだったシリーズに自分がそう思うこと自体に、登場人物達に申し訳ないような罪悪感も持って、読み終えた。シリーズ9作目を読んでいた頃までは思ってもみなかったことが起きてしまった――つまり、本を読んでいる、という意識をずっと持ちながら、それでも、彼女達が好きだから、読み終える。だけど、それでも、12作目も買うでしょうね。
‘The Story gently insists on kindness and tolerance, and exudes a beguiling
blend of charm and humour’ (Sunday Times)
平成23年3月5日
The Hidden Law (Mickael Nava)☀☀☀☀

ヒスパニックでゲイの弁護士ヘンリー・リオスシリーズ4作目。上院議員の殺人と彼を取り巻く人間模様、それに、ヘンリー自身の過去における父親との葛藤、AIDS患者である恋人ジョシュとのすれ違う気持ちが絡む。1作目、3作目(2作目は手に入らず。数時間費やしてもダメでした。残念。。)のヘンリーと同じ。信じる正義にはゆずらず、静かに、自分らしく、人生を生きる。それでも、理解し合えなかった父との過去にも、愛するジョシュとの気持ちがかみ合わない現在にも、心が揺れないではいられない。愛情を求める点では極めて人間的でありながら、かつ、普通の人間をはるかに超える魅力あふれる彼と、事件の展開に、引き込まれて一気に読み終えた。そして、最後に、わっと涙が溢れた。この物語は、ハードボイルドタッチのミステリーなのだろうけれど、同時に、心を打たずにはいられないラブストーリーでもある。
“The Hidden Law is a beautifully conceived but gritty novel. Nava writes
the kind of clean, powerful novels that build in emotional power almost
invisibly, leaving us breathless at the end.” (San Francisco chronicle)
もう一つ。私もそう思ったものね。2月13日に最初にこのシリーズを読んだ時。
" This is the first Henry Rios mystery I've read, and the glad tidings for me are that there
are three earlier novels in the series to discover.” (The Washigton Post
book World)
平成23年3月6日
The Death of Friends (Mickael Nava)☀☀☀☀☀
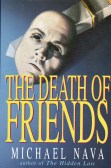
弁護士ヘンリー・リオスシリーズ5作目。LAの大地震の直後、殺人事件に巻き込まれたゲイの青年の依頼を受けたて、この物語は始まる。殺人の被害者は、ゲイであることを隠して生きることを選んだ、ヘンリーのかつての学友でもあった。真犯人にたどり着くまでには、登場する全ての人間の本性が暴かれていくのが、このシリーズの特徴である。それでも、最後にされた告白は衝撃的だった。自分の本質を隠して幸せになろうとして、自分が愛した人々も結局傷つける、それが人間の醜さであり、悲しさなのだ。しかし、この物語は、同時に、カミングアウトして生きてきたヘンリーとAIDSで急速に弱っていくジョシュとの美しいラブストーリーでもある。弱さと強さ、醜さと美しさが存在するから、愛おしい者達がまたわかるのかも。ジョシュの言葉にあるように。"But
the bottom line is another gay man did this to me." "What about the gay man who loves you," I said. He
looked at me tenderly. “That’s what’s keeping me alive.” (p.209)
前作を読んだ時点でも、そして、この物語のタイトルを見た時点でも、きっとそうなると覚悟していたつもりだったけれど、それでも物語の最後は泣けた。
“Micakel Nava has crafted an extraordinarily moving novel, a tale of love
and fear, of acceptance, rejection, and redemption. The mystery is a bonus.”
(Linda Barnes, author of Hardware)
シリーズの最後の2作もすでに手元にあります。読み続けたいけれど、同時に怖い気がします。ヘンリーには幸せになってほしい。すでに彼は、今まで心を引き付けた小説の主人公がそうであったように、私にとって、「生きている」のです。そして、ジョシュもそうだったから、急いでシリーズを読んできたことを、後悔もして、複雑です。
平成23年3月7日~8日
The Burning Plain (Mickael Nava)☀☀☀☀☀

弁護士ヘンリー・リオスシリーズ6作目。愛する者を失った後、深い喪失感とともに生きるヘンリーが、ハリウッドを舞台とする犯罪に自らも被疑者として巻き込まれていく。読み始めてしばらくはヘンリーの孤独に思いを重ねて感傷的になっていたら、物語はあっという間にジェットコースターのような連続殺人に展開、ヘンリー自身が自らも守る必要に迫られて、それどころではない感じに。今回は格段に激しい現代社会の偏見と暴力性が描かれる。しかし、それらに翻弄されているようで、実は自ら選んでいる選択肢が多いこともまた強調されていると感じた。”Hell’s
not a place, Rod, it’s something people do to each other.”(p.304) 偏見を受ける存在だから、たった一つの道しかないかったわけではない。生の質は、偶然性に左右される生の長さではなく、人間の質で決まる。喪失がどんなに大きくても、人は自分を自分らしく生きるしかなくて、そして、彼もまた例外ではない。喪失の後も人間の質を落とすことなく生きるヘンリーだから、また心惹かれる主人公となる。最後がいい。また感傷的になりました。逝った者と残された者の生に対しての答えを、私もまた信じたい気がする。"Will
I ever see you again?” (p.184) への応え。毎回、この作者の詩の選択に感嘆するのだけれど、今回は、ディキンソン。
シリーズについての書評。
“An exceptional series. Nava writes in a cool idiom whose clarity and precision
contain the heat of the inflammatory social issues and take the edge off
the characters’ emotional pain. Rios doesn’t win any friends for choosing
dispassionate justice over revenge. But he does it anyway, because he’s
one of the good guys-and Nava is one of the best.” (The New York Times
Book Review)
“Surprise twist, exquisite dialogue, and astute observation. Like Easy
Rawlins or V.I. Warshawski, Henry Rios is a fully developed human and humane
character.” (San Francisco Chronicle)
後一作となりました。
昨夜、その最後も、寝床で読み始めました。11ページまでで涙がぽろぽろでる感じ。嗚咽。ところがそこから突然、明るさがぐっと増してきて、100頁位まで、ミステリーの部分がない分、これはどうなるの、まさか突然、とかえって心配にも。180頁過ぎて今日のために眠ることにしました。
今夜は、絶対読み終えるでしょう。すでに頭の中で、こうなって終わって欲しいという強い希望があって、夜まで待ちきれない感じ。涙が出ないですむような終結であってほしいし、何かそうなりそうな予感があって、幸せです。本って本当にすごいです。今日の私は、プレゼントを夜にもらえることを知っている子どものように、朝から高揚して過ごすでしょうから。
平成23年3月9日
Rag and Bone (Mickael Nava)☀☀☀☀

弁護士ヘンリー・リオスシリーズ最終刊。心臓発作で倒れて入院したヘンリー。先に逝った愛する者を思う時、自分が今助かったことに対しても素直に喜べない複雑な思いがある。しかし、そのことを契機に、彼を気遣う人々の存在を再認識し、疎遠であった姉との繋がりが始まり、新しい出会いも得ていく。ヘンリーの孤独な思いの吐露にわっと悲しくなるのは11頁まで。殺人をめぐる謎解も、その過程で見えてくる複雑な人間模様も、いつものように読ませます。でも、ヘンリーがどうなって終わるのかが気になる私には、最後の頁までそれが最大の関心に。そして、「納得」。いつの間にか、彼の年齢も私に近くなりました。この一カ月、私を魅了したヘンリー・リオスに感謝。幸せでいてね。
“Rios’s humanity and decency shine through this satisfying novel and leave
the reader hoping that the author’s pronouncement of finis might be wrong.”
(Publishers Weekly)
テレビ画面に映し出される悲惨な映像に、言葉を失うような思いです。
とてもそんな気分にはなれなくて、
14日、予定していたディナーのための外出も止めました。
自分が今出来ることを考えて、それを行動していきたいと思います。