平成22年7月31日
Brookly (Colm Toibin)☀☀

50年代、母と姉と一緒に暮らすアイルランドの小さな街を出て、米国へ、Brooklyで働き、学び、恋をし、自らの人生を歩んでいく一人の女性Eillisの揺れる思いと決断を描いた話。姉の薦めで、自分では望んでもいなかった新天地での生活を始めたエリスが、孤独、ホームシック、希望、夢、恋、といった様々な思いに揺らぎながら、自分らしく生きていこうとする過程を描いた物語。同時に、どんなに自らの意志で自分らしく生きるといっても、人生は、様々な偶然性に満ちて、だからこそ「たった一つの選択」しか残されないような時もあるのかも、という思いで読み終えた。きっとEillisなら、その選択を、また最善をつくして生きていくだろうけれど、それでも、最後は、ほろ苦い感さも。2009年のコスタ賞を得ているということで期待して読み始めた。詳しい描写が淡々と続き、ユーモラスな箇所も多く、そのままでいくのかと思っていたので、最後に近づくにつれて、え、どうなるの、この結末、とまさにドキドキし始め、最後の最後で、そうなのか・・と感じた。途中では、自分ではさほど感情移入している気はしなかったけれど、選んだ、また選ぶしかなかった道での、彼女のこれからの幸せを信じていたい自分がいた。小説って、こんなものなのね。
最後の最後、”Eilis imagined the years ahead, when these word would come to mean
less and less to the man who heard them and would come to mean more and
more to herself.”(p.252) そうなんでしょうね。
“It stood out for its ability to use surface simplicity to mask (for a
time) vast depths of emotional and psychological complexity.” (John Lanchester,
Guardian, Books of the Year)
平成22年8月6~7日
Let The Great World Spin (Colum McCann)☁
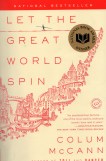
ニューヨークの街を舞台に、その地の過去、現在、未来と、時を超え、全く異なる境遇で生きる人々を、モザイクのようにちりばめて描き、次第にそれらの人々がいかに繋がっているかを見せていく話。70年代の世界貿易センターの綱渡りの男、アイルランド出身の宗教家のように生きる男、彼が助けようとしている黒人の娼婦の母娘、彼の兄、ベトナム戦争で子どもを失った黒人女性と裕福な白人女性。みな、何らかの孤独を抱えている中、相互に関連していく。こうなるのか、という意味では、見事だと思ったと同時に、こうしたのか、とその関係の付け方を冷静にみている自分にも気付いた。賞をとって、絶賛されている小説だけれど、上手に関係させてあると思いつつ、結局、その結び付け方のみに感心しただけだった。主要な登場人物の誰にも感情移入できないまま、それぞれの人々が生き生きと私の中では動きだすことなかった。
だから、絶賛の書評の中で、私の感想に一番近いのは、これ。
“Marvelously rich… a Joycean look at the lives of New Yorkers changed by
a single act on a single day.” (The Seattle Times)
平成22年8月9~10日
The Handmaid’s Tale (Margaret Atwood)☁

自由が規制された社会――そこでは、女性は、「主人の妻に代わって子ども」を生むことを義務づけられる。失った自由や恋人を思いながら、その運命を生きる一人の女性のストーリー。最後まで読んだけれど、途中、特に、日本人観光客に遭遇するあたりでは、もう、無理がありすぎ、という感じだった。恐怖の統制社会に、観光客が来れるなら、もう怖くないでしょ。これが一例で、ストーリー展開にも無理があるだけでなく、何よりも、主人公の行動にも感情にも共感できないから、とても楽しむわけにはいかなかった。ただ、それでも読み終えたのは、どうなるのかしら、とセンセーショナルな題材の結末が一応気になったから。その点で作者は成功しているといえるのかも。
“A novel that brilliantly illuminates some of the darker interconnections
between politics and sex….Just as the world of Orwell’s 1984 gripped our
imaginations, so will the world of Artwood’s handmaid!” (The Washington
Post Book World)
二つを比べる?!無理、無理。断然オーウェルに軍配あげます!!!
平成22年8月18日~19日
Sarah’s Key (Tatiana De Rosnay)☀☀☀

フランス人と結婚してパリで働くアメリカ人の編集者の女性Julia。夫は、魅力的だけれど自己中心的でもあることに、長い結婚生活を経た今、気づき始めてもいる。そうした中で、第2次世界大戦中、ドイツのパリ侵攻で、強制収容所へ連行されたパリのユダヤ人達の記録を特集として扱うことになる。アメリカ人である自分が初めて知る歴史上の真実と、それに無関心な夫の一族が、意外な接点を持って繋がっていく。1942年、ユダヤ人少女サラが連行時に鍵を手に「選択したこと」、その結末、そして、その後の彼女の人生と、2002年、サラの人生を過去に戻って知り、少しずつ変化するジュリアの人生と、最終的に「選択したこと」を、交互に描きながら、物語は、その二人を繋ぎ、関わり合った人々のあらたな人生の始まりを描きだす。
引き込まれて読んだ。サラの人生は、過酷そのもの。そして、題名の「サラの鍵」の意味するところは、ただただ重い。出来事の重さの前に、残酷さの前に、ひるまずに、敬意と優しさを持って忘れないように努力することは決してやさしいことではない。だからこそ、そうしようとするジュリアの口から最後に明かされる「選択したこと」には、じわっと涙が出ました。どんな非人間的な過去の歴史の事実に対しても、今を生きる人々が出来ることはあるのでしょう。「選択したこと」が、本当には選択の余地が全くない悲惨な状況での唯一の選択であった、そんな苦悩の選択を強いられた人々に、普通の人々が応答できる、それが「希望」。
“Mystery and compelling, it is not something that readers will quickly
forget. Highly recommended.” (Library Journal)
平成22年12月26日
Let the Right One In (John Ajvide Lindqvist)☀☀

世界的ベストセラーとなったスウェーデンの小説の英語訳版。12歳のOskarは、学校では、極めて残酷な苛めのターゲットである。その孤独な彼の前に現われたのが12歳のEliという不思議な「少女」。彼女もまた彼と同じ、それ以上の孤独を抱えている。12歳でもなく、人間でもない吸血鬼として生きるEli
と、Oskarの間に生まれる「恋」。生きるために血を吸う、すなわち人の命を奪うという設定から、ホラーなのといった場面も多い。でも、同時に、Oskarに降りかかる執拗な苛め、父親の飲酒問題、Eliを助ける男の欲望、そういった「今、私達の世界で実際存在しているもの」がホラーそのものなのである。そして、二人の間の恋を何とよぼうと、人間ではないEliが最後にOskarにした事は他の人間には出来なかったことなのだ。一気に最後まで読むしかないような物語、そして、同時に、これを幸せな人間賛歌のような気分で過ごしたクリスマスの翌日読んだことを、ちょっと考えてしまうようなお話。
"Please, dear God. Let her come back. You can have whatever you like.All
my magazines, all my books, my thing. Whatever you want. But jut make it so she comes back. To me. Please
, please God.” (p.167) "I hope you can like me even though you know
what I am. I like you. A lot.” (p.316)――どんな愛も、同じなのよね。そして、
"at least when you believe that this is the person you always want
to be with.” “You mean, when you feel you can’t live without that person.”(p.190-191)――最後は、そうだったね。
“Sweden’s Stephen King…a classic tale of horror.”(Tucson Citizen)
平成22年12月27日
The Boy in the Striped Pajamas (John Boyne)☀☀☀

第二次世界大戦、ナチ高官の父親の昇進によって、ベルリンから母親と姉とともに9歳の少年Brunoが、ポーランドの田舎に引っ越してくる。彼の窓からだけ見えるはるか遠くの「農場」へ探検に出掛けた彼は、鉄条網の向こう側にいる少年Shumuelと友達になる。ベルリンの生活や友達を恋しく思うBrunoには、全てを同じく置いてきたらしいShumuelはまさに自分と似た境遇の少年のように思える。友達になって、毎日のように格子ごしにおしゃべりをしながら、少しずつ、境遇の違いが見えてくる。食べ物に飢えていること、そこから出ることが出来ないこと、殴られることがあること、だけど、それでも、Brunoに完全に理解できないことがある。鉄条網の彼が探検できない世界の狂気である。母親達とベルリンに戻ることになって、最後の日にBrunoは、今まで見たことのない場所まで「探検」をする。本当に、本当に最後に近くなって、まさかの胸騒ぎで、本を読み急ぎ始めた。衝撃的な結末。「まさか」、その「まさか」が何百万人にもおこったのに、「向こうの世界」ではなくなった時、私達はやっと、その狂気を自らのものとして感じる。「まさか」と。それに自分が気づかされて、恥ずかしく、そして、悲しい。作者が記しているように、"the
rest of us live on the other side of the fence, staring through from our
own comfortable place, trying in our own clumsy ways to make sense of it
all. だから、作者も、この児童向けの作品に"the lost voices”を込めたのだろう。
"A book that tells a very bad story, gently.” (New York)
同感です。文学はだからすごいのです。
平成22年12月30日
No One Belongs Here More Tan You (Miranda July)☁

登場人物は、異なる状況、年齢も様々なのに、みんな同じように何がしかの孤独を抱えている、そんな16の短編である。年末の新聞で、今年の3冊というタイトルページで、2人もこの本の訳本を挙げて、そこに描かれた「孤独」を絶賛しているのを見て、すぐに2007年に出ているという原作をネット購入。自分の今ある場所に、かなわなかったことに、かないそうもないことに、孤独を感じながら、それでも生きている、生きるしかない、といった人々が、これらの短編に巧みに描かれているのだろうとは、16の短編を読み終える度に思いはするのだけれど、私には、共感という形では、登場人物の孤独は入りこんでこなかった。
だから、いくつもの賞を取ったというこの短編集への称賛の書評の中で、一番自分の気持ちに近いのは、これかと。結局、私向きではなかったということだろうな。「これらの孤独」に共感するには、私はあまりもロマンチスト過ぎ、鈍感すぎ、そして、幸せすぎる、そういうこと。
“Devastatingly personal…curiously uplifting.” (The Salt Lake Tribune)