平成28年8月
病院のベッドで本を読む。3年前には思いもしなかったことが、今の私に頻繁に起こっている。2年前の手術と入院の記憶がまだまだ鮮明なのに、この夏もまた同じように、手術を受けて弱った体を横たえて、病室で本を読むことになった。2年間で2回の手術・入院による年休ー考えなければならない、つらいことが今起こっている。転移を防ぐためにも一刻もはやく入院し、手術をした方がいいという医師の言葉に、それでも2週間は仕事のために延ばす必要があった。仕事に誠実でいることが、自分のするべき闘いと衝突するーこれも3年前には思いもしなかったこと。今回の病室は、今の自分も同じなのだろうが、生のために戦うしかない状態の人たちと共有する場。真向いの人は、すでに今後の治療はあきらめ、痛みを24時間止めながらホスピスへの転院を決めている。カーテン越しのお隣の人は、新しい抗がん剤によって激しい吐き気に毎日苦しんでいる。自分も弱って寝ているだけで会話を交わすこともほとんどないのに、二人の様子だけは看護師や医師、家族との会話で分かってしまう。生きることは大変なことだったのだ。自分にとっても、他の人にとっても。夜、部屋に死神がいる夢を見た。誰を待っているのだろう。
手術から10日が過ぎて、やっと本を手に取る気になれた。仕事の整理に追われて、入院準備も前夜。本を持っていくことも浮かばなかったけれど、入院当日、迷って一冊荷物にいれた。あとで家族が家から持ってきてくれた2冊にも、こんな状態だから読まない、と恩知らずにも言ったけれど、、結局読んだ。家族はよくわかってる。病院で読んだのは3冊。
Charles and Emma (Deborah Heiligman)☀☀☀
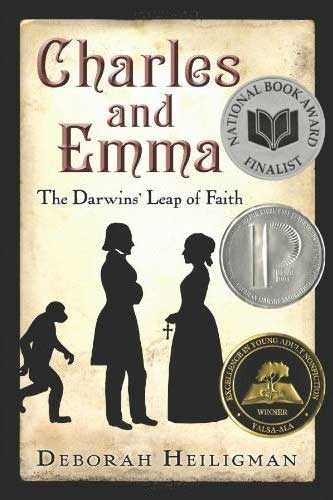
チャールズ・ダーウィンと妻エマとの結婚生活の始まりから二人の晩年までを記した物語。従兄妹同士でお互いをよく理解して始まった結婚が、お互いへの愛情と尊重、思いやりと優しさに満ちて最初から最後まで続いた様は、心が温まるような思いがした。物語は、残された文書、日記や手紙からの言葉を差し込みながら、史実に基づいて丁寧に描かれている。ダーウィンの偉大な仕事、信仰、そして結婚生活との関係も、とても興味深かった。“Every
thing that concerns you concerns me & I should be most unhappy if I
thought we did not belong to each other forever,” “When I am dead, know
that many times, I have kissed and cryed over this C.D.” (p.100) “we shall
be much less miserable together.” (p.149) “Emma was not all that interested
in science. She was only interested in Charles’s science because it was
his.”(p.181) “So different from each other, and dependent on each other
in so complex a manner.”(p.186) “Remember what a good wife you have been
to me.”(p.224) 残されている二人の数々の言葉に、優しい気持ちに満ちて本を終えた。理想の結婚なんて当人次第という人もいるだろう。でも、本当にそうかなあ。互いの譲れないことを尊重し、その譲れないもののゆえに愛することがないような結婚とは、結局、便宜上の繋がりで、思いがけない出来事を乗り越えることはできないと思うから。例えば事故、病、死。人生に起きる思いがけない偶然性。これを共に乗り越えることを「乗り越えなければいけない」と思う必要もないような繋がり、それが彼らの結婚だったのだ。世界で知らないものがいないダーウィンのような人の結婚生活を自分と比べるのも気がひけるけれど、それでも思ったことを書いておきたい。私も幸せな結婚をしたのだ。自分らしくいることを、その自分らしさゆえに愛してくれる人と歩むこと、そして私も同じように相手の譲れない部分について感じれるということは、有り難いことなのだ。出来事は、この3年、私にはとても厳しいものだけれど、それでも、この結婚生活が自分には今まで長くあったことを感謝しなければ。本の裏表紙にある言葉が一番この本について言い得ているかも―“In
her presence he found his happiness, and through her, his life.”
“Come for the science, stay for the love story.” (The Bulletin of the Center
for Children’s Books, Starred Review)
The Narrow Road to the Deep North (Richard Flanagan)☁
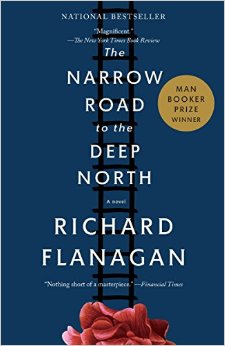
2014年マン・ブッカー賞受賞作品。第二次世界大戦中、軍医として従軍したオーストラリア人のDorrigo Evansは、日本軍の捕虜となり、悪名高い過酷な捕虜収容所で、泰緬鉄道の建設に関わることになる。酷い扱いを受ける他の捕虜たちを守ろうとするDorrigoの苦闘と日本軍の非道な行為が描かれる間に、戦争前の彼と叔父の若い妻であるAmyとの情事、結婚を約束したフィアンセとのエピソードが挿入される。戦後英雄扱いをされたDorrigoは、フィアンセと結婚し、外科医としても成功するが、いくつもの不倫を重ね、家庭は幸せなものではない。小説では、虐待行為をした日本軍将校や韓国人の兵士の戦後も語られる。読み始めてすぐ、これ何なのと下手な文章を書く作家の作品を読まされている感じで、何度も読むのをやめたくなった。その度に、本についている絶賛の書評を眺めて、受賞作品でもあるし、読み続けたらそう感じるのかもと最後まで読み切った。色々な人々の人生が描かれ、戦争と人生の偶然に翻弄される姿が、文学を愛するDorrigoにあわせたように、日本の俳句や英詩を適所に入れ込んで描いた物語(というところか)、でもまったくもって私には生きたものとは感じられなかった。最後まで読んで、自分にお疲れ様と言いたいぐらい。戦争中の日本軍のもとでの捕虜生活や過酷な鉄道作業の様子は、前読んだノンフィクションのThe
Railmanから詩情だけを無くしたパクリみたいだし、主人公へ感じる共感も皆無。差し込まれた人々のドラマチックな(つもりらしい)戦後の話も、挿入された詩も、作家の作為だけ目立って、完全に上滑り。だいたい文章がくさい。あ、読んで損した。読み終わって、よくこんな作品が賞を取れたなあと妙なところに感心してしまった。
書評には全く同意できないけれど、私がここまで書いてあるのだったらと参考にしたのは↓ 同意できないけれどね。
“Some years, very good books with the Man Booker Prize but this year’s
a masterpiece has won it.” (A.C. Granyling. Chair of Man Booker Prize Judges
2014)
The Buried Giant (Kazuo Ishiguro)☀
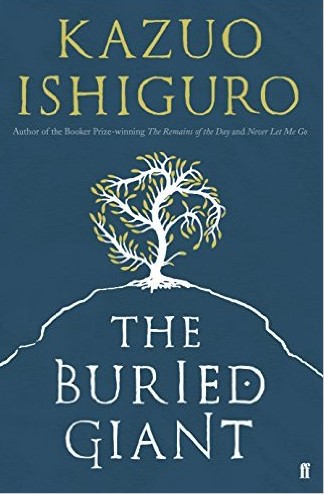
サクソン人とブリトン人の間に平和が保たれているアーサー没後のブリトン島を舞台に、ブリトン人の老夫婦AxlとBeatriceが、彼らの村を旅立ち、家を出て以来長く会っていない息子に会いにいくところから始まる、ファンタジー小説。ドラゴン、妖精、アーサー王の騎士、サクソンの戦士とファンタジーの王道のような要素満載で、それらをめぐる話がおそらく戦争という歴史と人々の保持する記憶の意味するものについて私たちに実は問いかけているというのは分かるような、そんな感じ。AxelとBeatriceの旅立ちから渡し舟のエピソードまでは物語に引き込まれたのに、他の登場人物が次々出てきてもストーリーに入り込めず、ともかく二人の旅の終わりについて知りたいという理由だけで駆け足状態で読む感じだった。二人に関わる部分だけがリアルに感じられ、それゆえ最後の島への船のくだりではまた物語に完全にはいりこんでいた、そんな感じの読書となった。間の膨大な部分にまったく入り込めないのでは、この本を楽しんだかといわれたら、やはり否でしょう。イシグロの作品だからと期待したけれど、そういう意味では、全くの期待はずれ。ただ、他の登場人物や何かを意味するのであろう隠喩らしい出来事や記憶云々の箇所は、私には響かなかったのにも関わらず、AxelとBeatriceの物語だけは心に染みた。そして最後は涙も。島へ向かう渡し舟に私もまた一人で乗り込むしかないだろう。その日が来たとき、恐れず、そして対岸に残る者に優しい言葉を残して、新しい記憶を紡ぐ未来を与えて、静かに一人で乗り込む勇気を私が持っていますように。
多くの絶賛の書評があるけど、私には納得できるものはなかったです。
“Mr. Ishiguro’s work is never simple. He has always been a trickster, a
shape-changer, courageously exploring the novel’s form, and this new book
is no exception. His language is plain and clear. But the stories he tells
with his clean words are powerful and disturbing. . . No doubt this book
will divide opinion powerfully: but it provokes strong emotions—and lingers
long in the mind.”(The Economist)
記憶と生について書きたかったなら、イシグロなら老夫婦の物語だけで本当に心打つ小説がかけたのにと思った。
ただ、これを病室で読まなかったら読後感も違ったのかもしれない。
4人部屋の病室には、もうすぐホスピスに移ることを決めている人、抗がん剤の副作用で苦しみほとんど食事はとれない人の、二人と私。彼女達と医師や家族との会話は筒抜けに聞こえる毎日。私の手術後数日してはいってきた4人目の人は、初めて受ける抗がん剤に看護師さんが何度も駆けつける大変な状況で、ナースステーションの近くの病室に5日後に移動。カーテン越しに避けることのできない現実が、自分の状況とも重なって、息苦しくなるような空間だった。でも、その移動された4人目のあとに来た人は、70歳半ばにはなっていると思われる人。急性の十二指腸炎で夜中に緊急に運ばれてきて、手術も無事終わって、今後も全く心配いらない回復状態だけれど、年齢のせいで傷口の治りが悪いからもう一週間ぐらい念のため病院にいるという。前の部屋がうるさくて嫌でどうしてもと静かな部屋に変更を希望されたとのことだった(会話が聞こえてわかってしまうのです)。訪問客に、「こんな痛いことは人生で一度もなかったから自分でもびっくり」と連発。生死をかけた手術や治療を受けている他3人の醸し出す部屋の静かな雰囲気にびっくりされたかなあと思ったけれど、それはなさそう。食器をカタカタと言わせておいしそうに元気に食事を食べる、売店で買ってきた間食をバリバリ音をたてて楽しむ、スリッパで歩く音もトイレの出入りの音も部屋に一人でいるかのような遠慮のなさ。彼女とカーテン越しに隣のホスピスへの移動を待つ方が痛み止めの点滴もずっとつけ、食事はもう何も一切口から取れないで点滴で生をつないでいる状態だとはすぐわかっただろうけれど、まったくそれに影響されない。他の二人に気をつかって、術後一週間して食事をとり始めた私はできるだけ音をたてないように食べ物を飲み込むように静かに食事をしていたから、「あ、こんな人もいるのね」と思った。でも、この健康でずっと生きてきた周りをまったく気にしない呑気なおばあちゃんがこの部屋に移動してきたことは、私には大きな救いだった。私もまた彼女のようには生きることはできない一人なのだけど、それでも、この羨ましいほどの健康に恵まれた幸せな人の言動は私をにっこりさせた。彼女がこの世界の大多数なのだ。生に自分が近いゆえに、死に近くなっている者の苦しみや不安は分からない、分かりようがない幸せな大多数。また、そうあるべきなのだ。だって、生きることは、他者にとっても賛歌なのだから。他者の生さえも人間には喜びなのだ。そう思った。
All That Is (James Salter)☀☀
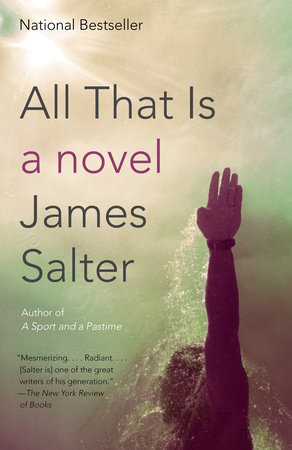
第二次世界大戦に従軍後、戦後、Philp Bowmanはニューヨークの出版社で編集者として働く。恋愛、結婚、離婚、そして、また複数の恋愛と、初老にいたるまでが描かれる彼の人生は、編集者の仕事では成功、一人との長い関係を維持できないという点では失敗なのであろう。そもそも、彼はそういう生き方ができないような男性なのだと読み進めて思えてくる。永遠に続くような人間関係に成功することには向いていない、実際本当には望んでもいないのかもと思われる人々の一人。自己中な、それゆえ女性には魅力的になってしまった男性なのだ。しかし、途中で挿入される彼に関係する人々の様々な恋愛模様は、悲しいかな、向いている、そうしたいと思っている人々でさえ、往々にしてそれを得ることは難しいことを描きだしている。迷い、裏切り、欲望、喪失、孤独、偶然に翻弄され、それでも生き続け、自分が幸せになりたいと思うのだ。そう感じさせるせいか、この自己中のBowmanや彼の恋愛(彼の場合、本当の意味で、そうと呼べるのかさえ分からないけれど。他者に尊敬をこめた愛情を感じていないような関係だから)に共感を感じることはなくても、彼のそれなりの幸せを願っているのに気づいた。この作家の文章自体が美しくて、読んでいて、あ、職業作家の本を読んでいると感じられる英文だったことも、その大きな理由かも。下手な作家の感想文のような英語で綴られる小説(Narrow
Road to the Deep South)を最近読んでうんざりしたばかりだから、それだけでも感謝。終始男性中心の都合のよい目線で女性が描かれているとは感じるけれど、描かれている人物達が少なくとも物語の中で生きているだけでも、読書する意味がある、そう思った。“The
idea of passing from this world to another, the next, was too fantastic
to believe. Or that the soul would rise in a way unknown to join the infinite
kingdom of God. There you had never known, the countless dead in numbers
forever increasing but never as great as the infinite. The only ones missing
would be those who believed there was nothing afterwards.” (pp.288-289) そうかもね。
““In telling this drama, Salter gives us joy, eroticism, disgust, beauty,
nostalgia, outrage, highbrow discussion and lowbrow humor. There are moments
of crushing tragedy…followed later by line of wry comedy…Throughout, the
story is populated with rich and living characters who stand at the centre
of our gaze.”(The Times)
The Magician’s Elephant (Kate Dicamillo)☀☀☀
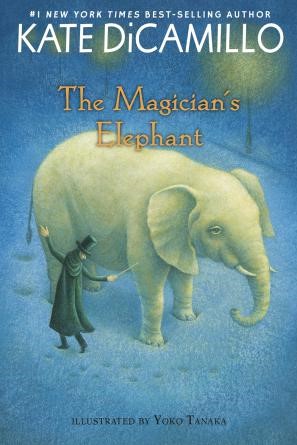
いつも以上に寒い灰色の冬を迎えたBalteseの町で、亡き父の友人だった男とくらす少年Peter は、占い師に、「妹は生きており、象がその居場所に導いてくれる」と言われる。そして、その夜、マジシャンがユリの花束の代わりに呼び出して、劇場の天井から貴婦人の上に落ちてきて、彼女を半身不随にしてしまったのが象だった。マジシャンは牢屋に入れられ、象も閉じ込められる。Peterを彼の父親のような「勇敢な兵士」とすることに取りつかれている元兵士、妹を見つけることを夢見るPeter、事故について同じ問いをマジシャンにし続ける貴婦人、転落して体が不自由になり象の世話をする石工、苦しさで生きる気持ちが失せていく象、全ての人々が最後にすべて一同に会することなったのは、その冬はじめての雪が降った夜。それぞれの記憶と夢が重なりあった、その時、奇跡はおこるのか。
この作家の作品なら引き込まれるはず。そう思って読み始めた。そして、その通り。これは、子ども向きに書かれたふりをした大人向けの寓話。私は楽しんだ。終わり方もいい。優しい余韻が残った。挿絵もぴったりだと思った。名前だけ見ると日本人の方のよう。それまでは、かなわぬ夢と失われた記憶、そして孤独をいただく個々の人々が描かれていたのに、171頁、179頁、189頁と人々が少しずつ増えていく挿絵は、奇跡とは、多くの人の想いが集まった時、集まった場で起こるのだと思わされて、好き。
“A book for quiet corners and Christmas evenings…. Kate DiCamillo has a
gift.” (The New York Times Book Review)
“Mysterious and charming. In DiCamillo’s talented hands, it’s also whimsical—the
result of a cast of eccentric and era-appropriate characters who aren’t
mean-spirited so much as humorously flawed.”
確かに、クリスマスを思わせるような夜。そして、本質的には悪人ではないけれど、人間であるがゆえに弱点がある、そうした人々ばかり。彼らはみなどこか私自身でもある、そんな気がします。
私の今の夢は叶うでしょうか。今願っている奇跡は起こるのでしょうか。それがたとえかなわなくても、起こらなくても、私もまたできるだけの優しい記憶と想いに満ちて自分の生を最後まで全うしたいと思います。
The Tiger Rising (Kate Dicamillo)☀☀
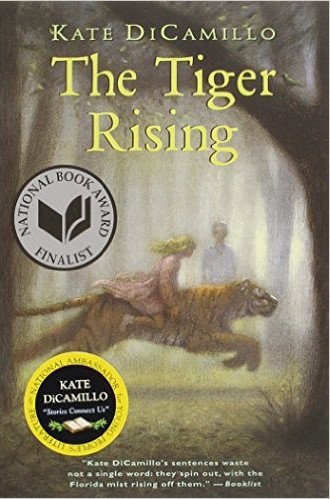
母の死後、悲しみから逃れるために引っ越してきた父と息子のRob。父はモーテルの雇人になって、二人はその一室で暮らす。Robは 新しい学校でいじめられ、足のただれが他の子どもにうつるのではと校長からも在宅を勧められる。そんなRobが見つけたのが森の中でオリに入れられた美しいトラ。モーテルの持ち主が借金のかたに手に入れたもので、Robは鍵を預かり世話を頼まれることに。新しく転校してきた少女Sistineは、Robにトラを解放すことを主張する。トラは解き放たれるのか。強い悲しみや怒りをみな口にしないことで、どうにか生きていこうとするけれど、それが本当には生きることを難しくさせることでもある。Rob、父親、Sistine-みな、自分の重荷を解き放つことができたエンディングは希望。“To
let sadness rise.” (p.38), “You got to rescue yourself.” (p.84) は難しいことだけど、可能なのだ。それを言うWillie
Mayは人間として賢いし、優しい。こんな人が回りにいるといいよね。息子のために父親は母親の名前をついに口にし、そのRobが父親の“complicated
hands” 見つめる(p.119-120) 自分を思い、理解しようとするお互いがいれば、モーテルの一室で作る“Macaroni and cheese”
も悪くないのだ。
“Powerfully and beautifully written.” (Angela Johnson)
この作家は文章が本当に巧い。
平成28年12月27日
One Crazy Summer (Rita Wiliams-Garcia)☀☀
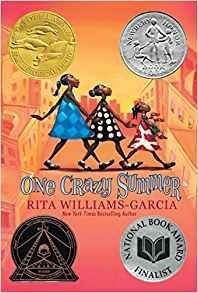
2010年ニューベリー名誉賞作品。1968年、ニューヨークのブルックリンからカリフォルニアのオーランドへ、母親Cecileと一夏を過ごすためにやってきた、11歳の、しっかり者で、妹たちの面倒を見る責任を自覚している長女Delphine、目立ちがり屋の次女Vonetta,
負けず嫌いの末娘のFernの3姉妹。Fernが生まれてすぐにCecileが出ていったために、3人で一緒にCecileと初めて過ごす。それなのに、当のCecileは歓迎をする様子は一切なく、食事の用意もしてくれない。朝は、コミュニティーセンターに行って、Black
Pantherに提供される無料朝食を食べ、そのサマーキャンプに参加し、一日を過ごし、夕方戻るという生活を娘たちに要求する。娘たちを決して入れようとしない台所で詩をひたすら書く母親と、その母親のもとで、初めて経験する黒人の政治活動と厳しい現実、母親への姉妹たちの思いが、Delphineによって語られる。マイノリティグループに正当な権利を与えていない社会で闘うこと、それまで3人三様にイメージしてきた、子ども達を捨て「詩人」として生きる道を選んだ母親、それらをより理解すること―3姉妹は、それを一夏の経験で成し得る。それが、Cecileが「母親」であることの感情を初めて示すことも可能にしてくれるのだ。結局、違った形であっても、父親も、お祖母ちゃんも、Cecileも、厳しい時代を必死に生きていたのだろう。そして、こうした三人娘のような子ども達が、逞しく今まで生き抜いてきた人たちなのだろうし、今からもこんな子ども達が社会を変えていくのだと思える
“In One Crazy Summer Willlimas-Garcia presents a child’s-eye view of the
Black panther movement within a powerful and affecting story of sisterhood
and motherhood.” (New York Times)
平成28年12月29日~30日
We are all completely beside ourselves (Karen joy Fowler)☀
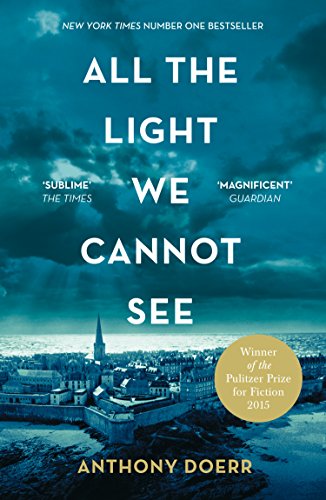
2014年ペンフォークナ賞受賞。マンブッカー賞フィナリストの作品。大学生のRosemaryは、姉妹のFernが5歳の時にいなくなり、6歳上の兄Lowellも、高校生の時に突然家を出ていくという経験を持っている。なぜ二人は突然家からいなくなったのか、現在の出来事が進行する中で、同時に、記憶も呼び起こされる形で、過去の二人の失踪について、全てが明らかになっていく。始まりは、ミステリーそのもので、かなり緊張感があったけれど、途中、Fernが「何者」か示され、さらに、Lowellとも再会した後からは、時には不必要とも感じられる詳細な説明が続き、終わりに近づく時は、「動物倫理」「家族関係」「人間心理」「言語と心理」、どれをも同じように絡んだ複雑な形で入れ込みたくて、結局、最後は消化不良よねと思った。すべての者が、「最初に」「家族の関係」にあったがゆえに、「最後まで」「家族全員」が、責任、罪悪感、孤独、喪失といった苦しみを背負うことになったわけで、それが家族の個々の運命を決めてしまう唯一の理由でよかったのではないだろうかと思った。誰かの存在を誰かの上位に置く、誰かを誰かより愛してしまう、より大切に思ってしまう―家族というのは、そうした問いを時には残酷につきつけて、本来無条件で愛し合っていると仮定して成り立っている家族を苦しめる厄介なものなのだと、自分でも知っているがゆえに、私には特にそう思えてならない。Fernという存在の設定自体は秀逸なのに(名前まで伏線があって)、あとで色々と続く「動物実験」の説明が不必要に感じられて惜しいし、終わりの数十頁は、そうしてしまっては興ざめ、という感じまでも。もし私が作家だったら、Fernも、Lowellも再び登場させないまま、家族の物語を書き終えたなあと。そして、そんなことを考えて読み終えたこの読書は、結局、私にとっては、自分が物語に入り込んだと言えるような楽しい読書ではなかったのだろう。
“Deliciously jaunty in tone and disturbing in material.” (Alice Sebold)