平成29年8月
Absent in the Spring (Mery Westmacott)☀☀☀
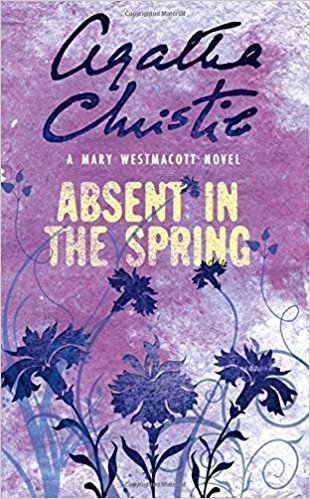
推理小説の女王と言われるアガサ・クリスティが別名で書いた、殺人事件のおこらない小説。初老の弁護士の妻である主人公Joanは、バグダッドに住む娘夫婦を病気見舞いのため訪問後、英国へ戻る途中、天候のため汽車が不通となり、数日途中駅の宿泊所に足止め状態となる。その間、誰ひとり知った人がいないまま一人だけの時間を長く持つことになる。そのために、彼女は自分自身の過去の出来事やその出来後に関わる3人の子ども、夫Rodneyとの会話を思い出して、それまで気が付かない、または気が付かないふりをしていた事柄を強く意識し始める。問題がないと考えていた家族との関係は一体どうだったのか。Joanが答えを得たことによって、それは変わるのか。物語は、Joanが帰宅したあとまで、サスペンス仕立てで一気に読ませる。さすがアガサ・クリスティという気がする。結局、殺人は、人間的な葛藤やエゴが引き起こすわけで、殺人にいたるしかなかった人間関係を読者に説得力ある形で示し得た彼女なら、殺人なしの人間ドラマを書けるのも当然。ほとんどの幸せでない人の人生も殺人などおこらずに終わるのだから。自己愛、自己欺瞞、自己中―自己をつけると、全てが問題があるようにされる。でも、本当にそうなのだろうか。私達はみな程度の差こそあれ、Joanなのだ。彼女が他者のためになす行為にはいつも自己愛が背後にあったとしても、その行為をそのまま享受してきた夫も子どもも完全な被害者ではないはず。結局は、Joanを極めて冷静に評価している3人の子どももRodneyも、十分自己中であり、自己愛に満ちているのでは。何よりも、Rodneyにその思いを強く持った。JoanにもRodneyの立場にも同じ程度に理解できるものがあって、中立のような立場だった私を、最後の最後、Rodneyの心の中でJoanに向けた言葉が突如変えた。Rodney、あなたは優しい人間なんかではない。狡い人間だ。そう思った。自分にとってたった一人とJoanが抱きしめるRodneyが、心では自分にその言葉を向けていると知っていたら。それはとても残酷な裏切り。もしこの作品が殺人事件を一つ持つなら、ここなのだ。そして、殺意を持つ側はRodneyの心の声を何らの理由で聴くことができたJoanになるはず。だから、Rodneyは、この声を永遠に聞かせないつもり。Joanのため?いやRodneyのため。彼の勝手な復讐。自らが選んだ人生を自分勝手にJoanのせいとしたゆえの復讐。そう思えた私も、どこかJoanと自分が似ているがゆえに、そう感じたのかも。そう思うこともまた怖いことなのだけれど。私には、Joanの方がRodneyよりはるかに人間としてまともに感じられる。”From
you have I have been absent in Spring.”(p.99) 多くの人間は、“you” が誰かさえ本当には知らないで、勘違いをしたまま、生きるのかも。“you” と自分に呼びかける人を、自分もまた、“you” と想える、そう自分の人生を思える私は、JoanでもRodneyでもないはず。同時に、普通の人間だから、二人のどこかを自分にも持っているはず。それであれば、どこに?この小説はまさに一級のサスペンス。
“I've not been so emotionally moved by a story since the memorable Brief
Encounter...Absent in the Spring is a tour de force which should be recognized
as a classic/” (New York Times)
身体の苦痛はどこまで私の在るべきと信じてきた精神を侵すのでしょうか。私はどこまで強いのでしょうか。この数ヶ月は毎日問いかけるようになりました。人間としてあるべきと信じてきた精神の高みを失わないだけの強さを持って、自分は少なくとも他者へ向ける微笑みを持って生きることができますように。祈りに近い日々が続きます。人生もサスペンスですね。どんなに強い祈りでも、叶うのかわからないのですから。でも、どんな結末のサスペンスになっても、自分は優しい登場人物で必ず終わりたいのです。
平成29年8月
Empathy (Sarah Schulman)☀
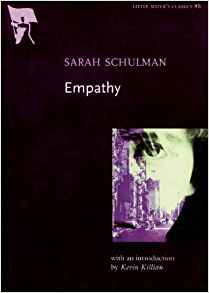
ニューヨーク、ロウア―・イーストサイドの住人で、街角でビジネスカードを配って、心の問題を抱える人々の診療を一時間10ドルで提供する、大学院で学んではいるが、無免許の精神科医Docと、そうしたDocの診療を求めてきたレスビアンのAnnaを中心に物語はすすむ。自分のアイデンティティの確認には他者が必要であり、家族、友人、恋人、そうした人々との関係で、完全なる確信を持てていない二人が、お互いとの関係を通して、過去、現在の自分について考えていく。当時のアメリカ社会への批判が随時入り込む―AIDS,
薬物、ホームレス、そして、セクシュアリティ。1992年にアメリカの著名なレスビアン作家のひとりによって書かれたパイオニア的作品と聞いて読み始めた。自分のアイデンティティと欲望、他者との関わり、精神、社会の在り方がいっぱい小説に盛り込まれているのは分かるけれど、なるほどこれを言いたいのか、こう説明するのよね、と思うことは度々あっても―例えば、
“Except to myself, I mean, how many times can a person be told in a multitude
of ways that she will never be fully human because she is not a man? The
logical conclusion is to become a man to herself, simply to retain the
most basic self-respect.”(p.165) “Since I was a child, he said, ‘there
have been two epithets that I have truly feared. I feared being told ‘You
want to be man,’ and I feared being told ‘You hate men.’ (p.165),” 登場人物の誰にも感情移入はできず、私は小説を読んでいると最後まではっきりと意識したままで終えた読書だったので、この本を読むことを楽しんだとはいえないよね。
“Insightful…funny…makes provocative statements about gender roles, sexual
orientation, AIDS, homelessness,drugs, and the therapeutic value of an
attentive ear.” (Publishers Weekly)
Tucker’s Countryside (George Selden)☀☀
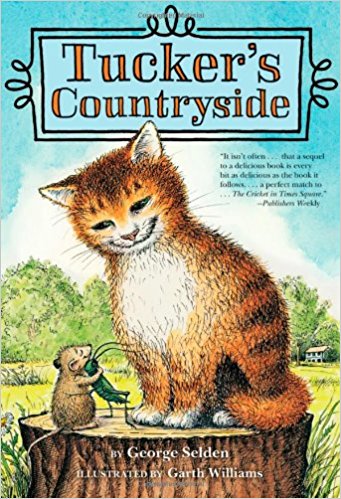
The Cricket in Times Squareで始まる人気シリーズの一冊。カントリーサイドに戻ったChesterから助けを求める伝言がタイムズ・スクウェアのHarryとTuckerに届けられる。二人(二匹というべきか)は、Chesterの住む町へ向かう。全ての住人が愛しているOld
Meadowが開発のため破壊される計画を阻止するべく知恵を絞るのだが、なかなか名案が浮かばないまま、夏が過ぎ去ろうとする。ブルドーザーもやってくる日が来て・・・。今年の始めに読んだThe
Cricket in Times Squareを楽しんだほどには、とは思うけれど、それでもChesterもHarryもTuckerも大好きだから、それはそれでよしとしましょう。終わりよければすべてよしと思えるような登場人物に会えるなら、それが子ども向けでも、青少年対象でも、構わない。小説の魅力はまさにそこにある。表紙の三匹を見るだけでにっこりしてしまう。
“It isn’t often…that a sequel to a delicious book is every bit as delicious
as the book it follows…. a perfect match to The Cricket in Times Square.”
(Publishers Weekly)
平成29年8月
Tuck Everlasting (Natallie Babbitt)☀☀☀
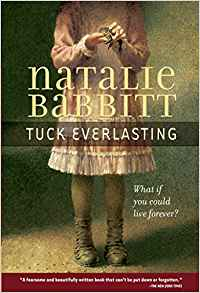
大きな秘密を抱えて、他の人達と交わることなく生きるTuck一家の4人と11歳の少女、Winnieの遭遇。Winnieは一体どちらを選択するのか。これは、子ども、青少年対象の本とされているけれど、もし私が、未来がただ前に自然に開けていくと信じていた子どもの時に読んでいたら、どう思ったのかなあ。自分は永遠の命を手に入れたいと思ったのかなあ。きっと考えもしなかったよね。十分長い長い人生が自分にある予感があの時あったのだから。今?理由は全く違うけれど、それでも私は永遠を選択はしないでしょう。限られているから、限られていると感じるしかないからこそ、自分に与えられた命をきちんと大事に生き抜きたい、それを一緒に生きようとしてくれる人を大切にしたい、そんな気持ち。それでも、そういう大切な人達をあとに残すことだけは、心残りで悲しい。人間とは不思議な生き物だなあと思うことが多くなりました。ともかくどうなるのか展開が気になって、斜め読みに近い速読。そして、納得できる終わり、子ども時代の私にも、今の私にも、です。"You
can't have living without dying. So you can't call it living , what we
got."(p.64)
"A fearsome and beautifully written book that can't be put down or
forgotten." --"The New Yorker"
平成29年9月
The Stolen (Alex Shearer)☀☀☀
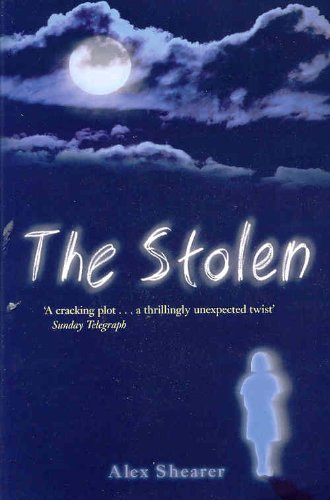
ベストフレンドを欲しがっている、12歳の赤毛とそばかすだらけのCarlyのクラスに、美しい少女Meredithが転校してきた時から、次々に起こる出来事。子ども離れしたMeredith、遠慮がちに振る舞う彼女の祖母、一体二人にはどんな秘密が。途中までは、きっと、こう来るのよね、もしかしたら、こう展開するのかも、と2パターンを浮かべて、魔女の出る青少年向けファンタジーの佳作(であると予想して読み始めた作品)を楽しむ気持ち読んでいたけれど、途中から、「え、こうなるの?」「う~ん、ここまでいっちゃうの?」という展開ぶり。子どもが読むと途中からの展開はかなり怖いかも。「老い」「家族」「死」―ここまで言うのというぐらいリアル。こんな展開なら、まさか最後も予想ずみのハッピーエンドとは違ったりして(でも、まさか)と、速読状態で、最後がどうなるか気になって一気読み。この魔女の邪悪さは大人でも怖い。"Oh
no! That’s not how it works at all. We do thing like this for the sheer
fun of it. For the joy of the wickedness! We don’t do things to get our
own back. We just do them!.” (p.71) こんな邪悪さには大人だって震えあがる。
"Alex Shearer is an excellent storyteller and this one has a nail-biting
twist。”(Mail on Sunday)
読み終えた後、この本の題名が一日に何度も浮かぶ。「どんなことがこれから起こるとしても、自分の人生は誰にも一度もStolenはされなかったのだから」と。少なくとも、私はStolenされたと感じることなく、ここまで生きてこられた。有難いこと。感謝するべきこと。
平成29年9月17日
A Man Called Ove (Fredrik Backman)☀☀
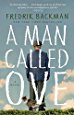
スウェーデンのベストセラー作品の英語版。幸せな長い結婚生活の後、病死の妻に先立たれたばかりの59歳の男、Oveは、世の中のあるべき社会規範やマナーに拘る、気難しい偏屈な老人。よく言えば、不正直や騙しが許せない、心の真っ直ぐで、正直な、そして心の温かい、真っ当な人間。Oveの父親、若き日の妻との恋愛、妻の父親との会話、長い間近所に住む家族との関係、新しく引っ越してきた家族との出来事、そうした人々とのエピソードが、現在進行のOveの日常に、回想として入れ込まれたお話。Ovenの拘りや生き方を表す出来事や言葉の「極端さ」(かなり、かなり、かなり、すごい)ににっこりしながら、妻との思い出の会話にはほろっとして、という、そんな読書に。”As
if she took away with her the few words he’d possessed.”(p.39), “And he
always felt that nothing in the world was impossible when she did that.
Of all the things he could miss, that’s what he misses most.” (p.69),”But
if anyone had asked, he would have told them that he never live before
he met her. And not after either.” (p.136)―その度に、自分の父親を浮かべてしまった。どちらかというと、似ているのかな。”He
was a man of black and white. And she was color. All the color he had.”(.37)。だから、Oveがしようとしたことと同じことをしたのかなあって。父は結局、そうして母をおって逝ってしまったけれど、母との関係もこんな感じだったのだろうなあって。父もまた、人間関係には不器用で正直な人だった(偏屈ぶりはOveの一万分の一ですけどね)。”Everything
will be fine, darling Ove.” (p.136)―今の私にとっては、同じように優しい言葉を心から伝えて行けるのか、そのことも気になる。その言葉を残していかなければいけない家族も、また、正直さや人間関係での器用さという点では、Oveのような人(名誉のためにいえば、偏屈ぶりは、Oveの十万分の一ですけどね)。でも、大丈夫なのでしょう。一つの大事な関係を失っても、それは何かで補えるもの、そんな気持ちにさせてくれるお話です。母が逝ったあとの父の孤独な生き方がどうしても私には思い出されてしまうけれど、Oveのようにも生きれるはず。そう思わせてくれた点では、よかった。ただ、物語も三分の2を過ぎたころ、本を途中で用事で置いても、先をたいして気にしていない自分に気付いた。物語の外に出てしまっている。最後もちょっとね。
“Poignant and unpredictable, Backman's book is filled with many twists
and turns, as well as enjoyable characters and situations.” (Columbia Tribune)