平成20年7月13日
Marley & Me(John Grogan)☀☀
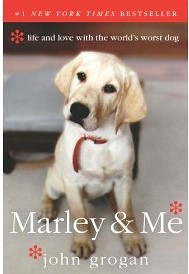
元気一杯の子犬を飼い始めた若い夫婦の実話。犬と自分達の生活を美化することなく淡々と記した(ように書いてある)がゆえに、読んでよかったと素直にいえる本。新聞社に勤める書き手と家族が、いつもハイパー状態で躾を全く受け付けない大型犬とどのように暮らしたか、どのように思いながら彼との生活を終えたのか――犬を一度でも飼ったことのある者であれば、何らかの思い出を重ねるだろうなと思う。読んでいったら、おかしくて、同時にほろっとしてしまうのかも、と誰でも予測できるような表紙の犬(こういう見かけの犬が大好き!元々、自分がこの一年間、犬を飼おうかな、と思っているので、思わず手に取ったのかも)と、“life and love with the world’s worst dog” の言葉。そして予測通りだった。このお話のように、若い時に犬を飼って暮らし始めるということは、それから広がっていく一方の自分の人生の春に、人間より短い一生の犬の黄昏時を共有するということ。でもそれを考えて犬を飼う人なんていない。だからこの若い夫婦が子どもを持ち、キャリアを充実させていく、人生の一番良い時期の最中に、まさに老いてしまった犬との間に起きることが、彼等の思いが泣かせた。自分が少女時代から飼っていた2匹の犬と、それぞれの最期を、そして、その犬達に一番優しくて、お別れの時には家族の中で一番激しく泣いていた母親を思い出しながら、何箇所かで涙が溢れてしまった。犬を飼うということは、自分の愛情をむけて一緒に生活を生きるということなんだとあらためて思った。今の私は、愛情を持ってしまうものとお別れする日を思うと、それだけで悲しくなる。だから飼うのは止めるにした。ただ、もしもいつか飼うような気持ちになれる日がきたら、この本の最後になって出てくる犬の名前にするつもり。だって、私の2匹の犬の名前は「ハッピー」と「ジョイ」だったから。3匹目になる犬はやっぱりこれしかないでしょ。
“A very funny valentine…Marley & Me tenderly follows its subject from sunrise to sunset…with hilarity and affection.” (New York Times)”
本当に長い間、新しい本を読む時間を持たないで過ぎた。この記録を見ると4月29日から2ヶ月以上である。授業に関係する物語は色々読み返していたので、こんなに長く新しい物語を読んでいなかったんだなと驚いた。先週、4年前の卒業生のYさんが、「このノートを読んで、自分も久しぶりにじっくり読んでみたくなりました。」とメールをくれた。そのメールに書かれた彼女の充実した仕事とすてきな出会いや出来事の数々。メールの内容が、それだけで素敵な物語を読んだような気持ちにさせてくれた。Yさん、じっくり読む時間もいつか必ずあるから、今はそのままがんばって、そのあなたの見つけた居場所でまさに自分だけの現在進行形の物語の中で輝いていてくださいね。
平成20年7月14日~19日
Wicked (Gregory Maguire)☂
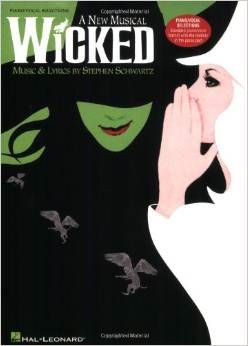
表紙に書いてあることから、あの有名な「オズの国」を、そして「西の邪悪な魔女」を、違った観点から描くブラックなファンタジーと思って読み始めたし、その印象は、106頁で止めてしまった時点でも変わらない。500頁以上もあるこの本を読み終えたら、巧く書かれていると感じるのだろうけれど、どうしても、これ以上読む気持ちになれなかった。Elphabaが発した言葉(88頁)なんか効果的ね、と思ったし、有名な物語を下敷きにどのように展開していくのだろうという興味は今でもあるのだけれど、所詮読書とは、自分がストーリー自体に入りこめなければ楽しく続けることは不可能であることを、あらためて証明。
検証できなかったけれど、表紙には
“Brilliant…A remarkable treat.” (New Orleans Times-Picayune)
平成20年7月20日~21日
Love in the Time of Cholera(Gabriel Garcia Marquez)☀
A love story of astonishing power” (Newsweek) と本の表紙に。そして、本の裏表紙をちょっと読めば、叶わなかった若い恋と半世紀を越える月日の後の恋の結末-それが物語の内容だとわかって誰でも読み始めることになるだろう。長い長い月日(51年9ヶ月と4日!!!)、多くの女性と関わりを持ちながらも(実に多いです)、一度も忘れることはなく、もう一度愛すること、愛されることを求めて、別の男性フベナルと結ばれた女性フェルミーナの前にあらわれる男性フロレンティーノの愛-これを「純愛」というか、「狂愛」というかは、読む人が決めるしかない。捉われた愛は怖いと感じれば、その男性さえも嫌になってくるし、捉われながらも、三文小説にあるような逆恨みや復讐をしかけるということなど一度も浮かぶことなく、「ある時」だけを待ち続ける男の想いに強い共感を覚える者もいるかも。私は前者。こんな男性、自分には絶対現れて欲しくない。現れても、返事はフェルミーナのあの4語(50頁)。だから、愛情のあり方という点での共感は、フェルミーナとフベナルの夫婦としての月日の幾つかのエピソードと二人がお互いへの最後の想いにだけだった。この有名なノーベル賞作家の巧さはわかる。時間も前後して、様々な過去・現在の秘密が明らかにされていく展開に、最後は一体どうなるのかが気になって、二日目には本を読み終えずに置くことができなかった。「永遠」を得るために、フロレンティーノが本当に必要とした月日が、物語の最後の頁になってついにわかるのも巧い。
ただ好きな本かといえば、否。長い月日の間、あれだけ様々な女性と関わりを持ちながら、その中の誰とも「永遠」を見つけられないなんて、私にはまさに理解し難い非人間的行為に思えてならないから。読み終えて、最初の恋と最後の恋の違いについての定義を思い出した。「最初の恋は、これは最後の恋だと思うもの、そして、最後の恋は、これこそが最初の恋なんだと思う」――というような言葉である。誰をいつまで愛するのか、どのように愛するかは、その人にしか決められない。でも愛情は、対象を伴うから、傷つけないで、傷つけられないで、自分の思い通りに愛する、愛されることもまた不可能なのである。だから、関わっていく人を結局一番愛してしまい、同時によりよく愛していこうとする人間に、私は心を打たれる。だから、これが一番納得。
“Spellbinding—a luminous novel by a master of storytelling.” (Joseph Heller)
平成20年平成20年7月22日
Chronicle of a Death Foretold (Gabriel Garcia Marquez)☀田舎町に現れたよそ者バヤルドと村の娘アンヘラの婚礼の翌日、アンヘラの双子の兄弟によって青年サンティアゴが殺される。その殺人は予告されていたにも関わらず、そして村人のほとんどがそれを知っていたにも関わらず、そして双子達は止めて欲しかったようにさえ見えるのに、なぜ殺人は予告どおりおきてしまうのか――物語は、この事件を振り返っていく謎解きの形で始まる。“On the day they were going to kill him”と始まる、2時間もかからずに読めるような短い話である。一人の命の喪失の見込みに対して、村の人々は、関心を示し、同時に無関心ともいえる。それこそが、基本的に善意の心を持っているはずの多くの他者からなる共同体そのものの不気味さなのかも。本を読んで、特定の人物に対して感情が動くというよりは、ストーリーの展開にただ引き込まれて、読み終えるまでは本を置くことができないことは確か。最後まで、殺人にまつわる真実らしきものを少しずつ知り、同時に、サンティアゴの死の必然性さえ知らずに終える読者としては、作者の巧さをともかく味わったというところだろうか。
本に載っている中で、一番納得したのは、表紙にあるものだった。
“Exquisitely harrowing…very strange and brilliantly conceived…A sort of metaphysical murder mystery.” (The New York Times Book Review)
続けて、この著名な作家の本を2冊読んだ。巧い書き手なのだと思う。この2冊を読む限り、結局、引き裂かれた長い月日の後、ついにお互いを理解し合い結ばれるような愛の形を、この作者は究極の愛と感じているのかもと思う。とても疲れるだろうな。体力のある超人だけが耐えられそう。若い時の燃えるような恋に、お互いが側にいることによってだけ満たされるような優しい時間を積み重ねていく、そんな長い月日の静かな努力の後にだけ得る愛に、ずっとずっとロマンスを感じる、ごく平凡な人間としての私がいる。
平成20年7月23日~24日
Shopaholic &Baby (Sophie Kinsella) ☀
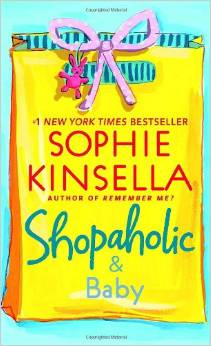
ショッピング中毒の愛すべき主人公ベッキーのヒットシリーズ5作目である。タイトルが示す通り、初めての子どもの出産を控えた彼女が、これまた想像できるとおり、前と変わることなく、勘違いと失敗と騒動を引き起こすことになる。すべてが想像できる通りに進むのは、読む前からわかっていたし、そのことに不平もないけれど、ここまでお決まりのコメディーのように想像通りに展開すると、さすがに、本の途中で、他の考えごとをしたりしても全く問題ないほどであった。一応結末までどうなるか確かめたけれど、これまだ想像通りの展開で終わった。これもそうあるべきで不満はないけれど、さすがに本の中に入ってベッキーの勘違いを思わず一緒に笑って入るほどには本に入ってはいけなかった。なんとなく抜かして読んでもいいかも状態。ただ、このシリーズ自体は、1年半位前に読んで、最初は、このベッキーにはまったという経緯がある。1作目の、主人公がショッピング中毒(想像を超える!)のために引き起こす騒動は新鮮で、そのために陥るベッキーの悲劇的な泥沼状態(思わず噴出す!!)を楽しんで読んだばかりでなく、恋人となるルーク(素敵です!!!)がかなりお気に入り状態で、何ページか、特定の好きな箇所を読み直した位。直後に、彼女のニューヨーク行きの2作目と、ルークと結ばれる3作目もすぐ買って読んだ。2作目はそれなりに物語に入って読んだけれど、3作目は、「ベッキー、相変わらずでいいのだけど、さすがに、もうちょっと」状態。結局、4作目は買うことはなかった。時間がたって、また読んみたくなった。軽いのりで楽しむジャンルの小説としては、1作目はお勧めである。おそらくそれを好きになる人は私のように2作目を必ず読んでしまうだろう。そこからは、好きだった人でも意見が分かれるのではと思う。
だから、彼女のシリーズ全体にあてた書評で、私が今納得するのは、これ。
“A have-your-cake-and-eat-it romp, done with brio and not a syllable of moralizing…Kinsella has a light touch and puckish humor.” (Kikus Review)
平成20年7月25日~31日
Eat Pray Love(Elizabeth Gilbert)☀
34歳、夫、仕事、家あり――全てが満たされているはずのニューヨーク在住の著者エリザベスが、離婚、恋人との別れを経て、いわゆる自分探しの長い旅をするエッセイ風物語。自分探しのテーマも、題名通り、イタリアでは食、インドでは祈り、バリ島では恋、と旅する場所で変化していく。文章を書くのが極めて上手な人の異文化の旅紀行プラス才能あふれるやり手の女性の自己探求物語という感じ。雑誌の最後についているエッセイを軽く読んでいる感じで、最後まで、エリザベスの34歳での自分探しの長旅自体には共感という感情は全く起きなかった。ただ、これだけの才能がある女性であれば、ある日自分は何を求めているのか、はたと人生の転機に深く考えてしまうことはあるのかも、ということは理解できるし、これを異文化への旅で見つけようと試み、実行しきるエネルギー・財力には感嘆するし、ユーモアや巧い喩えが上手に盛り込まれた文章は楽しめた。例えば、インドで出会ったアメリカ人―“You gotta stop wearing your wishbone where your backbone oughtta be.”(p.150)、半ば義務的に何かをする様――“I’m going to Grandma’s house, and I’m bringing an apple…I’m going to Grandma’s house and I’m bringing an apple…”(p.246)、少女の無邪気さ――“She says, ‘Mommy, if somebody brings me a sick tiger, do I bandage its teeth first, so it doesn’t bite me? If a snake gets sick and needs medicine, where is the opening?’…”(p.258)、自分の状況――“I feel somewhat like Dorothy in the poppy fields of Oz. Be careful! Don’t fall asleep in this narcotic meadow, or you could doze away the rest of your life here!” という具合だから。“monkey mind” (p.132)――この定義には笑えた。私にも多いにあるから、私こそ修行の必要ありかも。 “People follow different paths, straight or crooked, according to their temperament, depending on which they consider best, or most appropriate—and all reach You, just as rivers enter the ocean.”(p.206)――昔、アメリカ留学最初の年に出会ったタイ人のクラスメートが、キリスト教を盛んに褒め称えるアメリカ人のクラスメートを皮肉って、キリスト教は寛容ではないと批判し、仏教について同じようなことを説明していたなって思い出した。キリスト教を一番と信じながらも、東洋で悟りを開きたがる・開けると納得する・西洋人――いつの時代も滑稽なほど変わらない。会話をしているような読書。
だから、下にあるような書評には納得。
“Gilbert’s memoir reads like the journal of your most insightful, funny friend as she describes encounters with healers, ex-junkies and (yes!) kind handsome men.” (Glamour)
平成20年8月3日~4日
The Inheritance of Loss (Kiran Desai)☀☀☀☀
ヒマラヤの麓の街カリンボンに住むインド人の元エリート判事、彼の孫娘、彼女のネパール系の数学の家庭教師、判事の料理人、そしてニューヨークで不法移民として生きる料理人の息子、そして、その両方の街の人々――社会階級も年令も立場も異なる者たちが、複雑な文化の交差する2つの街で、西洋と自文化のどちらかに捉われすぎ、時には、自分のアイデンティティを見失い、自分が何を求めているかも、誰を愛しているのかも不確かになって生きている。“the luckiest boy in the whole wide world”(p205)で、生きることのできる場所はどこなのかを皆求めているのにである。限りなく異なるはずの二つの街がまるで同じように感じられたのは、作者が文化と人間との関係における永遠のテーマを、物語の中で両方の街を巧みに行き来しながら描いているから、そして、一度読み出すと本を置くのは難しいのは、時に詩とも感じられるような文に引き込まれたから。文化に捉われないで生きるのは不可能だったし、今からも私達は、行き過ぎた自文化主義や西洋(または東洋)文化への過大な称賛や憧憬に捉われる。個人の自由な生き方をむしろ拘束する鎖にしかならないにも関わらず。最後は、「生きていることへの希望」と取っていいんですよね。一気に胸が熱くなった、この最後は。2007年のマン・ブッカー賞を取っている本で、賞賛の書評が本にも沢山載っていたけれど、一番納得したのは、
“…from Harlem to Himalayas, she captures the terror and exhilaration of being alive in the world.”(Gary Shteyngart, author of Absurdistan)
読み終わった日に、中国のウイグル自治区でのテロ行為と、あの『収容所列島』のソルジェーニーツィン氏の死去のニュース。私達は、永遠に喪失への絶望と希望を繰り返すしかないのだろうか。
平成2008年8月5日~8日
Snow (Orphan Pamuk)☀☀ ☀
雪に覆われたトルコの街カルスに、12年目に国外に亡命したKarが足を踏み入れる。「なぜスカーフで頭を覆った少女達は自殺をするのか」を取材するのだと言いながら。イスラム主義者、クルド人民族主義者の思惑がからみあう選挙目前の街にクーデターが起こった時、Karの人生もまた無関係ではいられない。文化や政治から無関係で幸福に生きることは出来るのか、物語はその問いを「幸福に生きたい」といつも願って止まない私達に問いかけているように思えた。“Were you happy when you were a child?” (p.285)、 “How do you define happiness?”(p.353)-――Karもまた自分の答え通りに幸福を選択することは出来ないのだ。“Happiness is finding another world to live in, a world where you can forget all this poverty and tyranny. Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the whole world.”(p.353)。
普段の日は、眠りにつく前の時間が読書の時間。やっと読めると寝床で本の続きを読み始めることが多い。でもこの本は200頁あたりまでは、さほど待ちきれないという気分もなかった。なのに、4日目は、どうしても最後まで読みたくて、夜明け前に起きだして最後まで読み終えるしかなかった。朝でもすでに、真夏の暑さを感じる陽射しなのに、本を読み終わった時は、この本の中で降り続いていた雪が体に感じられるような気分だった。この著名なノーベル賞作家の本は2度目。My name is Red は、去年20頁位読んで、止めてしまったまま。もう一回読んでみようという気持ちになった。
“How much can we ever know about love and pain in another’s heart? How much can we hope to understand those who have suffered deeper anguish, greater deprivation and more crushing disappointments than we ourselves have known? ….in this novel [that is] as much about love as it is about politics.(The Observer, London)
夜TVに映し出された北京でのオリンピック開会式。トルコの選手の入場を、今までとは違った気持ちで見ている自分に気がついた。オリンピック、平和の祭典。その翌日には、地図上ではそのトルコとも国境を接しているグルジアでの戦闘が伝えられた。政治と無関係に幸福を求めることは不可能なのだ。答えは、悲しいほど明瞭。
平成20年8月21日~22
Last Orders (Graham Swift)☁
ロンドンのパブ、一人男の死後、彼の最後の願いをかなえるためにゆかりのある人々が集まる。それを実行する過程で、過去・現在、そして未来図が、登場人物の視座で語られていく。語り手が変わり、その語り自体も、時には雄弁、時にはわずか、それらが積み重なって明らかになるものーーといった感じでサスペンス風でもある。ただ、私は全く入り込めなかった。登場人物の誰もが、作者の計算したように上手に長さも調整して効果的に語っているのだなあって物語の外にいたまま思い、誰の思いにも行動にも感情移入は出来なかった。途中で止めようかとまで思ったけれど、ブッカー賞を取っている本で、もしかしたらと最後まで読んでみたけれど、結局最後までそう。物語って読者が主観的にとるものだから仕方がないよね。書評の一つは、下のような内容だった。ただ、“Endearing…A moving” までは、私にはなかっただけ。
“Endearing…A moving portrait of one man, one set of friends, one generation a they pass from the toil of the human city to the oblivion of sea of soil.” (Philadelphia Inquirer)
平成20年8月23日
The Last Lecture (Randy Pausch)☀☀ ☀
46歳の大学教授が、仕事も私生活も充実した、そうしたある日、末期の癌でもう来年の同じ日を迎えることができないとわかったら。彼のしたことは、多くの同じ運命に置かれた人々と同じ――残された月日に自分が出来ること、したいことを考え、実行する、そして何よりも愛する者達の幸せを確保してやる。そして、もう一つ、彼の「最後の講義」である。全米で多くの人にネット視聴され感動を引き起こしたという。私も一部はすでにCNNで視聴していたが、この本は、その「最後の講義」とそこに至るまでの思いを織り交ぜた内容で、彼の遺筆となったものである。10個もの “elephants” という苛酷な状況においても、大学では学生を引き付ける教え手であったであろうことを十分伺わせる語りを存分に見せているのだ。“After the lecture, she walked up and selected the giant elephant. I love the symbolism of that. She got the elephant in the room.”(p.50)自分の死を勇敢に受け止め、愛する人達に何を残すかを考えることのできた人達の話を聞いたり、読んだりしたことは今までもある。でも、いつも思うことは同じみたい。誰かを愛するから幸せになれる。誰かを心配するから憂いも残る。でも、自分以外の人と関係を築いた者だけが得られる豊かな思いは、自分の生がたとえ願ったよりも短いものであったとしても、それが意味があったと思う唯一の理由でもあるのだって。彼のような勇気はないから、そしてそれだからこそ、私も愛する人達を大切にして、丁寧に、丁寧に毎日を生きよう。
私も深く共感した箇所の一つ。私も子どもにはそう願っている。
“I want you to become what you want to become.・・・His life will be his life. I would just urge my kids to find their way with enthusiasm and passion. ”(p.198)
平成20年8月28
Lottery (Patricia Wood)☁
IQ76の青年Perryが、題名通り、lotteryで巨額のお金を得た時、彼に起こること、彼が選ぶことを自ら語る物語。育ててくれた祖母は彼に何を教えたのか、彼は何を人生で一番大事なこととして理解したのかを見ていく時、IQ76以上ある者が、そのために人生をより“lucky” に出来るわけではないのだとあらためて思う。物語が、低IQの主人公の宝くじ一等賞金獲得後、ということで、作者が感動させる作為が何か見え見えの展開になるのではと用心して、本に載せてあるたくさんの書評にざっと目を通してから購入した。下がその決め手となった書評二つ。
“Fear not: This novel about a mildly retarded man who wins the Washington State Lottery is no Forrest Gump retread—we much prefer this (admittedly folksy) narrator to Tom Hanks as a mentally challenged Zelig. Patricia Wood’s mentor, Paul Theroux, lent his literary wisdom to a book that managed to be heartfelt and totally not corny.” (New York)
確かに、Forrest Gumpよりは好きかも。
以下のは異議あり。
Fans of Mark Haddon’s The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and Daniel Keyes’s Flowers for Algernon would do well to pick up this captivating debut. I loved it.” (Martha O’Connor)
この2冊も読んだことがあるけれど、前者は大好きな本。後者は考えさせられた本。特に母親の行為の理由。知能では普通の人より劣っていても、心も人生の見方もずっと優れているということを物語の主人公の語りで示すような小説では、作家の視座が本当にはどこにあるのか(あるように見えるのか)で、読み手の気持ちは大きく左右される。だから、この本は私には好きという点でも、考えさせられるという点でも、これらの2冊より、ランクは下に。彼と祖母以外の家族があまりに一面的。
旅の一日、その土地の本屋を覗いてみて、購入したペーバーバックを片手にのんびり過ごすーーなんてイメージには憧れるけれど、せっかくだからやっぱり出かけようとなって、結局無理よね、と今まで思っていた。ついに今日実践。旅の途中の今日、ホテルの中庭でのんびり読んで過ごした。初めてのことをした充実感。この本屋の、いわゆる棚に並べられたものとは別に、シンプルなキャッチフレーズのもとに分けて置かれたお勧めペーバーバックのコーナー(日本人作家の英訳本もいくつか)、読んでみたいと思わせるものばかり。いい感じの本屋だった。
平成20年9月3日~4日
Three Cups of Tea (Greg Morernson & David Oliver Relin)☀☀
1990年代の前半、登山家としてパキスタンの北西部を訪れたアメリカ人Mortensonが、その後、そこに学校を建てていく経緯が、Relinというライターによって詳細に記されている。2001年9.11.以後のアフガニスタンでの活動も含んでいて、世界の関心がそこに向けられる前と後のアメリカ人やメディアの反応の違いも描かれて興味深かった。Mortensonのようなことを何人が出来るのかと思えば、正直、無謀すぎると感じた彼の初期の行動についても、出来ない人間の自分がコメントは出来るような立場ではないようにも感じる。だから、いいなと思ったことだけを記しておく。詳細に、時にはおきた問題や批判も含めて全て記してあり、活動への過度の美化が見えないこと、「教育」こそが解決策だという彼の一貫した姿勢が示されていること、そして、何よりも、彼が「教育」で助けようとした「無知」の人々も、文化の制約の中で多くのことを考えていることがきちんと示されていること、である。“We must turn these stones into school” (p.330) “We” の側の自発的な意志を共有できないような援助は成功しない。一つの爆弾を落とす時間はほんのわずか。同じようにそこから得るものも何もない。“three cups of tea” までを理解するまでに、3杯目を本当に口にするまで、そこで人々と本当に関わりあって一歩一歩進んでいったことは大変な努力だと思う。彼の生み出したものには希望がある。だから、
“Monterson’s book has much to say about the American failures in Afghnistan.” (The New York Review of Books)
ほんの数日前にアフガニスタンでボランティアをしていた日本人青年の死が報道されたばかり。3杯目を口にした彼の行動はそこに希望を残したとは信じるけれど、それでもあまりにも早すぎる死。
平成20年9月5日~7日
Austerlitz (W.G. Sebald)☀
1939年の夏、英国ロンドンに辿り着いた小さな子ども、今は建築物の研究家が、長い月日の後で、その名Austerlitzを頼りに、自分の過去を辿っていく。過去から切り離された者は、自分の出発場所を、自分が残してきた人々を、そして、それにいたった理由を理解しえるのだろうか。謎解きでありながら、その謎の答え自体よりも、そうした謎のあるまま人が生きなければならないこと、その答えを求める(または、謎を求めるしかないというべきか)ということは、どういうことなのか、考えさせられた。与えられた社会状況で選択肢は限られてくる。第二次世界大戦が人々の暮らしに影を落とす中では、普通の人々の選択肢は本当に限られたものとなる。そうした人々の過去の想いも、彼が巡っていくヨーロッパの建築物に反映されているのであり、だからこそ彼は引き付けられるのだろう。この名前だけ聞いたことがある作家の英語訳の本を読むのは初めて。読んでいる間、時には「え、またこれについて長く書かれるの?」と、しかも、その意味に?が3つ位飛ぶことも。ただ、読み終えた時には、自分の英語の能力や文学的感性で理解し味わえる範囲を超えて、実は、もっと深いところにこの物語の語りの良さがあるのだろう、と色々な意味で自分の力の至らなさの方に思いがいった。
“He evoke at once the minutiae and the vastness of individual existence, the inconsolable sorrow of history and the scientillating beauty of the moment and its ground of memory.”( W.S.Merwin)
平成20年9月8日~9日
Half of a Yellow Sun (Chimamanda Ngozi Adichie)☀☀☀
1960年前半のナイジェリアを始まりに、67年から70年のナイジェリア・ビアフラ間の戦争の終わりまでの、イボ族の女性OlannaとOkannaの双子の姉Kainene、そして、彼女らの人生に関わってくる人々、Odenigbo、Ugwu、Richardを中心に物語は展開する。いわゆる普通の暮らしの中では、微妙な感情のすれ違いでさえ、愛情を持っている者達を簡単にそして永遠に分断する。しかし、民族間の迫害と飢餓状況の中で、人間が本当に大切とするものが問われる時、人々はそれまでは秘められていた自分の内面の強さや弱さを見せながら、同時に、愛する者達のそれらを見つめながら、あらためて選択するしかない。特に納得したのはOlannaの選択。愛する人の弱さを受け入れ、赦す力こそ、人間らしくあるために必要なのだろう。“There are some things that are so unforgivable that they make other things easily forgivable.” (p.347) これはKaineneが言った言葉。彼女もまた納得のいく選択したのだ。少女時代、「ビアフラの悲劇」が家で話されていたのを覚えている。写真も見た。相変わらず、“unforgivable”とするべき出来事が世界で起きているのも、 “The World Was Silent When We Died.” なのも同じ。だから、ともかく語られる続けることーーそれがまさに必要なのだ。1977年生まれの、この若いナジェリアの女性作家が、一度読み始めたら本を置くのは難しい、この物語でそれを出来るのは素晴らしいことだと思った。だから、
“I look with awe and envy at this young woman from Africa who is recording the history of her country. She is fortunate—and we, her readers, are even luckier.” (Edmund White)
平成20年9月10日~12日
The Brief Wonderous Life of Oscar Wao (Junot Diaz)☀☀☀☀☀
ドミニカからの移民である母親と姉とニュージャージーに暮らすOscarという少年をめぐる話である。空想科学小説、日本の漫画、コンピューターゲームの毎日を過ごす、いわゆる”nerd” の体重過多の少年の夢は、作家になること、そして、愛を得ること。最初は、少年の日常に、彼の悲しき努力に微笑んでいただけの私なのに、気がついたら、少年にも、彼の姉にも、恋人にも、彼の母親にも、そして母親の両親にも、ドミニカの歴史にも気持ちがぐっと入り込んでしまった。人は、国や文化から離れて、自分の夢をかなえることは出来ない、同時に、自分らしくあると信じることから離れて、自己実現も無理。結局、夢がかなったなんで、誰が決めるのだろう。自分だけが知っていればいいし、人生はそれでいいんだよね。本当に不思議な読後感で、涙が目にたまった。読み終えてから、あまり考えずにいた本の題名を見直して、「そうよね。だからよかったんだよね。」とつぶやいた。“How many times I thought this is never going to happen to me.”(p.49 )”と思っていたのだから。それに、 “fuku” は、文化そのもの。私にも、誰にも、ある。それをどう生きたいのか、受け止めたいのか、自分だけがわかること。
絶賛の言葉の中で、読み終えた直後の私の思いそのものだったのは、これ。
“Completely engrossing…Diaz makes you care so much about these characters that once you’re done reading this novel, you’ll miss them.” (Newport News Daily Press)
丁度、12日の夜に、コンサートでモーツアルトを聞いた。ピアノ協奏曲23番イ短調の第2楽章に、涙がじわっと出た。なんか、モーツアルトの人生には、“fuku” がはっきり見えすぎてつらい。でも、彼には、The Brief Wonderous Lifeだったはず。翌日は、その楽章を何度も何度もリピートして聞いて過ごした私のような人間が、それ以上に、毎日のように彼の音楽に触れていたい人々が世界中に沢山いることも、ただ彼にはおまけのようなもの、彼にとってはね。自分の内からあふれてくる音楽に、“The beauty! The beauty!” を味わったよね。何度も、何度も。そう信じたい。
平成20日9月13日~14日
The Innocent Man (John Grisham)☀
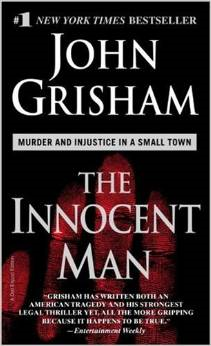
1982年、オクラホマの田舎町で起きた殺人事件。冤罪で死刑判決を受けた二人の男性。そのうちの一人、Ron Williamsonは、14年にわたる刑務所生活を、死刑執行におびえながらおくる。かつて、花形の野球選手として高校卒業と同時にプロベースボールチームにスカウトされ、街のヒーローとして街を出ていったはずの彼が、冤罪にいたるまでの転落、刑務所でさらに病んでいく身体と精神、その後のさほど長くはなかった刑務所の外での生活、それらを、作家がインタビューと記録を積み重ねて書き記したものである。詳細すぎるほどに、一人の人生が描かれたノンフィクションは、その描かれた人間の人生によって、本の印象も決まる。作家は、彼の人生を描き切り、読者の私は、彼の人生が人間の一生として悲しすぎるために、重い気持ちで本を終えた。これがベストセラーになった理由は、無実の者が冤罪をきせられていくサスペンスさながらの展開にあったのだとは思う。でも私は、10代で得た栄光を引きずったまま、その時の夢に破れ、それからは生きる意味を何一つ見出せなかった若者の悲しさを、彼を愛しながらもそれについてだけは助けてやれなかった家族の思いを、日本で今年起こった事件を思いながら、複雑な気持ちで読んだ。夢破れた後、また自分の夢を見出すことだけは、本人しか出来ないのが、悲しい。今まさに夢一杯の19歳の息子がいる今の私には、それが読み終えたときの思いだった。
Ronの死の直前の言葉。
“What was even the reason for my birth? I almost cursed my mother and dad—it was so bad—for putting me on this earth. If I had it all to do over again, I wouldn’t be born.”
平成20年9月16日~19日
Penfume (Patrick Suskind)☁
18世紀パリ、スラム街で生まれてすぐ捨てられたGrenouilleは、体に全く匂いがない、そして同時に、全ての匂いを認知・識別し、再生できる能力を持つ人間である。そんな彼が調香師として修行した後、何を望み、何を得るのか。物語は、匂いがないために悪魔だとして乳を与えることを拒否する女性と、彼女を説得しようとする僧との会話から始まる。調香師となるあたりまでは、「わあ、人間とは・・・と考えてしまうような結末かも」と期待し、物語の中ごろを読む頃には、匂いなるものを意図的に嗅ごうとしている自分にも気づいた。恐るべき影響力。家族が薄気味悪がるのに、フンフンと体に鼻を近づけて匂いをかいでみるほど、匂いフェチ寸前。でも、後半の展開は、あまりにホラー的。嫌になった。最後のちょっと手前で一回展開にはびっくりして、もう一度かすかに期待しかけたけれど、結末は、う~ん。ホント、後半の展開はなんだかね。彼の生き方を、全く180度違う方にもっていく方が、人間についてまで考えてしまったのに、少なくとも私は。これでは、匂いがない赤子だから乳を与えたくないと偏見そのものの女性が一番判断が正しかったってことになるよね。普通の人々と異なる身体を持った生のために、最初から最後まで、彼はこの世に他者として孤立して存在し続け、限りなく、限りなく破壊的な願望しか他者に対して持つことはない、ということ??欠損していたゆえに、最後まで行動は異常で、そして猟奇的?? なんだかな。こうした設定に読者が納得すると作家が思っているなら、読者に対して失礼、人間の生の尊厳に対しても失礼。
“Mesmerizing from first page to last…. a highly sophisticated horror tale.” (The Plain Dealer) の“horror tale” にだけ納得。ただ、この本は確かに一旦読み始めたら、ともかく途中での思いとは別に、結末を知るまでは読むのだろうとは思います。
平成20年9月23日
Doctor Dolittle Stories (Hugh Lofting)☀☀☀
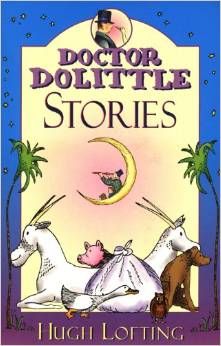
有名なドリトル先生のシリーズから少しずつ取って一冊にしたもの。初めて英語の原作で読んだけれど、子ども時代にアフリカ行きと航海だけを読んだ私には、昔好きだった場面との遭遇(特に、アヒルのDab-Dabが階段を降りてくるところ、判事の犬のしゃべりすぎ、好き!!)だけでなく、初めて読むエピソードもあって楽しめた。子ども時代にも好きな話ではあったが、大人になってあらためて読んでみると、動物語を話す時も、人間の言葉を話す時も、ホント同じまま、一貫した穏やかな言動がいい。心が暖まる感じ。Tommyがドリトル先生に初めて会った、あの雨の中での衝突の時の会話である。“ ‘I’m very sorry,’ I said. ‘I had my head down and I didn’t see you coming.’ To my great surprise, instead of getting angry at being knocked down , the little man began to laugh. ‘You know this reminds me,’ he said, ‘ of a time once when I was in India. ・・・・I didn’t hurt you, did I?' 'No,' I said. ‘I’m all right.' 'It was just as much my fault as it was yours, you know,’ said the little man. ‘I had my head down , too.” (p.135) ドリトル先生は、動物の言葉を話すからではなく、まさにその人間性のために、動物を、そしてもちろん人間も本当の意味で理解できるのだ。子どもの時には全く意識して思わなかったことを考えるから、なつかしい児童書を読んでみるのはいいかも。今回は、豚のGub-Gubが、ドリトル先生の物語でどう扱われているのかを知りたい理由があって、ただチェックのために見ようとしたのに、結局読み終わるまで止める気にはなれなかった。ちなみに、Gub-Gubは、ここでも、よくある豚の役割そのもの、さんざんな扱いである。救急車に乗せられて、大騒ぎをおこして、’We shouldn’t have started with that ridiculous pig. He always puts hoodoo on everything.” (p.363) と言われてしまう。でも、Gub-Gubは、乗るのは嫌がっていたんですけどね、と一応弁護したいな。ドリトル先生の家の動物は、みな憎めない。
本の裏表紙の言葉である。
“Any child who is not given the opportunity to make the acquaintance of Doctor Dolittle will miss out on something important.” (Jane Goodall)
平成20年9月24日~25日
The Diving Bell and The Butterfly(Jean-Dominique Bauby)☀☀
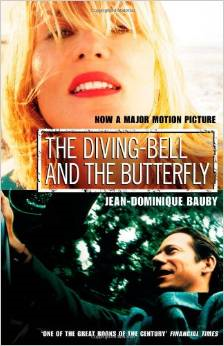
“Elle”の編集長であったBaubyは、1995年、43歳の時に脳溢血の発作の後、左目の機能を残し、食べることも、息をすることも、自分の力では出来ない、全身麻痺の状態でベッドに横たわることになる。まさに、”like a giant invisible diving bell holds my whole body prisoner” (p.3)。才能にあふれ、仕事も人生も楽しんでいた一人の男性が、そのベッドの上で、何を思い、何を考え、何を語りたがったのか。これは、彼が唯一残された左目のまばたきによって、アルファベットを指し示しながら、書き取ってもらった本の英訳である。かつて映画化で話題になった時、読んでみようとは思っていたけれど、悲しい気持ちになるのではと、延ばし延ばしになっていた。今、読んでみて思うのは、読んでよかったということ。こんなにも機知に富み、才能を持ち、人生を楽しむことができる人に起きたことは残酷。でも、どんな残酷な運命でも、彼の精神までは破壊できない。人を見つめ、人生を見つめ、自分自身を見つめる、彼の人間らしさを奪うことは出来ない。“my mind takes flight like a butterfly” (p.5) 彼の「蝶」は、全てを潜水服におおわれた重い身体の中でも飛ぶのだ。自分だったらと仮定するのは不可能。彼のようになれないのはわかっているから。それでも、彼と同じように、人間である自分だから、大事に、その人間らしさを使って生きていこう、自分のその幸運を、無駄なつまらない迷いに使わないで、いつも優しい思いであふれるようにして、大事な人達と生きていかなくては、と思った。“But I see in the clothing a symbol of continuing life. And proof that I still want to be myself. If I must drool, I may as well drool on cashmere.”(p.17)
本の裏表紙:
“A book of surpassing beauty, a testament to the freedom and vitality and delight of the human mind.” (Oliver Sacks)
本を読み終えた夜の訃報。自分でも遺骨を拾うのは、3回目となった。最初、80代半ばだった祖母とは48歳の年の差、70代だった母とは29歳の差、そして今60代で逝った叔母とは14歳。自分との年の差が小さくなる上に、愛した人達はだんだん逝き急いでいるようで、悲しい。最後のお別れの時に伝言を託した。ここで沢山の、沢山の蝶に出会えるよう、うんと頑張ってから、会うね、って。
平成20年10月5日
Stargirl (Jerry Spinelli)☀☀☀☀
アリゾナの砂漠の街の高校に、一人の少女が入ってくる。“Star girl”と自らを名乗る少女は、名前だけではなく、全てのことにおいて、周りの高校生とは「違う」。カフェテリアでは、その日が誕生日の者のために大声で歌い、ペットのラットを持参し、クラスメート全員の机の上にカードを置く。いつのまにか、一番目立つ人気者のようになった彼女は、それからも「違う」ままで居続けるのか。居続けることが出来るのか。この物語は、その少女を見つめる少年Leoの語りとなっている。ネット書店で、多くの若い人達がこれを好きと書いているのを見て、興味を持って購入。若い人向けなんだろうね・・・とは終始思いながらも、最後まで引き付けられて読んでしまった。“If you weren’t stuck in a homeschool all your life, you’d understand. You can’t just wake up in the morning and say you don’t care what the rest of the world thinks.”というLeoに、 “But how do you keep track o f the rest of the world? Sometimes I can hardly keep track of myself.”というStargirl (p.136)。その “what the rest of the world thinks” が、自分の行動の一番の基準になるような人生はつまらないと思っていても、実際には、その存在を気にして生きてきた臆病で平凡な私にいえることは、2つ――Stargirlにエール送ってあげたい。そして、彼女の行動を気にしなければ自分に何の影響もないのに、イライラし続ける輩にだけは絶対なりたくない、ということ。他者の異質性に、その自由さに、もっともらしい理由でケチをつけるような人間が、さらには排除までしようとする人間が、一番自分自身に満たされていない、不幸な、つまんない人間だもの。若い人達がこの本を好きな理由が十分わかる気がする。
“Spinelli has produced a poetic allegorical tale about the magnificence and rarity of true nonconformity.” (The New York Times)
本の表紙――ここ最近で一番気に入った!!!
平成20年10月13日
The Nanny Diaries (Emma McLaughlin and Nicola Kraus)☀☀
ニューヨークの富裕な夫婦の4歳の子どものNannyとなった21歳の大学生。彼女の9ヶ月に渡る多忙な毎日を描いた小説である。仕事と、時間があれば女性に関心が向けられているX氏と、子どもの習い事と子どもの通う学校への、多分に虚栄心からくる関心と、形式的な子どもとの時間以外には、子どもと時間も感情も共有しないX夫人、という悪条件に、そして(それゆえに)自分のための使いばかりを要求するX夫人に、彼女は振り回される。さらには、X夫妻の結婚生活への波乱の要素まで加わる。なんかストーリーが予想できちゃうのよね、と言いながら、前に買って読まないままでおいていたのを思い出して、休日の午後読み始めた。でも予想とはかなり違っていたかも。軽妙なやり取りや表現を楽しみ、X夫妻にあきれ、彼等にすっかり振り回されるNannyにイライラもし、でも最後にはほろっとした。子どもを持つということは、眠たい目を必死であけて本を読んでやる夜、体がつらい日でも子どもに「おはよう」と元気に声をかける朝、そうした日々の連続に成り立つもの。子どもを生むことで親になれるのではなくて、親であるのだからがんばろう、と共有する時間を大切にして生きる毎日の営みが親にしてくれるのだ。 “He’s such a amazing little person—he’s funny and smart—a joy to be with”(p367)――結局、子どもはみなそうなのだ。だから、至らぬことの多い私だって踏ん張れたのだと思った。Nannyが、最後から2番目に残したメッセージにも、かなりスッキリはした。“I’ve been raising your son!”(p.364) なんて叫ばせるような親ではホント駄目だよね!!!でも、彼女が最後の最後に残したX夫妻へのメッセージが好き。彼女の人間らしさが好き。最後のウィッシュも叶えられると思いたい。だから納得する書評は、
“Although The Nanny Diaries is screamingly funny, it’s also painfully sad A very effective combination” (USA Today)
“Nanny is cynical and wry but also compassionate!”(Newsday)
この連休の最初の土曜日は前日の夜から始まった顔面までも痛むような激しい頭痛に一日中苦しんだ。仕事上の行事と私的なことで、午前、午後と続けて2つ外出。ともかく家に夜帰るまで何とか持ちこたえられますようにとずっと祈るような気持ち。幸い、午後は、優しい幸せのオーラが一杯の卒業生の結婚式(彼女も、最後に、親と共有した時間を一番感謝していた!!)だったから、その時間だけは、頭痛はあっても、私までまさに幸せな気分一杯。ただ帰ると、ほとんど倒れるように横になったけど。同じような体調の悪い日、子どもが小さい時には、家でもずっと元気な振りをしていた。そんな強いスーパーウーマンの自分を一時でも経験させてくれた子どもに、今は、感謝したいかも。最近は、かなりの、それもかなりのパワーダウンです。。
平成20年10月19日
Love, Stargirl (Jerry Spinelli)☀☀☀☀
Stargirlの続編。アリゾナの高校から突然消えた彼女の、翌年の1月1日からの一年間の「手紙」である。出されることのないLeoへの「手紙」。読者には、彼女の日記でもある。ヤングアダルト向けの本というのは、前作と同様わかっているけれど、私は十分(十分以上)引き込まれた。そもそも、前作を読んで購入。前日に届いたのを、次の日が日曜日でラッキーと思いながら、午前中で読まないではいられなかったのだから。前作を読んだ時は、彼女らしい行動を自分は素直に認めることの出来る人間でいたいと思ったけれど、同時に、彼女のような子が高校生の時に自分の側に友人としていたら、本当はちょっと引いてしまうのかもという思いもあった。彼女の語りとなる今回は、彼女がもっともっと理解できた。彼女は、自分らしく生きたい全ての人の思いを反映しているのだ。前作では最後に、後日談のようなLeoのその後に実は泣けたのだけれど、続編でも、最後のところで胸が急にツーン状態。ここ、“Will we ever meet again?”(p314)への返答。“But I no longer hope to be found …..Let’s just be fabulously where we are and who we are.”(p316) 彼女がもっともっと好きになった。自分が好きになる本には、自分へのマジックがある。名作、古典、誰向けなんて全く関係ないわけで、結局、ある特定の本が意味を持つかどうかは、その当人の読者だけがわかること。表紙がまたまた気に入ってしまったこの本を置きながら、そのマジックのもと、私でも見つけてもらったから大丈夫だよって、まさに年甲斐もなく、そして図々しく、16歳のStargirlに自分を重ねてつぶやいた。
“Like a whimsical heroine, this is a story which, once read, is not easily forgotten.”(Time Out)
平成20年10月25日
The Road (Cormac McCarthy)☀☀☀☀
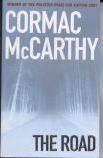
南を目指して、父と息子が旅をしている。彼等が恐れなければならないのは、「悪い人間」――彼等を殺し、何のためらいもなく喰らうであろう、人間であってそうではない者達。しかし、同じ怯えている側の人間さえも、また彼等のわずかな持ち物を盗んでいくかもしれないのだ。そうした者達、飢え、凍えるような寒さ、灰色の大地、暗闇の恐怖と闘い、人間らしくあるために、彼等は他の彼等のような人々の地を求めて、廃墟と化した街を通り抜け、住人のいなくなった家で、食料をあさり、体を温める。この状況では、父と子は共に生き、共に死ぬしかない。必要な時には使えるように、父はピストルを手放すことはない。守ってくれる父が逝く時は、子も逝くしかない。そして、子の生命が尽きる時には、また父も一人で彼を行かす気はない。その覚悟を示す物語の最初の二人の会話を読んだ時から、すでに何とも説明のつかない気持ちがこみ上げて、うっすら涙がたまった。だからこそ、最後の最後、結末は泣けた。読み始めて、数時間後に、本を終えるまで、本を置くことは出来なかった。最後、涙目で本を終えた時には、物語というより詩を読んだような気持ち。私達の過去にもあったし、現在にもあるし、未来にもありそうな、人間性の試される極限状況での、父の最後の決断も、子の思いも、私には、人間を人間にしているもの、そのものに思える。そして、私達の人間性の希望は、まさにそこにある。だから、泣いたけれど、この物語は美しい詩。そう素直に思わせる、この作者の力にも感嘆する思い。
“The Road is about tenderness despite everything. McCarthy has unmade the world, but against all the odds, this novel holds out a thin strand of hop: for the power of language and storytelling even at the end of all things. (Financial Times)
“McCarthy’s mesmerizing novel, slim but fiercely concentrated, is a masterpiece that will soon be considered a classic. Its weight and power are unanswerable. MCcarthy knows no way of writing apart from the beautiful.” (Herald)
今まで一度も読んでいなかった、この作家の作品をこれから読んでみることにした。それはそれで幸せな気分。
平成20年10月30日~11月2日
All the Pretty Horses (Cormac McCarthy)☀☀
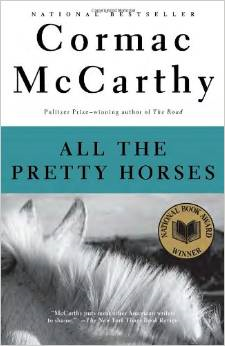
16歳、John Gradyは、17歳の友と、馬に乗り、テキサスからメキシコへ国境を越えて旅をする。意図せぬ仲間が加わり、思いがけない出来事が重なり、彼の冒険は、次第に危険なものとなっていく。Road を読んで、自分向きではないのかもと読むことがなかったこの作家の本を4冊購入してみた。これは、そのうちの3冊――3部作の男性ロードもの――の第一作という位置づけのようである。どうしても、若いカーボーイの男性が主人公ということもあり、舞台も、牧場や荒野、出来事も、喧嘩、暴力、恋愛さえ危険、という、ストーリー的には、確かに私向きではないみたい。それでも、Gradyと家族との関係、旅立つ思い、友との会話、無鉄砲な行動に、説明のつかない涙が何回かこみ上げた。最後は最後で、どうなるのと心配もあって、ほとんど速読状態。昔、若い時に、テキサス出身の友達の家がある牧場に、冬休み休暇に滞在したことがある。あの時のかなりのカルチャーショックを思い出した。この作品を読むと、テキサスやメキシコが、まさにそうしたカルチャーショックとともに「感じられる」のである。題名だけを聞いたことがあった、この作品を読むと、やはりこの作家は上手だなと思わずにはいられない。最後まで引き込まれることは確か。
“A storyteller’s tale in the highest sense, riveting in its detail and action, profound in its lesson.”(Atlanta Journal & Constitution)
平成20年12月26日
Twilight (Sephenie Meyer)☀☀☀

17歳のBellaが転校した高校で、初日から遭遇する美しき青年Edward。彼の不可解で謎めいた行動も、彼がヴァンパイアであれば不思議でもない。全米で多くの少女達のファンを持つこの小説の最終巻である4巻の発売日が、2008年の夏で、その時の熱狂振りをCNNで見たことがある。何、人間の少女とヴァンパイアの美青年のロマンス? 本屋で偶然見かけて、まあ、最初の巻ぐらい話題として読んでみて、あまりにも白けたら途中ですぐ止めましょ、ぐらいのつもりで購入、クリスマスの翌朝、スタート。あっいう間で読んだのは、この本の英語はとても簡単なせいもあるけれど、結構はまった。ロマンスの要素が人生の一番大事なこととして生きてきた私としては、ベジタリアンヴァンパイアなんて素敵・・・と17歳のBellaの気持ちも十分理解。すぐに4巻までネットで注文。27日から静岡に行くので、年末に広島に帰ってきたらすぐ読めるようにと準備周到になったところが、私のはまり方を正直に示している。
“Twilight will have readers dying to sink their teeth into it.”(School Library Journal)