平成21年7月19日
Nocturnes (Kazuo Ishigoro)☀☀
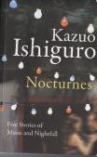
5編の短編からなる一冊。ベネチア、ロンドン、ハリウッド、と舞台も変わり、語り手も様々。共通点は、音楽と人生の黄昏。①Croonerの往年の有名シンガーと妻,
②Come Rain or Come Shineの友人夫婦,③ Malvern Hillsの旅先のミュージシャン夫婦, ④Nocturneの有名シンガーと離婚した女性,
⑤Cellistsの若きチェロリストとアメリカ人女性といった人々の人生が、語り手の音楽人生とともに浮かび上がる。どの物語も、サスペンス的な要素があって、途中では、どうなるのとハラハラもするけど(特に、②と④はね)、最後には、そんなこともきっとあるのよね、と静かに納得する感じ。同じ作者の長編 The
Remais of the Day, When we were Orphans, Never Let Me Go は以前読んでいて、特に、Never
Let Me Goでは、最後にかなり泣いたので、今回、彼の短編を始めて読んで、随分あっさりしている感じは受けた。感情移入とまではいかなかった。けれど、読んでよかったとは思う。若い日の夢、挫折、回顧、記憶、そして音楽、人生はそういうものでも彩られるしかないのだ。6月末、若い時に大好きだったシンガーの死が報道された。本当に長い間、自分が好きだったことさえも忘れていたのに、ヤフーニュースの見出しで知った瞬間は動揺した。報道のあった日は丁度金曜日で、夜は、家族とクラッシックのコンサートに行く予定だった。去年のゼミの卒業生が会場に来ていて、偶然近い席。彼女がかけてくれた言葉が、「先生、亡くなってしまって・・・」。若い時にとても好きだったと言ったことを覚えていてくれたようで、思いやり、やさしくいたわってくれるような口調だった。有難うね。家族に、「私が昔大好きだったから、言ってくれたのよ。」と説明しかけて、きょとんとしているので止めた。その昔の私を知らないものね。いつのまにか自然にクラシック音楽の方を好きと思うようになったのは、その家族となった人がそれを大好きだったから。ごく普通の人生を生きる者にも、また音楽は人生である。それにまつわる短編はできそう。そして、私の紡ぐささやかな短編は、この5編の短編よりは、ずっと単純で、それゆえに、幸せなのだろう。
平成21年7月20日
Unaccustomed Earth (Jhumpa Lahiri)☀☀☀☀☀
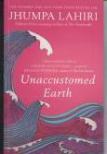
8編の短編からなる。①娘宅を訪問した父と娘、そして、お互いに言えないでいること、Unaccustomed Eath、②母親の秘めた恋と娘の気づいたこと、気づかなかったこと、Hell-Heaven、③結婚式に参加した夫婦の揺らぐ感情、A
Choice of Accommodations、④期待され過ぎる姉、期待から外れていく弟、Only Goodness、⑤ハウスメイトの恋愛への複雑な感情、Nobody’s
Business、そして、最後の3篇、⑥逝く運命を持つ母親と少年、そして、彼に部屋を使わせることになった少女、Once in a Lifetime、⑦少年の父親の再婚とクリスマス帰省、Year’s
End、⑧少年と少女の再会、Going Ashore、は時の流れを超えた一つのストーリーともなっていく。家族、移民、異なる文化、期待、失望、秘密、喪失、裏切り、孤独、葛藤、愛、選択、そうしたものが織り成す物語は、声高に叫ぶことなく、ただただ心に染み入っていく。これこそが小説。どんな家族にも、喪失と孤独は存在する。免れ得ないのだ。だから、何回も胸をつかれた。父に一緒に住むことを誘えないでいる娘、期待されようがされまいが、どちらにしても家を永遠に出る姉弟、同じ家にいながら、愛情は存在しながら、扉を隔てて、完全には心を理解することは不可能な者たち、そして、母の病とともに、仮住まいで少女の部屋を借り、そして、母亡き後の家では、自分の部屋を義理の妹達に与えるしかない青年。家の中のたった一つの自分の部屋さえ自分の居場所ではないのだという孤独感とともに、家族の笑い声を聞きながら、たった一人で座っていた、はるか昔の自分を思い出して、ちょっと泣けた。何年も前、作者の短編集Interpreter
of MaldiesとThe Namesakeも引き込まれるように読んだ。それでも、この短編集が、一番好きという気がするのは、共感するしかない過去の思いがそこにあるからかも。それでも、その痛みを受け止めて、最後まで読んで、静かな余韻とともに、本を置くことができるのは、全てが、美しく、そして、いとおしく思えるから。そんな物語。
素晴らしい書評であふれているけれど、全て納得です。
“Splendid…Reading her stories is like watching time-lapse nature videos
of different plants, each with tis own inherent growth cycle, breaking
through the soil, spreading into bloom or collapsing back to earth.”(New
York Times Book Review)
“Contains some of the best, most beautiful fiction written this decade—the
kind that will be read fifty years from now.”(New Statesman)
“Probably the most influential writer of fiction in America.” ((Jason Cowley,
Financial Times)
そうでしょう。この本なら。この作者なら。
平成21年7月26日~27日
The White Tiger (Aravind Adiga)☀☀
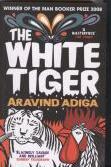
インドを訪問する中国首相にあてた手紙で、通称名“White Tiger”なる男が、彼の企業家としての成功までの半生を語り続ける。インドを舞台に、貧しいどん底の暮らしをする者達と、その者達をモノ扱いする富める者達の人生が交叉する瞬間の残酷さ、貧困ゆえの不条理な選択を背景に、主人公の語り手、彼は「いかに不可能とも思える場所にいたれたのか」の謎がわかってくる。一人の男の一代成功物語、というには、彼の「したこと」はおぞましく、しかし、同時に、彼のしたことを「おぞましい」という自分の倫理観を主張することをためらわせるような、人間らしく存在することを許されていない者の抑圧された暗い思いが、ほとんど「したこと」を思わず正当化してしまいそうになるほど、物語を読む中で迫ってくるーーそんな物語。他者による不当な扱いを、不当と叫ぶことが許されないような息苦しいような人生から抜け出す方法が彼にはあれしかなかったのか、そして、本当に
“I’ll say it was all worthwhile to know, just for a day, just for an hour,
just for a minute” (p.321)この最後の最後ーーそれに得意になって即答するには、自分の人生は幸せすぎる。だから、ここは、最後まであっという間に読ませる、この物語としての展開に感嘆したという読者としての素直な気持ちで、そのまま本を置きたい。2008年のブッカー賞を受賞しているだけあります。
こんな批評がありました。
‘Astonishingly assured and captivating…It is every bit as good as Bonfire
(of the Vanities) and it does for India what that book did for New York
City; and possibly what Charles Dickens did for Victorian Britain.’ (Tablet)
どの時代も、どの文化でも、持つ者と持たざる者の間には、お互いへの無理解があるだけ。そして、一方的に抑圧され、奪われているだけの側の心には、出口を必要とするマグマのような暗闇が底深く広がっていくだけ。
平成21年7月31日~8月1日
The Girl with the Dragon Tattoo (Stieg Larsoon)☀☀☀☀
2つの人物を中心にした物語が同時進行で語られ始める。一人は中年の有能な経済ジャーナリスト、Mikael Blomkvist。大会社の悪事を暴くはずが、反対に、根拠のない記事を書いたとして裁判で有罪となり、一時的に仕事を離れるしかなくなる。そのことがあって引き受けることになった大財閥のVanger家の35年前の殺人ミステリーの謎の再分析が、もう一人の人物を彼と遭遇させることになる。優れた分析能力の持ち主、過去に問題を多く抱えてきたらしい、ドラゴンの刺青を入れた若い女性、LIsbeth
Salanderである。2009年クライム・スリラー賞に輝くスイス作家の作品の英訳は、500頁を超える。100頁を過ぎた頃、楽しむことが出来ないほど暴力的になるのかも、と心配させたのに、300頁を過ぎるころからは、なんかロマンスの予感もあって、最終章に向けては、また暴力的、まさに猟奇的な色合い、さらに、最後は、最初の問題の記事に戻っていき、仕掛けられたトリックのハラハラ感もあり、最後の最後は、なんか複雑な展開をする危険なロマンスの前触れのような色合いで終わり。様々の種類のエンターテイメント要素を満載してあるだけでなく、主人公達二人のこれからの関係をも十分気にかけさせて終えるのだから、犯罪小説をほとんど読まない私でも、これはこのジャンルの小説として巧く書けているのに違いないと断言できそう。これは3部作の最初、次もすでに7月に英訳本が出ているようで、買って読むしかないと思わせるもの。作者はこの処女作である3部作を執筆後、50歳で、作品の大成功も知ることなく急逝したとのこと。彼の生の終焉そのものがミステリーになってしまったのが可哀想。
“What a cracking novel! I haven’t read such a stunning thriller debut for
years. The way Larsson interweaves his two stories had me in thrall from
beginning to end. Brilliantly written and totally gripping” (Minette Walters)
買っていた5冊、久しぶりに「美味しい」水遣りをもらった植木のような感じで、本を手にすると、楽しい気分で一杯のまま(これって、悲しいのだろうと、怖いのだろうと、関係なく、小説を読める瞬間が楽しいだけ!!)特に週末はノンストップ状態で読んでしまう。まあ、これで落ち着いた。これから一ヶ月は、学期中のように夜すぐ眠くなるということもなく本を手に取れるとなると、暑い夏、昼間の仕事だって楽しいのよね。
平成21年8月4~5日
The Girl Who Played with Fire (Stieg Larsoon)☀☀☀☀☀
三部作の2作目。今回も、BlomkvistとSalander、二人の物語が引き続き、離れて同時進行ですすみながら、ある時点で交差していく。今回は、Salanderが物語の進行を担っているといえるか。13歳のある日彼女におきたこととは何なのか、物語の最初から、そのミステリーが読者に提示され、彼女の様々な壮絶な過去の出来事が少しずつ読者に明らかにされる。同時に、Blomkvistと現在関係する人々と彼女の過去の人々が関わり会うしかない時、過去の犯罪が明らかになり、それに関係する新たな犯罪が現実となり、そして、起こりつつある犯罪の予感が、二人の人生に影を落としてくるのである。Salandeが、自分で全てを切り開いていこうとする姿は壮絶でもある。そして、最後に読者にわかる相関関係と、エンディングの鮮烈さ。前作の、35年前の殺人事件の謎解きに、それぞれに個人的な問題を抱えた二人が関わりあっていくストーリー展開に比べたら、今回は、少し規模が小さいかも、なんて、途中思ったけれど、一回も本を置くことなく、時間を見つけては、ただ読み続けたものね。Salandeの今を切り開いていくタフな姿と、ひらすら抑圧していくBlomkvisへの思い、一体、作者に彼女がどこに行き着かせてもらうのか気になってしかたがない。願わくば、少しは幸せにしてあげてね。最終巻は、10月に英訳本が出る。読むしかない。
平成21年8月30日~8月31日
The New York Triology(Paul Asuter)☀

ニューヨークを舞台にした3部作――City of Glass, Ghosts, The Locked Room。真夜中の間違い電話から始まった探偵、依頼された人物の張り込み、失踪した幼友達の捜索、3作をつなぐのは、全て人物の「失踪」。しかも、この失踪は、「本当に人生の舞台から失踪するのは誰なのか」という読者には最後までわからないサスペンスともなっていく。また1作目と2作目の登場人物は全く繋がりがないように見えたのに、3作目の最後になって、全てが繋がっていることに気づくという構成。この作家の作品は初めて読んだけれど、上手いよね。ただ、三作とも、他者を探っているはずの主人公が、最後は自分がその対象になっているような、怖いような展開でもあり、どうなるか知りたいと読み続けて、読み終わって、疲れたような気分も。自己の存在を必要以上につきつめていった後のような、めまいのような感じか。平素それをしない自分には良い頭の体操みたいな感じでもある。自分が本当に見ているのは、他者ではなくて、自分の存在そのもの。そして、他者を見抜こうとする時の不遜な探索の眼は、自分へ向ける厳しい視線になっていくしかない。自分自身の存在を揺るがすほどのである。怖い。
“Auster harness the inquring spirit any reader brings to a mystery, redirecting it from the grubby search for a wrongdoer
to the more rarefied search for self.”(Stephen Schiff, The New York Times
Book Review.)
平成21年9月1日~2日
Down River (John Hart)☀
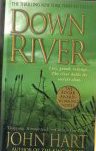
2008年のEdgar Awardを受賞した作品。5年前、犯してもいない殺人事件の容疑者となったAdamがニューヨークからノース・カロライナの故郷に帰ってくる。彼に不利な証言をした義母、家を出ていくように言った父、愛していた女性、彼が一番気にかけていた少女、殺された青年と親しかった義理の妹、彼の後を引きついだ義理の弟――その誰もが、彼がなぜ帰ったか知らない。それも当然である。帰郷を頼む古い友人からの不可解な電話一本が、彼の帰郷の理由だったのだから。そして、この友人さえ、彼が着いた時には町にはすでに姿がなかった。そして、大地主の父親の周りには、土地の売買をめぐってのいざこざが。この始まりは、十分賞にふさわしいよね、とわくわくさせる。しかも、帰るなり、凶悪事件、事件。またもや、疑いは帰郷したばかりの彼に。進行する事件と、5年前の殺人事件を結ぶヒントも、少しずつ示されて、フェアイナフ。最後までどうしても読んでしまう。人間の感情ということでは、「え、そういうこと?」と思うこともあったし、ミステリーのなぞ解きとしては、「そうくるんだ、なるほどね。。」程度だったし、「え、それで、それだけで、許せるの?」なんて思いも最後にはあったけれど、もともと「純文学で人間探求」というのを期待したわけではないのだから、このあたりは不満なし、ということで、ともあれ楽しんだ。Adamは出来た人間かも。私なら、最後にもっと、あ、言いたくなった。ま、小説自体が、若い時のブラッド・ピット様な俳優が演じれば、すぐそのまま映画ののりだから、これもありなのでしょ。ヒットはそこまでしないか。下の書評は、そうした私から言わせると、うーん、でも、そうなのかも。Adam人間出来すぎ。私なら、ちょっとは、彼女に、だって、あれだけのことをーーまた言いたくなった。
“Down River should settle once and for all the question of whether thrillers
and mysteries can also be literature.”(Publishers Weekly)
もう一つ紹介。これは確かにそうでしょう。
“The Thrills come fast and furious.”(The Washington Post)
平成22年12月26日~27日
The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest (Stieg Larsson)☀☀☀☀☀

Millenniusm 3部作の最終巻。瀕死の重傷で病院のベッドに横たわるSalanderと、その外で、彼女の無実を証明するために動くBlomkvist。相変わらず、クールで、他者に弱みをみせないで闘う姿勢を持ち続けるヒロインと、相変わらず、女性達に愛されながら、そうした特異なヒロインを理解し、助けようと続けるヒーロー。この図式に、おなじみの登場人物を襲う悪質な犯罪が盛り込まれ、最後は、Salanderの無罪を証明する法廷のシーン、そして、まさに最後の瞬間まで、物語に引き込まれる。9月に手に入れてから、ベッドの横に、ずっとおかれたまま、どうしてもまとまった読書の時間をとることができないで過ぎていたけれど、クリスマスの翌日、まさに、クリスマスの楽しい余韻とともに、幸せな休日を本とともに過ごした。終わり方も満足。Salanderは、最後まで彼女らしく、Blomkvistも、最後まで彼らしく、3部作を終えていたから。二人の関係が、微妙に変化しながら、毎回最後に描かれるのまで一緒。1作目は、ちょっと悲しく(そうしかないとは理解は出来るのだけど)、2作目は、壮絶で、3作目は、安らかさも(そして、私の期待も広がって)漂って、なんかよかった。作者が生きていたら、いつか続編も読めたのかも・・と残念さも増したけれど。
“The most original heroine to emerge in crime fiction for many years” (Boyd
Tonkin, Independent)
平成22年12月29日
Invictus (John Carlin)☀☀

Nesson Mandela大統領のもとに開催された1995年ラグビーワールドでの、南アフリカチームの勝利試合を、丹念なインタビューを連ねて、政治とスポーツが、そこでどのように結びついて、人々にアパルトヘイト後の新しいみんなの国としての南アフリカを認識させたのかを描くノンフィクション。世界中の人々が知るところのマンデラの政治闘争も、そういう意味では違った角度で描かれており、マンデラの政治家、そして人間としての魅力を再度認識するような小説となっている。
“He strove to persuade the prisoners that deep down all the guards were
vulnerable human beings; that it was the system that had many of them brutish.”(p.30)
かつて、マンデラの自伝を読んで強い感銘を受けた私としては、そして、もし世界のヒーローの誰かに会えるとしたら、マンデラに会って握手してもらいたい私としては、27年間の牢獄と、それ以上の長い闘いの後、赦しと優しさをもって、周りの人々に認められていた彼のことを読むだけで、幸せだった。
“Then I looked at Mandela there in the green jersey, waving the cap in
the air, waving and waving it, wearing that big, wide, special smile of
his. He was so happy. He was the image of happiness. He laughed and he
laughed and I thought, if only we have made him happy for this one moment,
that is enough.”(p.222)
“This outstanding book is not so much about rugby as about the ability of Mandela to harness the symbolic
power of sport. It shows us that sport gains its power not only from the achievements of its players, but
also from the dreams of those who watch them. (Daily Telegraph)
平成22年12月30日~31日
The Men who Stare at Goats (Jon Ronson)☀☀
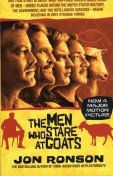
50年代~90年代にかけて、米国軍が、いわゆる戦闘以外での勝利方法としての平和的かつ心理的[超能力]闘争方法の研究について、どこまで力を入れていたかを、多くの関わった人々の証言を連ねて描き出すノンフィクション。イラクでの悪名高い虐待事件まで盛り込まれている。タイトルのとおり、ヤギを見つめて殺そうとするーーことの「おかしさ」は、それが試されて、本気で応用を考えられていたことを思うと、まさにブラックユーモアの極地かも。何度も、え、え、これ本当と思いつつ、頭が度々くらっとしたけれど、最後まで読むのをやめるのは無理。87頁、必ず声を出して笑うはず。丁度、下着に爆弾をつけて飛行機に乗り込んだ23歳のナイジェリア青年の逮捕で、下着まで透過するという検査が国際空港に取りつけられる予定という報道があったばかり。Goat-staring
strategy, the Barney song, remote viewingの愚かさも、下着につけた爆弾のおろかさも(もちろん、これを見つけるための装置を空港に必要とすることも)、こうした人間の愚かさが、世界の問題をさらに複雑にしているだけ。でも、そういって高見にたったように意見だけする、ずるい私達にも、解決策はもちろん提示できないまま、今年も暮れた。
“Simultaneously frightening and hilarious.” (The Times)