26年の4月から8月までは、理由もわからないまま、痺れる手足に、弱っていく身体に、仕事をするので精一杯で、読書をする余裕は全くない日々。仕事に行くのさえ無理と思えるような苦しい日の連続。
9月の手術の後からは、はやく回復して、少しでも前のように健康に暮らせることだけを祈る日々。仕事を休み、多くの人に迷惑をかけていることも、申し訳なくてつらかったです。でも、この日々は、8月までと違って、少なくとも読書はできました。今思えば、体を動かせないで、寝ているだけの者でも出来ることに読書があったことは、私にとって本当に救いだったかも。沢山の本を読みました。痛みを忘れ、今の、そして将来の心配を全て忘れるという境地までにはいたらなかったけれど、少なくとも物語を読む時には、その世界に引き込まれていたし、何よりも、物語の主人公達がいつも生きることにおいて勇敢で真摯であることも思い出せたことは幸運でした。
入院に持っていく本でバッグのかなり場所をとりましたが、それでも入院中に本が足りなくなって困るほど。一日に二冊以上読むことも。人は横にずっとなっているだけなら、これだけ本を読めるのだと驚くことに。日常では、続けて本を読むことはなかなか出来ないですものね。
以下、闘病中に読んだ本を、順不同で記しておくことに。動くことも出来ない状態で、パソコンも机についての作業もできないのでは、読むことはできてもメモを残すことはできない。読んだ時は色々なことを思ったのだけれど、今あらためて書こうとしたら、最初の一冊を書いてみて、いつものように書くのはとても無理だと気付いた。感想を思い出して記すのでは、自分が楽しめない。思ったことを一つか二つ記すだけにすることに。
The Alchemist (Paulo Coelho)☀
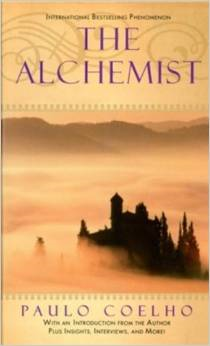
ブラジル人作家による世界的ベストセラーの英訳本。スペインのアンダルシアで羊飼いをする少年Santiagoが、不思議な人物との遭遇の後、夢を求めてエジプトに渡り、広大な砂漠を超えていこうとする。彼の夢を実現する過程で、彼自身の夢への思いの強さが問われるような出来事が次々と降りかかる。人生哲学のような言葉が散りばめられた寓話という感じ。でも、物語としてはどうなのでしょうね。完全に入り込むことは一度もできないまま、こう物語はすすめるのねと冷静に最後まで読み続けた感じ。物語に入り込めないので、人生哲学らしき言葉も、作家はこう思わせたいのねという感じになってしまう。しかも、その哲学的箇所さえ、印象に残ったのは2か所だけ。まず、ナルキッソスの死についての湖の返答。これがプロローグにあるのだから、期待はぐっと高まって読み始めたのになあ。もう一か所は、Santiagoが、死について考える箇所。“He
had lived every one of his days intensely since he had left home so long
ago. If he died tomorrow, he would already have seen more than other shepherds,
and he was proud of that.”(p.109) 人間の生死についてどうしても考えてしまう時に読んだせいか、そうよねと頷く自分がいた。
魔法、神秘性、ヒーローの成長、冒険、出会い、異国感、全部そろえて、哲学的コメントを散りばめたら、↓ということもあるのかも。
“This Brazilian wizard makes books disappear from stores.” (New York Times)
さすがに、↓は同意できず。これをThe Little Princeと並べるのは無理でしょう。物語とは、読者がその物語を一緒に生きる中で、同時に人間を知ること。The
Little Princeは、「作者が人生哲学述べている」と一度も読者に感じさせることなく、それでも読み終えて、人間について深く考えてしまう、そんな「本当の物語」ですもの。なんだかThe
Little Princeをまた読みたくなった。
“A memorable and meaningful as Saint-Exupery’s The Little Prince.”(Austin
American-Statesman)
A Monster Calls (Patrick Ness)☀☀
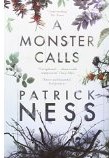
13歳の少年コナンは、重篤のガン闘病中の母親、彼が親しみを感じられない祖母、離婚して遠くで別の家庭をすでに持っている父、母親の病気からくる学校での孤立と様々な問題を抱えている。そうしたコナンは毎夜悪夢を見る。そしてある日、モンスターが現れる。これは、現在、過去、または未来の投影なのか。物語は、彼の悪夢と現実を絡ませて、出現したモンスターの意味するものを解き明かすミステリーとして進展していく。予想をつけながら、それでも予想とは違う結末だった。読み終わるまでは止めることはできないし、上手く書かれた小説だと感じる。ただ、自分が手術前日の病院のベッドで読み、その前日に手術を終えたばかりの家人をも思って複雑な思いも。生き抜いてほしい、そしてともかく自分も生き抜かなければと思い本を置いた。
“Exceptional…shines with compassion” (Daily Mail)
The One and Only Ivan (Katherine Applegate)☀☀
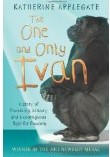
2013年ニューベリー賞受賞作品。モールの一隅のミニ動物園で、檻の中で長い間暮らしているゴリラのIvan。小さな象の赤ちゃんRubyが動物園に来て、彼は「自分のするべきこと」を考え、そして実行していく。自由とはそれがある時にはわからないけれど、失った時にはそれこそが大切だったとわかるもの。これも病床で読んだせいか、いつも以上にIvanに動けない自分の想いを重ねて読んだかも。実際にIvanのような状況にいたゴリラの実話に触発されて書かれたとあるように、ある種ファンタジーであっても、同時に、とても現実的な話にも感じる。誰だって檻の中では生きられない。その生きられないような檻を実際は長く生きてきたIvanがついに檻を出る努力をするのが、他者への想いから来ているのがいいのよね。人間もまたそうだから。他者への想いがこんなに溢れているのだから、その人達のためにも絶対動けるようになる、愛する人達のために、ともかく元気になる―それだけを願う日々が今からも続く。
The Saturday Big Tend Wedding Party (Alexander McCall Smith)☀☀
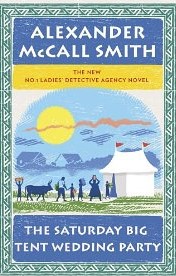
大好きなシリーズの12作目。主人公達の幸福が自分のだと感じられる限り、この世界が同じような安らぎに満ちている限り、少々ストーリーがマンネリ化していても、私には問題なし。
“those who have a great deal to complain about are so often silent in their
suffering, while those who have little to be dissatisfied with are frequently
highly vocal about it.”(p.125) “There are many people who have run out
of oxygen when arguing with that man. Maybe that is the way he wants it-maybe
that is his technique. He makes people run out of oxygen, and then they
fall over and he has won. There are people like that.”(p.182) “She thought,
of unequivocal pleasure-pleasure as hearing what all of us wanted to hear
at least occasionally: that there was somebody who liked us, whatever our
faults, and liked us sufficiently to say so.”(p.198)といった具合だから、人生哲学書みたいなものです。時には耳が痛いけれど。
The Limpopo Academy of Private Detection (Alexander McCall Smith)☀☀
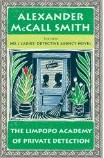
大好きなシリーズの13作目。この世界は、安らぎます。
The Minor adjustment Beauty Salon (Alexander McCall Smith)☀☀
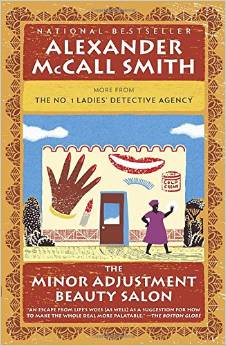
私の大好きなシリーズ14作目。ここ何作かは、前ほどには面白いとは思わないけれど、マンネリズムの中でも、主人公達の世界は暖かくて安心できることは確か。Mma
Ramotswe と Mma Makututsiの関係の進展が最後の最後にあります。「これでいいのよね」と思えることが、このシリーズがマンネリといいながら、読み続ける理由なのでしょうね。
“When you are in the company of Mma Ramotswe, you know that, despite the
clamor and chaos that passes for modern life, somewhere out there, all
is right with the world.”
(Book Reporter)
Wonders(R. J. Palacio)☀☀
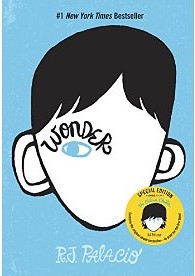
生まれつきの遺伝子障害のため人々が怖がるような異質の容貌を持つAugust。この少年の語りで物語はすすむ。それが病気のせいだとしても、彼を取り巻く世界は彼には優しいものではない。自宅で学んでいた彼が、普通の中学校に行くことを決意し、そこで同年輩の少年少女と会っていく。自分に向けられる偏見ゆえに、人々の優しさと残酷さの両方を彼が経験するというストーリー自体は、最初は、いわゆるよくある頑張る彼に、愛情深い家族、協力的な友人たちの間で織りなす感動物語という図式に涙が出て終わりかなあと身構えて読み始めたけれど、思った以上に彼の吐露する気持ちに素直にはいりながら読めた気がする。彼のユーモアのセンス、人々の自分への偏見を考えることができる賢さ、強さが、この物語の大きな魅力と感じた。“What
a piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculty!
In form and moving how express and admirable! In action how like an angel!
In apprehension how like a god! The beauty of the world!.... –Shakespeare,
Hamlet.”(p.205)
“A terrific story…Palacio is exploring some fundamental truths about how
human behave. And how they should behave.” (Telegraph Online)
How Starbucks Saved My Life (Michael Gates Gill)☀☀
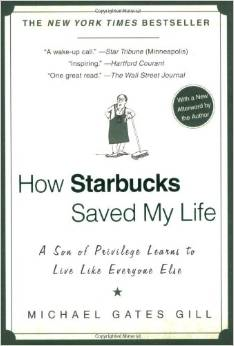
裕福な家庭に一生エリートたるべく生まれ、実際エリートコースをそのまますすんで重役にまでなった後、その広告代理店を突然解雇され、離婚し、すべてを失ったような状態の初老の白人男性、が主人公で語り手。アフリカ系アメリカ人である若い女性の店長から声をかけられ、それまでは思いもしなかったStarbucks店で働くうちに、人生の意味するものを再認識していく過程を描いた実話。病床で読んだせいか、人生を考えたといういくつものエピソートがいつも以上に頷けるものだったかも。時には書いてある以上の意味を取ってしまう時も。例えば、彼の同僚のあげる例として紹介されたもの。 “It
is tragic, but not serious.” の言葉が胸に響いた。今の自分の状況は、誰が考えてもtragicそのもの。でも、seriousにさせないで生きていくことは可能なのだって。
"An intensely readable tribute to the power of redemption through
work.” (Library Journal)
The Angel’s Game (Carlos Ruiz Safon)☀
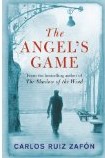
The Shadow of the Windはとてもおもしろかったから、同じ作者の作品で、しかもその前編にあたるということで期待していたけれど、前ほどではなかった。同じように最後までどうなるのか気になるのだけれど、こちらはとても重い。重すぎる。主人公Davidにふりかかる出来事が不気味すぎる。ただ前作と同じ現実と非現実の中間のような世界が存在したように感じさせるのも確か。最後まで、どうなるの?と気にはなったから。
Gone Girl(Gillian Flynn)☀☀
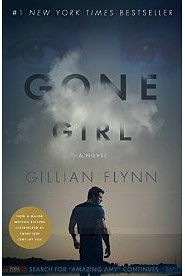
妻Amyがある日自宅から忽然と消える。残された夫Nickは、次第に妻の殺人容疑をかけられていくことに。夫と妻が語る彼等の結婚生活が交差し、読者は、二人の結婚生活はどのようなものだったのか、一体何が起きたのか、と二人の語りから考えていくことになる。どちらが真実を語っているのか、真実を見ているのか、語りそのものも一体信用できるのか、様々な疑いの中で、私も途中で持った事件の予想を何回か変えていったという点では、上手くできているサスペンス。最後には人間って怖いよねとは思うはず。
Dear Life(Alice Munro)☀
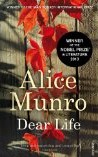
様々な人生の断片が綴られた短編集。ノーベル文学賞作家の高い評価を受けている最新作。そう思って買ったのだから、最初から期待し過ぎていたのかなあ。上手いのというのはわかる。でも、上手な短編を読んでいると思いながらも、最後までただ読むだけだった。どれにも感情移入できなかったのである。
The Rosie Project(Graeme SiMsion)☀☀☀
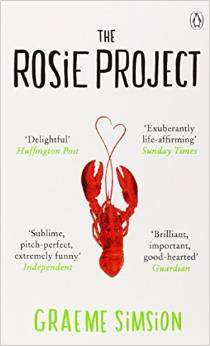
結婚に向けて、39歳の遺伝学の大学教員の男性Donが結婚計画なるものを立てて、それに基づいて行動した時、彼の遭遇したのは、彼の計画上の理想からは180度異なるRosie。「こんなストーリーならこうなる?」という想定とは異なっていて、最後まで楽しめた。くすっとする箇所がいくつもある。一昔前のロマンティックコメディの映画を見ている感じ。ちなみにまさにそんな映画の引用もあります。
Acid Row (Minette Walters)☁
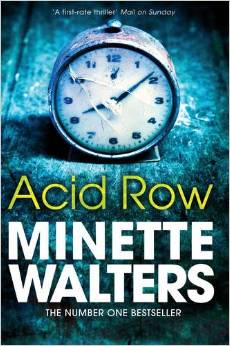
英国郊外にある低所得者用の団地に小児性愛者が移ってきたという噂から、少女の失踪が絡んで、人々のデモが起こる。そのデモが暴動と変わる時、警察も入れないような状態となってしまう。様々な人間にいくつもの事件が絡み、最後にいたっては脱出劇に。でも面白くなかった。魅力的な人物も出てこないし、現代社会の問題性をすべて入れ込んで、それをサスペンス仕立てにしていって、暴力的なこと盛り込んでハラハラさせて、と全てが計算されたような小説に感じる。全ての小説には作者の計算があるわけだけれど、この計算は私にはダメだったということ。
The Snowman (Jo Nesbo)☀
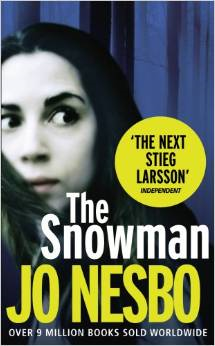
ノルウェーを舞台にして連続する猟奇殺人事件を主人公の刑事ホールが解決する。ホール刑事自身の私生活と事件の関係が絡み合って、最後までどうなるのかなあとは思い読み続けた。だけど、The
Girl with the Dragon Tattoのノルウェー版という言葉がついていたけれど、その魅力とは程遠いし、また同じ連続猟奇的事件を扱っていても、大・大好きなフロスト警部シリーズのあの楽しさもない。というわけで、このシリーズは読むのを止めた。主人公に感情移入できないと、いくらハラハラしても、結局読みたいとは思えないみたい。
The Luminaries (Elenor Catton)☀

19世紀のニュージーランドを舞台に、1人の富裕な男性の突然の失踪をめぐり、関係する人々の過去が絡みあいながら、事件の全貌が明らかになっていく。800頁の大作で、2013年マン・ブッカー賞受賞作品。素晴らしい書評が本に沢山記載されている。今まで、この本ほど読書中に、その記載に戻って、本を読む気力を引き起こした本はないかも。10回以上戻って、再度読み続けた。面白くないわけではないけれど、その書評のような思いを最後に得るのか、途中で何度も疑問になって、書評を読み直しては、やっぱり読もう、すごい読後感を味わえるかもしれないもの、と結局読み続ける必要があった。最後まで読んで、う~ん。歴史・文化・人間という3つの要素がミステリー仕立てで描かれていて、若い作家が良くかいたなあと思うし、自分の想像した結末とは異なって、面白い本ではある。でも800頁の大作を読んだのに、その満足感がなかったのは、物語の進展を気にかけるほど感情移入する人物が一人も存在しなかったから。だから、謎が解けても解けなくても、そんなに気にならないわけ。
書評が↓こんなのばかりなのです。誰だってこれを読むと読み続けるよねえ。
“The hype of novel that you will devour only to discover that you can’t
faind anything of equal scope and excitement to read once you have finished…Yes
it’s big. Yes it’s clever. Do yourself a favour and read The uminaries.”
(Independent on Sunday)
“Every now and then you get to read a novel that elevates you far beyond
the bric-a-brac of everyday routine, takes you apart, reassembles you,
and leaves you feeling as though you have been on holiday with a genius.
Eleanor Catton’s astonishing new novels does just that…Essential reading.”
(New Zealand Herald)
“
A Tale for the Time Being (Ruth Ozeki)☀

カナダの静かな沿岸部に住む作家Ruthが、打ち上げられた袋の中から日本から流れ着いたと思われる日記を見つける。15歳の東京に住む少女Naoの綴る日記は、帰国、父親の失業、家族の問題、貧困、虐め、自殺未遂といった彼女を取り巻く問題に、曾祖母のJikoと彼女の息子、Naoの大叔父の過去が重なって展開する。同時に、Ruthの現在の生活とも関わらずにはいられない。日本を描く洋書につきものの、読んでいると何か特殊なものとして語られ過ぎ、説明され過ぎと感じる日本的事象があるものだけれど、気にならず、むしろ面白く感じた。震災後の政府の対応や原発に対する政策、戦時中の特攻隊についての批判、興味深いところも。でも、今本を今読んでいるという感覚は絶えずあって、一度もそれを忘れて物語に入り込むことはできなかった。
Eleanor & Park(Rainbow Rowell)☀☀
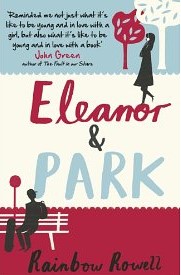
高校に編入してきた、一風変わった赤毛で太り気味の少女エレノアに、ごく普通の男の子パークが恋をする。義父のことで家庭内で大きな問題を抱えているエレノアと、家族には恵まれているパークが、違いを超えて、お互いを大切な存在に思っていく。みんなと異なっている女の子が学校にやってきて、普通に上手くやっている男の子が恋をする、でもそこに問題があって、二人の恋の行方は、というストーリーは、数年前に読んで好きだったStatgirlを思い出させた。若い時の恋を経験した者にはどんな世代でも共感できる、そんな感じはこの本にもある。Stargirlほどのマジックはこれにはなかったけれど、誰でも優しい気持ちで二人の恋の行方をおうことは確か。エレノアの家庭の様子が、こんな物語で普通期待する以上に臨場感があって、怖いほどでハラハラしてしまった。
The City of Palaces (Michael Nava)☀☀
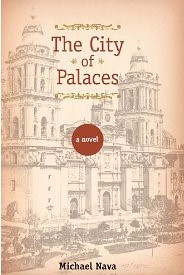
1910年代のメキシコを舞台に、ヨーロッパから戻ってきたばかりの若き医師Miguelと天然痘で後遺症が残り、独身のままで、貧窮の人々を助けることを自分の務めとしている貴族の娘Aliciaが、偶然の出会いの後、無神論者と信心深いクリスチャンという大きな違いを超えて結ばれる。物語は、二人の一人息子であるJozeとMiguelの従弟Luis、民主的な国家をつくろうとする政治家Madero等、二人と同時代を生きる人々の人生と、そうした人々の人生を翻弄するメキシコの激動の一時代を生き生きと描き出している。
数年前、私がすっかりはまったゲイの主人公ヘンリー・リオスのミステリー・シリーズの作者Michael Navaの新作。シリーズとは全く異なるタイプの物語で、予期したものと違いすぎて驚いた。でもがっかりはしなかったかも。作者Navaは、リオスもそうであったように、メキシコ系アメリカンのゲイであり、このメキシコを舞台とする物語にもまた自分のセクシュアリティに葛藤する人々が出てくる。自分のアイデンティティを基にしている点では、リオスシリーズと同じなのである。時代に翻弄されながらも自分らしく生きようと努めるMiguelとAliciaの思いを丁寧に描いている点で、まさに↓のいうように、正統派の小説なのだろう。Navaがまた作品を書き始めたことがともかく嬉しい。色々な作品を今から読めるのではと思ってワクワクする。
“This is a masterly work of old-fashioned storytelling, rich and spacious
and moving, a novel that deserves to be compared to The Leopard, Love in
the Time of Cholera, and Doctor Zhivago, but with its own intimacy and
grandeur. I fell in love with these people and did not want to say goodbye
to them.”
(Christopher Bram, author of Exiles in America)
The Hundred-year-Old Man who Climbed Out of the Window and Disappeared (Jonas Jonasson)☀☀
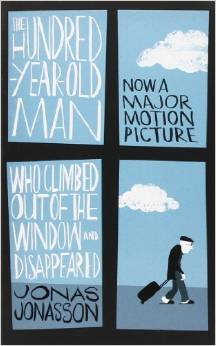
スウェーデンのベストセラーの英訳本。自分の100歳の誕生日を祝う催しの直前、老人ホームからスリッパで抜け出したアランの冒険談。このアランがただの高齢の老人ではなく、20世紀の世界の主要な出来事や要人と関わった人物となっているから、話はでかいこと、でかいこと。「ほらふき男爵」みたいな感じの荒唐無稽ともいえる話の連続だけれど、彼が巻き込まれる騒動に対するアランの極めて冷静な対処と行動で、それもありかと思わせるのは上手い。最後も納得。生きる力があふれていて、こちらも気持ちがいい。彼の元気が欲しい。
The World Eve Left Us (Boston Teran☂
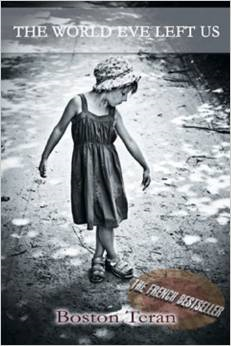
1950年代から70年代にまたがって、ニューヨークのブロンクスを舞台に、1人の聾唖の少女Eveと彼女の母親と友人の物語(のはず)。150頁でやめたので。物語に入り込めない。文体かなあ。
Don’t Ever Get Old(Daniel Friedman)☀☀☀
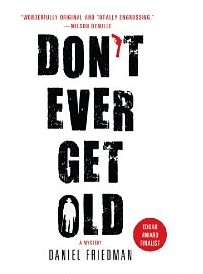
伝説ともなっている元殺人課刑事、87歳の老人Buckが主人公。死の間際の戦争中の知り合いから思いがけなく聞く、自分を痛めつけたナチス戦争犯罪者の生存と彼の持っているという金が事件の発端となり、意図しないうちに事件に巻き込まれていく。Buckが魅力的で、楽しい。老いの問題も抱えて、過去の記憶も生々しく、十分現実的でありながら、ちょっと非現実的に恰好いい老人なのである。面白い。結末も納得。続編が出ると書いてあって、それは楽しみと思えるから、幸せな読書になった。
“Wonderfully original and totally engrossing.” (Nelson Demille)
Alex (Pierre Lemaitre)☀☀
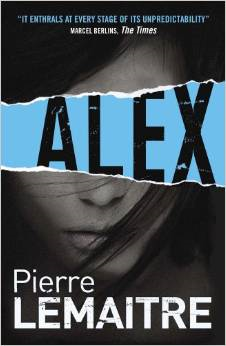
大ヒットの仏ミステリー作品の英訳。美しい若い女性、アレックスが一人の見知らぬ男に誘拐されて始まる物語は、誘拐事件から、複数もの猟奇的殺人事件、過去の虐待、とローラーコースターばりに物語が展開。被害者と加害者の境界も曖昧になって、「え、アレックスが・・なの」「え、理由はそうだったのか」と言った意外な展開で物語が最後まですすむ。ミステリー6冠と新聞に宣伝が出ていた。いったん読み始めると本を置くことなく読むことは確か。でも、私には、正義の施行を納得するには、暴力的過ぎたかも。コナン君がよく言うセリフと一緒で、どんなに憎むに値する人々がいても、憎むことができる理由があっても、「他の選択もあったでしょう」という感じは残るかなあ。
悲しいこと、つらいことがいくつもあった年でした。涙もずいぶん流したように思います。でも自分だけがと思ってはいけないですよね。理不尽な出来事で悲しい思いをした人々が今年もたくさんいたことはよくわかっているのですから。そして助けてくれる優しい人達がいる私はそれだけでも幸運なのですから。
小さい時から、家には本が沢山あって「まるで本屋のようなお家ね」と初めて訪れる友達にはびっくりされたものです。それらの多くの本を読み、そして子どものためにもまた多くの本を買ってくれた父も12月に今年のクリスマスを家族と過ごすことなく逝きました。母が大好きだった料理と父が大好きだった読書、そして二人が共通して大好きで一緒に長い時間を過ごしていたガーデニングー二人とも、それらの大好きなことさえ出来ない長くて苦しい闘病の月日を経て旅立ちました。大切に想う父のために料理ができなくて、そしてひとり残しておいていくしかなくて母はどんなにか悲しかったことだろう、そんな母がいなくなって父はどんなにか寂しかったことだろうと、今になってよく分かる自分が情けないです。長い月日、好きだったことを一切しないで、自分だけの孤独な世界にはいりこんでしまっていた父なのに、私達の手術のことを聞かされて声をあげて泣き出したと聞きました。心配だけをかけて、元気になった姿を見せる間もなくー。またもや大きな悔いが残りました。
今は、また二人で一緒になって、大好きなことを楽しんでいると、そして、最後まで満足な親孝行ができなかった私を、ふたりで笑って赦してくれていると、ただ信じたいです。私は、これからも、料理すること、読書することを大切にして生きていき、玄関前のささやかなスペースですが、お花をいつも咲かせておきたいと思います。これらの行為の度に、それらを大好きにさせてくれた二人を思い出していこうと思います。感謝の気持ちをいっぱいこめて思い出したいのです。