平成23年8月19日
Secret (Philippe Grimbert)☀☀

第二次世界大戦の後のパリに生まれたフィリップと彼の家族の秘密をめぐるフランス小説の英語版。人並み優れた美しい身体と能力を持っている両親と違って、彼は体も貧弱で、物語を書く方が好きな少年で、幼い時から、自分には自分よりずっと優れた身体能力を持った「兄」がいると想像している。戦争を経験したユダヤ人の両親も、彼等の親類も友人も戦争のことを彼には語らない中、彼は、空想の「兄」にまつわる戦争時の真相を知ることになる。「兄」についても、ある程度こうなるのだろうと読者が予測してしまうような始まりなのだが、明かされていく真相は全て半分ずつ違うという感じ。この読者の予測とのずれが、エンディングにいたるまで、何回か続くのが、この小説が賞を取る理由でもあるのだろう。愛は人間的感情の源でもある。優しさも欲望も、嫉妬も全てがそこから始まる。だから、戦争という非人間的な出来事の、前にも、最中にも、後にも、そうした人間的な様々な愛の感情が日常の中で並行して存在し続けたことは、当たり前なのだけれど、それでも、あらためてその当たり前を感じさせるのが小説の力といえるのだろう。
だから、この書評に一番納得です。
“A spare, remarkable novel that read as easily as a children’s take, yet
packs a grown-up punch.” (Independent)
平成23年8月20日~21日
Timburktu (Paul Auster)☀☀

主人公は、ミスター・ボーンズ、犬。ホームレスになったウィリーのたった一人の友達。ミスター・ボーンズは、人間の言葉を理解する。死期が迫ったウィリーは、自分の文才を認めてくれた高校時代の教員に最後に会おうとボルティモアの街を彷徨う。最初は、ユーモラスな感じで始まってにやっとしていたのに、ウィリーの人生が切なくなって、ウィリーの死後は、独りになったミスター・ボーンズのこれからが気になる。新しい飼い主達も、決して幸福ではない。それでも家も仕事も家族も得ている彼等に比べればウィリーは、格段の「失敗者」である。そのウィリーと夢で逢い続けるミスター・ボーンズの想いが胸にぐっとくる。何もかも人生でかなわなかったウィリーだけれど、ミスター・ボーンズがいたからいいよね、そう思った。ウィリーとミスター・ボーンズへの愛は、対等の者の間の愛だったから、この二人は愛し、愛されたということ。“The
bad grub, the lack of shelter, the hard knocks. It turned me into a sick
man, and it’s about to turn you into an orphan. Sorry, Mr. Bones. I’ve
done my best, but sometimes a man’s best isn’t good enough. “(p.62) 犬は、(失礼、多くの人もです)、「成功」のために愛することは出来ない。成功のおこぼれに預かりたいから愛することは出来ない。真実の愛はですけどね。エンディングで、題名の意味するところが一番わかるのだけれど、結末の意味することがわかっていても、勝手に別の解釈をすることにした。ただ、あとで、別版の犬の写真が表紙になっているのを見て、自然にじーんとしてしまったのは、結末は一つしかないと自分でも認めているからでしょうね。
オースターは物語に入り込めないことがあるので、読み始めるのを迷ったけれど、これは一気に読みました。“If God had sent his son
down to earth in the form of a man, why shouldn’t an angel come down to
earth in the form of a dog?” (p.35) そうかも。
納得する書評は
“A beautiful memory piece…The dark but tender memoir of a man and his canine
sidekick unfolded itself as a tragicomic story of a modern Don Quixote
de la Brooklyn.” (Rocky Mountain News)
平成23年9月6日
Crooked Letter, Crooked Letter (Tom Franklin)☁
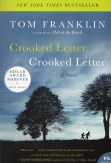
ミシシッピーの田舎町、少女が行方不明となる。その町では、20年前、同じように一人の少女が消えている。彼女とデートに出かけた少年Larryは、事件の関与を否定し、証拠もないまま起訴もされなかったにもかかわらず、今だに町の人々は彼を疑い陰口を言って避けている。その、友達もなく孤独に生きてきたLarryが何者かに撃たれ瀕死の重傷を負ったことから、20年前の事件、黒人警官Silasとの過去の交流、家族の秘密、その夜に本当におこったこと、そして現在の事件が次々と繋がってくる。旅行の最終日、空港の本屋で見つけて買った本である。旅行者がすぐ選べるように、ずらっとベストセラーが並べられて、これも読みたい、読みたいで迷った上、手荷物が増えるので、この一冊に決定。それもそのはず、表紙もそそれば、記されている多くの書評がすごい。ただ読み終わっての私の感想は、「なんだかなあ」。感情移入ができたのは、LarryとSilas達ではなく、彼等の母親達――負け犬のLarryのため良い事が起きるように毎夜祈り続ける母親、素っ気ない態度を取るSilasに食べ物をすすめる母親だけだった。
空港でざっと見た30以上の絶賛の書評を再度読んでいって、「う~ん、そこまでではないでしょ」と一つずつ否定して、それでも、ともかく自分の読後感に唯一近い箇所を選ぶと、↓でした。
“His life, so richly depicted by Franklin, reminds us all of how a twist of fate, a bit of cruelty, a
reluctance to forgive, and a label as commonplace as 'Scary Larry' can take away decades of joy and friendship for
a gentle, misunderstood man.” (Neil White)
“gentle” でありながら、誤解され、 ‘Scary Larry' となるーーその生きるのが下手なlarryは上手く描かれているから、彼ほど “gentle” ではない私は、何か彼ほどには赦しきれなくてすっきりしないのでしょうからね。
“gentle” であるから「利用して」異人を「作りだし」、最後は「赦しを求める」――これで「感動する」という作者の計算は、異人を作り出す社会そのものと感じてしまって、私には、この物語は、「なんだかなあ」なのです。
平成23年9月11日
The Art of Racing in the Rain (Garth Stein)☀☀☀
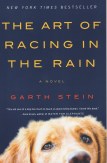
語り手は、老犬エンツォ。死が近づいている中、子犬の時からの飼い主、デニーとの自分の生活を回想していく物語。デニーが彼にとっての全てでもあるゆえ、彼の回想は、デニーの人生についてである。結婚、仕事、子ども、喪失、困難、苦悩を一緒に生き、デニーを心から愛し、幸せを願い、犬の自分に出来るだけのことをして支えてきたエンツォ。テストレーサードライバーのデニーがサーキットで運転する車の助手席に座って、そのスピードを愛し、犬は人間に生まれ変わることを信じ、何よりも、デニーに再会することを望んでいる。最後はこうなると予期して読んで、全く裏切られない、そんな物語。予期できるから不満?とんでもない。人間の描き方(特に後半の悪い奴)がステレオタイプ的だから不満?とんでもない。デニーのことを案じ、上手くいきますようにと祈って、エンツォと一緒に回想し続けた。デニーもいい。飼い主がデニーだったら、また会いたいよね!!犬がエンツォだったら、また会いたいよね!!!読んだ後は、“the
art of racing in the rain”が、“faster” が、“The car goes where the eyes go”
が愛おしく思える。p.127、p.267、それぞれジーンとし、また笑った。優しい気持ちになって本を置いた。私も “bark twice”!!
本の表紙にあった言葉、強く同感。
“This old soul of a dog has much to teach us about being human. I loved
this book.” (Sara Gruen, author of Water for Elephants)
納得の書評が多いです。
“It’s impossible not to love Enzo.” (Minneapolis Star Tribune)
“…Since finishing this engagingly unique novel, I’ve found myself staring
at my own dog, thinking, Hmm, I wonder…” (Wally Lamb)
“Enzo, and Denny, are heroes truly worth our attention.” (Marilyn Dahl,
Shelf Awareness)
平成23年9月12日
A Visit from the goon squad (Jennifer Egan)☁

今年のピューリッツア賞受賞作品。30代半ば、盗癖のあるSashaとその上司である著名な音楽プロデューサーBennieの登場で始まる物語は、章ごとに一つの物語の形で、過去と未来のBennieとSashaと、彼等の関わる人物達の人生の一断面を描きだす。主人公はこの二人ではなく、登場する全ての人々のようでもある。人々がともかく自分の人生を「生きる」しかなく、その生への執着(または無関心)が絡み合って、また互いの生が必然的に影響し合うしかない。こうした形式の物語として上手く出来ているのだろう。今まで小説形態にはないようなパワーポイントのプレゼンテーションのような頁が途中で長く続く。革新的?でも、私好みではない。過去、現在、未来が交差し、登場人物の繋がりがわかってくるという形式は、作者の技巧だけが走って、読み終えて感動から程遠いことが多いのだけれど、これも私にはそうだった。一つ一つの章の話しは結構引き込まれて読んだし、生きることにつきまとう困難、挫折、屈折した思い、孤独を、音楽のBGMつきで読んでいる感じではあったけれど、最後まで読み終えてみると、結局、どの登場人物も生きた人物として私には存在しなかった。登場人物の誰の運命も気にならない自分に気づいたから。
“A spiky, shape-shifting, new book…A display of Egan’s extreme virtuosity.”
(The New York Times)
平成23年9月13日
Incendiary (chris Cleave)☀

ロンドン、典型的な労働者階級のアパートに警官の夫と幼い子どもと住む一人の女性が物語の語り手である。爆弾撤去部隊に夫が属するために、毎日安否を気遣う。その強いストレスで、偶然知り合ったジャーナリストのJasperとの不倫もする。しかし、愛する夫と息子との平凡で普通の生活を壊すことを考えているわけではない。そんな彼女の日常が変わったのは、サッカースタジアムに観戦にいった夫と息子が、ビンラディンのテロ行為によって死亡した日から。空虚感と孤独を抱え生きる中で、彼女の生活は、Jasperと彼の同棲中の恋人Petra、そして、夫の元上司と深く関わっていくものとなる。途中まで読んでいて、この女性の傷をJasperが癒し、人生をまた生き始めるという「お決まりのストーリー」になるのなら、今のうちに読むのを止めようかと迷って、結局、読み続けた。読み終えて、こんな風に展開するとは思いもよらなかったというのが私の感想である。イギリスの階級意識、人間の自分勝手さ、そして、テロ行為の残酷さ、自分を取り巻く理解不可能な「彼等」――物語はそれらを全て含めようとしているのだろうね、そして、彼女の語りが向けられているのはなんとOsamなのだから、作者は工夫したのだろうな――こんな風な感想を持って読み終える小説は、私にとっては、物語としては全く生きていなかったということ。良い評をいくつも得ている劇を観に行って、折角座ったのだからと、結末を冷静に見守ったという感じ。ただ、良い評を得る理由自体は分かる気がすること、そして、語り手が感情移入を許さないほど、人間的であるのかも。そして、人間はみなそうなのかも。その点では、↓に同感。
“The eloquence of Cleave’s heroine is equal to the atrocity that claims
her family. She is by turns funny, sad, flawed, sympathetic, both damaged
and indomitable, and triumphantly convincing…the unnamed ‘I’ of Incendiary
is a true survivior.”
9月14日
The Diary of a Young Girl (Anne Frank)評価をつけるのはためらわれます。読むべき本という思いです。

『アンネの日記』。過去の普及版に付加された版も、英語版を読むのも初めて。少女時代に読んで以来、その後も様々な場で引用される度に、自分が知っているつもりになっていただけみたい。隠れ場所での生活の中でこれだけの思いを書くことができるような少女が、その生を途中で絶たれたこと、それが大勢の中のたった一人という事実に打ちのめされるべきなのだろうが、この日記は過酷な状況でアンネが記した生への讃歌でもあることを感じた。それを分かち合う気もちを大切にしたい、そんな思いで本を置いた。
“I’m young and strong and living through a big adventure; I’m right in
the middle of it and can’t spend all day complaining because it’s impossible
to have any fun! I’m blessed with many things: happiness, a cheerful disposition
and strength. Every day I feel myself maturing, I feel liberation drawing
near, I feel the beauty of nature and the goodness of the people around
me. Every day I think what a fascinating and amusing adventure this is!
With all that, why should I despair?” 昔読んだ時にもあった箇所なのだろうか。心に染みた。
体調が悪いと、したいことが一杯あっても、最低限の用事を済ませて、横になって本を読むことしかできません。それ自体は残念ですが、本はいつでも無限の喜びを与えてくれる気がします。この数日はそんな日が続きます。
9月15日
When You Reach Me (Rebecca Stead)☀☀☀☀

2010年のニューベリ賞受賞作品。1979年のニューヨークを舞台にシングルマザーの母親と暮らす12歳の少女Mirandaに届く謎の手紙から始まる様々な出来事と、謎への答えを得るまでの物語である。この賞を取ってだけあって、12歳の少女を取り巻く人間模様――幼友達、母親、母親のボーイフレンド、謎の少年、親友、苦手な少女との関係が少女の視点から上手に描かれて、物語の進展自体が少女の成長物語でもある。でもこの物語のすごいのは、読者もMirandaと同じ視点で数々の謎に直面して驚き考えること。一緒に「???」と思っているうちに、最後にたどり着いた最後の最後の謎の答え、私はぐっときました。
書評に納得以上です。
“Deeply, seductively weird…Closing revelations are startling and satisfying
but quietly made,their reverberations giving plenty of impetus for the
reader to go back to the beginning and catch what was missed.” (The Horn
Book Magazine, Starred)
実際私ももう一度頁をめくって確かめてしまいました。「表紙の意味」もよくわかってとても満足。
本当に↓。私には絶対書けない。
“Smart and mesmerizing.” (The New York Times Book Review)
9月18日
The View from Saturday (E.L. Konigsburg)☀☀
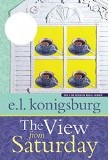
ニューベリー賞受賞作品。米国、ニューヨーク郊外の学校の6年生4人がチームを作り上級生チームと競い、Academic Bowlへ出場を目指す。彼等の指導をする車いすの女性教員と、彼等、そして家族達の物語が絡み合っていって、物語はいよいよコンテストへとすすんでいく。カニグスバーグのかつて同じニューベリー賞を受賞したFrom
the Mixed-up Files of Mrs. Basil E. Frankweilerがとてもよかったので読んでみた。私のとっては、そこまでではなかったけれど、これはこれでいい児童文学よねと思った。人って、互いの関係性においてのみ、生かされることが描かれており、この年齢になって、ますます真実だとわかるから。ただこれも、他者が(そして自分自身も)最低限の良心と善意を内に備えていることを前提としてだということもわかったのですけどね。コンテストの質問に4人がなぜ答えられるかという理由がそれぞれの異なる生活にあることも、語り手も語り時も過去に戻りながら示されるのも、上手。大人でも引き込まれて読んでしまう。何より、会話が楽しい。“How
many eighth graders does it take to screw in a lightbulb?” Noah replied,
“How many?” I answered, “Only one. They all know how to screw up.” (p.86)
“To wish you ‘Break a leg’ ’” I said. “ ‘Break a leg’ is what you say to
theater people instead of good luck.” “And what do you say to theater dogs?”
she asked. “You double it. You said, ‘Break two legs’ “. (p.112)といった具合。教員としては、先生の使った”unspeakable
act” (p.130)の定義――これ気に入りました。なるほど!!!
“Glowing with humor and dusted with magic.” (Publisher’s Weekly, starred
review)
16日、本格的な後期始まりの日なのに、痛みが激しいと、自分らしくふるまうこともできない。17日、もうこれ以上痛みには我慢できないと思った夕方、家族の差し出してくれる薬をついに取りました。薬を半量にして持ってきてくれた家族の思いが身に染みました。副作用をおそれて自分らしく一日一日を過ごせないのであれば、それは正しくないですよね。お母さん、あなたも、きっとそう思って、私達のために、この薬を取っていたのでしょう。かつてあなたが優しく膝に抱いていた男の子は、今年、素敵な女性と結婚しました。「お母さんはきっと式を見たかったよね」という言葉に、思わず「お父さんの目を通して、お母さんも一緒に見てくれるわ」と言っている自分がいました。それで、お父さんを泣かせてしまいましたけれど。物語より現実の方がはるかにおもしろいとわくわく生きてきたけれど、今、現実の哀しさもその分つらいのだとわかってきました。もう一度、会いたいです。お父さんに会わせてあげたいです。
平成23年12月
The Secret in Their Eyes (Eduardo Sacheri)☀☀

アルゼンチン、ブエノスアアイレス、刑事裁判所を退職したベンハミンは、25年前に関わった事件について小説を書き始める。1974年、新婚の銀行員の妻の殺害事件を回想していくことは、それに深く関わった自分の人生の回想でもある。一年前に丁度映画館で見た作品の原作(英訳)である。結末は原作と違っているという映画パンフでの記述に、すぐアマゾンで原作を手に入れようとしたのに、日本語訳も、英訳も出ておらず、原作のスペイン語版しかない。どうしても読みたいので、スペイン語版を買って、スペイン語を勉強して最後だけ読もうかしら、とまで思ったぐらい。あきらめていたのに、ふっと思ってタイトルを打ってみたら、今回は出ました。狂喜して、すぐ購入。この時期、忙しい週末が続いて、途中まで読んで、また読むの繰り返し。映画とほとんど同じストーリーであるために、もしかして、映画版が本になったの?と本を確かめて、やっぱり原作の英訳だと確かめて、ここまで映画と同じなのに最後だけ変える必要がなぜあったのかしら、と思いながら、本当に最後、わかりました。変更になった箇所が。映画は圧倒されるような終わり。映画館で、かつての同僚の先生もお見かけしたけれど、この映画の後では、声をかけるのは悪いかと止めたぐらい。観客はみな静かに出ていき、声も聞こえなかったです。終わりに言葉が出なかったのでしょう。原作はその部分が違っていました。映画の終わりは秀逸でしょう。原作を変更してある映画に不満なことが普通は多い気がしますが、これについていえば、映画がまさります。でも、原作もそれなりに納得しました。瞳の奥の秘密が指すものが、原作でもっと明瞭になって、読んでよかった。
“In straightforward prose, Sacheri builds as a startling psychological
mystery.” (Michael Greenberg)
“It’s a delight to read this novel in which everything happens like a explosion…seasoned
with winks of nostalgia, of sadness, of melancholy and desperation.” (Diario
de Ferrol)
平成12月22日~23日
Blackbird(Larry Duplechan)☀☀
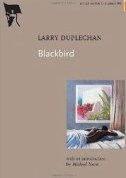
アメリカの黒人の高校生Johnnie。ゲイであることを誰にも知らせないでいる。新しい出会い、友人のカミングアウトーー心を揺るがせながら、自分らしくいることに迷い、居場所を問いかける彼の日常が描かれている。大多数の人々が当たり前としているセクシュアリティと異なって生きることは、簡単なことではない。親しい友達に隠し、自分を好きになってくれる少女に打ち明けるべき言葉を迷い、出会った若者への恋心を伝えるために優しい手の動きにも慄き、両親の失望や怒りに直面することを恐れる。ナイーブでありながら、同時に強さを求められる少年の日常の一瞬、一瞬に気持ちが自然に寄り添って、一気に読んでしまった。黒人作家のゲイ文学のパイオニア的作品ということで、復刻版を手に入れて読んでみたが、Navaが前書きを書いているのも納得である。彼の作品と同じような感じが漂っていたから。普遍的な人間の想いに共感し、そして、結末は希望。
Navaの前書きから。
“At other points in the story- which are more moving to me because he is
less defensive- Johnnie Ray’s loneliness and yearning are implied, as when
he describes his response to “somebody else’s troubles.”
“The combination of loneliness and yarning also rules the lives of the
people with whom he is friends, all of them misfits in one way or another
and, like him, dreaming of excape.”
“What makes Blackbird important and essential reading is not merely that
is it the first contemporary black coming out story, but its depiction
of late adolescence, that precarious approach to adulthood. In the end,
Blackbird is about learning to love, learning to heal, learning to fly.
This critic can say only one thing to black gay novelist Larry Duplechan:
We have all been waiting for this novel to arrive.”(Joseph Bean, The Adovocate)
クリスマスディナーを準備する楽しさに、自分の方がわくわくしたクリスマス、
楽しい思い出を重ねて、長く続いて、
そして、子どもがティーンエイジャーになって、
クリスマスイブかクリスマスのどちらかだけは一緒に過ごしましょう、
レストランでディナーということで予約してしまうからね、
と言ったクリスマスも、また何年も続きました。
そして、今年、長い年月の後、また二人のクリスマスになりました。
その二人きりのクリスマスディナーを予約したレストランで、
卒業したゼミ生のカップルに2組も会いました。
入るなり、入り口近くで「先生!」
途中で、「先生!」
二組とも、結婚して、幸せな二人の(当たり前でした)ディナー。
長い、本当に長い月日がたって、また二人になったことも
当然ですよね。ゼミ生が、かつての私の遠い、遠い過去のクリスマスを今
生きているのですから。
「ごめんなさいね、せっかくの先生のディナーを」と声をかけてくれた
彼女達は遠慮気味に言っていたけれど、
いえいえ、とんでもない、
二回も「先生!」と声をかけてもらえたクリスマスーー幸せだと思います。
翌日、ここ数年で一番よかったと思える映画を見ました。
終わった瞬間、何ともいえない気持ちに。
なぜか、クリスマスという言葉が浮かんだ、
美しい終わり。
優しさを忘れない限り、人生は詩。人は詩人。