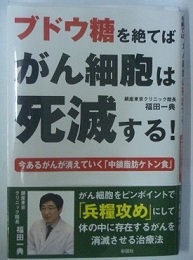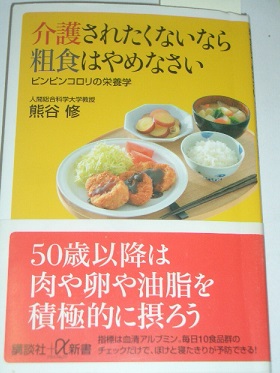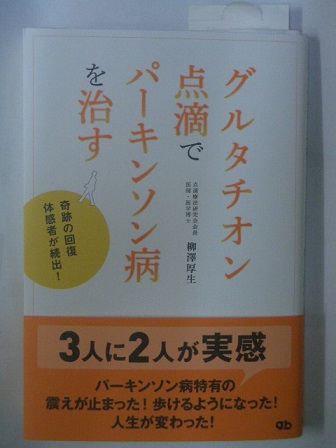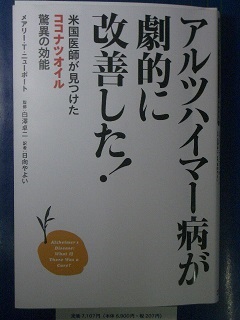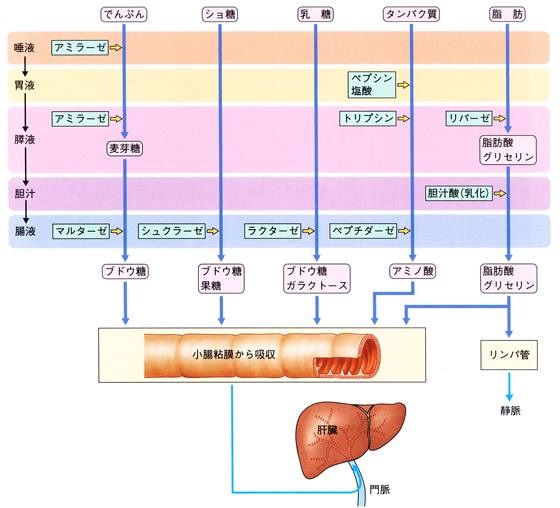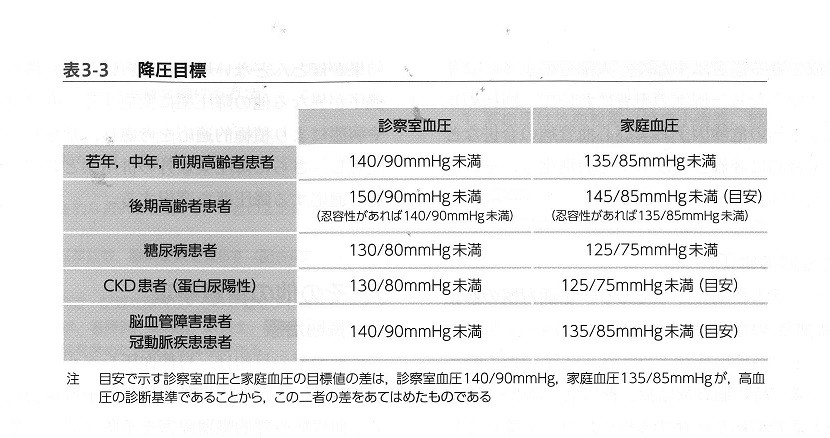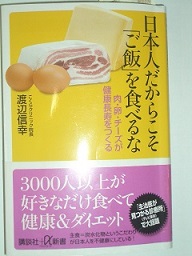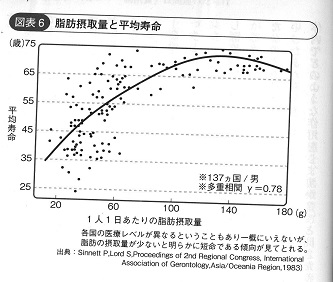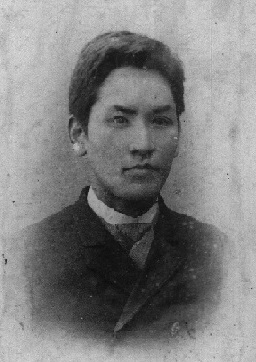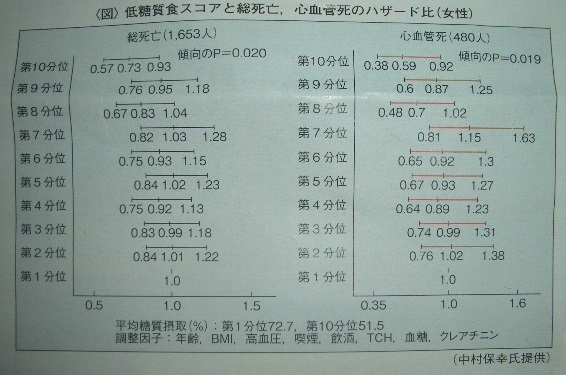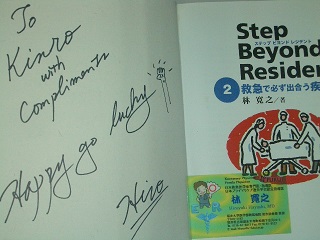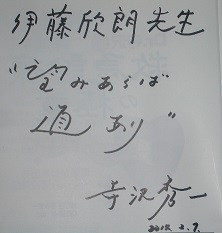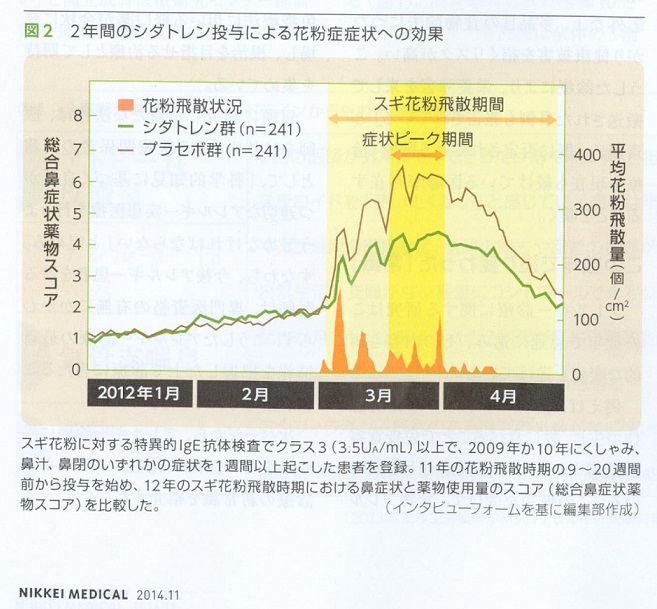
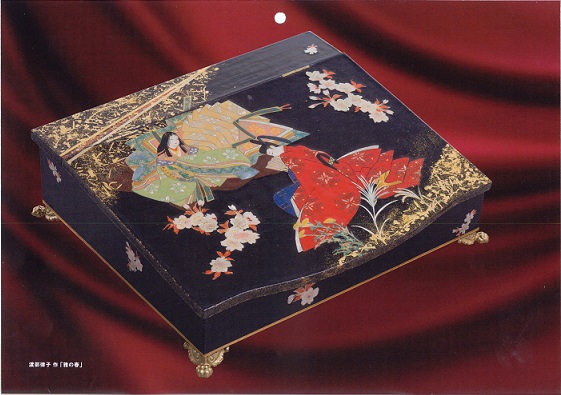


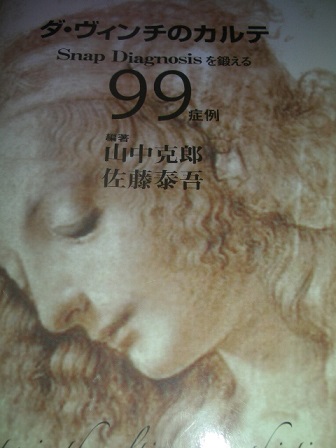
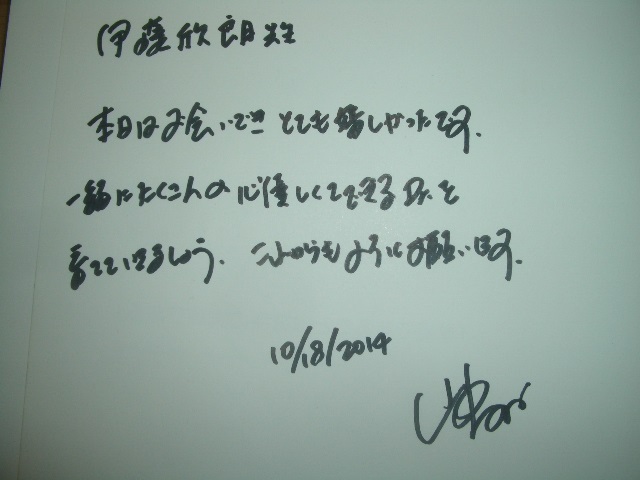


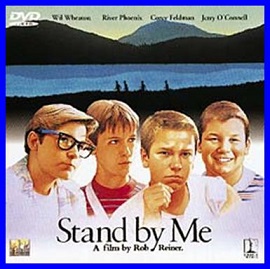
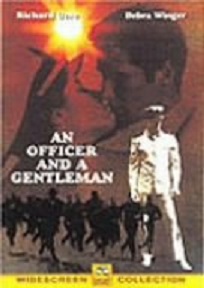
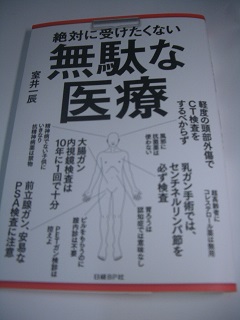

| �W�I�Ǐ� | ��\�I���� | �O���^�`�I���i����/�ێ��jmg | �j�R����mg |
| �ኈ��������� | DLB | 1000/1400 | 500 |
| �傹��� | LPC | 1200/1600 | 0 |
| ���s��Q | DLB�@NPH | 1400/1800 | 500 |
| �A�p�V�[ | FTLD | 1400/1800 | 250-500 |
| ���s��Q | CBD�@PSP�@MSA | 1600/2400 | 250-500 |
| ������ | �V�� | 1800/1800 | 1000 |
| �W���͍��� | ���X�y�N�g���� | 1000/1400 | 0 |
| ���ӊ� | ����� | 800/800 | 0 |
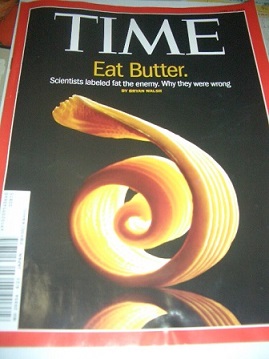

| ���b�_�� | ��ȐH�i�� | |
| �O�a���b�_�i�Z���j | �|�_�A���_�A�J�v�����_ | �|�A�o�^�[�Ȃ� |
| �O�a���b�_�i�����j | �J�v�����_�A�J�v�����_�A���E�����_ | �����A����A�R�R�i�c�I�C���A�p�[���I�C���Ȃ� |
| �O�a���b�_�i�����j | �~���X�`���_�A�p���~�`���_�A�X�e�A�����_ | �R�R�i�c�I�C���A�p�[���I�C���A���̑����A���ɍL�����z |
| �s�O�a���b�_�i�I���K�X�j | �I���C���_ | �I���[�u�I�C���Ȃ� |
| �s�O�a���b�_(�I���K�U�j | ���m�[���_ | �R�[�����A�Ȏ����A�哤���Ȃ� |
| �s�O�a���b�_�i�I���K�R�j | ���m�����_ | �����m���A�����ܖ��Ȃ� |
| �s�O�a���b�_�i�I���K�R�j | �d�o�` | �܂���A�T�o�Ȃǂ̐��� |
| �s�O�a���b�_�i�I���K�R�j | �c�g�` | �܂���A�T�o�Ȃǂ̐��� |
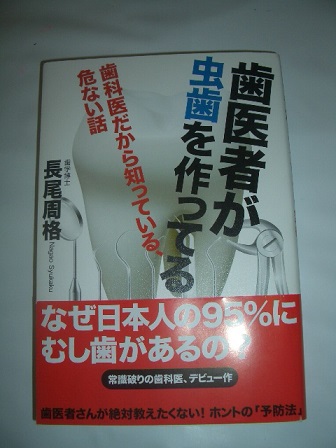
 |  |