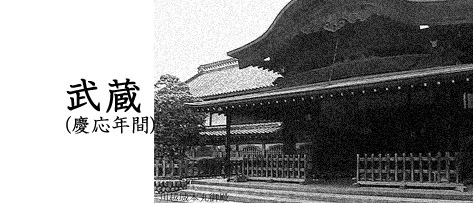
| 慶応年間リンク⇒ | 東北 | 関八州・江戸 | 東海・北陸・甲信 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 洋上 | 前ページへ |
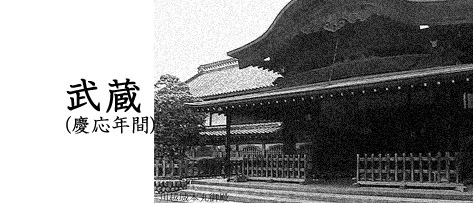
●慶応2年(1866)
5月28日−品川宿で米屋、旅籠、質屋など39軒が打毀される。
6月13日−秩父郡上名栗村(現入間郡名栗村)の農民が蜂起、米値下げ、質物返還を要求し、
多摩の幕府領農民と共に1万人が飯能の町へ押し出す。これが発端となり、武蔵国15郡上野国2郡参加10万人
ともいわれる武州一揆の嵐が8日間に渡って吹き荒れた。
6月−根岸に洋式競馬場が完成する。
忍藩、京都警護を命じられる。
10月20日−横浜に火事が起き、町屋の3分の1、外国人居留地の4分の1が焼失する。(豚屋火事)
10月26日−開成所の学生中村正直、菊池大麓ら14名が、イギリス留学のため横浜を出港する。
渋沢栄一、幕臣となる。
●慶応3年(1867)
1月3日−幕府、横浜に英仏語学所を開設し、諸藩士に就学を許可する。
1月11日−遣欧特使徳川昭武らがパリ万博参加のため、横浜を出港。渋沢栄一、徳川昭武に随行し、フランスへ渡航。
3月26日−幕府の新造軍艦開陽丸、榎本武揚が同乗しオランダより横浜に着く。
7月10日−品川・新宿・下板橋・千住・新井の5関門が廃止される。
幕府、埼玉郡町場村に関東郡代の陣屋を設置。
川越藩、藩校長善館を開く。
8月20日−荏原郡の幕領や下北沢・代々木村など8カ村の百姓、錬兵場のための土地召上げに反対して一揆。(駒場野一揆)
●慶応4年(明治元年・1868)
3月1日−近藤勇率いる甲陽鎮撫隊が内藤新宿より出陣。
3月14日−近藤勇、内藤隼人の変名で五兵衛新田(現・足立区・千代田線綾瀬駅北側)の豪農金子健十郎家へ到着、16日までに新撰組
隊士169人が集結。4月1日、下総流山へ。
4月25日−近藤勇、板橋で処刑。
4月28日−渋沢成一郎、彰義隊と袂を分かち振武軍を組織し、西多摩郡田無村・西光寺(現総持寺)に本営を置く。
閏4月11日−横浜でアメリカ人バンリードが邦字紙もしほ草を創刊する(岸田吟香が協力)。
5月下旬−飯能戦争が起こり、振武軍壊滅し渋沢は函館へ向かう。
児玉・那珂郡下で銃隊取立反対運動が起こる。
忍藩、東山道先鋒総督府に勤王誓書を提出する。
川越藩主・忍藩主、上京を許可される。
岩槻藩・岡部藩、勤王誓書を提出。