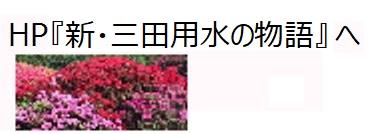 |
|
| 5月27日 新宿駅東南地域の発掘調査から渋谷川2万年をイメージする |
| 10月9日 水と緑の会主催「あるく渋谷川探訪ツアー」渋谷川の水源を求めて新宿・千駄ヶ谷を歩く(前編) |
| 2018年 |
| 5月9日 水と緑の会主催「あるく渋谷川探訪ツアー」渋谷川の水源を求めて新宿・千駄ヶ谷を歩く(後編)渋谷川上流の二すじの流れ:天龍寺方面からの流れと玉川上水余水の流れ |
| 2024年、バックナンバー16 渋谷の2万年ー渋谷川の歴史を振り返るー |
| 2023年、バックナンバー15 渋谷のコウホネの話-渋谷区立富谷小学校学校4年生「シブヤ未来科」の授業からー/『江戸名所図会』に描かれた駒場「空川」 |
| 2022年、バックナンバー14 駒場「空川」の歴史と文化をあるく(上) 駒場野公園から東大前商店街へ/(中)将軍の御成道から駒場池へ、そして古代人を偲ぶ/(下)偕行社崖下から遠江橋を経て河口部へ |
| 2021年、バックナンバー13 たこ公園コウホネの池が10年目の「底浚い」/「渋谷川中流」を稲荷橋から天現寺橋まで歩く(上) 淀橋台に広がる渋谷川の歴史と現在の姿/(中)渋谷川と三田用水で水車が回る/(下)渋谷川を通して見る広尾の地形と歴史/古地図に見つけた渋谷・南平台の谷間と川「渋谷川中流ツアー報告」番外編 |
| 2020年、バックナンバー12 江戸の絵図「代々木八幡宮」の謎/「春の小川 河骨川・宇田川を歩く」(上) 初台と代々木の水源を探る/(中) 参宮橋駅南から富ヶ谷1丁目へ/(下) 新富橋から渋谷駅の宮益橋まで宇田川本流をたどる |
| 2019年、バックナンバー11 渋谷の穏田川と芝川を歩く(上)「寛永江戸全図」に描かれた渋谷川の水源を探る/(中)水の町渋谷をイメージする/(下)キャットストリートに川の流れを追う |
| 2018年、バックナンバー10 渋谷の新名所/渋谷川遊歩道の名前が「渋谷リバーストリート」に決定/「代々木九十九谷」と「底なし田んぼ」を歩く(前編・後編)/夏休み番外編:動くナウマンゾウとツーショット/ |
| 2017年、バックナンバー9 新宿駅東南地域の発掘調査から、渋谷川2万年をイメージする/渋谷川ツアーの報告:渋谷川の水源を求めて新宿・千駄ヶ谷を歩く(前編)-渋谷川誕生の歴史を探る- /同(後編)渋谷川上流の二すじの流れ:天龍寺方面からの流れと玉川上水余水の流れ |
| 2016年、バックナンバー8 渋谷川ツアーの報告:渋谷川上流の河骨川と宇田川を歩く(前編・後編)/三田用水の流末を「文政十一年品川図」(1828)で歩く-猿町から北品川宿を通って目黒川へ- /TUCの講演会より: 都心の川・渋谷川の物語 -渋谷川の過去から未来へ-/その他 |
| 2015年、バックナンバー7 The Yoshino River Walk:: Gama Pond & Juban-Inari Shrine/渋谷川ツアーの報告:宇田川上流と代々木九十九谷を歩く(前編・後編)/鈴木錠三郎氏の「絵地図」に描かれた大山の池をさがす-大正11年頃の宇田川上流の風景から-/その他 |
| 2014年、バックナンバー6 渋谷川稲荷橋付近でアーバンコアの建設工事始まる-渋谷川の起点が水と緑の空間に- /The Hidden Kogai River & Legend of Aoyama area /渋谷川ツアーの報告:麻布・吉野川の流れを歩く(前編・後編)/A Tributary of the Shibuya River flowing by Konno Hachimangu Shrine /渋谷駅東口再開発のサプライズ-渋谷川暗渠が53年ぶりに姿を現した/その他 |
| 2013年、バックナンバー5 「渋谷川ツアーの報告:笄川の暗渠(前編)西側の流れと根津美術館(後編)東側の流れと地域の歴史/水と緑の会・渋谷リバース共催「あるく渋谷川ツアー」の報告:渋谷地下水脈の探訪/恵比寿たこ公園のコウホネを「せせらぎ」に株分け/「せせらぎ」にコウホネの花第1号!/に渋谷川の起点が変わる、ルートが変わる/「渋谷川ツアーの報告:宮下公園の渋谷川暗渠と金王八幡宮の支流/その他 |
| 2012年、バックナンバー4 たこ公園の小さな池に自然がいっぱい/渋谷川ツアーの報告:ブラームスの小径とキャットストリート/『あるく渋谷川入門』が点訳本に」/渋谷川(古川)支流・白金台から五之橋への流れ・その1とその2/他 |
| 2011年5月―10月、バックナンバー3 「発見!古川物語~歴史編~」を港区のケーブルテレビで放映/古川探訪のツアー「天現寺橋から東京湾浜崎橋まで」/恵比寿たこ公園にコウホネの池が完成/中田喜直と「メダカの学校」/その他 |
| 2011年1月―4月、バックナンバー2 渋谷駅の地下にひそむ渋谷川(テレビ東京放映)/緑の中の蝦蟇(がま)池の姿(NHKブラタモリ)/『あるく渋谷川入門』の登場人物(当時5歳)からのお便り/その他 |
| 2010年6月―12月、バックナンバー1 白金上水と麻布御殿/幻の入間川を歩く/箱根湿生花園のコウホネをたずねて/ビール工場のオブジェ/資料と証言から見る「蝦蟇(がま)池」の移り変わり/スイカを冷やした清水が麻布に/その他 |
2017年 5月27日

今年5月末の「あるく渋谷川ツアー」は、JR新宿駅東南口下から始まる渋谷川上流地域を歩きます。ツアーの出発点となる新宿駅東南の地域は今ではなだらかな斜面ですが、昔は幾つもの谷が入り組んだ複雑な地形であったことが近年の発掘調査で明らかになりました。このような地形は太古の渋谷川の成り立ちとどのように関わっているのか、発掘調査から見えてきた当時の湧水や川の流れの様子を考えます。
 「推定谷1」が始まる新宿駅東南口下
「推定谷1」が始まる新宿駅東南口下<渋谷川の2つの水源>
渋谷川の水源と言えば、「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」『江戸切絵図』に描かれた天龍寺の池が有名です。実はこの池がどこにあったのかは分かっていません。2002年に行われた天龍寺跡の発掘調査により、現在の天龍寺北側の境外(TOKYUREIT新宿ビル駐車場辺り)に明治の初めまで約126㎡、深さ最大0.9mの池(心字池)があったことが分かりました。湧水の可能性が高いということです。ただし池は大きくありませんし、切絵図の池と同じかどうかも分かりません。このように渋谷川が湧水池から始まったという説には無理なところがありますが、地形的にはこの土地に渋谷川の水源があったとみて間違いないようです。新宿駅の東南地域は新宿御苑に向かう緩やかな傾斜の谷奥に当たり、北から東南に開く幾つかの谷や湧水が発掘調査で見つかっています。発掘の際には、作業を止めなければならないほどの湧水が出た所もありました。これまでの発掘結果からは、渋谷川が特定の池を水源にしていたというよりも、谷間の湧水、小池、沼、湿地帯の水を集めて流れを作っていたとみる方が自然です。
もう一つの水源は玉川上水の余水の流れです。これは江戸時代の承応3年(1653)に生まれた言わば人工の水源で、四谷大木戸にあった水番屋の吐水口から南へ流れ出し、高遠藩内藤家下屋敷(現在の新宿御苑)の敷地を出た所で天龍寺方面からの流れと合流して渋谷に向かっていました。当時玉川上水は、新宿の地の尾根の上を甲州街道と並んで流れており、その両側は南北に下る崖になっていました。江戸幕府の地誌である『御府内備考第3巻』には、「左右谷にて至て深林の一筋道なり」と記されています。流れはその名の通り余水川と呼ばれていましたが、玉川上水の水量が多い時はさぞ勢いよく流れ落ちたことでしょう。
 |
天龍寺の北側境外で発掘された心字池の遺構(江戸~明治)。水色が池の輪郭。湧水であった可能性が高い。 |
<新宿駅東南地域の発掘調査>
しばらく前のこと、渋谷区郷土博物館・文学館学芸員の粕谷先生からこの地域の発掘についてお話を伺う機会がありました。その時に先生は「新宿御苑の北西側の地区(新宿駅東南の地域…筆者)を発掘したところ、数か所がV字の谷の形になって中に黒い土が溜まり、その底には水が湧いている所が見つかった」とおっしゃいました。このように地中に埋没している昔の谷を「埋没谷」(または「埋もれ谷」)というそうです。「谷の底には水が湧いている所が見つかった」という先生のお話に触発されて都立中央図書館に調べに行くと、渋谷区や新宿区のコーナーに「発掘調査報告書」が何冊も並んでいました。発掘調査は渋谷区千駄ヶ谷や新宿区4丁目、内藤町などで10回以上行われており、これからも続くようです。
<「推定谷」からの流れ>
『千駄ヶ谷5丁目遺跡3次調査』(2013年)と『千駄ヶ谷大谷戸遺跡 第3地点』(2016年)の中に興味深い地図資料がありました。「調査地点周辺の旧地形等高線と旧石器時代・縄文時代の遺構・遺物分布図」という長いタイトルの資料で、JR新宿駅の南の地域の発掘地区とそこで明らかになった遺構・遺物の分布を示しています。
 |
「調査地点周辺の旧地形等高線と旧石器時代・縄文時代の遺構・遺物分布図」。株式会社オークラコーポレイション、渋谷区教育委員会他『千駄ヶ谷大谷戸遺跡 第3地点』(2016年)より。 |
左側(西)の何本もの縦線はJR山手線などで、その上方(北)が新宿駅、下方(南)が代々木方面です。図の右側(東)の広いエリアが新宿御苑で、図のほぼ中央を南北に通る「く」の字の形の道が明治通りです。黒い太いケイで囲まれた所が発掘地区で、主にビルが立ち並ぶ場所です。図の右上から左下に斜めに横切っている「釘」のような形の細長い区画は環状5号線(明治通り)予定地で、ここで多くの発掘が行われ、旧石器時代や縄文時代の遺物が出土しています。
ところで図中に縦と横の3つの黒いベルトがありますが、これは「推定谷」と呼ばれています。粕谷先生によると、先ほどの「埋没谷」は発掘によって存在が確かめられた谷、「推定谷」は埋没谷や土地の傾斜など、発掘した地形の状況から存在が推定される谷です。この3つの「推定谷」のうち、北側と南側の2つの細い谷は縄文時代にはすでに埋まっていたようですが、この辺りに人が住み始めた約2万年前(ヴュルム氷期)には幾つもの湧水があり、そこから流れ出た水は川となり、谷を形成していたようです。現在の新宿駅東南の土地は甲州街道から緩やかに降りていますが、当時は湧水により刻まれた幾つもの谷が入り組んだやや険しい地形で、それらの谷底を「立川ローム層下の半粘土層に滞留する浅層の地下水に由来する」(*)渋谷川の源流が流れていました。そして新宿御苑の北西側にあった埋没谷を通って御苑内に流れ込んでいました。そこで、現代のグーグルマップに「埋没谷」と「推定谷」を描き込み、仮に1~3の番号を付け、谷間を通る川の流れを水色の点線で描いてみました。
(*)東日本旅客鉄道株式会社他『千駄ヶ谷5丁目遺跡3次調査』2013年

上図はグーグルマップに旧石器・縄文の頃の地形や川の流れと遺構などを書き入れたもの。黒い枠で囲った
所が「推定谷」、黄土色の線が「埋没谷」、薄い灰色の枠が発掘調査地区、水色の点線が想定される川の流れ。
茶色の線は今回のツアーで歩く道順
a
<推定谷の考え方>
 新宿ミライナタワーとザラの発掘
新宿ミライナタワーとザラの発掘
新宿駅の東南から新宿ミライナタワーの横を通って南に延びているのが「推定谷1」です。この谷の標高を「調査区全域に広がる固い地層(Ⅴ層)」を基準にして調べると、新宿ミライナタワーの土地は地中で東に傾斜しており、先生のお話では調査の時は1.5mぐらいの所に湧水跡があったそうです。現在はその上に柔らかい表土・盛土が積もっています。新宿ミライナタワーの反対側のザラ(ZARA)の場所は逆に西へ傾斜しており、ここには埋没谷も見つかっています。これらの結果を総合すると、ここに東と西から降りる幅約50mの谷があることが推定できます。新宿ミライナタワーには地中1.5mに湧水の跡が確認されていますから、この流れが谷間を通って南に向かっていたのでしょう。面白いことに現代の道路は「推定谷1」の谷底を南北に通っていて、歩いているとまるで谷底を歩いているように思えます。他の「推定谷」についても同じような方法で谷の存在を推定していますが、ここでは説明を省きます。
<3つの推定谷の繋がり>
発掘調査によると、「推定谷1」は北から南に向かったのちに東に曲がり「推定谷3」に至りました。また天龍寺や新宿高校校舎がある「埋没支谷」は南に向かって「推定谷3」に繋がっていました。この「推定谷3」の幅は100m近くあり、その中に比高差7mの大きな谷が埋没しており(F区埋没谷)、そこに沖積粘土層(川の土砂など)が厚く堆積していました。この谷を太古の渋谷川が流れていたことは明らかです。報告書によると、谷を発掘している最中に激しい湧水があって作業を停止せざるを得なくなったそうで、「地下に川が流れているが如くである」とか「湧き出る水との戦いだった」と記されています。太古の昔はこの地に豊かな湧水と川の流れがあったのでしょう。この「推定谷3」を挟むような形で両岸の高台に古代遺跡が分布しています。なお高島屋の南から新宿御苑にかけて東西に走る「推定谷2」にも「D区埋没谷」と湧水の存在が確認されています。「推定谷3」と「推定谷2」からの流れは新宿御苑内で合流しており、この地域一帯がとりわけ水資源に恵まれていたことが分かります。
 縄文時代3号住居跡(後期)『千駄ヶ谷大谷戸遺跡(環状第5の 1号線地区)』より。 |
「推定谷3」の南側の台地の南面には、縄文人の遺物と共に竪穴住居跡が3軒発掘されています。住居は4000-5000年ぐらい前(縄文中期後半ー後期)のものかと考えられます。この住居から少し西の高島屋の土地には縄文人が作った陥し穴がたくさん発見されました。イノシシやシカを捕まえる仕掛けだったのでしょう。この“陥し穴”という考古学用語?は意味が深いですね。「落ちる」以外に「攻め落とす」「おとしいれる」などのニュアンスが含まれています。この住居跡について報告書に興味深い記述があります。「調査時の3号住居跡(SI-3)は床面が現在の地下水位より下で降雨時は完全に床面が水没する状況(第108図)で、谷が埋まらず水路として機能していたとすれば、現状より地下水位が低かったことが考えられる。」発掘された住居跡は現在では雨が降ると水に浸かるような所にありますが、縄文時代に水が付きやすい場所に家を建てるわけがありません。当時はまだ谷が埋まらず川が流れていたとすれば、今よりも地下水位が低く、住居は乾燥した安全な場所にあったと考えられます。
|
 |
縄文人の住居跡の少し南の台地からは旧石器時代の遺物が出ています(第6図)。日本の旧石器時代は1万2千年から3万5千年前とされていますが、この土地で出土したナイフ形石器やフレーク(剥片、はくへん)などは2万年ぐらい前のもので、「推定谷1」の西側の斜面(ミライナタワーの場所)でも発掘されています。旧石器時代の人は狩猟を中心とした生活を営み、縄文人のように定住していませんでしたが、この場所で遺物が集中的に出てくるということは、この地が食料や水に恵まれ、また獲れた魚や動物をさばく活動の場として適していたのでしょう。
<現在の新宿御苑の水源>

新宿御苑の上の池。かつての鴨池が作られた場所。
ところで現在の新宿御苑の池の水は一体どこからくるのでしょうか。水源について新宿御苑の管理事務所に伺ったところ、「池の水源の調査はあまりされていませんが、湧水はないと考えられます。平成に入ったころは天龍寺の方からの湧水が流れ込んでいたが、平成10年ごろから始まった環状線の工事で地下の水路が分断されたようで、おそらくもう何も入ってきていないでしょう。現在の池の水は全て雨水で、水道水は全く入れていません」というお話でした。発掘の調査結果からの推測ですが、内藤町遺跡埋没谷、F区埋没谷、D区埋没谷の辺りの地下に湧水があり、2008年(平成20年)の発掘調査の頃まで地中を通って人知れず池に流れ込んでいたことも考えられます。今は環状5号線の工事が始まって流れのルートが途絶え、湧き出した水は地中に広がっているのでしょう。
<渋谷川と人々の歴史>
最後に旧石器時代・縄文時代から現在に至る渋谷川の流れをイメージしてみましょう。太古の昔、現在の新宿駅東南地域は渋谷川の源流域で、その流れは谷筋にそって分岐していました。こうした流れの近くで約2万年前から旧石器時代人が活動を始め、後に縄文人が竪穴住居を作って生活を営んでいました。2015年の発掘では弥生時代末から古墳時代前期の遺跡も初めて出ています。しかし古墳時代以降は江戸時代まで人が住んでいた形跡がありません。江戸時代になると渋谷川は歴史の表舞台に現れます。当時は新宿の天龍寺の近傍から川の流れが始まり、高遠藩内藤家の下屋敷を西から東に流れた後に、原宿、渋谷に向かっていました。武家屋敷の中ですから庭園用水に使われたと思われがちですが、幕臣の内藤家は贅沢や華美を好まない家風があり、屋敷内に作っていた田畑の灌漑にも使っていたようです。享保2年(1725)に隣接する旗本・御家人屋敷地に移ってきた新井白石の家の周りは一面の麦畑であったと伝えられています。内藤新宿では俗にいう「内藤唐辛子」が名物だったそうで、川の水は野菜類の栽培にも使われたのでしょう。
明治5年、内藤家下屋敷は「内藤新宿試験場」として生まれ変わり、新政府が勧農政策を進めました。同12年に宮内省の「植物御苑」になると、渋谷川の地形を利用した「鴨池」が作られ、鴨の飼育以外にも外来種の野菜や草花の栽培、動物の飼育、農学の研究教育が進められました。時代が変わって、日露戦争後の明治34年には国家の行事を行う皇室の庭園として改造されることになり、その名も「新宿御苑」と改められ、渋谷川は上の池から下の池に至る5つの池に作り替えられました。戦後は国民の公園となって現在に至っていますが、渋谷川の入り口と出口の跡は今も残っています。
以上、渋谷川の約2万年を猛スピードで眺めました。「あるく渋谷川ツアー」の当日は、このような渋谷川とそこに暮らす人々の歴史を一つ一つ確かめながら、新宿4丁目、新宿御苑、内藤町、新国立競技場までを歩きます。最後に発掘調査について親切にご指導をいただいた粕谷先生に改めてお礼申し上げます。
 |
 |
 |
||
|
F区埋没谷付近(新宿御苑北西の縁)に残る |
新宿御苑「下の池」からの流れ。渋谷川は御苑の東南端にある出口へと向かう。手前は日本で最初の擬木の橋(フランス製)。 |
|||
<参考資料>
千駄ヶ谷5丁目遺跡調査会『千駄ヶ谷5丁目遺跡 (高島屋タイムズスクエア他)』1997年
千駄ヶ谷5丁目遺跡調査会『千駄ヶ谷5丁目遺跡 2次調査報告書』1998年
東京都埋蔵文化センター『内藤町遺跡』2002年
オリックス・リアルエステート株式会社、他『天龍寺跡』2004年
株式会社アーバンコーポレイション、他『新宿4丁目遺跡』2008年
東京都埋蔵文化センター『千駄ヶ谷大谷戸遺跡(環状第5の1号線地区)』2008年
東京都埋蔵文化センター『千駄ヶ谷大谷戸遺跡 内藤町遺跡(環状5の1号線地区)』2009年
東日本旅客鉄道株式会社他『千駄ヶ谷5丁目遺跡3次調査』2013年
株式会社トーシンパートナーズ、渋谷区教育委員会『千駄ヶ谷大谷戸遺跡・第2地点』2013年
株式会社オークラコーポレイション、渋谷区教育委員会他『千駄ヶ谷大谷戸遺跡 第3地点』2016年
(終)
2017.10.9

|
<はじめに> 2017年5月28日朝9時、私たちはJR新宿駅南口に集まり、新宿4丁目、新宿御苑、内藤町、千駄ヶ谷に広がる渋谷川の水源地域を歩きました。スタート地点の新宿駅東南の地域は、約2万年前には幾つもの谷があり、渋谷川の揺籃の地であったことが近年の発掘調査から明らかになっています。前回『トピックス』の「新宿駅東南地域の発掘調査から渋谷川2万年をイメージする」でも紹介しましたが、この身近な街の地下にヴュルム氷期の谷の跡が残っていたというのは本当に驚きで、太古の谷間や渋谷川をイメージしながら街を歩いたのはこれまでにない体験でした。この他にも、下見の時からツアー当日まで、新しい発見がたくさんありました。ツアーは話題が多すぎて時間をだいぶオーバーしてしまいましたが、皆さまには熱心なご参加をありがとうございました。 |
 |
| 新宿駅東南部から新国立競技場にかけての渋谷川水源地域の地図。緑の枠は新宿御苑。地図の上部を横に流れるのは玉川上水。新宿駅近くの玉川上水の南側から2万年前の谷間が発掘された。原初の渋谷川はそれらの谷間に始まり、現在の新宿御苑の西端で1つの流れとなったと考えられる。江戸時代になるとこの流れは新宿御苑(当時は高遠藩内藤家下屋敷)の南端で北から来るもう一すじの渋谷川(玉川上水の余水)と合流し、南下して原宿・渋谷へと向かった。 |
|
<前編のルート>:JR新宿駅南口集合(9:00)-駅東南口下の広場-新宿ミライナタワー・高島屋前の推定谷1(旧石器と縄文陥し穴)-日本製粉本社跡地(建設現場)の推定谷2-環状5の1号線工事現場(D区埋没谷)-推定谷3と新宿高校グラウンド(F区埋没谷・旧石器遺物・縄文竪穴住居跡)-天龍寺裏道(埋没支谷・心字池)-天龍寺水琴窟と鐘楼-新宿高校(「旭橋」石樋)-新宿御苑内の通路(F区埋没谷とD区埋没谷の南端)-上の池(旧鴨池) |
|
<後編のルート>:新宿御苑内「上の池」(鴨池)-「中の池」(新井白石宅近傍)-「下の池」-模擬橋(天龍寺方面からの渋谷川出口)-玉藻池(内藤家下屋敷の庭園)-水道局新宿営業所と「水道碑記」-内藤町の渋谷川(玉川上水の余水の流れ)-多武峯内藤神社-水車エリアと「鉛筆の碑」-池尻橋(外苑西通り)-大番児童遊園・JR中央線土手(2つの流れの合流点)-外苑橋-新国立競技場前(13:00解散) |
|
日曜日の朝、いつもより人通りが少ない新宿駅を東南口まで歩き、そこで発掘調査の地図資料(*)に目を通してから、大きな長い階段を降りて下の広場に出ました。この広場を右(南)に曲がると甲州街道の高架道路の下に入りますが、その辺りから地図の「推定谷1」が始まります。原初の渋谷川はその谷間から流れ出していたと考えられます。この「推定谷」とは、発掘した地形や地層の状態から存在が推定される谷のことです。よく似た用語ですが、「埋没谷」は発掘で存在が確かめられた昔の谷、「埋没支谷」はその支流の浅い谷です(**)。考古学の難しい用語ですが、一言で言うと現在は地下に埋まっているが昔は地上にあった谷のことです。谷があったということは、そこに湧水や雨水の集まるところがあり、谷間を縫って川が流れていたことを意味しています。
(*)「調査地点周辺の旧地形等高線と旧石器時代・縄文時代の遺構・遺物分布図」『千駄ヶ谷大谷戸遺跡 第3地点』2016年。 (**)「Ⅱ遺跡の立地と周辺の遺跡」『内藤町遺跡』2002年。 |

| 新宿駅南部の発掘調査地域。茶色の線はツアーのルート。黒い枠の土地は推定谷。グレーの枠は発掘現場。★印は旧石器時代の遺物、●は縄文時代の陥し穴、■は縄文竪穴住居、●は湧水跡、○は近世以降の沼と池。上の水色の実線は玉川上水、点線は谷間を流れる原初の渋谷川のイメージ。 |
上の図は近年の新宿駅南の発掘調査で明らかになった埋没谷、推定谷、埋没支谷、旧石器出土地点、縄文竪穴住居跡などを現代地図に書き込んだものです。茶色の線は今回のツアーで歩いたルート、黒い枠に囲まれた土地は推定谷。グレーの枠は発掘現場です。それによると、新宿駅の東南の地域には3つの「推定谷」がありました。地図では「推定谷」に仮に1~3の番号を付けました。約2万年前(ヴュルム氷期)には、この辺りに幾つかの湧水があり、そこから流れ出た水や雨水が川となってそれらの谷間を作り出しました。2万年前といえば日本の旧石器時代に当りますが、新宿ミライナタワーや高島屋がある小高い丘や新宿高校のグラウンドから旧石器時代の遺物が多く出土しています。この土地にそんな昔から人が暮らしていたなんて驚きです。この辺りは江戸時代の初めまでかなり起伏が残っていたようですが、武家屋敷や町屋を作るために地面が均されて、今のように平らになりました。
私たちは新宿駅東南口の下の広場から出発し、甲州街道の高架道路の下を通り抜けて新宿ミライナタワーの前に出ました。かつて玉川上水が甲州街道と並行して流れていましたから、ここで玉川上水の流れを渡ったことになります。「推定谷1」は、先に述べたように甲州街道の高架下辺りから始まります。発掘調査によると、この場所の等高線を昔に遡って調べたところが、旧石器時代は新宿ミライナタワーの土地が東に下がっており、向かい側のザラの土地が西に下がっていることが分かりました。両者の傾きを考え併せると、この場所に南北に延びる谷が通っていたことになります。幅は50m位の細長い谷と推定されます。私たちが歩いた道路は、ちょうど南北に走るビルの谷間を通っていて、昔の谷や川岸を歩いているような気分になりました。
|
 千駄ヶ谷5丁目遺跡から出土したナイフ形石器,掻器,抉入(えぐりいり)石器など旧石器時代の遺物。素材は黒曜石、ガラス質安山岩。サイズは上左2点が長軸3.66cmと4.06㎝。渋谷区『図説渋谷区史』より。 |
 旧石器時代末期の尖頭器(ヤリの先端部)の出土状況。安山岩 で製作されている。出土場所は左と同じ。出典は左記。 |
|
新宿ミライナタワーと新宿高島屋がある高台からは、旧石器時代や縄文時代の遺跡・遺物がたくさん出土しています。またミライナタワーの東側の縁には湧水の跡も発見されており、この辺りに川や池があったことが考えられますから、古代人にとって暮らしやすい場所だったのでしょう。高島屋の下の土地からは縄文時代の「陥し穴」が6カ所も発見されました。川に水を飲みにきたイノシシやシカを捕まえる仕掛けです。「落し穴」ではなく「陥し穴」というのがミソですね。なお、古墳時代以後は江戸時代までの1000年以上の間、この辺りに人が住んでいたことを示す遺物や遺跡はないそうです。この土地は沼や湿地が多いため稲作に適さなかったのかもしれません。
「推定谷1」は高島屋の前で東に大きくカーブして新宿御苑に向かっていました。谷間を流れる渋谷川も谷の地形に沿って大きく曲がっていたのでしょう。私たちが川の流れをイメージした場所はちょうど新宿区と渋谷区の境界線になっていて、道路に渋谷区の標識が立っていました。大昔の川のルートが現代の区界と同じなんて、偶然とは思いますが不思議ですね。
|
<「推定谷2」―日本製粉本社ビル跡地の建設現場から環状5の1号線の工事現場へ>
 |
「推定谷2」はJR線路内に始まり、日本製粉本社ビル跡地の建設現場を通って新宿御苑に向かった。 |
|
高島屋を通り過ぎて明治通りを南に数十メートル歩くと、右側にローソンがあり、その先に日本製粉本社ビル跡地の大きな建設現場が見えました。「推定谷1」が北から南に向かっているのに対して、「推定谷2」は西から東に向かっています。「推定谷2」の場所の目印になる施設を述べると、西のJR線路内に始まり、日本製粉本社ビル跡地の建設現場を通って明治通りを横切り、大きな駐車場と環状5の1号線(明治通りバイパス)工事現場を抜けて、東の新宿御苑に届いて終わります。発掘調査によると幅約50mの東西に細長い谷です。 |
 「推定谷2」の東側にある白い塀の駐車場。その奥に新宿御苑の森が見える。 |
 白い塀の駐車場の中に入る。谷は右(東)側にある新宿御苑に向かう。 |
|
私たちは「推定谷2」に沿って明治通りを左(東)に横断し、少し南に歩いてファミリーマートの角を左(東)に曲がりました。道の突き当りには駐車場の白い塀があり、その奥に新宿御苑の緑の木々が見えました。「推定谷2」の谷間を流れた川は、この道の少し北側を通っていたと思われます。道を通り抜けて駐車場に出ると、「こんなところを行くの?」「駐車場が少し傾斜しているぞ」などの声が聞こえました。歩いてきた道を振り返ると、新宿御苑に向かって地面が緩やかに下がっていました。 |
 |
「推定谷2」の流れは環状5の1号線の工事現場から「D区埋没谷」(図の右塀裏の赤丸部分)を通って新宿御苑の土地に入った。(岡本様撮影) |
|
原初の渋谷川はこの谷間から新宿御苑に入りましたが、その地点は発掘の地図によるとちょうど新宿御苑のブロック塀と工事現場のフェンスの境目でした。そこで後に御苑の中から「推定谷2」の東端の様子を確認することにしました。この辺りは駐車場と工事現場ですが、ここに幅50mの谷と川の流れがあった思うとイメージが膨らみます。
<「推定谷3」―新宿高校グラウンドと縄文竪穴住居跡>
駐車場の道沿いのフェンスから北側を見ると、環状5の1号線の工事現場が新宿御苑と新宿高校グラウンドの間を長く伸びて甲州街道の方につながっていました。その間には縄文古代住居跡や旧石器の発掘場所、「推定谷3」、「F区埋没谷」があります。その真上を通りたいのはやまやまですが、道路工事で入れません。そこで私たちは新宿高校グラウンドの西側の縁に沿って北に向かい、グラウンドの西門まで歩きました。
|
 新宿高校のグラウンド発掘調査地域。環状5の1号線の工事現場が新宿高校グラウンドの南端(D区埋没谷近く)から北東に伸びており、そこから遺跡、遺物、埋没谷などが発掘された。 |
 西門近くのネット越しに見た新宿高校のグラウンド。その奥は工事現場と新宿御苑。グラウンドの左(北)側には「推定谷3」(図の茶色のライン辺りまで)があり、新宿駅方面からの流れと天龍寺方面からの流れが合流して新宿御苑に向かっていた。写真左端の水色の点線は谷間を流れる川のイメージ。 |
|
地図から見てグラウンドの左側(北)3分の1位が「推定谷3」です。この場所で「推定谷1(新宿方面)」からの流れと「埋没支谷(天龍寺方面)」からの流れの2つの川が合流し、幅100mに及ぶ大きな谷を形成していました。その近くには昭和の頃まで、池もあったということでした。また合流点にある「F区埋没谷」には7mの沖積粘土層(主に海や河川の年度が堆積した地層)が積もっており、発掘の際には驚きの報告がなされました。地下の湧水が大量に出てきて発掘を中止せざるを得なかったというのです。発掘報告書には「地下に川が流れているが如くである」と記されていました。おそらくはこの辺りに昔からの水の道があり、その〝地下水脈〟が伏流水となって生きていて、一気に湧き出したのでしょう。 グラウンドの先の環状5の1号線の発掘現場からは、縄文竪穴住居が3軒と旧石器時代のナイフ形石器などがたくさん見つかりました。発掘調査の報告書(『千駄ヶ谷大谷戸遺跡 第3地点』2016年)によると、この谷の南側から出土した3号住居の様子から、縄文時代には「推定谷3」はまだ埋まっていないで、谷間には川が流れていたことが分かりました(「新宿駅東南地域の発掘調査から-渋谷川2万年をイメージする」参照)。この地の縄文人たちは、川の近くに住んで魚を獲ったり川に集まった動物を捕まえたりしながら暮らしていたのでしょう。
|
 「3号住居」(4000年-5000年前)『千駄ヶ谷大谷戸遺跡(環状第5の1号線地区)』。 |
 新宿の縄文人(市谷加賀町)の復元。新宿歴史博物館特別展より。 |
|
新宿歴史博物館の資料によると、市谷加賀町の縄文竪穴住居には約5000年前に右上の写真のような顔をした縄文人が住んでいました。ツアーの参加者の方に写真を見せたところが、「想像でしょ?」と聞かれましたが、このモデルは発掘された縄文人の頭蓋骨に皮膚を精巧にかぶせて作ったもので、本物にかなり近いと思われます。お殿様のうりざね顔とは対照的で、自然や外敵と戦って生きていた縄文人の力強さが感じられます。とくに顎の骨が発達しており、おそらく硬い木の実や骨付きの肉をバリバリと噛んで食べていたのでしょう。 |
 「第3図E,F区の基本層序」『千駄ヶ谷大谷戸遺跡(環状第5の1号線地区)』より。(右図も同じ) |
 |
|
左の図は発掘調査の地区(新宿高校グラウンドの先の環状5の1号線の発掘現場)で、上半分 (白)は埋没谷、下半分(斜線)が高台です。図中の番号4は旧石器の集中地区で、大量の遺物が出土した場所です。8は谷に向かう斜面で、縄文竪穴住居や土器が出土しました。5と6は左図のボーリング調査の場所です。右の図は左図の5と6の地層を模式化したもので柱状図と呼ばれています。5の上層がローム層(火山灰や塵)であるのに対し、6の上層は沖積粘土層(川の土砂等)で7mほど堆積しています。人々の生活の場であった高台とその近傍の川が流れていた深い谷の存在が裏付けられています。 話はツアーに戻りますが、私たちはグラウンドの西門の先を左(西)に曲がり、いったん明治通りに出て北に50~60mほど歩き、セブンイレブン(新宿4丁目3-12)の角を右(東)に曲がりました。そこは緩やかな下りの坂道で、「推定谷1(高島屋前)」からの流れはこの道の近くを通って「推定谷3」へ向かったと考えられます。右下の写真はその坂道ですが、この坂を下り切った所が「推定谷3」の北西の隅でした。そこにある住宅の隙間からグラウンドの方を覗きこむと、奥は雑草が生えた空地になっているようで、少し離れて新宿御苑の森が見えました。 |
 明治通りのセブンから新宿御苑の方に向かう緩やかな坂道。高島屋の前を東に曲がった「推定谷1」はこの辺りで「推定谷3」に繋がっていた。点線は渋谷川支流のイメージ。 |
 写真は「推定谷3」の北西の隅に向かう坂道。右手の奥に谷間が伸びるが、住宅街のため入ることができない。 |
|
<新宿高校「朝陽同窓会」を訪問:「推定谷3」の上に立って> 「推定谷3」の発掘の場所は住宅や新宿高校のグラウンドの奥にあるため、ツアー当日に行くことができませんでした。それが残念で、後日(7月末)に新宿高校に連絡して事情を説明したところ、新宿高校「朝陽同窓会」の吉村様のご好意でグラウンドの中を見せていただけることになりました。夏の朝、気持ちも新たに校舎を通り抜けて奥のグラウンドに入ると、運動をしていた十数名の生徒さんが元気よく挨拶をしてくれました。東側の塀に沿って南の端までグラウンドを200mほど歩きました。道路工事の塀がびっしりと張られてその奥は何も見えませんでしたが、この土地の下に幅100mもの大きな谷があり、その谷間を旧石器時代から原初の渋谷川が流れ、斜面には縄文人が竪穴住居で暮らしていたのです。 |
 新宿高校初代校舎とプールの模型。1922年建築の鉄筋コンクリート造り2階建て。敷地の右端からグラウンドへと続いていた。 |
 新宿高校グラウンドの南側から撮影。約3分の1(茶色のラインより上)が「推定谷3」。 |
 環状5の1号線の工事現場。新宿高校側から南を眺める。左側(東)が新宿御苑。 |
 同5の1号線の「D区埋没谷」近く。 |
|
<「埋没支谷」の跡を辿って天龍寺「心字池」へ> 私たちは「推定谷3」から離れ、北の天龍寺に向かう小道に入りました。発掘調査の資料(*)によれば、この道にほぼ沿う形で北から南に走る「埋没支谷」が発見されており、原初の渋谷川支流もこの辺りを流れて「推定谷3」に向かったと考えられます。なだらかな上りの坂道を北に向かって進むと、左側に天龍寺の墓地やマンションが、右側に旅館や住宅が続いていました。 |
 |
天龍寺に向かう上りの坂道。この辺りには「埋没支谷」があり、渋谷川の支流が南に向かっていた。点線は渋谷川のイメージ。 |
(*)東京都埋蔵文化財センター『内藤町遺跡』(2002・3年)。
|
なだらかな上りの坂道を歩き、甲州街道手前の左手にある東急ライト新宿ビルの前まで来ました。このビルの一階部分は細長い屋内駐車場になっていますが、2002年にここで天龍寺の池が発掘されました。「心字池」と呼ばれており、規模は東西19.5m、南北8.5m、深さは最大90cmです。天龍寺のかつての境内の最北端に位置しており、「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」『江戸切絵図』に描かれた天龍寺の池とは違う場所のようです。 |
 |
甲州街道の側から撮影。道路の右に東急ライト新宿ビルの屋内駐車場入口(黒い部分)。この駐車場の中に「心字池」があった。 |
|
(*)オリックス・リアルエステート株式会社・他『天龍寺跡』(2004年) |
 「内藤新宿千駄ヶ谷辺図(部分)」『江戸切絵 図』(1862)。渋谷川が発しているとされる天龍 寺の池は確認されていない。東京都中央図書館 所蔵。 |
 2002年に発掘された天龍寺北端の「心字池」。水色の点線は池の輪郭。池から江戸時代や明治初期の遺物が出土した。『天龍寺跡』(*)より。 |
|
江戸城南西の「裏鬼門」にある天龍寺には、徳川家鎮守の役割が与えられていました。境内には今も立派な鐘楼がありますが、これを「時の鐘」またの名を「追い出しの鐘」と呼んでいました。本来は江戸城に登城する武士が時を知るための鐘でしたが、「内藤新宿」が元禄12年(1699)に開設されて以降は、遊廓を訪れた客に帰る時刻を告げる「追出しの鐘」としても役立ったそうです。同じ鐘の音が対照的な刻を告げていたとは…。 |
 水琴窟が作られた天龍寺中庭の井戸。 |
 天龍寺の「時の鐘」の鐘楼。 |
| 天龍寺に別れを告げて明治通りに出ると、北の方に百貨店の伊勢丹が見えました。伊勢丹の交差点は江戸時代の「追分」で、「内藤新宿」はそこから始まり甲州街道(現在の新宿通り)に沿って四谷大木戸まで続いていました。今も昔も繁華な街並みです。私たちは明治通りを右(東)に曲がって玉川上水が流れていた甲州街道に再び入り、少し歩いて新宿高校の前に出ました。
<旭橋(下水橋)と渋谷川の流れ> 新宿高校の道路沿いの校地には、寛政7年(1795)玉川上水に架設された「旭橋」の石樋が展示してあります。ふだんは校内に入って見せていただけるのですが、この日は日曜であったため、歩道からフェンス越しに石樋を眺めることになりました。「旭橋」は人が渡る橋ではなく、内藤新宿の下水や雨水を千駄ヶ谷方面に流すために玉川上水に架けた石樋で、直径100㎝、長さ3.4mほどの分厚い堂々たるものです。この橋について詳しい方もいらして、「石樋になる前は木樋だったよ」などとフェンスの外で話が盛り上がりました。この堅固な樋ならば汚水が玉川上水に漏れ出す心配はないと思いますが、当時の悩みは別のところにあったようです。石樋の脇の説明板には、「(前略)上水の水質保護のために機能した石樋から、下水は新宿御苑に沿って掘られた下水溝を通って千駄ヶ谷方面へ流れていく。しかし大雨や豪雨の時は排水が間に合わず、土地の低い天龍寺の裏あたりから出水し、旭町(現、新宿4丁目)一帯は水びたしになった。(後略)」と書かれていました。
新宿高校の敷地は「埋没支谷」の東側にあり、大正12年まで新宿御苑の中の湿地帯の一部でした。武英雄『内藤新宿昭和史』には「校舎は大正天皇から下賜された新宿御苑の旭町(現新宿4丁目)寄りの宮内省世伝御料地の一角で、カエルの鳴くどぶ池に建設されることになった。秋雨の中で立柱祭を営み、式後工事の安全祈願に各自石を投入して礎石とし、願を込めたという」と書かれています。その後、校庭の縁を現甲州街道が通過することになり、校舎は南側の渋谷区の敷地(現在のグラウンド)に移転しましたが、現在は校舎を立て替えて再び北側の新宿区に戻っています。水資源が豊かな場所でしたが、最初に校舎を建築する時には色々とご苦労があったようです。 |
 |
内藤宿「當時之形」。新宿区教育委員会『地図で見る新宿区の移り変わり・四谷編』より。玉川上水に架けられた石樋と下水のルートが描かれている。 |
|
ところで、新宿区教育委員会『地図で見る新宿区の移り変わり・四谷編』の中に、先の旭橋の下水橋を通っていた細い川のルートが出ていました。新宿の学芸員の方に伺ったところ、絵図は19世紀前半のもので、『御府内沿革図書』の中の資料です。玉川上水の北側にあった「内藤新宿年貢町屋」辺りの下水や雨水が、玉川上水に架かる旭橋を通って天龍寺と武家屋敷の間を南下し、千駄ヶ谷村の田んぼの縁を流れていく様子が描かれています。江戸時代には、内藤新宿から流れてくる下水や雨水も渋谷川の水源の一つになっていたようです。 |
 内藤新宿の宿場の模型。新宿歴史博物館。左側(北)の 人通りの多い道が甲州街道。町屋の右側(南)に玉川上水が流れ、上水の脇に桜並木がある。 |
 上は広重「玉川堤の桜」で、この場所の風景を描いたものとされるが、創作との説もある。東京都中央図書館所蔵。 |
|
|
 |
現在の甲州街道を歩いて新宿御苑に向かった。青い線は四谷大木戸まで |
|
これまで見てきた「推定谷3」や「推定谷2」の渋谷川の流れは、どのような形で新宿御苑の中に流れ込んでいたのでしょうか。新宿御苑の「新宿門」を入ると道が3本に分かれていましたので、御苑の縁をめぐる右側(西)の道に入り、緩やかなカーブの道を森の方に向かいました。この道は少しずつ下がっていて、谷に降りていくことを感じさせます。途中の広々とした敷地にヒマラヤシーダやモミジバスズカケノキなどの大きな木々が生えて見事でした。それらの前を通り、「推定谷3」の「F区埋没谷」の方へと歩きました。 |
 新宿御苑の看板より。新宿門①より入り、280m地点②で「推定谷3」の「F区埋没谷」、380m地点③で「D区埋没谷」を通り、480m地点④を左に曲がって「上の池」に着いた。 新宿御苑の看板より。新宿門①より入り、280m地点②で「推定谷3」の「F区埋没谷」、380m地点③で「D区埋没谷」を通り、480m地点④を左に曲がって「上の池」に着いた。 |
|
|
どなたか「この辺はふだん来たことがない場所だな。ラクウショウも初めてだ」と言っていました。生物学がご専門の鈴木先生にラクウショウについて伺うと、「地面の中に水分が多いいと気根が地上に出てくるのですよ。地中で呼吸ができないからです。見事な気根です」と。今でも水分をたっぷり含んだ土壌なのです。御苑の塀に沿った道はどんどん低くなっていきます。 |
 |
ラクウショウの気根(呼吸根)の群生。気 |
|
いちばん低くなった辺りに渋谷川の水路であったと思われる石組みがありました。「新宿門から280m」の標識の近くです。地図を見ると、そこはちょうど「推定谷3」の「F区埋没谷」が発掘された辺りでした。新宿御苑の管理事務所の方によると、「平成に入ったころは天龍寺の方からの湧水が流れ込んでいた」とのことですが、その場所はちょうどこの辺りでした。先に述べたように、御苑の西側は環状5の1号線の工事を行っています。ふつうの道路工事ならば地下水の流れが止まることはなさそうですが、この道路は片側の車道が地下トンネルとなるため、かなり深くまで掘り下げており、地下水の流れが遮断されてしまったのでしょう。右の写真は、下見の時にこの場所から見えた新宿ミライナタワーで、原初の渋谷川が「推定谷1」から「推定谷3」へと流れて来た方角です。ツアーはその約2週間後でしたが、その時は木々が生い茂って何も見えなくなっていました。
|
 御苑の北西の縁に残る渋谷川の水路跡の石組み(「F区埋没谷」付近)。 |
 川の流れをさかのぼる方向に新宿ミライナタワーが見える。 |
|
「F区埋没谷」の石組みを見た後、ちょっと寄り道して「W1」と看板に書かれた小道に入りました。少し行くと道の脇に「小川」が流れていました。幅2m足らずの小さな川が薄暗い道の脇に沿って流れています。これは何? もう天龍寺からの流れは入っていないはずですが…。道の標高はおよそ31mと低いので、おそらくその辺りの水が集まって自然の流れになっているのでしょう。地図上に「F区埋没谷」からの流れを描いて「上の池」まで結んでみると、ちょうどこの辺りが昔の川の場所のように思えました。昔の渋谷川の姿を見ているような気持になって、皆で喜んで記念写真を撮りました。
|
 |
道のすぐ近くに「小川」が!まるで昔の渋谷川のよう。 |
|
小川の小道から元の道に戻り、御苑の塀に沿って「D区埋没谷」に向かいました。先ほどの「推定谷2」の東の端に当たる場所(古いブロックの塀と新しい工事用フェンスの境)で、近くに380m地点の標識がありました。谷や川の痕跡がないか探したのですが、何も見つかりません。この土地の標高も川の流れをイメージさせるほど低くありません。後に新宿御苑の管理事務所の方に伺ったところ、「380mの標識の辺りは「母と子の森」というゾーンで、平成14年から17年にかけて新しく造成したものなので、以前の地形は残っていません」とのことでした。「推定谷2」は幅50mと小さかったため、工事で完全に埋められてしまったのかもしれません。 |
 昔の渋谷川は姿を変えて現在の「上の池」に。(岡本様撮影) |
|
|
次に480mの標識がある所まで進み、左に曲がってW4の小道に入り、薄暗い道をしばらく歩きました。すると突然周りが明るくなって、右手(南)に広々とした「上の池」が現れました。ゆったりと太鼓橋がかかり、その左右に池が広がっています。HPの「後編」で詳しく紹介しますが、「上の池」の場所には明治の初めまで渋谷川が流れていました。明治12年にこの地が「植物御苑」に改造された時、渋谷川の一部は皇室御料の「鴨池」に作り替えられました。現在の「上の池」はこの「鴨池」を前身とするもので、姿を変えた渋谷川と言うこともできます。 「推定谷2」と「推定谷3」からの渋谷川の流れを現代の地図に描いてみると、ちょうど「上の池」の太鼓橋の辺りで2つが合流するように見えます。約2万年前には渋谷川の2つの支流がこの辺りで一つになり、東の方に流れていたのでしょう。
|
 |
小川に沿う小道で皆で記念写真。
|
|
<「前編」の終わりに> 今回のツアーの報告「前編」では、新宿駅東南部の幾つかの谷間から始まった原初の渋谷川支流が、新宿御苑の「上の池」の辺りで一つの流れにまとまるまでをたどりました。約2万年前にこの地にあった推定谷や支流の跡を探るため、大都会の一角を右に左にと歩き、最後は合流点の新宿御苑「上の池」に着きました。いつも見慣れたビル街ですが、発掘調査の光を当てると、そこは渋谷川に関する新しい発見で一杯でした。発掘調査について色々とご指導を下さった渋谷区郷土博物館・文学館の粕谷先生、また貴重な資料や情報をご提供下さった新宿歴史博物館の今野先生に厚くお礼申し上げます。 「後編」では、「上の池」から新宿御苑の外縁をたどって「大木戸門」まで歩き、その後はもう一すじの渋谷川(玉川上水の余水)が流れていた内藤町を通り、新国立競技場の建設に沸く終着点の千駄ヶ谷に向かいます。その道筋で、江戸、明治、昭和と姿を大きく変えてきた渋谷川の形を探る予定です。話題が盛りだくさんで、時に脱線するかもしれませんが、よろしくご期待下さい。
(注)『千駄ヶ谷5丁目遺跡3次調査』第1章第4節(基本層序、p10)には「調査区全域に広く遺存するV層上面の高さを基準に旧地形の等高線図を推計したのが第8図である。ここでは平坦地形をなす調査区西側から東側に1.4m下る緩やかな傾斜が見られる。加えて本調査地点の東側に位置する新宿4丁目遺跡では、Ⅲ層~Ⅶ層の堆積から、調査区の西側に西ないし南西への傾斜が見られ、東西幅約50mの谷地形を推定することができる」とある。 <参考資料> |
2018.5.9

| 「前編」では、新宿駅東南口の広場から天龍寺を経て新宿御苑「上の池」まで歩き、約2万年にわたる渋谷川の歴史をたどりました。「後編」では、渋谷川を用いて作られた「上の池」「中の池」「下の池」を順に歩き、また新宿御苑の前身となった高遠藩内藤家下屋敷の庭園を今に伝える玉藻池を訪れます。次にお隣の内藤町に入って、玉川上水の余水から生まれたもう一すじの渋谷川と水車の跡を探ります。その後、JR線路脇の大番児童遊園に出て、渋谷川上流の二すじの流れが合流する所を確かめ、新たに親水空間が予定されている新国立競技場の前まで歩いてツアーを終えます。下の図は歩くルートを地図に書き入れたものです。話題満載ですので楽しんでお読みください。 |
 |
||
|
渋谷川上流の地域。茶色の線は「後編」の歩くルートで、道程は約3㎞。かつてこの地域には、西の天龍寺方面からと北の玉川上水から二すじの渋谷川が流れていた。これらの川は大番児童遊園の近くで合流し、JR中央線の土手を潜り抜け、国立競技場の前を通って渋谷へと向かっていた。図の上を東西に流れるのは玉川上水。地図はGoogleマップ。 |
||
|
<池上典「高遠藩四谷下屋敷再現図」に描かれた渋谷川の流れ> |
 新宿御苑の「上の池」。奥にかかる橋は「太鼓橋」。水面に映る木々の緑が美しい。 |
|
新宿御苑の「上の池」に着いた私たちは、池に架かる太鼓橋を渡り、左右に大きく広がる池やこんもりと茂った林の緑を眺めて楽しみました。池の周りには丸く刈りこまれたサツキが植えられ、所々で赤い花が咲いています。こんなに優雅な「上の池」が、明治39年(1906)に新宿御苑になるまでは鴨の飼育場であり、その前は池ではなくて渋谷川であったと話したところ、「ここが渋谷川だったなんて」と驚きの声が上がりました。そこで、この土地の幕末の様子を描いた「高遠藩四谷下屋敷再現図」(以下「再現図」)を皆さんにお見せしました。この絵図は高遠出身のデザイナー池上典氏の作品で、新宿御苑の前身である信州高遠藩・内藤家下屋敷とその周りの景色を描いています。新宿歴史博物館の許可を得て電子データから大型のA3用紙に印刷し、皆さんにお見せしました。伊那市立高遠町歴史博物館には何畳分もある作品が壁に飾られており、高遠町を訪れて実際に拝見しましたが、その大きさと細密な描写に圧倒されました。 |
 |
|
池上典氏「高遠藩四谷下屋敷再現図」。新宿歴史博物館所蔵(無断転載禁)。図は東から眺めた内藤家下屋敷の鳥瞰図。西の彼方に(図の上)天龍寺らしき屋根が見える。その辺りから渋谷川の流れが始まり、屋敷の南の縁(左)を通って東南(左下)の千駄ヶ谷に向かっている。屋敷の北(右)を東西(上下)に走るのが玉川上水と甲州街道で、東北の角(右下)が四谷大木戸の関所。屋敷の東(下)には渋谷川(玉川上水の余水)が北から南(右から左)に流れている。 |
|
ところで、「これは想像図なんでしょう?」という質問もありましたが、単なる想像図ではありません。池上氏は「再現図は問題提起の一つであると思って制作しています」と謙遜して述べておられますが、作成には多くの古文書や図録が用いられています。屋敷の配置は嘉永4年の大火後の「江戸藩邸図」等に基づいており、町並みは明治初期に外国人カメラマンが撮った愛宕山からの俯瞰写真を参考にしています。内藤家下屋敷の土地の用途は「新宿下屋敷図絵」(高遠町歴史博物館所蔵)を基本にしていると思われます。この図は敷地内を用途別に色分けしたものですが、細かいことがよく分かりませんでした。ツアーの準備をしていた時に偶然、高遠町歴史博物館に「再現図」が展示されていることを知って見学したのですが、イマジネーションが豊かで、しかもきちんと資料に基づいて再現されていることに感服しました。再現の方法については、池上典「再現図の制作にあたり」『信州高遠藩・歴史と文化』を参照して下さい(注1)。 |
|
<新宿御苑と渋谷川の歴史①―高遠藩・内藤家下屋敷の時代> 「上の池」から歩き始める前に、新宿御苑と渋谷川の歴史的な繋がりについて述べます。現在の新宿御苑のある一帯は、江戸から明治中頃にかけて土地の改造が繰り返されたため、その過程でこの地を流れていた渋谷川も大きく姿を変えて行きました。渋谷川の変化の跡を、江戸時代から現代に至るまで簡単にたどります。 まず江戸時代ですが、この地には後の新宿御苑の前身となる高遠藩内藤家の下屋敷がありました。天正18年に徳川家康が豊臣秀吉の命で関東に移封された時、家臣の内藤清成は、旧北条氏の残党に備えるため国府路(甲州街道)と鎌倉街道の交わる土地(現在の新宿御苑周辺)に布陣し、尾根に遠見やぐらを築いて警護しました。家康の入府後は、江戸城の西方を固める役割があったようで、布陣していた広大な土地をそのまま屋敷地として拝領しました。「馬で一息に回れる土地を与えよう」という家康の言葉に従って、清成は駿馬に跨り、北は大久保、西は代々木、南は千駄ヶ谷、東は四谷と走り回ったところが、馬が疲れ果てて死んでしまい、今の多武峯内藤神社に祀られているという伝承が残されています。家康の家臣で清成の同僚でもあった青山忠成(屋敷は現在の港区青山)にも似たような話があります。この二人には家康の信頼がとても厚かったのでしょう。 世の中が平和になり、江戸の町が発展して武家の屋敷地が足りなくなると、内藤家は数回に渡って幕府に土地を返納し、現在の新宿御苑と東隣りの内藤町の土地が残りました。玉川上水や甲州街道の土地も元は内藤家の敷地でした。この時代に渋谷川は、内藤家下屋敷の中にある田畑の灌漑に使われていました。その水源は天龍寺方面の湧水や雨水、そして内藤新宿から石樋で玉川上水を渡ってくる下水の流れでした。下水とはいっても当時はし尿を川に捨てる習慣がありませんので、主に雨水です。なお『江戸切絵図』(1862)の中の「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」には渋谷川の水源として天龍寺の池が描かれていますが、「前編」で述べたように、この池の存在は確かめられていません。 |
 |
内藤宿「當時之形」。新宿区教育委員会『地図で見る新宿区の移り変わり・四谷編』より。図の左端には、内藤新宿から南下して渋谷川に流れ込んだと考えられる下水溝が描かれている。流れの最上部(左上)に玉川上水に架けられた石樋が見える。(詳しくは「前編」の説明を参照) |
|
<新宿御苑と渋谷川の歴史②-明治の「内藤新宿試験場」の時代> 明治時代になると、時の政府は内藤家下屋敷を隣接した農地と共に買い入れました。金井利彦『新宿御苑』によると、土地の面積は内藤家の邸宅が9万8千坪、周りの土地が8万坪の合計17万8千坪(59ヘクタール弱)で、ここに明治5年に牧畜や園芸のための「内藤新宿試験場」を設けました(注2)。そして、渋谷川の流域に作られた田畑で植物の研究や品種改良を行いました。試験場にはヒマラヤシダ、ラクウショウなどの造園樹木が日本で初めて植えられ、リンゴやオリーブも試作されました。政府は内務卿大久保利通の下で殖産興業政策を推し進め、植物試験場や農業博物館を作り、ここで育てた西洋や日本の品種を地方に送って普及させました。今は有名な青森のリンゴや小豆島のオリーブもこの試験場で作られました。渋谷川が明治の農業の近代化と関わりがあったなんて意外ですね。 |
 |
 |
|
| 明治時代の殖産興業政策を進めた大久保利通。(Wikipediaより) |
小豆島のオリーブ。 |
<新宿御苑と渋谷川の歴史③―皇室の「新宿植物御苑」の時代>
 |
 |
|
| 福羽逸人(ふくば はやと)。明治時代の農学者、造園家。彼は新宿試験場、新宿植物御苑、新宿御苑の時代を通して植物の改良に生涯を捧げた。 | 明治41年当時の温室。温室は明治半ばの植物御苑の時代に完成し、洋ランから果樹にいたるまでが栽培されていた。(環境省HP『新宿御苑』より。左の写真も同じ。無断転載禁) |
|
明治12年(1879)になると、内藤新宿試験場の土地は皇室に献上され、皇室に食材や草花を供する「新宿植物御苑」になりました。この時に活躍したのが農学者の福羽逸人(ふくば・はやと)です。果樹、野菜、花の栽培、温室ブドウ園の創設、メロンの試作など、日本の果樹や園芸の改良、作出に大きく貢献しました。高級促成イチゴ「福羽苺」は日本で最初のイチゴで、現在の改良品種のほとんどがそのDNAを受け継いでいるそうです。福羽はシクラメン、フリージアなどの栽培も手掛け、それらを民間に普及させました。渋谷川はこの時代も植物の栽培に役立っていました。明治13年には川の流れを用いて「鴨池」が作られましたが、これが今日の「上の池」の始まりです。「鴨池」については後に触れます。 <新宿御苑と渋谷川の歴史④-皇室庭園「新宿御苑」と戦後の「国民公園」> 明治35年(1902)になると「新宿植物御苑」の改装工事が始まり、39年(1906)に現在の新宿御苑が完成しました。近代日本の国家行事を行うための皇室庭園が初めて誕生したのです。デザインはベルサイユ園芸学校の教授アンリ・マルチネに頼み、5年をかけて豪華な近代庭園に生まれ変わりました。その過程で、この地を流れていた渋谷川は庭園の池となって姿を消しました。時は流れて戦後のことですが、新宿御苑は一時的に都立農業科学講習所の用地となりましたが、昭和25年(1950)に正式に「国民公園」として復活しました。新宿御苑の使い方を巡っては、その後も遊園地化などさまざまな試みがあったようですが、桜などの庭木や温室栽培もだんだん増えて、昭和33年頃から国民の庭として今の姿になりました。新宿御苑が作られる時に渋谷川が消えていったのは残念ですが、数珠玉のように連なる美しい池に姿を変えて生き残ったとも言えます。もし植物御苑のままであったならば、近代化のうねりの中で官庁か軍用施設、あるいは民間に払い下げられ、暗渠になったり埋められていたかもしれません。 |
 |
|
牧大次郎「新宿御苑の庭園デザインと設計者アンリ・マルチネ」『日本庭園学会誌』2007 巻 (2007) 17 号より。1908年の地図に新宿御苑のデザイン構成を描きこんだもの。アンリ・マルチネの設計図には2階建てルネッサンス風宮殿が予定されていたが、財政的理由で実現しなかったという。設計図は戦災で焼失した。青色は渋谷川を用いて作られた新宿御苑の池(彩色と文字は筆者)。「F区埋没谷」と「上の池」の間にある細長い池は後に埋められて現在はない。 |
|
<「上の池」から旧御涼亭へ> 新宿御苑と渋谷川の歴史はこれぐらいにして、「上の池」に話を戻します。「上の池」の始まりは、先ほども述べたように皇室の「新宿植物御苑」の時代に造られた「鴨池」です。前掲『新宿御苑』には、「鴨池は、新宿千駄ヶ谷の境の谷筋の西部に地形を利用して造成され、現在の日本庭園の元となった」とあります。ここで「谷筋」とは渋谷川が流れていた谷間で、その西方に窪地を造成して池を作ったということでしょう。この池は鴨の飼育場に使われました。野村敏雄『新宿うら町おもてまち』(1993)によると、当時内藤新宿の周辺には鴨場が4つありました。「(前略)新宿にも鴨の群れがつぎつぎと飛んできた時代があった。明治のころである。(中略)、新宿御苑の鴨池だけでも毎日5,6千羽、時には1万羽を越える鴨が下りたり飛び立ったりするので、鴨は新宿の秋の名物とされていた」。鴨が大挙して飛び立つ時の鳴き声が聞こえて来るようです。明治時代になってから鴨が押し寄せるようになったとは考えられません。この辺りは昔から湿地帯でしたから、たくさんの鴨が集まるような土地柄だったのでしょう。 明治20年「東京実測図」には、人の顔のような奇妙な形をした「鴨池」が描かれています。池の中に目玉のような二つの島があり、池の周りには髭のような16本の水路が外に伸びています。この形には訳があって、同書によると「この鴨池から引き掘りと称する水路へ鴨を誘い出し、飛び立ったところを網ですくい取ったり鷹を放ってとらえる」とのことです。ちょっとかわいそうですが、鴨を捕まえる伝統的な方法なのでしょう。 |
 |
 |
|
| 明治20年「東京実測図」の部分図。図の左が鴨池。水色が玉川上水と渋谷川。緑が新宿植物御苑敷地。 | 鴨池の拡大図。人の顔のような形は鴨を捕まえるための仕掛け。 |
| さて、私たちは太鼓橋を渡った後、「上の池」の南側の道を水辺に沿って歩き出しました。「上の池」を過ぎると水面が川のように細くなりましたが、水が下手(東)に流れている様子はありません。しばらく歩いて小池の手前を左(北側)に回って進むと、やや大きな池の前に出て、対岸にエキゾチックな建物が見えました。新宿御苑でいちばん眺めが良いと言われる場所に建つ旧御涼邸で、昭和2年に昭和天皇のご成婚を祝って台湾在住の日本人有志から贈られたものです。屋根が尖っているのは中国南方(福建省)の様式だそうですが、周りの日本庭園と違和感なく調和していました。 |
 |
 |
|
| 台湾在住の日本人から昭和天皇に贈られた旧御涼邸。赤い尖った屋根が緑に映えて美しい。 | 旧御涼邸から眺めた池と周りの景色。御苑の中の見どころだ。 |
|
旧御涼邸の所で再び池の南側の道に入って「中の池」に向かいました。すぐ先に十字路がありましたが、ここを右に曲がって道なりに南に歩くと千駄ヶ谷門があります。この日は時間の都合で行きませんでしたが、千駄ヶ谷門を出て右(西)に300mぐらい行った所に江戸時代の儒学者新井白石の「終焉の地」があります。享保2年(1717)頃の話ですが、幕府の実力者新井白石は新将軍吉宗に遠ざけられて失脚し、小川町の屋敷も取り上げられて千駄ヶ谷に移り住みました。白石がこの地について述べた下りがあります。「千駄ヶ谷の新居のあたりは「武蔵野」の田園で近くには家はほとんどない。皆麦畑だ。庭に花でも植えて晴天には富士山でも眺めよう」(注3)。文面からのどかな情景が伝わってきますが、白石が田園生活に心癒されて綴ったとは思えません。白石の屋敷は内藤家が元禄10年に幕府に返納した土地で(注4)、当時は建つ家もまばらでしたから、小川町の町並を懐かしんで記したのではないでしょうか。 |
 |
|
新井白石終焉の地(千駄ヶ谷門近く) |
|
ここで、白石の家の北側にあった内藤家下屋敷の様子を見てみましょう。下は先程の「再現図」の部分図で、現在の千駄ヶ谷門近くの様子です。屋敷の南の縁には渋谷川がゆったりと流れ、この辺りで川幅が膨らんでいて自然の流れを感じさせます。川の南には畑と武家屋敷が、北の屋敷内に馬場や田畑が見えます。屋敷の中は田んぼや樹木畑(桑園)が整然と並んでおり、馬場には馬を走らせる武士の姿が見えます。この図は幕末とのことですが、当時の高遠藩は開明君主(頼寧、頼直)の下で藩政改革を進めていましたので、農園の経営や藩士の訓練の様子を描いたものかもしれません。屋敷の周りには武家屋敷がびっしり並んでいますが、白石が住んでいた享保の頃はもっと閑散としていたのでしょう。 |
 |
|
「内藤家下屋敷再現図」の中ほどより少し上(西)の部分図。現在の「中の池」の辺りか。屋敷内には田畑や馬場が整然と配置されている。 |
<「中の池」から「下の池」へ>
 |
 |
|
| 「中の池」の岸辺を歩く人々。池の景色をスケッチ している人を見かけた。 |
池の脇で記念撮影。この日は天気に恵まれました。 |
|
旧御涼邸の先の十字路を過ぎると、左手に「中の池」が広がりました。太陽の光を浴びて水面がキラキラ輝き、右手には芝生広場が開け、何とも言えない開放的な気持ちになります。「御苑の中でこんなところ歩いたことないよ」とおっしゃる方も。休憩所や施設がある池の北側を歩く人が多いのでしょう。「中の池」を見ながらツツジ山の横を通り抜け、「下の池」の脇を通って池尻に着きました。道の周りは灌木から木立に変わり、うっそうとした木々の間から池の水面が見えました。池尻には日本で初めて設置されたフランス製の「模擬橋」が架かっていました。木を模してコンクリートと石で作った橋で、これを輸入した時には橋の組み立てのために3人の技師が付いてきたとか。当時「下の池」の水は、この池尻でしばし渋谷川の姿を取り戻し御苑の外に流れ出ていました。そして、200mぐらい先にある大番児童遊園の手前で、北から流れてきたもう一すじの渋谷川(玉川上水の余水)と合流していました。この合流点には後程行きます。 |
 |
 |
|
| 池尻の木立の間から「下の池」を望む。かつてここに渋谷川が流れていた。 | 「下の池」の水は日本初の模擬橋の下を流れて御苑の外へ。 |
<江戸時代の「玉川園」の面影を残す玉藻池>
 |
 |
|
| 玉藻池の池尻には欄干の付いた橋がない。 |
玉藻池の排水路。池の水は新宿御苑の東側 |
|
さて、私たちは天龍寺方面からの流れといったん別れて、新宿御苑の北にある玉藻池に向かいました。「模擬橋」を渡り、大きなフランス式庭園の横を300mほど北に歩いて小暗い森の中に入ると、左の奥に玉藻池の池尻が見えました。水が流れ出す場所には下の池のような欄干の付いた橋はありません。「ここが玉藻池の池尻で、こちらから池の水が外に流れ出ています」と言ったところが、中学生のK君から「こっちですよ!」と言われ、そちらの方を見ると、道路の下を斜めに流れて数メートル離れた所に池の排水路が見えていました。「その通り。そちらです」とあわてて訂正。K君は今から頼もしいですね。皆で排水路を確かめた後、玉藻池の方に向かいました。この排水路の水は渋谷川(玉川上水の余水)が暗渠になる前は東南に150mぐらい流れてから御苑の外に出て、外苑西通りの池尻橋近くで渋谷川と合流していました。この場所にも後で行きます。 池の左側の道を少し歩くと、「大木戸休憩所へ」と書かれた看板が立っていました。そこの階段を降りると、緑の木々を水面に映した玉藻池が目の前に広がりました。内藤家下屋敷の時代はこの庭は「玉川園」と呼ばれ、江戸の名園の一つに数えられていました。その中心となる玉藻池(魚藻池)は、屋敷の北側を通る玉川上水本流と東側の渋谷川(玉川上水の余水)の両方から水を引いて作られており、「玉川園」という名も玉川上水に因んだものです。明治になると「玉川園」を管理する人がいなくなり、池の水が枯れるほど荒れ果てていたそうですが、後に再現されて昔の面影を今に伝えています。私たちは、池に架かる小橋を渡り、緩やかなスロープを歩いて大木戸休憩所に着きました。休憩所から池の方を見渡すと、森に囲まれた庭園の中に池と灯篭、そして松やツツジが見事に配置され、昔の大名屋敷にタイムスリップしたような気持になりました。 |
 |
 |
|
| 初春の玉藻池。池の小橋を渡ると、その先の高台に大木戸休憩所がある。 | 大木戸休憩所から見た玉藻池の景色(岡本敏之様撮影。) |
|
「玉川園」については、内藤家の3代目当主頼由(よりゆき・1735-1776)が儒臣の中根経世に作らせた『玉川園記』があります。漢文ですのでパスしますが、その大意が前掲『新宿御苑』に述べられていますので、少し長くなりますがご紹介します。「広大だった四谷荘の土地も江戸の家々が隙間もなくなってくるにつれて次第に土地を割愛して以前の3分の1位になっている。それでもなお広い荘は、北にこんこんと玉川上水が流れ、諸門には橋を渡って入る。玉川上水の両脇には松や杉の並木が茂り、あたかも砦のような状況である。その中に美しく大きな玉川園があり、その他は建物と林と肥沃な土地だけだ。」「この庭は一つ一つの木や石に細工を凝らして景色を作り上げた庭ではない。(中略)御先祖が功によって賜ったこの荘園を百余年もかけて次第に修景したもので、政務の余暇に遊び、宴を開いても節度があり、(中略)わが主君がこの庭に遊ばれる時には、荘内の田畑も見回られ、豊凶の様子や農民の苦労を聞かれるので、江戸在府中も高遠の領地を治めておられる時と変わりがない。住民も庭園に入園させてともに楽しませる」(注5) 。「玉川園」は大名家の権勢や富を誇るような庭ではなく、藩主が政務の疲れを癒したり、政道を顧みるための場であったようです。幕末の頃は藩主と領民との繋がりも深かったようで、私が高遠町を訪れた時には、内藤家の当主が今も町を訪れて人々と交流しているという話を聞きました。 |
 |
|
「内藤家下屋敷再現図」の東側。玉藻池は屋敷の北側(右)を流れる玉川上水本流と、玉川上水・水番屋の吐き口から発した渋谷川の流れを引いて作られた。玉藻池の水は屋敷の森の間を抜けて当時の池尻橋(図の左下)の南で渋谷川と合流し、千駄ヶ谷へと向かっていた。 |
|
ここで、先の「再現図」から玉藻池とその周りの土地の様子を確かめましょう。「玉川園」ができた年代は正確には分かりませんが、前掲『信州高遠藩・歴史と文化』によると安永元年(1772)の大火の頃なので(注6)、「再現図」はその90年ぐらい後の姿と考えられます。図の中央に玉藻池を中心とした「玉川園」があり、その北側に藩主の御殿が、南側に馬場か農園が描かれています。屋敷の北側には玉川上水が流れ、その終点に水番屋と吐き口があります。渋谷川(玉川上水の余水)は、ここから発して南に流れ、池尻橋の近くで玉藻池からの流れを併せ、さらに南の千駄ヶ谷へと向かっていました。屋敷の東側には多武峯内藤神社と境内の森が広がっていますが、この地域が現在の内藤町で、後に歩くルートです。
<「水道碑記」と玉川上水・吐き水門からの渋谷川の流れ> 話はツアーに戻ります。大木戸休憩所は涼しい風がそよいで清々しく、しばらくここに留まっていたい気持ちもありましたが、時間も押しているので出発しました。そして、休憩所の北の大木戸門を出て、御苑の北隣にある「水道局新宿営業所」に行きました。大木戸門の前を通る道路には、明治31年(1898)に淀橋浄水場が完成するまでは玉川上水の本流が流れていましたが、その後淀橋浄水場の余水のみとなり、道路が舗装された大正14年(1925)に暗渠となりました。 |
 |
 |
|
| 水道局新宿営業所の裏手にある白いかまぼこ型のフェンス。この中に水門のバルブがある。 | 玉川上水の歴史を説明する新宿区教育委員会の看板。 |
|
私たちは水道局の裏手に入りました。江戸時代はこの地は四谷大木戸と呼ばれ、玉川上水の水番屋があり、そこから玉川上水が地下に入り、石樋・木樋を使って江戸城や大名屋敷、町屋、社寺に上水を配っていました。水番屋の役人は水番屋で上水のゴミや石・泥を取り除き(芥留め)、また水量を調節して地下に流し込み、余分な水は吐き口を通して渋谷川に捨てていました。江戸時代の水番屋の場所に現代の水道局新宿営業所があるのは、この土地の歴史を感じさせますね。ところで、水道局の裏手には左上の写真のような「かまぼこ型」の白いフェンスが立っていて、そこに新宿区教育委員会による玉川上水の説明板が掛かっていました。何も知らないと、この看板を読んだだけで通り過ぎてしまいそうですが、実はこのフェンスの内側に貴重な“お宝”が鎮座しているのです。 |
 |
 |
|
| フェンスの中にあった2つの青いバルブ。中に入れないので、フェンスの上から撮影した。 | 玉川上水跡の吐き水門(昭和36年)。新宿歴史博物館 所蔵。左の写真と同型の2つのバルブ(赤い丸)が見える。 |
|
フェンスの脇の植え込みから中をのぞくと、丸いハンドルが付いた2つの青いバルブのようなものが見えました。左の写真がそれです。実はこの写真を撮る時に苦心談がありました。下見の時ですが、フェンスの中に入って写真を撮ろうとしたところが、どこからか大声がして叱られたのです。辺りを見渡しても誰もいません。やむを得ずフェンスの外から高くカメラをかざして適当にシャッターを押し、運よくファインダーに収まったのがこの写真です。それはともかく、このバルブはレトロないい形をしていますね。おそらく玉川上水の水門の開閉に使われていたものでしょう。右は玉川上水跡の「吐き水門」の写真ですが、よく見ると2つのバルブが写っています(赤い丸)。2つのバルブの間は左の写真より離れていますが、同じ物のようです。玉川上水は昭和39年に暗渠になりましたが、水道局がその時に記念に保管したのでしょう。こんな面白い遺物をなぜ見えないようにフェンスで囲っているのでしょうか。 |
 |
 |
|
| 江戸の上水について漢文で記した「水道碑記」 | 水道局新宿営業所は江戸時代に玉川上水の水番屋があった場所。灰色の線は等高線で、図の下(南)に向かって高度が下がる。 |
|
次に表通りにある水道局の正面に行きました。そこには江戸の上水の開設の由来と先人たちの功績を記した「水道碑記」がありました。上の左の写真ですが、明治28年に建てられて漢文で書かれており、高さ4.6メートルに及ぶ堂々としたものです。 ところで、渋谷川(水番屋から余水を流していたため余水川とも呼ばれていた)は水道局の敷地から始まり、現在の高速道路(御苑トンネルの出口付近)を横切る形で南に流れていました。もしここに高速道路が出来なければ、川跡は水道局裏の玉川上水からつながっていたことでしょう。 |
 |
 |
|
| 水道局裏の通路にある植え込みの辺りが玉川上水の水路。植え込みの先にかまぼこ型の白いフェンスが。 | 水道局から高速道路を挟んで南に伸びる渋谷川の跡。紫の花大根が咲き乱れて美しかった。(4月下見の時)。 |
|
(2022.11.26 追記)ここで、ホームページ『玉川上水今昔』の「庄司徳治コレクション」から、渋谷川に余水が流れていた頃の水道局南側の様子をご紹介します。写真は静かな流れですが、玉川上水の余水が吐き出された直後は、大きな急な流れとなって下ったことでしょう。後に述べる小山様がまだ子どもの頃、昭和の初め頃のお話ですが、「川は浅いが良く流れていて釣りをして遊んだ」そうです。玉川上水から流れる余水は渋谷川の大きな水源となり、江戸から明治の終り頃まで、流域の田んぼの灌漑や水車を回すのに役立ちました。 |
 |
写真は玉川上水の余水が流れている渋谷川の水路で、水道局新宿営業所(旧水番屋の地)の南側。1962~63年当時まで水が流れていた。水路の右側は新宿御苑。写真は |
|
<渋谷川の川跡を歩く> 高速道路の南側から始まる渋谷川の水路は、人が歩くような暗渠の道ではなく、謂わば雑草に覆われた細長い空地でした (注7)。しかし、川跡をネット越しに眺めただけで引き下がる訳にはいきません。ネット沿いにいったん内藤町に入り、住宅街の道を再び戻る形で川跡の土手の上まで来ました。そして、苔むした小さな階段を5段ほど降りて草むらに立ちました。地面にはフキの葉や雑草が茂り、緑の匂いがムンムンしていました。水路の真ん中には「けもの道」のように一すじの草の分け目があり、右は新宿御苑の高い柵が、左は川の石垣が続いていて、人の気配はありません。4月の下見の時は紫の花大根が咲いていましたが、5月のツアーの時はドクダミの花がいっぱいで、頭上には新宿御苑の木の枝が覆いかぶさり、ここが都心とは到底思えませんでした。 |
 |
|
川跡の草むらの両脇に川の水を貯める「堰」の跡と思 |
|
川跡を数十メートルほど南に歩くと、草むらの両側に石柱が立っていました。その先は道が急に下がっており、この辺りから川の高度が急に下がっていることが分かりました。後に内藤町の水車の場所を描いた地図を紹介しますが、この石柱は水車を回すために水を貯めて流す「堰」の跡と考えられます。水車を回す仕組みですが、渋谷川の流れをそのまま使って水車を回すのではなく、この石柱に板を渡していったん水を堰き止め、貯まった水をほぼ水平に内藤町の方に導き、この水路と元の川との高度差を十分につけたところで、元の川の方に水を流して水車を回すのです。渋谷川に水車を掛けるよりもこの方が水の勢いがつけられます。大雨で玉川上水が増水した時などは、水車が壊れない様に「堰」を開けて水をドッと下流に流したのでしょう。 私たちは、石柱の「堰」を確かめたところで前進するのを止め、先の階段まで戻りました。引き返すことになって皆さんとても残念がっていましたが、これには訳があります。この「堰」のしばらく先の左側に水路から住宅街に抜け出す扉があったのですが、その扉にカギがかけられていたのです。不審者を入れないためでしょう。下見の日は、この先で出られるだろうと思って川跡を下ったのですが、出る場所がどこにも見つからず、とうとう「堰」から400mぐらい先の外苑西通りの行き止まりまで来て、右脇の高い崖をよじ登って脱出しました。皆さんにそんな冒険をさせられないので、しぶしぶ引き上げた訳です。 <内藤町の余水の流れと水車> |
 |
 芳賀善次郎『新宿御苑の散歩道』、194頁。 |
|
|
内藤町の渋谷川の流れと分水路、水車。灰色の線は等高線。「堰」の先から川が急に下がる。左図は芳賀善次郎『新宿御苑の散歩道』194頁と「文明開化期」「明治のおわり」『東京時層地図』 の内藤新宿1丁目周辺から作成。地図はGoogleマップ。 |
|
私たちは元の階段の場所に戻って川跡の外に出た後、内藤町の住宅街を南に歩き始めました。先程の「堰」のちょうど横(東側)辺りにある朝日マンションの前を通り、左にクランク状に曲がって「けやき公園」に出ました。左上の地図の中ほどにある小さな公園(緑の丸)です。そこには、「新宿区みどりの文化財
保護樹林」という看板の付いた大きなケヤキが立っていました。かつて切り倒されるところを町の方の保存運動で残されたそうです。 この土地を流れる渋谷川は、玉川上水の余水によって一定の水量を保っていたため、流域に幾つかの水車が設けられました。右上の図は、芳賀善次郎『新宿の散歩道』(注8)にある3つの水車(新キ水車、在来水車、新水車)で、いずれも内藤家が設けた米つき用のものです。左の縦(南北)の太線が渋谷川で、「新規分水口」とは先程の「堰」から水を引き込んだ所か、その先のさらに水を分けた所でしょう。いずれにしても高度差をかなりつけてから水を落として水車を回しました。後に述べますが、日本で最初に鉛筆を製造した真崎鉛筆製造所(後の三菱鉛筆)の住宅兼工場は多武峯内藤神社の西側にありましたから、神社から近い「新キ水車」(八号地)が工場の水車と思われます。現在の「けやき公園」の辺りでしょうか。 なお、水車は内藤町だけではなく、西側の新宿御苑の中にも設けられていました。前掲『新宿御苑』によると、明治7年には殖産興業政策を担当する勧業寮出張所に対し、渋谷川から玉藻池まで水を引いて水車を設ける「水車用水についての願書添付図面」が出されています。この本によると、明治20年代にも御苑内製糸場の動力に水車が使われており、渋谷川が単に玉川上水の余分な水を捨てるための川ではなく、日本の近代工業を支える重要な動力源であったことが分かります。 前掲『新宿御苑の散歩道』には、当時の工場の土台だったらしい赤レンガが小山家(八号地)や小川家(十号地)に残っていると書いてありました。下見の時ですが、今も当時の小山家や小川家があれば何か関連のお話が聞けるのではないかと思って歩いていると、偶然「けやき公園」の近くに「小山」という表札を見つけました。玄関ベルを鳴らして良いものかどうか迷っていると、タイミングよく町内会の方が家に来られて御主人が外に出てこられました。私が訪問の理由を告げると「2人もお客がいて驚いたなー」と言いながら、町内会の用件が終わった後に話をして下さいました。工場のレンガについて伺うと、「まだうちの庭に置いてあるよ」と。案内されたお庭には空まで伸びるような大きなケヤキの木が立っており、その足元にレンガが1列に並んでいました。「この地域はケヤキが多くて、この木も何十年も経っているんだ。このレンガは明治初期のもので大きいんだよ。後から作られたものは小さいけど。」当時の工場は土台に赤レンガを使っていたため、工場が他に移った後も庭や床下にゴロゴロと転がっていたそうです。 |
 三菱鉛筆の看板(後出)に描かれた真崎鉛筆製造所のスケッチ。工場の脇には水車を回す分水路があった。 |
 |
|
| 小山家のケヤキの巨木と下に並んだ工場跡のレンガ。 |
|
渋谷川(玉川上水の余水)についてもお話を伺うことができました。「昭和39年に渋谷川は暗渠になり、周りの家は皆水洗便所になった。それまで川は浅いが良く流れていて、釣りをして遊んだ。雨の時コイがたくさん流れてきた。水門があるので、1回渋谷川に来てしまうと帰れない。金魚も流れて来た。ある時鴨の親子が川をさかのぼってきた。お母さん鴨の後ろに4、5羽の小さな子鴨が付いて泳いでいたよ。あまり可愛いので2階の窓から写真を撮ったんだが、その写真は今はどこにいったかね。家の裏には御苑の玉藻池から水が流れ出していて、そこは川も深くて幅も広くなっていて、魚がたくさんいた。子どもたちがその辺りによく入って怒られていた。他の所は浅かったが。この辺りには宮内庁の人や軍人がたくさん住んでいた。陸軍大将で陸軍大臣まで務めた宇垣一成もいた。うちの前辺りが水車の水路だっただろう。あそこもうちの土地だった。自分では水車は見たことがないけれど。工場の跡のレンガは大きかった。この辺りでは工場ではなくても、レンガがいいとなって使った家もある。」小山様のお話は本当に面白くて、また私が研究している宇田川や河骨川についても良くご存じで驚きました。小山様、貴重なお話を本当にありがとうございました。 |
 |
 |
|
| 多武峯内藤神社(野沢有様撮影) | 神社隣りの内藤児童遊園にある「鉛筆の碑」 |
|
ツアーの話に戻ります。「けやき公園」を過ぎて南の多武峯内藤神社に向かいました。伝説にあった内藤清成の愛馬の塚がある多武峯内藤神社でお参りをしてから、隣の内藤児童遊園に立てられた「鉛筆の碑」と三菱鉛筆の「看板」を見学しました。明治20年、パリの万国博覧会で鉛筆の便利さを初めて知った真崎仁六は、日本で最初の鉛筆を10年かけて独力で考案しました。真崎は内藤家の水車を借り、渋谷川の水を動力に用いて鉛筆工場を始めました。「何しろ動力は水車で、その水も玉川上水の余水だから、流れたり流れなかったりした。水が来ると真崎夫婦は夜中でも飛び起きて十人ほどの職工を起こして徹夜でも機械を回した」(前掲『新宿の散歩道』、193頁)。もし鉛筆が高価な外国製しかなかったら、当時の学校教育にも大きく影響していたでしょう。 |
 |
 真崎鉛筆製造所の看板を眺める参加者の方々。 |
| 真崎鉛筆製造所(後の三菱鉛筆)の歴史の看板。 |
|
| 次に内藤町の住宅街を離れ、東側を通る外苑西通りに出て南に向かって歩きました。「大京町交番前」の信号を超えると、道路の右下に先程の川跡が見えました。「あっ、ここが余水の流れだ」との声が。ここは下見の時に崖をよじ登って脱出した場所です。 |
 |
 |
|
| 紫の花大根が咲く川跡。外苑西通り「大京町交番前」信号の先で4月に撮影。奥が渋谷川上流。 | 川跡は外苑西通りで右に曲がり、道路沿いに南に進んだ。今は板で塞がれて入れない。左は外苑西通り。 |
|
渋谷川の川跡は外苑西通りで突き当り、ほぼ直角に右に曲がって40~50メートルほど道路と並行して進み、
|
 |
 |
|
| 川跡の崖の上に「沖田総司の逝去の地」と書かれた看板がある。右側の崖下が川跡。 |
看板にはこの場所に池尻橋がかかっていたと記されている。 |
|
池尻橋の近くには昔から池尻水車がありました。その場所は、池上典氏の「再現図」では橋のすぐ北にあり、渋谷川に直接掛かる形で描かれています。前掲『東京時層地図』の「文明開化期(140年前)」を見ると、同じような場所に水車のマークがありますが、池尻橋より南にも水車のマークがあり、これは玉藻池からの流れに掛かっているようです。池尻水車の用途ですが、一般に農業用と考えられますが、すぐ近く(国立競技場の土地)に江戸幕府や明治陸軍の火薬庫がありましたので、火薬の製造に使われたのかもしれません。 |
 |
内藤町から千駄ヶ谷にかけての渋谷川の流れ。「明治のおわり」『東京時層地図』より。渋谷川は北(中央上)から南(下)に流れており、途中で玉藻池(左上)からの流れを併せ、中央線の手前(中央下)で新宿御苑「下の池」(左)からの流れと合流していた。渋谷川が玉藻池からの流れと交わる所(中央付近)の少し北側を見ると、細い道が川を東西に横切っているが、池尻橋はこの辺りか。当時、外苑西通りはまだない。 |
|
この土地は新選組の沖田総司が最後の時を過ごした場所としても有名で、川跡が外苑西通りに突き当った所の真上に「伝 沖田総司逝去の地」という小さな看板がありました。彼が亡くなった場所には諸説があるようで、『渋谷昔口語り』(渋谷区教育委員会)の「角田哲司さんが語る」によると「池尻橋の水車のある植木屋の納屋」で、この土地の古老の間では「現在の地番で大京町29のビルの所」とされています。以前にこの辺りを歩いていた時に、ご近所にお住いの方からテレビ局が取材にきたという話を聞きましたが、沖田総司のファンにとって外せない場所なのでしょう。 <大番児童遊園 二すじの渋谷川の合流点> |
 |
外苑西通りの反対側にある
|
|
 |
 |
|
| 川の跡地に作られた大番児童遊園の階段。細長い低い土地なので川跡とすぐに分かる。 | 公園には動物のかわいいオブジェが。流れはJR中央線の土手に向かっていた。 |
| 玉川上水から南下してきた渋谷川は、この辺りで天龍寺方面からの渋谷川と合流し、1本の大きな川となって南に向かっていました。明治28年(1895)になると、甲武鉄道(後のJR中央線)がこの地に開通して線路の土手が築かれ、川の流れを通すためのトンネルが作られました。大番児童遊園の先には高さ数メートルの線路の土手がありますが、その土手の雑草の間に高さ2m強、横幅10mほどの赤レンガの壁が見えました。これがトンネルを塞いだ跡で、いかにも時代を感じさせます。 |
 JR中央線の土手の赤レンガは渋谷川が流れていた土手のトンネル跡(2枚の写真は野沢様撮影)。 |
 |
|
| 北と西からの渋谷川の二つの流れは大番児童遊園の手前で合流し、線路の土手のトンネルを通って南に向かった。 |
|
私たちは線路の土手に沿って歩いて再び外苑西通りに入り、JR中央線のガードを潜って建設中の新国立競技場に行きました。工事現場は塀で囲まれているので中の様子は分かりません。そこで、競技場の向かいにある東京体育館の高台に上って競技場の中を見ることにしました。時間は正午を過ぎて日は高くなり、帽子をかぶっていても暑いです。皆さんが疲れていないか心配になり「大丈夫ですか?」と声をかけたところ、「軽い軽い」「最後まで頑張る!」などの元気なお返事をいただいて一安心。皆で東京体育館正面の階段を登りました。高台から新国立競技場の工事現場を眺めると、広大な土地にたくさんの背の高いクレーンがそそり立って、そこは別世界でした。 <子供たちの水泳場だった昭和初めの渋谷川> |
 |
線路の土手下のトンネルを潜り抜けた渋谷川は、新国立競技場の前を渋谷に向かって流れていた。赤い点線は、新国立競技場建設のために渋谷川暗渠から移設された千駄ヶ谷下水道幹線。 |
|
渋谷川は、1964年の東京オリンピックまで国立競技場の前の土地を流れていました。鳩森八幡神社宮司の矢島輝様が著した『千駄ヶ谷の歴史』には、昭和の初め頃の渋谷川に関する興味深い証言が残されています(注9)。「母親に、芝の川(玉川上水原宿村分水…筆者)に行って泳いでくるのはいいけれど、下の川に行ってはいけないと、よく注意されました。下の川というのは今の渋谷川です。こちらの方は子供の背が立たないほど水深があり危険を伴いますが、芝の川は一㍍位だからおぼれる心配もなかった訳です」。「千駄ヶ谷駅の所は、今の中央線(現在の総武線)ですが、あの土手から川へ飛び込み、達者な者は流れを利用して、丁度観音坂の下あたりまで泳ぎました」。観音坂の下とはJR中央線の土手から450mぐらい南の地点ですから、当時の子供たちの元気な様子が伝わってきます。しかし水の事故も時々あったようです。内藤町の小山様は渋谷川(玉川上水の余水)の流れは浅かったと述べていましたが、線路の土手の手前で合流した後は、かなりの水量と速さになったのでしょう。 |
 |
| 千駄ヶ谷を南に流れる渋谷川(大正末期~昭和初期)。北東の角地は徳川家達邸。その裏に当時の要人宅が並ぶ。図中の方位と彩色、一部の文字は筆者。『千駄ヶ谷昔話』渋谷区教育委員会、20頁。 |
|
『千駄ヶ谷昔話』(渋谷区教育委員会)にも面白い話が出てきます(注10)。「徳川邸の裏手(現外苑西通り)には、渋谷川の支流(余水川)が流れ、鮒や川海老が泳いでいました。またプールのない時代のこと子ども達にとっては恰好の水泳場でした。外苑橋近くの大橋染物店では、この川で染め物を晒したそうです。その後、慶応病院から出る汚水が川を濁したため、水泳は禁止となり悔しい思いをしたことを思い出します」。徳川邸とは下の図の右上の徳川家16代当主・徳川家達の屋敷です。「観音坂下には渋谷川の支流が流れていましたが、夏には水泳の恰好の場所となりました。その折でしょう、身の丈三尺もあろうかという鰻が捕れ、近所の人に一円で売ったといいます」など。さぞ清らかな流れだったのでしょう。良い話ばかりではなかったようで「大雨が降ると、この川は溢れ、どの家庭も浸水し、大変困ったとのことです。」とありました。なお、文中の「余水川」とは渋谷川の地元の呼び名の一つで、水源が玉川上水の余水であることに因んでいます。 |
 |
目の前に広がる新国立競技場の工事現場。東京体育館の高台より。 |
|
私たちは、東京体育館の高台から工事現場と外苑西通りを見下ろして、当時の渋谷川の様子を色々とイメージしました。外苑西通りは今より細い道で、その奥に道と並んで川が流れていました。先程の矢島様よると、渋谷川は護岸工事が十分でなかったようで、土手がくずれ、竹が川の両側からかぶさるような有様だったとか。川と岸辺の景色は時代によってもかなり違っていたようです。時は流れ、「渋谷川」は1964年の東京オリンピック大会に向けて暗渠化され、下水道幹線となりました。当時の日本は高度成長期の最中で、アジア大会や東京オリンピックを成功させて国際舞台に躍り出ることが国の目標でした。清潔な国として水洗トイレを整備することも。当時もこの同じ場所で、今日のように大工事が行われていたのでしょう。それから50年を経て、2020年に再び東京オリンピックが開かれることになり、新国立競技場の建設が急ピッチで進められています。東京都によると、新国立競技場の西側には「渋谷川の記憶の継承と親しみのある里庭の景観」が創られるそうで、どのような川の流れが見られるのか今から楽しみです。
<終わりに> 東京体育館の高台に立って本日のツアーの予定を終えました。新宿から千駄ヶ谷にかけての渋谷川上流の姿を追い求めて、ヴュルム氷期、縄文時代、江戸時代、明治時代から2020年東京オリンピックまで、約2万年の時を半日で駆け抜けました。予定の時間を大分オーバーしてしまいましたが、見どころや説明したいことがたくさんあって、中味を省くことがなかなかできませんでした。参加者の皆さんに喜んでいただいたようで良かったです。最後に、今回のツアーに参加下さった皆様方、そして「前編」「後編」の長い原稿をお読みいただいた方々に心からお礼申し上げます。内藤町の小山様には渋谷川に関する興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。新宿歴史博物館の今野慶信様、伊那市立高遠町歴史博物館の笠原千俊様には貴重な情報をご提供いただき感謝致します。(終) <注釈> |
(頁トップへ)
Copyright © 2017 Kimiko Kajiyama All Rights Reserved
r
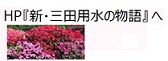



 新宿駅東南口の広場。右脇は甲州街道の高架道路。「推定谷
新宿駅東南口の広場。右脇は甲州街道の高架道路。「推定谷


