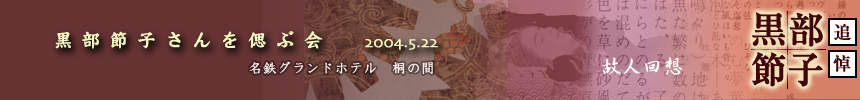
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
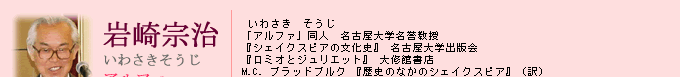 |
|||||
………
つまり、サルトルが『存在と無』という本の中で、黒部さん多分読んでらっしゃたと思います、何々が「ない」ということ、それは「無」そのものとしては存在し得ないと言っている。つまりある人がピエールを探しにいって、部屋へ入った。そのときピエールが「いない」ということが、「無」なんだというんですね。ピエールを探すからピエールが「いない」と思うんであって、ピエールを探すというこの人間がいなければ「無」というものは浮んでこないというんです。
黒部さんの詩集に、 『いまは誰もいません』 という詩集がありますが、「だれもいません」というのは、いままでたくさんの人がいた、あるいは自分にとって大切な人がいた、そのことがあるから、そういう体験があるから、「いまは誰もいません」というのが、非常に大きな意味を持つわけです。これは批評家の言葉でいうと、否定的含意――negative implicationというんですが、花もない、水もない、本もない、どんどんないないを続けていくと、その言葉のあとに非常に豊かな存在が出てくるんですね。その存在は存在であって存在でない。そういうことを小柳さんもさきほど言おうとなさったんではないかと思うんですけど、僕の言葉で言うとそういうことになるわけです。
もう一つ言いたいことは、イメージというものは、本格的な詩人の場合には、ある集合として広がりを持ってヴィジョンになるというふうに思うんですね。アンソロジーというのは、一人一人の詩人の大きいヴィジョンを見せてくれませんから、普通の場合、つまらないんですけど……。 金子みすず の詩集が本屋に行くとこんなにあるんで、一体これ何者だろうと思って(笑)、このあいだ数冊読んでみたんですけど、あの人も(あんまり褒めようと思って読んだわけじゃないけど)、でも褒めざるを得ないような美しいものと、それからちらっと見せてくれる優しいヴィジョン的なものがあって、まあいい詩人なんだなと思って……。 西脇順三郎 、これも勉強会でやった記憶がありますが、西脇順三郎の詩にはヴィジョンがしっかりあります。で、小野十三郎の「葦の原」の風景が出てくる詩、あれもそう有名ではないかもしれませんが、ヴィジョンがある。
金子みすずがよく知られるようになったのは、矢崎節夫という人が非常に骨折って、そしてみすずの詩集を整理して出版して、それから講演会でみすずの話しをしたり、非常にアクティブに動いているんですね。
詩人というものは、賞をいただいて詩人として残る、これがいいことだと小柳さんおっしゃって、僕も確かにそう思うんですが、黒部さんの場合にも、賞をいただいた。これはよかった。で、この次は、これまで柏木さんや小柳さんや、中野嘉一さんや、いろんな方が黒部さんのことを書いていらっしゃるけれど、そういう黒部節子論がくっついた『黒部節子詩集』が出るといい。土曜美術社や思潮社から<日本詩人シリーズ>のようなものが出てますけれど、ああいうものに入るのが一ついいことでないかと思います。それから、黒部節子の詩を、やはり僕としては、詩の歴史の流れの中で、象徴派の詩、それからシュールの詩ですね、そういうものの後に来た、多分シュールの詩――僕はシュールだと思いますけれど、厳密に言えば、シュールを踏まえて、バシュラール的なヴィジョンを構築した詩――として、これはきちんと歴史的に位置付ける必要があると思うので、誰かそういう位置付けをやってくれないかなと思っているわけです。
小柳さんのような方がいらっしゃるから、あるいはご令息の晃一さんも非常に熱心に作品の整理発表をなさってくださっているので、そういう願いもだんだん実っていくのではないかと思います。
今日は、この会に出られて非常に嬉しく思っておりまして、こういう会を企画、準備してくださった発起人の方々に大変感謝しております。
さっき名簿を見てて、東海女子大の学生さんがいらしていることを知って、東海女子大というのは去年の春まで仕事していたところで、あそこではあまり詩的なことで人と話しをすることはなかったんだけど、若い方々が黒部さんの詩を読んで、そのうちに卒論に黒部節子論というのが出てくるといいなと思っているんです。
少し長くなってしまいましたが、終ります。どうもありがとうございました。
●詩集『いまは誰もいません』1974年刊
次は、「アルファ」45号(74年11月)の「編集後記」に寄せられた岩崎氏による論考である。
十月一日、黒部節子の詩集『いまは誰もいません』が出た。作品集『耳薔帆O』(1969)以降の作品を集めたもの。<家>の主題による<空間詩学>作品集とでもいえようか。
サルトルは、「ピエールがいない」という言葉は、ピエールがいると思って眺めているという人間によって発せられるものだ、と述べた。<無>の認識は、存在への期待を前提として成り立つものであり、存在の意識と切りはなされた<無>の意識はない。
エンプソンは、「きみは細君をぶたなくなったかい?」という否定文は、妻をぶつのがこれまでの習慣だったという事実を前提として含んでいる、と述べた。否定文にはしばしばこういう「否定的含意」があって、それが文の<曖昧>を生み出す。そして<曖昧>こそすべてのすぐれた詩に見出されるものだというのが、エンプソンの考えであった。
黒部節子の詩集『いまは誰もいません』の題は、象徴的である。<無>の認識と「否定的含意」にみちた世界、現実と想像の愉しい戯れと、その陰に見えかくれする<虚無>と<不安>の世界、それが黒部節子の<詩>の世界、少なくともその一部なのだから。
●金子みすず(1903〜1930)

明治36年(1903年)山口県大津郡仙崎村(今の長門市)に生まれる。
大正末期、すぐれた作品を発表し、西條八十に『若き童謡詩人の巨星』とまで称賛されながら、
昭和5年(1930年)26歳の若さで世を去った。没後その作品は散逸し、
幻の童謡詩人と語り継がれるばかりとなったが、童謡詩人・矢崎節夫の長年の努力により遺稿集が見つかり、出版された。
その優しさに貫かれた詩句の数々は、今確実に人々の心に広がり始めている。
●西脇順三郎(1894〜1982)

慶応大学卒業後にイギリスへ留学し、文学者、画家、ジャーナリストらとの交友からモダニズム文芸の洗礼を受け、
滞英中に英文詩集『Spectrum』を自費出版。昭和2年瀧口修造らと日本初のシュールレアリスム詩誌「馥郁タル火夫ヨ」を刊行し、
翌年「詩と詩論」を創刊して、新詩運動の指導的推進者となる。日本語の第一詩集『Ambarvalia』を出版後、
10年以降は沈黙を守ったが、戦後ふたたび精力的に詩作を発表し、学殖詩人として活躍し、
詩業の集大成となる『失われた時』他、多くの詩集を刊行した。