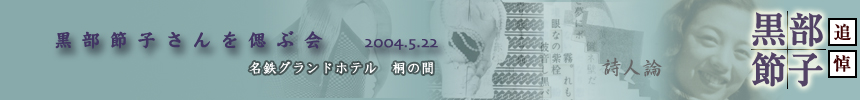
 |
|
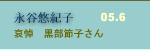 |
|
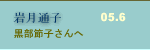 |
|
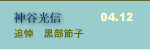 |
|
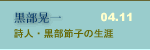 |
|
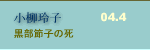 |
|
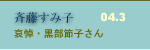 |
|
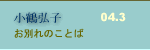 |
|
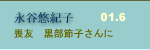 |
|
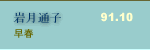 |
|
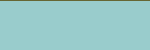 |
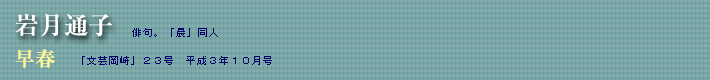
風は冷たいが、立春の空はなんと明るいのだろう。日陰から日向に躍り出た時のように、私は目を細める。
二月四日、そう、春の先ぶれにふさわしい、詩人黒部節子さんの誕生日、私は、庭のエリカや水仙を剪って、彼女に届けた日々を思い出す。地蔵ヶ入の私の所から歩いてわずか六・七分の道のりである。丘の多い岡崎の地形らしく、まず坂を上り、六供の浄水塔から市民会館通りへと坂を下り、今度は附属小学校の北門に沿ったゆるやかな坂がかりを経て、最後に黒部家の石段を上り切る。 そして、まだ芽吹かない蔦のからまる彼女の家の扉を開けた。シャム猫が飛び出し、彼女の声が聞こえたものだった。
先日、車の運転中にラジオをつけたら「詩人とは見果てぬ夢のように、詩を追い求めつづける人だ……」という。私は急いで、ボリュームを上げた。逗子とかスペインの地名が出てきて、どうやら詩人高橋睦郎氏のエッセイの朗読らしい。聞いている内に、黒部節子さんが浮かんだ。「詩人って、冒険家だわ。あの人みたいに………」と私は思っていた。
黒部さんとの出会いは、一九七〇年。丸二十年が過ぎた。初対面の日も、附属小学校のこども達の声が、高台の彼女の家に吹き上り、彼女の詩に顔をのぞかせる校庭のポプラは、六月の陽に白っぽくチラチラとふるえ立っていた。ロンドンにあるという「地球平面協会」は、今もなお在るのだろうか。
彼女は、
――千行詩を書きたいと思うの。今までは削って削って、一本の線にしたいと思ったけれど。削り落した中にも、いいものがたくさんありそうな気がするから……。とも言った。
私より十四年長の彼女は、当時三十八歳だったと思う。一九七四年出版の詩集『いまは誰もいません』には、長詩「川の家」二九五行があり、彼女は言葉通り千行詩への途上にいたことが分かる。その黒部さんが、四十前の若さで脳内出血に倒れた。四日目に意識が戻り徐々に徐々に失われた言葉をとり戻しながら、残された左手で記す「エスキス」(下絵の意)のシリーズが展開していった。
――病気になる前は、私には色々な抽斗があったのだけれど、倒れて、それがたった一つになってしまったの。でも、頭ではもう限界だった。倒れたから、詩を書き続けられたとおもうの。
或る日、彼女は病気に感謝するかとも思われるような口ぶりで、私にそう話した。半身の自由こそ失ったが、御主人に支えられ、人が見出し難い、さらに大きな魂の自由を得た、そんな風に彼女は見えた。
詩作の新たな試みは、次々と止む事がなかった。彼女は岡崎の「アルファ」(ギリシャ語のAの意)の編集の外に、札幌の「灣」、東京の「暦象」に詩を出していた。「ほら」と見せてくれる彼女の詩法は、思いがけない贈り物のように、いつも私をわくわくさせた。
あれは、黒部さんが二度目に倒れる数ヶ月前のことだと思う。一篇の原稿をもって、私に会いにみえた。電車の中で、少女が隣席のおえいさんの膝の上の箱の中に、赤ん坊を空想する話であった。作品の女性名を、おえいさんにするかEさんにするか………。
――本当に、赤ん坊が入っていたの。嘘なら何でもないのだけれど………。
――おえいさんと書いても、もう誰も傷つかないのでしょう?Eさんでは、かえって浮き上がってしまうから、私なら、やはりおえいさんにします。と私は答えた。
本当の事を言いだすって、些細なことでも神経にふれるほど痛む。それは、よくある事だ。虚構の中で、三人姉妹の長女である彼女の詩には、姉さんが、又つけ火をした弟が現実感をもって出てきた。が、変型しても、事実だから苦しいという、この日の困惑ぶりは、黒部さんの世界に、又新たな胎動がはじまっているように、私には思われた。
長男の黒部晃一さんと友人の小柳玲子さんが編んだ第六詩集『まぼろし戸』は、一九八七年の日本詩人クラブ賞を受けた。「赤い電車」はこの中に入っている。
黒部さんの声を最後に聞いたのは、六年前つまり彼女が再び倒れた一九八五年の一月であった。私の第一句集にふれた、朝日新聞の北川透氏の批評を、彼女は電話で読みあげてくれた。そして「豊橋の板倉鞆音先生が御病気だから、近い内に永谷さんと三人でお見舞いしましょう」とつけ加えた。しかし、約束は果たせなかった。
二月の空を見上げていると、無性に黒部さんに会いたかった。病室を訪ね、私は彼女のベッドへ歩み寄っていった。 昔ながらの美しい面差しは、しずかに早春の光を反していた。