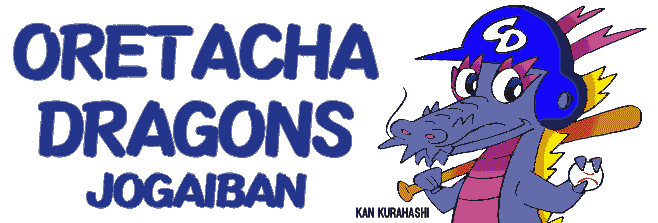
 中日スポーツ連載4コママンガ「おれたちゃドラゴンズ」のホームページ
中日スポーツ連載4コママンガ「おれたちゃドラゴンズ」のホームページ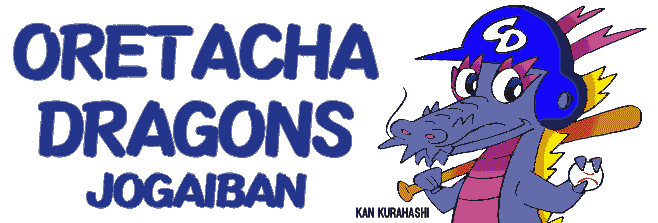
キーワードは「郷土愛」 2011.12.24 今年もあと1週間となりました。まだこのあと大晦日まで行事も仕事もあって気が抜けませんが、ちょっと時間があるので今年最後の更新をしておきましょう。
今さら言うまでもありませんが、今年は3月の大震災で大変な年になりました。亡くなった方やご家族だけでなく、多くの方の人生が大きく捻じ曲げられたことでしょう。傷跡が消えることはないでしょうが、一日も早く平穏な生活が訪れることを願うばかりです。
さて私にとっての今年というと、これまた人生の一つの転換点であったような気がします。
一つは初めての小説を出版したことと、もう一つは母親が死去したことです。すでに私が25歳のときに父が他界し、そして50歳になる今年に母が亡くなったというのは、なにやら判りやすくて気持ちが良いくらいです。母は80歳を越えほぼ平均寿命まで生きたわけで、その点では人生を無事卒業したと言っても良いんじゃないかと思います。また小説については、すでにこのサイトでも度々書きましたので繰り返しませんが、出版後に講演会を依頼されるなどの反響もあって、ほぼ今年はそれに忙殺されて終わったという印象です。
村国男依という人物を、せめて地元の人に知ってもらいたいということで不慣れな講演も何度か行い、次第に知名度も上がってきたようで嬉しい限りです。あとはこれを一過性の話題ではなく、地域に定着させていくことにつなげていければと思っています。これは私個人の力では何ともなりませんので、地域の方々が自分を愛するように郷土も愛し、その結果としていにしえの英雄を偲ぶという行動に広げていってもらうしかありません。今回の大震災で被災された東日本、特に東北の方々を見ていると、やはり自分が住んでいる郷土に対する愛情というものを、あらためて認識させられました。誰もが、もっともっと自分の郷土を愛しても良いと思います。愛すれば過去についても深く興味が湧くだろうし、また未来に向けてもより良い地域にしていこうという向上心につながっていきます。
なんだか堅苦しい話になってしまいましたが、今年を振り返るとワタシ的には「郷土愛」ということになるんでしょうか。
さて来年は、と言ってもまだ何も予定がありませんが、とりあえず次の小説に本気で取り組まなければと思っている次第です。あと何年、生きられるか判りませんので、やりたいことをやっておかないとね。
みなさんも良いお年をお迎えください。
監督退任と球団経営 2011.10.26
この周辺記も更新できずにいるうちに、あれよあれよと言う間にドラゴンズがヤクルトを猛追し、特に9月以降は驚異的な勝ち方で逆転優勝。球団初のリーグ連覇を成し遂げました。
最後の正念場、ヤクルトとの4連戦で見事4連勝したのはいいんですが、突然にマジック4が点灯し、優勝が目前になったものですから、皆大騒ぎ。私のところにも中日新聞の記者が取材に来て、感想や殊勲選手などのコメントを聞かれました。はなむけに私は落合監督を殊勲者と答えておきましたよ。
22日に発売の月刊ドラゴンズは、優勝の記事は全く載ってませんが、それもそのはず、私の原稿は5日に締め切りで、他の記事にしても12日くらいが限度でしょうから、とても優勝のことは書けません。「CSがんばれ」というような見出しになってますが、そんな事情がありますので、皆さん、ひとつご理解ください。こちらの「画竜点睛」の原稿も私は落合監督にしておきました。
落合監督の退任についてはいろいろな意見がありますね。ドラゴンズが急浮上したキッカケについても、いろいろ報道されています。まあ、それらすべてをひっくるめて、私は退任もやむを得ないかなと思います。
一番の要因は8年という長期政権になったことで、どうしても新規一転を求めたくなるのは自然の流れじゃないかと思うのです。成績は連覇を成し遂げたように素晴らしいものですが、8年間Aクラスが続くとファンもありがたさが薄れてきます。不景気もからんで球団に入る収入も減ってきて、勝つだけではどうしようもなくなってきたということでしょう。営利企業が自分の収益を増やそうと考えての行動ですから、ファンとはいえ部外者がそれに文句を言っても仕方のないところがあります。ファンの意見を取り入れて収益アップにつなげるかどうかは経営陣の能力次第ではありますが。
「画竜点睛」でも書きましたが、プロ野球の1軍監督の使命は勝つことで、観客を増やすことではないでしょう。それを監督に求めると、たとえば欽ちゃん球団のような形態になってきます。それはやはり球団が考えなければいけません。
なぜ観客が入らないか。一番は経済状況が厳しくて、各家庭で10円20円の節約をしている中、4000円もの出費は厳しいものがあります。1人ではつまらないので家族4人でとなると大変です。さらに飲食、交通費まで含めると、ちょっとした旅行にでも行った方がという金額になります。それだけの出費をする決断をして出かけても、必ず勝つとは限りません。惨敗の試合もあるし、勝ったとしても1点で勝利なんてこともドラゴンズ戦ではままあります。四球で出てバント、ヒット1本で得点となると、金額的に高価な得点です。
それよりは温泉でも行った方が、温泉は逃げることもないし、食事などもメニューは一定で、「今日は板長が不振で魚一匹です」なんてことはないでしょう。しかも観光業界は値下げなど、かなりの努力をしています。
ドラゴンズの公式ファンクラブもいろいろサービスをしていますが、よく見るとグッズなどはもらえるけれど、観戦料が割引になる特典はないようです。一度、アンケートを取って、ファンが一番望んでいるものを聞いてみると良いと思うんですが。
ちなみに私の感覚だと内野席は1000円ずつ値下げ、外野は1500円が適価だと思うんですが。それとビールは500円でしょう。値下げすればもう一杯余分に飲んで収益も上がりますよ。それが酒飲みの習癖です。
外野席で楽しむというのも良いでしょうが、私は目が悪いせいか、とても野球を楽しむという感覚になれず、それよりはテレビのほうが選手の表情も見られるしリプレイや実況もあって、野球を観ている感覚があります。球団ではドラゴンズ戦を有料でネット配信する計画もあるようですが、それは良い試みだと思います。地元にいても見られない試合もあるし、時間帯で切られる場合もあり、有料チャンネルで見るしかありません。ドラゴンズ戦に特化した配信があれば私も利用したいですが、ぜひビジターゲームも配信できるようにしてほしいですね。こうなると他のチームもネット配信して、ゲーム単位で料金を徴収する方法がファンには一番嬉しいと思います。
時代は変わっていきますから、それに対応していくことが必要です。同じ態勢を続けていると組織や系列、行動パターンが出来上がって、うまく機能しているうちは効果がありますが、環境が変わるとそれがネックになってきます。自分のほうから社会を見るのではなく、社会のほうから組織を見て、はたしてそれで良いのか、変える必要は無いのかを常に問う姿勢が必要ということでしょう。
マイブーム男依 2011.7.15
プロ野球もそろそろオールスターが迫ってきて、ペナントレースも半ばという状況です。
それにしてもヤクルトは強いですね。もともと細かく繋ぐ野球が得意な球団でしたが、ここへきて投手陣も力をつけてきて、投打にバランスの取れた隙のない野球を見せています。これまで長打で勝ってきたチームが統一球の影響で調子を崩す中、ヤクルトはコツコツと安定した野球で首位を独走という展開になっています。
ドラゴンズも2位につけてはいますが、どうしてもヤクルトには分が悪いですね。これに勝とうと思うと、バカスカ打てない以上、ヤクルトのような粘っこい野球をやるしかないと思いますが、やっぱり粘っこさはヤクルトのほうが一枚上手。とりあえずはヤクルト以外の試合で勝ちを拾って勝機を見出すしかなさそうです。
さて3月に出版した歴史小説「赤き奔河の如く」ですが、あちこちで紹介していただき、徐々に知名度も上がっているようです。WEBで検索してみたところ、神奈川や岡山、熊本などの図書館にも入ったようで、面白い広がり方をするものだなあと見ております。あんまり図書館に入ってしまうと本の販売に影響があるのかもしれませんが、それでも私の小説を図書館が購入して、遠い街の人が読んでくれていると思うと、なかなか嬉しいものがあります。
前回、このページで江南市の村国神社を紹介しましたので、今回は隣の岐阜県各務原市の村国神社を紹介しましょう。
各務原市は村国氏の本拠地と思われ、ゆかりの神社が2カ所あります。一つは各務おがせ町の村国神社(写真上)で、こちらがおそらく村国氏の中心神社であろうと思われます。
すでに小説を書き始めた10年ほど前にご挨拶に行き、書き上がったときにもお礼に出かけるなど、何度かお邪魔しておりますが、だんだん綺麗に整備されている感じがします。今回も「パワースポット」という立て札が新設されていましたが、あんまり時流に乗っかるのはいかがなものかという感じもしました。さらにもう一つは鵜沼山崎町の村国真墨田神社(写真下)で、飛鳥時代の創建当初は今よりさらに木曽川沿いにあったということです。
戦国時代に、このあたりの勢力の変遷で何度か移設されたあと、現在の場所に落ち着いたということで、村国神社ほどの重みは感じられませんが、それでも地元の人の信仰のよりどころとなっているようです。現在、社務所なのか別館の新設中で、また立派な施設になっていくのでしょう。こちらは今回、初めてお邪魔いたしました。
各務原市には他にも男依や村国氏にゆかりの寺などもあるようで、壬申の乱のあと、この地域に村国氏が勢力を広げたことがうかがわれます。
今回の小説は別に地域起こしを狙って書いたものではありませんが、結果として出来上がってみると、私自身、地元への愛着が強くなったような気がします。信長や秀吉だけでなく、せっかくこんな英雄が地元にいたんですから、もっと活用して地域起こしにつなげていければと思っています。
今のところ地元でも関心を持っている人は少ない状況ですが、江南市、各務原市、さらには安八町や関ヶ原町など壬申の乱ゆかりの町と、連携を発展していければと夢をふくらませているところです。
他にも壬申の乱の戦闘があった滋賀県の各地や、大海人皇子の脱出ルートとなった三重県、潜伏していた奈良県吉野町や村国郷があった大和郡山市など、関連する土地は数多くあります。各地の歴史愛好家の皆さん、いっしょに壬申の乱で遊びませんか?
江南の村国神社 2011.5.17
4月に出版した歴史小説「赤き奔河の如く」の関連で、このところ忙しい日々を送っております。初めての小説出版ということで、親類、知人、お世話になった方々へ献本して、また少しでも多くの皆さんに読んでいただこうとPRにも励んでいるところです。この小説の主人公、村国男依について少し紹介しますと、飛鳥時代の美濃の小豪族で、経緯は判りませんが大海人皇子の舎人となります。天智天皇の死後、帝位を継いだ(と思われる)大友皇子に対して大海人皇子が吉野から伊賀、伊勢を通って美濃に入り挙兵。不破から琵琶湖東岸を南下しつつ近江朝廷軍と数度の戦いを繰り広げ、最後の瀬田の戦いで朝廷軍を壊滅させました。これが672年の壬申の乱ですが、このとき前線で大海人軍の指揮を執っていたのが村国男依です。
美濃の小豪族が抜擢され、大活躍したというのが痛快ですが、このときの男依はおそらく二十代後半の若者であり、同じく活躍した舎人たちも同年代の若者たちだったわけで、若者が活躍し時代を動かした幕末と似たところがあります。
このあと、大海人皇子は即位し天武天皇となるわけですが、近江から飛鳥へ都を戻し、平安京に移るまでの約百二十年、奈良に都が置かれ、白鳳文化が花開くことになります。
あの戦いがなかった、あるいは大海人皇子が負けていたならば近江朝廷は継続し、また違った歴史、文化になったわけで、歴史的にも大きな戦いだったと思われます。
私は地元の人間なので、ちょっと身びいきかもしれませんが、村国男依はもう少し有名になっても良いのではないかと思います。この小説がそんな機会につながっていけばと願っています。
先日、地元のミニコミ紙の取材があり、せっかくならゆかりの場所で写真を撮ってもらおうと江南市の村国神社へ行って来ました。
私の故郷は江南市村久野町といいますが、古くは村国郷と呼ばれていたらしく、どうやら男依が乱の褒美としてもらった領地だったようです。その名残りがこの村国神社というわけです。実はこの神社、私の子供時代の遊び場でした。というのも、この神社に隣接して父親が珠算と書道の塾をやっていて、待ち時間などにみんなで野球やかくれんぼをした場所なのです。一般に熱田社と呼ばれている村の神社ですが、境内の一角に村国神社の石塔があり、子供のころからその名は知っていました。
しかし村国男依との関係を知ったのは三十歳を過ぎてからで、当時は中臣鎌足を主人公とした小説を書いていました。いずれ続編として壬申の乱を書くときは男依を主人公にしようと思った次第です。
今回あらためて訪れてみると、村国神社の石塔は二本あり、私が子供のころから知っていたのは上の写真のほう。なんと私の曽祖父とその弟が建てたものらしく、裏に名前がありました。
ほかに境内の反対側にもう一つ立派な石塔があるのを発見いたしました(下の写真)。これも古くからあったようで、村国神社の文字は著名な作詞家のものだそうです。
それにしても、子供時代の遊び場や見知っていた石塔が、40年も経ってから人生に絡んでくるとは、なんだか深い因縁のようなものを感じます。自分の縁者が立てた石塔だったことも、また一層その思いを強くしました。
目に見えない様々な縁がつながって、なんだか自分一人の力で書いた小説というよりは、いろいろな力によって書かされたという感じがして、ひょっとしたらこれが我が人生の最大の仕事だったのでは、言い換えればこれを書くための人生だったのではとまで思っているところです。個人的にかなり思いのこもった小説になりましたが、通常の歴史小説という観点から読んでも面白い物語になったと思います。
特に日本書紀では男依の戦闘部分については記述が少なく、そのあたりを想像力を最大限に膨らませて書いた後半は、これまでの壬申の乱がテーマの小説と比べても、格段に面白いと自負しております。
歴史好きの皆さん、面白い歴史小説をお探しなら、「赤き奔河の如く」がおすすめですよ。
原発のこと 2011.4.5
前回の「プロ野球開幕のこと」の末尾で原子力発電のことに触れました。
「これまであまり考えてなかったんですが、私も急に脱原発派になりました。」という部分ですが、それについてあまりにも短絡的ではないかというご意見をいただきました。普段、何も考えずに電力を使用している立場では、原発を批判できないという趣旨のご意見でした。
それについてメールでご返事をしたんですが、同様の感想を持たれた方がいるかもしれないと思いまして、その方のご了解を得てメールを転載させていただきます。
「はじめまして。
真正面からのご意見をいただきまして、ありがとうございます。たしかに反原発、脱原発とお経のように唱えるだけでは意味のないことでしょうね。
たった一文で書いてしまったので、そのように感じられたかもしれません。あの文章のテーマはプロ野球の開幕が趣旨でしたので。もっとちゃんとした文章量で言うべきことでしたね。多少の誤解があると思いますのは、私は電力会社を批判しているわけではなく、原子力発電からの脱却を考えないといけないという立場です。
たしかに現状では、太陽光などのクリーンエネルギーと言われるものでは十分な発電量ではありません。けれども将来的にそうした安全な方法で電力をまかなうことができれば、それに移行していくことは歓迎されることでしょう。
Aさんがどういうお立場なのか判りませんが、発電は原子力発電しかいけないと、こだわっていらっしゃるわけではないと思います。今回の事故で、そうした動きが加速していくことを願うばかりです。そうした方法がもし見つかれば、電力会社としても安全面にかけるコストも軽減でき、経営的にも助かるのではないでしょうか。
理想と言われるかもしれませんが、遠い目標を掲げることは大切なことだと思います。
もう一つ、ご意見の中にあったのは「電気の使い方を反省すべき」という趣旨かと思います。
これは全く同意見です。
かねてから深夜のテレビ放送は廃止にしても良いと思ってましたし、都会の真夜中のネオンなども不必要だと思ってます(それがどのくらいの節電になるかは判りませんが)。当然、自分の電気の使い方にも反省すべき点はあるでしょう。自分が使っているときには、これが危険な原子力発電が何%、火力が何%という意識では使っていなかったのは事実です。
今回のようなリスクをもった電力だということを認識しながら生活することも大切なことでしょうね。そのことについて「これまであまり考えなかった」という表現で書いたわけです。長文になりましたが、多少私の真意は伝わったでしょうか。
いただいたメールでご指摘がありました2点について、お答えさせていただきました。またご意見がありましたら、お願いいたします。
ありがとうございました。
くらはし かん 」
結局、ご理解いただけたようで良かったのですが、それにしても時節柄、多くの人が原子力発電について考えているということを実感しました。
電力会社としては現在の時点で原発ほど好都合な方法は他になく、推進したいのは当然かもしれません。しかし今回のようなリスクのある方法だと再認識されると、この先の推進は難しいのではないでしょうか。安全なクリーンエネルギーへの転換を、国として強力に進めるべきだと多くの人が感じていることでしょう。
今回の大震災は不幸なことですが、せめてこれを契機に社会全体を、安全で効率性の高いシステムに変えていくことができればと願っています。メールをいただいたAさんには他に、ソーラーを利用したバスや、電力会社で石炭を燃やしたときに出るフライアッシュという灰がセメントに有効利用されている話も伺いました。そうした効率の良い安全なサイクルを、社会のあらゆる部分で構築していきたいものですね。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
プロ野球開幕のこと 2011.3.18
東日本の大震災の影響で、プロ野球の開幕をどうするかという問題が、,昨日一応の解決を見ました。
セ・リーグは予定どおり3/25開幕、楽天など被害を受けた球団をかかえるパ・リーグは4/12に延期になりました。被災地の状況がまだ安定していない中、セ・リーグが予定どおり開幕することには批判もあるところです。特に電力不足で計画停電が行われている関東地方で、東京ドーム、神宮球場、横浜スタジアムの試合を行った場合、膨大な電力消費が許されるのかというところが一番の問題だと思います。
普通に考えた場合は全く国民感情を無視したもので、この点でセ・リーグも延期すべきという批判になっていると思います。
私も当初そのような考えだったんですが、ここにきて球団経営サイドから漏れるコメントで、ちょっと考えが変わってきました。たとえば「延期する理由は無い」と発言していた中日の球団代表も17日には「あくまで条件が整えばという前提であり、強行するつもりはない。不測の事態が起これば中止など、いつでも考える」とコメントしています。
つまり3/25から東京ドームでナイターをしようとしても政府、あるいは東京電力から中止要請がくれば中止するということで、この中止は雨天中止などと同じ扱いですよということでしょう。そのために野球中継ができなくても、あるいは場内の販売ができなくても、これは仕方ないことで球団としては不可抗力ですということでしょう。
球団側、あるいは野球機構が頭から開幕を延期してしまうと、様々に組まれた契約が球団サイドの責任で不履行になるために損害賠償ということになる恐れがあります。これを避けるにはと考えると、一応契約どおり開幕しておいて、球団外からの要因で中止せざるをえなかったという形にしたいというのが経営側の考えるところです。私が経営者でも、そうしたいです。なにしろ巨額の損失ですから。
前述の球団代表のコメントは、そのあたりを汲み取ってくれよというニュアンスが感じられますが、いかがでしょう。そのあたりを言わずにいて「プレーで力を与える」「日本経済に活力を」というようなキレイごとばかりを強弁するから、真意が伝わらず誤解されるんです。「開幕しますが、出来ないときは雨天中止と同じですよ」といえば「ああー、なるほど」と思いますがね。特に巨人のあのお方。巨人だけは電力を融通してもらえるのかと国民は誤解しますよ。
と、まあ私の推測を書いてみましたが、どうなることでしょうかね。電力不足が改善しない状況下で、本当に関東でナイター試合を(東京ドームはデーゲームであっても)強行するなら大変な批判を受けることになると思いますが。
いずれにしろプロ野球の開幕日など、被災地の方にとっては、どうでも良いことです。それよりも原発をなんとかしましょう。これまであまり考えてなかったんですが、私も急に脱原発派になりました。(付記)私の推測を書いたまでで、事実かどうかは判りませんよ。また3/25開幕を支持するものでもありませんので、念のため。
初夢 2011.1.7
皆さん、明けましておめでとうございます。私にしては珍しく、年明け早々に更新です。
とは言っても別に特別な出来事もなく、時間が空いたのでご挨拶しておこうということなんですが。昨年の暮れには恒例となった高校同級生のコンサートがあって、夜遅くまで気持ちよく歌ってきましたよ。ミスもしまくりでしたが、お客さん側も気心の知れた者ばかりで気楽なもの。やっぱりこういう集まりが一番良いなあと思った次第です。
小さな集まりとはいえ、それなりに段取りがいろいろあって大変ですが、できる限り続けられればと思いました。わが校長のモットーではないですが、時間的にも空間的にも無限の世界の中で、知り合えたというのは何かの縁でしょうから、我々の歌はともかく、同級生が顔を合わせる機会になればと思いますよ。
さて正月は日曜日がうまく絡んだおかげで、前もって漫画を描いておく必要もなく、31、1、2日と休んで3日から「おれドラ」を再開。しかし少し休んだだけで調子は狂うもので、なんか今週はダメですね。ちっとも気分が乗りません。
この時期は選手の活動も地味で、また判りにくくネタがないのも一因でしょう(と逃げる)。トークショーなんかは各地でやってますが、あれをネタにするのも問題があります。多くの選手は私服で登場するわけで、どんな恰好をしているのか私には判らない。適当に描いて、一緒に写真が載っちゃったりすると違いがありありなので、描きづらいんです。
それから選手がどこにいるかというのも判らない。うっかりナゴヤ球場で練習している漫画をかいたところ、翌日グァムから帰国なんてこともありましたからね。所在が判っている選手しか描けません。できればナゴヤ球場に無人カメラを設置して、WEBで見せてくれないかと思うくらいです。そんなことで、いろいろな制約の中で描くものですから、出来の良い作品を描くのは難しいですね。一度でいいから5人くらいスタッフを抱えて、選手の様子をリポートしてもらって描いてみたいものですが、それこそ初夢。まあ今年も無い知恵をしぼって描き続けようと思いますよ。
今年もよろしくお願いいたします。
BACK NUMBER 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998上期 1998下期