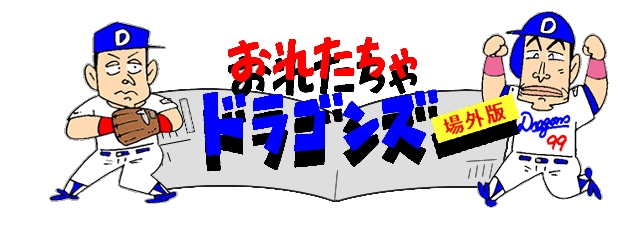
 中日スポーツ連載4コママンガ「おれたちゃドラゴンズ」のホームページ
中日スポーツ連載4コママンガ「おれたちゃドラゴンズ」のホームページ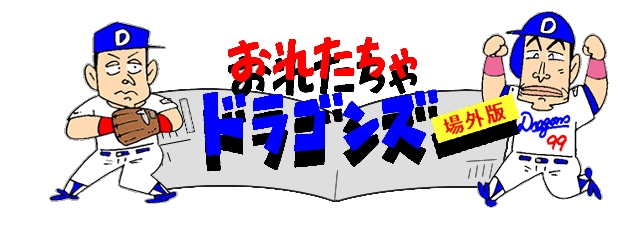
大晦日に考える 2003.12.31 今年も今日一日を残すのみとなってしまいました。「あっという間…」と書こうとして、いや、そうでもなかったなあと思い返しました。野球については、やっぱり今年は阪神の独走であまりに早くマジックが点灯したせいで、そのあとシーズンの終了まで長かったような気がします。ドラゴンズでは山田監督の解任のあと落合新監督が就任し、このオフはなかなか目が離せない盛りだくさんの毎日でした。
社会に目を向けると、小泉内閣の改革はほとんど進まず、北朝鮮、イラク問題に振り回されっぱなしの一年でした。それを糾弾する野党とのマニュフェスト対決がありましたが、それでも自公連立政権は継続しています。政権が変わればそれで解決とは思いませんが、とりあえず国民としても新規巻き直しという気分にはなります。そんなわずかな望みに期待したくなるほど、社会に閉塞感が充満しているように思います。
近ごろ妙に殺伐とした事件が頻繁に起こっていますが、こうしたことも社会の閉塞感と関係があるのではないでしょうか。もちろん何もかも社会のせいだという気はありませんが、将来についての不安とか、政治に対する不信感で、生きることに投げやりになっている人が増えているような気がします。今さえ楽しければそれでいい、自分さえ良ければいいというように、自分の欲求をコントロールできない人が多くなり、その無制御な欲求や甘えがぶつかって他人を傷つけるケースが増えているように思います。
些細な例ですが、朝、犬を連れて近所を散歩していると、田畑の中にゴミが散乱しているのをよく見かけます。それも結構まとまった量のゴミが、車の窓から投げ捨てられたように、ごっそりと落ちています。決められたゴミの日に、決められた収集場所に出せばそれで済むことなのに、本当に「自分さえ良ければ」の典型のような光景です。おそらくこれを捨てた人は、自分が捨てたゴミも、きっと誰かが始末してくれるという甘えた考えなのでしょう。こういう一人一人の小さな甘えが、社会をさらに悪くしていると思うのです。
政治とか国際関係とかを改善させるのは、個人の力ではなかなか難しく、そうしたニュースを見ていても無力感を感じますが、せめて自分の周囲から環境を良くするしかないと思います。なんだか固い話になってしまいましたが、そんなことを最近考えています。
来年はサル年。年賀状やホームページのインデックスのイラストにも描きましたが、少し原点に帰って、猿から人間になったころの素朴な心持ちを忘れないようにしたいと思います。それでは良いお年をお迎えください。
がんばれ合理主義 2003.11.11
ドラゴンズの新監督に落合博満氏が決まり、すでに秋季キャンプも始まりました。
「6勤1休」、「1、2軍の合同キャンプ」、「終日打撃練習」、「トスバッティングの禁止」など、少なくとも今までのドラゴンズでは見られなかったキャンプ風景が話題になっています。一つ一つ監督の思惑を聞くと、非常に合理的な考え方であることに驚かされます。マスコミで報道されていますので、いちいち説明はしませんが、職人的な合理主義をヒシヒシと感じます。実を言いますと私も非常に合理的なことが性格的に好きで、若い頃は「合理至上主義」を生活のモットーとしていたくらいです。あまりに合理的であろうとして体のほうがついていけず、さすがに今では少し丸くなりましたが、やはり基本としては合理主義崇拝者です。複数の物事を処理するときには常に優先順位を考えるし、効率よくできる方法を無意識に考えてしまいます。そして夏にはかき氷、好きな作家ははゴーリキー、「太陽にほえろ」で好きな刑事はゴーリさん、というくらい合理的なことが好きです。
こういった合理主義を信奉する人間は、どちらかというと技術系で職人的な人のように思います。何かを作るという最終目的が明確にある場合、そこへどうやったらたどり着くか、どのルートが最短距離か、消費量はどうやったら最小に抑えられるか、そういうことを考えながら一つ一つの過程を積み上げていくわけです。
同じ作るといっても芸術作品はまた別です。迷って試行錯誤することで作品に深みが出たり、思わぬ効果が出たりするわけで、最終目標が明確でない点で相違があるように思います。私が芸術をするとき、あまり深みがないのは精神が合理的すぎるせいかもしれません。ほっとけ。
民族で言うとゲルマン民族は非常に合理的な考え方をするように思います。ドイツの町並や社会制度などを見聞きするとき、非常に理に適っていると感心しうらやましく思いますが、そのかわり彼らの作り出す芸術は、どうも堅苦しくて自由さがありません。逆にラテン民族の国だと、町もごちゃごちゃしていて車の運転もいい加減、とても合理的とは思えませんが、そのかわりに芸術は型に囚われない自由なものが生まれる、そんな良さがあります。
日本人はどうかというと、どうもあまり合理的とは思えません。先進国とは言いながら政治や社会制度などはいい加減で曖昧だし、それを直そうという動きもあまり盛り上がらない。曖昧な状態に耐えられる人間が多いということです。
社会に余裕があって曖昧さから生じる無駄な物も許されるとき(たとえばバブルの頃)には、曖昧さも一つの文化として肯定できたのですが、今の日本のように余裕のないときには、特に政治、社会、経済においては効率の良い合理的なシステムを作り出すことが必要です。無駄な公共事業はしない、集めた年金をドブに捨てるような運用はやめさせる、そういった当り前のことが直せない、現状のままで平気でいられる国民というのは、私は本当に理解できません。何を怒っているかというと、先の衆議院選挙の低投票率についてです。自分が投票しなくても何とかなるだろう、偉い人がが何とかするだろうという曖昧な奴隷根性が日本をダメにしているのです。
今の日本を救えるのは職人のような合理主義者だと思います。いっそのこと「職人党」とか「合理党」、あるいは「ゲルマン党」とかいう党を作って、国民に訴えたほうが論点が判りやすいかも知れません。
話が妙な方向にいってしまいましたが、とにかく今必要なのは合理主義的改革です。合理主義がドラゴンズを、日本を、そして世界を救うのです。がんばれ合理主義! がんばれ職人! 来年の夏は参議院選挙だぞ!!
新監督は誰? 2003.10.6
前回、4年ぶりにナゴヤドームへ行ったことを書きましたが、実のところ出不精の私がなぜ出かけたのかと言いますと、「はたして来季も山田監督でいくのか」というところを探ってみたい気持ちがありました。8月の終盤から負けが込みだし、9月に入っても5連敗で、さすがに私も漫画を描いていて耐え切れない思いをしておりました。これは私だけだろうか、現場の雰囲気はどうなんだろうということで出かけたわけです。9/7の時点ではまだ監督の休養などという話はいっさい出ておらず、普通にいけば契約通り来季も当然指揮をとるという認識はありましたが、記者の人にこっそり聞いてみると「このままじゃ来季はわからないですよ」と、どこかのオーナーのような言葉が返って来ました。その暴君オーナーのような大声じゃなくてヒソヒソ声だったという違いはありましたが。
やはりムードとして、このままじゃ来季は戦えないという気分がチームの周辺に漂っていたのは事実で、期せずしてその日のヤクルト戦で山田監督は途中退場、それがドラゴンズの監督としての最後の姿になってしまいました。
言うまでもないことですが、山田監督に低迷のすべての責任があるわけではありません。しかしポイントポイントで「おやっ」と思う采配、判断がありました。選手の起用法、投手の交代、作戦などゲーム内のことだけでなく、「ブルースリー」の命名やギャラードの放出、蔵本選手の投手転向など、「ちょっと違うんじゃないか」という不信感が徐々に積もっていったように思います。もちろん選手のことはファンなどよりも監督のほうがよく承知しているわけで、その情報に基づいての判断なのでしょうが、結果が出なければやはり批判の対象になってしまいます。そしてチームの成績まで悪くなると、もうこれは何をやっても止まらない、加速しながら落ちるところまで落ちるしかありません。
だから監督は、最初の小さなほころびも見逃さないような気配りが必要なのです。あの星野監督でも、一方では選手を怒鳴りながら、また一方では選手の奥さんの誕生日には花束を贈るという気配りがありました。取材陣全員と食事をし、話題を提供し食事代も持つという配慮もありました(緊張のあまり食事の味が分からないという声もありましたが)。あそこの記者は気に入らないから取材は受けんというようなことを言っちゃダメです。
さて今やファンの関心は「新監督は誰?」ということに移りました。最初は中日OBを中心に高木、大島、谷沢、鈴木孝、牛島、宇野など10人以上の名前が挙がっていました。最近ではかなりしぼられてきた形で、野村克也前ヤクルト監督や落合博満氏の名前が出ています。この二人のうちで選ぶなら、私は落合さんですね。
今さら言うまでもなく実績は申し分のない人物で、最近は臨時打撃コーチとしてキャンプ時に各チームで指導する姿を見受けます。問題があるとすれば一匹狼的な性格で、はたしてチームをまとめていく包容力があるかどうかです。しかし血液型がO型なので、意外にオールマイティーで親分肌を発揮してうまくやっていくかもしれません。個人的に気掛かりなのは、また「おっかあ」や「福嗣君」まで表に出てくるのかという点ですが、まあこれはカミさんだけに「神のみぞ知る」というところです(おやじか俺は)。
本当のところは、私は谷沢さんや宇野さんのような中日の生え抜きに監督をやっていただきたいというのが本心です。やはり監督も出せないようなチームはさびしいし、かつて選手時代に応援した人物なら、監督になったとき、たとえ低迷してもファンは応援しようという気持ちが強いと思うのです。そんなこんなで最後に私が勝手に組閣してみましょうか。
監督/谷沢、ヘッド兼打撃/落合博、打撃/宇野、投手/牛島、今中、バッテリー/中尾、内野守備走塁/仁村、外野守備走塁/平野
これでどーだ!
4年ぶりのドーム観戦 2003.9.9
9月に入ってドラゴンズは5連敗。借金も今季最大の2になり5位に転落。順位はともかく、このところの元気のなさが気になっったので、9/7に久しぶりにナゴヤドームに出かけました。どれくらい久しぶりかと思い返してみると、前回訪れたのは99年の夏ごろだから、なんと4年ぶり! 地下鉄の「ドーム前矢田駅」も初めて使ったし、そこからドームへの立派な歩道橋も初体験で、びっくりしました。「たしかに以前の大曽根から歩くよりは楽になったけど、まだまだちょっと遠いなー」と思いつつ、マスコミ用の入り口を探しましたがドームの外を半周まわっても見つからない。「入り口まで変わったのか!」と驚きましたが、なんのことはない、1階と2階を間違えてました。いかにドームに来ていないか、入る前から実感しました。
グラウンドではドラゴンズの選手が打撃練習を始めたころで、1塁側のカメラマン席でそれを見ていましたが、気のせいか活気がない。選手もそうですがマスコミ陣も倦怠ムード。優勝の望みもなく連敗続きでは暗くなるのも無理はありませんが、おまけに前日の試合後、監督が監督室の机をひっくりかえして暴れたらしいので、取材もしにくいムードだったようです。
1塁フェンス際でバント練習する選手が次々と目の前を通りすぎるのですが、やはりあまり明るい表情の選手は見受けられませんでした。新聞社の人に荒木選手、福留選手を紹介してもらいました。荒木選手は噂通りの礼儀正しさで、顔じゅう汗だらけで挨拶をしてくれました。福留選手には「いつも失礼してます」というと「いいじゃないですか。もっと描いてやってくださいよ」と、ぶっきらぼうな顔で言われました。
そのあと落合投手にも久しぶりにお会いしました。以前にラジオ番組でご一緒して以来で5年ぶりくらいでしょーか。そのときは小島弘務投手も一緒だったので、落合さんはなんだか「いじめられっ子」の感じだったのですが、さすがに投手陣のまとめ役という風格がありました。「こんなとこにいらっしゃるとは」と驚いていました。
4年ぶりにドームで見る野球は、以前よりいくぶん快適になったように思いました。私が一番苦痛だったのは、申し訳ないけれど応援団の太鼓で、あの単調なリズムをを3時間聞かされるのは拷問に近いと思ってましたが、最近は中日の選手が打席に入るときにテーマ曲が流れるおかげで、音楽と応援団の応援がちょうど良い割合になったように思います。チアドラなどのアトラクションも効果的でした(私としてはもう少し時間を取ってもいいと思いますが)。
不満が残ったのは大型スクリーンでのリプレイの映像です。打って打球の行方を追うところまでで切れてしまう。なんじゃありゃ。アウトかセーフの瞬間まで見て、そのあとの選手の満足気な表情まで見たいというのが、お客さんの当然の気持ちでしょう。なぜそこまでしないのか。先日8/31の中日スポーツ4面の「審判の目」というコラムで元セ・リーグ審判部副部長の岡田功氏が書いている。ダイエー王監督の「便器問題」に関連させて「珍プレー番組」で取り上げられる審判の屈辱について。『(前略)各球場のスーパースクリーンには、際どいジャッジのプレーに関しては、リプレーはその直前でやめることで合意しているため、そのトラブルはない。が、テレビの珍プレー番組で”まな板”に上げられる審判にとっては生活権まで奪われかねない問題。テレビ局の良心に期待したい。』。なんじゃこりゃ。リプレーで誤審がばれちゃうと生活が脅かされるからやめてくれってことか。いい加減にせい。それじゃやっとチャンスをつかみかけた若手がサヨナラホームランを打ったのにファールと誤審されて、また今年も下積みで年俸が上がらないのは生活権を脅かされとるのと違うんかい!
仮にも審判は技能職でしょ。言ってみれば職人です。職人はその技能がなくなったら現場からは身を引くしかないんです。そのくらいの覚悟があって初めて「おれがルールブックだ」と言えるんです。職人が「生活権の保障」とかサラリーマンのようなことを言っちゃダメです。
その点では球場側にしたって、誰のために仕事をしているか認識が足りません。一番気に掛けなきゃいけないのはお客さんでしょう。お客さんの要望を無視して、客が入らないと言っているのは愚の骨頂です。そればかりか審判の誤審を助長することにもなっています。「臭いものにフタ」では、不祥事の資料を出さない官僚と同じことです。スクリーンに映すことで判定がはっきりする。審判も気をつけて判定するようになる。それでも判定できなければビデオ判定を導入する。事態が前向きに好転するじゃないですか。ことなかれ主義では、何も改善しませんよ。
あとは飲食物の値段ですね。相変わらず高すぎます。球団関係者もこぼしていましたが、あれでは観客は買いません。ビールが800円では、もう1杯飲みたくても我慢してしまいます。それよりは500円にして2杯買ってもらったほうが、利益も上がるんじゃないでしょーか。買いたくても我慢してるお客さんがいっぱいいるんです。そのあたりの心理を読まなくては。売り上げが伸びないのはチームの成績のせいだけじゃありません。
さてさて肝心のゲームのほうはというと、このところの連敗のパターンと一緒で、チャンスは作るけど点にならない、そのうちにピッチャーが打たれるという典型的なゲームで、監督の退場というおまけまでつきました。
「気合いを出せ」とか「悔しくないか」とかという問題じゃなくて、客観的にチーム力が弱々しい今の状況では、こういうゲームになるのは仕方がないと思います。外国人選手の補強の失敗に始まって、若手の伸び悩み、主力の故障と、組織が機能不全を起こしているような状態です。とうとう今朝のスポーツ紙面に「山田監督、続投再検討」という記事が出ましたが、やはり大きな改革が必要な段階に来ているように思います。チームも、その周辺も。
この夏の味方 2003.8.2
長かった梅雨も終わって、やってきました暑い夏。ジトジトと雨模様が続くのも困りますが、夏の猛暑にも毎年うんざりさせられます。
室内の温度計を見ていると、今のところ32.、3度が上限で、これくらいまでならなんとか耐えられるなあという感じです。今年は梅雨が長引いたせいで冷夏だそうですすが、これくらいの気温でちょうどいいんじゃないですか。ここ数年は35、6度なんて気温も当然のようにあったので、かなり楽な気分です。
クーラーが売れないとか海水浴場が不振とか各方面で困っている方々もいらっしゃるようですが、人間の体で耐えられるのは、せいぜいこのくらいでしょう。お金儲けよりも、みんなが快適に過ごせる夏を喜ぼうじゃありませんか。
さて、夏に合わせたわけじゃないけれど、この6月頃から泡盛を飲むようになりました。ご存じのとおり沖縄の焼酎で、沖縄へ行ったときにはオリオンビールとともに必ず飲むのですが、最近この泡盛をそろえている酒屋を近くに見つけました。
これまではビールしか飲むものがなくて、経済的な理由から発泡酒になり、さらに酒税の値上げで格安の低アルコールビールにしていたのですが、もういい加減にうんざりして、他に飲むものがないかと、ずっと思っていたところにこの泡盛。これがなかなか調子いいんです。ビールだと開けた以上は全部飲まなきゃいけませんが(残したっていいんだけど貧乏性で)、その点、泡盛なら量の調節もできるし、水で割ってアルコールの濃淡も調節可能。そんなことは普通の焼酎でもウイスキーでも同じですが、やはり泡盛のいいところは沖縄を疑似体験できるというところでしょう。沖縄のあの開放的なムードを思い出すことができる。これで沖縄民謡でも聞きながら、ゴーヤーチャンプルでもつまめば、もう完全にトリップできます。
トリップを助けるために、特にボトルに魚のイラストがいっぱい描かれている「海人(うみんちゅ)」(720・)という泡盛を選んで、それが空になったあとは2.7・のペットボトルの「かりゆし」という泡盛を、ボトルに移しながら飲んでいます。2.7・で2500円程度。おそらく2ヵ月はもつと思われるので、これはかなり家計にもやさしい酒です。家計だけでなく焼酎は体にも良いという話で、これはもう理想的な酒じゃないでしょうか。
先日、中日スポーツのコラムで、名古屋のタレントの宮地佑紀生さんが、やっぱり長年かかって泡盛にたどりついたと書いていらっしゃったので、意外に愛好家は多いんじゃないかと思った次第です。
問題があるとすれば、あまりに飲みやすいので昼間からちょっと薄めにして飲みたくなることと、冬場にどういった飲み方をするのかということでしょう。
今は氷と水で飲んでいますが、寒くなるとどうするんでしょうねえ。お湯割りの焼酎は匂いが鼻について好きじゃないので、湯はダメでしょう。氷は冷たすぎるので常温の水で割ればいいのかな。まあ、それは冬になってから考えましょう。
とにかくこの夏は泡盛。心強い味方を得ました。
突然、邪馬台国について考える 2003.6.19
毎月、月の後半になると歴史読本に連載している4コマ漫画「日本史ピンからキリ探訪(タンポー)」のために、日本史に関する本を図書館で借りてきて読んでいるのですが、今月は邪馬台国についての本を何冊か読んでいるところです。
邪馬台国の所在地をめぐっては、研究者だけでなく素人愛好家の間でも盛んに意見が交され、日本史最大の謎として、よく話題に上るところです。あまりにポピュラーすぎて、へそ曲がりな私などは「九州だろーが大和だろーが、どっちでもいいじゃないか」と思って関心も薄かったんですが、今回それに関係する本を読んでみると、やはりなかなか面白い問題だなあと再認識いたしました。
というのは、これはただ単に邪馬台国という国の所在地さがしということだけじゃなく、のちに日本の中央政府となる大和朝廷との関係、あるいは天皇家との関係ということについて、大きく関連していく問題であるわけです。仮に邪馬台国が大和に生まれて、それが発展して大和朝廷になったとすれば一番単純明快なわけですが、古事記などによると最初はやはり九州に拠点があって、神武天皇が東征して大和に至ったと書いてあります。そうなると邪馬台国は九州にあって、それがそっくり大和に移動したのか、あるいは邪馬台国からの分派が新天地を求め大和にたどりついたのか、はたまた邪馬台国は滅びて別の国が東征したのか、いろんなパターンが考えられるわけで、これを考え始めると蟻地獄の穴に落ちるように邪馬台国マニアになってしまうわけです。
私が今回読んだ本を紹介すると、まず1冊目が「古事記が明かす邪馬台国の謎」(加藤真司、歴史群像新書、1994)という本で、この著者は、邪馬台国は九州北部にあって、その分派が大和へ移動したという説をとっています。
この加藤さんという人は岐阜生まれの建設省のお役人で、吉野ヶ里歴史公園の整備をされている(当時)そうなのですが、非常にソフトな語り口で、古事記や魏志倭人伝をもとに無理なく九州説を説いていらっしゃいます。私も読んだあとには、すっかり同意見になってしまって、こんなお役人に説得されたら消費税の値上げも個人情報保護法案も、なんでも賛成しそうで恐いなと思いましたが、とにかく理解しやすい説得力のある内容です。特に古事記に書かれてあるイザナギ、イザナミや天照大御神、スサノオ、海幸、山幸、大国主命などの神話の解釈には、目からウロコが落ちるようなところがあって、モヤモヤしていた神話が非常にリアルなイメージに変わりました。
次に読んだのが「邪馬台国論争99の謎」(出口宗和、二見書房、1998)という本で、これはもう邪馬台国の所在に関するあらゆる可能性を紹介するもので、書物、遺跡、出土物などをめぐっての、これまでの論争の経緯を詳しくまとめてあります。
九州、大和だけでなく四国、中国、中部、さらにはジャワ、フィリピン、はてはエジプト説まであったというのは驚きです。これを読むと、せっかく前の本で固まったイメージが崩れ出してなにがなんだか分からなくなってしまいます。この著者の意見はというと、あとがきになってやっと表明してあります。邪馬台国は大和であろうと。
さらにもう1冊。「朴炳植(パク・ピョングシク)日本古代史を斬る」(朴炳植、学習研究社、1991)。これは直接に邪馬台国のことを扱っている訳ではなく、韓国人で古代韓国語の研究者としての立場から日本の古代を見た場合に、日本語の解釈とは違った姿が見えてくるという内容です。
日本の古代史は、これまで一般的に考えられている以上に朝鮮との関わりが大きいと私も思っていて、最近では韓国人の研究者の著作をいくつか読んだりしているのですが、この本もまた日本国内で新羅、百済、伽耶系の部族の抗争が天武天皇のころまで続いていたという韓国色の濃い内容です。真偽のほどは分かりませんが、これに近い事実はあったのではなかろうかと私も思います。
ちなみにこの著者は邪馬台国について、「所在地論争は笑い話。大和にあったのは明白」として魏志倭人伝の新たな解釈を示しています。ちなみにヤマタイではなくヤマト国と読むのが正しいとも言っています。
なんだか今回は格調高い内容になってしまいましたが、まあ私もマンガを描いてブラブラしているんじゃなくて、こうして勉強しているということの一端を皆さんにも知っていただけたんじゃないでしょうか。この勉強がどんな格調高いマンガになって結実するのか。それは歴史読本9月号をご覧ください。さあ、描かなくっちゃ。締切りは近いぞ!
早くもレース予想大崩壊 2003.5.2
ハァ〜、フウ〜、へ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜と、出るのはため息ばかり。いったいどうなっているのでしょーか、ドラゴンズは。5/1の試合を終わった段階で15勝14敗。貯金が1つあればいいじゃないかと言われるかもしれませんが、ほんの1週間前までは貯金も6あって、4月末には2ケタ近くまでいけるんじゃないかと期待をしてたところが、この体たらく。
前回の周辺記にも書きましたが、私の今年のペナントレース予想では4月末に貯金10で首位独走のはずだったんです。それもついこの前までは実現可能なペースできていたのに、4/26からの5連敗でもろくも崩れ去りました。
一番大きな原因は谷繁の故障でしょう。川上以外、調子がいま一つな先発投手陣をなんとか誘導してきた谷繁が抹消になり、中野ががんばってはいるものの投手陣に今まで以上の負担がかかり不安定に。点を取ってもすぐに取られてしまう展開が続き、今度は打撃陣のほうにも不調の波が来たようです。井端、立浪の故障、アレックス、クルーズの不振で打線はもうガタガタです。立浪は無理をして出場を続けていますが、あの走塁や守備を見ると、ここは休養したほうがいいんじゃないでしょーか。選手生命を縮めるんじゃないかと心配です。
それともう一つ問題なのは先発投手陣の不調です。開幕前はコマがそろって、あれほど万全だと誰もが太鼓判を押していたのに、川上の4勝をのぞいては朝倉、野口、山本昌がそれぞれ1勝ずつ、バルデスに至っては勝てないままファーム落ちです。なんでしょーか、これは。
バルデスについては、阪神での抑えの経験から投球は合格点。先発への転向についてもメジャーではもともと先発志向だったということで問題なしと言われていました。オープン戦でも3、4イニングずつしか投げていない。しかし一番の問題はスタミナにあったようで5イニング以上の登板になると全然ダメです。メジャーでの実績を見てみると6年間で先発経験は22回。年平均で3、4回。ほとんどはショートリリーフだったようです。虚像を信じこんで、オープン戦で長い回を投げさせなかったツケが回ってきたと言われても仕方がないところです。
あとは朝倉です。昨年11勝の実績で、今年も2ケタは確実と誰もが信じていました。私も先の中日新聞のシミュレーションでは、4月の月間MVPは川上と朝倉の争いになると描いたのですが、とんでもないことになりました。球速は出てるのに打たれる。下半身が使えておらず伸びがないということなのか、相手が研究をしてタイミングを合わせてきているのか、おそらくどちらもあるのでしょう。
だんだん気分が滅入ってきてしまいますが、今後どうしたらいいのか。幸いにも谷繁が近々復帰のようで、せめて盗塁の心配だけでもなくなれば投手陣が楽になり、勝ち始め、野手にも好影響が波及していくことを信じたいところです。不振に陥ったのと同じ経過で立ち直るのを願うしかありません。打線については当面は立浪、アレックス、クルーズを休ませ、荒木、大西、福留、渡辺、高橋光、谷繁、井上、神野でどうでしょう。
さて明日から9連戦。はたしてどんな結果になるのか恐い気もしますが、ドラゴンズ選手たちの奮起に期待しましょう。まだまだシーズンは始まったばかりです。
マジック80を楽しもう 2003.3.17
日毎に日差しが強くなり、ウグイスが鳴き、スギ花粉が飛びかう春この頃。皆様いかがお過ごしでしょーか。もう10年以上、花粉症に悩まされている私ですが、花粉の量が多いといわれている今年、意外にも軽い症状で驚いています。もちろん外出のときはマスクをしていますが、それでも例年なら薬を手放せず、仕事中も原稿の上に鼻水を落とさないように注意するのが大変でした。それが今年は薬いらずでなんともない。油断してマスクなしで外出すると多少グシュグシュきますが、それも軽いものです。何が原因だろうと考えると、どうも毎朝食べているヨーグルトくらいしか思い当たるものがない。
これは別に花粉症対策で食べ始めたわけじゃなくて、たまたまもらったヨーグルトを家でクローンにクローンを重ねて食べ続けているもので、もう1年くらいになります。少量のヨーグルトに牛乳を加え、常温で一晩おいておくと発酵してできあがり。牛乳代はかかりますが、それでもヨーグルトを買うことを思うと安上がりでしょう。花粉症だけでなく、おそらく健康にもいいんじゃないでしょーか。
そんなことで久しぶりにハッピーな春を過ごしていますが、それにもまして嬉しいのがドラゴンズの好調さではないでしょーか。星野監督時代から「投手はいいが打線がねー」というのが合言葉のドラゴンズでしたが、今年は全然違う。特に福留を1番において左右のジグザグ打線にしてからは猛爆につぐ猛爆。イラクを一日も早く攻撃したいブッシュ大統領もうらやましがるほどの攻撃ぶりです。
TOPICSでもお知らせしましたが、中日新聞恒例のプロ野球開幕特集の記事で、2003年のペナントレースの勝手なシミュレーションイラストを描きました。その中で書いたように今年はドラゴンズがスタートダッシュに成功、6月に疲れが出て巨人、阪神と三つ巴になるけれど、7月に立浪選手の2000本安打カウントダウンでチームに良い緊張感が生まれ再び上昇カーブ。球宴明けの阪神戦で阪神を撃破したあとは巨人とのマッチレースに。6連戦が4回続く厳しい8月を先発6本柱がそろうドラゴンズは勝ち越しで乗り越え、そして勝負の9月。9連戦という過酷なスケジュール、そしてその後半に巨人と当たる15、16、17日の3連戦が優勝を決める天王山に。それを制したドラゴンズは10月に優勝、そして日本シリーズでは山崎の活躍でパを制したオリックスと対戦。山崎に苦しめられながらも4-3で競り勝ちドラゴンズは49年ぶりの悲願の日本一!!!
というような私の独断によるレース展開をイラストで描いたんですが、これを描いたのが2月の終わりごろ。しかし最近のオープン戦の猛打ぶりを見ていると、まさに確信に近くなった感があります。若干違うかなと思うのが、巨人がペタジーニの外野守備を断念するのが5月と描きましたが、これはもう少し早まりそうな気がします。
今年は巨人、ヤクルト、広島の3チームで4番打者がぬけ、打順が不安定。ペタジーニを補強した巨人も打撃はともかく、守備やチームの結束という点では昨年より戦力ダウン。松井の抜けた穴を痛感するシーズンになりそうです。横浜も戦力不足。不気味なのは阪神ですが、コーチを含めてあれだけの個性豊かな面々が和気藹々と結束できるとは思えず、おそらく恒例の内部衝突で空中分解するでしょう。そうなると残るはドラゴンズです。
ついでに順位予想もしておきましょう。中日、巨人、阪神、ヤクルト、広島、横浜の順になります。鈴木孝政さんといっしょなのが気になりますが、これはもう決まっているから仕方がない。みなさーん、10月には49年ぶりの日本一です! 死ぬまでにドラゴンズ日本一を見てみたいというファンは、なんとか10月まで死なないように!
だんだんテンションが上がってきたので、このへんでやめますが、今年は本当にチャンスの年です。優勝までのカウントダウン、マジック80が消えていくのを一緒に楽しみましょう。
5年ぶりの沖縄 2003.2.11
新年が明けたと思ったら、あっというまに2月になってしまって、この周辺記の更新も2月からということになってしまいました。まさしく、光陰矢のごとしです。
さて私、2/6〜9の4日間、沖縄のドラゴンズキャンプを見学に行ってきました。6日の早朝8時5分の便だったのでラッシュにつかまり、あやうく遅刻しそうになりましたが、JALのお姉さんに叱られながら空港内を走り、なんとか出発直前の飛行機に間に合いました。
沖縄は5年ぶりで、新しくなった那覇空港にもびっくりしましたが、なんにもなかった北谷球場の回りが一大ショッピングタウンに変貌しているのにも驚きでした。報道で、観覧車などができているのは知っていましたが、実際に目にしてやはり時の流れを感じました。
伊藤球団代表がミラー獲得断念を表明した翌日だったので、ピリピリした雰囲気を想像していましたが、それほどでもなく、特に投手陣はどの選手も明るい顔をしていたのが印象的でした。野口、平井投手が交代でバッティングマシンで、バントや打撃の練習を楽しげにやっているのを見て、今年は2人とも登板の意欲がありありだなと思いました。
7日は2軍の読谷球場へ行きました。予想気温が20度だったのでTシャツにジャケットという軽装で出かけたのですが、意外に風が強くて寒いの何の。そのせいか選手の練習も何か熱がこもっていないような印象でした。特に投手陣はベテランの山本昌、落合、紀藤、川崎、それに故障明けの正津といったところがいて、彼らがマイペース調整をしているせいか、若手までがのんびりとしたムードで動いているように見受けられました。投手コーチの指導力が課題のような気がしました。
しかし野手ではルーキーの森岡、桜井、瀬間仲らが一生懸命練習しているのが新鮮でした。また怪我から復帰の森野も特守に汗を流していたし、キャンプ直前に肩を痛めた井上も黙々と肩を動かしていました。
8日は再び1軍の北谷球場へ。この日は川上、野口、岩瀬、遠藤、朝倉、山北、小笠原といったといころが打撃投手として福留、井端、谷繁、関川、渡辺、荒木らと対戦。いきなりの投打の主力の対決に取材陣も注目していました。やはりこの時期は投手のほうが仕上がりが早いということで、打ちあぐんでいた打者もいましたが、それでも福留あたりは川上投手の球を長打にして、今年も好調なところを見せていました。
午後3時ころまで球場にいて、その後、宿舎に帰り中日スポーツの漫画を描く。いつもならラジオなどの情報で描くところを、自分の見たものの中から題材を選んで漫画にするということで、普段より自由な気分で描けたような気がします。それとせっかく沖縄に来ているんだから通常と違うことをやろう考えて「沖縄キャンプ日記」と題して私自身が登場する日記のような漫画にしました。普段はあまり漫画に自分は登場させないのですが、ちょっと冒険してみました。いかがなものだったでしょうか。
キャンプにはいろいろな人が訪れて、そんな人の顔を見るのも楽しいものです。宇野、牛島、与田、彦野、鈴木孝といったOB解説者をはじめ、秋山、デーブ大久保、橋本ら他チームの解説者、在名各局のアナウンサーなどなど。峰竜太さんも生番組のために来ていました。元監督の中さんも中日新聞の仕事で来ていらっしゃって、2度夕食をご一緒させてもらいました。長い経験をもとにお話しになる言葉は重みがあって、やはりプロの目は違うなーと感心することしきりでした。
最終日は新聞の漫画が休みだったので、帰りの飛行機の時間まであちこち見て回りました。北谷のアメリカンビレッジをのぞいたあと、ちょっと足を伸ばして南海岸の新原ビーチまで行って、砂浜でピザと生ビールで昼食を取りました。潮が引くと700メートルも干潟になるという海岸で、はるか沖のほうで波が白くうち上がるのを1時間ほど眺めていました。
そのあと国際通りで買い物をして帰りました。今回買おうと決めていたアロハシャツと沖縄民謡のCDもちゃんと買えたし、満足のいく旅でございました。それもこれも、いろいろとお世話してくださった中日新聞社の末次さん、村井さん、下条さんのおかげです。何から何までありがとうございました。沖縄から送った土産ものが今日届きました。明日にでも沖縄民謡を聴きながら、海ブドウとミミガーで一杯やりたいと思っています。
BACK NUMBER