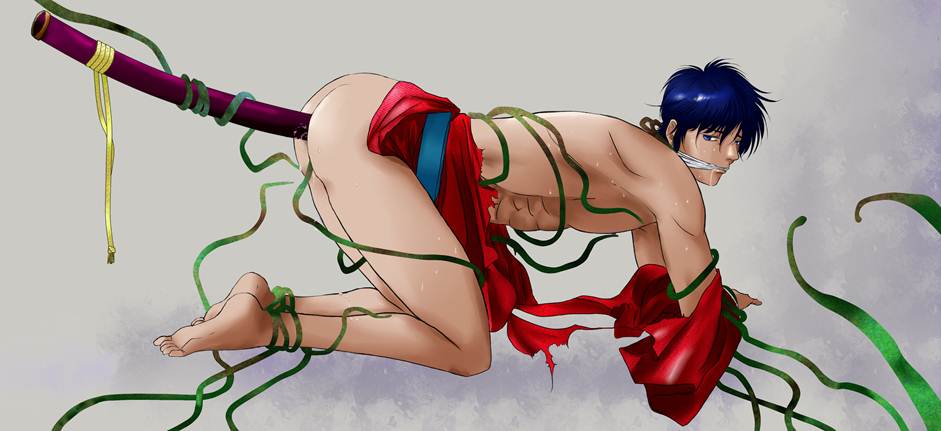桔梗
新皇のたまご
「イリアのは触手だけど、コレはあくまで“ただの蔦”です。拘束するのにどうしても必要でしたしね。それから……大人の玩具は……えっと、どう説明したらいいのかな」
口は動かしながらも、手は事務的に将門を責めることを止めない。
すでに先走りが溢れて、杏珠の手を濡らすがまだ将門は、必死に耐えているようだ。
切羽詰まった声を上げながらも、まだこちらの思惑通りにはいかない。
屹立した彼自身にまぶしながら、強くしごきたてる。
それをしながら、同時に後ろを嬲ることも忘れない。
とろりとした媚薬のおかげで指はスムーズに動く。ぐちゅんぐちゅんとすごい音がして、身体が痙攣する。
「お、覚えてろ……き、っさま……殺してやる!」
蔦に押さえこまれながらも、こちらを振り返る将門の端正な顔が涙に濡れていた。
はしばみ色のきつい目は、異様な色香を放っている。睨みつけられて杏珠は、ぞくっと震え上がった。
一瞬、将門を責める手が止まる。
「気に入らぬ!」
それまで傍観を決め込んでいた桔梗が、衣擦れの音をたてて立ち上った。
将門の正面にまわりこみ、その黒髪をつかんで引っ張った。のけぞった顔は、涙と涎にまみれている。この状況でまだ自尊心を手放せないのは、彼にとっては不幸だ。
ただ桔梗の前のような姫君から見れば、その鼻っ柱をへし折ってやりたいと思うのではないか。
「……畜生……ろす……絶対、殺してや……」
最後まで、将門は言い続けることができなかった。
桔梗が、男の唇を吸ったからだ。
「………う………うぅっ……!」
前髪をつかまれたまま、唇を口腔を蹂躙されているらしい。
鼻にかかった呻き声は、桔梗ではなく将門のものだ。最初に杏珠が教えた以上に桔梗は、彼の血の気の失せた唇を嬲っている。
将門が喉を鳴らすのを見て、ようやく桔梗は唇を離した。
「やってみるがよい。わらわを殺せるなら殺してみよ!」
滲んだ紅を着物の袂で拭きながら、桔梗は嫣然と微笑んだ。
ゆったりとした足取りで、部屋の隅に放り出された太刀を取り上げると、愛おしげに抱える。
将門の太刀だ。
「どけ……杏珠よ」
太刀を抱きながら、桔梗は言う。
「ダメ……よ。桔梗の前」
「わらわの言葉が分からぬか。杏珠?」
桔梗は、太刀の柄を握る。だがそれはあまりに長く重い。
姫が扱うには大きすぎる。その身に余るほどの長さがあるのだ。
「どかぬと斬るぞ?」
将門と同じはしばみの眸の中に狂気の色が宿るようだ。
その状況にあって、将門の中がヒクヒクと収縮する。赤黒い怒張が固さを増すのを見て、杏珠はその場を、桔梗に譲った。
「礼を申すぞ。杏珠よ」
きつい目を細めて笑うと、桔梗は年相応の幼げな顔になる。愛らしくも可憐なその面差しとは、裏腹に身体に見合わぬ得物を振り上げる。
杏珠は、あせった。
とりあえず蔦を解くが将門は、四つん這いのままで桔梗を待っている。
「桔梗の前。危ないってば」
心得のない者が長い刃物をあつかえば、それに振り回されて刀勢で自らを傷つけてしまう。
だが、桔梗は鞘ごと太刀を将門へ刺し貫いた。
「………あ……あっ……あっ!!!」
腰を抜かす杏珠の前で、将門が喘ぐ。
まるで女が恋しい男のものをその身のうちに受け入れるように、将門は桔梗の太刀を受け入れたのだ。
ぷちゅっと粘ついた水音を立てながら、無防備な尻の窄まりが太刀を呑み込んでいく。
まったく余裕のない表情で将門は、あさましく腰を揺すりたてる。
目の縁から涙が、唇からは涎が溢れる。
朱塗りの鞘が、捲れ上がってヒクヒク蠢く粘膜を穢す。
桔梗は、長い太刀をいっそう深く将門の奥へと進めながら、うっとりと言った。
「小次郎……キモチよさそう……すごく」
潤んでとろけた目は、後ろにいるはずの桔梗だけを見ているに違いない。
「……あぁぁっ……っ……んっ……んくっ!!」
突き上げられながら将門は、口をパクパクさせている。
ここにいる杏珠の存在など、最初からなかったように、二人の呼吸が重なっていく。
「あっ……はぅっ…っ…んっ ふぅっんっ、くぅあ………!」
獣じみた息使いの中、将門が叫ぶ。
「桔梗、桔梗……き、きょ……お!!」
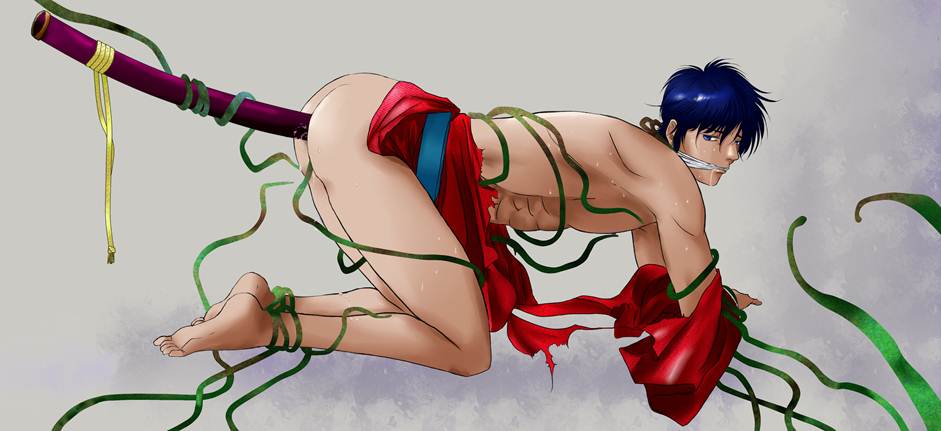
口は動かしながらも、手は事務的に将門を責めることを止めない。
すでに先走りが溢れて、杏珠の手を濡らすがまだ将門は、必死に耐えているようだ。
切羽詰まった声を上げながらも、まだこちらの思惑通りにはいかない。
屹立した彼自身にまぶしながら、強くしごきたてる。
それをしながら、同時に後ろを嬲ることも忘れない。
とろりとした媚薬のおかげで指はスムーズに動く。ぐちゅんぐちゅんとすごい音がして、身体が痙攣する。
「お、覚えてろ……き、っさま……殺してやる!」
蔦に押さえこまれながらも、こちらを振り返る将門の端正な顔が涙に濡れていた。
はしばみ色のきつい目は、異様な色香を放っている。睨みつけられて杏珠は、ぞくっと震え上がった。
一瞬、将門を責める手が止まる。
「気に入らぬ!」
それまで傍観を決め込んでいた桔梗が、衣擦れの音をたてて立ち上った。
将門の正面にまわりこみ、その黒髪をつかんで引っ張った。のけぞった顔は、涙と涎にまみれている。この状況でまだ自尊心を手放せないのは、彼にとっては不幸だ。
ただ桔梗の前のような姫君から見れば、その鼻っ柱をへし折ってやりたいと思うのではないか。
「……畜生……ろす……絶対、殺してや……」
最後まで、将門は言い続けることができなかった。
桔梗が、男の唇を吸ったからだ。
「………う………うぅっ……!」
前髪をつかまれたまま、唇を口腔を蹂躙されているらしい。
鼻にかかった呻き声は、桔梗ではなく将門のものだ。最初に杏珠が教えた以上に桔梗は、彼の血の気の失せた唇を嬲っている。
将門が喉を鳴らすのを見て、ようやく桔梗は唇を離した。
「やってみるがよい。わらわを殺せるなら殺してみよ!」
滲んだ紅を着物の袂で拭きながら、桔梗は嫣然と微笑んだ。
ゆったりとした足取りで、部屋の隅に放り出された太刀を取り上げると、愛おしげに抱える。
将門の太刀だ。
「どけ……杏珠よ」
太刀を抱きながら、桔梗は言う。
「ダメ……よ。桔梗の前」
「わらわの言葉が分からぬか。杏珠?」
桔梗は、太刀の柄を握る。だがそれはあまりに長く重い。
姫が扱うには大きすぎる。その身に余るほどの長さがあるのだ。
「どかぬと斬るぞ?」
将門と同じはしばみの眸の中に狂気の色が宿るようだ。
その状況にあって、将門の中がヒクヒクと収縮する。赤黒い怒張が固さを増すのを見て、杏珠はその場を、桔梗に譲った。
「礼を申すぞ。杏珠よ」
きつい目を細めて笑うと、桔梗は年相応の幼げな顔になる。愛らしくも可憐なその面差しとは、裏腹に身体に見合わぬ得物を振り上げる。
杏珠は、あせった。
とりあえず蔦を解くが将門は、四つん這いのままで桔梗を待っている。
「桔梗の前。危ないってば」
心得のない者が長い刃物をあつかえば、それに振り回されて刀勢で自らを傷つけてしまう。
だが、桔梗は鞘ごと太刀を将門へ刺し貫いた。
「………あ……あっ……あっ!!!」
腰を抜かす杏珠の前で、将門が喘ぐ。
まるで女が恋しい男のものをその身のうちに受け入れるように、将門は桔梗の太刀を受け入れたのだ。
ぷちゅっと粘ついた水音を立てながら、無防備な尻の窄まりが太刀を呑み込んでいく。
まったく余裕のない表情で将門は、あさましく腰を揺すりたてる。
目の縁から涙が、唇からは涎が溢れる。
朱塗りの鞘が、捲れ上がってヒクヒク蠢く粘膜を穢す。
桔梗は、長い太刀をいっそう深く将門の奥へと進めながら、うっとりと言った。
「小次郎……キモチよさそう……すごく」
潤んでとろけた目は、後ろにいるはずの桔梗だけを見ているに違いない。
「……あぁぁっ……っ……んっ……んくっ!!」
突き上げられながら将門は、口をパクパクさせている。
ここにいる杏珠の存在など、最初からなかったように、二人の呼吸が重なっていく。
「あっ……はぅっ…っ…んっ ふぅっんっ、くぅあ………!」
獣じみた息使いの中、将門が叫ぶ。
「桔梗、桔梗……き、きょ……お!!」