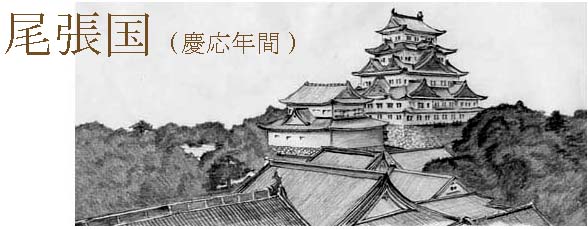
| 慶応年間リンク⇒ | 東北 | 関八州・江戸 | 東海・北陸・甲信 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 洋上 | 前ページへ |
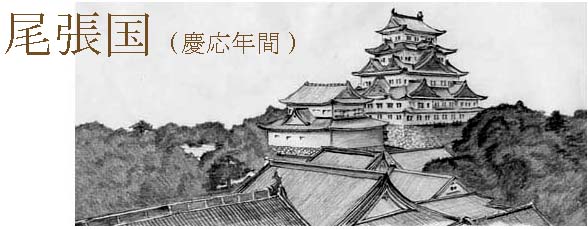
●慶応3年(1867)
2月11日−尾張藩、洋物改所を設置する。
4月20日−英国公使館員アーネスト・サトウ、大坂から横浜への帰途、宮(熱田)到着。
●慶応4年(明治元年・1868)
1月−尾張藩、鳥羽伏見の戦直後、最終的に討幕の立場を明らかにし、14人の佐幕派家臣を処刑。(青松葉事件)
1月−尾張藩主徳川慶勝が東海道諸藩に「勤皇誓書」の提出を促す。
2月8日−刈谷藩で家老3人が下城途中で斬殺され、討幕への藩論統一が図られる。
5月−入鹿池堤防(河内屋堤)が決壊。最終的に26ヶ村が濁流に流され、23ヶ村浸水、
死者941人、負傷者1471人といわれている。