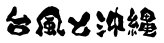 ・台風とは ・歴代の台風 ・台風の進路 ・沖縄の赤瓦 ・屋敷囲い ・住居様式 ・台風がもたらすもの ・台風対策 ・本土との相違 ・2011年5月台風第2号 ・リンク集 ・沖縄気象台 ・宮古島地方気象台 ・石垣島地方気象台 ・南大東島地方気象台 ・気象庁台風情報 ・バイオウェザー台風情報 ・台風情報リンク集
|
1933年 (昭和8年) |
石垣島台風 | 八重山地方を直撃した台風は、風速50メートルを超える猛烈さで、各地に甚大な被害をもたらした。、人的被害は死者5人、家屋は全壊1600余戸、半壊1400余戸にも達し、農作物はほぼ全滅に近い状態であった。木造の桟橋が損壊し、これを機にコンクリート桟橋が築造され大型船の接岸が可能となった。また木造校舎も倒壊したため校舎のコンクリートへの改築が検討された。八重山の経済に長期に亘り大きな打撃を与えた台風であった。 |
||||||||||||||
| 1945年 (昭和20年9月) |
枕崎台風 | 終戦から約1ヶ月後、沖縄、日本本土に大きな台風が襲来した。これが枕崎台風だ。沖縄、奄美大島を通過した後、鹿児島県枕崎市に上陸した台風は、枕崎測候所で中心部の最低気圧が今でいう916hPaとなっている。猛烈な台風であったことはいうまでもなく、伊勢湾台風、室戸台風と並んで三大台風と言われている。死者2,473人、行方不明者1,283人、負傷者2,452人で特に広島県において多数の死傷者を出した。 占領米軍の被害も相当なものであったようだ。 |
|||||||||||||||
| 1949年 (昭和24年7月) |
グロリア | 最大瞬間風速70メートルという猛威な台風が沖縄を直撃した。多くの家屋が全壊し、米陸軍施設、空軍施設の大部分が破壊、知念にあった米軍政府や沖縄民政府は屋根を吹き飛ばされるなど被害を受け、沖縄民政府は那覇へ移転となった。また北美小、仲西小、普天間小など多くの学校の校舎が、この台風によって壊滅的な被害を受けた。沖縄での死者は40名にものぼった。家屋が壊れなんと近くの墓の中に避難する者もいたらしい。昔の沖縄の墓は中がことの外広いからだ。 また、米軍施設も大きな被害を被った。天顔地域の米軍基地内では倉庫の屋根が台風の猛威で吹き飛ばされた。 |
|||||||||||||||
| 1952年 (昭和27年7月) |
キット | 石垣島を襲ったこの台風は、最大瞬間風速44.3m/sとさほど大きな風速ではなかったものの、風速10~20m/sの風が3日間吹き続き、降水量は4.8ミリと実に少ないものだった。海上に漂う塩分が水しぶきとなって農作物に降り大変な被害をもたらした。草木も赤く枯れてしまった。このように雨はさほど伴わず風だけが吹く台風を「風台風」または「火風(ピーカジ)」という。夏場水不足に悩む沖縄では、やってくる台風に降雨を期待するがこのような風台風はまったく益のないものだ。 |
|||||||||||||||
| 1956年 (昭和31年) 9月7日~9日 |
エマ (台風12号) |
来襲以前より年内最大と噂された台風エマは、9月8日に沖縄本島を直撃し、台風の目も本島を横断した。台風エマの暴風観測地は最低気圧が936.6ミリバールと当時としては琉球気象台開設以来の最低気圧、瞬間最大風速70m以上で風測器で測定不能であった。 当時のリュウキュウアン・レヴイユウの報道によれば米陸軍の損害は180万ドル(当時のB円で2億1600万B円=日本円2億1600万円)にのぼった。台風直後操業できたのは、水道、電力、通信網の約半分、ホワイトビーチは砂崩れのため40%は使用不能だった。陸軍病院の退避用仮建築物は全壊した。 民家が家ごと宙返りし約一丈下の空き地に真っ逆さまに落下する事態まで起きた。幸い住民は間際で危険を察知し難を逃れた。 民政府は、琉球政府と連絡を取りあらゆる援助を行った。応急修理や復旧建設のため57年度琉球政府予算の予備費1千万円を災害対策費に充てたともいわれる。民間の電話の不通はもとより、肝心な警察専用電話すら予算のめどが立たず思うように復旧できずにいたようだ。このどさくさに紛れて風雨の中、コソ泥、スリが横行、10日朝那覇署には現行犯の検挙、盗難被害届が山のようにきた。停電にともない市販のローソクも1本3円から5円に値上がり、品切れ状態続いた。ラジオは沈黙、夜は暗闇の状態。この暗闇で一際利を上げたのが映画館だったようだ。 10日に発表された被害状況は、死傷者48名、建物の倒壊7千余にも上った。建物はほとんど全てが木造であった。当時の新聞は8日から10日にかけてエマ一色だったとのこと。 |
|||||||||||||||
| 1959年 9月15日 |
サラ (宮古島台風) |
宮古島測候所で最低気圧908.1ミリバール(ヘクトパスカル)を観測し、当時の日本国内記録となった。瞬間最大風速70mで猛烈な台風だった。 人が吹き飛ばされた 死者6名,重軽傷者83名だった。 宮古島における被害は次の通り。
前年に石原裕次郎の映画主題歌で「風速四十米」という歌があったが、風速70mともなれば洒落にもならない。 当時の新聞によると宮古ではこの台風の眼に入ったとき星空を仰ぎ見ることができたそうだ。 本島那覇市の国際通りでは、「銀座の柳」の並木が強風ですっかり枝をもぎ取られハダカになってしまった。(今日柳並木はありませんが…) |
|||||||||||||||
| 1959年 10月16日~17日 |
シャーロット | 1959年16日深夜から17日未明にかけて那覇は壊滅状態だった。首里では崖崩れで車が埋まった。安里川では民家が流されるなど大変な被害。国際通りの安里方面は40cm程浸水した。水は濁流と化し、足が地に着かないほどの深さに達し、天井にぶらさがって一命を取り留めた人もいた。 台風シーズン年中行事とまで言われるガーブ川の氾濫によって那覇市場・平和通りは腰の高さまで水浸しになった。とにかく猛烈な豪雨で車に乗っていては視界はゼロといった状態。那覇市で5500戸が浸水した。隣の浦添市でも屋富祖通りはまるで川のようだった。北部大宜味村で37名、東村で5名、南部佐敷村で2名計44名の死者と19名の重軽傷者をだした。これまでにない被害の大きさだった。とくに北部では山崩れの惨事が目立った。 北部行きの1号線(現在の国道58号線)は名護七曲り許田、世富慶間の4キロ21カ所で沿道の土砂が崩れて不通となった。 シャーロットが過ぎ去った那覇市の平和通り商店街は、泥沼化し悪臭を放った。保健所による消毒も混乱の中思うように進まなかった。 農作物の被害も大きなもので、水稲、野菜などほぼ全滅に近い状況であった。 この台風は、降雨量556ミリでこれは沖縄の気象台始まって以来の記録であった。瞬間最大風速も58メートルを記録した。 シャーロットは空前の水害をもたらした雨台風だった。 |
|||||||||||||||
| 1959年 11月 |
エマ (台風20号) |
シャーロットの後を追うようにやってきたエマは雨台風だった。 雨量330㎜の豪雨だった。(1956年のエマと同名) 那覇市平和通りの市場はシャーロットの時と同じかそれ以上の浸水騒ぎとなった。商人たちは3たび商品が傷むのを避けるため準備よろしく避難したせいか、被害商品は少なく済んだ。ひめゆり橋では3棟が流され、内一棟が道路の上にのっかり交通を遮断した。一方地方では、佐敷村で田畑5千坪が埋没、北部(大宜味、国頭村)、中部でも崖崩れ、浸水がおこった。 琉球のシンボル守礼門の扁額「守礼之邦」が落ちた。 これらの惨状から、人呼んで「魔の13日の金曜日沸滅、三りんぼうの惨事」といった。 また、台風をいいことに質屋を襲う覆面強盗もでた。 台風サマサマだったのは、ニコヨン(日雇い労働者)だ、台風の後片付けで引っ張りだこだった。台風がないと仕事にありつけないという当時の沖縄の弱い経済基盤を象徴するものであった。 |
|||||||||||||||
| 1966年 (昭和41) 9月5日 |
コラ (第2宮古島台風) |
宮古島に影響を与えた台風で、最大瞬間風速は85.3m/sで、日本の観測史上1位の記録となった。 今考えても身震いするような風速である。 自転車程度のスピードであったため、宮古島はほぼ1日暴風に見舞われた。死者がでなかったのは幸いであった。気象庁はこの台風に「宮古島台風」と命名するつもりであったが、先の「サラ」がすでに「宮古島台風」と呼ばれていたため、「第2宮古島台風」となった。 農作物に多大な被害を与えた。 |
|||||||||||||||
| 1986年 8月24、25日 |
台風13号 | これは、NHKの放送で話題になった台風である。番組「島がゆれた~台風の道・沖縄南大東島~」では、台風による大波が海底にまで影響し、波浪による揺れが地震計で計測された。 | |||||||||||||||
| 2003年9月11日 | 台風14号 (マエミー) |
近年では最も被害の大きい台風の一つであった。最大瞬間風速74.1m/s を記録し、気圧も一時912hPaまで下がった。地鳴り生じるほどの凄まじさで、いたるところで車が横転したり、樹木や電柱が軒並み倒れ道路を塞いだり、家屋の窓ガラスがサッシの障子ごと外れ吹き飛ぶケースもあった。宮古空港管制塔は窓ガラス(ペアガラス外側12㎜、内側10㎜、間に空気層)が割れる被害に見舞われた。学校等体育館の屋根葺き材が全て吹き飛びぶなど公共施設にも多くの被害が出た。宮古島どこを廻っても被害だらけの状態だった。なかでも風力発電用の大型プロペラ風車羽が吹き飛んだり、はたまたコンクリート基礎の根本部分からタワーごと倒壊したのはこの台風の猛烈さを物語っている。 | |||||||||||||||
その他昭和20年~30年代の台風 |
|||||||||||||||||