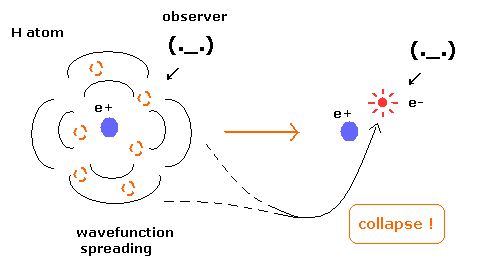
トップページ (2電子原子も含む正確な新ボーア模型)
電子スピンは存在しない。
ボーア模型のパウリの排他原理は役に立つ。
シュレディンガー方程式がボーア・ゾンマーフェルト模型の一部である厳密証明。
ご存じのとおり、シュレディンガー方程式は 粒子の確率密度を示すだけで 具体的な運動状態を示してくれない。
量子力学の標準的な解釈によれば、観測者が観察しようとした瞬間に 全空間に広がった確率密度波が 1点に収縮する (= 波束の収縮 )。
もちろん この過程は 一瞬の出来事だから 光速を越えている (= 非局所性という)。
Fig.1 は 水素原子の1つの電子が観測と同時に1点に収縮する現象を示している。
(Fig.1) 波動関数の収縮は 光速を越えている。
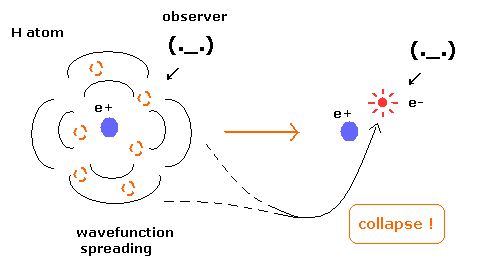
電子、陽子、C60フラーレン分子 まで 干渉という波の性質を示すことが分かっている。
例えば この C60フラーレン分子が 経路中にたった1つしかないときでさえ 2重スリット実験で干渉効果を示す。
(Fig.2) 単一の C60 フラーレン分子が自分自身と干渉する。
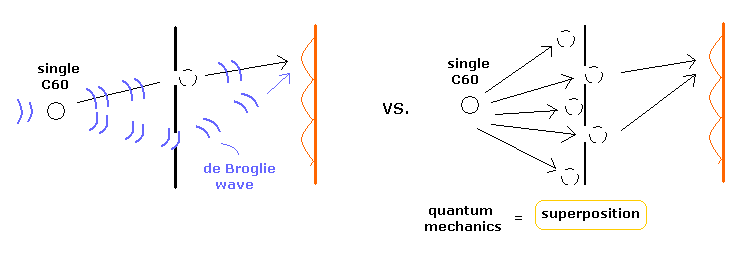
標準的な量子力学的な解釈によれば、この単一の C60 分子の自分自身との干渉は 奇妙な重ね合わせ (= superposition ) によって起こるとされている。
この重ね合わせ状態では 単一の C60 分子が 何と 同時に ありとあらゆる場所に存在することができる (= Fig.2 右 )。
そのため この超常現象をリアルな模型で示すことは不可能である。
あなたがたは なら単一粒子と その周囲に広がっている 実在のドブロイ波 を使って この奇妙な2重スリットの現象を説明すればいいじゃないかと 思われるかもしれない (= Fig.2 左図 )。
しかし もし ドブロイ波の実在性を認めてしまうと シュレディンガーの波動関数の収縮理論 (= Fig.1 ) がまったく無意味な産物になってしまう。
なぜなら シュレディンガーの波動関数は 具体的な粒子や波の動きを表すことができず ただ確率密度しか示せないことになっているからである。
また 想像がつくと思われるが 実在のドブロイ波を認めることは ボーア模型(+ エーテル理論 )を意味している。
つまり 量子力学的な確率密度の概念に賛成のときは、Fig.2 左図の 非常に自然で "局所的な" 解釈を諦めなければならない。
(Fig.3) さまざまな古いボーアのヘリウム模型の失敗。
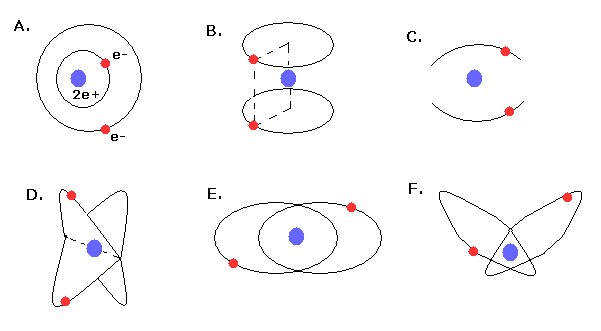
古いボーア模型のヘリウムの失敗と古典的原子のカオス のページに示したように 1920 年代のコンピューターのなかった時代に 3体問題である ヘリウム原子を ボーア模型で説明することは不可能だった。
一方 近似計算で 量子力学的な変分法は ヘリウムの基底状態に近い値を得ることができた。
3体問題が難解であったため、この量子力学の変分法は具体的な姿形を示せないにも関わらず ボーア模型にとって代わることができた。
1920 年代から コンピューターが一般的に普及する 1980 から 1990 年代の間に 量子力学が 非常に奇妙で神秘的なロジックに頼っているにも関わらず、それを疑うこと自体を 人々が止めてしまった。
しかし 今は トップページ や このページに示したように、コンピューターを使用して 量子力学の最新の変分法よりも正確な ボーア模型のヘリウム (+ パウリの排他原理 ) を表すことができた。
また このページに示したように、通常の量子力学の教科書は ボーア模型の電子が電磁波放射して核に落ちていく説明の部分を変更すべきである。
1920 年代には 彼らは ボーア磁子は 円運動ではなく 奇妙な電子スピンによって生じていると主張し始めた。
しかし この決断は 非実在で ”数学上の”概念である スピノルを生んでしまい、かつ 私たちが スピンの実在の姿は何か? と問うこと自体を強制的に禁止してしまった。
(Fig.4) 電子スピンは幻想である。
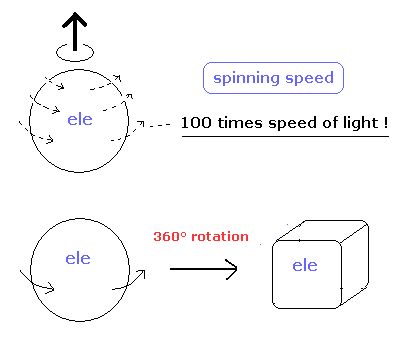
1つの電子は 非常に軽くて小さい。
そのため 電子の角運動量を 1/2 ħ にしようとするならば、電子の表面の回転スピードが 光速の100倍以上の速度に達しなければならない。
また スピンする電子などのフェルミ粒子は 何と1回転しても元に戻らない(2回転してようやく戻る)。
結果的に 私たちは 最終理論である 超ひも理論においてさえ 数学上のみの概念であるスピノルに頼らなければならない。スピンとは何かを問うことも許されず。
( 実際に 多くの有名な物理の本は この奇妙なスピンが実際何なのか 触れること自体を避けている。)
さらに ボーア・ゾンマーフェルト模型の微細構造の解釈が 相対論的なディラック方程式に置き換えられてしまった。
(Fig.5) 多世界解釈と ボーム解釈。
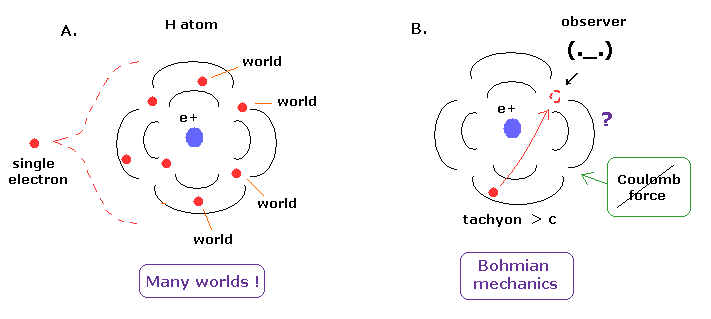
Fig.1 の 非局所的な波動関数の収縮を説明するために、コペンハーゲン解釈、多世界解釈 ボーム解釈 (= パイロット波 ) などが考案された。
コペンハーゲン解釈では 観測者が観測の行為をしない間は 波動関数がその重ね合わせ状態をずっと保つ。
そして 観測行為を始めた瞬間に、波動関数が収縮して 単一の点粒子に収縮してしまうのである。
そのため お気づきのとおり、この解釈では 観測者が特別扱いされすぎているのである。
そして 明確な収縮のメカニズムに関しては Shut up and calculate ! で説明しようとしない。
Fig.5B の ボーム解釈では、私たちが観測しようとした瞬間、粒子が 超光速のスピードで観測地点に飛んでくるというものである。
このタキオン状の性質 (+ スピンと電荷がない ) のために、この理論は一般的に受け入れられていない。
結果的に 現在の量子力学では Fig.5A の 多世界解釈しか残っていないのである。
多世界においては、単一粒子が 同時に 無数の異なった状態をとることができる。
そして 私たちが観測しようとするとき、その無数の世界のうちの1つの世界を見ることになる。
よって 量子力学の非局所性の収縮にも関わらず、粒子は光速を越える必要がないというわけである。
その代わりに、私たちは 非常に奇妙な無数の平行世界( パラレルワールド )を受け入れなければならない。
無限の状態の各状態から それぞれまた無限の状態が分岐するため 瞬く間に恐ろしいほどの世界が必要になる。
しかし あなたがたが 実在のボーア・ゾンマーフェルト模型を諦めるなら、この非常に奇妙な多世界解釈を "リアリティー" として受け入れなければならない。
また 超ひも理論は 4次元の残りの 6次元空間の幾何学的構造が無数のパターンをとることができ、そのそれぞれが異なった素粒子模型を与えるため、無数の非実在の理論が ひも理論に含まれていると言える。
それを逆手にとって 多世界解釈の無数の世界が超ひもの無数の理論を意味していると解釈を変えることもできなくない。
つまり 多世界解釈の考えは 超ひも理論にとって非常に好都合なのである。(ランドスケープともいう。)
(Fig.6) 光子対の 超光速 (= "spooky" ) のリンク。
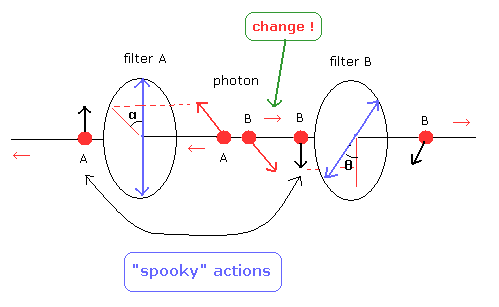
もし あなたがたが 単一粒子とその周囲の実在のドブロイ波 (= Fig.2 左 ) のモデルを用いて 2重スリットの実験を説明しようとするならば、量子力学の物理学者達は ベルの不等式の破れ を持ちだしてきて あなたを批判するだろう。
しかし このベルの不等式の破れというものは 非常に超自然的な現象なのである。
2つのエンタングルした光子対がどんなに互いに離れていても、そのうちの 1つの光子 (= A ) が 偏光フィルター A を通過して 自身の偏光軸を変えた瞬間に、もう1つの光子Bが 自身の偏光軸を 遠く離れた偏光フィルター A のものと同じにしてしまうというものである。
この過程は 一瞬なので もちろん超光速である (= 非局所性 )。
しかし このページに示したように、この超自然的な現象は 光子という”粒子”の実在性に対する誤解から生じていると言っていい。
もし 通常の分割可能な電磁波を利用すれば、このベルの不等式の破れを 古典的かつ 局所性の理論で説明できる。
さらに、光子という粒子に固執すると、遅延選択実験という 非常に奇妙な世界を受け入れなければならない。
そのため 光子を 剛体球としてではなく 電磁波として考えるほうが非常に自然である。
( ちなみに ラムシフトのラムが 光子の粒子性に反対していた話は非常に有名である。)
しかし 光子の粒子性を諦めることは 光子を量子化しようとする 量子電磁力学などを無意味なものにしてしまう。
銀河系が地球から遠く離れるにつれ、そこから放たれたであろう 光子の波長が 引き伸ばされていることが観測されている (= 赤方偏移 )。
そのため ドップラーシフトと 光子の粒子性が 本当だという仮定のもとで、彼らは 宇宙は非常に速いスピードで加速膨張していると結論づけた。
しかし 上記で述べたとおり、もし 光子という粒子の実在性を諦めて 宇宙空間を占める何かしらの 媒質を認めたとしたら、この膨張宇宙 (= インフレーション) の仮説は変更される可能性がある。
なぜなら これら古典的な電磁波が 宇宙空間を占める媒質 (= エーテル ) の中を進む過程で 長い距離を進めば進むほど 電磁波がエネルギーを失いやすくなり 赤方偏移を引き起こしやすくなるからだ。(= 疲れた光理論とも言う。)
(Fig.7) 宇宙の加速膨張か エネルギー消失仮説か?
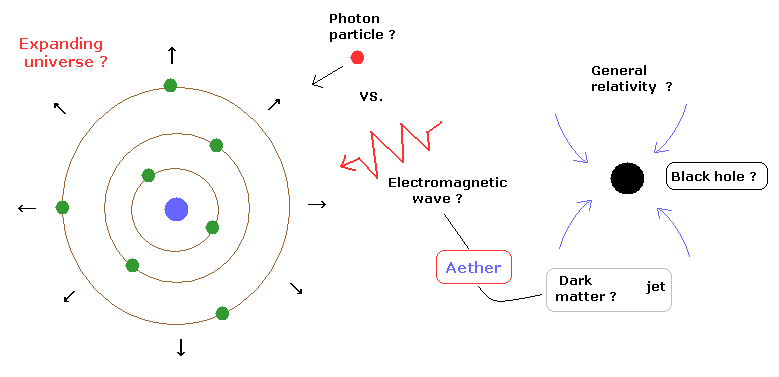
実は、ハッブル自身 膨張宇宙という考えがあまり好きではなく、エネルギー消失仮説のほうを原因として選んでいたようである。
宇宙の加速膨張理論は 非常に奇妙な ダークエネルギーや ビッグバンの仮説を作り上げる。
一般相対論によれば、観測者に関わらず すべての宇宙空間は 等しく曲がって見えなければならないとしている (= 等方的 )。
加速膨張理論と アインシュタインの方程式を組み合わせると 初期宇宙は 必ず特異点を含み (一様に限らず)、 これはつまり 初期宇宙では 一般相対性理論が破たんしていることを意味している。
しかし 彼らは 一般相対論を捨てようとはしない。なぜなのだろうか?
また 彼らは 非常に速い宇宙の加速膨張を 多世界解釈の世界の分岐 増加 に結びつけようとしている。
( しかし 多世界解釈というのは各1つの行為をとっても無限種類なければならず、はっきり言って これで補い切れる数ではないと思うが・・。)
ブラックホールは シュバルツシルト解から得られるが、これにも特異点が含まれる。
ご存じのとおり、ブラックホールはすべてを飲み込みため 直接観察することができない。
ブラックホールの存在は 完全に一般相対性理論に依存している。
( アインシュタイン自身は ブラックホールを信じていなかった。)
(Fig.7-2) ”便利な”光子は まったく無傷で ダークマター、エネルギー、ヒッグスを通過できる?
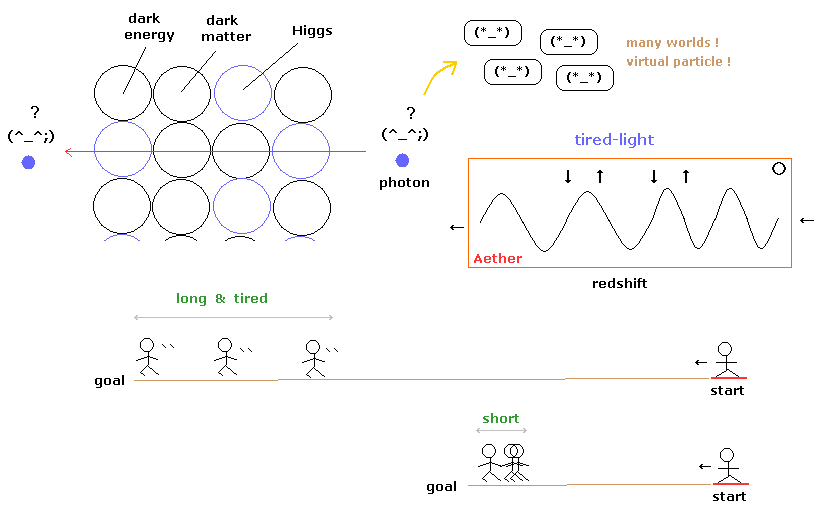
上で述べたように、奇妙な加速膨張宇宙の概念は 光子という粒子 が 宇宙空間に充満する ダークエネルギー、ダークマター、ヒッグス粒子などの無限の粒子の中を 非常に長期間にわたって まったく無傷で通り抜けられることを 前提条件にしている。
このページ (= 単一光子の干渉 ) に示したように、光子の粒子性の存在は 奇妙な多世界解釈様の重ね合わせを生み出す源となっている。
また 相対論の エネルギーと運動量の各2乗の関係式は このページに示したように、相対論に反する 仮想粒子なるものを生み出してしまう。
つまり、現在 地球から観測できる電磁波 (光子?) の情報だけで、 初期宇宙の詳細を判断することができず、 例えば ヘリウム 4、重水素、リチウムの比率だけから ”想像上の”ビッグバンを証明することはできない。
ダークマター効果や 重力、重力レンズに関係する 宇宙空間を占めるエーテルを無視することは また想像上のブラックホールに対する誤解の原因にもなり得る。
よって 宇宙ジェットや x線などの 間接的な観測のみで 相対論の因果率に反する ”見えない”ブラックホールの実在性の証明にはなり得ない。
マルチバースの 弦理論は こういった種の 一般相対論をベースとした 観察できないレベルの物や特異点などを 非常に好むようである。
なぜなら、現在のところ 一般相対論と量子力学を融合させる唯一の理論が ひも理論だからである。そして今度はこの量子論でこれらの問題を解決しようとする。
もちろん、一般相対論が間違っていたら、ひも理論自身も含めた 上記の解釈すべてを変更しなければならない。
また 一般相対論は 局所慣性系をベースにしているため、特殊相対論が間違っていたら、一般相対論も間違いである。
銀河系の縁のほうの星の回転スピードが内側の星と対して変わらない現象が知られている。
これは 通常の遠心力と重力理論を組み合わせても 説明することができない。
(Fig.8) ダークマターは ”宇宙空間のエーテル”の回転である。
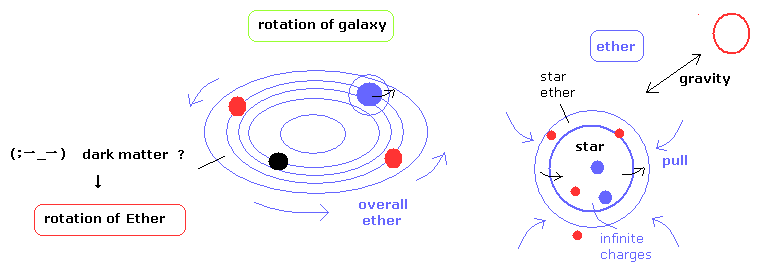
これはつまり 銀河系の回転において 一般相対論が破綻していることを意味している。
( しかしそれでも 彼らは一般相対論をあきらめようとしない。これは奇妙である。)
この穴埋めのため、奇妙な ダークマターなる概念が導入された。
このダークマターと上記のダークエネルギーは 宇宙の物質の大半を占めると言われているにも関わらず、まったく観測することができないおかしなものである。
これをするぐらいなら、宇宙空間の媒質 (= エーテル ) を認めて、上記の現象が この空間を占めるエーテルの回転とすれば自然に説明することができる。
ひも理論は 私たちの現実の世界の 臨界次元を決定する際に、数学上の概念である ゴーストや グラスマン数に頼っている。
グラスマン数は フェルミ粒子のように反交換で 次の関係式を満たす。
(Eq.1)
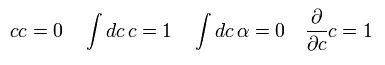
つまり グラスマン数では 積分が微分と同じなのである。
2つのグラスマン数でゼロ ( cc=0 ) ならば、積分もゼロになるべきだと思うが・・・。
これは奇妙である。
いずれにしろ、このグラスマン数は この現実の世界に実在する数ではない。
また ひも理論では、次の ゼータ関数を用いた "数学上"のトリックに頼らなければならない。
(Eq.2)
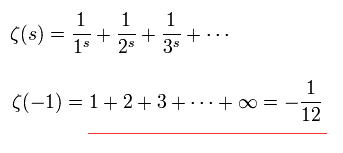
もちろん Eq.2 の計算は間違いである。
しかし このページに示したように、ひも理論は対称性を保つため この間違った数学を用いている。
結局のところ、この奇妙なひも理論を否定しない限り、上記のブラックホールや膨張宇宙の概念は生き残ると思われる。
もちろん、私たちは 宇宙の端や 初期宇宙や ブラックホールの内部に実際に行くことができないので これらの実際の状態を知ることができない。
率直に言えば、現在の宇宙理論は 空想上の概念に頼りすぎていると言わざるを得ない。空想上のひも理論と共に。
(Fig.9) ひも理論 = 多世界解釈。
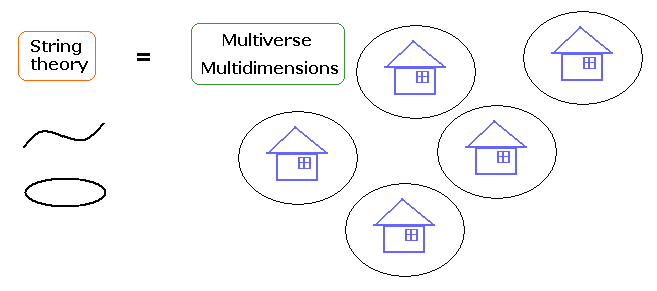
結論は、無限種類の異なった理論を含んでいる 超ひも理論は 多世界解釈にちょうど等しいと言える。
また 個人的には もし量子力学が正しいならば、この非常に奇妙な多世界解釈を受け入れなければならないと思う。
そのため あなたがたが 多世界解釈を回避したいと思うならば、ボーア模型を受け入れる以外に道がないだろう。
なぜなら、多世界解釈や ひも理論は 量子力学が根源になっているからである。
もしくは 量子力学を語るとき 哲学的な話をするしかない。
(Fig.10) 相対論は 影響力のある ディラック方程式によって生き残った。

このページに示したように、相対論が今まで生き残ってきた主要な要因は ディラック方程式にあると言っていい。
この非常に影響力のある式は 量子電磁力学、標準模型、超ひも理論における必須アイテムになっている。
電子の異常磁気能率の精密な計算結果の実験値との一致が 量子電磁力学 しいては 量子論の勝利のごとく言われている。
しかし このページに示したように 通常のディラック方程式の関係式を用いれば 余分な値を γ の項 (= 頂点) に人為的に移動すれば、この部分は 繰り込みで除去されるので g因子の異常磁気能率の値を操作することが可能である。
重要な点は 一般の人々が容易に これらの込み入った(単なる数学上の)理論に近付くことができないできないため、サイエンス本の言うことを信じるしかないということである。
私自身、この非常に込み入った量子電磁力学を2年以上にわたって勉強していた際は まだ量子力学を信じていた。
はっきりいうと、この非常に込み入った場の量子論こそが リアルなサイエンスの発展の 最大の妨げになっていると思われる。
この 数学のみと化した場の量子論と 役にたたない量子化学こそが 私が量子力学を疑うことになった 2大要因である。
( これらの理論を知ることによって ”洗脳”が解かれたといっていい。 )
(Fig.11) ヒッグスとは何か? 海? 抵抗? それとも 単なる数式?
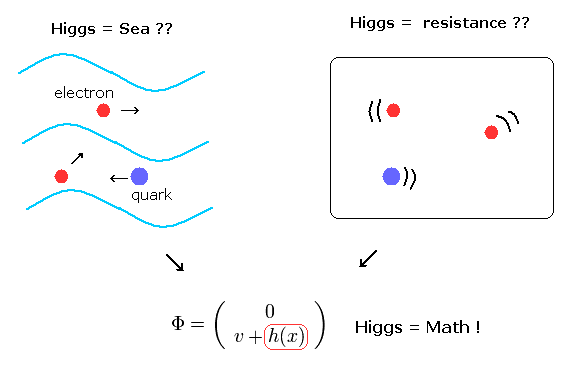
あなたがたは 現在の理論の ヒッグス粒子が空間上に敷き詰められている状態は 言ってみれば ”エーテル理論”そのものに等しいのではないかと思われるかもしれない。
しかし 彼らは決してこのことを認めようとはしない。
なぜなら ヒッグス粒子は 相対論的なクライン・ゴルドン方程式がベースになっているため、エーテルを否定した特殊相対論に依存しているからである。( このページも参照のこと。 )
しかし 現在の 空間状に無限のヒッグス粒子 (場) が存在する標準模型は エーテルを否定した相対論に完全に矛盾していると 思われる。
また 陽子の 125 倍もの質量を持つヒッグス粒子が 私たちの周りに敷き詰められているとしたら、なぜ まったく感じることができないのであろうか?
ヒッグス”粒子”は ヒッグス”場”と異なるもので、ヒッグス粒子は この場の中に隠れていると 主張する人たちがいるが、はっきり言って 言い訳のように聞こえてならない。
最初から(引きずり)エーテルを素直に認めてしまえば、こんな苦しいことにならなかっただろうし、非常に抽象的な場の量子論や 相対論に反する奇妙な仮想粒子に頼る必要もなくなる。
(Fig.12) 光子の”質量項”は ゲージ変換で不変でない。
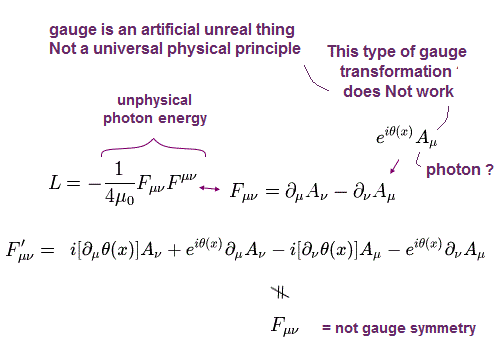
このページに示したように 彼らがどうしてヒッグス粒子を必要とするようになったかは もとはと言えば相対論の非常に厳しい制限にあると言っていい。
この厳しい制限の中で、ゲージ対称性という数学上の方向に進まざるを得なかったのである。
このゲージ変換対称性を保つために、ヒッグス粒子が必要となったわけだが、一般の人たちで この非常に抽象的な理由を知っている方々は少ないと思われる。
( 実際、テレビなどで 肝心なこの部分の説明が必ずといっていいほど省かれているからである。)
ただテレビなどで説明を省いているのは つまるところ この標準理論が単なる”数学上”の概念のものだからである。
( 決して彼らが悪いわけではない。)
(Fig.13) 新しいヘリウム原子模型 (= A.) は 電気的に分極していない。
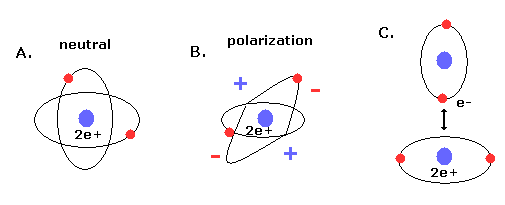
このページに示したように、2つの電子軌道が ちょうど対称的かつ垂直に交わっていると、ヘリウム原子核の周囲に 電子のマイナス電荷の偏りが生じない (= Fig.13A, neutral )。
もし この2つの電子軌道が非対称だと 原子核周囲の空間が 電気的に分極してしまい (= Fig.13B)、この分極によって 他原子と容易に 弱い結合を形成してしまう ( 例えば Fig.13C )。
要するに、これらの分極するケースでは ヘリウムが容易に液体などに凝集しやすくなり 事実に反することになる。
この 2つの電子軌道を垂直に交わらせ 空間上の電子分布を一様にさせるには 電子のドブロイ波の干渉効果に頼らざるを得ない。4つの基本的な力では説明できないからである。
量子力学のヘリウム模型は この波の力に言及してないので ヘリウムの 電気的な中性状態を説明することができない。
ご存じのとおり、スピン-スピン磁気相互作用は クーロン力に比較して格段に弱いため まったく説明にならない。
もちろん 実在のドブロイ波は エーテル理論(地球と共に動く)に他ならない。 (電磁波もドブロイの関係式を満たす。)
しかし コンピューターを用いて 非常に難解なヘリウムの3体問題を計算できない限り、私たちは 相対論が致命的なパラドックス を抱えているにも関わらず、それをベースとしたディラック方程式に頼らざるを得なかったのである。
量子力学の非常に奇妙な世界にも関わらず 現在の量子論が信頼されている もっとも主要な要因が 量子電磁力学 (QED) における 異常磁気モーメントの高次補正における実験値との正確な一致であろう。
実際 一般向けの物理の本なんか見ていると 小数何桁までの完璧の一致は 量子電磁力学がこの世で最も成功した理論であることを証明している とか何とか書いてある。
その割には どうしてこういう一致した計算結果になるかなど 数学的、物理的なしっかりとした根拠などは 今だに分かっていないのである。
実は このページ ( QED の異常磁気モーメントは操作可能である ) に示したように、この異常磁気モーメントの計算結果は 私たちの好きなように変更できるのである。
実際、この世で最も成功したとか おっしゃっている方々は 自分で計算したことがないのではと思われる。

2012/9/5 updated This site is link free.