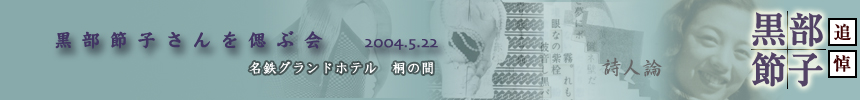
 |
|
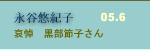 |
|
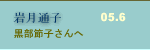 |
|
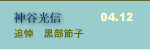 |
|
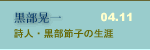 |
|
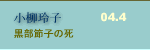 |
|
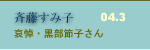 |
|
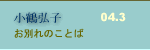 |
|
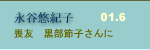 |
|
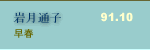 |
|
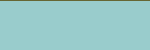 |
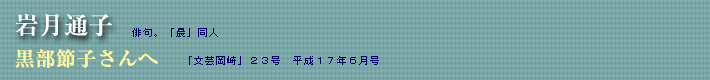
立春の光の中、節子さんの誕生日、貴女のいない、でも、もう、そこらじゅうに貴女のいる、二月の風が、ごうごうと吹きぬける。「節子さんの夢を見ました」と私が言うと、
「うちには、時々やって来ますよ」
と貴女の写真に囲まれた部屋で、黒部さんが微笑んだ。そして、つぶやいた。
「あと、十年位い、よかったかなあ」
貴女が昭和六十年一月三十日、五十三歳のお誕生日間近に倒れ、回復できないままの満十九年が過ぎ、二十年目の平成十六年二月十一日、私たちは貴女を喪った。誕生も死も、きらきらと眩しい早春、予感の季節に……。
去年は、黒部さんの御都合で、二月四日ではなく、私は七日の夕方、貴女を訪ねた。いつものように、貴女の枕元でハッピーバースディを歌った。貴女の詩を朗読した。あれから随分歳月がたつのに、貴女には詩を読むのは、何年ぶりだったろう。
第一、かぐわしい蘭とケーキのほかに、ふと貴女の詩集を手にして家を出たのも、いつ以来か、思い出せない。けれど、手にした時、貴女に読む詩はとうに決まっていた。「虹」。
三十年前に、貴女の指示通り、私は朗読した。名古屋伏見の桜画廊で。黒部節子詩集『いまは誰もいません』出版記念会。三十年、手ずれして毛羽立った表紙。
「感情ヌキ」「ゆっくり」「もっとゆっくり」貴女が私に話した通り、「虹」のページにメモが残る。鉛筆書きも、薄れて。
読みはじめると、貴女は、それまで歌も音楽もまるで届かないように見えた貴女は、突如瞠いて私を追った。枕から首をもたげて、聴こうとしていた。声の在処に向って。
「黒部さん。節子さんが聴いています。そうよ。節子さんの打ち合わせ通りだもの」
「虹」の朗読中、貴女の感覚は、熱を帯びて輝きつづけた。驚いた。喜んだ。黒部さんも私も。
「これからは、いつも『虹』を読みます」と私は夢中になって喋った。探しに探していた鍵を、やっと見つけた、と私には思われた。
それから四日目に、貴女は逝った。
私は受話器を置くと、飛び出しそうになった。が、留まった。何ができるかしら。貴女に、枕花を作った。その朝咲いた淡いピンクの二輪のカトレアで。
供華をささげて、貴女へと歩いた。三十四年前、初めて貴女に会いに行った日のように。
坂を上って行くと、幾度も幾度も、節子さん、貴女とすれ違う心地がした。
早朝の黒部家は、静まりかえって、ひんやりとしていた。玄関近くの部屋に、北枕の貴女がいた。黒部さんが白布をとり、いえ、私が白布をとったのか。いつもより更に神々しい貴女の顔が現われた。枕元の畳に、花を置いた。私は貴女に、話し続けた。
「ありがとう。節子さん」
「エッセーをまとめたいんです」傍らで、黒部さんが言われた。
お通夜があり、岡崎の密葬があった。貴女の出身地、三重県松阪市の三月の本葬に行き、ご親族の「お別れ会」に出席した。そして五月に名古屋で、詩人による「偲ぶ会」に参加した。二度、「虹」を朗読した。
なきがらに
花降り
光降る
涅槃
初めて、多行の句が、私に生れた。
松阪の本葬から帰宅した翌朝、日曜日だった。私は伊賀八幡宮から南へ、伊賀川に沿って、蕾のふくらんだ桜並木を歩いた。日曜のせいか、誰もいなかった。突然、涙が溢れ号泣した。堰を切って。二十年、貴女と話せないことを、私もこんなにも堪えていたのだった。貴女はごくかすかな五感を保ち、平穏な時は、村上華岳の菩薩を思わせた。しかし、苦しそうな時もあった。嗚咽しながら、歩いた。川の流れと共に。私から限りなく溢れ出る力に、私自身圧倒されながら……。
黒部さんと御長男の晃一さんのご意向で、節子さんの遺稿随筆集『遠くのリンゴの木』編集のお手伝いをした。貴女に贈った私の朗読テープが、十九年ぶりに戻り、私は自分の声に再会した。ひとり家の洋間で録音した。貴女の詩の朗読カセットテープ。およし一時間。昭和六十年三月十九日の日付。貴女が倒れて五十日後。その最初の一篇も、やはり「虹」だった。能管、福原百之助作曲「嵯峨野秋霖」をバックに。
「岩月さんと節子は、波長があったんだね」
「どこかしら、節子はいつも楽しそうに見えた」
黒部さんの言葉に、私は深く頷いた。