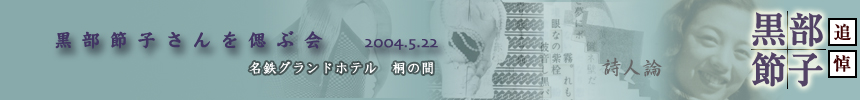
 |
|
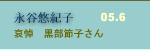 |
|
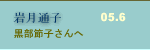 |
|
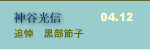 |
|
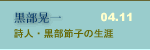 |
|
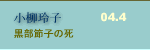 |
|
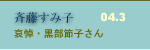 |
|
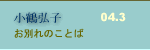 |
|
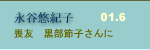 |
|
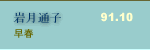 |
|
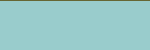 |
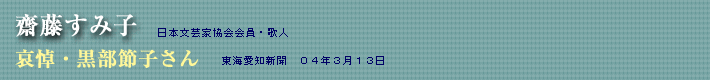
詩人の黒部節子さんが二月十一日に亡くなった。無常迅速な時間は二十年を経過したが、遂に黒部さんの意識は戻らなかった。
黒部さんの詩集は詩集『白い土地』(一九五七)から始まっている。詩画集『柄』(一九六六)、詩集『いまは誰もいません』(一九七四)等、好調に詩集を世に問われていたが一九八五年脳内出血に倒れ、以後長期療養に入ったまま意識は戻らなかったのだ。
だが黒部さんの真価は、眠った状態の中で世に知らされることになる。倒れた後に、ご子息と東京の小柳玲子さんの編集によって出版された詩集『まぼろし戸』(一九八七)が、詩壇で権威のある「詩人クラブ賞」を受賞した。
更に、それまでの詩集に未収録であった作品を小柳さんが編集して出版された詩集『北向きの家』(一九九六)が、「土井晩翠賞」を受賞したのだ。著者は眠ったまま、二つの大きな賞を取ったということで、文学の世界ではかなり話題になったものである。
黒部さんの作品傾向を端的にいうならば、<幻想的>ということであろうか。日常生活の中において、かすかに忍び寄るものの気配を、美しくからめとった作品が多い。生活の中の苦しみとか現実的な煩雑さなどは、作品にする前に消去され、感情を純化しながら詩の言葉を紡いでおられたのであろうと、しみじみ思い起こす。
だから、人によっては難解ととられたであろうが、黒部さんは頑固に自分の作風を貫いたといえよう。難しくてわかりにくいと、言われようと何と言われようと、読者には媚びない高い精神を持続した人であった。
私は家も職場も黒部さんのお宅に近く、年齢も近かったので、黒部さんが健康な時から親しくおつき合いをさせていただいた。
実は黒部さんの脳内出血は、二回目であった。一回目の後遺症で右半身がきかず、足を少しひきずりながらそれでも元気で、左手で右手で書くのと同じくらい、ふくらみのあるやさしい字を書いて、私を驚かせた。
「右手がダメになったのなら、かわりに左手で、右手の分まですればいい」
「ダメとわかったものにいつまでもかかわっていると、屈辱的な事態に追い込まれる」
などと、二人でゆっくり話し合ったことがある。あの時黒部さんは、右半身の障害を乗り越えて、再生をはかろうとしておられた。そして私もまた、離別という修羅場をくぐって、目に見えない障害を負っていた。
意識がまだ戻らないと聞いて、見舞いにゆくのを私は遠慮していたが、それでも黒部さんの病状はいろいろな人から伝わってきていた。
「太陽に当らないため肌の色はますます白く血色がよく、童女のように清らかなひとみを見開いている」と言った人があったが、終焉までそうであったとに違いないと、私は思うことにしている。