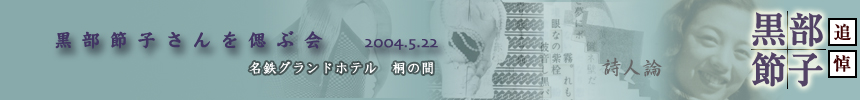
 |
|
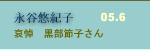 |
|
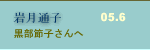 |
|
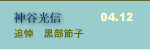 |
|
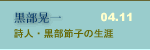 |
|
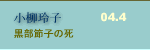 |
|
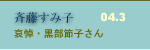 |
|
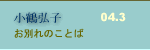 |
|
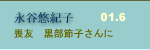 |
|
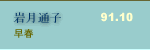 |
|
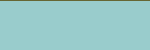 |
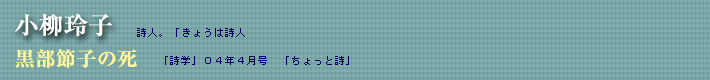
この二月十一日、黒部節子の死がご家族から伝えられた。一九八五年脳内出血により意識を失って以来十九年間眠り続けていた詩人は、 ほんとうの深い眠りに入ったのだった。
空には
劇場がある
砂漠は晴れていて
森は曇っているという
子供は死んでいて 鳩は
生きているという
どちらがほんとうなのかわからない
でも
<夜も昼も>
と叫んでいる声がする
―――詩集『まぼろし戸』から(空には)全文
黒部さんは若い日に詩誌「アルファ」を数人の詩人と創刊しそこに魅力ある詩を毎号発表していた。 ほかに板倉鞆音訳のケストナーやリンゲルナッツ、の詩が掲載されている私にはまたとない刺激的な詩誌であった。 私は臆面もなく彼女にファンレターを書き、「たぶんあなたは気配といったものを書こうとしているのでしょう」などと感想を述べた。 赤面の至り。その後、四十歳の頃彼女は高血圧の発作で倒れ、文通は途絶えていた。
私が彼女と直接出会ったのは彼女が奇跡的に病を克服し、上京された時である。 彼女の才能に瞠目していた嵯峨信之さんが「ぜひ上京しなさい。 逢いたい詩人がいたら逢わしてあげる、誰がいいか、西脇さんでも茨木さんでもいいよ」といったらしい。 ところが黒部さんが逢いたかったのは小柳玲子で、嵯峨信之をあきれさせてしまった。
病後の黒部さんは右半身に軽い麻痺が残っていたため左手で書くようになっていたが、いままでの理知的に構成されていた詩に、 いわく言い難い気配がさらに濃く漂いはじめ読者を魅了した。二度目の発作で倒れる一、二年前から「本星崎」の連作詩を発表していたが、 この詩には間もなく彼女が住むことになるこの世とあの世との境界の世界が描写されていたようである。 うす墨色の静謐な詩を五編書いたところで彼女は倒れ、二度と意識が戻らなかった。
いまになって大きなことをいうようで気がひけるが、私は黒部節子その人より、黒部節子の詩のよき理解者であったと思う。 彼女の意識がほぼ戻らないだろうと伝えられてから、私は彼女の詩集を二冊も編集発行した。 その詩集は二冊ともに詩壇の伝統ある賞を受けることになった。回復の見込みの少ない詩人に賞が与えられることは稀なので、 ご家族は驚愕されてしまったが、こっそり、一番、驚愕したのは私である。やすらかで、静かなのは黒部さんだけである。
夕方
田んぼが青白く光りだすころ
病人は悪くなります
少しずつ
そして急に悪くなります
隣の仏間とつづいた広い畳の
向うに とても遠く
庭が見えます
―――詩集『北向きの家』より (夏の部屋)部分
黒部さんの死は春であったが、彼女の世界はこんな季節で、おそらく死は彼女をこのように迎えきたのだと、信じている。