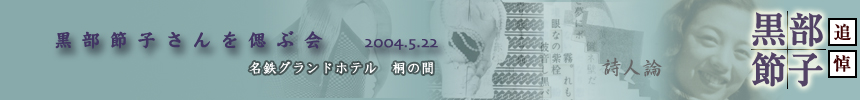
 |
|
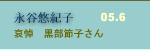 |
|
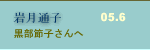 |
|
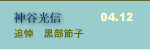 |
|
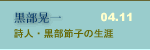 |
|
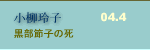 |
|
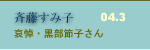 |
|
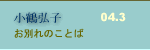 |
|
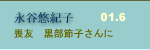 |
|
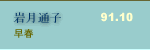 |
|
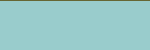 |

本年二月十一日、詩人であり私の母であった黒部節子が、長い闘病生活を終えて七十二年の生涯を全ういたしました。私は、最後に母と交わした会話が何であったのか(もう十九年前のことになりますが)遠い記憶をたどりながら、あらためて三つの異なった母の人生――若く健やかだった青年期、障害を抱えて生きた壮年期、そしてずっと床に病臥していた晩年の姿を思い出していました。
松阪市法田町の櫛田川のほとりに、母の生家は今も静かに佇んでいます。祖父竹雄の仕事の関係で、生後すぐに伊賀上野へ移り住み、その後の小学校時代は東京ですごすことになったため、法田の家で実際に生活していたのは、正月や夏期休暇など特別の期間に限られていました。幼少時代に各地を転々と移り住んだことは、母の精神形成に大きな影響を与えることになりました。
戦災のため松阪に疎開した母は、飯南高等女学校に転入し、高校二年のときに松阪南高校(現松阪高校)に編入しました。このとき、国語の先生であった親井修氏に現代詩の講義を受け、親井氏が主催していた詩誌「詩表現」(昭和22年創刊)に、最初の詩を発表しています。奈良女子大学時代には、親井氏から詩人であり太宰治の主治医としても知られていた中野嘉一氏を紹介され、中野氏主催の詩誌「暦象」に長く参加することになります。
結婚後は愛知県岡崎市に転居します。高台の上に建てられた岡崎の家は私たち子供にとっても思い出深い場所です。この岡崎の家を拠点として、母は新しい生活をスタートさせました。母の処女詩集のタイトルである「白い土地」は、この未知で新しい土地に対して冠せられています。私たち子供は男ばかりの三人で、育児や教育で人並みの苦労はあったにせよ、このときはまだ病気の予感もなく、幸福な家庭を育んでいたと言ってよいのかもしれません。しかし若いときに母が残した詩を読むと、生を謳歌するみずみずしい言葉の陰に、何かしら生への不安、死への予兆を思わせるくらがりを感じることがありました。
私たち子供がもっとも手のかかる年齢にさしかかったあたりから、母は主催する詩誌「アルファ」の編集や、随筆・脚本の執筆、高校教師の職務など、多忙を極めてきました。幼少時に多くをすごすことのなかった松阪市法田町の生家をモチーフとした詩が登場し出したのはこの頃です。最初の病気に倒れる一年前には、生家と自らの家系について綴った二九五行に及ぶ長大詩「川の家」が生まれています。浮世の世界よりも、遠い過去に幼い魂が感応した滅びゆく家の幻影を見始めたのも、あるいは何かを予感したのでしょうか。
四十歳のときに、母は名鉄メルサの喫茶店内で、人事不省に陥りました。脳内出血でした。四日後に意識を回復した母を、私は学校からの帰り道すがら病院に見舞いました。病室のベッドに横たわりながら、私の呼びかけに対して、言葉を失った母は私の方を見てずっと笑っていたのを覚えています。久しく見ていなかった笑顔でした。この日を境に、母は右半身の自由とともに、人が生きてゆく上で背負わざるを得ない業のようなものをも失ってしまったような気がしてなりません。それまで気高く厳しかった母は、童女のようにいつも微笑んでいる優しい母に変わりました。「病気前は私のお姉さんのような存在だったのに、病気後は可愛い妹さんのような存在になった」とは、「アルファ」創刊当時からの母の古い友人の言葉です。
詩人にとって、言語機能が損なわれたのは何より辛かったはずですが(最初は私たち子供の名前さえ思い出せなかったそうです)、持ち前の忍耐強さも手伝って、少しずつ言葉を取り戻していきました。右半身には結局麻痺が残ったままでしたが、左手できれいな文字を書けるようにも快復しました。この頃の母は、決して軽くはない障害を抱えながらも、穏やかでいつも愉しそうにしていたのを思い出します。病気後の母を知る多くの方が、ゆっくりと半身を引きずるように歩く姿に独特な優美さを感じたと言っています。病気になった自分をごく自然に受け入れ、言わば詩の化身となったようなその姿に。
偶然の符合かもしれませんが、病気後十年ほど経って、再び郷里の生家をモチーフとした何篇かの詩が登場してきています。また、後にある詩人が、「彼女が間もなく住むことになるこの世とあの世との境界の世界」と称した「本星崎」という連作詩を発表し、これが母の絶筆となりました。
昭和六十年一月末日、母は自宅で再び昏睡状態に陥りました。私たちも全く予期していなかったことでした。母はそのまま深い眠りに入り、ベッドで病臥する身となりました。しかし二度と眼を醒ますことはありませんでした。父と家政婦さんの献身に支えられて、十九年という歳月がすぎていきました。生前に母は「いつか私は松阪の家に帰っていくだろう」と書いたことがありましたが、結局、松阪には戻ることなく三十年近く住んだ岡崎の家で人生を終えることになりました。しかし、母はずっと眠り続けながら、今では誰も住む者がいなくなった松阪の家へ帰っていたのではないかと思うことがあります。倒れる六年前に書いた松阪の生家についての書簡体エッセイ「乗客ひとり」の結びを見ると、母はどこかで今日までの自分を予期していたのかもしれません。
…………
急な階段をのぼってゆくと、二階のくらい窓から草原が見え、ぼんやりした川が見えます。そのずっと向うに、うす墨をはいたような鉄橋。 今、小さな灯をつけた汽車が音もなくわたっていきます。汽車が神山(こやま)さんの麓にかくれてしまうと、急にあたりが暗くなりました。
もう、仕掛けておいたお米が炊けたころです。それよりも早く戸を締めなくてはなりません。
Kさん。お元気で。ときどき、思い出して下さい。 そのときはきっと、私はここにいますから。
たぶん母は生涯を通して、自分の<ふるさと>を探し続けたのだと思います。そしてすべてから解放された今、ようやくその<ふるさと>にたどり着き、「川の家」にも書かれた懐かしい人々に再会しているに違いない――そのように考えています。