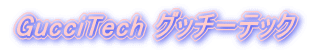2011年11月12日 ㈱秋月電子通商の8ch-10bit Data-Loga&XBee Module 無線化
![]() ㈱秋月電子通商で販売されている、PIC16F877を使ったデータロガキット(2023年9月現在、5,500円 完成品)のシリアル通信を使い、Digi International社のRFモジュール Zigbee XBeeを装着して
データ情報を無線通信かしてみました。
㈱秋月電子通商で販売されている、PIC16F877を使ったデータロガキット(2023年9月現在、5,500円 完成品)のシリアル通信を使い、Digi International社のRFモジュール Zigbee XBeeを装着して
データ情報を無線通信かしてみました。
2011年10月02日 ボトムガムケースを使ったセンサーライト
![]() ボトムガムケースを使ったセンサーライト!ケースは白いビニール材料のもので、中にLEDの証明を入れると、ほんのり白く全体が光、心地よい光を放ちます。この中に、8ピンのPIC12F1822マイコンと
赤外線センサーライトモジュールを入れ、人が通るとセンサーが感知し、最大4分20秒ほど点灯し、消灯時には、徐々に暗くなる動作をさせました。
ボトムガムケースを使ったセンサーライト!ケースは白いビニール材料のもので、中にLEDの証明を入れると、ほんのり白く全体が光、心地よい光を放ちます。この中に、8ピンのPIC12F1822マイコンと
赤外線センサーライトモジュールを入れ、人が通るとセンサーが感知し、最大4分20秒ほど点灯し、消灯時には、徐々に暗くなる動作をさせました。
2011年06月27日 多チャンネル版!学習リモコン受信機。最大6chの登録が可能!
![]() 1ch版学習リモコンを多チャンネル化しました。登録したいマスターリモコンを用意し、最大6chのボタンを登録し、ON/OFFさせることが出来ます。家電協フォーマット、NECフォーマット、SONYフォーマットの
3種類のフォーマットに対応します。出力は、リレー接点c、a、bの3端子を設けました。動作はオルタネート動作と、パルス動作の2択です。一度登録すると電源を切っても記憶しています。
使用したマイコンは、18ピンのPIC16F1827です。
1ch版学習リモコンを多チャンネル化しました。登録したいマスターリモコンを用意し、最大6chのボタンを登録し、ON/OFFさせることが出来ます。家電協フォーマット、NECフォーマット、SONYフォーマットの
3種類のフォーマットに対応します。出力は、リレー接点c、a、bの3端子を設けました。動作はオルタネート動作と、パルス動作の2択です。一度登録すると電源を切っても記憶しています。
使用したマイコンは、18ピンのPIC16F1827です。
2011年05月30日 ボタン電池1個で動作する超小型、3桁LED表示の直流電圧計。
![]() ボタン電池1個で動作する、超小型直流電圧計を作りました。18ピンのPIC16F1827を使い、内部の12bitA/Dコンバータと外部リファレンス電圧IC LM336Z-2.5Vを使いました。そのおかげで、精度も1%以内で、
ちょっと計測するには十分な制度です。電池の消耗を減らすため、7セグメントLEDは、間欠表示させています。電流も一緒に計測することが出来ます。
ボタン電池1個で動作する、超小型直流電圧計を作りました。18ピンのPIC16F1827を使い、内部の12bitA/Dコンバータと外部リファレンス電圧IC LM336Z-2.5Vを使いました。そのおかげで、精度も1%以内で、
ちょっと計測するには十分な制度です。電池の消耗を減らすため、7セグメントLEDは、間欠表示させています。電流も一緒に計測することが出来ます。
2011年05月23日 3種類のフォーマットに対応した、学習リモコン受信機
![]() 1ch版の学習するリモコン受信機です。各社テレビ、リモコン照明機器、扇風機、オーディオなどのリモコンを使った信号を登録し、登録した信号を再現させて、同じ動作をさせるモジュールです。
動作はオルタネートのみで、押すたびにON/OFFを繰り返します。リモコン信号は家電協フォーマット、NECフォーマット、SONYフォーマットに対応します。使用マイコンは、8ピンのPIC12F1822です。
1ch版の学習するリモコン受信機です。各社テレビ、リモコン照明機器、扇風機、オーディオなどのリモコンを使った信号を登録し、登録した信号を再現させて、同じ動作をさせるモジュールです。
動作はオルタネートのみで、押すたびにON/OFFを繰り返します。リモコン信号は家電協フォーマット、NECフォーマット、SONYフォーマットに対応します。使用マイコンは、8ピンのPIC12F1822です。
2011年05月13日 100円リモコンを入手し、信号を解析してみました
![]() 大阪にある共立電子産業㈱社の店舗で「デジット」と言う店があります。結構レアな電子部品をかなりの数を置いています。そこで見つけた100円リモコンですが、どのような通信を行うのか、
解析してみました。解析した結果。NECフォーマットであることが分かりました。使用したマイコンは、8ピンのPIC12F1822です。
大阪にある共立電子産業㈱社の店舗で「デジット」と言う店があります。結構レアな電子部品をかなりの数を置いています。そこで見つけた100円リモコンですが、どのような通信を行うのか、
解析してみました。解析した結果。NECフォーマットであることが分かりました。使用したマイコンは、8ピンのPIC12F1822です。
2010年11月13日 滴の様に流れるLEDフラッシュを製作。繋いで動作が可能です
![]() クリスマス時期になるとホームセンターなどではイルミネーション商品がたくさん展示されます。毎年、すごい数と新しいものが出品され、いつも見とれていました。ある時、滴が流れるようなLED照明があり、
それは感動しました。値段を見て驚いたのですが、片面20個くらい、両面で40個くらいのLEDモジュールが5連で3万円には驚きました。それなら自分で作ろうと考えました。使用したマイコンは、6ピンのPIC10F222です。
クリスマス時期になるとホームセンターなどではイルミネーション商品がたくさん展示されます。毎年、すごい数と新しいものが出品され、いつも見とれていました。ある時、滴が流れるようなLED照明があり、
それは感動しました。値段を見て驚いたのですが、片面20個くらい、両面で40個くらいのLEDモジュールが5連で3万円には驚きました。それなら自分で作ろうと考えました。使用したマイコンは、6ピンのPIC10F222です。
2010年05月24日 180度位相が異なる2相のパルス発生器を製作
![]() 簡易2相パルス発生器を製作しました。それぞれの位相は180度異なります。周波数は、2Hz~250kHzと、1Hz刻みで設定ができ、ディーティ比も1%~99%まで可変できます。
Amazonにも似たような基板が売られていますが、周波数は150kHZまでで、2相の波形は出せません。スイッチング電源などの実験や試験にには役に立つと思います。
簡易2相パルス発生器を製作しました。それぞれの位相は180度異なります。周波数は、2Hz~250kHzと、1Hz刻みで設定ができ、ディーティ比も1%~99%まで可変できます。
Amazonにも似たような基板が売られていますが、周波数は150kHZまでで、2相の波形は出せません。スイッチング電源などの実験や試験にには役に立つと思います。
2009年08月26日 SHT11を使った温度、湿度計の製作
![]() SENSIRION社の温度・湿度センサー SHT11を使った計測器を作りました。このセンサーは、温度においては標準温度精度:0.4℃、標準相対湿度精度:3%RHと言う、高性能なセンサーです。
応答時間も温度は;5秒、湿度は;8秒とされています。インターフェースは「センシバス」と言う独自の信号を持っています。使用したマイコンは、40ピンのPIC16F877Aです。
SENSIRION社の温度・湿度センサー SHT11を使った計測器を作りました。このセンサーは、温度においては標準温度精度:0.4℃、標準相対湿度精度:3%RHと言う、高性能なセンサーです。
応答時間も温度は;5秒、湿度は;8秒とされています。インターフェースは「センシバス」と言う独自の信号を持っています。使用したマイコンは、40ピンのPIC16F877Aです。
2009年07月08日 ブラシレスモータを駆動させ、回転数制御が可能
![]() 旧、コパル電子㈱社で、今は日本電産コパル㈱と言う会社で製造されていたブラシレスモータを駆動してみました。現在は、販売されていないようです。このモータには、駆動コイルの他に、
回転信号FGが内蔵されていて、1回転に6パルス出力されたものです。この信号を使い、回転数を表示し、さらにフィードバックさせてモータのディーティを可変しています。
使用したマイコンは、28ピンのPIC16F886を使いました。
旧、コパル電子㈱社で、今は日本電産コパル㈱と言う会社で製造されていたブラシレスモータを駆動してみました。現在は、販売されていないようです。このモータには、駆動コイルの他に、
回転信号FGが内蔵されていて、1回転に6パルス出力されたものです。この信号を使い、回転数を表示し、さらにフィードバックさせてモータのディーティを可変しています。
使用したマイコンは、28ピンのPIC16F886を使いました。
2009年05月25日 CCP機能を使って、デジタル回転計の製作
![]() モータ開発が多いため、回転数を計測するツールが欲しくて、自作してみました。10rpm~50,000rpmまでの範囲を計測できるものです。センサーは反射型を使い、軸に反射シールを貼って計測します。
rpmとrpsの単位切り替えも行えます。また、計測サンプリング速度も0.5秒と1秒も切り替えることが出来ます。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876を使いました。
モータ開発が多いため、回転数を計測するツールが欲しくて、自作してみました。10rpm~50,000rpmまでの範囲を計測できるものです。センサーは反射型を使い、軸に反射シールを貼って計測します。
rpmとrpsの単位切り替えも行えます。また、計測サンプリング速度も0.5秒と1秒も切り替えることが出来ます。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876を使いました。
2009年04月30日 CCP機能を使って、直流モータの回数を転制御!
![]() とある100均で電池駆動の撹拌機が売られていました。モータとスイッチ、先端は小さな金属の攪拌棒です。大きなものは無理ですが、ちょっとした小さいものであれば、これで間に合いますが、
攪拌する材料によっては、回転数を変えたい時があります。そこで、この撹拌機に回転数可変機能を搭載しました。使用したマイコンは、8ピンのPIC12F683を使いました。
とある100均で電池駆動の撹拌機が売られていました。モータとスイッチ、先端は小さな金属の攪拌棒です。大きなものは無理ですが、ちょっとした小さいものであれば、これで間に合いますが、
攪拌する材料によっては、回転数を変えたい時があります。そこで、この撹拌機に回転数可変機能を搭載しました。使用したマイコンは、8ピンのPIC12F683を使いました。
2008年08月30日 はじめての16ビットマイコンを触る!遅延パルサーの製作
![]() 16ビットマイコンの勉強で、遅延パルス発生器と言うものを製作しました。基準パルスを発生させ、そのパルスから設定した時間後に、別のパルスを発生させるものです。時間設定は広範囲にわたり、
100nS~99.999999秒まで設定が行えます。最近のマイコンを使えば、もっと簡単に作ることが出来ると考えています。使用したマイコンは、28ピンのdsPIC30F4012を80MHzで動かしています。
16ビットマイコンの勉強で、遅延パルス発生器と言うものを製作しました。基準パルスを発生させ、そのパルスから設定した時間後に、別のパルスを発生させるものです。時間設定は広範囲にわたり、
100nS~99.999999秒まで設定が行えます。最近のマイコンを使えば、もっと簡単に作ることが出来ると考えています。使用したマイコンは、28ピンのdsPIC30F4012を80MHzで動かしています。
2008年08月17日 位相角ピンポイントパルサーの製作
![]() 商用周波数などの波形で、狙った位置にパルスを打ち込むという、おもしろいパルス発生器を製作しました。打ち込める位相は、0度~360度のどの位置にもパルスを打ち込めます。打ち込める波形は
正弦波を対象とし、その周波数は、10Hz~200Hzの範囲の波形で制御が可能です。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876Aを使いました。
商用周波数などの波形で、狙った位置にパルスを打ち込むという、おもしろいパルス発生器を製作しました。打ち込める位相は、0度~360度のどの位置にもパルスを打ち込めます。打ち込める波形は
正弦波を対象とし、その周波数は、10Hz~200Hzの範囲の波形で制御が可能です。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876Aを使いました。
2008年06月29日 商用周波数パルス可変スイッチの製作
![]() 商用周波数を使った負荷をかけるものは、工具などをはじめとして、たくさんあります。可変方法も色々とあり、一番高価なものは、インバーターを使用するものです。また、安価にできるものとして、
トライアック素子などを使用した位相制御で可変するものがあります。それぞれ特徴があるのですが、今回は、1サイクルの位相時間を計測し、その位相で、ONの数とOFFの数の比、つまりデューティーを
設定できるものを作りました。応用はいろいろとあります。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876Aを使っています。
商用周波数を使った負荷をかけるものは、工具などをはじめとして、たくさんあります。可変方法も色々とあり、一番高価なものは、インバーターを使用するものです。また、安価にできるものとして、
トライアック素子などを使用した位相制御で可変するものがあります。それぞれ特徴があるのですが、今回は、1サイクルの位相時間を計測し、その位相で、ONの数とOFFの数の比、つまりデューティーを
設定できるものを作りました。応用はいろいろとあります。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876Aを使っています。
2008年06月17日 I2Cバス・RTC-8564を使った日付と時間を表示させる
![]() I2Cバス通信を勉強するため、I2Cバスを持ったRTCモジュール、エプソントヨコム㈱社製のRTC-8564NBを使い、日付と時間を表示させるものを作りました。I2Cを使い慣れると、色々なものが存在し、
特に、センサー系には、多くの半導体があるようです。使用したマイコンは、40ピンのPIC16F877を使いました。
I2Cバス通信を勉強するため、I2Cバスを持ったRTCモジュール、エプソントヨコム㈱社製のRTC-8564NBを使い、日付と時間を表示させるものを作りました。I2Cを使い慣れると、色々なものが存在し、
特に、センサー系には、多くの半導体があるようです。使用したマイコンは、40ピンのPIC16F877を使いました。
2008年06月09日 フルカラーLEDのカラー表示の実験
![]() フルカラーLEDが色々なものが出回り、基本的には、RGBとして256色が発行できるようです。今回は、3つのRGB端子をPWM制御を行い、256色を目指してプログラミングをしようと思いましたが、
挫折してしまい、結局、6色しか点灯できないものになってしまいました。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876を使いました。
フルカラーLEDが色々なものが出回り、基本的には、RGBとして256色が発行できるようです。今回は、3つのRGB端子をPWM制御を行い、256色を目指してプログラミングをしようと思いましたが、
挫折してしまい、結局、6色しか点灯できないものになってしまいました。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876を使いました。
2008年06月06日 3桁7セグメントLEDを使った電圧計の製作
![]() 前から気になっていたのが、3桁や4桁の日の字型、7セグメントLEDが、多くの種類が増えてきて、中には、青や白など、非常に綺麗なものまで、出てきています。これを使って、何かできないかと考え、
結局、直流電圧計を作ることにしました。割と精度の高いものを目指しました。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876を使いました。
前から気になっていたのが、3桁や4桁の日の字型、7セグメントLEDが、多くの種類が増えてきて、中には、青や白など、非常に綺麗なものまで、出てきています。これを使って、何かできないかと考え、
結局、直流電圧計を作ることにしました。割と精度の高いものを目指しました。使用したマイコンは、28ピンのPIC16F876を使いました。
Arduino Uno , Micro , Nano , Mega
2012年08月12日 環境計測モジュール 最終形に仕上げました!
![]() 当時、ATMEL社であったマイコンを使って、ATtiny2313-20PUを使い、I2Cで40文字×2行の液晶を制御し、ATmega328P-PUを使って温度・湿度センサーにSHT-11とBMP085と言う気圧センサー、
日時表示のRTC-8564NB、S9648の照度センサー、さらに、XBee無線モジュールとSDカードを搭載した、環境計測器を完成させました。データは、日時の他に、温度、湿度、気圧、照度などを
液晶に表示し、さらに、無線でデータを飛ばし、SDカードに記録するという、大変面白いデータロガを製作しました。
当時、ATMEL社であったマイコンを使って、ATtiny2313-20PUを使い、I2Cで40文字×2行の液晶を制御し、ATmega328P-PUを使って温度・湿度センサーにSHT-11とBMP085と言う気圧センサー、
日時表示のRTC-8564NB、S9648の照度センサー、さらに、XBee無線モジュールとSDカードを搭載した、環境計測器を完成させました。データは、日時の他に、温度、湿度、気圧、照度などを
液晶に表示し、さらに、無線でデータを飛ばし、SDカードに記録するという、大変面白いデータロガを製作しました。
2010年10月03日 温度、湿度、気圧、照度、日時を同時計測する
![]() Arduinoを始めるきっかけになったのは、「galileo7」と言うサイトで、日時、温度、湿度、気圧のデータロガが売られており、さらに、サンプリングしたデータを音声でしゃべってくれるという
大変おもしろいモジュールをキット販売したものでした。現在この会社は存在していませんが、わくわくして製作したのを覚えています。
Arduinoを始めるきっかけになったのは、「galileo7」と言うサイトで、日時、温度、湿度、気圧のデータロガが売られており、さらに、サンプリングしたデータを音声でしゃべってくれるという
大変おもしろいモジュールをキット販売したものでした。現在この会社は存在していませんが、わくわくして製作したのを覚えています。
2010年10月03日 Arduinoの事始め・・・!
![]() Arduinoを勉強するうえで、色々な書籍を集め、基板を集めました。現在では、ものすごい種類のArduinoが存在し、何より、無償でプログラミングができる環境が構築できることが、最大の魅力でした。
Arduinoは進化を遂げ、現在では32ビット級の半導体も無償で、簡単に制御できるようになっています。
Arduinoを勉強するうえで、色々な書籍を集め、基板を集めました。現在では、ものすごい種類のArduinoが存在し、何より、無償でプログラミングができる環境が構築できることが、最大の魅力でした。
Arduinoは進化を遂げ、現在では32ビット級の半導体も無償で、簡単に制御できるようになっています。
Raspberry Pi , Pi Pico
ESP32 , ESP8266 by Espressif Systems
ARM mbed by NXP Semiconductors
2011年06月07日 wiiリモコンとBluetoothを使いロボットアームを操作
![]() とあるWebサイトに、任天堂のwiiのリモコンを使った作品が紹介されていて、これは面白い!と思い、自分も丁度、任天堂のゲームを持っていたので、作ることにしました。その応用編として
㈱イーケイジャパンと言う会社が販売していた、ロボットアーム、MR-999と言うものを、確か2,000円弱で購入できたので、5軸の制御を行ってみました。高速動作はできなかったですが、
お祭りなどでも使えそうな、面白いおもちゃが出来ました。
とあるWebサイトに、任天堂のwiiのリモコンを使った作品が紹介されていて、これは面白い!と思い、自分も丁度、任天堂のゲームを持っていたので、作ることにしました。その応用編として
㈱イーケイジャパンと言う会社が販売していた、ロボットアーム、MR-999と言うものを、確か2,000円弱で購入できたので、5軸の制御を行ってみました。高速動作はできなかったですが、
お祭りなどでも使えそうな、面白いおもちゃが出来ました。
2011年06月07日 wiiリモコンとBluetoothの通信実験
![]() 任天堂のwiiのリモコンは、なんと、Bluetoothで動作していることが、とあるサイトに掲載されていて、それを応用して、I/Oインターフェースを製作して、LEDを光らせてみました。
それを応用すれば、色々面白そうなものができるのではと思いました。
任天堂のwiiのリモコンは、なんと、Bluetoothで動作していることが、とあるサイトに掲載されていて、それを応用して、I/Oインターフェースを製作して、LEDを光らせてみました。
それを応用すれば、色々面白そうなものができるのではと思いました。
Copyright (c) Gucci Tech.2007.All rights.