『ガラスの中のお月さま』久保 喬
ガラス工場のガラスの窓から、お月さまがさしこみました。
そのガラス工場の中には、ガラス板や、ガラスのびん、ガラスのさら、ガラスのはち、ガラスのくだ、ガラスのつぼなど、いろいろなガラスで作ったものが、いっぱいならんでいます。
みんなでそれは、千三百三十六もありました。そのガラスの一つ一つに、お月さまがうつっています。なんとたくさんのお月さま。千三百三十六のお月さまが、生まれたのです。
「きらきら、つるつるっ、つめたいなあ、ガラスくんは。」
「するする、すうっ、つめたいなあ、ガラスくんは。」
あちこちのガラスの中のお月さまが、つぶやきました。
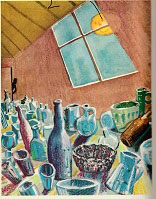 「ええ、つめたいのは、生まれつきですよ。」
「ええ、つめたいのは、生まれつきですよ。」
青白くて、ほっそりしているガラスびんがいいました。それはやがて、病院へいって、薬びんになるびんでした。
「でも、お月さまだって、つめたいじゃありませんか。」と、ガラスのさらがいいました。
「そうかなあ。」
「ひるまいらっしゃるお日さまなんか、ほてほてっとして、あったかいですよ。」
「そうそう、まるで、あついくらいだ。」と、ガラス板もいいました。
「しかたがないよ。わたしの光は、こんなによわい光だから。」と、お月さまは、さびしそうな顔をしていいました。
「でも、これで心だけは、あったかいつもりなんだが。」
「そうかしら、ふふう。」と、わらうような声でいったのは、むこうのすみのガラスのはちです。花のもようのあるはちですが、ふちのところが、ぎざぎざした形になっているためか、いじわるそうにみえました。
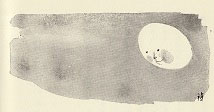
すると、そのとき、コトリ、コトリという音が、ひびいてきました。
ドアが、すうっあきました。
なんだか、黒い影のような人間が、はいってきました。からだをちぢめて、顔はきょろきょろと、あたりをしきりに見回しています。工場の人ではありません。
「あ、どろぼうだ。」と、ガラスたちは、すぐに気がつきました。
このごろ、ガラスどろぼうがおおい――と、工場の人たちが話しているのを、聞いたことがあるのです。
ガタッ!と、大きな音がしました。どろぼうが、なにかにつまずいたのです。そのために、ガタガタと、床の板がゆれました。
「ガチャ、ガチャ、ガチャ、ああ、あぶない。」
「こわれそうだわ。カチ、カチ、チリン。」
泣き声をだしたガラスもあります。
そのときです、きゅうに、さ―っと、あたりが明るくなりました。お月さまの光が、ふしぎに強くなってきたのです。
どろぼうはびくりとして、すぐまわりを見まわしました。
「あっ・・・。」と、ひくいさけび声が、どろぼうの口からでました。
じぶんとまるでおなじような、たくさんのどろぼうが、そこらにならんでいるのです。
ガラス板にも、ガラスのはちにも、つぼの中にも、どろぼうがうつっています。千三百三十六人のどろぼうが、いるのです。どろぼうは、ふるえだしました。それは、ガラスにうつった影だとおいことがわかっても、やっぱりおそろしかったのです。その人はぬすみをするのは、今夜がはじめてだったからです。
しばらく、そうして立っていた人は、どう思ったのか、ふいにくるりとからだをまわして、ドアのほうへむきました。そして、なにもとらないで、そのまますうっと、ぬけでるように外へでていきました。
コトリ、コトリという足音も、聞こえなくなりました。

ほおっ、ほおっ―。
と、ガラスたちは、ふかいといきをつきました。
「よかったなあ、だれも、とられなくて。」
「うん、よかったなあ。だれも、こわされなくて。」
「お月さまのおかげだったな。」
すると、そのとき、お月さまがしずかな声でいいました。
「なによりもよかったのは、あの人がぬすみをやめて、わるい人にならずに、すんだことだよ。」
それを聞いたガラスノはちが、
「ああ、お月さま、さっきはごめんなさいね。ほんとうに、あなたは心のあたたかいかたでしたね。」
きら、きら、きらと、ガラス工場の、たくさんのお月さまも、ガラスたちも、みんないっしょに、うれしそうに光りました。
挿絵:市川 禎男
|
|
|
|
