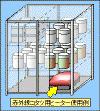|
�A�s |
|
�A �� ������@�y����@Sub Species�z �����̕��ޒP�ʂ́A�ォ���E�iKingdom�j�C���iPhylum�j�C�|�iClass�j�C���iOrder�j�C���iFamily�j�C���iTribe�j�C���iGenus�j�C���iSpecies�j�@�ƂȂ��Ă���A����X�ɍו�������ۂɈ���Ƃ������ޒP�ʂ�K�p����i���ꂼ��̕��ޒP�ʂɂ��A�Ⴆ�Έ��ȁA�����Ƃ������K��������j�B����ɂ��� �̓I�m�Ȓ�`��m��Ȃ����A�ʏ�͓�����̕ψقŒn���I�A���ԓI�Ɋu�����ꂽ�W�c���w���ꍇ�������̂ŁA����Ԃ��Γ���̒n��ɂQ�ȏ�̈��킪���݂��邱�Ƃ͂Ȃ��B��{�I�ɓ��� �ԂȂ̂Ō�z�͉\�B �@ �� ����ނ��@�y�F���E�ʒ��z ����F�̃N���K�^�ɑ��A�̑S�̂܂��͈ꕔ�ɐF�̓�������ނ��w���Ă����ĂԁB�L���ǂ���ł͒ʏ̃p�v�L�����\�Ƃ���L���C���N���K�^��j�W�C���N���K�^�A�I�E�S���I�j�N���K�^���A���O���������Ń��N���N����悤�Ȏ�ނ�����A���ɂ��z�\�A�J�N���K�^��m�R�M���N���K�^�A�c���N���K�^�̒��ԁA�L�`�ł̓J�i�u����n�i���O���̒��Ԃ��܂܂��B������̒��ɂ������̐F�ʕψق�����A�l�C�̂���J���[��͗l���Œ肵���肵�Ċy���ނ̂��ʔ����B �J�u�g���V�̒��Ԃɂ��V���J�u�g���n�߃w���N���X��S�z���d�m�ȂǑN�₩�ȐF�ʂ������̂����邪�A�ނ�̓C�����V�ƌĂ�Ă�̂��낤���H�i���͕��������Ƃ��Ȃ��c�悤�ȋC������j�B�܂��A����F�̒ʏ́F�����̒��ɂ��^�����h�D�X�ȂǕ�������炸�Ȕ���킪����A�F���Ƃ͂܂�������������������Ă���B �@ �� ����炢��Ԃ�[�ǁ@�y�C�����C���u���[�h�z �����̕��͂P�y�A�̐e������X�^�[�g�����Ǝv�����A���̎q���������ƂȂ�A���̒�����Ăуy�A������Ă������Ƃ��C�����C���u���[�h�ƌĂсA���{��ł͋ߐe��z�Ƃ����B �V���Ȑe���ɓ����������R�ƃC�����C���u���[�h�𑱂��Ă����ꍇ�����邪�A�����I�Ȍ`����T�C�Y����`�����邱�Ƃ��Ӑ}���ăC�����C���u���[�h���s���u���[�_�[�������B���������I�Ȍ̂�������x�̊m���ŏo��悤�ɂȂ�ƁA������n���ƌĂ肷��B ��ʓI�ɃC�����C���u���[�h�̐i�s�ɔ�����Q�i��`�A�⏬���A���B�s�\�Ȃǁj���w�E����Ă��邪�A�����ɉ�����ՊE�_�͂ǂ̂��炢�Ȃ̂��낤���H �i����܂���j �@ �ˁ@�n���A�u���[�h�A�y�A�����O�A�ݑ㎔�� �@ �� �����@�y�H���z �����̕ϑԃT�C�N���̍ŏI�X�e�[�W�ŁA�b���ł�匂��琬���ɒE�炷�邱�Ƃ��w���B�H����������̐����͂܂��̑S�̂��_�炩���A�F�������{���̐F�����ꍇ�������B��^�̍b���ɂȂ�قljH����̐��n���Ԃ������K�v�ŁA��^�̃J�u�g���V�ł͂Q�`�R�������̊� 匎��ɗ��܂邱�Ƃ�����i匎��ʼnz�~�����������j�B �@ �� �����ӂ���@�y�H���s�S�z �H���̒i�K�ʼn��炩�̏�Q������A����ɉH���ł��Ȃ�������Ԃ��w���B�d�x�̉H���s�S�ł͎��Ɏ���P�[�X�����邪�A�y�x�̂��̂ł������ɏ�Q���c��A���̌�̗ݑ㎔���ړI�Ƃ�����z���s���Ȃ��ꍇ������B �H���s�S�̌����ɂ͐�V�I�E��V�I�̓�ʂ肪���邪�A���R�����Ɣ�׃P�^�Ⴂ�ɍ������������A�{�����������ׂ��H���s�S�̈��q���������̂����I�悵�Ă����ʂ�����ƍl����B�܂�����Z�p�̐i�����������u�傫���Ȃ�߂����v���߂ɋN����ߌ��I�ȉH���s�S�����Ȃ��炸���݂���Ǝv����B����ȊO�ɂ�匎��̊����K���Ȃ��ꍇ��A�l�דI�ȃ~�X���ɂ��H���s�S�������B �c�����̒E��i���߁j�s�S�A匉��s�S������ɏ�����B �@ �� �����悤���ۂԂ�����@�y���|�p�X�|���W�u���b�N�z �{ ���͐��Ԃ�}���ؓ��̕ێ��Ɏg�����|�p�X�|���W�u���b�N�S�ʂ��w���̂����A�ŋ߂ł́u�I�A�V�X�v�Ƃ������i���̕����ʂ肪�ǂ��i�H�j�B��������p�r�̏��i�͑����[�J�[������o�Ă��邵�A�ŋ߂ł͂P�O�O�~�r�g�n�o�ɂ��u���Ă���̂Ō������Ƃ̂�����͑������낤�B���̂Ƃ���l�H匎��̑f�ނƂ��Ă͉��H�̗e�Ղ���ێ����̖ʂōł��D��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �ˁ@�l�H匎� �@ �� ���������@�y�I�A�V�X�z �ˁ@���|�p�X�|���W�u���b�N�A�l�H匎� �@ �� �����A���������@�y�I�K�A�I�K�N�Y�z �ˁ@�}�b�g �@ �� ������@�y������z �y�b�g�ƊE�i�H�j�ōL���g���Ă��錾�t�ŁA�X�g���[�g�Ɍ����u���ʁv���ƁB�j���A���X�I�ɂ͓V�����܂��Ƃ������Ɏ���ł��܂����Ƃ��w���̂��ȁH �u�c���N���͏��߂ŗ����₷���v �Ƃ� �u�H���s�S�ŗ�����������v �Ƃ������Ɏg���B���������_�炩���\���ł� �u���i���j�ɂȂ�v ����܂莀��ł��܂��ċ�̐��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����̂����邪�A�b�����t�ł͂Ȃ��Ȃ��g���Ȃ��B �@ �� ���@�y�����z �O���Y�N���K�^�E�J�u�g���V�S���̍����A�~��̐����E�c���Ǘ��ɉ����͕K�{�A�C�e���ƂȂ��Ă����B�����ɂ������Ȃ��Ă��A��������̂��̂����x�Ǘ�����Ă���Ζ��͂Ȃ����A�����̕��ɂƂ��Đ�p�̃u���[�f�B���O���[���i�ʏ́F�N�������j���m�ۂ��邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��A��͂肱���͉������ł��K���Ă���ƌ����邾�낤�B �����p�����Ƃ��Ă͎�Ɋϗt�A���p�Ƃ��Ċ���̃��[�J�[���̔����Ă���A�q�[�^�[�ƃT�[���X�^�b�g���t�����āA�T�C�Y�≿�i�т��荠�Ȃ��̂������Ă���B �@ |