|
|
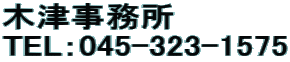
| ҸAӢЖӢK‘ҘӮНҗEҸкӮМ–@—Ҙ |
1.gif)
“–ҺРӮНҒAҺРҲхӮW–јҒAғAғӢғoғCғgӮQ–јӮМүпҺРӮЕӮ·ӮӘҒAҺРҲхӮӘӮPӮO–јҲИҸгӮМүпҺРӮНҸAӢЖӢK‘ҘӮМҚмҗ¬ӮӘӢ`–ұ•tӮҜӮзӮкӮДӮўӮйӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮӘҒA“–ҺРӮМҸкҚҮӮЕӮаҠY“–ӮөӮЬӮ·Ӯ©ҒH
.gif)
ҸнҺһӮPӮOҗlҲИҸгӮМҸ]ӢЖҲхӮрҢЩӮБӮДӮўӮйҺ–ӢЖҸҠӮЕӮНҸAӢЖӢK‘ҘӮрҚмӮиҒAҗEҸкӮМҢ©ӮвӮ·ӮўҸкҸҠӮЦӮМҢfҺҰҒE”хӮҰ•tӮҜҒAҸ]ӢЖҲхӮЙҢр•tӮ·ӮйӮИӮЗӮөӮДҒAҺь’mӮіӮ№ӮИӮӯӮДӮНӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBҗіҺРҲхҒAғAғӢғoғCғgҒAғpҒ[ғgӮИӮЗӮМӢж•ӘӮНҠЦҢWӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBғAғӢғoғCғgӮОӮ©ӮиӮPӮOҗlӮЕӮаҸAӢЖӢK‘ҘӮМҚмҗ¬Ӣ`–ұӮНҗ¶Ӯ¶ӮЬӮ·ҒBҸнҺһӮWҗlӮЕҒA–ZӮөӮўӮЖӮ«ӮҫӮҜҲкҺһ“IӮЙӮQҗlҢЩӮӨӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮ ӮкӮОҒAҚмҗ¬Ӣ`–ұӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒAҚмҗ¬ӮөӮДӮЁӮӯӮЩӮӨӮӘӮжӮўӮЕӮөӮеӮӨҒB
ҸAӢЖӢK‘ҘӮМ“а—eӮН‘еӮ«Ӯӯ•ӘӮҜӮДҺҹӮМӮжӮӨӮИӮQӮВӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB
ҒuӮўӮ©ӮИӮйҸкҚҮӮЕӮ ӮБӮДӮаҒv•KӮёӢLҚЪӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒAҗв‘О“I•K—vӢLҚЪҺ–ҚҖӮЖҒAҒu’иӮЯӮрӮ·ӮйҸкҚҮӮЙӮЁӮўӮДӮНҒvӢLҚЪӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒA‘Ҡ‘О“I•K—vӢLҚЪҺ–ҚҖӮЕӮ·ҒB
ӮИӮЁҒAҸAӢЖӢK‘ҘӮН–@—ҘӮЕҒA“НҸoӮӘӢ`–ұ•tӮҜӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Қмҗ¬ӮөӮҪҸAӢЖӢK‘ҘӮНҒAҸҠҠҚӮМҳJ“ӯҠоҸҖҠД“ВҸҗӮЙ“НӮҜҸoӮйӮұӮЖӮӘӢ`–ұ•tӮҜӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒiҳJ“ӯҠоҸҖ–@‘ж89ҸрҒjҒBӮұӮМҸкҚҮҒAҳJ“ӯҺТӮМүЯ”јҗ”ӮЕ‘gҗDӮ·ӮйҳJ“ӯ‘gҚҮҒAӮ ӮйӮўӮНҸ]ӢЖҲхӮМүЯ”јҗ”Ӯр‘г•\Ӯ·ӮйҺТӮМҲУҢ©Ҹ‘Ӯр“Y•tӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒiҳJ“ӯҠоҸҖ–@‘ж90ҸрҒjҒB
ӮИӮЁҒA–{—ҲӮНҸAӢЖӢK‘ҘӮНҠeҺ–ӢЖҸҠ’PҲКӮЕҚмҗ¬Ӯ·ӮЧӮ«ҺТӮЕӮ·ҒB—бӮҰӮОҒAҚHҸкӮӘӮQӮВӮ ӮиҒAӮPӮВӮНӮPӮOҗlҒAӮаӮӨӮPӮВӮНӮWҗlӮМҸ]ӢЖҲхӮЕүТ“ӯӮөӮДӮўӮйӮЖӮ·ӮкӮОҒAӮPӮOҗlӮМҚHҸкӮҫӮҜҚмҗ¬Ӣ`–ұӮӘӮ ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒA“ҜӮ¶үпҺРӮЙӢОӮЯӮДӮўӮйӮМӮЙҲк•ыӮҫӮҜҸAӢЖӢK‘ҘӮӘӮ ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйӮЖҒAӮЁҢЭӮўӮМӢОҳJҲУ—~ӮЙӮаүeӢҝӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBӮ»ӮМҸкҚҮӮНҒA“сӮВӮЖӮа“ҜӮ¶“а—eӮМҸAӢЖӢK‘ҘӮр”хӮҰӮйӮМӮӘҢ»ҺА“IӮЕӮ·ҒBӮЬӮҪҒA•Ўҗ”ӮМҺ–ӢЖҸҠӮр—LӮ·ӮйҠйӢЖӮӘ“ҜҲк“а—eӮМҸAӢЖӢK‘ҘӮр“K—pӮ·ӮйҸкҚҮӮНҒA–{ҺРӮӘҲкҠҮӮөӮД“НӮҜҸoӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB
ҒЎҗв‘О“I•K—vӢLҚЪҺ–ҚҖ
Ү@ҺnӢЖҒEҸIӢЖҺһҚҸ---ҸҠ’иҳJ“ӯҺһҠФӮМҠJҺnҺһҚҸӮЖҸI—№ҺһҚҸҒB<BR>
Ғ@Ң»ҸкҗEҒEҺ––ұҗEӮИӮЗҒAӢЖҺнӮЙӮжӮБӮДҲбӮӨҸкҚҮҒA“ъӢОҒEҢр‘ЦӢО–ұӮИӮЗӢО–ұҢ`‘ФӮвҗEҺнӮЙӮжӮБӮДҲбӮӨҸкҚҮӮНӮ»ӮкӮјӮкӮЙӮВӮўӮДҸ‘ӮӯҒB
ҮAӢxҢeҺһҠФ---’·ӮіҒAҲкҗДӮЙ—^ӮҰӮйӮ©Ңр‘ЦӮЙ—^ӮҰӮйӮ©ӮИӮЗӮрӢL“ь
ҮBӢx“ъ---“ъҗ”ҒA—^ӮҰ•ыҒiӮPҸTӮP“ъӮЖӮ©—j“ъӮЖӮ©ҒjӢx“ъӮМҗU‘Цҗ§Ӯв‘гӢxҗ§“xӮӘӮ ӮкӮОӮ»ӮкӮаӢL“ь
ҮCӢxүЙ---”NҺҹӢxүЙҒAҺYӢxҒAҗ¶—қӢxүЙҒAүДҠъӢxүЙҒA”N––”NҺnӢxүЙҒAҲзҺҷҒEүоҢмӢxүЙҒAҢc’ўӢxүЙӮИӮЗӮрӢK’и
ҮDҸAӢЖҺһ“]Ҡ·ӮЙҠЦӮ·ӮйҺ–ҚҖ---Ҹ]ӢЖҲхӮрӮQ‘gҲИҸгӮЙ•ӘӮҜӮДҸIӢЖӮіӮ№ӮйҸкҚҮӮМҢр‘ЦҠъ“ъҒAҢр‘ЦҸҮҸҳӮИӮЗӮЙҠЦӮ·ӮйӢK’и
ҮE’АӢаӮМҢҲ’иҒEҢvҺZ•ы–@---”N—оҒAӢО‘ұ”Nҗ”ӮИӮЗ’АӢаҢҲ’и—v‘fӮв’АӢа‘МҢnҒAҢvҺZӮМ•ы–@
ҮF’АӢаӮМҺx•Ҙ•ы–@---Ң»Ӣа•ҘӮўҒAӢвҚsҗUҚһӮИӮЗ
ҮG’АӢаӮМ’чҗШҒEҺx•ҘӮМҺһҠъ---“ъӢӢӮ©ҢҺӢӢӮ©ҒBүҪ“ъӮЙ’чҗШӮиҒAүҪ“ъӮЙҺx•ҘӮнӮкӮйӮ©ӮИӮЗ
ҮHҸёӢӢӮЙҠЦӮ·ӮйҺ–ҚҖ---ҸёӢӢҺһҠъҒAҸёӢӢ—ҰӮИӮЗ
ҮI‘ЮҗEӮЙҠЦӮ·ӮйӢK’и---”CҲУ‘ЮҗEҒAүрҢЩҒA’и”NҒAҢ_–сҠъҠФ–һ—№ӮЙӮжӮй‘ЮҗEӮИӮЗ
ҒЎ‘Ҡ‘О“I•K—vӢLҚЪҺ–ҚҖ
Ү@‘ЮҗEҺи“–---ҺxӢӢҸрҢҸҒAҢvҺZ•ы–@ҒAҺx•ҘҺһҠъӮИӮЗ
ҮAҸЬ—^---ҺxӢӢҸрҢҸҒAҺx•ҘҺһҠъӮИӮЗ
ҮBҸ]ӢЖҲхӮМҗH”пҒEҚмӢЖ—p•iӮИӮЗ---Ғ@ӮұӮкӮзӮМӮЩӮ©ӮЙҒAҺР‘о”пҒAӢӨҚП‘gҚҮ”пӮИӮЗҸ]ӢЖҲхӮӘ•ү’SӮ·ӮйҸкҚҮӮМӢK’и
ҮCҲА‘SҒEүqҗ¶ӮЙҠЦӮ·ӮйӮұӮЖ
ҮDҚРҠQ•вҸһӮЙҠЦӮ·ӮйӮұӮЖ
ҮE•\ҸІҒEҗ§ҚЩӮЙҠЦӮ·ӮйӮұӮЖ
ҮF—·”пӢK’иӮЙҠЦӮ·ӮйӮұӮЖ
|
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@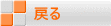 Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@
|
|
|

