THE SEVENTH EMIGRANT |
|||
| ������l����@����ōl���� |
| Toppage | Critic | �}���� | �����N | Emigrant | ����blog | |
THE SEVENTH EMIGRANT |
|||
| ������l����@����ōl���� |
�w����ܐV��x�@�u�А��v1951�N�Q���Q�� �u����͍��A�̐M������ׂ��v �@�Γ��u�a�����Ɍ����̖��ɂȂ��ė���ɂ�āA���ꏈ����肪���{�ɂ����Ă��M�S�ɋc�_�����悤�ɂȂ����B���{���}�����ꂼ��̗���ƌ���������{�A����������͕č��d�������Ă��邪�A�����̓��{�I�����͂������Ă��̂܂܂����̌����ɂȂ�Ȃ����Ƃ͓��R�ł���B �@���{�I�����͗����̗��j�I���͍�������I�ȂƂ��납������N���Ă��邪�A����ꌻ�n�ɂ��问���l�����ĉ���l�̂��̖��ɑ��錩���͗y���Ɍ`�����I�ȓ��퐶���̌��n���痧�_���˂Ȃ�ʁB�����ɓ��R�̍��ق������ė���͂��ł���B �@�����̓A�����J�ɃR�r��K�v���Ȃ���A���l�ɓ��{�Ɋ����𑗂�K�v���Ȃ��B�����܂Ō����ɗ������͉���ɏZ�ޑS�l���̐����̍Č����r���̖ڕW�ɂ����˂Ȃ�ʂƂ���ɂ����̐l�ԂƂ��Ă̐��X�������т�����̂ł���B �@����ɂ���Đ������[���ɂ��ꂽ����̐l���������̐��������ʂ���Ԃ����Ƃ͂S�A�T�A�U�N�ŊȒP�ɏo������̂ł͂Ȃ��B1952�N���ɂ͉���o�ς������o����悤�ɂ��낢��ƍl���������Ă��邪�A���̖ڕW���B�������邩�ۂ��ɂ��ẮA����Q�����{��]���ɂ����Ă��ے�I�ł���B �@����̔j��͓��{�����̐ӔC�ł��邩��A���̕����͓��{�ɋA�����ē��{�����̂����C�ɂ����Ĉׂ����߂�悢�A�ƌ����Ă݂����āA�������͐U��ʁB���ǂ͖L���ȃA�����J�̉����ɂ���ĂȂ���Ă��邪�A������Ō�܂ŃA�����J�ɂ����C������킯�̂��̂ł��Ȃ��B �@���킪�N�̂����C�ł���������A���̕��ɔj�ꂽ����Č��̐ӔC�킹��Ǝ咣���Ă݂����āA���X�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����Ƃł���B �@�����ŕM�҂������Œ��������Ƃ́A�j�ꂽ����̍Č��͑���ɎQ�����������̐ӔC�ɂ����Đ��s���ĖႤ���Ƃɂ��A��������A�M���Ƃ��A���A�ɉ��ꕜ���̂����C���Ƃ炵�߂邱�Ƃ���������悤�w�͂��ׂ��Ƃ������Ƃł���B�����č��A�M���ƂȂ������̌�ɂ����č��A�ɂ����ăA�����J�̒P�Ɠ����Ƃ��邩�ۂ��́A���A�ɂ����錈��ɂ܂O�͂Ȃ��B �@���������ɂ����ĉ��ꈽ�͗������Ɨ�������ΓƗ��ł��悵�A���͓��{�A�����邩�A�����J�ɋA�����邩�́A���̎��ɂ������ɂ���đS�l���̈ӎu�ɂ���Č��肷��悢�B �@����Z�������݂݂̂��߂Ȑ�������@���ɂ����1�������������o�����邩�A���̕��@�����肵�悤�Ƃ����d����ɗ����Ă����́A�߂������ɑ��鍑�ۏ�̌��ʂ��ƁA�ډ��̉���̏�Ԃɂ��Ă̔F������A�����܂Ō����I�Ȍ��_�Ȃ���Ȃ�ʁB�����Ă��̂��߂ɂ͋��S�����Ɉӌ����������킷�ׂ��ł���B �w����^�C���X�x�@�u�А��v1951�N�Q���R�� �u�����̋A���v �@�_���X���g�̓��{�K�₪���{�Ƃ̍u�a���������}���Ɏ������邽�߂̏����ł��邱�ƂƁA�폟������A�����J���s�퍑������{�ɑ����Ă̖������������������悤�ȑԓx������đΓ��̗���ɉ��ē��{���̊�]�Ɏ����X����Ƃ����ԓx���Ƃ��ċ��邱�Ƃ͓��{�����ɍD��ۂ��o���ċ���悤�ł���B �@�ܘ_�A�����J�����������ԓx���Ƃ��ċ��邩��Ƃ����ē��{�̌�������S�������͂��͂Ȃ��B�A�����J�̍���̐��ɂ���������̖��A�����J�Ƃ��Ĉׂ�����͈͂̂��̂����e�ɂȂ��ł��낤�B �@���{�̒���͋����ču�a��̌o�ω����ƍ��A�ɂ����S�ۏ�̊m�ɂ�Ɨ����A���}���A�瓇�̕Ԋғ���v�]���A�g�c����_���X���g�Ɋ�]���q�ׂ��Ɠ`�����ċ���B���̒��ŗ����Z���ɂƂ��čő�̊S���ƂȂ��Ă���̂͂킪���������̋A�����ł���B �@������̐����I�^�������肳���̂ɖ��S�ŋ������͈̂�l�Ƃ��ċ��Ȃ��͂��ł���B���܂Œ��ق��Č��Ȃ������̂��Ƃł����Ĉӎu�\�������߂�ꂽ��K���₱�����肽���Ɗ�]����Ǝ��̍l�����������ɈႢ�Ȃ��B������Γ��{�ɋA��̂���]���邩���̓A�����J�̐M����������]���邩�A�ɐ����I�ɕ\�����邱�Ƃ��o���邩�Ƃ����i�ɂȂ�Ɩ��������Ė����̖��Ƃ��Ď��グ�Ę_�c���ꂽ���Ƃ��Ȃ��̂Ŗ��m�Ɏ������Ƃ͍��̂Ƃ���s�\�ł���A�K�v�Ƃ���Ȃ�l�����[���s�Ȃ��O�͂Ȃ��ł��낤�B �@���{�A������]������̂͋��D�Ƃ������悤�Ȋ�������o�������̂��̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B�����l�����{�l�Ƃ͐l�팾�ꕗ�����K���قɂ���ٖ����ł���Ǝv���ċ�����̂͗����l�̒��ɂ͋��炭��l�����Ȃ��Ǝv���B �@�����ٖ����ł���ƍl���ċ���Ȃ�Γ������ق݂ł���A�����J�̓������ɓ��낤�����{�������ɑ����悤���A�ق݂̎x�z�������邱�Ƃɂ͉���ς�͂Ȃ��̂ł��邩��A���ɓ��{�ɋA��A�����J�ȏ�̌o�ω��������錩�ʂ����Ȃ�������{�A���̊�]�͐�O���{�̗̓y�ł���A���{���݂�̈ꕔ�ł������Ƃ�����������o�����̂ɉ߂��Ȃ��Ƃ�������������Ă͋��Ȃ��ł��낤���A�����l�����{�l�Ɠ���݂ł���Ƃ����������̂Ȃ���ƁA�����I����S�����������Ƃ��������̐����ӎ��͑O�r�ɔ@���Ȃ���ς��ċ��Ă����R�Ƃ��ď��z���čs�����Ƃ��鐸�_��N�N�����߂�B���ꂪ���{�ɋA�肽����]�ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B �@�A�����J�̌o�ω����͗����̕����ɐ��Ȃ鉶�b���o���ċ��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ����A���������{�ɋA�����ꍇ�A���{�ɂ͗����̕�����������͂͂Ȃ��Ƃ����l��������A�����J�ɋA���������������̂��߂ɂ͗��v�ł���Ƃ��ĐM����������]������̂�����͂��ł���B�l�͊�e���ق�Ɠ��l�ɂ��̂̍l����������Ă���͓̂��R�ł��葴���ɏO�����c�̕K�v�������Ă���B���A���������{�ɋA�����ꍇ�ɂ͌o�ϓI�����͖]�܂�Ȃ��Ƃ��������͋͂��ƒf�̌���������͂��Ȃ����Ǝv���B�Ƃ����͓̂��{�̒��삪�����̕Ԋ҂�v�]���ċ��鎖�����琄���ď������̊�]���K���ɗe���ꂽ�ꍇ�A�����̕����͓��{���{����ѓ��{�����̐ӔC�ƂȂ��Ă��邵�A���1945�N�̉���킪���{�̂��߂̈��]���ł����������ɑ��鍑���I�ǐS�����N�����ɂ͂����Ȃ��Ǝv���B �@����Ō����̌o�ϓI�����̖�肾���ŃA�����J�̓�������]�����͓��{�A������]����Ƃ����ԓx�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�����̐����I���含�Ƃ����Ⴂ����ɂ���ė�Âɍl���Ȃ���Ό�X����͖ܘ_�q���̂��߂ɂ������Ƃ͌����Ȃ��B �@��X�͌o�ϓI������v������ċ���B����͂����܂ł��Ȃ������̗͂Ŏ�����{���čs�����Ƃł���B�l�ԂƂ��Ė����Ƃ��ē��R�̂��Ƃł���A�����܂ł��O���̉����������Ƃ���l����ƒm�炸���炸�̂����Ɍ�H�݂ɑ��Ă��܂��B��X�͌o�ϓI������O�肷�邪����͕K�R�I�ɐ����I�Ɨ��ւ̊�]�Ƃ��Ȃ��Ă���B �@�����A���͂ǂ��Ȃ邩�͈�ɃA�����J�̈ӎu�ɂ���Č��肳���B���{�̐��}���ʂł͗����̎匠�y�ї̓y���͓��{�ɋA���ĖႢ�A�����J�̕K�v�Ƃ���R����n�͑d�̌`�����Ƃ�Ƃ�����]���o�ċ���悤�ł��邪�A�A�����J�̃A�W�A�ɉ����鍑�h�������A�����[�V�����A���{�A�����A��p�A�䗥�o�̐��ɂ�����ċ���Ƃ����⌵�Ȃ鎖���ƍ��ۏ�Ƃ���X�͐��ς��A�@���ɉ^���Â����邩������̔��f�łɂ��Ă���ɑΏ�����S�\���𐮂��Ă����Ȃ���Ȃ�ʁB��]�ƌ����Ƃ͓���ł͂Ȃ��B �����V��1969�N10���P�����L���� ����͉���l�̂��̂��I�����͓��{���A���}���Ȃ� �@����̓��{�Ԋ҂����߂���Č��͖ڑO�ɔ����Ă���B����ǂ�����Ƌ��ɁA�ߍ��������āu���A�s���v�Ƃ������t�����ɂ���悤�ɂȂ����̂́A�ǂ������낤���B �@���A�s���Ƃ������Ƃ́A���{���A�ɍۂ��Čo�ς̕ϓ����炭�鐶���̕s���ƁA�Z���̈�l��l���A�o�ύ����̔g�Ɋ������܂�鋰�|�������Ă���̂ł��邪�A���{���A������A�Ƃ��������ꉫ��l������\���N���������āA�Dࢂ̂Ȃ�����c�X�ƒz�������Ă��������ƌo�ς̋@�\���A���̏�łЂ����肩�����ł��邩��A�Z���̂��ׂĂ��A���̂�������ł��낤���Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����āA���̌o�ϕϓ��͂₪�č������A�Z���̒�����j�Y�A�|�Y�҂����o���A���Ǝ҂͂��܂��ɂ��ӂ�A���݂̐������ꂵ���Ȃ邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B �@�Ƃ��낪�A���݂̉���̐����Ƃ͓��{���A�����Ԃɋ}���ŁA����ɔ��Ȃ��o�ύ������ǂ���ʂ��邩�Ƃ�����̈Ă����������͈̂�l�����Ȃ��B�܂�Łu���{���A������A����l�͂��̓�����K���ɂȂ��̂��v�ƌ�������ł���B����̋A�������肷��Ƃ������ĉ�k�ł���A��n���ɏI�n���āA����ȉ���̌o�ς�A����l�̐����s���̉����ɂ��ẮA�ȂɈ�b�������Ă��Ȃ��̂ł���B�|���ꂩ��l����ƁA����l�̐����́A����l���g�̎�Ŏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�͂�����킩��B �@����͉���l�̂��̂ł���Ȃ���A�����͉��́A���̏�ɂȂ��āA�O������̓s���̂��߂ɁA���݂������s���̂��т��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��낤���B�|�����͊Ԉ���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B �@�����A�������Ƃ���A�����͂����œ��{���A�ɂ���Ĉ�l�̋]���҂��o���Ȃ����߂ɁA���܈�x�Ƃ�����l���Ă݂�K�v������͂��Ȃ����B�|��������ɕ��A���}���ŁA�����̔j�]�ƁA�����̋]���҂��o�����A������肼���ēK���Ȏ�����҂ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�|��������{���A�́A���ׂẲ���l�����{�{�y�Ɠ����A���邢�͖{�y�ȏ�ɁA�ЂƂ�ЂƂ肪�����̗����Ă���o�ϊ�Ղ��A��������ƌł߂��̂��l�������ׂ��ł���A���̎�����10�N��A���邢��20�N��ɂȂ��Ă��\��Ȃ��̂ł���B �@�l�ԂɂƂ��āA�����͂��ׂĂ̗~���ɗD�悷��B���������Ă̐l�Ԃł���B�����A���̐������A���{���A�̂��߂Ɏ������̂��ЂƂ�ł�����Ƃ�����A�����͓�������l�Ƃ��āA�����r�����܂ʂ��ĖT�ς��Ă悢���̂��낤���B�\�\���ׂ̈ɂ������́A���ݓ��m�A�����̂Ȃ����{���A������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@���ƂɌ��݂̉���̌o�ς́A�����炭�L�j�ȗ��ł͂Ȃ����Ǝv���邭�炢�Ȕɉh�̓r��ɂ���B���̔ɉh�́A����ꉫ��l������̎�ɂ���Ēz�������̂ł���B�����炭����10�N�A���邢��20�N������A����͓���A�W�A�̈�p�ɁA����ȕ����ƌo�ς����y�y�����݂��邾�낤�B�����͍��A���̌����Ɍ������Ă܂��i������A����̌��݂̐����o�ς̐��x�́A���Ȃ킿�A���̔��W�̉\����ۏႷ����̂ł���B �@���������āA����ɌJ�肩�������A���{���A���}���ł͂Ȃ�Ȃ��B�\�\1972�N�͕��A�̔N���Ƃ���Ă���B�������A������1972�N�����A�u���{���A���}���Ȃ��v�Ƃ��������̗v�]�ɐ��E�������A���ѓO����ׂ́u�Z�����[�v�̔N�ɂ��ׂ��ł���B �@����l�̐����ƁA����̔ɉh�A�����Ă��݂̍K���́A����ꎩ�g�̎�ɂ���Ď��A�z���A���ނق��͂Ȃ��B�����͂��̂��߂ɁA����l���m�Ƃ��Ɏ���Ƃ��Č��N���A�K�ȕ��@�ɂ��A���ė����{���͂��ߊW�҂ɑ��āA��̓I�s�������������ł͂Ȃ����B �@�E�̈ӌ��ɓ����̕��́A���N�l���A�܂��͍��L�������܂ł��A���������B 1969�N10���P�� ����l�̉���������i�ӔC�ҁ@��ԕq���j ����l�̉���������i���́j �i���N�l�j���ԏd���@�R���i�g�@�{��m�l�Y�@�����Ǖv�@����t�i�@�{���t�s�@�Ɖ����q�@����v�Ћg�@�{��\���@�g�l�ƒ��@�v�꒷���@���c�ĎO�@���@��Y�@�ӉԌ����@�V�ԗD��@���܉i���@��������@�m�Ԑe���@���R���P�@���ǗY��@�����T���@�{��k�g�@�Ɖ��q�q�@�r�_����@�q�@�����@�Ώ�_��@���@���@���{���q�@��Ԑ����@�����b�ǁ@�ʏ�v��@�����@�ׁ@�r���Βj�@�V�_�����@���{�����@�ɍ]���z�@�{����G�@��Ð��`�@�V�����@�e���h�ʁ@����B�m�@�Ό����p�@�m�O���P�@��ߔe���p�@�R�{�@���@�V�Ԑ^�h�@�Ċ�^�H�@�㌴�T���@��ԕq�� |
||
|
�y���ꂩ��̒�2011�z �E�u����ˑ��v�̈��S�ۏ�� ���ۊ��̌��ςƂR�E11���� �V�萷��^�䕔�����^���䍑�r�^�����@�w�^����p��^�����@���^�{�������i���炳���E����Ă�1936�N���܂�A�����w���_��������㉫��j�^���ׁE�܂�����1955�N���܂�A������w���ۉ��ꌤ������������ې����^�����炢�E���ɂƂ�1943�N���܂�A�����w��������w�^���Ƃ��E�܂Ȃ�1958���܂�A���ꍑ�ۑ�w�����E�č������^�ق��́E��������1953�N���܂�A������w��������ې����o�ρ^�܂��ƁE�悵1965�N���܂�A�����V��ҏW�ǐ����������^�݂₴�ƁE��������1931�N���܂�A����ΊO��茤�����\����ې����j �@���{�Љ�́A���������S�ň������Ƃ̐_�b�Ɋ�Â��v�l��~����A���ܕK���ŒE�p���悤�Ƃ��Ă���B�R�E11�́A������ʂŎv�l��~����̊o�������߂Ă���B���{�̈��S�ۏ�́A���k�ւ̌����̉������Ɠ��l�ɁA����ɉߑ�ȋ]���������Ă����B�č��Ɉˑ����Ă���Έ��S���Ƃ����v�l��~���炢�܂����o�����A���a�ň��肷��A�W�A�����m�̒����\�z��Nj����ׂ����B �͂��߂Ɂ|������ɗ����{�� �@�����{��k�Ђ���U�������}����Ȃ��A���̎����ւ̋ؓ��������Ȃ��B�ꕔ�ŕ����̒����͂�����̂́A�R�E11�ȑO�֖߂邱�Ƃ͂Ȃ��B�����̐l���ƂƂ��ɁA�l�X�̕�炵�����ł������⑺����u�ɂ��Ď���ꂽ�B�����āA�����c�����l�����̓y�n�ւ̋L��������D���悤�Ƃ��Ă���B �@66�N�O�A�����́A�̉A�e�ɕx��ł�������̕��i������h�����������˂��隺�ƓD�̍r�i�ւƕϖe�������B���ė��R�̏Փ˂̍��ԂŁA20���l�ȏ�̎��҂��o���A���ꌧ���̂S�l�ɂP�l���S���Ȃ����B66�N�Ƃ��������N�����߂����ɂ��S��炸�A����̐l�X�͉����̔ߌ��������������Ă͂��Ȃ��B�����̉ߒ��Ō��݂��ꂽ�ČR��n�����Ȃ����݂��A����̉����푈�֔�����Ă��邩�炾�B �@�ߋ��̏o�����ɂ���Ď���ꂽ���̂��߂�Ȃ��Ƃ���A�����E�����ł͂Ȃ��A�l�X�̌q�������b�ɂ����V���Ȓn��Â���A�����č��Â�����߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Đ��Ƃ��������V���ȓ��{�Â���ł���B���̕����������o���A�s���ւƓ��������A���ʂ��o���ɂ́A�������I���ʂ����K�v���B�ߋ��֖߂�̂ł͂Ȃ��A�V���ȓ��{�Љ��z�������ւ̌��f���A���A���߂��Ă���B�R�E11�́A���k�����łȂ����{�S�̂̓]���𑣂��Ă���̂��B �@�R�E11�́A�n�k�ƒÔg�Ƃ������R�̗͂ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�B����������̕ČR��n�̏W���́A�l�ׂ̌��ʂł���B�����āA����̐l�X���]���ʂƂ��ĕČR��n���������Ă���̂ł͂Ȃ��B��q����悤�ɁA�������݂ւ̐l�X�̑Ή��Ƃ��̌����́A����ɂ������n���ւ̐l�X�̑Ή��Ƃ��̌����Ƃ͈قȂ�Ƃ��낪����B �@�������A����̎��̂��@�ɒ��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ����������͂��߂Ƃ��錴�����n�n��̋]���ւ̑Ή��ƁA����̕ČR��n��O��Ƃ������{�̈��S�ۏᐭ��̋]���ւ̑Ή��ɂ́A���ʓ_������B�����c�����҂����܂łɉ����ׂ��A���ꂩ�牽���ׂ����Ƃ��Ă���̂��A�܂�A�R�E11�Ȍ�̐V���ȓ��{�Љ�̍\�z����������Ă���̂ł���B �@�ȉ��ł́A���A�W�A�����m�����̂Ȃ��Ō`������A�W�J����Ă������S�ۏᐭ������ꂩ��Č������A���炽�Ȏ��_��������B �P�D��㍑�ے����ւ̐V���Ȓ��� �@�A�W�A�����m�n��̐�㒁���́A�ĉp�\�̌R���͂�O�ɔs�k�����h�C�c�E�C�^���A�Ƃ��̎��ӏ�������������łł�����������ト�[���b�p�����`���Ƃ͈قȂ铹����ނ��ƂɂȂ����B�Q�̑����Ԉ��ۑ̐��̑Λ����������[���b�p�����ɑ��A���̒n��ł͕č������Ƃ����������Ƃ̊Ԃ̃n�u�E�A���h�E�X�|�[�N�̐��i�č������A�W�A�̐e�Đ����Ƃ̊ԂŌX�ɂQ���ԓ��������сA�A�W�A�̊e�����m�̈��S�ۏႪ���@�����������A�ԗւɂȂ����Ă����Ăԁj�ƁA���͂ƑΗ�������Ԃ��Ă��������ƃ\�A�̑R���͂Ƃ̊ԂŐD��Ȃ���풁�����i�s�����B �i�P�j����̋]���Ɉˋ�������㒁�� �@���̏I���ȑO����A���̒n��͒����ϓ��Ɍ������n�߂��B�Ƃ�킯�Љ��`�o�ς̍s���l�܂���o����������������\�A�́A���{��`�̍��X�Ƃ̌o�ϓI�A�����I�ȊW���P�𐄂��i�߂Ă����B���̌��ʁA���̑R������͒E���������̂́A�����͌��݁A�V���ȑ��݊�����������B�����͎s��o�ς����A���E���ɍH�Ɛ��i����H���i����������u���E�̍H��v�ƂȂ�A13���̐l��������s��ւƐ���������B�Љ��`�\�A�́A�����15�����ւƕ������Ȃ�����A�R���I�ɂ́u�卑�v�����F���郍�V�A�����ے����̈ێ����͂̈ꗃ��S���Ă���B �@�A�W�A�����m�n��̕č��̓������́A���I���������̍��Ƒ̐����قƂ�ǕύX�����ɐ��E�o�ςƂ̌��т���[�߂Ă����A�O���[�o�����̉��b���A�����Ɍ��ς���f�ՁE�ʉ݂ɂ��Ǝ㐫�����炯�o�����B�Ƃ�킯���̊ԁA�č��Ƃ̂Q���Ԉ��S�ۏ�Ɉˑ�����A�W�A�����Ɠ������R���I�֗^�����č��Ƃ̊ԂŒ������ێ����ꑱ���Ă����B�����āA�e�������č��ւ̈ˑ���[�߂Ă������߁A�����̍��X�͎���̒n��̒����̍\�z�����ւ̎�̓I�s���̑f�n�������Ȃ��܂܂ł���B �@�������ւ̕č��̌R���I�֗^�͕ČR�v���[���X�ł���B�A�W�A�����m�ɂ�����ČR�v���[���X�͂���܂ł��A�����Ȃ��A����̊�n�ɏے�����Ă���B���̂��Ƃ��Ӗ�����̂́A����ɕČR�������������A�A�W�A�����m�n��̈��S�ۏ�ɂ��āA�n��̊e��������l����@������Ă���Ƃ������Ƃł���B�܂�A���̒n��ɂ���e���̈��S�ۏᐭ��́A����ɊÂ��邱�ƂŁA����̕��S�Ɗ댯��������邱�Ƃ��\�ƂȂ����B�č��̔e���́A�A�W�A�����m�n��ł͕ČR�v���[���X�Ɏx�����A���ꂪ����̋]���̏�ɐ��������̂��B�č��̓������́A�č��e���փt���[���C�h�i�������j���邽�߂ɁA����ݑ�Ɏg�������Ă����B �i�Q�j�����̑䓪�ƐV���Ȃ鍑�ے����\�z �@����������㍑�ے����́A���A������Ă���B����͒����̑䓪�ɂ���ċN�������̂��B�����̌R���͋����ɑ��A�e���͕č��̌R���֗^�̈��艻�Ƌ��������߂�����ɂ���B��V�i�C�ɂ����钆���̊ւ��̗L��̊C���ɂ����āA���̌X���͌����Ɍ��Ď���B�Z���I�ɂ݂āA�����ȊO�̑��̕������������D�ʂɂȂ邱�Ƃ͍���ł���A�č��֗^�ɂ���Č��ێ�����邾���ŁA�s���萫���͉��P����Ȃ��B�ނ���A�����������̊Ԃł̕��͏Փ˂̉\�������܂��Ă���B�������I�ɂ��̒n����̒��������艻�����A�ω��ɑΉ��ł��鋦�����J�j�Y�����\�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̍��X�́A����̒n��ɂ����ĕč��ɂǂ̂悤�Ɋ֗^���Ă��炢�����̂�����\�z���A�č��̊֗^�̂�������߂����Ă��܂��܂ȋ��c��i�߂�ׂ����B������������ɑ��鎄�����̓����́A�ȉ��̂R�ł���B �@��P�̓����́A�����Ԃ̈��S�ۏ�̐��̍\�z�ւ̍s���ł���B��̃A�W�A�Ƃ������j�I�o���̌��@�Ⓦ�A�W�A�������n��K�͂̊����A�č������Ƃ���n�u�E�A���h�E�X�|�[�N�̐�������܂Ō㉟�����Ă����B�����ɂ́A�o�ς�G�l���M�[�̑��݈ˑ����[�܂钆�ŁA�A�W�A�����m�n��ɂ����鋤�ʂ̗��v�͑��債�Ă���B���ʂ̗��v�������o����̂́A���v���߂�������s���鑽���Ԃł̋��c�̏�i�t�H�[�����j�ł���B���̏��ʂ��āA�e���̗��v�Ɋ�Â��咣���Ȃ���A�Ȃ�炩�̍��ӂ邽�߂̋삯�������s���钆�ŁA���ʂ̗��v�������яオ��B���̂悤�ȃt�H�[�����ł̌��ߒ��������A�����Ԉ��S�ۏ�̐��̍\�z�̍s�����̂��̂Ȃ̂ł���B�Ƃ͂����A�A�W�A�����m�n��ɂ����鑽���̍��X�́A�t�H�[���������ʓI�Ɏg�����Ȃ���قǑ����Ԍ��ɏK�n���Ă͂��Ȃ��B�����t�@�V���e�C�g�i�����A�菕���j����m���ƋZ�p���K�v�Ȃ̂ł���B �@����܂ł̂Q���Ԃōs����n�u�E�A���h�E�X�|�[�N�̏ꍇ�ł́A���������Z�p�͕s�v�Ƃ���A�č��̑Ë��������o�����߂̌������������ɒT���o���Ă����B�č��̊֗^�̂�������̂��̂��A�����Ԃ̃t�H�[�����`���̏�Q�ƂȂ��Ă����̂��B���a�̉\��������܂ňȏ�ɍ��߂����I�ȍ��ے����̌`���ɂނ��������I�ӎu���s�����B �@��Q�̓����́A�A�W�A�����m�������n��̈��S�ۏ�ɐӔC���Ƃ��������҈ӎ��������Ƃ��B���̒n��̈��S�ۏ��_����Ƃ��A�e���̈��S�ۏ�͌R���͂����ăZ���t�E�w���v�i�����j�����߂���@���A������i�߂đ卑�ɂ��֗^�������������@�̂Q�̕��@�Ř_�����Ă����B���������l���́A�匠���Ƃ��\�������̂ł���Ƃ̑O��ɗ��B�����ł́A�匠���Ƃ��ꖇ��Ƃ��đz�肳��A���ƊԂ̌o�ϗ͂�R���͂̔�r��ʂ��Ċe���̈��S�ۏႪ�_�����Ă���B�l�X�̎��ӏ����ւ̗������ω����Ă��A���ƊԂ̈��S�ۏ��̊W�͕ς��Ȃ��Ƃ��闧�ꂾ�B�����̐l�ԎЉ�Ƃ͈قȂ�l�����ł���B �@���荑�₻�̍������ǂ̂悤�ɗ�������̂��ɂ���āA�W�͕ω�����B�A�W�A�����m�̒����`���ƈێ��ɑ��A�����҂Ƃ��Ăǂ̂悤�ɕ\���ɂ��A�s������̂����d�v�ł���B�����҂Ƃ��Ă̌��t�ƍs���̑��ݍ�p�̒�����A���ʂ̗��v�ƋK�͂�n�o�ł���B�o�ς̃O���[�o�����́A�ʉ݁A�ʏ��A�ʐM�i�C���^�[�l�b�g���܂ށj�Ȃǂ̋�ԂɐZ�����Ă���B�A�W�A�����m�̈�̊��͍��܂邱�Ƃ͂����Ă��A��܂邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�����̒n����ݍ��݁A�Ƃ��ɂ͒n����z���邳�܂��܂ȃ��x���ɂ����āA�n��̈���A�n���̈���Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�ƋK�͂ݏo�����Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B �@��R�̓����́A�R���͂ɂ��o�����X���d�������ꍇ�ł��A�A�W�A�����m�n������艻������@������Ƃ������Ƃ��B����́A����u�n��v�卑�Ƃ��āA���Ƃ��Β����ƕč����ύt����Ƃ��ł���B�č����u���E�v�卑�Ƃ��čs������Ƃ��Ă��A�A�W�A�����m�ɂ�����u�n��v�卑������A�����̋ύt�������ł���B�����Ƃ��댯�Ȃ̂́A�͂̋ύt���\�z���ē����o���Ƃ����B������������ɂ́A�e���̌R���͂̓����������߂邱�Ƃ��s�����܂��A�e���̌R���͂ɂ��Ă̓K�ȕ]�����A�헪�I�v�l�̃{�g���E���C���ɂȂ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ́A�e���̈��S�ۏ���l����Ƃ��A�R���͂ɂ����������̃R�X�g�Ɍ������̂��ǂ����ɂ��č����I�Ȕ��f�����ߍ������Ƃ��d�v���B���̂��߂̌R���𗬂͏d�������ׂ����낤�B����ł��A�o�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��Ƃ��A�����������͂��߂Ȃ��Ǝv���ĕ��͍s�g�֓˂��i�ގ��Ԃ����邩������Ȃ��B�����푈�����Ȃ��Ǝv�����ދ����Ȕ��f����A�����c�邱�Ƃ��ŗD�悷�錫�������S�ۏ�̊�{�ƂȂ�ׂ����B �Q�D�č��̕ϗe �@�f�E�v�u�b�V�����������ȗ��A�č������́A�\�z���ʑ��x�ŕϗe�𑱂��Ă���B����̓��ĊW���A��茒�S�ɂ��邽�߂ɂ́A�č��ŋN���Ă��鎖�Ԃ�������Ɣc�����邱�Ƃ��K�v�ł���B �i�P�j�č��Ӗ���������グ���߂��鍬������������ �@2008�N�哝�̑I���ŁA�I�o�}�́A�č��̋~����ł��邩�̂悤�Ȋ��҂�S���ē��I�����B�������A2010�N�̋c��I���ŁA���a�}�����@�����h�̒n�ʂɕԂ�炫�A�܂���@�ł��c�Ȃ𑝂₵���B�č��L���҂́A�I�o�}�ɂQ�N�Ԃ̗P�\����^���Ȃ������B���̋��a�}�����̌����͂́u����v�^���ł������B���ŁA�����V���g���A�����ċɒ[�ȁu�����Ȑ��{�v��`�҂̘A���ł���u����v�^���́A���a�}�̍�������̍��W����ێ�ւƓ������������łȂ��A�č��S�̂̐���c�_�̊��ς����B �@����^���ɒ��ڎx�����ꂽ���a�}�c���́A�}���ň��|�I�����ł���B�������A�ނ�̌f����u�����Ȑ��{�v������`�́A���a�}�嗬�h���y�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�}�ɂƂ��Ắu�т̌���v�ł���A���̔��Ŏv�z�́A���N�W���̍���������������ӂ̘g�g�݂������K�肵���B �@����̍��ӂ́A�����I�ȍ�ł��A11���܂łɌ��_���o�����}�h���ʈψ����ɐ摗�肵���A���s���s��h�������̈ꎞ������ɉ߂��Ȃ��B���̈ψ���ŏ��ňĂ����ӂł��Ȃ��ƁA�ꗥ���ł��Ȃ���A���̏ꍇ�A�R���\�Z���Ŋz�́A����10�N�ԂŁA���h���Ȃ��z�肵�Ă���4000���h���̂Q�E�T�{�A�P���h���ɏ��B �@�]���A���a�}�͌R���\�Z���ێ�����^�J�h���嗬�ł������B�������A�u����v�́A�R���E�O�����������ύt�A�Ԏ����ł��d������B�u�b�V������̌R�g�ւ̍����I����������A���a�}�x�C�i�[���@�c���̌R���\�Z�ێ���ڎw�����Ă��A�}���̎x�����Ȃ��������A�u����v��������̋����̏ł���B �@����A����}�́A��ÁE�����\�Z������A���݈Ӌ`��q���������Ƃ���B���������č������̏����A�R���\�Z�̑啝���łȂ��ɂ́A11���̍��ӂ͕s�\�ł���B �@�����I�ȐԎ������������Ȃ���A���ɓI�ɂ́A�ăh���̋��ʒʉ݂Ƃ��Ă̒n�ʑr���Ɍq����B�����A���[�����ɓx�Ɏ�̉����A�~������h���ɑ��肤��킯���Ȃ��A�l�����͓��ꋤ�ʒʉݑ��蓾�Ȃ��́A�ăh������̉����Ă��A�Ȃ��������@�ɂ�茻�݂̒n�ʂɗ��܂邱�Ƃ��Î�����B�܂��A�č��ɂ́A1970�N�ォ�瑝�����A���[�K���������Ő[�������������Ԏ����Ɋւ��āA�N�����g�������Ō�̂Q�N�ԂɒP�N�x�Ԏ��������������т�����B�č��ɂ́A�o�ϐ����̎����ƁA����}�哝�̂��畟���\�Z���ł��s���A�����I�ȁA���邢�͖����߂Ȑ����]�����\�ł���B�č��o�ς����{�������A���̂܂ܖv���͂��Ȃ��ł��낤�B�������A���̉��ł̍�����\�Z�\�z�́A�傫���ς��B �i�Q�j�O�A���ڐ݊֘A�\�Z�폜�̈Ӗ�����Ƃ��� �@���N�V���ɁA�č���@�́A2012��v�N�x�R���\�Z�Ă���C�������V�Ԋ�n�̃O�A���ړ]�֘A�\�Z���팸�����B�{�e���M���_�ŁA�ŏI�̗\�Z���ǂ̂悤�ɂȂ邩����ł��邪�A���{�����Ԏ����ł��ő�̑��_�ƂȂ������݁A�č��c��ɁA�O�A���E�Ӗ�Èړ]�ւ̖��ĂȔ��̐����o�����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �@���Z��@���ɂ�����ɐ����ꂽ�č����{��`�̏I���A�Ƃ����悤�Ȏ��Ԃ͋N���Ȃ������B�������A�Q�[���͊m���ɕς�����B���݁A�č��c����g��ł���Ώo�팸�́A�V���ȃQ�[���ɂ����Ă��č����D�ʂ�ۂ������邽�߂ł���B�����炱���A�R���\�Z�����őΏۂƂȂ�A�D�揇�ʂ̕t���ւ����s����B�O�A���֘A�\�Z�̍팸�́A�č��R������ɂ�����A�C�����V��n���݂̗D�揇�ʂ��傫�������������Ƃ��Ӗ�����B �@���݂̍����Ԏ����́A���F�g�i���푈�ȗ��̌X���P����Ȃ�A����10�N�Ԃ͑����B�č�����̊�͓������̂ł���B���{�����̌����Ɋ���҂��āA�Ђ����猻��ێ���]��ł�����͗����~�܂��Ă��Ă͂���Ȃ��B �@�č��̌㉟���ŁA�����ƌR���I�ɑΛ�����A���̂��߂ɉ���̊�n��č��ɒ���Ƃ����l�����́A�������č��Д��s���z�̂S���̂P�A���{�̂P�E�T�{��ۗL���A�܂��ăh���ۗ̕L�z�ł��A���������{�̂R�{�ŁA���E�ő�ł��錻���܂��Ă��Ȃ��B����A�����͕č��̖f�Ց��荑�Ƃ��āA�P�ʃJ�i�_�A�R�ʃ��L�V�R�Ƃ����A�k�Ď��R�f�Ջ���������ɋ��܂ꂽ�Q�ʂł����Ȃ��̂ɑ��A�č��́A�����̗A�o��Ƃ��āA�Q�ʍ��`�̂P�E�T�{�A�R�ʓ��{�̂Q�{�Ƃ����A���|�I�Ȏs��ł��錻��������B�����̌o�ς́A�T�^�I�ȑ��݈ˑ��W�Ȃ̂ł���B �@���{���A�č��A�����Ƃ̊W���A���̌����ɑ���������ɓ]�����Ȃ���A�č��́u�{���v���\�ɏo�����ɁA�u�j�N�\���K���v�̂悤�ȁA�V�����̂Ɍ�����ꂩ�˂Ȃ��B �R�D���{�̕ω��F�������ƂR�E11 �@���{�ɂ�����Q�̑傫�ȕω��Ƃ��āA2009�N�X���̐������ƂR�E11�ȍ~�̈�A�̏o���������グ��B �i�P�j����������ς��ʉۑ� �@�܂��A���݂̓��{�͐������ȑO�Ɠ��l�̉ۑ���������Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�o�u���o�ϕ���ȍ~�̎���ꂽ10�N�Ƃ��̌�̓��{�o�ς̒ᒲ�ɂ�������炸�A���Ƃ̋Ɛт͈����Ȃ��A�������J�����z���͒Ⴂ�܂܂������B���ϓI�ȍ����̋ꂵ����炵�Ƃ͗����ɁA�����̓V���肪�ڂɗ]����̂Ɖf��A�����x�z����̒E�炪�K�v���Ǝv���Ă����B������2009�N�̑��I���𐭌����̑I���ƍl���A�������[�����̂́A�����哱�ɑ����Đ����哱�ʼn��v��i�߂邱�Ƃ�}���f���Ă�������ł������B�h�u��I���◘�v�U���ɑ����ă}�j�t�F�X�g�Ɋ�Â������_���őI����킢�A��吭�}����蒅�����邱�ƁB���������ɑ����ď����J��i�߁A�����ɊJ���ꂽ�����`���������邱�ƁB���N�̎����}�����Ɍ��E�������A����}�̉\���ɂ������L���҂̎v�����A�������̌����͂ł������B �@��������A���V�Ԃ̌��O�E���O�ڐ݂Ƃ���������������悤�Ƃ������R�̖���N�͕]���ł���B�������A���R�͎���̌�������S�ɕ����āA�Ӗ�ÂɐV��n�����݂�����ċ��������ɍ��ӂ��A���C�����B���R���ᔻ�����ׂ��́A�u���O�E���O�v������Ƃ��ċ������_�ł͂Ȃ��A������������鏀�����o����S���Ȃ��܂܁A����H���𐄐i���銯���̎v���܂܂ɂȂ����_�ł���B���R���}�j�t�F�X�g�����Ɍ����ēw�͂��Ă����悤�Ɍ������̂ɑ��A��p�̐������͍������������Ɋ��҂��Ă������̂����X�Ǝ�����Ă������B����ő��Ř_�A�����ˑ��A�����J��ނȂǁA�����̐����s�M�𐭌����ȑO�����[�߂Ă��܂��A�����̐������s�\�͂�������B �@�ΕĊW�ł͓`���I�Ȍ��X�^�C�����ێ����A�č����Ɋ���H���ύX�̋c�_���o�Ă��Ă���ɂ��S�炸�A�����ĉ��ꌧ���ł͌����ڐ݂ɑ��锽�̐��_�����m�ɂ���ɂ��S��炸�A����H���ɂ����݂����Ƃ��Ă���B���{�����҂�����̂��A�����J����ɒ������Ă����Ƃ͌���Ȃ��̂ɁB �i�Q�j�R�11�����炩�ɂ����p���[�̒ቺ �@���B�́A�R�E11�̒n�k�A�Ôg�A�������̂��o�����āA����ƕ����̗ގ����A�������s�\�̗͂A�����ē��{�̃p���[�i���ێЉ�ɂ����鑶�݊��j�̒ቺ�����炩�ɂȂ����ƍl����B �@����ƕ����̗ގ������w�E���錾�����ڂɕt���悤�ɂȂ����B���̍��̐����́A���a�̖������S�̖����A����́A��������������̒Ⴂ�n��ɒn��ɉ������A�⏕�����t���Ƃ������̐ŋ����g���āu�[���v�����邱�ƂŁA���{�I���Ɏ��g�ނ��Ƃ�����Ă����B�����������ɕ����ׂ��Љ�I���S��댯���A�������������Łu�����v���邱�Ƃ͉��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�ȑO���疾�炩�ɂȂ��Ă��������̐������s�\�̗͂́A�R�E11�ȍ~�̕����̒x��A���˔\�������獑������邱�Ƃ̎��s�ɂ���āA��薾�m�ɂȂ����B�����哱���琭���哱�ւ̈ڍs�����܂��������A�G�l���M�[����ɂ����Ă����m�Ȍ����}���������A���{�̐���\�͂����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��I�悵���B �@�����āA���{�̃p���[�̒ቺ�B���E�͓��{�̐����̐������s�\�̗͂ɋC�t���A���{�̋Z�p�̐�i���̐_�b�ɂ��^���������n�߂Ă���B����́A�Љ�̍���ƎY�Ƌ��̊�@��O�ɁA���{�o�ς̐�s���ւ̕s���ɔ��Ԃ������Ă���B���S�ۏ���ŃA�����J�Ɉˑ����A�n�����]���ɂ���p���Ɂu�����\���v���Ȃ��Ƃ����������܂߂āA�����͓��{�̃p���[�̒ቺ���Ӗ����Ă���B�p���[�̒ቺ���������Ȃ��Ƃ�����A�����炢�̍��ƂƂ��Ă̓��{�ɁA�ǂ̂悤�ȑΊO�W���K���낤���B �S�D�����炢�̓��{�� �@�k�Ћ~���ɂ�����A�ČR�́A�g���_�`���Ə̂��āA��Вn�ւ̕����A���╜����ƂɌg������B�h�q�Ȃ��犄�蓖�Ă�ꂽ�n��ւ̗A���̑��ɕČR�́A���q���Ƃ̋����w���̂��ƂōЊQ�~��������W�J�����B���̍��ł́A���{�̃��f�B�A��_�����������ČR�Ƃ̋��������̈Ӌ`���L�߁A�����̍����ɕČR�̗L�p�����m�F�����悤�Ƃ����B�����ɁA�g���_�`���ɓ������ꂽ�ĊC�����ƕ��V�Ԋ�n�ƌ��т��āA����ւ̕ČR�����̐�������_�����B���̗����́A�]���ƕς��Ȃ����ꗘ�p�̍Č��ł������B����ł͍ЊQ�~���ƕČR��n�ɂ�镉�S�Ƃ͕ʂȂ��Ƃ��Ɨ�Âɑ������A���{�̃��f�B�A�̕U��Ƃ͑ΏƓI�ł������B �i�P�j�x�����鍑�A���{ �@�����Ō��߂����Ȃ��̂́A�g���_�`��킪�V���E�A�b�v����钆�ŁA�A�W�A��������̎x���������ɂ����Ȃ��Ă��܂������Ƃł���B�k�Ћ~���̊����́A���ӂ̃A�W�A�������h�������~�����ɂ��S���A�����ċ`�o�������Ă����B���{�l�̑����́A�~���₨���Ȃǂ̎x������{���鑤�ɂȂ�Ƃ͑z�������Ȃ������ł��낤�B��i���E���{�͎x���𑗂鑤�ɗ��ƁA�����ԁA�����̓��{�l�͂����l���Ă����B���{����芪�����ۊ��̕ω��́A�R�E11�ȑO�ɂ����݉����Ă����B���Ƃ��A�o�ϑ卑���ے����鐢�E��Q�ʂ��ւ������{�̌o�ϋK�́i�f�m�o���邢�͂f�c�o�j�͒����ɔ�����A�P�l�����荑�������ł̓V���K�|�[���ɂ���ȑO�ɔ�����Ă����B����ȕ���ȊO�ł́A���{�̋Z�p�͂͌��������ۋ����ɎN����A���ӂ̃A�W�A���������łȂ����Ă̋Z�p�V�����Ƀ}�[�P�b�g��D���Ă����B �i�Q�j�V�����̒S����Ƃ��Ă̒��� �@���{�́A�����ƃ|�X�g���������č����Ȃ��A�č���B��̐e���ȓ������Ƃ��ĕč��̑��ɕt���Ă����B�č������E�̒�����S������A�č��̔e���̂��ƂŌo�ϓI�ɉh�Ɛ����I���������ł���ƍl���Ă����B�X�E11�Ȍ�̕č��u��ɑ̐��v�́A�A�t�K���A�C���N�ł̐푈�ɂ������T���Ɠ����ɕ��n�߂��B�C���N����̓P�ނ��咣���Đ����ɂ����I�o�}�哝�̂ɂƂ��āA��Ɍ�̐V���Ȃ鍑�ے����̍\�z�A���̂��߂̕č��̈ʒu�Â����ő�̉ۑ�ł���B �@���A�W�A�ɂ����ẮA�o�ϓI�䓪�ɔ����āA�����̐����I�A�����ČR���I�g�����ڗ����Ă����B�Ƃ��Ɉ��S�ۏ�̊ϓ_����A�����̌R���͑����ɂ��n��̕s���艻�����O���鐺���A�������ӂ̍��X�ɂ����č��܂��Ă����B���s�����̕ύX�����߂钧��҂Ƃ��Ē����A�������ێ����鐨�͂̒��j�ɕč��������A���̑��Ɉʒu����̂����{���ƂƂ炦��̂��命���̗����ł������B �@2011�N�̓��A�W�A�ɂ����钆���̍s���́A�]���̊g���I�Ȏp���ɉ����āA�����ێ��̗�������߂���B�o�ϓI�ɂ݂�Β����́A�O���[�o���o�ςɐ[���g�ݍ��܂���A�f�ՁA�����A�����̊e�̈�ɂ����đ��݊������߂Ă���͕̂�����Ȃ��B�����āA�[���T���E�Q�[���I�ɑ�������̓y�����߂����Ē����́A���V�i�C�œ��{�Ɗ؍��A��V�i�C�Ńx�g�i���A�t�B���s���A�}���[�V�A�A�u���l�C�ȂǂƂ̊ԂőΗ����Ă����B �@�܂�A�����̏o���ɂ���āA�n��ْ̋������܂�\��������Ă����B�m���ɁA2010�N�ɒ����͂����̍��X�Ƃ̑Η�����C�ɋْ��ւƍ��߁A�����ăI�o�}�����̕č��Ƃ̊ԂŌ������Η��p���𐢊E���Ɍ��������B�������A��V�i�C���߂���̓y���ł́A�����̌R���I���݂�O��ɂ����������ł����������B���������͂����܂ł��Ȃ��A�썹�����ɂ����Ă��A�����͊C�R�͂ƍq��@�������ĂQ�̑傫�ȓ��������ʂ��Ύ��ӂ̎����x�z���m���ɂ��Ă����B���̒����̒��ɑD���̎��R�q�s�����߂鍑�ۖ@�̓K�p��č������߂Ă���B�����͕č��̎咣����q�s���R���������Ă��鎖�����w�E���A�`�r�d�`�m�Ƃ̍s���K�́i�b���b�j�̍쐬�Ɍ����Ĉ�v���Ă���B�����́A��V�i�C�ł݂�ƁA����҂��璁���ێ����͂̒��j�I�S����ւƕω�������̂��B �@�������������̕ω��𑨂��邱�ƂȂ��A����}�����̓��{�́A�����}��������ɑ������Ȃ������ύX��_������҂Ƃ��Ē�����G�����A���Ă̌R���I�⊮�W����������p���𑱂��Ă���B�č��́A1971�N�̕Ē����𐳏퉻����40�N���}���钆�A���݊����}�������������Ƃ̐V���ȊW�\�z�����߂Ă���B���S�ۏ�ƌo�ς̊ϓ_����A�I�o�}�����͒����Ƃ̑Η��Ƌ�����D������Ȃ���̊O����W�J����B�����ɁA���{�A�؍��A���B�Ȃǂ̋����̓������ƘA�g���A�`�r�d�`�m������C���h�A�p�L�X�^���ȂǂƂ̑����Ԙg�g�݂��\�z������B �@�R�E11��̓��{�̃p���[�ቺ�́A�����I�ȃp���[�̕ω��������炵�����ۂł͂Ȃ��B�O�q�̂悤�ȍ��ۊ��̕ω��ɂ��S�炸�A�ΕĊW���[�܂���ׂėǂ��Ƌ����O���ɂ����݂��Ă������߁A���{�����A�W�A�ł̑��݊������甖�߂Ă������Ƃ̋A�����B�����҈ӎ��������A�����ԃt�H�[���������ʓI�Ɏg�����Ȃ��āA�n������艻������V�����O����n��o���˂Ȃ�Ȃ��B�ߑ���{���߂����Ă����u�卑�v�ӎ�����E���āA���Ӎ��Ƃ��Ȃ₩�ȊW��z���鐬�n�����u���Â���v�ӎ������A���ꂩ��̓��{�ɂӂ��킵���B �T�D����̗��� �i�P�j�R�E11����{�]���̌_�@�� �@�R�E11�A�Ƃ�킯�����̌������̂́A����ɑ傫�ȏՌ����L���Ă���B����ł́A�Ӌ�����ɍݓ��ČR��n�̈��|�I�����������t���A���{�i�����j�́A�u�U��̕��a�v�����Ă���B�ƔF�����Ă����B�Ƃ��낪�A�����̌������̂́A�Ӌ��Ɋ댯�Ȍ����������t���A�������瓾����G�l���M�[�ŁA���{�i�����j�́A�u�U��̖L�����v�����Ă����Ƃ����A�����P�̍\���I���ʂ�����������ɂ����̂ł���B �@�����A���҂̊Ԃɂ́A�����t����ꂽ���̂ƁA���ꂳ����ꂽ���́A�Ƃ����������݂���B���Ƃ�茻���������n���Ă��邷�ׂĂ̒n��ɂ����āA�����U�v���Ή^�����������ƕ����B�������A�Ì��A�����A�����ēd�����n��t�����̗͂ɂ���āA���Ή^���͉����Ԃ���A�S��18�J���A54��̌������ї����A�����c���s���n���c��܂ł�����Ă���B �@�ɂ�������炸�A���Ɍ��������ۂ����n�������B�Z�����[�̌��ʁA������ނ����V�������������̈��ł���B����Ŋ������悭�m���Ă���̂́A���傤�Ǔ��������A���V�ԑ�֎{�݂Ə̂���V��n���ݖ��ɑ��āA����s���̈ӎu��}����s�����[���s��ꂽ����ł���B�����Ă�������A���Δh�����������B�����A�����̌������v��͓P�ꂽ���A����s�Ӗ�Â̐V��n���v��́A�P��Ȃ������B����ǂ��납�A���݂��Ȃ��A����s���A�����ĉ��ꌧ���Ɉ��͂����������Ă���B����͓��{���A���ĊW�Ɋւ������A�đ��̈ӌ���u�x���邱�ƂȂ��Ɏ����I�ӎv��������邱�Ƃ��ł��Ȃ����炾�B �@����́A�R�E11���A����I�Ŏ����I�ȓ��{�ɓ]������_�@�Ƃ��邱�Ƃ�����Ă���B�R�����{�A���ꌧ���O�ŁA�u�v�����\�Z���Вn�ցv�Ƃ������f�����f���ď����^�����n�߂��l�X�������B��������A�R�E11�܂����p���_�C���V�t�g�Ƃ��āA�u���q�������ۋً}�������ցv�Ƃ������z������ׂ����A�Ƃ����V�����e���������B�u�v�����\�Z�v�́A���Ēn�ʋ����͍ݓ��ČR�����S���邱�ƂɂȂ��Ă��钓���o����A���ʋ���ɂ���ē��{�������肵�A���㖈�N1881���~���T�N�ԕۏႷ��Ƃ������̂ł���B�����������̓������ɗ�����Ȃ��ߏ�T�[�r�X���A�ČR�̋��S�n��ǂ����A�Ђ��Ă͍\���I���ꍷ�ʂ𑱂��Ă���B �@����}�́A�O��͂��̓��ʋ���ɔ������ɂ�������炸�A����k�V�r���h�q���́A�u���ē����͍��̍����ŁA�\�Z�����ł���Ζh�q����ɐH���Ⴂ��������B�k�Ђ͓˔��I�Ȃ��̂ňꏏ�ɘ_����̂͂������Ȃ��̂��v�Əq�ׁA�O�Q���@�Ƃ��킸������̐R�c�Ŗ���A�����A�����Ȃǂ̈��|�I�����ŏ��F���ꂽ�B�܂��A�V�����{�����K�₵���u�V���I�̈��S�ۏ�̐����m������c���̉�v�̑O�����i�i����j�A���J���i�����j�A�����r���i�����j��́A�u���Ăō��ӂ����ČR���V�Ԕ�s��̕Ӗ�Èڐ݂}�h�Ő��i���Ă����v�Ƌ��������B���ꂾ���̑�ЊQ�ɒ��ʂ��Ȃ�����A�����]�@�ɐV�������{�݂̍����Nj�����̂ł͂Ȃ��A����H����Đ��I�ɓ��P�������悤�Ƃ��Ă���̂ł���B �i�Q�j���삩��n�܂鎩���Nj��̊X�Â��� �@�u����v��_���錾���̒��ɂ́A����̈Ӑ}�������Ĕ��M�������̂����Ȃ��Ȃ��B���ɒ������f�B�A�������鉫��ςɂ́A��n�̓��E������ӂ̂܂܂Ɏx�z�������悤�Ƃ��鐭�{�̍��������̈�ۑ���ᔻ�ɉ��x�����Ă�����̂�����B���̍ł�����̂��A�u����Љ�A�o�ς̊�n�ˑ��v�_�ł��낤�B �@����ɕČR��n��u��������u�\���I���ʁv���������Ă����傫�ȗv���̂P�ɁA�u����͊�n���Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��v�Ƃ������������[�����݂���B�S���ɗ��z���ꂽ������펯�ł���B��n�֘A�̌o�ώw�W�ƁA��n����ƌo�ϐU��������ޗ��ɂ��邱�Ƃ��^�⎋���鉫�ꌧ���̈ӎ��̒n�k�ϓ����炷��ƁA��n�ˑ�����̒E�p�̗���͉����Ƃǂ߂�����̂ł͂Ȃ��B �@�ČR�������A�����Ė{�y���A����A���ė����{�́A�ČR��n������I�Ɉێ����邽�߁A��n�����ꂴ��Ȃ�����̎Љ�o�ύ\���𐭍��I�ɂ���o���Ă����B���{���{�͒����ւ̍����ˑ����[�܂�قǁA����ł̕ČR��n�ێ������₷���Ȃ鐭��𐄐i�����B �@����o�ς���n�ɑ傫���ˑ����Ă��������͂������B1950�N��ɂ͊�n�֘A���������������Y��50�����Ă����B�{�y���A���_�ł�15�E�T���ƂȂ�A���̊����͌��葱���A���ł͂T���O��ɂ܂Œቺ�����B �@�ČR��n�����y�S�̂ɐ�߂銄����10�E�Q���A����{���ł�18�E�S�����߂�B�ɂ�������炸�A��n�͂T�����x�̌o�ό��ʂ������ݏo���Ȃ��B�ČR��n�̓y�n���p�̔����������R�Ƃ��Ă����B �@���V�Ԕ�s��̊�n�W�����ƁA��n�O�̋X��p�s��̏����Y���ׂ�ƁA��n�O���Q�E�T�{�ɏ��B�Y�Y�s�̖q�`�⋋�n��i�L�����v�E�L���U�[�j�����l���B��n���ێ���������A�ԊҁE�Ւn���p���������͂邩�Ɍo�ό��ʂ��傫���Ȃ邱�Ƃ͕ԊҐՒn�̎��Ⴊ�ؖ����Ă���B�ߔe�s�̐V�s�S�n��͕ԊґO�̂Q�O�{�߂����Y�U���z������A��100�l��������n�]�ƈ���4000�l�߂��ٗp�ݏo���X�ɕϖe�𐋂����B�k�J���̔��l�E�n���r�[��s��Ւn�̐��Y�U���z�͖�300�{�ɏ��B �@�ݓ��ČR�̍ĕ҂ɂ���āA���V�Ԕ�s����܂މÎ�[��n����̂U��n���Ԋ҂���邱�ƂɂȂ��Ă���B�풆���ɕČR���g�ݕ~���������ōł��엀�ŕ��R�ȗD�ǒn�S�ł���B�ߑ�]��������邽�߁A���ꌧ���������f�[�^�Ɋ�Â��Ă͂����o�����o�ϗU���\���́A�P��1000���~�]�ɏ��B �@�����������l��ςݏd�˂Ă����A�u���݁i�ČR��n�j�v���u�lj݁i���Ԍo�ρj�v���쒀���Ă�������������Ƃ炵�o����Ă���B �@���{���J��o����n���݂́u�U����v�͒n�����߂肳�����B�ČR���V�Ԕ�s��̖���s�Ӗ�Èڐ݂̌��Ԃ�Ƃ��ē�����ꂽ�k���U����͎s��������������Ȃ鍑�ˑ��^�Ɏd�����A����s�̎��Ɨ��͂���10�N�ň����̈�r�����ǂ��Ă����B �@�����������A�u�C�ɂ����ɂ���n�͑��点�Ȃ��v�ƌ������i����2010�N�P���ɖ���s���I���œ��I���ʂ������B���{�����V�Ԕ�s��̉��ꌧ���ڐ݂𐄐i�����ŋт̌���������u�n�������̂̓��Ӂv�͕��ꂽ�B�����āA����^�O���m�������N11���̌��m���I���ŁA���V�Ԕ�s��̌��O�ڐ݂����߂����ɑǂ��B����^���̕��j�]���̓y��ɂ́A�}�h���Ă��ĂȂ����܂��������ڐݔ��̌������_�ƁA��n���݂̐U����́u���z���v��[���F����������̖��ӂ��������B�A���ƃ��`��U�肩�����u�⏞�^�̊�n�ێ�����v�̌��E�Ƃ��������������̖��ӂ��N���ɂȂ����B �@�ČR���V�Ԕ�s��̈ڐݐ�Ƃ���Ĉȗ��A����s�́A����ƒn���������s����������h�����������ł����B��n����̑㏞�Ƃ��Ċl������U���A��̐�����n��Â���Ɍ��т��ۂ��Ƃ��������I�Ȗ₢����ɓ˂��t�����Ă����B���s���́A�������n�𑣂��d���O�@�����f���Ƃ��Ă���ꂽ�u�ČR�ĕҐ��i�@�v�Ɋ�Â���n�ڐ݂̐i�W�ɉ����ďo�������������ČR�ĕҌ�t���ɔ����Ȃ��A����̎�����Njy����X�Â�����f���Ă���B �@���s���̓��I��A���{�͎s�̌������Ƃɏ[�Ă�ČR�ĕҌ�t���𓀌�����ȂǁA�I���ȗh���Ԃ�������Ă����B�����A���s����2011�N�x�ɍĕҌ�t�����v�ス���A��֍����őΏ����錈�f���������B�A���ƃ��`�ɖ|�M���ꂸ�A���l�C���łȂ�����s�S�̂̊������Ɍ����A�X�Â���̗��z��Nj����铮�����ڗ��悤�ɂȂ��Ă���B�u�w�N�������Ƃ�����x�ł͂Ȃ��A�w�����B�ł�낤�x�Ƃ����ӎ����K�v�v�Ƃ�������s�̊X���̃��[�_�[�̂P�l�����������t�́A����̖�����C���ɂӂ��킵���B �@����̎{�����ԊҌ�A�l���ɂ킽�����u����U���v��v��2012�N�R���ɏI����������B27�N�Ԃ̕ČR�����ŗ�����ꂽ�Љ�{�����ɐ��{���ӔC���A���H���`�A�`�̐����ȂǁA���̖������ʂ����Ă������A�ߔN�͕��Q���肪�����яオ��悤�ɂȂ����B�s���{���̒����U���v��ŁA���Y�����̂Ɍ��茠���Ȃ��͉̂��ꂾ�����B���������甲���o���Ȃ��������Ɣ�́A���������ɋ߂�����╟���ɂ͏[�Ă��Ȃ��B�S�����ς̂قڔ{�ō��~�܂肷�鎸�Ɨ��A�S���̂T���̂P�ɊÂ�u�����Ɓv�䗦�ȂǁA�������������Ԍo�ς̗U���Ɍ��т��Ȃ����z��f����ׂ������}���Ă���B �@����́A�n��̏����������߂�u���Ȍ��茠�v���D���Ă����B�����A�悤�₭�A���̎������������A2012�N�x���牫�ꌧ�����肷�鎟���U���v�悪���Ă����B����U���̎p�́A�n��匠�Ǝ��Ȍ��茠�𗼗ւɂ��ėl�ς�肷��B����������]���������鉫��̎����Đ��̉c�݂́A�����t����ꂽ����ρA���{�Ɖ���̊W�������߂鎎���ƂȂ�ł��낤�B �܂Ƃ� �@�������ƂR�E11���o�āA���B�́A�����Ɨ��݁A���}���݂ł́A�s�������ˑ��̍�������ƕč��ˑ��̑ΊO����Ƃ����s���l�܂肩�甲���o�����Ƃ��o���������Ȃ����Ƃ��킩�����B�����s�M�̗��Ԃ��Ƃ��āA�����Ƃ����_�����𗘗p���Đ����I�������邩������Ȃ����A�����Ƃ̃C���[�W��p�t�H�[�}���X�Ɉ���J���Ă����Ԃ͍D�]���Ȃ��B �@�l�X�̕��a�ƈ��S����ɓ���邽�߂ɂ́A�n��̎Љ�W���{�i�\�[�V�����L���s�^���j�Ɏx����ꂽ�n��匠�̊m�����K�v�ł���B�n�������ɂ���āu�^����ꂽ�v�\�Z�⌠�������ł͕s�\���Ȃ̂��B�����������ɍs���ׂ��Љ�I�R�X�g��X�N���A�]���̂����Łu�����v���邱�Ƃ͉��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��́A�n��Љ�Ɛ��{�̓w�͂ɂ���ĕ��S�E�댯�����炷���A����ł��c�镉�S�E�댯��n��Љ�����ɕ��S���鎖�����߂��Ă���B �@����ɑ����Č����Ȃ�A�������S�ۏᐭ����̂āA���A�W�A�̈���ƕ��a�Ɋ�ʂ�����S�ۏᐭ���ł����Ă邱�Ƃ��B�������S�ۏᐭ��Ƃ́A����̐l�X�ɕ��S������������{�̈��S�̂�����ł���B3�E11���_�@�ɓ��{�̃G�l���M�[������������̂Ɠ��l�ɁA����Ɉˑ����Ă������{�̈��S�ۏ���ɍڂ��A����̐l�X�����{�{�y�̐l�X�Ɠ��������S�ň��S�ɕ�点��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ɂ��d�͎����W�ł����A�����̕��S�̏�œ������ɉh����\�����猈�ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�����{��k�Ђ���̕��������{�S�̂̉ۑ�ł���̂Ɠ��l�ɁA���60�N�ȏ�ɂ킽�艫��ɊÂ��A�ˑ����Ă������S�ۏᐭ��̌��ʂ��A���{�̉ۑ�Ȃ̂��B |
||
| �i�w���E�x2011�N10�����j | ||
|
|
| ���ȏ����@�B�����ꂽ���d�R�j ��c�Òj�i�������E������1948�N�Ί_�s���܂�B���Ί_�s�������R�c�@�B�����Ɂw���d�R���j�x�w���d�R�̌|�\�x�w���d�R�̐푈�x�j �I���Ȏ�i�ŗ��j�ۋ� ���̐ӔC��킸�Z���ɓ]�� �@���ȗp�}�����d�R�̑�n�拦�c��i��E�ʒÔ����Ί_�s���璷�j���u�V�������j���ȏ��������v�n�̈�Q�Ђ̌������ȏ���I�肷��܂ł̎�@�́A�u�����v�n���ȏ����̑����ꂽ���l�s�ȂǑ��n��Ɠ����ł���B���̍I���Ȏ�i�������ꉫ��ɂ��g�y����͕̂K�肾�Ǝv���Ă����B �@�����ł̉E�X���͋}�ɋN���������Ƃł͂Ȃ��B�푈�̌��҂͍�����A�ČR��̉��̊�n���݂̂��߂̓y�n���D�A�l�������̗��j�͂��Ȃ��ɒǂ����ꂽ�B�����a�F�O�����ق́u�Z���s�E�v�̌R�֗^�𔖂߂�悤�ȓW���ύX��A�c�NJԗł́u�W�c�����i�����W�c���j�v�̌R�֗^��ے肷���]�E��g�ٔ���N���������B �@���d�R�ł͗^�ߍ�����Ί_�s�̕ێ�a���ɂ���āA���q���A�ČR�̃w���R�v�^�[������Ŕ��J��Ԃ��Ă���B �@�^�ߍ����͐ϋɓI�Ɏ��q���U�v��}��A�Ί_�s�ł͎s�c���s���ƘA�����Ƃ肠���Ȃ����t�ɏ㗤�����B�h�q������O�ʂɏo�āA���̊ۂ�U���Ď��q�������}����܂łɂȂ����B�����̓��ɂ͍��h�ӎ��A�����S�A���@������i���鉡�f����|�X�^�[�������炱����ɓ\���A�n�g�̓��͂��܂�^�J�̓��ɑ�ϖe�𐋂��悤�Ƃ��Ă���B �@���̂悤�ȂȂ��ŁA���炪�_�������ɂ��ꂽ�̂ł���B ���t�����錄�� �@��Q�Ђ̗��j���ȏ��u�V�������{�̗��j�v�́A����I�肳��Ȃ��������̂́A�����i����j�̏d�v�ȗ��j�ȂǁA���ƐӔC�ɋy�Ԃ��͈̂Ӑ}�I�ɉB�����Ă���B �@���������̗��������A�E���l�����̒�R��A�������{���R����h�����Ď���J�邳���A���Ή^����e���������ƂȂǑS���Ȃ��B �@�R�����u�u�̌���̉̎��S�ԁv�ɂ́A�u�瓇�̂����Ȃ���@�₵�܂̂����̂܂���Ȃ�c�v�Ɖ�����̓y���ƏЉ�Ă��邪�A�������{�����������̗��N�A�����C�D���K�ōŌb���ҋ����邽�߂ɉ��ꌧ����̂��A���d�R�E�{�Â𐴍��Ɋ������悤�Ƃ����A�����镪���Ăɂ͑S���G��Ă��Ȃ��B �@���d�R�n��̋���ψ��͉ʂ����āA���̂悤�ȗ��j��m��Ȃ���A��Q�Ђ̋��ȏ���]�������̂��낤���B �@��Q�Дŗ��j���ȏ��̉B�������ς͉���L�q�ɂ��@���ɕ\��Ă���B �@���{�R���Z���⒩�N�l���E�Q������A�e�������������Ƃ͈�؋L�q����Ă��Ȃ��B�u�ČR�̖ҍU���œ�����������A�W�c����������l�����܂����v�Ƃ��A���{�R�͂܂������֗^���Ă��Ȃ��̂ł���B�܂�u�����v�̐ӔC�͏Z���ɂ���Ƃ������Ƃł���B �@���d�R�̐푈�}�����A�́A�R���Z���������n��ɋ����I�ɑދ����������Ƃɂ���ċN�������A���Ĕ��d�R�푈�}�����A�����҈ԗ�V��̎��T�ŁA����J���������́u��Ђꂽ���̏Z��������]�V�Ȃ�����c�v�ƒ������q�ׂ��B �@�܂�2006�N�܂ł̓��t�{�}�����A���S���Ƃ̃z�[���y�[�W�ɂ��u��̑�펞�ɉ��ꌧ���d�R�n��ɂ����ďZ���̕��X���}�����A�L�a�n�тւ̔���]�V�Ȃ�����A�q����Ԃ������H�Ƃ��\���łȂ��ߍ��Ȑ����̒��}�����A���W���I�ɔ������A�����̕����Ȃ��Ȃ��܂����v�Ƃ������B �@��Q�Ђ̋��ȏ��ɂ͐푈�}�����A�̋L�q�����Ȃ����A�R�̋����Ƃ�����ꂪ�Ӑ}�I�ɏ�����A�Z���ɐӔC��]�ł��镶���͈ȑO���炠�����̂��B���������d��Ȗ������ꂩ��ᔻ���邱�ƂȂ���肷���������Ƃ����j��c�Ȃ��A���{�����@��G�����鐨�͂ɔ��d�R�i����j�������錄��^�������Ƃ��l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B ������̗�] �@�����A����Ɉ��������ČR��̎x�z���łǂꂾ���̉��ꌧ�����s�E����A���Y��j��D��ꂽ���B����{�����Ԋ҂ɂ��Ă͉��̃A�����J�{�����������A���̉��ʼn����s���A�ǂ��������R�ʼn���̐l�X���{�y���A���߂��������B�L�q�͂Ȃ��B �@���̋��ȏ��́A���{���Ƃ̍��v�̂��߂ɂ͉���𑼍��֏��n�������͐�̎x�z��e�F���Ă����Ƃ������j���A���t�̂���ōI���ɉB�����Ă���̂ł���B �@���̂悤�Ȏj�ς��������l�����i����W��13�l���V�l�����j�̎��M�҂Ɠ����l���ł���j�������Ƃ͌��킸�ƒm�ꂽ���̂��B �@��Q�Ђ́u�V�����݂�Ȃ̌����v�͌��@�G���A�V�c�^���A�R���i���q���j�e�F�A���ē����̕K�v�����������Ă���B�������u���̂��߂ɂȂɂ��ł��邩�v���l���邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă���B �@���ꌧ���̈ӎv�����č��̍��v��D�悳���A��n��Q���Ȃ�������ɂ��A�j�������݁i����j�ō������\�������{�B����ɂ͈�ؐG�ꂸ�Ɂu���̂��߂ɉ����ł��܂����v�͂Ȃ��B���̋��ȏ����̑����邱�Ƃ͂��Ȃ킿�A����̍��ւ̗�]�ł���B �@�����͊J����ꂽ�B���͂₪�ĉ��ꒆ�ɐ����r���\���������B�ЂƂ�ЂƂ肪����Ă���B |
||
| �i����^�C���X20110914�j | ||
| �w����Љ��O�}�j�x �ڎ� �����ɍۂ��āi�}�j�Ҏ[�ψ����@���{����j ��P���@�ʎj�� �@��P�́@�Б�}�̌����i1945�N�`1950�N���j �@�@�@��P�߁@���}�O�̉��ꐭ�E �@�@�@��Q�߁@�����̖G�� �@�@�@��R�߁@�Q���m���I�� �@�@�@��S�߁@���}��� �@��Q�́@�����̕��A�^���i1951�N�`1953�N���j �@�@�@��P�߁@�Љ� �@�@�@��Q�߁@���A�^���̑ٓ� �@�@�@��R�߁@�C����ȂƓ}�̕��� �@�@�@��S�߁@�A���n�����Γ��� �@��R�́@�R�p�n�ڎ����Γ����i1953�N�`1958�N�j �@�@�@��P�߁@�R�p�n���̔��[ �@�@�@��Q�߁@�S�����ѓO���� �@�@�@��R�߁@���A�u�[���Ɠ}�̕��� �@�@�@��S�߁@��1�}�i�o�ƈꊇ�����p�~ �@��S�́@�������g�哬���i1959�N�`1967�N�j �@�@�@��P�߁@�������g��Ǝ�Ȍ��I �@�@�@��Q�߁@���A���̌��� �@�@�@��R�߁@��P�}�����ƐV� �@�@�@��S�߁@�������g��Ƒ�O�^�� �@��T�́@���한�A�����i1968�N�`1972�N���j �@�@�@��P�߁@���j�E����n���� �@�@�@��Q�߁@���NJv�V��Ȃ̒a�� �@�@�@��R�߁@�����Q���I���̏��� �@�@�@��S�߁@�T�E15���A�̈Ӗ� �@��U�́@���S���A�����i1972�N�`1980�N���j �@�@�@��P�߁@�V���ȓ����ւ̏o�� �@�@�@��Q�߁@���A��̏���� �@�@�@��R�߁@���ǒm���̒a�� �@�@�@��S�߁@80�N��̓W�] ��Q���@������ �@��P�́@�N�\�i�}30�N�̕��݁j �@�@�@�@�@�P�A�}�������� �@��Q�́@�L�^�i�}�W�̕��́j |
|||
| �P�A���}�ɏA�e�i�z���j�@�Q�A�e�Q�����{�̒m���y�і����c���I���i�z���j�@�R�A����∥�A�i����Q���m�����ҁ@���ǒC�Y�j�@�S�A����Q���m���I������i�����A���ǁA�����̊e���j�@�T�A�Q���m���y�ьQ���c���̑I�����i�萔�y�ѓ��[�j�@�U�A����Q�����{��]���i����j�@�V�A�錾�i���}���j�@�W�A�j�́i���}�̍��j�@�X�A����i���}�̍��j�@10�A�Љ��O�}�����͏��@11�A����}��E������i�{���y�юx���j�@12�A�Љ��O�}�����P���@13�A�����Љ��O�}�̐��i�i�ψ����@���ǒC�Y�j�@14�A�Љ��O�}���H�o�߁@15�A�]�����i1951�N�j�@16�A���{���A���i�������ӏ��@17�A���{���A���i�������@18�A�������{�̐ݗ��i�z���j�@19�A�]�����i1953�N�j�@20�A�A�����J�̗��������Ɋւ��錩���@21�A�č��̉��ꓝ���̌��Z�i�����ҁj�@22�A�č��̉��ꓝ���̌��Z�i�����ҁj�@23�A����Љ��O�}�ւ̗����@24�A���A�i�ψ����@�����ϐ��j�@25�A�{�����ԊҐՂɑ����{�ԓx�Ɨv���@26�A����ԊҐՂɊւ��鐺���@27�A���A��̓}�g�D�H���ɂ��āi���āj�@28�A���A��̏���菈���Ɋւ���v�����i��P���j�@29�A���A��̏���菈���Ɋւ���v�����i��Q���j�@30�A���ꌧ���E���}�i�����c�́j�ꗗ�@31�A���}�R���@32�A1980�N�x�}���s�̐� |
|||
| �Ҏ[��L�i�Ҏ[�ψ��@��×ǕF�j 1981�N�S���W�� ����Љ��O�}�j�Ҏ[�ψ��� |
|||
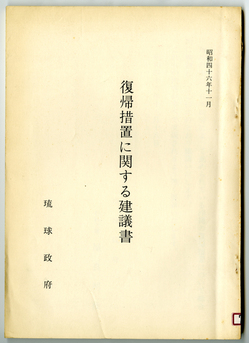
| ���ʂ̍\�}�u���A�����v����q�S�r �m�O�@�E�V ������x�z�̍\���^�����S�[�߂�c�_�K�v �@�n�k�A�Ôg�A���˔\�Ŏ��ʂ��`�u�������ߐs������A���������A�č������ȓ��{�ɖ{�������X�R���ꂽ���A���͂��̌�ǂ��Ȃ������A�Ǝv���Ă�����A�k�Ўx���̒����S���ɂȂ��Ă����B���������Ȃ�ސE����ӌ����������A�k�Ђ������������߁A�ݓ��ČR�⌴���ɏڂ����ƃ|�X�g���^����ꂽ�i����������.�������R��16���j�B�����m���āA����l�̖��_�Ɣ�Ў҂̐����A���S�Ƃ��V���ɂ������Ă���悤�ȕ��G�ȋC�����ɂȂ����B�k�Ўx���͑�Ȏd���ł���B�������A����l�݂̂Ȃ炸�A���{�l�A���{�����ւ̍��ʔ����������ނ́A����ɂ��Đ������Ӎ߂��P������Ă��Ȃ��B�č������Ȃɂ͗D�G�Ȑl�ނ����ɂ�������͂����B����l�Ɣ�Ўґo���̖��_�Ƒ������d�A���̏����ɂ��ĕĐ��{�͋�ʂ��ׂ����B�I�o�}�哝�̂̔C���ӔC�������B �����Ș_���j�] �@���āA���A���̌��̔��������A���̓��e�̘_���j�]�Ԃ肪�����[���B�Ⴆ�A�ނ́u���{���{�́w�����ق�����T�C������x�Ɖ���m���Ɍ����K�v������v�ƌ������A����͂����������ʂ̂Ȃ����Ƃ��B�Ȃɂ���A�ނ������u���{���{���I�݂ɑ���䂷�閼�l�v�ł��鉫��l�Ȃ�A����ȋ������ȂǍI�݂ɐ蔲������B�܂��ނ̌����Ƃ���A������������l�́u�R���̂P���A�R�������Ȃ��Ȃ�A��蕽�a�ɂȂ��ƐM���Ă��āv�u�Θb�s�\�v�A���Ȃ킿�A�����s�\�Ȑl�X�ł���B���̏�A����s���I�A���m���I���ւāA���⌧���ڐ݂����ۂ����O�ڐ݂������錧���̈ӎu�͋��łɂȂ���肾�B�����āA����̔��������ɂȂ������߂ɁA����m�������j��ς��Č����ڐ݂��̂߂u�����ق����ăT�C�������v���ƂɂȂ�B �@�ނ́u����̎�v�Y�Ƃ͊ό��Ƃ��v�u����l�͑ӂ��҂�����S�[���[���͔|�ł��Ȃ��v�u����͗������A�o�����i���ɔo�q�j�A�����^�]�����ł������B����͓x���̍����������މ��ꕶ���ɗR������v�Əq�ׂ�B�S�[���[�̕����́A�����̋ߏ��̏��w���ł��u�́[�H�S�[���[�A�����Ă�₵�v�Ƃ������炢�̉R�ł���B���̑��A�Ăł��ό��Ƃ͈��Y�Ƃ����A�������A�o�����i���ɍ��O�q�j�A�����^�]���͍����B�u�b�V���O�đ哝�̂ɂ͈����^�]�̑ߕߗ�������B�o�[�{���ȂǓx���̋��������D�ސl�������B���̂悤�ɁA�ĎЉ�ɂ����邱�Ƃ��A����Љ�̓��F�̂悤�ɍ��قƂ��ĝs�����ĕ��J���邱�Ƃ��A���ʂƂ����B �s�����I������ �@�ނ����ꌤ�C���s�ɍs���Ă̊w�������ɂ���Șb�������̂́A�w�������Ɏ����Ɠ����܂Ȃ����ʼn�������Ăق����������炾�낤�B�����łȂ���A�w�������́A�R����n�ɒ�R���鉫��l�ɋC�����A�Ќ��A�Εׂ��A�E�ϋ��������������Ă��܂�����łȂ͂����B�����Ȃ�A����ւ̊�n�������̕s�����������̎Ⴂ����ɂ���Ă��܂��B�����Ď��ۂ����Ȃ����B �@�ނ̕��̂̌��t�ɐ��ނ̂́A�u���J�A��A�A����A��蛁A�s�q���A�ӑāA���c�A���~�A���y�I�A�s�����v�Ƃ�������l�ւ̏���ȕ]���̉��������B����́A�u���������v�ȗ��A���{�l������l�ɋ��v�������b�e���Ɠ����ł���B�����āA���{�l��A�����J�l�݂̂Ȃ炸�A���E���̐A���n��`�҂���A���҂����̂悤�Ȃ������Ȃ߂Ă����B �@�ނ�͎���̐N���A�A���n�x�z�𐳓������邽�߂ɁA�u����������x�z����v�u�D�ꂽ�҂�������҂��x�z����v�Ƃ����_�����ł����グ���B�����āA������u�����v�u�D�ꂽ�ҁv�ƍ��߂ċU�����邽�߂ɁA�x�z�������҂J���A��߂悤�Ƃ���B�����ɂ����ẮA���̂悤�ȓ��{�l�̍��ʂ�����l���Ɍ����킹�A�����ɂ����āu���h�ȓ��{�l�Ƃ��Đ킢���ʁv�i�ڎ�^�r�w����u���v�[���N�x�j�܂łɒǂ��߂��B�����ē��Ă̍��ʂ͊�n�������Ƃ�����̓I�Ȍ`�ō��������B �����[�k�[���K �@����A�����̍��ʂƓ����Ċw���ƂȂ����ĉ���l�����A���X�R������������̂́A���ɉ���̎�����ւ̑傫�ȃv���[���g���B�u�������͍��ʂ�����Ȃ����A�����Ȃ��v�Ƃ����p������Љ���������炾�B�����āA�厖�Ȃ��Ƃ́A���̂悤�ȁu�]���̉������v�ɁA���_�⎖������ŗ����𐿂��Ƃ������A�u�����[�k�[���K�i�����牽���j�v�ƌ������Ƃł���B�������͎������̂܂܂ł����B �@�u��ؐl�v�ƌĂԂȂ�Ăׂ����B�i�A���n�x�z�ɕs�s���ȁj�u��ؐl�v�͐������B�������́u��ؐl�v��O�ꂵ�Đ�����̂ł���B �@�����A����������悤�ɂȂ�̂ɂ͈�l�ł͓���B����l���m�Řb���������Ƃ��K�{���B���ꂼ��̏��A�{��A�߂��݁A���|�Ƃ͉����B�S�Ƒ̂̂ǂ����ǂ̂悤�ɔ�������̂��B��������A���ʂɂ��x�z�̃��J�j�Y���₻�̎�_�������Ă���B�݂��̒m�b���w�э����A���ȍm�芴�A�����S��[�߂邱�ƂŁA���̉���l����ア�҂ւ̍��ʂ̓]���E�A���n�x�z�ւ̋��Ƃ���߂���B �@����l�����ŏW�܂�̂́u�r���I�v�Ɣ����ƕ|����������Ȃ��B���̔��ɑ��Ă��u�����[�k�[���K�v�Ȃ̂����A�����Č���������܂�A�u����l���w�r���I�x�ɂȂ邱�Ƃ��K�v�Ȏ��ɂ͕K�v���v�B����邱�Ƃ͂Ȃ��B�i���ɂ�E������1966�N�ߔe�s���܂�B�ނʂ�����[�i���C�^�[�j�B���ꍑ�ۑ�w���u�t�B�����Ɂu�E�V���䂭�v�ȂǁB����^�C���X2011.03.21�j ���ʂ̍\�}�u���A�����v����q�T�r �V��@��v �����@���Ӗ������m�^�R���̍ЊQ�x���͖��� �@�����{��k�Ђ̍ЊQ�ƌ�����@�̕ɒ��ʂ��Č��t�������Ȃ���A���������Ă���̂́A���Ђ���̖h�q�𑶍ݗ��R�Ƃ���R���́A�����̋��Ђ�O�ɂ������͂��ł���B�ČR�ł��낤�Ǝ��q���ł��낤�ƁA�����R���́A���ƂƌR�g�D����邱�Ƃ݂̂�ړI�Ƃ��鏃�R����\�͑��u�ł����āA�ЊQ���ɍ��������Ƃ�����ړI�����߂���L���Ă��Ȃ��B�j�����헪�����@���͂��߂Ƃ��邠���镺��͍�����������邽�߂ɑ��݂���̂ł͑S���Ȃ����A����킪�ؖ�����悤�ɁA��펞�ɂ����Ă͍����������R���̕W�I�ƂȂ�B �@���̈Ӗ��ŁA����̑�k�Ђɓ������āA�ČR�Ǝ��q���������ɂ܂��قƂ�ǖ��͂ƌ�����̂́A���ꂪ�R���ł�����蓖�R�ƌ����Γ��R�ŁA���ꂪ�ЊQ�x����{���Ƃ���g�D�ł���A���݂̌R����̐��番�̈�Ō���Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��L���I�Ȏx�����W�J�ł����͂��ł���B �@������k���N�����Ђ��Ƌ�������������ĉ�����ӂœ��ċ����R�����K���g�勭�s���Ȃ���A�����ɋN���鋺�Ђɑ��Ă͂قƂ�Ljׂ����ׂ��Ȃ��B����A���Ђƌ����Ă��������͉������𑁋}�ɑ���A�k���N�ɓG�ΓI�s���݂͂��Ȃ��B���������A���ė����{�����`���Ă������ЂȂǂǂ��ɑ��݂���̂��B�ނ���A��������x���̐��̋����ׂ��Ǝコ�������A�����������炳��Ă��鋺�Ђ̖{���ł͂Ȃ����B���Ђ́A���̍��Ƒ̐����̂��̂Ƃ����ق����A��萳�m�ł���悤�Ɏv����B ��̎҂̋�� �@����̐k�ЂŁA���{���{�͈ٗl�Ƃ������鑁���ŕČR�֎x���v�����A�I�o�}�����͕ČR�C���[�W���}���u���ē����̏d�v���v�Ƃ����v���p�K���_��搂������āA���ɂ�����Č��q�͋����O�������ɔh���������A��������˔\���������ꉫ�������ɑޔ�����n���B���̂����A�A�����J���ŊJ��Ƃ��Ď������̂��A���̕ČR�v���p�K���_���̒������ɁA���ꍷ�ʔ����ōX�R��������̃P�r���E���A����C������Ƃ������Ԃł���B �@���̍��ʎ�`�҂��A��k�ЂŔ�Ђ����l�����̎x���̗v�����u�䂷��v�ƌ��Ȃ��Ȃ��ƒN�������ł��邾�낤���B����̐l�Ԃɑ��āA��O���킵���l�퍷�ʔ��������Ĝ݂�Ȃ��������A���̊�@�ɂ����đΓ��������ɂ܂������C������A�����J�Ƃ��������܂���O���킵�Ă���B�����Ɏ����āA���ČR���������������Ă������������Ă����ƌ����邾�낤�B �@���������A����������ɐ�����l�ԂɁA���ČR�������Ƃ������̖̂��Ӗ����Ƌ��낵���m�ɔF�������Ă��ꂽ�̂��P�r���E���A���ɂق��Ȃ�Ȃ��B���A���̗B��̌��т́A�g�������Đ�̎҂Ƃ������̂̋���������Ɏ����Ă��ꂽ�_�ɐs����B���ꂪ�W��I�ɂ��̍\���I�\�͂ɂ��炳��Ă�����ČR�������Ƃ́A�Γ��ȓ��������J�Ȃǂł͑S���Ȃ��B���̓����́A���{�̃A�����J�ւ̑S�ʓI�������I�ȑ������ł���A���̎x�z�W�̍ʼn��w�ɉ������߂��Ă��鉫��̐l�Ԃ́A���������咣���R���A���n����ᔻ���鐳���Ȑ��������������ŁA�u�䂷��̖��l�v�ƕ��̂����d�g�݂ɂȂ��Ă���B���̎d�g�݂��������ē����ƌĂ����̖̂{���ł���A�l���`�I�ȍ��ʂ���ՂƂ�����ē����Ƃ́A�������������Ȃǂł͂Ȃ��A�Εėꑮ�Ƃ����ق�������ɋ߂��B �Εėꑮ�����{ �@�A�����J�Ƃ�����̎҂ɂƂ��Đ�̂���Ă��鉫��̐l�Ԃ́A�����̖��J�l�ł���A�Γ��Ȑl�ԂȂǂł��낤�͂����Ȃ��B�ČR�ԗ���瀂��E����悤���A�ĕ��Ƀ��C�v����悤���A�ČR�͐�̎҂Ȃ̂�������̎҂ł��鉫��̐l�Ԃɂ���ĕĕ���ČR���ق���邢���͖����B���ꂪ���Ēn�ʋ�������炷��A�����J�Ɠ��{���{�̘_���ł���B�ݓ��ČR�̔ƍ߂ɑ��ē��{�����ٔ�����������閧����܂ނ��̓��Ēn�ʋ���ɂ����āA����̐l�Ԃ́A�p������ĕ��̔ƍ߂�ƍ߂Ƃ��đi���铹����������Ă���̂ł���B �@�����Ă������Ď�������O�@���ŕی삳�ꂽ�ČR�́A����ɂ́A�N�Ԗ�6500���~�ɂ���邨�������֘A�\�Z���������̐ŋ��̂Ȃ�������{���{�ɂ���Ă��Ă����Ă���B�܂�́A���ē����Ƃ������̑Εėꑮ���A���A���̂悤�ȋ��Ȑ�̎҂��琬����̂ł���A����������̎҂̋���ʂ��āA����͓��ČR�������̍\���I�\�͂̂Ȃ��Ɋċւ���Ă��܂��̂ł���B���̐�̓I�ȍ\�������{�I�ɕς���ɂ́A��n���O�ڐ݂Ȃǂł͌����ĂȂ��A���ČR�������̉��������Ȃ��̂͂��͂▾���ł���B �u�}�~�́v�͖ϑz �@���{�̈��S�ۏᐭ��ɂ���A���ČR�������ɂ���A�����͉���ւ̍ݓ��ČR��n�̏W���Ƃ������ʐ���ɂ���Đh�����č\������Ă��鍻��̘O�t�ɉ߂��Ȃ��B�����āA���{�����Ő����̎��ҁE�s���҂Ɛ��\���̔��҂��o��Ƃ��������̋��Ђ�O�ɂ��āA���ČR�������̌R���́A�c��ȌR���\�Z�������݂Ȃ���قƂ�lj����ł��Ă��Ȃ��B�������́A���܂����A�u�����̈��S�v���R���Ƃ����u�}�~�́v�ɂ���Ėh�q����Ă���Ƃ����ϑz�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@���̂��߂ɂ��A�Ȃ��̗��ۂ��Ȃ��A�ČR��n���S�P���Ɠ��ČR�����������̐�������������ɐ�����҂��炠�����Ă����K�v������B���߂��Ă���̂́A���ē����ƌĂ��x�z�W�̉����Ɠ��Ĉ��ۏ��̔j���ł���B�����łȂ���A���A�������u����̐l�Ԃ͂䂷��̖��l�v�Ƃ������t���A����ɐ����鎄�������ؖ����Ă��܂����ƂɂȂ�B �@���A���̍��ʔ����ɂ���Ė��炩�ƂȂ������ČR�������̍����ɍ쓮����Εėꑮ�I�Ȑl���`�I���ʂ���̂��Ă������߂ɂ��A�ČR��n�P���Ɠ��ČR�������̉����ɂނ������l�Ȏ��H���A���Ȃ�ʍ��ʂ��Ă��鎄��������ɐ�����l�Ԃɂ���Ă����A���݂₩�ɓW�J����Ă����K�v������B���܋��߂��Ă���̂́A������R���e����ނ��A���\�L�̍���̂Ȃ����Ă��鎄�������A���̐l�X�Ƌ��ɐ������тĂ����q����ւ̖������̐M���ȊO�ł͂Ȃ��B�i���傤�E������1967�N�����ǎs���܂�B������w�����i����E���{���w�A���v�z��U�j�B�ߒ��Ɂu������v�B����^�C���X2011.03.22�j |
||