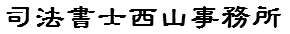業務案内
不動産登記
こんなとき・・・
などの場合に登記が必要となります。
1.相続が発生したとき
不動産の所有者が亡くなってしまった場合、その不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
特に亡くなってから何カ月以内に名義を変えなくてはいけないといった決まりはありませんが(相続税の申告は10カ月です)、そのままにしておくと、 相続人がさらに亡くなってしまったりして、関係者が思いのほか増えてしまい、遺産分割協議をするのが大変になってしまったりします。
相続による不動産の名義の変更の一般的な流れは次のようになります。
- 相続財産、遺言書、相続人の調査、確定
- 遺産分割協議・・誰がどの相続財産を相続するのか、相続人全員で話し合います。
- 上記協議を基に遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名し、実印を押印します。
- 協議により不動産を取得する相続人へ不動産の名義を変更するため、法務局に登記申請をします。
- 1,2週間で登記が完了し、相続人に新しく権利証(登記識別情報)が発行されます。
- 権利証等の書類を相続人にご返却し完了となります。
相続登記を申請するには、原則として亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(有効期限はありません。)、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書等の書類が必要となります。
当事務所では、戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成、また、オンライン申請により登録免許税の減税(最大4000円但し、平成24年3月31日まで)も受けられますのでぜひご利用ください。
こちらもご覧下さい。→相続登記Q&A、登記費用、相続登記必要書類
2.土地建物を購入した
土地や建物を購入したときは、登記簿の名義を売主から買主へ変更します。
通常、売買契約を締結し、その1カ月から2カ月後に売主、買主双方が集まり売買代金の決済(支払い)と登記申請をすることになります。
司法書士は、その場に立ち会い、売主、買主が持参した書類及び意思確認、本人確認等を行い、登記必要書類の確認と申請手続きをします。
登記についてご不明な点、費用についてはお気軽にお問合わせください。
こちらもご覧下さい。→所有権移転登記必要書類
3.建物を新築した
建物を新築したときは、自分の所有であることを公示するため所有権保存登記というものをします。
建物を新築した時は、主に次の2つの登記をします。
一つは、建物表題登記
もう一つは、所有権保存登記
表題登記というものは、土地家屋調査士が申請するもので、一番最初に登記簿を作る作業です。
これは、建物の所在や構造、床面積などを図面などで明らかにし、新築建物がどういう建物でどこに建っているものかを明らかにします。
表題登記が完了したら、司法書士が行う所有権保存登記となります。
所有権保存登記をすることよって、建物の権利証(登記識別情報)が出来上がります。
また、住宅ローンを組んでいる方は、所有権保存登記と一緒に建物に抵当権を設定することもあります。
4.住宅ローンを借り換えた
住宅ローンを借り換える場合、通常は次の2つの登記が必要となります。
一つ目は、抵当権抹消登記
二つ目は、抵当権設定登記
これは、そのままなのですが、従前借入をしていた住宅ローンを返済するので、その住宅ローンの抵当権を抹消し、新たに借入をする住宅ローンの抵当権を設定するものです。
通常は、従前の住宅ローンの返済と同時に新たな抵当権を設定するため、返済当日は結構移動等でバタバタしたりします。
借り換えの登記費用のお見積りも無料でしておりますので、ご不明な場合はお気軽にお問合わせください。
なお、住所が変更されていたりする場合は、住所変更登記も必要となります。
5.住宅ローンを完済した
通常マイホームを買った時には銀行、信用金庫等からお金を借り、住宅ローンを組まれていらっしゃると思います。
その際に銀行等は、貸し付けたお金の担保として、抵当権という権利を購入した不動産に対して設定し、その権利を登記しています。
この抵当権という権利は、住宅ローンが返済できなくなった場合に強制的に不動産を競売にかけ、その売却代金から貸し付けたお金を回収することができるという権利です。
この権利は、もちろん住宅ローンを完済すれば消滅するものですが、完済をしても、抵当権設定登記が自然に消えるわけではありません。
住宅ローンを完済すると、銀行等から、当時の抵当権設定契約書や、抵当権設定登記を抹消するための書類が渡されると思いますので、それらの書類を使い登記申請することにより、初めて登記されたものを抹消することができます。
この書類の中には有効期限があるものも含まれていますので、書類を受け取ったらなるべく早めに手続きをしましょう。
こちらもご覧下さい。→抵当権抹消登記必要書類、登記費用
6.登記簿に記録されている住所から移転した
登記簿に記録されている住所から引っ越し等で住所を移転した場合、その住所を新しい住所へ変更することが必要です。
と言いましても、通常は住所を移転したからといって、住民票の様に何日以内に変更しなければいけないという訳ではありません。
例えば、その不動産をご売却する、抵当権を設定する、抵当権を抹消する等の場合には変更が必要となります。
こちらもご覧下さい。→住所変更等登記必要書類、登記費用
7.不動産を贈与したい
不動産を贈与するときは、登記簿の名義を贈与された人の名義へ変更します。
ただし、注意点があります。
それは高額な贈与税がかかる場合がありますので、事前に税務署等で確認する必要があることです。(要件に該当すれば、非課税の特例などもあります)
参考→贈与税|タックスアンサー|国税庁
贈与税につきましては、司法書士は専門ではございませんが、分かる範囲で適切な窓口をご案内しております。
贈与証書等も一緒に作成しております。ご不明な点はお問合わせください。
こちらもご覧下さい。→所有権移転登記必要書類、登記費用