STEVE KUHN / STEVE SWALLOW
アコースティック・ピアノとエレキベースの組み合わせは色でいうと単色、そんな感じ
"TWO BY 2"
STEVE KUHN(p), STEVE SWALLOW(electric bass)
1995年3月 スタジオ録音 (OWL : 084 755 8)
STEVE KUHNの初リーダー・アルバムというと"THREE WEVES"らしいが、その時のメンバーがベースにSTEVE
SWALLOW、ドラムスにPETE LA ROCCAだった。だから、SWALLOWとの付き合いは1966以来ということになる。心の底まで知り尽くした盟友と言えるのだろう。
個人的にはSTEVE KUHNの名盤といえば、1989年録音の"OCEANS IN THE
SKY"(JAZZ批評 82.)を推薦したい。MIROSLAV VITOUS(b)とイタリアのベテラン・ドラマーALDO ROMANOの丁々発止のやり取りが素晴らしい。
一方、STEVE SWALLOWといえば、早くしてエレキ・ベースに転向したミュージシャンといえる。勿論、アコースティック・ベーシストとしても一流で良く歌うベース・ラインが印象的であった。その代表作は1967年録音のGARY
BURTONの"DUSTER"(JAZZ批評 74.)であろう。特にSWALLOWの書いた曲である"GENERAL MOJO'S WELL LAID PLAN"におけるアコースティック・ベースは良く歌っていたし、ギターにロックあがりのLARRY
COYELL、ドラムスにROY HAYNESを迎え当時としては新しい感覚のジャズを展開していた。その後、エレキ・ベースに逸早く転向したが、1994年にはJOHN
SCOFIELD & PAT METHENYの競作"SUMMERTIME"(JAZZ批評 7.)で共演している。普段はエレキ・ベースを毛嫌いする僕ではあるが、このアルバムのSCOFIELD作の"NO
MATTER WHAT"におけるSWALLOWのベースラインは逞しくも良く歌っていて大好きだ。
余談が過ぎたようだ、本題に移ろう。
①"GENTLE THOUGHTS" エレキ・ベースというよりはエレキ・ギターといった方がぴったりとする音色。エレキ・ベースといっても5弦ベースや6弦ベースもあるのでギターの音色がしても不思議はない。最近では7弦ベースというもあるらしい。
②"TWO BY TWO"
③"REMEMBER" エレキ・ベースというのはどうしても電気での増幅に頼るので指で弾くというピチカートのアッタク感とかビート感が薄くなってしまうのが惜しい。ましてや、アコースティック・ベースの一流ベーシストだっただけに勿体無いと思ってしまう。
④"WRONG TOGETHER" ベース・ソロの音色はギターのそれと変わらない。軽いボサノバ調。
⑤"EIDERDOWN" あたかもエレキ・ギターの如し。
⑥"LULLABY"
⑦"LADIES IN MERCEDES" これもボサノバ調。
⑧"DEEP TANGO" 今度はタンゴだそうだ。
⑨"POEM FOR #15" 詩の朗読で始まるが何となく辛気臭い。
⑩"MR CALYPSO KUHN" そして、カリプソ。
⑪"EMMANUEL" 最後に哀しいバラード。
アコースティック・ピアノとエレキベースの組み合わせは色でいうと単色、そんな感じ。僕にはそういう印象が強い。それに選曲も極めてオーソドックスで似たような曲調が多い。従って、全11曲、曲ごとの起伏も少なく変化に乏しいといえる。
やはりアコースティック・ベースとの組み合わせの方が色とりどりの色彩が楽しめる。KENNY
DREWとNIELS-HENNING ORSTED PEDERSEN "DUO LIVE IN CONCERT"(JAZZ批評 292.)ような丁々発止のインタープレイがあるわけでもなく、JAN LUNDGRENとGEORG
REIDEL "LOCKROP"(JAZZ批評 338.)、あるいは、TERJE GEWELTとCHRISTIAN JACOB "HOPE"(JAZZ批評 275.)のように聴くものの心を洗い沸き立たせてくれるわけでもない。
期待したほどのアルバムではなかったというのが素直な感想。 (2007.10.20)

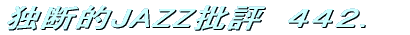


![]()