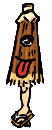 その第一弾1968年公開「妖怪百物語」は、日本古来の妖怪たちを特撮で再現。なかでも、ろくろ首やカラ傘のお化けの操演技術はなかなかのもの。のっぺらぼうは、役者の呼吸する方法に苦労したとか。本所の七不思議「おいてけ堀」の話なども出てきます。
その第一弾1968年公開「妖怪百物語」は、日本古来の妖怪たちを特撮で再現。なかでも、ろくろ首やカラ傘のお化けの操演技術はなかなかのもの。のっぺらぼうは、役者の呼吸する方法に苦労したとか。本所の七不思議「おいてけ堀」の話なども出てきます。「妖怪百物語」/「日本海大海戦」/「キングコング対ゴジラ」/「ガメラ対ギャオス」/「仮面の忍者赤影」/「怪奇大作戦」/「ウルトラQ」up
その1 「ゴジラ」シリーズといえば東宝映画、「ガメラ」シリーズは大映映画。その大映には「大魔神」シリーズもありますが、ガメラ・大魔神の影にかくれて大映の妖怪映画三部作というのがあります。「妖怪百物語」「妖怪大戦争」「東海道お化け道中」
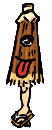 その第一弾1968年公開「妖怪百物語」は、日本古来の妖怪たちを特撮で再現。なかでも、ろくろ首やカラ傘のお化けの操演技術はなかなかのもの。のっぺらぼうは、役者の呼吸する方法に苦労したとか。本所の七不思議「おいてけ堀」の話なども出てきます。
その第一弾1968年公開「妖怪百物語」は、日本古来の妖怪たちを特撮で再現。なかでも、ろくろ首やカラ傘のお化けの操演技術はなかなかのもの。のっぺらぼうは、役者の呼吸する方法に苦労したとか。本所の七不思議「おいてけ堀」の話なども出てきます。
そして出演者がこれまた妖怪に負けずにいいんです!
レッツゴー三匹の正次の兄ルーキー新一(服の両端を引っ張りながら、「いやぁ〜ん、いやぁ〜ん」ってギャグ知ってます?)が、カラ傘のお化けとコンビを組んで笑わせてくれます。ほんとは怖い話なんだろうけど…??
さらに林家正蔵。百物語を語る師匠として出演。ちゃんと、かつらでチョンマゲだからまたいい!まだ声が震えていない頃で、じっくり味わえます。怪談話というのは話術だけではなく、口元・目つきなどと体全体で凄みを伝えるものだということがよくわかります。
「時を告げます鐘の音が、ボォ〜ムと…」という口元の閉め方や、「言い伝えというものはそれだけの謂われがあって昔から伝えられてきたもので、おろそかにはできません。どうかおまじないはなさってくださいまし。」と言った時のかっと見開いた目つきなど…。こっちは妖怪より怖いかも?
三作とも、大映DVDとして徳間ジャパンコミュニケーションズから出ています。日本の妖怪のリーダーと呼ばれる「油すまし」なんて名前は、この映画で有名になったんじゃないかなあ。
1967年公開の「日本のいちばん長い日」(監督:岡本喜八)にはじまる東宝の8.15シリーズというのがありました。翌年の「連合艦隊司令長官山本五十六」に続く第三弾として1969年公開の「日本海大海戦」をとりあげます。
この作品をとりあげるのは、これが、特撮の神様と言われた円谷英二が実質的に特撮を監督した最後の作品となったからです。そういう意味でも、これまでの特撮技術の頂点を極めた作品と言えると思います。
 東宝ご自慢の大プールをいっぱいに使った海戦シーンは圧巻!煙突からもくもくと黒煙をあげ一列縦隊で進む艦隊のまわりに水柱が上がる。随所にはさまれる本物の軍艦「三笠」(これは私の住む横須賀に記念艦として残っています:左写真)を使ったロケーション、実物大のセット・シーン、そして合成シーンが本編と特撮シーンを無理なく融合しています。
東宝ご自慢の大プールをいっぱいに使った海戦シーンは圧巻!煙突からもくもくと黒煙をあげ一列縦隊で進む艦隊のまわりに水柱が上がる。随所にはさまれる本物の軍艦「三笠」(これは私の住む横須賀に記念艦として残っています:左写真)を使ったロケーション、実物大のセット・シーン、そして合成シーンが本編と特撮シーンを無理なく融合しています。
この構成もさることながら、実は船の数が多すぎて、プールに余地がない。そこで、ポンプで水の流れる動きを作り、各ミニチュアの船首の下から石けん水を出して波頭の感じを出し、カメラ・ワークを加えて動きを表現したそうです。
出演も、主役の東郷元帥に三船敏郎以下オールスター・キャストで、明治天皇に歌舞伎界の大御所、先代の松本幸四郎。ロシアの諜報活動・革命工作をする明石大佐に仲代達矢、砲術長に佐藤允、山本権兵衛総理大臣に辰巳柳太郎、乃木大将に笠智衆、そして乃木大将に母親への送金を頼み戦死する一兵卒 役で黒沢年男、さらに広瀬少佐(船内に取り残された部下を捜しに行って戦死、それを称えて銅像が立ち、唄にもなった)に加山雄三という錚々[そうそう]たる顔ぶれ。
ストーリー的には歴史を歪曲する部分があると批判を受けたりもしたようですが (でも、この戦勝がアメリカとの戦争につながることを暗示しつつ、 東郷自身が勝つことの恐ろしさを知ったとナレーションを入れたラスト。東郷が妻に連れられ、息子が戦死した盲目の女性の店に立ち寄るという創作場面の台詞に込められた制作者の思いなど、いいところもあると思うんですが)、特撮の面からはアナログな最高峰だと思います。最近のCGをつかった特撮は、たしかにリアルな面もありますが、どうもなじめません。飛行機などを吊るピアノ線などが見えたって、それはそれ、ご愛嬌で人間を感じられて、いいもんだと思います。DVDが東宝株式会社から発売されました。ミニチュア艦船の一大パノラマ絵巻とも称される迫力海戦模様をご覧ください。パノラマと言えば「連合艦隊司令長官山本五十六」のラストシーンも名場面です。「昭和18年4月18日、長官山本はブーゲンビル島上空において戦死した。真珠湾攻撃より1年4か月。日米開戦に極力反対した山本五十六は、こと志と違い、皮肉にも彼自身、戦争遂行の重大責任を担い、自らの死によってその節を全うしたのである」というナレーションが続き、エンドロールとともに流れるテーマ曲は気に入っています。
円谷英二は、戦争中の昭和17年に「ハワイ・マレー沖海戦」という映画を撮っていますが、やはり大プールに真珠湾の模型をつくり、完成した作品を戦後アメリカ軍が見て、実写だと勘違いしたという話も残っているそうです。ディズニーのCGをがんがん使った新作「パール・ハーバー」より絶対いいと思うけどな…
第一作は、昭和29年(1954年)の公開。この年、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験の死の灰を日本のマグロ漁船第五福竜丸が浴び死者が出た。これを受けて、広島・長崎に続き戦後も核の被害にあった日本から反核のメッセージを、水爆実験でよみがえった怪獣が東京を襲い、東京に核爆弾が落ちたのと同じ惨状を比喩的に描いた作品。 台詞をはじめ端々に戦争体験が投影され、日本人の魂を語ったものと言ってもいいでしょう。また、科学万能批判の視点も見逃せません。
その後「ゴジラの逆襲」・・・とシリーズ化されていきますが、特にその中の1962年(昭和37年)公開「キングコング対ゴジラ」をあげます。
だって、おもしろいんだもん。脚本が、役者が!
東宝創立30周年を記念して、ゴジラものでは初のカラー作品、日米の両雄を戦わせたわけですが、さあ勝敗は?
 最後の決戦の舞台は熱海城をはさんで…えっ、秘宝館じゃないよ!
最後の決戦の舞台は熱海城をはさんで…えっ、秘宝館じゃないよ!
それにしても、この話、ゴジラ、キングコングそれぞれにスポンサーがついてるんです。ゴジラにはセントラル製薬、キングコングにはパシッフィック製薬。このパシフック製薬の多湖宣伝部長を演じる有島一郎が実におかしい。これにふりまわされるテレビ会社の社員に高島忠夫と藤木悠との弥次喜多コンビ。関沢新一の脚本がふるっているうえに、これらの役者陣が生き生きと演じています。
笑えるゴジラ映画です。映画全盛期の一流の娯楽大作!東宝から発売されたDVDには映像特典のほか、当時本編の助監督だった梶田興治と出演者の藤木悠のオーディオコメンタリー付。ゴジラ見るなら、この作品から!!
湯浅憲明監督いわく「円谷という巨大な砦に竹槍で挑戦」して完成した1965年(昭和40年)公開「大怪獣ガメラ」。科学的なリアリティーに足をとられず自由な発想で「ウチはウチ、と開き直って作った」ことにより、みごとにキャラクターを確立した作品となりました(なにしろカメが口だけでなく手足から火を吹いて飛ぶんですから)。最初から子供の味方という設定を前面に押し出し、対戦相手の怪獣もユニークな存在となりました。その代表格が新作ガメラにも引き継がれたギャオスでしょうか。
1967年(昭和42年)公開「大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス」 
ギャオスは吸血コウモリがモデルといった怪獣かな。血液が好物で人を食う、そして武器は口から出す超音波メス。なんでも背骨が首のところで二股に分かれ音叉のような働きをして超音波を発生するしくみになっているとか。苦手なものは太陽光線。紫外線にあたると細胞が破壊され縮んでしまうので夜行性とか。こうした言葉の羅列が子供心に科学的興味をかきたててくれたような気がしました。
ここで、ちょっと余談ですが、ゴジラもガメラも最初に襲う町は東京、次作の対戦場所は大阪、それも大阪城を舞台に。そして次々作 (ゴジラ映画は間に海外ゲストのキングコングとの対戦を挟み、東宝オリジナルキャラのモスラとの対戦のとき)では名古屋を襲うという、当然のように破壊される目玉は名古屋城と 、お決まりのパターンのようです。三大都市の昔の面影を見て楽しむというのも一興です。ギャオス襲来におののく名古屋市民の避難場所が中日球場だったり…。 平成版に続きようやく昭和のガメラ作品のDVDも発売。
昭和42年(1967年)に東映テレビ特撮史上、エポックメイキングな作品が登場。初の巨大ロボットもの「ジャイアントロボ」、初のスペースオペラともいうべき「キャプテンウルトラ」そして、初の特撮時代劇「仮面の忍者 赤影」です。
 「赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光るすずしい目 仮面の忍者だ赤影だ 手裏剣しゅしゅしゅ(orしゅっしゅ) しゅっ しゅ しゅ 赤影は行く」という名曲「忍者マーチ」
(→音楽館へ)とともに「だいじょうぶ!」が決め台詞の青影、大凧に乗って天空を舞う白影を従えて…四部からなるロングバージョンとなりましたが、第1部のオープニング口上は
「赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光るすずしい目 仮面の忍者だ赤影だ 手裏剣しゅしゅしゅ(orしゅっしゅ) しゅっ しゅ しゅ 赤影は行く」という名曲「忍者マーチ」
(→音楽館へ)とともに「だいじょうぶ!」が決め台詞の青影、大凧に乗って天空を舞う白影を従えて…四部からなるロングバージョンとなりましたが、第1部のオープニング口上は
「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教がはやっていた。それを信じない者は、恐ろしい祟りに見舞われるという。その正体は何か?藤吉郎は金目教の秘密を探るため、飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は……『赤影参上!』」
と、まあかっこよかったぁ〜。 各部の全話を網羅したDVDも発売されましたね。
奇想天外な忍法、怪物、はては化学兵器まで登場するという大胆な時代劇特撮アクションでありました。新作映画「RED SHADOW」とはまた違うシリアスなつくりでもあり、忘れられない一作だよね。
 「闇を引き裂く怪しい悲鳴…誰だ、誰だ、誰だ!悪魔が今夜も騒ぐのか…」というテーマ曲も懐かしい、まずは、「怪奇大作戦」からいきましょうか。
「闇を引き裂く怪しい悲鳴…誰だ、誰だ、誰だ!悪魔が今夜も騒ぐのか…」というテーマ曲も懐かしい、まずは、「怪奇大作戦」からいきましょうか。
「これぞ元祖=X-FILE
だ!」というキャッチコピーがあるんですが、怪奇現象や科学犯罪に立ち向かうS.R.Iという組織のメンバーの活躍を描くSFミステリーとでも申しましょうか。SRIとは科学捜査研究所の略称で、警視庁の嘱託を受ける半官半民の研究所。所長は元警視庁鑑識課課長で、FBIに学び、日本における科学捜査の必要性を痛感、「いかに複雑で怪奇に満ちた犯罪であろうとも、その優れた科学力と、鋭い推理を駆使して謎を解き、犯人を暴き出す」(第1話ナレーション)というもの。怪獣ブームが下火となり、大人向けの特撮ドラマを模索した中から生まれたようです。
放映は昭和43年(1968年)から44年にかけてですが、今見ても、その発想の豊かさなどは見劣りがしないはずです。科学犯罪というものをモチーフにしたことにより、当時の若きシナリオライターたちがいろんな角度から文明批評をぶつけることができたことにもよるようですが、それ以上に、その科学犯罪や怪奇現象に人の怨念とか執着心とかを絡めて、いわば人間の暗部にスポットを当てた作品が多くなっていることが古さを感じさせない要因のようです。これはTBSからやってきた橋本洋二のドラマツルギーによるものらしいのですが…つまり人間ドラマに重きをおいているんですね。
DVD化に向け各方面へ権利の確認も済んで、ようやっと発売へ。
http://www.dus.jp/digital_ultra_series/kaiki/kaiki.html
この中に、横須賀を舞台にした話があります。第15話「24年目の復讐」
深夜の横須賀港。アメリカ兵が突如、海から現れた黒い人間に海中に引きずり込まれて溺死する事件が連続しておこる。S.R.Iは水棲人間の可能性を探る。そしてかつて日本軍の施設があった猿島へ。そこには沈没した潜水艦の艦内で奇跡的に生存していた元日本兵が…
戦後も基地の町となった横須賀を舞台に、沖縄出身のライター上原正三と横須賀出身の監督鈴木俊継とによる戦争被災を綴る一頁にも…
さてと「マイティジャック」も捨てがたいし、「快獣ブースカ」ってのもありますが、やっぱりウルトラシリーズでしょうか。
あえてウルトラシリーズと呼ぶのは、実は子供心にもウルトラマンのような巨大ヒーローものは好きではなかったんです。人間がヒーローのような救世主に頼るのではなく人智を尽くして怪獣と戦うというか、そういうほうが好きだったみたいですね。ということで、原点にあたる「ウルトラQ」から。
放映は昭和41年(1966年)。「これから30分、あなたの目はあなたの身体を離れて、この不思議な時間の中に入っていくのです・・・」という石坂浩二のナレーションはあまりに有名(知る人ぞ知る)!
ゴジラをはじめとした怪獣は映画館に行かなければ見ることができなかった、そんな自分ですからテレビで毎週、怪獣ものが見られるという感激もあったでしょうが、恐怖を感じた作品もありました。うちの妹なぞは、いまだに 精神と肉体が遊離してしまった少女が事件を起こす「悪魔ッ子」は怖かったと言います。日本作SFテレビドラマの原点と言ってもいいでしょうか。怪獣が出ない回もあるんですが、そういったものは非常にメーッセージをいま見ても感じます。怪獣はもちろん忘れがたいキャラクターが目白押し。私はガラモンが一押しですね。よく記憶違いのためか、ガラモンとピグモンを混同している人がいるんですが、まあ同じ着ぐるみなので仕方ありませんけど、ピグモンはウルトラマンで等身大キャラとして登場したやつですから。いずれにせよ両作品で2作品にわたって復活登場を遂げています(ウルトラQ「ガラダマ」「ガラモンの逆襲」、ウルトラマン「怪獣無法地帯」「小さな英雄」)から人気キャラには違いないでしょう。語りだすと尽きないんですが、ぼちぼちと・・・
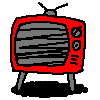 パナソニックからDVDも出てますから、それぞれ30分〜アンバランスゾーンを体験してみてください。もちろんモノクロ作品ですよ。
パナソニックからDVDも出てますから、それぞれ30分〜アンバランスゾーンを体験してみてください。もちろんモノクロ作品ですよ。