嘆棫岯偺攚崪亅楨偲惂屼宯偺媄弍巎
| 悽奅偱嵟傕愺偄働乕儁幃姫忋婡 |
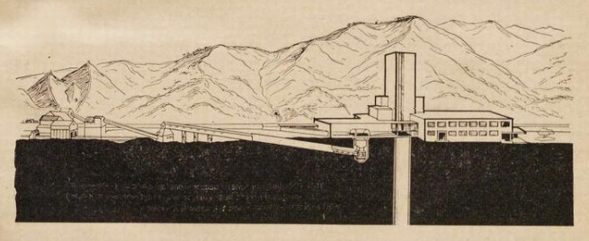


 儅僂僗on丂塇杫扽峼塣斃棫岯
儅僂僗on丂塇杫扽峼塣斃棫岯
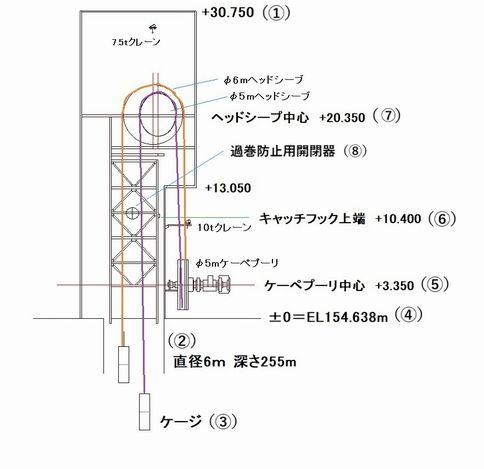
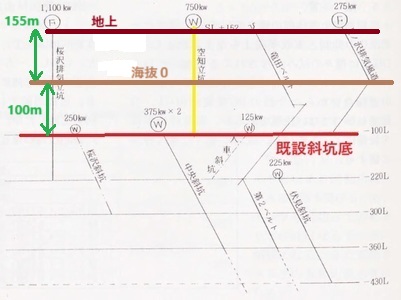
 僉儍僢僠僼僢僋
僉儍僢僠僼僢僋 夁姫杊巭梡奐暵婍
夁姫杊巭梡奐暵婍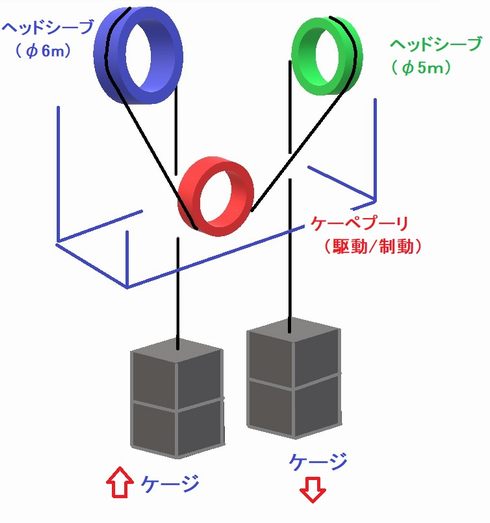 妸幵偺攝抲
妸幵偺攝抲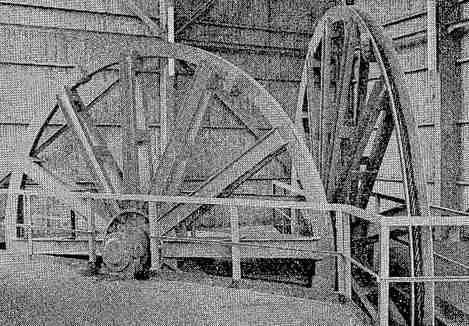 僿僢僪僔乕僽
僿僢僪僔乕僽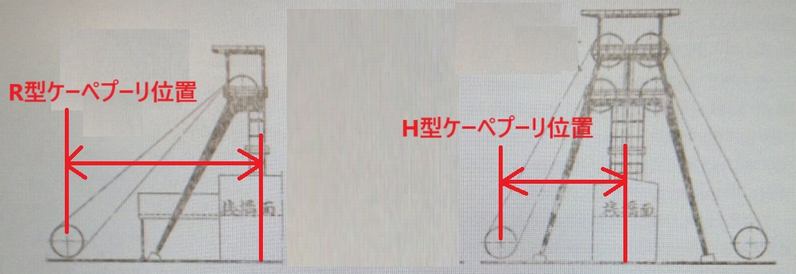 働乕儁僾乕儕/岯岥嫍棧
働乕儁僾乕儕/岯岥嫍棧 庡惂摦婡
庡惂摦婡
 暃惂摦婡
暃惂摦婡
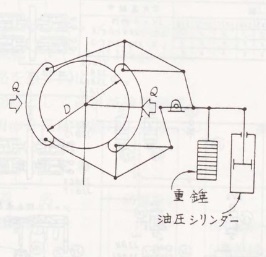 惂摦憰抲
惂摦憰抲| -100mL傑偱偺楬 |




| 怴媄弍亀僩儔儀儔亁 |

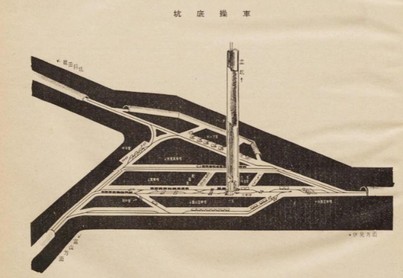
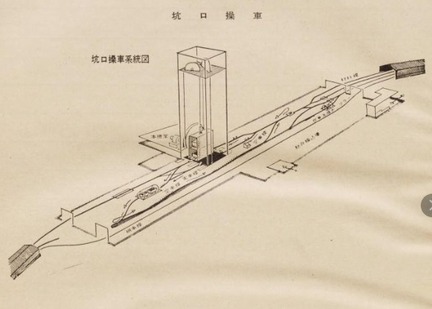
| 塣斃暿 | 姫忋嫍棧 | 嵟戝懍搙 |
|---|---|---|
| 扽峼姫 | 300m埲壓 | 10m/s(36km/h) |
| 丂丂丂 | 300乣400m | 10乣15m/s(36乣54km/h) |
| 丂丂丂 | 400乣600m | 15乣20m/s(54乣72km/h) |
| 丂丂 | 600m埲忋 | 20乣25m/s(72乣90km/h) |
| 恖堳姫 | 200乣300m | 10.5m/s(37.8km/h) |
| 丂丂丂 | 300乣400m | 11.5m/s(41.4km/h) |
| 丂丂丂 | 400m埲忋 | 12.0m/s(43.2km/h) |

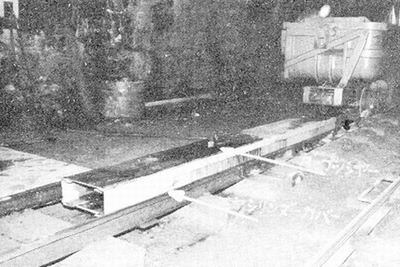
| 揹婡偺偼側偟 |
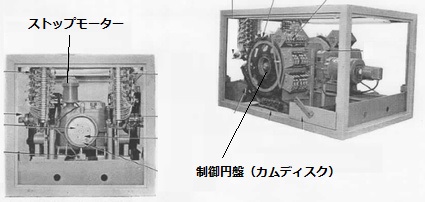 塣揮挷惍婍
塣揮挷惍婍
| 丂丂 | 捈棳 | 岎棳 |
|---|---|---|
| 婰崋 | DC乮DC=direct current乯 | AC乮AC=alternating current乯 |
| 亇 | 僾儔僗儅僀僫僗桳傝 | 僾儔僗儅僀僫僗柍偟 |
| 揹棳/揹埑 | 棳傟傞曽岦偑堦掕 | 棳傟傞曽岦偑廃婜揑乮50乣60夞/昩乯曄壔 |
| 巊梡椺 | 姡揹抮丒帺摦幵 | 壠掚丒岺応 |
| 夞楬 | 恑傒傗抶傟偼枹敪惗 | 媡曽岦揹埑偵傛傝抶傟敪惗 |
| 岠棪 | 偡傋偰偺揹婥偑晧壸捠夁偵傛傝柍岠揹椡枹敪惗 | 岦偒偺曄壔偛偲偵晧壸偲揹尮娫偺柍岠揹椡敪惗 |
| 拁揹 | 僶僢僥儕/僐儞僨儞僒偵拁揹壜擻 | 拁揹晄壜 |
| 幷抐 | 忢帪揹埑偺偨傔幷抐帪偵壩壴傗姶揹偺壜擻惈 | 廃婜揑偵揹埑僛儘偲側傞偺偱捠揹拞偺幷抐梕堈 |
| 憲揹 | 掞峈偑戝偒偔敪擬丄挿嫍棧偵偼晄岦偒 | 崅埑憲揹帪偺懝幐彫丄墦曽傊憲揹壜 |
| 曄埑 | 僐儞僶乕僞偵傛傝壜擻24V仺12V仺5V | 僩儔儞僗偵傛傝1000V仺200V側偳梕堈 |
| 儌乕僞乕偲偺憡惈乮夁嫀乯 | 帴懇偱壛尭偟偨揹埑偱夞揮悢惂屼壜 | 堦掕懍搙偱慇嵶側惂屼晄壜 |
| 儌乕僞乕偲偺憡惈乮尰戙乯 | 壜曄掞峈婍乮儃儕儏乕儉乯偱夞揮惂屼 | 廃攇悢傪帺桼偵嶌傝弌偣傞僀儞僶乕僞乕傪梡偄偰夞揮惂屼 |
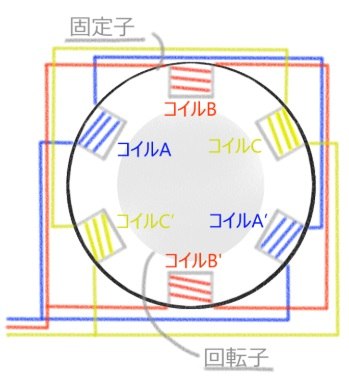

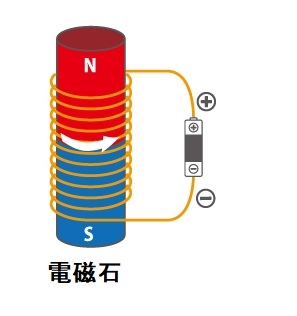
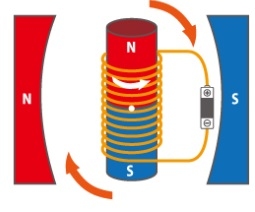
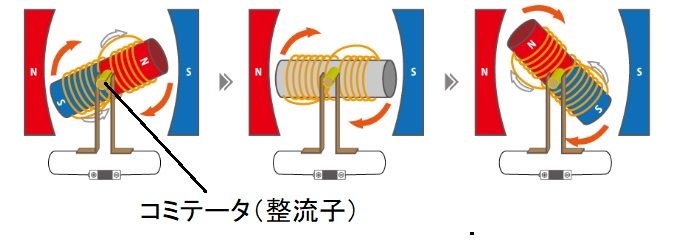

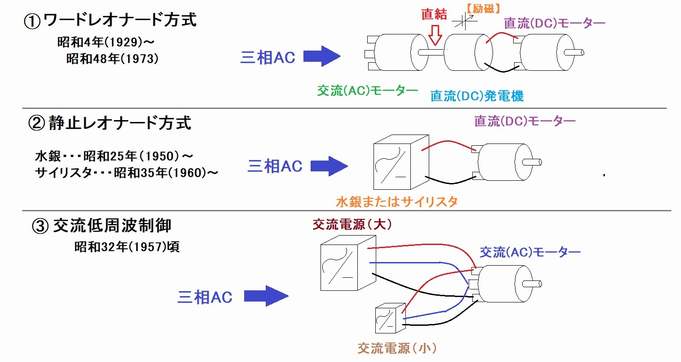
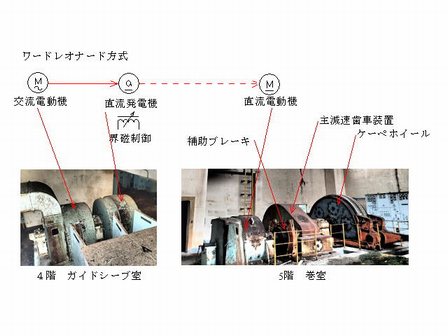

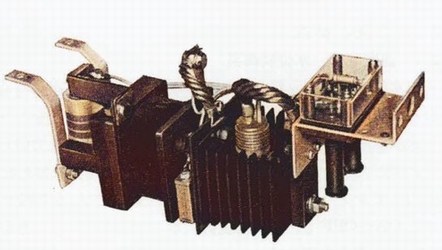

| 嫤嬈丄晉巑揹婡乮姅乯偲僨儅乕僌幮 |
 晉巑揹婡
晉巑揹婡
 僨儅乕僌幮
僨儅乕僌幮
| 惓寧4擔偺揮恎 |
 岯奜廤拞娔帇幒
岯奜廤拞娔帇幒


 棫岯楨儊僀儞傊
棫岯楨儊僀儞傊
.jpg) 嬻抦棫岯傊栠傞
嬻抦棫岯傊栠傞