①から⑯まで巡って①へ戻るコース ; 約 4.8km

- 1.小前田屋台
 毎年10月には、小前田の鎮守である諏訪神社の祭礼行事として、秩父往還を各町内の祭り屋台が曳き回されていたが、昭和32年(1957年)交通量の増加に伴い中止となった。 140号線のバイパス道路の完成により平成10年(1998年)再開された。
毎年10月には、小前田の鎮守である諏訪神社の祭礼行事として、秩父往還を各町内の祭り屋台が曳き回されていたが、昭和32年(1957年)交通量の増加に伴い中止となった。 140号線のバイパス道路の完成により平成10年(1998年)再開された。
祭りは10月の第一週の土・日曜日に開催される。
屋台は本町・仲町・上町の3台があり明治の初め頃建造された。
屋台は芸座、歌舞伎舞台が作られるような仕掛けになっており、手の込んだ彫刻で飾られている。
上町の屋台は、皇居の車寄せを手掛けた彫刻師、弥勒寺音八(みろくじおとはち)の作。
屋台は分解して各町内の保存庫に保管していたが、現在は組んだ状態で道の駅「アルエット」に収蔵され何時でも見られる様になっている。- 2.橋屋遺跡
 この地域は、古来より人々の生活の痕跡が認められてる。
この地域は、古来より人々の生活の痕跡が認められてる。
縄文時代前期から晩期にかけての集落跡が荒川左岸沿いの河岸段丘上に形成されるようになった。
橋屋遺跡はその中の一つで、縄文時代の最後を飾る晩期の集落跡で、土器、石器、土製品、石製品などが出土している。
荒川左岸の崖面の下方は湧水があり、生活し易い環境にあったのではないだろうか。- 3.鎌倉街道
 中世、鎌倉幕府が開かれると、各地から鎌倉に連絡する道として「鎌倉術道」が整備された。
中世、鎌倉幕府が開かれると、各地から鎌倉に連絡する道として「鎌倉術道」が整備された。
荒川左岸沿いの崖面に沿って鎌倉街道上道が通っていた。
此処から北の方に曲がって、深谷市と寄居町の境辺り通って児玉を経由して上州に向かう道である。
他に、小前田宿の一番西縁の部分、諏訪神社へ向かう道筋も鎌倉街道とされている。
なお、文永(ぶんえい)8年(1171年)9月、日蓮上人が幕府から佐渡へ配流された折にこの街道を通行したという伝承もある。
時は移って徳川家康が江戸に幕府を開設するや、主要交通路も中仙道・奥州街道・日光街道など江戸を中心とすることになって、鎌倉街道は自然にさびれていった。 しかし、一部は中仙道の脇往還に属した所もあった。
「深谷の史跡めぐり」の中の鎌倉街道
*5.中瀬の史跡めぐり-1.鎌倉街道跡の碑
*10.針ヶ谷・櫛挽・本郷の史跡めぐり-3.鎌倉街道
- 4.お茶々の井戸
 荒川左岸沿いの崖面に沿って鎌倉街道上道が通っていた。 此処から北の方に曲がって、児玉を経由して上州に向かう道である。
荒川左岸沿いの崖面に沿って鎌倉街道上道が通っていた。 此処から北の方に曲がって、児玉を経由して上州に向かう道である。
この街道の往来がさかんであった頃、ここに茶店があった。
この茶店に「茶々」と称する美しい娘が居て、客あしらいが良かったため街道筋の話題となり店はおおいに繁昌したという。
この井戸は水深はあまりないが、どんな日照りの時でも固渇したことがないと言われた。
この井戸を汲み干すと雨を招くという伝承が信じられ、旱魃に苦しむ年には、雨乞いのために村人総出で水を汲み出したという。
昭和30年(1955年)、寄居に玉淀ダムがに完成し水位は下がったが、その前は現在の水位よりも高く、名前の通り荒ぶる川だった。
荒川には舟に水車を付けて粉をひく舟車が多数有ったが、昭和24年(1949年)のカスリン台風の時に流されてしまい、それを契機に舟車は廃れていった。- 5.小前田古墳群
 古墳時代になると、荒川沿いの段丘上に「小前田古墳群」や「黒田古墳群」が造られるようになる。
古墳時代になると、荒川沿いの段丘上に「小前田古墳群」や「黒田古墳群」が造られるようになる。
6世紀前半から7世紀前半まで、およそ1世紀に亘って作られた小前田古墳群は、寄居町桜沢にかけて100基余の古墳が存在したと推定されている。
しかし、近代の食料増産のため開墾され原型を留めていない。
河原石積みの横穴式石室からは勾玉、管玉、切子玉、鉄刀、鉄製轡などが出土している。
円墳だけでなく全長30m、後円部径20mの帆立貝式の前方後円墳も発見されている。- 6.櫛挽用水
 昭和34年(1959年)から41年にかけて行われた土地改良事業で櫛挽用水の整備が行われた。
昭和34年(1959年)から41年にかけて行われた土地改良事業で櫛挽用水の整備が行われた。
水源を荒川に求め、玉淀ダムやトンネル水路などの幹線用水路が整備され、水利に恵まれなかった荒川左岸櫛挽台地を潤した。
- 7.諏訪神社
 文中(ぶんちゅう)年間(1469~87年)に花園城主・藤田氏行が信濃国諏訪社から分霊し、社殿の整備をした。 しかし藤田氏の離散により社殿は荒廃してしまった。
文中(ぶんちゅう)年間(1469~87年)に花園城主・藤田氏行が信濃国諏訪社から分霊し、社殿の整備をした。 しかし藤田氏の離散により社殿は荒廃してしまった。
永禄(えいろく)5年(1562年)小前田羽雌箭(はしや)の住人・長谷部吉永が現在地に境内を移したと伝わる。
明治7年(1874年)小前田村の村社となった。
本殿は地元小前田の棟梁藤井友八により安政(あんせい)5年(1858年)に竣工した流し造りである。
氏子の間では「お諏訪様は女の神様だ」と言われ、安産のご加護があるとして古くから信仰されている。
諏訪神社の秋の例大祭は、現在では十月第二土・日曜日に行なわれている。秋の例大祭には御輿の渡御がある。 いつ頃から始まったか記録にはない。
渡御の日程は、夕方御輿が神社を出て秩父往還(国道140号)を東に下り、下宿で折り返し仲宿のお仮屋で一泊し翌日神社に戻る。
この渡御も、国道の交通量の増加により昭和39年(1964年)に取り止めとなった。しかし、バイパスの開通により昭和56年(1981年)に復活した。
御輿の担ぎ手は、黒帽子に白鉢巻き、着物は白鳥、白の地下足袋である。
行列は、宮司、太鼓、諏訪神社の高張り提灯、総代表、議員、各区区長、御神輿、各区高張り、金棒、各区総代、各地区副区長、一般市民の順で進行する。- 8.秩父鉄道小前田駅
 明治34年(1901年)上武鉄道株式会社が熊谷-寄居間を開業した。
明治34年(1901年)上武鉄道株式会社が熊谷-寄居間を開業した。
深谷市内では、小前田駅と武川駅の2つの駅が開通と同時に開業した。
その後、大正5年(1916年)上武鉄道株式会社は秩父鉄道株式会社に改称。
小前田駅から熊谷に向かって600m程の所に、線路が排水路を跨ぐレンガ造りの橋台がある、この橋台のレンガは深谷市上敷免(じょうしきめん) にあった日本煉瓦製造で造られたもの。
(開業当時のレンガとすると、同じ深谷産のレンガを使った東京駅舎(1914年竣工)よりも古い事になる。)- 9.小前田宿
 江戸時代になると交通量や物資流通量が増加するに伴い花園地区は、交通の要衝としての地位を得ていった。
江戸時代になると交通量や物資流通量が増加するに伴い花園地区は、交通の要衝としての地位を得ていった。
小前田宿は以前からの鎌倉街道上道の他に、熊谷から秩父・甲州を結ぶ秩父往還と中山道の脇往還としての機能を持つ川越―八幡山道が交わる地点に当る。
秩父往還は、熊谷市石原の「秩父道しるべ」を起点に、秩父市大滝に至る全長32里の道。
起点より三里半にあたる小前田村に問屋場がおかれた。
これは公用旅行者および公用物資運搬のために、昼夜の別なく人馬を常備することを義務づけられていた。 常備の人馬は、日に人足5人、馬2頭と定められていた。- 10.武州一揆
 慶応2年(1866年)6月、困窮の極に達した秩父郡名栗村の農民が蜂起した武州一揆は、米価引下げ、高利引下げを旗じるしに、武蔵と上野の一部を席巻した。
慶応2年(1866年)6月、困窮の極に達した秩父郡名栗村の農民が蜂起した武州一揆は、米価引下げ、高利引下げを旗じるしに、武蔵と上野の一部を席巻した。
小前田村へ来襲した一隊は、名主佐次右衛門宅で米百俵、田中茂左衛門宅では三百俵・金百両の施しを受けて立去り、熊谷方向へ向かった。
また、別の隊百人余りは夜五ツ時(夜8時頃)頃小前田村に達した、百姓佐五郎は米五拾俵・金子五拾両差出しことなきを得た。
小前田村役人は関東御取締出役を案内して、大谷村で追いつき、四十数名を召取った。
幕府は川越・忍・館林・高崎・岡部各藩に一揆の鎮圧を命じた。 岡部藩第13代藩主安部信発(のぶおき)は本庄宿に集結した一揆の鎮圧にあたった。- 11.小前田氏館跡
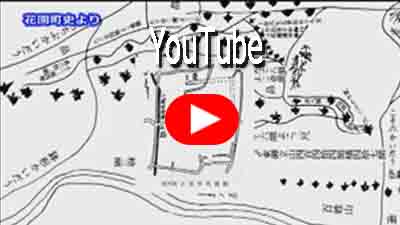 この辺一帯が小前田野三郎信国の館跡。 現在も「陣屋」の字名が残っている。
この辺一帯が小前田野三郎信国の館跡。 現在も「陣屋」の字名が残っている。
町田家に寛文(かんぶん)4年(1664年)の小前田村の絵図が残っている、その絵図によると周囲を土塁で囲まれた屋敷の跡が描かれている。 現在は土地改良事業で、その痕跡は残っていない。
戦国期、武蔵七党と呼ばれる各武士団が、それぞれの地域で支配を強めていった。
この辺り一帯に勢力を持っていたのが、猪俣党の中の藤田氏一族。
この藤田氏の一門藤田信国は、小前田に館を設け小前田野三郎と称した。
時は下り天文(てんぶん、てんもん)年間(1532〜1555年)、その当時の小前田氏は藤田康邦に従っていて、当初は北条氏と戦ったが、天文15年(1546年)の川越夜戦後には、鉢形城主となった北条氏邦に仕え、鉢形城小前田衆という小武士団に組み込まれていた。
天正(てんしょう)18年(1590年)に北条氏に属していた各城は豊臣方の攻撃に遭う。
鉢形城もその対象で、小前田氏は鉢形城に入城し西丸にあって奥方および若君光福丸の守護に当った。
しかし、戦力差は覆すことができず、主君氏邦の奥方である大福御前を護りながら樋口の天神山城を目指していたが、途中山賊と遭遇し、交戦の末討死したという。
その後の小前田氏の動向は資料に残っておらず、行方が分かっていない。- 12-1.町田家(1)
 町田土佐守康忠は、1500貫を領知して鉢形城外の寄居町小園に居住していたとされる、小前田に移住したのは鉢形落城後のことと伝えられている。
町田土佐守康忠は、1500貫を領知して鉢形城外の寄居町小園に居住していたとされる、小前田に移住したのは鉢形落城後のことと伝えられている。
天正(てんしょう)18年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めで、北国勢の前田利家、上杉景勝ら五万の軍勢が鉢形城に迫ってきた。
鉢形城主北条氏邦が同年4月2日、信頼している町田康忠の長子土佐守秀房に籠城に対しての奮戦を讃え、この時わずか六歳の光福丸について将来を託した文書(町田家文書)が残っている。
書状読み下し;籠城に相働き候こと、存分たるべし、殊に以て光福丸の儀、先日大殿、たって仰せ渡しの通り、忠節を謁べく者也、よって件の如し、 4月2日 氏邦 町田土佐守殿
大意;籠城に際して、必死の奮戦、抽んでて心に痛み入る。 殊に光福丸の事、先日、父である私からも特にお頼みいたしたように、今後も、忠節を尽くしてもらいたい。- 12-2.町田家(2)
 町田秀房は鉢形城落城の2ケ月前の4月初めに鉢形城を脱出。
町田秀房は鉢形城落城の2ケ月前の4月初めに鉢形城を脱出。
4月15日、前田利家に助命を懇願、利家はこれを許し相応の地に蟄居し養育するよう命じた。
土佐守と一族は光福丸の養育地として小前田を選びここに居住、養育につとめた。しかし、病弱な光福丸は落城9年目の慶長4年(1599年)7月15日、13歳の若さで病死した。
遺骸は、小前田原中の空円房という小堂の本尊下の地中に葬ったという。光福丸の墓石がないのは、このためという伝承がある。
鉢形城主北条氏邦は落城後、前田家お預けとなり、町田康忠・次男秀延ら主従9人で現在の石川県七尾市で五百石の禄高で召し抱えられた。
慶長2年(1597年)8月8日、北条氏邦は五十七歳で没した。
町田康忠等七人の家臣は、氏邦の遺骨を守って26日鉢形に戻り、28日葬儀を営んだ。 ついで、9月7日町田康忠は氏邦に殉じた。
その後、町田土佐守秀房とその子九郎左衛門長延は、光福丸と町田康忠入道長膳の菩提のため、慶長5年(1600年)一寺を建立、光福山医王院長善寺と称した。- 13.花園村道路元標(花園村誕生)
 都市と都市との間の距離は、基本的には市町村役場からの距離を示す、そのための花園村道路元標が大正7年(1918年)ここに設置された。当時此処に花園村役場が置かれていた。
都市と都市との間の距離は、基本的には市町村役場からの距離を示す、そのための花園村道路元標が大正7年(1918年)ここに設置された。当時此処に花園村役場が置かれていた。
明治17年(1884年)新政府は行政の効率化のため村の統廃合を計画。
この地区は用土村・武蔵野村・小前田村の三ヶ村を武蔵野村連合として合併し一つの村へ、
荒川村・黒田村・永田村・北根村・田中村の五ヶ村を黒田村連合として合併してもう一つの村へと、統廃合を計画した。
しかし各村の思惑により統合は進展しなかった。
武蔵野村連合では新村名に反発した武蔵野村と小前田村が離脱し前武村設立の動きを見せた。
一方の黒田村連合では荒川村を除外する動きが生まれ、三田村設立の動きを見せた。
そんな中、隣接する折之口(おりのくち)村連合では長在家(ながざいけ)村・菅沼村・瀬山村・明戸村の四ヶ村が連合を脱退して新村樹立の動きを見せ、人見村連合に所属していた上原(かみはら)村と黒田村連合の田中村に合流を勧誘。
黒田村連合の騒動と三田村設立が実現出来なくなった事で、田中村はこのグループに合流した。
残された黒田村・永田村・北根村は、武蔵野村と小前田村に呼びかけ五ヶ村合併案を提示するなど紆余曲折を経て、
武蔵野村・小前田村・荒川村・黒田村・永田村・北根村の六ヶ村合併が決定したが、ここでも各村の思惑により村名がなかなか決定されなかった。
タイムリミットが迫る中、明治21年(1888年)12月27日に人見村連合区長の仲裁を受け、この地が古来より藤田氏の領地であったことにちなみ、その居城であった「花園城」の名をとって「花園村」とすることに決し、明治22年(1889年)の町村制の施行により「花園村」が誕生した。
最初の村役場は観音堂に設けられ、明治23年(1890年)観音堂前の共有地を利用して平屋建の庁舎を新築した。
その後明治45年(1912年)から大正年間に掛けて町田家を借りて役場にした。 その時に花園村道路元標がここに設置された。
大正15年(1926年)小前田の駅前通りに役場が完成し、昭和53年(1978年)まで役場があった。
その後現在の総合支所に移転した。
花園町は明治22年から100年以上続いたが、平成18年(2006年)1月深谷市、岡部町、川本町と合併し深谷市となった。- 14.長善寺
 町田土佐守秀房とその子九郎左衛門長延が主君鉢形城主北条氏邦の子光福丸、父町田康忠入道長膳の菩提のため、慶長5年(1600年)一寺を建立、光福山医王院長善寺と称したと云われている。
町田土佐守秀房とその子九郎左衛門長延が主君鉢形城主北条氏邦の子光福丸、父町田康忠入道長膳の菩提のため、慶長5年(1600年)一寺を建立、光福山医王院長善寺と称したと云われている。
しかし、昭和36年(1961年)寺の屋根を藁ぶきより瓦ぶきにする工事の際に発見された棟札によると、寺は寛保(かんぽう、かんぽ)3年(1743年)4月に建立されたとあり、時期がずいぶん異なる。
また、棟札には光福丸の菩提を弔った寺とする記述は無かった。
門前の板碑は長興善寺のもので創建の趣旨・年代・長興善寺とのかかわり等について不明な点が多い。- 15.長善寺の石仏群
 門前に庚申灯、巡礼供養碑などの石碑群がある。
門前に庚申灯、巡礼供養碑などの石碑群がある。
これはただの碑ではなく、右左と書いてある、本来ここに在った物ではなく小前田の中の違う場所にあった物がお寺の方に集まってきた。
街道筋に道しるべとして使われていたもの、江戸期中期頃から大山参りが盛んになった、 右大山・小川・川越、下に秩父と読める。
赤く塗られた物があるが、願掛けをしてそれが叶うとお礼参りをして赤く塗った。
左/くまがや、右/小川・川ごえ・ちゝぶ。
面が北に向いて立っていた、立っていた場所は左、熊谷、宿の中のどこかに立っていた。- 16.長善寺の馬頭尊
 江戸時代に小前田宿では、宿の両端に馬頭尊が建立され、それが上の馬頭さま、下の馬頭様と呼ばれて小前田宿の終始の目標となり、また鎮守の祭りでの御神輿渡御の区切りともなった。
江戸時代に小前田宿では、宿の両端に馬頭尊が建立され、それが上の馬頭さま、下の馬頭様と呼ばれて小前田宿の終始の目標となり、また鎮守の祭りでの御神輿渡御の区切りともなった。
上の馬頭尊は、秩父街道と児玉本庄道の交さする辻に建てられていた。
江戸時代、熊谷方面の穀倉地帯から寄居・秩父への米売り馬の往来が多かった。
ある時、その馬がこの辺りで死んだため、追善供養として文化4年(1807年)馬頭尊が建立され、上の馬頭尊と呼ばれ、馬子たちのみならず多くの人達の信仰を集めた。
ところが明治の世になり、小前田上組には火災が何回かあり、誰が言うとなく、馬頭尊のたたりであるとの噂が広まり、ついに馬頭尊を忌みきらい始めた。
おりから明治30年(1897年)古社寺保存法が公布され、各地でお堂や石仏の統合などが行なわれた。
これを期に馬頭尊を長善寺門前に移動したが、火の災いを恐れて民家が無い西北の方向に向けて建てられた。
下の馬頭尊は、秩父街道の菅谷川越道の分岐点に、諏訪神社の神輿御渡にあたって下の折り返し地点の目標に道じるべを兼ね、安政六年(1859年)建立された。
以来、数度にわたる秩父街道の改修で、人家の裏の方に取り残されていたが、大正5年(1916年)土台石が崩れ危険となったため、長善寺門前に移した。