②→③→④→①→⑤→⑥・・・・⑯→⑰→②を巡るコース ; 約 4km

1. 鎌倉街道跡の碑
2. 中瀬河岸場跡
3. 中瀬八坂祭
4. 旅籠 「播磨屋」
5. 廻船問屋 「石藤」
6. 「かんの灸」 跡地
7. 大斎藤家旧宅
8. 大斎藤元屋敷跡
9-1. 桃井可堂(1)
9-2. 桃井可堂(2)
10. 桃井可堂塾跡
11. 中瀬神社
12. 中瀬神社跡地
13. 廻船問屋 「河十」
14. 河田菜風墓
15. 吉祥寺
16. ふれ愛観音(吉祥寺)
17. 芭蕉句碑(吉祥寺)
- 1.鎌倉街道跡の碑
 鎌倉時代、源頼朝(よりとも)が中瀬の渡しを渡り新田の荘へ通ったと吾妻鑑に載っている。
鎌倉時代、源頼朝(よりとも)が中瀬の渡しを渡り新田の荘へ通ったと吾妻鑑に載っている。
元弘(げんこう)3年(1333年)新田義貞(よしさだ)が生品神社(いくしなじんじゃ)で挙兵し鎌倉に攻め上った軍勢の進撃路は諸説あるがこの辺りで利根川を渡ったのではないか。 目印にしたと伝わる深谷市高島の榧(かや)の木はこの碑から300mの位置にある。
日光例幣使街道(にっこうれいへいしかいどう)が対岸を通る。
江戸時代、中瀬は利根川の渡船場として栄えた。
「深谷の史跡めぐり」の中の鎌倉街道
*7.小前田の史跡めぐり-3.鎌倉街道
*10.針ヶ谷・櫛挽・本郷の史跡めぐり-3.鎌倉街道- 2.中瀬河岸場跡
 堤防が出来る前、小角(こすみ)と云う字があった、そこに「河十」と「石川」の2軒の廻船問屋があった。
堤防が出来る前、小角(こすみ)と云う字があった、そこに「河十」と「石川」の2軒の廻船問屋があった。
この辺りには浅間山の噴火による栗石が多く、この石を江戸城の石垣に利用するために此処から船で運んだ、それが船運の始まり。
寛永(かんえい)18年(1641年)江戸川開削で江戸と利根川が結ばれ、正徳(しょうとく)2年(1712年)には江戸城紅葉山御殿の材木を、河十問屋が秩父から買い付け中瀬河岸から送って以降急速に発展した。
中山道筋の宿場や秩父方面からも荷物が集まった。
主な出荷品は廻米、藍、材木、木炭、生糸などで、江戸からは塩、醤油、干鰯(ほしか)、瀬戸物、お茶等が運ばれた。
この地図は40年ほど前、郷土史家が聞き取りをして明治・大正期の町並み記録したたものです。 江戸時代の河岸場も問屋、旅籠、茶屋、質屋、料理屋、鍛冶屋、菓子屋、髪結等が並び、船が着くと酒の肴などを仕込んだ「煮売船(にうりぶね)」、風呂を積んだ「湯船(ゆぶね)」などが寄って来て賑やかだった。
中瀬河岸場付近は広瀬川の水を合わせ水量が豊かで、倉賀野から来た荷物は百石船・二百石船などの大型船に積み替えられ、人も乗り換えさせられ役人が人相書を照らし合わせる取締りが行われた。
船運は、江戸までに途中寄る所もあり2~3日かかり、帰りは15日位かかった。
明治16年(1883年)高崎線が開通し、それを境に河岸場は衰退していった、廻船問屋「河十」は明治23年(1890年)廃業した。- 3.中瀬八坂祭
 近年深谷祭りと同じ日になってしまって残念だが、深谷市指定文化財となっている中瀬八坂祭の屋台は中瀬の繁栄を今に伝える。
近年深谷祭りと同じ日になってしまって残念だが、深谷市指定文化財となっている中瀬八坂祭の屋台は中瀬の繁栄を今に伝える。
中瀬の屋台は明治の初め頃から建造気運が盛り上がり、明治12年(1879年)頃までには完成したと思われる。
江戸に直結した河岸場だけに、屋台を曳く時には皆揃いの赤い長襦袢を着て実に華やかな祭りであったと伝わる。
屋台は前部が舞台、後部が囃子となっていて、大正10年頃までは川岸(かし)・延命地(えんめいち)・上中瀬(かみなかぜ)・原(はら)の4会所で順番に屋台芝居が催された。
川岸屋台の前飾りは天岩戸、中羽目は農業の神様猿田彦(さるたひこ)、後飾りは鳳凰と竜、竜の首がとてつもなく長く今にも人を飲み込もうとするほどの迫力ががあったが度々の落下があり、今の様な短い首となってしまった。
製作者は熊谷玉井の小林源八・直光(げんぱち・なおみつ)親子の共作と伝わる。- 4.旅籠 「播磨屋」
 水戸の天狗党が、文久4年(1864年)筑波山で旗を揚げた。 その前年、桃井可堂の弟子だった川俣茂七郎(しげしちろう・もしちろう)と小田熊太郎などが中瀬に来て播磨屋に逗留し御用金の取立てをした。
水戸の天狗党が、文久4年(1864年)筑波山で旗を揚げた。 その前年、桃井可堂の弟子だった川俣茂七郎(しげしちろう・もしちろう)と小田熊太郎などが中瀬に来て播磨屋に逗留し御用金の取立てをした。
伊勢崎藩がその様子を記録した文書が残っている。
「5月24日中瀬村に来たり候、浪士は小田熊太郎・川俣茂七郎・大幡外記等20人、播磨屋へ旅宿いたし、村々へ差紙をもって候、御用金申付け候。 斎藤安兵衛から300両」。
面白いのは、血洗島村の渋沢宗助(渋沢栄一の本家)。「惣助へ差紙を附け候処、出し申さず候、岡部の陣屋に願い候て警護の役人多くあい集い候、この家には浪人来ず候」 渋沢の家には行かなかった。
金を巻上げた時は必ず受け取りを出す。 深谷宿の旧家にこの時の証文が残っている。 他に、泉屋が150両、松屋50両などと書かれている。
川俣茂七郎は秋田県酒田松山藩の浪人、筑波山の麓で壮烈な戦死を遂げた。
小田熊太郎は加須の代官の息子、天狗党の戦いでは一軍の大将になって壮烈な戦死を遂げている。- 5.廻船問屋 「石藤」
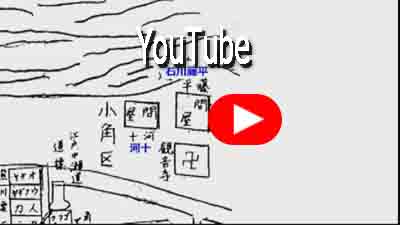 廻船問屋石川藤平は近在きっての大地主で桃井可堂の後援者でもあった。
廻船問屋石川藤平は近在きっての大地主で桃井可堂の後援者でもあった。
長屋門が残っている。
桃井可堂の息子は八郎(はちろう)と宣三(せんぞう)。 可堂の学者的性格を継いだ次男の宣三が家を継いだ。 宣三が石川藤平に出した手紙が見つかった。
「且又新地武兵衛殿」 新地は島村の事、田島武兵衛は渋沢栄一と親交が有った人物。
古文書では石川東平となっている。- 6.「かんの灸」 跡地
- 7.大斎藤家旧宅
 昭和54年、斎藤家は家・屋敷を不動産業者に売却、屋敷跡を整地作業中あたりは暗くなりかけた頃、ブリキのようなものが光っていたのでよく見たところ小判であった。
昭和54年、斎藤家は家・屋敷を不動産業者に売却、屋敷跡を整地作業中あたりは暗くなりかけた頃、ブリキのようなものが光っていたのでよく見たところ小判であった。
発見場所は便所の手洗い付近と云われたが確証はない。
当時、小判団地と言われ行商人が来て小判団子など売っていた。
発見された小判489枚のうち136枚に村名・屋号・名前等が墨書きしてあった。 斎藤家は名主役をつとめ、利根川筋上流の村々からの上納金は役人の指図により斉藤家で一時預かりしていた準公金のようである。
小判の所有権を巡り紛糾し十数年を経て国100枚、旧斎藤家194枚、土地購入者117枚、小判発見者78枚で和解した。
桃井可堂が若い頃奉公に来て、文書蔵に篭って勉強した所でもある。- 8.大斎藤元屋敷跡
 祖は天正(てんしょう)19年(1591年)この地に土着。
祖は天正(てんしょう)19年(1591年)この地に土着。
斎藤善松は延享(えんきょう)2年(1745年)ごろ奉公先の日本橋の両替商から中瀬に戻り、両替商や荷為替手形を割引くなど金融業を起こした。
斎藤家は代々名主役を務め、家業も隆盛を極めたようである。
昭和21年(1946年)「自作農創設特別措置法」が制定され、中瀬村での不在地主の国の買収畑地35町6反余りのうち、半数以上は斎藤家の畑だったと云われた。
近代、斎藤安雄は英語塾を開き村民に教授した、明治19年中瀬小学校校長に就任し、明治27年埼玉県議会議員に当選。 以来、貴族院議員・衆議院議員を歴任し政界で活躍。 また、深谷銀行頭取・埼玉農工銀行頭取・武州銀行取締役等を務め財界でも活躍した。- 9-1.桃井可堂(1)
 桃井可堂は深谷市北阿賀野で享和(きょうわ)3年(1803年)守道(もりみち)の二男として生まれた。 通称は儀八、号は可堂、始め福本氏を名乗り農業を営んだ。
桃井可堂は深谷市北阿賀野で享和(きょうわ)3年(1803年)守道(もりみち)の二男として生まれた。 通称は儀八、号は可堂、始め福本氏を名乗り農業を営んだ。
12歳のとき隣村、血洗島村の渋沢仁山(じんざん)に師事した。
その後、中瀬村の斎藤家で家事経理を任された。
22歳のとき江戸遊学を志し、東条一堂の門に入り名を桃井可堂と改めた。
清川八郎・那珂五郎と共に、「一堂の三傑」と言われる迄になった。
29歳のとき桃井塾を開く、多くの門弟を集め庭瀬藩や亀山藩主の師となった。
また、友交関係も広く勝海舟・島田虎之助・藤田東湖など当時の一流の人々と親交を深めた。
文久(ぶんきゅう)3年(1863年)盟友の清川八郎が浪士隊を率いて上洛するに及んで、可堂も尊攘討幕の実行に意を決し、江戸での塾を閉じ郷里の中瀬へ戻り、各地の勤皇の志士に働きかけ天朝組を組織し、沼田城を取ってそこを拠点として旗を揚げ攘夷討幕を推し進めて行こうとした。
この時可堂61歳、一流の学者として江戸で安楽に生活できる境遇を投げうち、身を捨てて尊攘を決行しようとした可堂が、如何に国の行く末を案じていたかを窺い知る事ができる。- 9-2.桃井可堂(2)
 可堂は挙兵の盟主に、利根川の対岸、新田の岩松俊純 を擁そうとした。
可堂は挙兵の盟主に、利根川の対岸、新田の岩松俊純 を擁そうとした。
岩松氏は新田氏の後裔で徳川氏の祖にあたり、幕府から特別に遇せられていた。
可堂の挙兵は規模が大で、長州・久留米・宇都宮・津和野・島原なのど各藩の勤皇の志士や可堂の門人などが加わり文久3年(1863年)11月12日冬至の日に決行しようとした。
しかし、越後の湯本多門之助が変心し南町奉行所に訴え出た。
また総師として立てようとした岩松俊純は参加を拒み安部播磨守に訴状を差出した。
「武州榛沢郡中瀬村住宅にて学問きょうゆつかまつりまかりあり候浪人、桃井儀八」と書いてある、可堂は浪人。
訴えたのを知った可堂は同志を解散し、罪を一身に引き受けるべく12月15日朝、中瀬を出立し忍藩に自首したが、忍藩は関わり合いを恐れて拒否。
ついで川越藩の大川平兵衛を通じて訴えた。 翌年、江戸町奉行に引き移され、ついで福江藩に預けられた、老中が可堂のかっての弟子だった事もあり厚遇されたが、 可堂は「封建の飯は食(は)まず」と自ら食を断って元治元年(1864年)7月22日この世を去った。 享年62歳、明治維新の3年前だった。- 10.桃井可堂塾跡
 幕末、中瀬河岸場の近くで桃井可堂の天朝組、渋沢栄一らの慷概組(こうがいぐみ)の二つの派が尊皇攘夷の挙兵の計画を立てた。
幕末、中瀬河岸場の近くで桃井可堂の天朝組、渋沢栄一らの慷概組(こうがいぐみ)の二つの派が尊皇攘夷の挙兵の計画を立てた。
深谷の一角で天朝組、慷概組の二つの挙兵計画が立てられたのは特筆すべきで、深谷の草奔の志士たちが、如何に血燃えたぎっていたか。
桃井可堂は、文久3年(1863年)3月、江戸の塾をたたんで帰郷し、家を借りて塾を開いた。 この家を世話したのが渋沢喜作。
1階は8畳4間と土間、2階は8畳2間。 階段が3つ有った、一つは隠し階段、西の方に杉林があり人目に触れず逃げる事ができた。
浪士達が中瀬河岸場から入って来て此処へもぐり込み、2階の8畳間で密談した。 怪しんだ八州廻りが見張っているので、これをかわすために昼間は詩吟をやり夜密談した。
荒井佐助という人に 「八州回りが来ているので、浪人が来るが泊めて面倒を見てほしい」 と言った内容の手紙を出している。
明治10年代後期より明治20年代前期に撮られた、桃井可堂塾に使われた建物の写真。 中瀬小学校の2階から撮った写真は、お年寄りの方の中には覚えている方がいる。- 11.中瀬神社
 神社の入口には日露戦争で活躍した東郷平八郎元師が書いた「中瀬神社碑」がある。
神社の入口には日露戦争で活躍した東郷平八郎元師が書いた「中瀬神社碑」がある。
明暦2年(1656年)中瀬延命地より原に奉還、十五社大神と称した。 堤防を作るため現在地に遷座して中瀬神社と改称した。
御神体は十五童子の上に弁才天、毘沙門天、大黒天の三体神が鎮座している。
中瀬神社は最近1500万円かけて整備されたが、8年ほど前盗難に遭い貴重な彫刻多数が持ち去られた。
彫刻は天保11年(1840年)中瀬出身で江戸住人の石川三代の孫(源豊光)の作と伝わる。
昭和48年市の文化財に指定された。- 12.中瀬神社跡地
 大正2年(1913年)から河川敷にあった建物の移転が始まり、中瀬神社のほか川岸・上中瀬・原・向島の住家百戸以上が移転し、移転後の大正6年頃堤防が完成した。
大正2年(1913年)から河川敷にあった建物の移転が始まり、中瀬神社のほか川岸・上中瀬・原・向島の住家百戸以上が移転し、移転後の大正6年頃堤防が完成した。
当時の堤防は現在のような立派なものではなく、数回にわたり補強工事が行われてきた。
堤防が出来て中瀬の土地もずいぶん狭くなった、中瀬神社は鉄塔の辺りにあった。
川原に木がある辺りが第一渡船場で鎌倉時代の渡船場、源頼朝が渡ったと伝えられている。
二本目はグランドの辺り、 最後が向島の渡船場。利根川の流れの変化に伴い、渡船場も移動していった。- 13.廻船問屋 「河十」
 堤防が出来る前、小角(こずみ)と云う字があった、廻船問屋「河十」はそこにあった。
堤防が出来る前、小角(こずみ)と云う字があった、廻船問屋「河十」はそこにあった。
この辺りには、浅間山の噴火による栗石が多く、この石を江戸城の石垣に利用するために此処から船で運んだ。 それが船運の始まり。
正徳(しょうとく)2年(1712年)江戸城紅葉山御殿の材木を河十問屋が秩父から買い付け中瀬河岸から送ってから急速に発展した。
河十は度々火災に会い、江戸の終わり頃消失し、この建物は明治2年(1869年)の建築、右側は明治5年増築。
養蚕農家の造りをしている、3階に煙り出しが付いていて、2階で養蚕をやっていた。
昔は3階に見張りを置き、敵が来ると床下に非難した。 床下に非常口が4ヵ所あり、座敷と座敷の間は板戸になっていて、その板戸も防御の役をはたした。
明治5年郵便が制度化され、深谷で第一号の郵便局は此処で開業した。 格子に郵便局の窓口の面影を残している。
郵便物は前の道を、東京⇒熊谷⇒中瀬⇒前橋へと馬車で配送された。
立派な長屋門が有ったが、昭和20年(1945年)8月14日夜の熊谷空襲の時、この辺りも焼夷弾の攻撃を受け、長屋門も蔵とともに焼失した。
その時その場所で37歳のご夫人と8歳の子供が死亡した。 この終戦前夜の空襲により死者2名、重傷者3名、被災した建物13戸に及んだ。 供養を兼ねた桜が大きくなっている。
仕分場、問屋時代は此処が帳場。
蘭引(らんびき)が残っている、海水から蒸留水を作る、河舟では使わないが東京湾に出たときに使った。
床が高い造りとなっており、これは水害対策と強盗対策が大きな理由。
最盛期には使用人が45人、当時の使用人が使っていた下駄箱が残っている。
明治16年(1883年)高崎線が開通し、それを境に河岸場は衰退していった。 廻船問屋「河十」は明治24年(1891年)179年続いた問屋業を廃業した。- 14.河田菜風墓 (かわたさいふう)
 文政(ぶんせい)4年(1821年)中瀬で生まれ(河田十郎右衛門の長男として生まれ)、幼時から吉祥寺25世住職観海(かんかい)について和漢を学び、中瀬に立ち寄った遊歴学者から詩文・書画を学修した。
文政(ぶんせい)4年(1821年)中瀬で生まれ(河田十郎右衛門の長男として生まれ)、幼時から吉祥寺25世住職観海(かんかい)について和漢を学び、中瀬に立ち寄った遊歴学者から詩文・書画を学修した。
天保(てんぽう)9年(1838年)18歳の若さで自宅を教場として塾を開き、10年後の嘉永(かえい)2年には28歳で「宣興塾」(せんこう)と名付けた正式な塾を開き、披露の会には著名な文人墨客が出席した。
門弟は五百数十人を数えた。
明治6年(1873年)58歳のとき、中瀬小学校が開校され、これを契機に35年に及ぶ「宣興塾」を閉じ村の教育顧問となって後進の育成に協力した。
明治13年(1880年)享年60歳で没した。
明治23年(1890年)菜風の遺徳を偲び「河田菜風翁碑」が建立され、平成7年(1995年)吉祥寺境内に移された。
桃井可堂が菜風に宛てた手紙が見つかった、菜風は学者同士では交友が有ったが政治活動はしなかった。- 15.吉祥寺
 長勢山義光院と号し、天台宗世良田長楽寺末寺で、開山は聖一国師猿圓爾辨圓(しょういつこくしえんにべんえん)師、本尊は阿弥陀如来。
長勢山義光院と号し、天台宗世良田長楽寺末寺で、開山は聖一国師猿圓爾辨圓(しょういつこくしえんにべんえん)師、本尊は阿弥陀如来。
新田氏縁の河田對馬守義賢が父但馬守義光の菩提を弔うため、永禄(えいろく)5年(1562年)建立と伝えられている。
義賢と義光の亡くなった年代が離れすぎているので、義賢の子孫河田幸七が中興開山したしたものとも云われる。
堤防工事のため大正2年(1913年)現在地に移転した。
山号の長勢山(ちょうせいざん)これを訓読みすると「ながせ」(中瀬)となる。院号は義光(ぎこう)院、河田義光(よしみつ)を音読みして「ぎこう」。
本堂は享保(きょうほ)13年(1728年)建てられた。 欄間は江戸三大彫物師、石川勝右衛門作。
本堂天井絵、可水斎(かすいさい)守英(しゅえい・もりひで)と読める。 狩野探信(1653年~1718年)の門下生に守英と言う名が出てくるが同一人物かは定かでない。
天正16年(1588年)小角に観音堂が建立されたが天和(てんわ)2年(1683年)大洪水により流失してしまった。
寛保(かんぽう)2年(1742年)原地区に再建された。 その後大正2年堤防工事のため現在地に移転した。
本尊は聖観世音菩薩(せいかんぜおんぼさつ)、運慶の作と伝わる。
大銀杏は樹齢450年。
あまり見かけない袴付きの鐘楼は最近再建された。
このお釈迦様の像は、よく見掛ける釈迦如来像と比べると、手の組み方や螺髪(らほつ)に特徴がある、初期のガンダーラ像をイメージさせるこだわりが感じられる像。- 16.ふれ愛観音(吉祥寺)
 吉祥寺境内に、さわってお参りするために造られた「ふれ愛観音」がある、作者は美術院国宝修理所長なども務めた西村公朝師。
吉祥寺境内に、さわってお参りするために造られた「ふれ愛観音」がある、作者は美術院国宝修理所長なども務めた西村公朝師。
目が不自由な方や、車椅子の方、子供達も容易にさわれるよう低い場所に安置される事を考慮し、視線が上を向いている。 この様な方達がお参りし易い様、お線香をたてる場所は作っていない。
先々代の住職、三崎良泉師の縁で平成6年「ふれ愛観音」が吉祥寺に奉安された。
観音様は三十三回姿を変えて人を救うという数に合わせて、三十三体が製作され、延暦寺・永平寺など、宗派を超えて全国の寺院に納められており、吉祥寺に奉安されているのは二十一体目の「ふれ愛観音」。
後ろの文字は奉安されるお寺の住職が書く慣わし、三十七世住職の瀧川善海師が書いたもの。- 17.芭蕉句碑(吉祥寺)
 中瀬は利根川筋にあって船運により栄えた村で文人・墨客の往来が盛んだった。
中瀬は利根川筋にあって船運により栄えた村で文人・墨客の往来が盛んだった。
中瀬斉藤家には文女・南々・寄三の三姉弟があり、斎藤の三俳人として近在で有名であった。
この碑は斎藤4代目当主、斎藤南々の発願により芭蕉の150年遠忌を期に、天保(てんぽう)12年(1841年)建碑された。
句碑の文字は、天保の三大家と称された田川鳳朗(たがわほうろう)の書。
- 頓(やが)天(て)志奴(しぬ)氣之幾(けしき)盤(は)
見(み)衣(え)壽(ず)
蝉(せみ)農(の)己恵(こえ)
「 やがて死ぬけしきは見えず蝉の声 」
蝉は、もうすぐ秋になれば、はかなく死んでしまうに決まっている。それなのに今は少しもその様子がなく、やかましいばかりに鳴き立てていることだ。
無常迅速の観想の句で、こんなにしきりに鳴き立てている蝉も、一時のことですぐ死んでしまうのだ、人間もまた同じことなのだ。
芭蕉47歳のときの句- 頓(やが)天(て)志奴(しぬ)氣之幾(けしき)盤(は)
