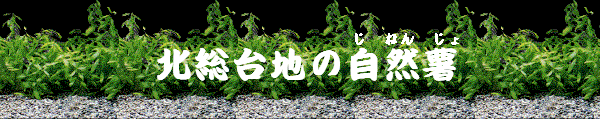|

ヒゲを焼きます |
●人数分の分量(1人50g〜70g位)を包丁で切りとります。包丁が無くとも簡単に折れます。
●自然薯のヒゲ根をむしり、更にガスコンロの火であぶると簡単にヒゲが燃えます。あぶり過ぎて自然薯を焦がさないで下さい。
●たわし等で軽く土や汚れを洗い流します。あまり擦り過ぎると皮が剥けてぬるぬるして持ちづらくなります。
●乾いたフキンやキッチンペーパー等で水気をふき取って下さい。
●自然薯の個体差によって、アクが出ることもあります。出てくるアクもまたじねんじょうの生命力です。アクには抗酸化力の高いポリフェノールが多く含まれています。 |
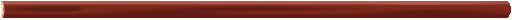 |
 |
 |
●自然薯の食べ方は、やはり『とろろめし』です。『山かけ』やそのまま『短冊きり』にして鰹節を掛けて食べる方法もありますが、まずは『とろろめし』を食べてみて下さい。
●自然薯は特に皮に風味と栄養があります。間違っても皮を剥いたり削ったりしないで下さい。皮ごと摩りおろして下さい。
(あまりにも自然薯が黒い場合は包丁の背で薄く皮を剥いてもよいです)
|

細かいオロシガネ |
●下ごしらえが終わったら『自然薯』をすりおろします。すり鉢で直接すりおろす事も出来ますが細かな目のおろし金を使えば、ほぼすりおろしは出来上がりです。
●おろし金ですりおろし、更にスリコギとすり鉢できめ細かくすりおろします。
●自然薯のネバリは相当なものです。
ナガイモとのネバリの差は歴然としています。すりおろした自然薯が一緒に持ち上がってしまうほどです。
|

ネバリの強さはこのとおり |
 |
●『だし汁』を作ります。
鰹節などでだしを取り、みそ、又は、しょうゆ等好みのものを混ぜて『だし』とします。
分量は味噌汁には少し塩っぱすぎるくらいの加減です。
※だし汁は冷ましてから入れて下さい。
(熱いだし汁で折角の自然薯を茹で上げないで下さい)
|

好みのネバさにして出来上がり |
●作って冷ましておいた「だし汁」をとろろに少しずつ混ぜていきます。
(好みで生たまごを1個先に混ぜても良い)
※注意すべきはだし汁を一気に加えて混ぜないことです。
だし汁が少し混ざってとろろが緩くなったら少量のだし汁を加えて徐々に伸ばしていくことです。
※失敗しない方法は鰹節でだし汁を作り3〜5倍に伸ばし、最後に『つゆの素』を少しづつ加えお好みの味にすることです。
(とろろのネバリはだし汁を加える量で調節して下さい)
●出来上がりましたら熱い御飯(あるいは麦ご飯)にかけてお召し上がり下さい。 |
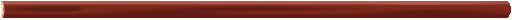 |
 |
 |
●一般的な食べ方です。
マグロのぶつ切りにすりおろした自然薯とわさびを加え、はい出来上がりです。
※自然薯はネバリが凄すぎるのでだし汁で2倍〜3倍に伸ばした方が食べやすいと思います。 |
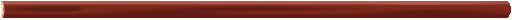 |
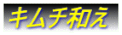 |
 |
●これは簡単、絶品です。
自然薯の短冊切り(スライス)と市販のキムチを混ぜて出来上がりです。
・酒のつまみには最高です。
※歯ごたえを好みの方は自然薯を厚目に切ってお楽しみ下さい。
|
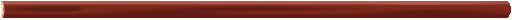 |
 |
 |
●自然薯を短冊切りにしてかつお節、醤油を掛けてはい出来上がり。
※さくさくして自然薯本来の味がお楽しみいただけます。 |
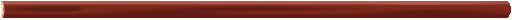 |
 |
 |
♪♪唐沢寿明がテレビCMで紹介♪♪
●すりおろした自然薯に大根おろしをのせ、アジポンをかけて
出来上がり。
※これは簡単、自然薯そのもので絶品です。 |
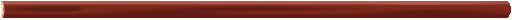 |
 |
 |
●だし汁で2倍位に薄めた自然薯を掛けて出来上がり、本格的な自然薯そばの味は格別です。 |
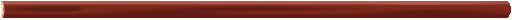 |
 |
 |
●素上げ すりおろした自然薯を丸く団子状にして海苔で巻き、油で揚げるだけでおいしく召し上がれます。
●鍋料理にすりおろした自然薯を団子状にしていれるだけです。鍋の出し汁がしみ込み、もちもちです。
●お好み焼きにだし汁等で薄めた自然薯を入れますとふっくらと仕上がります。
●かき揚げ短冊切りにした自然薯にセリ(みつば又は長ネギ)を天ぷら粉とまぜあわせ油であげるとおいしく召し上がれます。 |
| ※我が家の食べ方を紹介させて頂きましたが、その他いろいろの召し上がり方がありますのでお試し下さい。 |
 |