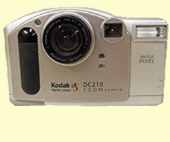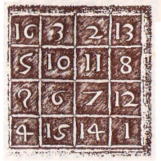Towasowrai�@
���ꂱ��
| �@��R���Ɨ���ɂ݂��܂� �@2011/3/17�B�e�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜�N���b�N�Ŋg�� �@ �@��R�́A���̊p�x���猩��ƓƗ���Ɍ����܂��B�g�b�v�y�[�W�̎ʐ^�́A��R�̉E���t�߂��炱��������Ă��܂����A���̎ʐ^�ł́A����̉�����R�_���A�E��̉����O��勴�ł��B �Ζʂ̉������������̍���ɂ́A�_���ɒ��ޑO�̓��̂悤�ȍ��Ղ������Ă��܂��B ��R��Ëv��Ύ��ӂ��������Ă���ƁA�v�������Ȃ����̂ɏo��܂��B�J�����ɂ͎��܂��Ă���܂��A�������Ȃǂɂ��o���킵�܂��B�@����Ȃ��̂◷��Ȃǂ��u�ց`�v�Ǝv�����̂��u�G�`�v�Ɗ��������̂Ȃǂ��E���W�߂��̂��u�Ȃɂ���v�ł��B�@�����u���ꂱ��v�ɂ́A�����l��������ꂽ���ƂȂǂ��W�߂Ă݂܂����B |
| �@�P�[�v�^�E���u���[�@���� ���͂P�P�����ɂ́A�`���[���b�v�̋�����A�����݂����̂ŁA�����������A�Ԑ���̍��ɒI���o�����˂Ȃ�Ȃ������E�E�E�B ����ɂ��Ă��炫�n�߂��x���̂ŁA���N�̓l�b�g�ւ̔��킹�����H�v���āA���������Ⴂ�ʒu����炩����悤�ɂ��������̂ł��B |
||
|
�@�R�N�O�Ɍ�������LED�V�[�����O���C�g�����ALED�ł��S�Ă̒���������������ł͂Ȃ��悤�ł��B ���N�V�F�[�h���O���đ|�����Ă��Ă��A�{�̂܂ł͊O���Ă��Ȃ������̂ŁA���߂ĊO���Ă݂ăr�b�N���ł��B ���M�̂��߂Ɋ��S�ɖ��ɂ͏o���Ȃ��̂ł��傤�ˁB |
||
  �@�v�킸 �u�얳�s�v�c���v�@���ƍ��� �@�����A���J���~�����悤�ŁA���̔�����̒��ɐ^��ۂ̔������̂�������ł����B �V�������O�A�ӂ�͔��Â������̂ŁA���������Ă���̂��ƈ�u�v�������A�����Ȃ̂ł���Ȗ�Ȃ��B �@�D�F�Ɍ������蔒���������肵�Ă�����ɁA���z�̗֊s���L���L���Ƃ������A�s�J�s�J�Ƃ������A�ƂĂ����t�ɏo���Ȃ��P�����������Ǝv������A����ɗ֊s�Ƀ����O���|�����āA�����Ȃ�����������菬���݂ɗh��Ȃ���P���������B�@�Q�ĂăJ���������o�������A�����x�������B �@�����A�ڊo�߂�Ƒ��z�̏オ�铌���Ɍ������A���ӂ̍��������Ă��������n�܂�̂����A����Ȃɕs�v�c�Ȍ���q�߂��̂́A���߂Ă̏o�����ł����B�@ �Q�ĂăR���p�N�g�J�����Ɏ��߂悤�Ƃ������A�s�v�c�������܂�킯���Ȃ��ł��B �����̌[���Ȃ̂��ȂƁAῂ����ĂƂĂ�����ł͌����Ȃ��Ȃ������z�ɍĂэ��������B |
||
| �@����11������A���낻��~�����Ă�B �@�P�P���ɓ������Ƃ����̂ɁA�n�C�r�X�J�X�A�܂��܂��Q��c��܂��Ă��܂��B ���敗���x�ł��Ђ�����Ԃ�̂ŁA�R���N���[�g�̃x�[�X�ɔ���t���Ă��邪�A���낻��}��藎�Ƃ��ē~�����Ă��炢�����̂ɁA�{�l�͑S�����̋C������܂���B ���͖Z�����Ȃ�̂ŁA���ڂɎ}��S�Đ藎�Ƃ��āA�Q�K�̓����ʼn߂������Ă�肽���̂ɁA���ނ�n�C�r�X�J�X����B �@�����ߏ��ŌF�̖ڌ�������������A���R���L���ł����̂��A���R�����������Ȃ����̂��A�g�����̂����ł��肢���܂���B |
||
| �@�A���Ă��Ă��ꂽ�� �ŋߏ������������Ȃ��Ȃ����ȂƎv���Ă����Ƃ�����A�^������J�����������邪�A�t���ς��ז����ď�肭�B��Ȃ��������A�Ȃ��K���ȋC���ɂ����Ă��炢�܂����B �C�����Ă�����A�����̓��W���������B |
||
| �@�݂�Ȃǂ��֍s�����H �݂�Ȃǂ��֍s���Ă��܂����̂��낤�E�E�E�B �m�A�̔��M�ɏ���āA������q�y�����̂ĂĂ������̂��낤���B ���������A���̍��ɂ͐F�Ƃ�ǂ�̒���������ь����Ă���̂��Ƃ��A�{���Ƃ������t�����Ȃ��̂�����ƁB�i����Ɍo���j �V�ϒn�ق̗\���łȂ���ƋF���Ă��邪�A�悤�₭�J���X����H�����܂����B |
||
| �@��Đ��| �E�@���̒��ł��A�P�Q���̈�Đ��|����ԑ�ʂɗ����t�S�~���W�߂˂Ȃ�܂���B �E�@�������Q���Ԕ������āA�����͎ʐ^�̂悤�ɂV�O���b�g���܂��X�W�߂܂����B�i�ʐ^�Ɍ����Ă�̂͂V�܂ł����j �E�@�\��͂X�`�P�O�����Ȃ̂ŁA�݂�ȂP�܂���Q�܂������āA�������Ɛ�グ�܂����A�Ƃ̎��ӂ܂ł���Ă�����ƁA���������͂���ȏł��B �E�@����Ȓ��A���蓾�Ȃ��قNJ��������Ƃ�����܂����B �E�@�S�~�W�Ϗ�܂ŁA���e�ɂԂ牺���ĉ^��ł���ƁA�V��ł����q�����A�u��`���܂��v�ƌ����āA�P�N���ƔN�����炢�̌Z�����A50m�ʂ��P���^��ł��ꂽ�B�@ �E�@�܂ɂ͑��ŃM���[�Ƌl�ߍ���ł���̂ŁA��l�ɂ͌��\�d���̂ł����B �E�@�������ł��A�����̉Ƃ̃S�~���^��ł���̂��������邱�Ƃ�����q�����Ȃ̂ŁA����Ȃ��Ƃ��T���b�Əo����̂Ɋ��������B�@ �E�@��������Ă��̂��A�ʂ肪����̑�l����l���������Ă���āA�r�j�[���܂�����ł��ꂽ�B �E�@�܂��܂��̂Ă����̂���Ȃ��ȂƁA�C�t�����ꂽ��Đ��|�̂����v�ł����B |
||
�@�H������@�̓���ւ�
  �E�@���傤�ǂQ�O�N�g�p���� �H������@���A���Ɍ̏Ⴕ���B�@�f�l�ł��G�ꂻ���ȏ��̓����e���Ă݂����A��H��̌̏�̂悤�ŁA����ɂR�O�b���炢�����āA�ُ�\�����Ȃ� ��~���Ă��܂��B �E�@�o����𐔐�~������ �T�[�r�X�}�����Ă�ł��A��C���i�����������Ȃ̂ŁA�����ւ���I�������B �E�@����ւ����������Ă�ۂɁA���̓d���H���A�蔲���������̂��� ���߂Ďv�����B�@ ����ƂāA���̕ǂɃR���Z���g�����Ă�����A�����������炢�Ȃ��Ƃ��v�����B�@ �E�@���낪���̓d���R���Z���g�A���h���������� �K���I�ɂ����Ȃ̂ŁA���łɒ������Ƃ��ċC���t�����B
�E�@�v���̓d�C�H���m���A�Ȃ�����ȍH�������Ă��܂����̂��A���̎v���Y���Ƃ������ł����B�@ �E�@�ǂ̎�t���́A�K���ʂ�AFL150�~���Ɏ{�H����Ă��邵�A�d����VVF�̃�2�A�Ł@���Ȃ����A�R���Z���g���̂ɖ�肪�������̂��B�@ �E�@���̃}���[�^�R���Z���g�́A1995�N�O�b�h�f�U�C����܂̗D����̂Ȃ̂����A�c�O�Ȃ��獡�͓���s�B �E�@�}���[�^�R���Z���g�́A��t�����z�[���\�[�Ō������o���邵�A��t�� �r�X���Ă����A�Q�̃x��������ɋN���オ��A�ǂ̌����ɉ����Ē��ߏグ�Ă����D�ꂽ�\�������Ă���B�@ ����āA�p�{�[�h�� �B�~�߂���K�v���Ȃ��B �Ȃ��A�B�~�ߗp�̌��́A�ꉞ�Q�p�ӂ���Ă��邪�B �E�@�Ƃ��낪�A�p�ӂ����͓̂K���nj� �R�Q�~���܂ł������B�@���������Ɍ�����ǂ� ���� �S�T�~���������̂ŁA�}���[�^�R���Z���g�����t���Ȃ������̂��B�@ �E�@�����œd�C�H���m�͍l�����B�@�d���Ȃ��A�]�����ł�邩�ƁB�@VVF�P�[�u���́A�ł��̂ŕ��������Ƃ��ł��邵�A���v������āB �E�@�{�[�h�B �Q�{�ŗ��߂邱�Ƃ��l�������낤���A�����ɂ��ߑł����Ă��A�؍ނɓ͂��Ȃ��ʒu�Ȃ̂Œ��߂��̂��낤�B�@����ȃ{�[�h�B���A�������킹���Ȃ������̂��낤�B �E�@�����l���Ă݂�ƁA�蔲���H���ŕЂÂ���ɂ́A���Ȏ���������̂��ȂƊ������B�@ �ւ��ɁA�p�{�[�h�� �R�[�X�X���b�h�ʼn��~�߂���悤�ȁA������d�����A���̓]�����d���R���Z���g�̕����A�����I�ɂ͎�O�ɂ���̂ŁA���ɂ��肪���������̂ł��B �E�@���̌� ���ׂĂ݂�ƁA�䂪�Ƃ̓��ǂ� �S�ĂS�Tmm���Ȃ̂����A���ʂɃ}���[�^�R���Z���g���t���Ă���B�o�����đ����Ă݂�� �[�����S�R�Ⴄ�B�@�}���[�R���Z���g�ɂ͎�t�[�����Q��ނ������悤���B �d�C�����A�Ԉ���� �����Ǘp�������Ă��Ă��܂����̂����[�̂悤���B�@ ����A���������̂Ɏ��ւ���C�́A����ς� �Ȃ������ƌ�����̂��H�E�E�E |
||
�@�h�g�N�b�L���O�q�[�^�̓���ւ�
 �@ �@ �@�h�g�̃��[�X�^�[�i���Ă��j���g����ELB����Ԃ悤�ɂȂ�A�댯�Ȃ̂ŏC���g�p����߁A2�K�ŋx�~���Ă����@��Ɠ���ւ������Ă݂��B�@�i�����̏�@��g�ݍ���2�K�@�A�E��2�K�@��g�ݍ����́j �ǂ����2002�N���A2�K�@�͉��ʋ@�킾���x�~���Ԃ����������̂ŁA���[�X�^�[�����͂��ꂢ�ȏ�Ԃł����B�@�Ԍ����@��5�����Ⴄ�̂Ŋ��C����R���͂��܂��n�}��܂���B���̃����R���͏����������ĉE��1�K�@�ɃZ�b�g����\��ł��B�@��펖�Ԑ錾���ɗ]�v�ȏo���}�����Ė��X�ł��B |
||
�@���N�̒���A�����ςł��B �@�@���@�Q�K�x�����_���猩���낷�B �ߘa���N�A���N�̒���A���������������ł��B�@ �V��̐��������̓��`���x���������A�Ԃ������珇�ɍ炫�����čs���āA��̕�����ō炫����Ă����̂ŁA���낻�남�I�����ȂƎv���Ă�����A���x�͉������܂ň�Ăɍ炫�n�߂܂����B�@ �ǂ��Ȃ��Ă�̂��ȁA�����炫�H�@�܂��͔엿�����������Ƃ��H�@�����y�ɒn�A�����Ă���̂ɁA�S�[���ɕ������Ɋ撣���Ă��ꂽ�A�T�K�I�N�A���̂����ɍ炫�s�����Ă����Ȃ��ƁA�P�T�Ԍ�ɂ͉�̂��邩��ˁB |
||
�@���ǂ������� �@�@�䂪�ƂɗV�тɂ��郁�W������A�A�܂����قǒ��������ƌ������A�ǂ����܂��B �@�~�J�����Q���ׂĂ����ƁA�������Ĉꏏ�ɓ˂����Ă��邱�Ƃ��ǂ�����܂��B �@������H�A���ɑҋ@���Ă���̂ł����A��������3�C�ł͕���ŐH�ׂ��Ȃ��悤�ł��B �@���W���Љ�̃}�i�[�����G�Ȃ�ł��傤�ˁB |
||
�@�f�W�J�����p�\�R���̎v���o
�f�W�J�����ŏ��ɍw�����悤�ƁA�X�܂���������N���N���͍��ł��Y��Ȃ����A�����x��Ẵp�\�R���I�т����N���N�������̂ł��B �f�W�^���@��Ƃ̊������A���̃R�_�b�N DC210����n�܂����̂����m��܂���B dejikame omoide.pdf �@�@ pasokon henreki.pdf |
||
| �@���N�̒���͑听�� �E�@���ɍ��N�͏�̕�����łȂ��A�y�ɋ߂�������ł��ĂщԂ�t���Ă����̂ŁA�����̐����ɂ������ł܂��B �E�@�E�S��̐������Ƀl�b�g�ɂ����Ȃ�U�������A2���ʃq�S�_�Ɋ����Ă���U�������̂��ǂ������̂ł��傤���H �E�R�{�̃q�S�_�𗧂āA����s�̂悤�Ɏd���Ă��̂ŁA�炫�n�߂̍��������Ԋy���߂����A���̈�ĕ���Good�ł����B  |
||
| �@�|�[�^�u���i�r�̃x�X�g�|�W�V���� ���̃��f���ł����W�I�A�����Z�O�e���r�ACD�AUSB�͎g����̂ŏ\�����Ǝv������A�[�Ԍ㐔�������Ȃ������u����ς�i�r�~�����v�Ƃ����B ���Ăǂ����邩�A�U�X�Y��Ńv���ɑ��k�����肵�����A���ǃR���p�N�g��5�C���`�|�[�^�u���i�r���O�t�����邱�Ƃɂ����B�i�R�X�g�ʂȂǁj �R���p�N�g�i�r�Ƃ͌����A�^�]���E���Ղ�Ȃ����S�Ȑݒu�ꏊ�ɖ��Y�ށB�@����Ƃď���ȃG�A�[�o�b�N�̏�́A�ۈ�����NG�B �I�[�f�B�I�̍����ݒu�Ă����邪�A�^�]�Ȃ���͉����đ��삵�ɂ����A���X�B �z�Վ���t����C�W���Ă�����ɁA�z��O�̎�t���@���v�������B �z�Վ���t����t�l�Ɏ��t���Ă͂ǂ����ƌ����B�@���ꂾ�Ƌz�����s����Ȃ̂ŁA������ɉ��������āA�����Ă��Ȃ��悤�ɂ���Ηǂ����ƂɋC���t�����B �z�Վ���t��̉��ɂc�`�̃S���ށi���ʃe�[�v�t�j��������������ŁA��ɏ�����̒e���͂ŌŒ肵���B �d���R�[�h���I�o���Ȃ��悤�ɁA��̃I�[�f�B�I�R���\�[������ʂ��A���z������̉t����ʕی���l�������̂ŁA�i�r��t�ʒu�Ƃ��Ă̓x�X�g�|�V�����ɐݒu�o���܂����B |
||
| �@�������^��ł���邨�� �G�M�̏�ɕ��ׂĂ݂��̂́A��V�A�����E�m�q�Q�A�痼�A�����̂��킢���������ł��B ��V�ȊO�͐A�����o�����Ȃ��̂ɁA����Ȃ̂����̊Ԃɂ���t�������Đ�̂��n�߂Ă���l�́A���\������܂��B �ꐳ�̂���Ő����Ԃ̂悤�ɕ��ׂĂ݂܂����B�@�ǖ}�l�ȉ��̍˔\�Ȃ��ł����A���N����낵�����肢���܂��B |
||
| �@����Ȑ��o�܂����i�_�j �����̌��ʁA�_�X�ɐi���j���[�����Ă��邱�Ƃ��������A����ƌ����ɒH����܂����B �_�X�E�o��p�ƂȂ�A��肾�����̈ꕔ�����ʐ^�B ���̐ƍ��e���ɂƂ̊֘A�͗����o���Ȃ��������A���߂Ă̓��@�����A�ʐ^�̂悤�Ȓ��߂̂悢�����ŁA���K�ɉ߂������Ƃ��ł��܂����B |
||
| �@���a100�N�L�O������̂��ȁH �S���ŋL�O���Ƃ⎮�T��������悤�����A�P�O�N������a100�N�i2025�j�ɂ��A�����悤�Ȏ��Ƃ��v�悳���̂��낤���B ���a100�N�́A�R���s���[�^�̃V�X�e���g���u�����A2000�N����Ɠ����悤�ɐS�z����Ă���N�Ȃ̂ŁA�����N�����g�p���Ă��銯�����̃A�v���P�[�V�����\�t�g�ɂ͒��ӂ��K�v�Ȃ悤�ł��B 2025�N�ɂ́A���j�A�����V�����͂قڊ������Ă���̂��ȁH �����������H�A���j�A�J�ƂɌ����ē��{�����M���Ȃ��Ă��鍠��������܂���B |
||
| �@45�N�Ԃ�̑��͏��̌������� �c�Ⴊ�����c�����ł̂��̐ϐ�ł́A���ԏꂪ�Ԃ���ĔߎS�ȉƂ������������܂����A��������̗���̒���������̂悤�ł��B �����̉Ƃ���̗���ł͂Ȃ��A�_�����z���ėƂ̉�������̗���̏ꍇ�A�ǂ��������ƂɂȂ�̂��낤���A���l���ƂȂ���C�ɂȂ�܂��B �䂪�Ƃ̏ꍇ�A�O�̂����̗��Ⴊ�A�ʐ^�̂悤�ȕ������ł������A���ԏ�̉����ɂ͒��ړ͂����A���ɐ������ł��܂��B ���̐���̉��ɂ́A�T�c�L�̐A�͂�ی삷��K�[�h���o�b�`���d�|���Ă���̂ŁA���̈ʂ̗���ł��A�͂ɂ̓_���[�W�Ȃ����ł��B ���̎ʐ^�F�@ ��~���̍Œ��A�v��ʃz�b�g�������Ƃɏo��܂����B �K���X���ɂԂ��������W�����A�ڂ̑O�̐V��ɗ����Ă����̂ŁA����ĂďE���グ�āA�����̐����ɓ���Ă��炭�l�q���݂邱�ƂɁB �Ƃ��낪�A�����̊Ԃɂ����𐁂��Ԃ��ă~�J����˂����Ă���B �Ȃ���ɂ����������Ă��ƁA�����������Ŕ�яo���Ă����܂����B �ǂ����A���̃~�J����H�ׂɂ����ɖ߂��Ă��邱�Ƃł��傤���A���x�͏��ɔ�ׂ惁�W������B |
||
| �@�Ȃ��悵�̃q���h���ƃ��W�� �����O�ɂ́u���̒��v�Ɏw�肳��Ă������W���ł����A�ŋ߂͂߂����菭�Ȃ��Ȃ�A�����Q�H�ł���Ă��Ă͏㉺�ɕ���ŐH�������Ă����܂��B �q���h��������ƁA�P�H���K���Ȃ�����A�T�̖őҋ@���܂��B ���W���������Ȃ����̂��A�q���h�����キ�Ȃ����̂��H�@���ʂ̓q���h�����߂Â��ƁA���W�������̓p�b�Ɣ�ї����Ă����̂��A���̊Ԃɂ����ǂ��Ȃ��Ă��܂����B �A���A�q���h���͑�����鐔�H������悤�ŁA���̃q���h���̎��͈�Ăɔ�ї����Ă��܂��悤�ł��B�@���̃q���h�����������ʂɃ��W�������ɗD�����̂����m��܂���B �摜�N���b�N�Ŋg�� �@�����́A45�N�Ԃ�̑��A�X�b�|�����������~�������āA���Ƃ��~�J���ɂ��ǂ蒅�����悤�ł����A������Ԗ��̏�̃��W���́A�����K���ɐႩ�����ł��B |
||
| �@�����X�J�C�c���[�������� ��2�W�]��L�̉��[�������Ă���̂ŁA��400m�ʂ���オ�����Ă���悤�ł� �o�ዾ�̕����悭������̂����A�����̃f�W�J�����Ƃ��̒��x�ɂ����f��Ȃ��̂��c�O�B�@ ����Google�}�b�v�̋������������Ă݂�ƁA50�L����Əo���B �����炭�~�̊Ԃ����̂��ƂȂ̂��낤���A�V�C�̂������̊y���݂�������܂����B�@�@�摜�N���b�N�Ŋg�� |
||
| �@��Â�Ȃ�܂܂ɁE�E�E�k�R����� �@�L���ȁu�k�R���v���v���Ԃ�Ɏ�ɂ��āA243�i������ƓǂݏI�������A�Z�������ǂ�Ȃ���Ȃ̂ŁA���������悤�Ȕ���Ȃ��悤�ȁH�@���Ɖ��ǂ߂Ε�����悤�ȋC�����邪�E�E�E�B ���i�́u��Â�Ȃ�܂܂ɁE�E�E�v�Ƃ́A�u�q�}�ɂ܂����āv���x�Ɍy���������Ă������A�Z�����������ăn�b�Ƃ�������B ����ł��u�k�R�ȁv���u�g�[���i�v�Ɠǂނ��Ƃ�m��A�c�ɂ̕������v���o���B�@ ���c�قŁu�Ƃ��ˁ[�v�Ƃ����̂�����A�u�₵���v���́u�ǓƂŎ₵���v�Ƃ����Ӗ������A���c�قɂ͋����Ƃ̉e�����傫���ƕ����̂ŁA���̕����̌����A�u�k�R�v���炫�Ă���̂ł́H�Ɗ������� �ǂ����낤���H�@ �摜�́A��g���X�@�V���k�R���i�����E���lj��搶�Z���j�����p �@�@�摜�N���b�N�Ŋg�� |
||
| �@�p�\�R���̃g���u�� �E�p�\�R���͉Ɠd��������������Ȃ��Ȃ��Ă������������A�g���u������������Ƃ�͂�Ɠd�ł͂Ȃ����Ƃ�Ɋ����܂��B �E�l�p�Ƃ��āAWin95,98,XP�ƌo�����Ă������A���C�ɓ���̂w�o�}�V�������ɑ剝�������邱�ƂɂȂ����B �E�C����p��������ɂ͔N���������߂��Ă������AOS�̃A�b�v�f�[�g�����o���Ȃ鍠�Ȃ̂ŁA�����ւ��͌������Ă͂����̂����E�E�E�B �E���������ւ��ƂȂ�ƁA�莝���̃\�t�g�Ŏg���Ȃ��Ȃ���̂����邱�Ƃ�������A�����̔�p���l����ƂȂ��Ȃ����f�����Ȃ������B �E2013�N1���A����XP�}�V�����_�E�����č����Ă��鎞�A��ʂ͏��������i15.4�C���`���C�h�^�j�A�n�f�W�t��VALUESTAR Vista���f���̃p�p��������Ă��炤�B �E����ɍăC���X�g�[�����Ȃ���A�f�B�X�v���C��傫�����̂ɑւ��悤�ƒ��ÓX����邤���ɁA19�C���`���C�h�^��VALUESTAR�̎荠�Ȓ��Õi���������B �E2008�N�������f���ŃN���[�j���O�ς݂Ƃ��ŁA�X���ł̗����グ�e�X�g�����\�b���x�������̂ŁA����Ȃ玩���̍�Ƃɂ͏\�����낤�ƁA�R���ԔY��Ŕ����Ă����B �E���̏������������́A���^�̃e���r���f���Ȃ̂ŁA�����͘^���Q�[����p�Ƃ��Ďg�p���Ȃ���A���C�����g���Ԃ������̃o�b�N�A�b�v�@�Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃɂ����B �E�����Ƃ����Â�Vista�Ȃ̂����A�ǂ����Ă�XP�̈����₷���ɖ����ɖ���������͎̂��������Ȃ̂��낤���H XP�̃n�[�h�͊m�ۂ��Ă���̂ŁA�ǂ��炩XP�}�V���ɂ��Ă��܂������ȁB �p�\�R���̃g���u�������͂����灨�@�p�\�R���g���u���@ |
||
| �@���������G�A�R�������E�E�E �t�@�����[�^���Œ肵�Ă����x�����i�̑����������ĕ��ꗎ���A���Ƌ��ɔߎS�Ȃ��ƂɂȂ��Č̏Ⴕ�Ă��܂��܂����B�i2001�N���@�g�p10�N�j�@�����̕��ʂ��̂悢�ꏊ�̎��O�@�Ȃ̂ŁA���̒ɂݕ��ɂ͔[�������Ȃ����A���Ƃ����O�ŏC���ł������Ȃ̂ň���S�B �K��������C���i������ł��A�����̎��t�������H�������Ė����ɏC�������B ���C�������� ���ʂ͋╲�h���ŕ�C���A�{���g�̗����ɂ̓t���b�g�o�[�ĂăK�b�`���Œ肵���̂ŁA����Ŗ��R�N�ȏ�͎����Ƃł��傤�B ����ɂ��Ă��A���̃G�A�R���̃G�l���M�[�������(COP)�����߂Ē��ׂĂ݂�ƁA��[��2.78 �g�[��3.99�Ƃ̂��ƁB�ȃG�l�̐i���݂ł́A���̔{�ȏ�̌�����������O�ł��̂ŁA����̌̏���_�@�Ɏv�����Ĕ��������������ǂ������̂��ƁA�d�C��̒l�グ���ɂ݂Ȃ���V���ȔY�݂ƂȂ�܂����B |
||
| �@�K�^�̒lj��ۏT�[�r�X �i�v���Y�}�e���r�j �v���Y�}�́A�g�p�S�N�ʂ܂łُ͈�͖��������Ǝv�����A5�N�ڂɓ������ӂ肩��A�ʐ^�̂悤�ȏǏ�ʂ̍����ɖڗ��悤�ɂȂ�A�A���e�i�̐����ȁH�Ƃ��A�掿�̒������ȁH�Ƃ� �F�X����Ă݂����A����ɉ��P���Ȃ��̂Ń��[�J�[�ɑ��k�����Ƃ���A�����f�f�ɖK�₵�Ă��ꂽ�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�摜�N���b�N�Ŋg��j �@�Z�p�҂����꒲������������ʁA�����A�蒲���ƂȂ������A�e���r�w�����ɂR�N�lj��ۏi�ƐӂP���~�j�ɉ������Ă����̂ŁA�p�l����Y�h���C�u���������Ă��Ɛӂ̂P���~�����̕��S�ōςނ̂��L�������B �w�����ɂ́A�Q���~�̒lj��ۏؔ�͒ɂ��Ȃ��Ǝv���Ă������A�������Ă��Ė{���ɍK�^�ł����B�@ ���Ȃ݂�50�C���`�̃p�l����Y�h���C�u�̕��i��A�o���Z�p����21���~���̐����ƂȂ�Ƃ���Ȃ̂ŁA���ꂪ�lj��ۏ؊����̐��U�����悾������Ǝv���ƃ]�b�Ƃ��܂��B ����ɂ��Ă��ASED�e���r�ɖ���������܂��L���m�����`��B�@ �@ |
||
| �@�K�^�̃N���[�o�[ �A���Ē��ׂĂ݂�ƁA�l�t�ɂ́u�K�^�v�̈Ӗ�������Ƃ��B ���̂����v���������̂��A�ŏI���́u���̂��ݎ��v�ł́A���\�C�������ꂽ�}�X�̒��ɁA�P�C�������������u�⋛�v���Q�b�g���܂����B �݂�Ȃ�30���ȏ�A�Ō�̍Ō�܂Ō�����Ȃ��������������̂ŁA�m���ɏ����ȍK�^�ł����B �i���[���I�[�o�摜�́A���т����₽�����ɂ����C�Ȏq���B�j �ߊl�������́A�X�^�b�t�����Ă��ɂ��Ă���āA�݂�Ȃł��y���l�B �N���[�o�ɂ́A5�t�E6�t�E7�t�E8�t�Ȃǂ���������Ă���悤�Ȃ̂ŁA���̎��͕K���u��N�W�v���Ă����܂��傤�l�B |
||
| �@�����̂��h ���Ԃ̃K���X�˂ɂԂ���̂ł͂Ƃ��������ŁA7�`8�H�̏������������������Ȃ����ь������i�Ƀr�b�N����������B �܂�Ńq�b�`�R�b�N�f�� �u���v�̌��i �K���X�˂��J���Ă�������l�q���Ȃ��A�ώ@���Ă��邤����2����̒�̃��~�W�Ɏ~�܂�n�߂��B �悭����Ɩ����ق�̎q�������Ɍ�����B ���X�A�e���炵�����z�o�����O���Ȃ��牽�������ڂ��ŗ^���Ă����B �ӂ�̓X�b�J���Â��Ȃ�A�V���b�^�[�����낵�Ă�������l�q���Ȃ��A�ǂ���炱���Ŗ���߂����C�炵���B �߂��ɗт�X�͈�t����̂Ɂu����ȏ��ő��v�Ȃ́v �ƌ��������Ȃ�䂪�Ƃ̌��֑O�̒����ł����B �t���ς̉e�ɂ������������A�������Ă͉��z�Ȃ̂ŁA���̂܂܂����Ƌx�܂��邱�Ƃɂ����B ���x�ݏ��������E�E�E�B ����ɂ��Ă������C�ɓ������̂��ˁE�E�E�B���������܂�ɂ���̂��ȁH �NjL�F�@�����������Ɨ[���ɑ吨�i7�H�j����Ă��āA���܂��Ă����܂����B���x�Q�̑������܂藈�Ă���A�l�q���������߂Ă��܂����B���[���I�[�o�摜�́A���̎��̏��������A�G�i�K�̂悤�ł��B �X�ɁA3���ڂ�4���ڂɂ������悤�ɂ���Ă��āA��x�͉��H���H���x�߂��̂ł����A�݂�Ȑe���̌��ǂ��Ĕ��ł����Ă��܂��A���܂�ɖ߂��Ă͂��܂���ł����B�@���̂܂ܖ����ɐ������āA�����щ��Ȃ���������������Ă���邱�Ƃł��傤�B �@�@ |
||
| �@�����H�ƊF�����H �@�����ɂ��̓܂������グ�Ă���ƁA���z�̌����_�Ԃ��炩�����ɂ��ڂ�邱�Ƃ�����A����Ȃ�R���p�N�g�f�W�J���ł����_���V�R�t�B���^�[�ɂȂ�A���Ƃ��B�e�ł��邩���Ƒҋ@���Ă�����A�قڋ��̎��ɋ��R�B�e���邱�Ƃ��o���܂����B�����Ă��Ȃ��̂ɂ��ꂾ���B�e�ł���Α喞���ł��B �@������x�ƌ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���ƁA�啪�O�Ɍ������Ƃ̂���F�����H�̂��Ƃ��v���o���A�Â��ʐ^��T���o���Ă݂܂����B �i�摜�N���b�N�Ŋg��j �@�X�C�X�𗷍s���A���[���b�p�ō����u������]�ޒ��V�����j�i�t�����X�j����3842���[�g���̓W�]��ɏ������Ƃ���A���R�ɂ��u�F�����H�v�ɑ����������Ƃ�����B �@�x�m�R��荂��3842���̉_�̏�́A�����ɂ��r�ꂽ�V�C�Ō������K�X��������Ԃ����A�݂�Ȏ��X�_�Ԍ����郂���u�������F�����H�ɑ勻���������B �@���̎����V�R�t�B���^�[�̂��A�ŁA�f�W�J���ƃr�f�I�ł��Ȃ�B�e�ł����̂����A��Ƀp�\�R���̃g���u����JPG�f�[�^�������Ă��܂����B ���ɉ�����������Ă������̂��X�L���������̂����ʐ^�i�����������j �̐S�̊F�����H�̎ʐ^�ŗB��c���Ă���̂��A���s�L��Word�����ɓ\��t�����ʐ^�݂̂Ƃ������e���ł����A���̎ʐ^�������ɓ\�낤�Ƃ���Ƃ��܂������Ȃ��̂ŁA���Ȃ����s�L�̈ꕔ���f�ڂ��Ă����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�C�X ��������̗� .pdf |
||
�@����Ȃ� Picture Mate 300 (PM-300)
�@NTT�������^���������Ă��������ۂ͉��P���ꂸ�A�Ă��t������菜�����߂Ƀr�f�I�p�^�[�����P���ԗ��������ɂ��Ă���Ə����Ă��ꂽ�B �@���Ƀt�@�[���E�F�A�̍X�V���I�����Ă���PM-300�͎g���������Ȃ��Ɣ��f���ANTT�Ղ���M-ISP200�`���[�i�Ɍ_��ύX���āA����ƑS�ĉ�������B �@����ɂ��Ă��A����PM-300�͗]�蕁�y���Ȃ������悤�ŁAWEB��ɂ��g���u������w�nj������Ȃ����A�J�X�^�}�[�T�[�r�X�̐l���u���߂ĐG��v�݂����Ȃ��Ƃ��Ԃ₢�Ă����B �v���Ό�TV�̈�ԏ����̃`���[�i�Ȃ̂��B�@�L�O�Ɏc���Ă��������������A�����^���i�Ȃ̂Œ��J�ɔ��ɋl�ߒ����ĕԋp���܂��BGood by PM-300 |
||
| �@����ꌻ���|�X�g�i�X�֍��o���j �����|�X�g�̂��ƂׂĂ݂�ƁA���\�}�j�A������̂ɂ��r�b�N���ł��B �|�X�g�́A�����ɂ́u�X�֍��o���v�ƌĂԂ����ł����A�ی^�̓S���|�X�g�́A���a24�N����g���n�߂��悤�ŁA�X�֍��o��1�������̌`�ł��B�@���̌�A1���^�͏��a45�N�Ɋp�^�ɕύX����A�Ȍ�p�^�͌��݂Ɏ���14���^�܂Ői�����Ă���悤�ł��B �@�ς��|�X�g�Ƃ����A�X�C�X�̃����O�t���E���b�z�i3454���j�̎R���X�ǂɂ���A����Ɠ����Ԃ��|�X�g�ɂ��r�b�N���������Ƃ�����܂��B�i���{�̕x�m�R�T���ځi2305���j�̊ȈX�ǂƎo����g�����Ă���j�@ ��̕�����Ȃ��̂́A�a�̎R�̊C�̒�ɐݒu���ꂽ�Ԃ��|�X�g�ł��B�_�C�o�[�̂��߂̂悤�ł����A2011�N�ɂ�3���ʂ�˔j�����Ƃ�������A�^�ʖڂȃ|�X�g�Ȃ̂ł��B�@�@�@�C��|�X�g�͂������� �ʐ^�N���b�N�Ŋg��@�@�@ |
||
�@�}�W�b�N�X�N�G�A���v���o���܂����B
���̓V�˂̐����V�т̂悤�ȃ}�W�b�N�́A�ĊO�m���Ă��Ȃ��̂����m��܂���B�ɂԂ��ɔ`���Ă݂Ă��������B �������N���b�N�@���@magic squer.pdf |
�@�}�W�b�N�X�N�G�A���������
�@���̎�̃}�W�b�N���ŋ߂͌������Ȃ��Ȃ����C�����܂����A���������܂肫���Ă��āA�ÓT�I������ł��傤���B �c�A���A�߂����������ɂȂ�Ƃ������̂ł����A����ȊO�Ɏd�g�܂�Ă���i�]��m��A�V�˂̗V�ѐS�Ɋ������܂��B �������N���b�N�@���@magic squer_3.pdf |
| �@���w����[�ł���` �S���ɂ��Z�z�̕�[��͎c���Ă���悤�ł����A�]�ˎ���̘a�Z�̂悤�Ȃ��̂ɏ��߂Đڂ��܂����B ��̓V�˂������A������������[�������Ȃ�܂��ˁH �u�z�[�m�[�H�v�E�E�E�uOh No !�v �Ɖ]���ł��傤�ˁA�����ƁB �ʐ^�N���b�N�Ŋg�� |
||||||
�@�n�f�W�����낢��
�E�ʐ^�F�@�䂪�Ƃ̕W����190���゠��A�����^���[�܂ł̎��E���ǂ��̂ŁA�ʐ^�̂悤�ȃR���p�N�g�^�Ŏ����ł��Ă��܂��B�A���A���̃^�C�v�����t���Ă��邨��́A���ӂɂ͑S���������܂���B�R���p�N�g�ȏ�ɍ����\�ŁA�����Ă����̂ɂȂ��H�B ���̑��C�ɂȂ邱�ƁA�u�݂�ȉ��ł���Ȃɒ����x�����g���Ă���̂��H�v�Ƃ����^��ł��B�ݒu�����d�C������Ȃ̂ł��傤�A�����ƁB�@�@�@�@�ʐ^�N���b�N�Ŋg�� |
||||||
| �@����33�ω����@���J�� �J�����Ċ�ɂ���ߎS�ȉ��E�ɁA�ω��l�̎��߂͂Ƃǂ��̂ł��傤���B �k��Ȃ��~���Ƃ��Ă��������܂��悤�ɁA�u�얳�ϐ�����F�v�Ǝ�����킳���ɂ͂����܂���B �ʐ^�N���b�N�Ŋg�� |
||||||
| �@���Ă������Ƃ́E�E�E �d���Ȃ���B�̓c�ɂ��瑗���Ė�炢�A�J���Ă݂�ƁA�Ă̗l�q�������ꂽ�����̂ƈႤ�B�������Ƃ�����悤�Ȗ����悤�ȉ��F���F�����Ă���B �ꗱ�������Ă݂Ă����܂ʼn��F���悤�ȁA�ÕĂ��ȂƂ��F�X�B�ꎞ�̒p�Ǝv���ēd�b���Ă݂�ƁA���Ă���Ƃ̂��ƁB�@ �@�_�Ɛ��܂�̔��̎������A�ƂĂ���Ȃ��Ȃ����o�����ł����B���l�̋�J���v���ƁA�{���ɐ\����Ȃ����Ƃł����B �ʐ^�N���b�N�Ŋg�� |
| �@�z�[���C�������̊m���Ƃ́E�E�E ���B �����ɂ���x�����o��������܂����A���̓����T�ɂ��ƃA�}�`���A�ł́A 1/8,000�`1/14,000�̊m���A���E���h�ɂ���2,000�`3,000���E���h ��1��ʂ̊m���������ł��B���̊��ɂ́A�o���҂����ɂ����Ƃ��銴���� ���܂��̂ŁA�R�[�X�⋗�������ɂ���Ă̘b�̂悤�ł��B �v���̏ꍇ�ɂ́A���R�Ȃ���A�}�`���A��3�{�ʂɊm�����オ�邻���ł��B �����̏ꍇ�A�S���t���n�߂�21�N�ځA172���E���h�ڂ̍K�^�ł����B30 ���~�̕ی����́A�K�^�߂����Ƃ��Ƃ��Ďg���ʂ����܂������A�m���� �炷��Ɠ�x�ƂȂ��o�����̂悤�ł��B �ʐ^�N���b�N�Ŋg�� |
| �@�h�g���Ȃ߁h���āA����ȂɉԂ��E�E�E�H�H ���܂��B���N�C�p���p���ƉԂ��炢�Ă����̂͋L ���ɂ��邪�A���N�͑�������悤�ȋC�����܂��B ��������܂����ƁA�S���Ԃ�t���Ȃ������������� ���āB�g���Ȃ߂���ނ����邻��������A���m�� �Ȃ߂̂悤�Ȃ��̂ƍ��A����Ă����̂��낤���H�@ ���̔����Ԃ��I��鍠�ɂ͉��̃T�c�L�������� �Ăɍ炫�o�����Ƃł��傤�B�@ �ʐ^�N���b�N�Ŋg�� |
| �@���܂��畷���Ȃ��h�_�u���i�b�g�h�̂��� ��Ă�����ł��傤�B ��a���̌����̓i�b�g�ɂ���܂��B�_�u���i�b�g�ŃK�b�`���Œ肵�Ă��܂��A �����i�b�g�̕�����ɂȂ��Ă���̂���a���̌����B �_�u���i�b�g�@�́A ����ɏo��悤�ɂȂ��Ă���A����邱�Ƃ������Ǝv���܂����A��������� �ĊO���������ŋ����Ă���ꍇ�������̂����H �i���������ЂQ�N�ڈʂɑ��y�ɋ���������Ƃ�����܂��B�j ���^�C����A�H��ݔ��Ȃǂɏo���肷�邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�ڂɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂������A���Y���C���̗���ݔ��ȂǂŎd�������Ă���ƁA�u�댯�ȃ_�u���i�b�g�v�ɏo���킷���Ƃ�����܂��B �i����̈����ꏊ�Ń��b�N��Ƃ��邱�Ǝ��Ԃ�����Ɍ�����ꍇ�ȂǁA�@���ʁA���ォ��ˑR�i�b�g���~���Ă���ȂǁA���̎�̃_�u���i�b�g�������悤�ł��B�j �]�k�F�@���b�N�i�b�g�̗����h�~��Ƃ��āA�O�p�f�ʂ̃��C���[���{���g�̓��ɃK�b�`����������d�l������܂� �����A�ŋ߂͂����ƗD�ꕨ���l�Ă���Ă���悤�ł��B �ʐ^�N���b�N�Ŋg��@�@�@�@�@�@�@�@�ڍ׃����́��@�����畷���Ȃ��_�u���i�b�g |
| �@�X�C���R�[�` �X�C���R�[�`�iSWIMCOACH�j�@980�~���̃X�F�[�f�����̐����������� ����́A�������Ɖj���ɍs���̂��ƂĂ��y�����̂ŏЉ�Ă݂܂��B �����ăX�C���R�[�`�̉҂ł͂���܂���B 4�A5�A8�̑������̓��A4�͑S���j���܂��A���̐����̂��A �ŁA�����ւŃv�J�v�J�̒��ԊO��ɂȂ炸�ɁA3�l�őΓ��ɗV�т܂�邱�� ���o���A3�l���ƂĂ��y�������ł��B ����ȃO�b�h�A�C�f�A���i���A���{���ɂȂ��̂��s�v�c�ł��B�@ ��̌^�^�C�v�ł͂Ȃ��A�W���P�b�g�^�C�v�̕��Ȃ炠��悤�ł����A�X�b�|���� ����̎��Ⴊ����悤�ŁA�ߏ��̌��c�����v�[���ł͒��p�֎~�ɂȂ��Ă� �܂��B�@�W���P�b�g�^�ł����������p����Έ��S�Ȃ̂ł��傤���A���p�~�X�� �ǂ̌����̂��߂ɁA���̗D�ꕨ�܂ňꏏ�ɋ֎~�ɂȂ�̂͐S�O�ł��B ���A�ŋ��N���炨�q����ɂȂ��Ă��܂������A�������c�̉��O�v�[���ɍs�����Ƃ���A���\���Ȃ��Ƃ������ƂŁA �������p�����Ă݂܂����B �Ď���������A�u�ȂA���̎q�v���Ċ�����Ă܂����B��������̔��A�������Ґ���ɒ��킳���Ă��A����� �����畂���オ���Ă��āA�M���S�z�͑S������܂���B �ʐ^�N���b�N�Ŋg��@�@�@�@�@�@�@�@ �@�X�C���R�[�`�𒅂�������͂������N���b�N |
|
| �@���h�_���i���h����j �@���R�j��ƕ\���̏]���^�̍��h�_���Ƃ����ƁA�d�͎��R���N���[�g���ŁA����̒��������ꕔ�|�R�b�Ɖ���ł���A�������ӂ�̐����������琅������o���Ă���B����̒��́A����͂�t�ɕ����A���L������܂萅�����邩�A�܂��͓y�ɖ��t�ɕ����s�����Ă���B���̒��x�̂��Ƃ����m��Ȃ������B�i�������̋�����f�����Ă��܂��Ȃǂ�����j �@���t�ɂȂ������h�_���́A�y�ւ�������A���̏㗬�ɍX�ɍ��h�_���葱����̂��퓅�炵���A�R�̒���܂Ŏ��X�ɑ����Ă��I���Ȃ��̂����h�Ƃ������Ƃ炵���B �ߔN�A���h�_���ɂ����j������悤�ɂȂ��Ă��邪�A����ȃA�C�f�A�œ����Ă���Ƃ͒m��Ȃ������B �����̏d�͎��R���N���[�g�̉�����A�X���b�g�ɐ���P�H���Ȃǂ�����Ă���悤�ł���B �R����̓y������ł���A�����̉͐��C�ɂ��{������������A���������Z�݈Ղ��Ȃ�炵���B ����ƂāA�W���ɋ߂����h�_���ł́A�X���b�g�^�͏Z�����s���������炵���A�]���^�̐��𗭂߂鎮�̂��́i�s���ߌ^�j�ɂȂ�炵���B�@���ɁA���̎ʐ^�̉���100���ʂɂ������莮�̍��h�_���������Ă����B �����뎩�R�͑z��O�A���N�̂悤�ȍ��J�̎��A���̍��h�_���̗l�q�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���H �����̂�����́A�u���h�_���v�ȂǂŌ������Č��ĉ������B���R�ЊQ�̑��������A�F�X�l���������܂��B |