![]()

�����Q�O�N�X���c����@
�@
�@�@�@�@�@�����Q�O�N�x��ʉ�v��\�Z�ɌܐF��L��
�@�@�@�@�{�ݑg���^�c���S���P���V�A�V�X�S���V��~�̕�
�@�@�@�@���\�Z���v�コ��܂����B
�@�@�@�@�@���̂��Ƃɂ��āA�c�����玿�₪�W�����A��
�@�@�@�@�܂��܂ȋc�_���W�J����܂����B
�@�@�@�@�@���̕�\�Z�́A�ܐF�䐹���ɖ�T�O�O����e
�@�@�@�@�̒��ԏ�����݂�����̂ŁA��ɍw�������U����
�@�@�@�@�̈ꕔ�i��X�O�O�O�j�����Č��݁A���݂�
�@�@�@�@�钓�ԏ�͏����i�I�m��s�S�悪�Q�����j�ɔ���
�@�@�@�@�������݂̗\��n�Ƃ��Ďc���Ƃ������̂ł���B
�@�@�@�@�@����ɑ��c�����炳�܂��܂Ȏ��^���o�����
�@�@�@�@���������̎�Ȃ��̂قƕ����ďЉ��ƁB
�@�@�@�@�@�P�A�@���ԏ��������Ȃ���O���E���h��
�@�@�@�@�@�@�@�ԏ�ɂ���J�����̂ł͂Ȃ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@�O���E���h�́A�ܐF�䐹�����ݎ��n����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������̂ł���A�v�]�ɂ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł��茻�݂����̂悤�Ɏg�p���Ă���B
�@�@�@�@�@�Q�A�@���݂̃O���E���h�́A������萮������
�@�@�@�@�@�@�@�Ă���A���̊Ԃɂ����N�싅�̃��g����
�@�@�@�@�@�@�@�[�O�̎勅��ƂȂ��Ă��Ė{���ɒn���̂�
�@�@�@�@�@�@�@�߂̃O���E���h�Ƃ��Ďg�p���Ă���̂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@���݂��n���Ƃ̍��ӂɊ�Â��g�p���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���g�����[�O�̎勅��ƂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��āA�g���c��ɂĂ��̈ʒu
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Â����������Ƃ��ׂ��ł́B
�@�@�@�@�@�R�A�@����̒��ԏ������̂ɖ�X�O�O�O�̓y�n������Ƃ������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@���A�Ȃ��U�����w�������̂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@�U���̒n���҂͂W���ŁA�ꊇ���ĂłȂ���Ό��ɉ����Ă���Ȃ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂ł�ނȂ��w�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@����Ȃ�A���̓y�n�̍w���𒆎~���A���̓y�n�i�쑤�̎R�сj���w����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��w�͂͂��Ȃ������̂��B
�@�@�@�@�@�S�A�@���݂̒��ԏ�͏����i�I�m��s�S�悪�Q�����j�ɔ����A�������݂̗\��n
�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��Ďc���Ƃ������Ƃł����A����Ȃ�I�m��s�ɉ������S�����Ă����
�@�@�@�@�@�@�@����悢�o�͂Ȃ����A�܂����ԏꑝ�݂͂��̎��_�Ō��݂�������̂ł͂�
�@�@�@�@�@�@�@�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@�����ԏ�݂��傤�Ƃ���̂͌��݂̒��ԏꂪ�傫�ȑ��V�̏ꍇ���Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�߂̓��H�ɎԂ����ӂ�A�n���̕���A���Q��̕��X�ɂ����f������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̂Œ��ԏꑝ�݂����邱�ƂɂȂ����B�܂��A�I�m��s�S�悪�Q���ɂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă͂��̎��_�ŋI�m��s�����̕��S�����Ă����������ƂɂȂ�ƍl
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����B
�@�@�@�@�@�Ƃ��������^�����킳��܂������A���������ł��������̂́A���̎��^�������c
�@�@�@�@������͂��̈Č��͌ܐF��{�ݑg���c��Ō��܂������̂ł��邪�A�A�����Z�ƂȂ�
�@�@�@�@�A�ꕔ�����g����L��A���̉�v���n�������c�̍������S���@�ɂ�錒�S�����f
�@�@�@�@�䗦�ɓ��R�ւ���Ă��邽�߁A���ꂩ��͂����������ꕔ�����g���Ƃ����ǂ��^��
�@�@�@�@�̉^�c��C�������Ƃ�����ɂ͂����Ȃ��A��͂肻�ꂼ��̋c��ŏ\���_�c������
�@�@�@�@�őΉ����Ă����ׂ��A�Ƃ����O��ɗ����Ď��₳�ꂽ���Ƃł��B
�@�@�@�@�@���́A����̖��ɂ��Ă͓��R�A�ꕔ�����g����L��A���ł����Ă��A������
�@�@�@�@����傫�Ȏ��Ƃɂ��Ă͂��ꂼ��̋c��ŋc�_���A���̌��ʂ������āA�c���
�@�@�@�@�\�̋c���͑g���c��ɗՂނׂ��ƍl���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@����̌��ɂ��ẮA�ꕔ�̑g���c�����玩���������\���ɑg�ݍ����c��ŋc
�@�@�@�@�_���Č��߂����ƂɂƂ₩�������̂͂������������������������Ă��܂������A��
�@�@�@�@�͂��̌��ʂ͑��d���ׂ��Ǝv���܂��A���������A�g���c��łǂ�Ȃ��Ƃ��c�_����
�@�@�@�@���̂��A���Ȃ�����ł͌��ʂd���Ȃ�����{��c�ł̎��^�͂�ނȂ�
�@�@�@�@�̂ł͂Ǝv���܂��B
�@�@�@�@
�C��s��������ۑ�@
�@
�@�@�@�@�@���̂��ѕ����Q�O�N�x�̋c��s���܂����B
�@�@�@�@�@����̎��̋c��́A�\�Z��c��ł̏o��
�@�@�@�@���A���̈�ʎ���Ȃǂ̓z�[���y�[�W�Ō��J����
�@�@�@�@����܂��̂ŁA���C��s�����g��ł��鎖�Ƃ�
�@�@�@�@���ꂩ��̉ۑ�ɂ��ĕ��܂��B
�@
�@
�P�A�@�C��s�����̌��đւ����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�����P�X�N�R���c��ɒ��Ɍ��݊�����Ă����
�@�@�@�@���������܂����A���̊���͏����̒��Ɍ��݂�
�@�@�@�@�����Ċ����ςݗ��ĂĂ������̂ō��N�x�͂P���S
�@�@�@�@���~�̗\�Z���v�コ��Ă���܂��B
�@�@�@�@�@�s���ǂ̐����ɂ��܂��ƁA�s�������݂ɂ͍���
�@�@�@�@�⏕�����t���Ƃ������x�����S���Ȃ��A���ׂĎ��O�ł܂��Ȃ�
�@�@�@�@�Ȃ���Ȃ�Ȃ����ߌ��݂̎����Ƃ��Ă͂P�O�N�悩�A�P�T�N��ɂ͕K�����đւ��Ȃ�
�@�@�@�@��Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂����z���ď����ł������߂Ă��������Ƃ̂��Ƃł���܂����B
�@�@�@�@�@���Ȃ݂Ɍ����ɂ͔��ɌÂ��k�x�U���x�̒n�k�ɂ͑ς����Ȃ��Ɨ\�z����Ă���A
�@�@�@�@�ϐk���C���o���Ȃ��L�l�ł��A���͎s�������đւ��ɂ��āA�s���̊F�l���獡�͏\
�@�@�@�@���ȗ����������Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A����C�n�k�̂��Ƃ��l����A���̒��ŋ�
�@�@�@�@������吨�̐E����A�s������K���s���̊F�l�̈��S���l�����ꍇ�����������
�@�@�@�@�đւ���]��ł��܂��B
�@�Q�A�@�C��s���a�@�̌��đւ����ɂ��āB
�C��s���a�@��{�\�z(��)�����\����܂����B
�����Q�T�N�ɊJ�@��
�@�@�@�C��s���a�@�́A���݁A�a�����A���167���i�ғ�137���j�A�f�ÉȂ͓��Ȃ��͂���10�f��
�Ȃ����f�Â��s���Ă��܂��B
�@�@�@�C��s�̒��j��Ë@�ւƂ��āA�s���̈��S�ƌ��N������Ă���A�s������́A����Ƃ��s
�@�@���a�@�ł̈�ÃT�[�r�X�̏[����]�ސ��������B
�@�@�@�������Ȃ���A���a38�N�̖{�ٌ��݂�����ɒz��40���N���o�߂��A�{�݂̘V�����A��襉�
�@�@�������ɂȂ��Ă���B���{�݂͑ϐk���̖��͂������̂��ƁA���҂̃A���j�e�B�⌻�݂�
�@�@��ËZ�p�����ւ̑Ή��A���S�Ǘ��A�Ɩ������̌����}�邱�ƂȂǗl�X�ȓ_�ŁA���߂���
�@�@��ÃT�[�r�X�̒�����ȏƂȂ��Ă���A���Ґ��̌����A�o�c�̈����ւƌq����
�@�@����B
�@�@�@���̂悤�ȏ̒��A����A�s���a�@���A�s���̗v�]�ɉ����A�C��s�̒��j��Ë@�ւƂ�
�@�@�āA����Ƃ��p�����Ēn���Â�W�J���Ă������߂ɂ́A�V�z�ɂ��{�ݐ������s���Ă���
�@�@���Ƃ��s���Ƃ�����B
�@�@�@�s���a�@���A����Ƃ��A�n��̒��j��Ë@�ւƂ��āA�s�����K�v�Ƃ����Â���Ă�
�@�@�����߂ɂ́A�w�s���a�@�̖����̖��m���x��}���Ă������Ƃ��ł��d�v�ƂȂ�B�s���a�@���A
�@�@�����镪��ɂ����Ċ����Ȉ�Â����߂邱�Ƃ͍���ł���A�o�c�̎��_������K���łȂ��B
�@�@�n���Ì��̒��ŁA���߂Ďs���@�a�@�̖������������K�v������B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA���̂قNJC��s���a�@��{�\�z(��)�����\����܂����A���̎�Ȃ��̂���
�@�@��܂��B
�@�@�P�j�V�a�@���ݗ\��n
�@�@�@�@�@�C��s�͗\��n�Ƃ��āA�W���X�R�Ւn�ƊC�쎄�����Z�����n�Ƃ��Č������Ƃ��Ă�
�@�@�@�@�܂����A���́A�����炭�W���X�R�Ւn�Ɍ��܂�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@�@�Q�j�a����ʂƕa���K��
�@�@�@�@ �@�a�����
�@�@�@�@�@�@�@���}�����a�����܂ވ�ʋ}�����a�@�i��10���l��̕a�����F�S������707���A�C
�@�@�@�@�@�@��s448���j�Ƃ��A���A�×{���i�ݑ�E�{�݁j���̋@�\�ɂ��ẮA������
�@
�@�@�@�@�@�@���ڒS���Ă���n��̈�Ë@�ցE�����{�݁E���T�[�r�X���Ə��Ƃ̘A�g�ƌ��
�@�@�@�@�@�@�x���@�\�̏[����}���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����������A�s���Ƃ��č\�z���Ă�
�@�@�@�@�@�@�����Ƃ��}���ƂȂ��Ă���w�n���P�A�̐��x�̘g�g�݂̒��ŊC��s���a�@
�@�@�@�@�@�@�i�n��A�g���E�K��Ō�X�e�[�V�����j���n��A�g�̒��j�ƂȂ�A���̖������ʂ�
�@�@�@�@�@�@���Ă������Ƃ��ł��d�v�ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@ �A�a���K��
�@�@�@�@�@�@�@�V�a�@�̊Ō���10�F�P�Ƃ��A�K���a���K�͂́A��ʕa���i���}���a���܂ށj
�@�@�@�@�@�@�@50���~�R�a����150��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���Ȍn�a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�O�ȁE���`�O�Ȍn�a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�����E���}�����E�J���a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@ �B�f��
�@�@�@�@�@�@�@�@���ȁ@�A�O�ȁ@�B���`�O�ȁ@�C�����ȁ@�D��A��ȁ@�E�w�l�ȁ@�F��ȁ@
�@�@�@�@�@�@�@�G���@��A�ȁ@�H�畆�ȁ@�I�����ȁi�y�C���N���j�b�N�j�@�J���ː��ȁ@
�@�@�@�@�@�@�@�K������Z���^�[(�������Z���^�[)
�@�@�@�@�@�@�@�����f�Z���^�[
�@�@�@�@�@�@�@������Z���^�[�i�������Z���^�[�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�ߔN�A�d�q�������̕��y�ƂƂ��ɓ����������̏d�v���͂܂��܂����債�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��킯�㕔����������ǂɂ��Ă͌��������A�Ώۊ��҂Ƃ��������Ă���A�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏d�v�Ȍ�������ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂������펾���ł͌����ƂƂ��ɓ���������p�������ɍs����P�[�X����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������A�V�a�@�ɂ�������̈�̒��̈�Ƃ��āA���ȁA�O�Ȃ��A�g����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̏�����Z���^�[�i�������Z���^�[�j��ݒu����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E������n�������ݔ����[�����A���A���ŁA�ŋۑ�����s���X�y�[�X�Ɛݔ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������ɐ�������B
�@�@�@ �@�@�@ �E������̉Ɗ��ҊĎ����u��ݒu����B
�@�@�@�@�@�@�@���f�Z���^�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�s��(���N��)�ƈ�̂ƂȂ����ݒu���������A�s���̕ی��t�A�Ǘ��h�{�m����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���f�@�Z���^�[�Ƃ̘A�g�A���̋��L����}������I�ȉ^�c���s���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���茒�f�A����ی��w�����̏[����}��ƂƂ��ɁA���p�҂̃j�[�Y�ɑΉ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������A��h�b�N�E�h���h�b�N�𒆐S�Ƃ������f���j���[�̐ݒ���s���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�s���̗��������߂邽�߁A���݂̋x�����f�̊g�[����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���茒�f�A����ی��w���A�l�ԃh�b�N�A�e�킪���ΏۂƂ������f�ɂ��āA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�@�L�A�s��A�z�[���y�[�W����ʂ��Ďs���ɂ��L����M����B
�@�@�@ �C�V�a�@�̌��݂ɌW��A�������ݎ��Ɣ�B
�@�@�@�@�@ �E�V�a�@���݂ɌW�鑍��p�́A4,300,000��~�ł���B
�@�@�@�@ �D�V�a�@�̌��݃X�P�W���[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�V�a�@�̌��݃X�P�W���[���͈ȉ��̒ʂ�Ƃ��邪�A���a�@�̏i�{�݂̘V��
�@�@�@�@�@�@�@���A�ʂ����ׂ���Ë@�\�y�ьo�c���P�̍���j����A�ł�������肱�����
�@�@�@�@�@�@�@�����J�@���ׂ��w�͂��邱�Ƃ��]�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E��{�v�F����21�N10���`����22�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���{�v�F����22�N�S���`����23�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���ݍH���F����23�N�S���`����25�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�a�@�J�@�F����25�N�S��
�@�@�@�@�@�@
�@�R�A�@�C��s�h�Б�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�C��s�̖h�Б�͖{�N�i�����P�X�N�j�R���ɍ��肳�ꂽ�C��s�n��h�Ќv���
�@�@�@�@�@�����đȂ���Ă������ƂɂȂ�B�n��h�Ќv��ł́A�����ł��ǂ��ł��N��
�@�@�@�@�@�肤��ЊQ����s���̐����A�g�̋y�э��Y��ی삷��ƂƂ��ɁA�h�Ђ̂��߂̔���
�@�@�@�@�@�����������[�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���̂��߉ߋ��̑�ЊQ�����P�Ƃ��A�{�s�̒n
�@�@�@�@�@���I�����A����A��A�Љ�\���̕ω������l���ɓ���A�s�A���y�ъW�@��
�@�@�@�@�@�Ǝs������̂ƂȂ��čЊQ�ɋ����܂����𐄐i���邱�Ƃ��d�v�ŁA���̂��߂ɂ́A
�@�@�@�@�@�s�̖h�Ў{��̕�������A�g�߂Ȗ��ł���ЊQ���̖h�Б̐��Ȃǖh�Б���
�@�@�@�@�@�ۑ�ɂ��āA���펞�����Ў������펞�̍ЊQ�T�C�N���Ŏ����A�ݏ��E�����A����
�@�@�@�@�@�̊ϓ_���炵���݂Â�������邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�@�@�@�@�@�����Ėh�ЂɊւ����{�ڕW�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@���@�h�Ќ���Ɍ������܂��Â���B
�@�@�@�@�@�@�@���@�h�Ќ���Ɍ������l���B
�@�@�@�@�@�@�@���@�ЊQ�ɋ����̐��i�g�D�j���B
�@�@�@�@�@�̂R�_�̖h�Ѓr�W������������A�ЊQ�\��v��A�ЊQ���}��A�ЊQ�����A����
�@�@�@�@�@�v�悪�ׂ������Ă��Ă���B
�@�@�@�@�@�@����ł͂��̊�{�v��ɂ��ƂÂ���̌���́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C��s�Ôg��A�C��s�����̈�قւ̖h�Ћ��_�̐ݒu�A�C��s�����̈�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ق̒������A�y�ъe�n��̔��̐ݒu�A�e�����{�݂̑ϐk�f�f�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���C�A���Òn��̍�����A����h�Бg�D�̐ݗ��h�ЌP���̎��{�A�Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g���s������B
�@�S�A�@�C��s�Ôg��ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�a�̎R���Í`�i�C��n��j�̎��Ӓn��ɂ����ẮA�n�`�I�ȓ�������ߋ��Ɋ��x
�@�@�@�@�@�ƂȂ��Ôg�Z����Q���Ă��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���ɁA����R�O�N�ȓ��ɓ�C�n�k���T�O���A����C�n�k���U�O�`�V�O���̊m����
�@�@�@�@�@��������ƌ����Ă���A���n��ɂ͍�����T������Ôg�����P����ƌ����
�@�@�@�@�@�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���̒n�k�����ɔ������n��̒Ôg�Z����Q�́A��4,900���сA��13,000�l�ɋy�сA
�@�@�@�@�@�n��S�̂őz�肳����Q�z�͖�5,000���~�ƁA�a�̎R�����ōő�̔�Q���\����
�@�@�@�@�@��Ă��܂��B�܂��A���ݕ��ɂ͎s��������h�E�x�@�E�s���a�@���̎�v�����{�݂�
�@�@�@�@�@���łȂ��A�d�́A�S�|�A�Ζ����̎�v��Ƃ����n����ق��A���s�E�a�̎R�s�ƋI��
�@�@�@�@�@�n�������ԁA�����S�Q�����ʉ߂��Ă��邽�߁A��Q�����ꍇ�A���암�ւ̕���
�@�@�@�@�@�E�l���̃��C�t���C������Ⴢ���ƍl�����܂��B
�@�@�@�@�@�@���̂��߁A�n��Z���E�ՊC�����n��Ɠ��̊�@�ӎ��͍����A�Ôg��ɂ��āA
�@�@�@�@�@�n�悩����ɋ����v�]������Ƃ���ŁA���̂悤�ȏ̒��A�C��s�A�ՊC����
�@�@�@�@�@�n��v��Ƌy�ю�����̊�����̂ƂȂ������c���ݗ����A����A���y��ʏȋy
�@�@�@�@�@�јa�̎R���ɑ��āA�a�̎R���Í`�i�C��n��j�ł̒Ôg��̑������{�Ɍ���
�@�@�@�@�@���v�]���������s���Ă������Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B
�@�@�@�@�@�@�Ôg��̊T�v�i�ڍׂ͍��y��ʏȋߋE�n�������ǂɂ����Č������j
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@��H�@�@�@�@������݂̐��グ�A�q�H���ւ̐���̐ݒu�A�h�g��̐V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�ѐ��グ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����Ɣ�@�@�@200�`300���~
�@
�@�T�A�@�C��s�����w�Z�̓����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�w�Z�����ɂ��āA����ψ���ł͏��q���̐i�W�ɂ��q���̐��̌����ɔ����A
�@�@�@�@�@�w�Z����ɗl�X�Ȗ�肪�����Ă��Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�ȏɑΉ����āA��
�@�@�@�@�@�͂���w�K�����ێ����邽�߁A�w�Z�̓K���K�́A�K���z�u��i�߂Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�K���K��
�@�@�@�@�@�@�@�c�t���@�@���Ȃ��Ƃ���̉��ɕ����̃N���X�A�P�N���X�P�O�l�ȏ�̉�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���K�v�B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�N���X�ւ��̏o���鎙�������]�܂������A�Œ�ł��P�N���X�Q�O�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�̐l���͕K�v�B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�P�w�N�S�w���A�w�Z�S�̂łP�Q�w�����x�B
�@�@�@�@�@�@�K���z�u��
�@�@�@�@�@�@�@�c�t���@�@�m�`�c�t���A���Α��A���̂R�c�t������̗c�t���Ƃ��A����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Α��c�t���{�݂��ĊJ������B
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ÁA�哌�A���c�t���̂R�c�t������̗c�t���Ƃ��A���哌�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t���{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���×c�t���͌��s�̒ʂ�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�m�`�A���Α��A���̂R���w�Z����̏��w�Z�Ƃ��A�����Α��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ÁA�哌�A��菬�w�Z�̂R���w�Z����̗c�t���Ƃ��A���哌��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���Ï��w�Z�͌��s�̒ʂ�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���C����ɂ��Ă͋��犈���̊��͂��ێ�����ϓ_����A�K���K
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��ۂ����悤�A���Z�⏬�K�͍Z�̂��肩���ɂ��Č�����i��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@���Ñ��A���̓�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A���Ñ�w
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�C����A���A��O���w�Z�̎O�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�T��A�F���w�Z�̓�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A���c�r���Ӓn
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���J������B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���C�쒆�w�͌��{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�X���c��̎��̈�ʎ���ŁB
�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�̓������ɂ��ẮA�C����A���A��O
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�̓����́A��O���w�Z�����㕽���R�O�N�܂ł͈�
�@�@�@�@�@�@�@�w�N�R�w�����ێ��ł���Ƃ������Ƃ���A�P�Ƃł�����
�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̕ی�҂̋����v�]�ɂ��A�Ƃ肠�����͊C����
�@�@�@�@�@�@�@�A��w�Z���s���ē�������Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�T�쒆�w�Z�ƒF���w�Z�ɂ��ẮA���c�r����
�@�@�@�@�@�@�@�n���J���ɂ͂U�O���ȏ�Ƃ����c��Ȕ�p��������A��
�@�@�@�@�@�@�@�̂��Ƃ��s�����Ŏ����̂߂ǂ������Ă��Ȃ�����ł���
�@�@�@�@�@�@�@�A����ψ���Ƃ��Ă��A�T��A�F�Ƃ��ɂ��ꂼ�ꌻ�n�J
�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ������Ƃ�����ɓ���Ȃ���A�Č��������Ă�����
�@�@�@�@�@�@�@�������ƂɂȂ�܂����B
�@
�U�A�@�����S�Q�����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�����S�Q�����ɂ��Ă͍����S�Q����ʏa�ؑc��i�L�c�s�A�C��s�A����
�@�@�@�@�@�ȁA���A�x�@�j���тɍ����S�Q���L�c�C��Ԑ������i���c��i�L�c�s�A�C��s�A�L
�@�@�@�@�@�c�S������j������A�����S�Q����ʏa�ؑc��ɂ����Ă͒Z���I�ȏa�؉���
�@�@�@�@�@���Ƃ��āA�L�c�s����C��s�Ɏ���Ԃ̊e�a�،����_�̉��ǂ�A�������������Ȃ�
�@�@�@�@�@�̌��������Ă������ŁA����܂ŁA�L�c�s���������̌����_�A���Ò����c�����_�A
�@�@�@�@�@��������_�A�����ĕ����P�X�N�R���ɂ͊C��s�␅�����_�̉��ǂ����{����܂����B
�@�@�@�@�@�܂��A�����ĕ����P�U�N����͍��������̈������������{����A�����̌�ʗʒጸ
�@�@�@�@�@���}��������B
�@�@�@�@�@�@����A�����S�Q���L�c�C��Ԑ������i���c��ł́A�����Q�Ԑ��A�o�C�p�X�Q�Ԑ��A
�@�@�@�@�@�v�S�Ԑ��ł̐����v�]�����ĎQ�������A���y��ʏȋߋE�n�������ǘa�̎R�͐썑��
�@�@�@�@�@�������ł́A�o�C�p�X���[�g����Ɍ����A�����P�V�N�x�����ӂ̊��������I���A
�@�@�@�@�@���N�x�ɂ����Ĉ�ʍ����S�Q���␅�g�����ƂƂ��āA�␅�����ԉ�����P�D�P����
�@�@�@�@�@�����Ɖ�����A�{�N�P�O���ɂ͒n���Z���̊F�l�ւ̎��Ɛ�����J����A���̌�H
�@�@�@�@�@�����ʁA�n�����������{���ė\���v�ɓ����Ă����\��܂��A����ƕ��s���č��N
�@�@�@�@�@���ɂ͓s�s�v�挈�肳���\��ł���Ƃ������Ƃł��B
�@
�@�V�A�@�����R�V�O�����̃o�C�p�X�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@���̎��Ƃɂ��Ă͂����Ԃ�ȑO����v�悳�ꂽ�Ȃ��ւ�炸�A�n�����ӂ��Ȃ�
�@�@�@�@�@�Ȃ�����ꂸ�A�n���̊F�l�̋��͂ƊW�҂̓w�͂ɂ��悤�₭�����P�U�N�P�Q��
�@�@�@�@�@�Q�S���ɓs�s�v�挈�肳��A���גr�炩��ؒÌ����_�t�߂܂ʼn�����Q�C�T�S�O
�@�@�@�@�@���A�����Q�O���̗\��ŕ����P�V�N�x��茧�ɂ����Ď��Ɖ�����܂����B
�@�@�@�@�@�@���݂͋N�_������I�z��s�t�߂܂ł̖��P�C�T�U�O���̋�Ԃ���H��Ƃ���
�@�@�@�@�@���Ƃ�i�߂Ă��܂��A���݂͑��H����Ō����p�n�̗������Ƃ�i�߂Ă��茻
�@�@�@�@�@���_�łU�����x�̗�������I���Ă���Ƃ������Ƃł��A�܂��A����ƕ��s���Čv
�@�@�@�@�@�擹�H�̐�������A�������̃R���T���^���g��Ђ����������ɏ����͂����Ă����
�@�@�@�@�@���ł��B
�@
�@�W�A�@��a�����ԓ��i�C��g���ԁj�̎l�Ԑ����ɂ��āB
�@
�@�@�@�@�@�@��a�����ԓ��i�C��g���ԁj�̎l�Ԑ����͕����W�N�P�P���Q�X���ɓs�s�v�挈��
�@�@�@�@�@����A�����P�O�N�P�Q���Q�T���ɍ��̎{�H���߂��o����A�����P�S�N�V���ɑ��ʒ�
�@�@�@�@�@�����J�n�A�����P�T�ʂV������p�n�����n�܂�A�����A���ÁA����̊e�g���l��
�@�@�@�@�@�H���͕����P�U�N�ɒ��H�A�C��A���ÃC���^�[�`�F���W�͕����P�V�N����J�n����
�@�@�@�@�@�Ă���A�����Q�S�N�x�ɂ͏㉺���Ƃ������̗\��ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@
�@�X�A�@�C��s�������ɂ��āB
�@
�@�@�@�@�@�@�C��s�̉������ɂ��Ă͑S���ł��Œ�ɋ߂������̒B�����ł����A���݊���
�@�@�@�@�@���Ă��鉺���������A�����Ƃ����_����łȂ����Q��ɏd����u�����������ł���
�@�@�@�@�@�܂��A�ł͊C��s�͉��������ǂ�����̂��Ƃ����ƁA�{�N�S���ɏo����܂����C��
�@�@�@�@�@�s�����v��ɂ��ƁA�������̌��݂͂��Ȃ��Ƃ������_�ł���C��s�̛��A������
�@�@�@�@�@����Ƃ��ẮA�܂������������̕��y�ɓw�߂Ă����Ƃ������Ƃł���܂��B
�@�@�@�@�@�@���͉��������݂ɂ͐��S���Ƃ����c��Ȏ�����K�v�Ƃ��܂����������̐ܒv��
�@�@�@�@�@���Ȃ��Ǝv���܂����A����Ȃ�Ό��ݔ_�����ł͔_�Ɨp���H�֏��̕��������
�@�@�@�@�@�����Ă��錻�����ӂ܂��A�_�Ɨp���H�̉��C��L����Ƃ��Ă̐��ʂ̊m�ۂƂ���
�@�@�@�@�@�����Ƃɗ��ӂ��Ă������������ƍl���Ă��܂��B
�P�O�A�@�����H���C����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�����C��H�����ɂ��ẮA���݂����r�̊������Ŋg���H�������{���Ă���܂�
�@�@�@�@�@���A���㊎���n�����o�đ��c�n����o�Ęa�̎R�s�Ɏ��镔���̉��Ǘ\��͑S���o��
�@�@�@�@�@�Ă��Ȃ��̂�����ł���܂��B
�@�@�@�@�@�@���Y�����͔��ɋ�襂ō����̎����Ԃ̑�^���ɔ����R���܂܂Ȃ炸���[�̃�
�@�@�@�@�@�b�V�����ɂ͒���t�߂̏Z���͂��Ƃ��ʋΎ҂����ɍ����Ă���̂�����ł�
�@�@�@�@�@��܂��B
�@�@�@�@�@�@����A�C��C���c�A�i�C��s�c��A�I���쒬�c��j�ɂ����č��N�x���猧���
�@�@�@�@�@���킹�A�����C��H�����̊g���ɂ��Ă��v�����s���Ă����Ƃ������ӂ��Ȃ����
�@�@�@�@�@�����B
�@�@�@�@�@�@
�P�P�A�@�����C��������̃o�C�p�X�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�����C��������̉��C�ɂ��ẮA���a�S�W�N�Ɍ����C����������C���i���c��
�@�@�@�@�@�i�C��s�A���������j���ݗ�����A�܂��A�C��s�ʏ��n������Q�E�������ėL�c��
�@�@�@�@�@������Ɏ���Ԃ̉��C���������{����A���̌�A�d���A�����쉈���̖����C�Ԃ�s
�@�@�@�@�@�v�擹�H�Ƃ��āA�����U�N�ɂ͗����c�Ì������s�s�v�挈�肢����A�����P�Q�N��
�@�@�@�@�@�莖�ƒ��肳��Č��ݗp�n���A�H�������{����Ă���B
�@�@�@�@�@�@�ߔN�L�c������̎ԗ��̒ʍs���������������A�d���n�悩��ʏ��n��Ɏ��鋷�
�@�@�@�@�@�ȓ��H�Ō�ʏa�������N��
�@�@�@�@�@���A���s�͂��Ƃ����ӏZ���̐����ɂ��傫�ȉe���𗈂��Ă���A����Ɍ����ΎR
�@�@�@�@�@���錧���͋}���z�A�}�J�[�u�A�Z���A�~�G�̐ϐ�A������������X�̈�������
�@�@�@�@�@�狾�g���l���̌��݂��]�܂�Ă���B
�@�@�@�@�@�@���ł͕����P�V�N�x���狾�g���l���̒����𑱂��Ă��邪�A���ニ�[�g�����
�@�@�@�@�@�����Ă̒��������{����\��ŁA���݁C�n�������Ɍ����ď������Ƃ̂��Ƃł��B
�@
�P�Q�A�@�C��s�̃S�~�����{�݂ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�C��s�̃S�~�����{�݂͏��a�T�U�N�ɋ��p�J�n�˗��A�����R�N�Ƀ_�C�I�L�V����
�@�@�@�@�@����H�����s���A�����܂łQ�U�N�ԉғ����Â��Ă���܂��A�v�����g���[�J�[��
�@�@�@�@�@���ϗp�N���͂P�O�N�ł����A���̌�̈ێ��Ǘ����K���ł������̂��傫�Ȏ��̂�
�@�@�@�@�@�Ȃ������ɉ^�]�𑱂��Ă��܂��A�������ߔN�A�{�s�̃S�~�����ʂ������A����ɂ�
�@�@�@�@�@���̋��Ă���Ƃ͂����A�ꕔ�̎Y�Ɣp�����܂ŏ������A�܂��A���̎s���̃S
�@�@�@�@�@�~�܂ŏ������Ă��錻��ł́A���܂Ŏ��̂����S�z�ł���܂��B
�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�S������́A���Ò��̃S�~�����{�݂��^�]���~����Ƃ̂��ƁA�]��
�@�@�@�@�@�ĂS������͉��Ò��̃S�~���ꏏ�ɏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����A�����
�@�@�@�@�@�������������Ȃ��Ƃ��Ă��A�\�͓I�ɂ��]�T������Ƃ��Ă��A�����V�������Ă���
�@�@�@�@�@����{�݁A��������������S�~�����ꌚ�݂Ɍ����Ă̎��g�݂��]�܂�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@����Ȓ��A�{�s���A�L��ł̃S�~�����ɕ��j�����߁A�C��s�A�I���쒬�A�I�m��
�@�@�@�@�@�s�ƂƂ��Ɂu�L��S�~�����{�ݐ������c��v�𗧂��グ�����P�X�N�P�O���P�P����
�@�@�@�@�@�犈�����n�߂܂����B
�@�@�@�@�@�@�V�����L��S�~�����ꌚ�݂Ɍ����ē����n�߂܂������A�����炭�A�e�s��������
�@�@�@�@�@����𗘗p���傤�Ƃ���V�N��ɂ͊�������ł��傤�A���łɌ��n���I�m��
�@�@�@�@�@�s�A�I���쒬�ł��ꂼ��P�ӏ��������Ă���Ƃ��������Ƃł�����A����ǂ͊Ԉ�
�@�@�@�@�@���Ȃ����݂Ɍ����Đi�ނ��Ƃł��傤�B
�{�s�̊w���ۈ�ɂ��Ă̌���Ɖۑ�B
�@�@�@����A�T��n��̂��镃�Z����w���ۈ�ɂ��Ă̑��k������܂����B
�@�@�@�@�@���̕��͋T��n��ɍݏZ���A�v�w�������ŁA���N����q�������w�̏��w�Z�ɒ�
�@�@�@�@�@�����ƂɂȂ�A�T��̊w���ۈ��\�����Ƃ���A������T�O�l�łT�R�l�̉��傪��
�@�@�@�@�@��A���ɂ��T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙�����D�悷��ƌ����A�T�R�Ԗڂ̐\����
�@�@�@�@�@�Ƃ��đI�l����͂����ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���Ȃ݂ɃI�[�o�[�������̂Q�l�������ł��Ȃ������ƌ������Ƃł��B
�@�@�@�@�@�����Ŏs�̎q��Ďx���Z���^�[�̒S���҂��獕�]���w�Z�̊w���ۈ炪����ɒB����
�@�@�@�@�@���Ȃ��̂ł����ɒʂ��Ă͂Ɛi�߂��A��ނȂ����]�ɐ\�����Ƃ���A����ǂ͊w
�@�@�@�@�@�Z����o�X�ɂč��]���w�Z�̋߂��̃o�X��i�Z�傩���R�O���j�ō~��A�w���ۈ珊��
�@�@�@�@�@�ʂ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�o�X�₩�狳���܂ő��}����l���Ȃ���Ύ�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�Ƃ����A�S���҂���g���ɒN���Ȃ��ꍇ�̓T�|�[�g�Z���^�[���瑗�}�̂��߂̔h
�@�@�@�@�@�����Ă͂ǂ����Ƃ̘b������A�}���͒v�����Ȃ��Ƃ��Ă��킸���R�O�����悤�̂�
�@�@�@�@�@�T�|�[�g�Z���^�[�ɂ��肢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��p��������A���Ƃ��Ȃ�Ȃ���
�@�@�@�@�@���Ƃ��肢���܂������A����͂��邱�Ƃɂ��Ă͎s�̏��Ɍ��߂��Ă���̂łǂ�
�@�@�@�@�@���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ���ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���̕��͎s�̏��Ɍ��߂�ꂽ���j�ł���Ύd�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�����ƒN�������p
�@�@�@�@�@�ł��鐧�x�ɂȂ�Ȃ��̂��B�Ƃ������Ƃő��k�Ɍ������܂����B
�@�@�@���̘b���Ď������������Ƃ�
�@�@�@�@�@�܂��A���������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�C�T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙���̂��߂̊w���ۈ�ƌ������ƁB�T�쏬�w�����D�悷��ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������̒n��̊w���ۈ�����������ł���B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�A�T��n��ɏZ��ł��Ȃ���A���w���ɂ��悤�ƒ�ɑ���z�����S���Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�A���}�ɂ��āA���ɑ���ɂ��Ă͏��ɂ���ċ`���Â����Ă��邻���ł���ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�A����A���Y�����̑��ɁA�T�쏬�w�Z�ɒʂ��q���B�Q��������I�[�o�[�Ƃ������Ƃœ����ł��Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ł����A���q����Ƃ��Ă̎s���ɈՂ����{��Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�����ŁA�w���ۈ�ɂ��ĊȒP�ɒ��ׂĂ݂܂��ƁB
�@�@�@���������@�ł̒�`�H�i�w���ۈ�Ƃ�������g�p���Ă��Ȃ��B�j
�@�@�@�@�@�u���̖@���ŁA���ی㎙�����S�琬���ƂƂ́A���w�Z�ɏA�w���Ă��邨���ނ�10��
�@�@�@�@�@�����̎����ł��āA���̕ی�҂��J�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA����
�@�@�@�@�@�Œ�߂��ɏ]���A���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p���ēK�ȗV
�@�@�@�@�@�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}�鎖�Ƃ������B�v
�@�@�@�@�@�i��U���̂Q��V���j
�@�@�@�����E���T�Ȃǂɂ���`
�@�@�@�@�@�u�e�������Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A�ƒ�
�@�@�@�@�@�ɂ����ۈ���s���{�݁E���ƁB�v
�@�@�@�@�@�u���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w�����C���ی��莞�ԕۈ炷�邱
�@�@�@�@�@�ƁB�v
�@�@�@�w���ۈ�̉^���c�̂ɂ���`
�@�@�@�@�@�u�E�E�E�E�E�������ƒ���q�E���q�ƒ�̏��w���̎q�ǂ������̖����̕��ی�
�@�@�@�@�@�i�w�Z�x�Ɠ��͈���j�̐��������{�݂��w���ۈ�ł��B�w���ۈ�Ɏq�ǂ�����
�@�@�@�@�@���������Ĉ��S���Đ��������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ���āA�e���d���𑱂����
�@�@�@�@�@�܂��B�w���ۈ�ɂ͐e�̓��������ƉƑ��̐��������Ƃ�������������܂��B�v
�@�@ �@ �ȏ�̂悤�ɁA�w���ۈ�ɂ��Ē�`�Â����Ă��܂����A�n���̊w�Z�ɒʂ���������
�@�@�@�ۂƂ����悤�Ȃ��Ƃ͑S���ӂ���Ă��Ȃ����A�܂��厖�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐e��
�@�@�@�����Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A���̕ی�҂��J
�@�@�@�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p����
�@�@�@�K�ȗV�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}��B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA�n���̏��w�Z�ɒʂ������Ɍ��肵���l�Ȓ�`�Â����S���Ȃ��ꌾ���܂���B
�@�@�@�s�̒S���҂Ƃ̂��Ƃɂ��Ă̋��c�̒��ŁA
�@�@�@�@���}�ɂ��āA���ɂ�茈�߂��Ă���Ƃ��������͊ԈႢ�ŁA��W�v���ł́A�u�w��
�@�@�@�̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��Č}�����K�v�ł��B�܂��y�j����ċx�ݓ��̒����x�Ɗ��Ԓ�
�@�@�@�̊w���ۈ�ɂ��Ă�����}���������Ƃ��܂��B�v�L����Ă���A���ł́u�ۈ�I
�@�@�@����̎����̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��ĕی�҂��}���邱�ƂƂ��܂��v�Ƃ̋L�ڂ���
�@�@�@��A����ɂ��Ă͓y�j���y�ђ����x�Ɠ��ȊO�͓��ɂӂ���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@�@�@�@����ɁA�S���҂̕������Ƃ��R�O���̓��̂�ł����Ă����̊ԂɎ��̂ł���������Ύs
�@�@�@�̐ӔC����ꂩ�˂Ȃ����Ԃ��l���A�ی�҂�[���������߂Ɏv�킸���������o������
�@�@�@�ł͂Ȃ����B�����Ă������Ƃł͂Ȃ����A����͂���Ƃ��āA����Ȃ��Ƃ��̐e�̐ӔC�Ƃ�
�@�@�@�������Ƃ��������Ƃ��đΉ����ׂ��ł͂Ȃ����
�@�@�@�@�܂��s�O�̏��w�Z�ɒʂ������ɂď��ł͊C��s�w���ۈ����R���Ɂu�w���ۈ�̑�
�@�@�@�ۂƂȂ鎙���́@�i�P�j�s���̏��w�Z�ɏA�w���Ă�����w�N�����R�w�N�܂ł̎�����
�@�@�@�ی�҂��J�����Œ��ԉƒ�ɂ��Ȃ����́B�i�Q�j�O���Ɍf������̂̂ق��A�s��������
�@�@�@�K�v�ƔF�߂����́B�v�ƂȂ��Ă���B����̃P�[�X��(�Q)�ɑ�������̂ł͂Ȃ�����
�@�@�@�v���邪�ǂ��葱������������̂��Ƃ������Ƃ��낪�s���ł���A����������Ă��Ȃ��B
�@�@�@���̓_�ɂ��Ă͕ی�҂̗���ɗ��������J�ȑΉ����K�v�ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�@���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w����ΏۂƂ������Ƃ��炷��Ό}���͂Ƃ�
�@�@�@�����A����ɂ��Ă͓��R�d�����ł�����A�s�������悤�ɃT�|�[�g�Z���^�[�𗊂�Ȃ�
�@�@�@��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����A�o�ϓI�Ȗʂ�����A����̃P�[�X�̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�ی�҂�
�@�@�@�ӔC�͈̔͂őΉ����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɋT��̏ꍇ����Q�O���Z�O��
�@�@�@�s���������Ĉړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ɂ��Ă͉���Ή�����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�ȏ�̂��Ƃ��w�E���A���̂Q���ɂ��āB���������肢�����B
�@�@�@�@ 1�A���ɂ��ƁA�n���̏��w�Z�ɂ��悤�������ΏۂƂȂ��Ă��邪�A���̎��w�ɒʂ��q���B
�@�@�@�@�@�@�@�͒u������ɂ���Ă���A�q��Ďx���Ƃ����ϓ_����l����Ɛ������Ɍ�����悤�Ɏv���B
�@�@ �@�@�Q�A�\�����݂̗v�����ɂ́A�w���ۈ珊����̋A��͕ی�҂��}���ɗ���悤������Ă��邪
�@�@�@�@�@�@�@�w�Z����w���ۈ珊�ւ̈ړ��ɂ��ẮA����������Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���w�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@���������A���Y�ۈ珊�̋߂��Ńo�X���~��Ċw���ۈ珊�ɒʂ��ꍇ���̋����@���Ɋ�
�@�@�@�@�@�@�@��炸�͕ی�҂�����}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�����Ȃ���Ă���B�q���̈��S
�@�@�@�@�@�@�@���l����Ɠ��R�̂��Ƃ�������Ȃ����A�n���̏��w�Z�ɂ��悤�����ɂ͑S������������
�@�@�@�@�@�@�@�z�����Ȃ���Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂��B���������āA�����ɑ��k�ɍs�������X�ɑ���
�@�@�@�@�@�@�@�̂ݎw�����āA�n���̏��w�Z�ɒʂ��ی�҂ɑ��Ă͖ٔF���Ă���̂ł͂Ƌ^���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@���悤�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���B����ɂ��Ă��A�������̂���悤�ɉ��߂�ׂ��ł���B
�@�@�@�@����̌��ŒS���ۂɊF����͑����������Ă��������A��肠��������ɂ��Ă͕ی�҂Ƒ��k��
�@�@�@�@�@�@�@��ی�҂̐ӔC�ō��]�ۈ珊�ɒʂ����Ƃ�F�߂�Ƃ̉����������܂����B�W�҂�
�@�@�@�@�@�@�@�v���ȑΉ��Ɋ��ӂ��܂��B
�@�@�@�@
�č����{������{���{�ɒ����u�N�����v�v�]���v�Ƃ�
�u�D������{�v�i�։��p�V�j���
�@�@�@�Ăт��̖{���Q�l�ɔN�����v�v�]���ɂ��ėv�_���L���Ȃ��玄�̍l�����q�ׂ�
�@�@�݂����ƂƎv���܂��B�u�N�����v�v�]���v�͂X�R�N�V�������T�~�b�g�̍ۂ̋{��N�����g��
�@�@��]��k�ł́u���ĊԂ̐V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v���ӂ���������
�@�@�ł���B���̌���{�̐����͍א���t�A�H�c���t�A�����ĂX�S�N�U���ɑ��R���t�������A
�@�@���ꂩ��܂��Ȃ��\���ɍݓ��č����H��c�����Γ��v�]�����\�A���ꂪ�u���ĊԂ�
�@�@�V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v�̈�Ƃ��Đݒu���ꂽ�K���ɘa�E����
�@�@��������ɍ̗p����A�u�N�����v�v�]���v�Ƃ��Ē�ቻ�����Ƃ����킯�ł���B�Ȍ㌇��
�@�@�����ƂȂ����N�H�Ɍ��\����Ă����B
�@�@�@���{�̐������\�ܔN�̐������A�����A�������钆�č��ɑ����������A����
�@�@����u�č��ɂ����{�����v�Ƃ����`�e�̂������̂Ȃ����ĂQ���Ԃُ̈�ȃ��J�j�Y
�@�@���ƁA���̋��͂Ȕ}�̂ł���u�N�����v�v�]���v�́A�����{�̗��j�I�]���_�Ƃ���
�@�@�ׂ������ƍ����̒��ŁA�č��Ɏ��˂����܂�ē��{�̐����V�X�e���̒��ɂ��������
�@�@���U����Ă��܂����B���́u�N�����v�v�]���v�͂O�S�N�A�։��p�V���̒����u���ۂł���
�@�@�����{�v�����\����A�u�킵�Y���v�i����Ƃ̏��т悵�̂肪�ӔC�ҏW���߂�G��
�@�@���B�j�O�U�N�~���ŏ��т悵�̂肳��́u�������ł����̎����𐢂ɍL�߂邽�߂ɏ�������
�@�@�ɂ���v�Ƃ������Ƃ���u���ė��E�N�����v�v�]���ɓ{��v�Ƃ������W���g�܂�A�����]
�@�@�_�Ƃ̐X�c�����u�����S�ʔᔻ�v�i���{�]�_�Ёj�̒��ŁA�u�O�S�N�T���R���A����
�@�@�ڍ��w�r�����̏��X�ň���̐V�����������A�Ƃ������{�̕����玄�ɍ��}�𑗂���
�@�@����C����������͡{�ۂł��Ȃ����{�[�A�����J�̓��{������������ł���p���҂͊։�
�@�@�p�V����A�m��Ȃ����������̐l�̒����ɂ͓��{�̍���J�����{�l�̍������߂��Ă���悤�ȋC�������v��
�@�@�������ƂŎ��グ�A�Ȍ�W�҂̊ԂɍL�����グ����悤�ɂȂ��������ł���B
�@�@�@�X�U�N����n�܂����u�N�����v�v�]���v�O�S�N�Ɂu���ۂł��Ȃ����{�Łv�����ɔ��\�����܂ŁA���̎��X�̓�
�@�@�t�A�����͒m���Ă����Ƃ��Ă��@��ʂ̍���c�����^�}����}���قƂ�ǒm��Ȃ��������Ƃɋ����ł���B�u����
�@�@�ł��Ȃ����{�v�̘b���A���҂̊։��p�V����������āA������J�����A���̏��ы��N�����A���i��
�@�@��A�ނ�͊։�����̘b�����ςȂ��ɂ��Ȃ������B�ނ�́u�N�����v�v�]���v�͂��A�X�����c���@�Ă���
�@�@���̗v���������̂ł��邱�Ƃ��������A����ł͓��{�̍��v�ɂȂ�Ȃ��A�A�����J�𗘂��邾���ł͂Ȃ����Ƌ`
�@�@����R�₵���B�����Ă��̌�̓W�J�́A�������̒ʂ�ł���B����ɐ�������A�}�X���f�B�A�ɗx�炳��
�@�@�����{�̗L���ҁi���{�����j���炪�����̎���i�߂Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�@�@�u�N�����v�v�]���v����͓��đo�������݂ɒ�o�������Ă������̂ŁA�ߋ��\���N�ԓ��{�Ői�߂��Ă����A
�@�@�u���v�v�̂��Ȃ�̕������č����{�̗v���𒉎��ɔ��f���Ă������̂ŁA�O�T�N����Ő��������A�V��Ж@�A����
�@�@�Ƌ֖@�A�X�����c���@���܂�������ł���B�����āA�����̒��߂�����́A��Ð��x���v�ł���B���̗�R��
�@�@��]���Ԃ�́u�P�퉻���ꂽ�������v�Ƃ����ق��͂Ȃ��A�匠���ƂƂ��Đq��Ȃ炴����̂��B����ł͕č���
�@�@�B�̕����܂������A������A�����J�̑����ł͂Ȃ����B
�@�@�@����͂Ȃ��������[�@�Ă⋳���{�@�����@�āA�h�q�����i�֘A�@�ĂȂǏd�v�@�ĂȂǐ摗�肵�A���
�@�@���x���v�@�Ă̐������}�����̂��B����͂܂��ɂO�U�N�U���Ƀu�b�V���đ哝�̂Ƃ̍Ō�̎�]��k���Z�b�g����
�@�@�Ă������߂ŁA�u�N�����v�v�]���v��Ð��x���v�̐i�W������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�����ꂽ��Ð��x���v�@�́A���I��Ô�̗}���������ł��o�������̂ŁA���̂��߂ɍ����A�Ƃ�킯�����
�@�@�Ɏ��ȕ��S�̑���𔗂���e�ƂȂ����B
�@�@�@�����͂O�Q�N�Ɋ��Ɉ�Ð��x���v�ɒ��肵�Ă���A���̂Ƃ��͂���܂ł̏���t��z�����P�p����A���S
�@�@�藦���ɑւ���ꂽ�B���̍ہA�V�O�ˈȏ�̍���҂̈�Ô�ȕ��S���́A��ʏ����҂��P���A������ݏ���
�@�@�҂��Ƃ���A����҂̎��ȕ��S�𑝂₵�Ă���B����҈ȊO�ɑ��Ă��A�O�R�N����T�����[�}���{�l�̈��
�@�@��ȕ��S������O���Ɉ����グ��ꂽ�ق��A�Z������������x�[�X����ܗ^���܂߂��N���x�[�X�ɕύX
�@�@����A�ی������S�����₳��Ă���B
�@�@�@���ꂪ�O�U�N�̈�Ð��x���v�ł͎��\�˂��玵�\�l�˂̈�ʏ����҂͂O�W�N�S������ɁA���\�ˈȏ�̌�
�@�@����ݏ����҂͂O�U�N�P�O������O���ɑ��₳��B�܂��A�u������ݏ����v�̒�`������������ꂽ���߂ɁA�e
�@�@������Ώێ҂̐����������B���̏�A�u���z�×{��x�v����������A����ҁA���𐢑���킸�A���z�Ȉ�
�@�@�Ô���������ꍇ�̎��ȕ��S���x�z�������グ��ꂽ�B
�@�@�@����ɁA�u�������҈�Ð��x�v���n�݂���O�W�N����]���͕}�{�Ƒ��Ƃ��ĕی�����Ƃ�Ă����l���܂߁A
�@�@���\�܍ˈȏ�̂��ׂĂ̍���҂��A�ی����̎x�����`�����ۂ����邱�ƂɂȂ����B�܂��A����҂������ɓ�
�@�@�@���Ă���u�×{�a���v�ł̐H�����M��͂O�U�N�\������ی��ΏۊO�ƂȂ�A�×{�a�����̂��Q�O�P�Q�N�܂łɌ�
�@�@�݂̔����ȉ��ɍ팸����邽�߁A�������@���҂͗L���V�l�z�[���Ȃǂ֓]�o�𔗂���B�[�I�Ɍ����A����
�@�@�������T�N�Ԃɂ킽���Đ��i���Ă����u��Ð��x���v�́v�Ȃ���̂̎��Ԃ́A�����A�Ƃ�킯����҂Ɏ��ȕ��S��
�@�@��𔗂邱�ƂɏI�n���Ă����̂͒N�̖ڂɂ����炩�ł���B
�@�@�@���҂̎��ȕ��S�����܂�A���I�ی��ŃJ�o�[�����͈͂�������A�k�����邱�ƂɂȂ�A���ȕ��S���J�o�[
�@�@���邽�߂̖��ԕی����o�ꂷ��B�u���ꂪ���ɏo���邱�Ƃ͖��ɂ�点��v�ƌ������Ƃł���A���I��Õی���
�@�@�k�����Ă����A����A�����́u���ȐӔC�v�ŏ����ɔ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐V����e���r�ŃA�t��
�@�@�b�N��A���R�ȂǃA�����J�n�ی���Ђɂ���Õی����i�̐�`���킪�ٗl�ȂقljߔM���Ă���̂́A��Ð�
�@�@�x���v�ɒ[�������ۂł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�����ЂƂA����ł����̂����{�́A�����������Ȃ�悤�ȉ��v���i�߂��Ă����B���ꂪ�u�V��Ж@�v�̐�
�@�@�肾�A�u��Ж@�v�Ƃ����@���͂���܂ő��݂��Ȃ������A��А��x�Ɋւ��Ă͏��@��L����Ж@�ȂǗl�X�Ȗ@��
�@�@������ł����A��������ɂ܂Ƃ߂ĐV�����u��Ж@�v���A�����Ă��̖ڋʂƈʒu�Â����Ă����̂��A����
�@�@�J���狭���v�]����Ă����A�u�O�����Ή��̍����v�i�������z�������������j�̉��ւł���B���ꂪ���ւ����Ƃ�
�@�@���Ȃ邩�A�Ђ炽�������ΊO����Ƃ����z�̔��������������邱�ƂȂ��ɁA���Њ����g���Ă��Ƃ����₷�����{
�@�@��Ƃ��P���ɂ����߂邱�ƂɂȂ�B������u�O���ɂ����{��Ƃ̏�����v�̉��ւł���B
�@�@�@�V��Ж@�͂O�S�N�P�Q���ɗv�j�Ă����\����O�T�N�ʏ퍑��ɖ@�Ă���o����A�O�U�N����{�H����邱�Ƃ�
�@�@�Ȃ��Ă����A�����̂قƂ�ǂ��m��Ȃ��ԂɁA�܂��ɊԈꔯ����̔N���C�u�h�A�̎������������A�G�ΓI��Ɣ���
�@�@�ւ̍����I�S���ɂ킩�ɕ����A�Ƃ��ɁA��������d�|����ꂽ���{��Ƃɂ͖@�I�ɕۏ��ꂽ�h�q�ق�
�@�@��ǖ������ƂɊ�@�������������B�����}�̓}��(�X�����c���Ŋ����A���̏��ы��N�c���⏬�i�c��)
�@�@������u�O�����މ��̍����v���ւɑ��锽�Θ_�����o���A��o�������O�Ɉ�N�ԓ�������邱�ƂɂȂ����B��
�@�@��Ȋ댯�Ȃ��Ƃ����蔭�Ԑ��O���������Ƃɂ͜ɑR�Ƃ������ł��邪�A���̎����}(�X�����c���Ŋ���
�@�@���A���̏��ы��N�c���⏬�i�c���j�c�������̓����ɂ��A��N�ԓ�������邱�ƂƂȂ�A���{�̊�Ƃ��h
�@�@�q����u���邱�Ƃ��o�����̂ł���B
�@�@�@����ɂ��Ă��A�Ȃ��������ݓ��{�̑��Ƃ��������ɂ���킽���ɂЂƂ����u�O�����Ή��̍����v�̉��ւȂ�
�@�@�Ƃ������Ƃ��i�߂��Ă����̂��B�ӊO�ɂ����Ƃ͉�Ж@�����ł͂Ȃ��̂��A�ӊO�ɂ���v��ɂ��Ċ�ƍ�
�@�@����v�����������Ɍ������ꂷ����j����߂��A���̐V����������v����ł́A�]���̓��{�I�ȑΓ�����
�@�@�͓���Ȃ�A�G�Ύ��������܂߂��z������������̊�ƍĕ҂̎嗬�ƂȂ�Ƃ����Ă���B����ɁA�Ő��ʂł�
�@�@�O���ɂ����{��Ɣ������㉟�����邽�߂ɐŐ����v���O�S�N���猟������Ă���Ƃ����A����������A�̉��v��
�@�@���̂��ׂĂ̓����̎i�ߓ��ƂȂ��Ă���̂��u�Γ�������c�i�i�h�b�j�v�c���͓��t�����厖�A���c���͌o�����S
�@�@����b�A�����Ă��̉����g�D�ɂ͂P�R�l�̓��{�l�̑��ɁA�ݓ��č����H��c���̊�����č��،���Ђ̖����A
�@�@��l�̊O���l�ٌ�m���܂ނP�O�l�̊O���l���u�O���l���ʈψ��Ƃ��Ė���A�˂Ă��邻���ł���B
�@�@�@�����āA���̑Γ�������c��啔��O�S�N�A�u�Γ��������i�v���O�����y�ю��{�v�Ƃ��������̒��ŁA
�@�@�u�������z���������E�������e�Ղɍs����悤�Ɂv�Ƃ����ړI�Łu�O�����Ή��̍����v�̉��ւ��ƍ�����v��
�@�@�̎������������A�Ő���̗D���[�u�ȂǂƂ��������Ƃ���̗�Ƃ��Ă������Ă��B����ȊO�ɂ��A�ߔN�A���{��
�@�@�傫���h�邪���Ă���B������\�����v�̑������A���́u�Γ��������i�v���O�����v�̈���������Ƃ����L��
�@�@��Ă���B���͏���̌����\�����v�́A�����̂��߂ł͂Ȃ��A�O���ɂ����{��Ƃ̔����𑣐i���邽�߂�
�@�@�u���{�����v�����������đg�D�I�ɐi�߂��Ă����̂ł���B
�@�@�@04�N�ł́u�Γ������C�j�V�A�`�u�v�̕��ɂ́o�č����{�́A���{�ɂ�����l�����Ԃ̕ω��ɂ��A����A
�@�@����y�ш�ÃT�[�r�X����ɂ����铊�����d�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E�����B�����Ă����̕���ɂ����ĕč�
�@�@��Ƃ����̓��ӕ���������l�X�Ȏ��̍����T�[�r�X��ł��邱�ƁA�܂����������V���ȃT�[�r�X�̒�
�@�@�����{�̏���җ��v�̑���Ɏ�������̂ł��邱�Ƃ��w�E�����B�č����{�͂����̕���ɂ����铊���𑣐i��
�@�@�邽�߁A���{���{�ɑ��A���Y����ɂ����铊�����\�Ƃ��邽�߂̋K�����v��v�������B�p���邳��Ă���B
�@�@�@�����ăA�����J�̓��{�����͂܂��܂������X�����c���Łu�ȈՕی��v����Ð��x���v�Łu��Õی��v�����̂�
�@�@�炢�͋���A��ÃT�[�r�X�A�u���ρv�ւƉ��X�Ƒ��������ł���B���������N�����̕č��ɂ����{�������~��
�@�@��̂��A�����Ȃ鍑���ȊO�ɂȂ��ł͂Ȃ����A�ڊo�߂���{�B
�@�@�@���ċK�����v�y�ы�������C�j�V�A�`�u�Ɋ�Â����{���{�ւ̕č����{�v�]���̖`���ɂ�
�@�@�@�O�T�N�Ł@�@�č��́A������b�̓��{�o�ω��v�Ɍ������p���I���g�݂�����������B�����̎��g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͓��{�𐬒��O���ɏ悹�A��葽���̖f�Ջy�ѓ����@���n�o�����A�č��͂܂��A�����ƍ\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����͏����ʓI�ɒ��Ă����K�����v�E���ԊJ�����i�{���ƁA�\�����v���ʐ��i�{���̂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g�݂�]������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̗v�]���ɐ��荞�܂ꂽ�́A��v�����A���f�I����ɂ�����A���v�ɏd�_��u���A�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ϐ������x�����A���{�̎s��J������肢�������������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B����ɕč��͓d�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A�m�I���Y���A��ÁA�_�ƁA���c���A��������ȂǁA���������v�̎�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���d�v�ł���ƈʒu�Â�������̖��Ɉ����������ɏœ_�ĂĂ���B
�@�@�@�O�U�N�Ł@�@�č��́A���{�̌o�ω��v�𐄐i����Ƃ�������������b�̌��ӂ����}����B�V�����@��݁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����𑣂��A��茒�S�ȃr�W�l�X�������o�����v�́A���ꂩ��扽�N�ɂ��n����{�̌o�ϐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɗ��͂��ێ����x����ł��낤�B�܂��A�č��͓��{�����̉��v���i�҂̎��g�݂�S�����v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���㐔�����A���N�ɂ킽��A�����̊��������������邱�Ƃ����҂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̕č�����̒́A�d�C�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A��Ë@��A���i�A���Z�T�[�r�X�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɩ@���T�[�r�X�A�������A�_�ƁA���Ђ̖��c���A���ʁA��������ƍL�͈͂ȕ���ɂ����āA�p
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ��v�̐i�W��}�邱�Ƃ̏d�v�����������Ă�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԕ���i�č��́j�̑�\�����C�j�V�A�`�u�֒���I�ɎQ�����A���m������Ă���邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŁA��X�̍�ƂɕK�v�ȑ����̏��邱�Ƃ��o�����A�����͂��̂悤�ȎQ���̋@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���傷�邱�Ƃ����҂���B
�@
�@�@�@�ȏオ�����F����ɓ`���������̖{�̓��e�̈ꕔ�ł��B�������ł��傤���A�������������m��Ȃ��Ԃɋ�����
�@�@�����Ƃ��i�s���Ă��܂��A���̂��Ƃ����{�̏������ǂ��ς��Ă����̂����̕n��ȓ��ł͑z�������܂���
�@�@�̖{��ǂ�ł���Ɖ�������傫�ȓ{�肪�킢�Ă��ĂȂ�܂���B
�@�@�@���̔N�����v�v�]���͓��đo�����o�������Ă���A���R���{���o���Ă��܂����A����Ƃ��Ď������Ă��Ȃ�
�@�@�����ł��B��Ȃ�����ł͂���܂��A�ǂ����F�l�A��x�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�Łu�N�����v�v�]���v
�@�@�Ȃ���̂������Ŋm���߂Ă��������B�����Ǝ��̌����Ă��邱�Ƃ��������Ă���������Ǝv���܂��B
�@�@�@�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�@http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@
�X�����c���͓��{�����ɂƂ��Đ��������v�Ȃ̂�
�@�@����A����H.D���玟�̗l�Ȃ��莆���܂����B
�@�@�O���A�M�Z�ɂ͐V���ȖڕW�Ɍ������čĂъ������n�߂�ꂽ���ƁA���ɂ����c�Ɋ����܂���B�n��ɍ�
�@������������ʂ��ĊC��s������肢�������O�i�����Ă������������܂��悤���҂��Ă���܂��B
�@�@���Đ���A�M�Z�̃z�[���y�[�W�ŗX�����c�������グ�Ă���̂�q�����āA���ɓ������ӌ��ŁA
�@���X�Ȃ���M�Z�̓��@�͂̐[���Ɋ��S�������܂����B�i�����j
�@�@�X���ɂ��Ă͌������܂������A������������v�̖��̂��Ƃō��v�ɔ�����悤�Ȑ������������邱
�@�Ƃ����͂��߂�ւ肽���҂ł��B
�@�@�����̐}���͐挎���s����܂������̂ł����A���݂̎��̑z���Ɠ����ł��̂Ő����x���ڂƂƂ�����
�@�����������肢�����܂��B�ƌ������ƂŁA���̂悤�Ȗ{�𑗂��Ă��������܂����B
�u�D������{�v�i�։��p�V�j
�@�@�ڂ���Ƃ͂��̂��ƂŁA���̂���A�����̍����ɂƂĂ̂킩��ɂ��������X�����c���A�������̋^
�@��_�����炩�ɂȂ�܂����B�����āA���ы��N�c�������ߔ��Δh�̋c���͂Ȃ����̂悤�ɋ��d�ɔ���
�@��̂����A���v���Ȃ��}���̂��A�X�����c����č��ƂȂ��b������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ���������
�@�����̖{�����炩�ɂ��Ă��܂��B�F����ɂ��̖{�̂��ׂĂɖڂ�ʂ��Ă������������Ǝv���܂����A����
�@�ł͗v�_���L���Ă݂����Ƒz���܂��B
�@�@���{��卬���Ɋׂꂽ�X�����c���@�A���{�̏��������ɂ킽��ł��낤�A�l�X�ȉЍ����c�����Q�O�O�T
�@�N�ő�̐����ۑ�́A���ׂď����̎v�f�����Ɍ��������B���̔N�̉ߔ��̎��ԂƃG�l���M�[����
�@����Ƃ�������X�����c���Ƃ́A���ǂȂ����̂��B
�@�@���̗X�����c�����ɂ́A�Ō�܂ł����₯�ɂ͂قƂ�nj���Ȃ��������ʂ�����B���{�̍\��
�@���v�̖{�ہA���邢�͐����Ə���Y�̌l�I���O�A�ȂǂƎ�肴������Ă������̖��̔w���
�@�͕č�����̎��X�Ȉ��͂Ƃ���������̈��q���B����Ă����̂ł���B
�@�@1995�N11���ɕč����{������{���{�ɒ��ꂽ�u�N�����v�v�]���v�ɂ́A�ȈՕی��Ɋւ��Ď���
�@�悤�ȋL�q������B
�@�@�o�č����{�́A���{���ȉ��̂悤�ȋK���ɘa�y�ы������i�̂��߂̑[�u������ׂ��ł���ƐM����B
�@�E�E�E�E�E�X���Ȃ̂悤�Ȑ��{�@�ւ��A���ԉ�Ђƒ��ڋ�������ی��Ɩ��Ɍg��邱�Ƃ��֎~����B�p�Ƃ�
�@��B�@�h�֎~����Ƃ͓��������̂��̂ł͂Ȃ����B�h�@
�@�@�����Ă���ȗ��č����{�͊ȈՕی��̔p�~��v���������A
�@�@1999�N�̗v�]���ł́@�o�č��͓��{�ɑ����ԕی���Ђ����Ă��鏤�i�Ƌ�������ȈՕی�
�@�i�J���|�j���܂ސ��{�y�я������ی����x���g�傷��l�������ׂĒ��~���A�����̐��x�����ł܂���
�@�p�����ׂ����ǂ����������邱�Ƃ��������߂�B�p�܂�č��͊��ƂƂ��Ă̊ȕۂ�p�~���Ė��ԉ�Ђ�
�@�J������Ɨv�����Ă���̂ł���B
�@�@���{�̖��ԕی��s��͉ߋ�20�N�ȏ�ɂ킽���ĕč��ɂ������W����Ă����A���̗��j��U���
�@������ʼn��߂��l����A�X�����c���̖{���͂P�Q�O���~�ɂ̂ڂ銯�c�ی��̎s��J����肾�ƌ���
�@���Ƃ��킩��B�������������c�����������ł͍����ő��̓��{�����̎O�{�߂��K�͂̋���Ȗ��ԕ�
�@����Ђ��a�����邾���̂��Ƃ��A�����A�č����]��ł���̂͂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�č��͖��c��
�@��̊ȈՕی��Ƃ��̎��Y�P�Q�O���~���ǂ����傤�ƍl���Ă���̂��B
�@�@2004�N�̋K�����v�v�]���ɂ͂��̋L�q��v��ƁA�ȕۂ̐��{�ۗL���������S�Ɏs��֔��p��
�@���A�u���{�ۏ����邩�̂悤�ȔF���������ɐ����Ȃ��悤�\���ȕ�����v��点��B�܂萭�{�̊֗^
�@�����S�ɒf���点�����Ȗ��ԉ�ЂƂȂ����ȕۂɑ��ẮA�O���n�ی���ЂƊ��S�ɑΓ��ȋ�����
�@����v�����Ă����B�����Ċȕۂ̏��NJ������Ȃ�����Z���Ɉڊǂ������̗������茟���������A
�@�\���y���V�[�}�[�W���Ȃǂ̌��\���`���Â���v�������Ȃǂ̊č���������B
�@����ɁA�ȕۂ�Ƌ֖@�Ȃǂ̓K�p�ΏۂƂ��A�u���̎s��x�z�͂��s�g���Č���c�Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��悤�v
�@��������ψ���ɒ���������ƌ��������Ƃ��L�q����Ă���B
�@�@�v����ɕč��ɂƂ��Ė��c���̓S�[���ł͂Ȃ��ȕۂ���̉������A�ŏI�I�ɂ͕����A��́A�o�c�j�]
�@�ɒǂ����݁A�l���`��c�Ə��n�ȂǗl�X�Ȏ�i��M���āA�ȕۂ��i���Ă���P�Q�O���~�ɂ̂ڂ鎑�Y��
�@�č��n���ԕی���Ђɋz�������邱�Ƃ��ŏI�I�Ȃ˂炢�Ȃ̂ł���B
�@�@�ȕۂ͏����ł��邱�ƂƁA���R���Ƃ����ȈՂȉ����葱������F�Ƃ��Ă���B���X�ȈՐ����ی����x
�@�́A���Ԃ̐����ی��ɉ����ł��Ȃ��Ꮚ���҂ɂ��ی��Ƃ����Z�t�e�B�l�b�g����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�吳�ܔN�ɑn�݂�����̎҂Ńr�W�l�X�ƌ��������{�Љ�̈��艻���u�ł���B
�@���ꂪ�č��l�ɂ͒P�Ȃ�s��Ƃ��Ă����ڂ�Ȃ��B���艻���u���͂�������̓��{�Љ�ǂ��Ȃ낤��
�@��؊S���Ȃ��̂ł���B�u�����疯�֎����𗬂��v�u���ɏo���邱�Ƃ͖��Łv�ƌ����Ƃ��̖���
�@���{�����̖��ł͂Ȃ��A���{�����̍s�����ɐӔC��Ȃ��č����ԕی���Ђ́u���v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�������ł��傤���A�����͂��K�ߑ����̍���c�����X�����c���ɂ��āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɍ��́A
�@�����̗��v�ɂȂ���̂����Ȃ������ɐ����ӔC���ʂ����Ȃ��̂��A���킩�蒸�����ł��傤���A�{��
�@�͗X�����c���ɍŌ�܂Ŕ������A�^�̍��v����낤�Ƃ��������}�̗E�C����c���B������X������
�@�������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�����ł͂Ȃ������̂��B�ŋߎ��͂��Â������v���Đ���܂���A����
�@�Ђ�����ɉ��̂��߂炢���Ȃ�������ӐM���c���Ɏ^���������A�䂪���̂U�l�̗^�}�c���́A�ǂ�
�@�قnj����ɑ��Đ����ӔC���ʂ������̂ł��傤�B�ނ�͕č��́u�N�����v�v�]���v�m���Ă����̂ł���
�@�����B�@�������̂��Ƃ͐����Ă݂����҂ł��B
�@
�@
�@
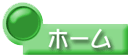 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@

�@�@�@�@�{�ݑg���^�c���S���P���V�A�V�X�S���V��~�̕�
�@�@�@�@���\�Z���v�コ��܂����B
�@�@�@�@�@���̂��Ƃɂ��āA�c�����玿�₪�W�����A��
�@�@�@�@�܂��܂ȋc�_���W�J����܂����B
�@�@�@�@�@���̕�\�Z�́A�ܐF�䐹���ɖ�T�O�O����e
�@�@�@�@�̒��ԏ�����݂�����̂ŁA��ɍw�������U����
�@�@�@�@�̈ꕔ�i��X�O�O�O�j�����Č��݁A���݂�
�@�@�@�@�钓�ԏ�͏����i�I�m��s�S�悪�Q�����j�ɔ���
�@�@�@�@�������݂̗\��n�Ƃ��Ďc���Ƃ������̂ł���B
�@�@�@�@�@����ɑ��c�����炳�܂��܂Ȏ��^���o�����
�@�@�@�@���������̎�Ȃ��̂قƕ����ďЉ��ƁB
�@�@�@�@�@�P�A�@���ԏ��������Ȃ���O���E���h��
�@�@�@�@�@�@�@�ԏ�ɂ���J�����̂ł͂Ȃ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@�O���E���h�́A�ܐF�䐹�����ݎ��n����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������̂ł���A�v�]�ɂ����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł��茻�݂����̂悤�Ɏg�p���Ă���B
�@�@�@�@�@�Q�A�@���݂̃O���E���h�́A������萮������
�@�@�@�@�@�@�@�Ă���A���̊Ԃɂ����N�싅�̃��g����
�@�@�@�@�@�@�@�[�O�̎勅��ƂȂ��Ă��Ė{���ɒn���̂�
�@�@�@�@�@�@�@�߂̃O���E���h�Ƃ��Ďg�p���Ă���̂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@���݂��n���Ƃ̍��ӂɊ�Â��g�p���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���g�����[�O�̎勅��ƂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��āA�g���c��ɂĂ��̈ʒu
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Â����������Ƃ��ׂ��ł́B
�@�@�@�@�@�R�A�@����̒��ԏ������̂ɖ�X�O�O�O�̓y�n������Ƃ������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@���A�Ȃ��U�����w�������̂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@�U���̒n���҂͂W���ŁA�ꊇ���ĂłȂ���Ό��ɉ����Ă���Ȃ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂ł�ނȂ��w�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@����Ȃ�A���̓y�n�̍w���𒆎~���A���̓y�n�i�쑤�̎R�сj���w����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��w�͂͂��Ȃ������̂��B
�@�@�@�@�@�S�A�@���݂̒��ԏ�͏����i�I�m��s�S�悪�Q�����j�ɔ����A�������݂̗\��n
�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��Ďc���Ƃ������Ƃł����A����Ȃ�I�m��s�ɉ������S�����Ă����
�@�@�@�@�@�@�@����悢�o�͂Ȃ����A�܂����ԏꑝ�݂͂��̎��_�Ō��݂�������̂ł͂�
�@�@�@�@�@�@�@�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ف@�����ԏ�݂��傤�Ƃ���̂͌��݂̒��ԏꂪ�傫�ȑ��V�̏ꍇ���Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�߂̓��H�ɎԂ����ӂ�A�n���̕���A���Q��̕��X�ɂ����f������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̂Œ��ԏꑝ�݂����邱�ƂɂȂ����B�܂��A�I�m��s�S�悪�Q���ɂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă͂��̎��_�ŋI�m��s�����̕��S�����Ă����������ƂɂȂ�ƍl
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����B
�@�@�@�@�@�Ƃ��������^�����킳��܂������A���������ł��������̂́A���̎��^�������c
�@�@�@�@������͂��̈Č��͌ܐF��{�ݑg���c��Ō��܂������̂ł��邪�A�A�����Z�ƂȂ�
�@�@�@�@�A�ꕔ�����g����L��A���̉�v���n�������c�̍������S���@�ɂ�錒�S�����f
�@�@�@�@�䗦�ɓ��R�ւ���Ă��邽�߁A���ꂩ��͂����������ꕔ�����g���Ƃ����ǂ��^��
�@�@�@�@�̉^�c��C�������Ƃ�����ɂ͂����Ȃ��A��͂肻�ꂼ��̋c��ŏ\���_�c������
�@�@�@�@�őΉ����Ă����ׂ��A�Ƃ����O��ɗ����Ď��₳�ꂽ���Ƃł��B
�@�@�@�@�@���́A����̖��ɂ��Ă͓��R�A�ꕔ�����g����L��A���ł����Ă��A������
�@�@�@�@����傫�Ȏ��Ƃɂ��Ă͂��ꂼ��̋c��ŋc�_���A���̌��ʂ������āA�c���
�@�@�@�@�\�̋c���͑g���c��ɗՂނׂ��ƍl���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@����̌��ɂ��ẮA�ꕔ�̑g���c�����玩���������\���ɑg�ݍ����c��ŋc
�@�@�@�@�_���Č��߂����ƂɂƂ₩�������̂͂������������������������Ă��܂������A��
�@�@�@�@�͂��̌��ʂ͑��d���ׂ��Ǝv���܂��A���������A�g���c��łǂ�Ȃ��Ƃ��c�_����
�@�@�@�@���̂��A���Ȃ�����ł͌��ʂd���Ȃ�����{��c�ł̎��^�͂�ނȂ�
�@�@�@�@�̂ł͂Ǝv���܂��B
�@ �P�A�@�C��s�����̌��đւ����ɂ��āB
�@�@�@�@���������܂����A���̊���͏����̒��Ɍ��݂�
�@�@�@�@�����Ċ����ςݗ��ĂĂ������̂ō��N�x�͂P���S
�@�@�@�@���~�̗\�Z���v�コ��Ă���܂��B
�@�@�@�@�@�s���ǂ̐����ɂ��܂��ƁA�s�������݂ɂ͍���
�@�@�@�@�⏕�����t���Ƃ������x�����S���Ȃ��A���ׂĎ��O�ł܂��Ȃ�
�@�@�@�@�Ȃ���Ȃ�Ȃ����ߌ��݂̎����Ƃ��Ă͂P�O�N�悩�A�P�T�N��ɂ͕K�����đւ��Ȃ�
�@�@�@�@��Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂����z���ď����ł������߂Ă��������Ƃ̂��Ƃł���܂����B
�@�@�@�@�@���Ȃ݂Ɍ����ɂ͔��ɌÂ��k�x�U���x�̒n�k�ɂ͑ς����Ȃ��Ɨ\�z����Ă���A
�@�@�@�@�ϐk���C���o���Ȃ��L�l�ł��A���͎s�������đւ��ɂ��āA�s���̊F�l���獡�͏\
�@�@�@�@���ȗ����������Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A����C�n�k�̂��Ƃ��l����A���̒��ŋ�
�@�@�@�@������吨�̐E����A�s������K���s���̊F�l�̈��S���l�����ꍇ�����������
�@�@�@�@�đւ���]��ł��܂��B
�@�Q�A�@�C��s���a�@�̌��đւ����ɂ��āB
�C��s���a�@��{�\�z(��)�����\����܂����B
�����Q�T�N�ɊJ�@��
�@�@�@�C��s���a�@�́A���݁A�a�����A���167���i�ғ�137���j�A�f�ÉȂ͓��Ȃ��͂���10�f��
�Ȃ����f�Â��s���Ă��܂��B
�@�@�@�C��s�̒��j��Ë@�ւƂ��āA�s���̈��S�ƌ��N������Ă���A�s������́A����Ƃ��s
�@�@���a�@�ł̈�ÃT�[�r�X�̏[����]�ސ��������B
�@�@�@�������Ȃ���A���a38�N�̖{�ٌ��݂�����ɒz��40���N���o�߂��A�{�݂̘V�����A��襉�
�@�@�������ɂȂ��Ă���B���{�݂͑ϐk���̖��͂������̂��ƁA���҂̃A���j�e�B�⌻�݂�
�@�@��ËZ�p�����ւ̑Ή��A���S�Ǘ��A�Ɩ������̌����}�邱�ƂȂǗl�X�ȓ_�ŁA���߂���
�@�@��ÃT�[�r�X�̒�����ȏƂȂ��Ă���A���Ґ��̌����A�o�c�̈����ւƌq����
�@�@����B
�@�@�@���̂悤�ȏ̒��A����A�s���a�@���A�s���̗v�]�ɉ����A�C��s�̒��j��Ë@�ւƂ�
�@�@�āA����Ƃ��p�����Ēn���Â�W�J���Ă������߂ɂ́A�V�z�ɂ��{�ݐ������s���Ă���
�@�@���Ƃ��s���Ƃ�����B
�@�@�@�s���a�@���A����Ƃ��A�n��̒��j��Ë@�ւƂ��āA�s�����K�v�Ƃ����Â���Ă�
�@�@�����߂ɂ́A�w�s���a�@�̖����̖��m���x��}���Ă������Ƃ��ł��d�v�ƂȂ�B�s���a�@���A
�@�@�����镪��ɂ����Ċ����Ȉ�Â����߂邱�Ƃ͍���ł���A�o�c�̎��_������K���łȂ��B
�@�@�n���Ì��̒��ŁA���߂Ďs���@�a�@�̖������������K�v������B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA���̂قNJC��s���a�@��{�\�z(��)�����\����܂����A���̎�Ȃ��̂���
�@�@��܂��B
�@�@�P�j�V�a�@���ݗ\��n
�@�@�@�@�@�C��s�͗\��n�Ƃ��āA�W���X�R�Ւn�ƊC�쎄�����Z�����n�Ƃ��Č������Ƃ��Ă�
�@�@�@�@�܂����A���́A�����炭�W���X�R�Ւn�Ɍ��܂�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@�@�Q�j�a����ʂƕa���K��
�@�@�@�@ �@�a�����
�@�@�@�@�@�@�@���}�����a�����܂ވ�ʋ}�����a�@�i��10���l��̕a�����F�S������707���A�C
�@�@�@�@�@�@��s448���j�Ƃ��A���A�×{���i�ݑ�E�{�݁j���̋@�\�ɂ��ẮA������
�@
�@�@�@�@�@�@���ڒS���Ă���n��̈�Ë@�ցE�����{�݁E���T�[�r�X���Ə��Ƃ̘A�g�ƌ��
�@�@�@�@�@�@�x���@�\�̏[����}���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����������A�s���Ƃ��č\�z���Ă�
�@�@�@�@�@�@�����Ƃ��}���ƂȂ��Ă���w�n���P�A�̐��x�̘g�g�݂̒��ŊC��s���a�@
�@�@�@�@�@�@�i�n��A�g���E�K��Ō�X�e�[�V�����j���n��A�g�̒��j�ƂȂ�A���̖������ʂ�
�@�@�@�@�@�@���Ă������Ƃ��ł��d�v�ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@ �A�a���K��
�@�@�@�@�@�@�@�V�a�@�̊Ō���10�F�P�Ƃ��A�K���a���K�͂́A��ʕa���i���}���a���܂ށj
�@�@�@�@�@�@�@50���~�R�a����150��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���Ȍn�a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�O�ȁE���`�O�Ȍn�a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�����E���}�����E�J���a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@ �B�f��
�@�@�@�@�@�@�@�@���ȁ@�A�O�ȁ@�B���`�O�ȁ@�C�����ȁ@�D��A��ȁ@�E�w�l�ȁ@�F��ȁ@
�@�@�@�@�@�@�@�G���@��A�ȁ@�H�畆�ȁ@�I�����ȁi�y�C���N���j�b�N�j�@�J���ː��ȁ@
�@�@�@�@�@�@�@�K������Z���^�[(�������Z���^�[)
�@�@�@�@�@�@�@�����f�Z���^�[
�@�@�@�@�@�@�@������Z���^�[�i�������Z���^�[�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�ߔN�A�d�q�������̕��y�ƂƂ��ɓ����������̏d�v���͂܂��܂����債�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��킯�㕔����������ǂɂ��Ă͌��������A�Ώۊ��҂Ƃ��������Ă���A�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏d�v�Ȍ�������ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂������펾���ł͌����ƂƂ��ɓ���������p�������ɍs����P�[�X����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������A�V�a�@�ɂ�������̈�̒��̈�Ƃ��āA���ȁA�O�Ȃ��A�g����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̏�����Z���^�[�i�������Z���^�[�j��ݒu����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E������n�������ݔ����[�����A���A���ŁA�ŋۑ�����s���X�y�[�X�Ɛݔ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������ɐ�������B
�@�@�@ �@�@�@ �E������̉Ɗ��ҊĎ����u��ݒu����B
�@�@�@�@�@�@�@���f�Z���^�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�s��(���N��)�ƈ�̂ƂȂ����ݒu���������A�s���̕ی��t�A�Ǘ��h�{�m����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���f�@�Z���^�[�Ƃ̘A�g�A���̋��L����}������I�ȉ^�c���s���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���茒�f�A����ی��w�����̏[����}��ƂƂ��ɁA���p�҂̃j�[�Y�ɑΉ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������A��h�b�N�E�h���h�b�N�𒆐S�Ƃ������f���j���[�̐ݒ���s���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�s���̗��������߂邽�߁A���݂̋x�����f�̊g�[����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���茒�f�A����ی��w���A�l�ԃh�b�N�A�e�킪���ΏۂƂ������f�ɂ��āA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�@�L�A�s��A�z�[���y�[�W����ʂ��Ďs���ɂ��L����M����B
�@�@�@ �C�V�a�@�̌��݂ɌW��A�������ݎ��Ɣ�B
�@�@�@�@�@ �E�V�a�@���݂ɌW�鑍��p�́A4,300,000��~�ł���B
�@�@�@�@ �D�V�a�@�̌��݃X�P�W���[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�V�a�@�̌��݃X�P�W���[���͈ȉ��̒ʂ�Ƃ��邪�A���a�@�̏i�{�݂̘V��
�@�@�@�@�@�@�@���A�ʂ����ׂ���Ë@�\�y�ьo�c���P�̍���j����A�ł�������肱�����
�@�@�@�@�@�@�@�����J�@���ׂ��w�͂��邱�Ƃ��]�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E��{�v�F����21�N10���`����22�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���{�v�F����22�N�S���`����23�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���ݍH���F����23�N�S���`����25�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�a�@�J�@�F����25�N�S��
�@�@�@�@�@�@
�@�R�A�@�C��s�h�Б�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�C��s�̖h�Б�͖{�N�i�����P�X�N�j�R���ɍ��肳�ꂽ�C��s�n��h�Ќv���
�@�@�@�@�@�����đȂ���Ă������ƂɂȂ�B�n��h�Ќv��ł́A�����ł��ǂ��ł��N��
�@�@�@�@�@�肤��ЊQ����s���̐����A�g�̋y�э��Y��ی삷��ƂƂ��ɁA�h�Ђ̂��߂̔���
�@�@�@�@�@�����������[�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���̂��߉ߋ��̑�ЊQ�����P�Ƃ��A�{�s�̒n
�@�@�@�@�@���I�����A����A��A�Љ�\���̕ω������l���ɓ���A�s�A���y�ъW�@��
�@�@�@�@�@�Ǝs������̂ƂȂ��čЊQ�ɋ����܂����𐄐i���邱�Ƃ��d�v�ŁA���̂��߂ɂ́A
�@�@�@�@�@�s�̖h�Ў{��̕�������A�g�߂Ȗ��ł���ЊQ���̖h�Б̐��Ȃǖh�Б���
�@�@�@�@�@�ۑ�ɂ��āA���펞�����Ў������펞�̍ЊQ�T�C�N���Ŏ����A�ݏ��E�����A����
�@�@�@�@�@�̊ϓ_���炵���݂Â�������邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�@�@�@�@�@�����Ėh�ЂɊւ����{�ڕW�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@���@�h�Ќ���Ɍ������܂��Â���B
�@�@�@�@�@�@�@���@�h�Ќ���Ɍ������l���B
�@�@�@�@�@�@�@���@�ЊQ�ɋ����̐��i�g�D�j���B
�@�@�@�@�@�̂R�_�̖h�Ѓr�W������������A�ЊQ�\��v��A�ЊQ���}��A�ЊQ�����A����
�@�@�@�@�@�v�悪�ׂ������Ă��Ă���B
�@�@�@�@�@�@����ł͂��̊�{�v��ɂ��ƂÂ���̌���́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C��s�Ôg��A�C��s�����̈�قւ̖h�Ћ��_�̐ݒu�A�C��s�����̈�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ق̒������A�y�ъe�n��̔��̐ݒu�A�e�����{�݂̑ϐk�f�f�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���C�A���Òn��̍�����A����h�Бg�D�̐ݗ��h�ЌP���̎��{�A�Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g���s������B
�@�S�A�@�C��s�Ôg��ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�a�̎R���Í`�i�C��n��j�̎��Ӓn��ɂ����ẮA�n�`�I�ȓ�������ߋ��Ɋ��x
�@�@�@�@�@�ƂȂ��Ôg�Z����Q���Ă��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���ɁA����R�O�N�ȓ��ɓ�C�n�k���T�O���A����C�n�k���U�O�`�V�O���̊m����
�@�@�@�@�@��������ƌ����Ă���A���n��ɂ͍�����T������Ôg�����P����ƌ����
�@�@�@�@�@�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���̒n�k�����ɔ������n��̒Ôg�Z����Q�́A��4,900���сA��13,000�l�ɋy�сA
�@�@�@�@�@�n��S�̂őz�肳����Q�z�͖�5,000���~�ƁA�a�̎R�����ōő�̔�Q���\����
�@�@�@�@�@��Ă��܂��B�܂��A���ݕ��ɂ͎s��������h�E�x�@�E�s���a�@���̎�v�����{�݂�
�@�@�@�@�@���łȂ��A�d�́A�S�|�A�Ζ����̎�v��Ƃ����n����ق��A���s�E�a�̎R�s�ƋI��
�@�@�@�@�@�n�������ԁA�����S�Q�����ʉ߂��Ă��邽�߁A��Q�����ꍇ�A���암�ւ̕���
�@�@�@�@�@�E�l���̃��C�t���C������Ⴢ���ƍl�����܂��B
�@�@�@�@�@�@���̂��߁A�n��Z���E�ՊC�����n��Ɠ��̊�@�ӎ��͍����A�Ôg��ɂ��āA
�@�@�@�@�@�n�悩����ɋ����v�]������Ƃ���ŁA���̂悤�ȏ̒��A�C��s�A�ՊC����
�@�@�@�@�@�n��v��Ƌy�ю�����̊�����̂ƂȂ������c���ݗ����A����A���y��ʏȋy
�@�@�@�@�@�јa�̎R���ɑ��āA�a�̎R���Í`�i�C��n��j�ł̒Ôg��̑������{�Ɍ���
�@�@�@�@�@���v�]���������s���Ă������Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B
�@�@�@�@�@�@�Ôg��̊T�v�i�ڍׂ͍��y��ʏȋߋE�n�������ǂɂ����Č������j
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@��H�@�@�@�@������݂̐��グ�A�q�H���ւ̐���̐ݒu�A�h�g��̐V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�ѐ��グ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����Ɣ�@�@�@200�`300���~
�@
�@�T�A�@�C��s�����w�Z�̓����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�w�Z�����ɂ��āA����ψ���ł͏��q���̐i�W�ɂ��q���̐��̌����ɔ����A
�@�@�@�@�@�w�Z����ɗl�X�Ȗ�肪�����Ă��Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�ȏɑΉ����āA��
�@�@�@�@�@�͂���w�K�����ێ����邽�߁A�w�Z�̓K���K�́A�K���z�u��i�߂Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�K���K��
�@�@�@�@�@�@�@�c�t���@�@���Ȃ��Ƃ���̉��ɕ����̃N���X�A�P�N���X�P�O�l�ȏ�̉�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���K�v�B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�N���X�ւ��̏o���鎙�������]�܂������A�Œ�ł��P�N���X�Q�O�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�̐l���͕K�v�B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�P�w�N�S�w���A�w�Z�S�̂łP�Q�w�����x�B
�@�@�@�@�@�@�K���z�u��
�@�@�@�@�@�@�@�c�t���@�@�m�`�c�t���A���Α��A���̂R�c�t������̗c�t���Ƃ��A����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Α��c�t���{�݂��ĊJ������B
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ÁA�哌�A���c�t���̂R�c�t������̗c�t���Ƃ��A���哌�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t���{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���×c�t���͌��s�̒ʂ�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�m�`�A���Α��A���̂R���w�Z����̏��w�Z�Ƃ��A�����Α��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ÁA�哌�A��菬�w�Z�̂R���w�Z����̗c�t���Ƃ��A���哌��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���Ï��w�Z�͌��s�̒ʂ�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���C����ɂ��Ă͋��犈���̊��͂��ێ�����ϓ_����A�K���K
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��ۂ����悤�A���Z�⏬�K�͍Z�̂��肩���ɂ��Č�����i��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@���Ñ��A���̓�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A���Ñ�w
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�C����A���A��O���w�Z�̎O�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�T��A�F���w�Z�̓�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A���c�r���Ӓn
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���J������B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���C�쒆�w�͌��{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�X���c��̎��̈�ʎ���ŁB
�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�̓������ɂ��ẮA�C����A���A��O
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�̓����́A��O���w�Z�����㕽���R�O�N�܂ł͈�
�@�@�@�@�@�@�@�w�N�R�w�����ێ��ł���Ƃ������Ƃ���A�P�Ƃł�����
�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̕ی�҂̋����v�]�ɂ��A�Ƃ肠�����͊C����
�@�@�@�@�@�@�@�A��w�Z���s���ē�������Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�T�쒆�w�Z�ƒF���w�Z�ɂ��ẮA���c�r����
�@�@�@�@�@�@�@�n���J���ɂ͂U�O���ȏ�Ƃ����c��Ȕ�p��������A��
�@�@�@�@�@�@�@�̂��Ƃ��s�����Ŏ����̂߂ǂ������Ă��Ȃ�����ł���
�@�@�@�@�@�@�@�A����ψ���Ƃ��Ă��A�T��A�F�Ƃ��ɂ��ꂼ�ꌻ�n�J
�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ������Ƃ�����ɓ���Ȃ���A�Č��������Ă�����
�@�@�@�@�@�@�@�������ƂɂȂ�܂����B
�@
�U�A�@�����S�Q�����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�����S�Q�����ɂ��Ă͍����S�Q����ʏa�ؑc��i�L�c�s�A�C��s�A����
�@�@�@�@�@�ȁA���A�x�@�j���тɍ����S�Q���L�c�C��Ԑ������i���c��i�L�c�s�A�C��s�A�L
�@�@�@�@�@�c�S������j������A�����S�Q����ʏa�ؑc��ɂ����Ă͒Z���I�ȏa�؉���
�@�@�@�@�@���Ƃ��āA�L�c�s����C��s�Ɏ���Ԃ̊e�a�،����_�̉��ǂ�A�������������Ȃ�
�@�@�@�@�@�̌��������Ă������ŁA����܂ŁA�L�c�s���������̌����_�A���Ò����c�����_�A
�@�@�@�@�@��������_�A�����ĕ����P�X�N�R���ɂ͊C��s�␅�����_�̉��ǂ����{����܂����B
�@�@�@�@�@�܂��A�����ĕ����P�U�N����͍��������̈������������{����A�����̌�ʗʒጸ
�@�@�@�@�@���}��������B
�@�@�@�@�@�@����A�����S�Q���L�c�C��Ԑ������i���c��ł́A�����Q�Ԑ��A�o�C�p�X�Q�Ԑ��A
�@�@�@�@�@�v�S�Ԑ��ł̐����v�]�����ĎQ�������A���y��ʏȋߋE�n�������ǘa�̎R�͐썑��
�@�@�@�@�@�������ł́A�o�C�p�X���[�g����Ɍ����A�����P�V�N�x�����ӂ̊��������I���A
�@�@�@�@�@���N�x�ɂ����Ĉ�ʍ����S�Q���␅�g�����ƂƂ��āA�␅�����ԉ�����P�D�P����
�@�@�@�@�@�����Ɖ�����A�{�N�P�O���ɂ͒n���Z���̊F�l�ւ̎��Ɛ�����J����A���̌�H
�@�@�@�@�@�����ʁA�n�����������{���ė\���v�ɓ����Ă����\��܂��A����ƕ��s���č��N
�@�@�@�@�@���ɂ͓s�s�v�挈�肳���\��ł���Ƃ������Ƃł��B
�@
�@�V�A�@�����R�V�O�����̃o�C�p�X�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@���̎��Ƃɂ��Ă͂����Ԃ�ȑO����v�悳�ꂽ�Ȃ��ւ�炸�A�n�����ӂ��Ȃ�
�@�@�@�@�@�Ȃ�����ꂸ�A�n���̊F�l�̋��͂ƊW�҂̓w�͂ɂ��悤�₭�����P�U�N�P�Q��
�@�@�@�@�@�Q�S���ɓs�s�v�挈�肳��A���גr�炩��ؒÌ����_�t�߂܂ʼn�����Q�C�T�S�O
�@�@�@�@�@���A�����Q�O���̗\��ŕ����P�V�N�x��茧�ɂ����Ď��Ɖ�����܂����B
�@�@�@�@�@�@���݂͋N�_������I�z��s�t�߂܂ł̖��P�C�T�U�O���̋�Ԃ���H��Ƃ���
�@�@�@�@�@���Ƃ�i�߂Ă��܂��A���݂͑��H����Ō����p�n�̗������Ƃ�i�߂Ă��茻
�@�@�@�@�@���_�łU�����x�̗�������I���Ă���Ƃ������Ƃł��A�܂��A����ƕ��s���Čv
�@�@�@�@�@�擹�H�̐�������A�������̃R���T���^���g��Ђ����������ɏ����͂����Ă����
�@�@�@�@�@���ł��B
�@
�@�W�A�@��a�����ԓ��i�C��g���ԁj�̎l�Ԑ����ɂ��āB
�@
�@�@�@�@�@�@��a�����ԓ��i�C��g���ԁj�̎l�Ԑ����͕����W�N�P�P���Q�X���ɓs�s�v�挈��
�@�@�@�@�@����A�����P�O�N�P�Q���Q�T���ɍ��̎{�H���߂��o����A�����P�S�N�V���ɑ��ʒ�
�@�@�@�@�@�����J�n�A�����P�T�ʂV������p�n�����n�܂�A�����A���ÁA����̊e�g���l��
�@�@�@�@�@�H���͕����P�U�N�ɒ��H�A�C��A���ÃC���^�[�`�F���W�͕����P�V�N����J�n����
�@�@�@�@�@�Ă���A�����Q�S�N�x�ɂ͏㉺���Ƃ������̗\��ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@
�@�X�A�@�C��s�������ɂ��āB
�@
�@�@�@�@�@�@�C��s�̉������ɂ��Ă͑S���ł��Œ�ɋ߂������̒B�����ł����A���݊���
�@�@�@�@�@���Ă��鉺���������A�����Ƃ����_����łȂ����Q��ɏd����u�����������ł���
�@�@�@�@�@�܂��A�ł͊C��s�͉��������ǂ�����̂��Ƃ����ƁA�{�N�S���ɏo����܂����C��
�@�@�@�@�@�s�����v��ɂ��ƁA�������̌��݂͂��Ȃ��Ƃ������_�ł���C��s�̛��A������
�@�@�@�@�@����Ƃ��ẮA�܂������������̕��y�ɓw�߂Ă����Ƃ������Ƃł���܂��B
�@�@�@�@�@�@���͉��������݂ɂ͐��S���Ƃ����c��Ȏ�����K�v�Ƃ��܂����������̐ܒv��
�@�@�@�@�@���Ȃ��Ǝv���܂����A����Ȃ�Ό��ݔ_�����ł͔_�Ɨp���H�֏��̕��������
�@�@�@�@�@�����Ă��錻�����ӂ܂��A�_�Ɨp���H�̉��C��L����Ƃ��Ă̐��ʂ̊m�ۂƂ���
�@�@�@�@�@�����Ƃɗ��ӂ��Ă������������ƍl���Ă��܂��B
�P�O�A�@�����H���C����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�����C��H�����ɂ��ẮA���݂����r�̊������Ŋg���H�������{���Ă���܂�
�@�@�@�@�@���A���㊎���n�����o�đ��c�n����o�Ęa�̎R�s�Ɏ��镔���̉��Ǘ\��͑S���o��
�@�@�@�@�@�Ă��Ȃ��̂�����ł���܂��B
�@�@�@�@�@�@���Y�����͔��ɋ�襂ō����̎����Ԃ̑�^���ɔ����R���܂܂Ȃ炸���[�̃�
�@�@�@�@�@�b�V�����ɂ͒���t�߂̏Z���͂��Ƃ��ʋΎ҂����ɍ����Ă���̂�����ł�
�@�@�@�@�@��܂��B
�@�@�@�@�@�@����A�C��C���c�A�i�C��s�c��A�I���쒬�c��j�ɂ����č��N�x���猧���
�@�@�@�@�@���킹�A�����C��H�����̊g���ɂ��Ă��v�����s���Ă����Ƃ������ӂ��Ȃ����
�@�@�@�@�@�����B
�@�@�@�@�@�@
�P�P�A�@�����C��������̃o�C�p�X�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�����C��������̉��C�ɂ��ẮA���a�S�W�N�Ɍ����C����������C���i���c��
�@�@�@�@�@�i�C��s�A���������j���ݗ�����A�܂��A�C��s�ʏ��n������Q�E�������ėL�c��
�@�@�@�@�@������Ɏ���Ԃ̉��C���������{����A���̌�A�d���A�����쉈���̖����C�Ԃ�s
�@�@�@�@�@�v�擹�H�Ƃ��āA�����U�N�ɂ͗����c�Ì������s�s�v�挈�肢����A�����P�Q�N��
�@�@�@�@�@�莖�ƒ��肳��Č��ݗp�n���A�H�������{����Ă���B
�@�@�@�@�@�@�ߔN�L�c������̎ԗ��̒ʍs���������������A�d���n�悩��ʏ��n��Ɏ��鋷�
�@�@�@�@�@�ȓ��H�Ō�ʏa�������N��
�@�@�@�@�@���A���s�͂��Ƃ����ӏZ���̐����ɂ��傫�ȉe���𗈂��Ă���A����Ɍ����ΎR
�@�@�@�@�@���錧���͋}���z�A�}�J�[�u�A�Z���A�~�G�̐ϐ�A������������X�̈�������
�@�@�@�@�@�狾�g���l���̌��݂��]�܂�Ă���B
�@�@�@�@�@�@���ł͕����P�V�N�x���狾�g���l���̒����𑱂��Ă��邪�A���ニ�[�g�����
�@�@�@�@�@�����Ă̒��������{����\��ŁA���݁C�n�������Ɍ����ď������Ƃ̂��Ƃł��B
�@
�P�Q�A�@�C��s�̃S�~�����{�݂ɂ��āB
�@�@�@�@�@�@�C��s�̃S�~�����{�݂͏��a�T�U�N�ɋ��p�J�n�˗��A�����R�N�Ƀ_�C�I�L�V����
�@�@�@�@�@����H�����s���A�����܂łQ�U�N�ԉғ����Â��Ă���܂��A�v�����g���[�J�[��
�@�@�@�@�@���ϗp�N���͂P�O�N�ł����A���̌�̈ێ��Ǘ����K���ł������̂��傫�Ȏ��̂�
�@�@�@�@�@�Ȃ������ɉ^�]�𑱂��Ă��܂��A�������ߔN�A�{�s�̃S�~�����ʂ������A����ɂ�
�@�@�@�@�@���̋��Ă���Ƃ͂����A�ꕔ�̎Y�Ɣp�����܂ŏ������A�܂��A���̎s���̃S
�@�@�@�@�@�~�܂ŏ������Ă��錻��ł́A���܂Ŏ��̂����S�z�ł���܂��B
�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�S������́A���Ò��̃S�~�����{�݂��^�]���~����Ƃ̂��ƁA�]��
�@�@�@�@�@�ĂS������͉��Ò��̃S�~���ꏏ�ɏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����A�����
�@�@�@�@�@�������������Ȃ��Ƃ��Ă��A�\�͓I�ɂ��]�T������Ƃ��Ă��A�����V�������Ă���
�@�@�@�@�@����{�݁A��������������S�~�����ꌚ�݂Ɍ����Ă̎��g�݂��]�܂�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@����Ȓ��A�{�s���A�L��ł̃S�~�����ɕ��j�����߁A�C��s�A�I���쒬�A�I�m��
�@�@�@�@�@�s�ƂƂ��Ɂu�L��S�~�����{�ݐ������c��v�𗧂��グ�����P�X�N�P�O���P�P����
�@�@�@�@�@�犈�����n�߂܂����B
�@�@�@�@�@�@�V�����L��S�~�����ꌚ�݂Ɍ����ē����n�߂܂������A�����炭�A�e�s��������
�@�@�@�@�@����𗘗p���傤�Ƃ���V�N��ɂ͊�������ł��傤�A���łɌ��n���I�m��
�@�@�@�@�@�s�A�I���쒬�ł��ꂼ��P�ӏ��������Ă���Ƃ��������Ƃł�����A����ǂ͊Ԉ�
�@�@�@�@�@���Ȃ����݂Ɍ����Đi�ނ��Ƃł��傤�B
�{�s�̊w���ۈ�ɂ��Ă̌���Ɖۑ�B
�@�@�@����A�T��n��̂��镃�Z����w���ۈ�ɂ��Ă̑��k������܂����B
�@�@�@�@�@���̕��͋T��n��ɍݏZ���A�v�w�������ŁA���N����q�������w�̏��w�Z�ɒ�
�@�@�@�@�@�����ƂɂȂ�A�T��̊w���ۈ��\�����Ƃ���A������T�O�l�łT�R�l�̉��傪��
�@�@�@�@�@��A���ɂ��T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙�����D�悷��ƌ����A�T�R�Ԗڂ̐\����
�@�@�@�@�@�Ƃ��đI�l����͂����ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���Ȃ݂ɃI�[�o�[�������̂Q�l�������ł��Ȃ������ƌ������Ƃł��B
�@�@�@�@�@�����Ŏs�̎q��Ďx���Z���^�[�̒S���҂��獕�]���w�Z�̊w���ۈ炪����ɒB����
�@�@�@�@�@���Ȃ��̂ł����ɒʂ��Ă͂Ɛi�߂��A��ނȂ����]�ɐ\�����Ƃ���A����ǂ͊w
�@�@�@�@�@�Z����o�X�ɂč��]���w�Z�̋߂��̃o�X��i�Z�傩���R�O���j�ō~��A�w���ۈ珊��
�@�@�@�@�@�ʂ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�o�X�₩�狳���܂ő��}����l���Ȃ���Ύ�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�Ƃ����A�S���҂���g���ɒN���Ȃ��ꍇ�̓T�|�[�g�Z���^�[���瑗�}�̂��߂̔h
�@�@�@�@�@�����Ă͂ǂ����Ƃ̘b������A�}���͒v�����Ȃ��Ƃ��Ă��킸���R�O�����悤�̂�
�@�@�@�@�@�T�|�[�g�Z���^�[�ɂ��肢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��p��������A���Ƃ��Ȃ�Ȃ���
�@�@�@�@�@���Ƃ��肢���܂������A����͂��邱�Ƃɂ��Ă͎s�̏��Ɍ��߂��Ă���̂łǂ�
�@�@�@�@�@���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ���ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���̕��͎s�̏��Ɍ��߂�ꂽ���j�ł���Ύd�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�����ƒN�������p
�@�@�@�@�@�ł��鐧�x�ɂȂ�Ȃ��̂��B�Ƃ������Ƃő��k�Ɍ������܂����B
�@�@�@���̘b���Ď������������Ƃ�
�@�@�@�@�@�܂��A���������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�C�T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙���̂��߂̊w���ۈ�ƌ������ƁB�T�쏬�w�����D�悷��ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������̒n��̊w���ۈ�����������ł���B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�A�T��n��ɏZ��ł��Ȃ���A���w���ɂ��悤�ƒ�ɑ���z�����S���Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�A���}�ɂ��āA���ɑ���ɂ��Ă͏��ɂ���ċ`���Â����Ă��邻���ł���ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�A����A���Y�����̑��ɁA�T�쏬�w�Z�ɒʂ��q���B�Q��������I�[�o�[�Ƃ������Ƃœ����ł��Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ł����A���q����Ƃ��Ă̎s���ɈՂ����{��Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�����ŁA�w���ۈ�ɂ��ĊȒP�ɒ��ׂĂ݂܂��ƁB
�@�@�@���������@�ł̒�`�H�i�w���ۈ�Ƃ�������g�p���Ă��Ȃ��B�j
�@�@�@�@�@�u���̖@���ŁA���ی㎙�����S�琬���ƂƂ́A���w�Z�ɏA�w���Ă��邨���ނ�10��
�@�@�@�@�@�����̎����ł��āA���̕ی�҂��J�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA����
�@�@�@�@�@�Œ�߂��ɏ]���A���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p���ēK�ȗV
�@�@�@�@�@�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}�鎖�Ƃ������B�v
�@�@�@�@�@�i��U���̂Q��V���j
�@�@�@�����E���T�Ȃǂɂ���`
�@�@�@�@�@�u�e�������Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A�ƒ�
�@�@�@�@�@�ɂ����ۈ���s���{�݁E���ƁB�v
�@�@�@�@�@�u���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w�����C���ی��莞�ԕۈ炷�邱
�@�@�@�@�@�ƁB�v
�@�@�@�w���ۈ�̉^���c�̂ɂ���`
�@�@�@�@�@�u�E�E�E�E�E�������ƒ���q�E���q�ƒ�̏��w���̎q�ǂ������̖����̕��ی�
�@�@�@�@�@�i�w�Z�x�Ɠ��͈���j�̐��������{�݂��w���ۈ�ł��B�w���ۈ�Ɏq�ǂ�����
�@�@�@�@�@���������Ĉ��S���Đ��������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ���āA�e���d���𑱂����
�@�@�@�@�@�܂��B�w���ۈ�ɂ͐e�̓��������ƉƑ��̐��������Ƃ�������������܂��B�v
�@�@ �@ �ȏ�̂悤�ɁA�w���ۈ�ɂ��Ē�`�Â����Ă��܂����A�n���̊w�Z�ɒʂ���������
�@�@�@�ۂƂ����悤�Ȃ��Ƃ͑S���ӂ���Ă��Ȃ����A�܂��厖�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐e��
�@�@�@�����Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A���̕ی�҂��J
�@�@�@�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p����
�@�@�@�K�ȗV�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}��B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA�n���̏��w�Z�ɒʂ������Ɍ��肵���l�Ȓ�`�Â����S���Ȃ��ꌾ���܂���B
�@�@�@�s�̒S���҂Ƃ̂��Ƃɂ��Ă̋��c�̒��ŁA
�@�@�@�@���}�ɂ��āA���ɂ�茈�߂��Ă���Ƃ��������͊ԈႢ�ŁA��W�v���ł́A�u�w��
�@�@�@�̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��Č}�����K�v�ł��B�܂��y�j����ċx�ݓ��̒����x�Ɗ��Ԓ�
�@�@�@�̊w���ۈ�ɂ��Ă�����}���������Ƃ��܂��B�v�L����Ă���A���ł́u�ۈ�I
�@�@�@����̎����̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��ĕی�҂��}���邱�ƂƂ��܂��v�Ƃ̋L�ڂ���
�@�@�@��A����ɂ��Ă͓y�j���y�ђ����x�Ɠ��ȊO�͓��ɂӂ���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@�@�@�@����ɁA�S���҂̕������Ƃ��R�O���̓��̂�ł����Ă����̊ԂɎ��̂ł���������Ύs
�@�@�@�̐ӔC����ꂩ�˂Ȃ����Ԃ��l���A�ی�҂�[���������߂Ɏv�킸���������o������
�@�@�@�ł͂Ȃ����B�����Ă������Ƃł͂Ȃ����A����͂���Ƃ��āA����Ȃ��Ƃ��̐e�̐ӔC�Ƃ�
�@�@�@�������Ƃ��������Ƃ��đΉ����ׂ��ł͂Ȃ����
�@�@�@�@�܂��s�O�̏��w�Z�ɒʂ������ɂď��ł͊C��s�w���ۈ����R���Ɂu�w���ۈ�̑�
�@�@�@�ۂƂȂ鎙���́@�i�P�j�s���̏��w�Z�ɏA�w���Ă�����w�N�����R�w�N�܂ł̎�����
�@�@�@�ی�҂��J�����Œ��ԉƒ�ɂ��Ȃ����́B�i�Q�j�O���Ɍf������̂̂ق��A�s��������
�@�@�@�K�v�ƔF�߂����́B�v�ƂȂ��Ă���B����̃P�[�X��(�Q)�ɑ�������̂ł͂Ȃ�����
�@�@�@�v���邪�ǂ��葱������������̂��Ƃ������Ƃ��낪�s���ł���A����������Ă��Ȃ��B
�@�@�@���̓_�ɂ��Ă͕ی�҂̗���ɗ��������J�ȑΉ����K�v�ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�@���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w����ΏۂƂ������Ƃ��炷��Ό}���͂Ƃ�
�@�@�@�����A����ɂ��Ă͓��R�d�����ł�����A�s�������悤�ɃT�|�[�g�Z���^�[�𗊂�Ȃ�
�@�@�@��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����A�o�ϓI�Ȗʂ�����A����̃P�[�X�̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�ی�҂�
�@�@�@�ӔC�͈̔͂őΉ����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɋT��̏ꍇ����Q�O���Z�O��
�@�@�@�s���������Ĉړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ɂ��Ă͉���Ή�����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�ȏ�̂��Ƃ��w�E���A���̂Q���ɂ��āB���������肢�����B
�@�@�@�@ 1�A���ɂ��ƁA�n���̏��w�Z�ɂ��悤�������ΏۂƂȂ��Ă��邪�A���̎��w�ɒʂ��q���B
�@�@�@�@�@�@�@�͒u������ɂ���Ă���A�q��Ďx���Ƃ����ϓ_����l����Ɛ������Ɍ�����悤�Ɏv���B
�@�@ �@�@�Q�A�\�����݂̗v�����ɂ́A�w���ۈ珊����̋A��͕ی�҂��}���ɗ���悤������Ă��邪
�@�@�@�@�@�@�@�w�Z����w���ۈ珊�ւ̈ړ��ɂ��ẮA����������Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���w�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@���������A���Y�ۈ珊�̋߂��Ńo�X���~��Ċw���ۈ珊�ɒʂ��ꍇ���̋����@���Ɋ�
�@�@�@�@�@�@�@��炸�͕ی�҂�����}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�����Ȃ���Ă���B�q���̈��S
�@�@�@�@�@�@�@���l����Ɠ��R�̂��Ƃ�������Ȃ����A�n���̏��w�Z�ɂ��悤�����ɂ͑S������������
�@�@�@�@�@�@�@�z�����Ȃ���Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂��B���������āA�����ɑ��k�ɍs�������X�ɑ���
�@�@�@�@�@�@�@�̂ݎw�����āA�n���̏��w�Z�ɒʂ��ی�҂ɑ��Ă͖ٔF���Ă���̂ł͂Ƌ^���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@���悤�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���B����ɂ��Ă��A�������̂���悤�ɉ��߂�ׂ��ł���B
�@�@�@�@����̌��ŒS���ۂɊF����͑����������Ă��������A��肠��������ɂ��Ă͕ی�҂Ƒ��k��
�@�@�@�@�@�@�@��ی�҂̐ӔC�ō��]�ۈ珊�ɒʂ����Ƃ�F�߂�Ƃ̉����������܂����B�W�҂�
�@�@�@�@�@�@�@�v���ȑΉ��Ɋ��ӂ��܂��B
�@�@�@�@
�č����{������{���{�ɒ����u�N�����v�v�]���v�Ƃ�
�u�D������{�v�i�։��p�V�j���
�@�@�@�Ăт��̖{���Q�l�ɔN�����v�v�]���ɂ��ėv�_���L���Ȃ��玄�̍l�����q�ׂ�
�@�@�݂����ƂƎv���܂��B�u�N�����v�v�]���v�͂X�R�N�V�������T�~�b�g�̍ۂ̋{��N�����g��
�@�@��]��k�ł́u���ĊԂ̐V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v���ӂ���������
�@�@�ł���B���̌���{�̐����͍א���t�A�H�c���t�A�����ĂX�S�N�U���ɑ��R���t�������A
�@�@���ꂩ��܂��Ȃ��\���ɍݓ��č����H��c�����Γ��v�]�����\�A���ꂪ�u���ĊԂ�
�@�@�V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v�̈�Ƃ��Đݒu���ꂽ�K���ɘa�E����
�@�@��������ɍ̗p����A�u�N�����v�v�]���v�Ƃ��Ē�ቻ�����Ƃ����킯�ł���B�Ȍ㌇��
�@�@�����ƂȂ����N�H�Ɍ��\����Ă����B
�@�@�@���{�̐������\�ܔN�̐������A�����A�������钆�č��ɑ����������A����
�@�@����u�č��ɂ����{�����v�Ƃ����`�e�̂������̂Ȃ����ĂQ���Ԃُ̈�ȃ��J�j�Y
�@�@���ƁA���̋��͂Ȕ}�̂ł���u�N�����v�v�]���v�́A�����{�̗��j�I�]���_�Ƃ���
�@�@�ׂ������ƍ����̒��ŁA�č��Ɏ��˂����܂�ē��{�̐����V�X�e���̒��ɂ��������
�@�@���U����Ă��܂����B���́u�N�����v�v�]���v�͂O�S�N�A�։��p�V���̒����u���ۂł���
�@�@�����{�v�����\����A�u�킵�Y���v�i����Ƃ̏��т悵�̂肪�ӔC�ҏW���߂�G��
�@�@���B�j�O�U�N�~���ŏ��т悵�̂肳��́u�������ł����̎����𐢂ɍL�߂邽�߂ɏ�������
�@�@�ɂ���v�Ƃ������Ƃ���u���ė��E�N�����v�v�]���ɓ{��v�Ƃ������W���g�܂�A�����]
�@�@�_�Ƃ̐X�c�����u�����S�ʔᔻ�v�i���{�]�_�Ёj�̒��ŁA�u�O�S�N�T���R���A����
�@�@�ڍ��w�r�����̏��X�ň���̐V�����������A�Ƃ������{�̕����玄�ɍ��}�𑗂���
�@�@����C����������͡{�ۂł��Ȃ����{�[�A�����J�̓��{������������ł���p���҂͊։�
�@�@�p�V����A�m��Ȃ����������̐l�̒����ɂ͓��{�̍���J�����{�l�̍������߂��Ă���悤�ȋC�������v��
�@�@�������ƂŎ��グ�A�Ȍ�W�҂̊ԂɍL�����グ����悤�ɂȂ��������ł���B
�@�@�@�X�U�N����n�܂����u�N�����v�v�]���v�O�S�N�Ɂu���ۂł��Ȃ����{�Łv�����ɔ��\�����܂ŁA���̎��X�̓�
�@�@�t�A�����͒m���Ă����Ƃ��Ă��@��ʂ̍���c�����^�}����}���قƂ�ǒm��Ȃ��������Ƃɋ����ł���B�u����
�@�@�ł��Ȃ����{�v�̘b���A���҂̊։��p�V����������āA������J�����A���̏��ы��N�����A���i��
�@�@��A�ނ�͊։�����̘b�����ςȂ��ɂ��Ȃ������B�ނ�́u�N�����v�v�]���v�͂��A�X�����c���@�Ă���
�@�@���̗v���������̂ł��邱�Ƃ��������A����ł͓��{�̍��v�ɂȂ�Ȃ��A�A�����J�𗘂��邾���ł͂Ȃ����Ƌ`
�@�@����R�₵���B�����Ă��̌�̓W�J�́A�������̒ʂ�ł���B����ɐ�������A�}�X���f�B�A�ɗx�炳��
�@�@�����{�̗L���ҁi���{�����j���炪�����̎���i�߂Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�@�@�u�N�����v�v�]���v����͓��đo�������݂ɒ�o�������Ă������̂ŁA�ߋ��\���N�ԓ��{�Ői�߂��Ă����A
�@�@�u���v�v�̂��Ȃ�̕������č����{�̗v���𒉎��ɔ��f���Ă������̂ŁA�O�T�N����Ő��������A�V��Ж@�A����
�@�@�Ƌ֖@�A�X�����c���@���܂�������ł���B�����āA�����̒��߂�����́A��Ð��x���v�ł���B���̗�R��
�@�@��]���Ԃ�́u�P�퉻���ꂽ�������v�Ƃ����ق��͂Ȃ��A�匠���ƂƂ��Đq��Ȃ炴����̂��B����ł͕č���
�@�@�B�̕����܂������A������A�����J�̑����ł͂Ȃ����B
�@�@�@����͂Ȃ��������[�@�Ă⋳���{�@�����@�āA�h�q�����i�֘A�@�ĂȂǏd�v�@�ĂȂǐ摗�肵�A���
�@�@���x���v�@�Ă̐������}�����̂��B����͂܂��ɂO�U�N�U���Ƀu�b�V���đ哝�̂Ƃ̍Ō�̎�]��k���Z�b�g����
�@�@�Ă������߂ŁA�u�N�����v�v�]���v��Ð��x���v�̐i�W������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�����ꂽ��Ð��x���v�@�́A���I��Ô�̗}���������ł��o�������̂ŁA���̂��߂ɍ����A�Ƃ�킯�����
�@�@�Ɏ��ȕ��S�̑���𔗂���e�ƂȂ����B
�@�@�@�����͂O�Q�N�Ɋ��Ɉ�Ð��x���v�ɒ��肵�Ă���A���̂Ƃ��͂���܂ł̏���t��z�����P�p����A���S
�@�@�藦���ɑւ���ꂽ�B���̍ہA�V�O�ˈȏ�̍���҂̈�Ô�ȕ��S���́A��ʏ����҂��P���A������ݏ���
�@�@�҂��Ƃ���A����҂̎��ȕ��S�𑝂₵�Ă���B����҈ȊO�ɑ��Ă��A�O�R�N����T�����[�}���{�l�̈��
�@�@��ȕ��S������O���Ɉ����グ��ꂽ�ق��A�Z������������x�[�X����ܗ^���܂߂��N���x�[�X�ɕύX
�@�@����A�ی������S�����₳��Ă���B
�@�@�@���ꂪ�O�U�N�̈�Ð��x���v�ł͎��\�˂��玵�\�l�˂̈�ʏ����҂͂O�W�N�S������ɁA���\�ˈȏ�̌�
�@�@����ݏ����҂͂O�U�N�P�O������O���ɑ��₳��B�܂��A�u������ݏ����v�̒�`������������ꂽ���߂ɁA�e
�@�@������Ώێ҂̐����������B���̏�A�u���z�×{��x�v����������A����ҁA���𐢑���킸�A���z�Ȉ�
�@�@�Ô���������ꍇ�̎��ȕ��S���x�z�������グ��ꂽ�B
�@�@�@����ɁA�u�������҈�Ð��x�v���n�݂���O�W�N����]���͕}�{�Ƒ��Ƃ��ĕی�����Ƃ�Ă����l���܂߁A
�@�@���\�܍ˈȏ�̂��ׂĂ̍���҂��A�ی����̎x�����`�����ۂ����邱�ƂɂȂ����B�܂��A����҂������ɓ�
�@�@�@���Ă���u�×{�a���v�ł̐H�����M��͂O�U�N�\������ی��ΏۊO�ƂȂ�A�×{�a�����̂��Q�O�P�Q�N�܂łɌ�
�@�@�݂̔����ȉ��ɍ팸����邽�߁A�������@���҂͗L���V�l�z�[���Ȃǂ֓]�o�𔗂���B�[�I�Ɍ����A����
�@�@�������T�N�Ԃɂ킽���Đ��i���Ă����u��Ð��x���v�́v�Ȃ���̂̎��Ԃ́A�����A�Ƃ�킯����҂Ɏ��ȕ��S��
�@�@��𔗂邱�ƂɏI�n���Ă����̂͒N�̖ڂɂ����炩�ł���B
�@�@�@���҂̎��ȕ��S�����܂�A���I�ی��ŃJ�o�[�����͈͂�������A�k�����邱�ƂɂȂ�A���ȕ��S���J�o�[
�@�@���邽�߂̖��ԕی����o�ꂷ��B�u���ꂪ���ɏo���邱�Ƃ͖��ɂ�点��v�ƌ������Ƃł���A���I��Õی���
�@�@�k�����Ă����A����A�����́u���ȐӔC�v�ŏ����ɔ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐V����e���r�ŃA�t��
�@�@�b�N��A���R�ȂǃA�����J�n�ی���Ђɂ���Õی����i�̐�`���킪�ٗl�ȂقljߔM���Ă���̂́A��Ð�
�@�@�x���v�ɒ[�������ۂł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�����ЂƂA����ł����̂����{�́A�����������Ȃ�悤�ȉ��v���i�߂��Ă����B���ꂪ�u�V��Ж@�v�̐�
�@�@�肾�A�u��Ж@�v�Ƃ����@���͂���܂ő��݂��Ȃ������A��А��x�Ɋւ��Ă͏��@��L����Ж@�ȂǗl�X�Ȗ@��
�@�@������ł����A��������ɂ܂Ƃ߂ĐV�����u��Ж@�v���A�����Ă��̖ڋʂƈʒu�Â����Ă����̂��A����
�@�@�J���狭���v�]����Ă����A�u�O�����Ή��̍����v�i�������z�������������j�̉��ւł���B���ꂪ���ւ����Ƃ�
�@�@���Ȃ邩�A�Ђ炽�������ΊO����Ƃ����z�̔��������������邱�ƂȂ��ɁA���Њ����g���Ă��Ƃ����₷�����{
�@�@��Ƃ��P���ɂ����߂邱�ƂɂȂ�B������u�O���ɂ����{��Ƃ̏�����v�̉��ւł���B
�@�@�@�V��Ж@�͂O�S�N�P�Q���ɗv�j�Ă����\����O�T�N�ʏ퍑��ɖ@�Ă���o����A�O�U�N����{�H����邱�Ƃ�
�@�@�Ȃ��Ă����A�����̂قƂ�ǂ��m��Ȃ��ԂɁA�܂��ɊԈꔯ����̔N���C�u�h�A�̎������������A�G�ΓI��Ɣ���
�@�@�ւ̍����I�S���ɂ킩�ɕ����A�Ƃ��ɁA��������d�|����ꂽ���{��Ƃɂ͖@�I�ɕۏ��ꂽ�h�q�ق�
�@�@��ǖ������ƂɊ�@�������������B�����}�̓}��(�X�����c���Ŋ����A���̏��ы��N�c���⏬�i�c��)
�@�@������u�O�����މ��̍����v���ւɑ��锽�Θ_�����o���A��o�������O�Ɉ�N�ԓ�������邱�ƂɂȂ����B��
�@�@��Ȋ댯�Ȃ��Ƃ����蔭�Ԑ��O���������Ƃɂ͜ɑR�Ƃ������ł��邪�A���̎����}(�X�����c���Ŋ���
�@�@���A���̏��ы��N�c���⏬�i�c���j�c�������̓����ɂ��A��N�ԓ�������邱�ƂƂȂ�A���{�̊�Ƃ��h
�@�@�q����u���邱�Ƃ��o�����̂ł���B
�@�@�@����ɂ��Ă��A�Ȃ��������ݓ��{�̑��Ƃ��������ɂ���킽���ɂЂƂ����u�O�����Ή��̍����v�̉��ւȂ�
�@�@�Ƃ������Ƃ��i�߂��Ă����̂��B�ӊO�ɂ����Ƃ͉�Ж@�����ł͂Ȃ��̂��A�ӊO�ɂ���v��ɂ��Ċ�ƍ�
�@�@����v�����������Ɍ������ꂷ����j����߂��A���̐V����������v����ł́A�]���̓��{�I�ȑΓ�����
�@�@�͓���Ȃ�A�G�Ύ��������܂߂��z������������̊�ƍĕ҂̎嗬�ƂȂ�Ƃ����Ă���B����ɁA�Ő��ʂł�
�@�@�O���ɂ����{��Ɣ������㉟�����邽�߂ɐŐ����v���O�S�N���猟������Ă���Ƃ����A����������A�̉��v��
�@�@���̂��ׂĂ̓����̎i�ߓ��ƂȂ��Ă���̂��u�Γ�������c�i�i�h�b�j�v�c���͓��t�����厖�A���c���͌o�����S
�@�@����b�A�����Ă��̉����g�D�ɂ͂P�R�l�̓��{�l�̑��ɁA�ݓ��č����H��c���̊�����č��،���Ђ̖����A
�@�@��l�̊O���l�ٌ�m���܂ނP�O�l�̊O���l���u�O���l���ʈψ��Ƃ��Ė���A�˂Ă��邻���ł���B
�@�@�@�����āA���̑Γ�������c��啔��O�S�N�A�u�Γ��������i�v���O�����y�ю��{�v�Ƃ��������̒��ŁA
�@�@�u�������z���������E�������e�Ղɍs����悤�Ɂv�Ƃ����ړI�Łu�O�����Ή��̍����v�̉��ւ��ƍ�����v��
�@�@�̎������������A�Ő���̗D���[�u�ȂǂƂ��������Ƃ���̗�Ƃ��Ă������Ă��B����ȊO�ɂ��A�ߔN�A���{��
�@�@�傫���h�邪���Ă���B������\�����v�̑������A���́u�Γ��������i�v���O�����v�̈���������Ƃ����L��
�@�@��Ă���B���͏���̌����\�����v�́A�����̂��߂ł͂Ȃ��A�O���ɂ����{��Ƃ̔����𑣐i���邽�߂�
�@�@�u���{�����v�����������đg�D�I�ɐi�߂��Ă����̂ł���B
�@�@�@04�N�ł́u�Γ������C�j�V�A�`�u�v�̕��ɂ́o�č����{�́A���{�ɂ�����l�����Ԃ̕ω��ɂ��A����A
�@�@����y�ш�ÃT�[�r�X����ɂ����铊�����d�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E�����B�����Ă����̕���ɂ����ĕč�
�@�@��Ƃ����̓��ӕ���������l�X�Ȏ��̍����T�[�r�X��ł��邱�ƁA�܂����������V���ȃT�[�r�X�̒�
�@�@�����{�̏���җ��v�̑���Ɏ�������̂ł��邱�Ƃ��w�E�����B�č����{�͂����̕���ɂ����铊���𑣐i��
�@�@�邽�߁A���{���{�ɑ��A���Y����ɂ����铊�����\�Ƃ��邽�߂̋K�����v��v�������B�p���邳��Ă���B
�@�@�@�����ăA�����J�̓��{�����͂܂��܂������X�����c���Łu�ȈՕی��v����Ð��x���v�Łu��Õی��v�����̂�
�@�@�炢�͋���A��ÃT�[�r�X�A�u���ρv�ւƉ��X�Ƒ��������ł���B���������N�����̕č��ɂ����{�������~��
�@�@��̂��A�����Ȃ鍑���ȊO�ɂȂ��ł͂Ȃ����A�ڊo�߂���{�B
�@�@�@���ċK�����v�y�ы�������C�j�V�A�`�u�Ɋ�Â����{���{�ւ̕č����{�v�]���̖`���ɂ�
�@�@�@�O�T�N�Ł@�@�č��́A������b�̓��{�o�ω��v�Ɍ������p���I���g�݂�����������B�����̎��g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͓��{�𐬒��O���ɏ悹�A��葽���̖f�Ջy�ѓ����@���n�o�����A�č��͂܂��A�����ƍ\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����͏����ʓI�ɒ��Ă����K�����v�E���ԊJ�����i�{���ƁA�\�����v���ʐ��i�{���̂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g�݂�]������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̗v�]���ɐ��荞�܂ꂽ�́A��v�����A���f�I����ɂ�����A���v�ɏd�_��u���A�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ϐ������x�����A���{�̎s��J������肢�������������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B����ɕč��͓d�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A�m�I���Y���A��ÁA�_�ƁA���c���A��������ȂǁA���������v�̎�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���d�v�ł���ƈʒu�Â�������̖��Ɉ����������ɏœ_�ĂĂ���B
�@�@�@�O�U�N�Ł@�@�č��́A���{�̌o�ω��v�𐄐i����Ƃ�������������b�̌��ӂ����}����B�V�����@��݁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����𑣂��A��茒�S�ȃr�W�l�X�������o�����v�́A���ꂩ��扽�N�ɂ��n����{�̌o�ϐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɗ��͂��ێ����x����ł��낤�B�܂��A�č��͓��{�����̉��v���i�҂̎��g�݂�S�����v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���㐔�����A���N�ɂ킽��A�����̊��������������邱�Ƃ����҂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̕č�����̒́A�d�C�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A��Ë@��A���i�A���Z�T�[�r�X�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɩ@���T�[�r�X�A�������A�_�ƁA���Ђ̖��c���A���ʁA��������ƍL�͈͂ȕ���ɂ����āA�p
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ��v�̐i�W��}�邱�Ƃ̏d�v�����������Ă�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԕ���i�č��́j�̑�\�����C�j�V�A�`�u�֒���I�ɎQ�����A���m������Ă���邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŁA��X�̍�ƂɕK�v�ȑ����̏��邱�Ƃ��o�����A�����͂��̂悤�ȎQ���̋@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���傷�邱�Ƃ����҂���B
�@
�@�@�@�ȏオ�����F����ɓ`���������̖{�̓��e�̈ꕔ�ł��B�������ł��傤���A�������������m��Ȃ��Ԃɋ�����
�@�@�����Ƃ��i�s���Ă��܂��A���̂��Ƃ����{�̏������ǂ��ς��Ă����̂����̕n��ȓ��ł͑z�������܂���
�@�@�̖{��ǂ�ł���Ɖ�������傫�ȓ{�肪�킢�Ă��ĂȂ�܂���B
�@�@�@���̔N�����v�v�]���͓��đo�����o�������Ă���A���R���{���o���Ă��܂����A����Ƃ��Ď������Ă��Ȃ�
�@�@�����ł��B��Ȃ�����ł͂���܂��A�ǂ����F�l�A��x�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�Łu�N�����v�v�]���v
�@�@�Ȃ���̂������Ŋm���߂Ă��������B�����Ǝ��̌����Ă��邱�Ƃ��������Ă���������Ǝv���܂��B
�@�@�@�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�@http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@
�X�����c���͓��{�����ɂƂ��Đ��������v�Ȃ̂�
�@�@����A����H.D���玟�̗l�Ȃ��莆���܂����B
�@�@�O���A�M�Z�ɂ͐V���ȖڕW�Ɍ������čĂъ������n�߂�ꂽ���ƁA���ɂ����c�Ɋ����܂���B�n��ɍ�
�@������������ʂ��ĊC��s������肢�������O�i�����Ă������������܂��悤���҂��Ă���܂��B
�@�@���Đ���A�M�Z�̃z�[���y�[�W�ŗX�����c�������グ�Ă���̂�q�����āA���ɓ������ӌ��ŁA
�@���X�Ȃ���M�Z�̓��@�͂̐[���Ɋ��S�������܂����B�i�����j
�@�@�X���ɂ��Ă͌������܂������A������������v�̖��̂��Ƃō��v�ɔ�����悤�Ȑ������������邱
�@�Ƃ����͂��߂�ւ肽���҂ł��B
�@�@�����̐}���͐挎���s����܂������̂ł����A���݂̎��̑z���Ɠ����ł��̂Ő����x���ڂƂƂ�����
�@�����������肢�����܂��B�ƌ������ƂŁA���̂悤�Ȗ{�𑗂��Ă��������܂����B
�u�D������{�v�i�։��p�V�j
�@�@�ڂ���Ƃ͂��̂��ƂŁA���̂���A�����̍����ɂƂĂ̂킩��ɂ��������X�����c���A�������̋^
�@��_�����炩�ɂȂ�܂����B�����āA���ы��N�c�������ߔ��Δh�̋c���͂Ȃ����̂悤�ɋ��d�ɔ���
�@��̂����A���v���Ȃ��}���̂��A�X�����c����č��ƂȂ��b������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ���������
�@�����̖{�����炩�ɂ��Ă��܂��B�F����ɂ��̖{�̂��ׂĂɖڂ�ʂ��Ă������������Ǝv���܂����A����
�@�ł͗v�_���L���Ă݂����Ƒz���܂��B
�@�@���{��卬���Ɋׂꂽ�X�����c���@�A���{�̏��������ɂ킽��ł��낤�A�l�X�ȉЍ����c�����Q�O�O�T
�@�N�ő�̐����ۑ�́A���ׂď����̎v�f�����Ɍ��������B���̔N�̉ߔ��̎��ԂƃG�l���M�[����
�@����Ƃ�������X�����c���Ƃ́A���ǂȂ����̂��B
�@�@���̗X�����c�����ɂ́A�Ō�܂ł����₯�ɂ͂قƂ�nj���Ȃ��������ʂ�����B���{�̍\��
�@���v�̖{�ہA���邢�͐����Ə���Y�̌l�I���O�A�ȂǂƎ�肴������Ă������̖��̔w���
�@�͕č�����̎��X�Ȉ��͂Ƃ���������̈��q���B����Ă����̂ł���B
�@�@1995�N11���ɕč����{������{���{�ɒ��ꂽ�u�N�����v�v�]���v�ɂ́A�ȈՕی��Ɋւ��Ď���
�@�悤�ȋL�q������B
�@�@�o�č����{�́A���{���ȉ��̂悤�ȋK���ɘa�y�ы������i�̂��߂̑[�u������ׂ��ł���ƐM����B
�@�E�E�E�E�E�X���Ȃ̂悤�Ȑ��{�@�ւ��A���ԉ�Ђƒ��ڋ�������ی��Ɩ��Ɍg��邱�Ƃ��֎~����B�p�Ƃ�
�@��B�@�h�֎~����Ƃ͓��������̂��̂ł͂Ȃ����B�h�@
�@�@�����Ă���ȗ��č����{�͊ȈՕی��̔p�~��v���������A
�@�@1999�N�̗v�]���ł́@�o�č��͓��{�ɑ����ԕی���Ђ����Ă��鏤�i�Ƌ�������ȈՕی�
�@�i�J���|�j���܂ސ��{�y�я������ی����x���g�傷��l�������ׂĒ��~���A�����̐��x�����ł܂���
�@�p�����ׂ����ǂ����������邱�Ƃ��������߂�B�p�܂�č��͊��ƂƂ��Ă̊ȕۂ�p�~���Ė��ԉ�Ђ�
�@�J������Ɨv�����Ă���̂ł���B
�@�@���{�̖��ԕی��s��͉ߋ�20�N�ȏ�ɂ킽���ĕč��ɂ������W����Ă����A���̗��j��U���
�@������ʼn��߂��l����A�X�����c���̖{���͂P�Q�O���~�ɂ̂ڂ銯�c�ی��̎s��J����肾�ƌ���
�@���Ƃ��킩��B�������������c�����������ł͍����ő��̓��{�����̎O�{�߂��K�͂̋���Ȗ��ԕ�
�@����Ђ��a�����邾���̂��Ƃ��A�����A�č����]��ł���̂͂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�č��͖��c��
�@��̊ȈՕی��Ƃ��̎��Y�P�Q�O���~���ǂ����傤�ƍl���Ă���̂��B
�@�@2004�N�̋K�����v�v�]���ɂ͂��̋L�q��v��ƁA�ȕۂ̐��{�ۗL���������S�Ɏs��֔��p��
�@���A�u���{�ۏ����邩�̂悤�ȔF���������ɐ����Ȃ��悤�\���ȕ�����v��点��B�܂萭�{�̊֗^
�@�����S�ɒf���点�����Ȗ��ԉ�ЂƂȂ����ȕۂɑ��ẮA�O���n�ی���ЂƊ��S�ɑΓ��ȋ�����
�@����v�����Ă����B�����Ċȕۂ̏��NJ������Ȃ�����Z���Ɉڊǂ������̗������茟���������A
�@�\���y���V�[�}�[�W���Ȃǂ̌��\���`���Â���v�������Ȃǂ̊č���������B
�@����ɁA�ȕۂ�Ƌ֖@�Ȃǂ̓K�p�ΏۂƂ��A�u���̎s��x�z�͂��s�g���Č���c�Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��悤�v
�@��������ψ���ɒ���������ƌ��������Ƃ��L�q����Ă���B
�@�@�v����ɕč��ɂƂ��Ė��c���̓S�[���ł͂Ȃ��ȕۂ���̉������A�ŏI�I�ɂ͕����A��́A�o�c�j�]
�@�ɒǂ����݁A�l���`��c�Ə��n�ȂǗl�X�Ȏ�i��M���āA�ȕۂ��i���Ă���P�Q�O���~�ɂ̂ڂ鎑�Y��
�@�č��n���ԕی���Ђɋz�������邱�Ƃ��ŏI�I�Ȃ˂炢�Ȃ̂ł���B
�@�@�ȕۂ͏����ł��邱�ƂƁA���R���Ƃ����ȈՂȉ����葱������F�Ƃ��Ă���B���X�ȈՐ����ی����x
�@�́A���Ԃ̐����ی��ɉ����ł��Ȃ��Ꮚ���҂ɂ��ی��Ƃ����Z�t�e�B�l�b�g����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�吳�ܔN�ɑn�݂�����̎҂Ńr�W�l�X�ƌ��������{�Љ�̈��艻���u�ł���B
�@���ꂪ�č��l�ɂ͒P�Ȃ�s��Ƃ��Ă����ڂ�Ȃ��B���艻���u���͂�������̓��{�Љ�ǂ��Ȃ낤��
�@��؊S���Ȃ��̂ł���B�u�����疯�֎����𗬂��v�u���ɏo���邱�Ƃ͖��Łv�ƌ����Ƃ��̖���
�@���{�����̖��ł͂Ȃ��A���{�����̍s�����ɐӔC��Ȃ��č����ԕی���Ђ́u���v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�������ł��傤���A�����͂��K�ߑ����̍���c�����X�����c���ɂ��āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɍ��́A
�@�����̗��v�ɂȂ���̂����Ȃ������ɐ����ӔC���ʂ����Ȃ��̂��A���킩�蒸�����ł��傤���A�{��
�@�͗X�����c���ɍŌ�܂Ŕ������A�^�̍��v����낤�Ƃ��������}�̗E�C����c���B������X������
�@�������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�����ł͂Ȃ������̂��B�ŋߎ��͂��Â������v���Đ���܂���A����
�@�Ђ�����ɉ��̂��߂炢���Ȃ�������ӐM���c���Ɏ^���������A�䂪���̂U�l�̗^�}�c���́A�ǂ�
�@�قnj����ɑ��Đ����ӔC���ʂ������̂ł��傤�B�ނ�͕č��́u�N�����v�v�]���v�m���Ă����̂ł���
�@�����B�@�������̂��Ƃ͐����Ă݂����҂ł��B
�@
�@
�Ȃ����f�Â��s���Ă��܂��B
�@�@�@�C��s�̒��j��Ë@�ւƂ��āA�s���̈��S�ƌ��N������Ă���A�s������́A����Ƃ��s
�@�@���a�@�ł̈�ÃT�[�r�X�̏[����]�ސ��������B
�@�@�@�������Ȃ���A���a38�N�̖{�ٌ��݂�����ɒz��40���N���o�߂��A�{�݂̘V�����A��襉�
�@�@�������ɂȂ��Ă���B���{�݂͑ϐk���̖��͂������̂��ƁA���҂̃A���j�e�B�⌻�݂�
�@�@��ËZ�p�����ւ̑Ή��A���S�Ǘ��A�Ɩ������̌����}�邱�ƂȂǗl�X�ȓ_�ŁA���߂���
�@�@��ÃT�[�r�X�̒�����ȏƂȂ��Ă���A���Ґ��̌����A�o�c�̈����ւƌq����
�@�@����B
�@�@�@���̂悤�ȏ̒��A����A�s���a�@���A�s���̗v�]�ɉ����A�C��s�̒��j��Ë@�ւƂ�
�@�@�āA����Ƃ��p�����Ēn���Â�W�J���Ă������߂ɂ́A�V�z�ɂ��{�ݐ������s���Ă���
�@�@���Ƃ��s���Ƃ�����B
�@�@�@�s���a�@���A����Ƃ��A�n��̒��j��Ë@�ւƂ��āA�s�����K�v�Ƃ����Â���Ă�
�@�@�����߂ɂ́A�w�s���a�@�̖����̖��m���x��}���Ă������Ƃ��ł��d�v�ƂȂ�B�s���a�@���A
�@�@�����镪��ɂ����Ċ����Ȉ�Â����߂邱�Ƃ͍���ł���A�o�c�̎��_������K���łȂ��B
�@�@�n���Ì��̒��ŁA���߂Ďs���@�a�@�̖������������K�v������B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA���̂قNJC��s���a�@��{�\�z(��)�����\����܂����A���̎�Ȃ��̂���
�@�@��܂��B
�@�@�P�j�V�a�@���ݗ\��n
�@�@�@�@�@�C��s�͗\��n�Ƃ��āA�W���X�R�Ւn�ƊC�쎄�����Z�����n�Ƃ��Č������Ƃ��Ă�
�@�@�@�@�܂����A���́A�����炭�W���X�R�Ւn�Ɍ��܂�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@�@�Q�j�a����ʂƕa���K��
�@�@�@�@ �@�a�����
�@�@�@�@�@�@�@���}�����a�����܂ވ�ʋ}�����a�@�i��10���l��̕a�����F�S������707���A�C
�@�@�@�@�@�@��s448���j�Ƃ��A���A�×{���i�ݑ�E�{�݁j���̋@�\�ɂ��ẮA������
�@ �@�@�@�@�@�@���ڒS���Ă���n��̈�Ë@�ցE�����{�݁E���T�[�r�X���Ə��Ƃ̘A�g�ƌ��
�@�@�@�@�@�@�x���@�\�̏[����}���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����������A�s���Ƃ��č\�z���Ă�
�@�@�@�@�@�@�����Ƃ��}���ƂȂ��Ă���w�n���P�A�̐��x�̘g�g�݂̒��ŊC��s���a�@
�@�@�@�@�@�@�i�n��A�g���E�K��Ō�X�e�[�V�����j���n��A�g�̒��j�ƂȂ�A���̖������ʂ�
�@�@�@�@�@�@���Ă������Ƃ��ł��d�v�ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@ �A�a���K��
�@�@�@�@�@�@�@�V�a�@�̊Ō���10�F�P�Ƃ��A�K���a���K�͂́A��ʕa���i���}���a���܂ށj
�@�@�@�@�@�@�@50���~�R�a����150��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���Ȍn�a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�O�ȁE���`�O�Ȍn�a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�����E���}�����E�J���a�� �F50���~�P�a��
�@�@�@�@ �B�f��
�@�@�@�@�@�@�@�@���ȁ@�A�O�ȁ@�B���`�O�ȁ@�C�����ȁ@�D��A��ȁ@�E�w�l�ȁ@�F��ȁ@
�@�@�@�@�@�@�@�G���@��A�ȁ@�H�畆�ȁ@�I�����ȁi�y�C���N���j�b�N�j�@�J���ː��ȁ@
�@�@�@�@�@�@�@�K������Z���^�[(�������Z���^�[)
�@�@�@�@�@�@�@�����f�Z���^�[
�@�@�@�@�@�@�@������Z���^�[�i�������Z���^�[�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�ߔN�A�d�q�������̕��y�ƂƂ��ɓ����������̏d�v���͂܂��܂����債�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��킯�㕔����������ǂɂ��Ă͌��������A�Ώۊ��҂Ƃ��������Ă���A�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏d�v�Ȍ�������ƂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂������펾���ł͌����ƂƂ��ɓ���������p�������ɍs����P�[�X����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������A�V�a�@�ɂ�������̈�̒��̈�Ƃ��āA���ȁA�O�Ȃ��A�g����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̏�����Z���^�[�i�������Z���^�[�j��ݒu����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E������n�������ݔ����[�����A���A���ŁA�ŋۑ�����s���X�y�[�X�Ɛݔ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������ɐ�������B
�@�@�@ �@�@�@ �E������̉Ɗ��ҊĎ����u��ݒu����B
�@�@�@�@�@�@�@���f�Z���^�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�s��(���N��)�ƈ�̂ƂȂ����ݒu���������A�s���̕ی��t�A�Ǘ��h�{�m����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���f�@�Z���^�[�Ƃ̘A�g�A���̋��L����}������I�ȉ^�c���s���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���茒�f�A����ی��w�����̏[����}��ƂƂ��ɁA���p�҂̃j�[�Y�ɑΉ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������A��h�b�N�E�h���h�b�N�𒆐S�Ƃ������f���j���[�̐ݒ���s���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�s���̗��������߂邽�߁A���݂̋x�����f�̊g�[����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���茒�f�A����ی��w���A�l�ԃh�b�N�A�e�킪���ΏۂƂ������f�ɂ��āA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�@�L�A�s��A�z�[���y�[�W����ʂ��Ďs���ɂ��L����M����B
�@�@�@ �C�V�a�@�̌��݂ɌW��A�������ݎ��Ɣ�B
�@�@�@�@�@ �E�V�a�@���݂ɌW�鑍��p�́A4,300,000��~�ł���B
�@�@�@�@ �D�V�a�@�̌��݃X�P�W���[��
�@�@�@�@�@�@�@�@�V�a�@�̌��݃X�P�W���[���͈ȉ��̒ʂ�Ƃ��邪�A���a�@�̏i�{�݂̘V��
�@�@�@�@�@�@�@���A�ʂ����ׂ���Ë@�\�y�ьo�c���P�̍���j����A�ł�������肱�����
�@�@�@�@�@�@�@�����J�@���ׂ��w�͂��邱�Ƃ��]�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�E��{�v�F����21�N10���`����22�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���{�v�F����22�N�S���`����23�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E���ݍH���F����23�N�S���`����25�N�R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�E�a�@�J�@�F����25�N�S��
�@�R�A�@�C��s�h�Б�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�����đȂ���Ă������ƂɂȂ�B�n��h�Ќv��ł́A�����ł��ǂ��ł��N��
�@�@�@�@�@�肤��ЊQ����s���̐����A�g�̋y�э��Y��ی삷��ƂƂ��ɁA�h�Ђ̂��߂̔���
�@�@�@�@�@�����������[�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���̂��߉ߋ��̑�ЊQ�����P�Ƃ��A�{�s�̒n
�@�@�@�@�@���I�����A����A��A�Љ�\���̕ω������l���ɓ���A�s�A���y�ъW�@��
�@�@�@�@�@�Ǝs������̂ƂȂ��čЊQ�ɋ����܂����𐄐i���邱�Ƃ��d�v�ŁA���̂��߂ɂ́A
�@�@�@�@�@�s�̖h�Ў{��̕�������A�g�߂Ȗ��ł���ЊQ���̖h�Б̐��Ȃǖh�Б���
�@�@�@�@�@�ۑ�ɂ��āA���펞�����Ў������펞�̍ЊQ�T�C�N���Ŏ����A�ݏ��E�����A����
�@�@�@�@�@�̊ϓ_���炵���݂Â�������邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�@�@�@�@�@�����Ėh�ЂɊւ����{�ڕW�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@���@�h�Ќ���Ɍ������܂��Â���B
�@�@�@�@�@�@�@���@�h�Ќ���Ɍ������l���B
�@�@�@�@�@�@�@���@�ЊQ�ɋ����̐��i�g�D�j���B
�@�@�@�@�@�̂R�_�̖h�Ѓr�W������������A�ЊQ�\��v��A�ЊQ���}��A�ЊQ�����A����
�@�@�@�@�@�v�悪�ׂ������Ă��Ă���B
�@�@�@�@�@�@����ł͂��̊�{�v��ɂ��ƂÂ���̌���́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C��s�Ôg��A�C��s�����̈�قւ̖h�Ћ��_�̐ݒu�A�C��s�����̈�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ق̒������A�y�ъe�n��̔��̐ݒu�A�e�����{�݂̑ϐk�f�f�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���C�A���Òn��̍�����A����h�Бg�D�̐ݗ��h�ЌP���̎��{�A�Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g���s������B
�@�S�A�@�C��s�Ôg��ɂ��āB
�@�@�@�@�@�ƂȂ��Ôg�Z����Q���Ă��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���ɁA����R�O�N�ȓ��ɓ�C�n�k���T�O���A����C�n�k���U�O�`�V�O���̊m����
�@�@�@�@�@��������ƌ����Ă���A���n��ɂ͍�����T������Ôg�����P����ƌ����
�@�@�@�@�@�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@���̒n�k�����ɔ������n��̒Ôg�Z����Q�́A��4,900���сA��13,000�l�ɋy�сA
�@�@�@�@�@�n��S�̂őz�肳����Q�z�͖�5,000���~�ƁA�a�̎R�����ōő�̔�Q���\����
�@�@�@�@�@��Ă��܂��B�܂��A���ݕ��ɂ͎s��������h�E�x�@�E�s���a�@���̎�v�����{�݂�
�@�@�@�@�@���łȂ��A�d�́A�S�|�A�Ζ����̎�v��Ƃ����n����ق��A���s�E�a�̎R�s�ƋI��
�@�@�@�@�@�n�������ԁA�����S�Q�����ʉ߂��Ă��邽�߁A��Q�����ꍇ�A���암�ւ̕���
�@�@�@�@�@�E�l���̃��C�t���C������Ⴢ���ƍl�����܂��B
�@�@�@�@�@�@���̂��߁A�n��Z���E�ՊC�����n��Ɠ��̊�@�ӎ��͍����A�Ôg��ɂ��āA
�@�@�@�@�@�n�悩����ɋ����v�]������Ƃ���ŁA���̂悤�ȏ̒��A�C��s�A�ՊC����
�@�@�@�@�@�n��v��Ƌy�ю�����̊�����̂ƂȂ������c���ݗ����A����A���y��ʏȋy
�@�@�@�@�@�јa�̎R���ɑ��āA�a�̎R���Í`�i�C��n��j�ł̒Ôg��̑������{�Ɍ���
�@�@�@�@�@���v�]���������s���Ă������Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B
�@�@�@�@�@�@�Ôg��̊T�v�i�ڍׂ͍��y��ʏȋߋE�n�������ǂɂ����Č������j
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@��H�@�@�@�@������݂̐��グ�A�q�H���ւ̐���̐ݒu�A�h�g��̐V��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�ѐ��グ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����Ɣ�@�@�@200�`300���~
�@ �@�T�A�@�C��s�����w�Z�̓����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�w�Z����ɗl�X�Ȗ�肪�����Ă��Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�ȏɑΉ����āA��
�@�@�@�@�@�͂���w�K�����ێ����邽�߁A�w�Z�̓K���K�́A�K���z�u��i�߂Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�K���K��
�@�@�@�@�@�@�@�c�t���@�@���Ȃ��Ƃ���̉��ɕ����̃N���X�A�P�N���X�P�O�l�ȏ�̉�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���K�v�B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�N���X�ւ��̏o���鎙�������]�܂������A�Œ�ł��P�N���X�Q�O�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�̐l���͕K�v�B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�P�w�N�S�w���A�w�Z�S�̂łP�Q�w�����x�B
�@�@�@�@�@�@�K���z�u��
�@�@�@�@�@�@�@�c�t���@�@�m�`�c�t���A���Α��A���̂R�c�t������̗c�t���Ƃ��A����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Α��c�t���{�݂��ĊJ������B
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ÁA�哌�A���c�t���̂R�c�t������̗c�t���Ƃ��A���哌�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t���{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���×c�t���͌��s�̒ʂ�Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@�m�`�A���Α��A���̂R���w�Z����̏��w�Z�Ƃ��A�����Α��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ÁA�哌�A��菬�w�Z�̂R���w�Z����̗c�t���Ƃ��A���哌��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���Ï��w�Z�͌��s�̒ʂ�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���C����ɂ��Ă͋��犈���̊��͂��ێ�����ϓ_����A�K���K
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��ۂ����悤�A���Z�⏬�K�͍Z�̂��肩���ɂ��Č�����i��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����B
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�@�@���Ñ��A���̓�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A���Ñ�w
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�C����A���A��O���w�Z�̎O�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����w�Z�{�݂��ĊJ������B
�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�T��A�F���w�Z�̓�̒��w�Z����̒��w�Z�Ƃ��A���c�r���Ӓn
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���J������B
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���C�쒆�w�͌��{�݂��ĊJ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�̓������ɂ��ẮA�C����A���A��O
�@�@�@�@�@�@�@���w�Z�̓����́A��O���w�Z�����㕽���R�O�N�܂ł͈�
�@�@�@�@�@�@�@�w�N�R�w�����ێ��ł���Ƃ������Ƃ���A�P�Ƃł�����
�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̕ی�҂̋����v�]�ɂ��A�Ƃ肠�����͊C����
�@�@�@�@�@�@�@�A��w�Z���s���ē�������Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A�T�쒆�w�Z�ƒF���w�Z�ɂ��ẮA���c�r����
�@�@�@�@�@�@�@�n���J���ɂ͂U�O���ȏ�Ƃ����c��Ȕ�p��������A��
�@�@�@�@�@�@�@�̂��Ƃ��s�����Ŏ����̂߂ǂ������Ă��Ȃ�����ł���
�@�@�@�@�@�@�@�A����ψ���Ƃ��Ă��A�T��A�F�Ƃ��ɂ��ꂼ�ꌻ�n�J
�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ������Ƃ�����ɓ���Ȃ���A�Č��������Ă�����
�@�@�@�@�@�@�@�������ƂɂȂ�܂����B
�@ �U�A�@�����S�Q�����ɂ��āB
�@�@�@�@�@�ȁA���A�x�@�j���тɍ����S�Q���L�c�C��Ԑ������i���c��i�L�c�s�A�C��s�A�L
�@�@�@�@�@�c�S������j������A�����S�Q����ʏa�ؑc��ɂ����Ă͒Z���I�ȏa�؉���
�@�@�@�@�@���Ƃ��āA�L�c�s����C��s�Ɏ���Ԃ̊e�a�،����_�̉��ǂ�A�������������Ȃ�
�@�@�@�@�@�̌��������Ă������ŁA����܂ŁA�L�c�s���������̌����_�A���Ò����c�����_�A
�@�@�@�@�@��������_�A�����ĕ����P�X�N�R���ɂ͊C��s�␅�����_�̉��ǂ����{����܂����B
�@�@�@�@�@�܂��A�����ĕ����P�U�N����͍��������̈������������{����A�����̌�ʗʒጸ
�@�@�@�@�@���}��������B
�@�@�@�@�@�@����A�����S�Q���L�c�C��Ԑ������i���c��ł́A�����Q�Ԑ��A�o�C�p�X�Q�Ԑ��A
�@�@�@�@�@�v�S�Ԑ��ł̐����v�]�����ĎQ�������A���y��ʏȋߋE�n�������ǘa�̎R�͐썑��
�@�@�@�@�@�������ł́A�o�C�p�X���[�g����Ɍ����A�����P�V�N�x�����ӂ̊��������I���A
�@�@�@�@�@���N�x�ɂ����Ĉ�ʍ����S�Q���␅�g�����ƂƂ��āA�␅�����ԉ�����P�D�P����
�@�@�@�@�@�����Ɖ�����A�{�N�P�O���ɂ͒n���Z���̊F�l�ւ̎��Ɛ�����J����A���̌�H
�@�@�@�@�@�����ʁA�n�����������{���ė\���v�ɓ����Ă����\��܂��A����ƕ��s���č��N
�@�@�@�@�@���ɂ͓s�s�v�挈�肳���\��ł���Ƃ������Ƃł��B
�@�V�A�@�����R�V�O�����̃o�C�p�X�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�Ȃ�����ꂸ�A�n���̊F�l�̋��͂ƊW�҂̓w�͂ɂ��悤�₭�����P�U�N�P�Q��
�@�@�@�@�@�Q�S���ɓs�s�v�挈�肳��A���גr�炩��ؒÌ����_�t�߂܂ʼn�����Q�C�T�S�O
�@�@�@�@�@���A�����Q�O���̗\��ŕ����P�V�N�x��茧�ɂ����Ď��Ɖ�����܂����B
�@�@�@�@�@�@���݂͋N�_������I�z��s�t�߂܂ł̖��P�C�T�U�O���̋�Ԃ���H��Ƃ���
�@�@�@�@�@���Ƃ�i�߂Ă��܂��A���݂͑��H����Ō����p�n�̗������Ƃ�i�߂Ă��茻
�@�@�@�@�@���_�łU�����x�̗�������I���Ă���Ƃ������Ƃł��A�܂��A����ƕ��s���Čv
�@�@�@�@�@�擹�H�̐�������A�������̃R���T���^���g��Ђ����������ɏ����͂����Ă����
�@�@�@�@�@���ł��B
�@�W�A�@��a�����ԓ��i�C��g���ԁj�̎l�Ԑ����ɂ��āB
�@�@�@�@�@����A�����P�O�N�P�Q���Q�T���ɍ��̎{�H���߂��o����A�����P�S�N�V���ɑ��ʒ�
�@�@�@�@�@�����J�n�A�����P�T�ʂV������p�n�����n�܂�A�����A���ÁA����̊e�g���l��
�@�@�@�@�@�H���͕����P�U�N�ɒ��H�A�C��A���ÃC���^�[�`�F���W�͕����P�V�N����J�n����
�@�@�@�@�@�Ă���A�����Q�S�N�x�ɂ͏㉺���Ƃ������̗\��ƂȂ��Ă���B
�@�X�A�@�C��s�������ɂ��āB
�@�@�@�@�@���Ă��鉺���������A�����Ƃ����_����łȂ����Q��ɏd����u�����������ł���
�@�@�@�@�@�܂��A�ł͊C��s�͉��������ǂ�����̂��Ƃ����ƁA�{�N�S���ɏo����܂����C��
�@�@�@�@�@�s�����v��ɂ��ƁA�������̌��݂͂��Ȃ��Ƃ������_�ł���C��s�̛��A������
�@�@�@�@�@����Ƃ��ẮA�܂������������̕��y�ɓw�߂Ă����Ƃ������Ƃł���܂��B
�@�@�@�@�@�@���͉��������݂ɂ͐��S���Ƃ����c��Ȏ�����K�v�Ƃ��܂����������̐ܒv��
�@�@�@�@�@���Ȃ��Ǝv���܂����A����Ȃ�Ό��ݔ_�����ł͔_�Ɨp���H�֏��̕��������
�@�@�@�@�@�����Ă��錻�����ӂ܂��A�_�Ɨp���H�̉��C��L����Ƃ��Ă̐��ʂ̊m�ۂƂ���
�@�@�@�@�@�����Ƃɗ��ӂ��Ă������������ƍl���Ă��܂��B
�P�O�A�@�����H���C����ɂ��āB
�@�@�@�@�@���A���㊎���n�����o�đ��c�n����o�Ęa�̎R�s�Ɏ��镔���̉��Ǘ\��͑S���o��
�@�@�@�@�@�Ă��Ȃ��̂�����ł���܂��B
�@�@�@�@�@�@���Y�����͔��ɋ�襂ō����̎����Ԃ̑�^���ɔ����R���܂܂Ȃ炸���[�̃�
�@�@�@�@�@�b�V�����ɂ͒���t�߂̏Z���͂��Ƃ��ʋΎ҂����ɍ����Ă���̂�����ł�
�@�@�@�@�@��܂��B
�@�@�@�@�@�@����A�C��C���c�A�i�C��s�c��A�I���쒬�c��j�ɂ����č��N�x���猧���
�@�@�@�@�@���킹�A�����C��H�����̊g���ɂ��Ă��v�����s���Ă����Ƃ������ӂ��Ȃ����
�@�@�@�@�@�����B
�P�P�A�@�����C��������̃o�C�p�X�ɂ��āB
�@�@�@�@�@�i�C��s�A���������j���ݗ�����A�܂��A�C��s�ʏ��n������Q�E�������ėL�c��
�@�@�@�@�@������Ɏ���Ԃ̉��C���������{����A���̌�A�d���A�����쉈���̖����C�Ԃ�s
�@�@�@�@�@�v�擹�H�Ƃ��āA�����U�N�ɂ͗����c�Ì������s�s�v�挈�肢����A�����P�Q�N��
�@�@�@�@�@�莖�ƒ��肳��Č��ݗp�n���A�H�������{����Ă���B
�@�@�@�@�@�@�ߔN�L�c������̎ԗ��̒ʍs���������������A�d���n�悩��ʏ��n��Ɏ��鋷�
�@�@�@�@�@�ȓ��H�Ō�ʏa�������N��
�@�@�@�@�@���A���s�͂��Ƃ����ӏZ���̐����ɂ��傫�ȉe���𗈂��Ă���A����Ɍ����ΎR
�@�@�@�@�@���錧���͋}���z�A�}�J�[�u�A�Z���A�~�G�̐ϐ�A������������X�̈�������
�@�@�@�@�@�狾�g���l���̌��݂��]�܂�Ă���B
�@�@�@�@�@�@���ł͕����P�V�N�x���狾�g���l���̒����𑱂��Ă��邪�A���ニ�[�g�����
�@�@�@�@�@�����Ă̒��������{����\��ŁA���݁C�n�������Ɍ����ď������Ƃ̂��Ƃł��B
�@
�P�Q�A�@�C��s�̃S�~�����{�݂ɂ��āB
�@�@�@�@�@����H�����s���A�����܂łQ�U�N�ԉғ����Â��Ă���܂��A�v�����g���[�J�[��
�@�@�@�@�@���ϗp�N���͂P�O�N�ł����A���̌�̈ێ��Ǘ����K���ł������̂��傫�Ȏ��̂�
�@�@�@�@�@�Ȃ������ɉ^�]�𑱂��Ă��܂��A�������ߔN�A�{�s�̃S�~�����ʂ������A����ɂ�
�@�@�@�@�@���̋��Ă���Ƃ͂����A�ꕔ�̎Y�Ɣp�����܂ŏ������A�܂��A���̎s���̃S
�@�@�@�@�@�~�܂ŏ������Ă��錻��ł́A���܂Ŏ��̂����S�z�ł���܂��B
�@�@�@�@�@�@�����Q�O�N�S������́A���Ò��̃S�~�����{�݂��^�]���~����Ƃ̂��ƁA�]��
�@�@�@�@�@�ĂS������͉��Ò��̃S�~���ꏏ�ɏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����A�����
�@�@�@�@�@�������������Ȃ��Ƃ��Ă��A�\�͓I�ɂ��]�T������Ƃ��Ă��A�����V�������Ă���
�@�@�@�@�@����{�݁A��������������S�~�����ꌚ�݂Ɍ����Ă̎��g�݂��]�܂�Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@����Ȓ��A�{�s���A�L��ł̃S�~�����ɕ��j�����߁A�C��s�A�I���쒬�A�I�m��
�@�@�@�@�@�s�ƂƂ��Ɂu�L��S�~�����{�ݐ������c��v�𗧂��グ�����P�X�N�P�O���P�P����
�@�@�@�@�@�犈�����n�߂܂����B
�@�@�@�@�@�@�V�����L��S�~�����ꌚ�݂Ɍ����ē����n�߂܂������A�����炭�A�e�s��������
�@�@�@�@�@����𗘗p���傤�Ƃ���V�N��ɂ͊�������ł��傤�A���łɌ��n���I�m��
�@�@�@�@�@�s�A�I���쒬�ł��ꂼ��P�ӏ��������Ă���Ƃ��������Ƃł�����A����ǂ͊Ԉ�
�@�@�@�@�@���Ȃ����݂Ɍ����Đi�ނ��Ƃł��傤�B
�@�@�@�@�@���̕��͋T��n��ɍݏZ���A�v�w�������ŁA���N����q�������w�̏��w�Z�ɒ�
�@�@�@�@�@�����ƂɂȂ�A�T��̊w���ۈ��\�����Ƃ���A������T�O�l�łT�R�l�̉��傪��
�@�@�@�@�@��A���ɂ��T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙�����D�悷��ƌ����A�T�R�Ԗڂ̐\����
�@�@�@�@�@�Ƃ��đI�l����͂����ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���Ȃ݂ɃI�[�o�[�������̂Q�l�������ł��Ȃ������ƌ������Ƃł��B
�@�@�@�@�@�����Ŏs�̎q��Ďx���Z���^�[�̒S���҂��獕�]���w�Z�̊w���ۈ炪����ɒB����
�@�@�@�@�@���Ȃ��̂ł����ɒʂ��Ă͂Ɛi�߂��A��ނȂ����]�ɐ\�����Ƃ���A����ǂ͊w
�@�@�@�@�@�Z����o�X�ɂč��]���w�Z�̋߂��̃o�X��i�Z�傩���R�O���j�ō~��A�w���ۈ珊��
�@�@�@�@�@�ʂ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�o�X�₩�狳���܂ő��}����l���Ȃ���Ύ�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�Ƃ����A�S���҂���g���ɒN���Ȃ��ꍇ�̓T�|�[�g�Z���^�[���瑗�}�̂��߂̔h
�@�@�@�@�@�����Ă͂ǂ����Ƃ̘b������A�}���͒v�����Ȃ��Ƃ��Ă��킸���R�O�����悤�̂�
�@�@�@�@�@�T�|�[�g�Z���^�[�ɂ��肢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��p��������A���Ƃ��Ȃ�Ȃ���
�@�@�@�@�@���Ƃ��肢���܂������A����͂��邱�Ƃɂ��Ă͎s�̏��Ɍ��߂��Ă���̂łǂ�
�@�@�@�@�@���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ���ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���̕��͎s�̏��Ɍ��߂�ꂽ���j�ł���Ύd�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�����ƒN�������p
�@�@�@�@�@�ł��鐧�x�ɂȂ�Ȃ��̂��B�Ƃ������Ƃő��k�Ɍ������܂����B
�@�@�@���̘b���Ď������������Ƃ�
�@�@�@�@�@�܂��A���������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�C�T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙���̂��߂̊w���ۈ�ƌ������ƁB�T�쏬�w�����D�悷��ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������̒n��̊w���ۈ�����������ł���B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�A�T��n��ɏZ��ł��Ȃ���A���w���ɂ��悤�ƒ�ɑ���z�����S���Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�A���}�ɂ��āA���ɑ���ɂ��Ă͏��ɂ���ċ`���Â����Ă��邻���ł���ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�A����A���Y�����̑��ɁA�T�쏬�w�Z�ɒʂ��q���B�Q��������I�[�o�[�Ƃ������Ƃœ����ł��Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ł����A���q����Ƃ��Ă̎s���ɈՂ����{��Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�����ŁA�w���ۈ�ɂ��ĊȒP�ɒ��ׂĂ݂܂��ƁB
�@�@�@���������@�ł̒�`�H�i�w���ۈ�Ƃ�������g�p���Ă��Ȃ��B�j
�@�@�@�@�@�u���̖@���ŁA���ی㎙�����S�琬���ƂƂ́A���w�Z�ɏA�w���Ă��邨���ނ�10��
�@�@�@�@�@�����̎����ł��āA���̕ی�҂��J�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA����
�@�@�@�@�@�Œ�߂��ɏ]���A���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p���ēK�ȗV
�@�@�@�@�@�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}�鎖�Ƃ������B�v
�@�@�@�@�@�i��U���̂Q��V���j
�@�@�@�����E���T�Ȃǂɂ���`
�@�@�@�@�@�u�e�������Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A�ƒ�
�@�@�@�@�@�ɂ����ۈ���s���{�݁E���ƁB�v
�@�@�@�@�@�u���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w�����C���ی��莞�ԕۈ炷�邱
�@�@�@�@�@�ƁB�v
�@�@�@�w���ۈ�̉^���c�̂ɂ���`
�@�@�@�@�@�u�E�E�E�E�E�������ƒ���q�E���q�ƒ�̏��w���̎q�ǂ������̖����̕��ی�
�@�@�@�@�@�i�w�Z�x�Ɠ��͈���j�̐��������{�݂��w���ۈ�ł��B�w���ۈ�Ɏq�ǂ�����
�@�@�@�@�@���������Ĉ��S���Đ��������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ���āA�e���d���𑱂����
�@�@�@�@�@�܂��B�w���ۈ�ɂ͐e�̓��������ƉƑ��̐��������Ƃ�������������܂��B�v
�@�@ �@ �ȏ�̂悤�ɁA�w���ۈ�ɂ��Ē�`�Â����Ă��܂����A�n���̊w�Z�ɒʂ���������
�@�@�@�ۂƂ����悤�Ȃ��Ƃ͑S���ӂ���Ă��Ȃ����A�܂��厖�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐e��
�@�@�@�����Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A���̕ی�҂��J
�@�@�@�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p����
�@�@�@�K�ȗV�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}��B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA�n���̏��w�Z�ɒʂ������Ɍ��肵���l�Ȓ�`�Â����S���Ȃ��ꌾ���܂���B
�@�@�@�s�̒S���҂Ƃ̂��Ƃɂ��Ă̋��c�̒��ŁA
�@�@�@�@���}�ɂ��āA���ɂ�茈�߂��Ă���Ƃ��������͊ԈႢ�ŁA��W�v���ł́A�u�w��
�@�@�@�̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��Č}�����K�v�ł��B�܂��y�j����ċx�ݓ��̒����x�Ɗ��Ԓ�
�@�@�@�̊w���ۈ�ɂ��Ă�����}���������Ƃ��܂��B�v�L����Ă���A���ł́u�ۈ�I
�@�@�@����̎����̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��ĕی�҂��}���邱�ƂƂ��܂��v�Ƃ̋L�ڂ���
�@�@�@��A����ɂ��Ă͓y�j���y�ђ����x�Ɠ��ȊO�͓��ɂӂ���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@�@�@�@����ɁA�S���҂̕������Ƃ��R�O���̓��̂�ł����Ă����̊ԂɎ��̂ł���������Ύs
�@�@�@�̐ӔC����ꂩ�˂Ȃ����Ԃ��l���A�ی�҂�[���������߂Ɏv�킸���������o������
�@�@�@�ł͂Ȃ����B�����Ă������Ƃł͂Ȃ����A����͂���Ƃ��āA����Ȃ��Ƃ��̐e�̐ӔC�Ƃ�
�@�@�@�������Ƃ��������Ƃ��đΉ����ׂ��ł͂Ȃ����
�@�@�@�@�܂��s�O�̏��w�Z�ɒʂ������ɂď��ł͊C��s�w���ۈ����R���Ɂu�w���ۈ�̑�
�@�@�@�ۂƂȂ鎙���́@�i�P�j�s���̏��w�Z�ɏA�w���Ă�����w�N�����R�w�N�܂ł̎�����
�@�@�@�ی�҂��J�����Œ��ԉƒ�ɂ��Ȃ����́B�i�Q�j�O���Ɍf������̂̂ق��A�s��������
�@�@�@�K�v�ƔF�߂����́B�v�ƂȂ��Ă���B����̃P�[�X��(�Q)�ɑ�������̂ł͂Ȃ�����
�@�@�@�v���邪�ǂ��葱������������̂��Ƃ������Ƃ��낪�s���ł���A����������Ă��Ȃ��B
�@�@�@���̓_�ɂ��Ă͕ی�҂̗���ɗ��������J�ȑΉ����K�v�ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�@���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w����ΏۂƂ������Ƃ��炷��Ό}���͂Ƃ�
�@�@�@�����A����ɂ��Ă͓��R�d�����ł�����A�s�������悤�ɃT�|�[�g�Z���^�[�𗊂�Ȃ�
�@�@�@��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����A�o�ϓI�Ȗʂ�����A����̃P�[�X�̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�ی�҂�
�@�@�@�ӔC�͈̔͂őΉ����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɋT��̏ꍇ����Q�O���Z�O��
�@�@�@�s���������Ĉړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ɂ��Ă͉���Ή�����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�ȏ�̂��Ƃ��w�E���A���̂Q���ɂ��āB���������肢�����B
�@�@�@�@ 1�A���ɂ��ƁA�n���̏��w�Z�ɂ��悤�������ΏۂƂȂ��Ă��邪�A���̎��w�ɒʂ��q���B
�@�@�@�@�@�@�@�͒u������ɂ���Ă���A�q��Ďx���Ƃ����ϓ_����l����Ɛ������Ɍ�����悤�Ɏv���B
�@�@ �@�@�Q�A�\�����݂̗v�����ɂ́A�w���ۈ珊����̋A��͕ی�҂��}���ɗ���悤������Ă��邪
�@�@�@�@�@�@�@�w�Z����w���ۈ珊�ւ̈ړ��ɂ��ẮA����������Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���w�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@���������A���Y�ۈ珊�̋߂��Ńo�X���~��Ċw���ۈ珊�ɒʂ��ꍇ���̋����@���Ɋ�
�@�@�@�@�@�@�@��炸�͕ی�҂�����}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�����Ȃ���Ă���B�q���̈��S
�@�@�@�@�@�@�@���l����Ɠ��R�̂��Ƃ�������Ȃ����A�n���̏��w�Z�ɂ��悤�����ɂ͑S������������
�@�@�@�@�@�@�@�z�����Ȃ���Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂��B���������āA�����ɑ��k�ɍs�������X�ɑ���
�@�@�@�@�@�@�@�̂ݎw�����āA�n���̏��w�Z�ɒʂ��ی�҂ɑ��Ă͖ٔF���Ă���̂ł͂Ƌ^���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@���悤�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���B����ɂ��Ă��A�������̂���悤�ɉ��߂�ׂ��ł���B
�@�@�@�@����̌��ŒS���ۂɊF����͑����������Ă��������A��肠��������ɂ��Ă͕ی�҂Ƒ��k��
�@�@�@�@�@�@�@��ی�҂̐ӔC�ō��]�ۈ珊�ɒʂ����Ƃ�F�߂�Ƃ̉����������܂����B�W�҂�
�@�@�@�@�@�@�@�v���ȑΉ��Ɋ��ӂ��܂��B
�@�@�@�@
�č����{������{���{�ɒ����u�N�����v�v�]���v�Ƃ�
�u�D������{�v�i�։��p�V�j���
�@�@�@�Ăт��̖{���Q�l�ɔN�����v�v�]���ɂ��ėv�_���L���Ȃ��玄�̍l�����q�ׂ�
�@�@�݂����ƂƎv���܂��B�u�N�����v�v�]���v�͂X�R�N�V�������T�~�b�g�̍ۂ̋{��N�����g��
�@�@��]��k�ł́u���ĊԂ̐V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v���ӂ���������
�@�@�ł���B���̌���{�̐����͍א���t�A�H�c���t�A�����ĂX�S�N�U���ɑ��R���t�������A
�@�@���ꂩ��܂��Ȃ��\���ɍݓ��č����H��c�����Γ��v�]�����\�A���ꂪ�u���ĊԂ�
�@�@�V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v�̈�Ƃ��Đݒu���ꂽ�K���ɘa�E����
�@�@��������ɍ̗p����A�u�N�����v�v�]���v�Ƃ��Ē�ቻ�����Ƃ����킯�ł���B�Ȍ㌇��
�@�@�����ƂȂ����N�H�Ɍ��\����Ă����B
�@�@�@���{�̐������\�ܔN�̐������A�����A�������钆�č��ɑ����������A����
�@�@����u�č��ɂ����{�����v�Ƃ����`�e�̂������̂Ȃ����ĂQ���Ԃُ̈�ȃ��J�j�Y
�@�@���ƁA���̋��͂Ȕ}�̂ł���u�N�����v�v�]���v�́A�����{�̗��j�I�]���_�Ƃ���
�@�@�ׂ������ƍ����̒��ŁA�č��Ɏ��˂����܂�ē��{�̐����V�X�e���̒��ɂ��������
�@�@���U����Ă��܂����B���́u�N�����v�v�]���v�͂O�S�N�A�։��p�V���̒����u���ۂł���
�@�@�����{�v�����\����A�u�킵�Y���v�i����Ƃ̏��т悵�̂肪�ӔC�ҏW���߂�G��
�@�@���B�j�O�U�N�~���ŏ��т悵�̂肳��́u�������ł����̎����𐢂ɍL�߂邽�߂ɏ�������
�@�@�ɂ���v�Ƃ������Ƃ���u���ė��E�N�����v�v�]���ɓ{��v�Ƃ������W���g�܂�A�����]
�@�@�_�Ƃ̐X�c�����u�����S�ʔᔻ�v�i���{�]�_�Ёj�̒��ŁA�u�O�S�N�T���R���A����
�@�@�ڍ��w�r�����̏��X�ň���̐V�����������A�Ƃ������{�̕����玄�ɍ��}�𑗂���
�@�@����C����������͡{�ۂł��Ȃ����{�[�A�����J�̓��{������������ł���p���҂͊։�
�@�@�p�V����A�m��Ȃ����������̐l�̒����ɂ͓��{�̍���J�����{�l�̍������߂��Ă���悤�ȋC�������v��
�@�@�������ƂŎ��グ�A�Ȍ�W�҂̊ԂɍL�����グ����悤�ɂȂ��������ł���B
�@�@�@�X�U�N����n�܂����u�N�����v�v�]���v�O�S�N�Ɂu���ۂł��Ȃ����{�Łv�����ɔ��\�����܂ŁA���̎��X�̓�
�@�@�t�A�����͒m���Ă����Ƃ��Ă��@��ʂ̍���c�����^�}����}���قƂ�ǒm��Ȃ��������Ƃɋ����ł���B�u����
�@�@�ł��Ȃ����{�v�̘b���A���҂̊։��p�V����������āA������J�����A���̏��ы��N�����A���i��
�@�@��A�ނ�͊։�����̘b�����ςȂ��ɂ��Ȃ������B�ނ�́u�N�����v�v�]���v�͂��A�X�����c���@�Ă���
�@�@���̗v���������̂ł��邱�Ƃ��������A����ł͓��{�̍��v�ɂȂ�Ȃ��A�A�����J�𗘂��邾���ł͂Ȃ����Ƌ`
�@�@����R�₵���B�����Ă��̌�̓W�J�́A�������̒ʂ�ł���B����ɐ�������A�}�X���f�B�A�ɗx�炳��
�@�@�����{�̗L���ҁi���{�����j���炪�����̎���i�߂Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�@�@�u�N�����v�v�]���v����͓��đo�������݂ɒ�o�������Ă������̂ŁA�ߋ��\���N�ԓ��{�Ői�߂��Ă����A
�@�@�u���v�v�̂��Ȃ�̕������č����{�̗v���𒉎��ɔ��f���Ă������̂ŁA�O�T�N����Ő��������A�V��Ж@�A����
�@�@�Ƌ֖@�A�X�����c���@���܂�������ł���B�����āA�����̒��߂�����́A��Ð��x���v�ł���B���̗�R��
�@�@��]���Ԃ�́u�P�퉻���ꂽ�������v�Ƃ����ق��͂Ȃ��A�匠���ƂƂ��Đq��Ȃ炴����̂��B����ł͕č���
�@�@�B�̕����܂������A������A�����J�̑����ł͂Ȃ����B
�@�@�@����͂Ȃ��������[�@�Ă⋳���{�@�����@�āA�h�q�����i�֘A�@�ĂȂǏd�v�@�ĂȂǐ摗�肵�A���
�@�@���x���v�@�Ă̐������}�����̂��B����͂܂��ɂO�U�N�U���Ƀu�b�V���đ哝�̂Ƃ̍Ō�̎�]��k���Z�b�g����
�@�@�Ă������߂ŁA�u�N�����v�v�]���v��Ð��x���v�̐i�W������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�����ꂽ��Ð��x���v�@�́A���I��Ô�̗}���������ł��o�������̂ŁA���̂��߂ɍ����A�Ƃ�킯�����
�@�@�Ɏ��ȕ��S�̑���𔗂���e�ƂȂ����B
�@�@�@�����͂O�Q�N�Ɋ��Ɉ�Ð��x���v�ɒ��肵�Ă���A���̂Ƃ��͂���܂ł̏���t��z�����P�p����A���S
�@�@�藦���ɑւ���ꂽ�B���̍ہA�V�O�ˈȏ�̍���҂̈�Ô�ȕ��S���́A��ʏ����҂��P���A������ݏ���
�@�@�҂��Ƃ���A����҂̎��ȕ��S�𑝂₵�Ă���B����҈ȊO�ɑ��Ă��A�O�R�N����T�����[�}���{�l�̈��
�@�@��ȕ��S������O���Ɉ����グ��ꂽ�ق��A�Z������������x�[�X����ܗ^���܂߂��N���x�[�X�ɕύX
�@�@����A�ی������S�����₳��Ă���B
�@�@�@���ꂪ�O�U�N�̈�Ð��x���v�ł͎��\�˂��玵�\�l�˂̈�ʏ����҂͂O�W�N�S������ɁA���\�ˈȏ�̌�
�@�@����ݏ����҂͂O�U�N�P�O������O���ɑ��₳��B�܂��A�u������ݏ����v�̒�`������������ꂽ���߂ɁA�e
�@�@������Ώێ҂̐����������B���̏�A�u���z�×{��x�v����������A����ҁA���𐢑���킸�A���z�Ȉ�
�@�@�Ô���������ꍇ�̎��ȕ��S���x�z�������グ��ꂽ�B
�@�@�@����ɁA�u�������҈�Ð��x�v���n�݂���O�W�N����]���͕}�{�Ƒ��Ƃ��ĕی�����Ƃ�Ă����l���܂߁A
�@�@���\�܍ˈȏ�̂��ׂĂ̍���҂��A�ی����̎x�����`�����ۂ����邱�ƂɂȂ����B�܂��A����҂������ɓ�
�@�@�@���Ă���u�×{�a���v�ł̐H�����M��͂O�U�N�\������ی��ΏۊO�ƂȂ�A�×{�a�����̂��Q�O�P�Q�N�܂łɌ�
�@�@�݂̔����ȉ��ɍ팸����邽�߁A�������@���҂͗L���V�l�z�[���Ȃǂ֓]�o�𔗂���B�[�I�Ɍ����A����
�@�@�������T�N�Ԃɂ킽���Đ��i���Ă����u��Ð��x���v�́v�Ȃ���̂̎��Ԃ́A�����A�Ƃ�킯����҂Ɏ��ȕ��S��
�@�@��𔗂邱�ƂɏI�n���Ă����̂͒N�̖ڂɂ����炩�ł���B
�@�@�@���҂̎��ȕ��S�����܂�A���I�ی��ŃJ�o�[�����͈͂�������A�k�����邱�ƂɂȂ�A���ȕ��S���J�o�[
�@�@���邽�߂̖��ԕی����o�ꂷ��B�u���ꂪ���ɏo���邱�Ƃ͖��ɂ�点��v�ƌ������Ƃł���A���I��Õی���
�@�@�k�����Ă����A����A�����́u���ȐӔC�v�ŏ����ɔ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐V����e���r�ŃA�t��
�@�@�b�N��A���R�ȂǃA�����J�n�ی���Ђɂ���Õی����i�̐�`���킪�ٗl�ȂقljߔM���Ă���̂́A��Ð�
�@�@�x���v�ɒ[�������ۂł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�����ЂƂA����ł����̂����{�́A�����������Ȃ�悤�ȉ��v���i�߂��Ă����B���ꂪ�u�V��Ж@�v�̐�
�@�@�肾�A�u��Ж@�v�Ƃ����@���͂���܂ő��݂��Ȃ������A��А��x�Ɋւ��Ă͏��@��L����Ж@�ȂǗl�X�Ȗ@��
�@�@������ł����A��������ɂ܂Ƃ߂ĐV�����u��Ж@�v���A�����Ă��̖ڋʂƈʒu�Â����Ă����̂��A����
�@�@�J���狭���v�]����Ă����A�u�O�����Ή��̍����v�i�������z�������������j�̉��ւł���B���ꂪ���ւ����Ƃ�
�@�@���Ȃ邩�A�Ђ炽�������ΊO����Ƃ����z�̔��������������邱�ƂȂ��ɁA���Њ����g���Ă��Ƃ����₷�����{
�@�@��Ƃ��P���ɂ����߂邱�ƂɂȂ�B������u�O���ɂ����{��Ƃ̏�����v�̉��ւł���B
�@�@�@�V��Ж@�͂O�S�N�P�Q���ɗv�j�Ă����\����O�T�N�ʏ퍑��ɖ@�Ă���o����A�O�U�N����{�H����邱�Ƃ�
�@�@�Ȃ��Ă����A�����̂قƂ�ǂ��m��Ȃ��ԂɁA�܂��ɊԈꔯ����̔N���C�u�h�A�̎������������A�G�ΓI��Ɣ���
�@�@�ւ̍����I�S���ɂ킩�ɕ����A�Ƃ��ɁA��������d�|����ꂽ���{��Ƃɂ͖@�I�ɕۏ��ꂽ�h�q�ق�
�@�@��ǖ������ƂɊ�@�������������B�����}�̓}��(�X�����c���Ŋ����A���̏��ы��N�c���⏬�i�c��)
�@�@������u�O�����މ��̍����v���ւɑ��锽�Θ_�����o���A��o�������O�Ɉ�N�ԓ�������邱�ƂɂȂ����B��
�@�@��Ȋ댯�Ȃ��Ƃ����蔭�Ԑ��O���������Ƃɂ͜ɑR�Ƃ������ł��邪�A���̎����}(�X�����c���Ŋ���
�@�@���A���̏��ы��N�c���⏬�i�c���j�c�������̓����ɂ��A��N�ԓ�������邱�ƂƂȂ�A���{�̊�Ƃ��h
�@�@�q����u���邱�Ƃ��o�����̂ł���B
�@�@�@����ɂ��Ă��A�Ȃ��������ݓ��{�̑��Ƃ��������ɂ���킽���ɂЂƂ����u�O�����Ή��̍����v�̉��ւȂ�
�@�@�Ƃ������Ƃ��i�߂��Ă����̂��B�ӊO�ɂ����Ƃ͉�Ж@�����ł͂Ȃ��̂��A�ӊO�ɂ���v��ɂ��Ċ�ƍ�
�@�@����v�����������Ɍ������ꂷ����j����߂��A���̐V����������v����ł́A�]���̓��{�I�ȑΓ�����
�@�@�͓���Ȃ�A�G�Ύ��������܂߂��z������������̊�ƍĕ҂̎嗬�ƂȂ�Ƃ����Ă���B����ɁA�Ő��ʂł�
�@�@�O���ɂ����{��Ɣ������㉟�����邽�߂ɐŐ����v���O�S�N���猟������Ă���Ƃ����A����������A�̉��v��
�@�@���̂��ׂĂ̓����̎i�ߓ��ƂȂ��Ă���̂��u�Γ�������c�i�i�h�b�j�v�c���͓��t�����厖�A���c���͌o�����S
�@�@����b�A�����Ă��̉����g�D�ɂ͂P�R�l�̓��{�l�̑��ɁA�ݓ��č����H��c���̊�����č��،���Ђ̖����A
�@�@��l�̊O���l�ٌ�m���܂ނP�O�l�̊O���l���u�O���l���ʈψ��Ƃ��Ė���A�˂Ă��邻���ł���B
�@�@�@�����āA���̑Γ�������c��啔��O�S�N�A�u�Γ��������i�v���O�����y�ю��{�v�Ƃ��������̒��ŁA
�@�@�u�������z���������E�������e�Ղɍs����悤�Ɂv�Ƃ����ړI�Łu�O�����Ή��̍����v�̉��ւ��ƍ�����v��
�@�@�̎������������A�Ő���̗D���[�u�ȂǂƂ��������Ƃ���̗�Ƃ��Ă������Ă��B����ȊO�ɂ��A�ߔN�A���{��
�@�@�傫���h�邪���Ă���B������\�����v�̑������A���́u�Γ��������i�v���O�����v�̈���������Ƃ����L��
�@�@��Ă���B���͏���̌����\�����v�́A�����̂��߂ł͂Ȃ��A�O���ɂ����{��Ƃ̔����𑣐i���邽�߂�
�@�@�u���{�����v�����������đg�D�I�ɐi�߂��Ă����̂ł���B
�@�@�@04�N�ł́u�Γ������C�j�V�A�`�u�v�̕��ɂ́o�č����{�́A���{�ɂ�����l�����Ԃ̕ω��ɂ��A����A
�@�@����y�ш�ÃT�[�r�X����ɂ����铊�����d�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E�����B�����Ă����̕���ɂ����ĕč�
�@�@��Ƃ����̓��ӕ���������l�X�Ȏ��̍����T�[�r�X��ł��邱�ƁA�܂����������V���ȃT�[�r�X�̒�
�@�@�����{�̏���җ��v�̑���Ɏ�������̂ł��邱�Ƃ��w�E�����B�č����{�͂����̕���ɂ����铊���𑣐i��
�@�@�邽�߁A���{���{�ɑ��A���Y����ɂ����铊�����\�Ƃ��邽�߂̋K�����v��v�������B�p���邳��Ă���B
�@�@�@�����ăA�����J�̓��{�����͂܂��܂������X�����c���Łu�ȈՕی��v����Ð��x���v�Łu��Õی��v�����̂�
�@�@�炢�͋���A��ÃT�[�r�X�A�u���ρv�ւƉ��X�Ƒ��������ł���B���������N�����̕č��ɂ����{�������~��
�@�@��̂��A�����Ȃ鍑���ȊO�ɂȂ��ł͂Ȃ����A�ڊo�߂���{�B
�@�@�@���ċK�����v�y�ы�������C�j�V�A�`�u�Ɋ�Â����{���{�ւ̕č����{�v�]���̖`���ɂ�
�@�@�@�O�T�N�Ł@�@�č��́A������b�̓��{�o�ω��v�Ɍ������p���I���g�݂�����������B�����̎��g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͓��{�𐬒��O���ɏ悹�A��葽���̖f�Ջy�ѓ����@���n�o�����A�č��͂܂��A�����ƍ\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����͏����ʓI�ɒ��Ă����K�����v�E���ԊJ�����i�{���ƁA�\�����v���ʐ��i�{���̂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g�݂�]������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̗v�]���ɐ��荞�܂ꂽ�́A��v�����A���f�I����ɂ�����A���v�ɏd�_��u���A�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ϐ������x�����A���{�̎s��J������肢�������������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B����ɕč��͓d�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A�m�I���Y���A��ÁA�_�ƁA���c���A��������ȂǁA���������v�̎�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���d�v�ł���ƈʒu�Â�������̖��Ɉ����������ɏœ_�ĂĂ���B
�@�@�@�O�U�N�Ł@�@�č��́A���{�̌o�ω��v�𐄐i����Ƃ�������������b�̌��ӂ����}����B�V�����@��݁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����𑣂��A��茒�S�ȃr�W�l�X�������o�����v�́A���ꂩ��扽�N�ɂ��n����{�̌o�ϐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɗ��͂��ێ����x����ł��낤�B�܂��A�č��͓��{�����̉��v���i�҂̎��g�݂�S�����v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���㐔�����A���N�ɂ킽��A�����̊��������������邱�Ƃ����҂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̕č�����̒́A�d�C�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A��Ë@��A���i�A���Z�T�[�r�X�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɩ@���T�[�r�X�A�������A�_�ƁA���Ђ̖��c���A���ʁA��������ƍL�͈͂ȕ���ɂ����āA�p
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ��v�̐i�W��}�邱�Ƃ̏d�v�����������Ă�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԕ���i�č��́j�̑�\�����C�j�V�A�`�u�֒���I�ɎQ�����A���m������Ă���邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŁA��X�̍�ƂɕK�v�ȑ����̏��邱�Ƃ��o�����A�����͂��̂悤�ȎQ���̋@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���傷�邱�Ƃ����҂���B
�@
�@�@�@�ȏオ�����F����ɓ`���������̖{�̓��e�̈ꕔ�ł��B�������ł��傤���A�������������m��Ȃ��Ԃɋ�����
�@�@�����Ƃ��i�s���Ă��܂��A���̂��Ƃ����{�̏������ǂ��ς��Ă����̂����̕n��ȓ��ł͑z�������܂���
�@�@�̖{��ǂ�ł���Ɖ�������傫�ȓ{�肪�킢�Ă��ĂȂ�܂���B
�@�@�@���̔N�����v�v�]���͓��đo�����o�������Ă���A���R���{���o���Ă��܂����A����Ƃ��Ď������Ă��Ȃ�
�@�@�����ł��B��Ȃ�����ł͂���܂��A�ǂ����F�l�A��x�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�Łu�N�����v�v�]���v
�@�@�Ȃ���̂������Ŋm���߂Ă��������B�����Ǝ��̌����Ă��邱�Ƃ��������Ă���������Ǝv���܂��B
�@�@�@�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�@http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@
�X�����c���͓��{�����ɂƂ��Đ��������v�Ȃ̂�
�@�@����A����H.D���玟�̗l�Ȃ��莆���܂����B
�@�@�O���A�M�Z�ɂ͐V���ȖڕW�Ɍ������čĂъ������n�߂�ꂽ���ƁA���ɂ����c�Ɋ����܂���B�n��ɍ�
�@������������ʂ��ĊC��s������肢�������O�i�����Ă������������܂��悤���҂��Ă���܂��B
�@�@���Đ���A�M�Z�̃z�[���y�[�W�ŗX�����c�������グ�Ă���̂�q�����āA���ɓ������ӌ��ŁA
�@���X�Ȃ���M�Z�̓��@�͂̐[���Ɋ��S�������܂����B�i�����j
�@�@�X���ɂ��Ă͌������܂������A������������v�̖��̂��Ƃō��v�ɔ�����悤�Ȑ������������邱
�@�Ƃ����͂��߂�ւ肽���҂ł��B
�@�@�����̐}���͐挎���s����܂������̂ł����A���݂̎��̑z���Ɠ����ł��̂Ő����x���ڂƂƂ�����
�@�����������肢�����܂��B�ƌ������ƂŁA���̂悤�Ȗ{�𑗂��Ă��������܂����B
�u�D������{�v�i�։��p�V�j
�@�@�ڂ���Ƃ͂��̂��ƂŁA���̂���A�����̍����ɂƂĂ̂킩��ɂ��������X�����c���A�������̋^
�@��_�����炩�ɂȂ�܂����B�����āA���ы��N�c�������ߔ��Δh�̋c���͂Ȃ����̂悤�ɋ��d�ɔ���
�@��̂����A���v���Ȃ��}���̂��A�X�����c����č��ƂȂ��b������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ���������
�@�����̖{�����炩�ɂ��Ă��܂��B�F����ɂ��̖{�̂��ׂĂɖڂ�ʂ��Ă������������Ǝv���܂����A����
�@�ł͗v�_���L���Ă݂����Ƒz���܂��B
�@�@���{��卬���Ɋׂꂽ�X�����c���@�A���{�̏��������ɂ킽��ł��낤�A�l�X�ȉЍ����c�����Q�O�O�T
�@�N�ő�̐����ۑ�́A���ׂď����̎v�f�����Ɍ��������B���̔N�̉ߔ��̎��ԂƃG�l���M�[����
�@����Ƃ�������X�����c���Ƃ́A���ǂȂ����̂��B
�@�@���̗X�����c�����ɂ́A�Ō�܂ł����₯�ɂ͂قƂ�nj���Ȃ��������ʂ�����B���{�̍\��
�@���v�̖{�ہA���邢�͐����Ə���Y�̌l�I���O�A�ȂǂƎ�肴������Ă������̖��̔w���
�@�͕č�����̎��X�Ȉ��͂Ƃ���������̈��q���B����Ă����̂ł���B
�@�@1995�N11���ɕč����{������{���{�ɒ��ꂽ�u�N�����v�v�]���v�ɂ́A�ȈՕی��Ɋւ��Ď���
�@�悤�ȋL�q������B
�@�@�o�č����{�́A���{���ȉ��̂悤�ȋK���ɘa�y�ы������i�̂��߂̑[�u������ׂ��ł���ƐM����B
�@�E�E�E�E�E�X���Ȃ̂悤�Ȑ��{�@�ւ��A���ԉ�Ђƒ��ڋ�������ی��Ɩ��Ɍg��邱�Ƃ��֎~����B�p�Ƃ�
�@��B�@�h�֎~����Ƃ͓��������̂��̂ł͂Ȃ����B�h�@
�@�@�����Ă���ȗ��č����{�͊ȈՕی��̔p�~��v���������A
�@�@1999�N�̗v�]���ł́@�o�č��͓��{�ɑ����ԕی���Ђ����Ă��鏤�i�Ƌ�������ȈՕی�
�@�i�J���|�j���܂ސ��{�y�я������ی����x���g�傷��l�������ׂĒ��~���A�����̐��x�����ł܂���
�@�p�����ׂ����ǂ����������邱�Ƃ��������߂�B�p�܂�č��͊��ƂƂ��Ă̊ȕۂ�p�~���Ė��ԉ�Ђ�
�@�J������Ɨv�����Ă���̂ł���B
�@�@���{�̖��ԕی��s��͉ߋ�20�N�ȏ�ɂ킽���ĕč��ɂ������W����Ă����A���̗��j��U���
�@������ʼn��߂��l����A�X�����c���̖{���͂P�Q�O���~�ɂ̂ڂ銯�c�ی��̎s��J����肾�ƌ���
�@���Ƃ��킩��B�������������c�����������ł͍����ő��̓��{�����̎O�{�߂��K�͂̋���Ȗ��ԕ�
�@����Ђ��a�����邾���̂��Ƃ��A�����A�č����]��ł���̂͂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�č��͖��c��
�@��̊ȈՕی��Ƃ��̎��Y�P�Q�O���~���ǂ����傤�ƍl���Ă���̂��B
�@�@2004�N�̋K�����v�v�]���ɂ͂��̋L�q��v��ƁA�ȕۂ̐��{�ۗL���������S�Ɏs��֔��p��
�@���A�u���{�ۏ����邩�̂悤�ȔF���������ɐ����Ȃ��悤�\���ȕ�����v��点��B�܂萭�{�̊֗^
�@�����S�ɒf���点�����Ȗ��ԉ�ЂƂȂ����ȕۂɑ��ẮA�O���n�ی���ЂƊ��S�ɑΓ��ȋ�����
�@����v�����Ă����B�����Ċȕۂ̏��NJ������Ȃ�����Z���Ɉڊǂ������̗������茟���������A
�@�\���y���V�[�}�[�W���Ȃǂ̌��\���`���Â���v�������Ȃǂ̊č���������B
�@����ɁA�ȕۂ�Ƌ֖@�Ȃǂ̓K�p�ΏۂƂ��A�u���̎s��x�z�͂��s�g���Č���c�Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��悤�v
�@��������ψ���ɒ���������ƌ��������Ƃ��L�q����Ă���B
�@�@�v����ɕč��ɂƂ��Ė��c���̓S�[���ł͂Ȃ��ȕۂ���̉������A�ŏI�I�ɂ͕����A��́A�o�c�j�]
�@�ɒǂ����݁A�l���`��c�Ə��n�ȂǗl�X�Ȏ�i��M���āA�ȕۂ��i���Ă���P�Q�O���~�ɂ̂ڂ鎑�Y��
�@�č��n���ԕی���Ђɋz�������邱�Ƃ��ŏI�I�Ȃ˂炢�Ȃ̂ł���B
�@�@�ȕۂ͏����ł��邱�ƂƁA���R���Ƃ����ȈՂȉ����葱������F�Ƃ��Ă���B���X�ȈՐ����ی����x
�@�́A���Ԃ̐����ی��ɉ����ł��Ȃ��Ꮚ���҂ɂ��ی��Ƃ����Z�t�e�B�l�b�g����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�吳�ܔN�ɑn�݂�����̎҂Ńr�W�l�X�ƌ��������{�Љ�̈��艻���u�ł���B
�@���ꂪ�č��l�ɂ͒P�Ȃ�s��Ƃ��Ă����ڂ�Ȃ��B���艻���u���͂�������̓��{�Љ�ǂ��Ȃ낤��
�@��؊S���Ȃ��̂ł���B�u�����疯�֎����𗬂��v�u���ɏo���邱�Ƃ͖��Łv�ƌ����Ƃ��̖���
�@���{�����̖��ł͂Ȃ��A���{�����̍s�����ɐӔC��Ȃ��č����ԕی���Ђ́u���v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�������ł��傤���A�����͂��K�ߑ����̍���c�����X�����c���ɂ��āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɍ��́A
�@�����̗��v�ɂȂ���̂����Ȃ������ɐ����ӔC���ʂ����Ȃ��̂��A���킩�蒸�����ł��傤���A�{��
�@�͗X�����c���ɍŌ�܂Ŕ������A�^�̍��v����낤�Ƃ��������}�̗E�C����c���B������X������
�@�������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�����ł͂Ȃ������̂��B�ŋߎ��͂��Â������v���Đ���܂���A����
�@�Ђ�����ɉ��̂��߂炢���Ȃ�������ӐM���c���Ɏ^���������A�䂪���̂U�l�̗^�}�c���́A�ǂ�
�@�قnj����ɑ��Đ����ӔC���ʂ������̂ł��傤�B�ނ�͕č��́u�N�����v�v�]���v�m���Ă����̂ł���
�@�����B�@�������̂��Ƃ͐����Ă݂����҂ł��B
�@
�@
�@�@�@�@�@�����ƂɂȂ�A�T��̊w���ۈ��\�����Ƃ���A������T�O�l�łT�R�l�̉��傪��
�@�@�@�@�@��A���ɂ��T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙�����D�悷��ƌ����A�T�R�Ԗڂ̐\����
�@�@�@�@�@�Ƃ��đI�l����͂����ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���Ȃ݂ɃI�[�o�[�������̂Q�l�������ł��Ȃ������ƌ������Ƃł��B
�@�@�@�@�@�����Ŏs�̎q��Ďx���Z���^�[�̒S���҂��獕�]���w�Z�̊w���ۈ炪����ɒB����
�@�@�@�@�@���Ȃ��̂ł����ɒʂ��Ă͂Ɛi�߂��A��ނȂ����]�ɐ\�����Ƃ���A����ǂ͊w
�@�@�@�@�@�Z����o�X�ɂč��]���w�Z�̋߂��̃o�X��i�Z�傩���R�O���j�ō~��A�w���ۈ珊��
�@�@�@�@�@�ʂ��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�o�X�₩�狳���܂ő��}����l���Ȃ���Ύ�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�Ƃ����A�S���҂���g���ɒN���Ȃ��ꍇ�̓T�|�[�g�Z���^�[���瑗�}�̂��߂̔h
�@�@�@�@�@�����Ă͂ǂ����Ƃ̘b������A�}���͒v�����Ȃ��Ƃ��Ă��킸���R�O�����悤�̂�
�@�@�@�@�@�T�|�[�g�Z���^�[�ɂ��肢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��p��������A���Ƃ��Ȃ�Ȃ���
�@�@�@�@�@���Ƃ��肢���܂������A����͂��邱�Ƃɂ��Ă͎s�̏��Ɍ��߂��Ă���̂łǂ�
�@�@�@�@�@���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ���ꂽ�����ł��B
�@�@�@�@�@���̕��͎s�̏��Ɍ��߂�ꂽ���j�ł���Ύd�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�����ƒN�������p
�@�@�@�@�@�ł��鐧�x�ɂȂ�Ȃ��̂��B�Ƃ������Ƃő��k�Ɍ������܂����B
�@�@�@���̘b���Ď������������Ƃ�
�@�@�@�@�@�܂��A���������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�C�T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙���̂��߂̊w���ۈ�ƌ������ƁB�T�쏬�w�����D�悷��ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������̒n��̊w���ۈ�����������ł���B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�A�T��n��ɏZ��ł��Ȃ���A���w���ɂ��悤�ƒ�ɑ���z�����S���Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�A���}�ɂ��āA���ɑ���ɂ��Ă͏��ɂ���ċ`���Â����Ă��邻���ł���ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�A����A���Y�����̑��ɁA�T�쏬�w�Z�ɒʂ��q���B�Q��������I�[�o�[�Ƃ������Ƃœ����ł��Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ł����A���q����Ƃ��Ă̎s���ɈՂ����{��Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�����ŁA�w���ۈ�ɂ��ĊȒP�ɒ��ׂĂ݂܂��ƁB
�@�@�@���������@�ł̒�`�H�i�w���ۈ�Ƃ�������g�p���Ă��Ȃ��B�j
�@�@�@�@�@�u���̖@���ŁA���ی㎙�����S�琬���ƂƂ́A���w�Z�ɏA�w���Ă��邨���ނ�10��
�@�@�@�@�@�����̎����ł��āA���̕ی�҂��J�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA����
�@�@�@�@�@�Œ�߂��ɏ]���A���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p���ēK�ȗV
�@�@�@�@�@�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}�鎖�Ƃ������B�v
�@�@�@�@�@�i��U���̂Q��V���j
�@�@�@�����E���T�Ȃǂɂ���`
�@�@�@�@�@�u�e�������Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A�ƒ�
�@�@�@�@�@�ɂ����ۈ���s���{�݁E���ƁB�v
�@�@�@�@�@�u���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w�����C���ی��莞�ԕۈ炷�邱
�@�@�@�@�@�ƁB�v
�@�@�@�w���ۈ�̉^���c�̂ɂ���`
�@�@�@�@�@�u�E�E�E�E�E�������ƒ���q�E���q�ƒ�̏��w���̎q�ǂ������̖����̕��ی�
�@�@�@�@�@�i�w�Z�x�Ɠ��͈���j�̐��������{�݂��w���ۈ�ł��B�w���ۈ�Ɏq�ǂ�����
�@�@�@�@�@���������Ĉ��S���Đ��������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ���āA�e���d���𑱂����
�@�@�@�@�@�܂��B�w���ۈ�ɂ͐e�̓��������ƉƑ��̐��������Ƃ�������������܂��B�v
�@�@ �@ �ȏ�̂悤�ɁA�w���ۈ�ɂ��Ē�`�Â����Ă��܂����A�n���̊w�Z�ɒʂ���������
�@�@�@�ۂƂ����悤�Ȃ��Ƃ͑S���ӂ���Ă��Ȃ����A�܂��厖�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐e��
�@�@�@�����Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A���̕ی�҂��J
�@�@�@�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p����
�@�@�@�K�ȗV�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}��B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA�n���̏��w�Z�ɒʂ������Ɍ��肵���l�Ȓ�`�Â����S���Ȃ��ꌾ���܂���B
�@�@�@�s�̒S���҂Ƃ̂��Ƃɂ��Ă̋��c�̒��ŁA
�@�@�@�@���}�ɂ��āA���ɂ�茈�߂��Ă���Ƃ��������͊ԈႢ�ŁA��W�v���ł́A�u�w��
�@�@�@�̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��Č}�����K�v�ł��B�܂��y�j����ċx�ݓ��̒����x�Ɗ��Ԓ�
�@�@�@�̊w���ۈ�ɂ��Ă�����}���������Ƃ��܂��B�v�L����Ă���A���ł́u�ۈ�I
�@�@�@����̎����̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��ĕی�҂��}���邱�ƂƂ��܂��v�Ƃ̋L�ڂ���
�@�@�@��A����ɂ��Ă͓y�j���y�ђ����x�Ɠ��ȊO�͓��ɂӂ���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@�@�@�@����ɁA�S���҂̕������Ƃ��R�O���̓��̂�ł����Ă����̊ԂɎ��̂ł���������Ύs
�@�@�@�̐ӔC����ꂩ�˂Ȃ����Ԃ��l���A�ی�҂�[���������߂Ɏv�킸���������o������
�@�@�@�ł͂Ȃ����B�����Ă������Ƃł͂Ȃ����A����͂���Ƃ��āA����Ȃ��Ƃ��̐e�̐ӔC�Ƃ�
�@�@�@�������Ƃ��������Ƃ��đΉ����ׂ��ł͂Ȃ����
�@�@�@�@�܂��s�O�̏��w�Z�ɒʂ������ɂď��ł͊C��s�w���ۈ����R���Ɂu�w���ۈ�̑�
�@�@�@�ۂƂȂ鎙���́@�i�P�j�s���̏��w�Z�ɏA�w���Ă�����w�N�����R�w�N�܂ł̎�����
�@�@�@�ی�҂��J�����Œ��ԉƒ�ɂ��Ȃ����́B�i�Q�j�O���Ɍf������̂̂ق��A�s��������
�@�@�@�K�v�ƔF�߂����́B�v�ƂȂ��Ă���B����̃P�[�X��(�Q)�ɑ�������̂ł͂Ȃ�����
�@�@�@�v���邪�ǂ��葱������������̂��Ƃ������Ƃ��낪�s���ł���A����������Ă��Ȃ��B
�@�@�@���̓_�ɂ��Ă͕ی�҂̗���ɗ��������J�ȑΉ����K�v�ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�@���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w����ΏۂƂ������Ƃ��炷��Ό}���͂Ƃ�
�@�@�@�����A����ɂ��Ă͓��R�d�����ł�����A�s�������悤�ɃT�|�[�g�Z���^�[�𗊂�Ȃ�
�@�@�@��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����A�o�ϓI�Ȗʂ�����A����̃P�[�X�̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�ی�҂�
�@�@�@�ӔC�͈̔͂őΉ����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɋT��̏ꍇ����Q�O���Z�O��
�@�@�@�s���������Ĉړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ɂ��Ă͉���Ή�����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�ȏ�̂��Ƃ��w�E���A���̂Q���ɂ��āB���������肢�����B
�@�@�@�@ 1�A���ɂ��ƁA�n���̏��w�Z�ɂ��悤�������ΏۂƂȂ��Ă��邪�A���̎��w�ɒʂ��q���B
�@�@�@�@�@�@�@�͒u������ɂ���Ă���A�q��Ďx���Ƃ����ϓ_����l����Ɛ������Ɍ�����悤�Ɏv���B
�@�@ �@�@�Q�A�\�����݂̗v�����ɂ́A�w���ۈ珊����̋A��͕ی�҂��}���ɗ���悤������Ă��邪
�@�@�@�@�@�@�@�w�Z����w���ۈ珊�ւ̈ړ��ɂ��ẮA����������Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���w�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@���������A���Y�ۈ珊�̋߂��Ńo�X���~��Ċw���ۈ珊�ɒʂ��ꍇ���̋����@���Ɋ�
�@�@�@�@�@�@�@��炸�͕ی�҂�����}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�����Ȃ���Ă���B�q���̈��S
�@�@�@�@�@�@�@���l����Ɠ��R�̂��Ƃ�������Ȃ����A�n���̏��w�Z�ɂ��悤�����ɂ͑S������������
�@�@�@�@�@�@�@�z�����Ȃ���Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂��B���������āA�����ɑ��k�ɍs�������X�ɑ���
�@�@�@�@�@�@�@�̂ݎw�����āA�n���̏��w�Z�ɒʂ��ی�҂ɑ��Ă͖ٔF���Ă���̂ł͂Ƌ^���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@���悤�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���B����ɂ��Ă��A�������̂���悤�ɉ��߂�ׂ��ł���B
�@�@�@�@����̌��ŒS���ۂɊF����͑����������Ă��������A��肠��������ɂ��Ă͕ی�҂Ƒ��k��
�@�@�@�@�@�@�@��ی�҂̐ӔC�ō��]�ۈ珊�ɒʂ����Ƃ�F�߂�Ƃ̉����������܂����B�W�҂�
�@�@�@�@�@�@�@�v���ȑΉ��Ɋ��ӂ��܂��B
�@�@�@�@
�č����{������{���{�ɒ����u�N�����v�v�]���v�Ƃ�
�u�D������{�v�i�։��p�V�j���
�@�@�@�Ăт��̖{���Q�l�ɔN�����v�v�]���ɂ��ėv�_���L���Ȃ��玄�̍l�����q�ׂ�
�@�@�݂����ƂƎv���܂��B�u�N�����v�v�]���v�͂X�R�N�V�������T�~�b�g�̍ۂ̋{��N�����g��
�@�@��]��k�ł́u���ĊԂ̐V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v���ӂ���������
�@�@�ł���B���̌���{�̐����͍א���t�A�H�c���t�A�����ĂX�S�N�U���ɑ��R���t�������A
�@�@���ꂩ��܂��Ȃ��\���ɍݓ��č����H��c�����Γ��v�]�����\�A���ꂪ�u���ĊԂ�
�@�@�V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v�̈�Ƃ��Đݒu���ꂽ�K���ɘa�E����
�@�@��������ɍ̗p����A�u�N�����v�v�]���v�Ƃ��Ē�ቻ�����Ƃ����킯�ł���B�Ȍ㌇��
�@�@�����ƂȂ����N�H�Ɍ��\����Ă����B
�@�@�@���{�̐������\�ܔN�̐������A�����A�������钆�č��ɑ����������A����
�@�@����u�č��ɂ����{�����v�Ƃ����`�e�̂������̂Ȃ����ĂQ���Ԃُ̈�ȃ��J�j�Y
�@�@���ƁA���̋��͂Ȕ}�̂ł���u�N�����v�v�]���v�́A�����{�̗��j�I�]���_�Ƃ���
�@�@�ׂ������ƍ����̒��ŁA�č��Ɏ��˂����܂�ē��{�̐����V�X�e���̒��ɂ��������
�@�@���U����Ă��܂����B���́u�N�����v�v�]���v�͂O�S�N�A�։��p�V���̒����u���ۂł���
�@�@�����{�v�����\����A�u�킵�Y���v�i����Ƃ̏��т悵�̂肪�ӔC�ҏW���߂�G��
�@�@���B�j�O�U�N�~���ŏ��т悵�̂肳��́u�������ł����̎����𐢂ɍL�߂邽�߂ɏ�������
�@�@�ɂ���v�Ƃ������Ƃ���u���ė��E�N�����v�v�]���ɓ{��v�Ƃ������W���g�܂�A�����]
�@�@�_�Ƃ̐X�c�����u�����S�ʔᔻ�v�i���{�]�_�Ёj�̒��ŁA�u�O�S�N�T���R���A����
�@�@�ڍ��w�r�����̏��X�ň���̐V�����������A�Ƃ������{�̕����玄�ɍ��}�𑗂���
�@�@����C����������͡{�ۂł��Ȃ����{�[�A�����J�̓��{������������ł���p���҂͊։�
�@�@�p�V����A�m��Ȃ����������̐l�̒����ɂ͓��{�̍���J�����{�l�̍������߂��Ă���悤�ȋC�������v��
�@�@�������ƂŎ��グ�A�Ȍ�W�҂̊ԂɍL�����グ����悤�ɂȂ��������ł���B
�@�@�@�X�U�N����n�܂����u�N�����v�v�]���v�O�S�N�Ɂu���ۂł��Ȃ����{�Łv�����ɔ��\�����܂ŁA���̎��X�̓�
�@�@�t�A�����͒m���Ă����Ƃ��Ă��@��ʂ̍���c�����^�}����}���قƂ�ǒm��Ȃ��������Ƃɋ����ł���B�u����
�@�@�ł��Ȃ����{�v�̘b���A���҂̊։��p�V����������āA������J�����A���̏��ы��N�����A���i��
�@�@��A�ނ�͊։�����̘b�����ςȂ��ɂ��Ȃ������B�ނ�́u�N�����v�v�]���v�͂��A�X�����c���@�Ă���
�@�@���̗v���������̂ł��邱�Ƃ��������A����ł͓��{�̍��v�ɂȂ�Ȃ��A�A�����J�𗘂��邾���ł͂Ȃ����Ƌ`
�@�@����R�₵���B�����Ă��̌�̓W�J�́A�������̒ʂ�ł���B����ɐ�������A�}�X���f�B�A�ɗx�炳��
�@�@�����{�̗L���ҁi���{�����j���炪�����̎���i�߂Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�@�@�u�N�����v�v�]���v����͓��đo�������݂ɒ�o�������Ă������̂ŁA�ߋ��\���N�ԓ��{�Ői�߂��Ă����A
�@�@�u���v�v�̂��Ȃ�̕������č����{�̗v���𒉎��ɔ��f���Ă������̂ŁA�O�T�N����Ő��������A�V��Ж@�A����
�@�@�Ƌ֖@�A�X�����c���@���܂�������ł���B�����āA�����̒��߂�����́A��Ð��x���v�ł���B���̗�R��
�@�@��]���Ԃ�́u�P�퉻���ꂽ�������v�Ƃ����ق��͂Ȃ��A�匠���ƂƂ��Đq��Ȃ炴����̂��B����ł͕č���
�@�@�B�̕����܂������A������A�����J�̑����ł͂Ȃ����B
�@�@�@����͂Ȃ��������[�@�Ă⋳���{�@�����@�āA�h�q�����i�֘A�@�ĂȂǏd�v�@�ĂȂǐ摗�肵�A���
�@�@���x���v�@�Ă̐������}�����̂��B����͂܂��ɂO�U�N�U���Ƀu�b�V���đ哝�̂Ƃ̍Ō�̎�]��k���Z�b�g����
�@�@�Ă������߂ŁA�u�N�����v�v�]���v��Ð��x���v�̐i�W������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�����ꂽ��Ð��x���v�@�́A���I��Ô�̗}���������ł��o�������̂ŁA���̂��߂ɍ����A�Ƃ�킯�����
�@�@�Ɏ��ȕ��S�̑���𔗂���e�ƂȂ����B
�@�@�@�����͂O�Q�N�Ɋ��Ɉ�Ð��x���v�ɒ��肵�Ă���A���̂Ƃ��͂���܂ł̏���t��z�����P�p����A���S
�@�@�藦���ɑւ���ꂽ�B���̍ہA�V�O�ˈȏ�̍���҂̈�Ô�ȕ��S���́A��ʏ����҂��P���A������ݏ���
�@�@�҂��Ƃ���A����҂̎��ȕ��S�𑝂₵�Ă���B����҈ȊO�ɑ��Ă��A�O�R�N����T�����[�}���{�l�̈��
�@�@��ȕ��S������O���Ɉ����グ��ꂽ�ق��A�Z������������x�[�X����ܗ^���܂߂��N���x�[�X�ɕύX
�@�@����A�ی������S�����₳��Ă���B
�@�@�@���ꂪ�O�U�N�̈�Ð��x���v�ł͎��\�˂��玵�\�l�˂̈�ʏ����҂͂O�W�N�S������ɁA���\�ˈȏ�̌�
�@�@����ݏ����҂͂O�U�N�P�O������O���ɑ��₳��B�܂��A�u������ݏ����v�̒�`������������ꂽ���߂ɁA�e
�@�@������Ώێ҂̐����������B���̏�A�u���z�×{��x�v����������A����ҁA���𐢑���킸�A���z�Ȉ�
�@�@�Ô���������ꍇ�̎��ȕ��S���x�z�������グ��ꂽ�B
�@�@�@����ɁA�u�������҈�Ð��x�v���n�݂���O�W�N����]���͕}�{�Ƒ��Ƃ��ĕی�����Ƃ�Ă����l���܂߁A
�@�@���\�܍ˈȏ�̂��ׂĂ̍���҂��A�ی����̎x�����`�����ۂ����邱�ƂɂȂ����B�܂��A����҂������ɓ�
�@�@�@���Ă���u�×{�a���v�ł̐H�����M��͂O�U�N�\������ی��ΏۊO�ƂȂ�A�×{�a�����̂��Q�O�P�Q�N�܂łɌ�
�@�@�݂̔����ȉ��ɍ팸����邽�߁A�������@���҂͗L���V�l�z�[���Ȃǂ֓]�o�𔗂���B�[�I�Ɍ����A����
�@�@�������T�N�Ԃɂ킽���Đ��i���Ă����u��Ð��x���v�́v�Ȃ���̂̎��Ԃ́A�����A�Ƃ�킯����҂Ɏ��ȕ��S��
�@�@��𔗂邱�ƂɏI�n���Ă����̂͒N�̖ڂɂ����炩�ł���B
�@�@�@���҂̎��ȕ��S�����܂�A���I�ی��ŃJ�o�[�����͈͂�������A�k�����邱�ƂɂȂ�A���ȕ��S���J�o�[
�@�@���邽�߂̖��ԕی����o�ꂷ��B�u���ꂪ���ɏo���邱�Ƃ͖��ɂ�点��v�ƌ������Ƃł���A���I��Õی���
�@�@�k�����Ă����A����A�����́u���ȐӔC�v�ŏ����ɔ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐V����e���r�ŃA�t��
�@�@�b�N��A���R�ȂǃA�����J�n�ی���Ђɂ���Õی����i�̐�`���킪�ٗl�ȂقljߔM���Ă���̂́A��Ð�
�@�@�x���v�ɒ[�������ۂł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�����ЂƂA����ł����̂����{�́A�����������Ȃ�悤�ȉ��v���i�߂��Ă����B���ꂪ�u�V��Ж@�v�̐�
�@�@�肾�A�u��Ж@�v�Ƃ����@���͂���܂ő��݂��Ȃ������A��А��x�Ɋւ��Ă͏��@��L����Ж@�ȂǗl�X�Ȗ@��
�@�@������ł����A��������ɂ܂Ƃ߂ĐV�����u��Ж@�v���A�����Ă��̖ڋʂƈʒu�Â����Ă����̂��A����
�@�@�J���狭���v�]����Ă����A�u�O�����Ή��̍����v�i�������z�������������j�̉��ւł���B���ꂪ���ւ����Ƃ�
�@�@���Ȃ邩�A�Ђ炽�������ΊO����Ƃ����z�̔��������������邱�ƂȂ��ɁA���Њ����g���Ă��Ƃ����₷�����{
�@�@��Ƃ��P���ɂ����߂邱�ƂɂȂ�B������u�O���ɂ����{��Ƃ̏�����v�̉��ւł���B
�@�@�@�V��Ж@�͂O�S�N�P�Q���ɗv�j�Ă����\����O�T�N�ʏ퍑��ɖ@�Ă���o����A�O�U�N����{�H����邱�Ƃ�
�@�@�Ȃ��Ă����A�����̂قƂ�ǂ��m��Ȃ��ԂɁA�܂��ɊԈꔯ����̔N���C�u�h�A�̎������������A�G�ΓI��Ɣ���
�@�@�ւ̍����I�S���ɂ킩�ɕ����A�Ƃ��ɁA��������d�|����ꂽ���{��Ƃɂ͖@�I�ɕۏ��ꂽ�h�q�ق�
�@�@��ǖ������ƂɊ�@�������������B�����}�̓}��(�X�����c���Ŋ����A���̏��ы��N�c���⏬�i�c��)
�@�@������u�O�����މ��̍����v���ւɑ��锽�Θ_�����o���A��o�������O�Ɉ�N�ԓ�������邱�ƂɂȂ����B��
�@�@��Ȋ댯�Ȃ��Ƃ����蔭�Ԑ��O���������Ƃɂ͜ɑR�Ƃ������ł��邪�A���̎����}(�X�����c���Ŋ���
�@�@���A���̏��ы��N�c���⏬�i�c���j�c�������̓����ɂ��A��N�ԓ�������邱�ƂƂȂ�A���{�̊�Ƃ��h
�@�@�q����u���邱�Ƃ��o�����̂ł���B
�@�@�@����ɂ��Ă��A�Ȃ��������ݓ��{�̑��Ƃ��������ɂ���킽���ɂЂƂ����u�O�����Ή��̍����v�̉��ւȂ�
�@�@�Ƃ������Ƃ��i�߂��Ă����̂��B�ӊO�ɂ����Ƃ͉�Ж@�����ł͂Ȃ��̂��A�ӊO�ɂ���v��ɂ��Ċ�ƍ�
�@�@����v�����������Ɍ������ꂷ����j����߂��A���̐V����������v����ł́A�]���̓��{�I�ȑΓ�����
�@�@�͓���Ȃ�A�G�Ύ��������܂߂��z������������̊�ƍĕ҂̎嗬�ƂȂ�Ƃ����Ă���B����ɁA�Ő��ʂł�
�@�@�O���ɂ����{��Ɣ������㉟�����邽�߂ɐŐ����v���O�S�N���猟������Ă���Ƃ����A����������A�̉��v��
�@�@���̂��ׂĂ̓����̎i�ߓ��ƂȂ��Ă���̂��u�Γ�������c�i�i�h�b�j�v�c���͓��t�����厖�A���c���͌o�����S
�@�@����b�A�����Ă��̉����g�D�ɂ͂P�R�l�̓��{�l�̑��ɁA�ݓ��č����H��c���̊�����č��،���Ђ̖����A
�@�@��l�̊O���l�ٌ�m���܂ނP�O�l�̊O���l���u�O���l���ʈψ��Ƃ��Ė���A�˂Ă��邻���ł���B
�@�@�@�����āA���̑Γ�������c��啔��O�S�N�A�u�Γ��������i�v���O�����y�ю��{�v�Ƃ��������̒��ŁA
�@�@�u�������z���������E�������e�Ղɍs����悤�Ɂv�Ƃ����ړI�Łu�O�����Ή��̍����v�̉��ւ��ƍ�����v��
�@�@�̎������������A�Ő���̗D���[�u�ȂǂƂ��������Ƃ���̗�Ƃ��Ă������Ă��B����ȊO�ɂ��A�ߔN�A���{��
�@�@�傫���h�邪���Ă���B������\�����v�̑������A���́u�Γ��������i�v���O�����v�̈���������Ƃ����L��
�@�@��Ă���B���͏���̌����\�����v�́A�����̂��߂ł͂Ȃ��A�O���ɂ����{��Ƃ̔����𑣐i���邽�߂�
�@�@�u���{�����v�����������đg�D�I�ɐi�߂��Ă����̂ł���B
�@�@�@04�N�ł́u�Γ������C�j�V�A�`�u�v�̕��ɂ́o�č����{�́A���{�ɂ�����l�����Ԃ̕ω��ɂ��A����A
�@�@����y�ш�ÃT�[�r�X����ɂ����铊�����d�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E�����B�����Ă����̕���ɂ����ĕč�
�@�@��Ƃ����̓��ӕ���������l�X�Ȏ��̍����T�[�r�X��ł��邱�ƁA�܂����������V���ȃT�[�r�X�̒�
�@�@�����{�̏���җ��v�̑���Ɏ�������̂ł��邱�Ƃ��w�E�����B�č����{�͂����̕���ɂ����铊���𑣐i��
�@�@�邽�߁A���{���{�ɑ��A���Y����ɂ����铊�����\�Ƃ��邽�߂̋K�����v��v�������B�p���邳��Ă���B
�@�@�@�����ăA�����J�̓��{�����͂܂��܂������X�����c���Łu�ȈՕی��v����Ð��x���v�Łu��Õی��v�����̂�
�@�@�炢�͋���A��ÃT�[�r�X�A�u���ρv�ւƉ��X�Ƒ��������ł���B���������N�����̕č��ɂ����{�������~��
�@�@��̂��A�����Ȃ鍑���ȊO�ɂȂ��ł͂Ȃ����A�ڊo�߂���{�B
�@�@�@���ċK�����v�y�ы�������C�j�V�A�`�u�Ɋ�Â����{���{�ւ̕č����{�v�]���̖`���ɂ�
�@�@�@�O�T�N�Ł@�@�č��́A������b�̓��{�o�ω��v�Ɍ������p���I���g�݂�����������B�����̎��g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͓��{�𐬒��O���ɏ悹�A��葽���̖f�Ջy�ѓ����@���n�o�����A�č��͂܂��A�����ƍ\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����͏����ʓI�ɒ��Ă����K�����v�E���ԊJ�����i�{���ƁA�\�����v���ʐ��i�{���̂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g�݂�]������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̗v�]���ɐ��荞�܂ꂽ�́A��v�����A���f�I����ɂ�����A���v�ɏd�_��u���A�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ϐ������x�����A���{�̎s��J������肢�������������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B����ɕč��͓d�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A�m�I���Y���A��ÁA�_�ƁA���c���A��������ȂǁA���������v�̎�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���d�v�ł���ƈʒu�Â�������̖��Ɉ����������ɏœ_�ĂĂ���B
�@�@�@�O�U�N�Ł@�@�č��́A���{�̌o�ω��v�𐄐i����Ƃ�������������b�̌��ӂ����}����B�V�����@��݁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����𑣂��A��茒�S�ȃr�W�l�X�������o�����v�́A���ꂩ��扽�N�ɂ��n����{�̌o�ϐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɗ��͂��ێ����x����ł��낤�B�܂��A�č��͓��{�����̉��v���i�҂̎��g�݂�S�����v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���㐔�����A���N�ɂ킽��A�����̊��������������邱�Ƃ����҂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̕č�����̒́A�d�C�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A��Ë@��A���i�A���Z�T�[�r�X�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɩ@���T�[�r�X�A�������A�_�ƁA���Ђ̖��c���A���ʁA��������ƍL�͈͂ȕ���ɂ����āA�p
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ��v�̐i�W��}�邱�Ƃ̏d�v�����������Ă�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԕ���i�č��́j�̑�\�����C�j�V�A�`�u�֒���I�ɎQ�����A���m������Ă���邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŁA��X�̍�ƂɕK�v�ȑ����̏��邱�Ƃ��o�����A�����͂��̂悤�ȎQ���̋@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���傷�邱�Ƃ����҂���B
�@
�@�@�@�ȏオ�����F����ɓ`���������̖{�̓��e�̈ꕔ�ł��B�������ł��傤���A�������������m��Ȃ��Ԃɋ�����
�@�@�����Ƃ��i�s���Ă��܂��A���̂��Ƃ����{�̏������ǂ��ς��Ă����̂����̕n��ȓ��ł͑z�������܂���
�@�@�̖{��ǂ�ł���Ɖ�������傫�ȓ{�肪�킢�Ă��ĂȂ�܂���B
�@�@�@���̔N�����v�v�]���͓��đo�����o�������Ă���A���R���{���o���Ă��܂����A����Ƃ��Ď������Ă��Ȃ�
�@�@�����ł��B��Ȃ�����ł͂���܂��A�ǂ����F�l�A��x�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�Łu�N�����v�v�]���v
�@�@�Ȃ���̂������Ŋm���߂Ă��������B�����Ǝ��̌����Ă��邱�Ƃ��������Ă���������Ǝv���܂��B
�@�@�@�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�@http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@
�X�����c���͓��{�����ɂƂ��Đ��������v�Ȃ̂�
�@�@����A����H.D���玟�̗l�Ȃ��莆���܂����B
�@�@�O���A�M�Z�ɂ͐V���ȖڕW�Ɍ������čĂъ������n�߂�ꂽ���ƁA���ɂ����c�Ɋ����܂���B�n��ɍ�
�@������������ʂ��ĊC��s������肢�������O�i�����Ă������������܂��悤���҂��Ă���܂��B
�@�@���Đ���A�M�Z�̃z�[���y�[�W�ŗX�����c�������グ�Ă���̂�q�����āA���ɓ������ӌ��ŁA
�@���X�Ȃ���M�Z�̓��@�͂̐[���Ɋ��S�������܂����B�i�����j
�@�@�X���ɂ��Ă͌������܂������A������������v�̖��̂��Ƃō��v�ɔ�����悤�Ȑ������������邱
�@�Ƃ����͂��߂�ւ肽���҂ł��B
�@�@�����̐}���͐挎���s����܂������̂ł����A���݂̎��̑z���Ɠ����ł��̂Ő����x���ڂƂƂ�����
�@�����������肢�����܂��B�ƌ������ƂŁA���̂悤�Ȗ{�𑗂��Ă��������܂����B
�u�D������{�v�i�։��p�V�j
�@�@�ڂ���Ƃ͂��̂��ƂŁA���̂���A�����̍����ɂƂĂ̂킩��ɂ��������X�����c���A�������̋^
�@��_�����炩�ɂȂ�܂����B�����āA���ы��N�c�������ߔ��Δh�̋c���͂Ȃ����̂悤�ɋ��d�ɔ���
�@��̂����A���v���Ȃ��}���̂��A�X�����c����č��ƂȂ��b������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ���������
�@�����̖{�����炩�ɂ��Ă��܂��B�F����ɂ��̖{�̂��ׂĂɖڂ�ʂ��Ă������������Ǝv���܂����A����
�@�ł͗v�_���L���Ă݂����Ƒz���܂��B
�@�@���{��卬���Ɋׂꂽ�X�����c���@�A���{�̏��������ɂ킽��ł��낤�A�l�X�ȉЍ����c�����Q�O�O�T
�@�N�ő�̐����ۑ�́A���ׂď����̎v�f�����Ɍ��������B���̔N�̉ߔ��̎��ԂƃG�l���M�[����
�@����Ƃ�������X�����c���Ƃ́A���ǂȂ����̂��B
�@�@���̗X�����c�����ɂ́A�Ō�܂ł����₯�ɂ͂قƂ�nj���Ȃ��������ʂ�����B���{�̍\��
�@���v�̖{�ہA���邢�͐����Ə���Y�̌l�I���O�A�ȂǂƎ�肴������Ă������̖��̔w���
�@�͕č�����̎��X�Ȉ��͂Ƃ���������̈��q���B����Ă����̂ł���B
�@�@1995�N11���ɕč����{������{���{�ɒ��ꂽ�u�N�����v�v�]���v�ɂ́A�ȈՕی��Ɋւ��Ď���
�@�悤�ȋL�q������B
�@�@�o�č����{�́A���{���ȉ��̂悤�ȋK���ɘa�y�ы������i�̂��߂̑[�u������ׂ��ł���ƐM����B
�@�E�E�E�E�E�X���Ȃ̂悤�Ȑ��{�@�ւ��A���ԉ�Ђƒ��ڋ�������ی��Ɩ��Ɍg��邱�Ƃ��֎~����B�p�Ƃ�
�@��B�@�h�֎~����Ƃ͓��������̂��̂ł͂Ȃ����B�h�@
�@�@�����Ă���ȗ��č����{�͊ȈՕی��̔p�~��v���������A
�@�@1999�N�̗v�]���ł́@�o�č��͓��{�ɑ����ԕی���Ђ����Ă��鏤�i�Ƌ�������ȈՕی�
�@�i�J���|�j���܂ސ��{�y�я������ی����x���g�傷��l�������ׂĒ��~���A�����̐��x�����ł܂���
�@�p�����ׂ����ǂ����������邱�Ƃ��������߂�B�p�܂�č��͊��ƂƂ��Ă̊ȕۂ�p�~���Ė��ԉ�Ђ�
�@�J������Ɨv�����Ă���̂ł���B
�@�@���{�̖��ԕی��s��͉ߋ�20�N�ȏ�ɂ킽���ĕč��ɂ������W����Ă����A���̗��j��U���
�@������ʼn��߂��l����A�X�����c���̖{���͂P�Q�O���~�ɂ̂ڂ銯�c�ی��̎s��J����肾�ƌ���
�@���Ƃ��킩��B�������������c�����������ł͍����ő��̓��{�����̎O�{�߂��K�͂̋���Ȗ��ԕ�
�@����Ђ��a�����邾���̂��Ƃ��A�����A�č����]��ł���̂͂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�č��͖��c��
�@��̊ȈՕی��Ƃ��̎��Y�P�Q�O���~���ǂ����傤�ƍl���Ă���̂��B
�@�@2004�N�̋K�����v�v�]���ɂ͂��̋L�q��v��ƁA�ȕۂ̐��{�ۗL���������S�Ɏs��֔��p��
�@���A�u���{�ۏ����邩�̂悤�ȔF���������ɐ����Ȃ��悤�\���ȕ�����v��点��B�܂萭�{�̊֗^
�@�����S�ɒf���点�����Ȗ��ԉ�ЂƂȂ����ȕۂɑ��ẮA�O���n�ی���ЂƊ��S�ɑΓ��ȋ�����
�@����v�����Ă����B�����Ċȕۂ̏��NJ������Ȃ�����Z���Ɉڊǂ������̗������茟���������A
�@�\���y���V�[�}�[�W���Ȃǂ̌��\���`���Â���v�������Ȃǂ̊č���������B
�@����ɁA�ȕۂ�Ƌ֖@�Ȃǂ̓K�p�ΏۂƂ��A�u���̎s��x�z�͂��s�g���Č���c�Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��悤�v
�@��������ψ���ɒ���������ƌ��������Ƃ��L�q����Ă���B
�@�@�v����ɕč��ɂƂ��Ė��c���̓S�[���ł͂Ȃ��ȕۂ���̉������A�ŏI�I�ɂ͕����A��́A�o�c�j�]
�@�ɒǂ����݁A�l���`��c�Ə��n�ȂǗl�X�Ȏ�i��M���āA�ȕۂ��i���Ă���P�Q�O���~�ɂ̂ڂ鎑�Y��
�@�č��n���ԕی���Ђɋz�������邱�Ƃ��ŏI�I�Ȃ˂炢�Ȃ̂ł���B
�@�@�ȕۂ͏����ł��邱�ƂƁA���R���Ƃ����ȈՂȉ����葱������F�Ƃ��Ă���B���X�ȈՐ����ی����x
�@�́A���Ԃ̐����ی��ɉ����ł��Ȃ��Ꮚ���҂ɂ��ی��Ƃ����Z�t�e�B�l�b�g����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�吳�ܔN�ɑn�݂�����̎҂Ńr�W�l�X�ƌ��������{�Љ�̈��艻���u�ł���B
�@���ꂪ�č��l�ɂ͒P�Ȃ�s��Ƃ��Ă����ڂ�Ȃ��B���艻���u���͂�������̓��{�Љ�ǂ��Ȃ낤��
�@��؊S���Ȃ��̂ł���B�u�����疯�֎����𗬂��v�u���ɏo���邱�Ƃ͖��Łv�ƌ����Ƃ��̖���
�@���{�����̖��ł͂Ȃ��A���{�����̍s�����ɐӔC��Ȃ��č����ԕی���Ђ́u���v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�������ł��傤���A�����͂��K�ߑ����̍���c�����X�����c���ɂ��āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɍ��́A
�@�����̗��v�ɂȂ���̂����Ȃ������ɐ����ӔC���ʂ����Ȃ��̂��A���킩�蒸�����ł��傤���A�{��
�@�͗X�����c���ɍŌ�܂Ŕ������A�^�̍��v����낤�Ƃ��������}�̗E�C����c���B������X������
�@�������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�����ł͂Ȃ������̂��B�ŋߎ��͂��Â������v���Đ���܂���A����
�@�Ђ�����ɉ��̂��߂炢���Ȃ�������ӐM���c���Ɏ^���������A�䂪���̂U�l�̗^�}�c���́A�ǂ�
�@�قnj����ɑ��Đ����ӔC���ʂ������̂ł��傤�B�ނ�͕č��́u�N�����v�v�]���v�m���Ă����̂ł���
�@�����B�@�������̂��Ƃ͐����Ă݂����҂ł��B
�@
�@
�@�@�@�@�@�܂��A���������Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�C�T�쏬�w�Z�ɒʂ��Ă��鎙���̂��߂̊w���ۈ�ƌ������ƁB�T�쏬�w�����D�悷��ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������̒n��̊w���ۈ�����������ł���B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�A�T��n��ɏZ��ł��Ȃ���A���w���ɂ��悤�ƒ�ɑ���z�����S���Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�R�A���}�ɂ��āA���ɑ���ɂ��Ă͏��ɂ���ċ`���Â����Ă��邻���ł���ƌ������ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�A����A���Y�����̑��ɁA�T�쏬�w�Z�ɒʂ��q���B�Q��������I�[�o�[�Ƃ������Ƃœ����ł��Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ł����A���q����Ƃ��Ă̎s���ɈՂ����{��Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�����ŁA�w���ۈ�ɂ��ĊȒP�ɒ��ׂĂ݂܂��ƁB
�@�@�@���������@�ł̒�`�H�i�w���ۈ�Ƃ�������g�p���Ă��Ȃ��B�j
�@�@�@�@�@�u���̖@���ŁA���ی㎙�����S�琬���ƂƂ́A���w�Z�ɏA�w���Ă��邨���ނ�10��
�@�@�@�@�@�����̎����ł��āA���̕ی�҂��J�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA����
�@�@�@�@�@�Œ�߂��ɏ]���A���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p���ēK�ȗV
�@�@�@�@�@�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}�鎖�Ƃ������B�v
�@�@�@�@�@�i��U���̂Q��V���j
�@�@�@�����E���T�Ȃǂɂ���`
�@�@�@�@�@�u�e�������Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A�ƒ�
�@�@�@�@�@�ɂ����ۈ���s���{�݁E���ƁB�v
�@�@�@�@�@�u���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w�����C���ی��莞�ԕۈ炷�邱
�@�@�@�@�@�ƁB�v
�@�@�@�w���ۈ�̉^���c�̂ɂ���`
�@�@�@�@�@�u�E�E�E�E�E�������ƒ���q�E���q�ƒ�̏��w���̎q�ǂ������̖����̕��ی�
�@�@�@�@�@�i�w�Z�x�Ɠ��͈���j�̐��������{�݂��w���ۈ�ł��B�w���ۈ�Ɏq�ǂ�����
�@�@�@�@�@���������Ĉ��S���Đ��������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ���āA�e���d���𑱂����
�@�@�@�@�@�܂��B�w���ۈ�ɂ͐e�̓��������ƉƑ��̐��������Ƃ�������������܂��B�v
�@�@ �@ �ȏ�̂悤�ɁA�w���ۈ�ɂ��Ē�`�Â����Ă��܂����A�n���̊w�Z�ɒʂ���������
�@�@�@�ۂƂ����悤�Ȃ��Ƃ͑S���ӂ���Ă��Ȃ����A�܂��厖�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐e��
�@�@�@�����Ă��ĕ��ی�̕ۈ炪�\���ۏႳ��Ȃ����w�Z��w�N�����ɑ��A���̕ی�҂��J
�@�@�@�����ɂ�蒋�ԉƒ�ɂ��Ȃ����̂ɁA���Ƃ̏I����Ɏ��������{�ݓ��̎{�݂𗘗p����
�@�@�@�K�ȗV�ыy�ѐ����̏��^���āA���̌��S�Ȉ琬��}��B
�@�@�@�Ƃ������ƂŁA�n���̏��w�Z�ɒʂ������Ɍ��肵���l�Ȓ�`�Â����S���Ȃ��ꌾ���܂���B
�@�@�@�s�̒S���҂Ƃ̂��Ƃɂ��Ă̋��c�̒��ŁA
�@�@�@�@���}�ɂ��āA���ɂ�茈�߂��Ă���Ƃ��������͊ԈႢ�ŁA��W�v���ł́A�u�w��
�@�@�@�̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��Č}�����K�v�ł��B�܂��y�j����ċx�ݓ��̒����x�Ɗ��Ԓ�
�@�@�@�̊w���ۈ�ɂ��Ă�����}���������Ƃ��܂��B�v�L����Ă���A���ł́u�ۈ�I
�@�@�@����̎����̋A��ɂ��ẮA�����Ƃ��ĕی�҂��}���邱�ƂƂ��܂��v�Ƃ̋L�ڂ���
�@�@�@��A����ɂ��Ă͓y�j���y�ђ����x�Ɠ��ȊO�͓��ɂӂ���Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@�@�@�@����ɁA�S���҂̕������Ƃ��R�O���̓��̂�ł����Ă����̊ԂɎ��̂ł���������Ύs
�@�@�@�̐ӔC����ꂩ�˂Ȃ����Ԃ��l���A�ی�҂�[���������߂Ɏv�킸���������o������
�@�@�@�ł͂Ȃ����B�����Ă������Ƃł͂Ȃ����A����͂���Ƃ��āA����Ȃ��Ƃ��̐e�̐ӔC�Ƃ�
�@�@�@�������Ƃ��������Ƃ��đΉ����ׂ��ł͂Ȃ����
�@�@�@�@�܂��s�O�̏��w�Z�ɒʂ������ɂď��ł͊C��s�w���ۈ����R���Ɂu�w���ۈ�̑�
�@�@�@�ۂƂȂ鎙���́@�i�P�j�s���̏��w�Z�ɏA�w���Ă�����w�N�����R�w�N�܂ł̎�����
�@�@�@�ی�҂��J�����Œ��ԉƒ�ɂ��Ȃ����́B�i�Q�j�O���Ɍf������̂̂ق��A�s��������
�@�@�@�K�v�ƔF�߂����́B�v�ƂȂ��Ă���B����̃P�[�X��(�Q)�ɑ�������̂ł͂Ȃ�����
�@�@�@�v���邪�ǂ��葱������������̂��Ƃ������Ƃ��낪�s���ł���A����������Ă��Ȃ��B
�@�@�@���̓_�ɂ��Ă͕ی�҂̗���ɗ��������J�ȑΉ����K�v�ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�@���e���������ł���ȂǕی�҂��s�݂ł���w����ΏۂƂ������Ƃ��炷��Ό}���͂Ƃ�
�@�@�@�����A����ɂ��Ă͓��R�d�����ł�����A�s�������悤�ɃT�|�[�g�Z���^�[�𗊂�Ȃ�
�@�@�@��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����A�o�ϓI�Ȗʂ�����A����̃P�[�X�̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�ی�҂�
�@�@�@�ӔC�͈̔͂őΉ����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɋT��̏ꍇ����Q�O���Z�O��
�@�@�@�s���������Ĉړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ɂ��Ă͉���Ή�����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�ȏ�̂��Ƃ��w�E���A���̂Q���ɂ��āB���������肢�����B
�@�@�@�@ 1�A���ɂ��ƁA�n���̏��w�Z�ɂ��悤�������ΏۂƂȂ��Ă��邪�A���̎��w�ɒʂ��q���B
�@�@�@�@�@�@�@�͒u������ɂ���Ă���A�q��Ďx���Ƃ����ϓ_����l����Ɛ������Ɍ�����悤�Ɏv���B
�@�@ �@�@�Q�A�\�����݂̗v�����ɂ́A�w���ۈ珊����̋A��͕ی�҂��}���ɗ���悤������Ă��邪
�@�@�@�@�@�@�@�w�Z����w���ۈ珊�ւ̈ړ��ɂ��ẮA����������Ă��Ȃ��B�Ƃ��낪�A���w�ɂ���
�@�@�@�@�@�@�@���������A���Y�ۈ珊�̋߂��Ńo�X���~��Ċw���ۈ珊�ɒʂ��ꍇ���̋����@���Ɋ�
�@�@�@�@�@�@�@��炸�͕ی�҂�����}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�����Ȃ���Ă���B�q���̈��S
�@�@�@�@�@�@�@���l����Ɠ��R�̂��Ƃ�������Ȃ����A�n���̏��w�Z�ɂ��悤�����ɂ͑S������������
�@�@�@�@�@�@�@�z�����Ȃ���Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂��B���������āA�����ɑ��k�ɍs�������X�ɑ���
�@�@�@�@�@�@�@�̂ݎw�����āA�n���̏��w�Z�ɒʂ��ی�҂ɑ��Ă͖ٔF���Ă���̂ł͂Ƌ^���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@���悤�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���B����ɂ��Ă��A�������̂���悤�ɉ��߂�ׂ��ł���B
�@�@�@�@����̌��ŒS���ۂɊF����͑����������Ă��������A��肠��������ɂ��Ă͕ی�҂Ƒ��k��
�@�@�@�@�@�@�@��ی�҂̐ӔC�ō��]�ۈ珊�ɒʂ����Ƃ�F�߂�Ƃ̉����������܂����B�W�҂�
�@�@�@�@�@�@�@�v���ȑΉ��Ɋ��ӂ��܂��B
�@�@�@�@
�č����{������{���{�ɒ����u�N�����v�v�]���v�Ƃ�
�u�D������{�v�i�։��p�V�j���
�@�@�@�Ăт��̖{���Q�l�ɔN�����v�v�]���ɂ��ėv�_���L���Ȃ��玄�̍l�����q�ׂ�
�@�@�݂����ƂƎv���܂��B�u�N�����v�v�]���v�͂X�R�N�V�������T�~�b�g�̍ۂ̋{��N�����g��
�@�@��]��k�ł́u���ĊԂ̐V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v���ӂ���������
�@�@�ł���B���̌���{�̐����͍א���t�A�H�c���t�A�����ĂX�S�N�U���ɑ��R���t�������A
�@�@���ꂩ��܂��Ȃ��\���ɍݓ��č����H��c�����Γ��v�]�����\�A���ꂪ�u���ĊԂ�
�@�@�V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v�̈�Ƃ��Đݒu���ꂽ�K���ɘa�E����
�@�@��������ɍ̗p����A�u�N�����v�v�]���v�Ƃ��Ē�ቻ�����Ƃ����킯�ł���B�Ȍ㌇��
�@�@�����ƂȂ����N�H�Ɍ��\����Ă����B
�@�@�@���{�̐������\�ܔN�̐������A�����A�������钆�č��ɑ����������A����
�@�@����u�č��ɂ����{�����v�Ƃ����`�e�̂������̂Ȃ����ĂQ���Ԃُ̈�ȃ��J�j�Y
�@�@���ƁA���̋��͂Ȕ}�̂ł���u�N�����v�v�]���v�́A�����{�̗��j�I�]���_�Ƃ���
�@�@�ׂ������ƍ����̒��ŁA�č��Ɏ��˂����܂�ē��{�̐����V�X�e���̒��ɂ��������
�@�@���U����Ă��܂����B���́u�N�����v�v�]���v�͂O�S�N�A�։��p�V���̒����u���ۂł���
�@�@�����{�v�����\����A�u�킵�Y���v�i����Ƃ̏��т悵�̂肪�ӔC�ҏW���߂�G��
�@�@���B�j�O�U�N�~���ŏ��т悵�̂肳��́u�������ł����̎����𐢂ɍL�߂邽�߂ɏ�������
�@�@�ɂ���v�Ƃ������Ƃ���u���ė��E�N�����v�v�]���ɓ{��v�Ƃ������W���g�܂�A�����]
�@�@�_�Ƃ̐X�c�����u�����S�ʔᔻ�v�i���{�]�_�Ёj�̒��ŁA�u�O�S�N�T���R���A����
�@�@�ڍ��w�r�����̏��X�ň���̐V�����������A�Ƃ������{�̕����玄�ɍ��}�𑗂���
�@�@����C����������͡{�ۂł��Ȃ����{�[�A�����J�̓��{������������ł���p���҂͊։�
�@�@�p�V����A�m��Ȃ����������̐l�̒����ɂ͓��{�̍���J�����{�l�̍������߂��Ă���悤�ȋC�������v��
�@�@�������ƂŎ��グ�A�Ȍ�W�҂̊ԂɍL�����グ����悤�ɂȂ��������ł���B
�@�@�@�X�U�N����n�܂����u�N�����v�v�]���v�O�S�N�Ɂu���ۂł��Ȃ����{�Łv�����ɔ��\�����܂ŁA���̎��X�̓�
�@�@�t�A�����͒m���Ă����Ƃ��Ă��@��ʂ̍���c�����^�}����}���قƂ�ǒm��Ȃ��������Ƃɋ����ł���B�u����
�@�@�ł��Ȃ����{�v�̘b���A���҂̊։��p�V����������āA������J�����A���̏��ы��N�����A���i��
�@�@��A�ނ�͊։�����̘b�����ςȂ��ɂ��Ȃ������B�ނ�́u�N�����v�v�]���v�͂��A�X�����c���@�Ă���
�@�@���̗v���������̂ł��邱�Ƃ��������A����ł͓��{�̍��v�ɂȂ�Ȃ��A�A�����J�𗘂��邾���ł͂Ȃ����Ƌ`
�@�@����R�₵���B�����Ă��̌�̓W�J�́A�������̒ʂ�ł���B����ɐ�������A�}�X���f�B�A�ɗx�炳��
�@�@�����{�̗L���ҁi���{�����j���炪�����̎���i�߂Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�@�@�u�N�����v�v�]���v����͓��đo�������݂ɒ�o�������Ă������̂ŁA�ߋ��\���N�ԓ��{�Ői�߂��Ă����A
�@�@�u���v�v�̂��Ȃ�̕������č����{�̗v���𒉎��ɔ��f���Ă������̂ŁA�O�T�N����Ő��������A�V��Ж@�A����
�@�@�Ƌ֖@�A�X�����c���@���܂�������ł���B�����āA�����̒��߂�����́A��Ð��x���v�ł���B���̗�R��
�@�@��]���Ԃ�́u�P�퉻���ꂽ�������v�Ƃ����ق��͂Ȃ��A�匠���ƂƂ��Đq��Ȃ炴����̂��B����ł͕č���
�@�@�B�̕����܂������A������A�����J�̑����ł͂Ȃ����B
�@�@�@����͂Ȃ��������[�@�Ă⋳���{�@�����@�āA�h�q�����i�֘A�@�ĂȂǏd�v�@�ĂȂǐ摗�肵�A���
�@�@���x���v�@�Ă̐������}�����̂��B����͂܂��ɂO�U�N�U���Ƀu�b�V���đ哝�̂Ƃ̍Ō�̎�]��k���Z�b�g����
�@�@�Ă������߂ŁA�u�N�����v�v�]���v��Ð��x���v�̐i�W������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�����ꂽ��Ð��x���v�@�́A���I��Ô�̗}���������ł��o�������̂ŁA���̂��߂ɍ����A�Ƃ�킯�����
�@�@�Ɏ��ȕ��S�̑���𔗂���e�ƂȂ����B
�@�@�@�����͂O�Q�N�Ɋ��Ɉ�Ð��x���v�ɒ��肵�Ă���A���̂Ƃ��͂���܂ł̏���t��z�����P�p����A���S
�@�@�藦���ɑւ���ꂽ�B���̍ہA�V�O�ˈȏ�̍���҂̈�Ô�ȕ��S���́A��ʏ����҂��P���A������ݏ���
�@�@�҂��Ƃ���A����҂̎��ȕ��S�𑝂₵�Ă���B����҈ȊO�ɑ��Ă��A�O�R�N����T�����[�}���{�l�̈��
�@�@��ȕ��S������O���Ɉ����グ��ꂽ�ق��A�Z������������x�[�X����ܗ^���܂߂��N���x�[�X�ɕύX
�@�@����A�ی������S�����₳��Ă���B
�@�@�@���ꂪ�O�U�N�̈�Ð��x���v�ł͎��\�˂��玵�\�l�˂̈�ʏ����҂͂O�W�N�S������ɁA���\�ˈȏ�̌�
�@�@����ݏ����҂͂O�U�N�P�O������O���ɑ��₳��B�܂��A�u������ݏ����v�̒�`������������ꂽ���߂ɁA�e
�@�@������Ώێ҂̐����������B���̏�A�u���z�×{��x�v����������A����ҁA���𐢑���킸�A���z�Ȉ�
�@�@�Ô���������ꍇ�̎��ȕ��S���x�z�������グ��ꂽ�B
�@�@�@����ɁA�u�������҈�Ð��x�v���n�݂���O�W�N����]���͕}�{�Ƒ��Ƃ��ĕی�����Ƃ�Ă����l���܂߁A
�@�@���\�܍ˈȏ�̂��ׂĂ̍���҂��A�ی����̎x�����`�����ۂ����邱�ƂɂȂ����B�܂��A����҂������ɓ�
�@�@�@���Ă���u�×{�a���v�ł̐H�����M��͂O�U�N�\������ی��ΏۊO�ƂȂ�A�×{�a�����̂��Q�O�P�Q�N�܂łɌ�
�@�@�݂̔����ȉ��ɍ팸����邽�߁A�������@���҂͗L���V�l�z�[���Ȃǂ֓]�o�𔗂���B�[�I�Ɍ����A����
�@�@�������T�N�Ԃɂ킽���Đ��i���Ă����u��Ð��x���v�́v�Ȃ���̂̎��Ԃ́A�����A�Ƃ�킯����҂Ɏ��ȕ��S��
�@�@��𔗂邱�ƂɏI�n���Ă����̂͒N�̖ڂɂ����炩�ł���B
�@�@�@���҂̎��ȕ��S�����܂�A���I�ی��ŃJ�o�[�����͈͂�������A�k�����邱�ƂɂȂ�A���ȕ��S���J�o�[
�@�@���邽�߂̖��ԕی����o�ꂷ��B�u���ꂪ���ɏo���邱�Ƃ͖��ɂ�点��v�ƌ������Ƃł���A���I��Õی���
�@�@�k�����Ă����A����A�����́u���ȐӔC�v�ŏ����ɔ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐V����e���r�ŃA�t��
�@�@�b�N��A���R�ȂǃA�����J�n�ی���Ђɂ���Õی����i�̐�`���킪�ٗl�ȂقljߔM���Ă���̂́A��Ð�
�@�@�x���v�ɒ[�������ۂł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�����ЂƂA����ł����̂����{�́A�����������Ȃ�悤�ȉ��v���i�߂��Ă����B���ꂪ�u�V��Ж@�v�̐�
�@�@�肾�A�u��Ж@�v�Ƃ����@���͂���܂ő��݂��Ȃ������A��А��x�Ɋւ��Ă͏��@��L����Ж@�ȂǗl�X�Ȗ@��
�@�@������ł����A��������ɂ܂Ƃ߂ĐV�����u��Ж@�v���A�����Ă��̖ڋʂƈʒu�Â����Ă����̂��A����
�@�@�J���狭���v�]����Ă����A�u�O�����Ή��̍����v�i�������z�������������j�̉��ւł���B���ꂪ���ւ����Ƃ�
�@�@���Ȃ邩�A�Ђ炽�������ΊO����Ƃ����z�̔��������������邱�ƂȂ��ɁA���Њ����g���Ă��Ƃ����₷�����{
�@�@��Ƃ��P���ɂ����߂邱�ƂɂȂ�B������u�O���ɂ����{��Ƃ̏�����v�̉��ւł���B
�@�@�@�V��Ж@�͂O�S�N�P�Q���ɗv�j�Ă����\����O�T�N�ʏ퍑��ɖ@�Ă���o����A�O�U�N����{�H����邱�Ƃ�
�@�@�Ȃ��Ă����A�����̂قƂ�ǂ��m��Ȃ��ԂɁA�܂��ɊԈꔯ����̔N���C�u�h�A�̎������������A�G�ΓI��Ɣ���
�@�@�ւ̍����I�S���ɂ킩�ɕ����A�Ƃ��ɁA��������d�|����ꂽ���{��Ƃɂ͖@�I�ɕۏ��ꂽ�h�q�ق�
�@�@��ǖ������ƂɊ�@�������������B�����}�̓}��(�X�����c���Ŋ����A���̏��ы��N�c���⏬�i�c��)
�@�@������u�O�����މ��̍����v���ւɑ��锽�Θ_�����o���A��o�������O�Ɉ�N�ԓ�������邱�ƂɂȂ����B��
�@�@��Ȋ댯�Ȃ��Ƃ����蔭�Ԑ��O���������Ƃɂ͜ɑR�Ƃ������ł��邪�A���̎����}(�X�����c���Ŋ���
�@�@���A���̏��ы��N�c���⏬�i�c���j�c�������̓����ɂ��A��N�ԓ�������邱�ƂƂȂ�A���{�̊�Ƃ��h
�@�@�q����u���邱�Ƃ��o�����̂ł���B
�@�@�@����ɂ��Ă��A�Ȃ��������ݓ��{�̑��Ƃ��������ɂ���킽���ɂЂƂ����u�O�����Ή��̍����v�̉��ւȂ�
�@�@�Ƃ������Ƃ��i�߂��Ă����̂��B�ӊO�ɂ����Ƃ͉�Ж@�����ł͂Ȃ��̂��A�ӊO�ɂ���v��ɂ��Ċ�ƍ�
�@�@����v�����������Ɍ������ꂷ����j����߂��A���̐V����������v����ł́A�]���̓��{�I�ȑΓ�����
�@�@�͓���Ȃ�A�G�Ύ��������܂߂��z������������̊�ƍĕ҂̎嗬�ƂȂ�Ƃ����Ă���B����ɁA�Ő��ʂł�
�@�@�O���ɂ����{��Ɣ������㉟�����邽�߂ɐŐ����v���O�S�N���猟������Ă���Ƃ����A����������A�̉��v��
�@�@���̂��ׂĂ̓����̎i�ߓ��ƂȂ��Ă���̂��u�Γ�������c�i�i�h�b�j�v�c���͓��t�����厖�A���c���͌o�����S
�@�@����b�A�����Ă��̉����g�D�ɂ͂P�R�l�̓��{�l�̑��ɁA�ݓ��č����H��c���̊�����č��،���Ђ̖����A
�@�@��l�̊O���l�ٌ�m���܂ނP�O�l�̊O���l���u�O���l���ʈψ��Ƃ��Ė���A�˂Ă��邻���ł���B
�@�@�@�����āA���̑Γ�������c��啔��O�S�N�A�u�Γ��������i�v���O�����y�ю��{�v�Ƃ��������̒��ŁA
�@�@�u�������z���������E�������e�Ղɍs����悤�Ɂv�Ƃ����ړI�Łu�O�����Ή��̍����v�̉��ւ��ƍ�����v��
�@�@�̎������������A�Ő���̗D���[�u�ȂǂƂ��������Ƃ���̗�Ƃ��Ă������Ă��B����ȊO�ɂ��A�ߔN�A���{��
�@�@�傫���h�邪���Ă���B������\�����v�̑������A���́u�Γ��������i�v���O�����v�̈���������Ƃ����L��
�@�@��Ă���B���͏���̌����\�����v�́A�����̂��߂ł͂Ȃ��A�O���ɂ����{��Ƃ̔����𑣐i���邽�߂�
�@�@�u���{�����v�����������đg�D�I�ɐi�߂��Ă����̂ł���B
�@�@�@04�N�ł́u�Γ������C�j�V�A�`�u�v�̕��ɂ́o�č����{�́A���{�ɂ�����l�����Ԃ̕ω��ɂ��A����A
�@�@����y�ш�ÃT�[�r�X����ɂ����铊�����d�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E�����B�����Ă����̕���ɂ����ĕč�
�@�@��Ƃ����̓��ӕ���������l�X�Ȏ��̍����T�[�r�X��ł��邱�ƁA�܂����������V���ȃT�[�r�X�̒�
�@�@�����{�̏���җ��v�̑���Ɏ�������̂ł��邱�Ƃ��w�E�����B�č����{�͂����̕���ɂ����铊���𑣐i��
�@�@�邽�߁A���{���{�ɑ��A���Y����ɂ����铊�����\�Ƃ��邽�߂̋K�����v��v�������B�p���邳��Ă���B
�@�@�@�����ăA�����J�̓��{�����͂܂��܂������X�����c���Łu�ȈՕی��v����Ð��x���v�Łu��Õی��v�����̂�
�@�@�炢�͋���A��ÃT�[�r�X�A�u���ρv�ւƉ��X�Ƒ��������ł���B���������N�����̕č��ɂ����{�������~��
�@�@��̂��A�����Ȃ鍑���ȊO�ɂȂ��ł͂Ȃ����A�ڊo�߂���{�B
�@�@�@���ċK�����v�y�ы�������C�j�V�A�`�u�Ɋ�Â����{���{�ւ̕č����{�v�]���̖`���ɂ�
�@�@�@�O�T�N�Ł@�@�č��́A������b�̓��{�o�ω��v�Ɍ������p���I���g�݂�����������B�����̎��g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͓��{�𐬒��O���ɏ悹�A��葽���̖f�Ջy�ѓ����@���n�o�����A�č��͂܂��A�����ƍ\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����͏����ʓI�ɒ��Ă����K�����v�E���ԊJ�����i�{���ƁA�\�����v���ʐ��i�{���̂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g�݂�]������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̗v�]���ɐ��荞�܂ꂽ�́A��v�����A���f�I����ɂ�����A���v�ɏd�_��u���A�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ϐ������x�����A���{�̎s��J������肢�������������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B����ɕč��͓d�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A�m�I���Y���A��ÁA�_�ƁA���c���A��������ȂǁA���������v�̎�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���d�v�ł���ƈʒu�Â�������̖��Ɉ����������ɏœ_�ĂĂ���B
�@�@�@�O�U�N�Ł@�@�č��́A���{�̌o�ω��v�𐄐i����Ƃ�������������b�̌��ӂ����}����B�V�����@��݁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����𑣂��A��茒�S�ȃr�W�l�X�������o�����v�́A���ꂩ��扽�N�ɂ��n����{�̌o�ϐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɗ��͂��ێ����x����ł��낤�B�܂��A�č��͓��{�����̉��v���i�҂̎��g�݂�S�����v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���㐔�����A���N�ɂ킽��A�����̊��������������邱�Ƃ����҂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̕č�����̒́A�d�C�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A��Ë@��A���i�A���Z�T�[�r�X�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɩ@���T�[�r�X�A�������A�_�ƁA���Ђ̖��c���A���ʁA��������ƍL�͈͂ȕ���ɂ����āA�p
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ��v�̐i�W��}�邱�Ƃ̏d�v�����������Ă�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԕ���i�č��́j�̑�\�����C�j�V�A�`�u�֒���I�ɎQ�����A���m������Ă���邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŁA��X�̍�ƂɕK�v�ȑ����̏��邱�Ƃ��o�����A�����͂��̂悤�ȎQ���̋@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���傷�邱�Ƃ����҂���B
�@
�@�@�@�ȏオ�����F����ɓ`���������̖{�̓��e�̈ꕔ�ł��B�������ł��傤���A�������������m��Ȃ��Ԃɋ�����
�@�@�����Ƃ��i�s���Ă��܂��A���̂��Ƃ����{�̏������ǂ��ς��Ă����̂����̕n��ȓ��ł͑z�������܂���
�@�@�̖{��ǂ�ł���Ɖ�������傫�ȓ{�肪�킢�Ă��ĂȂ�܂���B
�@�@�@���̔N�����v�v�]���͓��đo�����o�������Ă���A���R���{���o���Ă��܂����A����Ƃ��Ď������Ă��Ȃ�
�@�@�����ł��B��Ȃ�����ł͂���܂��A�ǂ����F�l�A��x�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�Łu�N�����v�v�]���v
�@�@�Ȃ���̂������Ŋm���߂Ă��������B�����Ǝ��̌����Ă��邱�Ƃ��������Ă���������Ǝv���܂��B
�@�@�@�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�@http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@
�X�����c���͓��{�����ɂƂ��Đ��������v�Ȃ̂�
�@�@����A����H.D���玟�̗l�Ȃ��莆���܂����B
�@�@�O���A�M�Z�ɂ͐V���ȖڕW�Ɍ������čĂъ������n�߂�ꂽ���ƁA���ɂ����c�Ɋ����܂���B�n��ɍ�
�@������������ʂ��ĊC��s������肢�������O�i�����Ă������������܂��悤���҂��Ă���܂��B
�@�@���Đ���A�M�Z�̃z�[���y�[�W�ŗX�����c�������グ�Ă���̂�q�����āA���ɓ������ӌ��ŁA
�@���X�Ȃ���M�Z�̓��@�͂̐[���Ɋ��S�������܂����B�i�����j
�@�@�X���ɂ��Ă͌������܂������A������������v�̖��̂��Ƃō��v�ɔ�����悤�Ȑ������������邱
�@�Ƃ����͂��߂�ւ肽���҂ł��B
�@�@�����̐}���͐挎���s����܂������̂ł����A���݂̎��̑z���Ɠ����ł��̂Ő����x���ڂƂƂ�����
�@�����������肢�����܂��B�ƌ������ƂŁA���̂悤�Ȗ{�𑗂��Ă��������܂����B
�u�D������{�v�i�։��p�V�j
�@�@�ڂ���Ƃ͂��̂��ƂŁA���̂���A�����̍����ɂƂĂ̂킩��ɂ��������X�����c���A�������̋^
�@��_�����炩�ɂȂ�܂����B�����āA���ы��N�c�������ߔ��Δh�̋c���͂Ȃ����̂悤�ɋ��d�ɔ���
�@��̂����A���v���Ȃ��}���̂��A�X�����c����č��ƂȂ��b������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ���������
�@�����̖{�����炩�ɂ��Ă��܂��B�F����ɂ��̖{�̂��ׂĂɖڂ�ʂ��Ă������������Ǝv���܂����A����
�@�ł͗v�_���L���Ă݂����Ƒz���܂��B
�@�@���{��卬���Ɋׂꂽ�X�����c���@�A���{�̏��������ɂ킽��ł��낤�A�l�X�ȉЍ����c�����Q�O�O�T
�@�N�ő�̐����ۑ�́A���ׂď����̎v�f�����Ɍ��������B���̔N�̉ߔ��̎��ԂƃG�l���M�[����
�@����Ƃ�������X�����c���Ƃ́A���ǂȂ����̂��B
�@�@���̗X�����c�����ɂ́A�Ō�܂ł����₯�ɂ͂قƂ�nj���Ȃ��������ʂ�����B���{�̍\��
�@���v�̖{�ہA���邢�͐����Ə���Y�̌l�I���O�A�ȂǂƎ�肴������Ă������̖��̔w���
�@�͕č�����̎��X�Ȉ��͂Ƃ���������̈��q���B����Ă����̂ł���B
�@�@1995�N11���ɕč����{������{���{�ɒ��ꂽ�u�N�����v�v�]���v�ɂ́A�ȈՕی��Ɋւ��Ď���
�@�悤�ȋL�q������B
�@�@�o�č����{�́A���{���ȉ��̂悤�ȋK���ɘa�y�ы������i�̂��߂̑[�u������ׂ��ł���ƐM����B
�@�E�E�E�E�E�X���Ȃ̂悤�Ȑ��{�@�ւ��A���ԉ�Ђƒ��ڋ�������ی��Ɩ��Ɍg��邱�Ƃ��֎~����B�p�Ƃ�
�@��B�@�h�֎~����Ƃ͓��������̂��̂ł͂Ȃ����B�h�@
�@�@�����Ă���ȗ��č����{�͊ȈՕی��̔p�~��v���������A
�@�@1999�N�̗v�]���ł́@�o�č��͓��{�ɑ����ԕی���Ђ����Ă��鏤�i�Ƌ�������ȈՕی�
�@�i�J���|�j���܂ސ��{�y�я������ی����x���g�傷��l�������ׂĒ��~���A�����̐��x�����ł܂���
�@�p�����ׂ����ǂ����������邱�Ƃ��������߂�B�p�܂�č��͊��ƂƂ��Ă̊ȕۂ�p�~���Ė��ԉ�Ђ�
�@�J������Ɨv�����Ă���̂ł���B
�@�@���{�̖��ԕی��s��͉ߋ�20�N�ȏ�ɂ킽���ĕč��ɂ������W����Ă����A���̗��j��U���
�@������ʼn��߂��l����A�X�����c���̖{���͂P�Q�O���~�ɂ̂ڂ銯�c�ی��̎s��J����肾�ƌ���
�@���Ƃ��킩��B�������������c�����������ł͍����ő��̓��{�����̎O�{�߂��K�͂̋���Ȗ��ԕ�
�@����Ђ��a�����邾���̂��Ƃ��A�����A�č����]��ł���̂͂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�č��͖��c��
�@��̊ȈՕی��Ƃ��̎��Y�P�Q�O���~���ǂ����傤�ƍl���Ă���̂��B
�@�@2004�N�̋K�����v�v�]���ɂ͂��̋L�q��v��ƁA�ȕۂ̐��{�ۗL���������S�Ɏs��֔��p��
�@���A�u���{�ۏ����邩�̂悤�ȔF���������ɐ����Ȃ��悤�\���ȕ�����v��点��B�܂萭�{�̊֗^
�@�����S�ɒf���点�����Ȗ��ԉ�ЂƂȂ����ȕۂɑ��ẮA�O���n�ی���ЂƊ��S�ɑΓ��ȋ�����
�@����v�����Ă����B�����Ċȕۂ̏��NJ������Ȃ�����Z���Ɉڊǂ������̗������茟���������A
�@�\���y���V�[�}�[�W���Ȃǂ̌��\���`���Â���v�������Ȃǂ̊č���������B
�@����ɁA�ȕۂ�Ƌ֖@�Ȃǂ̓K�p�ΏۂƂ��A�u���̎s��x�z�͂��s�g���Č���c�Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��悤�v
�@��������ψ���ɒ���������ƌ��������Ƃ��L�q����Ă���B
�@�@�v����ɕč��ɂƂ��Ė��c���̓S�[���ł͂Ȃ��ȕۂ���̉������A�ŏI�I�ɂ͕����A��́A�o�c�j�]
�@�ɒǂ����݁A�l���`��c�Ə��n�ȂǗl�X�Ȏ�i��M���āA�ȕۂ��i���Ă���P�Q�O���~�ɂ̂ڂ鎑�Y��
�@�č��n���ԕی���Ђɋz�������邱�Ƃ��ŏI�I�Ȃ˂炢�Ȃ̂ł���B
�@�@�ȕۂ͏����ł��邱�ƂƁA���R���Ƃ����ȈՂȉ����葱������F�Ƃ��Ă���B���X�ȈՐ����ی����x
�@�́A���Ԃ̐����ی��ɉ����ł��Ȃ��Ꮚ���҂ɂ��ی��Ƃ����Z�t�e�B�l�b�g����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�吳�ܔN�ɑn�݂�����̎҂Ńr�W�l�X�ƌ��������{�Љ�̈��艻���u�ł���B
�@���ꂪ�č��l�ɂ͒P�Ȃ�s��Ƃ��Ă����ڂ�Ȃ��B���艻���u���͂�������̓��{�Љ�ǂ��Ȃ낤��
�@��؊S���Ȃ��̂ł���B�u�����疯�֎����𗬂��v�u���ɏo���邱�Ƃ͖��Łv�ƌ����Ƃ��̖���
�@���{�����̖��ł͂Ȃ��A���{�����̍s�����ɐӔC��Ȃ��č����ԕی���Ђ́u���v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�������ł��傤���A�����͂��K�ߑ����̍���c�����X�����c���ɂ��āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɍ��́A
�@�����̗��v�ɂȂ���̂����Ȃ������ɐ����ӔC���ʂ����Ȃ��̂��A���킩�蒸�����ł��傤���A�{��
�@�͗X�����c���ɍŌ�܂Ŕ������A�^�̍��v����낤�Ƃ��������}�̗E�C����c���B������X������
�@�������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�����ł͂Ȃ������̂��B�ŋߎ��͂��Â������v���Đ���܂���A����
�@�Ђ�����ɉ��̂��߂炢���Ȃ�������ӐM���c���Ɏ^���������A�䂪���̂U�l�̗^�}�c���́A�ǂ�
�@�قnj����ɑ��Đ����ӔC���ʂ������̂ł��傤�B�ނ�͕č��́u�N�����v�v�]���v�m���Ă����̂ł���
�@�����B�@�������̂��Ƃ͐����Ă݂����҂ł��B
�@
�@
�@�@�݂����ƂƎv���܂��B�u�N�����v�v�]���v�͂X�R�N�V�������T�~�b�g�̍ۂ̋{��N�����g��
�@�@��]��k�ł́u���ĊԂ̐V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v���ӂ���������
�@�@�ł���B���̌���{�̐����͍א���t�A�H�c���t�A�����ĂX�S�N�U���ɑ��R���t�������A
�@�@���ꂩ��܂��Ȃ��\���ɍݓ��č����H��c�����Γ��v�]�����\�A���ꂪ�u���ĊԂ�
�@�@�V���Ȍo�σp�[�g�i�[�V�b�v�̂��߂̘g�g�݁v�̈�Ƃ��Đݒu���ꂽ�K���ɘa�E����
�@�@��������ɍ̗p����A�u�N�����v�v�]���v�Ƃ��Ē�ቻ�����Ƃ����킯�ł���B�Ȍ㌇��
�@�@�����ƂȂ����N�H�Ɍ��\����Ă����B
�@�@�@���{�̐������\�ܔN�̐������A�����A�������钆�č��ɑ����������A����
�@�@����u�č��ɂ����{�����v�Ƃ����`�e�̂������̂Ȃ����ĂQ���Ԃُ̈�ȃ��J�j�Y
�@�@���ƁA���̋��͂Ȕ}�̂ł���u�N�����v�v�]���v�́A�����{�̗��j�I�]���_�Ƃ���
�@�@�ׂ������ƍ����̒��ŁA�č��Ɏ��˂����܂�ē��{�̐����V�X�e���̒��ɂ��������
�@�@���U����Ă��܂����B���́u�N�����v�v�]���v�͂O�S�N�A�։��p�V���̒����u���ۂł���
�@�@�����{�v�����\����A�u�킵�Y���v�i����Ƃ̏��т悵�̂肪�ӔC�ҏW���߂�G��
�@�@���B�j�O�U�N�~���ŏ��т悵�̂肳��́u�������ł����̎����𐢂ɍL�߂邽�߂ɏ�������
�@�@�ɂ���v�Ƃ������Ƃ���u���ė��E�N�����v�v�]���ɓ{��v�Ƃ������W���g�܂�A�����]
�@�@�_�Ƃ̐X�c�����u�����S�ʔᔻ�v�i���{�]�_�Ёj�̒��ŁA�u�O�S�N�T���R���A����
�@�@�ڍ��w�r�����̏��X�ň���̐V�����������A�Ƃ������{�̕����玄�ɍ��}�𑗂���
�@�@����C����������͡{�ۂł��Ȃ����{�[�A�����J�̓��{������������ł���p���҂͊։�
�@�@�p�V����A�m��Ȃ����������̐l�̒����ɂ͓��{�̍���J�����{�l�̍������߂��Ă���悤�ȋC�������v��
�@�@�������ƂŎ��グ�A�Ȍ�W�҂̊ԂɍL�����グ����悤�ɂȂ��������ł���B
�@�@�@�X�U�N����n�܂����u�N�����v�v�]���v�O�S�N�Ɂu���ۂł��Ȃ����{�Łv�����ɔ��\�����܂ŁA���̎��X�̓�
�@�@�t�A�����͒m���Ă����Ƃ��Ă��@��ʂ̍���c�����^�}����}���قƂ�ǒm��Ȃ��������Ƃɋ����ł���B�u����
�@�@�ł��Ȃ����{�v�̘b���A���҂̊։��p�V����������āA������J�����A���̏��ы��N�����A���i��
�@�@��A�ނ�͊։�����̘b�����ςȂ��ɂ��Ȃ������B�ނ�́u�N�����v�v�]���v�͂��A�X�����c���@�Ă���
�@�@���̗v���������̂ł��邱�Ƃ��������A����ł͓��{�̍��v�ɂȂ�Ȃ��A�A�����J�𗘂��邾���ł͂Ȃ����Ƌ`
�@�@����R�₵���B�����Ă��̌�̓W�J�́A�������̒ʂ�ł���B����ɐ�������A�}�X���f�B�A�ɗx�炳��
�@�@�����{�̗L���ҁi���{�����j���炪�����̎���i�߂Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@ �@�@�@�u�N�����v�v�]���v����͓��đo�������݂ɒ�o�������Ă������̂ŁA�ߋ��\���N�ԓ��{�Ői�߂��Ă����A
�@�@�u���v�v�̂��Ȃ�̕������č����{�̗v���𒉎��ɔ��f���Ă������̂ŁA�O�T�N����Ő��������A�V��Ж@�A����
�@�@�Ƌ֖@�A�X�����c���@���܂�������ł���B�����āA�����̒��߂�����́A��Ð��x���v�ł���B���̗�R��
�@�@��]���Ԃ�́u�P�퉻���ꂽ�������v�Ƃ����ق��͂Ȃ��A�匠���ƂƂ��Đq��Ȃ炴����̂��B����ł͕č���
�@�@�B�̕����܂������A������A�����J�̑����ł͂Ȃ����B
�@�@�@����͂Ȃ��������[�@�Ă⋳���{�@�����@�āA�h�q�����i�֘A�@�ĂȂǏd�v�@�ĂȂǐ摗�肵�A���
�@�@���x���v�@�Ă̐������}�����̂��B����͂܂��ɂO�U�N�U���Ƀu�b�V���đ哝�̂Ƃ̍Ō�̎�]��k���Z�b�g����
�@�@�Ă������߂ŁA�u�N�����v�v�]���v��Ð��x���v�̐i�W������������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�����ꂽ��Ð��x���v�@�́A���I��Ô�̗}���������ł��o�������̂ŁA���̂��߂ɍ����A�Ƃ�킯�����
�@�@�Ɏ��ȕ��S�̑���𔗂���e�ƂȂ����B
�@�@�@�����͂O�Q�N�Ɋ��Ɉ�Ð��x���v�ɒ��肵�Ă���A���̂Ƃ��͂���܂ł̏���t��z�����P�p����A���S
�@�@�藦���ɑւ���ꂽ�B���̍ہA�V�O�ˈȏ�̍���҂̈�Ô�ȕ��S���́A��ʏ����҂��P���A������ݏ���
�@�@�҂��Ƃ���A����҂̎��ȕ��S�𑝂₵�Ă���B����҈ȊO�ɑ��Ă��A�O�R�N����T�����[�}���{�l�̈��
�@�@��ȕ��S������O���Ɉ����グ��ꂽ�ق��A�Z������������x�[�X����ܗ^���܂߂��N���x�[�X�ɕύX
�@�@����A�ی������S�����₳��Ă���B
�@�@�@���ꂪ�O�U�N�̈�Ð��x���v�ł͎��\�˂��玵�\�l�˂̈�ʏ����҂͂O�W�N�S������ɁA���\�ˈȏ�̌�
�@�@����ݏ����҂͂O�U�N�P�O������O���ɑ��₳��B�܂��A�u������ݏ����v�̒�`������������ꂽ���߂ɁA�e
�@�@������Ώێ҂̐����������B���̏�A�u���z�×{��x�v����������A����ҁA���𐢑���킸�A���z�Ȉ�
�@�@�Ô���������ꍇ�̎��ȕ��S���x�z�������グ��ꂽ�B
�@�@�@����ɁA�u�������҈�Ð��x�v���n�݂���O�W�N����]���͕}�{�Ƒ��Ƃ��ĕی�����Ƃ�Ă����l���܂߁A
�@�@���\�܍ˈȏ�̂��ׂĂ̍���҂��A�ی����̎x�����`�����ۂ����邱�ƂɂȂ����B�܂��A����҂������ɓ�
�@�@�@���Ă���u�×{�a���v�ł̐H�����M��͂O�U�N�\������ی��ΏۊO�ƂȂ�A�×{�a�����̂��Q�O�P�Q�N�܂łɌ�
�@�@�݂̔����ȉ��ɍ팸����邽�߁A�������@���҂͗L���V�l�z�[���Ȃǂ֓]�o�𔗂���B�[�I�Ɍ����A����
�@�@�������T�N�Ԃɂ킽���Đ��i���Ă����u��Ð��x���v�́v�Ȃ���̂̎��Ԃ́A�����A�Ƃ�킯����҂Ɏ��ȕ��S��
�@�@��𔗂邱�ƂɏI�n���Ă����̂͒N�̖ڂɂ����炩�ł���B
�@�@�@���҂̎��ȕ��S�����܂�A���I�ی��ŃJ�o�[�����͈͂�������A�k�����邱�ƂɂȂ�A���ȕ��S���J�o�[
�@�@���邽�߂̖��ԕی����o�ꂷ��B�u���ꂪ���ɏo���邱�Ƃ͖��ɂ�点��v�ƌ������Ƃł���A���I��Õی���
�@�@�k�����Ă����A����A�����́u���ȐӔC�v�ŏ����ɔ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐V����e���r�ŃA�t��
�@�@�b�N��A���R�ȂǃA�����J�n�ی���Ђɂ���Õی����i�̐�`���킪�ٗl�ȂقljߔM���Ă���̂́A��Ð�
�@�@�x���v�ɒ[�������ۂł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�����ЂƂA����ł����̂����{�́A�����������Ȃ�悤�ȉ��v���i�߂��Ă����B���ꂪ�u�V��Ж@�v�̐�
�@�@�肾�A�u��Ж@�v�Ƃ����@���͂���܂ő��݂��Ȃ������A��А��x�Ɋւ��Ă͏��@��L����Ж@�ȂǗl�X�Ȗ@��
�@�@������ł����A��������ɂ܂Ƃ߂ĐV�����u��Ж@�v���A�����Ă��̖ڋʂƈʒu�Â����Ă����̂��A����
�@�@�J���狭���v�]����Ă����A�u�O�����Ή��̍����v�i�������z�������������j�̉��ւł���B���ꂪ���ւ����Ƃ�
�@�@���Ȃ邩�A�Ђ炽�������ΊO����Ƃ����z�̔��������������邱�ƂȂ��ɁA���Њ����g���Ă��Ƃ����₷�����{
�@�@��Ƃ��P���ɂ����߂邱�ƂɂȂ�B������u�O���ɂ����{��Ƃ̏�����v�̉��ւł���B
�@�@�@�V��Ж@�͂O�S�N�P�Q���ɗv�j�Ă����\����O�T�N�ʏ퍑��ɖ@�Ă���o����A�O�U�N����{�H����邱�Ƃ�
�@�@�Ȃ��Ă����A�����̂قƂ�ǂ��m��Ȃ��ԂɁA�܂��ɊԈꔯ����̔N���C�u�h�A�̎������������A�G�ΓI��Ɣ���
�@�@�ւ̍����I�S���ɂ킩�ɕ����A�Ƃ��ɁA��������d�|����ꂽ���{��Ƃɂ͖@�I�ɕۏ��ꂽ�h�q�ق�
�@�@��ǖ������ƂɊ�@�������������B�����}�̓}��(�X�����c���Ŋ����A���̏��ы��N�c���⏬�i�c��)
�@�@������u�O�����މ��̍����v���ւɑ��锽�Θ_�����o���A��o�������O�Ɉ�N�ԓ�������邱�ƂɂȂ����B��
�@�@��Ȋ댯�Ȃ��Ƃ����蔭�Ԑ��O���������Ƃɂ͜ɑR�Ƃ������ł��邪�A���̎����}(�X�����c���Ŋ���
�@�@���A���̏��ы��N�c���⏬�i�c���j�c�������̓����ɂ��A��N�ԓ�������邱�ƂƂȂ�A���{�̊�Ƃ��h
�@�@�q����u���邱�Ƃ��o�����̂ł���B
�@�@�@����ɂ��Ă��A�Ȃ��������ݓ��{�̑��Ƃ��������ɂ���킽���ɂЂƂ����u�O�����Ή��̍����v�̉��ւȂ�
�@�@�Ƃ������Ƃ��i�߂��Ă����̂��B�ӊO�ɂ����Ƃ͉�Ж@�����ł͂Ȃ��̂��A�ӊO�ɂ���v��ɂ��Ċ�ƍ�
�@�@����v�����������Ɍ������ꂷ����j����߂��A���̐V����������v����ł́A�]���̓��{�I�ȑΓ�����
�@�@�͓���Ȃ�A�G�Ύ��������܂߂��z������������̊�ƍĕ҂̎嗬�ƂȂ�Ƃ����Ă���B����ɁA�Ő��ʂł�
�@�@�O���ɂ����{��Ɣ������㉟�����邽�߂ɐŐ����v���O�S�N���猟������Ă���Ƃ����A����������A�̉��v��
�@�@���̂��ׂĂ̓����̎i�ߓ��ƂȂ��Ă���̂��u�Γ�������c�i�i�h�b�j�v�c���͓��t�����厖�A���c���͌o�����S
�@�@����b�A�����Ă��̉����g�D�ɂ͂P�R�l�̓��{�l�̑��ɁA�ݓ��č����H��c���̊�����č��،���Ђ̖����A
�@�@��l�̊O���l�ٌ�m���܂ނP�O�l�̊O���l���u�O���l���ʈψ��Ƃ��Ė���A�˂Ă��邻���ł���B
�@�@�@�����āA���̑Γ�������c��啔��O�S�N�A�u�Γ��������i�v���O�����y�ю��{�v�Ƃ��������̒��ŁA
�@�@�u�������z���������E�������e�Ղɍs����悤�Ɂv�Ƃ����ړI�Łu�O�����Ή��̍����v�̉��ւ��ƍ�����v��
�@�@�̎������������A�Ő���̗D���[�u�ȂǂƂ��������Ƃ���̗�Ƃ��Ă������Ă��B����ȊO�ɂ��A�ߔN�A���{��
�@�@�傫���h�邪���Ă���B������\�����v�̑������A���́u�Γ��������i�v���O�����v�̈���������Ƃ����L��
�@�@��Ă���B���͏���̌����\�����v�́A�����̂��߂ł͂Ȃ��A�O���ɂ����{��Ƃ̔����𑣐i���邽�߂�
�@�@�u���{�����v�����������đg�D�I�ɐi�߂��Ă����̂ł���B
�@�@�@04�N�ł́u�Γ������C�j�V�A�`�u�v�̕��ɂ́o�č����{�́A���{�ɂ�����l�����Ԃ̕ω��ɂ��A����A
�@�@����y�ш�ÃT�[�r�X����ɂ����铊�����d�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E�����B�����Ă����̕���ɂ����ĕč�
�@�@��Ƃ����̓��ӕ���������l�X�Ȏ��̍����T�[�r�X��ł��邱�ƁA�܂����������V���ȃT�[�r�X�̒�
�@�@�����{�̏���җ��v�̑���Ɏ�������̂ł��邱�Ƃ��w�E�����B�č����{�͂����̕���ɂ����铊���𑣐i��
�@�@�邽�߁A���{���{�ɑ��A���Y����ɂ����铊�����\�Ƃ��邽�߂̋K�����v��v�������B�p���邳��Ă���B
�@�@�@�����ăA�����J�̓��{�����͂܂��܂������X�����c���Łu�ȈՕی��v����Ð��x���v�Łu��Õی��v�����̂�
�@�@�炢�͋���A��ÃT�[�r�X�A�u���ρv�ւƉ��X�Ƒ��������ł���B���������N�����̕č��ɂ����{�������~��
�@�@��̂��A�����Ȃ鍑���ȊO�ɂȂ��ł͂Ȃ����A�ڊo�߂���{�B
�@�@�@���ċK�����v�y�ы�������C�j�V�A�`�u�Ɋ�Â����{���{�ւ̕č����{�v�]���̖`���ɂ�
�@�@�@�O�T�N�Ł@�@�č��́A������b�̓��{�o�ω��v�Ɍ������p���I���g�݂�����������B�����̎��g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͓��{�𐬒��O���ɏ悹�A��葽���̖f�Ջy�ѓ����@���n�o�����A�č��͂܂��A�����ƍ\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����͏����ʓI�ɒ��Ă����K�����v�E���ԊJ�����i�{���ƁA�\�����v���ʐ��i�{���̂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������g�݂�]������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̗v�]���ɐ��荞�܂ꂽ�́A��v�����A���f�I����ɂ�����A���v�ɏd�_��u���A�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ϐ������x�����A���{�̎s��J������肢�������������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B����ɕč��͓d�C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A�m�I���Y���A��ÁA�_�ƁA���c���A��������ȂǁA���������v�̎�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���d�v�ł���ƈʒu�Â�������̖��Ɉ����������ɏœ_�ĂĂ���B
�@�@�@�O�U�N�Ł@�@�č��́A���{�̌o�ω��v�𐄐i����Ƃ�������������b�̌��ӂ����}����B�V�����@��݁A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����𑣂��A��茒�S�ȃr�W�l�X�������o�����v�́A���ꂩ��扽�N�ɂ��n����{�̌o�ϐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɗ��͂��ێ����x����ł��낤�B�܂��A�č��͓��{�����̉��v���i�҂̎��g�݂�S�����v����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���㐔�����A���N�ɂ킽��A�����̊��������������邱�Ƃ����҂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�N�̕č�����̒́A�d�C�ʐM�A���Z�p�i�h�s�j�A��Ë@��A���i�A���Z�T�[�r�X�A��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɩ@���T�[�r�X�A�������A�_�ƁA���Ђ̖��c���A���ʁA��������ƍL�͈͂ȕ���ɂ����āA�p
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ��v�̐i�W��}�邱�Ƃ̏d�v�����������Ă�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԕ���i�č��́j�̑�\�����C�j�V�A�`�u�֒���I�ɎQ�����A���m������Ă���邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŁA��X�̍�ƂɕK�v�ȑ����̏��邱�Ƃ��o�����A�����͂��̂悤�ȎQ���̋@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���傷�邱�Ƃ����҂���B
�@
�@�@�@�ȏオ�����F����ɓ`���������̖{�̓��e�̈ꕔ�ł��B�������ł��傤���A�������������m��Ȃ��Ԃɋ�����
�@�@�����Ƃ��i�s���Ă��܂��A���̂��Ƃ����{�̏������ǂ��ς��Ă����̂����̕n��ȓ��ł͑z�������܂���
�@�@�̖{��ǂ�ł���Ɖ�������傫�ȓ{�肪�킢�Ă��ĂȂ�܂���B
�@�@�@���̔N�����v�v�]���͓��đo�����o�������Ă���A���R���{���o���Ă��܂����A����Ƃ��Ď������Ă��Ȃ�
�@�@�����ł��B��Ȃ�����ł͂���܂��A�ǂ����F�l�A��x�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�Łu�N�����v�v�]���v
�@�@�Ȃ���̂������Ŋm���߂Ă��������B�����Ǝ��̌����Ă��邱�Ƃ��������Ă���������Ǝv���܂��B
�@�@�@
�A�����J��g�ق̃z�[���y�[�W�@http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�O���A�M�Z�ɂ͐V���ȖڕW�Ɍ������čĂъ������n�߂�ꂽ���ƁA���ɂ����c�Ɋ����܂���B�n��ɍ�
�@������������ʂ��ĊC��s������肢�������O�i�����Ă������������܂��悤���҂��Ă���܂��B
�@�@���Đ���A�M�Z�̃z�[���y�[�W�ŗX�����c�������グ�Ă���̂�q�����āA���ɓ������ӌ��ŁA
�@���X�Ȃ���M�Z�̓��@�͂̐[���Ɋ��S�������܂����B�i�����j
�@�@�X���ɂ��Ă͌������܂������A������������v�̖��̂��Ƃō��v�ɔ�����悤�Ȑ������������邱
�@�Ƃ����͂��߂�ւ肽���҂ł��B
�@�@�����̐}���͐挎���s����܂������̂ł����A���݂̎��̑z���Ɠ����ł��̂Ő����x���ڂƂƂ�����
�@�����������肢�����܂��B�ƌ������ƂŁA���̂悤�Ȗ{�𑗂��Ă��������܂����B
�u�D������{�v�i�։��p�V�j
�@�@�ڂ���Ƃ͂��̂��ƂŁA���̂���A�����̍����ɂƂĂ̂킩��ɂ��������X�����c���A�������̋^
�@��_�����炩�ɂȂ�܂����B�����āA���ы��N�c�������ߔ��Δh�̋c���͂Ȃ����̂悤�ɋ��d�ɔ���
�@��̂����A���v���Ȃ��}���̂��A�X�����c����č��ƂȂ��b������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ���������
�@�����̖{�����炩�ɂ��Ă��܂��B�F����ɂ��̖{�̂��ׂĂɖڂ�ʂ��Ă������������Ǝv���܂����A����
�@�ł͗v�_���L���Ă݂����Ƒz���܂��B
�@�@���{��卬���Ɋׂꂽ�X�����c���@�A���{�̏��������ɂ킽��ł��낤�A�l�X�ȉЍ����c�����Q�O�O�T
�@�N�ő�̐����ۑ�́A���ׂď����̎v�f�����Ɍ��������B���̔N�̉ߔ��̎��ԂƃG�l���M�[����
�@����Ƃ�������X�����c���Ƃ́A���ǂȂ����̂��B
�@�@���̗X�����c�����ɂ́A�Ō�܂ł����₯�ɂ͂قƂ�nj���Ȃ��������ʂ�����B���{�̍\��
�@���v�̖{�ہA���邢�͐����Ə���Y�̌l�I���O�A�ȂǂƎ�肴������Ă������̖��̔w���
�@�͕č�����̎��X�Ȉ��͂Ƃ���������̈��q���B����Ă����̂ł���B
�@�@1995�N11���ɕč����{������{���{�ɒ��ꂽ�u�N�����v�v�]���v�ɂ́A�ȈՕی��Ɋւ��Ď���
�@�悤�ȋL�q������B
�@�@�o�č����{�́A���{���ȉ��̂悤�ȋK���ɘa�y�ы������i�̂��߂̑[�u������ׂ��ł���ƐM����B
�@�E�E�E�E�E�X���Ȃ̂悤�Ȑ��{�@�ւ��A���ԉ�Ђƒ��ڋ�������ی��Ɩ��Ɍg��邱�Ƃ��֎~����B�p�Ƃ�
�@��B�@�h�֎~����Ƃ͓��������̂��̂ł͂Ȃ����B�h�@
�@�@�����Ă���ȗ��č����{�͊ȈՕی��̔p�~��v���������A
�@�@1999�N�̗v�]���ł́@�o�č��͓��{�ɑ����ԕی���Ђ����Ă��鏤�i�Ƌ�������ȈՕی�
�@�i�J���|�j���܂ސ��{�y�я������ی����x���g�傷��l�������ׂĒ��~���A�����̐��x�����ł܂���
�@�p�����ׂ����ǂ����������邱�Ƃ��������߂�B�p�܂�č��͊��ƂƂ��Ă̊ȕۂ�p�~���Ė��ԉ�Ђ�
�@�J������Ɨv�����Ă���̂ł���B
�@�@���{�̖��ԕی��s��͉ߋ�20�N�ȏ�ɂ킽���ĕč��ɂ������W����Ă����A���̗��j��U���
�@������ʼn��߂��l����A�X�����c���̖{���͂P�Q�O���~�ɂ̂ڂ銯�c�ی��̎s��J����肾�ƌ���
�@���Ƃ��킩��B�������������c�����������ł͍����ő��̓��{�����̎O�{�߂��K�͂̋���Ȗ��ԕ�
�@����Ђ��a�����邾���̂��Ƃ��A�����A�č����]��ł���̂͂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�č��͖��c��
�@��̊ȈՕی��Ƃ��̎��Y�P�Q�O���~���ǂ����傤�ƍl���Ă���̂��B
�@�@2004�N�̋K�����v�v�]���ɂ͂��̋L�q��v��ƁA�ȕۂ̐��{�ۗL���������S�Ɏs��֔��p��
�@���A�u���{�ۏ����邩�̂悤�ȔF���������ɐ����Ȃ��悤�\���ȕ�����v��点��B�܂萭�{�̊֗^
�@�����S�ɒf���点�����Ȗ��ԉ�ЂƂȂ����ȕۂɑ��ẮA�O���n�ی���ЂƊ��S�ɑΓ��ȋ�����
�@����v�����Ă����B�����Ċȕۂ̏��NJ������Ȃ�����Z���Ɉڊǂ������̗������茟���������A
�@�\���y���V�[�}�[�W���Ȃǂ̌��\���`���Â���v�������Ȃǂ̊č���������B
�@����ɁA�ȕۂ�Ƌ֖@�Ȃǂ̓K�p�ΏۂƂ��A�u���̎s��x�z�͂��s�g���Č���c�Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��悤�v
�@��������ψ���ɒ���������ƌ��������Ƃ��L�q����Ă���B
�@�@�v����ɕč��ɂƂ��Ė��c���̓S�[���ł͂Ȃ��ȕۂ���̉������A�ŏI�I�ɂ͕����A��́A�o�c�j�]
�@�ɒǂ����݁A�l���`��c�Ə��n�ȂǗl�X�Ȏ�i��M���āA�ȕۂ��i���Ă���P�Q�O���~�ɂ̂ڂ鎑�Y��
�@�č��n���ԕی���Ђɋz�������邱�Ƃ��ŏI�I�Ȃ˂炢�Ȃ̂ł���B
�@�@�ȕۂ͏����ł��邱�ƂƁA���R���Ƃ����ȈՂȉ����葱������F�Ƃ��Ă���B���X�ȈՐ����ی����x
�@�́A���Ԃ̐����ی��ɉ����ł��Ȃ��Ꮚ���҂ɂ��ی��Ƃ����Z�t�e�B�l�b�g����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���
�@�吳�ܔN�ɑn�݂�����̎҂Ńr�W�l�X�ƌ��������{�Љ�̈��艻���u�ł���B
�@���ꂪ�č��l�ɂ͒P�Ȃ�s��Ƃ��Ă����ڂ�Ȃ��B���艻���u���͂�������̓��{�Љ�ǂ��Ȃ낤��
�@��؊S���Ȃ��̂ł���B�u�����疯�֎����𗬂��v�u���ɏo���邱�Ƃ͖��Łv�ƌ����Ƃ��̖���
�@���{�����̖��ł͂Ȃ��A���{�����̍s�����ɐӔC��Ȃ��č����ԕی���Ђ́u���v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�������ł��傤���A�����͂��K�ߑ����̍���c�����X�����c���ɂ��āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɍ��́A
�@�����̗��v�ɂȂ���̂����Ȃ������ɐ����ӔC���ʂ����Ȃ��̂��A���킩�蒸�����ł��傤���A�{��
�@�͗X�����c���ɍŌ�܂Ŕ������A�^�̍��v����낤�Ƃ��������}�̗E�C����c���B������X������
�@�������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�����ł͂Ȃ������̂��B�ŋߎ��͂��Â������v���Đ���܂���A����
�@�Ђ�����ɉ��̂��߂炢���Ȃ�������ӐM���c���Ɏ^���������A�䂪���̂U�l�̗^�}�c���́A�ǂ�
�@�قnj����ɑ��Đ����ӔC���ʂ������̂ł��傤�B�ނ�͕č��́u�N�����v�v�]���v�m���Ă����̂ł���
�@�����B�@�������̂��Ƃ͐����Ă݂����҂ł��B
�@
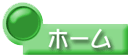 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@