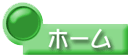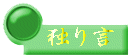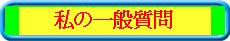
H25年11月議会一般質問(予定)
1、 南風園の改革は進んでいるか
平成24年1月12日に海南市高齢介護課に南風園に対する投書及び
DVDが送付され始まった南風園の虐待問題、その後7月4日まで南
風園は勿論、県、市、において調査し対策が練られ、市議会にお
いても報告にもとずき議論され、教育厚生委員会より、平成24年
5月18日、「海南市立南風園に関する申し入れ」を
【1】
指定管理者(社会福祉事業団)に対する市の指導を徹底す
ること
【2】
公募していない指定管理者の選定については慎重に行うこと
【3】
市及び県の調査が終わればその内容を分析し、事業団に対し改
善勧告を行い、期限を定めて改善計画を提出させ、その実施を
求めること、それができれば評価し、できない場合は事業団
に対し一部停止または指定管理者の取り消しを行うこと。
以上3項目行ってきたところであります。
7月5日には和歌山県知事より最終の監査結果及び介護保険法に
もとずく改善勧告が出され、こん日にいたるわけであります。
県からは
(1) 再度虐待行為が発生しないよう全職員を対象に研修を実施する
など、早急に講ずべき処置。
(2)虐待の再発防止に向けた組織体制の見直し
(3)高齢者虐待防止改善計画の策定
(4)虐待発生の原因を追究・分析し、発生防止策の検討・検証を
行う第三者を含めた虐待防止委員会の設置等
以上、4項目の勧告を受け、改革が始まりました。
県の勧告から1年4ケ月たった今、教育厚生委員会よりの申し入
れ、県の勧告がとど懲りなく実施されたのでしょうか。
私は全てにおいてその進捗状況は好ましい方向に向いてないのではな
いかと考えておりますのでその観点から質問いたします。
中項目
(1)どのような改革をしてきたのか。
今回の事象は
1、施設側が現場任せで、充分な指導監督ができて
いなかったこと。
2、職員への十分な教育がなされていなかったこと
ア、職員へのコンプライアンスルールの周知
イ、接遇意識の欠如
3 職員の介護負担に対する対応ができていなかっ
たこと。
4、事業団組織としての機能が果たされていなか
ったことが大きな原因になっていることが明ら
かであります。
そこで質問ですが
事象発生以来今日まで、市の指導及び南風園の改
革がどのように実視されたのか、その進捗状況と
成果をお聞かせください
(2) 虐待防止改善計画の進捗状況は。
6月議会において宮本憲治議員が質問の最後に当局の答弁に対し
て次のように言ってます。
「要は、提出期限を県に区切られて、平成24年10月5日には一
応提出したんだけれども、いろいろ不備があっていまだ完成し
ていないと。しかし、内容的には完成してなくてもできること
があるんで、やっていってることはありますよという内容です
ね。
この内容ではあかんと当局に認めてもらってから、いつ完成す
るのか、入所者、入所者の家族、全職員に周知すんのはいつま
でにやるんだということを本当はここから聞きたいんだけれど
、前へ進まないんですよね。
次の項目に行きます。
(「次の項目行ったらあかんよ。今のあかなよ。答弁聞かないと
」と呼ぶあり) 皆さん、非常に不消化で申しわけないんですけれども、
まだ先がありますので、また引き続き皆さんのほうで、一般質問
あるいは委員会の中で頑張っていただきたいと思います」
それを受けて今日私が質問するわけですが、その前に、部長
、なぜ平成24年10月5日には一応提出したんだけれども、いろ
いろ不備があって修正を命じられている、その部分については
完成していないと正直に言わないのです、だから疑われるんで
す、信用してもらえないんです。いいですか、今日はそういう
ことのないように。と申し上げて質問に入ります
虐待防止改善計画は、平成24年10月5日付で県のほうに提出
されて、修正の指摘を受けたもののそれ以後今日までの虐待防
止改善計画にもとずく取り組み状況とその成果は。
(3)経営及び管理体制は改善されたか
平成24年7月5日付けで県知事より海南市長あてに「指定介護
老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の遵守につい
て」という勧告書の (2}組織体制の見直しの項で、下記ア及び
イに留意して、盧待の再発紡止に向けた組織体制の見直しを図
ること
ア 開設者である海南市の管理監督体制の構築
開設者である海南市の管理監督責任を明確にするとと
もに.具体的にその責任ことができるよう必要な仕組
みを構築すること。
特に施設の指定管理者である祉会福祉法人 海南市
社会福祉事業団に対する海南市の管理監督が十分機
能できるようにすること.また、指定管理者において
施設の管理運営が十分機能するような取り組みを行
うよう指導すること、その内容が確認できる資料を
提出すること。
という内容で勧告を受けていますね、
そこで質問ですが
この勧告に対して市はどのような対処、どのような改善をされ
たのでしょうか
(4)虐待防止委員会の職員との面接について
平成25年5月30日 南風園虐待防止委員会の正副委
員長名で南風園理事長あてに南風園職員との面談の結果内
容についての報告書が出されていますが、これについて市
はどのような指導をしたしょうか
1、
海南市社会福祉事業団について。
(1)
南風園の利用料金制と白寿荘の経理上問題について。
南風園の利用料金制になって以後議会でこの問題について質
疑をしようにもお伺いする項目がなく、まさに5年に1度の指
定管理の契約時か一般質問でしかチャンスがありません。よう
する議会のチェック機能が果たせない状態であります。
この際、もとの指定管理料金制にもどすか、他に何か方法があ
ればいいのですがいかがでしょうか。
また、白寿荘は指定管理料金制になっており、同じ海南市社会
福祉事業団が指定管理受けており経理は事業団として行われて
おります、したがって役員報酬はすべて 南風園から支払われて
おり白寿荘には役員もおりません、ようするに経営者いない状態
であります。このことについてどうお考えでしょうか
H25年6月議会一般質問(予定)
質問 1、防災対策について
防災対策では、 過去5回質問して参りました。今回は6回目
です。なんどやつてもすっきりとした答えが得られない。
前回は、防災対策の質問はこれで終わりにしたいとの思いを
込めて、お伺いしましたが。残念ながらかみ合わないまま終わ
ってしまいました。
その後、私の質問について、危機管理課において県との協、
学者のかたがたとの協議を踏まえある程度の答えを示していた
だき、未だ意見の食い違いはある者のおおむね理解をしており
ますので、今回はそれらの問題には触れず、新たな問題につい
て、又、直立浮上式防波堤についてお伺いをしたいと思います
1-1 岡田地区の浸水について。
質問 ことし3月末に県から公表された市町村別の南海トラフ巨大地震に
よる津波浸水想定図を見て、これでは絶対に理解できないし、放置
すべきではないとの思いから質問をさせていただくものであります。
海南市の津波浸水想定図によりますと、亀川地区は全区津波浸水
地域外となっています。本当にこれでいいんでしょうか。国の想定の8
メートルという津波高さから考えても、私はこの8メートルはそうは思
っておりませんが、多田、且来、小野田は亀の川の遡上はあるとしても
大丈夫でしょう。しかし、室山、岡田地区はそうはいかないのではない
でしょうか。
なぜ、県は室山、岡田地区を浸水区域に入れなかったのか。県が
やらなければそれでいいというものではないと考えています。危機管
理課自身大した問題でないと考えているのですか。
答弁 しかしながら、今回公表された津波浸水想定では、河川の幅が広く
比較的規模の大きい亀の川は津波の遡上に関する計算はされてお
りますが、大坪川のような小規模の支流河川については、必ずしも
津波の遡上は計算されていないと聞いてございます。また、浸水想
定図では、岡田地区の亀の川周辺に一部わずかな津波の遡上によ
るものと思われる浸水域の表示が見受けられます。
このような状況から、議員御指摘の亀の川の水位より大坪川の水
位が2メートル低いことを考え合わせると、津波の大坪川の遡上によ
る岡田地区の浸水はないとは言い切れないと考えてございます。
市としましては、今回の津波浸水想定図の留意事項として示されて
いるよう、岡田地区に限らず他の地域においても、浸水想定区域外
であっても、浸水が発生したり、実際には水位が変化したりする場合
があるということを踏まえ、岡田地区の住民の皆様初め、市内の浸
水想定区域付近の地域の皆様には、想定にとらわれず津波からの
迅速な避難を心がけるよう啓発してまいりたいと考えてございます。
なお、亀川地区には、今年度市の職員が地域に入らせていただき
、防災に関する研修会、ワークショップを開催する計画でありますので
、その際にも岡田地区の皆様含め、地域の皆様と津波浸水対策に
ついて一緒に考えてまいりたいと考えております。
再質問 私たち、1番に登壇した磯﨑議員もおっしゃっておりましたが、東北
の津波の場所を見てまいりました。また、いろんなネットでも検証をし
てみますと、宮城県では、津波の高さ3.6メートル、3.6メートルでも中
小河川、小さい河川であっても3キロから6キロ遡上してるんです。そ
れで、水があふれて被害が出てる。
これは、我が海南市に当てはめますと、大坪川の河口まで、毛見の
、海岸から河口まで2キロです。河口から黒江駅の東側に700メート
ル、2.7キロということになります。 7メーターの津波は当然遡上し
てまいります。そして、大坪川、やっぱり亀の川より小さい、半分
以下でしょう。しかし、特殊な地形になってますので、川そのもんが小
さいけれども、海抜2メーター、あるいは3メーターの畑とか田んぼ
とか、広がってます。亀の川の堤防と、片や山の間を大きな川のよう
に広がっている。そこへ流れ込んでくると、私は言うてるんです。そうす
ると、シッキ団地で、それでも海抜4メーター、大坪川は最終フタツ池
まで突き当たります。ですから、シッキ団地で4メーターですから、7メ
ーター来ると、少なくとも1階が沈んでまうぐらいの、3メーターオーバ
ーするような水になる。 そのことを考えると、やっぱり県が計算に
入れておりませんからと、言うだけで済ませるわけには、私はいかな
いと思います。
私は常々これまでの質問でも申し上げてきたのは、いろいろな問題
、海南として、海南市の危機管理課としてこれをどう捉えてるかという
ことが大事じゃないかと、いつも言うてるんですけど、そのことについ
ては全く答弁が返ってこない。
課長は、市内の浸水想定地区付近の地域の皆様には、想定にとら
われず津波からの迅速な避難を心がけるよう啓発してまいりたいと言
ってますね。ところが、市民の皆様が目の前に津波想定図を見て、
浸水区域はここまでですよとあらわされた津波の想定図を出されて、
説明する課長が、いや、ここまでになってますけど、それは違います
よと、理解してもらえますか。岡田の人に、全く白で、浸水地域は全くな
い地図を示して、それでも可能性はありますよという説明するという
のは、理解してもらえますか。
その点について、お答えをいただきたいと思います。
答弁 東北の津波の検証から、岡田地区は100%浸水すると考えるかど
うか、また、県が岡田地区の浸水を認めないからといって、そのまま
でいいのかということでございますが、津波の浸水についてはさまざ
ま考え方がございますが、市では、浸水の有無やその確率につい
て、判断できる材料それからノウハウともにない状況であります。
したがいまして、市としましては、県の浸水想定図に岡田地区が含
まれていない理由を県に伺い、今年度亀川地区で計画している研修
会等においても、地域の皆様に御説明をする必要があると考えてお
ります。
次に、県の浸水想定図が出されると、岡田地区の皆様は大丈夫と
認識されると思うがいかがか、ということについてでございます。
今年度、本市において作成する市の地震津波ハザードマップは、
県が公表した津波浸水想定図をもとに作成することとなります。一般
的に、地震津波ハザードマップは県の津波浸水想定図と同様に、津
波浸水想定区域を何らかの色分けをして表現することから、例えば、
津波浸水想定区域外を色なしの白とするならば、室山、岡田地区は
白で示され、津波の来ない安全な地域と捉えられてしまうおそれがあ
ることは認識しております。
そのため、市としましては、今年度ハザードマップを策定するに当た
って、浸水想定範囲はあくまで想定の結果であって、決して安全が保
障されるものではないことを明確に示し、わかりやすく表現する必要
があると考えてございます。
その表現方法について我々職員が知恵を絞るとともに、ハザードマ
ップを作成するに当たって、専門的なノウハウを用い、先進事例の知
識も豊富に持つ専門業者の力も活用して作成するよう現在準備を進
めているところでございますので、御理解くださいますようお願いいた
します。
再々質問 ノウハウがないとか知識がないから県の言うとおりにせなあかんとい
うことだと思うんですよね。 私は、別にノウハウがなかっても、今ま
での経過とか実績とか踏まえれば、ある程度予測もつくし、常識で考
えても判断できることがたくさんあると思うんです。そこに全く踏み込
まない姿勢こそ、問題やと、私は言うてるんですよ。
津波で、ここは津波が来ますよと言うてるところは訓練も積み、いろ
いろやって、ある程度対応できます。しかし、ここまでしか津波が来ま
せんよという近辺の住民の皆さんが一番危ないんです。だから、その
点を、海南市としての考え方をきちっと持って、こうだと示して頂きた
いのです。
市民の皆さんは、地震津波ハザードマップでは岡田地区は浸水想
定区域外であるがでも実際には津波がくる可能性がありますよ、と言
うだけで、あんたの言ってること正しいなと、理解できますかと。何か根 拠示さなければできないでしょ。
そこで私が言ってるのは、こうしなさいと言うんじゃないですが。一つ
の例として挙げると、前回の想定では、串本で9mの津波が海南市で
は5.9メーター、減水率から言うと65%、ね。そして、実際に東北の地
震で串本で1.4m、海南市では90センチ。これもそのとおりの減水率で 67%、そして、今回の想定では、串本に到達する津波は18.8mと倍
に上がってる。にもかかわらず、海南市に到達する津波は8m、43%
、想定の差が出てるわけです。それはそれで仕方ない、悪いと言うて
ないですよ。ならば、18.8mの津波に対して65%を想定したら、最大
値約13mというのが出てくるでしょう。
県の想定では8mであるけれども、ひょっとすれば、実績に照らし合
わせれば、13mの津波が来るかもわからない。13mの津波と言えば
どこまで来るかわかりますか、何遍も問うてますけど。大体海南市全
域において、今の高速道路の近辺が14から13、海抜。だから、高速
の西については、最大値13mということになれば、津波はここまで来
ますよという形で示せば、県の浸水想定図が8mであっても、皆さん
に理解をいただくことができると、私は思てるんです。
ですから、何遍も言うようですが、海南市としての考え方を市民の皆
さんに示した上で対策を考えなきゃだめだ、そういうことを言うてるわ
けです。理解いただけましたか。
答弁 本市独自の考え方を持って対策を立てる考えに立てないかということ
でございますが、先ほど危機管理課長が答弁させていただきました、
津波による岡田地区の浸水予想の件につきましては、県が一定の
基準に基づいてハザードマップを作成し、浸水区域を色分けしている
ところでございますが、議員御提言の趣旨というのは、市民の皆様の
安全を本当に考えるならば、県は県として、海南市として独自に最大
限の津波を想定し、どこまで浸水する過疎の最大値を把握し、何ら
かの方法で住民にそれを周知できるように準備しておくことが必要で
はないかとのことであろうかと思われます。
危機管理課といたしましては、県のハザードマップを生かしながらも
、今回のような特殊な地形を持ち合わせたこの岡田地区において、
市として独自の津波高や浸水区域の設定というのは、先ほども言わ
せてもろたように相当に難しいものと思われますが、今後、議員提言
の趣旨を踏まえまして、もう少しお時間をいただきながら最大限の努
力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解のほどお願
いします。
まだ考えてもないくらいやって、問うても始まらんので、どうぞしっかり考えてください。
しかし、もうつけ加えて申し上げておきますと、亀の川と岡田の黒江あたりの水位が2メーターあるんです、両方とも満杯になったときね。で、津波でなくても、亀の川満杯になれば2メーターの落差があるんで、逆流してくるんです。それについては、市長から知事にもお願いしていただいて、逆流防止のゲートあるいはポンプ場、河口に設けていただきたいという話が進んでおります、おかげさまで。この間の知事の報告会でも、もう用地は確保したという報告を知事からいただいております。
それ、海に向かって流れる水でも岡田のほうへ逆流してくるんですよ。海から押してくる水は絶対入ってきます。その辺のところをきちっと。それはもう水の調査で建設課がいろいろやった結果が、そういう形であらわれてくるんやて。市の中で連携をしておるなら、そんなこと私が言わいでも、いっぺでわかるはずです。津波だけやない、そういう浸水もありますよというのは、もう把握してなけりゃ、危機管理室はだめでしょ、違いますか。
だから、これから考えてくれるのもいいですけども、言われてやるよりも、もっとしっかり考えなさいよということを申し上げておきます。
1-2 防潮堤について。
防波堤についても、前回、本当に大丈夫なのか、8メートルの津波に対してどんな役割を果たすのか、どの程度効果があるのかといったことについて質問させていただきましたが、納得できる答弁はいただけませんでした。今回は、具体的に心配している問題についてお伺いします。
防波堤の内にも外にも停泊している船、あるいは係留している小型の漁船、プレジャーボートなどについて、津波警報が出た場合、この対策は考えておりますか。
中項目2、直立浮上式津波防波堤についての浮上式防波堤可動時における船舶の動き、その対処方法についてどう考えているかについて御答弁申し上げます。
国の和歌山下津港海岸(海南地区)直轄海岸保全施設整備事業において施工が進められております直立浮上式津波防波堤は、世界初の航路上に浮上し設置されるという防波堤という特殊性から、海上防災対策及び船舶航行安全対策の観点より、当該海域を利用する船舶事業者等の関係者との間で、直立浮上式防波堤の可動時のさまざまな運用ルールを定める必要があると認識してございます。
これらの運用ルールを定めるについて、海南地区津波浸水対策に係る可動式防波堤の運用検討委員会を、国土交通省近畿地方整備局和歌山港湾事務所、和歌山海上保安部、和歌山県で組織し、運用ルール策定に向け、検討を開始しており、昨年3月には、関西電力、新日鉄住金、和歌山石油精製ほか、海域を利用する関係者による意見聴取会を開催したところであります。
また、本年3月28日に実施しました浮上式防波堤実証実験にて得られた浮上にかかる時間などのデータ初め、今後工事の施工とともに得られるさまざまなデータをもとに、津波発生時における浮上式防波堤可動に関する船舶への情報伝達の方法や、航行進路選択のタイミングなど、運用ルールづくりに向け検討を進めていくところであります。
市としましては、津波発生時に直立浮上式防波堤の可動に、船舶による支障が出ることのないよう、国・県等関係者に働きかけてまいるよう考えてございます。
以上でございます。
防波堤は、今、いろいろ研究しながらやっていただいてるということですけど、私が一番心配なんのは、この前の東北でもそうですけど、船の問題です。
防波堤の外の船、中の船。防波堤は引き波のときには引くように、穴があけてますわね。当然引き波の強い力がどんと引き寄せます。そのときはもう防波堤が立ってるわけで、そこに船が当たったり、あるいは漂流物が流れた、あの間へ挟まったらどうなるんよと。
課長は、いろんな、海南市からそういう検討会議へ提案していきたいと、言うてくれました。これは当然です。当然ですけど、提案するについて、この船の問題はこうしてほしいんですよというもんを持ってないと、何を提案するんですか。何にも持ってなしで、やってください、やってください、そんなことよそ行って通りますか。
だから、さっきから言うてるように、海南市としてそれぞれの問題について、市としての考え方を確立しなさいよということを、今言うてるんです。そのことで、再質問に入ります。
これを、今言うたように、海南市は、これも考えてないんでしょうから、どうもこれから考えるんでしょうけれども、やっぱりその辺について、同じことで、海南市としてこの問題についてどう考えてんのよというのをいっぺお聞きしたいんです
浮上式防波堤の船舶の対策に関し、海南市としてどうあるべきかの考え方については、津波来襲時に浮上式防波堤の可動に支障が出ることのないよう、まずは海岸法の定めにより、浮上式防波堤を含む海岸保全地域の管理者である和歌山県を中心に国土交通省近畿地方整備局和歌山港湾事務所や和歌山海上保安部の3者で構成する運用検討委員会にて、運用ルールの作成を進めていただきたいと考えております。
市は、本運用検討会において、主たる関係者として参画を求めるものとするとされておりますので、必要に応じ運用検討会での意見聴取会で意見を申し上げていきたいと考えております。
なお、市としての考えを述べるに当たってですけども、まずはプレジャーボート等について庁内管理下初め関係各課と、係留のあり方であるとかそういうことを検討して、懸念されることについて意見を述べていきたいというふうに考えております。
これもやっぱりまだ全然考えてないということだろうと思いますけど、意見聴取会で意見を申し上げ、一番中心になる関係者、だったら、その意見を申し上げる意見というのはどんなことよというのは考えてないということですね、まだ。
やっぱりそういうことは、きちっとやっぱり持ってないと、幾ら立派な検討会で呼び出し受けて意見を聴取していただいても、何もならないじゃないですか。海南市指定でこうしてほしいんやというもんを、やっぱりきちっと持つべきじゃないですかね。これも、もう言うときます。質問しようと思たけど、やめました。
質問 2、 医療センターの苦情について
1-1 自動精算機について。
1-2 受け付け体制について
1-3 玄関での障害者の問題について。
1-4 救急の問題について。
H24年12月議会一般質問
防災対策では、平成19年6月議会、平成22年6月議会、平成23年6月議会、平成23
年12月議会と過去4回質問して参りました。今回は五回目です。なんどやつてもすっきりと
した答えが得られないのは私の質問がまずいからでしょう。
そこで今回は、防災対策の質問はこれで終わりにしたいとの思いを込めて、ここが聞きた
いという点にしぼってお伺いします。
これまで海南市地域防災計画による、震災対策、津波対策、水害対策、実際にこういった災
害に見舞われた際、どう対応するのか、どう行動するのかといった計画や災害時の行政機能に
ついてお伺いしてまいりました。
東海、東南海、南海という3っの大きな震源が連動して起こる可能性が非常に高いと言われ
ております今日、仁坂吉伸知事も「3連動(東海・東南海・南海地震の)が来るだろうと和歌
山県では想定のもと対策している。我々が急ピッチで進めている対策が間尺に合わなかったら
困る。これからは、全体的に再検討しないといけない」とコメントしております。
当然本市においても今後起こりうる東海、東南海、南海の連動型地震の最悪の事態を想定し
、地震、津波対策において見直さなければならないし、少なくとも想定外の被害を起こさない
よう取り組まなければなりません。
さらに、最近の研究では震源地が3カ所であったものが1箇所増えて4カ所が連動するとも
言われており、そうなってくると当然、今回の東北太平洋沖大地震は連動型の地震で記録され
た、マグネチュード9.0を少なくとも想定した対応をしなければならないのではないでしょ
うか、以前は串本あたりの波の最高値は、8.8m海南市冷水では5.9mと想定されていま
したが、現在では串本で18m、海南市冷水で8mと想定されています。
私は、この8mという想定地に疑問を持っていますので、今回の質問はこのことを基本にし
ていきたいと思います。
質問 1、本市の防災対策について
1-1 津波対策について
1、 8mという想定高さについて
今回の東日本太平洋沖の大震災では、過去の震災で非常に大きな津波の経験がある
にもかかわらず、くにが作った低い想定に沿った対策を立て訓練をしてきた結果が大
きな被害、大勢の犠牲者を出す結果となり、国は想定外の一言ですませてしまいまし
た。
東海、東南海、南海の連動型地震に対しても見直しを行い当地方で8mと
いう想定高さを出してきましたが、この想定値をどうお考えでしょうかにつ
いて当局は、また、8mという想定値が出されて以後の対策、訓練はどうか
わりましたか。
2、
防潮堤について
約250億円もの大金をかけて建設中の防潮堤、世界でただ一つの浮上式とびらの
防潮堤、8mの津波に対してどんな役割を果たすのでしょうか、国は津波の時間少
し遅らせ、強さを弱くするとしていますが、どの程度効果があるのか検証していま
すか、また、市民の皆様への説明はできていますか。
1-2 津波避難訓練について
1、本年度の市の避難訓練について
11月18日に市の避難訓練が実施されましたが、全市一斉の訓練とお聞きしてい
ますがどのような想定で実視されたのですか。
海南市が想定している津波浸水地区の範囲はどうなっていますか。
津波浸水地域とそでない地域の訓練の状況は。
2、想定高さがかわって、避難訓練はどう変わったか
1-3 市民病院と黒江中学校の新校舎の津波対策について
1、津波対策はできているか
地震対策は十分対処できているようですが、津波対策はできていますか
2、免震構造は津波に対してはどうなのか
よく考えてみると免震構造というのは簡単に言えばゴムの上に建物全体が乗ってい
る 、いわゆる基礎と建物が直接つながっていない構造になっている様ですが、横
からの津波の力に対してはどうでしょうか。
シュミレーションや、構造計算に基づく被害の想定はできていますか。
H24年6月議会一般質問
1、小学校卒業するまでの子供の医療費無料化について。
2、南風園の問題について。
 H23年12月議会一般質問
H23年12月議会一般質問 実際に大規模な津波が来ていたらその被害は計り知れないものとなっていたと思います。被害を
最小限に抑えるためには何よりも津波から逃げ切ることであり、そのためには、津波に対する知識
と避難意識が大切であり、現在進めている一次避難場所の見直しについて地域と一緒になって協議
し、その結果を地域住民に周知、啓発をおこなうとともに、地域における津波避難の取り組みの強
化、警報時における防災行政無線の緊急性のある放送内容への改善を行って参りたいと考えており
ます。
まず市民が津波から逃げ切れるよう安全な津波指定ております、一次避難場所について、標高や
広さの確認、土砂災害などの危険性、一次避難場所からより高い所への移動は可能か二次避難所へ
の移動 が可能か、避難経路につきましては幅員や周辺建物の倒壊はないかなどの安全性について
建設課とともに点検及び見直しを行い、改修や整備が必要な場合は今後対応してまいりたいと考え
ております。また改修対応が出来ない避難場所や標高の低い避難場所でより高い所に行けない避難
場所については指定を取り消す予定であります。
また、一次避難場所や避難経路など津波避難につきましては、市民の皆様が津波から逃げ切れら
れるよう、地域の自主防災組織、自治会とともに、一次避難場所、津波避難ビルの指定、避難経路
、避難経路への海抜表示等について協議をしてまいりたいと考えております。また、避難生活を送
る二次避難場所につきましては、津波浸水予測範囲の外で標高等が十分でより安全な所に位置する
場所を指定してまいりたいと考えているところでございます。
前回の質問では、再質問で、それをどう市民の皆様に理解して頂けるか、また、避難勧告、指示
についてもどうまもっていただけるか、その対策は。とお聞きしたのですが、見事に無視されまし
た。しかし、このことにきちっと対応しなかった私の責任だと思います。従って今回はそのことも
含めて再度その後の対応についてお伺いします。
1-1-1 一次避難所の見直しの現状は
1-1-3 地域の皆様とどんな協議を行ってきましたか、そしてそのメンバーは
1-2、来るべき東海、東南海、南海地震による津波対策について
この問題について6月議会での答弁では
東日本大震災後、本市における災害対策については、全面的に見直さなければならないと考えて
いるところですが、基本となる津波想定や浸水域の見直しは、国の中央防災会議による見直しが行
われている中で、市としましても、国の見直しに対応してまいりたいと考えてでございます。その
ような中で、市としましては、短期的な取り組み、予算措置が必要な中期的な取り組み、国の被害
想定に対応した長期的な取り組みを行っていかなければならないと考えているところです。
との答弁でありました。このことをふまえてお伺いします
1-2-1 国の見直し結果が出るまでの対策はどうなっていますか
1-2-2 短期的な取り組み、中期的な取り組みの内容は
1-2-3 現在建設中の防潮堤はこのまま続けるということですが、東日本大震災と同程度の
津波に遭遇した場合の対策と住民への説明は
1-3、津波対策上の消防団員の行動について
1-3-1 東日本大震災のような津波に遭遇した場合、消防団員はどのような対応をすべきとお
考えですか。
1-4、自主防災組織の補助金について
東日本大震災以後津波避難対策を考える、上で自主防災組織の役割が非常に重要になってきています、当局
の答弁を聞いても自主防災組織という言葉が頻繁に出てくることからも、その重要性が伺えます。
先の6月議会においても、自主防災組織への補助金について見直しの提言をしておきました。差のことについて
お伺いします。
1-4-1 その後、自主防災組織への補助金について見直しは進んでいますか。
2、第一次海南市総合計画にかかわって
2-1、本市の人口減について
海南市総合計画、基本構想では目標人ロについて、
人ロ推計の結果を踏まえ、多様な子育て支援や福祉サービスの充実などの少子高齢化対策また生活基盤や広:域
交通網などの都市基盤の整備、さらには若者の定住促進につながる企業誘致や快適な住環境の創出、人ロ減少が
顕著である中心市街地の居住環境の整備など、快適で安心して暮らせる環境づくりを推進することで、人ロの定着に
努めます。
これらの施策を総合的かつ一体的に展開しつつ、人ロの減少に歯止めをかけることによって達成される目標として、
平成28年における海南市の目標人ロを55,000人と設定します
人ロ減少、特に若年層の減少が進めば、労働人ロの減少、地域社会の活力低下や、し高齢者の生活を支える若年
層への負担拡大、さらには税収の減少など、さまざまな課題が顕在化}してくるものと予想されます。}
若者定着を進めるためには、企業誘致や雇用増進などによる就労機会の確保、住環「都市機能や子育て支麟の
充実を図るとともに・豊かな自然環境など本市固有の地域資源を活かした地域の魅力向上や、楽しめる場の創出
など、若 い世代が豊かに、楽しく暮らせる環境整備が必要となってきます。さらに、人ロ減少に歯止めをかけるため
には、子どもや高齢者、障害者等にやさしいまちづくりなど住んでよかった、住み続けたいと思える魅力的なまちづくり
も必要となります。
地域の個性や強みを活かした賑わいと魅力あるまちづくりが求められています。特に本市の地勢や自然環境、交通
の利便性、また数多くの歴史的遺産等を一体的に捉え、保全・活用していくことで、交流人ロや定住人ロの増加を
促し、市民が誇りと愛着をもつことができるまちづくりを進める必要があります。
以上のような基本理念に基づき前期本計画に基づき今日まで人口減少を食い止めるべく様々な事業を展開してきた
わけですが残念ながら予想を上回る人口減少を招いてしまいました。
2-1-1 なぜこのような結果を招いたのか、後期基本計画を立てるに当たってどのような検証をされた
のでしょうか
2-1-2 「基本施策市民防災力・地域防災力の強化」の成果指標で地域防災訓練および防災講習等へ
の参加率目標値を10%としているのはなぜか。
大津波警報時の避難指示人口が20,000人にも上る割には10年後(五年後)の目標値とし
ては非常に低いのでは。
2-2、本市の職員削減について
2-2-1 いただいた資料によると、職員数(市長部局)はこの5年間で70名の減となっていますが、臨時
職員が27名、嘱託殖員が 8名、合計57名となっており、35名しか減っていないということに
なる、もちろん正と臨時では費用は3:1ということはわかっていますがしかも臨時職員、嘱託
殖員の仕事量もほとんど正規職員と変わらない現状からして、本市の職員が異常に多いといわ
ざるを得ない。このことについてどう思うか。
3、事業仕分けについて
先日、事業仕分けの資料を見せていただきますと、巷で来年から中止らしいといわれている、
農林水産祭りと市民総合体育大会が仕分け事業の中に含まれているではありませんか。私的に
申し上げると何でこんなことをするんや、仕分け人や一般判定員の皆様に失礼やないか。
3-1、農林水産業祭り、市民総合体育大会についてどうお考えですか
H23年6月議会一般質問
質問にはいる前に、今回の東日本太平洋沖大震災により、
亡くなられた皆様のご冥福をお祈りし、被害に遭われた
皆様のお見舞いと一日も早い復興をお祈り申し上げます。
1、大丈夫か我が市の防災対策(パート3)
平成19年6月議会、平成22年6月議会で、海南市地域防災計画による、震災対策、津波対策、
水害対策、実際にこういった災害に見舞われた際、どう対応するのか、どう行動するのかといった
計画や災害時の行政機能についてお伺いしてまいりました。
今回は去る3月11日に東日本太平洋沖で起こったマグ二チュード9.0という大地震、三つの震源
が同時に活動するという想定外の大地震に加え、 国内で過去最大と言われる明治三陸大
津波を超える大津波が発生し、想像を絶する被害であったことはすでに皆様ご承知のことと思います。
我が和歌山県にとっても人ごとではありません、東海、東南海、南海という3っの大きな震源が連動
して起こる可能性が非常に高いと言われております。そしてこのような連動型地震が起こるとすれば、
今後30年以内に87%の確率で発生すると予測されており、先日、管首相もこのことを受けて浜岡原発
の運転停止を決断したと言われております。
仁坂吉伸知事も「3連動(東海・東南海・南海地震の)が来るだろうと和歌山県では想定のもと対策
している。我々が急ピッチで進めている対策が間尺に合わなかったら困る。これからは、全体的に
再検討しないといけない」とコメントしております。
今回の東日本太平洋沖大地震は連動型の地震が起こるとすればマグネチュード8.6と想定されて
おり、これを超える大地震であった言われております、地震の大きさはマグネチュード0.2ごとに2倍
の大きさになると言われておりますから、まさに想定より4倍の大きな地震あり、津波であったと
思われます
当然本市においても今後起こりうる東海、東南海、南海の連動型地震の最悪の事態を想定し、
地震、津波対策において見直さなければならないし、少なくとも想定外の被害を起こさないよう取り
組まなければなりません。
すでに、海洋研究開発機構や東京大、京都大、名古屋大などが参加する「東海・東南海・南海
地震 の連動性評価」が成果をまとめた、そのメンバーでもある東京大学の古村教授は、東海、
東南海、南海の連動型地震についてマグネチュード8.9と予想しており、現在想定している8.7
に比べて倍の大きさの津波になると予想しております。
河田恵昭・関西大学教授(巨大災害)は防災の立場から「東日本大震災の大きさを直視す
べきだ」と言う。「過去のデータを解析する従来の方法論では、それ以上の地震が起きたときに
通用しない。物理的にどこまで大きな地震が起こりうるか。そこから考えるべきではないでしょうか」
とも言っておられます。
さらに、最近の研究では震源地が3カ所であったものが1箇所増えて4カ所が連動するとも言
われており、そうなってくると当然、今回の東北太平洋沖大地震は連動型の地震で記録された、
マグネチュード9.0を少なくとも想定した対応をしなければならないのではないでしょうか
ただ、国、県においても東海、東南海、南海の連動型地震についてはこれから見直しをしていく
のでしょうから、今回の質問ではその詳しい数値や、防災計画の見直しについて質問してもおそらく、
国や県の考えがでていない間はまともな答えが返ってこないと思います。
そこで、今回の東日本太平洋沖の大震災の現状を踏まえ、仮に東海、東南海、南海の連動型
地震がマグニチュード9.0と仮定すると、今までの想定ではマグニチュード8.7でありましたから、
串本あたりの波の最高値は、8.8m海南市冷水では5.9mと想定されていましたが、マグニチ
ュード9.0となると津波の大きさが3倍になると言われていますから、串本では26.4m、冷水では
17.7mとなります。
従って今回の質問は15mの津波高さを想定して質問をいたしたいと思います。
また、大津波警報が発令されてからの本市の対応をも考えながら、今の時点で本市の防災
計画について、どう考えているのかについて、お伺いして参りたいと思います。
尚、今回は私の前に7人の議員さんが、質問され、そのうち5人の議員さんが
防災対策について質問しております。
従って私としましては、重複はさけて、前の議員さんへの答弁も踏まえてお伺い
したいと思います。
尚、ご答弁いただくそれぞれの立場で今回の大震災をどうとらえたか、感想をお聞きしたいと思います。
1-1 まず、今回の東日本太平洋沖の大震災の現状を見てどのように感じましたか。
とくに、津波発生時の避難誘導、避難、第一次、第二次避難所の問題、行政の対応、津波から
今日までの行政のあり方、等について。また、津波の大きさ、高さ、速度、遡上は
1-2 本市においても東北太平洋沖の大震災による津波警報を受けて、防災計画に基づき対応された
と思いますがその結果について検証しましたか。
1-3 市役所及び行政機能について。
今回の東北太平洋沖の大震災ではマグネチュード9.0と言う大地震の上、被害の大きかった
岩手、宮城、福島三県の三陸海岸では軒並み20メートル以上の大津波に遭遇し、未曾有の
大被害に遭われました、中でも被災地のほとんどの市町村の行政機能が失われ、被災者の確認
や、義援金や支援物資の配布、復興計画の遅れ等に大きな支障をきたしていることはご承知の
とおりであります。
このことを本市に置き換て見た場合、人ごとではありません。
お伺いします、以前の質問でもお伺いしましたが震度6以上で15メートルの津波が押し寄せた場合
我が市役所はどうなりますか、そしていかなる場合においても行政機能を維持するための対応は
できていますか。
1-4 消防本部とその機能について。
我が市の防災拠点でありますこの建物、震度で15メートルの津波が押し寄せた場合は
どうなりますか、今回の東北太平洋沖の大震災では、宮城県南三陸町の総合防災庁舎(鉄骨
3階建て)が骨組みだけになった映像が良く流れていましたが同じような、ことになりませんか

1-5 市民病院について。
平成25年4月に開院予定の新市民病院、今、市民の皆さんの間では、地震については大丈夫
であろうが、15メートル以上の津波にはどうであろう、たとえ建物は健在であったとしても、5階
まで被災すればすべての医療器具が破壊され、病院としての機能が失われ震災時の医療機関と
しての役目を果たせないのではといった心配の声が各地で聞かれます。このことについてどの
ようにお考えですか。
1-6 避難及び避難所について。
・ 大津波警報よる避難指示と避難所について、避難指示を徹底するための本市の対応は。
結果避難したのはわずか5百数十人であったそうですが、本番でこのようなことでは、被
害は計り知れないものになると思いますがいかがでしょうか、また、その対策は。
・ 今回、避難所として指定された避難所に一部、津波の可能性のある場合は開設しないと
海南市地震ハザードマップに決められている避難所を開設していましたがどうしてですか。
・ 大津波警報、避難指示が解除されないまま、夜に避難所が閉鎖された理由、そして翌日
開設された理由を教えてください。
・ 津波に関わる一次、二次避難所みなおしについての考えは。
・ 学校、幼稚園、保育所の津波に対する避難計画は、そしてその訓練は
・ 今回の大津波警報よる避難指示に関係する自主防災組織に対する情報の伝達、や自
主防災組織の活動はまた、組織強化への対策は。
1-7 海南市津波ハザードマップについて、
・ このハザードマップを見ると浸水高さは津波の高さから標高を減じた値を当てているようです
が、津波の遡上を考慮に入れていないのはどういうことでしょうか。
・ 亀川地区は、津波の対象外となっていますが、東北太平洋沖の大震災による大津波を見る
と、無関係と言いきれないと思いますがいかがですか
・ 津波による河川の遡上について、全く考慮されていませんが、どのようなお考えでしょうか
1-8 液状化について
東海、東南海、南海の連動型地震の際の本市の液状化について想定と対策は。
1-9 地震による、ダム、ため池の被害想定と対策は。
1 緊急整備・早急整備の対策が必要と判断されたため池を対象として、順次整備
改修を進めて行きたいとのことですが、鳥居地区の慶権寺池、九品寺地区の新
池以外の対象となる池はありますか。
この質問についてはカットします。
2 3月11日、東日本大震災により、福島県須賀川市において、藤沼ダムの土堰堤
が決壊し大きな被害が発生している。海南市にあるため池も、ほとんどの池は土
の堰堤でできているが、この藤沼ダムの決壊の件を市はどのように捉えているのか」
3 少なくとも震度5以上の地震発生時には即座に池の状態を確認しなければいけ
ないと思いますがその対策は。
基本計画(案)についてこの問題についてはこれまで何回か質問して何回もお伺いをいたしました。
その結果、平成19年、20年度と2年間を費やして計画案を立て、21年度に国の
認定を受けるべく取り組んできたが、結果としてココの再建のめどが立たず、駅前
6商店街が何もせず、国からもそのことを指摘され、国の認定を受けられなかった
のが現状であり、市としてはココが再建され商店街が活性化に向けて気運が高まる
まで市の事業だけ進め、国に申請するチャンスをまつという考えであるようです。
私はいつまでも待つというのはいかにも商店街任せで無責任ではないか、せめて
期限を切って対応してはと提案しましたが市は考えを変えようとはしませんでした。
今日に至るまで同じ状況が続いているわけですが、ただココの状況が、RVFから
ココ商店組合が権利(転抵当付)を買い取ったことで、幾分、情勢も変わってきて
いるのではないかと、考えているところであります。そこで現在の中心市街地活
性化への取り組みの現状を再確認し、いくつかの問題点についても、お伺いをいしたいと思います。
1 現在の状況をどう見ているのか
中心市街地活性化を実現するためには、市の考えとしてはまずココにおいて
オークワが再開発をし、ココの再整備の見通しが立ってくれば、商店街の機運も
高まっていくのではないかとのようですが、商店街自身もまず、ココ
ありきのようお見受けします。いかがでしょうか。
2 街づくり海南と商店街の取り組みと姿勢は
以前から、市の答弁をお伺いしていると株式会社「まちづくりかいなん」という会社は
駅前6商店街と同格の立場としてしか受け取れないような感じがするが、定款を
見せていただくと海南市全体の商店街のまとめ役的な存在に見えてきます。
本当はどうなのでしょうか。このことをふまえてお願いします
3 オークワの再開はあるのか、オオクワとの協議は
RVFからココ商店組合が権利(転抵当付)を買い取ったということで事情
が変わったのでオークワの意向はどうかと特別委員会でお伺いしてもたしかな
返答はいただけなかった、本当はどうなのですか。
答弁 (産業振興課長(橋本正義君)
大項目1、中心市街地活性化基本計画案についての数点の御質問に御答弁させていただきます。
まず、中項目1、現在の状況をどう見ているのかという御質問でございますが、中心市街地
活性化基本計画の認定に至らなかった要因として、国からはココの再整備と商店街が推進
する事業が不足していることを指摘されております。ココ周辺の商店街はもともと最寄り品を
扱うジャスコやオークワと共存共栄を図っていくため、ジャスコやオークワにはない体回り品
を扱う専門店街として形成されたもので、集客性の高いジャスコやオークワで買えない商品
をカバーする商店街だったとも言えます。
つまり、専門店街である商店街だけでは集客が難しく、中核となる商業施設が必要でありま
すが、なおかつ商店街への誘客を図るためには、中核商業施設と連携しながら商店街自体
が魅力を向上させていく必要があり、商店街独自の取り組みが重要となります。また、ココの
再整備においても企業単体の取り組みではなく、行政、商店街、地域住民も連携し海南市の
中心市街地にふさわしく、地域住民に愛される場所にしていく必要があります。したがいまし
て、商店街がココに依存するのではなく、ココ再整備による集客効果と商店街の魅力向上を
図る取り組みが同時に重要であると考えております。
次に、中項目2、まちづくり海南と商店街の取り組みと姿勢はとの御質問でございますが、
中心市街地の活性化を推進する上で、株式会社まちづくり海南が中核となって、各商店街
と連携しにぎわいを創出する取り組みを推進していかなければなりません。株式会社まちづく
り海南は、中心市街地活性化法を根本として平成14年に策定された海南市中心市街地活性
化基本計画に基づき設立された第三セクターのまちづくり会社であり、まちづくり事業を計画、
推進し、商店街組合事業の支援、調整を行っていくものであり、当初は市民の交流の場を整
備、運営する事業や、テナントミックス事業などのまちづくり事業を計画されておりましたが、
JR高架下の駐車場管理海南市物産観光センターの管理運営が主体となり、その他のまちづ
くり事業が進行していないというのが現状であります。しかし、ココが閉鎖され中心市街地商店
街の事業環境がますます厳しくなっている中、商店街の魅力向上を図る機運が急速に高まって
おり、現在、空き店舗を活用して商店街を訪れた人々がぬくもりを感じ、たまり場となるような
コミュニティスペースの開設計画に取り組むとともに、商店街関係者だけでなく地域住民も含め
たグループを組織し、消費者、住民の目線によるまちづくりの企画、運営、事業推進を行って
いく体制を検討しており、地域の力を結集したまちづくり事業推進に努めるところであります。
今後は、市商工会議所もさらに連携を強化しながらまちづくり事業の推進を図ってまいりた
いと考えております。
次に、中項目3、オークワの再開はあるのか、オークワとの協議はとの御質問でございま
すが、ショッピングタウンココにつきましては、建物の権利関係について、現在も共有者間で
交渉が続いている中で、オークワからは事態が収拾した際には、ショッピングタウンココの
再整備に努めていきたいとの意向を以前から伺っているところであり、先日もオークワに確認
したところ、意向には変わりがない旨を伺ってございます。これまで、ショッピングタウンココの
建物の共有者であります、ココ組合とオークワRVFの間で、建物の権利関係の整理について
の交渉が続けられておりましたが、一方で、和歌山県農業共同組合連合会が仮事務所として
賃借したいとの申し出もあり、仮にこの話がまとまりますと、その間は中心市街地周辺のにぎ
わいに資するものであると思ってございますが、その後におきましては、将来的な観点から
地元商店街とともに集客効果を発揮した中心市街地の活性化につながるよう、オークワによる
ココの再整備が重要であると考えております。なお、ココ組合は、今回の賃貸借に関する交渉
を円滑に進めるため、RVFの建物持ち分及び地上権を抵当権つきで取得したと聞いてござい
ます。ココ組合がRVFの権利を取得したことに伴い、共有者からRVFが除かれ、ココ組合と
オークワの2社の共有となりましたが、ココ組合が取得したRVFの建物持ち分及び地上権に、
ココ建物に係る裁判の判決と同時の平成21年12月24日に東急ホームズの転抵当権が設定
され、この転抵当権が依然として残っていることから、当面、権利関係の整理、解決には、
一定の時間を要するものと考えております。今後もココ建物の権利関係、和歌山県農業共
同組合連合会からの申し出に対する動向に留意しながら引き続きココ再整備に向けて、
オークワとの連携を密にし、協議してまいりたいと考えておりますので、以上御理解いただ
きますようよろしくお願い申し上げます。
再質問
答弁をいただきましたが、商店街の皆さんが今後どう取り組んでいくのかということ
が全く見えてこないんですよね、現状でも。一方、商店街の関係者の話では、特に
ココのココ組合の皆さんは、市にいくら提案しても全く取り上げてくれないという声
もあるそうです。
市民病院が完成し、仮にオークワが再開されればそれでいいのでしょうかと問い
たいんです。商店街がみずからも再生のために何かをすべきではないのか。また、
駐車場問題についてもね、議会でもよく出てきておりますけども、市民病院の駐車
場、そこをまた利用するとかいろいろと出てきてます。しかしそうではなくて、商店
街みずから駐車場対策というものを持ってないのか。どうしたいということを持って
ないのか、いうことであります。そしてその点について、まちづくり海南や商店街の
方々、話し合ったことはないのか、市はね。さらにこの商店街を地域住民に愛さ
れる場所にするためには、行政、商店街、地域住民が連携していく必要があると
いうことですけども、地域住民はどんな役割を今まで果たしてきたんでしょうかね、
この中心市街地活性化で、商店街の振興のということで。その辺のところが全く
見えてこない。いかがでしょうか。
次に、当の株式会社まちづくり。この会社はやっぱり中核となって、海南市全体
の商店街というものを見据えた上で、中核、中心市街地活性化の問題には、
やっぱり6商店街を、指導的な役割の立場に立って、どうしていくか。単に
シャッターの店を再開さすとか、それも大事ですけど、それよりももっと大きなこの
商店街をココの再開発を含めて、どういう形のもんをつくり上げていくんやという
ビジョンをまず持った上で、やることじゃないんですか、やるべき会社じゃないんか
これは。そこらのところがほとんどできていない。残念ながらね、この会社、その
役割を果たしていないために駐車場の管理と「かいぶつくん」の管理に、その
精力を使いきってるような感じにしか私は見えないんです。今後、本来の目的の
会社として、活躍してもらうために、市は本当にこの会社を指導できるんか。これ
まで、そういう意味でどんな指導をしてきたのか。この会社自体、そういう立場に
立って、やっていかなければならないという自覚に立った活動をしているかどうか、
そのことについて詳しくお伺いしたい。
次3、オークワです。一貫して市当局はオークワの意向は全く変わらないと言いま
した。しかし、昭南跡地にオークワの進出をきめたときと、今では内容について、
店舗展開、ころっと変わっております。最初、立ち上げたときの形のもんであれば、
オークワの再開はまた別の形でできる。しかし一方に大きなスーパー中心とした
店舗展開をされてしまうと、こちらの商店街ココでは、その食材だけの店舗
では、商店街のもともとの設立の意味からいうたら全く合わない。皆さんも言ってま
したよね。ここの商店街はココやジャスコにない、そういう店舗を中心につくってきた
と、補完的な立場や。その中心が抜けたら集客能力がないと皆さんも認めてる
そうするとオークワの再開というのは、もともとのジャスコのような店舗構成になら
ないと全体としての再開発にならないんではないか、そういうふうに私は思うんです。
やりますよ、やりますよということやなしに、どういう形の再開をしてくれるんでしょう
かというところまで踏み込みべきではないでしょうか。その点いかがでしょう。
再質問答弁 (産業振興課長(橋本正義君)
まず、商店街みずからも再生のために何かすべきではないのか。また、その点について、
まちづくり海南や商店街の方々と話し合ったことはないのかということでございますが、中心
市街地の活性化には、新市民病院やココの再整備はもちろん商店街独自の取り組みも重
要であるため、まちづくり海南や商店街の方々とも個別に話をしてございます。特に、1番
街商店街サンサンタウン中央通り商店街、及び海南中央商業共同組合との協議につき
ましては、十数回にわたりこれまで協議を行ってございます。協議の内容としましては、他
市の取り組み事例や、国等の補助メニューの説明のほか、商店街で新たに人を呼び込むた
めの具体的な事業や取り組みができないかなどを検討してまいりましたが、事業費の捻出
や意欲的に取り組む人材が不足している点などが課題となっており、商業者、まちづくり
海南など関係団体との協議はしているものの、行政、商店街、地域住民が連携した具体
的な事業、取り組みが進んでいないのが現状であります。
次に、株式会社まちづくり海南が核となって、にぎわい創出を推進する上で、まちづくり
海南がどのように自覚しているのかということでございますが、まちづくり海南では、JR海
南駅高架下の駐車場、海南市物産観光センターの管理運営が主体となっており、その他
のまちづくり事業が進行していないというのが現状であります。これまで商店街ガイド
マップの作成や、ホームページにおいて、各商店やイベント等の紹介、PRなど、情報発信
は充実してきておりますが、会社設立以後、共通駐車場システム、共通商品券などの事業
を試みたものの実現に至らず、中心市街地ににぎわい創出をする効果的な事業が出て
きてございません。これは会社内でも十分認識されており、特に、ココが閉鎖され中心
市街地商店街の事業環境がますます厳しくなってきている折、私どもも日ごろからまち
づくり海南と対話する中、空き店舗を活用して商店街を訪れた人々のたまり場となる
コミュニティスペースの開設計画や、商店街関係者だけでなく、地域住民も含めたグル
ープを組織し、消費者、住民の目線によるまちづくりの企画、運営、事業推進を行って
いく体制を検討しており、地域の力を結集したまちづくり事業推進に努めようとしている
ところであります。今後は、市、商工会議所もさらに連携を強化しながらまちづくり事業
の推進を図ってまいりたいと考えております。
次に、オークワは組合に対して、再開発はしない意向を示しているということでございま
すが、組合ではココの建物の権利関係について事態が収拾した際には、オークワがココ
の再整備に努めていくことを前提に建物の権利関係の整理についての交渉を続けてき
たものであり、組合によるとそれは今でも変わっていないとのことですし、オークワにも
確認いたしましたが、意向に変わりがない旨を伺ってございます。昭南用地に整備
される株式会社オークワの店舗は国道沿いであることから中心市街地以外の広域から
の集客を図れる立地条件の中、一般的なスーパーとは違いアミューズメントゾーンに大
きなスペースをとり、また、書籍、CDレンタルのコーナーなど時間消費型施設として、
広域からさまざまな世代の人々が集い、にぎわい、交流する場を形成していく計画で
あります。一方、ココについては、株式会社オークワによりますと、周辺の専門商店街と
連携する高質スーパーマーケットとして、高質食材は扱いながらも、周辺住民を対象と
することから、低価格商品や生鮮食品、惣菜なども少量をパックにしたものをそろえると、
中心市街地における日常生活サポート機能を強化した店舗づくりを行いたいとのことで、
昭南用地とココの両施設で共存共栄を図っていくものであります。
再質問
これ以後は、1、2、3、まとめた形の質問に入っていきたいし、ちょっと深く入って
いきたいなと思いますので、部長さんに答弁をお願いしたいと思います。
まず、まちづくり海南です、ここに定款見せていただいております。発起人、出資者
、すばらしい方々が網羅されております。にもかかわらず、何と言いますか、経営陣、
経営陣は商店街の皆さんだけに、そこに市の部長さんが入っとるというような経営陣
であります。私は、このまちづくり海南というのは定款にあるように、まったく見えて
こない、先ほども言いました、大きなこの海南市の駅前の商店街を、あるいは中心
市街地活性化という観点からどうしていこうというときに、単にそういう駐車場の
管理や、かいぶつくんの管理も仕事の1つとしていいですけども、そうじゃなくて、
このココ再生をこういう形でやると、そして商店街とマッチした活動を立ち上げてい
くと、それに基づいていろんな仕事、いろんな事業をやっていかなければ、絶対成
功しないと思うんです。そこには駐車場の問題もあり、ココ自身をどんな形の店舗
として展開するのかという考え方もきちっと出す。その上でオークワとも話しをする、
ココ組合とも話しをする、あるいは商店街とも話しをする。今、答弁いただきました
けれども、オークワは高品質食、やっぱり食材を中心とした店舗展開になるという
ことですな。そうすると、あなた方が言うてるように、今の商店街の形態と合わないん
ですよ。今の商店街は、ジャスコや元のココのような店舗展開の補完的なそこには
ない店舗をつくってると皆さんおっしゃいました。ところが今度来るオークワは食材の
店舗だけであると、できたところで集客能力がない商店街に陥ってまうんではない
でしょうか。
だからこそビジョンをつくって、それに基づいて運動していく。また、おかしな話も聞
くんですよ。商店街のある人に、どう、しっかりやってもらわんと言うと、市は何して
くれんのよという方もいるらしい。市がやってできるもんではないんで、商店街や、
まちづくり海南の皆さんが大きな構想のもとにこういうことをやりたい、私たちも資
金も出してやりますからと、そこから市がバックアップするということになってくるん
です。初めから市が何かをやってくれると言うのでは、やめといたほうがよろしい、
私はそう思います。しかし、市もやめるにやめられん立場にありますからね、
その点について、やっぱり指導力も発揮するなり、、まちづくり海南の皆さんに
考え方を改めていただいて活動いただいてはと、思うんですが、その点はどう
なんでしょうか。
それとですね、6商店街あるんですね、、あなた方の答弁を聞いておりますと、
まちづくり海南とあと3商店街と10回とかいろいろ相談したということであります
けれども、あとの3商店街どうなってます。海南市がやるいうのは、6商店街に対
して平等に話しをして、それでまちづくり海南を通じて事業を立ち上げていくとい
うことが僕は基本やと思うんです。6商店街の中でいろいろありますよ、仲が悪い
商店街もある。しかし、それに合わせてたんでは、やることはできない。やっぱり
その6商店街が1つになる努力もしていただかないと、何にもならない。それを
証拠に、まちづくり海南の役員さんは3つの商店街からしか出てませんね、あと
の3つから出てません。それをいいことにその3つだけと相談してて、まとまりま
すか、この商店街は。
その辺のところもやっぱり指導的立場にたっていかなきゃあかん、それがが
まちづくり海南の仕事なんですよ。
先ほどちょっと申し上げてましたけれども、地域との連携どういう形でやってお
られるのかな。地域の皆さんはこのまちづくり海南にどんなかかわりをもっていろ
んな相談をされてますか。私はやっぱり、あんた方の言うてることはそのとおりや
と思うんです。地域と連携する。中心市街地は商店街だけのものではない、この
エリアの地域も含めた全体の活性化という皆さんが常におっしゃっています。
しかしその中で、地域の方々はどういう形でかかわってるか。あるいは、若者は
どういう形で取り組んでいますか、そういうところをりきちっと、ここの議会の皆
さんに、私たちはこうでありますというもんを出していただかないと、今のところ
では、オークワの判断を待ってるだけじゃ能がないと言わざるを得ないですね。
その点についていかがですか。
再質問答弁 (まちづくり部長 北口和彦君)
1つは、まちづくり海南の取り組み姿勢について、また、それを進めていく上での人の
指導力について、また、6商店街を包括した話し合いといいますか、まちづくり海南を
を中心として全体としての取り組み姿勢が必要ではないかと、また、地域との連携
どのようにされておるのか、そういった中で若者のかかわりといったものについての
御質問がございました。ただいまいただきました御質問に一括して私のほうから御
答弁を申し上げます。
中心市街地活性化計画における商店街の取り組みを企画、推進していく上でまち
づくり海南が商店街を取りまとめる中核的な立場でなければならないことは申し上げる
までもございません。まちづくり海南は、御指摘がございましたように、現在はJR海南
駅高架下の駐車場、海南市物産観光センターの管理運営が主体となっており、まして
その他のまちづくり事業が推進していないというのが現状でありますが、今後、市や
商工会議所ももっと積極的に連携をいたしまして、まちづくり海南が主導して中心市
街地の6つの商店街組合との話し合いの場をもって取りまとめをしながら、中心市街
地活性化計画における商店街の取り組みを意欲的に企画、推進していく体制を整え
ていきたいと考えております。また、最近市内では、市職員や商店街、地域企業、地
域住民等の有志による地域を盛り上げていくためのイベント活動も活発になっている
こともあり、現在、まちづくり海南では商店街だけの考えではなく地域住民等も巻き込
むことで、消費者、生活者の目線も含めたまちづくりの企画、運営、事業推進を行って
いく体制を検討しているところであります。同時に、中心市街地の活性化において、
ココ再開発が重要でありますので、今後もココ組合との連携を密にいたしまして、情報
収集をしながら対策を考えていくとともに、まちづくり海南も積極的にかかわり、再開
発されたココとの相乗効果を得られるような商店街の取り組みを検討してまいりたい
と考えております。
再質問
私、何遍も申し上げますけど、まちづくり海南、1つの大きな構想というものを
立ててそれに基づいていろいろな事業を展開していく、話し合いをしていくという、
そこがないとね、あれやります、これやりますじゃあ、今までと変わらないと思う
んです。それと、まちづくり海南が駐車場管理やかいぶつくんの管理に時間をとら
れて忙しいんやったら、もう外しなさい。だれにもそんなことできます。もっと大きな
ことに専念をしてもらったらいいんです。そいうことについて、どうですか。
再質問答弁 (まちづくり部長 北口和彦君)
ただいま議員から、まちづくり海南が中心市街地の活性化、商店街をリードして活性化
していく上でビジョンを持って、それに取り組む必要があるという御指摘をいただきました。
先ほど申し上げましたように、ただいま地域との連携で、若者たちのそういった取り組
みという芽生えがございます。そうした方々の意見、また取り組み内容を検討しながら、
まちづくり海南で中心市街地活性化に向けたビジョンをどうあるべきかということを検討
していただき、また、その中で市商工会議所も十分連携をしながらビジョンづくりに努め
てまいりたいというふうに考えてございますので御理解を賜りたいと存じます。
再質問
今ね、あんなことばっかり言ってるというような私語もありましたけどね、やはり
真剣に考えてください。質問は終わりますけども、まずビジョンを立てて、真剣に考えていただいて、まちづくり海南が本来の姿に戻っていただく。このためには大きな荒治療もやってください。それでないとだめです。2,000万の内部保留も使いなさい。
2、 本市の学校給食と食育について
食育 について
食育(しょくいく)とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な
食生活を実践することができる人間を育てることである。国民一人一人が、生涯を通じた健全な食生活
の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関する様々
な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習等の取組みを指す。2005年に成立した
食育基本法においては、生きるための基本的な知識であり、知識の教育、道徳教育、体育教育の
基礎となるべきもの、と位置づけられている。単なる料理教育ではなく、食に対する心構えや
栄養学、伝統的な食文化、食ができるまでの第一次産業についての総合的な教育のことである。
食育基本法の前文では
二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際
社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生
涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要で。
ある今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと
位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な
食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育
はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食 育は、心身の成長及び人格の
形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく
基礎となるものである。
一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切
さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の
増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の
問題 が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、
「食」のら 安全の確保の面からも、自「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と
水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香り
あふれる日本の「食」が失われる危機にある。
こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生ること
が求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する 消費者と生産者との
信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた
食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。
国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な
活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う
能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、
学校、地域等を中心に国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている
課題である。
さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に
貢献することにつながることも期待される。
ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民
の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
(教育関係者等の責務)
第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」
という。)に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び
関係団体(以下「教育関係者等」という。)は、食に関する関心及び理解の
増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる
機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるととも
に、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
(家庭における食育の推進)
第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心
及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室
その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、
健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及
及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子ども
を対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進
を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(学校、保育所等における食育の推進)
第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に
関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び
健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進の
ための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び
指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の
啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の
特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における
実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの
食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等に
ついての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
(学校における食育の推進・学校給食の充実)
近年、偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、子もたちの健康を
取り巻く問題が深刻化しています。また、食を通じて地域等を 理解することや、食文化の継承を
図ること、自然の恵みや勤労の大切さなどを理解することも重要です。
こうした現状を踏まえ、平成17年に食育基本法が、平成18年に食育推進基本計画が制定され、
子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校に
おいても積極的に食育に取り組んでいくことが重要となっています。文部科学省では、栄養教諭
制度の円滑な実施をはじめとした食に関する指導の充実に取り組み、また、学校における食育の
生きた教材となる学校給食の充実を図るため、より一層の地場産物の活用や米飯給食の充実を
進めています。
(栄養教諭制度について)
学校において食育を推進するためには、指導体制の整備が不可欠です。平成17年4月に
制度が開始された栄養教諭は、各学校における指導体制の要として食育の推進において重要
な役割を担います。平成18年3月31日に政府の食育推進会議において決定された食育推進
基本計画では、全都道府県における栄養教諭の早期の配置を求めています。栄養教諭の配置が
進むことにより、各学校において、栄養教諭を中心として食に関する指導に係る全体計画が作成
されることや教諭等により、体系的・継続的な学校全体の取組となることが期待されます。
1 学校、保育所における食育の現状は
食育推進基本計画に基づく学校、保育所における食育現状は、指針の作成(本市の食育推進
基本計画)や指導体制の充実、栄養教諭の配置は。
2 家庭における保護者やこどもたちへの食育の現状は
父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な
食習慣の確立食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発をどのように
実践しているか。
3 学校給食にかかわっての食育は
食を通じて地域等を 理解す ることや、食文化の継承を図ること、自然の恵み
や勤労の大切さなどを理解するとともに豊かな食文化の継承と言うことをどう
指導しているのか。
4 みかんを3回洗浄すると言うことについて
県の通達に従いみかんを3回洗浄していると云うことですが、本来みかん
というのはそのまま皮を拭いて食べるのが一般的な常識であると思うがなぜ
みかんを3回洗浄しなければならないのかその根拠は。
答弁 健康課長(芝村幸志君)
大項目2「本市の学校給食と食育について」
本市の食育推進基本計画は
議員御発言のとおり、平成17年に食育基本法が施行され、和歌山県では平成19年3月に、
食べて元気和歌山食育推進プランの名称で食育推進計画を策定いたしました。その後、県下の市町村では紀の川市と和歌山市の2市が作成されております。そこで、御
質問の本市の進捗状況でございますが、平成20年度に海南市食育推進本部設置要綱を定
め、副市長が本部長となりスタートしてございます。そして現時点では、小中学生及びその保
護者向けのアンケート調査を今月中の実施に向け準備をしている最中でございまして、年明
けには、今後の目標及び政策展開等の方向性や食育の取り組みについての素案ができる
予定となってございます。なお、計画の完成時期につきましては来年度前半になると考えて
ございます。
答弁 学校教育課長(井川勝利君)
大項目2「本市の学校給食と食育について」
中項目(1) 「学校、保育所における食育の現状は」について御答弁申し上げます。
市教育委員会としましては、国の食育推進基本計画に基づき、食育を学校教育指針の
重点項目のひとつとして「健康な心と体の育成」の中でも取り上げ、食育の充実や食に関する
指導の工夫・充実に努めることとしております。
たとえば、各小学校では、すべての学校で「食」に関する指導の全体計画を作成し、この計画
に基づいて計画的に指導をしているところです。子どもが社会に出てからも「食」、に関心を持ち
健康に過ごしていくために、「食」について自分自身で考えていくことができる力を育てるための
授業や体験学習を行っております。
たとえば、「地域の方々に協力を得ながら、自分たちで栽培した野菜を収穫し、その野菜を
自分たちで計画を立て、調理して食べる授業」や「食糧の生産・流通・消費にかかわる工夫や努力
を知り、自分が住んでいる地域の食文化、食にかかわる歴史等を理解する授業」「五感をはたら
かせて、お米を観察し味わうことで、お米の良さや食事の楽しさを感じ取らせる授業」「地域の環境
や条件に合わせて行われてきた先人たちの食に関する様々な工夫や努力に気づき、自らの食
生活を見直して、よりよい食生活を送ろうとする意識と実践力を養う授業」など様々な取組を
行っております。
大野小学校では、先日海草地方の学校給食教育研究発表会を開催し、食育に関する様々な
取り組みを発表し、市内各学校にその成果を普及、啓発したところです。
次に栄養教諭ですが、県内では12名配置されており、本市においても1名の栄養教諭が配置され、
専門性をいかして食育に関する様々な授業を実施しています。
また、本年度は食育の一環として「ごはん活用術体験学習」を大東小学校の児童と海南下津
高等学校の生徒が共同で、政府備蓄米を使った調理実習に取り組みました。このように、さま
ざまな学校における 食育を実践しております。
中項目2、家庭、保護者や子供たちへの食育の現状はについて御答弁申し上げます。
保護者に対しては、小学校1年生の保護者を対象に給食試食会を開催し、実際に給食を
食べながら給食の意義や献立等について説明し、家庭においても好き嫌いをなくしたり、
残さず食べることや食事のマナーについて指導していただくなどの協力を得るための取
り組みを行っています。また、給食連絡調整会を開催し、学校と保護者代表が学校給食
の果たす役割などを一緒に考える機会を持っています。さらに、各学校では給食だよりを
発行し、保護者と子供たちに対し食への興味、関心を高めてもらえるよう、望ましい食習慣
のあり方を家庭で親子が一緒に考える手だてをしています。例えば、献立の由来や食材に
ついての内容、季節折々の伝統行事などの際にいただく料理に関する内容や、子供たち
の給食時の様子を紹介し、学校給食の意義や望ましい食生活について啓発する取り組み
を行っています。
中項目3、学校給食にかかわっての食育はについて御答弁申し上げます。
学校給食にかかわっての食育は、各学校で作成されている食に関する全体計画の中で
位置づけております。例えば、準備や後片づけの仕方と安全、歯を大切にし、よくかんで食
べること、偏食をなくすこと、正しい食事の仕方について、しゅんの食べ物や地域の特産物に
関すること、楽しい食事の場をつくらせること、食べることができることへの感謝の気持ちに
ついて、手洗いや食事のマナー、献立の由来や食材、季節折々の伝統行事などの際にい
ただく料理に関する内容などを扱っています。また、栄養指導としては、給食に使われてい
るさまざまな食材についての栄養や、それが体にどのようによいかを子供たちに知らせ、
生涯にわたって食について自分自身で考えられる子供を育てるための取り組みを日々の
給食を通して行っております。
中項目4、ミカンを3回洗浄するということについて御答弁申し上げます。
学校給食では、最新の注意を払い子供たちに安全、安心な給食を提供しています。野菜
や果物については、平成20年6月改正の厚生労働省から出された大量調理施設衛生管理
マニュアルにより流水で3回以上水洗いすることが示されております。また、平成21年3月に
出された文部科学省の調理場における洗浄、消毒マニュアルでも流水による3回洗浄が示さ
れております。本マニュアルによれば、1回目、2回目、3回目のそれぞれの洗浄後の食材
に付着した残留細菌類を比較した結果、3回の洗浄をすることで大幅に残留細菌類が少な
くなっていることがデータで示されております。このように下処理室に持ち込んだ食材につい
ている泥、ほこり、細菌類をできるだけ減らして、非汚染作業区域である調理室に入れることが
必要となります。これは、食材そのものについて細菌などを除去することはもちろんですが、
特に、他の食材への2次汚染を防ぐためという意味でも必要な作業となります。このような
理由から、現状はミカンについても他の食材同様に3回の洗浄を行い、調理室で学級ごとの
数に分けております。このように子供たちに安全で安心な給食を提供するために、先ほども
申しましたとおり、食材についている残留細菌類等をできる限り少なくし、下処理、調理を行う
よう、念には念を入れているところでございます。
答弁 子育て推進課長(坂部孝志君)
中項目(1) 「学校、保育所における食育の現状は」について御答弁申し上げます。
保育所の食育は、食を営む力の育成に向け、その基礎を培うため毎日の生活と遊びの中
で乳幼児期から発達段階に応じて豊かな食の体験を積み重ね、仲間と楽しく食べることの
体験を通じ、食事を楽しみ合う子供に成長していくことを期待しているところでございまして、
保育所保育指針の中にも、食育基本法を踏まえ保育内容の一環として食育を位置づけて
いるところでございます。本市の保育所において、食べることへの興味や関心の持てる子供
を目標に子育て推進課に配置しております栄養士が定期的に各保育所を訪問指導すると
ともに、2カ月に1回、栄養士が中心に各園の所長、調理人が集まって給食検討会を開き
献立について意見を出し合っているところでございます。また、子供たちにつきましては、保
育所で夏野菜等、キュウリ、ナス、ミニトマト、サツマイモ等を栽培、収穫し、自分たちでつ
くったものが給食の材料になることで、野菜嫌いの子供も興味を持てるような取り組みを行
い、また、年長児を中心に、簡単なおやつ、月見だんごや芋餃子、焼き芋、お好み焼き、お
にぎりなどの自分の手でつくり、食べることに興味を持たせたり、年長児が低年児につくって
あげることによって、優しさや思いやり、感謝の気持ちが芽生えるような取り組みも行っている
ところでございます。
中項目(2) 家庭、保護者や子供たちへの食育の現状はについて御答弁申し上げます。
子供の食を営む力の育成について、保育所と家庭は連携、協力しながら食育を進めることが
家庭での食育の関心を高めていくことにつながり大変重要と考えているところでございます。
家庭に対し、保育所での子供の食事の様子や、保育所が食に対してどのように取り組んでい
るかなど日々の連絡帳などを通して伝えているところでございます。具体的な取り組みとして、
栄養バランスのとれた食物の摂取、元気の出る食材の利用、家庭でできる簡単な調理方法、
家族団らんの食事の推奨、また、郷土料理や行事食のいわれなどを記載した献立表を月ごと
に保護者に配付を行いまして、食に関する正しい情報や栄養管理に関する知識などさまざまな
情報を発信しているところでございまして、家庭からの食に関する相談にも応じるなど連携を
図っているところでございます。
中項目(3) 学校給食にかかわっての食育はについて御答弁申し上げます。
保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところでありまして、保育所における食事
の意味は大きく、食事は空腹を満たすだけではなく、人として信頼関係の基礎をつくる上におい
て大変重要なものととらえているところでございます。
保育所は、子供が初めて
集団生活を営む場となるため、保育士や友達と一緒に食事をすることへの楽しさを覚え、食べ
物やそれをつくってくれる人への感謝の気持ちが育つよう、紙芝居、絵本の読み聞かせなどさ
まざまな体験を通じ食育に取り組んでいるところでございます。食事前の手洗いや食事のあい
さつなど、マナーを身につけるのも重要ですし、毎日の給食サンプルを玄関に提示し、後園児に
保護者がその日の給食メニューを確認し、親子で食に対して会話が行わられるような取り組み、
また年度当初、主に3歳児の保護者を対象に給食試食会を開催し、子供たちが食べている様子
を給食の試食、そして栄養士から保育所給食についての説明と家庭とのつながり等について
話す機会を設けているところでございます。今後とも、保育所における食育の推進について、
より一層取り組んでまいりたいと考えてございますので、御理解いただきますようよろしくお願
い申し上げます。
再質問
海南市の基本計画、来年には何とかできあがるということでございますので、教育
委員会も巻き込んだ形の中で、1つの海南市としての考え方に基づいたそういう
食育計画というものを立ち上げていただきたい。れお願いしておきます。
それと保育所。給食の際の食材の取り扱いについてですが、学校では、厚生労
働省から出された大量調理施設衛生管理マニュアルにより対応しているというこ
とですので、保育所ではそういった形のものはないのですか。
食料の生産、流通、消費についてどのように教えてますか、各小学校ではすべて
の学校で食に関する指導の全体計画を作成し、この計画に基づいて、計画的に
指導しているそうですが、その内容を指導に基づき説明していただきたい。
地域の食文化、食にかかわる歴史について授業、たどんな授業をですか。
栄養教諭は、本市では1名が配属されている様子ですが、本市では何名が適正
な人数になっていますか。1名でその役割を十分果たせますか。栄養教諭と言うの
は、県採用で配置されるんですか。全国で1番少ないのは和歌山県。これだけ申し
上げておきます。
家庭や保護者、子供たちの食育の現状というところにね、朝食をとることの大切や、
調理方法等の啓発、指導を実際にはどんな形で啓発、指導しておりますか。
学校給食の意義や、望ましい食生活について啓発や指導は実際にどうやってま
すか。学校給食そのもんが、戦後立ち上がったときの目的と今とはころっと変わ
っております。そんな中で、どんな形でその意義をわかっていただいてるのか。
食材や納入先、こういった情報は保護者にも伝えておりますか。
学校給食にかかわっての食育について、しゅんの食べ物、特に本市にかかわ
る食材や特産物に関する食育はどのように取り組んでいますか。
残留農薬や細菌の付着、あるいは汚れ等についてどのように見分けていますか。
検査したことがありますか。また、そのことを保護者にどのように情報として提供し
ておりますか。
ミカンについて。1つはマニュアルにのっとって3回洗浄しているそうですが、県
の通達によると、表面の汚れが除去され分割、細切れされずに皮つきで提供され
るミカン等の果物にあっては、3から8まで省略して差し支えないとなっているんです。
それをあえて3回洗浄しているその根拠は何でしょう。ちなみにね、この通達一遍読
んでみます。県の通達でありますけどもね、大量調理施設衛生管理マニュアル。
野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、別添え2に従い流水で十分洗浄し、
必要に応じて次亜塩素酸ナトリウムの200ミリリットルの溶液に5分間、または、これ
と同等の効果を要するもので殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いすることと
なって、実際には1番、野菜果物は、1番、衛生害虫、異物混入、腐敗、異臭等が
ないかを点検する。異常品は返品または使用する。2番目に、各材料ごとに50グラム
ずつ清潔に容器に密封して入れマイナス20℃以下で2週間以上保存する。検食用と
して。3番目、問題の3番目、3番目から8番まで削ってもええと、省略してよいとい
うところですけど、3番目、専用の清潔な容器に入れかえるなど、10℃前後で保存
する。冷凍野菜は15℃以下で保存する。4番、流水で3回以上水洗いする。5番、
中性洗剤で洗うって、まだこれを毎回洗う、これ。マニュアルでは。流水で十分す
すぎ洗いと5回洗う。それで7番、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌した
後、流水で十分洗いすすぎする、2回洗うて。7回やるんやで、マニュアルからいう
と、それで8番、水を切ると、、何で3回のとこだけマニュアルどおりやるの
ですか。全部やったら7回洗わな。ちゃんと県のここからの通達、対応マニュアル
の厚生労働省からのここにもちゃんと書いちゃある。ミカンのように皮つきで供す
る場合には、3から8まで省略してもよろしいよと。うちの海南市のしかもミカンは
どこまで汚れてるのかということになりませんか。
それをうちの市長がですよ、北海道行って、東京行って、販売努力してるんです
よ。教育長も行って、同じようにうちのミカンは3回洗ってますよと一遍やったらど
うですか、そういう観点からいくとね、学校が危険を除去するために追及する余り、
本来ミカンというものの食べ方、非常にその落差があり過ぎるじゃないですか。
文化を大切、食の文化を大切にする、文化というのはそういうミカンならミカンの
食べ方、ミカンができたときから、古代から食べてる食べ方っつうのは、これを
やっぱり今食べてることを大事にしながら、そういう危険の除去ということと兼ね
合わせていかんとだめなんじゃないか。今でも皆さんがミカンをそのまま割って食べ
てるんですよ、家では、子供たち。そこに私はやっぱりもう1つ考えていただけなけ
ればならない問題あるんではないか。安全を追及するのはいいんですよ。徹底的
にやるのはいいけれども、それは物に応じて、時に応じてやっぱりその頭の考え方
ちょっとやわらかくしていただいて、これは何でかと言うたら、調理室にそういう残
留細菌持ち込んだら悪い。よくわかります。調理をしないミカンを調理室入れる必要
ないじゃないですか。はっきり言うと。そういう考え方もできるんじゃないですか。
何でも調理室に入れやなあかんの。何のために入れるんですか。
質問ですところで本市が調達しているミカンは地元産ですか。ミカンの残留農薬
及び付着細菌、本当にそれほど問題にしなきゃならないほどついてるんですか。
検査してますか。これ大変失礼やけどね、3回も洗わないかんほど汚染された
ミカン調達してるんですか。
答弁 (子育て推進課長(坂部孝志君))
本市の学校給食と食育についての御質問中、保育所にかかわって大量調理施設衛生
管理マニュアルについて保育所ではそういった通達はとの再質問に御答弁申し上げます。
児童福祉施設等における衛生管理につきましては、特に、乳幼児は食中毒等に感染し
やすく、また、重症化しやすいことから、児童福祉施設等において、調理従事者だけ
でなく、すべての職員が連携を図りつつ感染の予防に努めることが重要であるとさ
れております。平成9年3月31日付、厚生労働省家庭局企画課長通知で、同一メニュ
ーを回300食以上、または1日750食以上を提供する調理施設について感染予防を
期するため大量調理施設衛生管理マニュアルを参考するとともに、衛生管理を徹底
するよう指導通達を受けているところでございます。
答弁 (学校教育課長(井川勝利君)
食料の生産、流通、消費について、どのような教えをしていますかについてですが、食
料の生産については、社会科において、海南市教育委員会が独自に作成した副読本、
私たちの海南市を使い、農家でつくられる米や果物づくりなどを取り上げ、産地や農家
の苦労や工夫などについて教えております。また、流通については、産地から市場や
マーケットを経て家庭に届くまでの流れを、消費については、家庭での買い物の様子を
実際に調べることを教材として教えております。
次に、各小学校ではすべての学校で食に関する指導の全体計画を作成し、この計画に
基づいてどのように指導しているのかについて御答弁申し上げます。委員の皆様の机上
にお配りいたしましたのは、小学校の食に関する指導全体計画でございます。小学校で
は、低学年、中学年、高学年のそれぞれの発達の段階に応じて、食に関する指導の到達
目標を設定し、資料の中段の表に示している内容を学期ごとに指導しております。また、
食に関する指導は特定の教科だけでなく、学校の教育活動全体の中で教えていくという
方針のもとに、資料の下段の表に示しているように国語など各教科と関連させながら
指導しております。
次に、地域食文化、食にかかわる歴史についてどのような授業をしていますかについ
てですが、例えば、市内でとれるシラスやワカメなどを使った食事の歴史やむかしの食
事と今の食事が変わってきていることなどを取り扱っております。また、海南市にむかし
からあった塩田についての歴史や、塩が大切にされたことについて学習する授業を行って
います。
次に、栄養教諭は本市では1名が配属されているようですが、本市では何名が適正な
人数になっていますかについて御答弁申し上げます。
栄養教諭につきましては、特に配置の基準などは定められておりませんが、現代のよう
に食生活が多様化し、子供たちの将来の食生活を見据えた食育の重要性の機運が高
まる中、市内の小学校、中学校の食育の指導の充実を考えると増員が望まれます。
次に、、家庭、保護者や子供たちへの食育の現状はについての3点の再質問について
御答弁申し上げます。 朝食をとることの大切さや調理方法などの啓発、指導は実際に
はどのようにやっていますかについてですが、保健の授業の中で朝食をとることが体の
調子を整え、1日の生活リズムをつくり、心身ともに健康な毎日を過ごす上で大切であ
ることを指導しています。家庭科では、朝食が成長や毎日の活動に必要な栄養素として
重要であることを学ばせ、実際に調理実習をすることで生活に生かせるように指導して
おります。また、先ほども御答弁申し上げましたとおり、家庭に対しては、保健だよりや給食
だよりを配付し、朝食をとることの大切さを啓発し、協力を得るようにしております。
次に、学校給食の意義や望ましい食生活について、啓発や指導は実際にはどのように
していますかについて御答弁申し上げます。
各学校では、給食指導の年間指導計画の中で、児童の発達の段階に応じて指導してお
ります。特に、給食の時間では、教室やランチルームを使い、楽しく食事すること、健康に
よい食事のとり方、給食時の清潔、食事環境の整備などについて指導し、望ましい食習
慣などの形成を図るよう取り組んでおります。また、保護者に対しては、給食試食会を
実施し、給食だよりや学校だより等を発行して、学校の具体的な取り組みを知らせ、
給食についての情報を提供し理解を得るようにしております。
次に、食材の産地や納入元の情報を保護者に知らせていますかについてですが、海
南地域では、拠点校ごとに月1回の食材のチェックを行っており、このときには各小学
校交代で保護者の代表に参加していただき、食材の産地や納入元を確認してもらって
おります。また、下津地区では給食試食会の開催の折に保護者に対して食材の産地な
どを具体的に紹介しております。
次に、学校給食にかかわっての食育はについての2点の再質問について御答弁申し
上げます。 しゅんの食べ物、特に本市にかかわる食材や特産物に関する食育とは
どのように取り組んでいますかについてですが、しゅんの食べ物としてはミカンやビワ、
ワカメなどについて、海南市の特産物としてはシラスなどについて、これらを給食に出す
際には、給食だよりや給食の時間の放送等を通して、子供たちにその栄養素や特徴な
どを説明しながら給食指導をしているところです。
次に、残留農薬や細菌の付着、汚れ等についてどのように見分けていますか。検査を
したことがありますか。また、そのことを保護者にどのように情報として提供していますか
について御答弁申し上げます。
残留農薬や細菌の検査については、年2回、県教育委員会が市内の1校を抽出し、
学校給食用職員衛生検査を行っております。この検査では、病原性大腸菌O157、サル
モネラ菌、カンピロバクター、そして残留農薬であるスミチオンの4項目について検査を
行っております。本年度も2回実施しましたが、このような細菌や残留農薬は検出され
ませんでした。汚れなどについては、給食調理の現場で栄養教諭や栄養士、調理人が
まず目で見て確認するとともに、手でさわるなどして合わせて確認しております。現在、
保護者にはこの検査結果を報告しておりませんが、今後は情報提供していくことも検討
してまいります。
次に、中項目4、ミカンを3回洗浄するということについてについての4点の再質問につ
いて御答弁申し上げます。 マニュアルにのっとって3回洗浄しているそうですが、県の
通達によると表面の汚れが除去され、分割や細切されずに皮つきで提供されるミカンなどの
果物にあっては、③から⑧までを省略して差し支えないとなっているが、あえて3回洗浄して
いるその根拠はについて御答弁申し上げます。
先ほども御答弁させていただきましたが、文部科学省の調理場における洗浄消毒マニュ
アルによると、非汚染作業区域である調理室には細菌類をできるだけ減らして入れなけれ
ばなりません。これは、特に他の食材への2次汚染を防ぐためという意味でもあり、議員御
指摘のとおり、厚生労働省の基準であるミカンの洗浄にあっては省略できるとの記述が
追加されましたが、現在も3回洗浄を行っているところです。
次に、本市が調達しているミカンは地元産ですかについてですが、本市の給食で出して
おりますミカンにつきましては、すべて海南産のものであります。海南産のミカンであります。
次に、ミカンの残留農薬及び付着細菌の検査をしていますかについて御答弁申し上げます。
先ほどの答弁で申しました県教育委員会が行っております学校給食用食品衛生検査で
は、ミカンについての残留農薬及び付着細菌の検査を行っておりません。
次に、3回洗浄しなければならないほど汚染されたミカンを調達しているのですかについ
てですが、子供たちにより安全で安心な給食を提供するために、現在、給食で出している
ミカンは入念に3回の洗浄を行っているところですが、地元産の新鮮なミカンを調達してお
り汚染されているとは考えてございません。
再質問
わかります、調理室にね、できるだけ細菌を持ち込まないという気持ちはわかる。
それで根拠を問うたらね、例の厚生労働省のマニュアルに基づいてやる、
それはもうわかってんのよ。わかってるけども、厚生労働省の基準に言うても、
あえてミカン等はやらなくてもよろしいて言うてるやつを、念には念を入れてやって
いるんやけど、その根拠は何よと言ったら、またそのマニュアルでてくる。マニュアル
はわかってます。しかし、厚生労働省もマニュアルから省いてもよろしいという見解の
もとで、それをあえてうちは念には念を入れるのはわかるけど、念には念を入れる、
そうするとね、どうしても我々はこの海南市はミカン産地です。にもかかわらず、
そして厚生労働省もミカン等については省いてもよろしいっていうにもかかわらず、
洗うということはね、しかも他の野菜に影響したら悪いという、それは気持ちはわ
かります。しかし、洗うということは、ミカン農家の方、これ聞いたら何と思 うでしょ
うね。私たちは、
そんな何回も洗わなんほど汚染されたミカンを提供してませんよと言うの当たり前
でしょう。しかも、市長が先ほど言ったように売りに行ってるのにやな、売れることな
いわよ。やっぱりその辺のところはきちっと考えて対処していただきたいと私は思う
んよ。それで、確かに調理室は無菌で、もう病院みたいに無菌室にしたらどうです
か。1番安全やんよ。そうじゃなしに、調理室で調理せえへんのやったらそこへ入
れないでもいいでしょう。何でも調理室へ入れやなあかんのか、あれは。要するに外に置いといたらええんです。運んだらええんですよ、運ぶときに外へ出
すでしょう。さっき何かバナナの話ししてましたけどね、バナナは外国から、人の
手を隔て、いろんな場所を通ってくるからいろんな細菌もあるでしょう。しかし、ミカン
はここでとれて、ここで食べるんよ。それと、さっきから言わなんだけどね、ミカンに
3回も水みせたら味どうなると思います。しゅんのものをおいしく食べさすていった
でしょう。そのおいしさを残さんと、おいしさまで水で流してしまって、子供たちに食
べさすというあり方っちゅのはね、本当にいいんでしょうかね。それは安全との兼
ね合いもあります。、そのミカンを一遍検査しなさいよ、そんな残留細菌とか残留
農薬あるかないか。そこまでおっしゃるんやったら、3回洗わなあかんとおっしゃる
んやったら一遍検査したらどうですか。それにね、残留細菌であろうが、残留農
薬であろうが、許容範囲っていうのは何にでもあるんですよ。ゼロにしなさいとい
う法律はどこにもありません。ここまで以下なら大丈夫ですよと。それがまた1つ
の人間の抵抗力にもなるわけです。、わずかな細菌が入っても、それを子供たち
は抵抗力にかえて育っていくということもあるんです。。そういう意味からも、この
ミカンの産地の学校であるということを頭に入れた対策をしていただきたい。教育
長さん、そもそもこの前も言いましたけど、この17年度にミカンは抜いてもええって
言うたときには、教育長は、県の教育委員会におられました、あんたがつくったわ
けじゃないやろうけども、やっぱりそういう通達出したら、担当は別でも教育委員会
の皆さん、これをきちっと把握してるはずや。そのときからもうわかっているんで
しょう、ミカンやったら3回も洗らわなくてもいいというただし書きが出たんか、これ
はおわかりですか。何でミカン等は皮ごと出す場合は、3回洗浄、3回違うで
しょう、5回、7回洗浄せいでもええというようなね、通達何で出たんか、いうところ
を明らかにしていただきたいし、1つは、子供たちに食べ方を教える、あるいは、
こういうふうにして食べなさいと給食を通じて教える場合、3回、洗ってますよと、
そんなことが一般で通用するかどうか、正しい食育になるかどうかというのも一遍
教えていただきたいんです。教えてるんでしょうね、多分。それと私はやっぱり細
菌の多い、根菜のような土から直接出て洗ってっていう形の中で残留細菌
は多いとは思うんです。反対にミカンにそういう根菜からつく可能性しか多いんじゃ
ないかいなと私は思うんですよ。いずれにしてもすべてそういう形で許容範囲以下
の細菌であり、もしそういう残留農薬があったとしても許容範囲以下の、そこで
物事を考えなければ私はだめだと思うんです。食について考えるときも、
すべてのものについて。ですから、私、何で給食を通じて食育をどういうふうにし
てやってますかと質問したのは、ミカンに限って言えば、その洗って食べてくださ
いよという部分をどういうふうに説明するんでしょうか。
農家のミカン農家の方にしたら3回も水洗いしてたらう味は落ちてまうという話で
すけどね。海南の産地の小学校の給食はまずいミカンをずっと食べてやんなと言う
ことになる。せっかく旬のとれたてのものを食べられるものが、洗ったがためにまず
いミカンを食べなあかんということにもなりかねない。そんなところはやっぱり配慮し
ていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
答弁 (教育長(西原孝幸君)
本市の学校給食と食育についての中項目の4、ミカンを3回洗浄するということにつ
いてにかかわっての再度にわたる御質問の中で、1点はミカンの洗浄についての根拠
につい
てということが1つと、総括してお尋ねいただいているのは、食育についての、総合的な
考え方と、それから厚生労働省の基準が改正された、その中で記述された3回洗浄に
ついてのことについての御質問であったと思いますので、御答弁をさせていただきます。
まず、現在も給食では3回の洗浄を行っているところなのですが、先ほど議員からの
御指摘にもあります、大量調理施設衛生管理マニュアルというのは、厚生労働省から
出されている基準でございます。文部科学省のほうからは、学校給食衛生管理規則
という形で、この中で生食する野菜類及び果物類等は流水で十分洗浄されているという
記述がございます。また、同じように文部科学省から出されております、調理場にお
ける洗浄、消毒マニュアルの中では、野菜や果物などは3層シンクで流水による洗浄
をしますとそういう記入がございます。これらに基づいて現在も市内の給食の調理室
では、3層シンクの中でミカンについては3回の洗浄を行っているところでございますが、
先ほど議員の御質問にもありました厚生労働省の管理マニュアルについては平成20
年に改正をされております。その中で、先ほど議員の御質問にありました表面の汚れ
が除去され、分割、細切されずに皮つきで提供される、今質問にありますミカン等に
ついての果物にあっては、省略して差し支えないというそういう改正があったわけで
す。いずれの記述にも、改正後はミカンという表記がなされましたが、それ以前につ
いても、果物という包括的な表記でございます。その中では、先ほどから質問いただ
いておりますミカンであるとか、あるいは例えばナシであるとか、いろんな果物には食
べ方がありますので、それらを解釈上で包括的な基準、その中ではより安全なという
か、そういう基準に従っていたという経過もあるということで御理解いただきたいと思い
ます。それから現在市内で先ほどから課長のほうからも答弁をさせていただきました
食育についての総括的な考え方ですが、一般的に家庭などでミカンを食べる場合に
3回の洗浄をして食べることはありません。子供たちには、ミカンの産地として誇り
を持って、もっとミカンを食べようという意識を高めていくことが大切であると考えてお
ります。しかし、多くの子供たちに一斉に提供する給食の調理においては、厚生労働
省や文部科学省が示した基準や調理マニュアルをもとに、より安全で安心な給食を
提供するために対応してきているところでございます。食育の中では、子供たち1人1
人が将来にわたって、自分や家庭での安全な食習慣を身につけるための知識や考え
方、自分で選択できる力を育てること、さらに社会生活において一般に多くの人々が
食べる食材や調理した食事などを提供するときには、特に安全を保つために高い基準
が設けられているなどの仕組みを教えることが大切であるとも考えております。このよう
に幅広い視点で子供たちには教えることが必要であるととらえております。決して家庭で
ごく普通に食べているミカンを洗って食べなくてはならないというような理解につなげるよ
うなことがないような指導が大切であるとは考えております。給食の調理場では、安全
な給食の提供ということに最大限の配慮を常に行っており、ミカンの洗浄につきまして
も、先ほどから申し上げました厚生労働省や文部科学省から示されているマニュアルに
記述された内容をより安全性の高いレベルでの処理方法で実施している状況でありま
す。しかし、議員御指摘のように平成20年には、厚生労働省の基準でもミカンのような
皮をむいて食べる果物についての処理が改正され、さらに平成21年には県教育委員
会からも現状を踏まえた安全な処理について通知が出されております。教育委員会とし
ましては、今後、給食調理の現場を預かる学校長を初め、栄養教諭、栄養士、調理担当
者から意見を抽出し安全性を確認しながら対応してまいりたいと考えておりますので御
解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
再質問
答弁漏れ、もう1回言います、厚生労働省にしろ、県にしろミカン等については
省いてもええと改めて通達を出したその根拠を知ってますか。
このことに関して2回通達きてる以上、やっぱりそれに合わせた対応というのは
大事じゃないですかね。検討するにしてでも。うちはミカンの産地であるという
ことから考えてやっぱり効果という部分は絶対あるはずなんですよ。いかに安全
に、そして当たり前のの提供の仕方と、やっぱり兼ね合わせたことをいろいろ考
えてやらんといかんのやないかと、安全ばっかり追及してても本当の食育というこ
とになりますかと僕は言うてるんですよ。ですから、せっかく厚生労働省も、県も
これでよろしいて言う、それによって必ず何でそこに変えたか、根拠があるし、
文部科学省よりも新しい通達ですから、来たときにそれをきちっとやっぱり検証
すべきじゃなかったか、私は思った。そのことについて、答弁は抜けてました。
答弁 (教育長(西原孝幸君)
市の学校給食と食育についての御質問の中で、再度にわたる御質問にお答えを申し
上げたいと存じます。
厚生労働省のマニュアルの改正が平成20年度、それから県からの通知でございます
が、平成21年の12月にございました。その後について、現在も従来どおりの3回洗浄を
行っているわけですが、この通知の中では、県からの通知の中では、ミカンについては
下記を参考に安全性を確認しつつ実情に応じて判断し、取り扱い願いますという項目の
中で、3つの先ほど申し上げました学校給食衛生管理基準と、調理場における洗浄、
消毒マニュアルと、これが文部省から示されているもので、もう1つが大量調理施設衛生
管理マニュアル、これが厚生労働省から示されているものでございます。厚生労働省の基準がこのように改正される中で、先ほどから申し上げられているような注釈
中としてのミカンに分割、細切されずに皮むきで提供されるミカン等の果物にあっては
差し支えないという表記が追加された理由はということでございますが、詳細について
への理解は申しわけないのですが、答えしかねますが、果物という表記で包括されて
基準が示されている中では、先ほど申し上げましたように、例えばミカンであったりとか、
あるいはナシであったりとかいうような果物の処理について、いろいろな意見が出され
たということは聞いてございます。それらをもとにこれらの改正につながる要因の1つに
なっているのではないかと解釈しております。、教育委員会としましては、これらの3つ
のマニュアル基準を参考にした対応をしていかなくてはならないと考えております。
なお、先ほど答弁申し上げましたとおり、これらの内容を踏まえて早急に対応を検討
させていただきたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いを
申し上げます。
再質問
一度、教育委員会で御検討いただきたいと思うんですけれども、県の通達には、
学校給食への地場産物の活用は児童、生徒が食材を通して地域の自然や文化、
産業等への理解を深め、生産に携わる人々の苦労に触れ、食に対する感謝の
気持ちをはぐくむ上で重要と考え積極的な活用を啓発してきました。つきましては、
学校給食への地場産物活用の教育的効果を御理解の上、和歌山県の代表的な
特産物であるミカン等の学校給食への積極的な活用をお願いしますと、この前提
に立って、これらがあるわけ、県ではね。やっぱりその地場産物の取り扱い方は
一般的な食材とちょっと考え方を新たにしてですね、検討しなさいということでしょう。確かに
マニュアルはたくさん出てます。これ全部その通りしなければならない、と言うこ
とではないでしょう。
最後に参考までに小浜市の話をします、小浜市はもう既に食基本計画を市で
つくって食育課というのを設けた。そこの課長さんとお話しさせていただきました
が。そのかたはもちろん安全面は大変大事です。しかし食材によっては安全面に
十分配慮しながら食物に応じた対応をしていかなければならない。こう話して頂
きました。うちは丁寧に3回洗って食べてまますよと言ったところ、その課長さん
に、即刻、帰ったら教育委員会にお話をして中止しなさい、言われました。そうい
うこともあってね、今回質問しようかと思ったわけです。
もちろん私は、以前
に議会でのんの質問で3回洗ってます、っておやめになられた次長さんが喜々と
して答弁されていたのを見て、何か違和感を感じていましたし、それでいいんかい
ともおもっていました。
やはりその食物ごとに対応というのを考えるべきで、特に地場産品というのは、
ミカンがそんなことして子供たちに出されてんのかいって、これはちょっとね、
ミカンの農家の方、ショックやと思います。そのことを一遍考慮に入れて考えて
いただければと思います。終わります。
H22年6月議会一般質問
そこで、基本計画や、数値目標を踏まえて質問に入りますが。
まず、現在の状況を見てみますと、平成20年の基本計画策定時は都市福利機能
と市街地環境等の整備については市民病院の建て替えをはじめとしてそれなり進
んでいると思いますが、市民病院以外では具体的な取り組みの内容が見えてこない。
商業・アミューズメント機能を主に民間投資で強化する、と言う点にいささかお粗末
な状況と言わざるを得ない。駅前へのホテル誘致は消えてしまい、昭南跡地への
オオクワの誘致は縮小、さらにココは閉鎖、商店街は何もしない結局は行政だけが
お茶を濁している有様
1 現在の状況をどう見ているのか
1回目答弁
1点目の、「現在の状況をどうみているのか」ということについてでござい
ますが、中心市街地活性化基本計画(案)につきましては、平成19年度、
20年度の2箇年で計画案を取りまとめ、平成21年度は、国の認定を受ける
ため、内閣府と事前協議を行ってきたところでございます。
これまでの国との協議の中では、行政の取り組みは分かるが、商店街とし
ての取り組みがこの計画では伝わってこない、具体的には既存商店街に人を引
き込む戦略、また、人を呼び込むための魅力づくりが見えてこない、との指摘
を受けております。そうしたことから、基本計画の認定はショッピングタウン
ココの再整備が決まってからでも良いのではないか、との指摘、また、国の認
定を受けることにより、国の補助金が受けられる事業、国が支援することが望
ましいと思われる事業が見受けられない、といった指摘も受けております。
このことから、中心市街地の核施設であるココの再整備の見通しが立ち、
商店街に人を呼び込むための取り組みなど、認定により支援される国の補助金
採択を受けられる取り組みが具体化した時点で、改めて国の認定を受けられる
よう取り組んでいきたいと考えております。
このような中、去る5月9日には、ココが閉店となり、更に賑わいが失われ
、中心市街地の活力が大きく低下してきておりますが、今回のココの閉店につ
きましては、営業の悪化ということではなく、ココの建物に係る争いが大きく
影響しております。
ココの建物は3者の共有となっておりますが、共有者の一つである会社が、
ココ組合に対して多額の地代等を滞納し、これが組合の収支に大きく影響し、
施設の維持管理に係る経費を捻出することが困難な状態となったことが原因で
あるとお聞きしております。
現在も、共有者3者の間で交渉が続いておりますが、最終的な解決がいつ
になるか見通しが立っていない状況あるとお聞きしております。
また、オークワにつきましては、ココ組合との連携の中で、この事態が収
拾した際には、地元商店街とともに集客効果を発揮できるよう、ショッピング
タウンココ店の再整備に努めていきたいとの意向を改めて伺っているところで
あります。
いずれにいたしましても、中心市街地活性化には、ココ店の再整備が必要
であり、重要な位置づけとなることから、今後も引き続き、ココ組合、オークワ
との情報交換を密にしながら、取り組んでまいりたいと考えております。
再質問
1 現状はよくわかりましたし、ココの状況もよくわかりましたが、答弁では今後
も引き続き、ココ組合、オークワとの情報交換を密にしながら、取り組んでまい
りたいと考えております。ということですがココの再開を核にということですか。
2 ココ組合の皆さんは、ココの閉鎖を受けてそれぞれに商店街に新店舗を構えよ
うとしておりますが、当然、ココの再開は、オークワさんとの協議と言うことですか。
再質問答弁
1 「ココの再開を核に取り組んでいくのか」という御質問でございますが、これ
までも本市の中心市街地の核施設でありましたココの再整備は、立地的に見まし
ても、商店街の活性化の観点からも必要であると考えております。
また、国との協議の中でも、中心市街地の核施設であるココの再整備の見通し
が立ち、国の補助金が受けられる事業、国が支援することが望ましいと思われる
事業を見出していくことが必要である、といった指摘も受けておりますので、
ココの再整備を重要な位置付けとして取り組んでまいりたいと考えております。
2 計画や目標数値に変更はないのか
2 「計画や目標数値に変更はないのか」ということについてでございます。
まず、目標数値についてでありますが、計画案を取りまとめた平成21年度末
時点での、中心市街地における状況及び計画に基づく施設整備や事業実施後の状
況を考慮し、目標数値を設定しております。
しかしながら、現在、ココの閉店により、中心市街地を取り巻く状況が変化し
てきていることから、目標数値については大きく変わってきておりますが、中心
市街地の核施設であるココの再整備の見通しが立ち、また、商店街等における新
たな取り組みが具体化してきて、内閣府との認定協議が再開された段階で、目標
数値を再検討し、修正すべき場合は、修正してまいりたいと考えております。
なお、計画内容については、新たな事業が出てきた時点で、中心市街地活性化
協議会 にお諮りし、協議いただく中で、随時修正してまいりたいと考えております。
3 商店街の取り組みと姿勢は
1回目答弁
3点目の「中心市街地活性化に向けた商店街の取り組み姿勢」についてでご
ざいますが、国からの指摘事項にもありましたように、行政主導ではなく、ど
れだけ商店街などの民間事業者が本気で中心市街地の活性化に取り組むかが重
要なポイントになってくるものと考えております。
これまでも十数回にわたり、商店街の皆様と協議の場を持ち、検討しており
ますが、ココの再整備が見えてこない中で、具体的な取り組みを見出せていな
せていないのが現状であります。
かつての中心市街地の賑わいを取り戻し、ひいては市全体の活性化につなげ
ていくためにも、引き続き、商業関係事業者とともに、中心市街地活性に向け
た協議を続けてまいりたいと考えております。
再質問
1 当初、平成19年、20年に計画をまとめたと言うこですが、当然、それ以前
の段階で、ココを含めた商店街と協議され、商店街も積極的に取り組むとの意向
を受けて計画に入ったと思うのですが、どうでしょうか。
2 かつての中心市街地の賑わいを取り戻し、ひいては市全体の活性化につなげて
いくためにも、引き続き、商業関係事業者とともに、中心市街地活性に向けた協
議を続けてまいりたいと考えております、との答弁ですが、商店街との協議は本
当につづけて成果が得られると思いますか。
3 以前のの中心市街地活性化基本計画も行政だよりの商店街の協力が得られず
失敗に終 わったと言うことですが、そのときの教訓を今回の計画にどう生かさ
れていますか。
再質問答弁
次に、3項目目の「商店街の取り組み姿勢」に関わっての、「商店街も積極的
に取り組むとの意向を受けて計画策定に入ったのではないのか」という御質問に
ついてでございます。
中心市街地活性化基本計画の策定に先立ちまして、平成18年度に国の「市町
村の中心市街地活性化の取組に対する診断・助言事業」を実施しております。こ
の事業では商店街や商工会議所など、中心市街地活性化に関わりのあるメンバー
の意見交換会や、シンポジウムなどを行っておりまして、商店街など関係者の
機運を盛り上げつつ、平成19年度から基本計画 の策定に入ったところでございます。
次に、「今後も商店街との協議を続けて成果が得られるのか」という御質問
でございますが、今までの商店街との協議ではなかなか期待するような成果が出
ておりませんが、商店街関係者の方からは、ジャスコ跡地への新病院建設も今具
体的に進みつつある中で、ココの再整備の見通しが立ってくれば、商店街の機運
も高まってくのではない か、といった意見もお聞きしているところでありまし
て、市といたしましても、盛り上がりを期待しておりますので、引き続き、商店
街や関係事業者との協議を続けてまいりたいと考えております。
次に、「以前策定した中心市街地活性化基本計画の教訓を今回の計画にどう
生かしたのか」という御質問についてでございますが、前回の計画では事業実施
後のフォローアップや事業実施に伴う効果発現、計画の見直しに関して取り組み
が不十分でありました。今回、法律では、中心市街地活性化の基本理念として、
地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ、主体的
に取り組むことの重要性が規定されております。
このことから、本市におきましても、株式会社まちづくりとなり、前回の計画
策定時にはなかった「海南市中心市街地活性化協議会」を設立しておりまして、
この協議会では、商店街関係者、民間事業者、行政関係者など、計画実行当事者
が計画策定の協議や、計画策定後も、事業の推進や進捗管理を行うこととなって
おり、策定段階から行政主導の計画とは違った、地域ぐるみで取り組める、実効
性の高い計画となるよう取り組んできたところでございます。
4 保険、医療機能、子育て支援機能の強化を図るということですが、
どのような機能強化を考えているのですが、新たな事業の展開は。
1回目答弁
4点目の「保健、医療機能、子育て支援機能の機能強化及び新たな事業の展
開」についてございますが、中心市街地に集積している医療、福祉等の都市福
利施設は、中心市街地への来街目的や賑わいの創出、活性化に大きな役割を果
たしておりますので、更なる充実に努めることとしておりますが、現在のとこ
ろ、市民病院の建て替え以外では、事業内容に大きな変化がないのが現状で
ございます。
今後は、都市福利施設での事業内容の充実、より効果的な施策について、担
当部署と検討を進めてまいりたいと考えております。
再質問
1 現在のところ、市民病院の建て替え以外では、事業内容に大きな変化がない
のが現状でございます。今後は、都市福利施設での事業内容の充実、より効果
的な施策について、担当部署と検討を進めてまいりたいと考えております。と
言うことですが、何故進めないのですか、中心市街地への来街目的や賑わいの
創出、と言うこともあるかもしれませんが、「保健、医療機能、子育て支援機
能の機能強化及び新たな事業の展開」と言うのは、市民に対 する医療、福祉
サービスの向上にもつながり、大変いいことだと思いますが。
再質問答弁
次に、4項目目の「保健、医療機能、子育て支援機能の機能強化及び新たな
事業の展開」についての御質問でございますが、これまでの市民アンケートな
どの結果を見ましても、保健、医療や子育て支援といった分野は、特に要望の
多いところであり、市にとっても大きな課題であると認識しておりますので、
議員ご指摘のように、市民に対する医療、福祉サービスの向上につなげられる
よう、積極的に担当部署と検討を進めてまいりたいと考えております。
5 この計画の実行へのプロセスは
1回目答弁
5点目の「この計画の実行へのプロセス」についてでありますが、先程から
申し上げてまいりましたとおり、これまでの国との協議を踏まえますと、商店
街をはじめとする 商業関係事業者による新たな取り組み、また、国の補助金
が受けられるような事業を盛り込むこと、更にはココの再生が必要であること
から、中心市街地の核施設であるココの整備の見通しが立ち、商店街に人を呼び
込むための取り組みなど、認定により支援される国の補助金採択を受けられる
取り組みが具体化した時点で、改めて国の認定を受けられるよう取り組んでい
きたいと考えております。
また、現在の計画(案)の中で、新病院建設や昭南用地の活用など、行政が
主導的に実施する事業につきましては、中心市街地活性化、ひいては市全体の
振興、活性化のため、計画どおり進めてまいりたいと考えております。
また、海南市中心市街地活性化協議会については、事業の進捗状況や新たな
取り組みを検討していくための協議の場として、今後も継続していくこととな
っております。
再質問
1 ココや商店街の現状では計画の実行が無理であるが、当面は計画は計画としておい
ておきたいと言うことですか。 ある程度のタイムリミットを決めておくべきではないでしょうか。
再質問答弁
最後に5点目の「この計画の実行へのプロセス」に関わって、「ある程度の
タイムリミットを決めておくべきではないのか」との御質問についてででござ
いますが、中心市街地活性化には、ココの再整備が重要であり、再整備の見通
しが立つことで、商店街の方々の盛り上りも期待できるとともに、国の計画認
定も目指していけるものと考えております。
なお、現在の計画(案)に基づき、行政が実施する事業について計画どおり
進めてまいりたいと考えております。
中心市街地活性化について質問をした結果、平成19年、20年度と
2年間を費やして計画案を立て、21年度に国の認定を受けるべく
取り組んできたが、結果としてココの再建のめどが立たず、駅前6商
店街が何もせず、国からもそのことを指摘され、国の認定を受けられ
なかったのが現状であり、市としてはココが再建され商店街が活性化
に向けて気運が高まるまで市の事業だけ進め、国に申請するチャンス
を待つという考えであるようです。
私はいつまでも待つというのはいかにも商店街任せで無責任では
ないか、せめて期限を切って対応してはと提案しましたが市当局は
考えを変えようとはしませんでした。
2 、 岡田地区の浸水調査と大坪川について。
この問題については、私が初当選以来幾たびか取り上げて
参りましたが、今日まで、排水対策として大坪側の改良に取り
組んでくれています、が、未だ完成に至らず、大きな問題を抱
えたままであります。
一方岡田地区の浸水に大きく関わっています、流入する
水の問題についてはようやく平成19,20年度で調査が行わ
れ、21年度には県の補助をいただきさらなる調査が行われた
ということであります。
関係者一同大変期待をしているところであります、岡田、室山
地区の皆さんにとって悲願であります、機械排水機場の設置に
ついては依然として進展していないばかりか、その他の問題に
ついても私の4年前の質問からほとんど進展していないのが
現状であります。
既に大坪川の改修も完成したところでありますが、浸水対策
という観点から申し上げれば、ゴールは遙か前方であります。
近年、世界各地で地球温暖化が進む中異常気象による大規
模な災害が発生し大きな被害が出いるのはご承知のことであり
ます。我が国においても決して例外ではありません、県によりま
すと計画降雨量による計算では機械排水をしなくても十分流下が
あるということですが、私は今日の世界的な異常気象を考えた
場合、計画降雨量のが問題ではないのか、是非見直す必要があ
るのでと考えています。
そこでこのこともふまえながら質問いたします。
1 浸水調査の調査結果と分析は
1回目答弁
1点目の「浸水調査の調査結果と分析は」というご質問でございますが、岡田
地区は低地帯であり、宅地化が進む前は、雨水は地中に浸透したり田畑等に貯留さ
れ、河川への流出が抑えられていましたが、田畑の減少により雨水の浸透する能力や
貯留する機能が減少し、水路・河川への流出量が増加し度々浸水が発生している状況
でございます。
市といたしまして、岡田地区の浸水対策を講じてゆくため、平成19年度・20年度に
調査を行い、既存水路・河川の能力の把握や浸水対策を検討してまいりました。また
昨年度は岡田・室山地区における洪水流出量の増加に対応し、治水の安全度を少し
でも高めるため、貯留浸透事業としての調査を実施してまいりました。この貯留浸透
事業は、学校、公園などの施設またはその敷地を貯留浸透機能を持つ構造とするこ
とや、流域に存在するため池や既存の調整池を活用しそれらを改良して、流域における
雨水の流出抑制を図るものでございます。
調査の結果、岡田地区の雨水排水は、時間50㎜の降雨に対し、本川で
ある亀の川の水位が低い時は支川である大坪川の流下能力は十分であり、自然流下は可
能であるが、本川である亀の川の水位が高い時には、支川である大坪川の水が流れづ
らい状態になり大坪川の水位が上がること、背水の影響と申しますが、そのために自
然流下での排水が難しくとなり、ポンプ排水等の対策が必要であると考えられます。
また雨水調整池を4箇所、貯留規模は合計9,000㎥を設置することで、大坪川に流
入する流量が1秒間当り3㎥以上抑制でき、室山地区や岡田地区の下流域における
浸水の軽減が図れるとの結果がでております。
他の対策といたしましては、既存ため池の貯留機能の向上、グランドに貯留施設の設、
置中流域に調整池設置などが示されており、これらの施設を設置することにより、流
域からの雨水の流出を制限し、浸水被害の軽減に効果が図れるものと考えております。
再質問
1 調査の結果、岡田地区の雨水排水は、時間50㎜の降雨に対し、本川である亀の
川の水位が低い時は支川である大坪川の流下能力は十分であり、自然流下は
可能であるが、亀の川の水位が高い時には、流れづらいれづらい状態になり、
大坪川の水位が上がるこ、背水の影響と申しますか、そのために自然流下での
排水が難しくなり、ポンプ排水等の対策が必要であると考えられます。と答弁を
いただきました。
私としましましては調査の結果やっと当局と岡田室山の浸水についての認識が
一したのかなとなと大変感慨深いものがあります、また、岡田、室山の浸水
対策を取り上げて当局からポンプ排水の対策の必要性についても言及されたこと
は評価をいたしたいと思います。
さて、質問ですが、大坪川(県管理も含めて)の平常時と大雨時の亀の川と大坪
川(県管理も含めて)水位についてその数値を教え値を教えてください。
再質問答弁
9番 栗本議員のご質問中、大項目2「岡田地区の浸水調査と大坪川について」
に関わっての再度のご質問にご答弁申し上げます。
1点目は「県管理も含めて大坪川の平常時と、大雨あるいは満潮時の流下
能力と大雨時の亀の川と県管理も含めて大坪川の水位についての数値は」とのご質問
でございます。
市の管理する区間の準用河大坪川の流下能力につきましては、平常時と大雨時を含め、
本川である亀の川の水位が低く、背水(バックウォーター)の影響を受けない場合において、
下流部JRの線路付近では1秒間に15㎥、その地点から約200m上流の山崎川と合流
するところから上流にかけては1秒間に11㎥の流下能力で河川改修を行ってまいりまし
た。また県管理の2級河川大坪川につきましては、市の調査では1秒間に17㎥を満たす
流下能力を持っています。
2 大坪川の水道管移設の進捗状況
1回目答弁
2目の「大坪川の水道管移設の状況」につきまして、県管理河川の大坪川の
県道下にございます水道の導水管につきましては計画河床より突出した形となってお
り、上流側の市の管理する準用河川大坪川の流水の流下を阻害している状況となって
いるところから、水道部と工法や費用など諸課題について検討を行なってきたところで
ございます。移設につきましては、技術的な工法を検討したところ、移設に必要な区間
延長についても短い区間で処理でき、また概算工事費につきましても約4,500万円
程度になるものと報告を受けております。
今後とも、水道部や県関係機関と導水管の移設についての調整を図ってまいりたいと
考えており、併せて費用負担につきましても国の補助金等があれば活用できるよう
取組んでまいりたいと考えております。
大坪川の水道管移設の進捗は。」の中で、水道部に関るご質問に答弁申し上げます。
先程、議員のご発言にもありましたように、大坪川におましては、県道三田海南線橋梁
下に、県管理の大坪川を横断する形で水道管が埋設されております。
この管は、紀ノ川から室山浄水場への口径700mmのコンクリート製の導水管で、平
成15年に県から本市に移管されたものでございます。この導水管は、大坪川の浚
渫をするなどし、河床を掘り下げるとなりますと、浮き出るような形となり河川の流れ
に支障が出ることになるということは、水道部といたしましても十分認識をして
おります。
先程、建設課長から、当該個所の部分的改修につきまして、補助メニューがあれば、
浸水対策として出来るだけ早急に実施してまいりたい旨の答弁がありましたが、その
場合におきましては、水道部といたしましても、現場管理、或いは県公営企業課など
関係当局との調整など出来うる限り建設課と協調をし、進めてまいりたいと考えて
います。
なお、水道部といたしましても、延長10.7kmのこの導水管につきましては、
県の工業用水道時代も含め、供用開始後50数年が経過し、老朽化が著しく、漏水も
状況にあります。このため、近い将来、全線に亘って耐震化も併せた改修を、国庫
補助事業として実施していく計画をもっております。
このことから、現時点で、水道の単独事業費を投じて当該個所の改修を
先行して実施するということは難しいと考えております。
いたしましても、全線の中でも特に当該区間につきましては、早急な改修が必要と
の認識のもと、4年から5年掛かると思われる事業期間の中でも出来るだけ早期に
実施できるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
再質問
1 当初水道管の移設には2億円程度の費用がかかると聞いておりましたが、
技術的な工法を検討したところ、移設に必要な区間延長についても短い区間で
処理でき、また概算工事費につきましても約4,500万円程度になると言うこと
です、やはり大きなお金ですから単独事業としてではなく、国庫補助事業
で取り組んでいきたいというのは良く理解できます。
当局も、早急な改修が必要との認識のもと4年から5年掛かると思われる事業
期間の中でも出来るだけ早期に実施できるよう努めてまいりたいと考えてます
とのこと、私としましても一日も早い着工を望んではいますが、財政のことを考
えるとやむを得ないとおもいます、その辺の処は岡田、室山地区の方々の気持
ちも組んでいただき、財政難のおり適切な対応をお願いいしたいと思います。
答弁はいりません。
3 機械排水機場の設置に向けての取り組みは
1回目答弁
3点目は「機械排水機場の設置に向けての取組み」につきましてのご質問
でございます。
県におきましては、2級河川亀の川水系河川整備計画を策定しているところでございます。
この計画は「治水面での安全性の向上」所謂、安全で安心な流域を目指す計画でご
ざいまして、洪水対策として10年に一度程度の確率で発生する規模の大雨、概ね最大
60分雨量60mmが降った場合に発生する洪水を安全に流下させることを目標とし、河口
から多田地区の紺屋橋まで、4.8kmの区間について計画的に工事を実施し流下能力を
現状の2倍以上、190㎥/sを安全に流下させる計画となっております。
工事内容につきましてはこの全区間の河床掘削を行なうとなっており、下流側から順次
流下能力を上げていくことにより大坪川合流点付近まで改修が進めば、本川である
亀の川の水位が現況より最大約80㎝低下することから、大坪川の排水も現状より
改善されるものと考えており3点目は「機械排水機場の設置に向けての取組み」に
つきましてのご質問でございます。
また、県におきましても本年度より大坪川流域における「貯留浸透事業」が事業化さ
れており、本年度は調査等を行ってゆく予定と聞いておりますが、今後とも県と連携を
図りながら室山・岡田地区の浸水対策に取組みを図ってまいります。
再質問
1 「機械排水機場の設置に向けての取組み」についての答弁としては、ちよっと
かみ合っていないのかな、県の2級河川亀の川水系河川整備計画はよくわか
りました、じゃあ、機械排水機場の設置についてはどうなんですか、というのが
聞きたい処なんです。いかがですか。
再質問答弁
2点目は「機械排水機場の設置」につきましてのご質問でございます。
現在、県で策定中の亀の川水系河川整備計画による改修が進んだ場合、洪水時に
おきまして亀の川と大坪川の合流点付近では水位が約80㎝低下し、亀の川の背水
の影響が大坪川に対して減少されることから流下の向上が図られるとなっていますが
、大坪川と亀の川の合流する地点の水位は、大坪川のJR踏切付近の水位と比べ約
1.3m高いことから排水ポンプ場の設置は必要な対策であると考えております。また、
ポンプ場の排水能力に関しましポンプ場の排水能力に関しましては、県管理の大坪川
の流水を完全排水するとすれとば1秒間に17㎥を超える能力が必要なり、その費用に
つきましても大まかな試算によりますが約40億円と膨大な費用が要ると考えておりま
す。それとともに、亀の川の河川整備の進捗具合によりまして、亀の川の水位が上
昇した場合には放流できなくなることや、亀の川にポンプ排水することによる和歌山
市領の流域に与える影響をどのようにするのかなどの課題を解消してゆく必要があ
ると考えております。そうしたことから、市といたしましては先程もご答弁させていた
だきましたとおり、ポンプ場設置につきましては有効な浸水対策であると考えており、
今後県と協議を進めてゆきたいと考えおります。
4 現在取り組んでいる浸水対策の状況は(県及び市管理の大坪川も
含めて。)
1回目答弁
4点目は、「現在取り組んでいる浸水対策の状況」につきましてのご質問でございま
す。岡田地区への洪水の流入を止める対策といたしまして、まず且来地区の
亀の川に架けられている大師橋の上流で取水している農業用水路の取水施設があり口
ます。洪水時にその取水からの流入を少なくする方法として、本年度においてゲート
を設置する計画がありますので関係する方々と調整を図ってまいたいと考えておりま
また、農業用ため池を雨水調整機能を持たすための整備につきましても関係水利組合
す。とも協議を行ってまいりたいと考えております。
さらに、浸水被害を軽減するためには調整池の設置は非常に有効な対策と考えており
、既存の漆器商業団地内にある調整池を活用・整備し、大雨時における雨水の流出抑制
を図ってまいりたいと考えており、来年度用地取得に向け関係の方々と協議を行って
まいりたいと考えております。
また、この調整池の整備計画は、既存の貯留施設を調査したうえで改良を加え、貯留量
を現在の能力の約2倍の2,000tに貯留機能を増やすことができれば、大坪川に流入する
ピーク流量を1秒間に約1㎥下げる効果があり、流出量を抑制する有効な対策と考えて
おります。
また、県におきましても本年度より大坪川流域における「貯留浸透事業」が事業化、
されており本年度は調査等を行ってゆく予定と聞いておりますが、今後とも県と連携
を図りながら室山・岡田地区の浸水対策に取組みを図ってまいります。
再質問
1 よくわかりました、雨水調整機能を持った調整池の設置は非常に有効なと
対策で あろう私も思いますし、また、亀の川から流れ込む水を増水時遮断するも
大変有効でしょう、是非進めていただきたいと思います。ただこれらの対策は大
坪川に流れ込む水の量を調整して遅らす、一度に大量の水が流入し大坪川ので
流下能力を超えないようにしょうとするもの岡田、室山に流れ込む水を少なくす
る設置は是非必要であるし、今回の試みによって、機械排水機場の規模という
ことにはならない。 最終的には機械排水機場のが確定されることと思います。
いかがお考えでがえでしょうか。
再質問答弁
3点目につきまして、大坪川流域は約400haありますが、この流域に降った
雨水が集中する大坪川下流域の室山・岡田地区の流出抑制を行なう上で、調整池の
設置は非常に効果があると考えております。
しかしながら、議員ご提言にございますようにこの地域に流入する水を少
なくするためには調整池で貯留して流出を抑える対策だけではなく、ポンプ排水による
浸水の軽減対策も必要であると考えます。貯留浸透対策を進めて言った場合において
つどのくらいの排水能力がひようであるのかという試算はできておりませんが、亀の川
の整備には長い年数が要しますので、市といたしましては、貯留浸透事業としての
対策を順次進めながら、流域の浸水対策としてポンプ排水も含め総合的な施策を今
後検討してゆかなければならないと考えております。
岡田、室山地区の浸水対策について質問をした結果、今
回はほぼ満足のいく議論ができたと思います。私は初当選
以来、幾たびかこの問題を取り上げ、20年目にしてやっ
と岡田、室山地区の浸水対策の進むべき方向が、当局とお
なじスタートラインに立つことができたと感じています。
今回の調査により大坪川の流下能力が亀の川の水位(満
潮時や増水時)によつて著しく低下すること、満潮時や増水
時における亀の川と大坪川の高低差が亀の川の改修を終え
てなお、1.3メートル大坪川が低いということ、が明ら
かになって参りました。
このため市としてはとりあえずの対策として一度にこの
地域に流入する水を雨水調整池を4箇所、貯留規模は合計
9,000㎥を設置し、大坪川に流入する流量が1秒間当り
3㎥以上抑制でき、室山地区や岡田地区の下流域における
浸水の軽減が図れる、また、既存ため池の貯留機能の向上、
グランドに貯留施設の設置、中流域に調整池設置などの対
策を考えていく、さらには今年度中に亀の川から且来地区
を経由し、岡田地区に流れ込む水を軽減するために水門の
設置を予定しているとのことであります。
また、大坪川の流下能力のアップを阻んでいる水道管の
移設についても全線に亘って耐震化も併せた改修を実施し
ていく計画をもっており、この地域に流入する水を少なく
するために早急な改修が必要との認識のもと、4年から5
年掛かると思われる事業期間の中でも出来るだけ早期に実
施できるよう努めてまいりたい、そして最終的には調整池
で貯留して流出を抑える対策だけではなく、ポンプ排水に
よる浸水の軽減対策も必要であると考えます。
以上のような答弁をいただきやっと排水機場設置に向け
動き出したと、いっそうの活動を改めて決意しているとこ
ろであります。
3、 大丈夫か我が市の防災対策。
平成19年6月議会で、海南市地域防災計画による、震災対策、
津波対策、風水害対策、実際にこういった災害に見舞われた際、
どう対応するのか、どう行動するのかといった計画や災害時の行
政機能についてお伺いいたしました。
そこで今回は、平成19年3月議会の答弁と、昨年の集中豪雨
時の対応と会わせ、お伺いして参りたいと思います。
前回の質問では主に以下のような答弁をいただいております。
災害による道路の損壊等、移動に困難を来たす状況も考えられま
すが、災害対策本部員には、あらゆる手段により、いち早く総合体育
館に参集していただかなければならないと考えております。
機材でございますが、電話、無線機、パソコン、テレビ、ラジオ、発電
機等の資機材を設置することとなっております。
震災後の行政機能がどうなるか、ということにつきましては、災害の
程度によりまして、使える施設、使えない施設が異なってくることから、
現時点では、市民の方々に、震災後の行政機能について正確な情報
を提供することは難しいのではないかと思っております。
庁舎がどの程度の震度に耐えられるのかは、定かではございませ
んが、平日勤務中に大規模な地震が発生した場合の対策としまして
は、職員自身が身を守るため、机やテーブルなどの下に身を隠し、揺た
れがおさまったら、津波警報等の来庁者への伝達、来庁者の安全の
ための退避等の措置、施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、
落下防止措置、出火防止措置等々の措置をとることとしております。
「市役所庁舎の耐震診断をし、程度を把握し対策を立てるべきでない
か」という御 質問についてでございますが、構造上耐震対策ができ
にくいものとなっており、根本的な対応は取られていない現状にあり
ますので、今後、庁舎がどの程度の地震、震度に耐えられるかという
ことを、耐震診断により把握できないか等々について、専門家と協議
したいと考えております。
この答弁ではもう一つ、市役所や市民病院が倒壊するかもしれ
ないという危機感が感じ取れない、いったい本市の防災対策の
最悪の場合の想定とはどの程度の事態を予想されているので
しょうか。
質問では震度5以上の地震と言うことで質問しますが答弁は最
悪の場合想定してお答えをいただきたいと思います。
1、 まず、震度5以上の地震に見舞われたとき、市役所や市民病院
のような耐震改修ができない建物はどうなるのか、倒壊という辞退
が考えられる震度は
1回目答弁
まず1点目の震度5以上の地震に見舞われたとき、市役所や市民病院のような耐震改修でき
ない建物はどうなるのか、倒壊という事態が考えられる震度は、についてですが、本庁舎に
つきましては、昭和40年の建築でありまして、当時の建築基準法に基づき設計・施工されて
おりますが、当時の基準からすると、目安といたしましておよそ震度5から6までの地震に
耐えられるものとして建築されたものと考えてございます。しかしながら、建後40数年を
経過した現在はどの程度の震度に耐えられるかは不明でございますが、最近の震度の大きい
地震を例に挙げますと、平成7年の阪神淡路大震災のとき、海南市では震度4の強さで約1分
間程度揺れましたが、その際、本庁舎屋上階の望楼でガラスがわれるなどの被害がありましたが、
壁や床など構造上重要なか所には被害はおよびませんでした。その時、県下の設計事務所に
依頼して耐震の簡易調査を行ってございますが、その報告では、本庁舎は杭も打っておりま
せんし、地盤から1.5メートルぐらい下には水が湧いてくる土質で液状化現象も考えられ
ますことから、倒壊に至ると考えられる震度は6以上程度であるかと推測されます。なお、
本庁舎は、柱が外壁と離れて内側にあるため、外壁の外側からの補強もできず、柱と柱の間
に壁やブレースを造る工法では事務スペースが極端に狭くなることなどの理由により、耐震
改修は非常に困難な状況でございますので、抜本的解決策が見いだせない中、平成19年度
より庁舎建設基金を創設させていただき、庁舎建替えに向け積み立てを行っているところで
ございます。
次に、市民病院はどうなるのかにつきましては、平成7年1月の阪神・淡路大震災の折、
市民病院内においては特段の被害はございませんでしたが、震度5以上ということになりますと、
想像がつかない状況でございます。
また、現病院の建物につきましては、耐震診断の有無にかかわらず、基準に適合していないと
認識しております、ただ、倒壊する震度がどの程度なのかにつきましては、想定できていない
状況でございます。現在平成25年4月開院に向けて進めております、新病院建設を出来るだけ
早期に竣工し、患者さまが安心して療養できる環境を整えたいと思っております。
再質問
1 倒壊に至ると考えられる震度は6以上程度であるかと推測されますす、ということで
すが、中央防災会の予測によりますと我が地方の大震度は最大震度は6弱となっています、
そうすると最大震度は6弱の地震が起こると、当然倒壊という事態に直面すると考えなけれ
ならないが、どうして本市の防災計画では震度5以上というような曖昧な設定をしているの
か。震度5弱と震度6弱ではそのパワーも被害の程度も格段の差があると思うがその点は
どう把握しているのか
再質問答弁
まず、1点目の震度5以上の地震に見舞われたとき、市役所や市民病院のような耐震改修が
できない建物はどうなるのか、倒壊という事態が考えられる震度はとのご質問中、どうして本
市の防災計画では震度5以上というような曖昧な設定をしているのか、また震度5弱と6弱の
差について、どう把握しているのか、との再質問ですが、本市では震度5弱以上の地震を観
測したとき、または大津波警報が発令されたときは、総合体育館に対策本部を設置すること
としております。これにつきましては、近い将来高い確率で発生するといわれている東海・
東南海・南海地震が起こった場合、市域では震度5強から震度6弱の揺れが起こり、その後、
津波により最大波5から6メートルの大津波の来襲により市役所周辺は2から3メートルの浸
水になると予測されています。
したがいまして、大きな地震の後には必ず津波が来襲する可能性があることを念頭に、
初期本部機能の維持という観点から、津波浸水区域外にある総合体育館に対策本部を設置
することとしております。
次に、震度5弱と6弱の差についてですが、気象庁の震度階級の解説も踏まえ、建物で
申しますと、震度5弱では、耐震性が低い木造建物では、壁などに軽微なひび割れ・亀裂が
みられることがある。また、震度6弱では耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物
が傾いたりすることがある。倒れるものもある。鉄筋コンクリート造建物では、壁、梁、
柱などの部分に、ひび割れ・亀裂が多くなると認識してございます。
2、平日勤務中に震度5以上の地震に見舞われたとき本当に本
部を総合体育館に設置し、関係者が速やかに移動できるのか。
1回目答弁
2点目の平日勤務中に震度5以上の地震に見舞われたとき本当に本部を総合体育館に設置し、
関係者が速やかに移動できるのかということでございますが、地域防災計画では、震度5弱以上
の地震を観測した時若しくは大津波警報が発令された時、市役所が津波による浸水で本部機能が
果たせなくなるおそれがあることから総合体育館研修室に本部を設置することとしております。
平日勤務中に、地震が起こり大津波の来襲が予測され、災害対策本部を総合体育館に設置する
必要が生じた場合における、最悪の場合を想定しますと、庁舎が地震により一部倒壊し来庁者や
職員の負傷等を負うことが考えられます。その場合、来庁者や負傷者を海南保健福祉センターへ
避難させるとともに、総合体育館に移動できる職員については、道路の決壊等、移動に困難を
来す状況も考えられますが、あらゆる手段によりいち早く総合体育館に参集させなければなら
ないと考えており、昨年9月に職員を対象に平常時に地震が起こった場合を想定した訓練を
行いました。訓練では初動の確認として、市役所から総合体育館まで徒歩による移動及び本部
設置の訓練を行ったところであり、職員が移動に要した時間は、平均して30分程度であり
ましたが、これは、何も障害がない状況ですので、実際災害が起こればかなりの時間がかかる
ものと予測されます。
また、移動後の本部機能ですが、昨年の訓練で検証した結果、本部機能の初動として通信が
確保できるよう電話、無線機、FAX、パソコン、プリンター、コピー等の最低限必要な機材を
整備また確保したところです。なお、それ以上に必要な機材が生じた場合は、県や関係機関への
えているところです。
再質問
1 1の項目でも申し上げましたが、震度6弱の地震によ って、市役所、市民病院が
一部あるいは倒壊という事態に対する、対策は考えているのか。
2 そうした最悪の事態に直面した場合の市役所と相互体育館との移動ルーート
の家屋の倒壊をはじめとしたシュミレーションはできているのか。
3 総合体育館に最低限必要な機材を整備また確保市と言ことです具体的に教え
てください。
再質問答弁
次に、市役所、市民病院が一部あるいは倒壊という事態に対する、対策は考えているのかと
のご質問ですが、先ほどご答弁させていただいたとおり、市役所につきましては、来庁者、職
員の安全を第一に考え、救護、避難を最優先に行います。市民病院につきましては、入院患者
の生命・安全を最優先に近隣の受け入れ可能な災害拠点病院への搬送が第一と考えております。
次に、市役所と総合体育館との移動ルートの家屋の倒壊をはじめとしたシミュレーションは
出来ているのかとのご質問ですが、昨年の訓練では、国道370号、県道海南金屋線の2ルート
による検証を行いました。国道370号ルートでは歩道、道幅も広く比較的移動がスムーズに行わ
れました。県道海南金屋線については、距離的には国道370号ルートより短い状況でありますが
、歩道等が狭く家が道路に隣接している箇所があります。なお、それぞれのルートに至るまで、
特に県道海南金屋線については、住宅街を通る箇所が多く家屋等の倒壊による移動の障害が考
えられます。
いずれにいたしましても、その時の状況により、ルートを選択しなければならないと考えて
おります。
次に、総合体育館に最低限必要な機材の整備、確保について具体的な内容はとのご質問ですが、
災害対策本部における最低限必要である通信手段を確保するための機器として、パソコン2台、
プリンター1台、電話4回線、無線機能として防災行政無線同報系遠隔操作卓1台、防災行政
無線移動系の可搬統制台1台、無線機用FAX1台、無線機用パソコン1台、無線機4台を対策本部
室となる研修室内などに順次整備し、また停電時を想定し自家発電機を整備しております。また、
事務所内には、既存のコピー機1台、パソコン12台、プリンター1台、電話4回線、ファックス
2台、携帯電話1台などが利用できる状態となってございます。これらについては、今後さらに
検証し、その他の機器の必要性、また数量などについて検討してまいりたいと考えております。
3、 震度5以上の地震に見舞われたとき通常の最低限の行政機能を
持った施設を設置するのか。設置出来ない場合はどう対処するのか。
1回目答弁
次に、3点目の震度5以上の地震に見舞われたとき通常の最低限の行政機能をもつ施設を設置
するのか。設置できない場合はどう対処するのかということでございますが、最悪の場合として想定
すれば、市役所 本庁舎の倒壊、または倒壊しなくても本庁舎としての機能がほとんど失われる
場合が想定され、市民の方はもとより、庁舎などの行政施設内にいる多数の職員や来庁者の負傷
などが予測されます。このような場合には、通常の行政機能を最低レベルで果たすことすら非常に
あった職員や、負傷の程度が軽い職員が、災害対策の初動にあたり、対策本部設営、被害調査、
被災者の支援、業務の継続、災害復旧に取り組めるよう対策本部で対策を講じて行くこととしてお
ります。なお、通常の行政機能につきましては、耐震性等の問題もありますが、現在の本庁舎、
行政局、支所、出張所での対応と考えております行政事務行えそうな公共施設を選定し、分散
して業務を再開させることと考えております。
再質問
1 通常の行政機能につきましては、現在の本庁舎、行政局、支所、張所での対応と考えて
おりますが、これらの施設が、使用不能という状態でありましたら、被害を受けていな
い行政事務を行えそうな公共施設を選定し、分散して業務を再開させることと考えております。
ということですが。それでは、公共しせつの耐震診断は学校以外どこまで進んでいるですか。
再質問答弁
次に 学校以外の公共施設の耐震診断はどこまで進んでいるのかとのご質問ですが、学校を
除く本庁舎、行政局、消防本部、指定避難所、市民病院などの災害拠点施設・避難所となる構造
計算が必要な建物36棟のうち、耐震性を満たす建物は17棟、建替え予定は市民病院の7棟分
であります。したがいまして、耐震性が不十分と想定される建物は12棟で、これらの建物うち、
室山保育所につきましては耐震診断をうけておりますが、市役所建物や公民館施設などの11棟に
つきましては耐震診断は受けてございません。
4、 震度5以上の地震では庁舎そのものが危ないといわれていますが、
平日勤務中の事態に対する対策は、そして検討結果は。
1回目答弁
次に、4点目の震度5以上の地震では庁舎そのものが危ないといわれていますが、平日勤務中の
事態に対する対策は、そして検討結果はというご質問でございますが、庁舎がどの程度の震度に
耐えられるかは定かではございませんが、大地震の発生に対応するため、本庁舎に緊急地震速報
受信設備を設置しており、緊急地震速報が放送された場合、来庁者、職員は事前に自身の安全を
守るよう行動することができます。次に、地震発生時の対応としましては、来庁者と職員の安全を、
図り庁舎内での人的被害を出来るだけ少なくする措置を行い、揺れがおさまった段階で、負傷者
の救護、庁舎外の安全な場所への避難、出火防止などの措置をとることにしているところでござ、
います。なお来庁者の安全を手助け出来るよう来庁者用ヘルメット の配置や、ロッカー等の転倒
防止や窓ガラスの飛散防止について取り組んでいるところです。
再質問
なし
5、 消防本部について。震度5以上の地震に対する本部としての対策
は出来ていますか。
1回目答弁
5、「消防本部について、震度5以上の地震に対する本部としての対策は出来ていますか。」
のご質問にご答弁申し上げます。海南市において震度5弱以上の地震を観測した場合、市職員
初動マニュアル地震警報配備体制に基づき、消防職員全職員が、道路が寸断していなければ所属
の各署所に、道路状況が悪く所属に参集できない場合は最寄りの署所に参集し、海南市消防
地震警備計画に基づき活動することといたしております。
この海南市消防地震警備計画では、消防本部災害作戦室に警備本部、警備指揮所を設置し、
情報収集、連絡調整、指揮調整を行い、海南消防署、下津消防署、東出張所並びに各消防器具
置場に警備所を設け管轄区域内で発生した火災、救急、救助に対する指揮統制を行い、有線
電話、携帯電話が不通になることを想定し、消防無線にて各地区の現場状況、活動状況を
警備本部に連絡し、市災害対策本部と連携し海南市全域の状況を把握することといたしております。
しかしながら、阪神淡路大地震のような震度7、震度6強の規模の地震では、本市の消防
職員92名、消防団員716名の消防力をもって対応しても、すべての災害現場に出動は困難
であることから、阪神淡路大震災を教訓に、全国の消防機関による応援を速やかに実施する
ため、平成7年に創設された緊急消防援助隊の迅速出動に関する実施要綱に基づき、平成22
年4月1日現在 全国で4264隊の中から、あらかじめ取り決めた被害の発生がない都道
府県から先遣隊が調査に和歌山県に向た被害の発生がない都道府県から先遣隊が調査に和歌山
県に向制を整え出動することといたしております。
消防本部の対策といたしましては、震度7、震度6強の大地震の場合、緊急消防援助隊と一体
となって活動することといたしております。
再質問
なし
海南市におきましても、少子化により各学校の生徒数が少なくなり、学級数が減り、
それに伴って教員数も減ってきています。
教員数が少なくなることで、教科の専門性を生かした授業や、また、部活動での団体
競技でのクラブ員の確保が難しくなっている学校もあり、それらのことを一つ一つ解決
するためには学校を統合し、学級数を増やし活力ある学校にしていく必要があると考えている。
1-3、取り組みの経過と現状は。
第一回目 H17,8月に「各中学校の生徒数の推移と適正配置案」 について中学校区
6箇所で。
第二回目 H18,1月に「教育委員会が考える具体的な配置案」について 小学校区9カ所で 。
第三回目 H18,11月に「教育委員会が考える具体的な配置案」について、より具体的
に。小学校区9カ所で 。3回の説明会をする中で特に三中校区で参加してい
ただいた保護者の大多数の方々から「今の山中は現状でも生徒数が多く、ま
た、教育委員会が示した生徒数の推移表をみても極端に生徒数が減少する
ことがない従って山中は統合する必要はない」という意見が多数を占めました。
第四回目 H19,2月 大野小学校と内海小学校の育友会役員にたいし、説明会を開催。
その際にも、前回同様の意見が多数を占めており、 教育委員会としてもこれら
の意見を重く受けさせていただきました。
第五回目 H20,2月に二中校区、一中校区それぞれで幼、少、中の育友会の役員の方々
に説明会を開催した。
その中で出た意見としては、統合にはおおむね賛成するが、統合す時期を早くし
てほしいとの意見が大多数であった。
1-4、説明会での出席の割合は、そして意見は。
参加していただいた人が校区の保護者の方か、地域住民の方か把握していない
ので割合は算出していません。
1-5、現状での教育委員会の考えは
答弁漏れ
1-6、今後は。
一中、二中の統合をできるだけ早く実現したく、今後、精力的に説明会を開催し
統合に 向けてこれまでのご意見を基に統合を進めていくよう考えている。
再質問
4回にわたる説明会の結果、山中は平成30年までは1学年3学級を維持できる
うえに、保護者の統合反対の声が多く当面は三中は単独で、一中、二中の統合
を先行して行うということですが、たとえ1中、2中が統合して1学年4学級を実
現しても、H24年には3学級、H27年には2学級となり基へ戻ってしまう、そして
それまで6年しかない現状を教育委員かはどう考えているのか。
統合を何年後に想定しておられるのかわかりませんが、統合後数年しか統合の
効果を維持できないというのはいかがなものでしょうか。
答弁
教育委員会としては生徒数の減少が著しい中、将来的には一中、二中、山中の3校
統合の計画を持っていますが、一中、二中の保護者の方々が危機感を持っていると
ころでありますので、今は、できるところから段階的な統合を進めていく考えでございます。
2、亀川、巽中学校の統合について
2-1、中学校の適正規模化に当たって、現場の校長や教師と検討したか。
答弁 懇話会の構成員として現場の声を反映するため、校長会代表、
教職員組合代表の方も委員として参加していただきました。
再質問 答弁は少し違うように思う、私の説明が悪かったのでしょうから、
もう一度いいますが、懇話会にはかるもっと以前に教育委員会と亀
川や巽のように何十年前から2学級で教育に携わってきた校長先生
や教師、そして嘗ては大規模校であった1中、2中、3中の大中小
規模の教育を経験した先生たちそういう先生方の知識やノーハウを
生かすべく努力をしなかったのか。懇話会ではどういう意見が出さ
れたのか。
答弁 懇話会設立前にはそれらの方々の意見等を聞く機会はこざいません
でした。
懇話会での意見につきましてですが、小規模であっても長く一定の
生徒数を維持し、地域も教育熱心であり、着実に教育成果をあげてい
る保護者や地域の声を聞かずに適正配置の話はしにくいのではないか、
免許外担当教科を解消し部活動などより良い運営をするためには、
統合による規模の拡大が必要であるなどの意見が出ておりました。
適正配置では、こういう今までの学校の実績も踏まえつつ、しかし
将来的な生徒数減を見据え統合によって新しい学校を作り、小規模
校での実績をいかし、さらによりよい教育活動が望めると判断した
ものです。
2-2、なぜ統合なのか、海南市としての必要性は。
答弁 海南市におきましても、少子化により各学校の生徒数が少
なくなり、学級数が減り、それに伴って教員数も減ってきて
います。
教員数が少なくなることで、教科の専門性を生かした授業
や、また、部活動での団体競技でのクラブ員の確保が難しく
なっている学校もあり、それらのことを一つ一つ解決するた
めには学校を統合し、学級数を増やし活力ある学校にしてい
く必要があると考えている。
再質問
答弁のとおりだと思います、ただ、私は1中、2中、3中
の統合と亀川、巽中の統合は、基本的に違うのじゃないか、
そう考えています。
1中、2中、3中特に1中、2中、の場合は嘗ては大規模
校であった、それが答弁にもあったように少子化により各学
校の生徒数が少なくなってきて今日のような状況であります
が、一方、亀川、巽中は当初から2学級で何十年続いてきて
H30年まではその状態が続くというわけであります。
亀川、巽地区の皆さんにとっては今更何で、といわざるを
得ない、まさに統合について登壇して申し上げたように
1、少子化による学校生活上の課題として。(学級数が減る
と教員数が減る)
① 十分な学習指導ができるか懸念。
・少人数指導や選択授業が十分に展開できない。
・免許外教科担当の教員がでる。
・教科別教員の研修が十分にできない。
②部活動の衰退が懸念。
・設置する部が限定される。
・指導できる教員も不足する。
③学校全体の活力低下が懸念される。(子供は集団の中で
育つ)
・体育祭、文化祭等の学校行事が迫力に欠ける。
・生徒同士の刺激・高め愛が行われにくい。
以上のすべてについてハンディを負いながら、さらに教室
が足りない、運動場が狭いといった悪条件の中、校長先
生、教職員、保護者の皆様が一体となって学校運営、学
校教育に取り組んできたのが実情であります。
そこでお伺いしますが、
1、 1中、2中、3中と亀川中、巽中では、今は同じ小
規模校ですが、歩んできた過程はは違うんだ、教育
委員会はこのことをどうとらえ、評価して、今回の
適正配置に反映させているのか。
答弁
一中、二中、三中は過去、海南市では大規模な学校であり
ましたが、近年、少子化により生徒数が激減した学校であ
ります、亀川中、巽中につきましては、過去から、今と同
程度の規模でありながら、教師や生徒が一丸となり努力や
工夫を重ね、大規模校に負けない学力や、運動能力を養い
、すばらしい実績を残してきたことは認識しているところ
でございます。
再質問 2、 1中、2中、3中と亀川中、巽中では学力、運動力に
ついてどれだけ格差があるのか。
答弁
現在の亀川中、巽中につきましても、そのような伝統が受
け継がれているものと思っているところでございます。
再質問 3、それほど適正配置が必要だいうのなら、いままで亀
川中、巽中を放置してきたのはなぜなのか
答弁
今般の少子化問題は国として重要な問題であり、海南市
でも少子化が進むなかで、ここ数年前より海南市の環境の
変化など、全体の中学校のあり方を見直していかなければ
ならない時期になってきたところでございます。
そうしたなかで、平成15年に「海南市立中学校将来構想
懇話会」を立ち上げ、海南市における将来の中学校のあり
方について、検討していただき、平成16年度には教育委員
会としての基本的な考えをまとめるとともに、適正規模を
図るための適正配置案を作成いたしました。それに基づい
て、これまで説明会を開催し、保護者の意向にもよりまし
て、適正配置を進めてきたところでございます。
再質問 4、取り組みの経過と現状は。
答弁
第一回目 H17,8月に「各中学校の生徒数の推移と適
正配置案」について中学校区6箇所で。
第二回目 H18,1月に「教育委員会が考える具体的な
配置案」について
第三回目 H18,11月に「教育委員会が考える具体的な
配置案」について、より具体的に。
3回開催した説明会での意見としては。
・ 通学路の安全確保。
・ 多大な税金の投入や周辺環境の観点からあまり賛成で
きない。
強い反対や、積極的な推進の意見もなく教育委員会としても
具体的な計画を打ち出せず、今日に至っている。
再質問 第三回目をH18,11月に開催して今日まで 具体的な
計画を打ち出せていないということですが、実際には、大規
模特別委員会における質疑の中で、膨大な資金を必要とする
上に、地元の強い反対もないけれども、積極的な推進の
意見もないので計画が頓挫しているとのニュアンスの答弁を
しています。
冗談じゃない、この計画はもともと教育委員会が独自に出し
てきたもので、地元や保護者の要望、あるいは意見を聞いて
立ち上げたものではない。これは教育委員会がかってに立ち
上げた適正配置計画ではないですか、膨大な資金か゛かかる
といいますが、それは教育委員会も当局も承知の上でこの計
画を発表したのではないですか、資金が調達できない予想も
つかない事情ができたのですか、それをきちっと説明しないで、
地元の積極的な推進の意見がなく具体的な計画を打ち出せず、
今日に至っている、第三回目が終わってからすでに1年10ヶ
月(約2年)何の結論も出さず放置しているんです。
何なんです、地元の積極的な推進の意見ないといいますがそ
れは当たり前でしょう、
教育委員会ははじめから資金調達が難しいということで腰が
引けているではありませんか計画者が及び腰であるのに何で地
元が積極的ななれますか。まず、教育委員会な資金調達がい
かに難しかろうとこの計画を必ずなし遂げようという強い意
思表示をすべきじゃないですか、そうすれば亀川も巽も積極
的になるざるを得ないでしょう、いかがですか
質問を整理します。
再質問 1、資金か゛かかるといいますが、それは教育委員会も当局
も承知の上でこの計画を発表したのではないですか
答弁
海南市開発公社が所有しております鰹田池周辺整備事業用地
につきましては、教育委員会が適正配置案に示しております亀川
・巽中学校の統合用地として要望し、庁内の関係する部署におい
て協議を行い、当用地は現在の両学校の中間的な位置にあるこ
とから適地であり、統合校舎の予定地として教育委員会と市長部
局とで協議してございます。
再質問
1、 このことについて当局と話をしたが協議はしたが、資金についとの
ゴーサインは出していないということである。
2、 資金が調達できない予想もつかない事情ができたのですか
答弁
鰹田池周辺地を開発し、統合後の新校舎で開校するためには
多額の財政負担を伴うものであり、当初から担当課と協議してま
いりました。それとともに、教育委員会が適正配置計画について
保護者・地域住民の方に説明する中で、ご理解を得、皆様の気運
を盛り上げる必要がありますが、現在は、具体的な計画を打ち出せし
ず、財政措置の見通を持つまでに至っていないのが現状であります。
再質問
3、 第三回目が終わってからすでに1年10ヶ月(約2年)何の
結論も出さず放置しているのはなぜですか
答弁
説明会を開催できていないことは、議員ご指摘の通りでございま
して、保護者並びに地域住民の皆様が不安になられていることを
考えると、申し訳なく思ってございます。
第3回目説明会が終わってから、その後、説明会を開催できていな
い理由につきましては、先ほどの答弁で申し上げましたが、建設時
期や通学路等の具体的な計画を示せないこと、道路整備や宅地開発
など、現在の両校区内の状況が計画当時と比較しても予想以上の変
化と思われることなどから、具体策を出せないまま現在に至ってい
るところであります。
学校統合という大きな事業を実現するにあたっては、その基盤とな
る保護者や地域の皆様の理解や機運の高揚を確立することが大きな
要件であり、機運の高揚を図る一方で同時に具体的な計画を示し、
財源の確保も着実に進めながら事業実施を固めていくのが方策であ
ると考えております。鰹田池周辺地を開発することに伴う財政措置
が必要なことは認識してもらっていますが、教育委員会として全体
計画の具体化を進められず、資金面での見通しを得られない状況に
あります。このような進展を得られない状況であったため約2年間、
説明会も開催できていません。
教育委員会といたしましても2年間進展できない状況については
各委員とも危惧しており、最重要課題ととらえております。さらに
耐震化の実施が喫緊の課題として国から促されていることもあり、
適正配置について見直しも含めて早急に教育委員会議において今後
の適正配置の方向を示さなくてはならないと判断していることをご
理解願います。
再質問
4、 3回の説明会の中で資金についてどのように説明しているの
ですか。
答弁
3回の説明会において、質問に対する回答以外、資金面の具体的な
説明は特にしてございません。
再質問
5、 説明会での出席の割合は、そして意見は。
答弁
参加していただいた人が校区の保護者の方か、地域住民の方か把
握していない ので割合は算出していません。
再質問
6、 現状での教育委員会の考えは
答弁 答弁漏れ
再質問
7、 今後は。
答弁 亀川、巽中につきましては、道路整備などにより周辺の環
境も大きく変化しつつあり、今後も宅地開発などによる人口、
生徒数の推移を見守る必要もあることから、早期、かつ積極的
に統合への推進はできないものと考えているところで再度、
保護者、地域住民へこのような状況を説明し、ご意見を伺った
上で教育委員会として今後の方針を決めて参りたい。
再質問
1、 亀川、巽中につきましては、道路整備などにより周辺
の環境も大きく変化しつつあり、今後も宅地開発など
による人口、生徒数の推移を見守る必要もあることから、
早期、かつ積極的に統合への推進はできないということ
ですが、ではなぜ実現不可能に近いような適正配置案を
出してきたのですか
答弁
教育委員会がお示ししました「海南市における将来の中学校のあ
り方」につきましては、平成12,13年度に「少子化問題懇話会」
で少子化が学校教育に及ぼす影響や課題を明らかにし、適切な生徒
集団の形成、学校組織の充実等「本市における中学校の適正規模化
等について」協議していただき、その成果を引き継ぎ、平成15年
度には将来において良好な教育環境を創り出す観点から「本市にお
ける中学校の適正配置」を進めるため、学識経験者、市議会議員、
教育等関係団体代表、一般公募による委員で構成した「海南市立中
学校将来構想懇話会」で精力的に協議が行われ、平成16年3月に
その報告書が教育委員会に提出されました。
海南市教育委員会では、報告書の内容・趣旨・提案等をくみ取り、
鋭意その具体化に向けた検討を行い、本市の中学生が一層健やか
に成長し、素晴らしい人格を形成していくことができるような教育環境
を提供するという観点から、中学校の適正規模化及び適正配置等を
内容とする計画案3案を作りました。
このような経過を経て作成された計画案に基づき、市内で説明会を開
催した上で、将来的な最終案を教育委員会で決定したものです。
再質問
2、 再度、保護者、地域住民へこのような状況を説明し、
ご意見を伺った上で教育委員会として今後の方針を決
めて参りたい。そりゃないでしょう。
教育委員会がかってに適正配置を決め、これまた勝手
にやめてしまう、しかも資金調達が難しいことはかくし
て積極的な推進の意見がないから実現は難しい、今後
は保護者、地域住民の意見を伺った上で決める、親切に
ありがとうございます。しかしそれではだめですね、
保護者、地域住民の意見を聞くのであれば、鰹田池の問
題をきちっと片づけ、それにかわる案を示してそこから
始まるべきではないですか。
答弁
海南市教育委員会の定例会等では、これまでも市議会や特別委員
会での状況を報告し、ご意見を伺ってきましたが、今後開催する教
育委員会には、これまでの説明会における保護者・地域住民の皆様
のご意見を集約するとともに、鰹田池周辺の開発による亀川中・巽
中の統合については、現在に至る状況を十分説明し、教育委員会に
おいて再度協議し、今後の方向性を決定していただく予定でござい
ますので、早期に教育委員会の考えをお示ししたいと考えてござい
ます。
再質問
3、 とにかく早く結論を出すべきではないですか。